お腹の痛みをあまり感じないのに便がゆるい状態や水のような便が続くと、どのように対処すればよいか迷うことがありますよね。普通の下痢と比べて腹痛が少ない場合、原因に気づきにくく、対処が遅れる恐れがあります。
この記事では、痛みを伴わない下痢の具体的な原因や改善方法、検査を受けるタイミングについて解説します。便通の乱れが続くときは、放置せず早めに原因を突き止めることが重要です。

痛みを伴わない下痢とは
便がゆるい状態や液状に近い状態が続くにもかかわらず、腹部の痛みを強く感じない下痢があります。
お腹が痛くないのに長期間続く下痢は、原因が体調不良だけとは限らず、病気が潜んでいる可能性もあるため、まず症状の特徴を知ることが大切です。
症状の特徴
痛みを感じにくい下痢では、回数や水分量に注目すると原因を探りやすくなります。腸の動きが活発になりすぎているものの、炎症や刺激が比較的軽度な場合、激しい痛みを引き起こさないまま下痢が続くことがあります。
症状の特徴
- 1日に何度もトイレに駆け込むが、腹部への強い不快感は少ない
- お腹が痛くないのに便が水っぽい
- 疲労感や脱水症状を伴うことがある
- 食後すぐに便意を感じることがある
痛みが軽いからこその注意点
下痢の原因は多様ですが、痛みが軽いと症状を見逃しやすいです。
お腹が痛くないのに下痢が続くときは、消化器系のトラブルだけでなく、ストレスや生活習慣の乱れ、別の疾患の可能性もあり、痛みが弱いからと油断せず、体調を客観的に記録すると早期発見につながります。
日常生活で起こりやすい例
体調が優れないときだけではなく、普段から緩い便が続く方や一時的に緩くなる方もいて、例えばダイエットのために食事量を急激に減らしたり、過度のストレスを受け続けたりすると、腸内環境が乱れて下痢が起こりやすくなります。
こうしたケースでは食事や生活リズムを見直すだけで改善する場合もあります。

痛みを伴わない下痢に関する一般的なポイント
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 下痢の回数 | 1日に3回以上だと慢性的な下痢を疑う |
| 痛みの有無 | 腹痛が弱い、もしくはほとんど感じない |
| 便の状態 | 水分量が多く、粘り気が少ない |
| 他の症状 | めまい、倦怠感、脱水などがある場合は注意 |
| 要チェック期間 | 1週間以上続くなら医療機関の受診を検討 |
痛みを伴わない下痢の原因
お腹が痛くないのに水のような下痢が起こる背景には、複数の要因があり、食事内容だけでなく精神的ストレス、腸の病気などを含むさまざまな原因が考えられます。原因を正しく把握すると、必要な検査や治療を選ぶことが可能です。
食事や生活習慣の影響
体質に合わない食品や暴飲暴食など、日常的な習慣が腸内環境に影響を及ぼし、以下のような習慣が続くと、腸が刺激を受けて下痢を起こすことがあります。
食事や生活習慣の見直しポイント
- 脂質が多い食事の過剰摂取
- アルコールやカフェインの取りすぎ
- 食物繊維や水分の不足(便の硬さや腸内バランスに影響)
- 不規則な睡眠サイクル
ストレスや自律神経の乱れ
精神的な負担が大きい状況が続くと、自律神経のバランスが崩れて腸の働きが過敏になり、痛みのない下痢に発展することがあり、過度のプレッシャーや不安感があるとき、下痢と便秘を繰り返すケースも見受けられます。
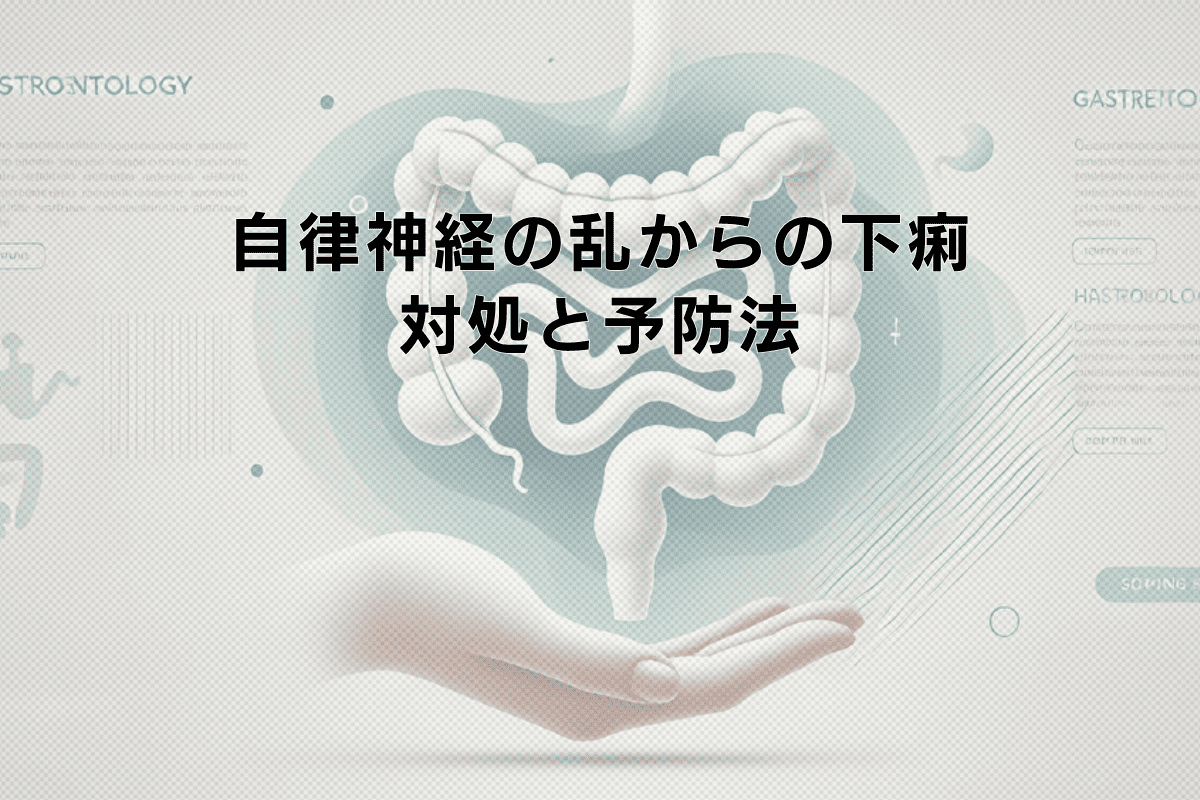
腸や消化器系の病気
潰瘍性大腸炎やクローン病、過敏性腸症候群など、腸や消化器系の病気が関係している場合も考えられ、症状が軽度でも慢性的に続くなら、検査によって疾患の可能性を排除することが必要です。
原因の分類
| 原因分類 | 具体的な内容 | 痛みの強さ |
|---|---|---|
| 食事・生活習慣 | 脂質過多、アルコール、カフェイン、夜更かし等 | 軽度~中等度 |
| ストレス関連 | 自律神経の乱れ、過敏性腸症候群 | 軽度の場合多 |
| 腸の病気 | 潰瘍性大腸炎、クローン病など | 個人差大 |
| 感染症 | 細菌・ウイルス感染、食中毒など | 急激に発症 |
検査を検討するタイミング
痛みを伴わない下痢が続くときは、そのまま自己判断で放置すると症状が悪化したり隠れた病気の発見が遅れる可能性があります。
経過観察の目安
症状が軽度でも、1週間から2週間ほど続く場合は注意が必要です。水分量の多い便が出ることで脱水が進むリスクもあるため、「ただの下痢だろう」と様子見にせず、早めの受診が望ましい場合があります。
検査を考えるタイミング
- 1週間以上下痢が継続し、改善の兆しがみられない
- 発熱や血便などの追加症状を伴う
- 食生活の改善を行っても変化が乏しい
- ストレス要因が減ったのに下痢が改善しない
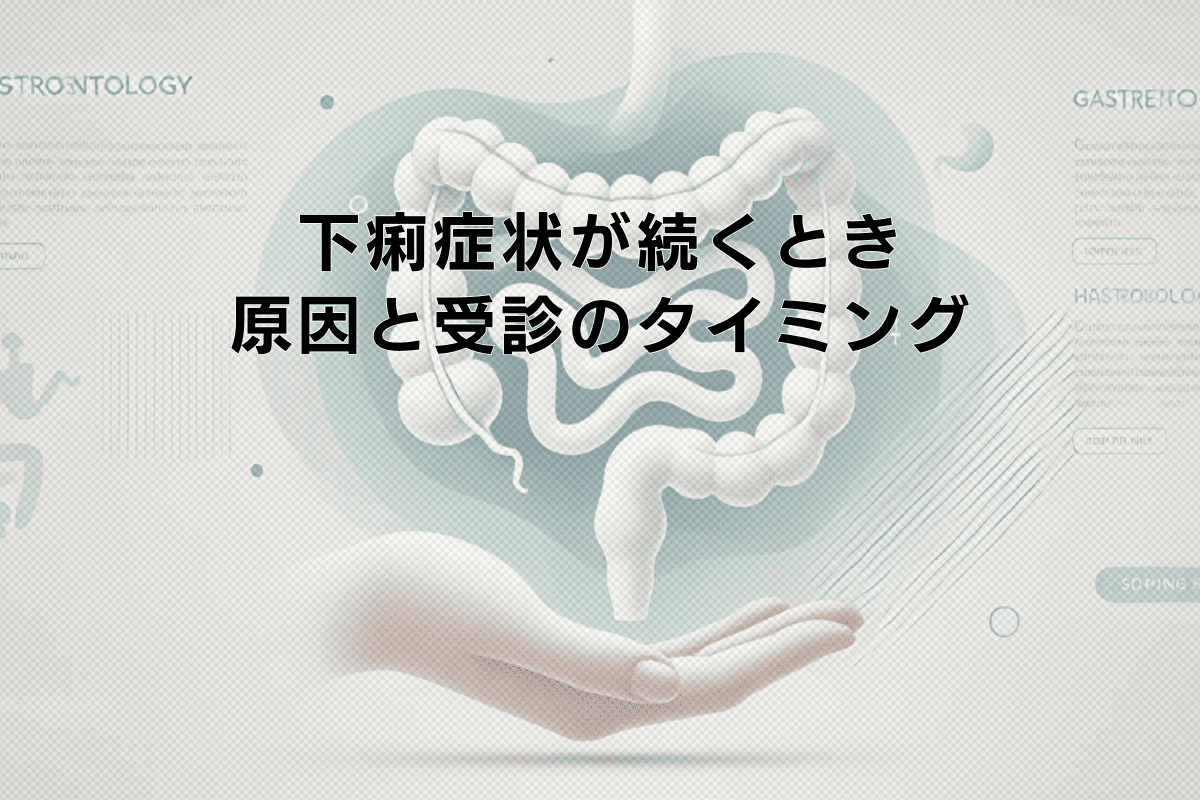
病気の可能性を疑うサイン
痛みの少ない下痢でも、場合によっては重い病気の初期症状となることがあります。潰瘍性大腸炎や大腸がんなどは早期発見が肝心です。血液や粘液が便に混じる、体重が急激に減少するなどのサインがあるなら、速やかに検査を検討しましょう。
検査の種類
腸の状態を詳細に調べるためには、大腸カメラや胃カメラ、超音波検査など多彩な手段があり、症状と疑わしい病気の種類によって検査内容が変わるため、医師と相談しながら選択します。

受診や検査を考える基準
- 慢性的な下痢が1週間を超えて長引く
- 血便、粘液便、発熱などのサインがある
- 体重減少や倦怠感が強くなった
- 精神的ストレスの緩和後も下痢が改善しない
主な検査内容
| 検査方法 | 主な目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| 大腸カメラ | 大腸内部の観察、ポリープや炎症の確認 | 直接観察が可能で、組織採取も可能 |
| 胃カメラ | 胃や十二指腸の異常を確認 | 消化性潰瘍や炎症、腫瘍などの発見に有用 |
| 超音波検査 | 腹部全体の状態を画像で確認 | 非侵襲的で苦痛が少ない |
| 便検査 | 細菌やウイルス、消化吸収の状態を調べる | 感染症の有無や血液の混在を確認できる |
内視鏡検査・大腸カメラ・胃カメラの役割
痛みを伴わない下痢が長引くときは、大腸カメラや胃カメラの検査が大切です。画像で直接消化管内部を確認できるため、病変の早期発見や正確な診断につながります。
大腸カメラでわかること
大腸内視鏡検査では、大腸の粘膜の色や炎症、潰瘍の有無、ポリープなどの病変を詳しく確認できます。必要に応じてポリープを切除できるほか、病変部の組織を採取して病理検査を行うことも可能です。

胃カメラでわかること
胃カメラは食道から胃、十二指腸までを観察し、炎症や潰瘍、腫瘍などを直接確認できます。痛みを伴わない下痢でも、胃の不調が原因になっている場合があるため、医師は総合的に判断して胃カメラの実施を提案することがあります。

内視鏡検査のメリット
内視鏡検査を受けるメリットは、病変を直接目視で確かめながら治療方針を決められることで、血便がなくても粘膜の炎症や微細な潰瘍が見つかるケースがあり、早期発見に役立ちます。
検査を受ける際の判断材料
- 長期的な下痢と腸内の違和感
- 定期的な腹部の張り感や不快感
- 既往歴に消化器系の病気があるか
- 40代以降で検診をしばらく受けていない
内視鏡検査で確認できる主な病変
| 対象領域 | 主な病変 | 特徴 |
|---|---|---|
| 大腸(大腸カメラ) | ポリープ、炎症性腸疾患、がんなど | 観察しながら切除も可能 |
| 胃(胃カメラ) | 胃潰瘍、胃がん、慢性胃炎、逆流性食道炎など | 早期発見に結びつきやすい |
自宅でできる対策
お腹の痛みを強く感じない下痢も、生活習慣を改善することで症状が和らぐ場合があり、正しい食事や睡眠時間の確保、ストレスマネジメントなど、日常生活の調整が効果を発揮することも少なくありません。
食事の工夫
下痢が続いているときは、脂っこいものや甘いものを控えめにして、消化にやさしい食品を取り入れてください。水分補給も重要で、スポーツドリンクや経口補水液を活用すると体のバランスが整いやすくなります。
水分補給のポイント
便がゆるい状態だと体内の水分や電解質が失われやすいので、普通の水だけではなく、ナトリウムやカリウムなどを含むドリンクを飲むとよいです。ただし、一度に大量ではなく、少量をこまめに摂取すると体に負担がかかりにくくなります。
ストレスケアと休養
ストレスが原因で自律神経が乱れているときは、十分な睡眠とリラクゼーションを心がけ、可能な範囲で休養を増やし、軽い運動や趣味で気分転換を図ることも有効です。
自宅で取り入れるとよい工夫
- 脂質や糖分を控えめにした食事
- こまめな水分補給(電解質を含むドリンクが望ましい)
- 規則正しい睡眠スケジュール
- ストレッチやウォーキングで気分転換
自宅でできる対策
| 項目 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 食事バランス | 消化に優しい食品を中心に摂取 | 腸への刺激を抑える |
| 水分補給 | ミネラルや糖分も適度に含んだ飲料を少量ずつ | 脱水予防と体力維持に有用 |
| 運動・リラックス | 軽めの有酸素運動や趣味を取り入れる | ストレス軽減で腸を安定 |
病院やクリニックでの治療
痛みを伴わない下痢がなかなか収まらない場合、医療機関での専門的な診断・治療が必要で、薬物療法や点滴などを利用しながら、生活習慣の改善指導も並行して行うケースが一般的です。
診察時の流れ
初診では、問診や触診を経て、必要に応じて血液検査や便検査が行われることがあります。その結果に基づき、内視鏡検査などの詳しい検査が追加されるかどうかが決定されます。
主な治療方法
症状に合わせて整腸薬や腸の動きを整える薬剤を処方する場合があります。また、感染が疑われるときは抗生物質、炎症性腸疾患と診断されたらは5-ASAなどの炎症を抑える薬や免疫調整薬などを使用することもあります。
生活指導との併用
薬によって腸内環境を整えても、食事やストレスが改善されなければ再発の可能性が高まります。そのため、医師によるカウンセリングや栄養指導など、生活改善と治療を同時に進めることが多いです。
病院での治療内容
- 問診と簡単な検査を経て、追加検査の必要性を判断
- 結果に応じて薬物治療や内視鏡検査を実施
- 栄養相談や生活改善指導を並行することが多い
- 慢性化を防ぐために定期的なフォローアップを行う
治療の流れ
| 治療段階 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 初診・問診 | 症状の詳細、生活習慣、既往歴などを確認 | 簡単な触診や検温も含む |
| 検査段階 | 血液検査、便検査、内視鏡検査などを実施 | 症状に応じて選択 |
| 治療計画の策定 | 薬物療法、食事指導、ストレスケア | 病状に合わせて複合的に対応 |
| 経過観察・再診 | 定期的に状態を確認して治療方針を見直す | 症状が落ち着くまで継続 |
受診前に知っておきたいポイント
医療機関で診察を受ける前に、あらかじめ準備しておくとスムーズに進むことが多いので、具体的な症状の記録や生活習慣のメモを取っておくと、問診や診断が行いやすくなります。
症状の記録とメモ
痛みを感じない下痢が1日にどのくらいの回数起こるか、便の色や粘液の有無、血の混在などを記録しておくと、医師に症状を正確に伝えられます。また、仕事や家庭でのストレスがあればそれも記載してください。
食事や生活習慣の管理
何をどのくらい食べたのか、どれくらいの水分を摂取したのかをメモしておくと、下痢との関係が把握しやすくなり、医師は原因の切り分けを行いやすくなります。
受診時に伝えるべき情報
医師へ伝える内容としては、下痢の期間や発症時期、きっかけになった出来事(旅行や外食など)、既往歴、アレルギーの有無などがあり、伝え忘れがないよう、あらかじめリスト化しておくことがおすすめです。
受診前に整理すること
- 下痢の発症時期と経緯
- 1日の排便回数、便の状態(色、形状、水分量など)
- 食事内容と水分摂取量
- ストレスや体調の変化、睡眠時間
情報をまとめるときに役立つ項目
| 項目 | 記録の例 |
|---|---|
| 発症時期 | ○月○日頃から症状が始まった |
| 排便回数 | 1日5回程度、ゆるい便が続いている |
| 便の状態 | 水分が多く、色はやや薄め |
| 食事・生活習慣 | 揚げ物を毎日食べていた、睡眠不足など |
| そのほかの症状 | 微熱、倦怠感、不安感など |
よくある質問
痛みを伴わない下痢に悩む方が抱える疑問点をまとめました。疑問や不安を解消して、早期の対策や受診を検討するきっかけにしていただければ幸いです。
- 痛みがなくても重大な病気の可能性はありますか?
-
痛みが少なくても、潰瘍性大腸炎や大腸ポリープなどの病変が見つかることがあり、血便や体重減少が見られるときは早めに受診してください。大腸カメラや胃カメラで直接チェックすると安心です。
- 市販薬で治らない場合はどうすればいいですか?
-
市販薬を数日試しても改善が見られない場合は、医療機関で詳しい検査を行うほうが確実です。特に下痢が長引くときや、脱水や全身の倦怠感を感じるときには早めの受診をおすすめします。
- 内視鏡検査はどれくらい負担がかかりますか?
-
個人差がありますが、大腸カメラでも鎮静剤を使う方法を選択すれば負担が軽くなる場合があり、胃カメラも経鼻内視鏡などの方法を選ぶと苦痛が少なく感じられます。
医療機関によって対応が異なるため、事前に相談してください。
鎮静剤については以下の記事も参考にしてください。
⇒【鎮静剤を使用した痛みの少ない内視鏡検査について】
次に読むことをお勧めする記事
【腸の内視鏡検査で分かること – 検査前の準備から検査後の注意点】
痛みを伴わない下痢の基本を押さえたら、次は実際の検査がどのようなものか知っておくと安心です。検査を検討されている方に特に参考になる内容です。
【腸の健康が体を支える 腸内環境を整える】
腸内環境を整えると免疫や代謝まで好影響。食事や生活習慣のコツを学び、下痢を繰り返さない体づくりを目指しましょう。
参考文献
Maeda K, Yamana T, Takao Y, Mimura T, Katsuno H, Seki M, Tsunoda A, Yoshioka K, Fecal Incontinence Guideline Preparation Committee. Japanese practice guidelines for fecal incontinence part 1-definition, epidemiology, etiology, pathophysiology and causes, risk factors, clinical evaluations, and symptomatic scores and QoL questionnaire for clinical evaluations-English version. Journal of the Anus, Rectum and Colon. 2021 Jan 28;5(1):52-66.
Holtz LR, Neill MA, Tarr PI. Acute bloody diarrhea: a medical emergency for patients of all ages. Gastroenterology. 2009 May 1;136(6):1887-98.
Powell DW. Approach to the patient with diarrhea. Principles of Clinical Gastroenterology. 2008 May 30:304-59.
Navaneethan U, Giannella RA. Definition, epidemiology, pathophysiology, clinical classification, and differential diagnosis of diarrhea. Diarrhea: Diagnostic and Therapeutic Advances. 2011:1-31.
Manatsathit S, Dupont HL, Farthing M, Kositchaiwat C, Leelakusolvong S, Ramakrishna BS, Sabra A, Speelman P, Surangsrirat S. Guideline for the management of acute diarrhea in adults. Journal of Gastroenterology & Hepatology. 2002 Feb 2;17.
Read NW, Krejs GJ, Read MG, Santa Ana CA, Morawski SG, Fordtran JS. Chronic diarrhea of unknown origin. Gastroenterology. 1980 Feb 1;78(2):264-71.
Greenberger NJ. Diagnostic approach to the patient with a chronic diarrheal disorder. Disease-a-Month. 1990 Mar 1;36(3):135-79.
Schiller LR. Diarrhea. Medical Clinics of North America. 2000 Sep 1;84(5):1259-74.
Tack J. Functional diarrhea. Gastroenterology Clinics. 2012 Sep 1;41(3):629-37.
Browning SM. Constipation, diarrhea, and irritable bowel syndrome. Primary Care: Clinics in Office Practice. 1999 Mar 1;26(1):113-39.










