便秘が解消したと思ったら急に下痢が続いてしまう、という症状を経験している方は多いです。日常生活に大きな支障をきたすだけでなく、「これは大きな病気の兆候ではないか」と不安に思うこともあるでしょう。
本記事では、便秘と下痢を繰り返す背景、原因、受診の目安、そして大腸カメラや胃カメラを含む検査内容まで幅広く解説します。
食事や生活習慣で見直すポイントにも触れていますので、便秘からの下痢が続くときの改善策を考えるきっかけにしていただければ幸いです。
便秘と下痢が交互に起こる仕組み
便秘から下痢へ急激に移行すると、体も心も大きな負担を感じやすくなり、まずは、腸内で何が起こっているのかという仕組みを把握することが大切です。
腸の動きや日々のストレス、食生活などが複雑に影響し合うことで、この症状が現れやすくなります。
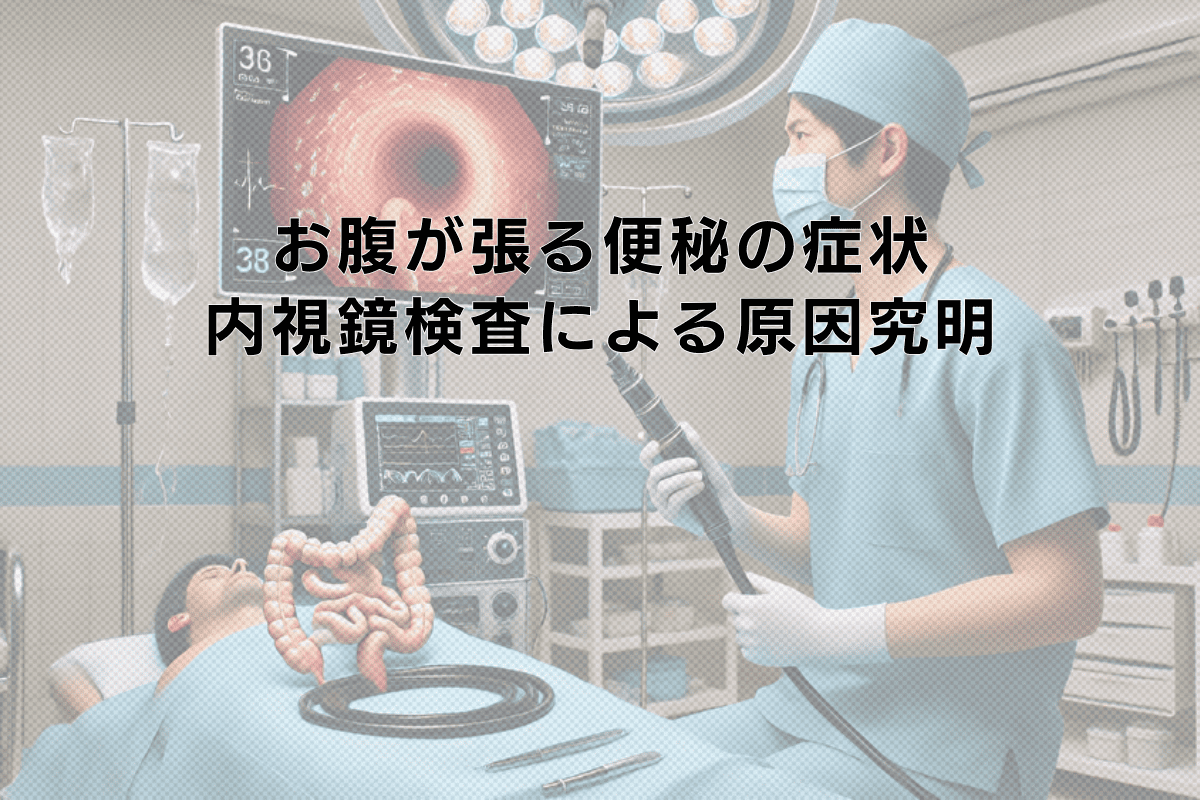
腸の蠕動運動に影響を与える要因
腸は、蠕動運動によって内容物を先へ先へと押し出し、蠕動運動は自律神経のバランスに左右されやすく、ストレスや睡眠不足、食事の偏りなどで乱れることがあります。
一時的に腸の動きが弱くなれば便秘に、逆に過敏に動きすぎると下痢が発生しやすい状態です。

便秘と下痢の境界が曖昧になる理由
長時間便が腸にとどまると水分が吸収されすぎて硬くなりますが、腸壁への刺激が強くなりすぎると、体が防御反応で急激に水分を分泌して下痢を起こすケースも見られます。
硬い便と柔らかい便が連続する形で便秘から下痢へ移行しやすくなるのです。
心理的要素との関連
過度なストレスや不安を感じる状態が続くと交感神経が優位になりやすく、腸が過敏になることがあります。便秘と下痢を繰り返す方の中には、緊張の多い環境や生活リズムの乱れが慢性的に存在している場合が少なくありません。
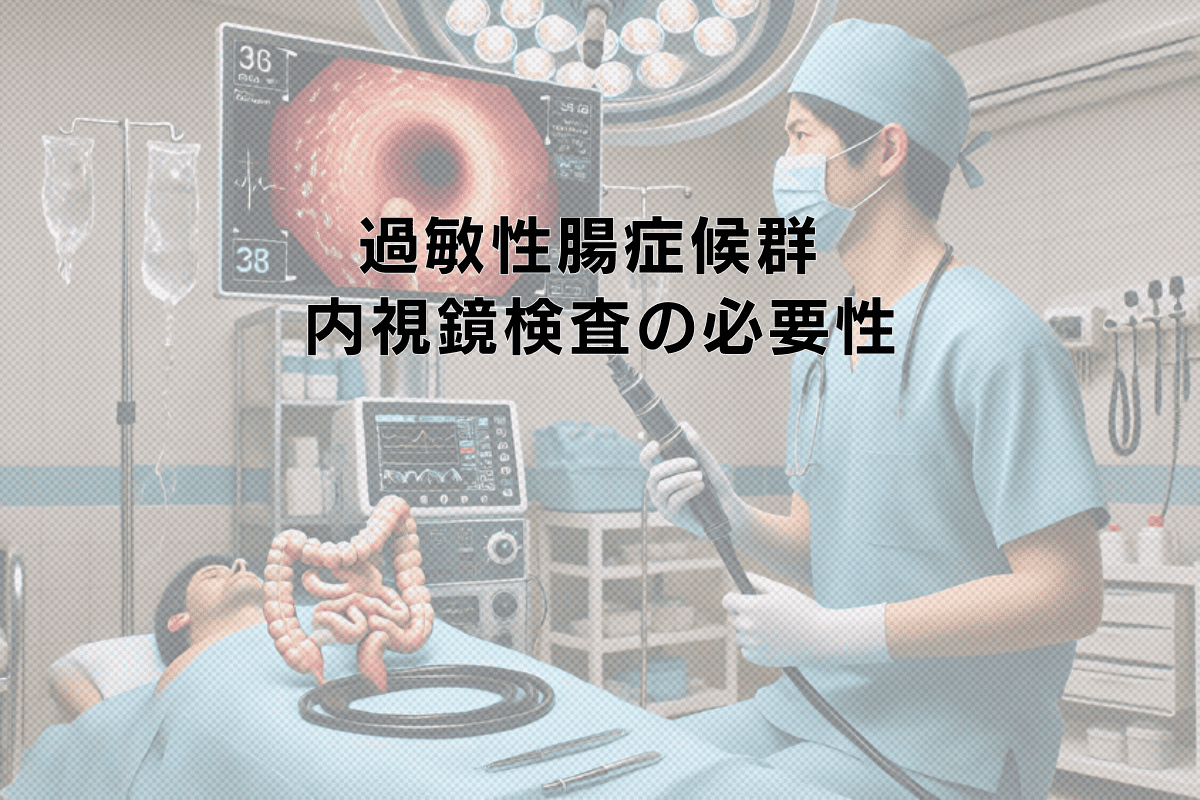
症状の見分け
| 状態 | 主な特徴 | 例 |
|---|---|---|
| 便秘優位のタイプ | 便が硬い日が続くが、ときどき下痢が混じることもある | 食物繊維不足、極度の水分不足など |
| 下痢優位のタイプ | 普段は下痢が多いが、便秘の状態も不規則に出る | 過敏性腸症候群のうち下痢型、感染後の腸トラブル |
| 混在型 | 固い便と柔らかい便が交互に出る | ストレス性、腸内フローラの乱れなど |

便秘から下痢を招く主な原因と背景
便秘が続くと腸内に老廃物がたまりやすくなり、その後何らかの刺激をきっかけに急に腸が動き出して下痢が起こるという現象がしばしば見られますが、原因は一つとは限らず、複数の要素が絡み合っていることが多いです。
食生活の乱れが与える影響
- 食物繊維を全く摂らない、もしくは過剰摂取している
- 水分摂取が極端に少ないか、急に大量の水分をとる
- 油分や糖分の多い食事が中心になっている
これらの食生活の乱れは、便の硬さや腸の動きに大きく作用します。食物繊維は便通を促すのに役立ちますが、摂りすぎるとガスや腹痛、さらに便秘悪化を伴うこともあるためバランスが重要です。

ストレスと自律神経の関係
ストレスが強いと、腸の運動を調整する自律神経が乱れやすくなり、夜更かしや不規則な睡眠リズムも、腸の働きに悪影響を与えます。心身の緊張状態が解けた瞬間に腸が急激に動き出し、下痢を起こすケースも少なくありません。
腸そのものの病気
過敏性腸症候群や炎症性腸疾患など、腸の機能や粘膜に異常がある場合も便秘や下痢が繰り返されます。大腸ポリープや大腸がんなどの器質的疾患が隠れている場合は、単なる体質やストレスだけでは説明できない症状も出やすいので要注意です。
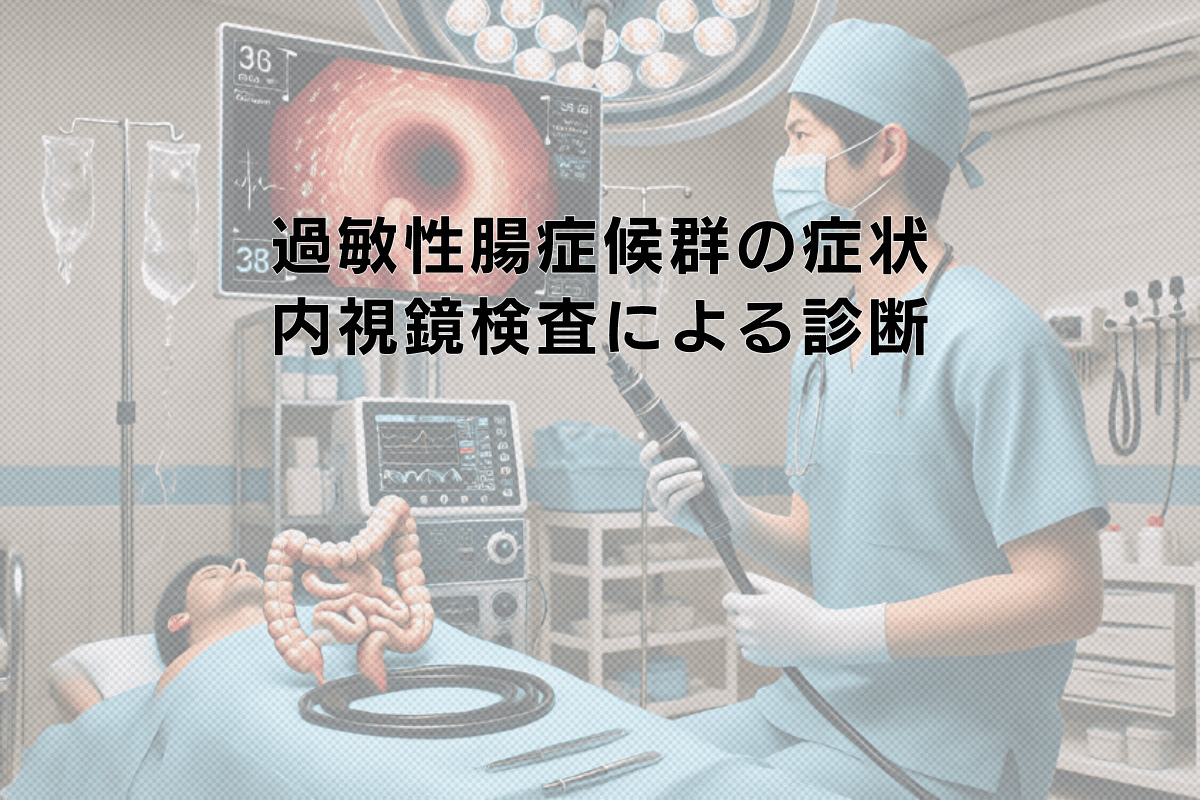

原因とチェックしたい症状
| 原因 | チェックすべき症状 | 備考 |
|---|---|---|
| 食生活の乱れ | 便の硬さが一定せず、下痢が不定期に起こる | 野菜不足や水分不足が深刻な場合あり |
| ストレスによる自律神経の乱れ | 仕事や家庭での緊張が続き、便意のタイミングが不規則 | 休日になると下痢になる人もいる |
| 腸疾患(過敏性腸症候群など) | 血便や激しい腹痛を伴い、体力の低下が顕著になることも | 早めの医療機関受診が必要になるケース |
受診を考える目安とポイント
便秘と下痢を交互に経験している場合、「どのタイミングで受診すればよいのか」と迷うことが多く、下痢が続く場合は、体内の水分バランスが崩れやすく、脱水状態に陥るリスクもあります。
自己判断に頼りきらず、正しい時期に受診することが重要です。
病院へ行ったほうがいい症状のサイン
- 血便や粘液便が出る
- 激しい腹痛、もしくは慢性化している腹痛
- 短期間での体重減少や強い倦怠感
- 一般的な食事調整や水分補給では改善しない
これらのサインが認められるときは、一時的な便秘・下痢の繰り返し以上の問題が潜んでいるかもしれないので、躊躇せずに医療機関で相談してください。
問診の準備と重要性
受診すると、医師から普段の生活習慣や食事内容、便の状態について詳細に尋ねられます。以下のような情報をメモしておくと診断がスムーズです。
- 排便の頻度や便の硬さ、色、臭い
- 食べたものや飲んだもの、食事の時間帯
- 仕事や家庭でのストレス要因
- 睡眠時間や運動習慣
受診までに行うセルフケア
軽度の便秘と下痢の繰り返しであれば、以下のようなセルフケアを試しながら様子を見るのも一案ですが、症状が長引くときや重症化する傾向があるときは早めの受診を検討しましょう。
- 適度な水分補給をこまめに行う
- 食物繊維を含む食品とタンパク質をバランスよく摂る
- 軽い運動やストレッチで腸の動きをサポートする
症状別の受診タイミング
| 症状の傾向 | 具体例 | 受診目安 |
|---|---|---|
| 軽度・短期的な症状 | 数日間だけ便秘と下痢を繰り返し、軽い腹痛 | 生活習慣の見直しで改善がない場合 |
| 中程度の症状 | 1週間以上継続する下痢と便秘の混在 | 体力低下や体重減少が見られたら早め |
| 重症・感染が疑われる症状 | 血便、大量の粘液便、高熱 | 即受診が望ましい |
検査内容と内視鏡検査の検討
便秘と下痢が続くとき、医療機関ではさまざまな検査を組み合わせて原因を探ります。最初は血液検査や便検査などから始まり、必要に応じて大腸カメラや胃カメラといった内視鏡検査に進むことがあります。
検査の流れ
- 問診・視診・触診
生活習慣や症状の経過、腹部の張りなどを確認 - 血液検査
炎症の有無や貧血、栄養状態を把握 - 便検査
潜血や細菌、ウイルスの有無をチェック - 画像検査
レントゲンやCT、超音波などで腸の形態的異常を調べる - 内視鏡検査
大腸カメラや胃カメラで粘膜の状態を直接観察
内視鏡検査準備と当日の流れ
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 検査前日~当日の食事 | 医療機関からの指示に従い、消化にやさしいものを摂る | 余計な残渣が残らないようにする |
| 下剤の服用 | 指定された時刻までに必要量を飲み切る | 飲みづらい場合は、無理せず少しずつ調整する |
| 検査当日の手続き | 身分証や保険証を準備し、問診票を再確認する | 間違った情報がないか改めてチェックする |
| 鎮静剤や麻酔の有無 | 希望を伝えることで痛みを軽減できる場合がある | 事前に医師や看護師に相談する |
| 検査終了後の注意 | 休憩スペースで体調を確認し、問題なければ帰宅する | まれに検査後の体調不良が起こるので安静を保つ |
便秘と下痢を繰り返す時期が長引くほど腸内環境は乱れやすくなるので、適度に休息を取りながら、生活習慣の見直しと医療機関での相談を両立させることを意識してください。
大腸カメラや胃カメラが重要な理由
腸や胃の粘膜に炎症や腫瘍がある場合、それが便秘や下痢の引き金になっていることがあり、内視鏡を使って直接観察すると、病気の早期発見やポリープの切除が可能になります。


内視鏡検査に対する不安の軽減策
検査前に下剤を飲む、検査時の苦痛が心配など、不安を感じる方は多いですが、最近は鎮静剤を使用して検査を受ける施設も増えており、また検査後すぐに帰宅できる場合もあります。医療スタッフに遠慮なく心配事を伝えることが大切です。
大腸カメラ・胃カメラでわかる主な病変
| 検査名 | 観察範囲 | 主に発見が期待される病変 |
|---|---|---|
| 大腸カメラ | 大腸全体(直腸~盲腸) | ポリープ、大腸がん、炎症、潰瘍など |
| 胃カメラ | 食道~胃~十二指腸 | 胃・十二指腸潰瘍、胃がん、逆流性食道炎 |
便秘から下痢を繰り返す人におすすめの生活習慣
医療機関での検査や治療だけでなく、日常生活で腸にやさしい習慣を意識すると、便秘と下痢の悪循環から抜け出しやすくなります。大幅な改善は難しくても、小さな工夫を積み重ねることで腸内環境を整えられます。
食事のポイント
- 水溶性食物繊維(海藻類、果物、根菜類など)と不溶性食物繊維(豆類、全粒穀物、野菜など)のバランスを取る
- 発酵食品(ヨーグルト、納豆、みそなど)を毎日の食卓に取り入れる
- 炭水化物・タンパク質・脂質を適度に配分し、急激な血糖値上昇を避ける
リズムを整える心がけ
- 毎日同じ時間に起床し、朝食をとって腸の活動を促す
- 夜はできるだけ早めに就寝し、睡眠不足を防ぐ
- 昼食後や夕方に軽いウォーキングを行い、腸を刺激する
ストレスケアの重要性
- 趣味や軽い運動で気分転換を図り、心身の緊張をほぐす
- 深呼吸やヨガの呼吸法を取り入れ、リラックスを意識する
- 無理な残業や詰め込みすぎの予定を減らし、オフの時間を確保する
腸への負担を減らすアイデア
| 取り組み | 具体例 | 期待できるメリット |
|---|---|---|
| 水分補給をこまめに行う | スポーツドリンクやミネラル豊富な水を利用する | 腸内の水分不足を防ぎ、便を柔らかく保つ |
| 腹部を温める | お腹にカイロをあてる、湯船にゆっくり浸かる | 血流を促進して腸の動きをサポートする |
| 適度な運動 | ウォーキング、軽いストレッチを日課にする | 自律神経のバランスが整いやすくなり排便改善 |
自宅で簡単にできるセルフケアの実践
受診を迷っているときや、検査の結果待ちのあいだなど、自宅で取り組めるケアを知っておくと役立ちます。腸に余計な負担をかけない工夫を日常に取り入れることで、症状の悪化を防ぎやすくなります。
腸内環境を整える食材の工夫
- ヨーグルトやチーズなどの乳製品:腸内細菌のバランスを保つ
- 納豆や漬物、ぬか漬けなどの発酵食品:整腸作用をサポート
- イモ類や根菜類:水溶性食物繊維が豊富で便の形成を助ける
体を冷やさない工夫
腸は冷えると動きが鈍くなることがあります。夏場の冷房による冷えや、冬の寒さで血行が悪くなると、便秘が続いた後の下痢を誘発することもあります。
腹巻きやブランケットなど、寝るときもお腹を温めるように意識すると腸が安定しやすいです。
腹式呼吸を取り入れる
下腹部を意識して大きく息を吸って吐く腹式呼吸は、腸に刺激を与える一方で副交感神経を優位にし、リラックス効果も期待できます。ストレスの軽減は便秘と下痢のサイクルを断ち切るうえでも重要です。
- 朝起きたときにベッドの上でゆっくり呼吸
- 仕事中の休憩に椅子に座ったままでも実践可能
- 就寝前に照明を落とした部屋で静かに行う
腸をいたわる方法
| やり方 | 効果 | ポイント |
|---|---|---|
| ガス抜きのポーズ(ヨガ) | 腹圧をかけて腸の動きを促す | 呼吸を止めないように注意し、痛みを感じる場合は無理をしない |
| 軽い腹部マッサージ | 血行を促し、蠕動運動をサポート | 指の腹で優しく、時計回りにマッサージする |
| 便意があるときは我慢しない | 自然な排便リズムを保ち、便をため込みすぎない | 仕事中でもできるだけ早めにトイレに行く |
よくある質問
症状がはっきりしない便秘と下痢を繰り返していると、不安や疑問を抱くことが多いです。多くの方から寄せられる質問を取り上げながら、少しでも安心材料を増やしていただければと思います。
- 下痢が続く日には、絶食したほうがいい?
-
絶食ではなく、胃腸にやさしい食事を少量ずつ摂る方法が望ましいです。完全に食事を抜いてしまうと体力や免疫力が落ち、回復が遅れる可能性があります。
消化にいいおかゆやスープなどを中心にして、水分補給も忘れないようにしてください。
- 便秘からの下痢を繰り返す場合、市販薬だけで対応しても大丈夫?
-
市販の下剤や下痢止めは一時的な症状緩和には役立つこともありますが、原因が解決していないと再発を繰り返すことが多いです。
過剰に頼ると腸の自律的な働きがさらに乱れるリスクもあるため、症状が長引く場合は医療機関で診察を受けるほうが賢明です。
- 大腸カメラ検査を受けるタイミングは?
-
便秘と下痢が続き、血便や体重減少、激しい腹痛などが伴う場合は検討をおすすめします。
40歳を超えたあたりから腸の病気のリスクが高まると言われているため、「これまで受けたことがない」という方は一度相談してみると安心感につながります。
- 便をやわらかく保つために気をつけることは?
-
適度な水分補給、バランスの良い食物繊維摂取、そして腸内細菌を意識した発酵食品の活用が基本です。生活リズムを整え、排便習慣を確立しておくことも重要なポイントです。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
検査前の食事や下剤の飲み方が不安な方へ。実際に準備を進める手順と当日の流れを写真付きで説明しており、初めてでも安心して検査に臨めます。
【腸の健康が体を支える 腸内環境を整える】
便秘と下痢を繰り返す背景には腸内環境の乱れが潜んでいます。腸活の基本と生活習慣の整え方を学び、長期的な体調管理に役立てましょう。
参考文献
Jamshed N, Lee ZE, Olden KW. Diagnostic approach to chronic constipation in adults. American family physician. 2011 Aug 1;84(3):299-306.
Tabbers MM, Boluyt N, Berger MY, Benninga MA. Clinical practice: diagnosis and treatment of functional constipation. European journal of pediatrics. 2011 Aug;170:955-63.
Corinaldesi R, Stanghellini V, Barbara G, Tomassetti P, De Giorgio R. Clinical approach to diarrhea. Internal and emergency medicine. 2012 Oct;7:255-62.
Wald A. Constipation: advances in diagnosis and treatment. Jama. 2016 Jan 12;315(2):185-91.
Sweetser S. Evaluating the patient with diarrhea: a case-based approach. InMayo Clinic Proceedings 2012 Jun 1 (Vol. 87, No. 6, pp. 596-602). Elsevier.
Getto L, Zeserson E, Breyer M. Vomiting, diarrhea, constipation, and gastroenteritis. Emergency Medicine Clinics. 2011 May 1;29(2):211-37.
Sharma A, Rao SS, Kearns K, Orleck KD, Waldman SA. Diagnosis, management and patient perspectives of the spectrum of constipation disorders. Alimentary pharmacology & therapeutics. 2021 Jun;53(12):1250-67.
Lacy BE, Levenick JM, Crowell M. Chronic constipation: new diagnostic and treatment approaches. Therapeutic Advances in Gastroenterology. 2012 Jul;5(4):233-47.
Faigel DO. A clinical approach to constipation. Clinical cornerstone. 2002 Jan 1;4(4):11-8.
Browning SM. Constipation, diarrhea, and irritable bowel syndrome. Primary Care: Clinics in Office Practice. 1999 Mar 1;26(1):113-39.










