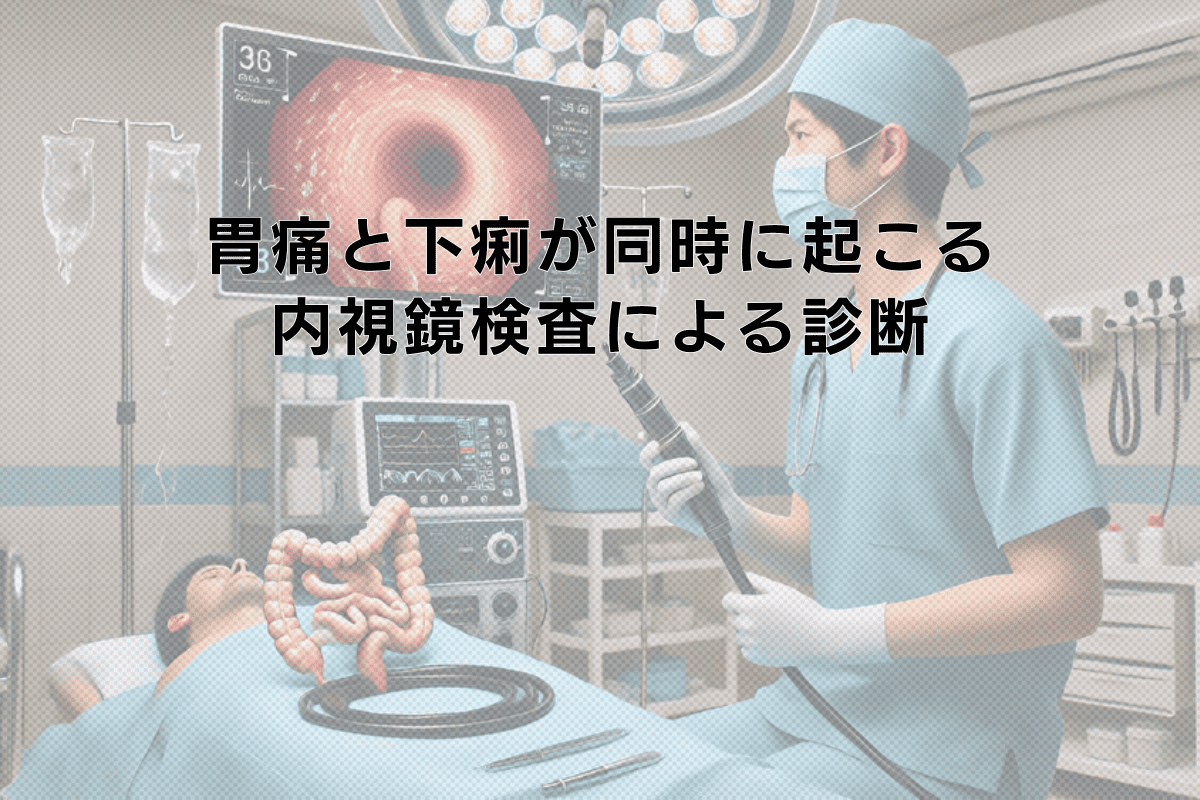胃痛と下痢が同時に起こると、普段の生活に大きな支障をきたし、急に襲ってくる腹部の痛みやトイレへ駆け込む不安は、仕事や学業、家事などに集中できなくなる要因となります。
加えて、これらの症状には潜在的に深刻な消化器の病気が隠れている場合もあるので、放置すると長期化したり重症化したりするリスクがあります。
原因には生活習慣の乱れやストレスなどさまざまなものが考えられますが、内視鏡検査によって明確に診断できるケースが多く、気になる症状が続く場合は早めに受診して原因を突き止めることが大切です。
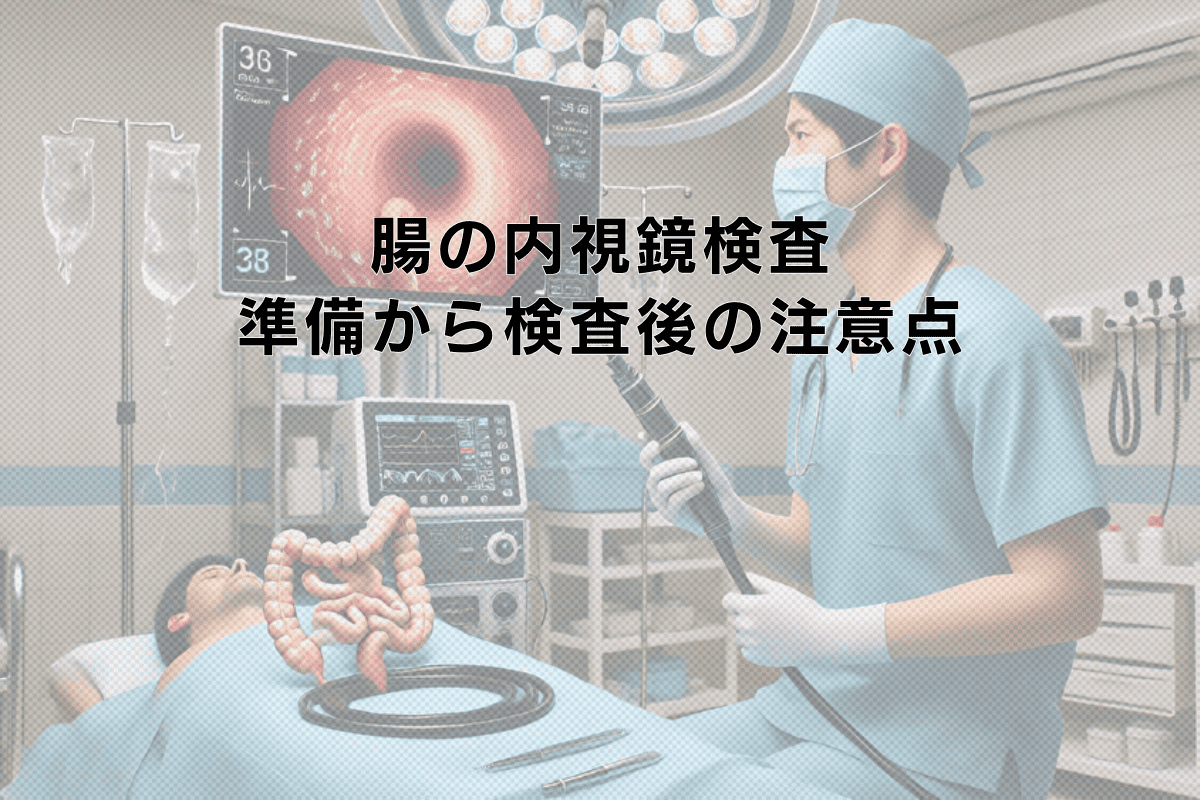
胃痛と下痢が同時に起こるメカニズム
胃痛と下痢が同時に起こる背景には、消化管全体の機能が乱れることが大きく関係します。胃腸は食べ物の消化と吸収を担う一方で、精神的な負担にも敏感で、原因を理解するためには、まず胃と腸の連携について知っておくことが重要です。
胃と腸の連動がもたらす影響
胃は食物を一時的に蓄え、十分に消化したうえで腸へ運び、腸は消化酵素や腸内細菌の働きによって栄養を吸収していきます。胃の状態が悪いと腸に負担をかける可能性があります。
胃痛を感じるタイミングと下痢のタイミングがほぼ同時になるのは、胃と腸が連動して刺激を受け、過剰に動いてしまうからです。こうした連鎖は、体調管理や検査によって早めに把握することが大切になってきます。
体内の水分バランスと電解質の変化
下痢が起こると大量の水分が腸管を通過し、通常であれば大腸で吸収されるべき水分が、腸の異常運動によって排出されることにつながります。
体内の水分バランスや電解質濃度が変化すると、胃痛を感じやすくなったり、さらなる下痢を誘発したりする要因となり、水分補給だけでなく、塩分やカリウムなどのバランスを整えることも考慮したいです。
胃痛と下痢が連動しやすい理由
胃痛と下痢が連動する主な理由には、消化管の神経支配が関係し、自律神経が乱れると、胃液や腸液の分泌量が急激に増えたり減ったりしやすく、胃もたれや急な腹痛が起こり、同時に下痢へとつながることがあります。
特に顕著になるのが、ストレスや生活習慣の乱れで、自律神経のケアと内視鏡検査などの医療的アプローチの併用が重要です。
胃痛と下痢が示す危険信号
症状が一時的で軽度であれば、食あたりや軽い感染症の可能性もありますが、同時に起こる胃痛と下痢が長期化する場合は、胃腸炎や潰瘍性大腸炎などの病気が隠れている場合があります。
特に便に血液が混ざる、強い嘔吐を伴うなどの症状が出ると、緊急対応が必要なケースも考えられ、放置せず専門医による診察と検査を受けることが大切です。
胃腸の状態と主な症状
| 状態 | よく見られる症状 | 注意したいサイン |
|---|---|---|
| 軽度の胃腸機能不調 | 胃のむかつき、軽い下痢 | 食後の不快感が長引く場合 |
| 過敏性腸症候群 | 下痢と便秘の繰り返し、腹痛 | 精神的ストレスとの関連が強い |
| 胃腸炎(感染性含む) | 発熱、吐き気、強い下痢 | 体重減少や高熱 |
| 潰瘍性大腸炎などの炎症 | 血便や粘液便、持続的な腹痛 | 排便回数の急増や倦怠感 |
| 重大な消化器疾患 | 長期間の下痢、胃痛の反復 | 血便、強い貧血、強い体重減少 |
考えられる背景とストレスとの関係
ストレスが重なると、自律神経のバランスが崩れやすくなり、胃と腸は神経ネットワークによって密接につながっているため、精神的な負担が肉体的な不調に直接反映されるケースが多いです。
胃痛 下痢 ストレスの関連を正しく理解し、原因を突き止めることが症状改善の近道になります。
ストレスが胃腸に与える影響
ストレスを感じると、交感神経が活発になり、胃酸の分泌量が増減したり腸管のぜん動運動が乱れたりし、緊張状態が続くと胃痛が起こりやすくなり、同時に腸が過剰な動きを示すことで下痢も誘発されやすくなります。
精神的ストレスが続く職場環境や、夜勤など生活リズムが崩れやすい人はこの傾向が強いです。

胃痛と下痢 同時 原因のひとつにある食生活の乱れ
ストレスが増すと、暴飲暴食や偏食に走る人もいますが、脂っこい食事や甘いものの過剰摂取、アルコールの飲み過ぎなどは、胃や腸に大きな負担をかけます。
ストレスからくる食欲不振や、逆にストレス解消を目的とした過食が続くと、胃腸の機能が低下して胃痛や下痢を同時に起こしやすいです。
ストレス性胃腸炎の特徴
ストレス性胃腸炎は、仕事や人間関係などで強い緊張を感じる人に多く見られ、特徴として、特に明確な器質的異常がないのに強い痛みや不調が続く点が挙げられます。
薬物療法だけでなくストレスマネジメントも重視され、内視鏡検査で大きな異常が見つからなかった場合でも生活習慣の改善に取り組むことが必要です。

ストレス軽減の心がけ
ストレスを完全に避けることは難しいかもしれませんが、適度な運動や趣味を楽しむ時間を増やす、十分な睡眠を確保するなどのセルフケアによって胃腸への負担を減らせる可能性があります。
ストレスと上手に付き合うことが、胃痛や下痢などの不快な症状を予防・軽減するうえで大切です。
胃腸トラブルに影響を与えやすいストレス要因
| ストレス要因 | 具体例 | 胃腸への影響 |
|---|---|---|
| 精神的負担 | 職場の人間関係、家族問題など | 自律神経の乱れ、胃酸過多 |
| 生活リズムの不規則 | 夜勤、徹夜、睡眠不足 | 胃腸運動の乱れ、過敏性腸症状 |
| 食生活の偏り | 暴飲暴食、甘い物の過剰摂取 | 胃腸への過度な負担、胃炎や下痢 |
| 運動不足 | デスクワーク中心の生活 | 代謝低下による便通不良や腹部膨満感 |
- 自分に合ったリラックス方法を見つける
- 無理のないスケジュールを組む
- 必要に応じて専門家へ相談する
症状を見極めるポイント
胃痛と下痢が続く場合、自己判断で軽視するのは避けたほうがよく、原因不明のまま放置すると、症状が慢性化したり悪化したりする可能性があります。
早めに専門医へ相談するためにも、いくつかの視点で症状を整理し、受診のきっかけをつかむことが大切です。
痛みの強さや継続時間
痛みの強さは人によって感じ方が異なりますが、激痛レベルの痛みが短時間で治まらず、断続的に繰り返す場合は深刻な病気が隠れていることがあります。
また、軽い痛みが何日も続く場合でも要注意で、痛みの継続時間と頻度を記録しておくと、医療機関での説明がスムーズです。
下痢の回数と便の性状
下痢が頻回に起こる場合は、急性の感染症だけでなく慢性的な炎症性腸疾患なども疑われ、便が水のようにさらさらしているのか、血液や粘液が混ざっているのか、色やにおいはどうかなど、観察しておくと診察の際に役立ちます。
下痢が長く続くほど体力や栄養状態が落ちていくので、早めの対処が必要です。
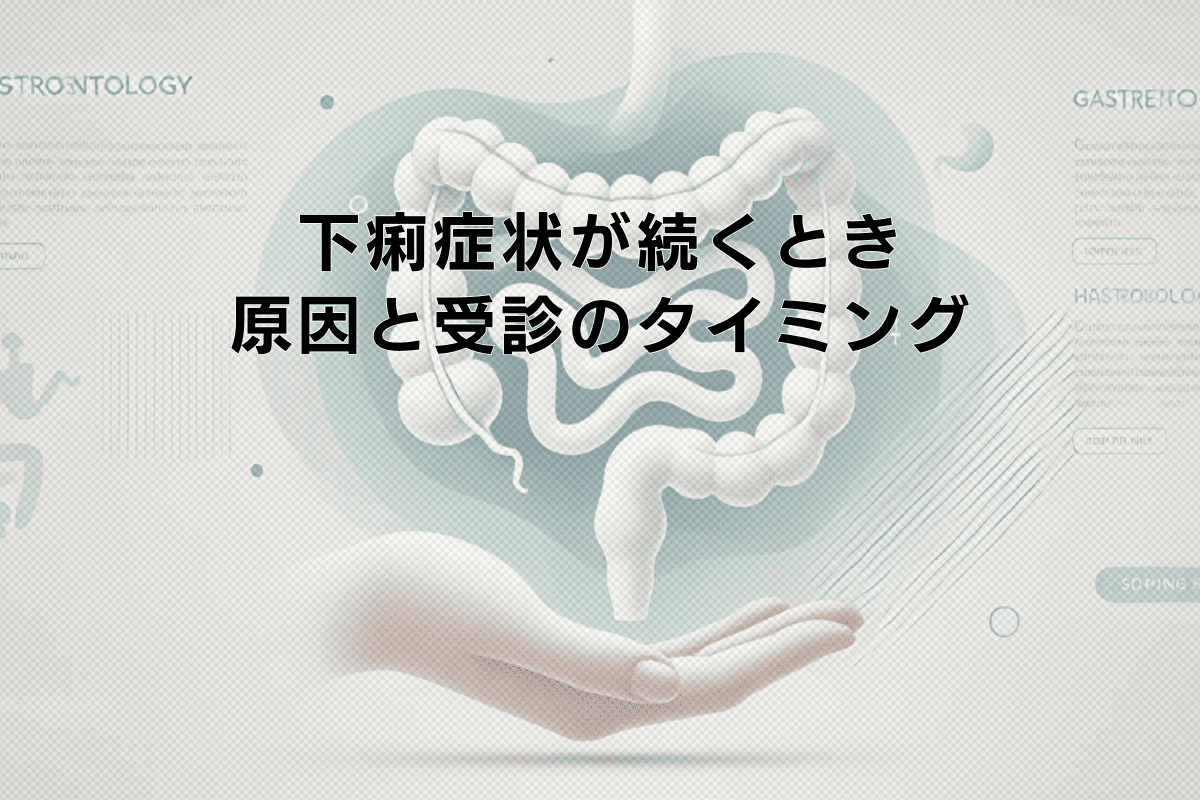
体温や体重の変化
胃痛と下痢を同時に感じている期間中に、発熱が伴うかどうか、体重が急激に減少していないかを確認すると、感染症や炎症性疾患などを予測しやすいです。
特に高熱が続く場合は、単なる食あたりではない可能性があり、慢性的な下痢により体重が落ちると栄養状態の悪化が懸念されます。
合併症や他の症状の有無
頭痛や吐き気、胸やけ、しびれなど、他の症状が一緒に出ている場合は消化器以外の病気も関連しているかもしれません。複数の症状が絡み合うと、自己判断だけで原因を特定するのが難しいので、専門医での診断が早期発見につながります。
消化器症状チェックの目安
| 観察ポイント | 具体例 | 注意すべき変化 |
|---|---|---|
| 痛みの種類 | キリキリする痛み、鈍い痛みなど | 持続時間が長い、夜間も強い |
| 下痢の性状 | 水様便、泥状便、血便など | 頻回に繰り返す、粘液や血が混ざる |
| 発熱の有無 | 微熱、38℃以上の高熱 | 連日続く熱、寒気や悪寒を伴う |
| 体重変動 | 急激な減少、減少の継続 | 1週間~2週間で2~3kg以上の減少 |
- 痛みの部位を明確にしておく
- 便の状態をメモに残す
- 発熱の有無をこまめに確認する
内視鏡検査の役割
胃痛と下痢を繰り返す場合、内視鏡検査を視野に入れるとより正確な診断が期待でき、胃や腸の粘膜を直接観察できるため、炎症や潰瘍などの有無を詳細に確認し、治療方針を決定しやすくなります。
内視鏡検査の基本的な流れ
医療機関で内視鏡検査を行う際は、医師が事前に問診や血液検査、超音波検査などを行い、検査の必要性やリスクを判断します。
検査当日には、消泡剤や腸管洗浄薬の服用など事前準備を行い、そのうえで内視鏡を挿入して胃や腸の中を観察し、医師は必要に応じて組織の一部を採取し、病理検査を行います。
内視鏡検査が示す利点
内視鏡では、小さな潰瘍や微細な出血点なども見逃しにくく、X線検査やCTスキャンではわかりにくい粘膜表面の変化を直接確認できるため、炎症や軽度の出血も発見しやすくなります。
さらにその場で組織検査の検体を採取することで、悪性疾患かどうかを早期に見極めることが可能です。
検査に対する不安への対処
内視鏡検査に対して「痛そう」「苦しそう」といった不安を感じる人は少なくありませんが、最近では鎮静剤を使用して検査中の苦痛を和らげる方法も一般的に行われています。
検査後は医師から検査結果の概要や治療方針の説明があるので、その場で疑問点を解消しやすいことが利点です。
除外診断のための価値
胃痛と下痢が同時に起こる原因には多くの疾患が含まれます。内視鏡検査によって粘膜の異常が見つからなかった場合でも、ほかの病気を除外できるという点で大きな価値があります。
逆に、わずかな異変をいち早く捉えて治療につなげることもできるため、長期的な視野で受けておくことが重要です。
内視鏡検査を考慮するタイミングと目的
| タイミング | 目的 | メリット |
|---|---|---|
| 症状が1か月以上続く場合 | 慢性化の有無を確認 | 炎症や潰瘍の早期発見 |
| 下血や血便が見られる場合 | 消化管出血の原因を特定 | 出血部位の特定と止血処置可能 |
| ポリープや腫瘍の疑いがある場合 | 悪性化リスクの有無を確認 | 微小な病変も発見可能 |
| 他検査で原因が特定できない場合 | 除外診断 | 不明原因の解明に役立つ |
胃カメラ検査でわかること
胃痛と下痢が同時に起こる原因の一部は、胃そのものの異常が腸に影響を及ぼしているケースです。胃カメラ検査(上部消化管内視鏡)は食道から十二指腸までを詳細に観察するため、胃痛のもととなる病変の有無を確認するのに適しています。
胃潰瘍や十二指腸潰瘍の発見
胃カメラ検査では、粘膜のただれや炎症の度合いなどを目視できるため、胃潰瘍や十二指腸潰瘍を正確に把握できます。
潰瘍があると、激しい胃痛だけでなく腸の動きにも影響を与え、下痢が続く可能性があり、治療薬の選択や再発防止の観点からも、潰瘍の有無を確認することは重要です。

ヘリコバクター・ピロリ菌との関連
ピロリ菌感染によって引き起こされる慢性胃炎は、胃痛の大きな要因となることが知られていて、胃カメラ検査の際に採取した組織からピロリ菌の有無を調べることで、感染症がある場合には除菌治療を検討できます。
ピロリ菌に長期間感染していると、下痢や消化不良が慢性化しやすいという報告もあります。

胃炎と食道炎の有無
軽度の胃炎や食道炎でも、症状が長引く場合は大きな苦痛を伴います。胃カメラ検査ではびらんや発赤などの軽微な炎症も見つけやすく、日頃からの食事指導や薬物治療に役立ちます。
特に逆流性食道炎があると、胃酸の逆流によって胸やけや喉の違和感が生じるだけでなく、消化の乱れで下痢を併発することがあります。
腹部不調の総合的なチェック
胃カメラで直接観察できるのは胃や十二指腸までですが、消化管の最上部を正確に把握することは下部消化管の異常を推測する助けにもなります。
例えば十二指腸の炎症が認められた場合、連鎖的に小腸や大腸の状態も観察すべき可能性もありますので、大腸カメラ検査を追加で行う判断材料となります。
胃カメラ検査により判明しやすい病変
| 病変名 | 特徴 | 関連する症状 |
|---|---|---|
| 胃潰瘍 | 胃酸の過剰分泌による粘膜障害 | 胃痛、吐き気、食欲不振 |
| 十二指腸潰瘍 | 胃酸やピロリ菌などで発症 | 腹部中央~右上部の痛み、夜間痛 |
| ヘリコバクター感染 | ピロリ菌による慢性的な胃炎 | 胃のむかつき、慢性的な痛み |
| 逆流性食道炎 | 胃酸逆流による食道粘膜のただれ | 胸やけ、呑酸、喉の違和感 |
| 表在性胃炎 | 胃表面の炎症 | 軽い胃痛、慢性的な胃もたれ |
- 食後の痛みが治まらないときに受診を検討する
- ピロリ菌除菌の有無を医師に確認する
- 胃酸逆流が続く場合は胃カメラを検討する
大腸カメラ検査でわかること
下痢が長引く場合や血便が確認される場合、あるいは腹痛が続くときには大腸カメラ検査(下部消化管内視鏡)の実施が考えられます。
大腸カメラでは大腸全体と一部の小腸を直接観察でき、炎症性腸疾患やポリープ、がんなどの有無を判別しやすいです。

大腸の炎症や潰瘍の発見
大腸に生じる潰瘍性大腸炎やクローン病は、下痢や血便、腹痛が長期化する特徴があり、大腸カメラを用いることで腸壁の炎症の程度や範囲を明確に把握し、薬物治療を行いやすくなります。粘液便や血便が続く人は早めの検査が望ましいです。
ポリープや腫瘍の発見
大腸ポリープや大腸がんは、初期には自覚症状がほとんどない場合がありますが、下痢を起こすことや、便が細くなる、便通のリズムが変わるなどの症状が出るケースもあります。
大腸カメラ検査ではポリープを見つけた段階で切除できることもあり、悪性化のリスクを抑えるうえでも意義が大きいです。
炎症性腸疾患と合併症の有無
潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患は、大腸と小腸の両方にわたる病変が生じます。大腸カメラ検査は炎症の広がりだけでなく、狭窄や瘻孔などの合併症の有無も確認しやすいです。
合併症が進行すると治療が複雑になるため、早期に発見できるかどうかが重要になります。
症状との対応関係の評価
下痢が続くタイミングや痛みの部位、出血の具合を医師にしっかり伝えることで、検査中に疑わしい部位を集中的に観察できます。
大腸カメラ検査後に得られる情報を基に、薬剤の選択や生活指導が行いやすくなり、症状のコントロールに役立ちます。
大腸カメラ検査で確認する主な項目
| 項目 | 具体例 | 主な症状 |
|---|---|---|
| 粘膜の炎症程度 | 潰瘍性大腸炎、クローン病 | 血便、腹痛、長引く下痢 |
| ポリープの有無 | 腫瘍性ポリープ、腺腫など | 無症状の場合も多い |
| 腫瘍 | 大腸がん、早期がん | 便が細くなる、便通異常 |
| 小腸末端部の異常 | クローン病が小腸にも及ぶ場合 | 強い腹痛、痩せ、血便 |
| 狭窄や出血箇所 | 腸管の狭窄、出血の有無 | 急激な腹痛、貧血、便秘と下痢の繰り返し |
- 血便を見たら早めに受診する
- 下痢の原因不明が続けば検査を検討する
- 腹痛と便通異常の繰り返しは軽視しない
日常生活で気をつけたい習慣
胃痛と下痢を同時に起こしやすい人は、生活習慣を見直すだけで症状が緩和する可能性があり、検査によって大きな病気が見つからなかった場合でも、再発を防ぐために日常的なケアが重要です。
食事のタイミングとバランス
不規則な食事時間や偏った内容は胃腸に強い負担をかけ、朝食を抜く、夜遅い時間にたくさん食べる、などの習慣が続くと、胃の働きが乱れて下痢につながりやすいです。
できるだけ同じ時間帯に腹八分目を心がけ、野菜やたんぱく質、炭水化物をバランスよく摂ることを意識すると、胃腸の調子が整いやすくなります。
水分補給とミネラル摂取
下痢が続くと体内の水分だけでなく電解質も失われるので、スポーツドリンクや経口補水液などを利用し、水分とミネラルを適度に補給しましょう。
カフェインやアルコールは利尿作用があり、体内の水分を余計に失いやすいため、胃痛や下痢が続いているときは控えるほうが無難です。
ストレスケアと睡眠
ストレスが胃痛や下痢を引き起こす大きな要因となる場合、リラックスできる時間を増やすことが大切で、軽い運動や入浴など、心身の緊張をやわらげる工夫を取り入れると、消化管の動きも安定しやすいです。
睡眠不足は自律神経を乱すので、質の良い睡眠を十分な時間確保すると不調の改善につながります。
体調管理と適度な運動
運動不足が続くと血行が悪くなり、胃腸の機能も低下しやすくなります。激しいスポーツではなくウォーキングや軽いストレッチなどの有酸素運動で十分です。
腸への刺激が穏やかに加わることで、便通のリズムも整いやすくなるので、毎日の生活のなかに少しずつ運動を取り入れてください。
胃腸の負担を減らすための食事選択
| 食品グループ | おすすめ例 | 控えめにしたい例 |
|---|---|---|
| 炭水化物 | 白米、全粒粉パン、うどん | 揚げ物が多い麺類、過度な糖分 |
| たんぱく質 | 魚、鶏肉、豆腐 | 高脂肪の肉類、過度な加工肉 |
| 野菜・果物 | にんじん、かぼちゃ、バナナ | 刺激の強い香辛料、未熟果物 |
| 乳製品 | プレーンヨーグルト、発酵食品 | 冷たい牛乳、過剰なチーズ |
| 飲料 | 常温の水、お茶、経口補水液 | アルコール、カフェイン |
- 毎日少しでも歩く時間をつくる
- 睡眠前のスマホ利用を減らし、熟睡を促す
- 甘い物や刺激物はほどほどにしておく
体調管理のポイントと注意点
| 項目 | 内容 | 継続的に意識したいこと |
|---|---|---|
| 食事バランス | 主食・主菜・副菜を組み合わせる | 一度に大量に食べず小分けに摂取 |
| 水分補給 | こまめな水分と塩分補給 | アルコールや刺激物の過剰摂取を避ける |
| ストレス発散 | 適度な運動や趣味時間 | 全く休みがない生活リズムを改める |
| 定期的な受診 | 症状が続く場合は内視鏡検査も検討 | 早期発見と早期治療の意識 |
よくある質問
- 胃痛と下痢が同時に起こってもすぐに内視鏡検査を受けるべきですか?
-
短期的で軽い症状であれば、まずは食生活や睡眠の見直しを行い、症状が改善するかを確かめる方法があります。
ただし、強い痛みが繰り返す、血便があるなどの場合は早めに専門医を受診し、内視鏡検査を含めた検査を受けるかどうか相談してください。
- ストレスによる症状と診断された場合は、薬だけで治せますか?
-
薬物療法は胃酸の分泌を抑えるなど、症状の軽減に有効な場合がありますが、ストレスの根本を解消しないと、また同じような症状が出やすくなります。
休養やリラクゼーションを心がけ、ストレスを軽減する工夫をあわせて行うことが大切です。
- 大腸カメラ検査は痛くないのでしょうか?
-
近年では鎮静剤を用いた検査が普及しており、不快感を最小限に抑えられることが多く、検査中に強い痛みを感じる際は医師が状況を確認し、カメラの挿入や検査方法を調整してくれます。
不安な点があれば事前に医師や看護師へ相談しましょう。 - 胃カメラと大腸カメラの両方を受けるメリットはありますか?
-
胃痛と下痢が同時に続くとき、上部と下部の両方に原因が潜んでいる可能性があり、胃カメラと大腸カメラを両方行うことで、消化管の全体像を把握しやすくなり、原因の取りこぼしを減らせます。
医師と相談し、自分の症状やリスクに合わせて検討することが望ましいです。
次に読むことをお勧めする記事
【腸の内視鏡検査で分かること – 検査前の準備から検査後の注意点】
胃痛と下痢の原因について理解できたら、次は実際の内視鏡検査について知っておくと安心です。検査を検討されている方に特に参考になる内容です。
【胃痛原因と予防のポイント 食事・ストレスとの関係を見直す】
胃痛と下痢について学んだ皆さんには、胃痛の原因をより詳しく知っていただくと、より包括的な理解と対策ができます。
参考文献
Shen B, Khan K, Ikenberry SO, Anderson MA, Banerjee S, Baron T, Ben-Menachem T, Cash BD, Fanelli RD, Fisher L, Fukami N. The role of endoscopy in the management of patients with diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2010 May 1;71(6):887-92.
Haryal A, Townsend MJ, Baskaran V, Srivoleti P, Giobbie‐Hurder A, Sack JS, Isidro RA, LeBoeuf NR, Buchbinder EI, Hodi FS, Grover S. Immune checkpoint inhibitor gastritis is often associated with concomitant enterocolitis, which impacts the clinical course. Cancer. 2023 Feb 1;129(3):367-75.
Hori K, Matsumoto T, Miwa H. Analysis of the gastrointestinal symptoms of uninvestigated dyspepsia and irritable bowel syndrome. Gut and liver. 2009 Sep 30;3(3):192.
Hibbard ML, Dunst CM, Swanström LL. Laparoscopic and endoscopic pyloroplasty for gastroparesis results in sustained symptom improvement. Journal of Gastrointestinal Surgery. 2011 Sep 1;15(9):1513-9.
Ross WA, Ghosh S, Dekovich AA, Liu S, Ayers GD, Cleary KR, Lee JH, Couriel D. Endoscopic biopsy diagnosis of acute gastrointestinal graft-versus-host disease: rectosigmoid biopsies are more sensitive than upper gastrointestinal biopsies. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2008 Apr 1;103(4):982-9.
Verschuren EC, van den Eertwegh AJ, Wonders J, Slangen RM, van Delft F, van Bodegraven A, Neefjes-Borst A, de Boer NK. Clinical, endoscopic, and histologic characteristics of ipilimumab-associated colitis. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2016 Jun 1;14(6):836-42.
Boston SE, Moens NM, Kruth SA, Southorn EP. Endoscopic evaluation of the gastroduodenal mucosa to determine the safety of short-term concurrent administration of meloxicam and dexamethasone in healthy dogs. American Journal of Veterinary Research. 2003 Nov 1;64(11):1369-75.
Cappell MS, Friedel D. The role of sigmoidoscopy and colonoscopy in the diagnosis and management of lower gastrointestinal disorders: endoscopic findings, therapy, and complications. Medical Clinics. 2002 Nov 1;86(6):1253-88.
Pearlman M, Covin Y, Schmidt R, Mortensen EM, Mansi IA. Statins and lower gastrointestinal conditions: a retrospective cohort study. The Journal of Clinical Pharmacology. 2017 Aug;57(8):1053-63.
Fry LC, Carey EJ, Shiff AD, Heigh RI, Sharma VK, Post JK, Hentz JG, Fleischer DE, Leighton JA. The yield of capsule endoscopy in patients with abdominal pain or diarrhea. Endoscopy. 2006 May;38(05):498-502.