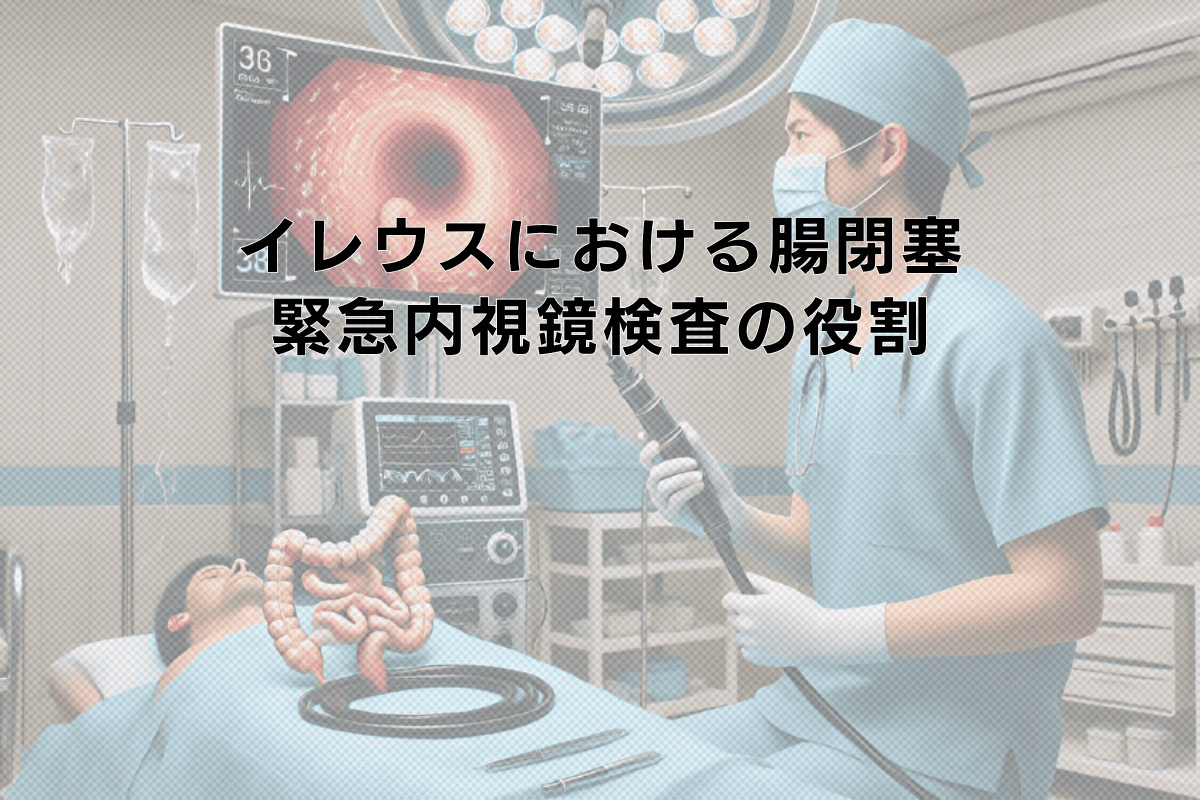腸の通過障害によって激しい腹痛や嘔吐を起こす状態として知られるイレウスや腸閉塞は、突然の症状が現れることも多く、日常生活に大きな支障を及ぼします。
特に、原因の特定が難しい場合や強い痛みがあるときには、緊急内視鏡検査で早めに原因を突き止めて治療を始めることが大切です。
この記事では、イレウスと腸閉塞の違いや原因から緊急内視鏡検査を用いたアプローチまでを分かりやすく解説し、治療の選択肢を知るきっかけになればと考えています。
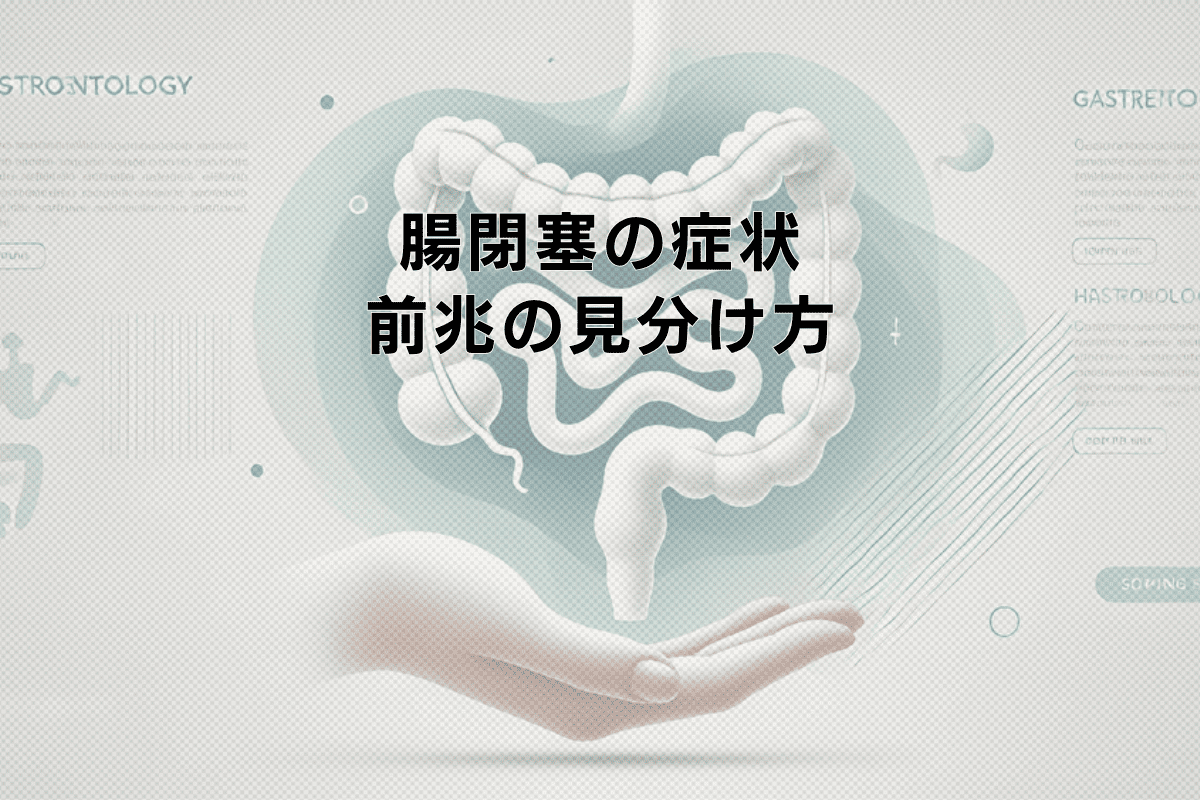
イレウスと腸閉塞の基礎知識
イレウスと腸閉塞は似たような用語として扱われる場合が多いですが、実際にはやや異なる背景や意味を持つことがあります。細かい違いを理解することが治療を行ううえで重要です。
イレウスと腸閉塞の定義
イレウスとは、腸管が物理的に閉塞しているかどうかにかかわらず、腸管内の内容物が通過できない状態を指し、腸閉塞という言葉は、おもに大腸や小腸の物理的な閉塞により腸内容が通過できなくなった状態を表します。
イレウスという用語自体は機能的なトラブルによる場合も含む幅広い概念であり、腸閉塞は主に機械的な閉塞に焦点を当てていると理解するのが一般的です。
イレウス・腸閉塞に関する誤解
イレウス・腸閉塞という表現を目にすることがありますが、「イレウス」と「腸閉塞」が全く同じ意味で使われる場合と、微妙に異なる意味を含む場合もあります。
最近のガイドラインでは「腸閉塞」と「イレウス」を区別して使うよう提案されています。
- 「イレウス」は機能的な原因、あるいは機械的な原因を含む広義の概念
- 「腸閉塞」は物理的に閉塞している状態を指す場合が多い
イレウスと腸閉塞の違いについて
イレウスと腸閉塞の違いを正確に知るには、医療現場でどのように診断され、どのように治療されているかを理解することが大切です。
医師は症状や検査画像から腸管が機能的に動いていないのか、それとも物理的に詰まっているのかを見極めます。
イレウスと腸閉塞の特徴比較
| 種類 | 原因の特徴 | 治療アプローチ |
|---|---|---|
| 機能的イレウス | 腸管自体の動きが低下または停止している | 薬物治療、腸管刺激、点滴管理など |
| 機械的イレウス(腸閉塞) | 腸管が物理的に閉鎖または狭窄している | 外科的治療、内視鏡的治療、減圧処置など |
| 混合型 | 機能低下と一部の物理的閉塞が同時に存在する場合 | 状況に応じて複合的なアプローチを行う |
こうした違いを踏まえて診療を行うことにより、不必要な手術や治療の延長を防ぎ、適切な処置を見極めやすくなります。
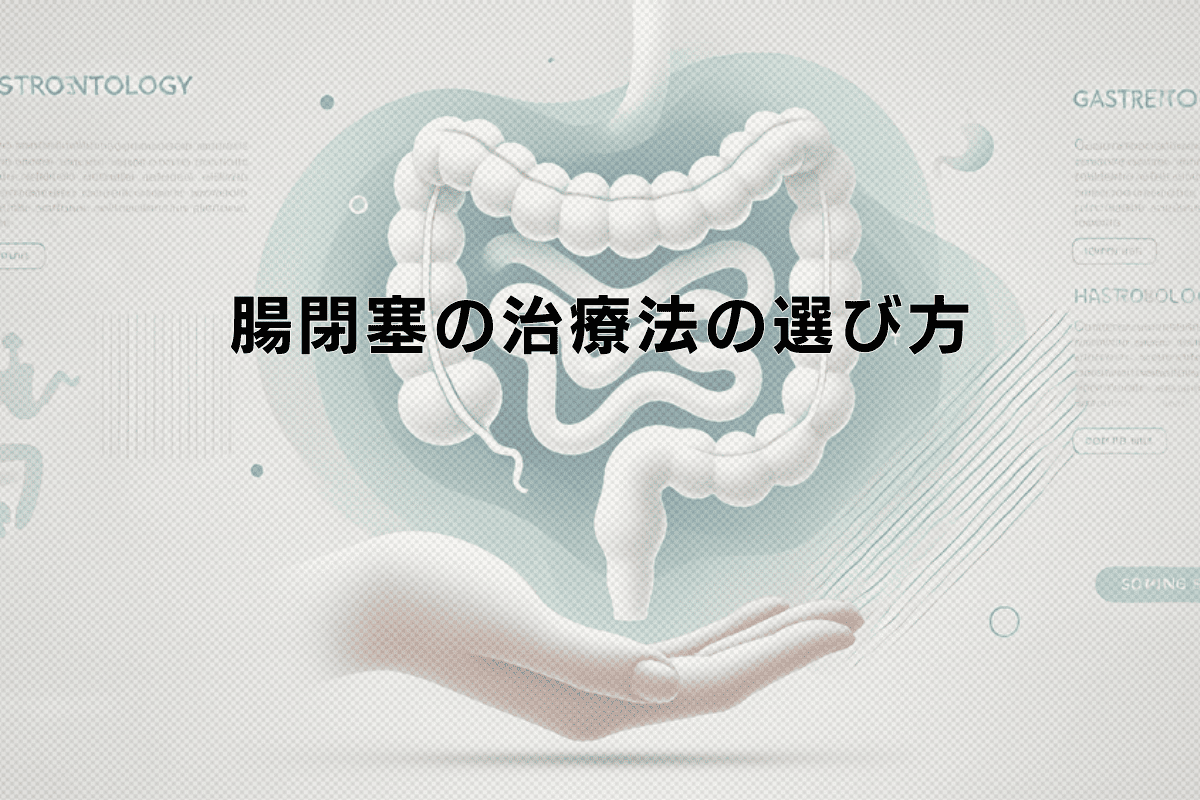
イレウスが起きるしくみ
イレウスは腸管の運動機能が低下して、内容物がうまく送れなくなる状態です。
手術後に腸が動かなくなる「術後イレウス」もよく知られていて、腸管の蠕動(ぜんどう)運動が何らかの要因で低下すると、ガスや内容物が溜まり、激しい膨満感や嘔吐を伴うことがあります。
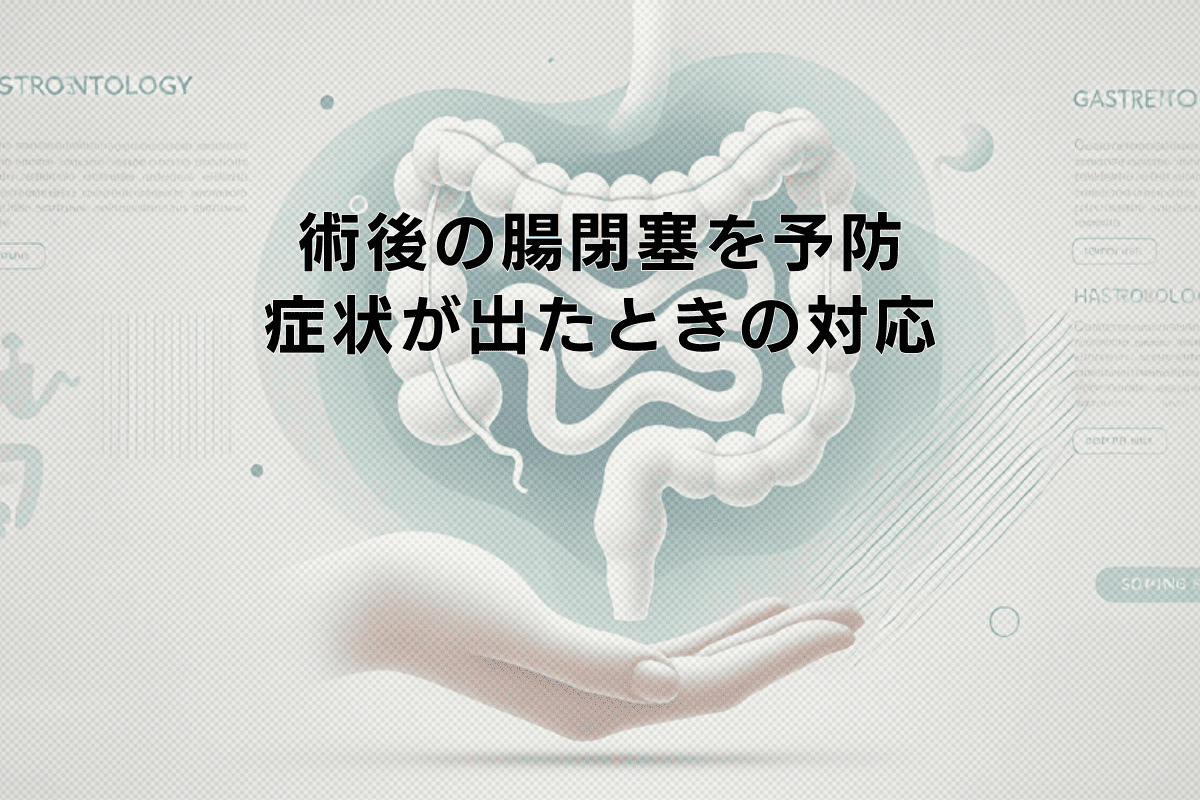
イレウス・腸閉塞の主な症状とメカニズム
イレウス・腸閉塞では、腸の通過障害により内容物が先へ進まずに滞るため、腹痛や嘔吐、食欲低下などが起こります。
原因が機能的か機械的かによって対処方法が大きく変わるため、これらの症状を正確に把握し、メカニズムを理解しておくことが大切です。
腹痛や嘔吐の特徴
腸内の圧力が高まることで、激しい腹痛や嘔吐が生じます。特徴的なのは、腸管が閉塞している部位より上流側に内容物がたまり、吐き気を催すことです。痛みの程度や嘔吐の回数・タイミングは閉塞部位や原因によって異なります。
- 小腸閉塞:嘔吐が起こりやすく、腹痛が周期的に起こることが多い
- 大腸閉塞:便やガスの排泄が止まり、腹部の膨満感が強くなる場合が多い

腸内圧の増大が引き起こす合併症
腸内圧が過度に高くなると、腸壁の血液循環が障害されるリスクがあり、血流障害が長時間持続すると腸壁の壊死(えし)につながり、穿孔(腸に穴が開くこと)を起こして腹膜炎を発症する場合もあります。
このような重篤な状態に陥ると、緊急の外科手術が必要です。
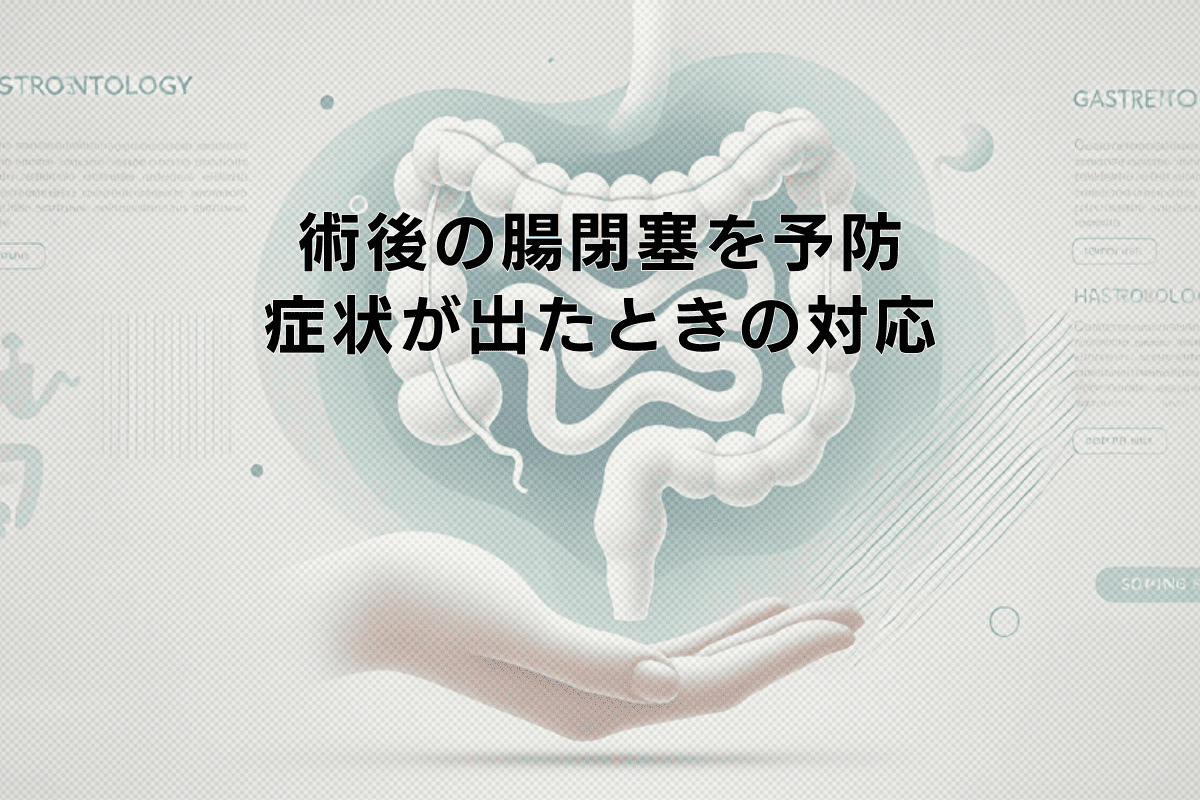
腸管圧上昇時に起こりうる変化
| 変化 | 具体例 |
|---|---|
| 血流障害 | 腸壁の壊死、潰瘍化 |
| 体液シフト | 血液中の水分が腸管内に移行し脱水が進む |
| 全身的な炎症反応 | 発熱、白血球増加、腹膜刺激症状 |
| 周辺組織への悪影響 | 近隣の臓器へ炎症が波及する可能性 |
こうした変化は短時間で急激に進行することがあり、早期の対処が重要です。
機能性イレウスに多い症状
機能性イレウスの場合、腸そのものの蠕動運動が大幅に低下していることが主な原因となるため、腹痛の強さは比較的軽いものの持続することがあり、また、便が出ない、排ガスがない、食欲低下が続くなどの症状が長引きます。
機能性イレウスでは、腸管造影や内視鏡検査を行っても物理的閉塞は確認されないことが多いです。
機械的イレウス(腸閉塞)に多い症状
物理的な閉塞がある場合は、腹痛が周期的に波打つように襲ってくるのが特徴で、閉塞部位より上の腸管が強く収縮し、閉塞部分を何とか乗り越えようとするため、痛みや嘔吐を伴うケースが多々あります。
結腸がんなどの腫瘍が原因の場合、便秘の既往や血便などがヒントになることもあります。
腸閉塞の原因とリスク要因
腸閉塞の原因は多岐にわたり、過去の腹部手術歴や高齢者特有の腸管の変化、がんなどが関与する場合があり、日常生活で見落とされがちなリスク要因もあるため、原因とリスクを正しく把握することが必要です。
腸閉塞の原因は一つではなく、複数の要因が重なり合い、患者さん個々人が抱えるリスクや既往歴によって、治療内容や経過観察の必要性が大きく変わってきます。
代表的な原因
- 癒着(ゆちゃく):過去の腹部手術や炎症などで腸管が周囲組織とくっつき、腸の動きを制限する
- 腫瘍:大腸がん、小腸の腫瘍が通過障害を引き起こす
- 鼠径ヘルニア:腸の一部が押し出され、閉塞や壊死を引き起こす
- 憩室炎や炎症性腸疾患:炎症や腫脹により腸管が狭くなり、腸閉塞の原因となる
高齢者のリスク要因
高齢になると腸管の動きが弱まるうえ、便秘を起こしやすくなり、さらに、加齢による腸管の狭窄や複数の基礎疾患が絡み合うことでイレウスや腸閉塞を生じやすくなります。
高齢者は脱水症状にも陥りやすいため、発症した際の重症化リスクが高いです。
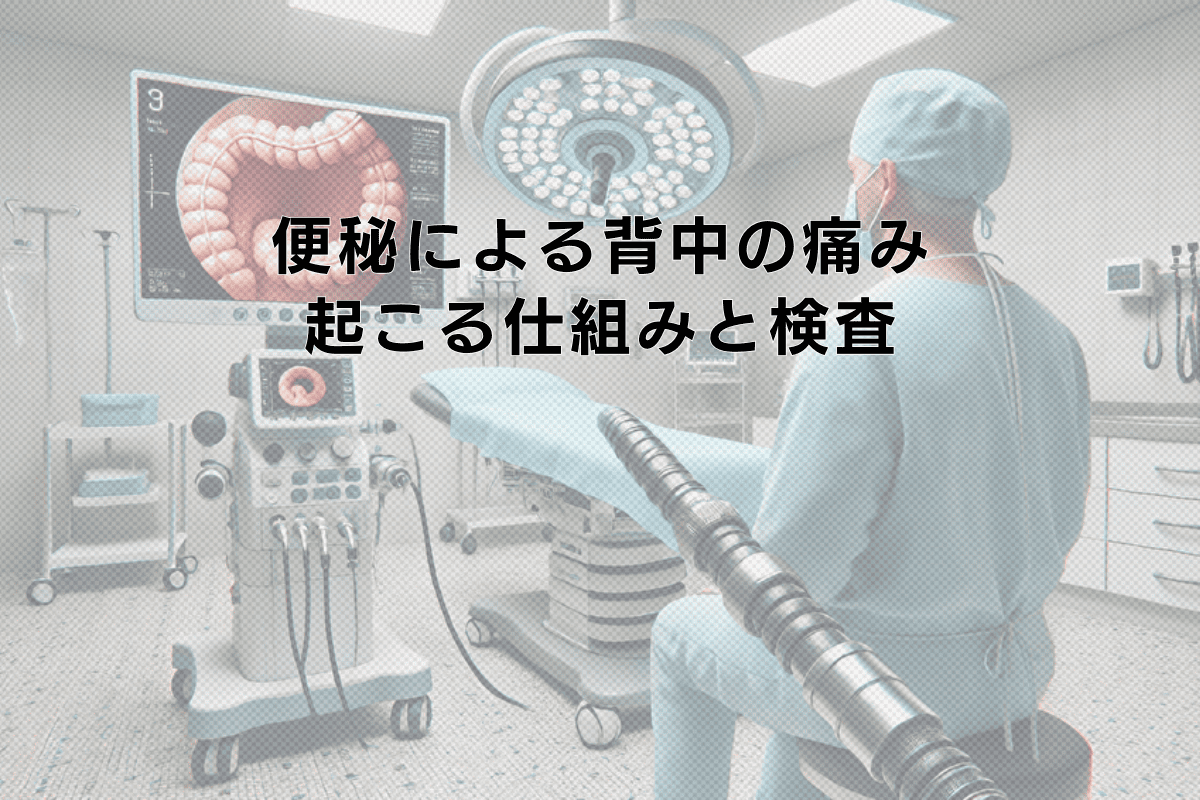
高齢者が気をつけたい点
| リスク要因 | 詳細 | 予防策 |
|---|---|---|
| 便秘 | 加齢、食物繊維不足 | 水分摂取、食物繊維摂取、適度な運動 |
| 筋力低下 | 腹筋の衰え、身体活動量の減少 | 体操や散歩などの軽い運動 |
| 基礎疾患の併発 | 糖尿病、高血圧、心臓病など | 定期受診、医師との相談により投薬・治療方針を調整 |
| 多種類の内服薬 | 下剤や利尿剤など | 内服薬の使用状況を医師に伝え、副作用を最小限にする |
術後イレウス
手術後に腸管の動きが低下してイレウスを起こすことがあり、これは腸管自体が麻酔や手術侵襲の影響を受け、しばらく動きづらくなることが背景にあります。
術後イレウスは自然に改善する場合もありますが、長引いて嘔吐や腹部膨満が強くなった場合は対処が必要です。
腸閉塞を招く食習慣や生活習慣
急激な食事量の増加、偏食、暴飲暴食などは腸管に大きな負担をかけ、また、不十分な咀嚼や水分不足、過度なストレスも腸管機能を低下させる原因になり得ます。
過去に腸閉塞を起こした経験がある人は、食事の内容や食べ方にも注意してください。
緊急内視鏡検査の重要性
強い腹痛や嘔吐、あるいは「腸閉塞ではないか」と疑われる症状が急に現れた場合、緊急の対応が必要になることがあります。放置すると腸管の血行障害や腹膜炎に至り、生命の危険を伴う場合もあるからです。
こうしたときに有用となるのが内視鏡検査で、腸内の状態を直接確認できる強みがあります。
緊急内視鏡検査を行うことで、閉塞の原因部位や種類を特定するだけでなく、その場で簡易的な治療を行うことも期待できます。
早期の原因特定と治療方針の決定が合併症予防に大きく役立つため、イレウス・腸閉塞が疑われる場合には前向きに検討すべき選択肢です。
内視鏡による診断が有効な理由
画像検査だけでははっきりしない微妙な狭窄や腸内の状態を、直接観察できる点は大きな利点です。
腸管造影やCT検査では捉えにくい粘膜の状態や局所的な病変を内視鏡で視覚的に把握でき、がんが閉塞を起こしている場合も速やかに発見できます。

緊急下での内視鏡検査の流れ
緊急内視鏡検査を行う際は、患者さんの全身状態やリスクを総合的に判断し、安全対策を整えたうえで実施し、点滴などを行い、脱水や電解質異常を補正したり、鎮静剤の使用を検討したりしながら進めます。
- 患者の状態評価(バイタルサイン、血液検査など)
- 前処置(腸管内容の排出や鎮静剤の選択など)
- 内視鏡の挿入と観察、必要があればその場で処置
- 検査後の安静・経過観察
治療的内視鏡の可能性
腸閉塞が腸内のポリープによって起こっている場合は内視鏡を使って除去することができ、また狭窄部分をバルーン拡張して通過を改善させることも検討することが可能です。
このように、内視鏡は単なる診断だけでなく、治療の一環としても期待できます。
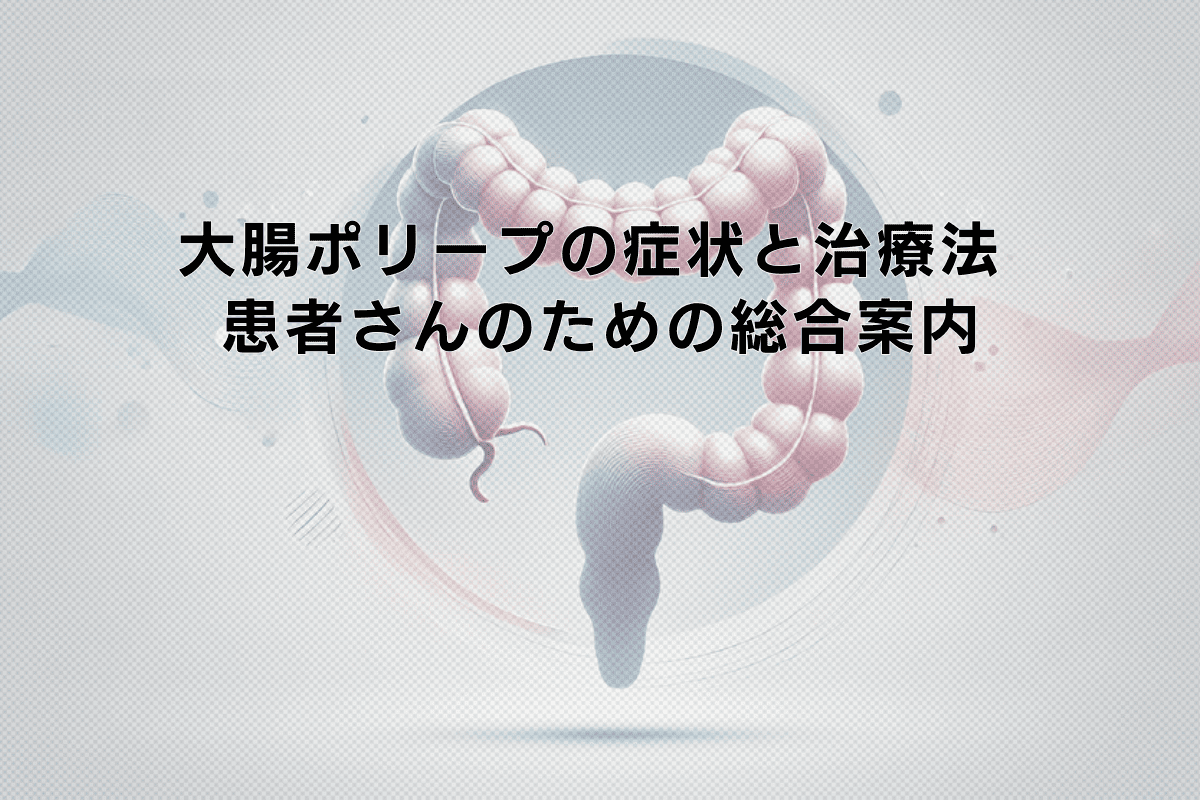
内視鏡で対応可能な主な処置
| 処置方法 | 対応できる病態 | 具体的な利点 |
|---|---|---|
| ポリープ切除 | 大腸ポリープ、小腸ポリープなど | がん化リスクを下げ、通過障害を軽減 |
| 異物除去 | 胆石、固形物など | 外科手術を回避できる可能性がある |
| バルーン拡張術 | 狭窄部位、術後吻合部狭窄 | 通過障害の緩和と症状改善に貢献 |
| ステント留置 | 癌による狭窄など | 一時的または長期的に通過路を確保できる |
内視鏡検査による診断と治療
内視鏡検査は、胃カメラと呼ばれる上部消化管用のものと、大腸カメラと呼ばれる下部消化管用のものが一般的ですが、緊急時には大腸カメラを応用して回盲部や小腸の一部まで確認することもあります。
また、口から小腸へアプローチする場合は小腸用の内視鏡を使用する場合もあります。腸閉塞が疑われる場合には、患者さんの状態によってどの方法を選ぶかを専門医が見極めることが大切です。
内視鏡検査で原因を特定できれば、腸内の圧迫部位や狭窄の程度によって治療の方向性を判断しやすくなり、外科的治療が必要な場合でも、術前に内視鏡で正確な情報を得ることで手術の範囲や方法を決める助けになります。

小腸内視鏡と大腸内視鏡
腸閉塞の原因が小腸にあるのか大腸にあるのかで検査方法が異なります。
大腸に問題があると考えられる場合は、大腸内視鏡で直腸から盲腸周辺までしっかり観察し、小腸の病変が疑われるときには口ないしは肛門から小腸までカメラを進める小腸内視鏡が検討されます。
胃カメラと大腸カメラの比較
| 項目 | 胃カメラ | 大腸カメラ |
|---|---|---|
| アプローチ部位 | 食道、胃、十二指腸 | 直腸、大腸(盲腸まで) |
| 対象とする症状 | 胃痛、吐血、胸やけなど | 血便、下痢、便秘、大腸ポリープなど |
| 検査時の前処置 | 6時間以上の絶飲食など | 下剤で腸を空にする、水分補給など |
| 緊急時の活用場面 | 消化管出血、重度の胃潰瘍など | 重度の大腸出血、大腸閉塞の確認など |

内視鏡検査後の治療方針
内視鏡検査を通じて、ポリープやがんが原因だった場合には切除やステント留置を検討しますが、癒着が強いなど内視鏡では対応が困難なケースの場合、外科手術に切り替えることが必要です。
どの治療を選択するかは、患者さんの全身状態や症状の進行度も含めて総合的に判断します。
内視鏡検査による患者負担
腸閉塞時に行う緊急内視鏡検査は、通常の健康診断目的の内視鏡検査よりも前処置が難しいケースが多く、吐き気が強く下剤の内服が困難だったり、体力の低下により鎮静剤の使用を慎重に検討したりする必要があります。
これらは医療スタッフの管理のもとで対応するため、不安があるときには主治医や看護師に相談しながら進めることが大切です。
内視鏡とその他の検査の組み合わせ
CT検査やX線検査、超音波検査などを先行させ、内視鏡単独ではわかりにくい腸の周辺臓器の状態を、画像検査で補足すると判断がしやすいです。
複数の検査を組み合わせることで、腸閉塞の原因をより正確に突き止められる可能性が高まります。
内視鏡検査前後の注意点
イレウスや腸閉塞が疑われる段階で内視鏡検査を受ける際には、患者の状態に合わせた準備やアフターケアが必要です。とくに検査前の食事や水分摂取は腸内環境に直接影響を及ぼし、検査の正確性に関わってきます。
体力が落ちている場合や高齢の方は、検査当日の移動や待ち時間に配慮し、検査後もしばらくは食事や活動量に制限が必要なケースがあるので、担当医やスタッフの指示をよく聞き、トラブルを最小限に抑える工夫をすることが大事です。
検査前の食事制限
腸閉塞が強く疑われる場合は、飲食物の摂取自体が困難なことも多く、場合によっては点滴のみで栄養や水分を補給して、腸を安静に保つ方法が選ばれます。
- 水分摂取は少量ずつ行い、嘔吐がある場合は無理をしない
- 食事を取ることができる場合は、消化に負担のかからないやわらかい食物を中心にする
検査当日の移動と準備
緊急内視鏡検査のケースでは、救急搬送されてくることもあるため、特別な準備が難しいかもしれません。
しかし、意識がはっきりしている患者さんの場合は、なるべく付き添いの家族や友人と連絡を取り、検査後の帰宅手段などを確保しておくと安心です。
内視鏡検査を受けるときに意識したいポイント
- 体力に不安がある場合はスタッフに早めに伝える
- 鎮静剤を使用するかどうか、医師と相談して決める
- 乗り物で受診する場合は吐き気や痛みに備えてビニール袋などを用意する
検査後の安静と食事再開
内視鏡検査後は、腸管が刺激を受けて一時的に動きにくくなる場合もあり、高齢者や持病のある方は、検査後の合併症リスクを軽減するためにしばらくベッドで安静にすることが多いです。
安静時間や食事再開のタイミングは、医師やスタッフが状態を見ながら慎重に決定します。
内視鏡検査後に注意する症状
| 症状 | 意味合い・注意点 |
|---|---|
| 腹痛 | 一時的なガス膨満や腸の過敏反応かもしれないが、強い痛みが続く場合は要連絡 |
| 発熱 | 感染症や穿孔が疑われる可能性もあるため注意が必要 |
| 下痢・出血 | 検査による刺激による軽微なものか、病変によるものかを判断する必要がある |
検査後の治療方針決定
内視鏡検査で閉塞の原因部位や性質がわかった場合、医師は外科的治療が必要なのか、あるいは内視鏡的治療で十分対応できるかを検討します。術後のフォローアップや再発防止策についても、検査結果をもとに方針を固めていく流れです。
医療機関の受診のタイミングと選び方
強い腹痛や嘔吐が続き、「もしかして腸閉塞ではないか」と疑う状況があれば、できるだけ早めに医療機関を受診して検査を受ける必要があります。
しかし、どのようなタイミングで受診すればよいのか、どの科を訪れればよいのかといった迷いを感じる方も少なくありません。
負担を軽減しながら迅速に診断や治療を行うには、患者自身が自分の症状や状態をできるだけ詳細に医療者へ伝えることも大切です。
受診の目安
- 激しい腹痛や断続的な嘔吐がある
- 便が数日間まったく出ない、ガスも出ない
- 腹部が張って苦しい、食事がほとんど取れない
- 過去に腸閉塞を起こした経験があり、同様の症状が再発している
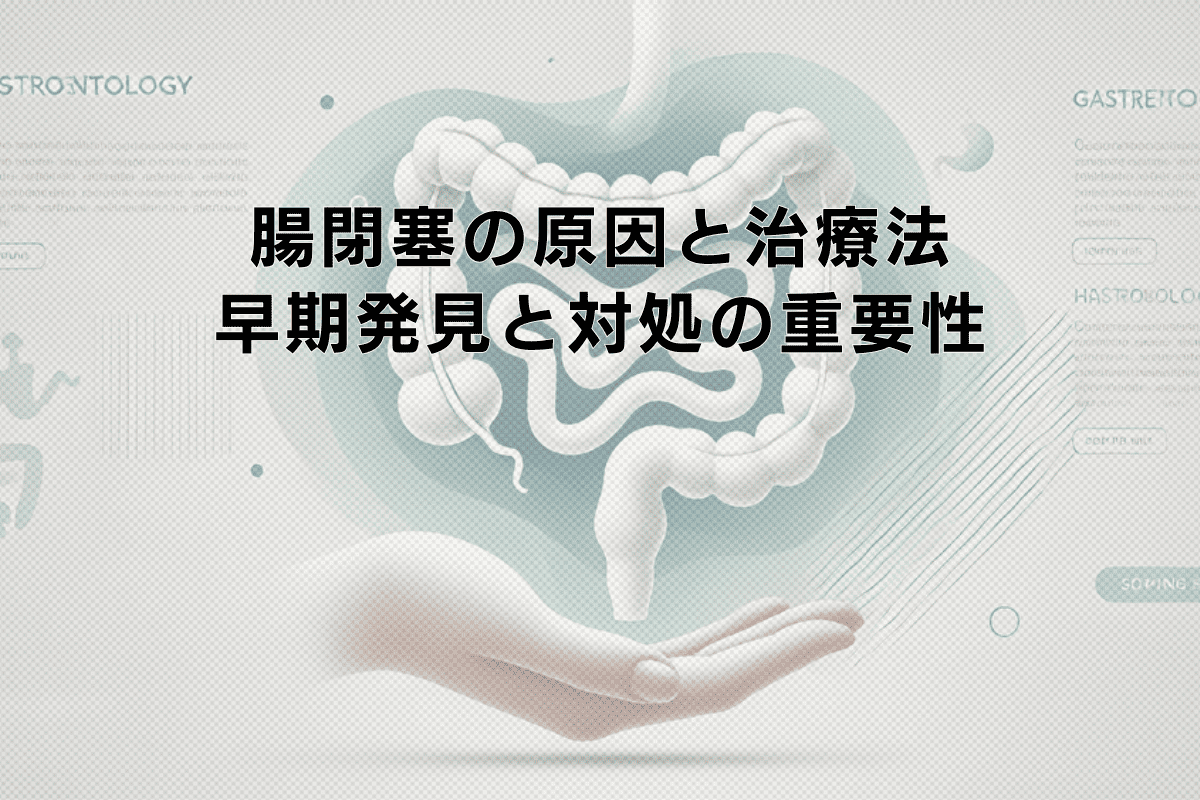
早期受診のメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 合併症の回避 | 腸壊死や腹膜炎など、重篤化を防ぎやすくなる |
| 短期的な入院で済む可能性 | 早期治療により長期入院を回避できる |
| 苦痛の軽減 | 嘔吐や腹痛のコントロールが行いやすくなる |
| 本人や家族の安心 | 原因と治療法が明確になり、精神的負担が軽くなる |
外科と内科、どちらを受診するか
腸閉塞の場合、外科と内科のどちらに行けばよいのか迷うケースが多く、初診では総合病院の救急外来や消化器内科を受診し、検査の結果から外科治療が必要と判明した場合に外科へ紹介されるという流れが一般的です。
セカンドオピニオンの活用
イレウス・腸閉塞の原因や治療方針は医療機関によってやや異なることがあり、疑問や不安を感じた場合は、セカンドオピニオンを求めることも一つの選択肢です。
別の専門医に見解を聞くことで、治療方針への納得度が高まり、患者本人の意思決定を明確にしやすくなります。
Q&A
イレウスや腸閉塞に関する質問は患者さんからよく寄せられ、体験したことがないとイメージしにくい部分も多く、疑問が尽きないでしょう。大切なのは、自身の症状や状況に合った情報を得て、早めに医療機関を受診することです。
- イレウス・腸閉塞は自然に治ることはありますか?
-
機能的なイレウスの場合、軽度であれば点滴や絶食などの保存的治療のみで改善に向かうケースもありますが、痛みが強かったり長引いていたりする場合は早めに受診してください。
放置すると悪化して外科手術が必要になる可能性があります。
- 腹痛があるけれど便やガスが少しでも出ていれば大丈夫ですか?
-
便やガスがわずかに出ていても、腸閉塞が進行している場合があります。特に高齢者や術後など、腸の動きが不安定な方は小さな兆候を見逃さず、異常を感じたら医師に相談することをおすすめします。
- 内視鏡検査は痛いのではないかと不安です。
-
緊急内視鏡検査では、可能な限り鎮静剤を使用することで不快感を軽減するように努めます。
腸閉塞が疑われる状態であれば、必要性とリスクをしっかり医師と相談してから行いますので、不明点や不安な点は事前に質問すると安心感が得られます。
- 以前腸閉塞を起こしたことがあるのですが、どんな生活習慣に気をつければ再発を防げますか?
-
まずは水分をしっかり摂取し、バランスの良い食事を心がけてください。過去に腸閉塞を経験した方は腸が弱りやすいことがあるため、便秘を起こしにくい環境づくりが大切です。
また、腸への負担を減らすために、急激な食事量の増加や暴飲暴食は避け、ストレス管理にも配慮しましょう。
次に読むことをお勧めする記事
【腸閉塞の初期症状と予防|早期発見のポイント】
イレウスと腸閉塞の基本を押さえたら、次は実際の初期症状の見分け方と予防法について知っておくと安心です。症状で悩まれている方に特に参考になる内容です。
【大腸がん検査方法の選び方 – 血液検査から内視鏡検査まで】
腸閉塞を学んだ皆さんには、大腸がん検診の知識も合わせて持つことで包括的な腸の健康管理に役立ちます。
参考文献
Ohmiya N. Management of obscure gastrointestinal bleeding: comparison of guidelines between Japan and other countries. Digestive Endoscopy. 2020 Jan;32(2):204-18.
Ohmiya N, Yano T, Yamamoto H, Arakawa D, Nakamura M, Honda W, Itoh A, Hirooka Y, Niwa Y, Maeda O, Ando T. Diagnosis and treatment of obscure GI bleeding at double balloon endoscopy. Gastrointestinal endoscopy. 2007 Sep 1;66(3):S72-7.
Ohmiya N, Arakawa D, Nakamura M, Honda W, Shirai O, Taguchi A, Itoh A, Hirooka Y, Niwa Y, Maeda O, Ando T. Small-bowel obstruction: diagnostic comparison between double-balloon endoscopy and fluoroscopic enteroclysis, and the outcome of enteroscopic treatment. Gastrointestinal endoscopy. 2009 Jan 1;69(1):84-93.
Sunada K, Yamamoto H, Kita H, Yano T, Sato H, Hayashi Y, Miyata T, Sekine Y, Kuno A, Iwamoto M, Ohnishi H. Clinical outcomes of enteroscopy using the double-balloon method for strictures of the small intestine. World journal of gastroenterology: WJG. 2005 Feb 21;11(7):1087.
Yamamoto H, Ogata H, Matsumoto T, Ohmiya N, Ohtsuka K, Watanabe K, Yano T, Matsui T, Higuchi K, Nakamura T, Fujimoto K. Clinical practice guideline for enteroscopy. Digestive Endoscopy. 2017 Jul;29(5):519-46.
Jackson P, Cruz MV. Intestinal obstruction: evaluation and management. American family physician. 2018 Sep 15;98(6):362-7.
Ribeiro IB, de Moura DT, Thompson CC, de Moura EG. Acute abdominal obstruction: Colon stent or emergency surgery? An evidence-based review. World journal of gastrointestinal endoscopy. 2019 Mar 16;11(3):193.
Sheedy SP, Earnest IV F, Fletcher JG, Fidler JL, Hoskin TL. CT of small-bowel ischemia associated with obstruction in emergency department patients: diagnostic performance evaluation. Radiology. 2006 Dec;241(3):729-36.
Sauerland S, Agresta F, Bergamaschi R, Borzellino G, Budzynski A, Champault G, Fingerhut A, Isla A, Johansson M, Lundorff P, Navez B. Laparoscopy for abdominal emergencies: evidence-based guidelines of the European Association for Endoscopic Surgery. Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques. 2006 Jan;20:14-29.
Harrison ME, Anderson MA, Appalaneni V, Banerjee S, Ben-Menachem T, Cash BD, Fanelli RD, Fisher L, Fukami N, Gan SI, Ikenberry SO. The role of endoscopy in the management of patients with known and suspected colonic obstruction and pseudo-obstruction. Gastrointestinal endoscopy. 2010 Apr 1;71(4):669-79.