大腸がんは胃がんや肺がんと並んで日本人に多く見られるがんの1つと考えられていますが、早期に発見しケアすれば治療の道が開けることも知られています。
大腸がんに対する検査方法はいくつかあり、それぞれに特徴やメリットがあります。血液検査や便潜血検査を入り口として考える方が多い一方で、内視鏡検査などの精密検査まで視野に入れることが重要です。
この記事では、大腸がんの検査方法について網羅的に解説し、どのように選べばよいかをわかりやすくまとめました。
大腸がん検査を受ける重要性
大腸がんに関する検査を考えるきっかけは人それぞれですが、近年はがん検診を定期的に受ける人が増える一方で、どの検査を受けるべきか悩むケースも多いです。
大腸がん検査の目的や注目される理由、検査を先送りにすることで生じるリスクについて整理します。
なぜ大腸がん検査が必要なのか
大腸がんは早期では自覚症状に乏しいことがあり、忙しい生活を送っていると健康診断以外での受診機会を逃しがちです。
一般に、便に血が混じる、下痢と便秘を繰り返す、お腹に張りや痛みを感じるといった症状が現れるのは比較的進行した段階に多いため、症状が軽い段階や無症状のうちに見つけるには検査がとても大切になります。
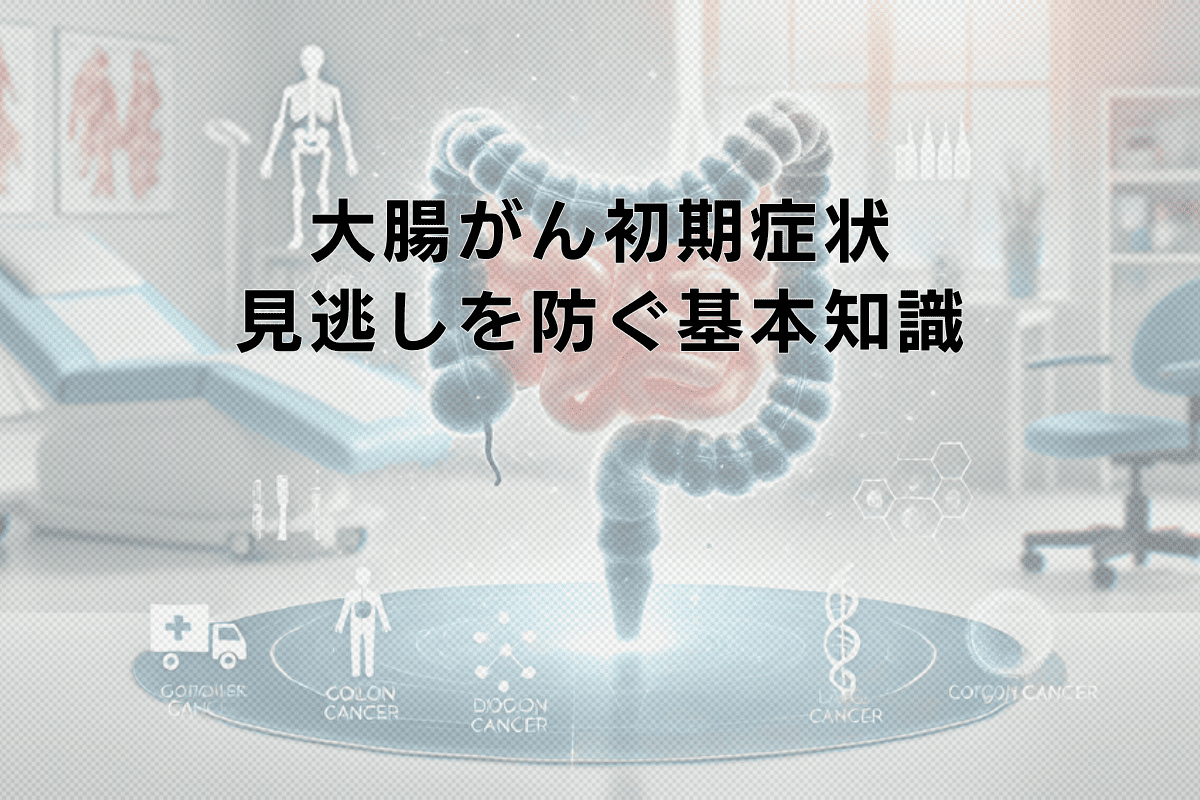
早期発見が治療効果に直結する理由
大腸がんに限らず、多くのがんは早期に発見できれば内視鏡治療や外科的手術などによる根治が期待しやすく、大腸ポリープの段階で除去が可能な場合もあるため、定期的な検査で小さな変化を見逃さないことが治療の成否に直結します。
症状が出てから検査を受けるのではなく、定期的・計画的に受ける習慣が重要です。
大腸がんリスクを高める生活習慣
大腸がんは生活習慣が大きく関与すると指摘されていて、高脂肪食や運動不足、アルコールの過剰摂取、喫煙などはリスク要因になり得ます。
もちろん遺伝的要因や年齢による発症リスクの増大もありますが、普段の食事や生活習慣を整えることがリスク軽減につながる可能性があります。

見逃してしまうとどうなるのか
大腸がんを見逃すと、進行に伴う症状が強くなり、治療の選択肢が限られる状況に陥りやすいです。
長期にわたる入院や身体的負担が増すだけでなく、仕事や家事など日常生活への影響も大きいものになるので、無症状でも検査を受けることが、将来的な負担を減らす一歩になります。
大腸がん検査の受診が注目される背景
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発症率の増加 | 食生活の欧米化や高齢化に伴う増加 |
| 早期発見の有効性 | 早期に見つけると内視鏡治療や外科的切除で対応しやすい |
| 検査方法の多様化 | 血液検査や便潜血検査、内視鏡など複数の選択肢 |
| 検診制度の普及 | がん検診を積極的に受けようとする啓発活動が増えている |
大腸がんの検査方法としては便潜血検査が広く知られていますが、血液検査の中でも腫瘍マーカーを用いたチェックや、さらに確実性を求めるなら内視鏡検査などの検討をおすすめします。
血液検査でチェックできること
人間ドックや検診で血液検査を実施した際に異常値が出たことをきっかけに、大腸がんを疑い、より精密な検査へ進む方も少なくありません。血液でわかる範囲と限界について紹介します。
血液で確認できる基本的な指標
血液を採取して行う検査では、ヘモグロビンや白血球数、赤血球数などの基礎的な項目を調べ、大腸がんだけでなく全身状態を把握する意味があるため、他の病気の可能性も含めて総合的に判断材料を得られます。
貧血が認められる場合、消化管で出血が起きているケースもあり、一つの目安となります。
大腸がんと腫瘍マーカー
血液検査の中で大腸がんと関係があるとされる腫瘍マーカーには、CEAやCA19-9といった項目が挙げられますが、これらの値はがん以外の要因でも上昇することがあり、正常範囲内でも大腸がんが否定されるわけではないです。
そのため、腫瘍マーカーのみで断定することは難しく、補助的な検査として用いられます。
血液検査のメリットと限界
血液検査は採血だけで済むため身体的負担が少なく、短時間で実施しやすいのがメリットであるものの、大腸がんを特異的に診断できるわけではありません。
腫瘍マーカーが高値を示しても別の病態と区別がつきにくいケースもあり、がんの早期発見を目指すうえでは、血液検査の結果を総合的に捉え、必要に応じてCT検査などの画像検査や内視鏡検査などを追加する流れが推奨されます。
血液検査を受けるタイミング
健康診断や人間ドックの基本メニューに血液検査が含まれていることが多く、年に1回程度の頻度で受ける方もいるでしょう。もし腫瘍マーカーなどで再検査をすすめられた場合は、医療機関にて精密検査の相談してください。
異常値が出た場合でも、他の要因の可能性もあるので、自己判断せず専門家の意見を聞くことが大切です。
血液検査と大腸がん診断の関係
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 検査の目的 | 全身状態の把握、貧血の有無、腫瘍マーカー測定 |
| 得られる情報 | 大腸がんの可能性を含むさまざまな疾患の兆候 |
| メリット | 採血のみで負担が少ない |
| 限界 | 大腸がんを確定できる検査ではなく補助的役割 |
大腸がんの検査方法として血液検査を受ける意義はありますが、最終的な診断にはほかの検査が必要になるケースが多いです。腫瘍マーカーだけで判断せず、複数の検査を組み合わせるアプローチが求められます。
便潜血検査で早期発見を目指す
健康診断の一般的な項目として広く実施されるのが便潜血検査で、便に含まれる微量の血液を検出することで消化管の出血リスクを確かめ、大腸がんの疑いがあるかどうかを判定する検査方法です。
どういった流れで行うのか、どのような結果が得られるのかを詳しく見ていきましょう。
便潜血検査の原理
大腸内で炎症や腫瘍、ポリープなどがあると、便にわずかな血液が混ざることがあります。便潜血検査では便に含まれるヘモグロビンの有無を調べることで、消化管出血の可能性をチェックします。
通常、2日法と呼ばれる方法で2日分の便を採取して調べる形式が広く採用されています。
陽性・陰性の判断と注意点
便潜血検査の結果が陽性となった場合、大腸がんの疑いが完全に確定したわけではなく、痔や炎症性腸疾患による出血の可能性も含まれますが、精密検査として内視鏡検査などを受ける推奨度は高くなります。
陰性だからといって大腸がんが絶対にないと断言できるわけでもないため、定期的に検査を受ける姿勢が必要です。
便潜血検査を行うメリット
便採取という手間こそあるものの、体内にカメラを入れたり大量に検体を採取したりする必要はないため、比較的容易に受けられる点が大きな魅力で、費用もそれほど高くなく、健康保険を利用できる検査項目に含まれていることが多いです。
大腸がんを含む腸管出血の早期発見に役立つため、多くの自治体や企業の定期健診で導入されています。

便潜血検査で知っておきたいメリット
- 検査準備が比較的簡単
- 費用が高くない
- 少量の便でチェック可能
- 健康診断で手軽に受けやすい
再検査が必要な場面
便潜血検査で陽性となった場合はもちろん、陰性でも腹痛や便通異常、体重減少など気になる症状があるときには、医療機関に相談すると、再検査として内視鏡検査や画像検査などを提案されるケースが多くなります。
放置すると進行がんを見逃すリスクが高まるため、速やかな行動が大切です。
便潜血検査結果が陽性だった場合に考えられる原因
| 原因 | 主な症状や特徴 |
|---|---|
| 大腸ポリープや早期大腸がん | 下血、血便、便通異常 |
| 痔 (痔核・裂肛など) | 便器が赤く染まる、肛門周辺の痛み |
| 炎症性腸疾患 (潰瘍性大腸炎・クローン病など) | 下痢、粘液便、腹痛 |
| 胃や十二指腸からの出血 | 黒っぽい便、吐血の合併がある場合も 免疫学的便潜血検査では上部消化管からの出血は検出されにくい |
便潜血検査の陽性結果は必ずしも大腸がんを意味しないものの、早めに内視鏡検査などへ進むことが肝心です。便潜血検査だけで大腸がんを完全に否定できるわけでもないので、定期的な検査スケジュールの一環として活用します。
大腸内視鏡検査の実際
大腸がんを疑う場合、より正確な状態を把握するために行われるのが大腸内視鏡検査です。
カメラを直接挿入して大腸全体の粘膜を観察し、必要に応じて組織を採取できるため、精密検査としての位置づけがある一方で、準備や検査の負担が気になる方もいます。

大腸内視鏡検査の流れ
検査前日や当日に下剤を服用し、大腸内をきれいにするところから始まります。腸の内容物が残っていると観察が不十分になるため、準備が重要です。
腸内洗浄後、検査室に入り肛門から内視鏡を挿入して観察していきます。検査時間は個人差がありますが10分~30分程度が一般的で、痛みが気になる方は麻酔や鎮静剤を使用して検査を受ける方法も選択できます。
大腸内視鏡検査の主な手順と所要時間
| 手順 | 目安の所要時間 |
|---|---|
| 前日~当日の下剤服用 | 数時間かけて排便 |
| 検査準備・問診 | 5~10分 |
| 内視鏡挿入・観察 | 10~30分 |
| 組織採取 (生検) | 数分程度 |
| 終了後の安静・説明 | 30分程度 |
検査中にできる処置
大腸内視鏡検査は診断だけでなく、同時に治療的処置を行える点が特徴です。
ポリープが見つかった場合、その場で切除し、ポリープが悪性の可能性がある場合は組織検査が行われ、早期がんであれば内視鏡的切除による完治も期待できます。
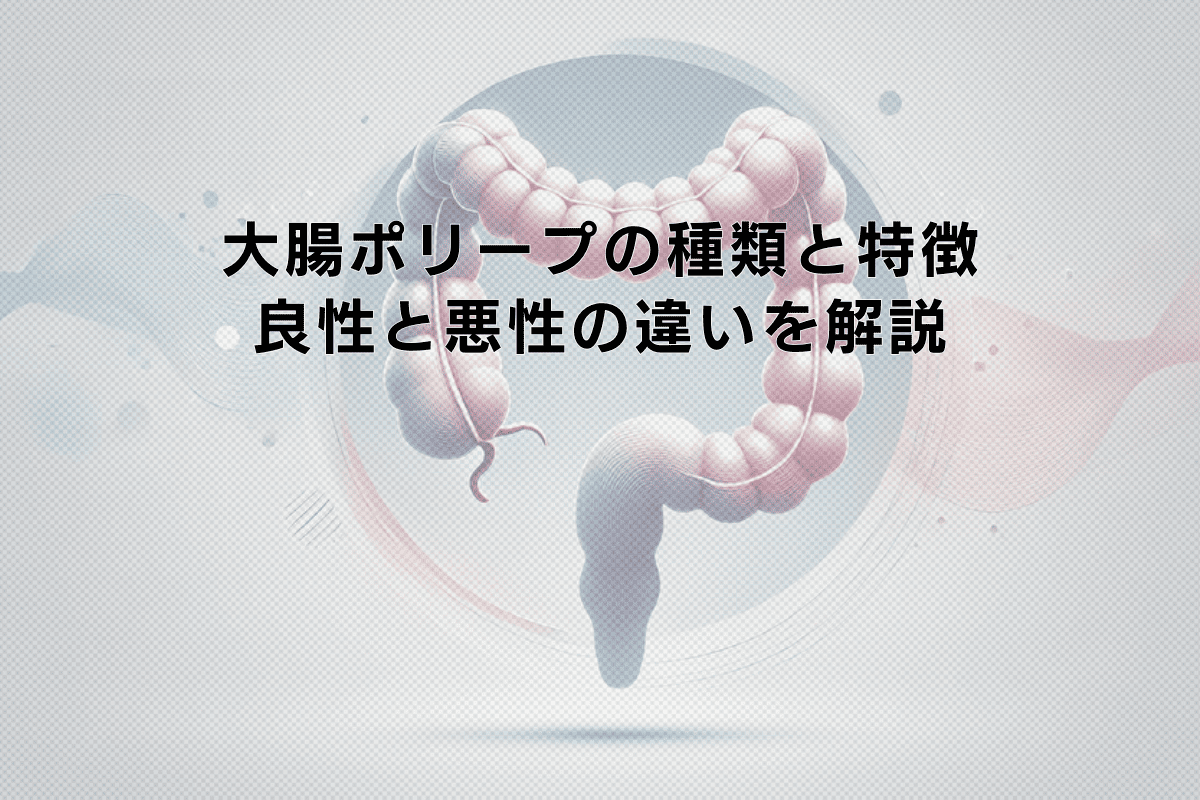
受ける際の負担と対策
大腸内視鏡検査の最大のハードルは下剤を飲んで腸内をきれいにする作業だと感じる方が多く、トイレに頻繁に行く必要があるため、時間的な余裕を持って検査を計画することが大切です。
検査中の痛みに不安がある場合、鎮静剤を使うことで負担を軽減しやすくなります。ただし、検査後は眠気などの影響を考慮して、車の運転などは避けましょう。
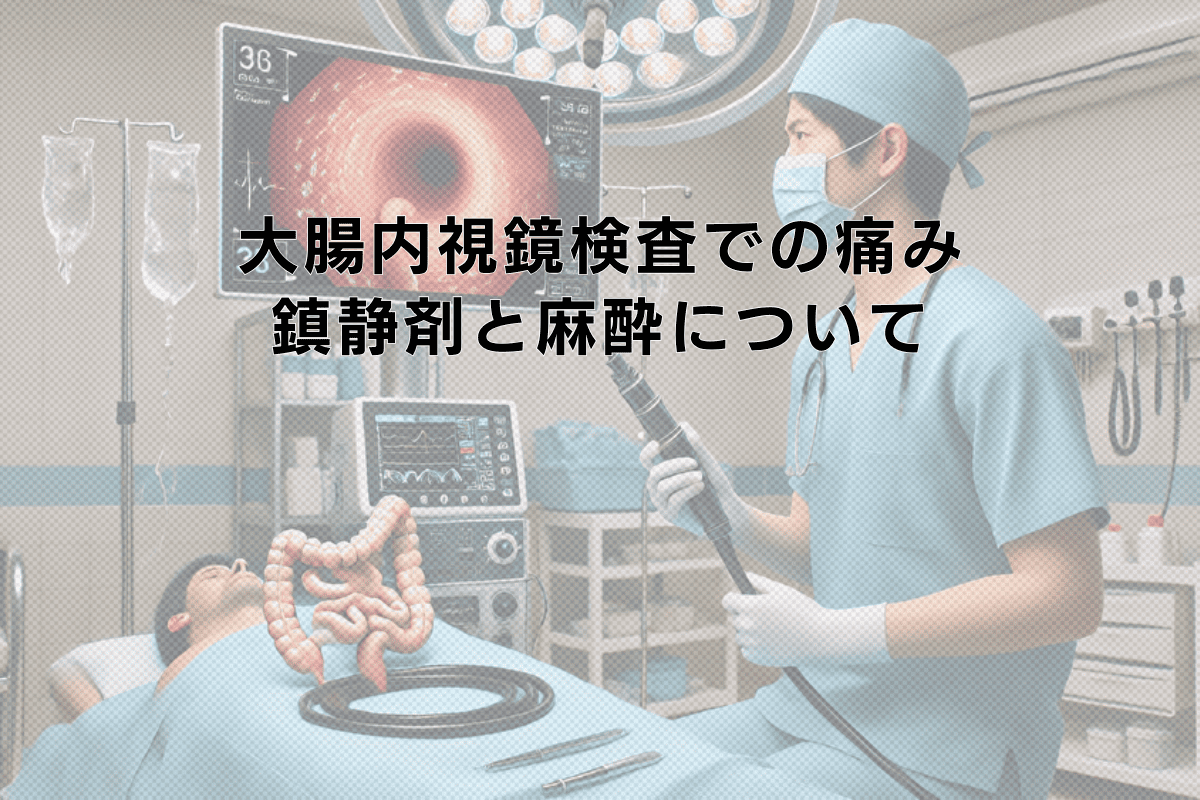
大腸内視鏡検査の利点とリスク
内視鏡検査は大腸がんの早期発見に役立ち、同時にポリープ切除なども可能なため、有効な検査法と位置づけられていますが、検査に伴う穿孔や出血などのリスクがゼロではありません。
極めてまれではありますが、理解したうえで受けることが望ましいです。
大腸内視鏡検査に関するメリット
- 直接大腸内を観察できる
- 病変を発見次第、治療的処置が可能
- 精度が高く、小さなポリープも見つけやすい
腹部超音波検査やCT検査との違い
大腸がんを含む消化器疾患の評価には、腹部超音波検査(エコー)やCT検査などの画像診断も行われ、それぞれに得意分野があり、内視鏡検査と組み合わせるケースもあります。
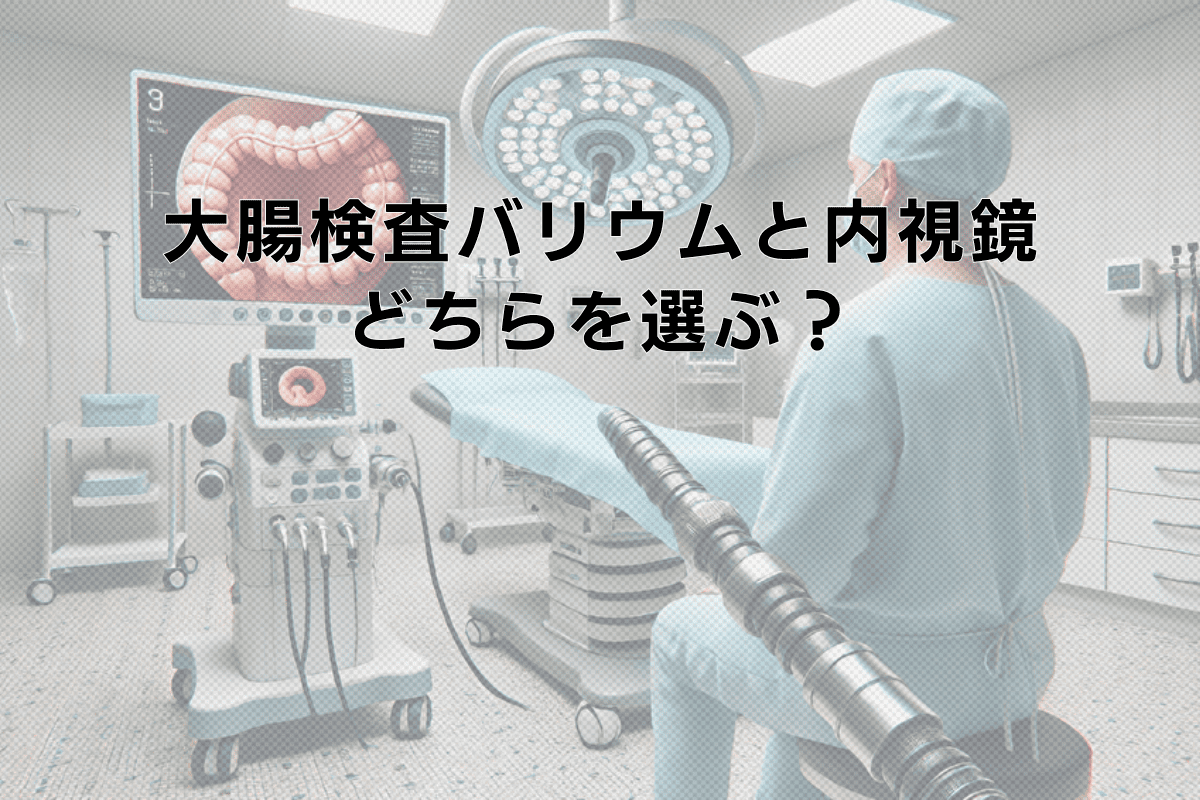
腹部超音波検査の特徴
腹部超音波検査は、超音波を使って肝臓や胆のう、膵臓などの腹部臓器を観察し、放射線被ばくがなく、妊娠中でも比較的安全に行えることが利点です。
ただし、腸内ガスなどがあると画像が見えにくいことがあり、大腸内部の詳細な観察には限界があり、また、大腸の壁の厚みや周辺組織への広がりを見る際に利用されることはあっても、がんの発見率においては内視鏡に劣る部分があります。
CT検査の長所と短所
CT検査はX線を使って身体の断面画像を得るため、がんの大きさや周辺臓器への浸潤状況などを立体的に把握でき、検査時間が短く、多くの情報を得られる点は長所です。
一方で放射線被ばくがあり、大腸内部の粘膜表面を直接観察できるわけではないため、小さいポリープの検出や粘膜の細部評価には向いていません。状況によっては内視鏡検査と組み合わせて総合的に診断される場合も多いです。
画像検査でわかること
| 検査法 | 特徴 | 大腸がん診断への有用度 |
|---|---|---|
| 腹部超音波 | 被ばくがなく安全、臓器の構造を把握しやすい | 腸内ガスがあると観察が不十分 |
| CT | 断面画像で広い範囲を把握、短時間で撮影可 | 粘膜面の詳細はわからない |
| 大腸内視鏡 | 粘膜を直接観察、治療も可能 | ポリープを切除できる |
画像検査と内視鏡検査の使い分け
腹部超音波検査やCT検査は、がんの進行度やほかの臓器への転移状況を評価する場面で有効です。
大腸内視鏡検査では確認しづらい周辺臓器との関係を把握する際、画像検査が大きく役立ち、腸壁の表面変化に焦点を当てる場合は内視鏡検査が得意分野です。
必要に応じて複数の検査を併用することで、大腸がんの有無や進行度を正確に把握する流れになります。
画像検査のタイミング
血液検査や便潜血検査で異常が疑われた場合に、CT検査や超音波検査へ進むケースがあり、特に症状が進んだり、大腸内視鏡検査で腫瘍が見つかったりした後に、がんのステージを判断するために画像検査が行われることも一般的です。
担当医の判断のもとで検査スケジュールが決まるため、指示に従って受診してください。
画像検査を活用する主な理由
- 腫瘍の正確なサイズや転移の有無を確認したい
- 手術や治療方針を立てるために立体的な画像が必要
- 別の疾患を合併していないか調べる
検査結果を総合的に評価し、大腸がんの疑いが強い場合は最終的に内視鏡検査や外科的生検で確定診断に至るのが一般的な流れです。
大腸カメラ検査における準備と注意点
大腸カメラ、つまり大腸内視鏡検査は、正確な診断や早期発見に直結する手段ですが、事前準備や検査当日の流れなど、気をつけるべきポイントがいくつかあります。
検査に向けた食事制限と下剤の役割
大腸カメラの検査前日や当日は、消化に良いものを中心に食事をとり、食物繊維の多い食品や刺激物を避けるように指示されることが一般的で、腸内をきれいにするための下剤を飲んで排泄を繰り返し、大腸内の視野をクリアにします。
この準備をきちんと行うかどうかで検査の正確性が大きく変わるため、怠らずに実施することが大切です。
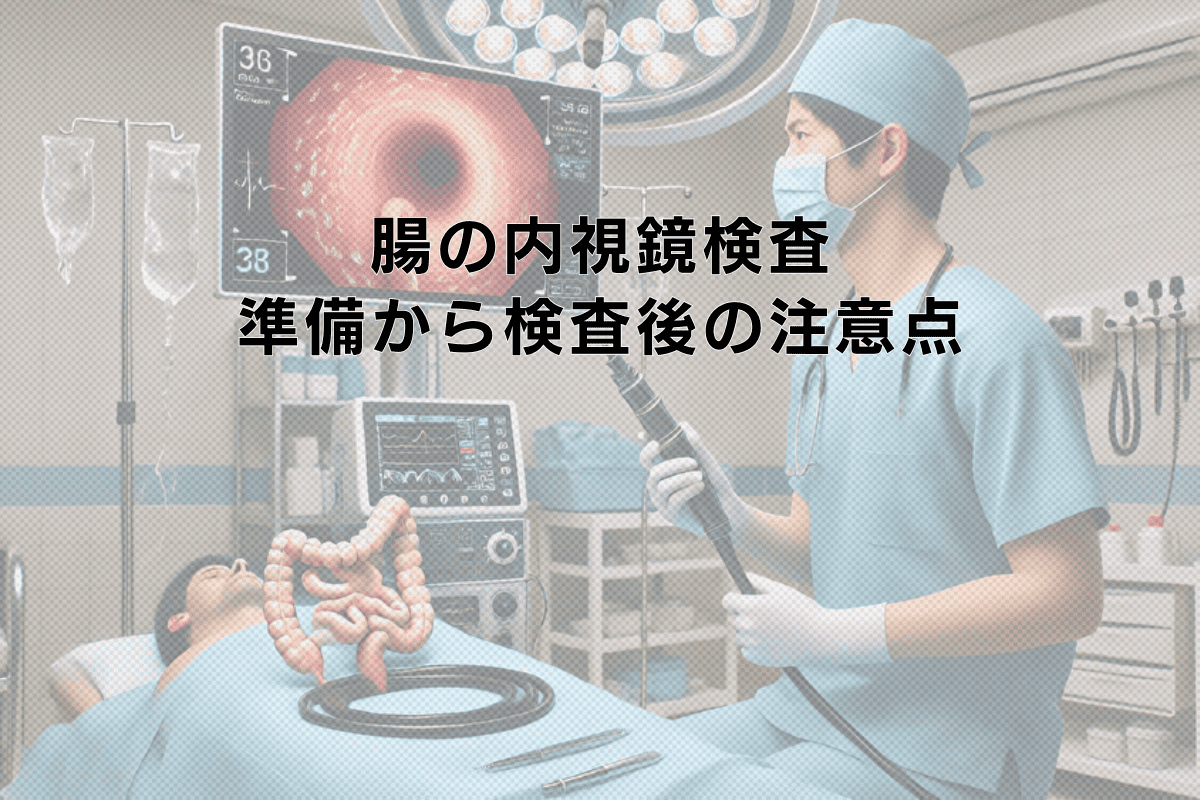
検査当日の流れと快適に受けるコツ
検査当日は医療機関で再度下剤を服用し、腸内がしっかり空になったかどうかを確認してから内視鏡検査に移り、個人差はありますが、下剤を飲んでから排便が落ち着くまでに2~3時間ほどかかります。
スムーズに排便が進むよう、適度に水分をとりながら指示に従います。検査中の痛みが心配な方は、鎮静剤や鎮痛剤を使うことでリラックスして受けられるでしょう。
大腸カメラ検査を受けるまでのスケジュール
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 前日 | 消化に良い食事に切り替え、早めに就寝 |
| 当日の朝~検査開始前 | 指示された時間に下剤を飲み、排便を繰り返す |
| 検査実施 | 内視鏡を挿入して観察 (10~30分程度) |
| 検査後 | 結果説明を受け、問題なければ帰宅 |
検査後の過ごし方
大腸カメラ検査は腸内が刺激されるため、検査直後は腹部に違和感や張りを感じることがあります。検査中に空気を入れるため、お腹が膨張した感覚が続く場合があるので、少し休んでから帰るのが安心です。
鎮静剤を使用した場合は眠気やふらつきが続くこともあり、車の運転や激しい運動は控えるように指導され、また、ポリープ切除などが行われた場合は医師の指示に従って安静を守ってください。
注意すべきリスク
大腸カメラ検査での合併症はまれですが、穿孔や出血などのリスクをゼロとは言い切れず、ポリープ切除などの処置を行った後は、出血や腹痛に注意が必要になります。
異常を感じた場合は放置せず、すぐに医療機関へ連絡することが重要です。
大腸内視鏡検査時に気をつけたい事項
- 検査前の食事制限と下剤の使用をきちんと守る
- 十分な水分補給を意識する
- 検査時は力まず深呼吸し、必要に応じて鎮静剤を検討する
- 検査後は無理な活動を避け、体調に変化がないか注意する
検査方法の選び方と組み合わせ
大腸がんの検査には血液検査、便潜血検査、大腸内視鏡検査、画像検査など多様な手段があります。実際には、どの検査を選ぶのか、あるいは組み合わせるのかをどう判断すればいいのでしょうか。
個々のリスク要因を考慮する
年齢や家族歴、過去に大腸ポリープが見つかった経験、あるいは腹部症状の有無などによって選ぶべき検査は変わります。
リスクが高いと考えられる人は早めの段階から内視鏡検査を受けることが望ましい場合もある一方、まずは手軽に便潜血検査や血液検査を受けて異常を拾い上げる方法を選ぶ方も多いです。
大腸がん検査を受けるタイミング
| タイミング | 検査の種類 | 特徴 |
|---|---|---|
| 健康診断・人間ドック | 便潜血検査、血液検査 | 定期的に受けやすく負担が少ない |
| 症状がある場合 | 内視鏡検査、画像検査 | 直接観察や詳細評価が可能 |
| 高リスクと考えられる場合 | 内視鏡検査、血液検査の腫瘍マーカー | 早期発見と厳重なフォローが必要 |
複数の検査を組み合わせるメリット
大腸がんを早期で見つけるためには、便潜血検査などのスクリーニングから始めて、陽性が出た場合に内視鏡検査へ進む流れが一般的で、血液検査の腫瘍マーカーを併用することで経過観察に役立てるケースもあります。
1つの検査で全てを補いきれない場合が多いため、複数の検査結果を突き合わせて総合的に評価すると誤診率を下げやすいです。
定期健診を活用する
職場や自治体の定期健診に便潜血検査が含まれているなら、まずはそれを活用し、必要に応じて追加検査を受ける形が一般的です。
何年も健診を受けずに放置してしまうと、万が一症状が出たときに進行がんだったという事態もあり得るので、面倒に感じることがあっても、将来のために定期的な検査を続ける価値は十分にあります。
よくある質問
大腸がん検査を受けるとなると、「どの検査を受ければいいのか」「痛みや費用はどうなのか」など、さまざまな疑問が湧いてきやすいです。ここでは、多くの方が気にするポイントをQ&A形式でまとめます。
- 便潜血検査が陰性なら大腸がんの心配はないのでしょうか?
-
陰性でも大腸がんを完全に否定できるわけではなく、便潜血検査はあくまで出血の有無を調べるものであり、ポリープや小さいがんがあっても発見されないケースがあります。
何か症状がある場合やリスクが高い方は、陰性でも内視鏡検査を検討すると安心です。
- 血液検査の腫瘍マーカーだけで大腸がんがわかりますか?
-
腫瘍マーカーはあくまでも補助的な検査で、値が高くてもがん以外の原因で上昇する場合がありますし、逆に正常でもがんが進行しているケースもあります。
血液検査だけで最終的な判断は難しく、内視鏡検査の結果を合わせて考えることが重要です。
- 大腸内視鏡検査は痛みが強いと聞きますが、本当ですか?
-
痛みの感じ方は個人差がありますが、医師の技量や検査機器の進歩により、以前ほど強い痛みを訴える人は減っています。
鎮静剤を使ってリラックスした状態で検査を受ける方法もあり、実際には思ったほどつらくなかったという声も多いです。不安があるなら事前に相談するとよいでしょう。
- 定期健診があるので、それだけ受けていれば十分ですか?
-
定期健診に便潜血検査が含まれている場合は、大腸がんスクリーニングとして一定の価値があります。
ただし、何らかの症状がある場合やリスクが高いと考えられる方は、健診だけでなく早期の段階から内視鏡検査なども考慮するほうが安心です。
次に読むことをお勧めする記事
【腸の内視鏡検査で分かること – 検査前の準備から検査後の注意点】
大腸がん検査について理解が深まった皆さんには、実際の検査手順や準備方法の知識も合わせて持っていただくと、より包括的な理解ができます。
【大腸がんのステージと検査スケジュール】
大腸がん検査の基本を押さえたら、次は治療方針に直結する“ステージ分類”を理解しておくと安心です。検査後の見通しを立てたい方に特に参考になります。
参考文献
Shinagawa T, Tanaka T, Nozawa H, Emoto S, Murono K, Kaneko M, Sasaki K, Otani K, Nishikawa T, Hata K, Kawai K. Comparison of the guidelines for colorectal cancer in Japan, the USA and Europe. Annals of gastroenterological surgery. 2018 Jan;2(1):6-12.
Tsuji I, Fukao A, SHOJI T, KUWAJIMA I, SUGAWARA N, HISAMICHI S. Cost-effectiveness analysis of screening for colorectal cancer in Japan. The Tohoku Journal of Experimental Medicine. 1991;164(4):269-78.
Ross WA. Colorectal cancer screening in evolution: Japan and the USA. Journal of gastroenterology and hepatology. 2010 May;25:S49-56.
Shimbo T, Glick HA, Eisenberg JM. Cost-effectiveness analysis of strategies for colorectal cancer screening in Japan. International journal of technology assessment in health care. 1994 Jul;10(3):359-75.
Saito H. Screening for colorectal cancer: current status in Japan. Diseases of the colon & rectum. 2000 Oct;43(Suppl 10):S78-84.
Inoue T, Murano M, Murano N, Kuramoto T, Kawakami K, Abe Y, Morita E, Toshina K, Hoshiro H, Egashira Y, Umegaki E. Comparative study of conventional colonoscopy and pan-colonic narrow-band imaging system in the detection of neoplastic colonic polyps: a randomized, controlled trial. Journal of gastroenterology. 2008 Jan;43:45-50.
Tashiro A, Sano M, Kinameri K, Fujita K, Takeuchi Y. Comparing mass screening techniques for gastric cancer in Japan. World journal of gastroenterology: WJG. 2006 Aug 14;12(30):4873.
Sekiguchi M, Igarashi A, Matsuda T, Matsumoto M, Sakamoto T, Nakajima T, Kakugawa Y, Yamamoto S, Saito H, Saito Y. Optimal use of colonoscopy and fecal immunochemical test for population-based colorectal cancer screening: a cost-effectiveness analysis using Japanese data. Japanese journal of clinical oncology. 2016 Feb 1;46(2):116-25.
Minamimoto R, Senda M, Jinnouchi S, Terauchi T, Yoshida T, Inoue T. Detection of colorectal cancer and adenomas by FDG-PET cancer screening program: results based on a nationwide Japanese survey. Annals of nuclear medicine. 2014 Apr;28:212-9.
Koo JH, Leong RW, Ching J, Yeoh KG, Wu DC, Murdani A, Cai Q, Chiu HM, Chong VH, Rerknimitr R, Goh KL. Knowledge of, attitudes toward, and barriers to participation of colorectal cancer screening tests in the Asia-Pacific region: a multicenter study. Gastrointestinal endoscopy. 2012 Jul 1;76(1):126-35.










