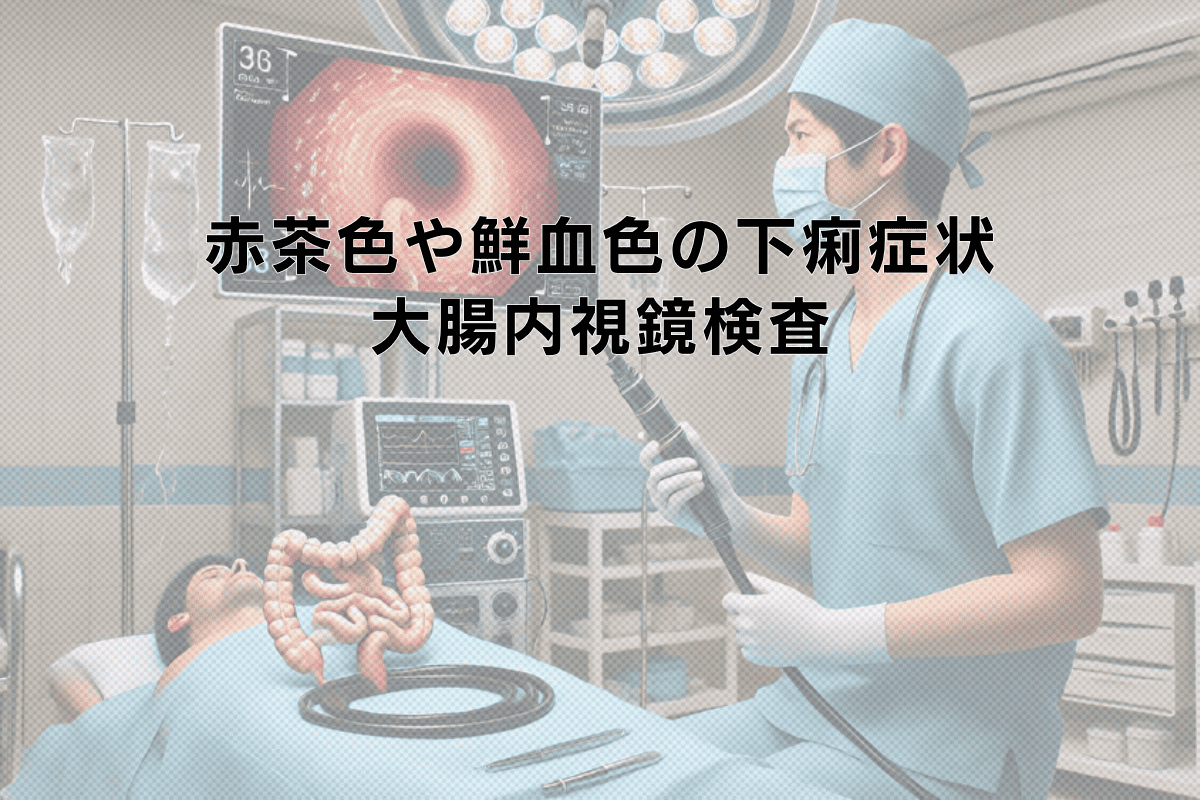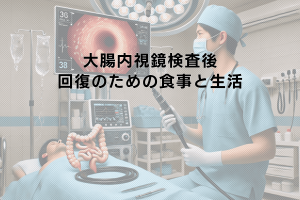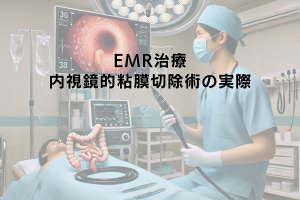下痢の便が赤茶色に変化したり、鮮血が混じって明らかに赤い色を帯びたりすると、大腸や肛門付近の出血を疑うきっかけになります。
原因を特定するうえで、本人の自覚症状だけでは判断が難しい場合も多く、内視鏡を使った精密な検査が重要です。
この記事では、赤茶色や鮮血を伴う下痢の原因や注意点を詳しく述べ、出血の疑いがある場合に大腸内視鏡検査が果たす役割や検査前後のポイントを解説します。
下痢が赤茶色になるメカニズム
赤みを帯びた下痢は、大腸や小腸の一部など消化管のどこかで出血が起きている可能性を示唆します。赤茶色の下痢だからこそ考えられるメカニズムを知っておくと、初期対応に役立ちます。
消化管内での血液の変化
便が茶色いのは、腸内での消化過程によってビリルビンなどの胆汁色素が変化するためで、血液が混ざると、その赤色素が便の色に影響を与えます。
上部消化管からの出血は黒っぽいタール便になることが多いですが、大腸付近の出血は比較的赤茶色になりやすいです。大腸に近いほど、血液が酸化・分解されにくく、より赤みを保ちます。
便の色と出血位置の目安
赤茶色の下痢か、鮮血に近い赤い下痢かによって、出血位置の目安が異なると考えられます。大腸よりも上の方で起きた出血では、血液が滞留して酸化が進むので暗めの色合いになりやすいです。
直腸や肛門付近で出血が起きている場合、より鮮やかな赤い色を帯びる傾向があります。
血液と混じり合った粘液
血液だけでなく、腸粘膜からの分泌物(粘液)が混じる場合もあり、粘液が増えると便がゼリー状になり、色合いに加えて形状や質感にも変化が生じることがあります。
粘液と血液の混合は腸管の炎症や潰瘍性病変が原因のこともあり、自己判断は難しいです。
受診すべきタイミング
赤茶色の下痢を放置すると、潜在的な疾患の悪化を招く場合があります。便秘との反復や、慢性的に下痢と腹痛が続くケースでは、医師の診察を受けたほうが安心です。胃腸のトラブルに慣れている方ほど、見落としがちなので注意してください。
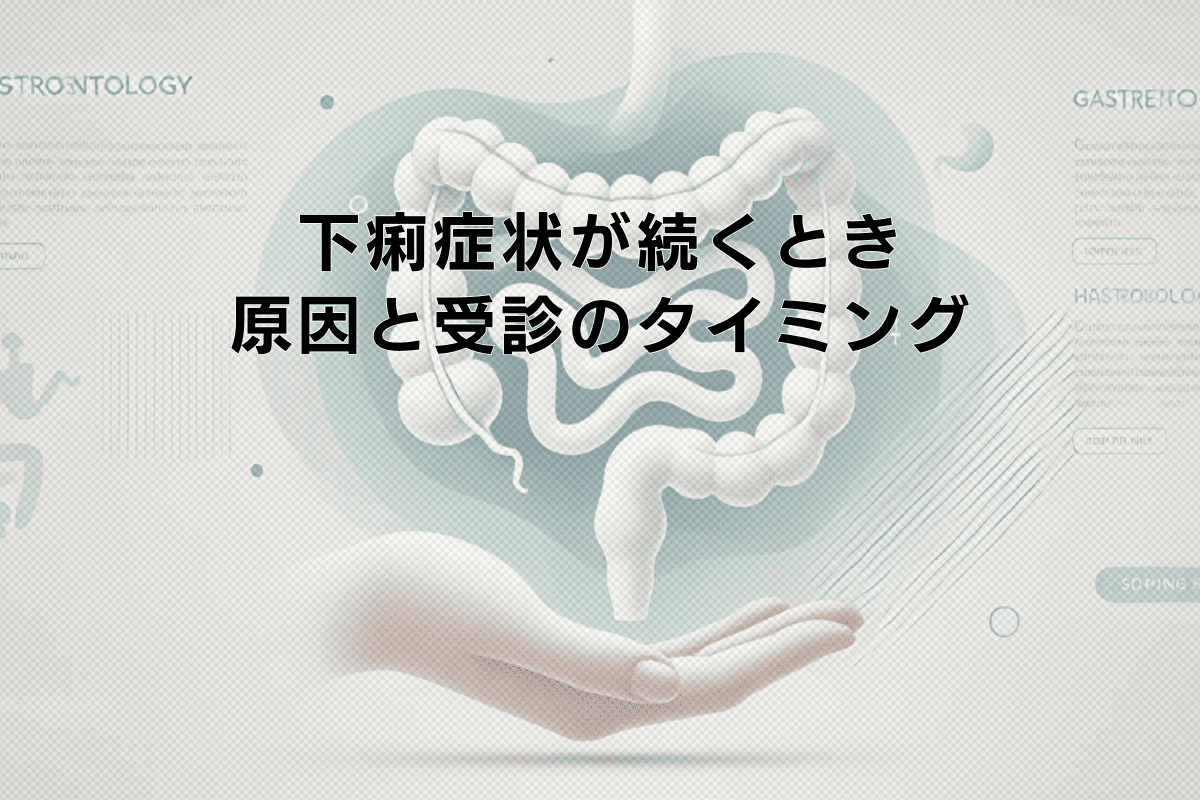
下痢の色の変化と関連部位
| 便の状態 | 疑われる主な部位 | 色の特徴 |
|---|---|---|
| 黒っぽいタール状 | 上部消化管(胃・十二指腸) | 酸化した血液が混ざり黒くなる |
| 赤茶色 | 小腸~大腸 | 血液が部分的に酸化し赤褐色になる |
| 鮮やかな赤色 | 直腸や肛門付近 | 酸化が進まず鮮血が残る |
少量の血液混入でも、便の色味や状態は大きく変化することがあります。脂質が多い食事、着色料を含む食品などでも便の色が変わることがあるため、一時的な変化かどうかを見極めることも大切です。
下痢が赤茶色になる際の要注意ポイント
- 便に血液のような粘液が混じるとき
- 腹痛や下腹部の不快感が長引くとき
- 排便時の痛みや強い残便感を感じるとき
- 風邪などに伴う一過性の下痢と違い、数日以上続くとき
便の状態をよく観察し、異常が疑われるときは自己判断をせず医師に相談してください。
下痢が鮮血色になる背景
血液が十分に酸化されず、ほぼそのまま混ざると下痢が鮮やかな赤い色を帯びることがあります。その場合、排便時にどのような感覚があるのか、血液だけでなく痛みや粘膜の状態がどうなのかが重要な手がかりです。
出血量と血液の色合い
直腸や肛門に近い部分での出血量が多い場合、真っ赤な血液が下痢便にそのまま混じる可能性が高まります。時間経過が短いため、酸化が進まず鮮血に近い状態で、肛門付近に裂傷がある場合や、強い炎症があるときに起きやすいです。
直腸や肛門近辺の炎症
痔核や肛門裂傷などの肛門疾患では、排便時に強い痛みや出血をともなうことがあります。
とくに鮮血が確認できる場合には肛門周辺の病変を疑い、痛みが強くてトイレを避けるようになると、便秘との繰り返しにつながり、症状が悪化しやすいです。
病変が浅い領域の出血
大腸の最終部分であるS状結腸や直腸に病変があると、鮮血に近い赤い下痢が出る場合があります。このような領域では、腸内で血液が滞留する時間が比較的短いため、便に混じる血液が酸化による変色を起こしにくいです。
重篤な疾患の可能性
鮮血色の下痢が続くときは、クローン病や潰瘍性大腸炎といった炎症性腸疾患も念頭に置く必要があるため、血便や粘液便、持続的な腹痛、体重減少などが重なれば、早めに専門医に相談することが大切です。
下血が疑われる際によくみられる関連症状
| 代表的な症状 | 発生しやすいシチュエーション | 考えられる主な原因 |
|---|---|---|
| 排便時の強い痛み | 肛門付近の傷や痔核があるとき | 肛門裂傷・切れ痔、内痔核など |
| 血液と粘液が混じった便 | 大腸下部の炎症や潰瘍があるとき | 潰瘍性大腸炎、感染性腸炎など |
| 便が真っ赤な色で下痢状 | 直腸付近で出血が起きているとき | 直腸ポリープ、直腸がんなど |
| 発熱や体重減少 | 全身症状をともなう炎症性腸疾患のとき | クローン病、潰瘍性大腸炎など |
肛門周辺の出血を軽視すると出血量が増えたり慢性化したりする可能性があります。下痢が赤いときは一時的なものか慢性的なものかを見分けるのが重要です。
受診の早さが大切と感じるサイン
- 排便時や肛門付近の強い違和感がある
- 過去に痔疾患の診断歴がある
- 血便とともに発熱や倦怠感が続いている
- 日常生活に支障をきたす腹痛や下痢がある
自己ケアでは対処しきれないケースが多いので、早めに胃腸科や肛門科などを受診してください。
出血を伴う下痢の可能性がある疾患の例
赤茶色の下痢や鮮血に近い赤い下痢は、多岐にわたる消化器疾患の症状として現れます。それぞれの疾患は症状や進行度が異なるため、早期発見と早期治療が重要です。
炎症性腸疾患
潰瘍性大腸炎やクローン病のような炎症性腸疾患では、腸粘膜がただれて出血しやすい状態にあり、下痢が続くことに加えて、血便や粘液便が特徴です。病変が大腸の下部に及んでいる場合は、鮮血が混じる傾向が強まります。
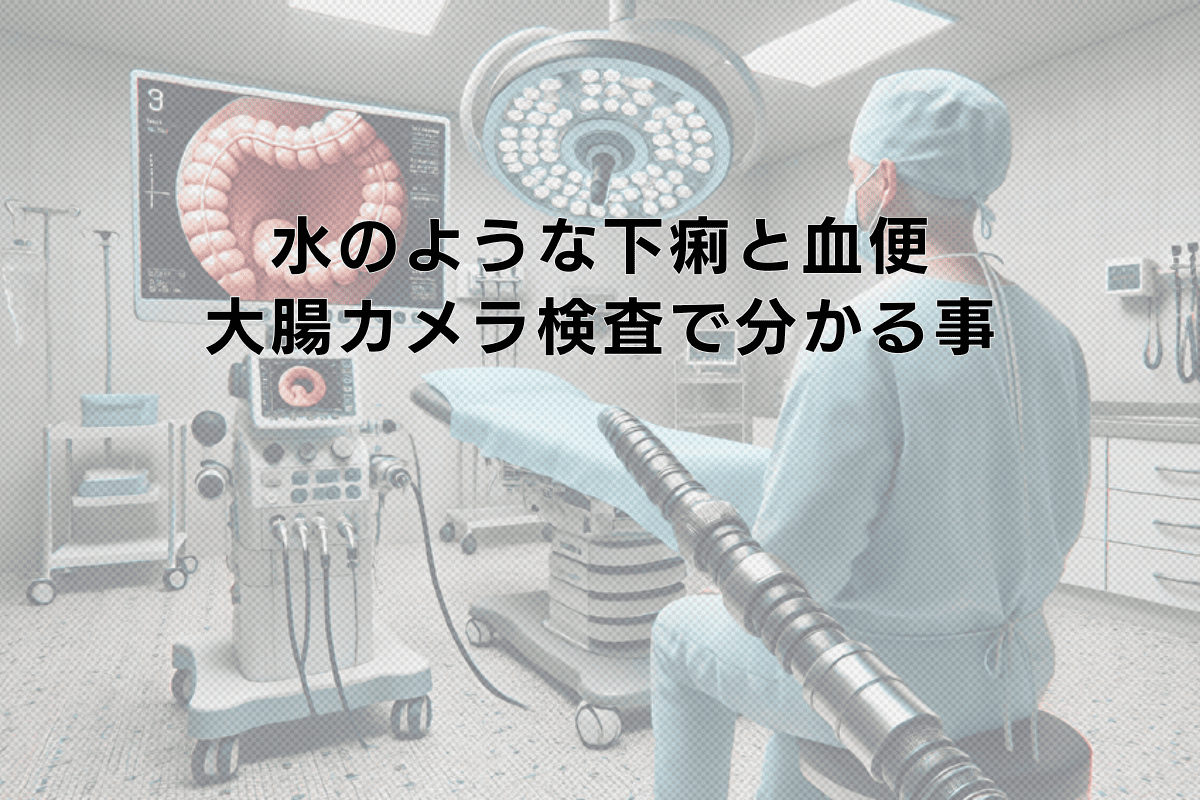
感染性腸炎
細菌やウイルス、寄生虫が原因の感染性腸炎でも、激しい下痢や腹痛とともに血が混じることがあります。出血量は比較的少なめのことが多いですが、発熱や嘔吐をともないやすく、脱水が進行すると体力を消耗しやすいです。
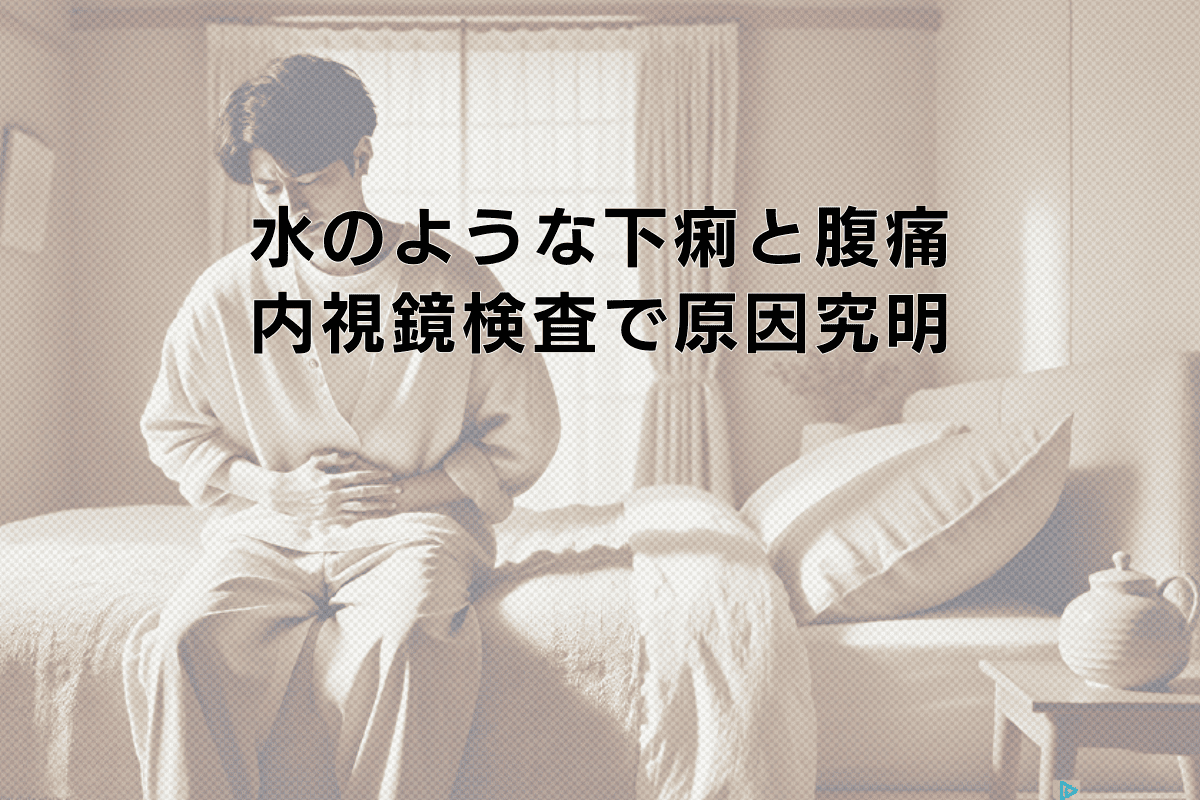
大腸がん・直腸がん
大腸や直腸に腫瘍ができると、便が通過する際に粘膜が傷つき、出血を起こす可能性があります。初期は症状が軽く見逃しやすいですが、進行すると便の形状変化や持続的な血便がみられ、便が赤茶色を帯びることもあります。
年齢や生活習慣を踏まえて、定期的に内視鏡検査を検討したほうが安心です。

痔核・肛門裂傷
肛門付近の血管が膨張して発生する痔核(いぼ痔)や、硬い便などによる切れ痔は、排便時に鮮血色の出血がよくみられますが、痛みの強さや血液の付着量などは人によって異なります。
腹圧の上昇や便秘との反復で悪化しやすいため、生活習慣の改善と合わせて早期の診察が大切です。
主な疾患と特徴的な症状
| 疾患名 | 主な症状 | 出血時の便の色 |
|---|---|---|
| 潰瘍性大腸炎 | 血便、腹痛、発熱、体重減少など | 赤~赤茶色 |
| クローン病 | 血便、下痢、口内炎、痔瘻など | 赤色、または暗めの赤茶色 |
| 大腸がん・直腸がん | 血便、便通異常、体重減少など | 赤茶色、または鮮血が混じる |
| 痔核(いぼ痔) | 排便時出血、肛門周辺の痛みや違和感 | 鮮血が付着しやすい |
| 肛門裂傷(切れ痔) | 排便時の激しい痛み、紙に血が付くなど | 鮮血に近い赤色 |
気になる初期症状の見極め方
- 血液の混ざり方(便に付着しているのか、全体に混ざっているのか)
- 痛みの部位や程度
- 発熱や倦怠感、体重減少の有無
- 便意の回数や便の形状の変化
これらを日常的にチェックすると、受診のタイミングがつかみやすくなります。
大腸内視鏡検査の役割
赤茶色の下痢や鮮血が混じる場合、視覚的な観察だけでは原因を正確に判断しにくいです。大腸内視鏡検査ではカメラを使って直接大腸の内壁を観察し、出血源を確認できます。
早期診断が必要な疾患を見逃さないためにも、専門的な検査が大切です。

内視鏡検査による詳細な観察
大腸内視鏡検査では、肛門から細長いスコープを挿入し、大腸全体の粘膜をモニターに映し出します。直腸から盲腸付近まで観察し、ポリープや炎症、潰瘍、腫瘍などの病変を見つけられます。
視覚的に捉えづらい軽度の炎症も発見しやすく、早期治療につながります。
生検と病理検査
疑わしい部位を発見した場合、内視鏡を操作して直接組織の一部を採取し、病理検査にまわします。炎症の状態や腫瘍の良性・悪性の判定など、より詳細な情報を得るうえで有用で、ポリープが見つかれば、その場で切除することも可能です。
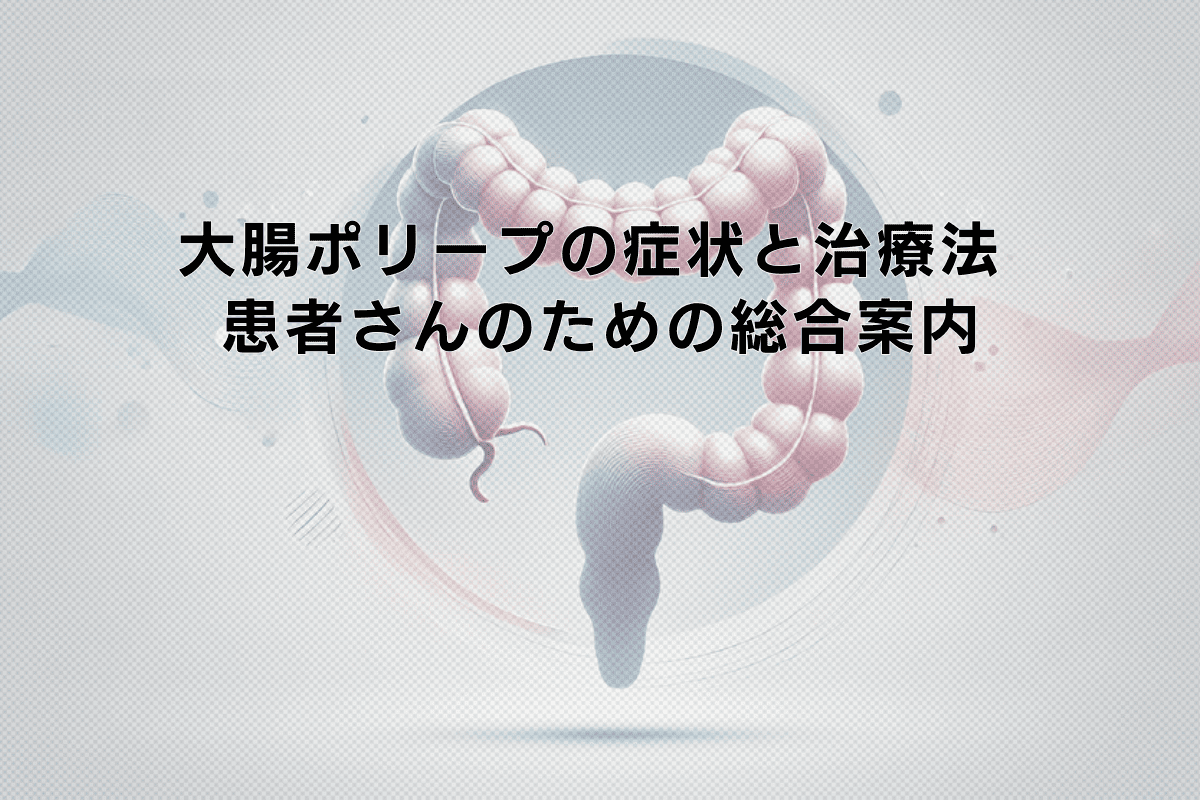
痛みを抑える工夫
近年は鎮静剤を使うことで、検査時の不快感や痛みを緩和する方法が広く行われています。また、スコープや技術の進歩によって検査自体の負担も軽減されてきています。検査への不安が強い方は、医療機関で相談しましょう。
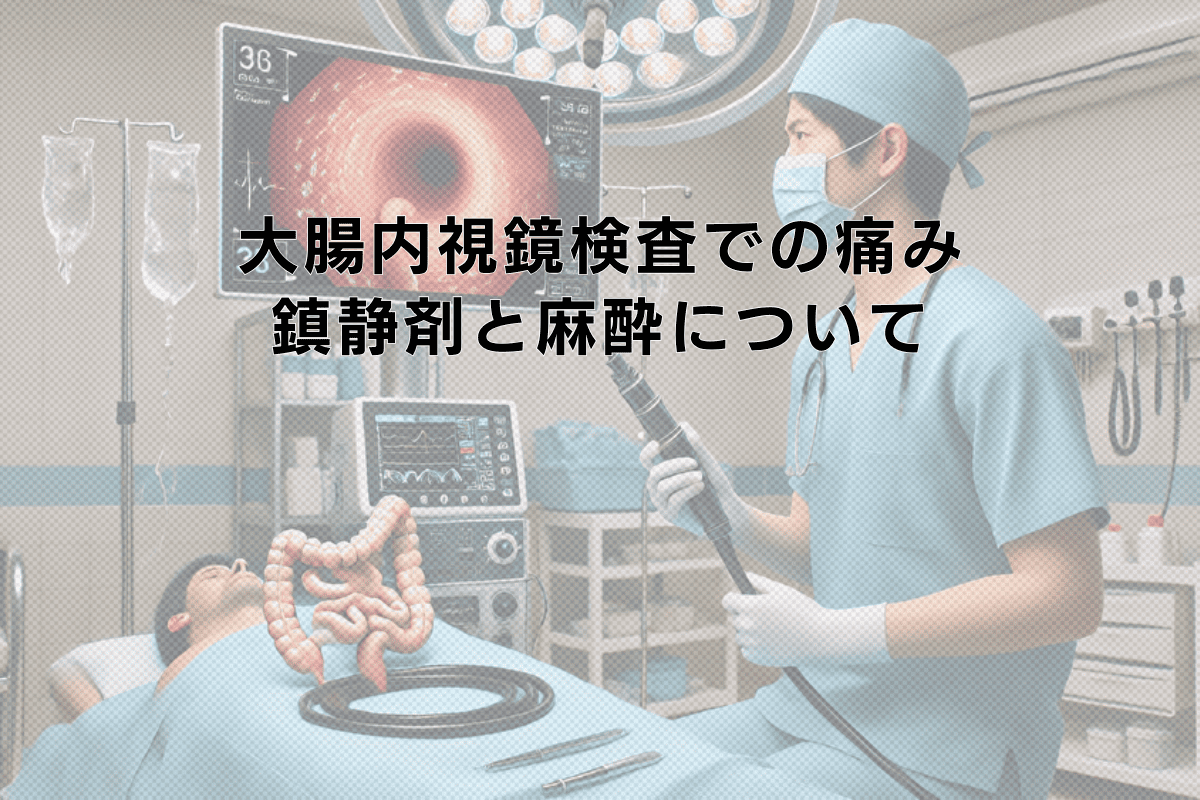
検査結果からの治療方針
内視鏡検査で得られた情報に基づいて、今後の治療方針を決定します。小さなポリープであれば内視鏡治療が検討され、大腸がんや炎症性腸疾患などが疑われる場合には専門的な治療へ進むケースもあります。
内視鏡検査で確認しやすい病変
| 病変の種類 | 主な特徴 | 検査後の対応 |
|---|---|---|
| ポリープ | 良性や悪性の可能性がある隆起性病変 | 内視鏡切除や病理検査 |
| 潰瘍 | 粘膜がただれて欠損している状態 | 投薬治療や生活習慣指導 |
| 出血部位 | 大腸壁に傷や炎症、腫瘍など | 止血処置、治療方針の検討 |
| 炎症所見 | 発赤や浮腫、びらんなど | 原因に応じた薬物療法 |
| 腫瘍 | 大腸がんなどを含む悪性の可能性 | 外科的治療や化学療法を検討 |
内視鏡検査は医師が直接映像を見ながら原因を突き止める手段として有用です。とくに血液が混じる下痢がある場合は、原因究明に大きく役立ちます。
大腸内視鏡検査を受けるときに意識したい点
- 検査前の食事制限や下剤の服用
- 痛みに弱い場合は鎮静剤の相談
- 検査後の出血リスクがゼロではないため安静が望ましい
- 発見された病変に応じて医師と治療方針を話し合う
手間のかかるイメージがあるかもしれませんが、正確な診断と早期治療には大切な手段です。
検査前の準備と注意点
大腸内視鏡検査の前には、腸をきれいにするための下剤の内服や食事制限などが必要で、検査を円滑に行うためには、検査前の準備がスムーズに進むかどうかで精度に影響が出ることがあります。
食事管理と下剤の服用
検査前日から消化に負担の少ない食事を心がけ、腸を空に近い状態にし、脂っこい食事や食物繊維の多い食材は避けるよう指示を受けることが多いです。
当日は指定された下剤を飲み、便が水に近い状態になるまで排出することが理想で、残渣が多いと内視鏡での観察が不十分になる恐れがあります。

準備段階で摂取しやすい食品や飲み物
| 食品・飲料の種類 | ポイント |
|---|---|
| おかゆ・白身魚 | 消化にやさしく腸に負担が少ない |
| スープ(具なし) | 電解質補給に適している |
| スポーツ飲料 | 水分とミネラルの補給になる |
| 水・お茶 | 脱水予防のためこまめに摂取 |
内服薬や持病の確認
高血圧や糖尿病などの持病がある場合、検査前の薬の飲み方を医師や薬剤師と相談する必要があります。心疾患などで抗凝固薬を服用している方は、内視鏡検査中の出血リスクを避けるために休薬の指示を受けることがあります。
自己判断はせず、医療スタッフに正直に申告してください。
検査当日の過ごし方
指定された時間までに下剤を服用し、トイレに通う回数を増やして腸内を洗浄し、腸内に残渣が残らないようにします。水やスポーツ飲料などで水分を適度に補給しながら進めると、脱水を防げます。
検査当日は食事制限があるため、準備を早めにしておくと慌てずに済みます。
準備に伴う体調トラブル
下剤で腸を空に近い状態にするとき、まれに腹痛や嘔気が起きる場合があるので、症状が強いと感じるときは、医療スタッフに相談するのが安心です。
自己判断で中断すると、内視鏡検査の精度が落ちたり、検査そのものが行えなくなったりする可能性があります。
スムーズな準備のために押さえたいポイント
- 指示通りの時間に下剤を飲む
- 短時間で大量の水分を摂取しすぎない
- 下剤の味が苦手なら飲みやすい工夫をする
- 体調不良があれば遠慮なく相談する
正確な結果を得るために、医師や看護師の指示を守ることが大切です。
内視鏡検査で発見される主な原因疾患
赤茶色の下痢や鮮血が混じる下痢の原因は多岐にわたり、内視鏡検査を行うと、以下のような疾患が見つかることがあります。早期発見は治療効果に直結するため、定期的な検査や異変を感じたときの受診が大切です。
大腸ポリープ
大腸の粘膜にできる隆起性病変で、良性の場合もありますが、放置すると大腸がんにつながるリスクが指摘されています。
内視鏡検査中に見つかった場合は、そのまま切除することが可能なケースもあります。大腸ポリープが成長していると、便に赤茶色の血液が付着することもあります。
大腸ポリープの種類
| 種類 | 特徴 | リスク |
|---|---|---|
| 腺腫性ポリープ | がん化リスクを伴うポリープ | 放置で大腸がんへ進行する恐れ |
| 過形成性ポリープ | がん化リスクは低いが定期観察が必要 | 大きくなると紛らわしい場合有 |
| 炎症性ポリープ | 炎症後に形成されることが多い | 原因となる炎症の治療が重要 |
潰瘍性大腸炎やクローン病
いずれも炎症性腸疾患に分類される病気です。腸管粘膜がただれることで出血しやすく、慢性的な下痢や腹痛を伴いやすいです。
発症メカニズムには免疫異常などが関与していると考えられており、内視鏡検査によって、腸の炎症範囲や重症度を把握しながら治療方針を立てます。
大腸がん
初期の大腸がんは症状がほとんどない場合がありますが、進行すると便に血液が混じったり、便通異常が生じたりします。内視鏡検査による早期発見が予後に大きく影響します。
大腸がんが疑われる場合、さらに詳しい画像診断や病理検査によって確定診断を行います。

痔核や肛門部の病変
下痢が赤い場合、肛門付近の病変による出血の可能性もあります。内視鏡検査では大腸の深部だけでなく、直腸周辺も観察範囲に含まれます。痔核や肛門周辺の病変がみつかった場合は、専用の治療が検討されます。
出血部位別の主な原因例
- 直腸・肛門付近:痔核、肛門裂傷、直腸ポリープなど
- S状結腸付近:潰瘍性大腸炎、ポリープ、大腸がんなど
- 上行結腸・横行結腸:炎症性腸疾患、ポリープ、大腸がんなど
下痢が赤茶色や鮮血色の場合、その発生部位を特定するために大腸全域のチェックが役立ちます。
観察範囲を確認するときに意識したい点
- スコープの到達範囲(盲腸まで届くか)
- 直腸付近の詳細観察
- 病変を見つけた際の生検・切除の可能性
- 必要に応じた追加検査(CTやMRIなど)
受診の目安と医療機関の選び方
赤茶色の下痢や鮮血が混じった下痢が見られたとき、どのタイミングで受診すべきか悩む方も少なくありません。大腸内視鏡検査が可能な医療機関を選ぶ際には、いくつかのポイントがあります。
早めの受診が望ましい症状
- 激しい腹痛をともなう血便
- 痛みが強い、または繰り返す下痢と出血
- 倦怠感や体重減少が続いている
- 排便時の出血が数日間以上持続
一時的な下痢でも、明らかに赤い血液が便に混ざっているときは受診を検討することが大事で、出血量が少なくても、潜在的な病気が進行している可能性があります。
内視鏡検査対応の施設を探すコツ
医療機関のサイトや情報誌などで「消化器内科」「胃腸科」「内視鏡検査対応」を掲げているところをチェックすると、すぐに検査を受けられる可能性が高いです。
診療予約システムを導入している施設を選ぶと待ち時間を減らしやすく、紹介状が必要な大きな病院だけでなく、消化器専門のクリニックや診療所も選択肢になります。
医療機関を選ぶときに確認したい要素
| 確認項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 診療科の専門性 | 消化器内科や胃腸科などがあるか |
| 内視鏡検査の実績 | 検査件数や医師の経験年数を把握できるか |
| 鎮静剤の有無 | 苦痛を減らすための鎮静剤を使用できるか |
| 診療時間や予約システム | 自分の生活サイクルに合わせやすいか |
| スタッフの対応 | 電話やメールでの問い合わせの印象はどうか |
かかりつけ医との連携
普段通院しているかかりつけ医がある場合、その医師に相談してから内視鏡検査を受けられる施設を紹介してもらう方法もあります。持病や常用薬がある方にとっては、連携のしやすい医療機関を選ぶといいでしょう。
二次検査や治療への移行
内視鏡検査の結果、大きなポリープやがんが見つかった場合などには、より専門的な医療機関での治療が必要になることがあり、その際には紹介状を持参して速やかに次のステップに進むと、治療の開始が遅れにくいです。
医療機関を選ぶ際に考慮したいポイント
- 受診の予約の取りやすさ
- 施設の場所や通院のしやすさ
- 医師との相性やコミュニケーションの取りやすさ
- 検査後に入院が必要になった場合の対応力
早期発見・早期対応が後々の治療負担を軽減することにつながります。
よくある質問
赤茶色の下痢や鮮血色の下痢が続くと、不安が高まるかもしれません。大腸内視鏡検査や治療に関して、よく尋ねられる疑問をまとめました。
- 下痢が赤茶色でも一時的に治まった場合は受診不要でしょうか
-
一時的に治まっても、また同じ症状が出るようなら医療機関を検討することをおすすめします。食生活による便の色の変化とは異なり、下痢と血液が混ざる状態は何度も繰り返すと消化管の病変を疑います。
- 検査は痛くないのでしょうか
-
鎮静剤を使う場合、検査中に強い痛みを感じることは少ないです。検査後に多少の腹部膨満感がある場合がありますが、医師や看護師がサポートします。不安なことは事前に相談すると安心です。
- 下痢が赤いときに自宅でできる対策はありますか
-
自宅での応急的な対策としては、水分補給と腸にやさしい食事を意識するくらいです。市販薬で止めるより、まずは原因を見極めることが大切なので、症状が続く場合は医療機関への受診を検討してください。
- 大腸内視鏡検査の費用はどのくらいかかるのでしょうか
-
保険診療であれば、病院やクリニックにもよりますが概算で数千円から数万円程度になることが多いです。ポリープ切除などの処置を行うと追加費用が発生します。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
実際に大腸カメラを受ける前に“どんな食事をどれだけ控えればいいの?”と疑問に感じた方へ。検査をスムーズに終えるコツを詳しく紹介しています。
【大腸ポリープの基本症状から治療法まで – 患者さんのための総合案内】
血便の原因について理解が深まると、検査で発見される可能性の高い大腸ポリープについても知りたくなる方が多いです。予防や早期発見との意外な繋がりが見えてくる内容です。
参考文献
Yokoyama T, Kondo H, Yokota T, Tokue Y, DaizoSaito, Shimada Y, Sugihara K. Colonoscopy for frank bloody stools associated with cancer chemotherapy. Japanese journal of clinical oncology. 1997 Apr 1;27(2):111-4.
Nagata N, Kobayashi K, Yamauchi A, Yamada A, Omori J, Ikeya T, Aoyama T, Tominaga N, Sato Y, Kishino T, Ishii N. Identifying bleeding etiologies by endoscopy affected outcomes in 10,342 cases with hematochezia: CODE BLUE-J Study. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2021 Nov 1;116(11):2222-34.
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Holtz LR, Neill MA, Tarr PI. Acute bloody diarrhea: a medical emergency for patients of all ages. Gastroenterology. 2009 May 1;136(6):1887-98.
Brandt LJ. Bloody diarrhea in an elderly patient. Gastroenterology. 2005 Jan 1;128(1):157-63.
Müller M, Willén R, Stotzer PO. Colonoscopy and SeHCAT for investigation of chronic diarrhea. Digestion. 2004 Apr 9;69(4):211-8.
Shah RJ, Fenoglio-Preiser C, Bleau BL, Giannella RA. Usefulness of colonoscopy with biopsy in the evaluation of patients with chronic diarrhea. The American journal of gastroenterology. 2001 Apr 1;96(4):1091-5.
Lu PH. Umbilical region pain, diarrhea, and bloody stools. Gastroenterology. 2011 Jan 1;140(1):e1-2.
TABRIZ CH, ZAHEDI M, HAYATBAKHSH AM, Jafari E, HAGHDOUST A, Hosseini SH. Frequency and distribution of microscopic findings in patients with chronic non-bloody diarrhea and normal colonoscopy.
Sujatha-Bhaskar S, Grigorian A, de Virgilio C. Fatigue and Bloody Diarrhea. InSurgery: A Case Based Clinical Review 2019 Oct 17 (pp. 303-309). Cham: Springer International Publishing.