超音波内視鏡検査とは、超音波を組み込んだ特殊な内視鏡で胃や腸の壁の内部構造を調べる方法で、胃カメラや大腸カメラなどの一般的な検査とは異なり、超音波画像によって病変の深さをより立体的にとらえることが可能です。
腫瘍の大きさや進展度を精密に確認しやすくなるため、がんをはじめとする消化器疾患の診断や治療方針の立案に役立ちます。
通常の検査だけでは判断がつきにくいケースで、超音波内視鏡が追加検査として活用されることも多いです。
この記事では、通常の内視鏡検査と異なるポイントや検査のメリット、検査の受け方、終了後の注意点などを詳しく紹介します。
超音波内視鏡検査の概要
胃カメラや大腸カメラと呼ばれる一般的な内視鏡と違い、超音波内視鏡では先端に超音波を発する装置が組み込まれています。
これにより、内視鏡で観察できる粘膜表面の情報だけでなく、粘膜の深い層や隣接する組織の断面像をとらえられる点が大きな特徴です。
超音波内視鏡検査で確認しやすい部分
超音波内視鏡検査は胃や大腸の内壁の深さだけでなく、周辺リンパ節や膵臓などの近接臓器の状態も評価できるため、腫瘍がどこまで浸潤しているのかを視認しやすく、早期発見や病期診断の精度向上につながります。
超音波内視鏡装置の基本構造
| 構成要素 | 役割 |
|---|---|
| 内視鏡本体 | カメラと光源を搭載し、胃や腸の内部を直接観察する |
| 超音波プローブ | 超音波を送受信し、組織の断面画像を得る |
| コントロール部 | 超音波周波数や角度を調整する |
| 処置チャンネル | 必要に応じて検体採取や処置器具を挿入するための通路 |
上記のように、一般的な内視鏡にプローブを加えた形で使われ、観察画像と超音波画像を同時に確認し、気になる病変の深さや周辺組織の様子を把握しやすくなるのです。
通常の内視鏡との一般的な違い
通常の内視鏡は主に粘膜表面を観察することに適しており、表層の病変や出血源などを確認しやすいです。
一方、超音波内視鏡では壁の内部や周辺臓器まで視野を広げられるため、腫瘍や炎症がどこまで広がっているのかを立体的にとらえる場合に役立ちます。
ただし、超音波装置を搭載しているため、通常内視鏡よりも機器がやや太くなる場合が多く、挿入時の不快感や鎮静剤の使用量に関しては個人差があります。
超音波内視鏡が活躍しやすいシーン
- 胃や大腸の粘膜下腫瘍が疑われるとき
- 膵臓や胆道系の病変を詳しく調べるとき
- 周辺リンパ節転移の可能性を評価するとき
- 腫瘍の深達度を詳細に把握し、治療法の選択を検討するとき
表面だけではわかりにくい病変や、従来の内視鏡検査で良悪性の判定が難しい腫瘤がある場合にも重要な情報を得られるため、多くのケースで早期の確定診断や正しい治療選択につながっています。
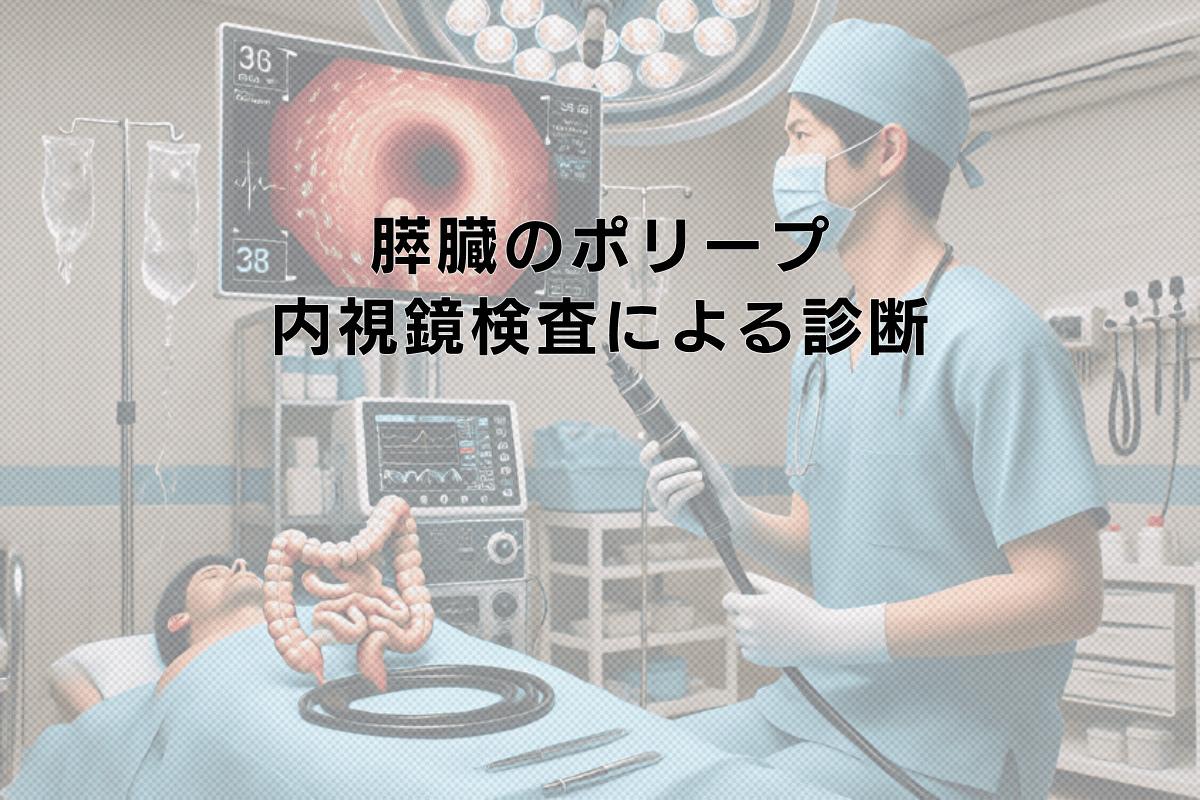
超音波内視鏡検査の歴史的背景
超音波内視鏡検査は、従来からある内視鏡検査と超音波検査技術の融合によって発展し、消化器分野で広く使われ始めたのは1980年代以降とされています。長年の改良や研究開発によって、より鮮明な画像と安全性の高い検査が可能です。
現在では多くの医療現場で採用され、内視鏡診断の大切な手段の1つとして活躍しています。
超音波内視鏡検査の目的
超音波内視鏡検査は、粘膜下や周囲の臓器を細かく調べるために行われます。通常の内視鏡だけでは得られない情報を補完することで、患者さんの症状や病変の性質を正確に把握できるメリットがあります。
病変の深達度評価
病変がどれほど深くまで浸潤しているのかを詳しく見極めることは、手術や内視鏡治療の方針を決定するうえで重要です。
たとえば早期がんと診断された場合でも、実際にどの層まで病変が及んでいるのかによって、内視鏡治療が適用になるか、外科的な手術が必要かが大きく異なります。

深達度評価における判断の目安
| 深達度の分類 | 内視鏡治療が検討されるケース | 手術が検討されるケース |
|---|---|---|
| 粘膜内(T1a) | 早期がんで、悪性度が低い腫瘍 | リスク因子の有無によって検討される |
| 粘膜下(T1b) | 腫瘍の大きさや位置によっては内視鏡的切除を検討 | 浸潤度が高ければ外科的切除が選択肢となる |
| 固有筋層(T2以降) | ほとんどの場合が外科的手術を必要とする | リンパ節転移の有無が治療方針を左右する |
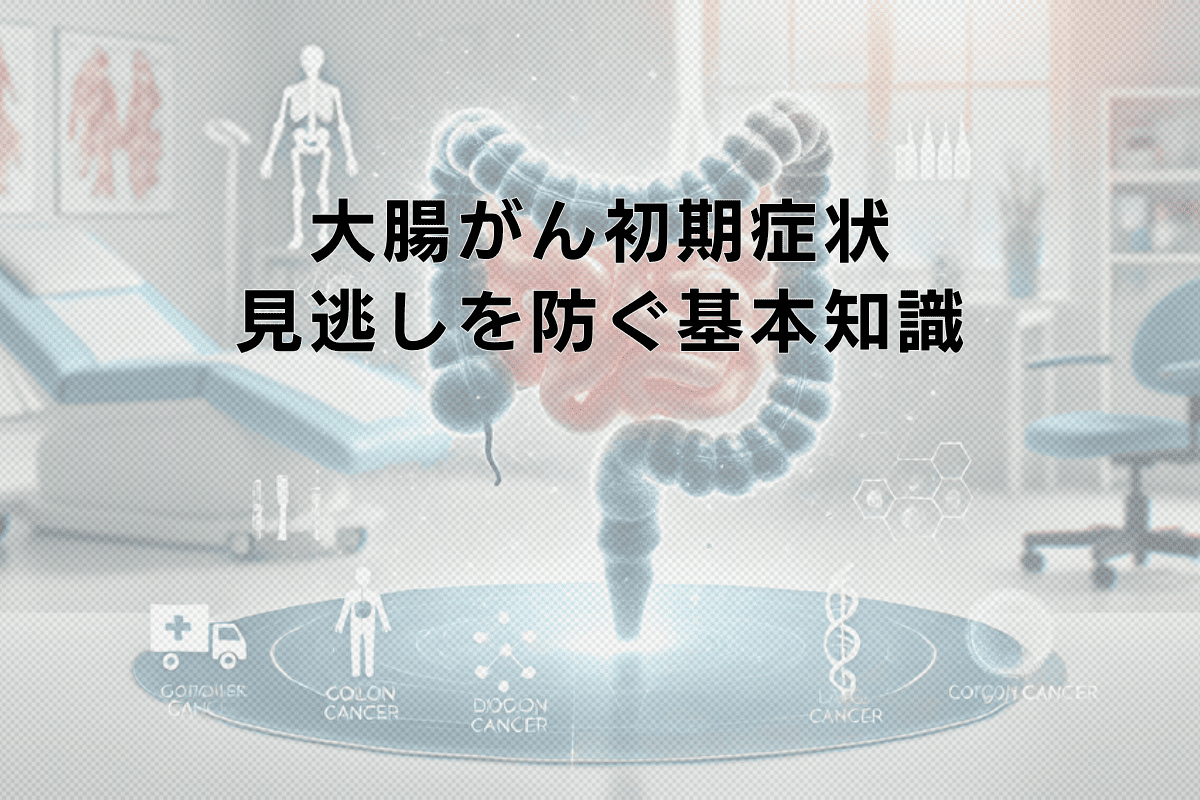
周辺臓器やリンパ節の評価
超音波内視鏡検査を行うことで、腸や胃の壁だけでなく、隣接する膵臓や肝臓の一部、胆のう、あるいは周囲のリンパ節が腫れているかどうかも検討できることがあります。
悪性腫瘍の場合、リンパ節転移の有無を早い段階で確認できるため、治療の選択に役立ちます。
良性腫瘍と悪性腫瘍の鑑別
表面的な内視鏡所見だけでは判断がつきにくい腫瘍もあり、粘膜下腫瘍のような、粘膜より深い層から発生する腫瘍は通常の内視鏡だけでは評価が難しいです。
超音波画像によって腫瘤の内部構造や境界の明瞭さを確認し、良性か悪性かの鑑別に寄与します。
穿刺による細胞診断
超音波内視鏡は、先端部分に処置チャンネルがついている機器があり、疑わしい部分を直接穿刺して細胞や組織を採取できます。超音波画像でターゲットを確認しながら穿刺できるため、精度の高い細胞診断が期待できます。
通常の内視鏡検査と異なるポイント
従来の胃カメラや大腸カメラと超音波内視鏡は、同じ「内視鏡」の名を持ちながらも機能面で明確な違いがあり、役割や検査内容を理解しておくと、検査を受ける際の不安や疑問を軽減しやすいです。
観察範囲の広がり
通常の内視鏡では、粘膜表面を直接観察し、潰瘍やポリープ、腫瘍などを目視で確認できます。
一方で超音波内視鏡は、その内部に超音波を発する装置を備え付けているため、壁の厚みや周辺リンパ節の状態まで観察の幅が広がり、より詳細な病状評価が可能です。
超音波内視鏡と通常内視鏡の比較
| 項目 | 通常内視鏡 | 超音波内視鏡 |
|---|---|---|
| 主な観察範囲 | 粘膜表面の状態 | 粘膜の深層や周辺臓器の断面像 |
| 挿入経路 | 口や肛門から挿入 | 口や肛門などから挿入(機器が太めになる場合あり) |
| 得られる情報 | 表面的な病変、色調、形状など | 病変の深達度、周辺組織やリンパ節の状態 |
| 検査時間の目安 | 5~30分程度(処置内容による) | 10~60分程度(穿刺等があると延長することあり) |
| 使用する鎮静剤の可能性 | ケースによって少量使用 | 通常内視鏡より多めの場合がある |
装置の違いと検査の体感
超音波を発する装置が付いている分、検査時に使用する機器の径がやや太くなりがちで、口から挿入する際につらさを覚えやすい場合もあります。
そのため、場合によっては鎮静剤や鎮痛剤を多めに使い、患者さんの負担を減らすことが検討されます。

得られる画像情報の質
超音波内視鏡では、内視鏡カメラの映像だけでなく、超音波による断層画像が手がかりとなり、腫瘍がどの層から発生しているかや、リンパ節への転移状況がわかりやすくなる点は大きな利点です。
しかし、空気や脂肪組織など、超音波が通過しにくい環境だと画質や精度が下がることもあります。
費用や保険適用の範囲
通常の内視鏡検査よりも高度な技術を要するため、かかる費用はやや高額になる傾向がありますが、医師が必要性を判断して行う場合は保険適用となることが多いです。

超音波内視鏡検査で診断しやすい疾患
超音波内視鏡は、消化器系疾患の中でも特に難易度の高い部位の診断に貢献し、早期がんや粘膜下腫瘍、胆膵疾患などで真価を発揮します。
早期胃がんや大腸がん
通常の内視鏡でも早期がんを発見することはできますが、実際にどの層まで浸潤しているかは超音波内視鏡を使うと把握しやすいです。
粘膜内でとどまっている場合は内視鏡による切除が検討されるケースが多いですが、粘膜下層や筋層まで侵食していると手術の必要性が高まり、こうした判断の精度を上げるために利用されます。
早期がん診断のポイント
- 病変の大きさや形状だけでなく、深達度を確認する
- 内視鏡切除の適応範囲を超えているか否かを評価する
- 超音波画像でリンパ節の腫れを確認し、転移の有無を推測する
上のような視点をもとに、病期診断の精確さを高められる点が特徴です。
粘膜下腫瘍や神経内分泌腫瘍
粘膜下腫瘍は、粘膜よりも深い層に発生するため、通常の内視鏡では表面が盛り上がっている程度しかわからないことが多いです。超音波内視鏡で内部の構造を確認することで、良性か悪性かの判断や、切除の適応を検討しやすくなります。
また、神経内分泌腫瘍のように内分泌機能を有する腫瘍の場合、超音波内視鏡で形状や血流を把握することが診断の手助けとなる場合があります。
粘膜下腫瘍に関する種類別の見分け方
| 種類 | 特徴 | 検討される治療 |
|---|---|---|
| GIST(消化管間質腫瘍) | 消化管の筋層などから発生し、良性から悪性まで幅広い病態を示す | 大きさやリスクに応じて外科的切除または内視鏡手術 |
| 脂肪腫 | 脂肪組織が固まり、やわらかい腫瘤を形成する | 良性であれば経過観察も選択肢となる |
| 神経鞘腫 | 神経鞘から発生し、辺縁が比較的はっきりしていることが多い | 良性が多いが、大きい場合は手術で摘出 |
| 神経内分泌腫瘍 | ホルモンを産生する細胞から発生し、多彩な症状を引き起こすことあり | 内視鏡切除または外科的切除 |
膵臓や胆道系の病変
胃カメラや大腸カメラでは直接見ることが難しい膵臓や胆道の状態も、超音波内視鏡なら確認しやすい場合があります。
特に膵臓は体の表面から深いところにあるため、一般的な超音波検査(体表から行うエコー)ではがんや腫瘍を見つけづらいことがあります。そこで、内視鏡を胃や十二指腸まで進めて膵臓に近づき、超音波を当てる方法が有効です。
その他の消化器疾患
慢性膵炎や胆のうポリープ、肝門部周辺リンパ節の腫れなど、消化器周辺の病変を幅広く評価し、通常の内視鏡検査と組み合わせることで、総合的な消化器内科の診断における精度アップが期待できます。
検査の流れと事前準備
超音波内視鏡検査を受けるときには、通常の内視鏡検査とほぼ同様の準備や流れがありますが、違いとしては検査時間や鎮静剤の使用方法が変わる場合があることが挙げられます。
予約と問診
- かかりつけの医療機関や検査を行う施設で予約をとる
- 医師による問診を受け、既往症や現在の症状などを説明する
- 血液検査や心電図など必要な事前検査を指示される場合がある
- 服用中の薬について相談し、休薬や調整が必要かどうかを確認する
問診時に不安や疑問があれば遠慮なく質問し、検査の必要性やメリットを自分の中で整理すると安心です。
事前準備に関する注意事項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 飲食制限 | 前日の夜から当日までの絶飲食について案内を受ける場合がある |
| 検査服の着用 | 院内で指定の検査着に着替えることが多い |
| 鎮静剤や麻酔の計画 | 鎮静剤を使用する場合は、検査後の送迎手段を考慮する必要がある |
| 服用薬の調整 | 血液をサラサラにする薬などは主治医の判断で調整を行う場合がある |
検査前日の過ごし方
胃や大腸の検査を行う場合、検査前日は消化に優しい食事を選んで早めに就寝してください。特に大腸の場合は下剤を飲んで腸内をきれいにする手順があるため、夕食は軽めに済ませましょう。
水分補給は十分に行い、アルコールやカフェインの多い飲料は控えてください。
前日のメニュー
- 主食:うどんやおかゆなど消化しやすいもの
- 主菜:白身魚の煮付けや鶏ささみなど脂分の少ない食材
- 副菜:柔らかく煮た野菜スープ
- 飲み物:水や麦茶など刺激の少ないもの
食物繊維の多い野菜や果物、油っこい食品などは避けると腸内をきれいにしやすいです。

当日の検査手順
多くのケースで、医師や看護師の指示に従いながら検査を受け、場合によっては鎮静剤を使用することもあるため、次のような流れが一般的です。
- 受付を済ませ、問診や血圧測定などを受ける
- 着替えや鎮静剤の準備を行う
- 検査室で内視鏡を挿入し、超音波による観察を進める
- 必要に応じて病変部の穿刺や組織採取を行う
- 検査終了後は安静室などで休む
検査自体は10~60分程度かかることがありますが、さらに鎮静剤の影響が残る場合は休憩や点滴を行うケースもあります。
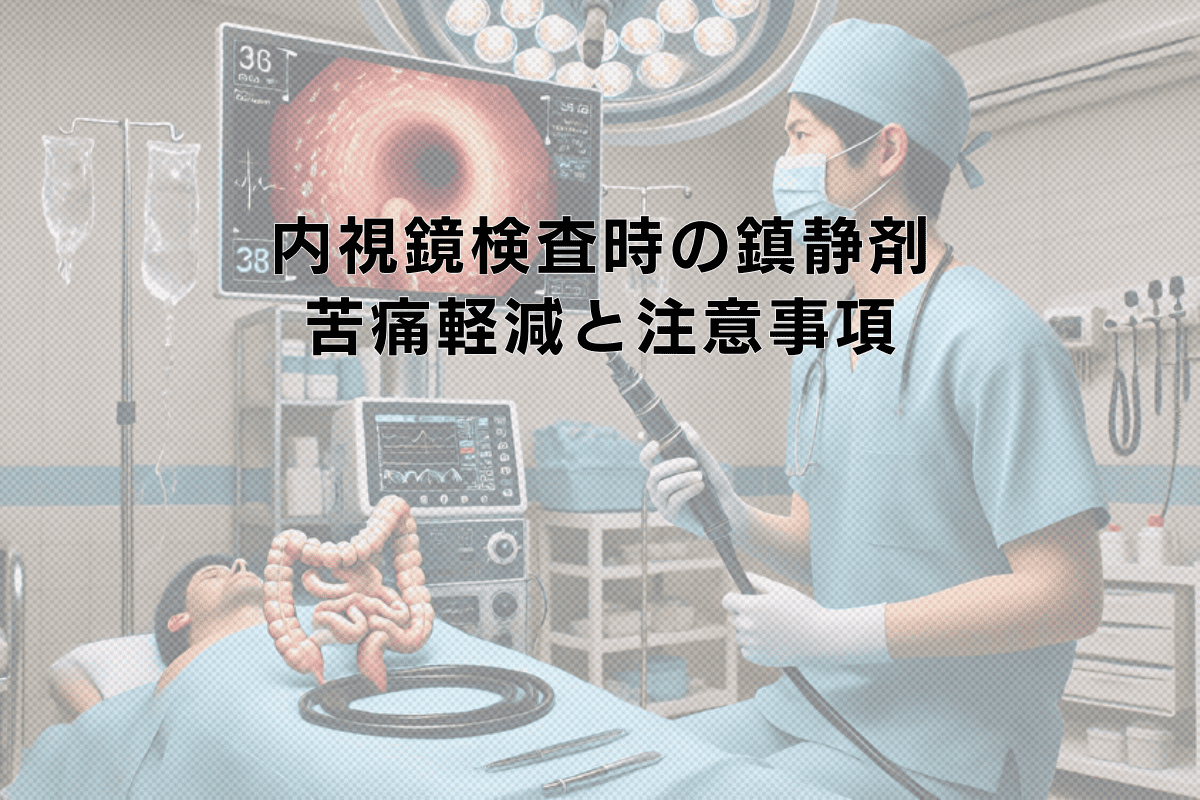
検査における安全管理
| 安全管理項目 | 具体的対策 |
|---|---|
| 鎮静剤の使用 | 血圧や心拍をモニターしながら慎重に投与する |
| 呼吸の確認 | 酸素投与やパルスオキシメーターの装着で酸素飽和度を監視する |
| 穿刺の際のリスク管理 | 出血や穿孔のリスクを考慮し、医師が慎重に操作する |
| アレルギー反応 | 麻酔薬や消毒薬に対するアレルギーを事前確認する |
医療スタッフがリスクを常に把握し、安全に配慮した環境で検査を進めます。
検査後の観察
検査後は、鎮静剤の影響でしばらくぼんやりすることがあるため、無理をせずに安静に過ごし、検査内容によっては、穿刺した部分からの出血や腹痛が起こらないか観察することも必要です。
医師からの指示があるまでは飲食を控える場合があります。
検査のメリットと考え方
超音波内視鏡検査は、詳細な情報を得やすいですが、通常の内視鏡よりも患者さんの負担が大きくなることがあるため、検査を受ける意味を正しく理解しておくことが大切です。
精密な診断につながる
腫瘍の深達度やリンパ節転移の有無をより高精度に確認しやすいため、がんのステージ判定や治療法の選択において大きな利点があり、治療期間や合併症リスクなどを見通すうえでも役立ちます。
- 内視鏡で確認できない深部情報の把握
- 周辺臓器との位置関係の正確な評価
- 必要に応じて直接穿刺による細胞や組織の採取
内科的治療と外科的治療の判断材料
| 診断の要素 | 内科的治療が検討されるケース | 外科的治療が検討されるケース |
|---|---|---|
| 病変の深達度 | 粘膜下層までの浅い病変 | 筋層以上に侵潤し、リンパ節転移のリスクが高い場合 |
| 大きさや形状 | 小さい腫瘍や限局性のあるポリープなど | 大きく増殖して他臓器にも影響が及ぶ場合 |
| 転移の有無 | 近接リンパ節への転移が認められない場合 | 転移が認められる場合や、悪性度が高い場合 |
| 患者の全身状態 | 体力があり、内視鏡による低侵襲治療を選択しやすい場合 | 高齢や合併症が多い場合でも積極的に手術を検討することあり |
患者への負担
検査の際には鎮静剤を使用することが多く、検査後の一定時間は安静が必要となるケースがあります。また、機器の直径が太めになる分、挿入時の負担が大きいと感じることもあります。
ただし、安全性に十分配慮しながら行われるため、大きなリスクは低いです。
検査後の注意点とフォローアップ
超音波内視鏡検査は、必要に応じて穿刺を伴うため、終了後も慎重な経過観察を心がけると安心です。痛みや出血などの合併症は稀ですが、何か気になる症状がある場合は早めに医療機関へ連絡してください。
検査終了後の過ごし方
- 鎮静剤を使用した場合は、検査後にしばらく安静にしてから帰宅する
- 当日は激しい運動や車の運転を避け、早めに就寝を心がける
- 痛みや吐き気が強く続く場合は医師に相談する
- 飲食は医師や看護師の指示に従って再開する
体がだるい、腹部に違和感があるなどの軽い症状は、時間とともに改善することが多いですが、急激に悪化するようなら受診が必要です。
検査当日のチェックポイント
| チェック項目 | 理由 |
|---|---|
| 発熱や寒気がないか | 穿刺後の感染などの兆候を早期発見するため |
| 血便や黒色便が出ていないか | 内視鏡下での処置後の出血などを確認するため |
| 強い腹痛がないか | 消化管の穿孔や合併症の可能性を排除するため |
| めまいや意識朦朧がないか | 鎮静剤の副作用や脱水などを疑うため |
組織や細胞診断の結果
穿刺で採取した組織や細胞の検査結果が出るまでは、数日から1~2週間かかることがあります。その間、通常の生活を送って差し支えないケースが多いですが、万が一体調に変化を感じたら医療機関と連絡してください。
次回受診の目安
超音波内視鏡の結果や患者の全身状態によって、追加で通常の内視鏡検査やCT、MRIなどの画像診断を行う場合があります。
再度の内視鏡検査が数か月先になることもあれば、転移リスクが高いと判断されればより短期間でフォローアップを行うケースもあります。
- 良性の可能性が高い場合:定期的な内視鏡検査で経過観察
- 悪性が疑われる場合:外科手術や内視鏡的切除、抗がん剤治療などの検討
- 病変が不明確な場合:専門的な追加検査(CT、MRI、PETなど)
日常生活への復帰
検査後の体調が安定していれば、翌日から通常の生活に戻る人が多いですが、無理をして疲労がたまると免疫力が低下し、感染症を引き起こしやすくなる懸念もあります。
十分な睡眠や栄養バランスを意識した食事を心がけるとともに、医師からの指示を守って体を労わることが望ましいです。
よくある質問
- 検査時に強い痛みはありますか?
-
通常の内視鏡検査と同様に、挿入時の違和感を覚えることがありますが、鎮静剤を使用することで痛みを感じにくくすることが可能です。
穿刺を行う場合も、狙った部位に的確に針を刺すため、強い痛みを感じる場面は多くありません。万が一痛みや不快感が強い際は、看護師や医師にすぐ伝えてください。
- どれくらいの時間がかかるのでしょうか?
-
検査の目的や追加の処置内容によって変わり、単に観察だけの場合は10~20分ほどで終了することもありますが、組織採取を含むと30~60分程度を見込むことがあります。
終了後の安静時間も合わせると、半日程度を要するケースが少なくありません。
- 食事や仕事はいつからできますか?
-
鎮静剤を使用した場合、当日は反応速度や集中力が低下するため、車の運転や重作業を避けるべきとされています。
食事の再開は、医師からの許可が下りてからが望ましいです。多くの人は翌日には普通の食事や仕事に復帰していますが、個人差があるため、無理のない範囲で様子を見ながら進めましょう。
- 妊娠中でも検査を受けられますか?
-
妊娠中の検査は、胎児への影響や母体の安全を最優先するため、慎重に検討されます。
超音波内視鏡検査がどうしても必要な場合には、産科主治医とも連携し、リスクとベネフィットをしっかり相談してから決定することになります。
安全対策を整えながら行うケースもありますが、状況によっては出産後に検査を延期する方が良い場合もあります。
次に読むことをお勧めする記事
【鎮静剤を使用した痛みの少ない内視鏡検査について】
超音波内視鏡に興味はあっても『苦しそう』とためらう方へ。鎮静下での内視鏡体験を具体的な流れや注意点とともに紹介しています。検査当日のイメージがわき、安心して準備ができます。
【大腸がん検査方法の選び方 – 血液検査から内視鏡検査まで】
超音波内視鏡を知った今、大腸がん検査の選択肢も整理してみませんか?血液・便潜血から内視鏡まで検査法の特徴を比較し、最適な受診計画を立てるヒントになります。
参考文献
Yanai H, Noguchi T, Mizumachi S, Tokiyama H, Nakamura H, Tada M, Okita K. A blind comparison of the effectiveness of endoscopic ultrasonography and endoscopy in staging early gastric cancer. Gut. 1999 Mar 1;44(3):361-5.
Nishimura M, Togawa O, Matsukawa M, Shono T, Ochiai Y, Nakao M, Ishikawa K, Arai S, Kita H. Possibilities of interventional endoscopic ultrasound. World Journal of Gastrointestinal Endoscopy. 2012 Jul 16;4(7):301.
Tamura T, Ashida R, Kitano M. The usefulness of endoscopic ultrasound in the diagnosis of gallbladder lesions. Frontiers in Medicine. 2022 Aug 29;9:957557.
Ishihara R, Mizusawa J, Kushima R, Matsuura N, Yano T, Kataoka T, Fukuda H, Hanaoka N, Yoshio T, Abe S, Yamamoto Y. Assessment of the diagnostic performance of endoscopic ultrasonography after conventional endoscopy for the evaluation of esophageal squamous cell carcinoma invasion depth. JAMA Network Open. 2021 Sep 1;4(9):e2125317-.
Shimizu S, Itaba S, Yada S, Takahata S, Nakashima N, Okamura K, Rerknimitr R, Akaraviputh T, Lu X, Tanaka M. Significance of telemedicine for video image transmission of endoscopic retrograde cholangiopancreatography and endoscopic ultrasonography procedures. Journal of hepato-biliary-pancreatic sciences. 2011 May;18:366-74.
Hashimoto S, Nakaoka K, Kawabe N, Kuzuya T, Funasaka K, Nagasaka M, Nakagawa Y, Miyahara R, Shibata T, Hirooka Y. The role of endoscopic ultrasound in the diagnosis of gallbladder lesions. Diagnostics. 2021 Sep 28;11(10):1789.
Isayama H, Nakai Y, Itoi T, Yasuda I, Kawakami H, Ryozawa S, Kitano M, Irisawa A, Katanuma A, Hara K, Iwashita T. Clinical practice guidelines for safe performance of endoscopic ultrasound/ultrasonography‐guided biliary drainage: 2018. Journal of Hepato‐Biliary‐Pancreatic Sciences. 2019 Jul;26(7):249-69.
Matsuyama M, Ishii H, Kuraoka K, Yukisawa S, Kasuga A, Ozaka M, Suzuki S, Takano K, Sugiyama Y, Itoi T. Ultrasound-guided vs endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration for pancreatic cancer diagnosis. World Journal of Gastroenterology: WJG. 2013 Apr 21;19(15):2368.
Kawakubo K, Kawakami H, Kuwatani M, Kubota Y, Kawahata S, Kubo K, Sakamoto N. Endoscopic ultrasound-guided choledochoduodenostomy vs. transpapillary stenting for distal biliary obstruction. Endoscopy. 2016 Feb;48(02):164-9.
Nickl NJ, Bhutani MS, Catalano M, Hoffman B, Hawes R, Chak A, Roubein LD, Kimmey M, Johnson M, Affronti J, Canto M. Clinical implications of endoscopic ultrasound: the American Endosonography Club Study. Gastrointestinal endoscopy. 1996 Oct 1;44(4):371-7.










