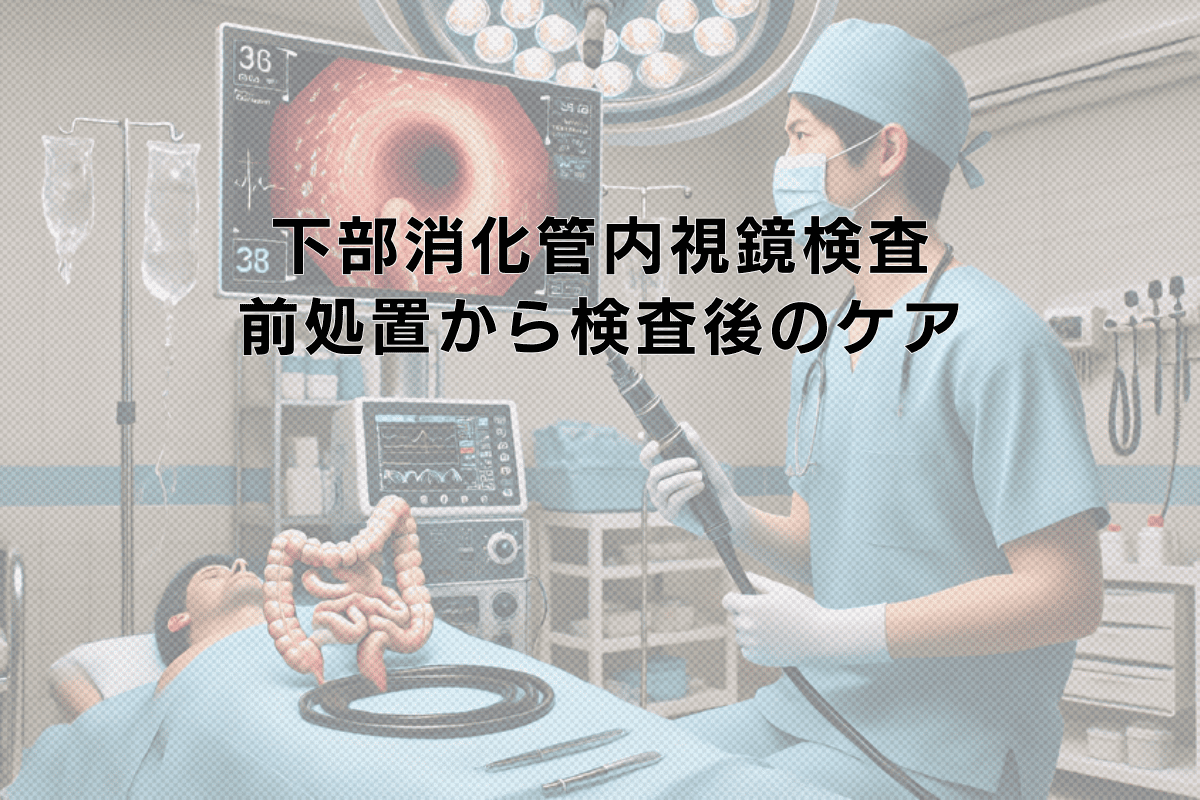消化器の病気が疑われる場合や、大腸がんなどの早期発見を目的とした検査として、下部消化管内視鏡検査は広く行われています。
検査に対して抵抗を感じる方も多いかもしれませんが、前処置を理解し、医療スタッフと相談しながら準備を進めれば、スムーズに受けられることが多いです。
この記事では、下部内視鏡検査を検討している方や医師から案内された方に向けて、前処置の進め方や検査当日の流れ、検査後の注意点などを詳しく紹介します。
下部消化管内視鏡検査とは
大腸や小腸の一部など、下部消化管を直接観察するための方法を指し、直腸や結腸に生じるポリープや腫瘍、炎症、潰瘍などを正確に確認できる点が特徴です。
さらに病変部位から組織を採取する生検やポリープの切除も同時に可能であり、早期の段階で病気を診断できるメリットがあります。
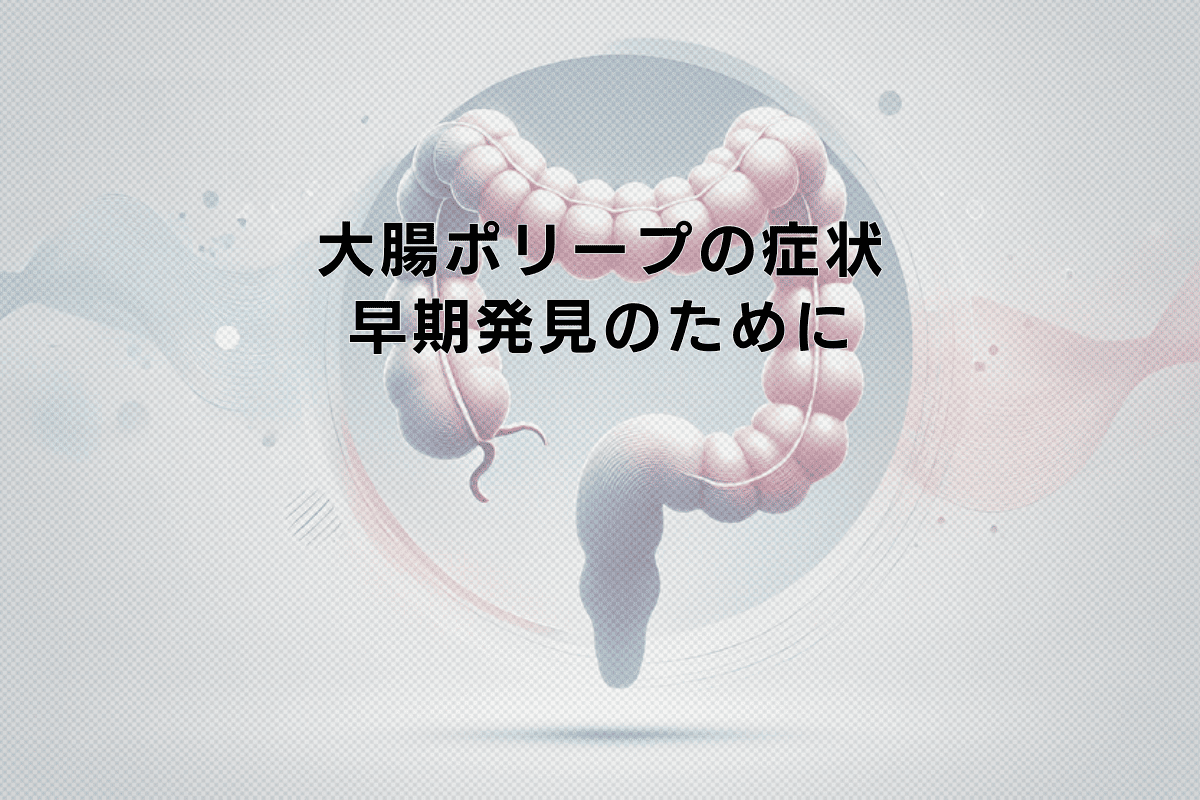
下部消化管を観察する目的
消化器症状が出現した際に、なぜ下部消化管の観察が重要なのでしょうか。
医師は腹痛や便通異常、下血などの症状がある患者さんに対して、大腸内の病変の有無を確認します。
肉眼では確認できない粘膜のわずかな変化を直接目視で評価することで、潜在的な病気を見落としにくくなるのです。
観察範囲と使用機器
観察範囲は肛門から大腸全域までが中心で、機器は先端に小型カメラやライトを搭載したスコープを使用し、医師がモニターを見ながら大腸内を移動させます。
スコープは細めのものや、軟性のものなど、患者さんの負担を軽くするためにさまざまな改良が重ねられています。直腸から盲腸付近までをくまなくチェックし、小腸末端の回腸まで確認する場合もあります。
どのような症状の人が受けることが多いか
便の性状が変わったり、下血があったり、腹痛が続いていたりする場合に医師が下部内視鏡検査を勧めることがよくあり、また、健康診断で便潜血陽性となった場合や、大腸がん検診で要精密検査となった場合にも検討されることが多いです。
症状がなくても予防目的で定期的に受ける方も増えています。
安心して受けるために大切なこと
「恥ずかしい」「痛そう」「怖い」という思いが強いと、検査に対してネガティブなイメージが先行するかもしれません。疑問や不安をできるかぎり医師・看護師に相談し、前処置や検査の流れを十分に把握することが重要です。
そのうえで日程や準備を進めることで、安全かつ負担の少ない検査を目指すことができます。
下部消化管内視鏡検査と他の検査の違い
| 検査名 | 観察方法 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 下部消化管内視鏡検査 | カメラを肛門から挿入して直接観察 | ポリープ切除や生検が可能で、詳細な診断に向いている |
| 便潜血検査 | 便中の血液の有無を化学的に調べる | 負担が少ないが、陽性の場合は精密検査が必要となる |
| 大腸CT(仮想大腸内視鏡) | CT画像を用いて3Dモデルを作成し観察 | 観察はできるが組織の採取やポリープ切除はできない |

検査の目的と必要性
大腸がんなどの悪性疾患だけでなく、慢性的な腸炎や腸管の奇形など、さまざまな病変を見つけられるのが下部消化管内視鏡検査の利点です。症状がなくても、定期的な検査による予防や早期発見がより良い健康管理につながります。
早期発見と大腸がん予防
大腸がんは早期で見つけられれば治療成績が良好ですが、初期段階では症状が出にくい病気でもあり、下部内視鏡検査でポリープを発見し、その場で切除することでがんになるリスクを減らすことが期待できます。
実際に、大腸内視鏡でポリープを切除しておくと、その後の大腸がん発症率が低下するという報告もあります。
大腸がん以外の疾患の診断
ポリープや腫瘍だけでなく、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患、憩室炎、虚血性大腸炎などを診断する際にも医師が下部内視鏡検査を選択することがあります。
粘膜の状態を直接見て病変を把握できるため、血液検査や画像検査だけでは得られない情報を得られる点が特徴です。
症状がない場合でも有意義な理由
便秘や下痢などの症状がなくても、大腸ポリープや初期の病気が潜んでいるケースがあります。
過去に大腸ポリープが見つかった方や、家族歴で大腸がんがある方、高脂肪食の習慣が長い方などは定期的な内視鏡検査を視野に入れると安心感につながるでしょう。
保険適用と費用面
大腸がん検診の精密検査として行う場合や、医師が症状に基づいて必要性を判断した場合には健康保険が適用されるケースが多いです。
費用は検査の内容や検査時の処置(生検、ポリープ切除など)によって変わります。
費用の概要と考慮点
| チェック項目 | 自己負担割合ごとの目安費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 検査のみ(組織採取なし) | 3割負担で約5,000円〜10,000円程度 | 検査機関や保険点数によって変化 |
| 組織採取あり | 3割負担で約10,000円〜20,000円程度 | 病理検査費用、採取個数に応じて増減する |
| ポリープ切除あり | 3割負担で約20,000円〜40,000円程度 | 入院を要する場合や切除法により差が生じる |

下部内視鏡検査の前処置
下部内視鏡検査の前処置は、診断精度を左右する大切な準備です。腸内に便が残っていると観察が妨げられ、病変の見落としにつながる可能性があり、正しい手順で準備を進めることで、医師が大腸内部をより鮮明に把握できます。
検査前日の食事制限
検査前日は消化に時間がかかり、腸内に長く滞留しやすいものを避ける必要があります。繊維質の多い野菜や海藻、キノコ類、脂っこい食品などは便が残りやすいため、医師や看護師から指示を受けた上で控えると安心です。
また、水分は適度に摂取し、便が硬くならないよう注意します。
下剤の服用と腸内洗浄剤の利用
検査当日までに処方された下剤を服用する場合もあり、さらに検査当日は腸内洗浄剤(経口腸管洗浄薬)を飲みながら排便を繰り返し、便をできるかぎり排出します。
腸内洗浄剤には何種類かあり、味や飲む量にやや違いがあります。体質によっては体調が崩れやすくなるため、なるべく早めに担当者へ体調を報告しながら進めましょう。
前処置がうまくいかない場合の対策
飲みづらさや吐き気が強い場合、下剤の量や濃度を調整する場合があり、便の状態が目標に達しないと、検査時間が長引いたり、再検査が必要になるリスクもあります。
個人差があるため、早めに医療スタッフへ相談して対策を取ることが望ましいです。
注意すべき薬剤や持病
持病で降圧薬や抗凝固薬などを内服している場合、検査当日または前日に服用を調整することがあります。たとえばワルファリンなどの血液をサラサラにする薬は、ポリープ切除などの際に出血リスクを増やす可能性があります。
自己判断で薬を中止するのではなく、必ず主治医に相談してください。
主な腸内洗浄剤の種類と特徴
| 薬剤名 | 一般的な飲む量 | 味や飲みやすさ | 留意点 |
|---|---|---|---|
| ポリエチレングリコール系 | 約2L | やや塩味や甘味がある場合が多い | 吐き気が出る場合は医師に報告する |
| ピコスルファート系 | 約1.8〜2L | レモン風味など飲みやすいタイプ | 下剤との併用で効果を高める |
| マグネシウム系 | 約1.5〜2L | 若干苦味を感じることがある | 腎機能が低下している人は慎重に |

検査当日の流れ
下部内視鏡検査当日は、院内での受付から検査終了まで医療スタッフがサポートを行います。時間や順番については混雑状況によって変わることがありますが、一般的な流れを把握しておくと落ち着いて検査にのぞめます。
受付と問診
まずは病院やクリニックの受付で手続きを行い、問診表の内容を確認し、前処置の進捗や体調について医師や看護師と話し合い、場合によっては下剤を追加で使用するかが検討されます。
血圧や脈拍などのバイタルサインも確認して、安全に検査を実施できるかを評価します。
スコープ挿入と大腸内の観察
医師は肛門からスコープを挿入し、大腸を奥へと進め、腸の曲がり角では痛みが生じやすいですが、鎮静剤を使うと強い痛みや苦痛を感じにくくなることがあります。
大腸全域を観察しながら必要があればポリープの切除や組織採取を行い、検査が終了したらゆっくりとスコープを引き抜きます。
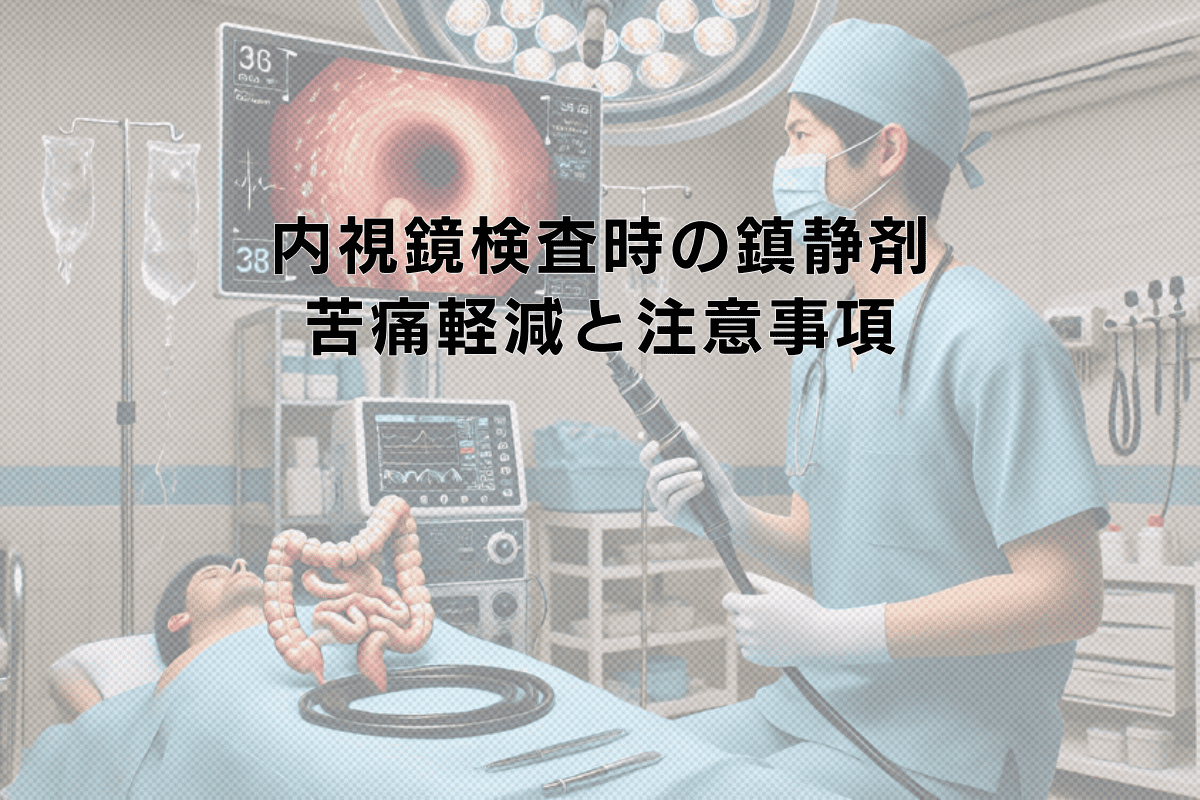
検査当日のタイムテーブル
| 項目 | 目安の時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 受付・問診 | 来院後〜30分 | 体調確認や前処置の状況確認 |
| 検査着への着替え | 約5〜10分 | ロッカーなどに荷物を預けることが多い |
| 内視鏡検査本体(挿入〜抜去) | 約15〜30分 | 個人差あり。処置の内容によっても変化 |
| 検査後の安静・観察 | 約30〜60分 | 麻酔や鎮静剤が効いている場合は休憩を長めに取る |
安静室での休息と帰宅の準備
検査終了後は安静室やリカバリールームで一定時間休むことが多く、鎮静剤を使用した場合には、意識がはっきりしてくるまで安静が必要です。帰宅後の食事や入浴のタイミングについては、医師や看護師から説明を受けましょう。
当日持参するもの
- 保険証、医療証
- 検査前処置の薬(予備分)
- 必要書類(問診票、検査案内など)
- 楽な服装と着替え(帰宅時用)
- 生理用品(女性の場合、念のため)
合併症とリスクへの対策
下部内視鏡検査は安全性の高い手技とされていますが、まったくリスクがないわけではありません。出血や穿孔などの合併症が起こる可能性をゼロにはできませんが、医師の熟練度や事前準備によってリスクを低減できます。
出血の可能性と対応
ポリープ切除や組織採取を行った場合、出血が生じる場合があります。大半は少量で自然に止まりますが、まれに入院などの対応が必要なケースもあります。
抗凝固薬を服用している方や血が固まりにくい病気を持つ方は、検査前に医師と服用プランを慎重に相談してください。
腸管穿孔に関するリスク
内視鏡挿入時やポリープ切除時に腸管を傷つけると、穿孔が起こるリスクがあり、まれですが重篤化する可能性があるため、経験豊富な医師が細心の注意を払って実施します。
腸が強い炎症を起こしている患者や高度な癒着がある患者さんは、事前の診察や画像検査で十分に状態を把握してから内視鏡検査に進みます。
鎮静剤や麻酔による副作用
鎮静剤や麻酔を使用した場合、呼吸抑制や血圧低下などが起こることがあるため、検査中は医療スタッフがバイタルサインを監視し、必要に応じて薬剤の量を調整します。
気分が悪くなったり、強い眠気が持続する場合は、遠慮せずに早めに申し出てください。
合併症を防ぐためのポイント
患者自身も協力することで、合併症のリスクを軽減でき、医師から指示された前処置を守ることや、検査中に痛みなどの不快感があれば正直に伝えることが大切です。
主な合併症と対処
| 合併症 | 具体的な内容 | 主な対処法 |
|---|---|---|
| 出血 | 組織採取部位や切除部位からの出血 | クリップ止血、入院での経過観察など |
| 穿孔 | 腸管に穴が空いてしまう | 症状が重ければ外科治療の検討 |
| 麻酔による副作用 | 呼吸抑制、低血圧、アレルギー反応 | 投薬量の調整、酸素投与、アレルギー対策など |
検査後のケアと生活上の注意点
検査後は大腸内に微小な傷ができている可能性があり、出血や腹痛などが起こる場合もあります。正しいケアを行えば、ほとんどの人は短期間で普段の生活に戻れます。
検査当日の過ごし方
鎮静剤を使用した場合は眠気やふらつきが残ることがあるため、自分で車やバイクを運転して帰宅するのは危険なので、公共交通機関や家族の送迎を利用するのが一般的です。激しい運動やアルコール摂取は避け、できるだけ安静に過ごします。
食事と水分摂取
多くの場合、検査後数時間すれば少量の水分を口にして問題ありませんが、ポリープ切除を行った場合は、一定期間は刺激の強い食事を控え、消化に良いものを摂ることが望ましいです。
出血や腹痛の有無を確かめながら段階的に普通の食事に戻します。
排便や腹部症状の観察
検査後は腸内に残った空気が原因で腹痛やお腹の張りを感じる場合があり、自然にガスを排出することで症状が軽快するケースがほとんどです。便に血が混じっているような異常があれば医療機関に連絡してください。
検査後に気をつける行動
- 当日はなるべく安静にして体力を回復する
- シャワーなどは短めに済ませ、長湯は避ける
- 強い腹痛や大量の下血があればすぐに受診する
- 普段と違う体調の変化を感じたら早めに報告する
ポリープを切除した場合の注意点
ポリープを切除した部位は一時的に出血リスクが高まるため、約1週間程度は重い物を持ち上げたり、激しい運動を行わないようにし、飲酒や辛いものなど、粘膜を刺激しやすい食事も控えましょう。
傷が治るまでは定期的な通院や経過観察が必要であり、再発の有無もチェックします。
日常生活への早期復帰に向けたメモ
| 注意事項 | 具体的な対策 |
|---|---|
| 食事 | やわらかく消化に良い食事を中心にして様子を見る |
| 運動 | ウォーキングなどの軽度な動きから始めて、無理をしない |
| 入浴 | 軽いシャワー程度にして、湯船に浸かるのは翌日以降に見送るケースが多い |
| 仕事復帰 | デスクワークなどは翌日から可能な場合もあるが、無理をしない |
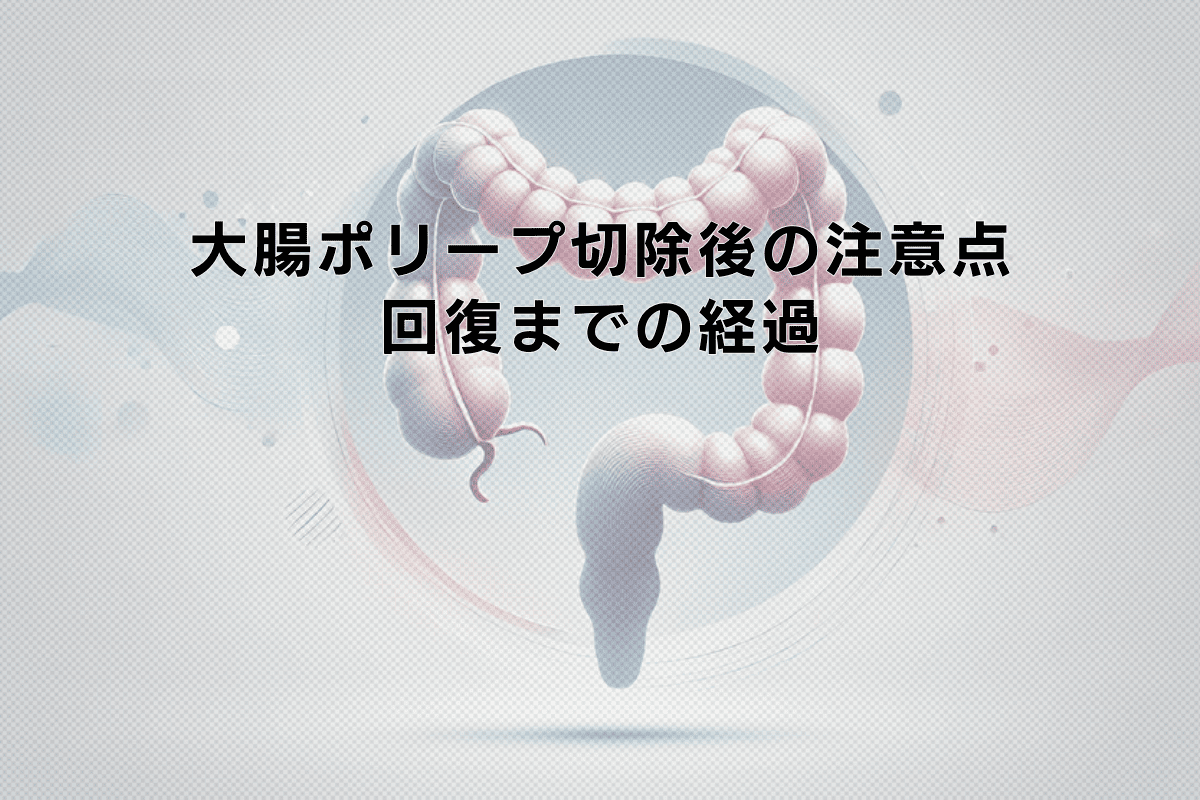
検査時の不安や疑問への対応
下部内視鏡検査には「恥ずかしい」「痛そう」「検査時間が長いのでは」などの不安を抱く方が少なくありません。どんな疑問や不安があっても、医療スタッフに相談すれば必要な情報を得られます。
痛みの軽減策
肛門からスコープを挿入するときに多少の違和感や痛みを感じる方もいますが、最近では鎮静剤を用いることで、眠っているような状態のまま検査を受けるケースも増えています。
痛みを最小限に抑えるために、体位を変えたり、腸の曲がり角に到達するときはスコープの扱いを工夫したりします。
鎮静剤使用時の注意事項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日帰りの場合の留意点 | 鎮静剤を使うと当日は眠気や集中力の低下が残るため、車の運転や重要な決定は控える |
| 長時間効くケースがある理由 | 個人差があるため、体質によっては予定よりも長く薬の効果が持続する |
| 不安なときの相談方法 | 外来の看護師や主治医に事前に伝え、少量から開始するなどの調整を検討できる |
プライバシーの配慮
肛門からスコープを挿入するため、通常は検査室が個別に区切られた空間になっており、検査着を着用して肌を大きく露出しないよう工夫しています。
恥ずかしさをやわらげるため、女性患者には女医・女性スタッフが検査を補助するなどの配慮も実施しているケースがあります。
受診タイミングの選び方
症状がなくても、40代後半から50代にかけては検診で要精密検査となる例が増えます。少しでも気になる症状があれば、医師の判断を仰ぎながら早めに検査を受けることを検討してください。
大腸がんは進行するまで自覚症状が乏しいことが多く、早期発見が鍵を握ります。
家族や職場の理解
検査の準備段階では、食事制限や下剤による排便コントロールが必要となるため、家族や職場にあらかじめ状況を伝えておくとスムーズです。
トイレに頻繁に行く可能性があること、検査翌日まで体がだるい場合があることなどをあらかじめ共有すれば、周りからの理解も得られやすくなります。
不安解消のためのアプローチ
- 医師や看護師に質問リストを用意しておき、聞きたいことを漏れなく確認する
- 過去に検査を受けた友人・知人から体験談を参考にする
- インターネットや書籍で信頼性のある情報源をチェックして知識を深める
よくある質問
最後に、検査を受ける方から寄せられることが多い疑問をまとめます。疑問を解消して、安心して下部内視鏡検査を受けるためにお役立てください。
- 胃カメラと同日に受けることは可能ですか?
-
医療機関によっては同日に胃カメラと下部内視鏡検査を組み合わせることがあります。ただし準備内容や患者さんの体調、利用する麻酔などの条件によっては同日実施が難しい場合もあるため、主治医に相談してください。
下記の記事も参考にしてください
⇒【胃カメラで分かる症状 検査の流れ】
胃カメラ検査の流れや見つかりやすい病気について詳しく解説しています。大腸内視鏡検査との同日実施を検討されている方に、胃カメラ検査の基本的な知識を提供します。 - 妊娠中でも検査を受けられますか?
-
妊娠中は、母体と胎児への影響を考慮して、緊急性が高い場合を除いて検査を見合わせることが一般的です。ただしどうしても腸内の状態を確認する必要がある場合は、産科医や消化器内科医と連携しながら慎重に行います。
- 高齢ですが受けても平気でしょうか?
-
高齢者でも、医師が必要性を判断し、安全な検査体制を整えることで多くの方が受けられます。体力や基礎疾患、認知機能などを総合的に評価し、鎮静剤の使用量などを調整します。
不安があれば遠慮なく相談し、必要なサポートを得るのがおすすめです。
- 下部内視鏡検査の前処置を自宅で行うのが不安です
-
腸内洗浄剤を一気に飲む必要があるため、トイレが近くにある環境で作業できるかがポイントです。移動が難しい場合や、高齢・持病がある場合は、医療機関内で前処置を完結できるプランを用意しているところもあります。
自宅での前処置が不安なときは、事前に問い合わせてください。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査での痛みを和らげる方法|鎮静剤と麻酔について】
下部消化管内視鏡検査の基本を押さえたら、次は実際の検査時の痛みや不快感をどう軽減できるかについて知っておくと安心です。検査への不安を感じている方に特に参考になる内容です。
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
「検査当日の前処置が不安」という声に応え、実際に食事をどう変えれば具体例を示しています。
参考文献
Nagata N, Yasunaga H, Matsui H, Fushimi K, Watanabe K, Akiyama J, Uemura N, Niikura R. Therapeutic endoscopy-related GI bleeding and thromboembolic events in patients using warfarin or direct oral anticoagulants: results from a large nationwide database analysis. Gut. 2018 Oct 1;67(10):1805-12.
Sumiyama K. Past and current trends in endoscopic diagnosis for early stage gastric cancer in Japan. Gastric Cancer. 2017 Mar;20(Suppl 1):20-7.
Mabe K, Inoue K, Kamada T, Kato K, Kato M, Haruma K. Endoscopic screening for gastric cancer in Japan: Current status and future perspectives. Digestive Endoscopy. 2022 Mar;34(3):412-9.
Tanaka S, Kashida H, Saito Y, Yahagi N, Yamano H, Saito S, Hisabe T, Yao T, Watanabe M, Yoshida M, Saitoh Y. Japan Gastroenterological Endoscopy Society guidelines for colorectal endoscopic submucosal dissection/endoscopic mucosal resection. Digestive Endoscopy. 2020 Jan;32(2):219-39.
Arakawa D, Ohmiya N, Nakamura M, Honda W, Shirai O, Itoh A, Hirooka Y, Niwa Y, Maeda O, Ando T, Goto H. Outcome after enteroscopy for patients with obscure GI bleeding: diagnostic comparison between double-balloon endoscopy and videocapsule endoscopy. Gastrointestinal endoscopy. 2009 Apr 1;69(4):866-74.
Ryozawa S, Itoi T, Katanuma A, Okabe Y, Kato H, Horaguchi J, Fujita N, Yasuda K, Tsuyuguchi T, Fujimoto K. Japan Gastroenterological Endoscopy Society guidelines for endoscopic sphincterotomy. Digestive Endoscopy. 2018 Mar;30(2):149-73.
Kusano C, Gotoda T, Ishikawa H, Suzuki S, Ikehara H, Matsuyama Y. Gastric cancer detection rates using GI endoscopy with serologic risk stratification: a randomized controlled trial. Gastrointestinal Endoscopy. 2024 Jul 1;100(1):55-63.
Niikura R, Nagata N, Yamada A, Honda T, Hasatani K, Ishii N, Shiratori Y, Doyama H, Nishida T, Sumiyoshi T, Fujita T. Efficacy and safety of early vs elective colonoscopy for acute lower gastrointestinal bleeding. Gastroenterology. 2020 Jan 1;158(1):168-75.
Pasha SF, Shergill A, Acosta RD, Chandrasekhara V, Chathadi KV, Early D, Evans JA, Fisher D, Fonkalsrud L, Hwang JH, Khashab MA. The role of endoscopy in the patient with lower GI bleeding. Gastrointestinal endoscopy. 2014 Jun 1;79(6):875-85.
Rey JF, Lambert R, null and the ESGE Quality Assurance Committee. ESGE recommendations for quality control in gastrointestinal endoscopy: guidelines for image documentation in upper and lower GI endoscopy. Endoscopy. 2001 Oct;33(10):901-3.