抗生物質や抗がん剤などの服用によって下痢の症状が続くと、日常生活で大きな不便を感じることが多く、腸管自体に炎症や潰瘍などが隠れていると、原因が複雑に絡み合って治りづらくなります。
この記事では、下痢の原因になる薬の特徴や、どのようにして下痢を起こすのか、さらに長く続く下痢の場合に内視鏡検査で腸管を確認する必要性などについて詳しく解説します。
薬が原因で起こる下痢とは
体調を整えたり、特定の病気を治療したりする目的で使われる薬の中にも、副作用として下痢を起こすものがあり、服用する薬が増えると、その分だけ腸への影響も複雑になる傾向があります。
早期に下痢の理由を見極めることで、内視鏡検査のタイミングを逃さず、より正確に腸管の状態を把握できます。
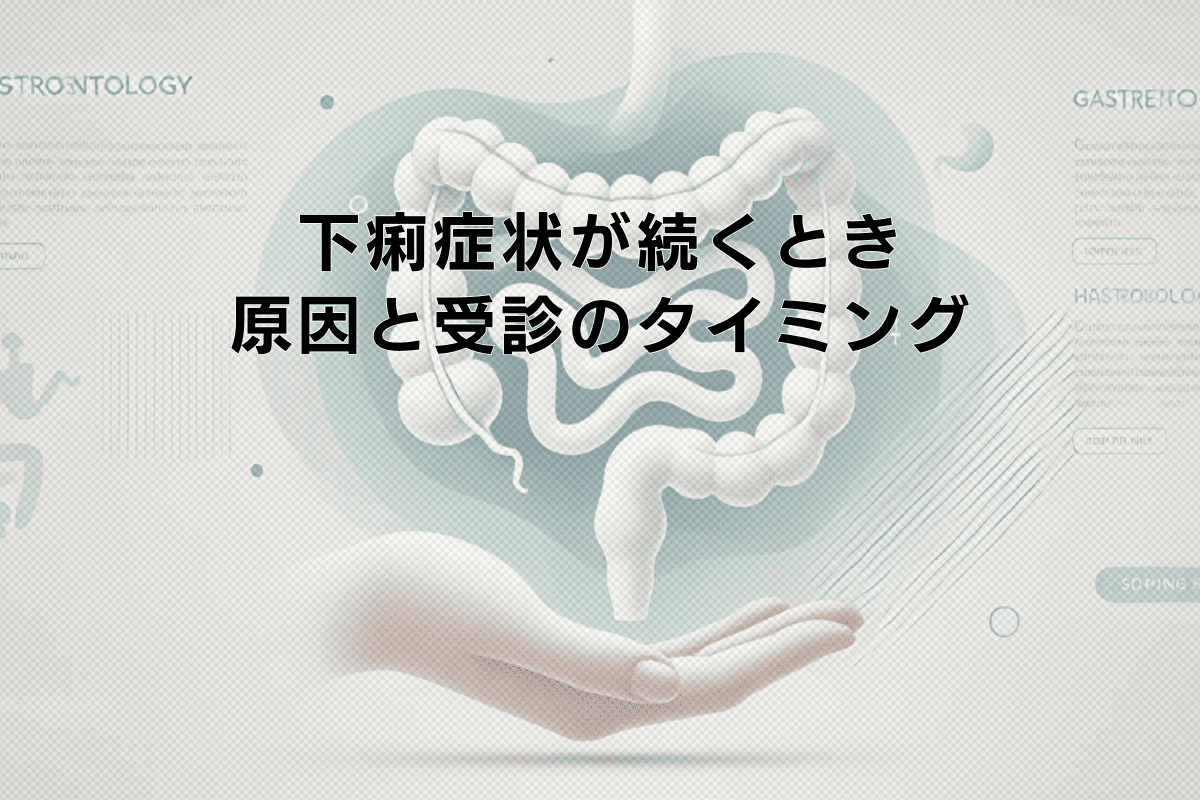
副作用としての下痢の位置づけ
多くの薬には副作用があり、そのひとつとして下痢が生じる可能性があります。下痢に関係しているのは、消化管の動きを促進する作用や、腸内細菌叢のバランスを崩す作用、腸粘膜に直接刺激を与える作用などです。
日常的に服用している薬によって腸が過敏状態になり、結果として下痢が続くパターンが認められます。
下痢が起こりやすい人の特徴
ふだんから胃腸が弱いと感じる人や、高齢の方、基礎疾患による免疫力低下がある人は、薬の影響を受けやすいです。
複数の薬を併用しているケースでは、相互作用によって下痢が悪化する例もあり、小児の場合も、消化器の機能が未発達であるため、注意が必要です。
薬物性下痢とほかの下痢の違い
ウイルスや細菌が原因の感染性下痢や、過敏性腸症候群などの機能性下痢とは異なり、薬物性の下痢では服用開始のタイミングや服用量が大きく影響します。
薬を中断または変更することで症状が改善する場合は、薬との関係性が高いと推測できますが、腸管に炎症が広がってしまった場合には、下痢だけでなく腹痛や発熱など、ほかの症状が伴うこともあります。
早期のアプローチが大切
単に「薬を飲んだらお腹がゆるい」と自己判断して放置すると、慢性化する恐れがあるので注意が必要です。
薬による下痢が疑われるときは医師に相談して処方内容の調整を検討し、必要に応じて内視鏡検査で腸内の状態を観察すると、早期の原因特定に役立ちます。
薬物性下痢の判断ポイント
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 下痢の開始時期 | 服薬開始直後に起こるか、しばらく経過してから起こるか |
| 他の症状の有無 | 発熱、嘔気、腹痛、血便などがないか |
| 服用薬の種別や併用薬 | 消化管への刺激が強い薬が含まれていないか |
| 下痢の頻度や便の性状 | 水様便、粘液便、脂肪便などの違い |
下痢を引き起こす主な薬剤の種類と特徴
さまざまな薬の中でも、腸管への刺激が大きいものや、腸内細菌のバランスを崩しやすいものは、比較的下痢を起こしやすいです。代表的な例を知っておくことで、服薬時の注意点を把握しやすくなります。
抗生物質と腸内細菌叢の乱れ
抗生物質は細菌感染症の治療に欠かせない存在ですが、有害な細菌だけでなく腸内の常在菌まで抑制してしまう場合があり、その結果、腸内の細菌バランスが乱れて下痢が起こる可能性があります。
特に長期投与や広範囲に作用する抗生物質を使用しているときは、注意しましょう。
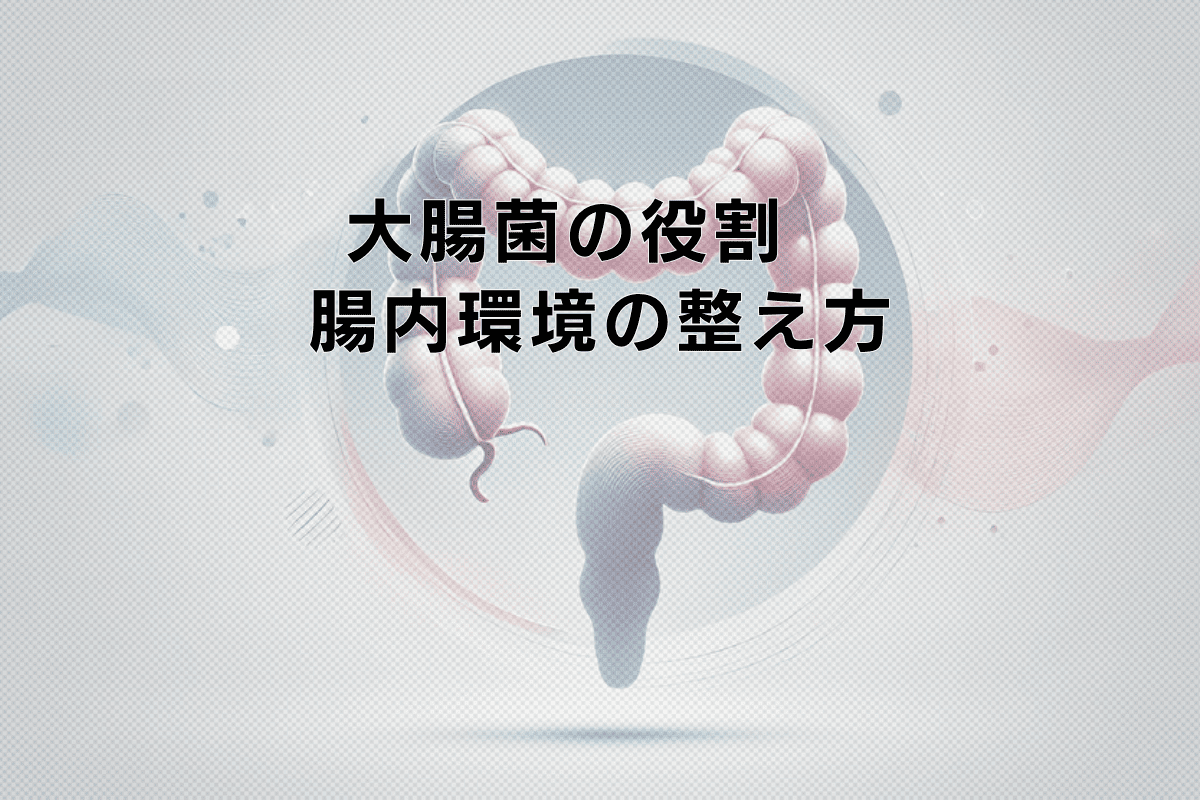
抗がん剤による粘膜ダメージ
がん治療に用いられる抗がん剤は、細胞増殖を抑える効果がある一方で、腸粘膜の上皮細胞にも影響を与え、腸粘膜が荒れてしまい、水分の吸収が不十分になり、下痢を起こしやすくなります。
治療の効果を保ちながら症状を軽減させるために、医師と相談しながら投薬プランを調整することが大切です。
免疫調節薬やステロイドの影響
免疫系を調整したり、炎症を抑えるステロイドも、長期的な服用で下痢を引き起こすケースがあります。炎症抑制効果が強い薬は、腸壁の正常な防御機構に影響を与えることがあるため、下痢や便通異常を起こす場合があります。
消化管運動を促進する薬
一部の便秘薬や胆汁酸製剤などは、腸の蠕動運動を活発にする作用を持っています。本来は便通を良くするための薬ですが、過剰に動きすぎることで水分吸収が間に合わず、下痢を誘発する可能性があります。
下痢を起こしやすい薬
| 薬の分類 | 具体例 | 主な作用 |
|---|---|---|
| 抗生物質 | ペニシリン系、セフェム系など | 腸内細菌のバランスを崩して下痢が生じやすくなる |
| 抗がん剤 | フルオロウラシル系、イリノテカンなど | 腸粘膜を傷つけて水分吸収を乱す |
| 免疫調節薬・ステロイド | プレドニゾロン、タクロリムスなど | 腸壁の防御機構を弱めて便通異常が続く |
| 消化管運動促進薬 | ルビプロストン、リナクロチドなど | 蠕動運動を高めるが、過剰になると下痢につながる |
下痢のメカニズムと腸管への影響
薬によって下痢になる理由は、単に腸が刺激されるだけにとどまりません。腸管全体の機能が変化し、水分吸収や粘膜のバリア機能が損なわれることなど、複数の要因が絡み合って症状が続きます。
腸内細菌叢の乱れが及ぼす影響
健康な腸には多種多様な細菌が共存し、免疫機能や栄養素の吸収をサポートしていています。
薬によって特定の菌が過剰に死滅したり、逆に増殖したりすると、発酵異常や粘膜障害が生じやすくなります。下痢だけでなく腹部膨満感や便のにおいの変化も伴う場合もあります。
粘膜や絨毛への刺激
腸管の内壁には粘膜があり、そこで栄養や水分の吸収を行いますが、抗がん剤や強い抗生物質などは、この粘膜にダメージを与えやすくなります。
粘膜が剥がれたり、炎症を起こしたりすると、吸収不全が進み水っぽい便が増え、さらに、絨毛構造が乱れると長引く下痢の原因になりやすいです。
蠕動運動の変化
消化管が適度に収縮と弛緩を繰り返すことで、消化物はゆっくりと移動し、十分な吸収が行われます。
しかし薬によって蠕動運動が異常に亢進したり、逆に低下したりすると、便が固まる前に排出されてしまったり、水分過剰な状態になったりします。
腹痛や嘔気が伴うケース
薬の副作用で腸管が大きく刺激されると、下痢だけでなく腹痛や嘔気、吐き気などを感じる方もいます。これは腸の神経と脳内の嘔吐中枢が密接に関係していることも影響しています。
症状が複数重なる場合は体力を消耗しやすくなり、内視鏡検査を検討するきっかけとなります。
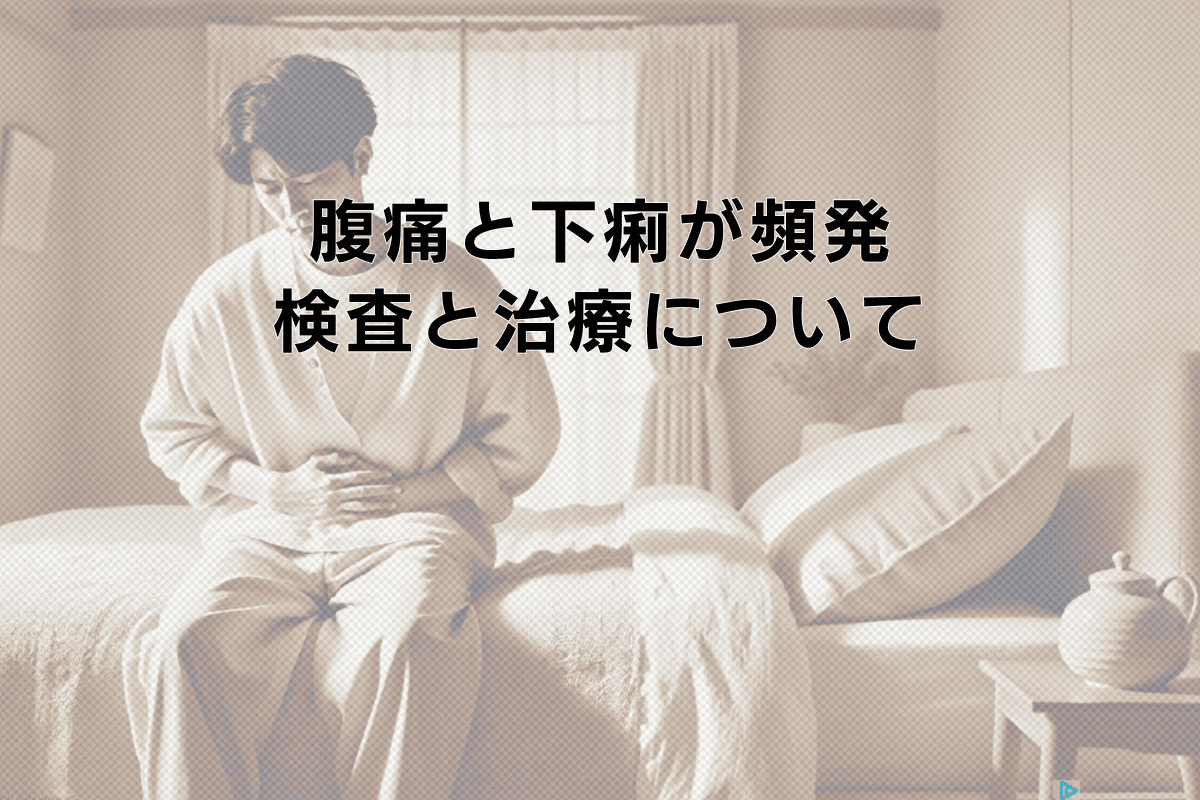
薬による腸管変化
| 作用機序 | 腸管への影響 | 具体的症状 |
|---|---|---|
| 細菌叢の乱れ | 善玉菌の減少や悪玉菌の増加による炎症 | 水様便、便のにおいの変化 |
| 粘膜障害 | 粘膜剥離や潰瘍化 | 下痢、血便、腹痛 |
| 蠕動運動の亢進または低下 | 食物や水分の移動速度の異常 | 急な便意、腹痛、便秘と下痢の繰り返し |
| 消化管神経への刺激 | 嘔気や吐き気、腹部不快感 | 食欲不振、体重減少 |
下痢症状と内視鏡検査の適応
下痢が続く場合、原因が薬だけなのか、それとも腸内にほかの病変や感染症が隠れているのかを確認する必要があります。内視鏡検査の適応を判断することで、より正確な診断と治療につながります。
長引く下痢の指標
1~2日程度の下痢であれば、まずは食事や水分補給に気をつけて経過を観察することが多いですが、下痢が1週間以上続いたり、血便や発熱を伴ったりする場合は、腸管の状態を精密に調べる必要があります。
薬が主因であっても、薬の副作用で腸が炎症を起こしている可能性もあるからです。
内視鏡検査のメリット
大腸内視鏡検査では、直腸から盲腸まで直接観察し、粘膜の状態や病変の有無を確認できます。炎症や潰瘍、ポリープが存在するかどうかを目視でき、必要に応じて組織を採取することで正確な診断を得られます。
また、上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)を併用することで、上部からの影響を含めた総合的な評価が可能です。
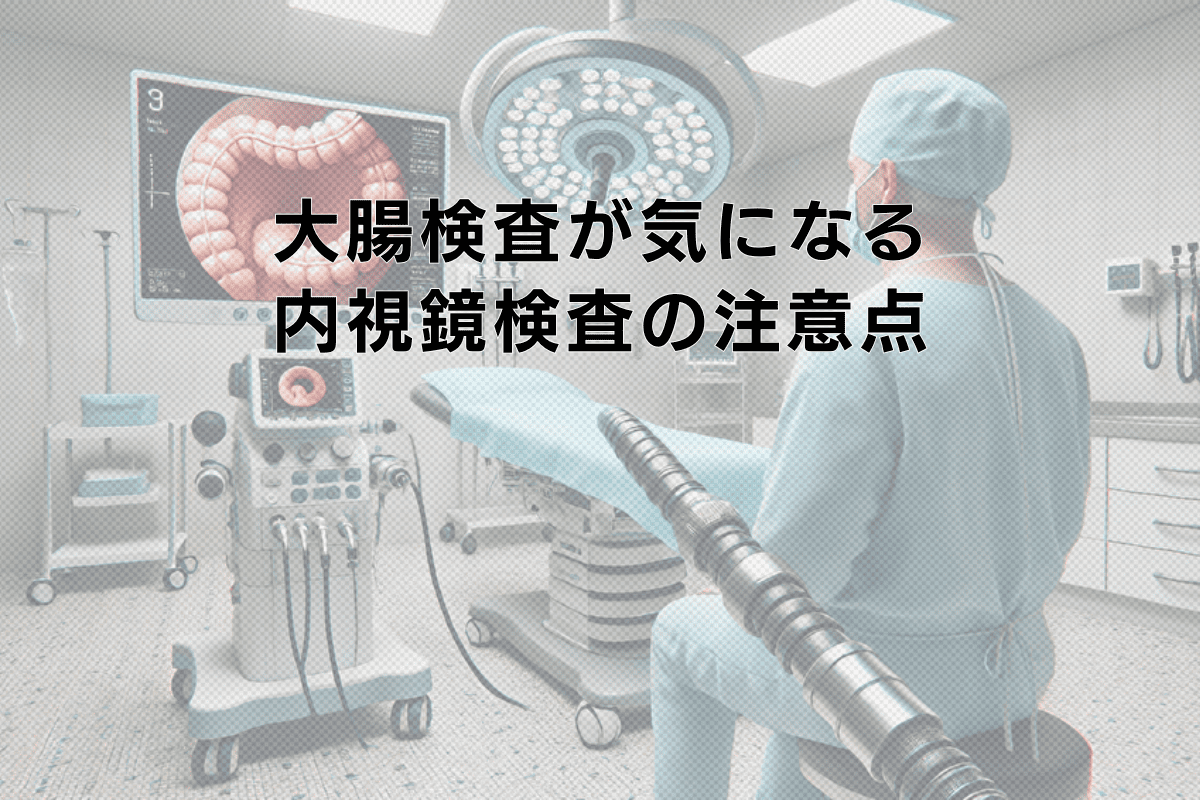
検査の進め方と注意点
内視鏡検査を行うときは、下剤の服用など事前の準備が必要で、薬による下痢の症状が出ているときは、準備段階で体力を消耗しがちなため、医師の指示に従い休憩を挟みながら進めることが大切です。
さらに、服用薬の中断や切り替えが必要な場合もあるため、主治医との連携が欠かせません。
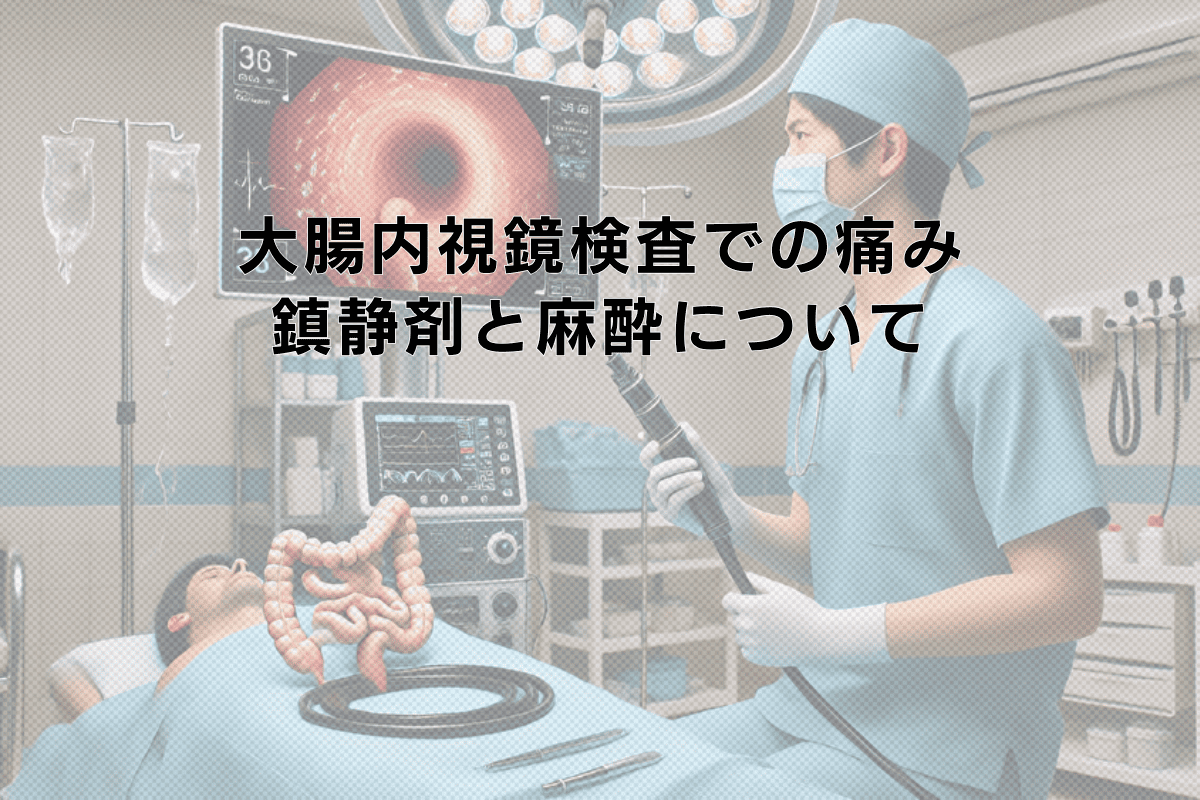
内視鏡以外の検査との比較
便培養や便中の病原体検査、腹部超音波検査、CT検査なども組み合わせることで、腸管外に問題がないか確認できます。
内視鏡検査は直接観察が可能で診断精度が高い一方、侵襲があるため、患者さんの体力やリスクを考慮しながら時期を選ぶことが大切です。
内視鏡検査を検討する目安
- 1週間以上の下痢が続いている
- 血便や黒色便がある
- 39℃前後の発熱が断続的に起きる
- 下痢に加えて体重が急激に減少している
- 腸管以外の合併症状(皮疹や関節痛など)が伴う
内視鏡検査で確認できる所見と追加検査
内視鏡検査を行うと、粘膜表面の様子だけでなく、微小な病変や組織レベルの異常も把握しやすくなり、薬による下痢が続いていた場合、粘膜に炎症やびらんが起きているかどうかの確認が重要です。
粘膜の炎症や潰瘍
内視鏡で見ると、正常な粘膜は淡いピンク色をしていますが、炎症が進んだ粘膜は赤くただれていたり、白く膜状になっていたりします。潰瘍があれば粘膜がえぐれるように欠損しているため、そこでの出血が下痢とともに見られる場合があります。
腸管運動の状態
内視鏡挿入中に腸管の動きもある程度観察できます。蠕動運動が強く、内視鏡が通過しにくいほど動いている場合や、逆にほとんど動かない場合は、薬の影響や病態を考慮した追加検査が必要です。
組織生検の意義
異常が疑われる部位があれば、内視鏡下で小さな組織を採取する「生検」を行い、顕微鏡レベルでの診断を目指し、特定の薬による細胞障害や、感染症の有無を判別するうえで大切なステップです。
必要に応じて多数の部位から複数回採取し、正確な診断を行います。
感染症や腫瘍性病変との鑑別
薬による下痢と似た症状を示す病気には、潰瘍性大腸炎やクローン病、あるいは大腸がんなどが含まれ、これらの病気では、内視鏡所見や組織所見によって明確に区別できる場合があります。早期に鑑別できれば、治療方針を早めに立てられます。
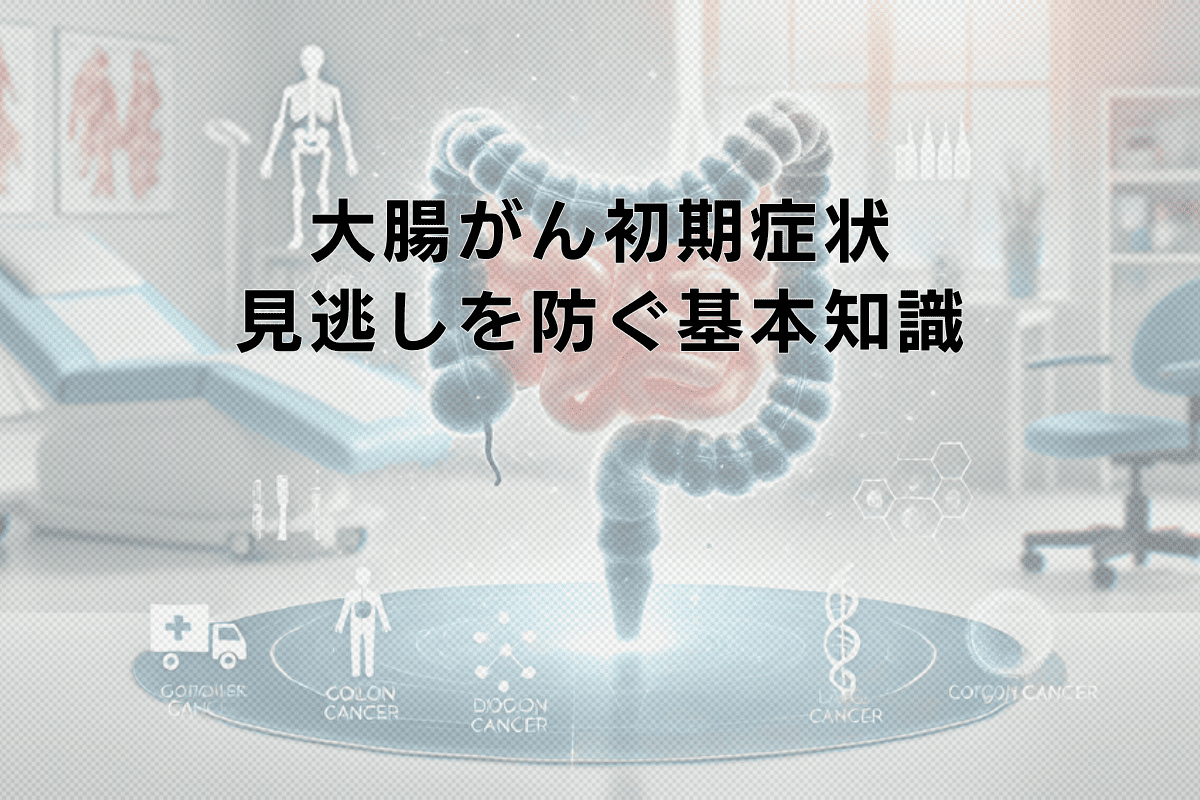
主な内視鏡検査所見
| 所見 | 可能性のある原因 | 治療または追加検査 |
|---|---|---|
| 粘膜のびらんや発赤 | 薬による刺激性腸炎、感染性腸炎、炎症性腸疾患など | 薬の変更・減量、生検による病理確認 |
| 潰瘍や深い傷 | 消化管潰瘍、クローン病、悪性腫瘍など | 生検、CT検査、血液検査などを追加 |
| ポリープや腫瘤状病変 | ポリープ様変化、大腸がん等 | 切除や組織診断、場合によって外科治療の検討 |
| 粘膜表面が滑らか | 特筆すべき異常所見なし | 必要に応じて他の検査で確認 |
下痢を伴う患者への治療と注意点
薬による下痢が原因と考えられる場合でも、腸内環境や粘膜の状態によってアプローチが異なり、服用薬の調整や、腸内細菌を整える治療、栄養管理など、さまざまな視点が必要です。
服用薬の見直し
下痢の症状が続く場合、まず疑うのは「下痢を起こしやすい薬」で、医師は患者さんの病気の状態や優先度を踏まえ、可能であれば同効の別の薬に変更したり、服用量を減らしたりして症状の変化を観察します。
ただし、主要な治療薬を勝手に中止すると病気そのものが悪化するリスクがあるため、自己判断は避けてください。
腸内環境を整える
抗生物質を服用している場合は、腸内細菌の乱れが顕著になることがあり、対策として、プロバイオティクス製剤や乳酸菌サプリメントなどを活用し、腸内環境を整える試みが行われます。
食事面ではヨーグルトや発酵食品を意識して取り入れるとよいでしょう。
腸内バランスを整える食材
- ヨーグルトやチーズなどの発酵乳製品
- 納豆や味噌などの発酵食品
- 食物繊維を多く含む野菜や果物
- プレバイオティクスを含むオリゴ糖製品
電解質と水分補給
下痢が続くと体内の水分と電解質が大量に失われるため、脱水や電解質異常が懸念され、経口補水液などで塩分やミネラルも補給しながら適度に水分を摂取することが大事です。
とくに高齢の方は脱水に陥りやすいため、早めの対策が重要になります。
症状が強い場合の対処
腹痛や嘔気が強く、食事や水分がうまく摂取できない場合は、点滴や入院治療が検討されることもあります。医師は腸の状態やバイタルサインを総合的に評価し、必要に応じて内視鏡検査を行ったうえで治療方針を決定します。
下痢症状改善のための対策
| 対策 | 具体的内容 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 服用薬の見直し | 薬の中止、減量、別の薬への切り替え | 下痢の原因除去 |
| 腸内環境を整える療法 | プロバイオティクス、食事指導 | 常在菌バランスの回復 |
| 水分・電解質補給 | 経口補水液、点滴など | 脱水や電解質異常を防ぐ |
| 症状が強い場合の追加ケア | 点滴や入院治療、強力な止瀉薬の使用 | 身体負担の軽減と腸管修復の促進 |
日常生活での対策と予防策
下痢になりやすい薬を必要とする人でも、生活習慣を整えたり、食事に気を配ったりすることで、腸への負担を軽くする方法があり、普段からの体調管理が、不測の下痢の重症化を防ぐうえで重要です。
規則正しい食生活
薬によって腸が敏感になりがちなときこそ、消化に優しい食事を心がけると良いです。香辛料の強いものや脂質の多い料理を控え、炭水化物やタンパク質、ビタミンなどをバランスよく摂取することで、腸内環境を整えやすくなります。
ストレス管理と睡眠
ストレスや睡眠不足は、自律神経の乱れを招き、腸の動きが過剰になったり抑えられたりします。深呼吸や軽い運動、入浴などでリラックスを心がけ、十分な睡眠をとることで、薬の副作用が現れにくい心身状態をつくりやすいです。
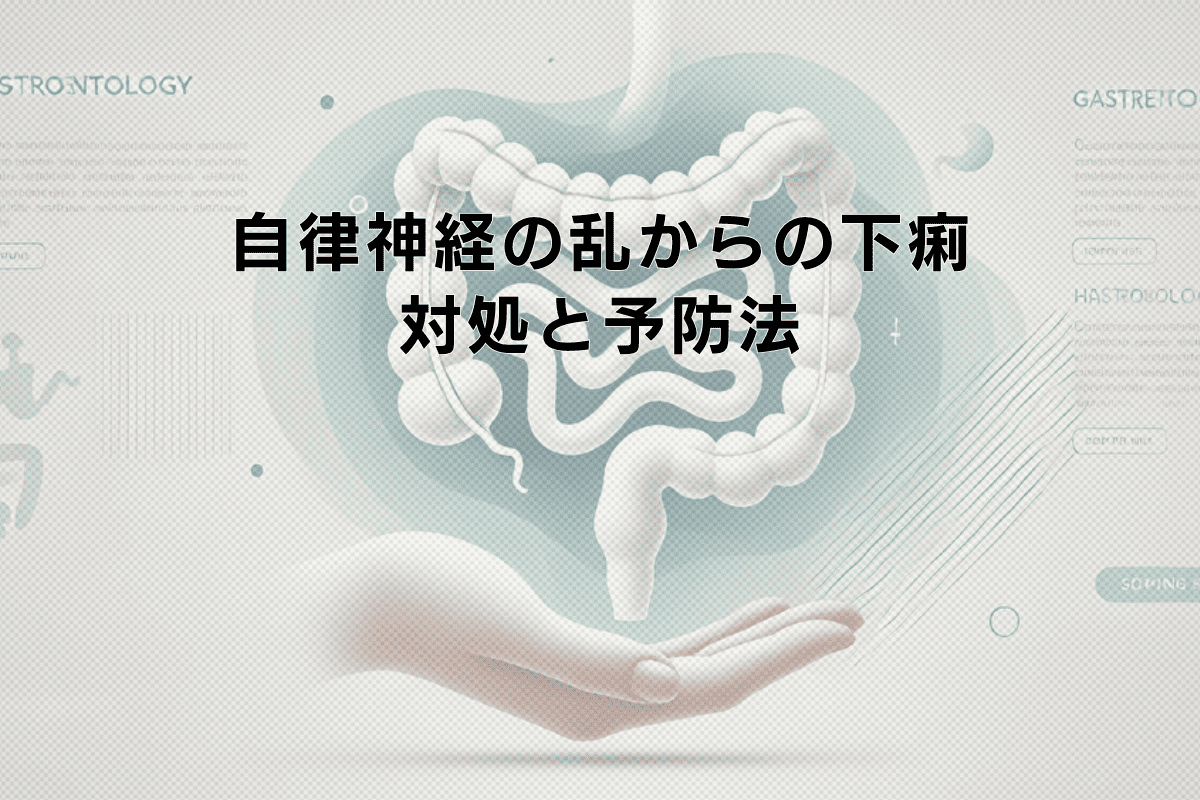
トイレ環境の整備
下痢が突然起こると、不安やストレスが増すものです。職場や自宅でトイレが近くにある場合は安心感が高まり、下痢による心理的負担を軽減できます。外出の際はトイレの位置を把握しておくと、急な症状にも対応しやすいです。
日常生活で意識したいポイント
- 脂質や刺激物を過度に摂取しない
- 適度な運動を取り入れて腸の動きを整える
- 水分補給をこまめに行い、脱水を防ぐ
- スケジュールに余裕を持ち、ストレスを軽減する
服用スケジュールの工夫
薬によっては、食後に飲むと下痢症状が緩和する場合や、1日2回を1回にまとめると副作用が軽減する場合もあり、医師と相談しながら、自分のライフスタイルに合わせた服用スケジュールを検討するのが大切です。
ただし自己判断で変更するとリスクが高まるため、必ず専門家の助言を得ましょう。
生活習慣と腸内環境を関連づける一覧
| 生活習慣 | 腸への影響 | 改善のための工夫 |
|---|---|---|
| 食事 | 栄養バランスが悪いと下痢が長引きやすい | バランスの良い献立、過剰な刺激物や脂質を避ける |
| ストレス | 自律神経を乱し蠕動運動を過剰にする | リラクゼーション法、十分な睡眠 |
| 運動不足 | 代謝の低下、腸管の動きの低下 | ウォーキングや軽い筋トレで血行を促す |
| 水分補給 | 水分不足で便が固くなったり脱水のリスク | 経口補水液やミネラル豊富な水でこまめに補給 |
よくある質問
薬の副作用としての下痢は身近な問題でありながら、はっきりとした原因や対策が見えにくい場合があります。最後に、多くの方から寄せられる疑問に対して簡潔にお答えします。
- 薬による下痢と食あたりの違いはどう見分ければいいですか?
-
食あたりの多くは嘔吐や腹痛も強く、数日で改善することが多いですが、薬による下痢は服用のタイミングと関連があり、薬を中止すると改善するケースがあります。ただし、確定的に判断するには医師の診察が必要です。
- 下痢が気になるとき、薬はすぐ中断してもいいのでしょうか?
-
医師の指示なしで中断すると、原疾患が悪化する恐れがあり、特に免疫調節薬や抗がん剤の場合は、自己判断でやめないほうが賢明です。症状がひどいと感じるときは、早めに主治医へ相談してください。
- 下痢を避けるために止瀉薬を常用してもいいですか?
-
止瀉薬は一時的に症状を和らげる方法ですが、根本原因が薬にある場合は逆に状態を複雑にすることがあります。長引く下痢の背景にはほかの病気が隠れていることもあるため、医師の判断に従って服用の可否を決めましょう。
- 高齢の家族が薬による下痢で苦しんでいます。受診の目安はありますか?
-
高齢者は脱水や電解質異常を起こしやすいため、2~3日続く場合でも早めに受診を考え、血圧の低下や意識レベルの変化などがある場合は、さらに緊急性が高まります。時間外でも医療機関に連絡してください。
次に読むことをお勧めする記事
【下部消化管内視鏡検査の手順と注意点|前処置から検査後のケアまで】
内視鏡の理論を押さえたら、実際の検査がどのように進むのか気になりませんか?準備から検査後のケアまで詳しく説明しています。
【大腸がん初期症状の見逃しを防ぐ 便の変化や腹痛の基本知識】
薬による下痢を学んだ皆さんには、大腸がんの初期サインも合わせて知っておくと、より包括的な便通トラブルの理解につながります。
参考文献
Matsumoto T, Kudo T, Esaki M, Yano T, Yamamoto H, Sakamoto C, Goto H, Nakase H, Tanaka S, Matsui T, Sugano K. Prevalence of non-steroidal anti-inflammatory drug-induced enteropathy determined by double-balloon endoscopy: a Japanese multicenter study. Scandinavian Journal of gastroenterology. 2008 Jan 1;43(4):490-6.
Nagata N, Yasunaga H, Matsui H, Fushimi K, Watanabe K, Akiyama J, Uemura N, Niikura R. Therapeutic endoscopy-related GI bleeding and thromboembolic events in patients using warfarin or direct oral anticoagulants: results from a large nationwide database analysis. Gut. 2018 Oct 1;67(10):1805-12.
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Ando T, Sakumura M, Mihara H, Fujinami H, Yasuda I. A review of potential role of capsule endoscopy in the work-up for chemotherapy-induced diarrhea. InHealthcare 2022 Jan 24 (Vol. 10, No. 2, p. 218). MDPI.
Kurahara K, Matsumoto T, Iida M, Honda K, Yao T, Fujishima M. Clinical and endoscopic features of nonsteroidal anti-inflammatory drug-induced colonic ulcerations. The American journal of gastroenterology. 2001 Feb 1;96(2):473-80.
Yagi K, Endo S, Nakamura A, Sekine A. Clinical course of drug-induced collagenous colitis and histological changes after drug withdrawal in a Japanese case series. European journal of gastroenterology & hepatology. 2012 Sep 1;24(9):1105-9.
Yanai S, Nakamura S, Kawasaki K, Toya Y, Akasaka R, Oizumi T, Ishida K, Sugai T, Matsumoto T. Immune checkpoint inhibitor‐induced diarrhea: Clinicopathological study of 11 patients. Digestive Endoscopy. 2020 May;32(4):616-20.
Philip NA, Ahmed N, Pitchumoni CS. Spectrum of drug-induced chronic diarrhea. Journal of clinical gastroenterology. 2017 Feb 1;51(2):111-7.
Chassany O, Michaux A, Bergmann JF. Drug-induced diarrhoea. Drug safety. 2000 Jan;22:53-72.
Püspök A, Kiener HP, Oberhuber G. Clinical, endoscopic, and histologic spectrum of nonsteroidal anti-inflammatory drug-induced lesions in the colon. Diseases of the Colon & Rectum. 2000 May;43:685-91.










