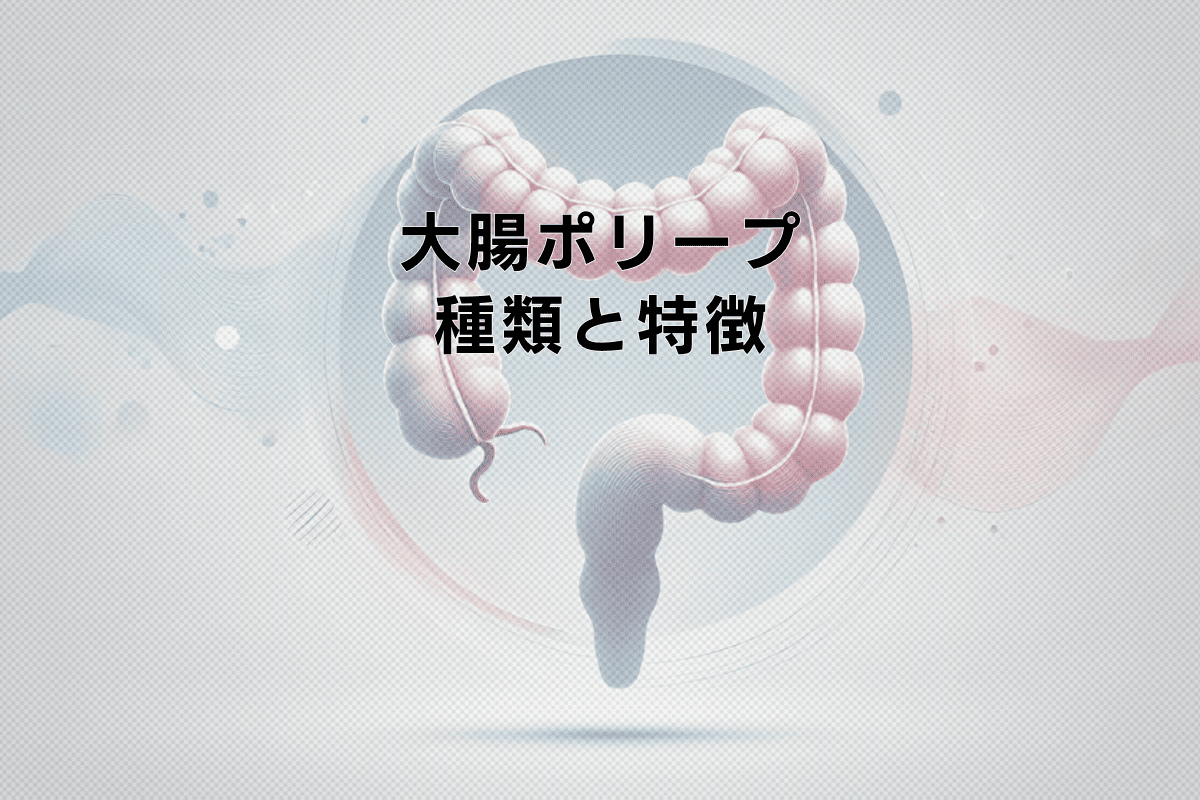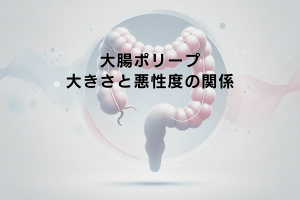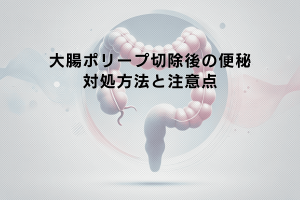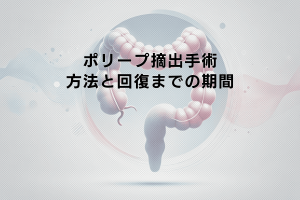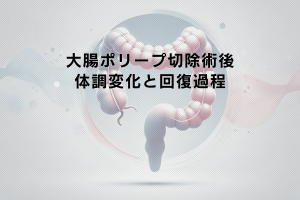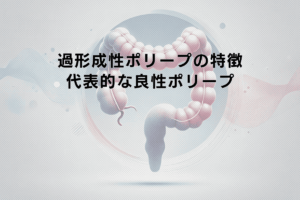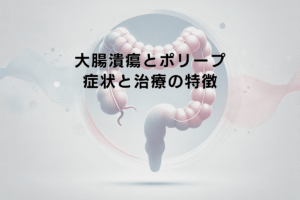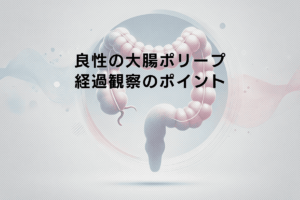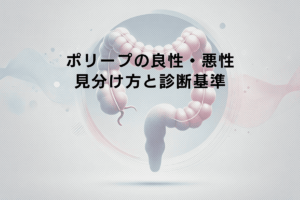大腸に発生するポリープは、多くの場合は自覚症状が乏しく、検診や内視鏡検査をきっかけに見つかることがよくありますが、種類によっては将来的にがん化するリスクがあり、早めの発見と対応が大切です。
大腸内視鏡検査の受診率が上がったことで「大腸ポリープ」という病名は知られつつありますが、実際にどのようなタイプがあるのかを理解している方はまだ多くありません。
本記事では、過形成性ポリープと腺腫を中心に、大腸ポリープの多様な特徴や検査の意義、さらに日常生活で意識したいことを詳しく解説します。
大腸ポリープとは何か
大腸ポリープとは、大腸の粘膜にできる隆起性の病変の総称で、いわゆる「いぼ」のようなものをイメージする方もいるかもしれませんが、形状や大きさ、細胞の状態は実にさまざまです。
ポリープそのものは良性のものが大半ですが、一部は時間をかけて悪性化する場合があります。大腸がんの予防に取り組むうえでも、まずはポリープを正しく知ることが重要です。
ポリープができるメカニズム
大腸の内側には粘膜が広がっていますが、この粘膜に異常増殖が起きることでポリープが形成されると考えられています。
細胞分裂が何らかの原因で過度に活性化したり、遺伝的要素や生活習慣によって粘膜がダメージを受けたりすることが大きく関わっていると指摘されています。
良性と悪性の違い
ポリープは大きく分けて良性と悪性(がん)の2つがありますが、初期の段階では外見や自覚症状だけで判別するのは難しく、内視鏡検査で切除して組織検査を行うことで正確な診断が確定します。
良性でも放置すると悪性化するものがあるため、早期発見と正しい処置が必要です。
大腸ポリープの主な症状
ほとんどのポリープは初期段階で自覚症状が出ないため、見落とされがちで、大きくなると便に血が混じったり、腹痛や便通異常などが現れることがあります。
ただし、これらの症状は痔など他の疾患とも共通するため、正確な判断には内視鏡検査が欠かせません。
大腸ポリープの頻度
大腸内視鏡検査を受けると、40代以降で何らかのポリープが見つかる割合は決して低くなく、とくに食事の欧米化や生活習慣の変化を背景に、若い世代でもポリープが見つかるケースが増加傾向にあります。
正しいタイミングでの検査を検討することが大切です。
大腸ポリープにおける年齢別発見割合
| 年齢層 | ポリープ発見率の傾向 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 20〜30代 | 低め | 比較的まれだが、遺伝要因などにより若年でも発症可能 |
| 40〜50代 | 中程度 | 健康診断や人間ドックの機会が増え、発見も増加 |
| 60代以上 | 高め | 生活習慣の影響や加齢に伴いリスクが上昇 |
過形成性ポリープの特徴
大腸にできるポリープにはいくつかのタイプがありますが、そのなかで比較的良性の傾向があるものとして過形成性ポリープが知られています。大腸に発生しやすく、大きくなることはあまり多くありません。
大腸カメラ検査で見つかった場合でも、がんに進行する可能性はほかの腺腫性ポリープに比べて低いとされています。
過形成性ポリープの外観
内視鏡で観察すると、一般的に淡い色合いで表面が平滑、もしくはやや隆起していることがあり、大きさは数mm程度のものが多く、複数個見つかるケースもあります。
形態だけでは腺腫などとの区別が難しい場合があるため、切除して組織検査を行うことが望ましいです。
大腸における主なポリープ形態
| タイプ | 形状の特徴 | がん化リスク |
|---|---|---|
| 過形成性 | 表面が滑らかで小型が多い | 低め |
| 腺腫性 | 隆起や凹凸がみられることがある | 比較的高め |
| 炎症性 | 炎症部位に伴う不整形 | リスクは低いが要経過観察 |
良性でも油断禁物
過形成性のポリープは基本的にがん化しにくいとされていますが、まったくリスクがないわけではありません。とくにサイズが大きくなったり、形状に変化が認められたりする場合は、慎重な経過観察や切除を検討することが必要です。
自覚症状が乏しいからといってそのままにしておくと、ほかの部位に別のポリープができていた可能性を見逃すこともあります。
過形成性ポリープができる原因
原因ははっきりと解明されていませんが、飲食習慣や腸内環境の影響が示唆されていて、過度な脂質摂取や偏った食事によって腸内に炎症が生じやすい環境になると、粘膜細胞に負担をかける可能性があります。
過形成性ポリープが見つかった方は、普段の食生活を見直すきっかけにすることが大切です。
過形成性ポリープに対する検査の進め方
内視鏡検査で過形成性ポリープが疑われる場合、医師は大きさや数、表面の見え方などを総合的に判断して切除を行うかどうかを決め、必要に応じて組織検査を行うことで、腺腫や悪性細胞の有無をチェックできます。
過形成性ポリープと向き合う際の注意点
- 定期的な内視鏡検査で変化の有無を確認する
- 食事や生活習慣を改善して腸内環境を整える
- 家族歴やほかの疾患の有無を踏まえて医師に相談する
腺腫性ポリープの特徴
腺腫性ポリープは、大腸内で見つかる良性ポリープの中でも比較的がん化リスクが高めの種類といわれて、大きいものや形状が不規則なものは要注意であり、見つけ次第切除を勧められることが多いです。
大腸ポリープの種類の中でも腺腫は代表的で、内視鏡検査の結果で最も警戒されるタイプといっても過言ではありません。
腺腫の分類
腺腫性ポリープはさらに細かい分類があり、管状腺腫や絨毛腺腫などがあり、管状腺腫はがん化リスクが中等度とされ、絨毛腺腫はより高いリスクを抱える傾向があります。
いずれも早期発見が重要であり、サイズが小さいうちに切除しておくことで大腸がんを防ぐ可能性が高まります。
腺腫の代表的なタイプ
| 名称 | 組織学的特徴 | がん化リスク |
|---|---|---|
| 管状腺腫 | 腺管構造の増殖が主体 | 中等度 |
| 管状絨毛腺腫 | 管状構造と絨毛構造の両方を含む | 中〜高程度 |
| 絨毛腺腫 | 絨毛状構造が大部分を占める | 高め |
腺腫性ポリープの大きさとリスク
腺腫は大きさが大きくなるほどがん化の可能性が高まり、5mm以下の小さなものでも放置すると徐々に成長し、1cmを超える段階になると悪性化のリスクがさらに上昇します。
そのため、腺腫と診断された場合は早期の切除を検討することがよくあります。
腺腫ができやすい要因
食事の欧米化や喫煙、過度のアルコール摂取、肥満などが腺腫のリスクを高め、また、家族や近親者に大腸がんを含む消化器系のがんが多い場合は腺腫性ポリープができやすいと言われることがあります。
こうしたリスク要因を持つ方は、若いうちから内視鏡検査を受けることが望ましいです。
腺腫性ポリープの治療方針
腺腫性ポリープが内視鏡で発見された場合、多くは内視鏡的切除が選択肢で、これは内視鏡用のスネアなどを使い、電気メスでポリープを切り取る手法です。
ポリープの根元から切除できれば再発リスクは比較的低く、入院期間も短く済む場合があります。
腺腫性ポリープに関する主な治療手法
| 治療方法 | 特徴 | メリット |
|---|---|---|
| 内視鏡的切除 | 大きさや形状に応じてスネア等で除去 | 体への負担が軽く、短期間で完結 |
| 外科的手術 | 内視鏡治療が難しい場合に切開して切除 | 大きな病変に対応しやすい |
| 経過観察 | ごく小さいものやリスクが低い場合に選択 | 不要な切除を回避できる |
大腸ポリープの検査
大腸に発生する過形成性や腺腫性のポリープを見つけるには、やはり内視鏡検査が重要で、いわゆる大腸カメラとも呼ばれ、肛門からスコープを挿入して大腸内部を直接観察します。
大腸内視鏡検査は怖い、痛そうと敬遠されがちですが、最近は鎮静剤を使うなどで負担を減らす取り組みが進んでいます。

検便との違い
大腸検査としては便潜血検査もよく知られていますが、これは便の中に血液が混じっているかを調べるもので、簡便でコストを抑えられる反面、ポリープがあっても出血がなければ見逃す可能性があります。
一方、内視鏡検査なら小さなポリープでも直接視認できるため、より確実に発見しやすい点がメリットです。

検査前の準備
大腸内視鏡検査を行う前には、腸内をきれいにするために下剤を飲むなどの処置が必要になり、これは腸の内容物が残っていると視界を妨げ、正確な診断が難しくなるためです。
検査前日からの食事制限や当日の飲水ルールなどについては、医療機関の指示を守ることが大切になります。

大腸内視鏡検査当日の流れ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付・問診 | 体調確認や簡単な説明 |
| 下剤の服用 | 腸内を空にして視界を確保 |
| 検査本番 | 鎮静剤を用いるケースもある |
| ポリープ切除の可否 | 発見したポリープをその場で切除するか判断 |
検査中の所要時間と痛み
検査時間はポリープの数や大腸の長さ、技術者の熟練度によって異なりますが、おおむね15〜30分程度で、痛みや不快感は、腸の曲がり角を通過するときに発生しやすいです。
ただし、鎮静剤を使用することで意識レベルをやや低下させ、検査の苦痛を軽減できる場合があります。
検査後の注意点
検査後は鎮静剤や麻酔の影響が残っている可能性があるので、しばらく休んでから帰宅します。ポリープを切除した場合は、出血や腹痛が起きないかどうかを観察します。
大量の出血や激しい腹痛が続くようであれば、担当医に相談することをおすすめします。
- 下剤の影響で体内の水分や電解質が失われやすい
- 検査後はゆっくり休み、水分補給をこまめに行う
- 出血や腹痛などの異常を感じたら早めに連絡する
大腸ポリープの治療
大腸にできたポリープは、内視鏡検査で発見された段階で切除を提案されることが多く、とくに腺腫性のものや大きいものは、放置するとがんに進行するリスクがあるため、見つけた時点で対応しておくのが良いケースがほとんどです。
一方、過形成性のようにがん化リスクが低いとされる場合でも、医師の判断で切除を行うことがあります。
内視鏡的ポリープ切除術(ポリペクトミー)
ポリープ切除術では、内視鏡に取り付けられた細いワイヤのような器具(スネア)でポリープを根元からくくり電気的に焼き切ります。ポリープが小さい場合は日帰りで行えることが多く、入院が必要になるケースも長くはありません。
切除した組織は病理検査に回して、がん細胞の有無を調べます。
ポリープ切除に利用される道具
| 器具名 | 特徴 |
|---|---|
| スネア | ワイヤでポリープを挟み、電気で切除 |
| ホットバイオプシー | 小型の鉗子でポリープをつまんで焼き切る |
| EMR(粘膜切除術) | 粘膜を薬液で持ち上げ、広範囲を切除する方法 |
ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)
サイズが大きいポリープや平坦型の病変には、ESDという高度な技術を使う場合があります。粘膜下層を注射液で膨らませたうえで慎重に剥離していく方法であり、病変を一括で切除しやすい利点があります。
ただし、技術的に難易度が高く、専門的な施設で行う必要がある場合が多いです。
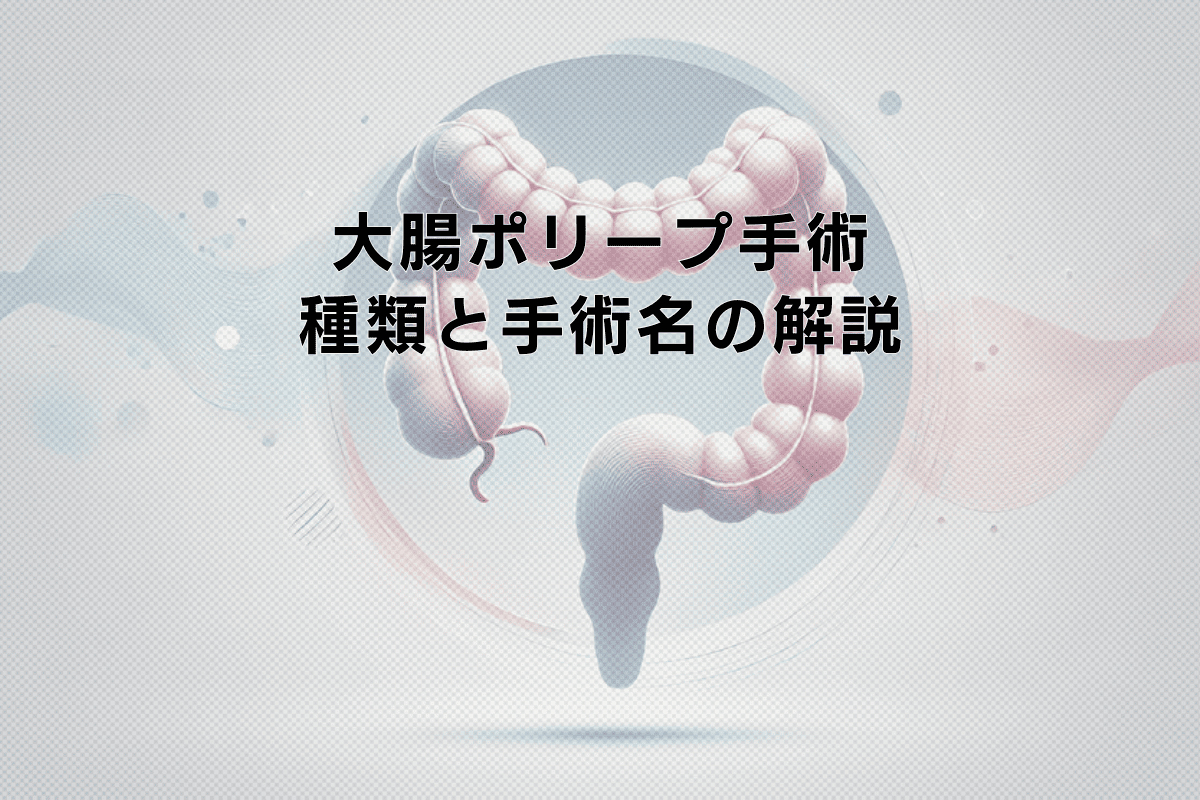
外科手術が必要なケース
ポリープが非常に大きかったり、内視鏡での切除が困難な形状をしている場合、外科手術が検討されることもあり、開腹または腹腔鏡手術で該当部分の腸を切除し、縫合する方法です。
がん化が強く疑われる際や、リンパ節転移のリスクが高いと考えられるときも、外科手術が選択肢になることがあります。
切除後の経過観察
切除が終わったからといって安心しきるのは危険です。大腸の粘膜は新しいポリープを再び生じる可能性があるため、一定の期間をあけて再度の内視鏡検査を受けることが推奨されます。
検査の頻度は医師の判断やポリープの性質によって異なりますが、1年〜3年程度のスパンで観察することが多いです。
- ポリープのサイズや数
- 切除時の病理検査結果
- 家族歴や生活習慣
上記のような要素を総合的に考慮して再検査のタイミングが決まります。
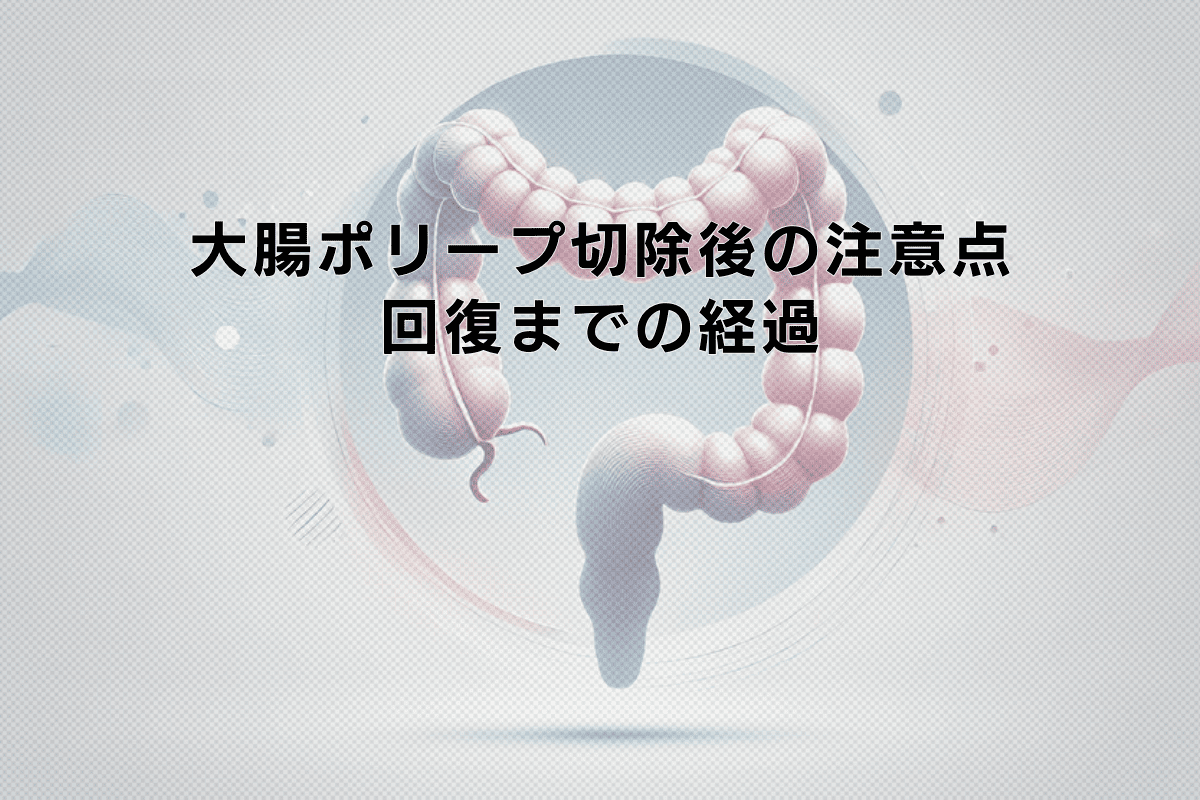
再発予防と生活習慣
大腸ポリープは、一度切除しても再びできる可能性があり、再発を防ぐためには、適度な運動やバランスの良い食生活、禁煙などの生活習慣が関わる点が大きいです。
腸に負担をかける習慣を見直していくことで、ポリープの発生リスクを下げられる可能性が高まります。
食事のポイント
野菜や果物、食物繊維を豊富に含む食品を積極的に摂ると、便の通過がスムーズになり、腸への負担を減らす効果が期待できます。
また、赤身肉や加工肉の過剰摂取は大腸ポリープだけでなく大腸がんのリスク要因と指摘されているため、適度な摂取量を守りましょう。
バランスを考えた食事
| 食材群 | 例 | 推奨される食べ方 |
|---|---|---|
| 野菜・果物 | ブロッコリー、キャベツ、りんごなど | サラダ、スープ、蒸し料理 |
| 主食(穀物・パンなど) | 全粒粉パン、玄米、ご飯 | 食物繊維を意識して選択 |
| タンパク質 | 魚、鶏肉、大豆製品 | 加工肉は控えめに |

適度な運動
定期的に運動を行うことで腸のぜん動運動が活発化し、便通が良くなる効果が期待でき、ウォーキングや軽めのジョギング、水泳などの有酸素運動を週に数回程度取り入れると、腸だけでなく全身の健康維持にも役立ちます。
禁煙と節酒
喫煙者の方は、できるだけ早い段階で禁煙を心がけたほうがよく、たばこに含まれる有害物質が血液を通じて体全体に回り、腸にも影響を及ぼす可能性があります。
アルコールも適量を超えると肝臓機能や胃腸の粘膜に負荷をかけるため、節度ある量にとどめることが大切です。
- タバコは腸粘膜への負担を増やす一因
- お酒は適量を超えないよう管理する
- 水分補給をこまめに行って便秘を避ける
ストレスマネジメント
ストレスがたまると食生活が乱れたり、睡眠不足に陥ったりする可能性があり、これらの要因は腸内環境にも影響し、ポリープ再発のリスクを高めることが考えられます。
適度なリラックス法や趣味を見つけてストレスをコントロールしましょう。
再発予防の主なポイント
| 項目 | 具体的な取り組み |
|---|---|
| 食生活 | 食物繊維やビタミンを豊富に摂取する |
| 運動 | 毎日のウォーキング、週に数回のジョギングなど |
| 禁煙・節酒 | たばこをやめ、アルコールを控える |
| ストレス管理 | 趣味やリラクゼーションを取り入れる |
大腸ポリープと内視鏡検査の重要性
大腸に過形成性のポリープや腺腫が見つかった場合、多くの方は驚くものの、自覚症状がない場合は「すぐにどうこうなるわけではない」と考えて後回しにしてしまいがちです。
しかし、良性であっても放置すればリスクが高まる可能性が否定できないので、内視鏡検査を定期的に受けることで、ポリープをいち早く見つけ、正しいタイミングで対処できます。
早期発見のメリット
大腸がんは日本人にとって身近ながんの1つで、死亡原因としても上位に位置していますが、ポリープ段階で切除できれば、がん化リスクを大幅に低減できる可能性が高いです。
とくに腺腫性のポリープはがんの前段階ともいわれており、早期発見が将来的なリスク管理に直結します。
- 数mm程度の小さなうちに切除すれば手技も簡便
- 後遺症や長期入院の必要が少なくなる
- 予後が良好になりやすい

内視鏡検査のタイミング
40歳を過ぎたあたりからは、定期的な大腸内視鏡検査を検討する価値があり、家族歴や既往症によっては30代からでも受けた方がいい場合があります。
検査の間隔はポリープの有無や切除の履歴によって異なるため、医師と相談しながら決めることが大切です。
年代別に意識したい検査の目安
| 年代 | 検査の頻度 | 理由 |
|---|---|---|
| 30代 | 家族歴や症状がある場合は検討 | 若年でも腫瘍性ポリープが見つかることあり |
| 40〜50代 | 2〜3年に1回程度 | ポリープが発生しやすくなる時期 |
| 60代以上 | 1〜2年に1回程度 | リスクが高まるため頻度を増やす |
大腸ポリープと胃カメラの関連
大腸カメラと同様に、胃カメラも消化管を直接観察できる有用な検査で、大腸にポリープが見つかった場合、消化管全体の状態を把握するために胃カメラも提案されるケースがあります。
胃の粘膜にもポリープや潰瘍ができることがあり、消化管全般の健康状態を総合的にチェックすることが将来的なリスク回避につながります。

健診の活用
一般的な健康診断では、便潜血検査や腹部超音波などで消化器の状態をある程度チェックできますが、大腸ポリープの発見にはやはり直接観察する内視鏡検査の精度が高いです。
健診で異常の可能性が指摘されたら、早めに専門医の受診を検討してください。
よくある質問
大腸にポリープが見つかった際、多くの方が疑問に思う点を挙げてみました。過形成性のポリープと腺腫性のポリープが混在することもあるため、実際に検査や治療を受ける際には医療従事者に質問しましょう。
- 内視鏡検査はどれくらい痛いですか?
-
個人差が大きいですが、鎮静剤を使用することで痛みや違和感を和らげやすいです。緊張や恐怖心が強い場合は、事前に担当医に相談してみるといいでしょう。
- ポリープを切除しても再発しますか?
-
切除した部位からの再発は多くないですが、大腸全体にわたり新たなポリープが出現する可能性はあります。定期的な内視鏡検査を継続することが重要です。
- 過形成性ポリープなら切除しなくてもいいのでしょうか?
-
過形成性はがん化リスクが低いとはいえ、ポリープの大きさや数によっては切除を勧める場合があります。医師の判断を仰ぎ、適切に対応することをおすすめします。
- 大腸ポリープがあると便潜血検査は必ず陽性になりますか?
-
必ずしも陽性になるわけではありません。出血しないポリープやごく微量の出血の場合、便潜血検査では見逃されることがあります。より確実な判断のために内視鏡検査が大切です。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
大腸ポリープの基本を押さえたら、次は実際の検査準備について知っておくと安心です。検査を初めて受ける方や、前回の準備がうまくいかなかった方に特に参考になる内容です。
【大腸がん検査方法の選び方 – 血液検査から内視鏡検査まで】
大腸ポリープについて理解が深まったところで、さらに大腸がん検査全般についても知っておくと、より全体像が見えてきます。検査選択の判断に役立つ包括的な情報です。
参考文献
Tanaka S, Saitoh Y, Matsuda T, Igarashi M, Matsumoto T, Iwao Y, Suzuki Y, Nozaki R, Sugai T, Oka S, Itabashi M. Evidence-based clinical practice guidelines for management of colorectal polyps. Journal of Gastroenterology. 2021 Apr;56:323-35.
Hiraoka S, Kato J, Fujiki S, Kaji E, Morikawa T, Murakami T, Nawa T, Kuriyama M, Uraoka T, Ohara N, Yamamoto K. The presence of large serrated polyps increases risk for colorectal cancer. Gastroenterology. 2010 Nov 1;139(5):1503-10.
Sano W, Hirata D, Teramoto A, Iwatate M, Hattori S, Fujita M, Sano Y. Serrated polyps of the colon and rectum: Remove or not?. World journal of gastroenterology. 2020 May 21;26(19):2276.
Hirata T, Kawakami Y, Kinjo N, Arakaki S, Arakaki T, Hokama A, Kinjo F, Fujita J. Association between colonic polyps and diverticular disease. World Journal of Gastroenterology: WJG. 2008 Apr 21;14(15):2411.
Konishi K, Kaneko K, Kurahashi T, Yamamoto T, Kushima M, Kanda A, Tajiri H, Mitamura K. A comparison of magnifying and nonmagnifying colonoscopy for diagnosis of colorectal polyps: a prospective study. Gastrointestinal endoscopy. 2003 Jan 1;57(1):48-53.
Turner KO, Genta RM, Sonnenberg A. Lesions of all types exist in colon polyps of all sizes. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2018 Feb 1;113(2):303-6.
Ackroyd FW, Hedberg SE. Colonic polyps. Annual review of medicine. 1985 Feb;36(1):619-25.
Liljegren A, Lindblom A, Rotstein S, Nilsson B, Rubio C, Jaramillo E. Prevalence and incidence of hyperplastic polyps and adenomas in familial colorectal cancer: correlation between the two types of colon polyps. Gut. 2003 Aug 1;52(8):1140-7.
Shinya HI, Wolff WI. Morphology, anatomic distribution and cancer potential of colonic polyps: an analysis of 7,000 polyps endoscopically removed. Annals of surgery. 1979 Dec 1;190(6):679-83.
Colucci PM, Yale SH, Rall CJ. Colorectal polyps. Clinical medicine & research. 2003 Jul 1;1(3):261-2.