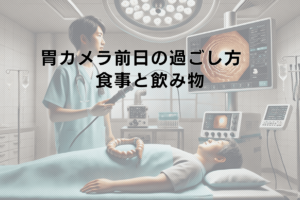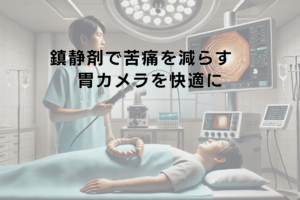私たちの胃は食物の消化に大きくかかわる器官であり、日々の生活習慣やストレス、ピロリ菌などさまざまな要因によって病気が発症しやすくなります。
そこで、胃カメラを使った内視鏡検査を受けて早めに状態を調べ、治療や予防につなげていくことが重要です。
本記事では、胃カメラ検査の方法と流れ、経鼻と経口の違い、見つかりやすい病気、そして検査後の過ごし方までを詳しく紹介します。
胃カメラ検査の特徴
医療機関では患者さんができるだけリラックスしながら胃カメラ検査を受けられるよう、さまざまな工夫を行っています。
胃カメラ検査が必要な背景
胃は消化の入り口となる器官であり、食道から胃、そして十二指腸へと食べ物が通る時に物理的・化学的刺激を受けやすい場所です。

さらに、胃酸やピロリ菌の影響、アルコール、喫煙、ストレスなどが加わって、胃がんや食道がん、胃潰瘍をはじめとする病気を引き起こしやすいです。
胃がん、食道がんは早期発見が難しい場合があるため、内視鏡による直接的な観察が大切になります。
大腸内視鏡検査との同日実施について
胃カメラ検査を受ける際、大腸内視鏡検査を同日に実施する例があり、特に人間ドックなどで健康診断を受ける方は、胃と大腸の両方を一度でチェックすることを希望する方も多いです。

医師と患者さんのコミュニケーション
内視鏡検査はカメラを使って粘膜を詳細に観察するため、検査中は細かな所見を逐一確認する時間が続きます。
医師、スタッフによる説明や患者への声かけが丁寧であればあるほど、不安は軽減される傾向があります。
経口と経鼻の違い
胃カメラ検査には口から内視鏡を挿入する「経口」と、鼻から細いカメラを通す「経鼻」があり、どちらも同じように胃や食道、十二指腸の粘膜を直接観察できる方法ですが、使用する内視鏡の太さや検査中の感覚に違いがあります。
自分に合った方法を選ぶことで、苦痛をできるだけ減らしながら胃カメラ検査を受けやすくなります。
経口内視鏡検査の特徴
経口内視鏡は内視鏡自体の操作性が高いのが利点です。
また拡大観察機能のある機種を用いれば、粘膜の詳細を観察し、がんを発見しやすくなります。
カメラが比較的太めであるため、挿入時に咽頭反射によって違和感が生じやすいですが、熟練した医師であれば経鼻内視鏡よりスムーズに検査が進む場合もあります。
のどの麻酔や鎮静剤を使用することで、ある程度の苦痛を軽減することは可能です。
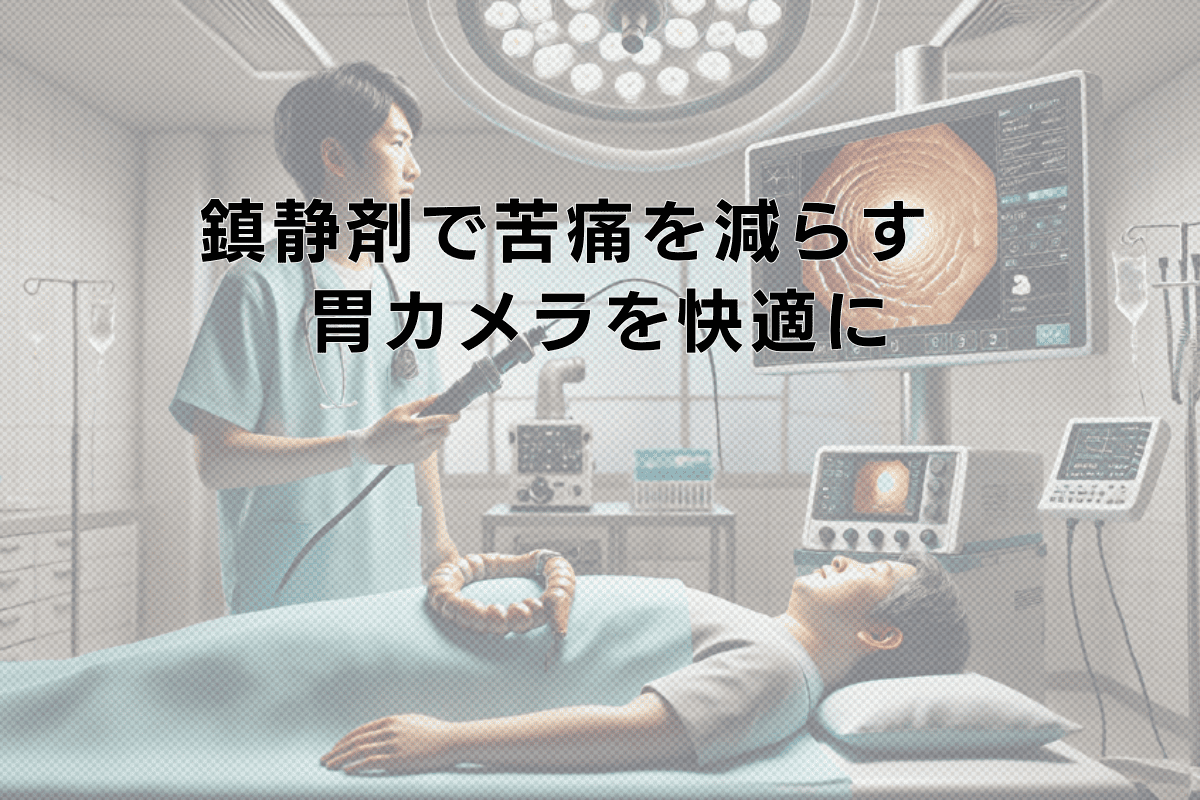
経鼻内視鏡検査の特徴
経鼻では鼻から細い内視鏡を挿入するため、のどを刺激しにくく、嘔吐反射が強い方に向いていて、検査中も口から呼吸できるので比較的楽に感じるケースが多いです。
ただし、鼻腔が狭い方や、鼻炎、鼻出血を起こしやすい方は、経鼻が難しい場合があるため、事前の診察で医師と確認することが大切です。
それぞれのメリット・デメリット
経口と経鼻にはメリット・デメリットがあり、大きな違いは検査時の咽頭反射が起きる頻度と、挿入可能なカメラの太さです。
経口の方が高性能なカメラを使いやすい場合がある一方、患者さんの苦痛感はやや大きく、経鼻は痛みや嘔吐反射が少ないものの、鼻腔の状態によって検査ができないこともあります。
経口と経鼻の主なメリット・デメリット
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 経口 | 内視鏡が太めで操作しやすい 詳細な観察が可能 | 咽頭反射が起こりやすく苦しさを感じやすい |
| 経鼻 | 口呼吸ができ、嘔吐反射が少ない傾向にある | 鼻出血や鼻の痛みが出る場合がある |
医師と相談して検査方法を選ぶ
検査方法をどちらにするかは、患者さんの希望や症状、過去の検査経験などを踏まえて決めます。
事前に医師へ相談し、検査への不安や疑問を率直に伝えることで、より適した方法を選択できます。
基礎疾患の有無なども含めて判断することも重要です。
胃カメラ検査で分かる主な病気
胃カメラは、内視鏡を使って消化管を直接観察し、病変の有無や程度をチェックするために行い、胃や食道、十二指腸までを視野に入れ、粘膜の色調や形状、潰瘍や腫瘍などがないかを詳しく確認します。
胃カメラを受けることで早期発見しやすくなる病気がいくつかあります。
胃がん
日本人に多いがんの1つとして知られ、初期には無症状のことが多いです。
胃カメラ検査で胃の粘膜を隅々まで観察することにより、わずかな凹凸や色調の変化を見つけやすくなります。
早期発見が治療において重要とされ、症状がない場合でも定期的に検診を受けておくと早期に対処しやすいです。
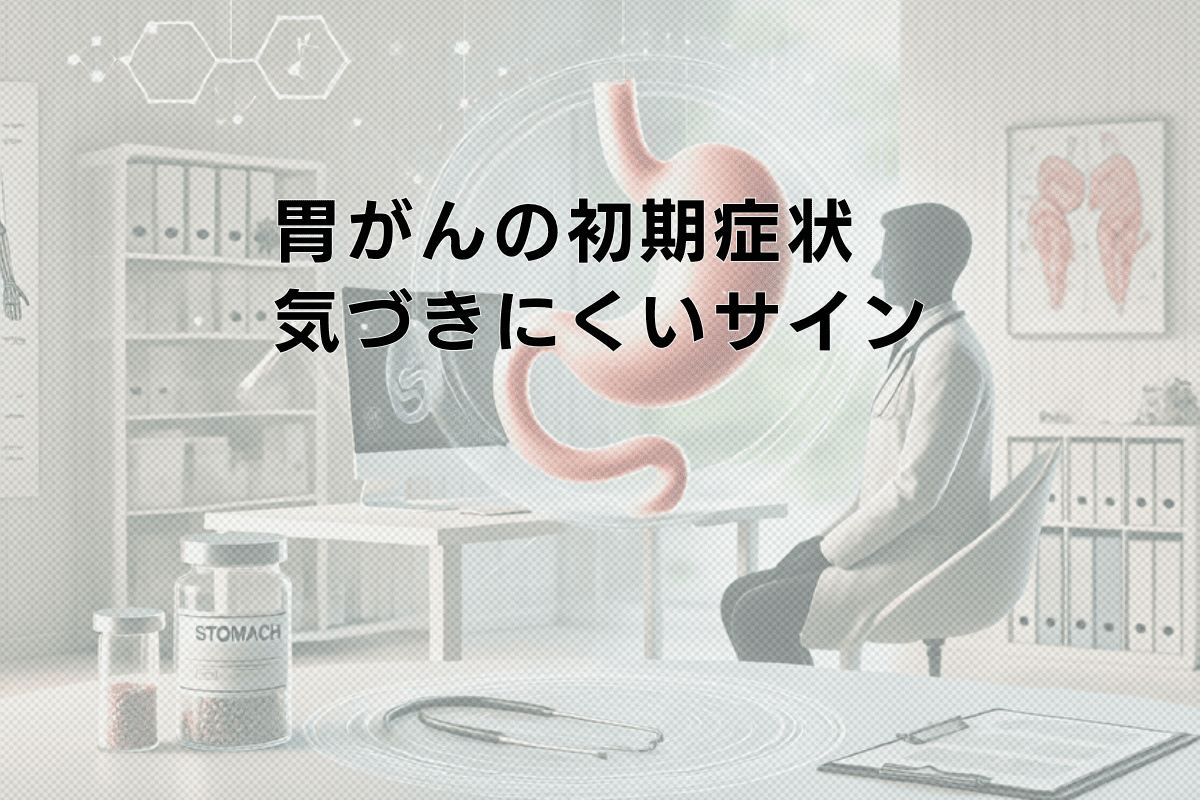
胃潰瘍と十二指腸潰瘍
胃潰瘍や十二指腸潰瘍は、胃酸の分泌過多やピロリ菌感染、ストレスなどが要因で発生し、強い腹痛や吐き気、出血などを引き起こすことがあります。
内視鏡検査中に潰瘍の部位や深さ、出血の有無を観察して治療方針を決められます。

逆流性食道炎
胃酸が食道に逆流することで食道粘膜が炎症を起こし、胸やけや呑酸(酸っぱいものがこみ上げる感じ)などの症状を引き起こす病気で、胃カメラで観察すると、食道下部にただれが生じていることがあります。
症状が長引く場合は放置せずに検査を受けて、薬物治療や生活習慣の改善を検討することが大切です。
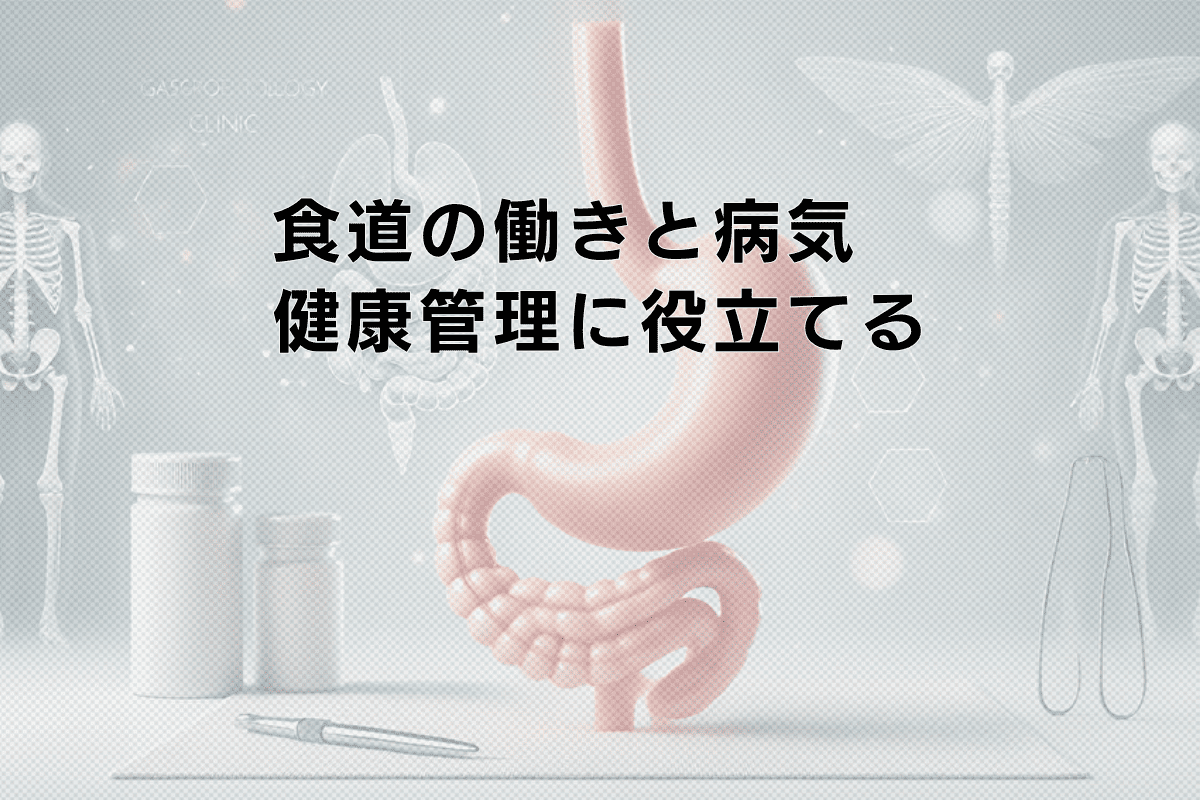
食道がん
消化器に起こる難治性がんの一つ。初期には無症状のことがほとんどです。
アルコール、喫煙がリスクとなる他、逆流性食道炎が原因で起こる場合もあります。
定期的な健診が重要であるとともに、少しでも違和感があれば検査を受けるようにしてください。
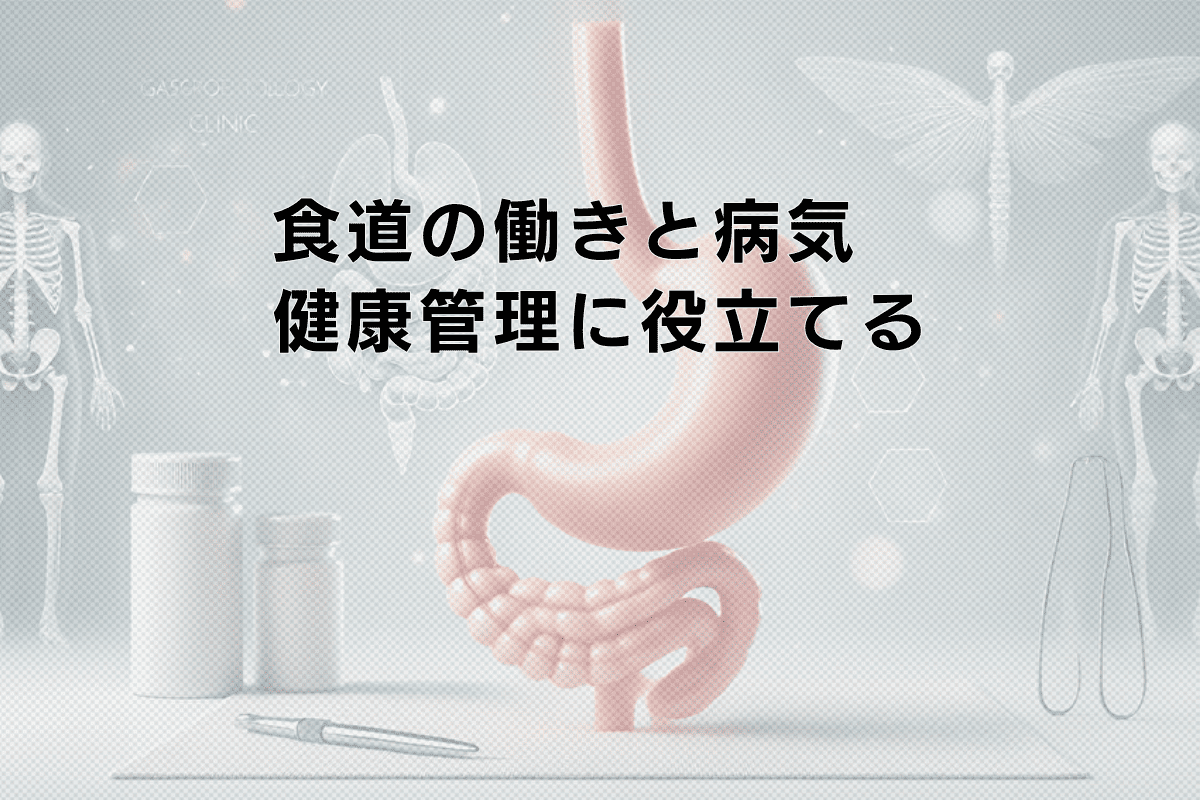
ピロリ菌感染
ピロリ菌が胃に定着すると慢性胃炎や胃潰瘍を起こし、胃がんの発症リスクも高まります。
胃カメラ検査と合わせてピロリ菌の有無を調べる検査を行うと、除菌治療への道筋ができ胃の健康維持に役立ち、除菌によって症状の改善や病気の発生を抑制できる可能性があります。

胃カメラで発見されやすい主な病気と特徴
| 病気 | 特徴 |
|---|---|
| 胃がん | 日本人に多いがん。初期は症状が出にくいが内視鏡で発見しやすい |
| 胃潰瘍・十二指腸潰瘍 | ピロリ菌感染などが主な原因。強い腹痛や吐き気、出血を伴うことがある |
| 逆流性食道炎 | 胸やけや呑酸を感じることが多く、放置すると食道粘膜の損傷が進む |
| 食道がん | 難治性がんの一つ。アルコール、喫煙、逆流性食道炎がリスク |
| ピロリ菌感染 | 慢性胃炎や胃潰瘍、胃がんのリスクを高める。除菌治療を行うと改善が期待できる |
検査当日までの流れと注意点
胃カメラ検査を受ける際は、検査日が決まった後から当日までに守るべきルールや準備があり、正しい準備を行っていないと、胃の中に食物が残っていて観察が難しくなったり、薬の影響で検査ができなくなったりする場合があります。
安全かつ正確な検査を行うためにも、医師やスタッフから案内される内容に沿って行うことが大切です。
事前の食事制限
通常、検査前日の夜以降は食事を控えるよう案内していて、食べ物が胃に残っていると、カメラの視野を遮ったり嘔吐しやすくなったりするため、十分な断食時間を確保することが必要です。
水やお茶など透明な水分は比較的許可されることが多いですが、事前に診療時に確認してください。
内服薬の調整
持病がある方や、日頃から飲んでいる薬がある方は、検査前の内服に関して医師へ申し出ることが大切です。
血液をサラサラにする薬や糖尿病の薬などは、検査に影響を与える恐れがあるため、一時的な中断や変更が必要になる場合がありますが、自己判断で服用を中止しないようにしましょう。
当日の服装と体調管理
検査当日は、楽に着脱できる服装が望ましいです。検査後に体を休められるよう、ゆとりのある時間設定で来院してください。体調が悪化しているときや、発熱しているときは無理に来院せずに一度お問い合わせいただくほうが安心です。
同意書と事前説明
初めて受診される方や、検査内容が変更となる場合には、同意書を確認したり説明を受けたりすることがあり、検査に対する不安や疑問点を解消してから実際の手順に進むと、気持ちも落ち着きます。
検査当日までに押さえておきたい準備と注意点
- 検査前日は夜9時以降の食事を控える(医師の指示に従う)
- 水・お茶など透明な飲み物以外は飲まないようにする
- 持病の薬については必ず事前に医師へ伝える
- 検査日当日の体調に不安がある場合は、早めに連絡をする
- 検査に伴うリスクや説明内容をしっかり理解しておく

検査当日のステップ
検査前に、受付から検査終了後までの流れをイメージしておくと安心感が高まります。胃カメラ検査では、わずかな緊張がのどや胃の動きを敏感にしてしまうこともあるため、少しリラックスできるよう気持ちの準備をしてください。
受付と問診
来院されたら受付にて手続きを済ませ、待合スペースで過ごしていただき、その後、看護師や医師が問診を行い、体調や既往歴、現在の症状などを確認します。
また、経鼻か経口かどちらで行うか再度希望を確認することがあるため、遠慮なく要望を伝えてください。
局所麻酔や鎮静剤の使用
検査が始まる前に、のどや鼻への局所麻酔を用いる場合がありますが、これは挿入時の違和感を軽減するための処置です。また、不安が強い方や嘔吐反射が強い方には、鎮静剤を用いることを提案する場合もあります。
鎮静剤を使うと眠気が強くなるため、検査後の帰宅方法などを事前に検討してください。
内視鏡の挿入と観察
準備が整ったら、実際に内視鏡を挿入します。ゆっくりとしたペースでカメラを進め、食道から胃、十二指腸にかけて観察していきます。
ポリープや炎症、出血、粘膜の変化などを詳細に見極め、必要があれば生検(組織を一部採取)を行うことがあり、多少の出血や痛みを感じることもありますが、多くは一時的です。
内視鏡挿入時の主な観察ポイント
| 観察部位 | 確認する内容 |
|---|---|
| 食道 | 逆流性食道炎、食道がん、粘膜下腫瘍などの有無 |
| 胃 | 胃炎、胃潰瘍、胃がん、ポリープ、ピロリ菌感染の有無 |
| 十二指腸 | 潰瘍や腫瘍、ポリープなどがないか |
| 粘膜の色調・形状 | 炎症やただれ、潰瘍、血管透見度、隆起や陥凹の形状 |
| 出血の状態 | 出血点の有無、範囲、止血可能な状況かどうか |
検査終了後の休憩
検査が終わったら、処置室やリカバリースペースで少し休んでいただき、鎮静剤を使っている場合は、眠気が残っていることが多いので、無理に立ち上がらず安静に過ごしてください。
看護師が血圧や脈拍を確認し、回復の具合を見守ります。意識がはっきりしてきたら、検査結果の説明を受ける流れに入ります。
検査当日の流れ
- 受付を済ませたら問診を実施(症状や既往歴を再確認)
- 局所麻酔や鎮静剤の使用を検討し、医師・患者で相談
- 内視鏡を挿入して胃や食道、十二指腸を観察
- 検査終了後はリカバリースペースで体調が安定するまで休憩
検査後の過ごし方と治療へのつながり
胃カメラ検査のあとは、口や鼻の違和感が残ったり、喉がイガイガしたりすることがありますが、多くの場合は短時間で落ち着きます。重要なのは検査結果をどう受け止め、どのような治療や予防策を取っていくかです。
検査直後の注意点
鎮静剤を使用した場合は、検査後にしばらくフラフラしたり眠気が強く残ることがあるので、自転車や車の運転は避け、できれば付き添いの方と一緒に帰宅するほうが安全です。
また、検査中に空気を入れて胃をふくらませるため、検査後にゲップが出やすかったり、腹部の張りを感じたりするかもしれないので、無理に我慢せず、楽な姿勢で過ごすとことが重要です。
結果説明と治療計画
検査当日に概ねの所見について医師から説明がありますが、生検を行った場合は後日改めて結果を確認する必要があります。
もし胃や食道に炎症や潰瘍、がんなどの病変が見つかった場合は、治療計画を立てます。
ピロリ菌感染があれば除菌治療、がんが見つかった場合は内視鏡もしくは手術による切除などを検討することになります。
胃カメラ検査後の代表的な治療方針
| 病変 | 主な治療方針 |
|---|---|
| 胃潰瘍・十二指腸潰瘍 | 胃酸抑制剤・ピロリ菌除菌治療・生活習慣の見直し |
| 逆流性食道炎 | 生活習慣改善・胃酸抑制剤の服用 |
| 胃がん・食道がん | 内視鏡的切除・外科手術・薬物療法 |
| ポリープ | 良性の場合は経過観察、悪性や疑いがあれば切除 |
| ピロリ菌感染 | 除菌療法・定期的な内視鏡検査 |
再検査や追加検査の必要性
病気が見つかった場合でも、症状や進行度によっては再検査や追加検査を受ける必要があり、がんの疑いがある場合は、CT検査や大腸内視鏡なども併用することがあります。
治療の効果を確認するために定期的な内視鏡検査を提案されることもあるので、医師や専門医とスケジュールを検討してください。
生活習慣の見直しと予防
たとえ検査で異常が見つからなくても、胃や消化管の健康を維持するためには適度な運動やバランスの良い食生活が大切で、また、喫煙や過度な飲酒は消化器系の粘膜に負担をかけるため、予防の観点からも控える努力が有効です。
次回の健康診断や人間ドックで再び胃カメラ検査を受ける場合に備え、日頃の習慣を見直すことをおすすめします。
胃の健康を守るために意識したい生活習慣
- 食事はよく噛み、偏った食事を避ける
- 適切な範囲での飲酒量を心がける
- タバコは可能な限り控える
- ストレスを溜め込みすぎず、適度に発散する方法を探す
- 定期的な健康診断やクリニックでの相談を行う
胃カメラ検査に対する疑問と対策
初めて胃カメラ検査を受ける方や、過去につらい経験をした方は、さまざまな疑問をお持ちかもしれません。検査の苦痛や費用、保険適用などは多くの患者さんが気にするポイントです。ここでは代表的な疑問と、それに対する対策を紹介します。
胃カメラは苦しい?
胃カメラ検査は、人によっては嘔吐反射や不快感が強く出る場合がありますが、咽頭反射が敏感な方は経鼻内視鏡を選択したり、鎮静剤を使用したりといった対策で苦痛を軽減できます。
医師と事前にコミュニケーションを取ることが大切です。
費用や保険適用について
胃カメラ検査は健康保険が適用されるケースが多いため、自己負担額は3割程度が一般的でが、人間ドックなど特別なコースで行う場合や、精密検査以外の検査では保険が適用されない場合があります。
検診の場合でも病気が疑われる場合は保険診療へ切り替わる可能性もあるため、事前に問い合わせて確認すると安心です。
胃カメラ検査時の費用目安
| 区分 | 費用の目安(3割負担の場合) |
|---|---|
| 通常の保険診療 | 約3,000円~6,000円程度 |
| 生検(組織検査)実施時 | 約5,000円~10,000円程度 |
| 健康診断・人間ドック | 施設やコースによって異なり、保険適用外の場合は全額自己負担 |

人間ドックや健康診断との違い
人間ドックや健康診断で行う胃カメラ検査は、予防や早期発見を目的としたスクリーニング的な意味合いが強い一方、医療機関での保険診療としての胃カメラ検査は、症状がある場合や胃がんなどの疑いがある場合に精密検査として実施します。
検査の内容や精密度に違いがあるため、目的に応じて使い分ける必要があります。
今後のスケジュールと定期的な受診
一度胃カメラ検査を受けて異常がなかったとしても、胃がんやピロリ菌感染などのリスクは年齢や生活習慣によって変動する場合があります。
医師から「1年ごとに検査を受けると安心」などの提案を受けたら、忘れずにスケジュールを押さえておきましょう。逆流性食道炎などは再発しやすいので、症状が出たときは早めに受診しておくことが大切です。
定期的な受診を考えるときのポイント
- ピロリ菌感染がある方は除菌治療後も年1回を目安に継続的に検査を受ける
- 胃がん、食道がんの家族歴がある方は定期検査を検討
- タバコやお酒が多い方は生活習慣を見直しながら定期検査を継続
- 逆流性食道炎など症状を感じる場合はすぐに相談する
- 人間ドックや健康診断とあわせて医師の判断を仰ぎ、適切な時期に精密検査を行う
胃は私たちの身体のなかでも食事やストレスの影響を直接受けやすい器官であり、病気の発見や治療において内視鏡検査の果たす役割は非常に重要です。
もし、胸やけや胃の痛みなどの症状が続いている方は早めに受診して検査を検討し、問題が見つからなかった方も1~2年に1回といったペースでの検診をおすすめします。
次に読むことをお勧めする記事
【内視鏡検査費用の目安と流れ 胃と大腸のチェック方法】
胃カメラ検査の流れについて理解できたら、次は実際の費用や保険適用について、以下の記事で一緒に勉強してまいりましょう。検査を受ける準備を具体的に進めたい方に特におすすめです。
【大腸内視鏡検査とはどのような検査なのか】
胃カメラ検査についての理解が深まりましたら、さらに大腸の内視鏡検査についても知っておくと、より包括的な健康管理につながります。以下の記事で一緒に学んでまいりましょう。
参考文献
Coleman WH. Gastroscopy: a primary diagnostic procedure. Primary Care: Clinics in Office Practice. 1988 Mar 1;15(1):1-1.
Marlicz W, Ren X, Robertson A, Skonieczna-Żydecka K, Łoniewski I, Dario P, Wang S, Plevris JN, Koulaouzidis A, Ciuti G. Frontiers of robotic gastroscopy: a comprehensive review of robotic gastroscopes and technologies. Cancers. 2020 Sep 28;12(10):2775.
Schindler R, Eusterman GB. Gastroscopy: the endoscopic study of gastric pathology. Annals of Surgery. 1937 Nov 1;106(5):958.
Froehlich F, Schwizer W, Thorens J, Köhler M, Gonvers JJ, Fried M. Conscious sedation for gastroscopy: patient tolerance and cardiorespiratory parameters. Gastroenterology. 1995 Mar 1;108(3):697-704.
Tanner NC. A critique of gastroscopy. British Medical Journal. 1944 Dec 12;2(4382):849.
Hungin AP, Thomas PR, Bramble MG, Corbett WA, Idle N, Contractor BR, Berridge DC, Cann G. What happens to patients following open access gastroscopy? An outcome study from general practice. British Journal of General Practice. 1994 Nov 1;44(388):519-21.
Meyers MA, Ghahremani GG. Complications of fiberoptic endoscopy: I. Esophagoscopy and gastroscopy. Radiology. 1975 May;115(2):293-300.
Park DJ, Lee HJ, Kim SG, Jung HC, Song IS, Lee KU, Choe KJ, Yang HK. Intraoperative gastroscopy for gastric surgery. Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques. 2005 Oct;19:1358-61.
Mylonaki M, Fritscher-Ravens A, Swain P. Wireless capsule endoscopy: a comparison with push enteroscopy in patients with gastroscopy and colonoscopy negative gastrointestinal bleeding. Gut. 2003 Aug 1;52(8):1122-6.
Voutilainen ME, Juhola MT. Evaluation of the diagnostic accuracy of gastroscopy to detect gastric tumours: clinicopathological features and prognosis of patients with gastric cancer missed on endoscopy. European journal of gastroenterology & hepatology. 2005 Dec 1;17(12):1345-9.