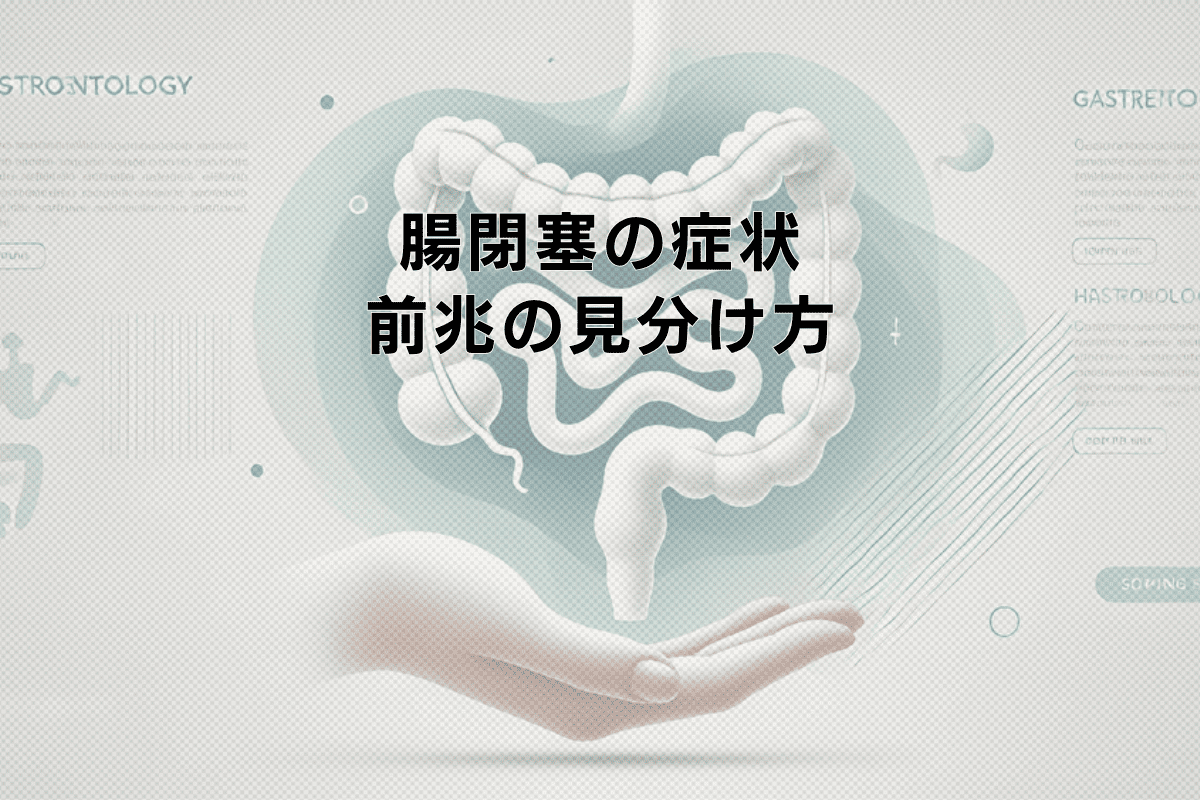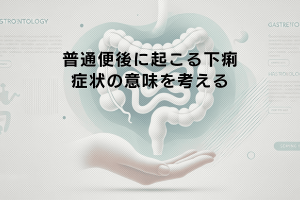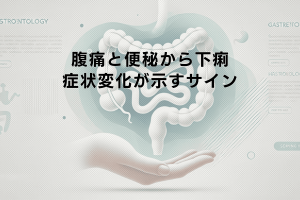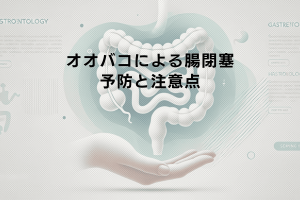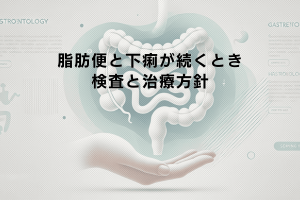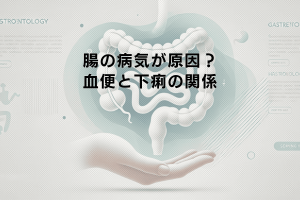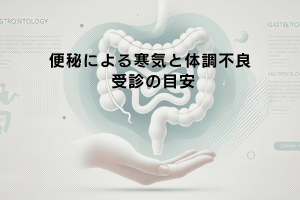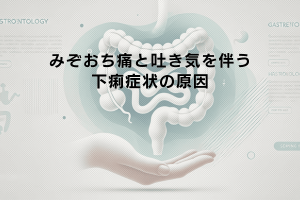腸閉塞は腸管が物理的または機能的に詰まってしまい、食べ物や消化液の通過が妨げられる状態で、腹痛や嘔吐、便通異常などの症状を引き起こし、重症化すると手術が必要になる可能性があります。
初期段階ではお腹の不快感程度で済むことがあり、気づきにくい点も特徴です。
腸内の状態を知るために内視鏡検査を検討する人も増えており、腸閉塞が疑われる場合は自己判断を避け、病院を受診して早めに検査を受けることが大切になります。
腸閉塞の基本的なメカニズム
腸閉塞とは、消化管の内容物がスムーズに通過できなくなる病態で、胃や小腸、大腸など各部位で起こる原因が異なりますが、症状としては腹部膨満や嘔吐などが共通して見られることが多いです。
原因を正確に把握し、適切な治療へ進むために内視鏡検査などで腸の状態を調べるケースもあります。
物理的な閉塞と機能的な閉塞
腸閉塞は大きく分けると、物理的な要因で腸が詰まるケース(腸閉塞)と、腸の動きが低下することで内容物が進まなくなるケース(イレウス)があります。
物理的な閉塞としては腸管がねじれていたり、腸管内に腫瘍や硬い便が詰まったりする状況が該当します。
一方、機能的な閉塞は麻痺性イレウスなどと呼ばれ、腸の蠕動運動が著しく落ちることで起こることが特徴です。
腸管の動きと蠕動運動の重要性
腸管は食べた物を消化吸収するために、自律神経の働きによって一定のリズムで収縮と弛緩を繰り返し、これを蠕動運動といい、食物を先へ送り出す機能を担っています。
蠕動運動が低下すると、腸内にガスや食物残渣が停滞しやすくなり、お腹に張りや痛みなどの症状が起こりやすいです。
腸閉塞のお腹に関連する症状の多様性
腸閉塞が起こった場合、次のような症状が現れ、急性腹痛や嘔吐、ガスが出ない、排便が止まるなど、突然の変化として出る場合があれば、じわじわと痛みが続くケースもあります。
ガスや便が通らずに腹部が大きく膨れるため、外見的にも明らかな膨満感がある人もいます。
腸閉塞と内視鏡検査が関連する理由
物理的な閉塞であれば造影検査やレントゲンなどで特有のガス像を確認することが多いですが、腸管内部を直接観察するために内視鏡検査を行うケースもあります。
腸閉塞の原因が腸内の腫瘍やポリープである可能性があるなら、カメラで視認して判断し、同時に組織の一部を採取することが大切です。
腸閉塞と腸管内の状態
| 状態 | 特徴 |
|---|---|
| 物理的閉塞(腸閉塞) | 腸管が狭窄やねじれなどにより実際に詰まる |
| 機能的閉塞(イレウス) | 腸の運動が低下し、内容物が送り出されなくなる |
| 腸内ガスの増加 | 排出が阻まれると腹部膨満を起こしやすい |
| 急性または慢性の経過 | 短時間で進むケースもあれば、慢性的に続く場合もある |

腸閉塞の主な症状
腸閉塞となるお腹の症状は、人によって軽度の場合と重度の場合があり、単なる便秘と見分けがつきにくいケースもあるため、症状の特徴や程度を把握することは重要です。
とくに腹部膨満や痛みの質、嘔吐の有無などに注目すると、腸内の異常を早めに疑うきっかけになるかもしれません。
腹部膨満感の特徴
腸閉塞が進行すると腸管内のガスや内容物が停滞して、お腹が強く張り、お腹を叩くと太鼓のように高い音が響く鼓腸音が聞こえることもあります。
腹部が膨れるだけでなく、みぞおち付近や下腹部に激しい圧迫感を覚える場合もあり、症状が進むと動くのも難しくなります。
嘔吐や吐き気の出方
腸閉塞で嘔吐が起こる場合、胃に近い部分で閉塞していると、食べた物が逆流しやすくなるため頻回に吐くことがあります。
大腸など下部での閉塞でも、腸内のガスや液体が逆流して吐き気を起こすことがあり、吐瀉物に便のような臭いが混じるケースも見られます。嘔吐が続くと脱水症状になるおそれがあるので、注意してください。
便秘やガスが出ない状態
長期間にわたる便秘だけでなく、突然に便が出なくなる状態も注意を要し、腸閉塞の場合、ガスすら排出できなくなることがあり、特有の腹痛と組み合わさることで深刻な状態に陥る可能性があります。
特に高齢者は症状を自覚しにくい場合もあるため、周囲の人が便の状態や食事内容を観察することが大切です。
腹痛の種類とタイミング
腸閉塞の腹痛はけいれん性の激痛を伴う場合が多いとされていますが、痛み方は人それぞれです。
一定の間隔で痛むこともあれば、常に鈍痛が続き、ときに刺すような痛みに変わるなど、変動性があり、また、体を動かすと痛みが増す、仰向けに寝ると圧迫感が増すなど、姿勢の変化で症状が増悪するケースもあります。
症状と関連するセルフチェック項目
- 1週間以上排便がなく、腹痛や膨満感を伴う
- 強い吐き気や嘔吐が収まらない
- 腹痛が周期的に強まる
- 何日もガスが出ず、お腹がパンパンに張る
- 体重が急激に落ちる、食欲がまったく湧かない
代表的な症状のまとめ
| 主な症状 | 具体的な特徴 |
|---|---|
| 腹部膨満 | 腸内にガスが溜まり張りが強い |
| 嘔吐・吐き気 | 胃や腸の内容物が逆流し、臭いを伴うこともある |
| 便秘・ガスの停滞 | 排便およびおならがまったく出ない状態になる |
| けいれん性腹痛 | 一定の間隔を置いて強烈な痛みを感じる場合が多い |
腸閉塞のお腹に関連する前兆
腸閉塞前兆は、はっきりとした激痛がない段階から現れることがあり、小さなサインに気づけるかどうかが、早期発見と早期治療の鍵です。
普段の便通や食事の状況から微妙な変化を感じ取れるよう意識すると、病院を受診するタイミングを逃しにくくなります。
少量しか食べられない・胃もたれ
急激な食欲不振というよりも、「少し食べるとすぐお腹がいっぱいになる」感覚が継続し、胃もたれや吐き気につながるケースもあり、食事の量が減った結果、栄養不良に陥る可能性もあります。
これが慢性化すると、体力が落ちて腸閉塞のリスクが高まるので注意が必要です。
腹痛ではなく違和感や張り感
キリキリした痛みではなく、重苦しい違和感や軽い張り感が前兆として現れることがあります。
外見上は大きく張っていなくても、内部でガスや内容物の移動が滞りつつある場合は要注意で、腸閉塞となるお腹の症状は決して急激な激痛だけではないので、違和感の段階で専門家の意見を聞くことが大切です。
ガスや便の通過がスムーズでない
普段から便秘気味の方はさらに悪化して、腸内に老廃物やガスが留まりやすくなる場合があります。
排便があったとしても少量だったり、コロコロとした硬い便しか出ない状態が続くと、閉塞の一歩手前かもしれません。便やガスの性質が明らかに変化した場合も要チェックです。
体重の減少やだるさ
食事量が減ると当然体重も落ちやすくなりますが、異常に体重が落ちる場合や疲労感・だるさが増す場合は、腸内の異常を視野に入れることが必要です。
腸閉塞前兆の時期でも、栄養吸収がうまくいかず体力が急激に落ちるケースがあるため、自己流ダイエットと勘違いしないように注意しましょう。
前兆に関する要点
| 前兆の種類 | 具体的な兆候 |
|---|---|
| 食事量の減少 | 少し食べても満腹感が持続し、栄養不足が進みやすい |
| 腹部の張り | 激痛ではなく鈍い痛みや違和感が継続する |
| 排便・ガスの異常 | 硬い便のみ、少量しか出ない、ガスが通りにくい |
| 全身状態の悪化 | 体重減少、疲労感、脱力感の増加 |
早期に観察したいポイント
- 便やガスの量や回数に顕著な変化がある
- 食後に胃もたれや吐き気が常に続く
- 胃腸薬や整腸剤を使っても改善しない
- 急に体重が落ちて、服がゆるくなった
- お腹の動き(グルグル鳴る音)が減ったと感じる
腸閉塞の原因
腸閉塞の原因は多岐にわたり、過去に腹部手術を受けたことのある方や、高齢者、腸管にポリープや腫瘍がある場合などでリスクが高まる傾向があります。原因を明確に知ることで、適した検査や治療の方向性をつかめるでしょう。
癒着による腸管の狭窄
過去の手術や炎症により、腸の表面が癒着を起こすことがあり、癒着部分が腸管を狭くし、食物や消化液が通過しにくくなると腸閉塞が起こりやすくなります。
癒着性腸閉塞は一度発症すると再発の可能性があるため、普段から便通に気を配ることが必要です。
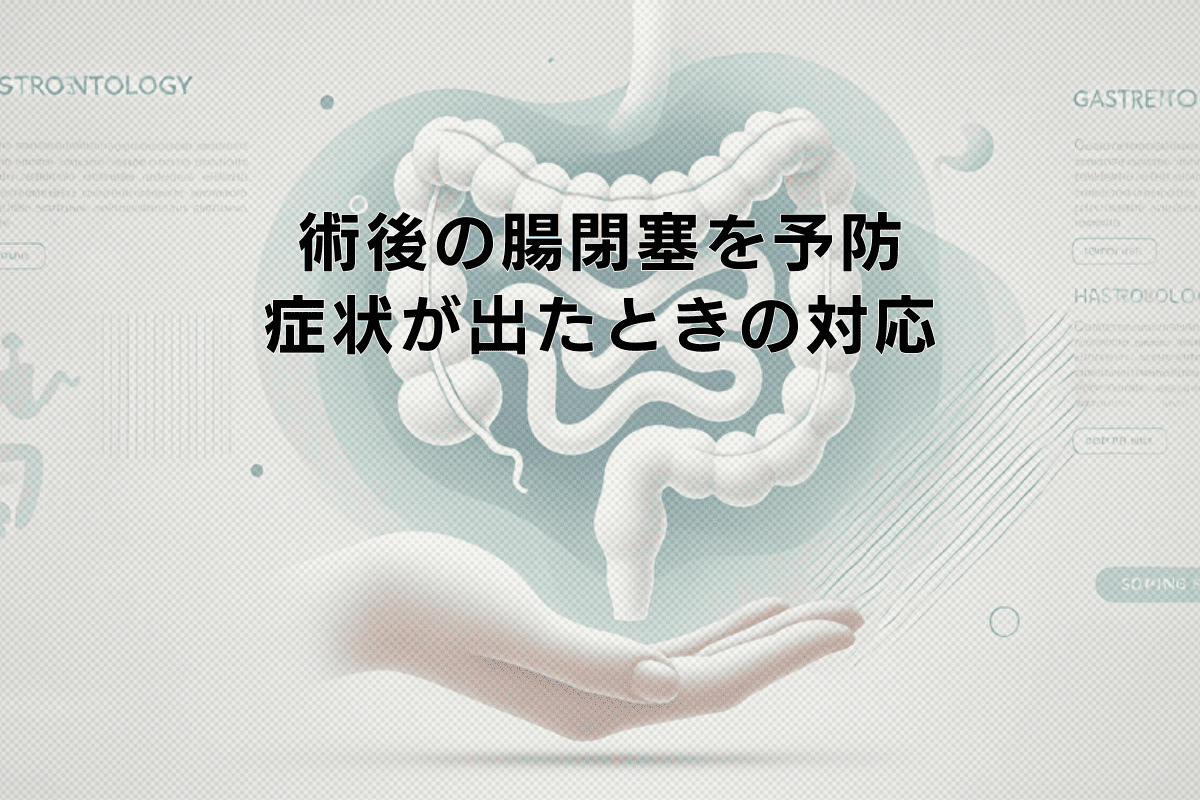
腸管内の腫瘍やポリープ
大腸がんなどの腫瘍が腸管内を塞ぐ形で腸閉塞の原因になる場合があり、良性のポリープでも大きくなると腸管を狭くし、閉塞を起こすことがあります。
定期的に大腸カメラを受けて早期発見に努めることで、重篤な腸閉塞を回避することが可能です。

腸重積や捻転
腸重積とは、腸の一部が別の部分の内側に入り込んでしまう状態で、小児に多いと言われていますが、大人でも腫瘍やポリープがきっかけで腸重積が起こるケースがあります。腸捻転は腸がねじれることで、急激な閉塞と痛みを伴います。
嚥下障害や食事の誤嚥
腸閉塞そのものの原因として直接関わるわけではありませんが、誤嚥や消化不良を起こす習慣があると胃腸に余分な負担がかかります。
高齢の方や嚥下力が弱い方が固形物を無理に食べると、腸の動きが滞った状態に陥りやすくなり、結果的に腸閉塞リスクが高まることがあります。
主な原因の対比
| 原因 | 特徴 |
|---|---|
| 癒着 | 過去の手術や炎症で腸がくっつき、通路が狭くなる |
| 腫瘍やポリープ | 腸管内を物理的に塞ぎ、閉塞を引き起こす |
| 腸重積・捻転 | 腸が一部入り込む、またはねじれて急激に詰まる |
| 嚥下障害や誤嚥 | 消化機能に負担がかかり、腸の動きが低下しやすい |
腸閉塞と内視鏡検査の関係
腸閉塞が疑われる場合、レントゲンやCTなどの画像検査を行うことが一般的ですが、腸管内の状態を正確に知るには内視鏡検査が大きな役割を持ちます。
大腸カメラや胃カメラ検査は腫瘍やポリープの有無を確認できるため、腸閉塞の原因究明にもつながります。
大腸カメラ検査でわかること
大腸カメラを挿入することで、大腸内部の状態を目視でチェックでき、狭窄部分がある場合は、どの程度詰まっているか、炎症や腫瘍がどのレベルなのかを直接確認できる利点があります。
また、発見したポリープや腫瘍の一部を切除して組織検査に回すことも可能です。
胃カメラ検査の活用
胃カメラは主に胃や十二指腸の検査に用いられますが、上部消化管に閉塞や重大な狭窄が疑われる場合には重要な手段です。内視鏡検査によって原因を突き止めれば、適切な治療計画を立案しやすくなります。

内視鏡検査が実施できないケース
腸閉塞の状態が深刻で腸管が完全にふさがっている場合や、重度の腹膜炎を伴う場合など、内視鏡を挿入できないことがあります。
また、患者さんの全身状態が悪化しているときは、内視鏡検査よりも緊急手術を優先する場合もあるため、事前に医師との十分な相談が必要です。
検査から治療への流れ
内視鏡検査で腸閉塞の原因が腫瘍やポリープによるものだと判明したときは、内視鏡治療を検討することがあります。ポリープであれば内視鏡下で切除できるケースが多いため、開腹手術よりも負担が軽減されます。
ただし、癒着や重度の狭窄では外科手術が必須となることも珍しくありません。
内視鏡検査のメリット
| 種類 | 観察部位 | メリット |
|---|---|---|
| 大腸カメラ | 大腸・直腸 | ポリープやがんの有無を直接確認し切除も可 |
| 胃カメラ | 胃・十二指腸 | 上部消化管の病変を視認し組織検査可能 |
| カプセル内視鏡 | 小腸全域 | 小腸を詳細に観察しやすい 腸閉塞を起こしているときは検査不可 |
| 経鼻内視鏡 | 食道・胃・十二指腸 | 苦痛が軽減されやすく、会話もできる |
腸閉塞に気づいた際の対処法
腸閉塞の疑いがあるときは、自己判断で下剤などを使用せずに医療機関を受診することが重要です。状態によっては短時間で重篤化する危険があり、処置を受けなければ腸管壊死など取り返しのつかない事態になるおそれがあります。
医療機関を早めに受診
腹痛が強い、嘔吐が続く、便やガスがまったく出ないなどの症状があれば、救急受診も検討してください。特に高齢者や持病のある人は症状が急激に悪化しやすいため、迷わず専門の医師に相談すると安心です。
水分摂取の注意点
軽度の場合は水分補給で症状が落ち着くケースもありますが、嘔吐が多いときや完全閉塞が疑われるときは、飲食物が逆流して危険な状態になることがあります。無理に飲食を続けると逆効果になるため、専門家の指示を仰いで判断しましょう。
下剤や整腸剤の使用を避ける理由
腸閉塞が起きているときに下剤を使うと、腸管内の圧力が上がって症状が悪化する可能性があります。整腸剤も腸の動きを活性化させることがあり、閉塞部分に負荷をかけかねないので、自己判断で使用するのは避けるほうが安全です。
病院で想定される処置
軽度であれば点滴や鼻チューブなどを使って腸の圧力を下げ、自然に通過が回復するか経過観察することがあり、内視鏡やX線で原因を調べ、状況によっては手術が必要な場合もあるでしょう。
適切な対応を受けることで、合併症のリスクを減らせます。
病院での検査や処置内容
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| レントゲン・CT撮影 | 腸の膨張やガス像を確認し、閉塞の位置を推測 |
| 内視鏡検査 | 腸管内部を直接観察し、原因を特定 |
| 点滴治療 | 脱水症状や電解質異常を改善しつつ腸を休ませる |
| 手術 | 癒着剥離、腫瘍切除など物理的な閉塞除去を行う |
対処で意識したいポイント
- 激痛や嘔吐時は医療機関へ直行する
- 素人判断で下剤や整腸剤を使わない
- 脱水リスクが高いため体調に注意する
- 便意がなくても無理に排便を試みない
- 病院の診察を早めに受けて原因究明を進める
腸閉塞予防のために意識したい生活習慣
腸閉塞にならないようにするためには、食事内容や生活リズムの見直しが大切です。体質的なリスクを完全に取り除くことは難しいものの、負担を軽減して腸の動きを維持する工夫をすることで、腸閉塞に至る確率を下げられる可能性があります。
食物繊維と水分補給
便通を良好に保つためには、食物繊維を適度に摂取し、十分な水分を補給することが重要ですが、野菜や果物を過度に摂りすぎたり、短時間で大量の水を飲んだりすると逆効果になる場合もあります。
個人の体質や活動量に合わせてバランスよく取り入れることがポイントです。

ゆっくり噛んで食べる習慣
胃や腸に負担をかけずに消化しやすくするためには、よく噛んで食べることが望ましく、特に高齢者や歯のトラブルがある人の場合、食べ物が大きく飲み込まれると腸に負担をかけるので要注意です。
噛む回数を意識するだけでも腸への負担軽減に貢献します。
適度な運動とストレッチ
体を動かす習慣があると、腸の蠕動運動も活発になりやすく、ウォーキングや軽い筋トレ、ヨガなどは腸内環境の改善に寄与すると考えられます。
長時間座りっぱなしで同じ姿勢を取り続けると腸の動きが停滞しやすいため、適度にストレッチを取り入れると良いでしょう。
定期的な検査の必要性
腸閉塞お腹の症状がなくても、ポリープや軽度の癒着が進行している可能性があり、大腸カメラ検査や胃カメラ検査を定期的に受けることで、重度の状態に至る前に発見と対処ができるチャンスが生まれます。
特に家族に大腸がんの既往歴がある方は、早期の受診を心掛けましょう。
健康的な生活習慣のヒント
- 野菜や海藻など食物繊維を含む食材をバランスよく摂取する
- 食事のときは焦らず、時間をかけてよく噛む
- 1日30分以上のウォーキングなどを習慣に取り入れる
- 便秘が続くときは早めに医師に相談する
- 腹部や腰回りのストレッチを意識して行う
主な生活習慣と腸への影響
| 習慣 | 腸への影響 |
|---|---|
| 食物繊維の摂取 | 便のかさ増しを助け、通過をスムーズにする |
| こまめな水分補給 | 消化物をやわらかくし、排出をスムーズにする |
| 適度な運動 | 血行改善と腸の蠕動を促進 |
| 良質な睡眠 | 自律神経の安定に寄与し、腸の働きを整えやすくする |
| 定期検診 | 初期の異常を早期発見でき、早期対策に役立つ |
よくある質問
腸閉塞に関する疑問は多岐にわたります。少しでも不安や疑問点を解消し、必要に応じて受診や検査を検討するきっかけになれば幸いです。個々の状況によって最適解は異なるため、最終的には医療機関の診察を受けてください。
- 便秘との違いは何ですか
-
単なる便秘では腹痛があっても完全な閉塞状態はあまり起こりません。腸閉塞の場合は激しい腹痛や嘔吐、ガスも出なくなる状態が一気に進行することが特徴です。
便秘が長引き、急激に痛みが増すなどの変化があれば早めに医師の診察を受けることをおすすめします。
- 自分で判断して下剤を使っても大丈夫ですか
-
腸閉塞の疑いがあるときに下剤や強い整腸剤を使うと、腸管を圧迫するリスクが大きくなります。腸が詰まっている状態で無理に動きを促すのは危険とされ、悪化につながる恐れがあるため、自己判断は避けましょう。
- 大腸カメラの準備食で腸閉塞を起こす可能性はありますか
-
大腸カメラの準備食はできるだけ腸の負担を減らすよう考慮されています。
体質や既往症によっては準備食や下剤で体調を崩すリスクがありますが、医師から指示された内容を守れば、一般的には腸閉塞を起こすリスクは大きくないと考えられます。
ただし、進行がんによる強い狭窄がある場合は閉塞する危険がありますので、事前に医師に相談しましょう。
- 症状があるのに検査を先延ばしするとどうなりますか
-
腸閉塞は急激に進行するケースもあり、放置すると腸管壊死や腹膜炎など重篤な合併症を起こす恐れがあります。
症状を我慢しているうちに手術が必要な段階まで進行する可能性もあるため、できるだけ早めに専門家の診察を受けることを意識してください。
次に読むことをお勧めする記事
【腸閉塞の原因と治療法|早期発見と対処の重要性】
腸閉塞の症状について理解を深めたら、次は実際の治療法や対処について知っておくと安心です。早期発見から治療選択まで、具体的な情報を提供しています。
【腸の内視鏡検査で分かること – 検査前の準備から検査後の注意点】
症状の背景をつかんだ皆さんには、検査そのものの目的と準備・当日の流れも併せて把握しておくと、全体像がより明確になります。
参考文献
Rami Reddy SR, Cappell MS. A systematic review of the clinical presentation, diagnosis, and treatment of small bowel obstruction. Current gastroenterology reports. 2017 Jun;19:1-4.
Mullan CP, Siewert B, Eisenberg RL. Small bowel obstruction. American Journal of Roentgenology. 2012 Feb;198(2):W105-17.
Al Salamah SM, Fahim F, Hameed AM, Abdulkarim AA, Al Mogbal ES, Al Shaer A. How predictive are the signs and symptoms of small bowel obstruction. Oman medical journal. 2012 Jul;27(4):281.
Gore RM, Silvers RI, Thakrar KH, Wenzke DR, Mehta UK, Newmark GM, Berlin JW. Bowel obstruction. Radiologic Clinics. 2015 Nov 1;53(6):1225-40.
Corral JG, Rojo CN, de la Fuente Olmos R. Bowel obstruction: signs indicating the need for urgent surgery. Radiología (English Edition). 2023 Mar 1;65:S92-8.
Pickleman JA, Lee RM. The management of patients with suspected early postoperative small bowel obstruction. Annals of surgery. 1989 Aug;210(2):216.
Tamburrini S, Serra N, Lugarà M, Mercogliano G, Liguori C, Toro G, Somma F, Mandato Y, Guerra MV, Sarti G, Carbone R. Ultrasound signs in the diagnosis and staging of small bowel obstruction. Diagnostics. 2020 May 3;10(5):277.
Taylor MR, Lalani N. Adult small bowel obstruction. Academic Emergency Medicine. 2013 Jun;20(6):527-44.
Pujahari AK. Decision making in bowel obstruction: a review. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR. 2016 Nov 1;10(11):PE07.
Silva AC, Pimenta M, Guimaraes LS. Small bowel obstruction: what to look for. Radiographics. 2009 Mar;29(2):423-39.