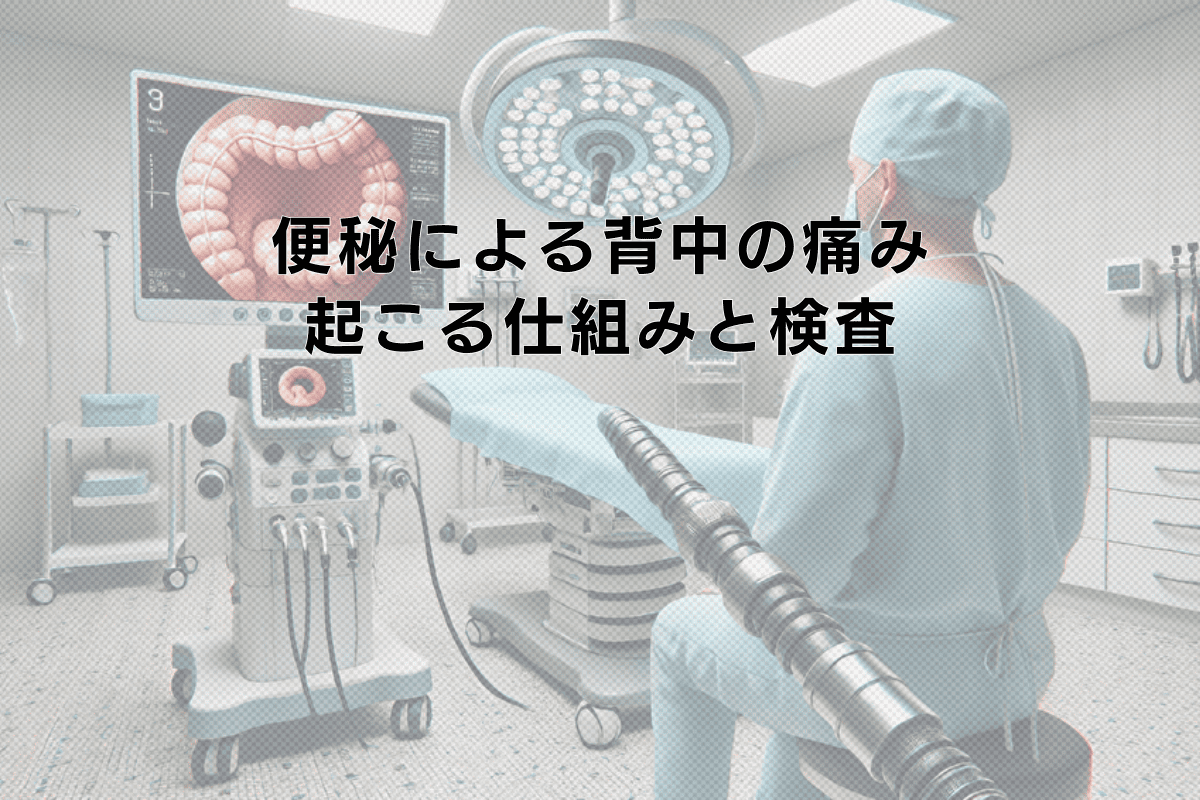便秘によって背中が痛くなると聞くと、あまり関係がないように思われるかもしれませんが、実際には腸内にたまった便やガスが内臓や神経を圧迫し、痛みを起こすことがあります。
ひどくなると食欲不振や倦怠感なども伴い、日常生活への支障が大きくなる場合も少なくありません。
もし長期的な便秘が続いているのに加え、背中の痛みや腹部の違和感が同時にあるなら、早めに医療機関を受診し、正確な診断と適切な検査を受けることが大切です。
本記事では、便秘によって背中が痛くなるメカニズムから、大腸カメラや胃カメラ検査の必要性まで詳しく解説します。
便秘と背中の痛みの関連
便秘を抱えている方が、背中や腰のあたりに張りや痛みを感じるという声は意外と多いですが、その背景にはいくつもの要因が複雑に絡み合っています。
腸と背中周辺の神経のつながり
消化器官と背中は直接的な距離があるように見えますが、実は腹部・背部を取り巻く神経や血管、筋肉は互いに連動している部分があります。
たとえば、腸の異常刺激が周辺の神経に伝わり、それが背中の筋肉に影響を与えて痛みとして感じるケースがあり、特に腰の上部から背中中央にかけて違和感が生じるときは、腸内の圧迫やガス溜まりを疑います。
便秘による姿勢の悪化
便が長期間とどまると腹部が張り、下腹部や骨盤まわりの筋肉に負担がかかり、それに伴って姿勢が崩れやすくなり、背中や腰の筋肉へ余計な負担がかかることが少なくありません。
普段の姿勢維持には腹筋や背筋など多くの筋肉が協力し合っていますが、便秘がきっかけとなり、お腹をかばうような姿勢が続くと背中の筋肉がこわばり、痛みを誘発することがあります。
ガス膨張による内圧の増加
便秘になると便だけでなくガスも排出されにくくなり、腸内にガスがたまると内圧が上昇して周囲の組織を圧迫し、特に下行結腸付近にガスがたまると背骨や背中側の神経が影響を受け、ピリピリとした痛みや鈍い圧迫感が出やすくなります。
ガスの膨張は食生活や腸内環境の乱れでも加速するため、注意が必要です。
背中の痛みが長引くリスク
便秘が原因の背中痛は、姿勢やストレッチなどで一時的に和らげることができる場合もありますが、根本の便秘が改善しない限り症状が繰り返されやすいです。
また、痛みが慢性化してしまうと、筋肉がこわばる悪循環から抜け出しにくくなり、日常的な動作に支障が出てくることが考えられます。
便秘による背中の痛みの仕組み
便秘と背中の痛みを結びつける仕組みには、腸管内圧の上昇や神経反射、腹腔圧の変化など多角的な生理学的要素が含まれます。
腹腔内圧の上昇と神経圧迫
便秘時に腸内の便やガスがたまると腹腔内圧が増し、これが背中方面の神経や血管に影響を及ぼし、腸の走行は背骨に沿う形で存在する区間も多く、腸管が拡張することで周辺の交感神経や副交感神経が刺激されやすくなります。
こうした神経刺激が、背中に痛みとしてあらわれるひとつの要因です。
背中の痛みと腸内圧の関連イメージ
| 体内要素 | 起きている変化 | 痛みとして感じる理由 |
|---|---|---|
| 腸管の拡張 | ガスや便による膨張 | 周囲の神経を物理的に刺激する |
| 血管やリンパ管の圧迫 | 腸管の拡張が血管やリンパの流れを妨げる | むくみや循環不良が筋肉に負荷を与える |
| 神経の過敏化 | 長時間の圧迫や炎症による神経刺激 | 痛覚が増幅しやすい状態になる |
内臓‐体性反射による痛みの飛び火
内臓と体表の特定の部位は、同じ神経レベルで情報をやり取りしていることがあり、これを内臓‐体性反射と呼び、腸の痛みや炎症が背中や肩、腰などの体表に関連痛を起こす仕組みです。
便秘によって腸内に負担がかかると、この反射機構を通じて本来は腸が発している痛み信号が背中へ伝わることが想定されます。
腸内ガスの停滞と便塊形成
便秘になると、糞便が腸管内に留まっている時間が長くなるため、水分が過度に吸収されて固い便塊が形成されやすくなり、さらにガスも排出されにくくなるため、大腸の各部位に偏ったガス溜まりが発生しやすくなります。
大腸がS状結腸や下行結腸付近で曲がっている部分にガスが溜まると、背骨方向へ圧力がかかり、背中痛を感じやすい状態です。
腸内で起きる変化
- 水分が過剰に吸収されて便が固くなる
- ガスが偏って溜まりやすくなる
- 腸壁が伸展し、神経への刺激が強まる
- 背側の組織や神経を間接的に圧迫
これらが複合的に絡み合い、背中に痛みをもたらすメカニズムを成立させています。
筋肉や筋膜の緊張との相互作用
便秘が続くと、下腹部の重さや張り感から姿勢が崩れ、腹筋や骨盤周辺の筋肉がかたくなり、その影響が連動して背中の筋肉まで緊張状態に陥り、痛みを生じやすくなるのです。
特に、長時間のデスクワークや運動不足などで元々背中や肩周りの筋肉がこりやすい方は、便秘による内臓の負担がさらに悪循環を招きやすいと考えられます。
便秘と他の症状
便秘が引き起こす症状は背中痛だけではなく、全身状態にも多様な影響を及ぼし、腸内環境が乱れると、肌トラブルや頭痛などの一見関係なさそうな不調も起きやすくなり、全体的な生活の質が下がることが見受けられます。
腹部の張りや吐き気
腸内に便やガスが溜まると腹部が膨らむだけでなく、食欲低下や吐き気があらわれることもあります。
食後にすぐお腹が苦しくなる、少量の食事でも満腹感が続く、といった不快感が持続すると、栄養摂取が不足しがちになり、疲れや免疫力低下の原因になります。
胃腸症状と影響
| 症状 | 予想される原因 | 生活への影響 |
|---|---|---|
| 腹部の張り | 腸内ガスや便が溜まり腸管を圧迫 | 衣服がきつい、動きづらい |
| 吐き気・嘔気 | 消化機能の低下と腸内圧の上昇 | 食事摂取量の減少、栄養不足リスク |
| 食後の膨満感 | 食べた物がスムーズに下行しない | 仕事や活動への集中力が落ちる |
| げっぷの増加 | ガスが上部消化管に逆流 | 胃酸の逆流など2次的な症状も出やすい |
頭痛や倦怠感
便秘が長引くと、老廃物やガスが腸内に停滞し、腸管粘膜から体内に吸収される毒素が増える可能性が指摘されています。
この毒素が代謝や神経伝達物質に影響し、頭痛やだるさ、集中力の低下などをもたらす場合があります。特に、起床時からどんよりと重い感覚がある方は要注意です。
肌荒れや吹き出物
腸内環境が悪化すると、有害物質の排出がスムーズにいかず、皮膚や呼吸器など別の排出経路に負担がかかることが考えられ、肌荒れやニキビ、吹き出物といった皮膚トラブルが起こりやすくなることもあります。
背中に限らず、顔や首周りの肌荒れが気になる方は、便秘を含む生活習慣の見直しが大切です。
他の症状との関連
- 過度な疲労感や睡眠の質の低下
- 口臭や便のにおいの強まり
- イライラや気分の落ち込み
- 肝臓や胆のうへの負担増
こうした不調をトータルで管理するには、一部の症状のみを対処するのではなく、腸内環境の改善を含めた全身的なアプローチが必要です。
内臓疾患が潜んでいる場合
便秘に加えて腹痛や背部痛が長期間続く場合、大腸ポリープや大腸がんといった重い疾患の可能性を無視できません。
また、逆流性食道炎や胆石症、慢性膵炎など消化器領域の病気が便秘に影響し、背部痛を発生させているケースもあるため、自己判断で様子見を続けるのは危険なので、定期的な内視鏡検査や検診を視野に入れることが重要です。
便秘で考えられるリスク
単なる便秘と捉えて軽視していると、後に重大な疾患が見つかったり、健康を大きく損なったりするリスクがあります。特に高齢の方や生活習慣病のある方は、便秘が慢性化しやすく、合併症が起こる可能性が高まるため注意が必要です。
大腸ポリープや大腸がんへの進展
便秘が続くと、大腸内に便やガスがとどまり、腸内細菌のバランスが崩れやすくなり、大腸粘膜を刺激し、慢性的な炎症状態を引き起こす原因のひとつになり得ます。
慢性炎症は大腸ポリープや大腸がんのリスクを高める要因のひとつであるため、長期にわたって便秘を放置することはよくありません。
便秘と大腸疾患の関連
| 疾患名 | 便秘との関係性 | リスクを高める要因 |
|---|---|---|
| 大腸ポリープ | 腸内環境の悪化や粘膜の慢性刺激 | 食生活の乱れ、遺伝、加齢など |
| 大腸がん | 慢性炎症と腸内環境の著しい乱れ | 長期的な便秘、過剰な脂肪・たんぱく摂取 |
| 潰瘍性大腸炎 | 腸内バリア機能の低下で炎症が長引く | 自己免疫異常、腸内フローラ異常 |
腹圧上昇による内臓下垂やヘルニア
便秘によって強くいきむ習慣が続くと、慢性的に腹圧が高まり、この状態が長引くと、骨盤底筋や腹筋が弱り、内臓の位置が下がる「内臓下垂」が起こる可能性があります。
さらに腹圧上昇は、鼠径ヘルニアなどを誘発しやすくする要因にもなるため、高齢者や出産経験の多い女性は注意が必要です。
痔や肛門周辺の疾患
便が硬くなることで排便時に肛門に強い負担がかかり、切れ痔やいぼ痔などの肛門トラブルを起こすリスクが高まります。長期にわたってこうした症状が続くと、排便自体が苦痛になり、便秘がさらに悪化する悪循環に陥りやすいです。
血圧や心臓への影響
便秘のときに強くいきむ行為は、一時的に血圧を上昇させ、心臓や脳血管に負担をかけることがあり、高血圧や心臓病を抱えている方は、これがトリガーとなり、心筋梗塞や脳卒中などの発作リスクを高める可能性も否定できません。
便秘が重い方ほど、排便動作の負担を軽減できるよう適切な対処が必要です。
便秘が起こすリスク
- 大腸ポリープ・大腸がんなど消化器疾患
- 内臓下垂やヘルニア
- 切れ痔やいぼ痔などの肛門疾患
- 血圧急上昇による心血管系への負担
リスクを見過ごすと、体全体の健康を損ねる可能性が高いため、便秘が長期化している場合は早急に原因を突き止めることが大切です。
便秘の診断と検査
便秘と背中の痛みが重なる場合、自己流の対処法だけでは改善が難しいケースがあります。
単に食物繊維を増やしたり下剤を使ったりしても根本的な原因がわからないままでは症状をくり返す可能性があるため、医療機関で適切な診断と検査を受けることが大事です。
問診と視診
医師の診察では、まず問診によって症状の出始めや痛みの部位、便の状態や排便回数、食生活やストレス状況などが細かく聞かれ、視診や腹部の触診も行われ、腸の働きを推測したり、腹部にしこりや腫瘤がないかどうかを確認したりします。
背中の痛みと便秘の関係を推測する上では、触診の際に腸内のガスや便の溜まり具合が判断材料になることもあります。
問診で見られる主な項目
| 問診項目 | 関連する情報 | 診断へのヒント |
|---|---|---|
| 排便回数と便性状 | 週に何回か、便の硬さや色など | 便秘の程度や腸内環境のヒント |
| 背中の痛みの程度 | 疼痛の強さ、持続時間、誘因など | 便秘以外の要因も考える必要があるか |
| 食生活と水分摂取 | 食物繊維の量、アルコール摂取など | 生活習慣由来の便秘かどうかを推測 |
| 既往症や家族歴 | 過去の消化器疾患や家族の病歴 | 大腸がんリスクや慢性疾患の有無を推測 |
血液検査と尿検査
血液検査では、貧血や炎症反応、肝機能・腎機能、血糖値などがチェックされ、貧血は消化管出血や栄養吸収不良のサインである場合があり、便秘と合わせて大腸内の異常を疑う材料になることがあります。
尿検査は、糖尿病や腎機能の評価を行う上で有用です。これらの検査結果を総合して、内視鏡検査が必要かどうかが判断される場合もあります。
超音波検査やCT
腹部の画像検査として超音波やCTスキャンが行われることがあり、ガスや便の溜まり具合、腸壁の異常、腫瘍やポリープの可能性などが見られるため、背中痛の原因が腸管以外の腎臓や胆嚢などにないかを含めて検討できます。
特にCTでは、大腸がんや他の臓器疾患がないかをある程度推測しやすいことが利点です。
画像検査の特徴
| 検査方法 | 特徴 | 検出しやすい病変 |
|---|---|---|
| 腹部超音波 | 非侵襲的でリアルタイムに観察できる | 大きな腫瘤、胆石、水腎症など |
| 腹部CT | 詳細な断面画像が得られ、診断精度が高い | 腸管の異常、肝臓・腎臓の病変、腫瘍など |
| MRI | 腫瘍や血管病変、組織の状態を精密評価 | 特に詳細な組織画像が必要な場合 |
画像検査で異常が見つかった場合は、さらに詳しい検査として大腸カメラを行うことがあります。
大腸カメラ・胃カメラ検査
便秘が長期化して背中の痛みが強い場合、腸内にポリープや腫瘍、炎症などが潜んでいる可能性を見逃せません。大腸カメラ(大腸内視鏡)では、大腸内を直接観察し、必要に応じて組織の一部を採取する生検が行えます。
胃カメラ(上部消化管内視鏡)は、主に胃や十二指腸の状態を確認し、胃潰瘍や胃がんなど便秘や背部痛に間接的に影響を与える病変がないかをチェックする手段です。
胃カメラ・大腸カメラ検査が重要な理由
便秘と背中の痛みを自覚している方は、単なる便秘の症状と思い込んでしまうことが多いですが、根本に重大な消化器疾患が潜んでいるリスクも考慮することが必要です。
胃カメラや大腸カメラ検査を適切に受けることで、早期発見や早期治療につなげられる可能性があります。
大腸カメラでわかること
大腸の内部を直接カメラで観察し、ポリープや炎症、腫瘍の有無を確認でき、大腸ポリープは良性の場合でも、大きくなったり悪性化したりするリスクがあるため、見つかった段階で内視鏡的に切除できれば大きな負担を減らすことが可能です。
便秘による背中痛が続いている場合、腫瘍などの病気を除外するためにも大腸カメラの実施が欠かせません。
大腸カメラで発見できる主な病変
| 病変名 | 特徴 | 対応策 |
|---|---|---|
| 大腸ポリープ | 良性腫瘍だが一部悪性化のリスクあり | 大きさや形状に応じて内視鏡切除を検討 |
| 大腸がん | 進行度により治療法が変わる | 早期発見で内視鏡手術や外科手術が可能 |
| 潰瘍性大腸炎 | 粘膜に炎症や潰瘍が生じる自己免疫性疾患 | 内科的治療が中心、重症例は手術検討 |
| 痔核や肛門近辺 | 痔核や直腸脱など排便障害を起こすことがある | 保存的治療~手術まで状態により判断 |
胃カメラでわかること
胃や十二指腸に異常がある場合も、反射的に背中に痛みを感じるケースがゼロではなく、胃カメラでは胃潰瘍や胃炎、胃がんなどを確認し、必要があれば生検を行います。
便秘と直接の関連は薄いように見えても、上部消化管の異常が便通に影響を及ぼす可能性も考えられるため、総合的なチェックとして意味があります。
検査のタイミング
背中の痛みが続き、他の検査や投薬で改善が見られない場合や、40代以降で便秘が急に悪化した、あるいは家族に大腸がんの既往がある方は、大腸カメラや胃カメラの検査タイミングを早めに検討するとよいでしょう。
専門医との相談を通じて、検査が必要かどうかを判断してもらうことが効果的です。
胃カメラ・大腸カメラ検査が推奨される状況
- 便秘が1か月以上続いており、背中に痛みを感じる
- 便に血が混じったり体重減少が顕著にみられる
- 40歳以上で初めて便通異常が出始めた
- 家族に大腸がんや胃がんの既往歴がある
適切なタイミングで内視鏡検査を受けることで、深刻な疾患を早期に発見できる可能性があります。
背中の痛み改善のための対策
便秘による背中の痛みは、生活習慣やセルフケアを見直すことで軽減する場合があります。内視鏡検査の結果、重篤な病変が見つからなかった場合であっても、日常的に便秘が続いていると将来のリスクが高くなるため、早めの対策が望ましいです。
水分摂取と食物繊維の活用
便を柔らかくし、腸内での移動を促進するためには水分と食物繊維のバランスが重要です。
1日1.5リットル以上の水分をこまめに補給するとともに、野菜や果物、海藻類、全粒穀物などから食物繊維を適度に摂取すると便秘が緩和しやすい傾向があります。
ただし、食物繊維の摂り過ぎがかえってガスを溜める場合もあるため、自分に合った量を把握することが必要です。
食物繊維の種類と特徴
| 種類 | 主な食品例 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 水溶性食物繊維 | りんご、こんにゃく、海藻など | 便を柔らかくして排出を促しやすい |
| 不溶性食物繊維 | ごぼう、豆類、きのこ類など | 腸内でかさを増し、ぜん動運動を促進 |
両方のバランスを考えながら取り入れると、より効果的に便通の改善を図れます。

適度な運動と姿勢改善
運動不足は腸の動きを鈍らせる要因のひとつであり、結果的に便秘や背中痛を悪化させる可能性があります。
軽いウォーキングやヨガ、ストレッチなどで腹筋や背筋をほぐし、腸のマッサージ効果を高めると同時に、血行促進による疲労回復効果も得られます。
さらに、背筋を伸ばして座るだけでも腹腔内圧を整えやすくなり、便通が促されることがあるため、デスクワークの合間に姿勢チェックを習慣づけると便利です。
マッサージや入浴などのセルフケア
お腹や腰回りを軽くマッサージすると、腸の動きを促進したりガスを移動させたりするのに効果が期待できます。
入浴によって体を温めると血行が良くなるほか、リラックス効果で副交感神経が優位になり、腸のぜん動運動が活発化しやすくなることもあり、セルフケアを続けることで、慢性的な背中の痛みや便秘の緩和につながる場合があります。
背中痛や便秘に役立ちそうな施策
- 腹部を時計回りにやさしくさする
- 入浴後に腰回りを温める
- 長時間同じ姿勢を避け、適度に立ち上がる
- 腹式呼吸を意識して腸を刺激する
これらを意識すると腸と背中の負担が軽くなり、日常的な痛みを抑えやすくなるでしょう。
薬物療法や医師の指導
市販の下剤や整腸剤を自己判断で使う方も多いですが、合わない薬を長期間使うと腸の自然な動きが失われるリスクがあります。
専門医による検査で腸の状態を把握した上で適切な薬を選択すれば、背中痛の原因となる便秘を早期にコントロールしやすくなります。また、生活習慣のアドバイスや専門的なリハビリ指導なども受けられるため、医師との連携は重要です。
よくある質問
- 便秘が原因で背中が痛い場合、痛みの特徴はどのように現れますか?
-
多くの方は鈍い痛みや張り感、あるいは圧迫されるような感覚を背中や腰のあたりに覚えることが多いです。特にガスが溜まっているときには、鋭い痛みというよりも膨満感に伴う違和感が強調されます。
姿勢を変えたり、お腹を温めるなどで一時的にやわらぐ場合もありますが、便秘そのものを改善しない限りくり返します。
- 背中の痛みを和らげる対策として、どのような体操やストレッチが有効でしょうか?
-
背骨や腰周りを適度に動かす体操が有効で、やさしく骨盤を前後に動かす運動や、四つ這いになって背中を丸めたり反らしたりする動きが代表的です。
上体をひねって腰から背中にかけて伸ばすストレッチも効果が期待できます。ただし痛みが強いときには無理な動きは避け、緩やかな動きから始めることが大切です。
- 大腸カメラ検査は痛いイメージがあるのですが、実際どうなのでしょうか?
-
近年では検査時の苦痛を軽減する技術が進歩しており、鎮静剤を使った検査も一般的になっていて、多くの方が眠るような感覚で検査を受けられるようになりました。
医療機関によって施行方法が異なるため、検査前に説明を受けて疑問点を解消しましょう。
- 胃カメラと大腸カメラの両方を一度に受けるメリットは何でしょうか?
-
消化管全体を一度の受診で詳細にチェックできる点が大きなメリットで、胃や十二指腸、大腸の異常を総合的に判断できるため、原因不明の腹部痛や背部痛がある場合、早期に包括的な診断が行いやすいです。
時間や通院回数もまとめて済ませられるため、忙しい方にも向いています。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸検査が気になる方へ 内視鏡検査の注意点】
便秘と背中痛の仕組みを理解したら、実際の大腸カメラ当日の流れや準備、鎮静の有無まで把握しておくと安心です。初検査を控える方に特に参考になります。
【腹痛原因を知って早めの対応 消化器の病気を見逃さない】
背中痛と便秘を学んだ皆さんには、痛む部位別の腹痛と関連疾患も合わせて知ると包括的な理解が進みます。受診の目安が整理できます。
参考文献
Rao SS, Rattanakovit K, Patcharatrakul T. Diagnosis and management of chronic constipation in adults. Nature Reviews gastroenterology & hepatology. 2016 May;13(5):295-305.
Jamshed N, Lee ZE, Olden KW. Diagnostic approach to chronic constipation in adults. American family physician. 2011 Aug 1;84(3):299-306.
Trager RJ, Mok SR, Schlick KJ, Perez JA, Dusek JA. Association between radicular low back pain and constipation: a retrospective cohort study using a real-world national database. Pain reports. 2021 Sep 1;6(3):e954.
Camilleri M, Ford AC, Mawe GM, Dinning PG, Rao SS, Chey WD, Simrén M, Lembo A, Young-Fadok TM, Chang L. Chronic constipation. Nature reviews Disease primers. 2017 Dec 14;3(1):1-9.
Rao SS, Ozturk R, Laine L. Clinical utility of diagnostic tests for constipation in adults: a systematic review. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2005 Jul 1;100(7):1605-15.
Seltzer R. Evaluation and diagnosis of constipation. Gastroenterology Nursing. 2012 Sep 1;35(5):343-8.
Rey E, Balboa A, Mearin F. Chronic constipation, irritable bowel syndrome with constipation and constipation with pain/discomfort: similarities and differences. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2014 Jun 1;109(6):876-84.
Costilla VC, Foxx-Orenstein AE. Constipation in adults: diagnosis and management. Current treatment options in gastroenterology. 2014 Sep;12:310-21.
Wald A. Constipation: advances in diagnosis and treatment. Jama. 2016 Jan 12;315(2):185-91.
Slappendel R, Simpson K, Dubois D, Keininger DL. Validation of the PAC-SYM questionnaire for opioid-induced constipation in patients with chronic low back pain. European journal of pain. 2006 Apr 1;10(3):209-17.