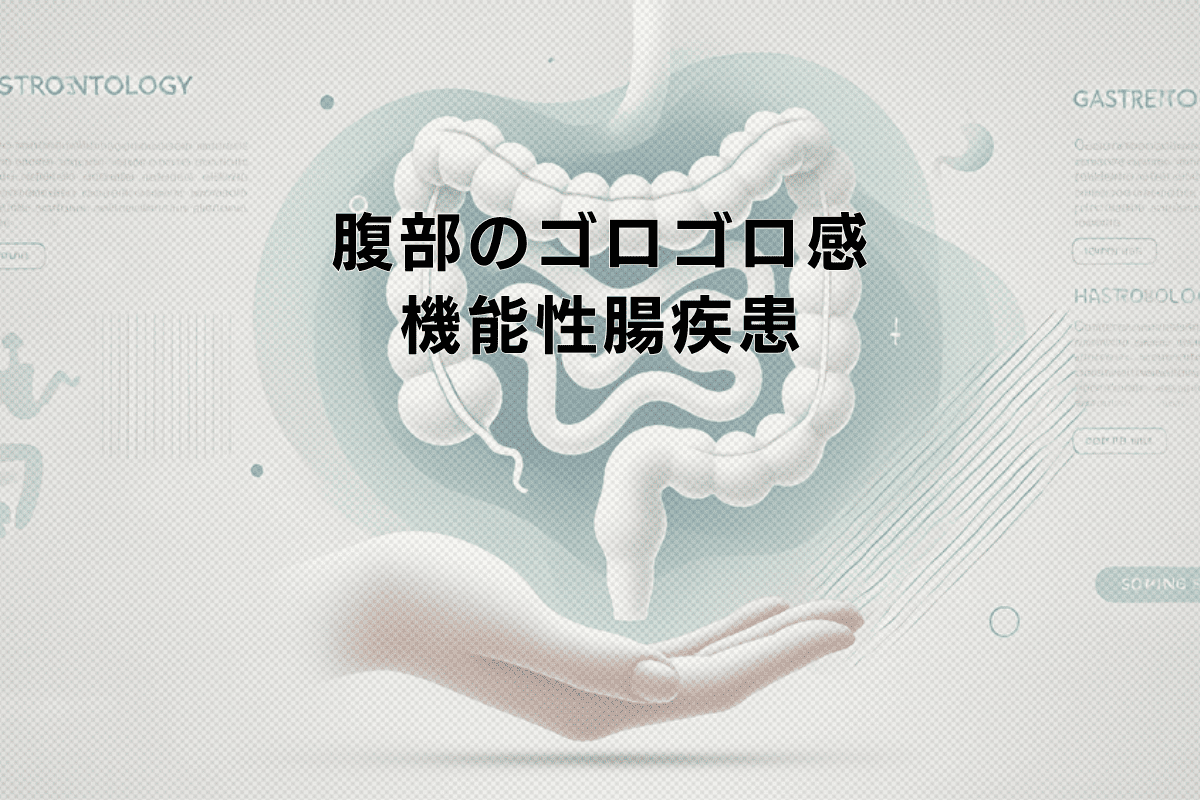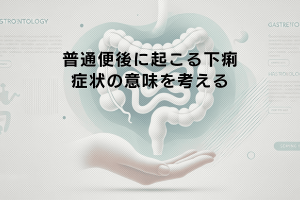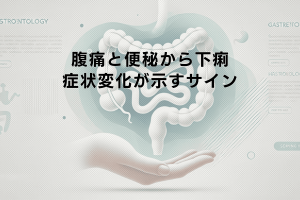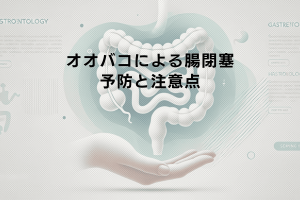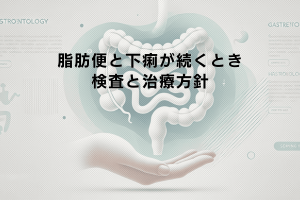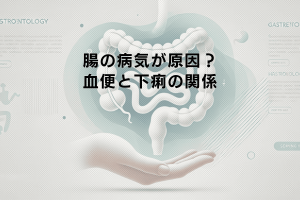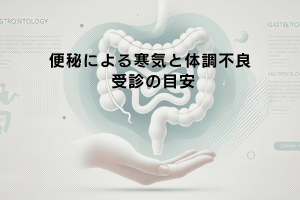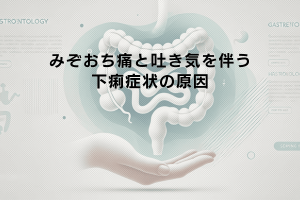腹部のゴロゴロ感とは、腸内にガスが多く発生していたり、消化管の動きが過度に敏感になったりすることで、お腹の中から音が聞こえたり違和感が生じたりする状態です。
これに下痢が加わると、日常生活に支障をきたすほどの不快感を感じる方も珍しくありません。
しかし原因はさまざまで、単なる食べ過ぎやストレスによる一時的な症状なのか、あるいは機能性腸疾患などの背景が潜んでいるのかを判断するには、適切な検査と専門医の見解が必要です。
この記事では、腹部のゴロゴロ感と下痢が続く場合に考えられるメカニズムや注意すべきポイント、検査方法などを詳しく解説し、より安心して対策を取っていただくための情報を提供します。
腹部のゴロゴロ感と下痢が起こる仕組み
腹部のゴロゴロ感や下痢などの消化器症状が続くと、仕事やプライベートなどに影響を及ぼす可能性があります。特に朝の通勤途中や外出時に突然の下痢に悩まされると、行動範囲が制限されることもあるため、不安を抱える方も少なくありません。
腸の活動と音との関連
ゴロゴロ音は、腸が動くときに発生する腸雑音の一種で、食事後に盛んに腸がぜん動運動を行う際や、空腹時にも腸管内に残る少量の液体やガスが動くことで音が生じます。
通常は健康な人にも聞かれますが、以下のような原因によって音が大きく聞こえたり、伴う症状が増えたりすると問題視されます。
- 腸内ガスの過剰増加(発酵しやすい食品の摂取や炭酸飲料など)
- ストレスによる自律神経の乱れで腸が過敏になる
- 食事の不規則などで空腹時間が長くなりやすい
要因が重なると、腸内環境が乱れてゴロゴロ音が目立つだけでなく、下痢や便秘などの便通異常も起こりやすいです。
下痢が起こるメカニズム
下痢は、腸管が異常に早く動いて内容物が十分に水分吸収されないまま肛門まで届くタイプや、炎症や感染などで腸粘膜の吸収機能が低下するタイプなど、いくつかのパターンに分けられます。
急性の下痢は、ウイルスや細菌が原因となる食あたりや感染症が多いですが、慢性的に続く下痢は機能性腸疾患やストレス、大腸の疾患などが背景にあるかもしれません。
ストレスと腸内環境の密接な関係
精神的なストレスがかかると、自律神経が乱れて腸管の正常なぜん動運動が過度に亢進したり、反対に低下したりして、急激な便意や腹痛を伴う下痢、あるいは便秘に見舞われやすくなります。
特にストレスが強い環境に長期間いると、腸内フローラのバランスが崩れやすくなるため、慢性的にお腹の調子を崩す方もいます。
腸内環境とストレス
| 主な要素 | 具体的な影響 | 見られる症状 |
|---|---|---|
| 自律神経の乱れ | 交感神経優位で腸の運動が過度に活発化 | 急な腹痛・下痢、ガス過多によるゴロゴロ感 |
| ストレスホルモン | コルチゾールなどが分泌増加 | 腸内細菌バランスの乱れ、便通の不安定 |
| 食事リズムの乱れ | ストレスによる暴食や過度の制限 | 消化不良・体重の変動・栄養不足 |
| 睡眠不足 | 免疫力の低下と腸粘膜の修復不全 | 慢性下痢または便秘、疲労感が増しやすい |

腸と他の臓器の連動
消化管は単独で働いているわけではなく、胃や膵臓、肝臓などさまざまな臓器と密接に連動していて、胃の消化液や胆汁、膵液の分泌状態が変化すると、小腸・大腸の消化・吸収過程に影響を与えます。
腸内での栄養素の分解やガス発生の度合いが変われば、ゴロゴロ感や下痢の誘発に繋がる要素が増えることがあります。
機能性腸疾患の特徴
腹部のゴロゴロ感や下痢が続く背景には、器質的な疾患(潰瘍やポリープなど)がなくても、腸の働きが過剰に敏感になっている機能性腸疾患が隠れているケースがあります。
これは腸管そのものに炎症や腫瘍などは見られないにもかかわらず、慢性的な症状を起こす疾患です。
代表的な機能性腸疾患
機能性腸疾患でよく知られているのが、過敏性腸症候群と呼ばれる病気で、大きく下痢型、便秘型、混合型などに分類され、なかでもお腹がゴロゴロ鳴りやすく、突発的な下痢が多いのが下痢型です。
機能性腸疾患の特徴
- 特定の検査で腸の異常所見が見つからない
- 下痢や便秘、腹痛、ガス溜まりなどが繰り返される
- ストレスや生活習慣の乱れと症状が連動しやすい
過敏性腸症候群の主な分類
| タイプ | 便通傾向 | 代表的な症状 |
|---|---|---|
| 下痢型 | 水様便や軟便が頻繁 | 突発的な便意、腹部のゴロゴロ、腹痛 |
| 便秘型 | 排便回数が少なく固い便 | お腹の張り、腹痛、食欲低下 |
| 混合型 | 下痢と便秘が交互 | 症状予測が難しく、ストレスを受けやすい |
| 分類不能型 | 明確に分類不可 | 断続的な下痢・便秘、腹鳴や腹痛など |
ストレスと神経伝達物質のかかわり
腸は“第二の脳”と呼ばれるほど多くの神経伝達物質があり、気分や感情との関連性が高く、セロトニンは腸にも多く分布し、腸管運動に影響を与えています。
ストレスや精神的な緊張が長引くと、セロトニンなどの分泌バランスが崩れやすく、それが腸の過敏性を高めて腹部のゴロゴロ感や下痢を招くことがあります。
器質的疾患との鑑別が重要
機能性腸疾患は、腸自体に炎症や構造的な変化が見つかるわけではなく、検査をしても異常が見当たらないのが特徴ですが、大腸がんや潰瘍性大腸炎など重篤な病気を除外します。
症状が軽度だからといって、自己判断で放置すると、万が一の発見が遅れるリスクがあるため注意が必要です。
器質的疾患を示唆するサイン
- 血便やタール便が続く
- 急激な体重減少や食欲不振
- 夜間の強い腹痛や発熱を伴う
- 50歳以上で初発の下痢や便通異常
こうしたサインがあるときは、すみやかに医療機関を受診し、内視鏡検査などを検討することが大切です。
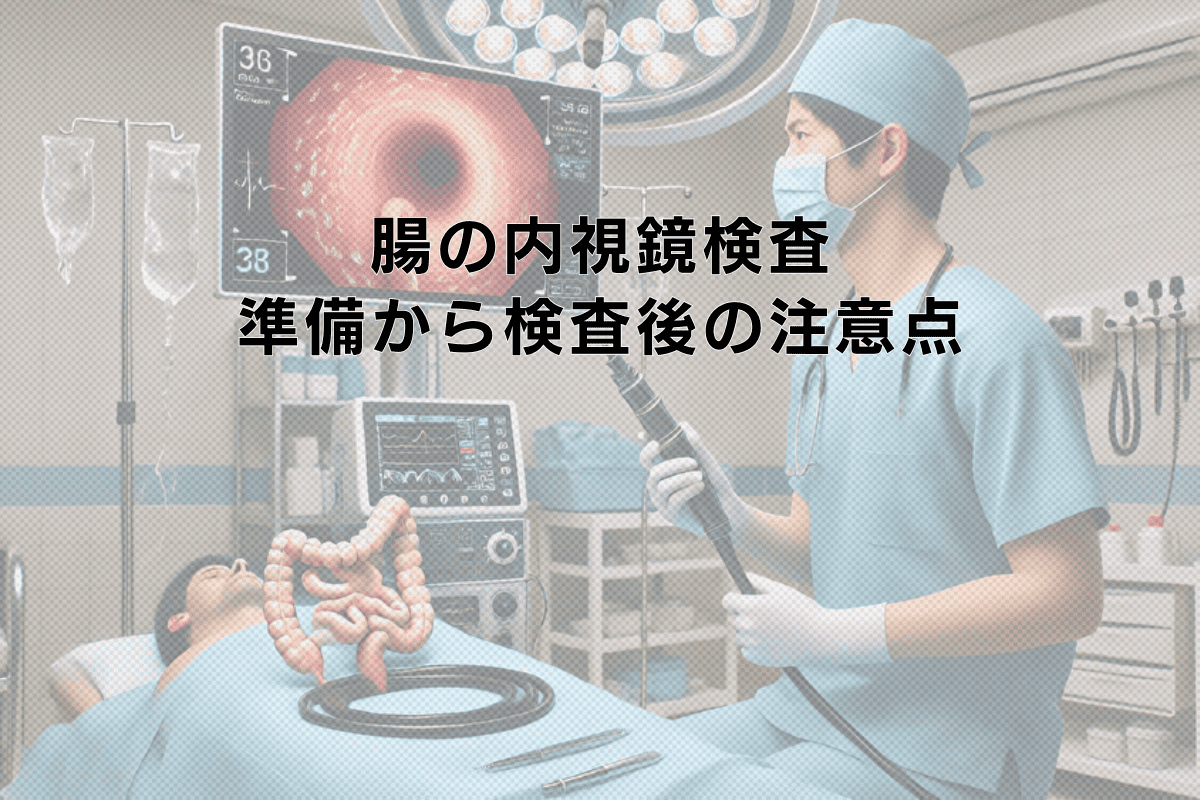
症状が続く場合に考えたいチェック項目
長期間、腹部のゴロゴロ感や下痢に悩まされる方は、機能性腸疾患を疑う一方で、下記のような要因を改めて振り返ってみると、何らかの共通点や解決策が見えてくることがあります。
| チェック項目 | 関連性 | 改善の手がかり |
|---|---|---|
| 食事内容・タイミング | 脂質や刺激物の多い食事、食事時間の不規則 | バランスの良い食事、アルコール控えめなど |
| 生活リズム・睡眠 | 深夜まで活動、睡眠不足、運動不足 | 睡眠リズムの調整、軽い運動習慣 |
| ストレスの程度 | 職場や家庭での精神的負担 | カウンセリングやストレス発散法 |
| 既往歴・家族歴 | 過去の胃腸疾患、家族に大腸がんの既往 | 定期的な内視鏡検査の必要性を検討 |
下痢が続くリスクと注意点
一時的な下痢であれば、単なる軽い胃腸炎や食べ過ぎによる消化不良などで自然回復が見込める場合もありますが、腹部のゴロゴロ感と下痢が長く続くときは、身体全体への悪影響を考慮しなければなりません。
脱水と電解質異常
下痢が続くと水分と電解質を大量に失うため、脱水状態に陥りやすくなり、体内のナトリウム、カリウム、マグネシウムなどが不足すると、倦怠感やめまい、筋力低下などが起き、重症になると意識障害に至ることもあります。
主な電解質と体内での働き
| 電解質 | 体内での主な役割 | 不足時に起こりやすい症状 |
|---|---|---|
| ナトリウム | 体液の浸透圧維持、神経興奮の伝達 | 食欲不振、低血圧、脱力感 |
| カリウム | 筋収縮や心臓のリズム調整 | 不整脈、筋力低下、疲労感 |
| マグネシウム | 筋肉・神経の働き、酵素活性の調整 | こむら返り、心疾患リスク増加、神経過敏 |
下痢が続くとこれらが失われやすいため、経口補水液などでの補給を意識したり、医療機関で点滴を行うなどの対応が必要になる場合があります。
栄養吸収不良
腸管での水分吸収だけでなく、栄養素の吸収も不十分になりがちで、特に脂溶性ビタミンやミネラルが吸収されにくくなると、皮膚や髪、爪、粘膜などにトラブルが現れることもあります。
慢性的な下痢によって栄養不足になると、体重減少や免疫力低下にも繋がるため、放置は危険です。
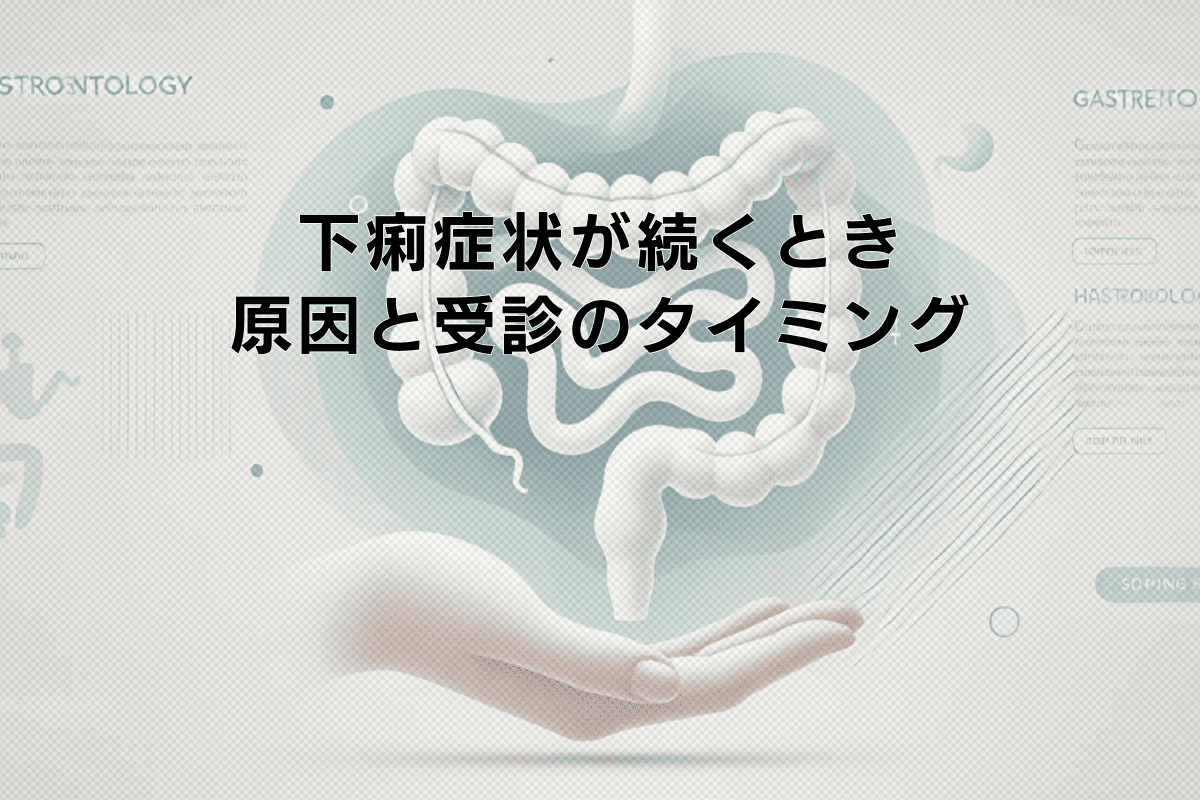
大腸ポリープやがんの見落とし
長期にわたる下痢の背景には、大腸ポリープや大腸がんが隠れていることもあり得ます。40代以降で急激に便通が乱れ始めた場合、あるいは下痢と便秘を繰り返す場合などは、内視鏡検査で腸内を直接確認することが望ましいです。
適切な時期に受診することで、早期発見・早期治療が可能になります。
精神的ストレスの増大
下痢があると外出が不安になり、心理的にもプレッシャーを抱え、仕事や通学、旅行などのシーンでトイレの場所を常に気にしなければならず、他人に理解されにくいストレスから、より一層精神的に追い込まれるケースも少なくありません。
身体面だけでなく心の健康のためにも、原因を突き止めて適切な対応を取ることが大切です。
長引く下痢で起こり得ること
- 脱水や電解質異常
- 栄養不良による免疫低下
- 重篤な大腸疾患の見落とし
- 精神的ストレス増大や対人関係の影響
検査の重要性:大腸カメラ・胃カメラのメリット
腹部のゴロゴロ感と下痢が同時に続く場合、消化器官全般をチェックすることが必要です。
機能性腸疾患を含め、腸内ポリープや炎症性疾患、大腸がんなどを排除するために、大腸カメラ(大腸内視鏡)や胃カメラ(上部消化管内視鏡)検査が検討されることがあります。
大腸カメラによる詳細な観察
大腸カメラは肛門から内視鏡を挿入し、大腸全体を観察する検査で、ポリープや腫瘍、粘膜の炎症や潰瘍などを直接確認でき、必要があれば検査中に組織採取(生検)やポリープ切除も行えます。
痛みが心配な方には、鎮静剤を使う検査も選択できるため、比較的楽に受けることが可能になってきています。
大腸カメラで確認できる主な病変
| 病変名 | 主な特徴 | 処置 |
|---|---|---|
| 大腸ポリープ | 良性~悪性まで幅広く、形状や大きさがさまざま | 内視鏡切除が可能 |
| 大腸がん | 粘膜から浸潤し、進行度によって治療法が異なる | 外科手術・内視鏡治療・化学療法など病期次第 |
| 炎症性腸疾患 | 潰瘍性大腸炎やクローン病など粘膜に炎症や潰瘍が見られる | 免疫調整薬や栄養療法など症状に応じて治療 |
| 憩室や憩室炎 | 大腸壁の一部が袋状に突出した憩室に炎症が生じる | 保存的治療(抗生物質)や外科的対応が必要になる場合 |
胃カメラによる上部消化管の診断
一方、胃カメラは口から内視鏡を挿入し、食道、胃、十二指腸までを観察し、胃や十二指腸潰瘍、ピロリ菌感染、逆流性食道炎などが疑われる場合に有効です。
下痢中心の症状でも、上部消化管の異常が腸まで影響していることもあるため、総合的に消化管をチェックできます。
同時検査の利点
場合によっては大腸カメラと胃カメラを同日の連続検査で受けられる施設もあり、これにより、下部消化管と上部消化管の両方を短期間で詳しく調べることが可能になり、来院回数を減らすメリットがあります。
ただし、麻酔や準備の手間が増えるなどの負担もあるため、自分の体調や医師の提案を考慮しながら決定しましょう。
検査前後の注意点
- 検査前日の食事制限や下剤服用などの指示に従う
- 検査後は麻酔や鎮静剤の影響で安静が必要な場合がある
- ポリープ切除などを行った際は食事や運動制限の可能性あり
- 定期的な検査スケジュールを立て、再発や新たな病変の確認
これらを守ることで、より正確で安心な検査となり、腹部症状の原因解明につながります。

日常生活での対処と予防
腹部のゴロゴロ感と下痢を改善するには、薬や医療機関での検査だけでなく、日常生活の習慣を見直すことが不可欠です。食事や運動、メンタルケアなど、複数の側面から体調管理を行うと効果が出やすくなります。
食事バランスの見直し
腸に負担をかけない食事を心がけることで、ゴロゴロ感や下痢を緩和できる場合があります。
食生活改善のポイント
- 脂質や刺激物を控え、腹八分目を意識する
- 水分を十分に摂るが、一気に飲みすぎない
- 溶性食物繊維(果物や海藻、大麦など)を取り入れ、腸内環境を整える
- 発酵食品(ヨーグルト、納豆、キムチなど)で腸内細菌を補う
食材とその特徴
| 食材 | 特徴 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| バナナ | 水溶性食物繊維、カリウムを含む | 腸内細菌叢のバランス補助、便通調整 |
| りんご | ペクチン豊富 | 腸内の善玉菌増加、便を軟らかくする |
| 大麦・オートミール | βグルカンなどの食物繊維を含む | 腸内環境改善、血糖値の急上昇を抑制 |
| 納豆・ヨーグルト | 発酵食品 | 善玉菌補給、腸の動きをサポート |
適度な運動とストレッチ
腸は身体の動きに連動して揺さぶられ、ぜん動運動が活性化されるため、適度な運動は便通やガス排出を促します。
ウォーキングや軽いジョギングなど有酸素運動を週に数回行うと、腸の動きが良くなるだけでなく、ストレス軽減にもつながります。加えて、腹式呼吸やヨガのポーズなどを行うと、腸周りの血流が向上し、下痢や腹痛のコントロールに役立ちます。
ストレスマネジメント
心因性の要因が強い機能性腸疾患の場合、ストレスをどう緩和するかが症状の改善に大きく影響します。カウンセリングやマインドフルネス、リラクゼーション法などを取り入れ、日常的に心をケアすると、腹部症状も落ち着く方が多いです。
睡眠の質や時間を十分に確保することもストレス軽減には欠かせません。
ストレスケア
- 規則正しい生活リズムを守る
- 深呼吸や瞑想を5~10分程度行う
- 軽い運動で血行促進とリフレッシュを図る
- 趣味や好きな音楽などで気分を転換する
精神的な安定が図られると、自律神経系のバランスが整い、腸の過度な収縮や分泌異常が和らぐ可能性があります。
適切な薬物療法
市販の整腸剤や医師から処方される下痢止め、腸管運動調整薬などを活用し、急性の症状を緩和する方法もあります。
しかし、長期にわたる薬剤使用は副作用や依存リスクもあるため、医師と相談しつつ、必要最低限の使用を心がけることが大切で、特に抗生物質の乱用は腸内細菌叢を乱す恐れがあるため注意してください。
症状が落ち着かないときの流れ
腹部のゴロゴロ感や下痢が一時的に良くなっても、また数日で再発するという方も多いかもしれません。
その場合、適切な手順を踏んで、段階的に原因究明と対策を進めることが重要で、自己判断で民間療法に走ると、発見が遅れるケースもあります。
生活習慣の見直し
まずは食事内容の改善や運動、ストレスケアなど、基本的な生活習慣を整えるだけでも症状が軽減することがあり、軽度の機能性腸疾患なら生活習慣だけでコントロールできるケースもあります。
ライフスタイルを再点検するチェック
| 項目 | 自己評価 | 改善の余地 |
|---|---|---|
| 朝食をしっかり摂っているか | いつも摂っている/時々/ほとんどなし | 運動量に対するカロリーや栄養のバランス |
| 水分摂取量 | 1日1.5リットル以上/~1リットル程度/それ以下 | 下痢でも水分補給は大切 |
| 便意を我慢していないか | ほとんど我慢しない/時々我慢/よく我慢する | 便意を逃すと便秘や下痢の不調が長引く |
| 夜更かしや睡眠不足 | 規則正しい/やや不規則/常に不足 | 腸の修復や免疫維持に影響 |
セルフチェックを行い、習慣を少しずつ変えていくと、腸への負担が軽くなって症状が緩和する場合があります。
症状が続く・再発する
生活習慣を改善しても症状が長引く、あるいは再発する場合は、機能性腸疾患や大腸の器質的疾患などの可能性を疑って、医療機関を受診しましょう。
腸の専門医や消化器内科を受診し、問診や血液検査、画像検査、内視鏡検査の必要性を判断してもらいます。
検査と診断
医師の判断で大腸カメラや胃カメラなど、消化管全般を調べる検査が提案されるかもしれません。
ここで異常が見つからなければ機能性腸疾患の可能性が高まり、薬物療法やメンタルケアなどが中心の治療となり、大腸ポリープや腫瘍など器質的異常が見つかった場合は、切除や手術などの治療計画が立てられます。
長期的なケア
検査や治療後も、再発予防や腸内環境の維持を目的に、生活習慣の管理が必要です。特に機能性腸疾患の場合は、症状の波があるため、定期的な通院やカウンセリング、薬の調整などで長期的に上手く付き合っていくことが望まれます。
症状安定後に継続すべきポイント
- 定期的な検診や内視鏡検査(必要に応じて)
- ストレスを溜めないライフワークバランス
- 腸にやさしい食習慣と水分補給の確保
- 睡眠リズムの維持と適度な運動
よくある質問
- 腹部がゴロゴロ鳴るだけなら放置しても大丈夫ですか?
-
短期間なら問題ない場合もありますが、下痢や腹痛などが加わって生活に支障をきたすようなら早めの受診が大切です。
特に数週間続く場合は機能性腸疾患の可能性や他の疾病を排除するためにも、専門医と相談してください。
- 下痢が続く場合、まず薬局で買える下痢止めを使ってもいいでしょうか?
-
一時的に下痢止めを使うのは悪いことではありませんが、原因を把握する前に長期的に使うと、腸の動きを無理に抑えて症状をこじらせるリスクがあります。
複数日にわたって下痢が収まらない場合は、医療機関で検査を受けることが大切です。
- 仕事が忙しくてなかなか検査に行けないのですが、大腸カメラはどのくらい時間がかかりますか?
-
検査そのものは10分~30分ほどで終了することが多いですが、前処置として腸を空にする下剤の服用などに数時間要する場合があり、クリニックによっては半日程度を要するため、予定を組んで行うことが必要です。
メリットとしては腸の内部を直接確認できるため、正確な診断が得られる確率が高いことが挙げられます。
- 胃カメラと大腸カメラを同日に受ける利点は何でしょうか?
-
上下の消化管を一度にチェックできるため、複数日の来院を避けたい方や消化器全般の病変を一気に確認したい方にとって便利です。
ただし、同日に受ける場合は準備や麻酔の影響などで体への負担が大きくなることもあるため、医師と相談しながら検討するとよいでしょう。
次に読むことをお勧めする記事
【緊張による下痢症状と過敏性腸症候群 – 内視鏡検査の必要性】
腹部のゴロゴロ感と下痢の基本を押さえたら、次は実際の検査や診断の流れについて知っておくと安心です。過敏性腸症候群の詳しい分類や治療選択肢について、専門医の視点から詳しく解説した内容です。
【腸にいい食べ物を知る 腸内環境を整える方法】
腹部症状について理解が深まった皆さんには、日常の腸内環境ケアの知識も合わせて持っていただくと、より包括的な健康管理ができます。予防と改善の両面から腸の健康を支える実践的な方法を学べます。
参考文献
Ono M, Kato M, Miyamoto S, Tsuda M, Mizushima T, Ono S, Nakagawa M, Mabe K, Nakagawa S, Muto S, Shimizu Y. Multicenter observational study on functional bowel disorders diagnosed using Rome III diagnostic criteria in Japan. Journal of Gastroenterology. 2018 Aug;53:916-23.
Oshima T, Miwa H. Epidemiology of functional gastrointestinal disorders in Japan and in the world. Journal of neurogastroenterology and motility. 2015 Jul 3;21(3):320.
Thompson WG, Longstreth GF, Drossman DA, Heaton KW, Irvine EJ, Müller-Lissner S. Functional bowel disorders and functional abdominal pain. Gut. 1999 Sep 1;45(suppl 2):II43-7.
Longstreth GF, Thompson WG, Chey WD, Houghton LA, Mearin F, Spiller RC. Functional bowel disorders. Gastroenterology. 2006 Apr 1;130(5):1480-91.
Bharucha AE, Chakraborty S, Sletten CD. Common functional gastroenterological disorders associated with abdominal pain. InMayo Clinic Proceedings 2016 Aug 1 (Vol. 91, No. 8, pp. 1118-1132). Elsevier.
Iovino P, Bucci C, Tremolaterra F, Santonicola A, Chiarioni G. Bloating and functional gastro-intestinal disorders: where are we and where are we going?. World Journal of Gastroenterology: WJG. 2014 Oct 21;20(39):14407.
Lacy BE, Crowell MD, DiBaise JK. Functional and motility disorders of the gastrointestinal tract. New York: Springer; 2015.
Tighe MP, Beattie RM. Functional Abdominal Pain and Other Functional Gastrointestinal Disorders. Textbook of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition: A Comprehensive Guide to Practice. 2016:215-31.
Kruse FH. Functional disorders of the colon: the spastic colon, the irritable colon, and mucous colitis. California and Western Medicine. 1933 Aug;39(2):97.
Wiklendt L, Mohd Rosli R, Kumar R, Paskaranandavadivel N, Bampton PA, Maslen L, Costa M, Brookes SJ, O’Grady G, Dinning PG. Inhibited postprandial retrograde cyclic motor pattern in the distal colon of patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology. 2023 Jul 1;325(1):G62-79.