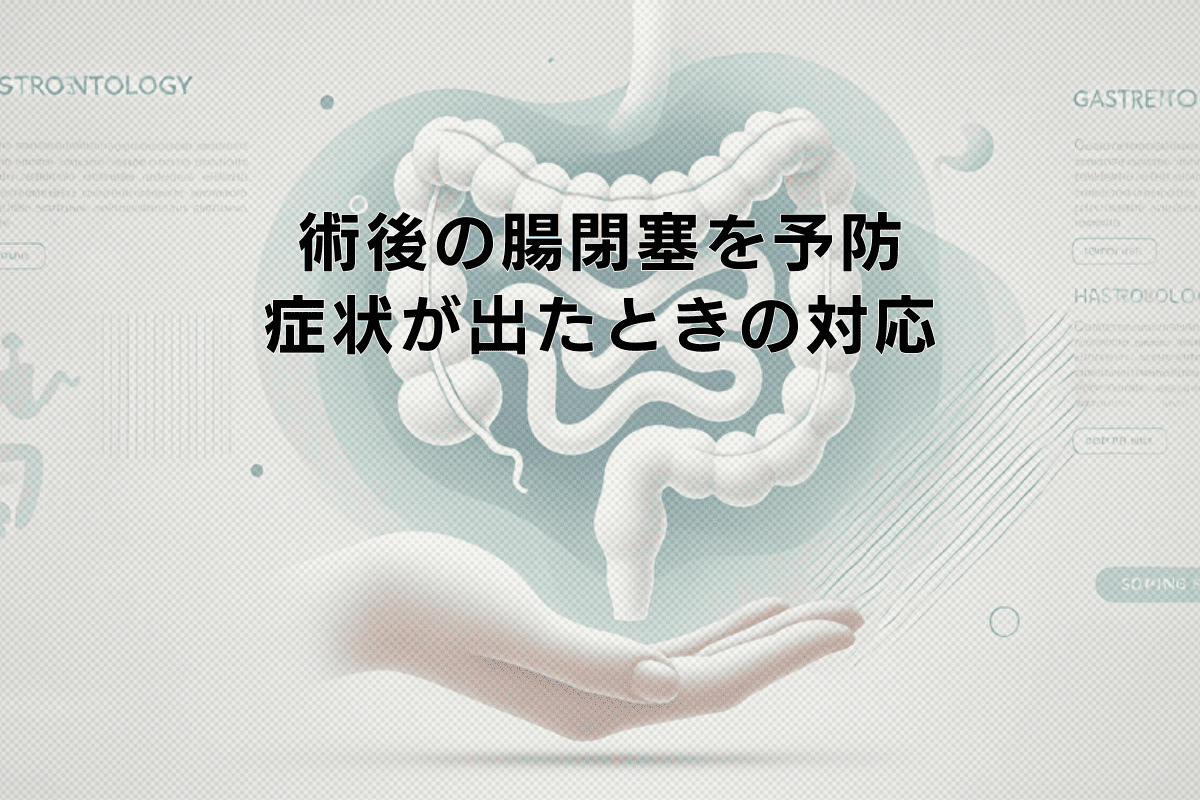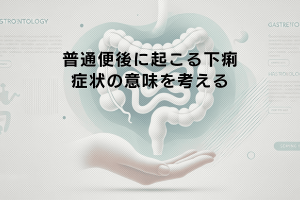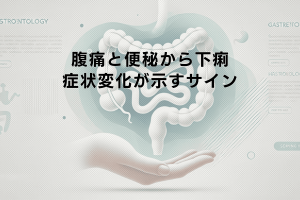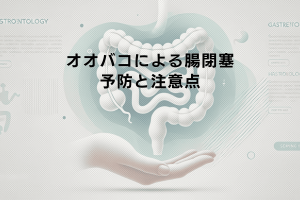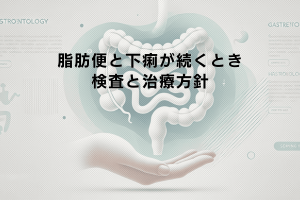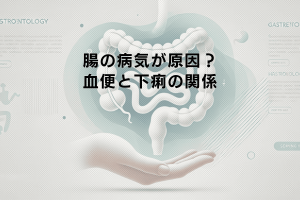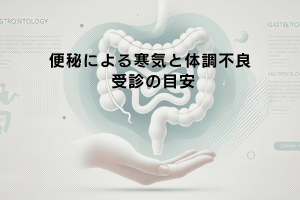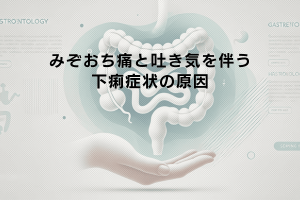お腹の手術を受けた後、腸閉塞という状態になることがあります。
これは、食べた物や消化液の流れが腸の中で滞ってしまう病気です。特に、手術の影響で腸が癒着を起こすことが原因で発症することが多いです。
中には、腸への血流が途絶えてしまう絞扼性(こうやくせい)腸閉塞という緊急性の高い状態もあります。
この記事では、術後の腸閉塞をできるだけ防ぐための方法と、もし症状が現れた場合にどのように対応すればよいかについて、分かりやすく解説します。
術後腸閉塞とは?基本的な知識
術後腸閉塞は、腹部や骨盤内の手術を受けた後に、腸管の内容物(食べ物、消化液、ガスなど)の通過が物理的または機能的に妨げられる状態を指します。
通過障害が起こると、腹痛、吐き気、嘔吐、お腹の張りなどの症状が現れます。早期に適切な対応をとることが重要です。
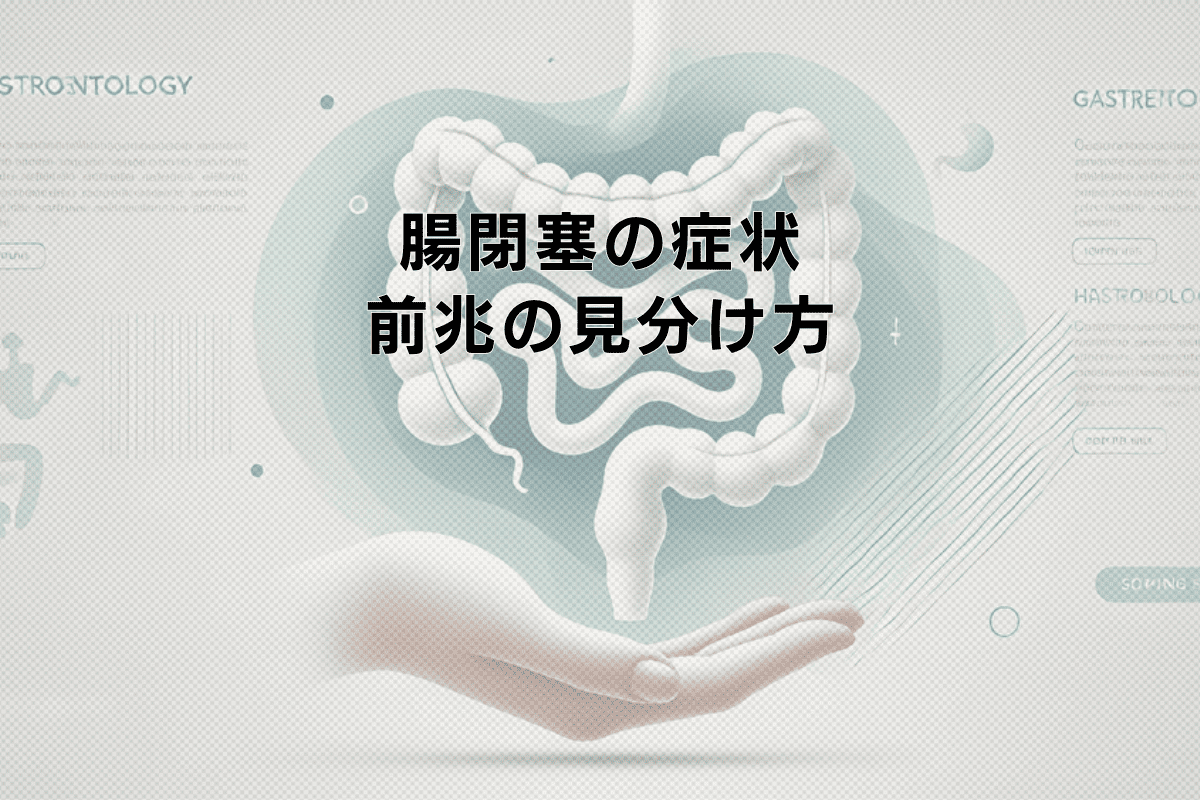
腸閉塞が起こる原因
腸閉塞の原因は多岐にわたりますが、術後に限定すると、最も多いのは腸管の癒着で、手術操作によって腹腔内に炎症が起こり、その治癒の過程で本来離れているはずの腸管同士や、腸管と腹壁などがくっついてしまう現象です。
この癒着部分が折れ曲がったり、他の腸管を締め付けたりすることで、内容物の通過が妨げられます。
癒着以外にも、手術操作による腸管の動きの一時的な麻痺(イレウス)、ヘルニア(脱腸)、腫瘍、炎症性疾患などが原因となることもあります。
主な原因の概要
| 原因 | 説明 | 術後との関連 |
|---|---|---|
| 癒着 | 手術などの炎症により腸管同士や腹壁がくっつくこと | 最も多い原因 |
| 腸管麻痺(イレウス) | 手術侵襲や麻酔により腸の動きが一時的に悪くなること | 術後早期に多い |
| その他 | ヘルニア、腫瘍、異物など | 比較的まれ |
なぜ手術後に起こりやすいのか
腹部の手術では、程度の差はあれ、腹腔内に何らかの操作が加わり、メスで切開したり、臓器を剥離したり、縫合したりする行為そのものが、組織にとっては傷であり、炎症反応を起こします。
この炎症が治る過程で、フィブリンという糊のような物質が分泌され、これが組織同士を結びつけ、結果として癒着が生じます。
手術の範囲が広範囲であったり、出血量が多かったり、術後に感染を起こしたりすると、癒着が起こる可能性は高まります。
また、手術中は手術による侵襲や薬剤の影響等で一時的に腸管の動きが抑制されるため、術後しばらくは腸の動きが鈍くなる麻痺性イレウスという状態にもなりやすいです。
これは通常、時間とともに回復しますが、回復が遅れると腸閉塞の症状が出ることがあります。
腸閉塞の種類
術後腸閉塞は、大きく分けて単純性腸閉塞と絞扼性腸閉塞の二つに分類されますが、緊急度や治療方針が大きく異なるため、区別することが非常に重要です。
単純性腸閉塞
単純性腸閉塞は、腸管の血流は保たれたまま、内容物の通過だけが妨げられている状態で、主に癒着によって腸管が折れ曲がったり、狭くなったりすることが原因です。
症状は比較的ゆっくり進行することが多く、腹痛、嘔吐、腹部膨満感などが現れます。多くの場合、絶食や点滴、胃管やイレウス管による減圧処置といった保存的治療で改善が期待できます。
絞扼性腸閉塞
絞扼性腸閉塞は、腸管の通過障害に加えて、腸管への血流が途絶えてしまう状態で、癒着した部分で腸管がねじれたり、索状物(ひも状の癒着)によって締め付けられたりすることが原因で起こります。
血流が途絶えると、腸管は短時間で壊死(組織が死んでしまうこと)に陥り、穿孔(穴が開くこと)して腹膜炎を起こしたり敗血症を来たしたりする危険性があります。
症状は急激に発症し、持続的で激しい腹痛、嘔吐、ショック状態などを呈することがあり、絞扼性腸閉塞は緊急手術が必要となる、生命に関わる危険な状態です。
単純性と絞扼性の主な違い
| 項目 | 単純性腸閉塞 | 絞扼性腸閉塞 |
|---|---|---|
| 血流 | 保たれている | 遮断されている |
| 主な原因 | 癒着による狭窄・屈曲 | 癒着による捻転・絞扼 |
| 緊急度 | 比較的低い(要観察) | 非常に高い(緊急手術) |
術後腸閉塞の主な症状
術後腸閉塞の症状は、閉塞の程度、場所、原因、そして単純性か絞扼性かによって異なり、典型的な症状を知っておくことで、早期発見・早期対応につながります。
腹痛の特徴と変化
腹痛は腸閉塞の最も一般的な症状で、単純性腸閉塞では、腸が内容物を先に送ろうとして強く動く(蠕動運動)際に痛みを感じるため、間欠的(痛んだり治まったりを繰り返す)な痛みであることが多いです。
お腹がグルグルと鳴る音を伴うこともあります。
一方、絞扼性腸閉塞では、血流障害による虚血(血が足りない状態)や壊死が起こるため、持続的で非常に激しい痛みを特徴とします。
痛みの部位がはっきりしていることもあります。痛みが急に始まって、どんどん強くなる場合は特に注意が必要です。
吐き気・嘔吐について
腸管の内容物が先に進めなくなると、逆流して吐き気や嘔吐を起こし、閉塞部位が口に近い小腸の上部であるほど、早期から嘔吐が見られ、閉塞部位が大腸に近いほど、嘔吐の出現は遅くなる傾向があります。
最初は胃液のようなものを嘔吐しますが、時間が経つと胆汁が混じって黄色っぽくなったり、さらに進行すると便のような臭いのするものを吐いたりすることもあり、さらに、嘔吐によって脱水症状が進むこともあります。
嘔吐物の変化
| 段階 | 嘔吐物の特徴 | 考えられる状態 |
|---|---|---|
| 初期 | 胃液、食べ物 | 閉塞の始まり |
| 中期 | 胆汁様(黄色・緑色) | 小腸での閉塞 |
| 後期 | 糞便様(便臭) | 閉塞の進行、小腸下部や大腸での閉塞 |
お腹の張りと排便・排ガスの停止
腸管内に内容物やガスが溜まることで、お腹が張る感じ(腹部膨満感)が現れ、お腹を叩くとポンポンと鼓のような音がすることがあります。
閉塞が完全な場合、便やガスが肛門から全く出なくなりますが、閉塞部位より肛門側に溜まっていた便やガスが少量出ることもあるため、おならが出たから大丈夫とは限りません。
絞扼性腸閉塞の危険なサイン
絞扼性腸閉塞は時間との勝負なので、以下の症状が見られる場合は、ただちに医療機関を受診することが重要です。
- 突然発症し、持続する激しい腹痛
- 冷や汗、顔面蒼白、脈が速くなるなどのショック症状
- 押さえると非常に強く痛む場所がある(限局性圧痛)
- 高熱
これらのサインは、腸管の壊死や腹膜炎が進行している可能性を示唆し、自己判断せず、救急要請もためらわないでください。
術後腸閉塞の予防策
完全に予防することは難しいですが、手術前からいくつかの点に気をつけることで、術後腸閉塞のリスクを少しでも減らすことが期待でき、体力や栄養状態を整えて手術に臨むことが基本です。
食生活の見直し
手術前だからといって特別な食事制限が必要なわけではありませんが、バランスの取れた食事を心がけ、良好な栄養状態を保つことが大切で、特に、タンパク質は傷の治りを助け、体力維持に役立ちます。
また、便秘がちな方は、食物繊維を適切に摂取し、水分を十分に摂ることで、腸の動きを整えておくことが望ましいです。
ただし、手術の種類や元々の病気によっては、医師から食事に関する指示がある場合があります。その際は、必ず医師の指示に従ってください。
栄養バランスのポイント
| 栄養素 | 主な役割 | 含まれる食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 組織修復、体力維持 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 炭水化物 | エネルギー源 | ご飯、パン、麺類 |
| 脂質 | エネルギー源、細胞膜構成 | 植物油、魚油 |
| ビタミン・ミネラル | 体の調子を整える | 野菜、果物、海藻 |

適度な運動の重要性
日頃から適度な運動習慣を持つことは、全身の血行を促進し、腸の動きを活発にする助けとなり、ウォーキングや軽いジョギング、ストレッチなど、無理のない範囲で体を動かすことを心がけましょう。
体力をつけておくことは、手術そのものや術後の回復にも良い影響を与えます。
ただし、これも手術内容や病状によって運動が制限される場合があります。事前に医師に相談し、許可された範囲で行ってください。
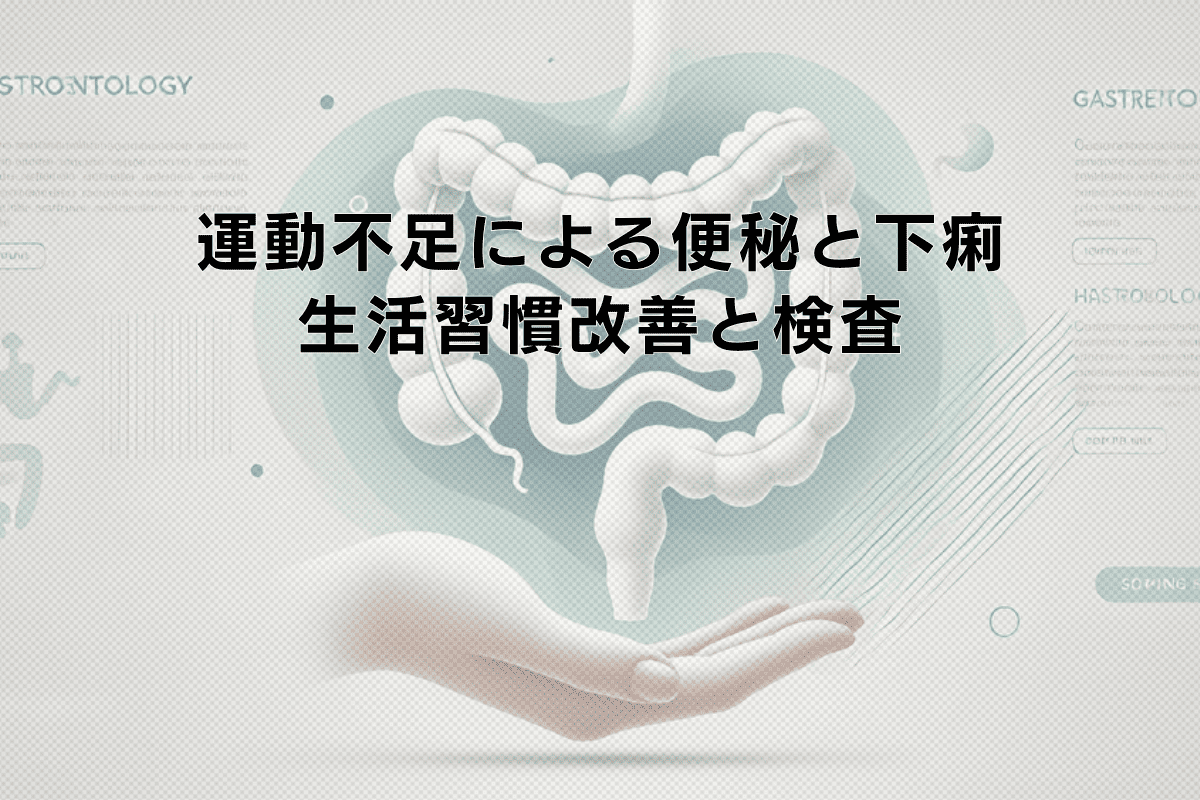
医師との情報共有
過去に腹部の手術を受けたことがあるか、腸閉塞になったことがあるか、便秘や下痢などの便通異常があるか、現在服用中の薬はあるかなど、ご自身の健康状態に関する情報は、些細なことでも手術前に医師に正確に伝えておくことが重要です。
これらの情報は、手術計画や術後の管理方針を決定する上で役立ちます。
また、手術の内容や術後に起こりうる合併症(腸閉塞を含む)について、医師から十分な説明を受け、疑問点があれば遠慮なく質問し、理解を深めておくことも大切です。
術後腸閉塞の予防策
手術が無事に終わった後も、腸閉塞を予防するために気をつけるべき点がいくつかあります。医療スタッフの指示に従いながら、ご自身でもできることに取り組みましょう。
早期離床のすすめ
「離床」とは、ベッドから起き上がり、歩行などの活動を開始することで、手術後は安静が必要な期間もありますが、医師や看護師の許可が出たら、できるだけ早くから体を動かすことが推奨されます。
早期離床は、腸の蠕動運動を促し、癒着の形成を抑える効果が期待できます。また、肺炎や血栓症(エコノミークラス症候群)などの他の合併症予防にもつながります。
最初はベッドサイドに座ることから始め、徐々に歩行距離を伸ばしていくなど、無理のない範囲で進め、痛みがある場合は、我慢せずに医療スタッフに伝え、痛み止めを使用するなどして対応してもらいましょう。
早期離床のメリット
- 腸蠕動運動の促進
- 癒着形成の抑制
- 血栓症・肺炎の予防
- 筋力低下の防止
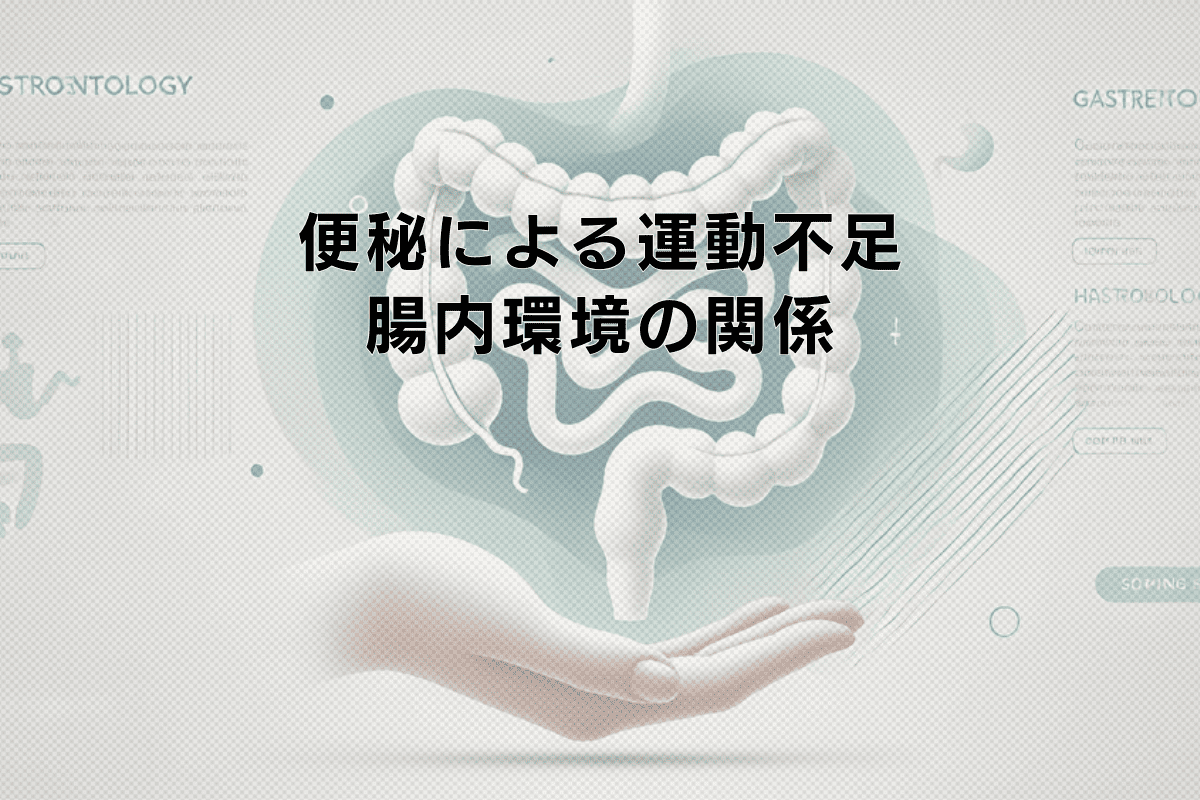
食事開始のタイミングと内容
手術後の食事は、腸の動きが回復するのを確認しながら、医師の指示に従って段階的に開始され、通常は水分から始まり、流動食、粥、常食へと進んでいきます。
焦って早く食べ始めたり、消化の悪いものを食べたりすると、腸に負担がかかり、腸閉塞のリスクを高める可能性があります。
食事を開始する際は、少量ずつ、よく噛んでゆっくり食べることを心がけ、食物繊維の多い食品や脂肪分の多い食品は、最初は避けた方が良い場合があります。食事内容についても、医師や管理栄養士の指示に従ってください。
術後の食事の進め方
| 段階 | 食事内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 水分摂取 | 水、お茶、薄いスープ | 少量ずつ試す |
| 流動食 | 重湯、具なしスープ | 腸への負担が少ない |
| 粥食 | 三分粥、五分粥、全粥 | 消化の良いおかずと組み合わせる |
| 常食 | 通常の食事 | 消化の良いものから徐々に |
水分補給のポイント
脱水は腸の動きを鈍らせる一因となり、手術後は、点滴で水分補給が行われますが、飲水が可能になったら、こまめに水分を摂りましょう。特に、食事量が少ない時期や、発熱・嘔吐などがあった場合は、意識して水分補給を行うことが大切です。
ただし、心臓や腎臓に持病がある方は、水分摂取量に制限がある場合がありますので、医師の指示に従ってください。
痛みの管理
手術後の痛みは、体を動かすことを妨げ、早期離床の妨げになります。痛みを我慢しすぎると、交感神経が刺激されて腸の動きが悪くなることもあり、痛みがある場合は、医師や看護師に伝え、痛み止めを使用してもらいましょう。
痛みをコントロールすることで、早期離床が進み、結果的に腸閉塞の予防につながります。
術後腸閉塞を疑う症状が出たときの対応
どれだけ予防策を講じても、術後腸閉塞を完全に防ぐことはできません。万が一、腸閉塞を疑う症状が出た場合に、どのように対応すればよいかを知っておくことが重要です。
まずは何をすべきか
腹痛、吐き気・嘔吐、お腹の張り、排便・排ガスの停止といった症状が現れたら、まずは食事や飲水を中止しましょう。腸に新たな負担をかけるのを避けるためです。
そして、安静にして様子を見ますが、症状が続く場合や悪化する場合は、自己判断せずに速やかに医療機関に連絡・受診する必要があります。
自己判断せず医療機関へ
少しお腹が痛いだけ、昨日食べ過ぎたかな、などと自己判断するのは危険です。特に、絞扼性腸閉塞の場合は、治療が遅れると命に関わります。
術後にこれまで経験したことのないような腹痛や嘔吐などの症状が出た場合は、手術を受けた医療機関、または最寄りの消化器科や救急外来に連絡し、指示を仰いでください。
夜間や休日であっても、症状が強い場合や急激に悪化している場合は、救急車の要請も検討してください。
連絡・受診の目安
| 症状 | 対応 |
|---|---|
| 軽い腹痛、軽い吐き気 | 食事を中止し安静。改善なければ医療機関へ連絡。 |
| 持続する腹痛、繰り返す嘔吐、強い腹部膨満感 | 速やかに医療機関へ連絡・受診。 |
| 激しい腹痛、冷や汗、高熱 | ただちに救急外来受診または救急車要請。 |
伝えるべき情報
医療機関を受診する際には、以下の情報を正確に伝えることが、迅速かつ適切な診断・治療につながります。
- いつ、どのような手術を受けたか
- いつから、どのような症状があるか(痛みの性質、始まった時間、嘔吐の回数や内容、最後の排便・排ガスはいつか)
- 他に持病はあるか、普段飲んでいる薬はあるか
- 過去に腸閉塞になったことがあるか
可能であれば、お薬手帳や手術に関する資料を持参すると良いでしょう。
緊急性の高い症状とは
繰り返しになりますが、絞扼性腸閉塞を疑う症状は特に緊急性が高く、持続する激しい腹痛、冷や汗、顔面蒼白、頻脈(脈が速い)、高熱、意識が朦朧とするなどの症状が見られたら、一刻も早く専門的な治療を受けることが必要です。
これらの症状は、腸管の壊死や腹膜炎、敗血症(血液中に細菌が入り全身に炎症が広がる状態)など、生命を脅かす状態を示唆している可能性があります。
医療機関での診断と治療
医療機関では、症状や身体所見、検査結果などを総合的に評価し、腸閉塞の有無、原因、重症度(単純性か絞扼性か)を診断し、適切な治療方針を決定します。
診断方法:問診から画像検査まで
診断は、まず詳細な問診(症状の経過、既往歴など)と身体診察(お腹の張り具合、圧痛の有無、腸蠕動音の聴診など)から始まります。その後、必要に応じて以下の検査が行われます。
主な検査
| 検査種類 | 目的 | わかること |
|---|---|---|
| 腹部X線検査(レントゲン) | 腸管内のガスや液体の貯留を確認 | 拡張した腸管、鏡面像(ニボー)の有無 |
| 腹部超音波検査(エコー) | 腸管の拡張、腸管壁の肥厚、腹水の有無などを確認 | リアルタイムで腸の動きや血流も評価可能 |
| 腹部CT検査 | 閉塞部位や原因、絞扼の有無を詳細に評価 | 腸管壁の状態、血流障害のサイン、腹水の有無など |
| 血液検査 | 炎症反応、脱水の程度、電解質異常、臓器障害の有無を確認 | 白血球数、CRP、電解質、腎機能、肝機能など |
検査結果を総合的に判断し、診断を確定し、特にCT検査は、閉塞の原因や絞扼の有無を判断する上で非常に有用な情報を提供します。
保存的治療:絶食と点滴
単純性腸閉塞で、絞扼の所見がない場合は、まず保存的治療が行われ、これは、手術をせずに腸を休ませて自然な回復を待つ治療法です。
主な内容
- 絶食・絶飲:腸への刺激を避け、腸管を安静に保ちます。
- 点滴:食事や水分が摂れないため、水分や電解質、栄養を補給します。脱水の改善も目的とします。
- 胃管・イレウス管の挿入:鼻から胃や小腸まで細いチューブを挿入し、溜まった消化液やガスを体外に排出します(減圧処置)。これにより、お腹の張りや吐き気が軽減され、腸管の負担が減ります。
治療により、多くの場合、数日から1週間程度で症状が改善し、食事が再開できるようになりますが、保存的治療を行っても改善が見られない場合や、症状が悪化する場合は、手術が検討されます。
外科的治療が必要な場合
保存的治療で改善しない単純性腸閉塞や、癒着が非常に強い場合、または再発を繰り返す場合には、外科的治療(手術)が検討されます。
手術の目的は、閉塞の原因となっている癒着を剥がしたり(癒着剥離術)、狭くなっている部分を切除してつなぎ合わせたりすることです。
手術方法は、開腹手術と腹腔鏡手術があります。
腹腔鏡手術は、お腹に小さな穴を数カ所開けてカメラや器具を挿入して行う手術で、傷が小さく、術後の回復が早いという利点がありますが、癒着の範囲や程度によっては開腹手術が必要となる場合もあります。
絞扼性腸閉塞の緊急治療
絞扼性腸閉塞と診断された場合、あるいはその可能性が強く疑われる場合は、時間的猶予はなく、原則として緊急手術が行われます。手術の目的は、締め付けやねじれを解除して血流を再開させること、そして壊死に陥った腸管を切除することです。
手術が遅れると、腸管の壊死範囲が広がり、大量切除が必要になったり、腹膜炎や敗血症を併発して生命に関わる事態になったりする危険性が高まるため、迅速な診断と緊急手術の判断が極めて重要です。
退院後の生活と再発予防
腸閉塞の治療が終わり、無事に退院できた後も、再発を予防するために日常生活で気をつけるべき点があります。一度癒着が原因で腸閉塞を起こすと、再発しやすい傾向があるため、油断は禁物です。
食生活で気をつけること
退院直後は、消化の良いものを少量ずつ、よく噛んで食べることから始め、徐々に通常の食事に戻していきます。
食事のポイント
| ポイント | 具体的な内容 |
|---|---|
| よく噛む | 一口30回以上を目安に、ゆっくり時間をかけて食べる |
| 食べ過ぎない | 腹八分目を心がけ、一度に大量に食べない |
| 消化の良い食品を選ぶ | 脂肪分の多いもの、硬いもの、食物繊維が多すぎるものは避ける |
| 水分を十分に摂る | 便通を整え、腸の内容物を流れやすくする |
特に注意が必要な食品としては、こんにゃく、きのこ類、海藻類、ごぼうなどの不溶性食物繊維が多いもの、餅や団子など粘り気の強いもの、干物やナッツ類など硬いものが挙げられます。
絶対に食べてはいけないわけではありませんが、食べる際は少量にし、特によく噛みましょう。
日常生活での注意点
食生活以外にも、日常生活で以下の点に気をつけると、再発予防につながります。
- 適度な運動:ウォーキングなど、腸の動きを促す軽い運動を習慣づける。ただし、腹圧がかかりすぎる激しい運動は避ける。
- 規則正しい生活:睡眠時間を確保し、ストレスを溜めないようにする。
- 便通の管理:便秘にならないよう、食生活や水分摂取に気を配る。必要であれば医師に相談の上、緩下剤を使用する。
- 体を冷やさない:体の冷えは腸の動きを悪くすることがあるため、腹巻をするなど保温を心がける。
再発のサインを見逃さない
注意していても、腸閉塞が再発することはあります。以前経験したような腹痛、吐き気、お腹の張りなどの症状が現れた場合は、「またか」と思わずに、早めに医療機関を受診することが大切です。
特に、絞扼性を疑う激しい痛みの場合は、ためらわずに救急受診してください。
定期的な受診の意義
退院後も、医師の指示に従って定期的に通院し、経過観察を受けることが重要で、体調の変化や不安な点があれば、その都度医師に相談しましょう。
定期的な診察を受けることで、再発の兆候を早期に発見したり、生活上のアドバイスを受けることができます。
よくある質問 (FAQ)
最後に、術後腸閉塞に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- どんな手術の後が腸閉塞になりやすいですか?
-
基本的に腹部や骨盤内の手術であれば、どんな手術でも腸閉塞のリスクはあります。
開腹手術、大腸がんや婦人科がんの手術など、広範囲にわたる操作が必要な手術や、術中・術後に腹膜炎を起こした場合などは、癒着が起こりやすく、腸閉塞のリスクが高まる傾向があります。
腹腔鏡手術は開腹手術に比べて癒着のリスクは低いとされていますが、ゼロではありません。
- 腸閉塞はどのくらいの期間で治りますか?
-
治療期間は、腸閉塞の種類(単純性か絞扼性か)や重症度、治療法(保存的か手術か)によって大きく異なります。単純性腸閉塞で保存的治療がうまくいった場合は、数日から1週間程度で軽快することが多いです。
手術が必要になった場合や、絞扼性腸閉塞の場合は、入院期間はさらに長くなり、退院後も、完全に元の状態に戻るまでには時間がかかることがあります。
- 予防のために特別な食事は必要ですか?
-
術後や退院後の食事は、基本的に「消化の良いものを、よく噛んで、食べ過ぎない」ことが原則です。
特定の食品を厳しく制限する「特別な食事」が必要なわけではありませんが、ご自身の体調に合わせて、腸に負担のかかりにくい食事を心がけることが大切です。
食物繊維が多い食品や脂肪分の多い食品は、摂りすぎに注意が必要です。不安な場合は、医師や管理栄養士に相談してください。
- 絞扼性腸閉塞はどのように見分けるのですか?
-
患者さん自身が単純性か絞扼性かを確実に見分けることは困難ですが、絞扼性腸閉塞を疑うべき危険なサインはあります。
それは、「突然発症し、持続する激しい腹痛」「冷や汗や顔面蒼白などのショック症状」「限局性の強い圧痛」「高熱」などで、腸管への血流が途絶え、壊死が始まっている可能性を示唆します。
このような症状が見られた場合は、絶対に自己判断せず、ただちに救急医療機関を受診してください。
次に読むことをお勧めする記事
【腸閉塞の症状から診断まで – 状態に応じた適切な検査】
術後腸閉塞の基本を押さえたら、次は受診後にどの検査が行われるかを知っておくと安心です。検査の流れや注意点を整理しています。
【腸にいい食べ物を知る 腸内環境を整える方法】
術後腸閉塞の予防を学んだ皆さんには、日常的な腸の健康管理の知識も合わせて持っていただくと、より包括的な腸の健康維持ができます。食事を通じた腸内環境改善の具体的な方法をご紹介しています。
参考文献
Nakamura T, Sato T, Naito M, Ogura N, Yamanashi T, Miura H, Tsutsui A, Yamashita K, Watanabe M. Laparoscopic surgery is useful for preventing recurrence of small bowel obstruction after surgery for postoperative small bowel obstruction. Surgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Techniques. 2016 Feb 1;26(1):e1-4.
Yamada T, Okabayashi K, Hasegawa H, Tsuruta M, Yoo JH, Seishima R, Kitagawa Y. Meta-analysis of the risk of small bowel obstruction following open or laparoscopic colorectal surgery. Journal of British Surgery. 2016 Apr;103(5):493-503.
Yamada T, Hirata K, Ichikawa D, Ikeda M, Fujita F, Eto K, Yukawa N, Kojima Y, Matsuda A, Shimoyama R, Ochiai H. Clinical impact of laparoscopic surgery and adhesion prevention material for prevention of small bowel obstruction. Annals of Gastroenterological Surgery. 2022 Sep;6(5):651-7.
Nakashima M, Takeuchi M, Kawakami K. Effectiveness of barrier agents for preventing postoperative bowel obstruction after laparoscopic surgery: a retrospective cohort study. Surgery Today. 2021 Aug;51:1335-42.
Fujii S, Tsukamoto M, Shimada R, Okamoto K, Hayama T, Tsuchiya T, Nozawa K, Matsuda K, Ishibe A, Ota M, Itano O. Absorptive anti-adhesion barrier for the prevention of bowel obstruction after laparoscopic colorectal cancer surgery. Journal of the Anus, Rectum and Colon. 2018 Jan 26;2(1):1-8.
Hayashi S, Fujii M, Takayama T. Prevention of postoperative small bowel obstruction in gastric cancer. Surgery today. 2015 Nov;45:1352-9.
Kunitomi Y, Nakashima M, Takeuchi M, Kawakami K. Efficacy of Daikenchuto in the prevention of bowel obstruction in patients with colorectal cancer undergoing laparoscopic surgery: An observational study using a Japanese administrative claims database. Supportive Care in Cancer. 2023 Feb;31(2):133.
Attard JA, MacLean AR. Adhesive small bowel obstruction: epidemiology, biology and prevention. Canadian Journal of Surgery. 2007 Aug;50(4):291.
Yang S, Zhao H, Yang J, An Y, Zhang H, Bao Y, Gao Z, Ye Y. Risk factors of early postoperative bowel obstruction for patients undergoing selective colorectal surgeries. BMC gastroenterology. 2021 Dec;21:1-0.
Fahim M, Dijksman LM, Derksen WJ, Bloemen JG, Biesma DH, Smits AB. Prospective multicentre study of a new bowel obstruction treatment in colorectal surgery: reduced morbidity and mortality. European Journal of Surgical Oncology. 2021 Sep 1;47(9):2414-20.