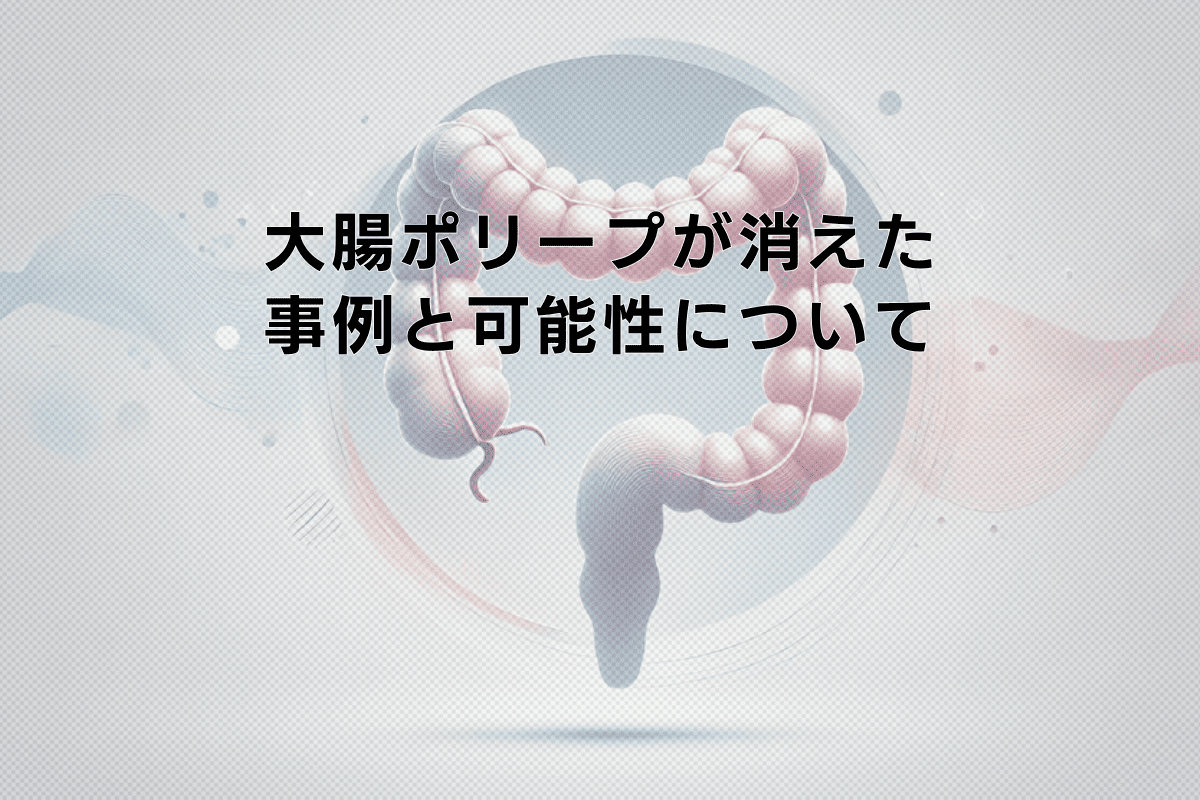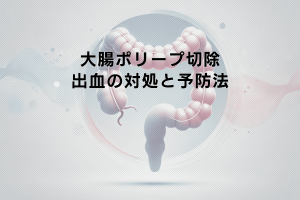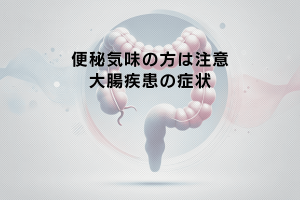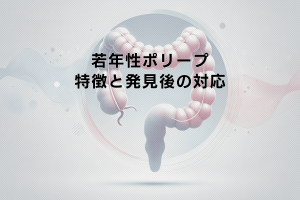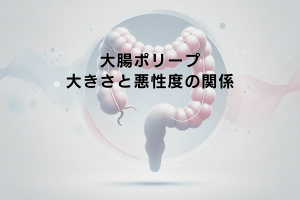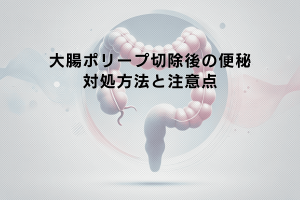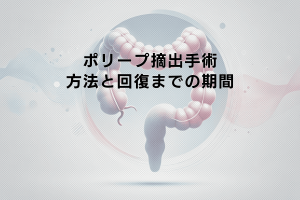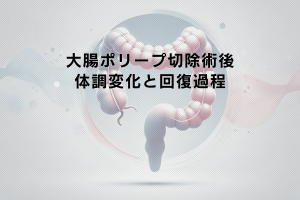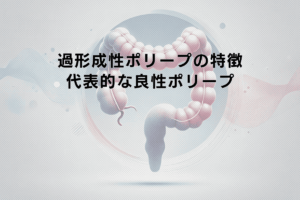大腸ポリープが消えたという話を聞いたことがあるかもしれません。実際にポリープが自然に小さくなったり、見えなくなったりすることはあるのでしょうか。
この記事では、大腸ポリープの基本的な知識から、ポリープが消えるといわれる背景、食事や生活習慣との関連性、そして私たちが日々の生活で何に気をつけるべきかについて、詳しく解説します。
大腸ポリープとは何か?基本的な知識
大腸ポリープという言葉を耳にしたことがある方は多いでしょう。ここでは、大腸ポリープの定義、種類、発生原因、そして一般的な症状について、基礎から分かりやすく説明します。
大腸ポリープの定義と種類
大腸ポリープとは、大腸の粘膜(内側の表面)にできる、いぼ状やきのこ状の隆起物を指し、大きさや形、そして性質は様々です。
ポリープの多くは自覚症状がないまま進行することがあり、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)などで偶然発見されることも少なくありません。ポリープの種類を理解することは、その後の対応を考える上で非常に重要です。
腫瘍性ポリープと非腫瘍性ポリープ
大腸ポリープは、大きく分けて腫瘍性ポリープと非腫瘍性ポリープの2つに分類できます。
腫瘍性ポリープの代表的なものには腺腫(せんしゅ)があり、腺腫は、それ自体は良性ですが、放置するとがん化するリスクがあるため、前がん病変とも呼ばれます。大腸がんの多くは、この腺腫から発生すると考えられています。
一方、非腫瘍性ポリープには、過形成性(かけいせいせい)ポリープや炎症性ポリープなどがあります。過形成性ポリープは、基本的にはがん化するリスクは低いと考えられていますが、一部にはがん化の可能性が指摘されるものもあります。
炎症性ポリープは、大腸の炎症(例えば潰瘍性大腸炎やクローン病など)に伴って発生するもので、がん化のリスクは低いです。
ポリープの種類
| ポリープの分類 | 代表的な種類 | 特徴 |
|---|---|---|
| 腫瘍性ポリープ | 腺腫 | 良性だが、がん化する可能性がある(前がん病変) |
| 非腫瘍性ポリープ | 過形成性ポリープ | 基本的にはがん化リスクは低いが、一部注意が必要なものもある |
| 炎症性ポリープ | 大腸の炎症に伴い発生、がん化リスクは低い |
ポリープの形状による分類
ポリープは、その形状によっても分類されます。代表的なものとして、有茎性(ゆうけいせい)ポリープと無茎性(むけいせい)ポリープがあります。
有茎性ポリープは、きのこのように茎があり、粘膜からぶら下がるような形をしていて、無茎性ポリープは、茎がなく、粘膜から平たく盛り上がるような形をしています。
無茎性ポリープの中でも、表面が平坦なものは表面型ポリープや平坦型ポリープと呼ばれ、発見が難しい場合もあります。
大腸ポリープが発生する主な原因
大腸ポリープが発生する原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発生すると考えられていて、主な原因として、生活習慣と遺伝的要因が挙げられます。
生活習慣との関連
近年の研究により、食生活の欧米化が大腸ポリープや大腸がんの増加に関与していることが指摘されていて、動物性脂肪や赤身肉(牛肉、豚肉、羊肉など)の過剰な摂取、食物繊維の摂取不足などがリスク要因として挙げられます。
また、肥満や運動不足、喫煙、過度な飲酒なども、大腸ポリープの発生リスクを高める可能性があり、腸内環境の悪化や、発がん物質への暴露機会の増加などを通じて、ポリープ発生に関わると考えられています。
生活習慣における主なリスク要因
| 要因 | 具体的な内容 | 考えられる影響 |
|---|---|---|
| 食事 | 動物性脂肪・赤身肉の過剰摂取、食物繊維不足 | 腸内環境の悪化、発がん物質の生成促進 |
| 運動 | 運動不足 | 腸の蠕動運動低下、免疫力低下 |
| その他 | 肥満、喫煙、過度な飲酒 | 全身の炎症促進、発がん物質への暴露 |
遺伝的要因について
大腸ポリープの発生には、遺伝的な要因も関与しています。特定の遺伝子変異が原因で、多数のポリープが発生したり、若いうちから大腸がんを発症したりする遺伝性大腸がん症候群と呼ばれる病態があります。
代表的なものに、家族性大腸腺腫症(FAP)やリンチ症候群などがあります。
大腸ポリープの一般的な症状
大腸ポリープの多くは、初期の段階では自覚症状がほとんどないため、症状がないからといって安心はできません。しかし、ポリープが大きくなったり、数が増えたりすると、様々な症状が現れることがあります。
初期症状は気づきにくい
小さなポリープや初期のポリープでは、ほとんどの場合、自覚症状はなく、これが大腸ポリープの発見を遅らせる一因ともなっています。
症状がないままポリープが成長し、場合によってはがん化が進行することもあるため、定期的な検診による早期発見が非常に重要です。
進行した場合に見られる症状
ポリープが大きくなったり、数が増えたり、あるいは出血したりすると、以下のような症状が現れることがあります。
- 血便(便に血が混じる、便の表面に血が付着する)
- 便通異常(便秘や下痢を繰り返す、便が細くなる)
- 腹痛、腹部膨満感
- 貧血(ポリープからの慢性的な出血による)
大腸ポリープが自然に消えることはあるのか?
大腸ポリープが自然に消えた、という話を聞くと、期待を抱く方もいるかもしれません。しかし、医学的に見て、大腸ポリープが自然に消えることは一般的な現象なのでしょうか。
ポリープが小さくなる・消える現象の医学的見解
一般的に、一度できた腫瘍性ポリープ(特に腺腫)が自然に完全に消滅することは稀ですが、ポリープの種類や状態によっては、サイズが縮小したり、一時的に見えなくなったりする現象が観察されることもあります。
これにはいくつかの要因が考えられます。
自然退縮のメカニズム(仮説)
ポリープの自然退縮が起こる正確なメカニズムは完全には解明されていませんが、いくつかの仮説が提唱されています。
例えば、ポリープへの血流が何らかの理由で途絶え、組織が壊死・脱落する可能性や、体内の免疫システムがポリープ細胞を攻撃し、排除する可能性などが考えられます。
また、ポリープ表面の炎症が改善することで、見かけ上のサイズが小さくなることもあり得ます。ただし、これらはあくまで仮説の段階であり、全てのポリープに当てはまるわけではありません。
炎症性ポリープの場合
非腫瘍性ポリープの一種である炎症性ポリープは、大腸の炎症が原因で発生するため、原因となっている炎症が治療などによって改善すると、それに伴って炎症性ポリープも縮小したり、消失したりすることがあります。
これは、腫瘍性ポリープの自然退縮とは異なる現象として理解することが必要です。
自然に消えるポリープと消えないポリープの違い
全てのポリープが同じように振る舞うわけではなく、ポリープの種類や大きさによって、自然に小さくなったり消えたりする可能性には違いがあります。
ポリープの種類による違い
炎症性ポリープは原因となる炎症の改善に伴い縮小・消失することがあるものの、がん化する可能性のある腺腫性ポリープが自然に完全に消失することは、一般的には期待しにくいと考えられています。
過形成性ポリープも、基本的にはがん化リスクは低いとされますが、自然消失することは稀です。
ポリープの種類と自然退縮の可能性
| ポリープの種類 | 自然退縮の可能性 | 備考 |
|---|---|---|
| 腺腫性ポリープ | 稀、または期待しにくい | がん化のリスクがあるため、経過観察または切除を検討 |
| 過形成性ポリープ | 稀 | 基本的にはがん化リスクは低い |
| 炎症性ポリープ | あり得る | 原因となる炎症の改善に伴う |
ポリープの大きさとの関連性
非常に小さなポリープの場合、検査時の腸管の状態や観察角度によって、一時的に見えにくくなることがあります。
ごく初期の小さな病変が免疫応答などによって排除される可能性も完全には否定できませんが、ある程度の大きさになったポリープ、特に数ミリ以上の腺腫が自然に消えることは、医学的には考えにくいです。
大腸ポリープが「消えた」と言われる事例の背景
実際に大腸ポリープが消えた、という経験談を見聞きすることがあり、医学的な観点から見ると、背景にはいくつかの可能性が考えられます。
検査方法による誤認の可能性
大腸ポリープの診断は、主に大腸内視鏡検査によって行われますが、検査時の条件や技術的な限界から、ポリープの存在や大きさが誤って認識される可能性も皆無ではありません。
検査機器の精度と限界
近年の内視鏡機器は非常に高性能化しており、微細な病変も発見できるようになっていますが、それでも100%完璧というわけではありません。
非常に小さなポリープや、ヒダの間に隠れているポリープなどは、見逃されたり、あるいは前回見えていたものが今回見えなかったりすることがあり得ます。
検査時の腸管の状態による影響
大腸内視鏡検査を正確に行うためには、腸管内がきれいになっていることが重要で、下剤の服用が不十分で残渣(便の残り)が多い場合や、腸の蠕動運動が活発な場合などは、ポリープの観察が困難です。
前回はっきりと見えていたポリープが、次回の検査時には残渣に隠れて見えなかったり、あるいは腸管の収縮によって一時的に見えにくくなったりすることで、消えたように感じられる可能性があります。
検査結果に影響を与える可能性のある要因
| 要因 | 具体例 | 影響 |
|---|---|---|
| 腸管の前処置 | 下剤の服用不足、残渣の付着 | ポリープの観察不良、見逃し |
| 腸管の動き | 蠕動運動の亢進、腸管の収縮 | ポリープの一時的な不明瞭化 |
| ポリープの特性 | 微小なポリープ、平坦なポリープ | 発見の困難さ、観察角度による見え方の変化 |
食事療法や生活習慣改善による影響の考察
食事や生活習慣の改善が、大腸ポリープの成長を抑制したり、場合によっては縮小させたりする可能性については、多くの研究が進められています。
直接的にポリープを消すとまでは言えなくても、腸内環境を整え、体の防御機能を高めることで、何らかの良い影響を与えることは考えられます。
食物繊維の役割
食物繊維は、便通を改善し、便の量を増やして腸内をきれいに保つ働きがあり、また、腸内の善玉菌のエサとなり、腸内環境を整える効果も期待できます。
これにより、発がん物質が腸管粘膜に接触する時間が短縮されたり、腸内細菌叢のバランスが改善されたりすることで、ポリープの発生や成長を抑制する可能性が指摘されています。
抗酸化物質の重要性
野菜や果物に多く含まれるビタミンC、ビタミンE、βカロテンなどの抗酸化ビタミンや、ポリフェノールなどの抗酸化物質は、体内の活性酸素を除去する働きがあります。
活性酸素は細胞を傷つけ、がん化の引き金の一つになると考えられています。これらの抗酸化物質を積極的に摂取することで、細胞のダメージを軽減し、ポリープの発生や進行を抑える効果が期待できるかもしれません。
免疫力の向上とポリープの関係性
私たちの体には、異物や異常な細胞を排除しようとする免疫システムが備わっていて、免疫力が正常に機能していれば、ポリープのような異常な細胞の増殖をある程度抑えることができます。
腸内環境と免疫
腸は、体内で最大の免疫器官とも言われ、腸内環境の状態は全身の免疫力に大きな影響を与えます。
善玉菌が優勢なバランスの取れた腸内環境は、免疫細胞を活性化し、体の防御機能を高め、逆に、悪玉菌が増えたり、腸内細菌の多様性が失われたりすると、免疫力が低下し、ポリープのような病変が発生・進行しやすくなる可能性があります。
ストレス管理の意義
過度なストレスは、自律神経のバランスを乱し、免疫機能を低下させることが知られていて、また、ストレスは腸の動きや腸内環境にも悪影響を与えることがあります。
適切なストレス管理を行い、心身の健康を保つことは、間接的にポリープ対策にもつながるでしょう。
大腸ポリープを小さくする、あるいは進行を遅らせる可能性のある食事
大腸ポリープの発生や進行には、日々の食事が深く関わっていると考えられています。
特定の食品がポリープを直接的に消し去るわけではありませんが、バランスの取れた食事を心がけることで、ポリープの成長を遅らせたり、新たなポリープの発生リスクを低減したりする効果が期待できます。
食物繊維を豊富に含む食品とその効果
食物繊維は、消化されずに大腸まで届き、腸内環境の改善や便通促進に役立つ重要な栄養素です。大腸ポリープの予防や進行抑制においても、食物繊維の積極的な摂取が推奨されています。
水溶性食物繊維と不溶性食物繊維
食物繊維には、水に溶けやすい水溶性食物繊維と、水に溶けにくい不溶性食物繊維の2種類があり、水溶性食物繊維は、善玉菌のエサとなり腸内環境を整えるほか、食後の血糖値の急上昇を抑える効果もあります。
不溶性食物繊維は、便の量を増やして腸を刺激し、排便を促す効果があり、どちらの食物繊維もバランス良く摂取することが大切です。
食物繊維の種類と主な働き
| 食物繊維の種類 | 主な働き | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| 水溶性食物繊維 | 善玉菌のエサになる、血糖値上昇抑制、コレステロール吸着 | 海藻類、果物、こんにゃく、大麦 |
| 不溶性食物繊維 | 便量増加、腸の蠕動運動促進、有害物質の排出促進 | 豆類、きのこ類、野菜、穀類 |
おすすめの食材例
食物繊維を効率よく摂取するためには、以下のような食材を日々の食事に取り入れることをお勧めします。
- 野菜類(ごぼう、ブロッコリー、ほうれん草、キャベツなど)
- きのこ類(しいたけ、しめじ、えのきなど)
- 豆類(大豆、納豆、豆腐、小豆など)
- いも類(さつまいも、じゃがいも、こんにゃくなど)
- 海藻類(わかめ、ひじき、昆布など)
- 果物類(りんご、バナナ、キウイフルーツなど)
- 穀類(玄米、大麦、全粒粉パンなど)

抗酸化作用のある栄養素と食材
私たちの体内で発生する活性酸素は、細胞を傷つけ、老化や様々な病気の原因になると考えられていて、大腸ポリープの発生やがん化にも、この活性酸素が関与している可能性があります。
抗酸化作用のある栄養素を摂取することで、活性酸素によるダメージを軽減し、ポリープのリスクを低減する効果が期待できます。
ビタミンC、E、βカロテンなど
代表的な抗酸化ビタミンとして、ビタミンC、ビタミンE、βカロテン(体内でビタミンAに変わる)が挙げられ、野菜や果物に豊富に含まれています。
主な抗酸化ビタミンと多く含む食品
| 抗酸化ビタミン | 多く含む食品例 |
|---|---|
| ビタミンC | パプリカ、ブロッコリー、柑橘類、いちご、キウイフルーツ |
| ビタミンE | ナッツ類(アーモンドなど)、植物油、アボカド、かぼちゃ |
| βカロテン | 緑黄色野菜(にんじん、ほうれん草、かぼちゃ、小松菜など) |
腸内環境を整える食事のポイント
腸内には数百兆個もの細菌が生息しており、腸内フローラと呼ばれる生態系を形成していて、腸内フローラのバランスが、私たちの健康に大きな影響を与えることが分かってきました。
善玉菌を増やし、腸内環境を良好に保つことは、大腸ポリープの予防や進行抑制にもつながります。
発酵食品の活用
ヨーグルト、納豆、味噌、キムチ、チーズなどの発酵食品には、乳酸菌やビフィズス菌といった善玉菌や、善玉菌のエサとなる物質が含まれています。日常的に摂取することで、腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整える効果が期待できます。
オリゴ糖の摂取
オリゴ糖は、消化酵素で分解されにくく大腸まで届き、善玉菌のエサとなる糖類です。玉ねぎ、ごぼう、アスパラガス、バナナ、大豆製品などに含まれています。また、市販のオリゴ糖製品を利用するのも一つの方法です。
ポリープ対策で避けたい食事・食習慣
大腸ポリープのリスクを高める可能性のある食事や食習慣についても理解しておくことが大切です。以下のような点に注意しましょう。
加工肉や赤身肉の過剰摂取
ハム、ソーセージ、ベーコンなどの加工肉や、牛肉、豚肉、羊肉などの赤身肉の過剰な摂取は、大腸がんのリスクを高めることが多くの研究で示されています。
これらの食品に含まれるヘム鉄や、調理過程で生成される発がん性物質などが関与していると考えられています。
高脂肪食のリスク
動物性脂肪を中心とした高脂肪食は、胆汁酸の分泌を促進し、腸内細菌によって二次胆汁酸という発がん促進物質に変えられる可能性があり、また、高脂肪食は腸内環境を悪化させる一因です。
揚げ物や脂質の多い肉類などの摂取は控えめにし、魚や植物性の油(オリーブオイル、えごま油など)を適度に摂るように心がけましょう。
食事以外で大腸ポリープ対策として考えられること
大腸ポリープの予防や進行抑制には、食事だけでなく、運動習慣や禁煙・節酒、ストレス管理、そして定期的な検診といった総合的なアプローチが重要です。
適度な運動習慣の重要性
定期的な運動は、大腸ポリープや大腸がんのリスクを低減する効果があることが多くの研究で示されています。運動は、腸の蠕動運動を活発にし、便通を改善するだけでなく、免疫機能を高めたり、体内の炎症を抑えたりする効果も期待できます。
運動の種類と頻度の目安
特別な運動でなくても、日常生活の中で体を動かす機会を増やすことが大切で、ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなどの有酸素運動が推奨されます。
週に合計150分程度の中等度の運動、または75分程度の高強度の運動を目指すと良いでしょう。
運動習慣のポイント
| ポイント | 具体例 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 種類 | ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなど | 全身持久力の向上、生活習慣病予防 |
| 頻度・時間 | 週に150分(中等度)または75分(高強度) | 腸の蠕動運動促進、免疫力向上 |
| 継続性 | 無理なく続けられる範囲で | 長期的な健康維持 |
禁煙と節酒の推奨
喫煙と過度な飲酒は、大腸ポリープや大腸がんのリスクを高めることが明らかになっていて、健康のためには、禁煙と節度ある飲酒を心がけることが重要です。
喫煙のリスク
タバコの煙には多くの発がん物質が含まれており、これらの物質は血液を通じて全身に運ばれ、大腸の粘膜にも到達し、喫煙は、大腸ポリープの発生リスクを高めるだけでなく、ポリープががん化するリスクも高めます。
アルコールの影響
アルコールの過剰な摂取も、大腸ポリープや大腸がんのリスク要因の一つで、アルコールそのものや、アルコールの代謝物であるアセトアルデヒドに発がん性があると考えられています。
また、飲酒は葉酸などの栄養素の吸収を妨げ、間接的にがんリスクを高める可能性も指摘されています。飲酒する場合は、適量を守ることが大切です。
ストレス管理と質の高い睡眠
心身の健康は、腸の健康とも密接に関連しています。過度なストレスや睡眠不足は、免疫機能の低下や腸内環境の悪化を招き、間接的に大腸ポリープのリスクを高める可能性があります。
ストレスが腸内環境に与える影響
ストレスは自律神経のバランスを乱し、腸の蠕動運動に影響を与えたり、腸内細菌叢のバランスを崩したりすることがあります。また、ストレスは免疫細胞の働きを抑制し、体の防御機能を弱めることも知られています。
睡眠不足のリスク
質の高い睡眠は、体の修復や免疫機能の維持に必要です。睡眠不足が続くと、ホルモンバランスが乱れたり、免疫力が低下したりして、様々な健康問題を起こす可能性があります。
定期的な検診の意義
大腸ポリープや大腸がんは、早期に発見し、適切な治療を行えば、良好な経過が期待できる病気で、定期的な検診を受けることが非常に重要です。
早期発見・早期治療の重要性
多くの大腸ポリープは、初期には自覚症状がありません。症状が出てからでは、病状が進行している可能性もあります。
検診によって症状のない段階でポリープを発見し、必要であれば切除することで、大腸がんへの進行を防ぐことができます。
検診の種類と推奨頻度
大腸がん検診としては、まず便潜血検査(便に混じった微量の血液を調べる検査)が広く行われています。便潜血検査で陽性となった場合は、精密検査として大腸内視鏡検査を受けることが一般的です。
また、年齢や家族歴、既往歴などに応じて、最初から大腸内視鏡検査を選択することもでき、検診の推奨頻度は、個人のリスクによって異なりますので、かかりつけ医や専門医に相談し、適切な間隔で検診を受けましょう。
主な大腸検診の種類
| 検査方法 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 便潜血検査 | 便中の血液の有無を調べる | 簡便、低侵襲、一次スクリーニングとして有用 |
| 大腸内視鏡検査 | 肛門から内視鏡を挿入し、大腸全体を直接観察する | ポリープの発見・切除が可能、最も精密な検査 |
| 注腸X線検査 | バリウムと空気を肛門から注入し、X線撮影する | 大腸全体の形状を把握できるが、小さな病変の発見は難しい場合がある |

大腸ポリープに関するよくある質問(Q&A)
- 大腸ポリープが見つかったら、必ず手術が必要ですか?
-
必ずしも手術(内視鏡的切除を含む)が必要というわけではありません。ポリープの種類、大きさ、形状、数、そして患者さんの全身状態などを総合的に判断して、切除するかどうか、あるいは経過観察とするかを決定します。
- ポリープ切除後の食事で気をつけることはありますか?
-
ポリープ切除後は、数日間から1週間程度、消化の良い食事を心がけることが一般的です。刺激物(香辛料、アルコール、炭酸飲料など)や、脂肪分の多い食事、食物繊維の多い硬い野菜などは、腸への負担となる可能性があるため、控えるよう指示されることがあります。
- 大腸カメラ検査はどのくらいの頻度で受けるべきですか?
-
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)を受ける頻度は、個人のリスクによって異なります。一般的には、40歳を過ぎたら一度は検査を受けることが推奨されています。検査の結果、ポリープが見つからなかった場合でも、年齢や家族歴などを考慮して、数年ごとの定期的な検査が勧められることがあります。
- 便潜血検査で陽性が出たら、必ずポリープがありますか?
-
便潜血検査で陽性となっても、必ずしも大腸ポリープや大腸がんがあるとは限らず、痔などの肛門疾患や、大腸の炎症など、他の原因で出血している可能性もあります。
しかし、便潜血検査陽性は、大腸からの出血を示唆する重要なサインであり、精密検査(通常は大腸内視鏡検査)を受けることが必要です。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸ポリープの悪性化リスク|画像でみる特徴と症状】
ポリープが自然に消えるかもしれない」と感じたからこそ、「本当に安全なのか?」という疑問が生まれるかもしれません。そうした不安に応えるべく、悪性化リスクの視点から詳しく解説しています。
【大腸ポリープ毎年発見される方の検査と予防対策】
自然に見えなくなるケースから、再発や今後の発生予防に関心が広がるかもしれません。こちらの記事では、生活習慣改善や検査戦略を通じたリスク管理について詳しく説明しています。
参考文献
Yokota T, Saito Y, Takamaru H, Sekine S, Nakajima T, Yamada M, Sakamoto T, Taniguchi H, Kushima R, Tsukamoto S, Shida D. Spontaneous regression of mismatch repair-deficient colon cancer: a case series. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2021 Aug 1;19(8):1720-2.
Sano Y, Hotta K, Matsuda T, Murakami Y, Fujii T, Kudo SE, Oda Y, Ishikawa H, Saito Y, Kobayashi N, Sekiguchi M. Endoscopic removal of premalignant lesions reduces long-term colorectal cancer risk: results from the Japan Polyp Study. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2024 Mar 1;22(3):542-51.
Tanaka S, Saitoh Y, Matsuda T, Igarashi M, Matsumoto T, Iwao Y, Suzuki Y, Nozaki R, Sugai T, Oka S, Itabashi M. Evidence-based clinical practice guidelines for management of colorectal polyps. Journal of Gastroenterology. 2021 Apr;56:323-35.
Kawai K, Sunami E, Tsuno NH, Kitayama J, Watanabe T. Polyp surveillance after surgery for colorectal cancer. International journal of colorectal disease. 2012 Aug;27:1087-93.
Tanaka S, Saitoh Y, Matsuda T, Igarashi M, Matsumoto T, Iwao Y, Suzuki Y, Nishida H, Watanabe T, Sugai T, Sugihara KI. Evidence-based clinical practice guidelines for management of colorectal polyps. Journal of gastroenterology. 2015 Mar;50:252-60.
Mizuno KI, Suzuki Y, Takeuchi M, Kobayashi M, Aoyagi Y. Natural history of diminutive colorectal polyps: L ong‐term prospective observation by colonoscopy. Digestive Endoscopy. 2014 Apr;26:84-9.
Iwama T, Tamura K, Morita T, Hirai T, Hasegawa H, Koizumi K, Shirouzu K, Sugihara K, Yamamura T, Muto T, Utsunomiya J. A clinical overview of familial adenomatous polyposis derived from the database of the Polyposis Registry of Japan. International journal of clinical oncology. 2004 Aug;9:308-16.
Lee HW, Moon W, Park SJ, Park MI, Kim HH, Choi JM. Disappearance of a large pedunculated polyp after diagnostic colonoscopy. Endoscopy. 2013 Dec;45(S 02):E169-70.
Hofstad B, Vatn MH, Andersen SN, Huitfeldt HS, Rognum T, Larsen S, Osnes M. Growth of colorectal polyps: redetection and evaluation of unresected polyps for a period of three years. Gut. 1996 Sep 1;39(3):449-56.
Cravens E, Lehman GA. Disappearing rectal polyps. Gastrointestinal endoscopy. 1991 Jan 1;37(1):88-91.