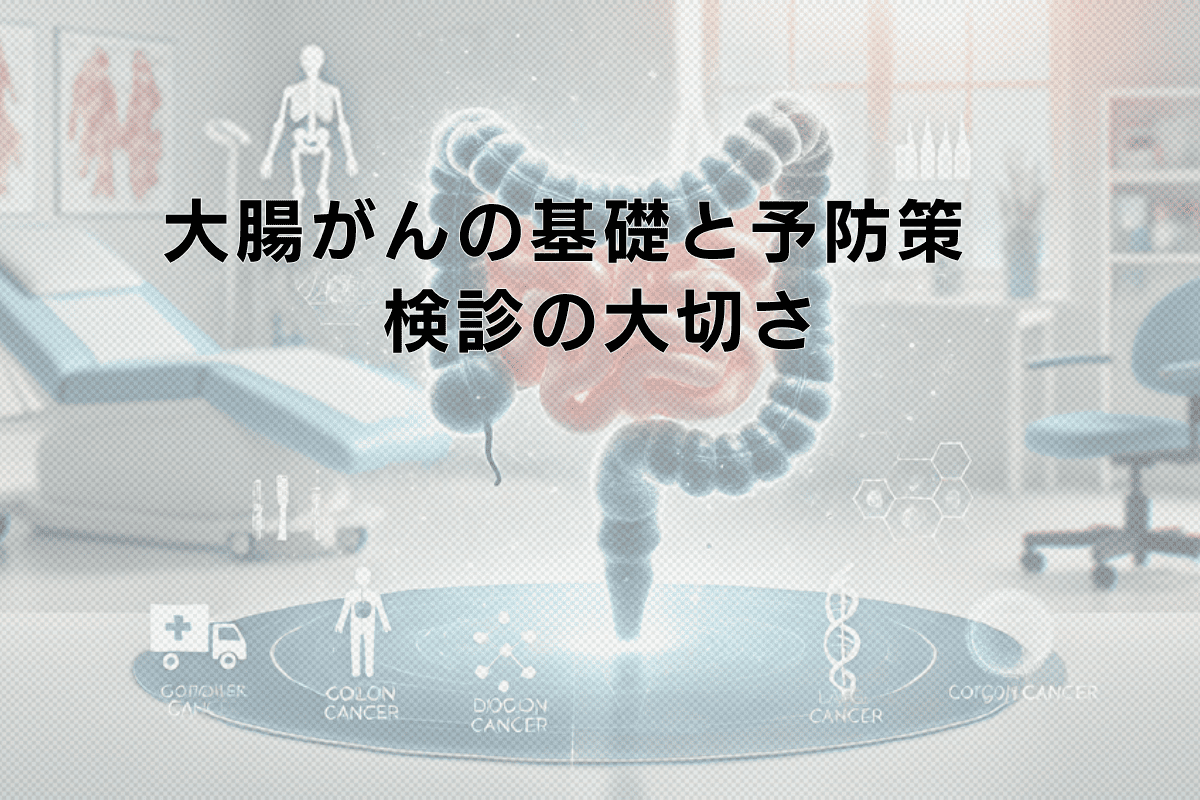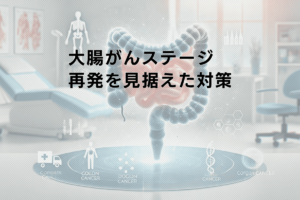大腸がんは結腸や直腸など、大腸の一部にがん細胞が発生する病気であり、日本でも多くの人が罹患しています。
以前と比べて食生活の変化や高齢化などにより、大腸がんが増える傾向にありますが、検診で早期発見できれば治療の選択肢が広がり、完治を目指しやすくなることも特徴です。
ここでは大腸がんの基礎知識から症状、検査、治療、再発に関する情報までを、できるだけわかりやすく紹介します。
大腸の仕組みとがんの発生
大腸がんを理解するためには、まず大腸の構造やどのようにがんが発生するのかを知ることが重要です。
大腸の中でも結腸や直腸など、部位ごとにがんの症状や転移の傾向、治療方法が異なりますが、共通して大腸粘膜の細胞が異常に増殖し、腫瘍を形成していく仕組みがあります。
大腸の役割を確認する
大腸は小腸から続く消化管の終末部分であり、水分を吸収して便を形成する重要な役割を担います。
大腸は全長がおおむね1.5~2mほどで、結腸(盲腸・上行結腸・横行結腸・下行結腸・S状結腸)と直腸、肛門管から構成されます。
ここで便を固形化して体外に排出するため、日々の排便習慣と深く関係しています。

がんの基本的な発生メカニズム
がんとは、細胞が正常な増殖の制御から逸脱し、無制限に増殖して腫瘍を作る病気です。
大腸がんの場合、粘膜上皮の細胞が遺伝子変異などによって腫瘍化し、初期の小さな病変(ポリープや腺腫など)から進行していくことが多いです。腸の壁深くまで浸潤したり、リンパ節や他の臓器へ転移を起こしたりする恐れがあります。
ポリープと大腸がんの関係
大腸がんの多くは、はじめ腺腫性ポリープと呼ばれる良性の小さな腫瘍から発生します。ポリープは粘膜が隆起した状態です。
サイズが大きくなるにつれてがん化リスクが高まる傾向があり、内視鏡検査で見つかったポリープの切除によって、大腸がんの発生を抑えることにつながる可能性があります。
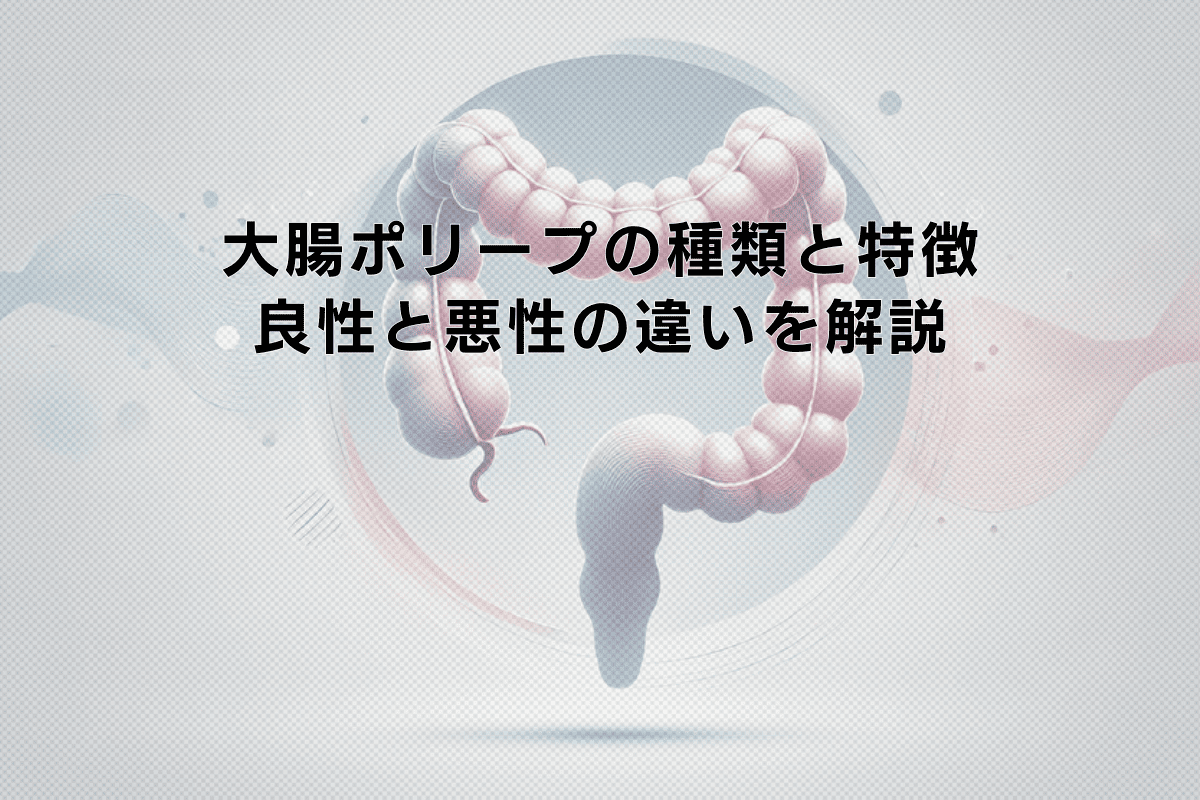
大腸の主な部位と特徴
| 部位 | 位置・役割 | 特徴 |
|---|---|---|
| 盲腸 | 小腸との接合部に近い | 虫垂が付属し、便の通過は比較的速い |
| 上行結腸 | 盲腸から右脇腹方向に伸びる部分 | 水分の吸収が盛んで便はやや液状 |
| 横行結腸 | 右から左へ腹部を横切る結腸の中央部分 | 大腸の中でも長めで屈曲が多い |
| 下行結腸 | 左脇腹を下向きに伸びる部分 | 便が固まってくる |
| S状結腸 | 骨盤内をS字形状で走る部分 | 便がより固形化して直腸へ移動する |
| 直腸 | S状結腸から肛門まで続く管状の部分 | 排便に関与し、肛門括約筋で制御される |
| 肛門管 | 直腸の末端で外部と通じる開口部 | 外括約筋・内括約筋により便の排泄を調整 |
大腸がんに影響するリスク要因
大腸がんは食生活の欧米化や肥満などと関連があると考えられていて、特に以下の習慣や体質はリスク上昇につながりやすいです。
- 肉中心の高脂肪食が多い
- 野菜や食物繊維が少ない食事
- 飲酒や喫煙の習慣
- 運動不足による肥満
- 遺伝的要因(リンチ症候群や家族性大腸腺腫症など)
大腸がんの主な症状とサイン
大腸がんは、早期の段階でははっきりした自覚症状がない場合が多いため、ある程度進行してから見つかるケースも少なくありません。ただし、体の変化を見逃さずにいることで、少しでも早く異常を発見できる可能性があります。
自覚しやすい症状例
- 便に血が混じる(血便)、あるいは便が黒ずむ
- 下痢や便秘を繰り返す、またはこれまでと便の性状が変わる
- 便が細くなり、量が少なく感じる
- 腹痛や腹部の張りが続く
- 貧血の症状(疲れやすさ、めまいなど)が出る
これらの症状は大腸がん以外の腸疾患や痔などでも起こるため、一概にがんだけを疑う必要はありませんが、気になる症状が持続したり悪化したりする場合は早めに医療機関を受診することが大切です。
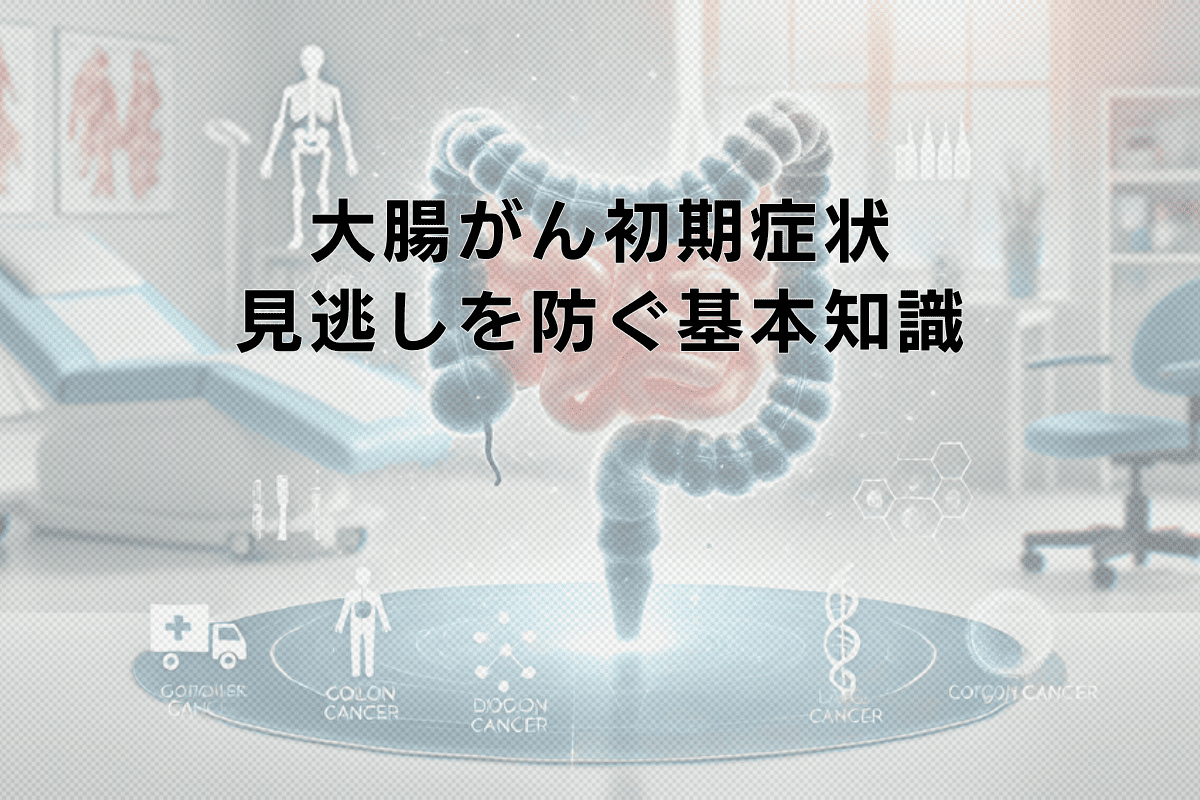
結腸がんと直腸がんの違い
大腸がんと一口にいっても、結腸(特に横行結腸やS状結腸)に生じる場合と、直腸に生じる場合で症状がやや異なることがあります。
例えば結腸の右側(盲腸や上行結腸)にがんができると便がまだ液状で通過が早いため、血便が目立ちにくく、貧血が進んで初めて気づくケースがあります。
一方、左側(下行結腸やS状結腸)や直腸にがんがある場合は便が固形化しており、通過障害を起こしやすく血便や便秘・腹痛などの症状を感じやすいです。

大腸がんの主な症状と関連部位
| 症状 | 関連しやすい部位 | 特徴 |
|---|---|---|
| 血便 | 下行結腸・S状結腸、直腸 | 鮮血が付着しやすい |
| 下痢・便秘 | 横行結腸・左側結腸、直腸 | 便の通過障害が生じると便秘や下痢が交互に起きる |
| 腹痛・腹部膨満感 | どの部位でも起こりうる | がんによる腸管狭窄で痛みや膨満感が続く |
| 貧血 | 右側結腸(盲腸、上行結腸など) | 血便が目立ちにくいかわりに貧血で気づくことが多い |
注意したい便の変化
大腸がんが進行すると、腫瘍が大きくなって腸管内を狭くしたり、粘膜から出血を伴ったりするため、便の見た目や量に変化が生じやすいです。具体的には便が細くなる、粘液が混じる、鮮血が表面に付着するなどがあります。
腹痛と体重減少
進行性の大腸がんでは腫瘍が腸管を狭くすることで腸閉塞(イレウス)のリスクが高まるほか、腫瘍からの出血や体力の消耗によって体重減少を引き起こすことがあります。
普段と比べて急に食事量が変わっていないのに体重が減る場合も、念のため医師に相談するとよいでしょう。

大腸がんの診断と検査方法
大腸がんの疑いがある場合や、症状が現れないうちに早期発見をめざすには、いくつかの検査方法があります。なかでも大腸内視鏡検査は粘膜を直接観察でき、生検やポリープ切除も行えるため有力な手段です。

便潜血検査
便の中に肉眼では見えない微量の血液が含まれているかを調べる検査で、大腸がん検診の代表的な方法です。
陽性であれば大腸内視鏡検査などの精密検査に進む必要があります。
ただし、簡易的かつ費用が比較的安い反面、痔やほかの腸疾患でも陽性となる場合があります。
また陰性でもがんがないとは限らないため、腹痛や便秘・下痢などの腹部症状があれば、陰性でも大腸内視鏡検査を受けることをお勧めします。
大腸がん検査の主な種類
| 検査名 | 方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 便潜血反応検査 | 便を採取し、血液の有無を調べる | スクリーニングとして広く実施、陽性時は追加検査が必要 |
| 注腸造影検査 | バリウムなどの造影剤を大腸に注入しX線撮影 | 粘膜の表面形状がわかるが、小さな病変の発見には限界あり |
| 大腸内視鏡検査 | 内視鏡を肛門から挿入して大腸を直接観察 | 病変があれば生検やポリープ切除が可能、最も精密な検査方法 |
| CTコロノグラフィ | CTを使い、大腸の3D画像を作って観察 | 内視鏡挿入なしで大腸内部を疑似的に可視化、病変があれば内視鏡検査が必要 |
大腸内視鏡検査
肛門からスコープを挿入し、大腸全体の粘膜を直接観察し、小さなポリープや粘膜の細かい変化も見つけやすく、疑わしい病変があればその場で組織採取(生検)を行い、確定診断を目指します。
さらに、腺腫性ポリープなどが発見されれば、内視鏡で切除することが可能であり、将来のがん化を防ぐ手立てになります。

病理検査による確定診断
内視鏡検査や手術で採取した組織を顕微鏡で観察し、がん細胞の特徴を調べるのが病理検査です。
組織学的にがん細胞が確認されれば大腸がんと確定診断され、がんの種類や分化度などを調べることで、進行度や治療方針の検討に役立ちます。
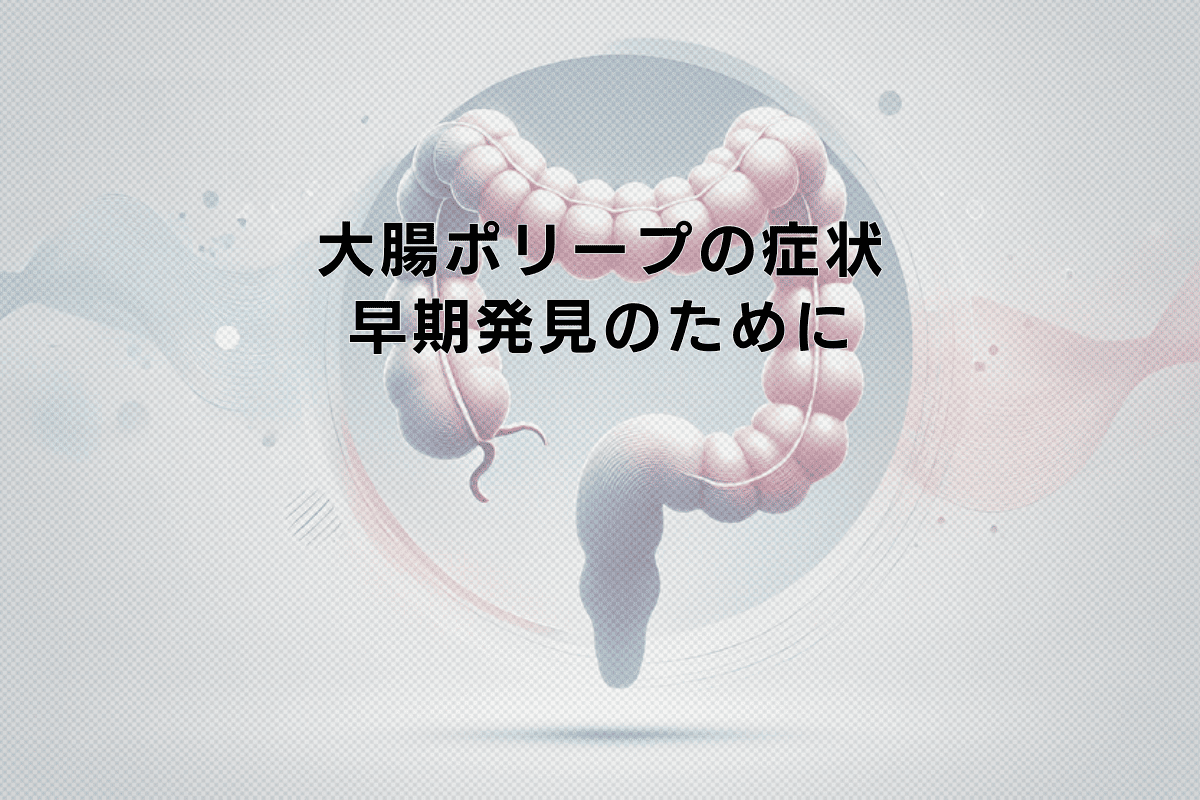
進行度を調べる検査
大腸がんと確定した後は、CTやMRI、PET-CTなどの画像検査で腸壁の浸潤度やリンパ節転移、他臓器への転移の有無を調べます。
これによってがんのステージを分類し、手術か内視鏡治療か、または化学療法や放射線治療を組み合わせるかなど、具体的な治療計画を立てることが可能です。
大腸がんのステージ分類と進行
大腸がんは、腫瘍の深達度やリンパ節転移、遠隔転移の有無などを総合してステージが決まり、ステージはI~IVの4段階で表され、治療の選択や予後の見通しに影響を与えます。
ステージ分類の目安
- ステージI:腫瘍が粘膜や筋層の浅い部分にとどまる
- ステージII:腸壁の深いところまで浸潤するがリンパ節転移はない
- ステージIII:腫瘍が深く浸潤し、リンパ節への転移がある
- ステージIV:遠隔臓器(肝臓、肺など)への転移が見られる
大腸がんのステージ分類(概略)
| ステージ | 腫瘍の深達度 | リンパ節転移 | 遠隔転移 |
|---|---|---|---|
| I | 粘膜下層~筋層まで | なし | なし |
| II | 腸壁の筋層より深いところまで | なし | なし |
| III | いずれの深達度でも | あり | なし |
| IV | いずれの深達度でも | ありまたはなし | あり |
進行度と治療方針
早期(ステージIや一部のステージII)であれば内視鏡治療や外科手術のみで十分対応できるケースがあります。
ステージIIIでは手術と合わせて化学療法を行うことがあり、ステージIVで遠隔転移がある場合は、外科治療だけで根治が難しい場合もあるため、化学療法や放射線療法を組み合わせるなど多角的なアプローチを取ります。
リンパ節転移と多臓器転移
大腸がんが進行すると、リンパ節へ転移しやすくなります。
また、大腸以外の臓器へも転移することがあり、血流を介した血行性転移では肝転移が最も多いです。
転移の有無は治療方針に大きく影響し、外科的切除が可能かどうかを慎重に検討する必要があります。
早期発見のメリット
早期段階(腸粘膜内、粘膜下層までの浸潤など)で大腸がんが見つかった場合、内視鏡切除だけで完治に至る可能性があります。
大きく浸潤していなければリンパ節転移リスクも低いため、外科手術を回避できるケースもあるため、大腸内視鏡検査を定期的に受けることは大きな意味を持ちます。
大腸がんの治療方法と特徴
大腸がんの治療は、病期や患者の全身状態、腫瘍の部位などによって異なり、代表的な治療は、内視鏡による切除、外科手術、化学療法、放射線療法などです。
内視鏡治療
粘膜内、または粘膜下層のごく浅い部分までにとどまる早期がんでは、大腸内視鏡を用いた内視鏡切除(ポリペクトミー、内視鏡的粘膜切除術(EMR)、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)など)が有力な選択肢です。
これにより開腹手術をしなくてもがんを切除できる可能性があります。
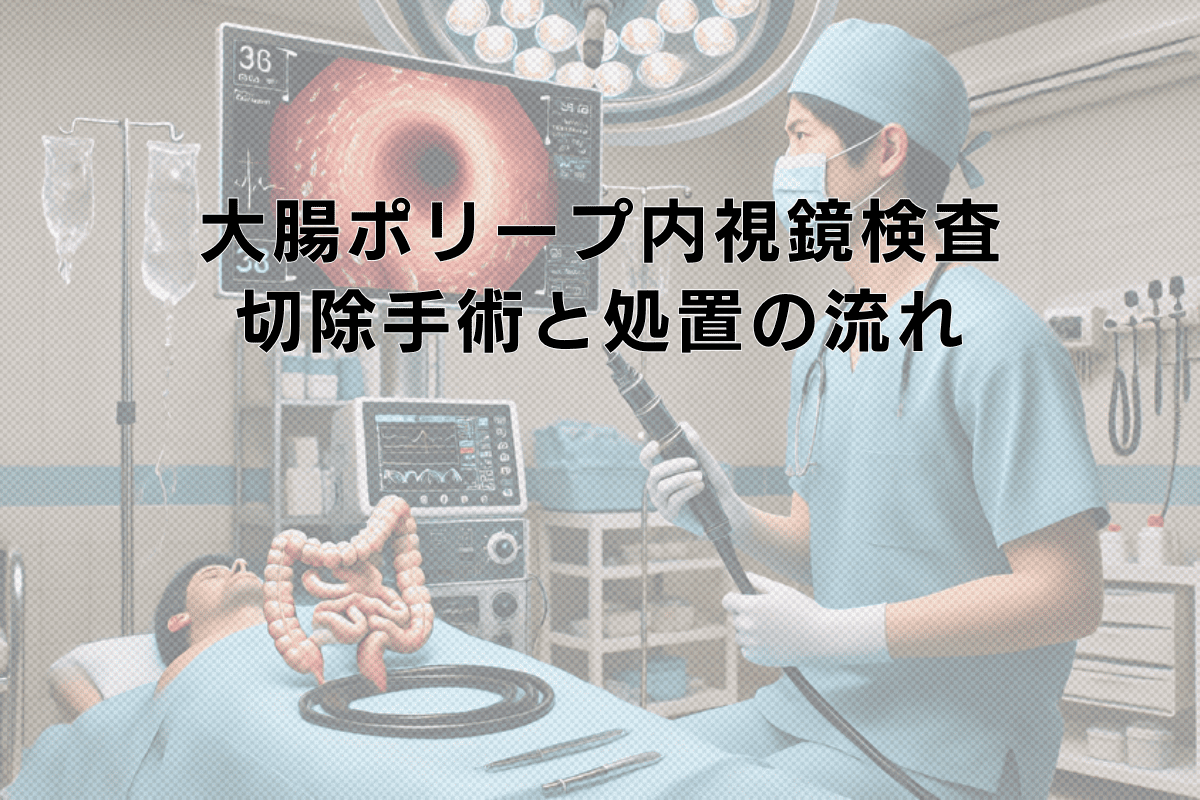
大腸がんの主な治療方法
| 治療法 | 方法 | 適応 |
|---|---|---|
| 内視鏡切除 | 内視鏡下でポリープや粘膜を切除 | 早期がん(粘膜内または粘膜下層浅い浸潤) |
| 外科手術 | 結腸や直腸の一部を切除、リンパ節郭清も行う | 進行がん(リンパ節転移ありなど) |
| 化学療法 | 抗がん薬を使用し、がん細胞の増殖を抑制 | 手術後の再発予防や転移がある場合など |
| 放射線療法 | 放射線を照射し、腫瘍を縮小または消滅させる | 直腸がんの手術前後や局所再発がある場合など |
| 分子標的薬 | がん細胞の特定の分子を標的とする薬 | 化学療法と組み合わせ、再発や転移例で活用 |
外科手術
進行した大腸がんでは、腫瘍を含む大腸の一部と、その付近のリンパ節を切除する外科手術が基本です。
結腸がんなら結腸切除、直腸がんなら直腸切除が行われますが、腫瘍の位置によっては肛門を温存できるかどうかが変わり、直腸の下部にがんがある場合、人工肛門(ストーマ)を造設する可能性もあります。
化学療法
手術後の再発防止や、手術が難しいステージの治療に抗がん薬が用いられ、近年は分子標的薬を併用するケースもあり、腫瘍の成長に関わる特定の分子を狙って効果を高める方法が進んでいます。
化学療法は副作用が問題になることがあるため、患者さんの体力や副作用対策を踏まえて治療計画を立てます。
放射線療法
直腸がんでは、腫瘍が骨盤腔内にあるため、放射線が照射しやすい環境にあり、術前または術後に放射線療法を組み合わせることで、腫瘍を縮小させたり局所再発を防いだりする効果が期待できます。
結腸がんでは骨盤内に位置しないため、放射線療法を行うことは少ないです。
再発と経過観察の重要性
大腸がんの治療を終えても、再発や新たな病変が発生する可能性があり、ステージIII以上だった場合や複数のリンパ節に転移が確認された場合は再発リスクが高まるため、術後の経過観察が重要です。
再発のパターン
大腸がんが再発する場合、大腸内の手術部位近くに局所再発するケースや、肝臓や肺などの遠隔転移として再発するケースがあり、再発時には再度手術や化学療法、放射線療法など、がんの部位や患者の状態に応じた治療が検討されます。
大腸がん再発リスクに影響する要因
| 要因 | リスクへの影響 |
|---|---|
| ステージ(深達度、リンパ節転移数など) | 進行度が高いほど再発リスクが上がる |
| 腫瘍の分化度 | 低分化型がんほど再発しやすい可能性がある |
| 血管・リンパ管侵襲の有無 | 浸潤がある場合、転移リスクが高まる |
| 遺伝的要因 | 遺伝性疾患を持つ場合、再発や多発性がんに注意 |
| 化学療法の併用状況 | 適切な化学療法が施されたかどうか |
術後のフォローアップ
大腸がん手術後や内視鏡切除後も、定期的な大腸内視鏡検査や画像検査、血液検査(腫瘍マーカーなど)を受けることで早期再発を見逃さないようにします。
フォローアップの頻度はステージや治療内容、患者の年齢などによって異なりますが、一般的には術後5年程度は注意深く経過を追うことが推奨されています。
生活習慣の見直し
大腸がんの治療後は、再発予防の観点から食生活や運動習慣の見直しが推奨されます。
高脂肪や高カロリーの食事を控え、野菜や果物、食物繊維を多く摂るなどの心がけは、がんのリスクを下げるだけでなく、全身の健康維持にも役立ち、また、喫煙や過度の飲酒も控えてください。
術後の生活習慣チェック
- 食事:野菜や果物、魚中心でバランスよく
- 運動:適度な有酸素運動や筋肉トレーニング
- 体重管理:肥満や急激な体重増加に注意
- 禁煙:タバコはがんリスクを上げる大きな要因
- 節酒:適量の飲酒を心がけ、過度な飲酒は控える
大腸がんの予防と検診の活用
大腸がんは検診や内視鏡検査によって比較的早期に発見できるがんの1つとされ、多くの地域や企業でも大腸がん検診が実施されています。定期的な検診を受けることは、症状のない段階での発見につながりやすいです。
大腸がん検診の仕組み
多くの場合、40歳以上や特定の年齢層を対象に便潜血検査が行われ、陽性の場合は精密検査として大腸内視鏡検査などが行われます。
便潜血検査は簡便で費用も抑えられるため、広く普及していますが、陰性だからといって絶対安心とはいえない点に注意が必要です。
検診の大まかな流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 便潜血検査 | 2日法などで2回分の便を検体とする |
| 2. 結果判定 | 陰性か陽性かを判定 |
| 3. 陽性の場合 | 大腸内視鏡検査などで精密検査 |
| 4. 異常なし | 次回の定期検診を受ける |
検診と年齢・家族歴
大腸がんは50歳代から増加し始めるため、この年代以降は意識的に検診を受けることが望ましいです。
さらに、家族に大腸がんの既往歴がある場合は、遺伝的要因や生活習慣などでリスクが高いと考えられるため、40歳未満であっても早めに検診をスタートすることが検討されます。
生活習慣による予防策
生活習慣を改善することで、大腸がんリスクをある程度下げることが期待されます。
肉類や脂肪の摂取を控えめにし、食物繊維を多く含む野菜や豆類を積極的に摂取すること、適度な運動で腸の動きを促進し、定期的な排便を維持することは大腸の健康に役立ちます。
便通異常に早く気づく
大腸がんだけでなく、炎症性腸疾患など、消化器の病気は便通に変化が現れるケースが多く、便秘、下痢、血便、粘液便、便が細くなるなどの異常が続くようなら、早めに受診して検査を受けることが大切です。
大腸がんとの向き合い方
最後に、大腸がんとの向き合い方として、患者さん自身が情報を得る方法や医療者とのコミュニケーション、日常生活の工夫などを紹介します。
治療選択に関する情報収集
大腸がんと診断された場合、医師の説明を聞くだけでなく、自分でも病気や治療法の情報を整理することが大切です。
信頼性の高い医療機関のウェブサイトやがん専門の公的機関の情報を活用し、わからない点があれば遠慮なく主治医に質問しましょう。
大腸がん情報を得る手段
- 医療機関の公式サイトやパンフレット
- 国立がん研究センターや日本医師会など公的機関の資料
- 認定NPO法人や患者会の発行する情報
- 学会や専門医が監修する書籍
セカンドオピニオンの検討
手術や化学療法など大きな治療方針を決める段階で、迷いや不安がある場合は別の医療機関でセカンドオピニオンを求めることも選択肢の1つです。
ただし、時間的猶予が限られるケースもあるため、主治医とも相談しつつ判断してください。
食事や生活リズムの工夫
大腸がんの治療中や術後は、消化器に負担をかけない食事を心がけるなど、日常生活の工夫が必要となる場合があり、下痢や便秘が続くようなら、医師や管理栄養士に相談して食事内容を調整することも大切です。
適度な運動で体力を維持することも、治療を乗り越えるうえで役立ちます。
家族や周囲のサポート
大腸がんの治療期間や再発予防のための通院は長期にわたることがあり、家族や友人のサポート、職場での理解などが得られると、治療を続けやすくなります。
周囲に支援を求めることを遠慮せず、自分の状態や必要な助けを具体的に伝えることも重要です。
生活面で意識したいポイント
- 食事量や食材の選び方:消化に良いものを中心に、バランス良く
- 適度な運動:散歩や軽い筋力トレーニングで体力維持
- ストレスマネジメント:趣味やリラクゼーションを取り入れる
- 定期通院・検査:再発や新たな病変の早期発見
- 周囲への相談:治療計画や休職・復職のタイミングなど
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査とはどのような検査なのか】
大腸がんの基礎知識について理解できたら、次は実際の検査方法について、この記事で一緒に勉強してまいりましょう。検査を受けることを検討している方や検査に不安を感じている方に特におすすめです。
【大腸がん初期症状の見逃しを防ぐ 便の変化や腹痛の基本知識】
大腸がんについての基礎的な理解が深まりましたら、さらに早期発見のためのサインの見分け方についても知っておくと、より実践的な健康管理につながります。この記事で一緒に学んでまいりましょう。
参考文献
Nakagawa-Senda H, Hori M, Matsuda T, Ito H. Prognostic impact of tumor location in colon cancer: the Monitoring of Cancer Incidence in Japan (MCIJ) project. BMC cancer. 2019 Dec;19:1-9.
Takada H, Ohsawa T, Iwamoto S, Yoshida R, Nakano M, Imada S, Yoshioka K, Okuno M, Masuya Y, Hasegawa K, Kamano N. Changing site distribution of colorectal cancer in Japan. Diseases of the colon & rectum. 2002 Sep 1;45(9):1249-54.
Hashiguchi Y, Muro K, Saito Y, Ito Y, Ajioka Y, Hamaguchi T, Hasegawa K, Hotta K, Ishida H, Ishiguro M, Ishihara S. Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum (JSCCR) guidelines 2019 for the treatment of colorectal cancer. International journal of clinical oncology. 2020 Jan;25:1-42.
Kobayashi H, West NP, Takahashi K, Perrakis A, Weber K, Hohenberger W, Quirke P, Sugihara K. Quality of surgery for stage III colon cancer: comparison between England, Germany, and Japan. Annals of surgical oncology. 2014 Jun;21:398-404.
Watanabe T, Muro K, Ajioka Y, Hashiguchi Y, Ito Y, Saito Y, Hamaguchi T, Ishida H, Ishiguro M, Ishihara S, Kanemitsu Y. Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum (JSCCR) guidelines 2016 for the treatment of colorectal cancer. International journal of clinical oncology. 2018 Feb;23:1-34.
Kono S. Secular trend of colon cancer incidence and mortality in relation to fat and meat intake in Japan. European journal of cancer prevention. 2004 Apr 1;13(2):127-32.
Oba S, Shimizu N, Nagata C, Shimizu H, Kametani M, Takeyama N, Ohnuma T, Matsushita S. The relationship between the consumption of meat, fat, and coffee and the risk of colon cancer: a prospective study in Japan. Cancer letters. 2006 Dec 8;244(2):260-7.
Tamakoshi K, Wakai K, Kojima M, Watanabe Y, Hayakawa N, Toyoshima H, Yatsuya H, Kondo T, Tokudome S, Hashimoto S, Suzuki K. A prospective study of body size and colon cancer mortality in Japan: The JACC Study. International journal of obesity. 2004 Apr;28(4):551-8.
Yamamoto S, Inomata M, Katayama H, Mizusawa J, Etoh T, Konishi F, Sugihara K, Watanabe M, Moriya Y, Kitano S, Japan Clinical Oncology Group Colorectal Cancer Study Group. Short-term surgical outcomes from a randomized controlled trial to evaluate laparoscopic and open D3 dissection for stage II/III colon cancer: Japan Clinical Oncology Group Study JCOG 0404.
Yamauchi S, Hanaoka M, Iwata N, Masuda T, Tokunaga M, Kinugasa Y. Robotic-assisted surgery: expanding indication to colon cancer in Japan. Journal of the Anus, Rectum and Colon. 2022 Apr 27;6(2):77-82.