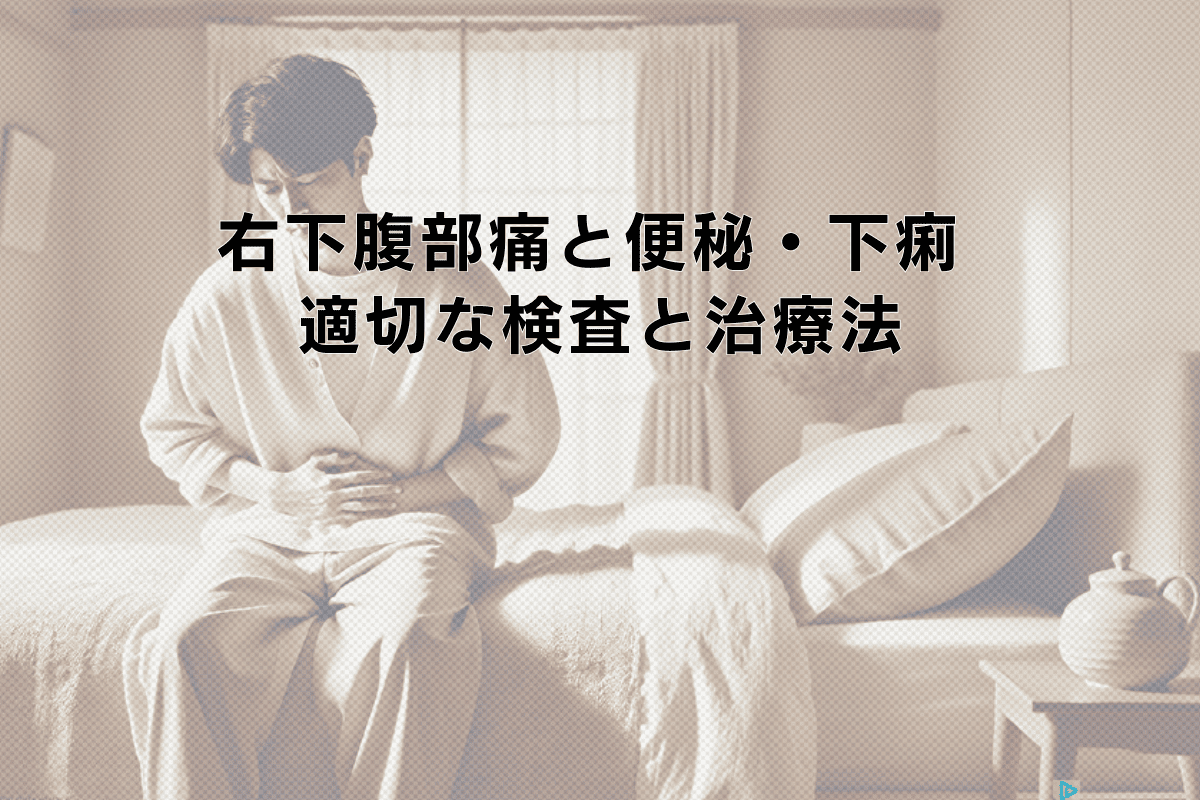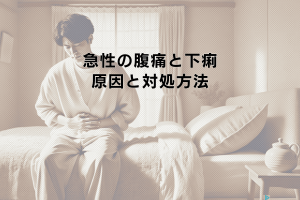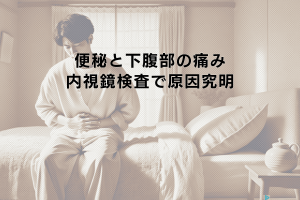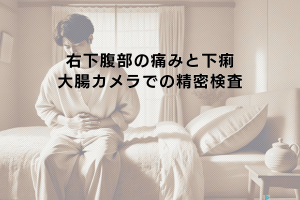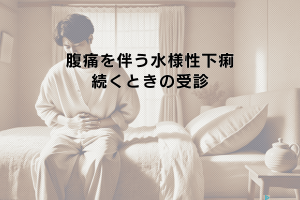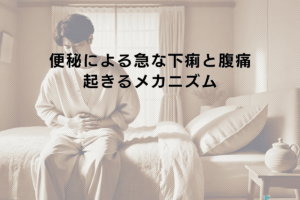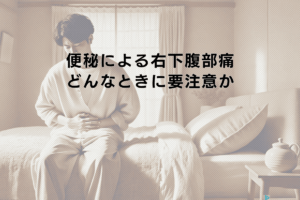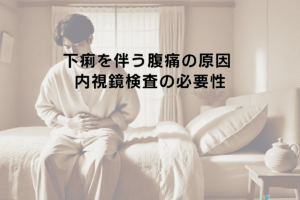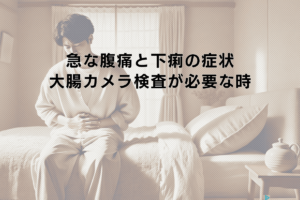右下腹部に痛みを感じ、それに伴って便秘や下痢の症状が現れると、多くの方が不安を感じるでしょう。この症状は、様々な消化器系の病気のサインである可能性があります。
ここでは、右下腹部の痛みを伴う便秘や下痢について、考えられる原因、医療機関で行う検査、治療法について詳しく解説します。
症状が続く場合は、自己判断せずに、お近くの医療機関にご相談ください。

右下腹部痛と便秘・下痢の基礎知識
右下腹部の痛みや便通異常は、多くの方が一度は経験するかもしれない症状ですが、症状が何を意味するのか、正確に理解している方は少ないかもしれません。
右下腹部とはどの範囲か
人間の腹部は、いくつかの領域に分けて位置を表現し、右下腹部とは、おへそを中心として体を縦横に四分割した際、右下の領域で、右の腰骨の内側あたりから、足の付け根に近い部分までを含む範囲です。
この領域には、大腸の一部(盲腸、虫垂、上行結腸)、小腸の末端部分、女性の場合は右の卵巣や卵管、男女共通で尿管などが位置していて、臓器のいずれかに異常が生じると、右下腹部に痛みを感じます。
右下腹部に位置する主な臓器
| 臓器名 | 主な機能 | 関連する可能性のある症状例 |
|---|---|---|
| 虫垂 | リンパ組織が集まる | 右下腹部痛、発熱、吐き気 |
| 大腸(盲腸、上行結腸) | 水分吸収、便の形成 | 便秘、下痢、腹痛、腹部膨満感 |
| 小腸(回腸末端) | 栄養吸収 | 下痢、腹痛、体重減少 |
便秘の定義と症状
便秘とは一般的に、3日以上排便がない状態、または毎日排便があっても残便感がある状態を指しますが、排便の頻度には個人差があるため、一概に日数だけで定義するのは難しい側面もあります。
便秘に伴う主な症状としては、腹痛、腹部膨満感、食欲不振、吐き気などがあり、また、硬い便を無理に出そうとすることで、痔の原因になることもあります。
下痢の定義と症状
下痢とは、便中の水分量が異常に増加し、泥状便や水様便が頻回に排出される状態です。
下痢の原因は多岐にわたり、ウイルスや細菌による感染、食べ過ぎや飲み過ぎ、ストレス、特定の薬剤の副作用、あるいは何らかの病気の一症状として現れることがあります。
下痢に伴う症状としては、腹痛、腹部不快感、発熱、吐き気、嘔吐などがあり、脱水症状を起こすこともあるため注意が必要です。
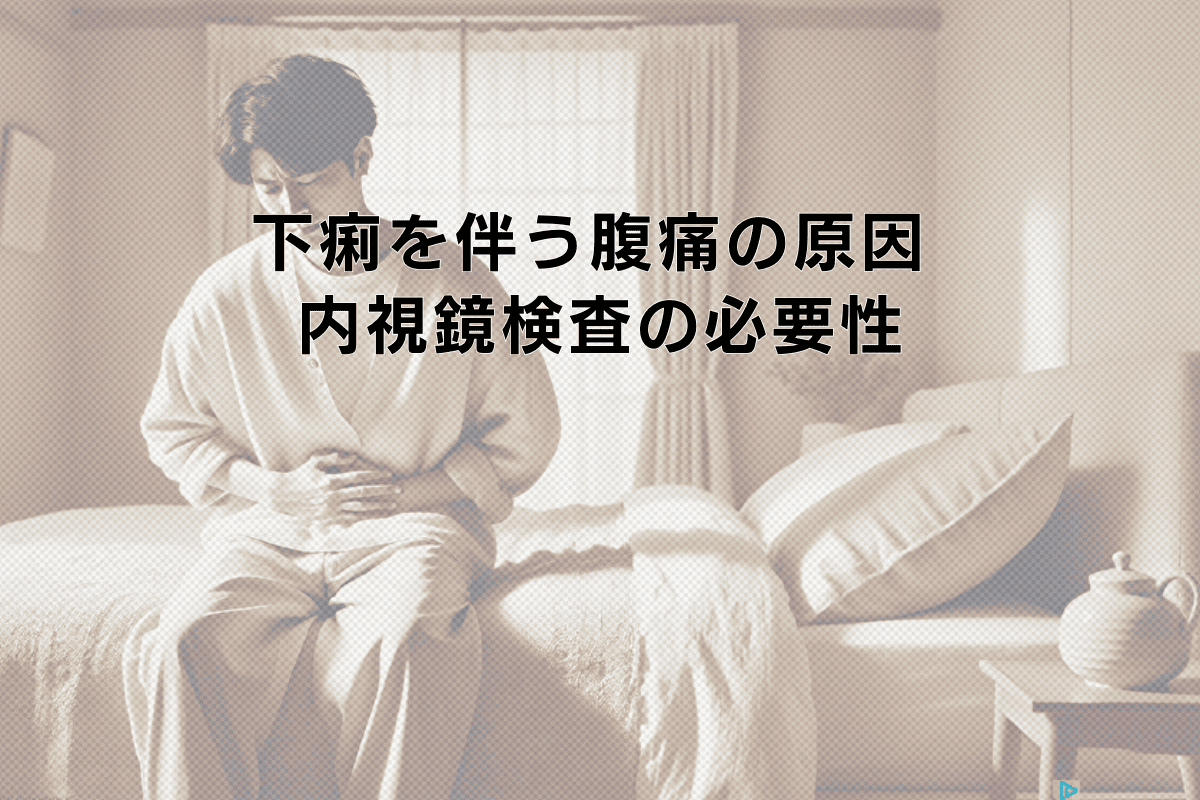
右下腹部痛と便秘・下痢が同時に起こる意味
右下腹部の痛みに加えて、便秘または下痢の症状が同時に見られる場合、消化管、特に大腸や小腸の機能的あるいは器質的な問題が考えられます。
例えば、腸の動きが悪くなると便秘になりやすく、炎症が起これば下痢や痛みを起こすことがあり、症状が組み合わさることで、原因となっている病態を推測する手がかりとなる場合があります。
しかし、自己判断は禁物であり、症状が続く場合は専門医の診察を受けることが大切です。
右下腹部痛と便秘を伴う場合に考えられる主な原因
右下腹部の痛みに便秘が伴う場合、いくつかの疾患が考えられます。
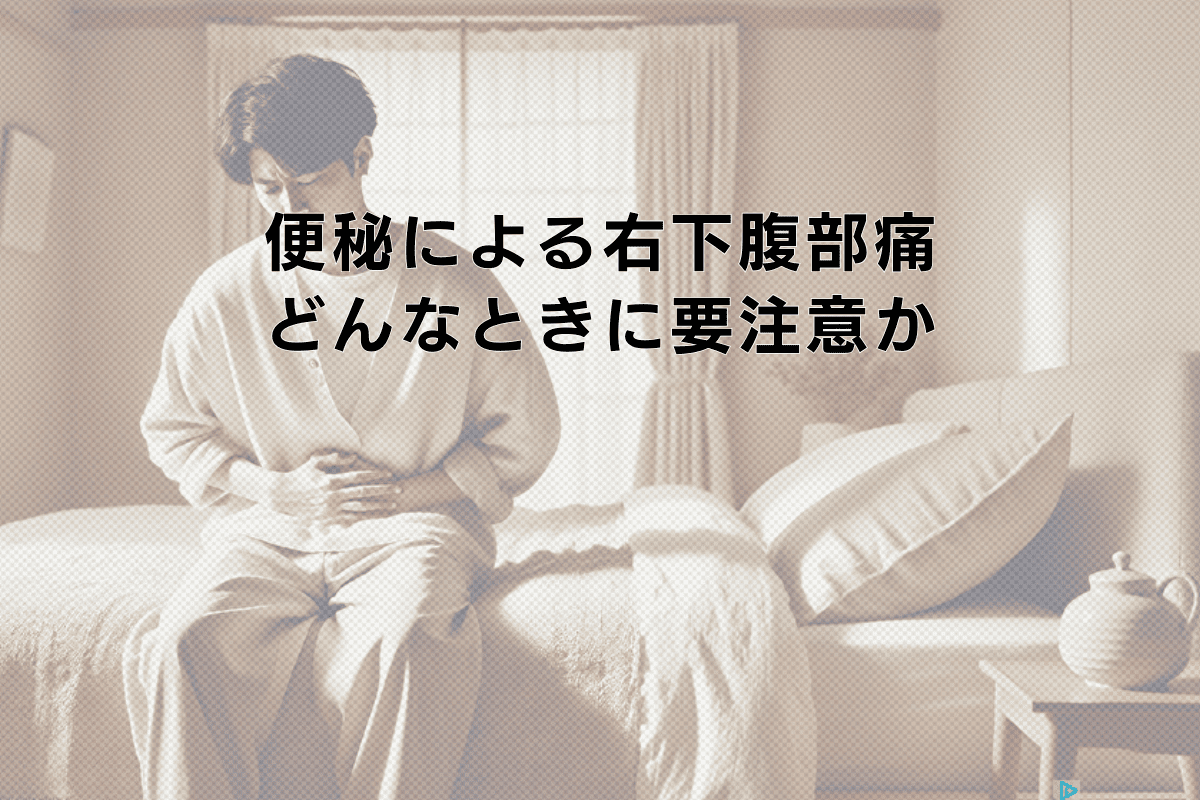
急性虫垂炎(盲腸)
急性虫垂炎は、盲腸として知られていますが、正確には盲腸の先にある虫垂という小さな突起に炎症が起こる病気で、初期症状として、みぞおちの痛みや吐き気が現れ、時間経過とともに痛みが右下腹部へ移動します。
発熱や食欲不振を伴うこともあります。虫垂炎が進行すると、便の通過が悪くなり便秘傾向になることがあり、炎症が腹膜に広がると腹膜炎という重篤な状態になる可能性があるため、早期の診断と治療が重要です。
便秘症
便秘症そのものが、右下腹部痛の原因となることがあり、腸内に便が長期間滞留すると、腸が過度に張ったり、腸内細菌のバランスが崩れたりして、腹痛や不快感を起こします。
特にS状結腸や直腸に便が溜まりやすいですが、上行結腸など右側の大腸に便が溜まることでも右下腹部痛を感じることがあります。
便秘症の主な種類と特徴
| 便秘の種類 | 主な特徴 | 考えられる原因 |
|---|---|---|
| 弛緩性便秘 | 大腸の運動機能が低下し、便を押し出す力が弱くなる | 運動不足、加齢、食物繊維不足 |
| 痙攣性便秘 | ストレスなどで大腸が過緊張し、便の通りが悪くなる | 精神的ストレス、環境の変化 |
| 直腸性便秘 | 便が直腸まで来ても便意を感じにくい | 排便の我慢、加齢 |
大腸憩室炎
大腸憩室とは、大腸の壁の一部が外側に袋状に飛び出したもので、憩室に便などが詰まり、細菌感染を起こして炎症が生じた状態が大腸憩室炎です。
大腸のどの部分にも憩室はできますが、日本人では右側の大腸(上行結腸や盲腸)に多く、症状としては、腹痛(多くは憩室のある部位)、発熱、吐き気などが見られます。
炎症の程度によっては便秘を起こしたり、重症化すると穿孔(腸に穴が開くこと)や膿瘍(膿のたまり)を形成することもあります。
感染性腸炎
細菌やウイルスなどの病原体に感染することで起こる腸炎で、原因となる病原体によって症状は異なりますが、一般的に腹痛、下痢、発熱、嘔吐などが主な症状です。
しかし、病原体の種類や感染部位、炎症の程度によっては、初期に便秘傾向を示し、その後下痢に移行したり、右下腹部に限局した痛みとして感じられたりすることもあります。
特に、腸の動きが一時的に麻痺するような状態になると、便秘と腹痛が目立つことがあります。
右下腹部痛と下痢を伴う場合に考えられる主な原因
右下腹部の痛みに下痢が伴う場合も、様々な原因が考えられ、感染症から慢性的な炎症性疾患まで、幅広く考慮する必要があります。
感染性腸炎
前述の通り、感染性腸炎は下痢の代表的なもので、サルモネラ菌、カンピロバクター、ノロウイルス、ロタウイルスなど、多くの病原体が原因です。
病原体が小腸や大腸に感染し炎症を起こすと、腸管からの水分分泌が過剰になったり、水分吸収が妨げられたりして下痢を起こします。
炎症が右側の大腸や小腸末端に強い場合、右下腹部痛が顕著になることがあり、多くは数日から1週間程度で自然に軽快しますが、脱水症状や症状の悪化には注意が必要です。
炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎)
炎症性腸疾患は、腸に慢性的な炎症や潰瘍が生じる原因不明の病気で、主にクローン病と潰瘍性大腸炎があり、遺伝的な要因や免疫系の異常、腸内細菌叢の変化、食生活などが複雑に関与して発症すると考えられています。
クローン病は、口腔から肛門までの消化管のあらゆる部位に炎症が起こりうる病気で、小腸の末端(回腸)や大腸に好発し、右下腹部に位置する回腸末端に病変があると、右下腹部痛や下痢、体重減少、発熱などの症状が現れます。
潰瘍性大腸炎は、主に大腸の粘膜に炎症や潰瘍が生じる病気で、多くは直腸から連続的に上方へ炎症が広がりますが、病変の範囲によっては右側の大腸にも影響が及び、主な症状は、粘血便(粘液や血液の混じった便)、下痢、腹痛です。
クローン病と潰瘍性大腸炎の比較
| 項目 | クローン病 | 潰瘍性大腸炎 |
|---|---|---|
| 主な炎症部位 | 消化管全体(特に小腸末端、大腸) | 大腸(特に直腸から連続的に広がる) |
| 炎症の深さ | 腸壁の全層に及ぶことがある | 主に粘膜層 |
| 主な症状 | 腹痛、下痢、体重減少、発熱 | 粘血便、下痢、腹痛 |
過敏性腸症候群(IBS)
過敏性腸症候群は、腸に明らかな炎症や潰瘍などの器質的な異常がないにもかかわらず、腹痛や腹部不快感、便通異常(下痢、便秘、またはその両方)が慢性的に続く病気です。
ストレスや生活習慣の乱れ、腸内細菌叢の変化などが関与していると考えられていて、下痢型、便秘型、混合型、分類不能型があり、下痢型の場合、ストレスを感じた時などに急な腹痛とともに下痢が起こることがあります。
薬剤性腸炎
特定の薬剤の副作用として腸炎が起こり、腹痛や下痢を起こすことがあり、代表的なものは、抗生物質による偽膜性腸炎です。
抗生物質の使用によって腸内細菌のバランスが崩れ、クロストリジウム・ディフィシルという菌が異常増殖して毒素を産生することで発症します。
また、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)なども、長期使用により腸粘膜を障害し、潰瘍や炎症を起こすことがあり、原因となる薬剤を特定し、中止または変更することが治療の基本です。
女性特有の原因と注意点
女性の場合、右下腹部痛の原因として婦人科系の疾患も考慮に入れ、消化器系の症状と似ている場合もあるため、注意深い鑑別が必要です。
卵巣の病気(卵巣嚢腫、卵巣出血、卵巣捻転など)
右側の卵巣に何らかの異常が生じると、右下腹部痛の原因となります。
卵巣嚢腫は、卵巣内に液体や脂肪などが溜まって腫れる病気で、小さなうちは無症状のことが多いですが、大きくなったり、茎捻転(卵巣がお腹の中でねじれること)を起こしたりすると、急激な下腹部痛が生じます。
卵巣出血は、排卵時などに卵巣から出血するもので、出血量が多いと腹痛を起こし、卵巣茎捻転は緊急手術が必要です。
子宮内膜症
子宮内膜症は、子宮内膜またはそれに似た組織が、子宮の内側以外の場所(卵巣、腹膜、ダグラス窩など)で発生し、増殖する病気です。
月経周期に伴って出血や炎症を繰り返し、月経痛、下腹部痛、腰痛、性交痛、排便痛などの症状を起こし、右側の卵巣や骨盤腹膜に病変があると、右下腹部痛の原因となることがあります。
骨盤内炎症性疾患(PID)
骨盤内炎症性疾患は、子宮、卵管、卵巣などの骨盤内の臓器に細菌などが感染して炎症を起こす病気の総称で、性感染症(クラミジア、淋菌など)が主な原因です。
症状としては、下腹部痛(片側または両側)、発熱、おりものの異常などが見られ、炎症が右側の卵管や卵巣に及ぶと、右下腹部痛として感じられます。
治療が遅れると、卵管の閉塞や癒着を起こし、不妊症や異所性妊娠(子宮外妊娠)のリスクを高めます。
骨盤内炎症性疾患の主な症状
- 下腹部痛(片側または両側)
- 発熱、悪寒
- おりものの量の増加や性状の変化(色、臭いなど)
- 不正性器出血
- 性交痛
妊娠初期の可能性
妊娠可能な年齢の女性で、右下腹部痛と便秘または下痢が見られる場合、妊娠の可能性も考慮する必要があり、妊娠初期には、ホルモンバランスの変化により便秘や下痢を起こしやすくなることがあります。
また、子宮が大きくなる過程で靭帯が引っ張られて下腹部痛を感じることもありますす。
異所性妊娠(子宮外妊娠)は、受精卵が子宮内膜以外の場所(主に卵管)に着床する状態で、卵管破裂などを起こすと激しい腹痛や腹腔内出血をきたし、生命に関わることもあるため、特に注意が必要です。
医療機関で行われる検査
右下腹部痛と便秘・下痢の症状で医療機関を受診した場合、原因を特定するためにいくつかの検査を行います。
問診と身体診察
まず、医師が症状について詳しく尋ね、いつから症状があるか、痛みの性質(ズキズキ、シクシクなど)、強さ、持続時間、食事との関連、便の状態(色、形、回数)、既往歴、服用中の薬、生活習慣などについて確認します。
その後、視診、聴診、触診、打診などの身体診察を行い、腹部のどこが痛むか、圧痛(押さえたときの痛み)や反跳痛(押さえて離したときの痛み)、筋性防御(腹壁が硬くなること)の有無、腸蠕動音などを確認し、原因疾患の手がかりを探ります。
血液検査
血液検査は、体内の炎症の程度や貧血の有無、肝臓や腎臓などの臓器の機能、電解質のバランスなどを調べるために行います。
白血球数やCRP(C反応性タンパク)の値は炎症の指標となり、これらの数値が高い場合は、虫垂炎や憩室炎、感染性腸炎などの炎症性疾患が疑われ、貧血がある場合は、消化管からの出血の可能性も考えます。
血液検査で確認する主な項目
| 検査項目 | 何がわかるか(一例) | 異常値の場合に考えられること |
|---|---|---|
| 白血球数 (WBC) | 炎症や感染の有無 | 高値:感染症、炎症性疾患など |
| CRP (C反応性タンパク) | 炎症の程度 | 高値:炎症性疾患、組織の損傷など |
| ヘモグロビン (Hb) | 貧血の有無 | 低値:消化管出血、鉄欠乏など |
画像検査(超音波検査、CT検査など)
画像検査は、腹腔内の臓器の状態を視覚的に評価するために行い、 腹部超音波検査(エコー検査)は、体に超音波を当てて、その反響を画像化する検査です。
簡便で被ばくの心配がなく、リアルタイムに臓器の動きや血流も観察でき、虫垂炎、憩室炎、卵巣嚢腫、胆石症などの診断に有用で、虫垂の腫れや周囲の炎症、憩室の壁の肥厚などを確認できます。
腹部CT検査は、X線を使って体の断面像を撮影する検査で、超音波検査よりも広範囲を詳細に観察でき、小さな病変や腹腔内のガス、液体貯留なども捉えられます。虫垂炎や憩室炎の診断、炎症の波及範囲の評価、腫瘍性病変の検索などに有用です。
内視鏡検査(大腸カメラ)
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)は、先端に小型カメラが付いた細い管を肛門から挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体を直接観察する検査で、炎症、潰瘍、ポリープ、がんなどの病変を詳細に確認できます。
また、検査中に疑わしい部分があれば組織を採取して病理検査(生検)を行うことで、確定診断に繋げられ、炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎)、大腸がん、大腸ポリープ、憩室症などの診断に非常に重要です。
下痢や血便が続く場合や、原因不明の腹痛がある場合などに行うことを検討します。
大腸内視鏡検査で発見可能な主な病変
- 大腸ポリープ
- 大腸がん
- 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)
- 大腸憩室症、憩室炎
- 感染性腸炎、虚血性腸炎
右下腹部痛と便秘・下痢に対する治療法
右下腹部痛と便秘・下痢の治療は、原因となっている疾患によって大きく異なり、ここでは、一般的な治療の考え方と、代表的な治療法について説明します。
原因疾患に応じた治療の基本方針
治療の最も重要な点は、正確な診断に基づいて原因疾患を特定し疾患に対する治療を行うことで、感染性腸炎であれば抗菌薬や整腸剤、症状に応じた対症療法が中心です。
急性虫垂炎や大腸憩室炎では、軽症であれば抗生物質による保存的治療、重症例や合併症がある場合は手術を検討します。
炎症性腸疾患の場合は、炎症を抑える薬物療法が中心となり、長期的な管理が必要で、便秘症であれば、生活習慣の改善や緩下剤の使用などを行います。
保存的治療(食事療法、薬物療法)
多くの消化器疾患において、保存的治療が第一選択となります。 食事療法は、症状や疾患に応じて内容を調整し、下痢をしている場合は、消化の良い、低脂肪・低残渣の食事を心がけ、刺激物を避けます。
便秘の場合は、食物繊維を多く含む食品や水分を十分に摂取することが推奨され、炎症性腸疾患では、病状に応じて栄養療法(経腸栄養や完全静脈栄養)を行うこともあります。
薬物療法で使用するのは、症状を和らげる薬(鎮痛薬、整腸剤、止痢剤、緩下剤など)や、原因疾患そのものを治療する薬(抗生物質、抗炎症薬、免疫抑制薬など)などです。
症状に応じた薬物療法
| 症状 | 使用される可能性のある薬剤の種類 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 痛み | 鎮痛薬、鎮痙薬 | 痛みの緩和 |
| 便秘 | 緩下剤(酸化マグネシウム、刺激性下剤など) | 排便の促進 |
| 下痢 | 止痢剤、整腸剤、吸着剤 | 便の性状改善、腸内環境の調整 |
外科的治療が必要な場合
保存的治療で改善が見られない場合や、病状が進行して重篤な合併症(穿孔、膿瘍形成、腸閉塞など)を起こしている場合、あるいは悪性腫瘍が原因である場合などには、外科的治療(手術)が必要です。
急性虫垂炎では、炎症が強い場合や穿孔の危険性がある場合に虫垂切除術を行い、大腸憩室炎でも、穿孔や膿瘍、頻回な再発などの場合に手術(腸管切除など)を検討します。
大腸がんの場合は、病期に応じて内視鏡治療や外科手術、化学療法などを組み合わせた集学的治療を行い、手術の適応や方法は、個々の患者さんの状態によって慎重に判断します。
日常生活での注意点とセルフケア
右下腹部痛や便秘・下痢の症状を予防したり、悪化させないためには、日常生活でのセルフケアも重要で、バランスの取れた食事を心がけ、暴飲暴食を避けましょう。
便秘気味の方は、食物繊維や水分を十分に摂取し、適度な運動を取り入れることが効果的で、下痢をしやすい方は、冷たいものや刺激物の摂りすぎに注意し、腸に負担をかけない食事を意識することが大事です。
十分な睡眠と休息を取り、ストレスを溜め込まないようにすることも大切で、ストレスは自律神経のバランスを乱し、腸の働きに影響を与えることがあります。 また、排便習慣を整えることも重要です。
日常生活でのセルフケアポイント
- バランスの取れた食事(食物繊維、発酵食品など)
- 十分な水分摂取
- 適度な運動習慣
- 質の高い睡眠と十分な休息
- ストレスマネジメント

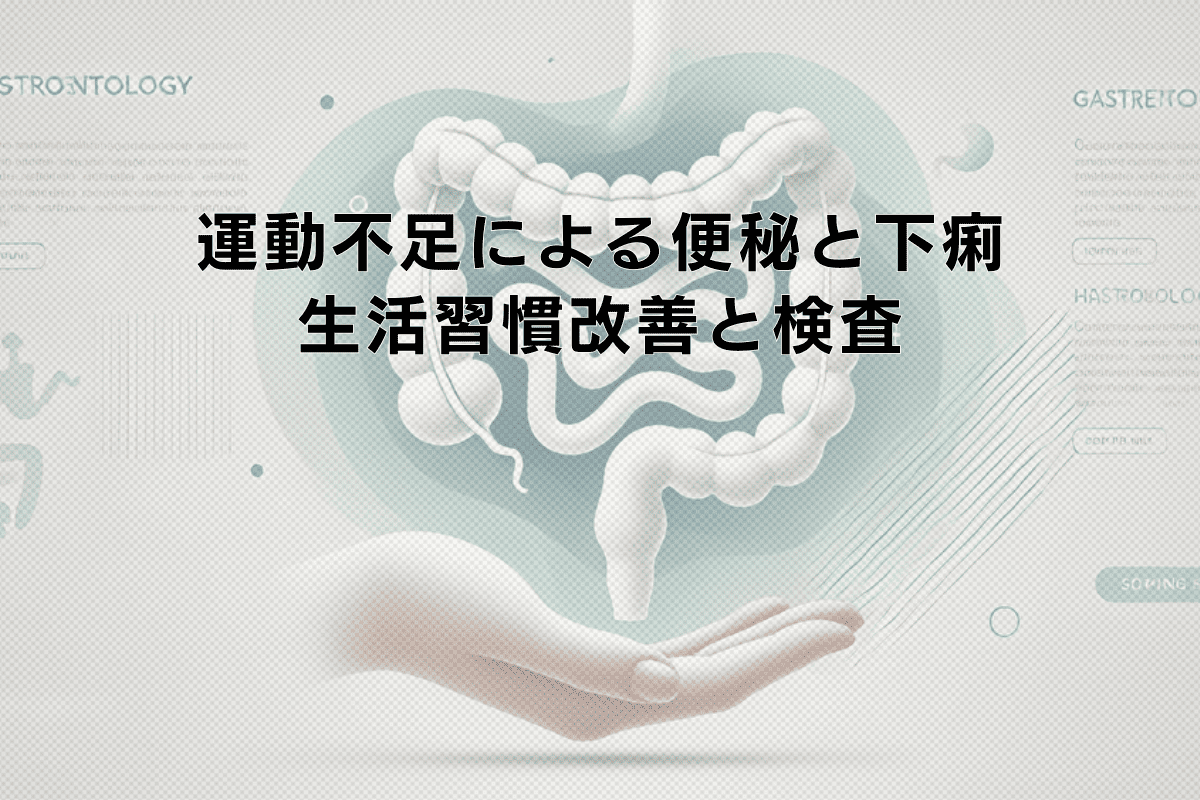
症状が悪化するサインと緊急受診の目安
右下腹部痛や便通異常は、時に緊急を要する病気のサインであることがあり、どのような場合に医療機関をすぐに受診すべきか、目安を知っておくことは非常に大切です。
我慢できないほどの激しい痛み
突然発症した、これまでに経験したことのないような激しい腹痛や、徐々に強まって我慢できなくなるような痛みは、緊急性の高い状態です。
虫垂炎の穿孔、卵巣茎捻転、腸閉塞、消化管穿孔など、放置すると生命に関わる病気が隠れていることがあるので、市販の鎮痛薬でごまかさず、速やかに医療機関を受診してください。
高熱や悪寒、嘔吐が続く場合
38℃以上の高熱が続く、悪寒(寒気と震え)がある、吐き気や嘔吐が頻繁に起こり水分も摂れない、といった症状は、重症な感染症や炎症が体内で進行しているサインかもしれません。
腹痛を伴う場合は、虫垂炎、憩室炎、腎盂腎炎、骨盤内炎症性疾患などが重症化している可能性があり、脱水症状や敗血症(血液中に細菌が入り込み全身に重篤な影響を及ぼす状態)に至る危険性もあるため、早期の対応が必要です。
血便や黒色便が見られる場合
便に血液が混じる(血便)、あるいは便が黒くタール状になる(黒色便)場合は、消化管のどこかから出血している可能性があります。鮮やかな赤い血便は、大腸や肛門付近からの出血(大腸炎、憩室出血、痔など)を示唆します。
黒色便は、胃や十二指腸など上部消化管からの出血が、胃酸の影響で黒く変色したもので、出血量が多い場合は貧血やショック状態を起こすこともあるため、速やかに医療機関を受診し、出血の原因と部位を特定することが重要です。
注意すべき便の状態
| 便の状態 | 考えられる出血部位(一例) | 対応 |
|---|---|---|
| 鮮血便(真っ赤な血) | 大腸、肛門付近 | 医療機関を受診 |
| 暗赤色便(レンガ色) | 小腸、大腸 | 医療機関を受診 |
| 黒色便(タール便) | 食道、胃、十二指腸 | 速やかに医療機関を受診 |
意識がもうろうとする、顔面蒼白などのショック症状
激しい腹痛に加え、冷や汗が出る、顔面が蒼白になる、脈が速く弱くなる、血圧が低下する、意識がもうろうとするといった症状は、ショック状態を示している可能性があります。
大量出血や重症感染症、重度の脱水などにより、生命維持に必要な血液循環が保てなくなった危険な状態で、迷わず救急車を要請するなど、緊急の対応が必要です。
よくある質問(Q&A)
右下腹部の痛みや便通異常に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 右下腹部の痛みが続く場合、何科を受診すればよいですか
-
右下腹部の痛みが続く場合、まずは消化器内科やかかりつけの内科を受診することをお勧めします。
問診や診察の結果、婦人科系疾患が疑われる場合は産婦人科へ、泌尿器科系疾患が疑われる場合は泌尿器科へ紹介されることもあります。症状が急激で我慢できないほど強い場合は、救急外来を受診することも検討してください。
- 市販の痛み止めや整腸剤を飲んでも大丈夫ですか
-
軽い症状の場合、市販薬で一時的に症状が和らぐこともありますが、痛み止めは根本的な原因を治すものではなく、むしろ重篤な病気のサインを隠してしまう可能性があります。
症状が続く場合や、いつもと違う強い症状がある場合は、自己判断で薬を飲み続けずに、医療機関を受診して正確な診断を受けることが大切です。
- 検査にはどのくらいの時間がかかりますか
-
血液検査や尿検査は、採血・採尿自体は数分で終わりますが、結果が出るまでに数十分から1時間程度かかるのが一般的で、 腹部超音波検査は、検査自体は15分から30分程度です。
腹部CT検査は、検査室に入ってから出るまで20分から30分程度ですが、造影剤を使用する場合は準備や検査後の安静時間を含めると、もう少し時間がかかることがあります。
大腸内視鏡検査は、前処置(下剤の服用など)に数時間かかり、検査自体は20分から40分程度ですが、検査後の安静時間も考慮すると半日から1日がかりになることが多いです。
- 予防のためにできることはありますか
-
右下腹部痛や便秘・下痢を起こす全ての病気を完全に予防することは難しいですが、リスクを減らすために日常生活で心がけられることはあり、 まず、バランスの取れた食事が基本です。
食物繊維を豊富に含む野菜や果物、海藻類を積極的に摂り、脂肪分の多い食事や刺激物を控えめにしましょう。ヨーグルトなどの発酵食品も腸内環境を整えるのに役立ちます。
十分な水分摂取も、便秘予防やスムーズな消化吸収に大切で、適度な運動は、腸の蠕動運動を促し、便秘解消に繋がります。
次に読むことをお勧めする記事
【便秘と腸の痛みが続くときに受けるべき検査】
右下腹部痛と便通異常の基本を押さえたら、次はどの検査を受けるかの判断基準を確認しておくと安心です。長引く症状で迷う方に特に参考になります。
【腸にいい食べ物を知る 腸内環境を整える方法】
右下腹部痛や便通異常について理解が深まったところで、日常的な腸内環境の改善についても知っておくと、より包括的な健康管理ができます。
参考文献
Yamashita S, Tago M, Katsuki NE, Nishi TM, Yamashita SI. Relationships between sites of abdominal pain and the organs involved: a prospective observational study. BMJ open. 2020 Jun 1;10(6):e034446.
Murata A, Okamoto K, Mayumi T, Maramatsu K, Matsuda S. Age-related differences in outcomes and etiologies of acute abdominal pain based on a national administrative database. The Tohoku journal of experimental medicine. 2014;233(1):9-15.
Tomizawa M, Shinozaki F, Hasegawa R, Shirai Y, Motoyoshi Y, Sugiyama T, Yamamoto S, Ishige N. Abdominal ultrasonography for patients with abdominal pain as a first-line diagnostic imaging modality. Experimental and Therapeutic Medicine. 2017 May 1;13(5):1932-6.
Yamamoto W, Kono H, Maekawa M, Fukui T. The relationship between abdominal pain regions and specific diseases: an epidemiologic approach to clinical practice. Journal of epidemiology. 1997;7(1):27-32.
Katsuki NE, Tago M, Yamashita S, Kunami N, Hyakutake M, Yamashita SI. The relation between the site of abdominal pain and the organ involved: a retrospective study of 472 cases. JOURNAL OF HOSPITAL GENERAL MEDICINE. 2019 Sep 30;1(3):41-4.
Marincek B. Nontraumatic abdominal emergencies: acute abdominal pain: diagnostic strategies. European radiology. 2002 Sep;12:2136-50.
Gans SL, Pols MA, Stoker J, Boermeester MA, Expert Steering Group. Guideline for the diagnostic pathway in patients with acute abdominal pain. Digestive surgery. 2015 Jan 28;32(1):23-31.
Miller SK, Alpert PT. Assessment and differential diagnosis of abdominal pain. The Nurse Practitioner. 2006 Jul 1;31(7):38-47.
Brown HF, Kelso L. Abdominal pain: an approach to a challenging diagnosis. AACN advanced critical care. 2014 Jul 1;25(3):266-78.
Boyle JT. Abdominal pain. Pediatric gastrointestinal disease. 4th ed. Hamilton: BC Decker Inc. 2004:225-43.