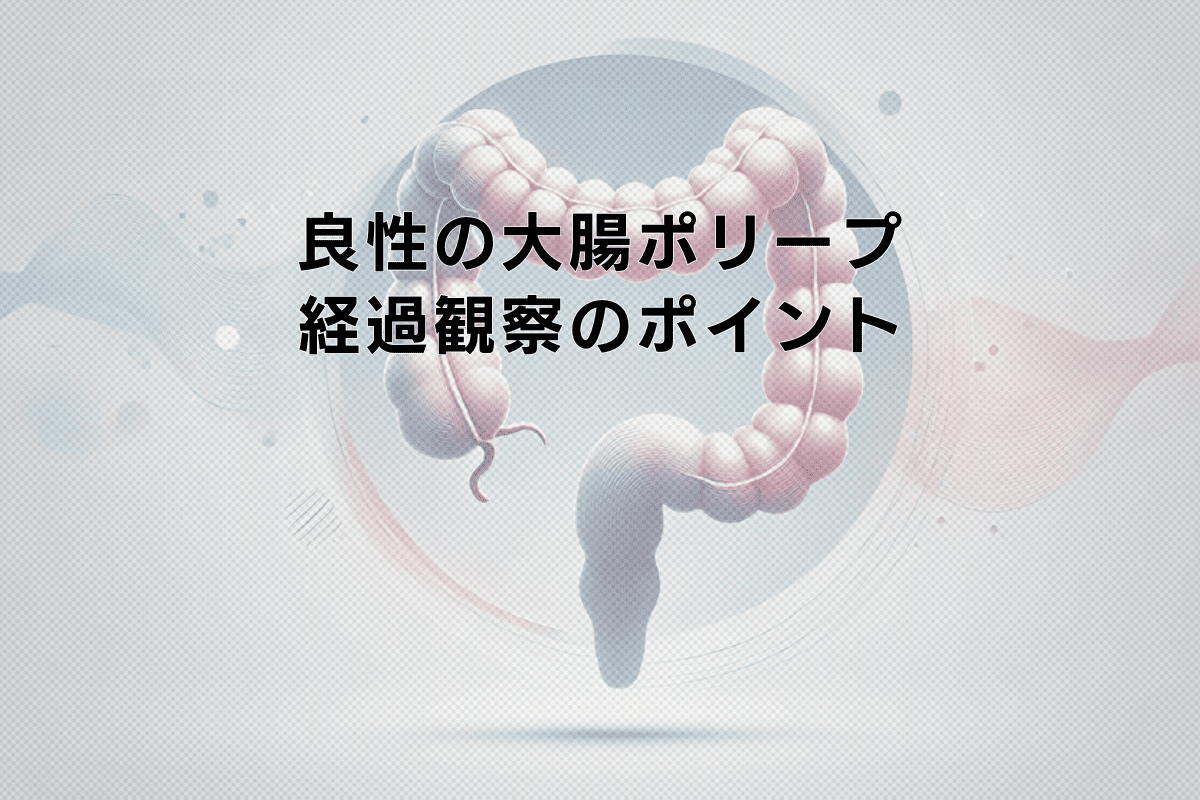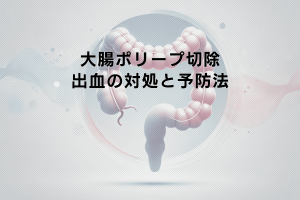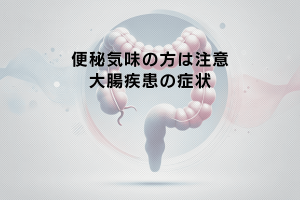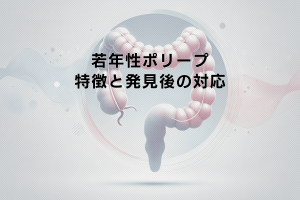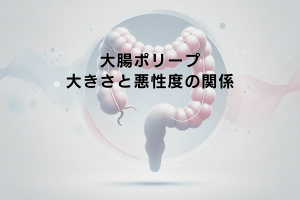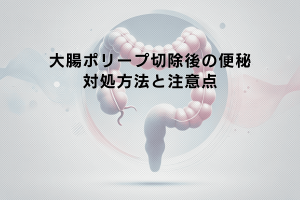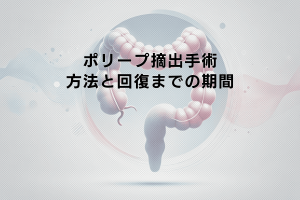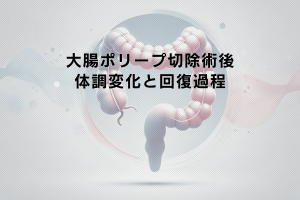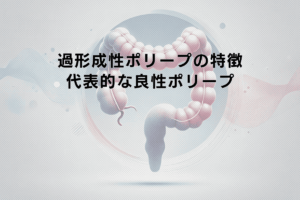大腸ポリープが見つかると、多くの方が不安を感じるかもしれません。特に良性と診断された場合、すぐに治療が必要なのか、それとも様子を見ても良いのか、判断に迷うこともあるでしょう。
この記事では、良性の大腸ポリープ、特に1cm程度のポリープに焦点を当て、経過観察のポイントについて詳しく解説します。
ポリープの性質や大きさ、検査方法、そして経過観察中の注意点などを理解することで、ご自身の状態をより深く把握し、医師との相談に役立ててください。
大腸ポリープとは何か?良性と悪性の違いを理解する
大腸ポリープは、大腸の粘膜表面にできる隆起性の病変の総称です。さまざまな種類があり、その性質によって対応が異なります。
大腸ポリープの基本的な定義
大腸ポリープとは、大腸の内側の壁(粘膜)から発生する、きのこ状やいぼ状の隆起のことです。
大きさや形、数は人によって様々で、単発でできることもあれば、複数個できることもあり、多くは無症状ですが、サイズが大きくなると便潜血や腹痛などの症状を起こすこともあります。
ポリープの種類と特徴
大腸ポリープは、その組織のタイプによっていくつかの種類に分類され、代表的なものには、腺腫性ポリープ、過形成性ポリープ、炎症性ポリープなどがあり、特に注意が必要なのは腺腫性ポリープです。
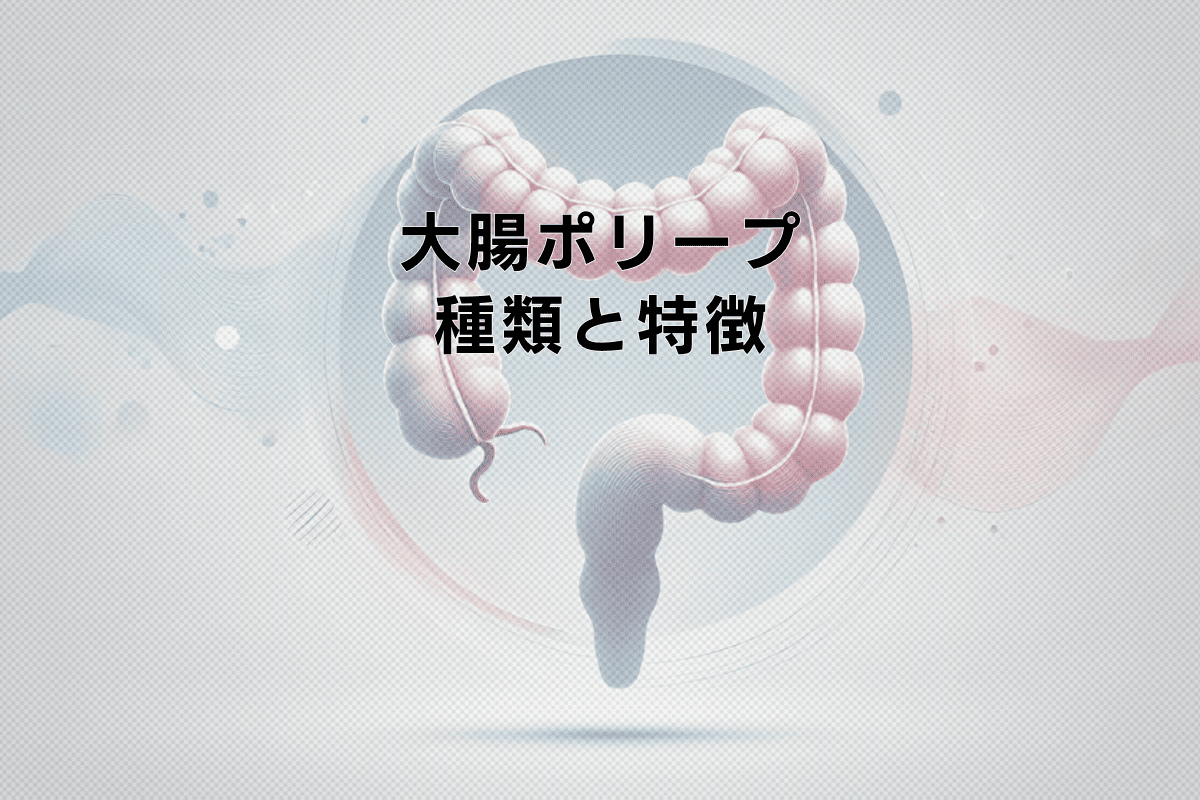
腺腫性ポリープ
腺腫性ポリープは、大腸ポリープの中で最も多く見られるタイプで、良性ですが、放置すると一部ががん化する可能性があるため、前がん病変とも呼ばれます。そのため、発見された場合には切除を検討することが一般的です。
過形成性ポリープ
過形成性ポリープは、基本的にはがん化のリスクが低いと考えられていますが、サイズが大きいものや特殊なタイプ(鋸歯状ポリープなど)の中には、がん化の可能性が指摘されるものもあります。
炎症性ポリープ
炎症性ポリープは、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患に伴って発生することが多いポリープで、がん化のリスクは低いとされていますが、背景にある炎症性腸疾患の管理が重要です。
主なポリープの種類とがん化リスク
| ポリープの種類 | 特徴 | がん化リスク |
|---|---|---|
| 腺腫性ポリープ | 最も一般的。前がん病変。 | あり(放置すると一部がん化) |
| 過形成性ポリープ | 多くはがん化リスク低い。一部注意が必要なタイプも。 | 低い(一部例外あり) |
| 炎症性ポリープ | 炎症性腸疾患に伴う。 | 低い(基礎疾患の管理が重要) |
良性ポリープと悪性ポリープ(がん)の見分け方
ポリープが良性か悪性(がん)かを見分けることは非常に重要で、主に内視鏡検査時の観察と、採取した組織を調べる生検(病理組織検査)によって診断します。
内視鏡検査での観察ポイント
大腸内視鏡検査では、医師がポリープの大きさ、形、色調、表面の模様などを詳細に観察し、特殊な光(NBIなど)を用いたり、色素を散布したりすることで、より詳細な情報が得られ、良悪性の推定に役立ちます。
一般的に、いびつな形をしていたり、表面が不整であったり、出血しやすいポリープは悪性を疑う所見です。
生検による組織学的診断
最終的な診断は、ポリープの一部または全部を採取し(生検またはポリープ切除)、顕微鏡で細胞の顔つきを調べる病理組織検査によって確定します。
検査により、ポリープの種類(腺腫、過形成性など)や、がん細胞の有無、がん細胞がある場合はその深達度(どのくらい深く浸潤しているか)などが分かります。
なぜ良性のうちに発見することが大切なのか
大腸がんの多くは、良性の腺腫性ポリープから発生すると考えられていて、良性のポリープの段階で発見し、切除することで、大腸がんへの進行を未然に防げ、これが、大腸がん検診や定期的な内視鏡検査の大きな目的の一つです。
早期発見・早期治療が、大腸がんから身を守るための鍵となります。
良性大腸ポリープが見つかる主な経緯と検査方法
良性の大腸ポリープは、多くの場合、自覚症状がないまま検診や人間ドックなどで偶然発見されます。ここでは、ポリープ発見のきっかけとなる検査や、診断に用いられる主な検査方法について解説します。
検診や人間ドックでの発見
多くの方が大腸ポリープを指摘されるのは、自治体や職場が実施する大腸がん検診や、ご自身で受ける人間ドックがきっかけです。これらの検診が早期発見に重要な役割を果たしています。
便潜血検査の役割
大腸がん検診で広く行われているのが便潜血検査です。これは、便に混じった微量の血液を検出する検査で、ポリープやがんが出血している場合に陽性となります。
ただし、早期のがんやポリープでは出血しないこともあり、便潜血検査が陰性であってもポリープがないとは限りません。陽性となった場合は、精密検査として大腸内視鏡検査を受けることが推奨されます。

精密検査としての内視鏡検査
便潜血検査で陽性だった場合や、医師が大腸の精密検査が必要と判断した場合に行われるのが大腸内視鏡検査です。直接大腸の内部を観察できるため、ポリープの有無や位置、大きさ、形状などを正確に把握できます。
自覚症状からの発見は稀
小さな良性ポリープの段階では、自覚症状が出ることはほとんどありません。
ポリープが大きくなったり、がん化したりすると、血便、便通異常(便秘や下痢)、腹痛、貧血などの症状が現れることがありますが、症状が出たときには病状が進行していることもあり、症状がないうちから定期的な検診を受けることが大切です。
ポリープの大きさと症状の関連
| ポリープの大きさ | 主な症状 | 備考 |
|---|---|---|
| 数ミリ程度 | ほとんど無症状 | 検診での発見が多い |
| 1cm程度 | 無症状が多いが、稀に便潜血 | がん化リスクを考慮し始める大きさ |
| 2cm以上 | 便潜血、便通異常、腹部膨満感などが出現しやすくなる | がん化リスクが比較的高い |
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)の詳細
大腸内視鏡検査は、肛門から細いカメラ(内視鏡スコープ)を挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体を観察する検査で、ポリープの発見だけでなく、必要に応じて組織を採取したり、小さなポリープであればその場で切除したりすることも可能です。
検査前の準備(食事制限など)
正確な検査を行うためには、大腸の中をきれいにする必要があり、検査前日から消化の良い食事を摂り、検査当日は下剤を服用して腸管を洗浄します。食事制限や下剤の服用方法については、検査を受ける医療機関の指示に従ってください。

検査の流れと所要時間
検査自体は通常15分から30分程度で終了しますが、ポリープの切除などを行う場合は、もう少し時間がかかることもあります。検査後は、リカバリールームでしばらく安静にし、医師からの結果説明を受けます。
鎮静剤の使用について
検査時の苦痛を和らげるために、鎮静剤(静脈麻酔)を使用することがあり、鎮静剤を使用すると、うとうとした状態で検査を受けることができ、不安や不快感が軽減されます。
鎮静剤の使用については、医師とよく相談し、希望や体調に合わせて決定します。
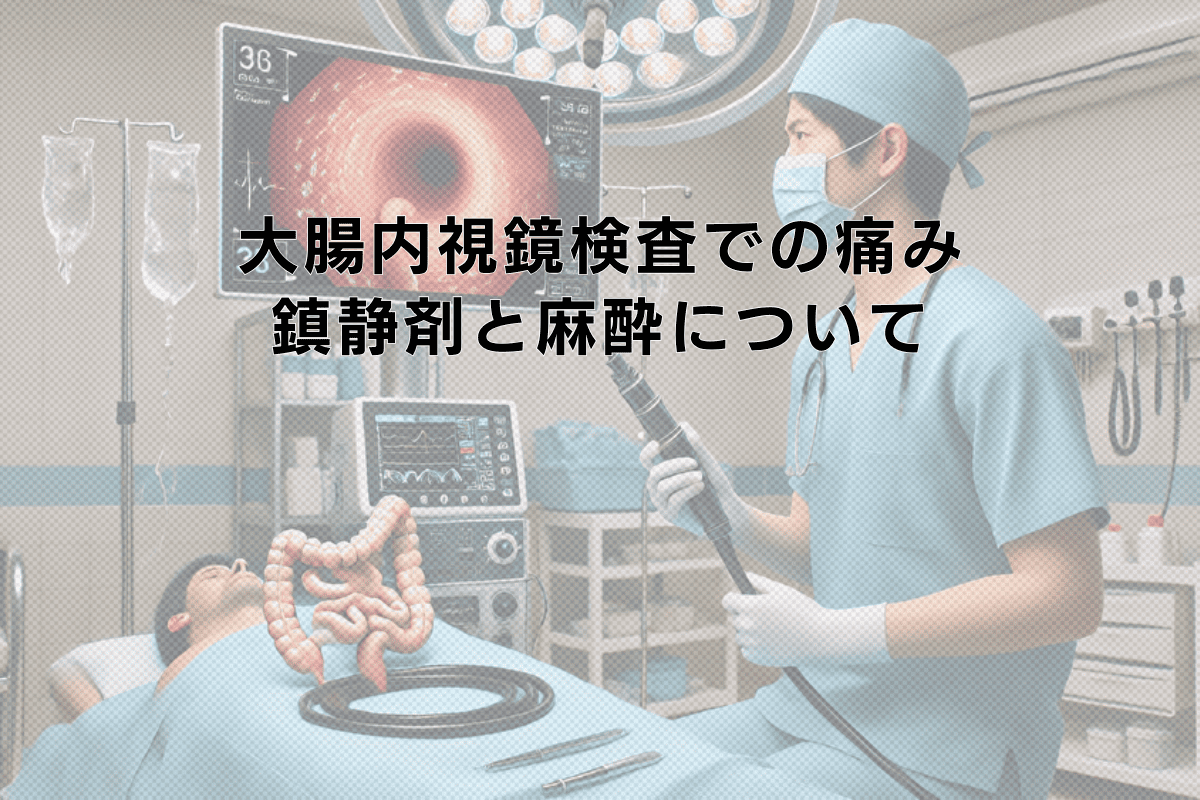
その他の検査方法(CTコロノグラフィなど)
大腸内視鏡検査以外にも、大腸ポリープを調べる検査方法があり、CTコロノグラフィ(CTC、仮想内視鏡検査)は、CTスキャンで得られた画像から大腸の3D画像を構築し、ポリープなどを検出する検査です。
内視鏡を挿入しないため、身体的な負担は比較的軽いですが、小さなポリープの検出率は内視鏡検査に劣る場合があり、また、組織の採取やポリープの切除はできません。
異常が見つかった場合は、改めて大腸内視鏡検査が必要です。
1cmの良性大腸ポリープ どう考える?
大腸ポリープの大きさが1cmと聞くと、それがどの程度の意味を持つのか気になる方も多いでしょう。ここでは、1cmの良性大腸ポリープについて、そのがん化リスクや治療の選択肢、医師の判断基準などを解説します。
ポリープの大きさとがん化リスク
一般的に、大腸ポリープは大きくなるほどがん化するリスクが高まると言われていて、特に腺腫性ポリープの場合、この傾向が顕著です。
大きさ別の一般的ながん化率
ポリープの大きさとがんが含まれる頻度には関連があります。あくまで目安ですが、5mm以下のポリープではがんの可能性は低いですが、1cmを超えると数%程度、2cmを超えるとさらに高い確率でがん細胞が含まれる可能性があります。
ポリープの大きさとがん化の可能性
| ポリープの直径 | がん化の可能性(一般的な目安) | 推奨される対応(一例) |
|---|---|---|
| 5mm未満 | 低い(1%未満など) | 経過観察または切除を検討 |
| 6mm~9mm | やや高まる(数%程度) | 切除を推奨することが多い |
| 1cm~1.9cm | 高まる(10%前後) | 原則として切除を検討 |
| 2cm以上 | 非常に高い(20~50%程度) | 速やかな切除が必要 |
※上記はあくまで一般的な目安であり、ポリープの種類や形状、患者さんの状態によって判断は異なります。
1cmというサイズの意味合い
1cmという大きさは、大腸ポリープを評価する上で一つの目安となります。1cm以上のポリープは、それ以下のものに比べてがん化のリスクが上昇し始めるため、より積極的な対応(多くは内視鏡的切除)を検討する段階と考えられます。
ただし、1cmのポリープがすべてがんになるわけではありませんし、良性のまま経過することも多いです。
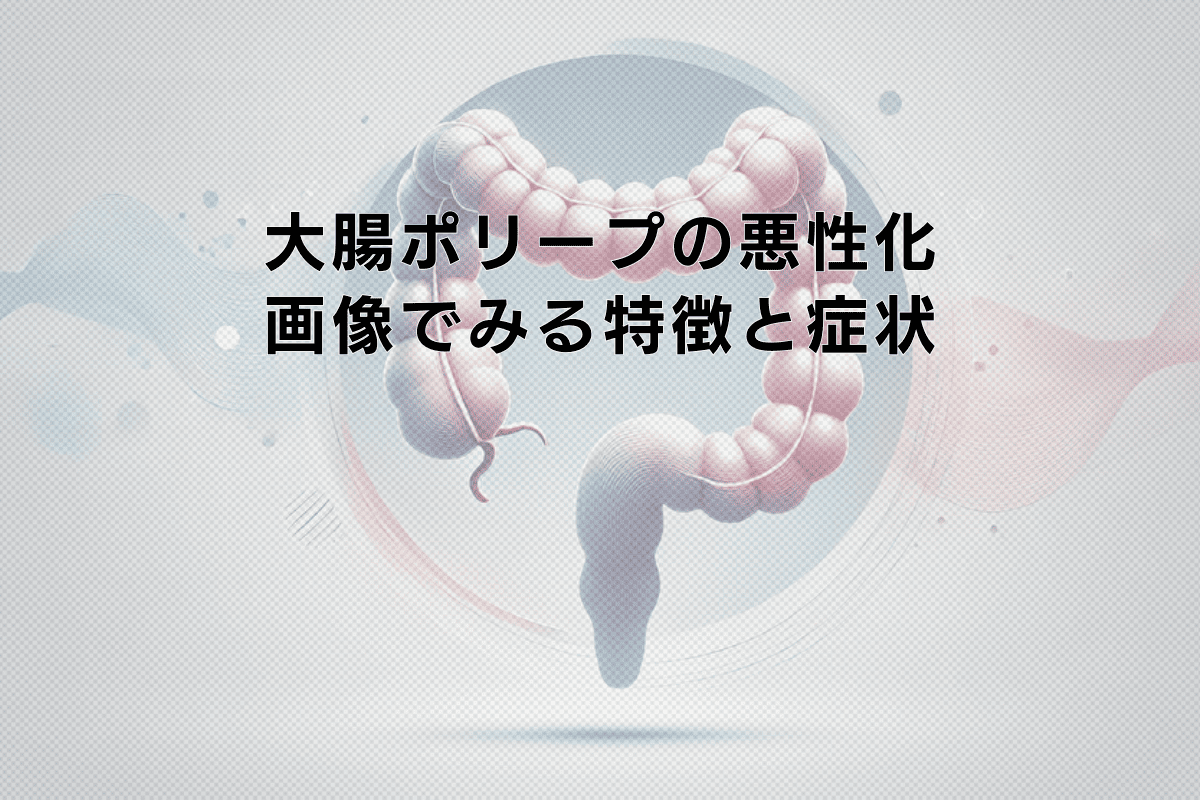
1cmのポリープが見つかった場合の選択肢
1cmの良性大腸ポリープが見つかった場合、主な選択肢は内視鏡的切除と経過観察です。どちらを選択するかは、ポリープの詳しい状態や患者さんご自身の状況を総合的に判断して決定します。
内視鏡的切除
内視鏡を使ってポリープを切除する方法で、多くの場合、大腸内視鏡検査の際に同時に行うことができます。
切除したポリープは病理検査で詳細に調べ、がん細胞の有無や種類を確認します。1cm程度のポリープであれば、比較的安全に切除できることが多いです。

経過観察
すぐに切除せず、定期的に内視鏡検査を行い、ポリープの大きさや形に変化がないかを確認する方法です。ポリープの種類や形状、患者さんの年齢や他の病気の有無などを考慮し、切除によるリスクと利益を比較して選択されることがあります。
医師が切除を勧める場合、経過観察を提案する場合
医師がどちらの選択肢を提案するかは、いくつかの要因を考慮して判断します。
ポリープの形態や表面構造
内視鏡で観察したポリープの形がいびつであったり、表面が陥凹していたり、特殊な模様(NBI拡大観察などでの所見)が見られたりする場合は、がん化のリスクが高いと判断され、大きさが1cm程度でも切除を強く勧めることがあります。
患者さんの年齢や全身状態
患者さんの年齢が比較的若く、他に大きな病気がない場合は、将来的ながん化のリスクを考慮して積極的に切除を勧める傾向があります。
一方、ご高齢であったり、重い持病をお持ちで内視鏡治療のリスクが高いと判断される場合には、ポリープの悪性度が低いと推定されれば経過観察を選択することもあります。
経過観察を選択した場合の注意点
経過観察を選択した場合でも、それで安心というわけではなく、定期的な検査を必ず受けることが重要です。また、万が一ポリープに変化が見られた場合には、速やかに次の対応(多くは切除)を検討する必要があります。
良性大腸ポリープの経過観察 具体的な進め方
良性の大腸ポリープと診断され、経過観察の方針となった場合、具体的にどのように進めていくのでしょうか。ここでは、経過観察の目的、頻度や期間の目安、そして定期検査の重要性について解説します。
経過観察の目的と重要性
良性大腸ポリープの経過観察は、ポリープが将来的にがん化するリスクを管理するために行い、放置することで見逃される可能性のある変化を早期に捉えることが主な目的です。
ポリープの成長や変化の監視
経過観察の最大の目的は、ポリープが大きくなっていないか、形や表面の状態に変化が生じていないかを定期的に確認することです。これらの変化は、がん化の兆候である可能性があるため、注意深く観察します。
新たなポリープの発生の確認
一度ポリープができた方は、新たに別の場所にポリープが発生しやすい傾向があると言われているため、経過観察では既存のポリープだけでなく、大腸全体を観察し、新しいポリープができていないかも確認します。
経過観察の頻度と期間の目安
経過観察の頻度や期間は、一律に決まっているわけではありません。最初に発見されたポリープの数、大きさ、種類(組織型)、そして患者さん個人のリスク要因(年齢、家族歴など)を総合的に考慮して、医師が判断します。
ポリープの数、大きさ、種類による違い
一般的に、ポリープが小さい(例:5mm未満)、数が少ない(例:1~2個)、がん化リスクの低い種類(例:小さな過形成性ポリープ)である場合は、検査間隔を長めに設定できることがあります。
逆に、ポリープが大きい(例:1cm以上)、数が多い、腺腫性ポリープである場合などは、より短い間隔での検査が推奨されます。
経過観察間隔の一般的な目安
| ポリープの状態(初回検査時) | 推奨される次回の内視鏡検査間隔(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| ポリープなし、またはリスクの低い小さなポリープのみ | 3年~5年(またはそれ以上) | 個々の状況による |
| 1cm未満の腺腫性ポリープ 1~2個 | 1年~3年 | 切除した場合も含む |
| 1cm以上の腺腫性ポリープ、または多数のポリープ | 6ヶ月~1年 | 切除後のフォローアップとして |
※これはあくまで一般的な目安であり、実際の検査間隔は担当医の指示に従ってください。
初回検査後のフォローアップ間隔
最初の内視鏡検査でポリープが見つかり、経過観察となった場合、次回の検査は通常、数ヶ月後から数年後に行われます。
1cm程度の良性ポリープで、切除せずに経過観察となった場合、半年から1年後に再度内視鏡検査を行い、変化がないかを確認することが多いです。変化がなければ、その後は徐々に検査間隔を延ばしていくこともあります。
定期的な大腸内視鏡検査の必要性
経過観察において最も重要なのは、指示された間隔で定期的に大腸内視鏡検査を受けることです。自己判断で検査を中断したり、間隔を空けすぎたりすると、ポリープの悪性化を見逃すリスクが高まります。
検査間隔の決定要因
検査間隔は、前回の検査所見(ポリープの大きさ、数、組織型、切除の有無など)、患者さんの年齢、大腸がんの家族歴、過去のポリープの既往などを総合的に評価して決定します。
医師はこれらの情報を基に、個々の患者さんにとって最も適切と考えられる検査スケジュールを提案します。
検査を受ける際の心構え
定期的な検査は、将来の健康を守るための大切な機会と捉え、検査前の準備(食事制限や下剤の服用)は確かに大変ですが、正確な検査のためには欠かせません。
不安な点や疑問点があれば、遠慮なく医師や看護師に相談し、安心して検査に臨みましょう。
経過観察中に気をつけるべき生活習慣
経過観察中であっても、特別な生活制限が必要になることは通常ありません。
しかし、大腸の健康を維持し、ポリープの成長や新たな発生のリスクを少しでも低減するためには、バランスの取れた食事や適度な運動など、健康的な生活習慣を心がけることが望ましいです。
経過観察中の食事と生活習慣のポイント
良性大腸ポリープの経過観察中、あるいはポリープを切除した後でも、再発や新たなポリープの発生を予防するためには、日々の食事や生活習慣に気を配ることが大切です。
食事療法でポリープの成長を抑えられるか
特定の食事療法だけでポリープの成長を完全に抑えることは難しいですが、食生活の改善が大腸の健康維持に寄与し、ポリープのリスク低減につながる可能性は指摘されています。
食物繊維の重要性
食物繊維は、便通を整え、腸内環境を改善する働きがあり、野菜、果物、きのこ類、海藻類、豆類、全粒穀物などに多く含まれています。
これらの食品を積極的に摂取することで、便が大腸内に滞留する時間を短縮し、発がん物質と腸管粘膜との接触時間を減らす効果が期待できます。
食物繊維を多く含む食品
| 食品カテゴリー | 具体的な食品例 | 摂取のポイント |
|---|---|---|
| 野菜 | ごぼう、ブロッコリー、ほうれん草、キャベツ | 毎食、彩り豊かに取り入れる |
| 果物 | りんご、バナナ、キウイフルーツ、柑橘類 | 皮ごと食べられるものは皮も一緒に |
| 豆類・穀物 | 納豆、豆腐、玄米、オートミール | 主食や副菜に積極的に活用 |
避けるべき食事、推奨される食事
高脂肪食(特に動物性脂肪の過剰摂取)や加工肉(ハム、ソーセージ、ベーコンなど)の摂りすぎは、大腸がんのリスクを高めるので、摂取は控えめにし、魚や鶏肉(皮なし)、大豆製品などをタンパク源として選ぶとよいでしょう。
また、赤身肉の摂取も適量を心がけることが推奨され、一方で、抗酸化作用のあるビタミンCやビタミンE、カロテノイドなどを多く含む緑黄色野菜や果物の摂取は、積極的に行ってください。
特定の栄養素とポリープの関係
カルシウムやビタミンDが、大腸ポリープや大腸がんの予防に役立つ可能性を示唆する研究報告があります。
カルシウムは乳製品、小魚、緑黄色野菜などに、ビタミンDは魚介類やきのこ類に多く含まれるほか、日光を浴びることでも体内で生成されます。バランスの取れた食事を心がける中で、これらの栄養素も意識して摂取してください。
- 食物繊維を豊富に摂る
- 動物性脂肪や加工肉の摂取を控える
- 赤身肉は適量にする
- 野菜や果物を十分に摂る

運動習慣と大腸ポリープ
定期的な運動は、大腸の健康維持にも良い影響を与えると考えられていて、運動不足は便秘の原因の一つにもなり得ます。
適度な運動の推奨
ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなど、有酸素運動を週に数回、合計で150分程度行うことが一般的に推奨され、無理のない範囲で、楽しみながら続けられる運動を見つけることが大切です。
運動は腸の蠕動運動を活発にし、便通を改善する効果も期待できます。
運動が腸内環境に与える影響
適度な運動は、腸内細菌叢のバランスを整える助けとなる可能性も指摘されていて、健康的な腸内環境は、免疫機能の維持や炎症の抑制にも関与しており、大腸全体の健康にとって重要です。
禁煙と節酒のすすめ
喫煙と過度なアルコール摂取は、大腸ポリープや大腸がんのリスクを高めることが知られています。
喫煙と大腸がんリスク
喫煙は、大腸がんを含む多くのがんの確実なリスク因子です。禁煙することで、大腸がんのリスクを下げることができます。禁煙が難しい場合は、禁煙外来などで専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
アルコール摂取とポリープ
アルコールの過剰な摂取も、大腸ポリープや大腸がんのリスクを高め、飲酒する場合は、適量を守ることが重要です。
「節度ある適度な飲酒」としては、1日平均純アルコールで20g程度とされていて、これは、ビール中瓶1本、日本酒1合、ワイングラス2杯弱に相当します。
ストレス管理と睡眠
慢性的なストレスや睡眠不足は、免疫機能の低下や腸内環境の乱れを引き起こす可能性があります。
直接的にポリープの発生や成長に関与するかどうかは明確ではありませんが、全身の健康を維持する上で、十分な睡眠時間を確保し、自分に合ったストレス解消法を見つけて実践することは大切です。
大腸ポリープの再発と予防のためにできること
一度大腸ポリープが見つかったり、切除したりした方は、将来的に再びポリープができる(再発する)可能性があります。また、まだポリープが見つかっていない方も、予防のためにできることがあります。
ポリープ切除後の再発リスク
大腸ポリープを切除した後も、安心はできません。ポリープができやすい体質や生活習慣が変わらなければ、別の場所に新たなポリープが発生したり、ごく小さくて見逃されたポリープが成長したりすることがあります。
そのため、切除後も定期的な内視鏡検査によるフォローアップが重要です。
再発しやすいポリープの種類
一般的に、腺腫性ポリープ、特にサイズが大きいものや数が多いもの、特殊なタイプの腺腫(絨毛腺腫や鋸歯状病変など)を切除した場合は、再発のリスクが比較的高いと考えられています。
ポリープ切除後の一般的なフォローアップ間隔の目安
| 切除したポリープの状態 | 推奨される次回の内視鏡検査(目安) | その後の検査間隔(目安) |
|---|---|---|
| 低リスクの腺腫(例:1cm未満、1~2個、管状腺腫) | 1年後 | 異常がなければ3~5年ごと |
| 高リスクの腺腫(例:1cm以上、3個以上、絨毛成分を含む、高度異型) | 6ヶ月~1年後 | 異常がなければ1~3年ごと |
| 多数のポリープ(例:10個以上) | 医師の指示による(より短い間隔) | 医師の指示による |
※上記はあくまで一般的な目安です。個々の状況により異なりますので、必ず担当医の指示に従ってください。
定期検査による早期発見の重要性
再発したポリープも、小さいうちに発見して対処すれば、がん化を防げ、定期的な内視鏡検査は、この早期発見のために不可欠です。医師から指示された検査スケジュールを守り、継続して検査を受けましょう。
新たなポリープの発生予防
ポリープの発生を完全に予防する方法はまだ確立されていませんが、リスクを低減するためにできることはあり、主に食生活と生活習慣の改善が中心です。
食生活の見直し
前章で述べたように、食物繊維を多く含む食事、バランスの取れた栄養摂取、動物性脂肪や加工肉の制限などが推奨されます。これらは、腸内環境を整え、大腸の健康を保つ上で役立ちます。
- 野菜・果物・全粒穀物を増やす
- 赤身肉・加工肉の摂取を控える
- カルシウムやビタミンDを意識する
生活習慣の改善
適度な運動習慣、禁煙、節酒も重要で、大腸だけでなく全身の健康増進にもつながります。肥満も大腸がんのリスク因子の一つとされているため、適正体重の維持も心がけましょう。
大腸がん検診の継続
ポリープの既往がない方でも、年齢とともに大腸がんのリスクは上昇するため、推奨される年齢になったら定期的に大腸がん検診を受けることが大切です。
推奨される検診開始年齢と頻度
日本では、一般的に40歳以上の方を対象に、年1回の便潜血検査による大腸がん検診が推奨されていて、便潜血検査で陽性となった場合は、精密検査として大腸内視鏡検査を受けます。
家族に大腸がんの方がいるなど、リスクが高いと考えられる場合は、より早期からの検査や、内視鏡検査を直接受けることを医師と相談することも考慮しましょう。
家族歴と遺伝的要因の考慮
大腸がんや大腸ポリープは、家族内で多発することがあり、遺伝的な要因が関与している場合もあります。特に、家族性大腸腺腫症(FAP)やリンチ症候群(遺伝性非ポリポーシス大腸がん)などの遺伝性疾患が知られています。
血縁者に若年で大腸がんを発症した方や、多数のポリープが見つかった方がいる場合は、遺伝カウンセリングや専門医への相談を検討することも一つの選択肢です。
良性大腸ポリープ経過観察に関するよくある質問(Q&A)
良性大腸ポリープの経過観察について、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。ご自身の状況と照らし合わせながら、参考にしてください。
- 経過観察中にポリープが大きくなったらどうなりますか?
-
経過観察中の定期的な内視鏡検査でポリープの増大が確認された場合、大きくなり方やポリープの形状、これまでの経過などを総合的に判断し、内視鏡的切除を検討することが一般的です。
特に、がん化のリスクが高まるサイズ(例えば1cmを超えるなど)になったり、表面の性状に悪性を疑う変化が見られたりした場合には、積極的に切除を勧めます。
- 経過観察中にポリープが悪性化する可能性はどのくらいですか?
-
良性の腺腫性ポリープががん化するまでには、通常数年から10年以上かかると言われていますが、ポリープの種類や大きさ、個人の体質などによって、そのスピードは異なります。
1cm未満の小さな良性ポリープが、次回の検査までの短期間(例えば1~2年)で急に悪性化する頻度はそれほど高くありませんが、ゼロではないので、医師の指示に従った定期的な経過観察が重要です。
- 経過観察をやめても良い場合はありますか?
-
経過観察を自己判断で中止することは推奨されません。経過観察の終了時期や、検査間隔の延長については、必ず担当医と相談して決定してください。
長期間にわたりポリープの大きさや数に変化がなく、年齢や全身状態などを考慮して、医師がこれ以上の積極的なフォローアップは利益よりも不利益が上回ると判断した場合などに、経過観察の方針が見直されることがあります。
- ポリープが自然に消えることはありますか?
-
小さなポリープや、炎症などによる一時的な隆起の場合、まれに自然に縮小したり消失したりするように見えることもありますが、一度診断された腺腫性ポリープなどの腫瘍性ポリープが自然に完全に消滅することはありません。
むしろ、時間とともに増大したり、がん化したりするリスクを考慮する必要があります。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸ポリープの内視鏡治療 – 早期発見と切除術の重要性】
良性ポリープの経過観察を理解したら、実際の内視鏡的切除がどのように行われるかを知っておくと安心です。手技の違いやフォローの目安を具体的に把握できます。
【腸にいい食べ物を知る 腸内環境を整える方法】
経過観察中の生活習慣について学んだ皆さんには、腸内環境を整える具体的な食事方法の知識も合わせて持っていただくと、より包括的な健康管理ができます。
参考文献
Huck MB, Bohl JL. Colonic polyps: diagnosis and surveillance. Clinics in colon and rectal surgery. 2016 Dec;29(04):296-305.
Bond JH. Polyp guideline: diagnosis, treatment, and surveillance for patients with nonfamilial colorectal polyps. Annals of internal medicine. 1993 Oct 15;119(8):836-43.
Bond JH, Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology. Polyp guideline: diagnosis, treatment, and surveillance for patients with colorectal polyps. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2000 Nov 1;95(11):3053-63.
Bonnington SN, Rutter MD. Surveillance of colonic polyps: are we getting it right?. World journal of gastroenterology. 2016 Feb 14;22(6):1925.
Baile-Maxía S, Jover R. Surveillance after colorectal Polyp resection. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology. 2023 Oct 1;66:101848.
McFerran E, O’Mahony JF, Fallis R, McVicar D, Zauber AG, Kee F. Evaluation of the effectiveness and cost-effectiveness of personalized surveillance after colorectal adenomatous polypectomy. Epidemiologic reviews. 2017 Jan 1;39(1):148-60.
Rutter MD, East J, Rees CJ, Cripps N, Docherty J, Dolwani S, Kaye PV, Monahan KJ, Novelli MR, Plumb A, Saunders BP. British Society of Gastroenterology/Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland/Public Health England post-polypectomy and post-colorectal cancer resection surveillance guidelines. Gut. 2020 Feb 1;69(2):201-23.
Parker J, Gupta S, Torkington J, Dolwani S. Comparison of recommendations for surveillance of advanced colorectal polyps: A systematic review of guidelines. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2023 Jun;38(6):854-64.
Gorji L, Albrecht P. Hamartomatous polyps: Diagnosis, surveillance, and management. World Journal of Gastroenterology. 2023 Feb 28;29(8):1304.
Fu X, Qiu Y, Zhang Y. Screening, management and surveillance for the sessile serrated adenomas/polyps. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2014 Mar 15;7(4):1275.