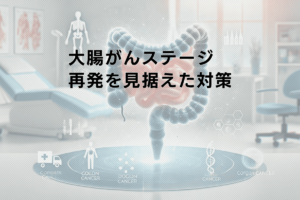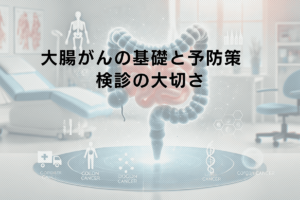大腸は食物の消化と栄養吸収を終えたあと、便を形成して排泄に備える重要な役割を担っていて、大腸に腫瘍が生じる大腸がんは、日本でもがん罹患数の上位を占め、進行すると命に関わる恐れがあります。
早期の大腸がんははっきりとした自覚症状がない場合も多く、初期発見のためには便の色や形状の変化、血便などの症状や検査のポイントを理解しておくことが欠かせません。
この記事では、大腸がんの症状や検査方法、治療の概要を詳しく解説し、適切なタイミングで医療機関を受診する大切さをお伝えします。
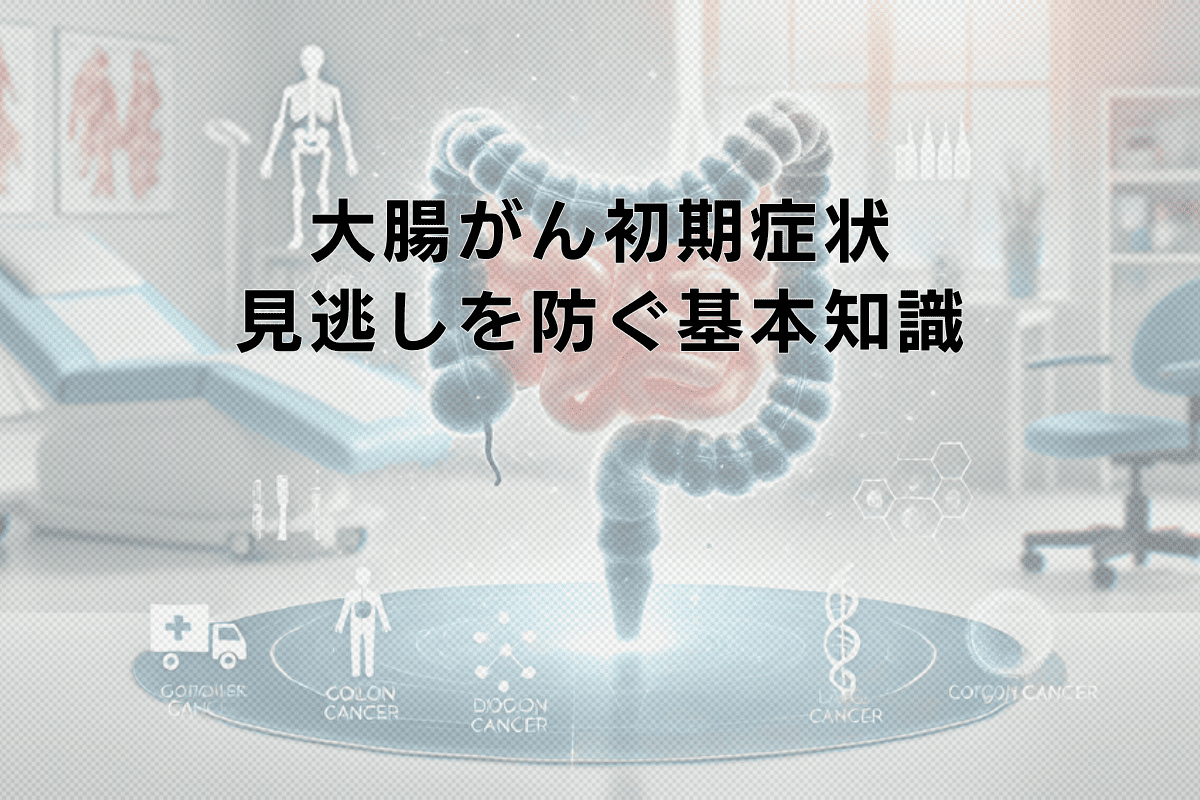
大腸がんとは何か
大腸がんは、大腸(結腸・直腸)の粘膜細胞から発生するがんの総称であり、発生部位によって結腸がんや直腸がんなどに分類されます。
主に便の通過路となる結腸と、便を溜める直腸を含む大腸は、体内でもっとも長い器官のひとつです。
食生活の変化や高齢化などの要因も相まって、大腸がんの患者数は増加傾向にあり、性別を問わず罹患リスクがあるがんの1つとして知られています。
大腸の役割と構造
大腸は、小腸から送られてきた食物残渣から水分やミネラルを吸収しながら、便を形成する場で、大腸は大きく盲腸、結腸、直腸に分かれており、結腸はさらに上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸に区分されます。
直腸がんと結腸がんでは症状や検査法は共通点が多いものの、治療のアプローチは部位によって変わります。

大腸がんが増加している背景
近年、大腸がんの発生が増えている背景には、食生活が欧米化したことや、肉類や脂質を多く摂取する習慣、運動不足、肥満、喫煙や飲酒などの生活習慣が影響していると指摘されています。
また、高齢化が進むことで50代以上の人口が増え、大腸がんのリスクが高まっていることも原因です。
初期の大腸がんと自覚症状
大腸がんの初期段階ではほとんど自覚症状がなく、検診や内視鏡検査によってはじめて発見されるケースが多いです。
症状がないからといって安心はできず、徐々にがんが大きくなると進行期の症状が現れる場合があるので、少しでも気になる便や腹部の状態があるときは、早めに専門医に相談してください。
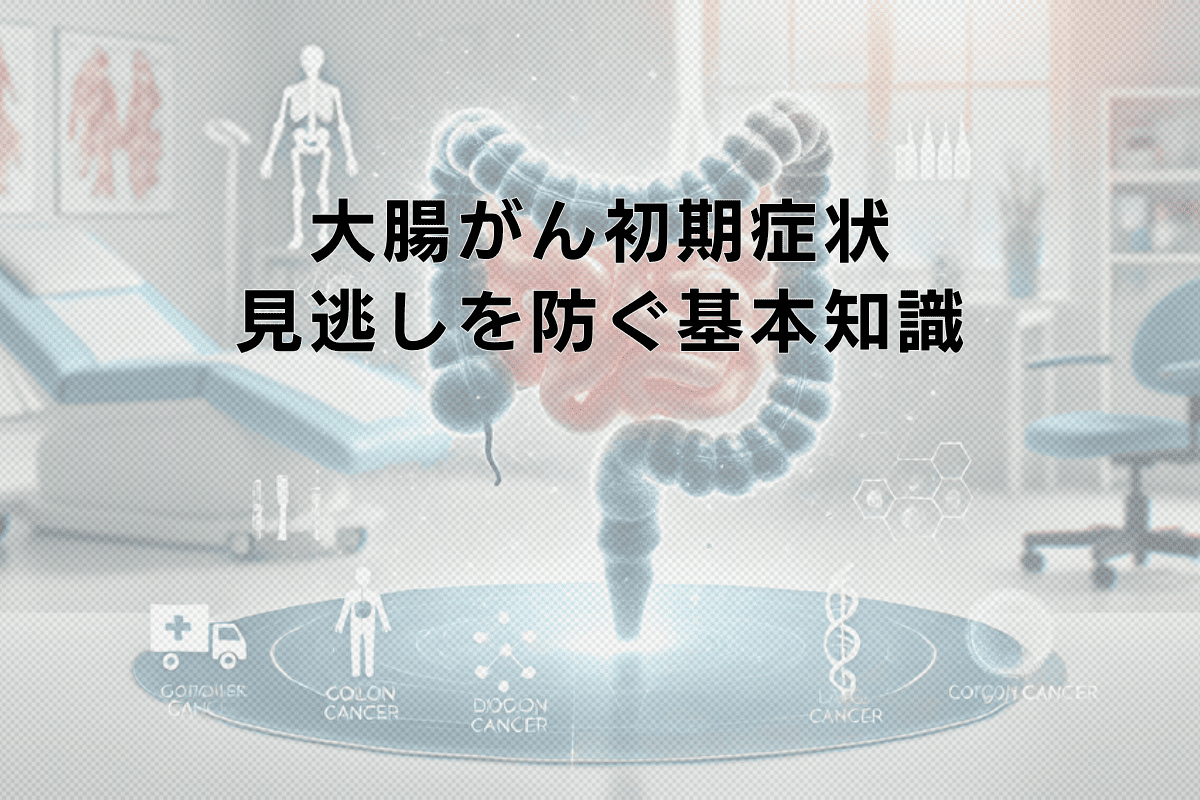
家族歴との関係
大腸がんの中には家族性大腸腺腫症やリンチ症候群など、遺伝的要因が関与するケースがあり、血縁者に大腸がんの人が多い場合、リスクが高い可能性があるため、定期的な内視鏡検査を受けることが推奨されます。
大腸がんが引き起こす主な症状
このパートでは、大腸がんの進行度や発生部位によって生じる主な症状を説明します。早期の段階では気づきにくいものの、進行とともに目立つ変化や不調が現れます。
便通の異常や便の形状変化
大腸がんが進行すると、便が通過する大腸内部の空間が狭くなり、便の通りが悪くなり、具体的には、便が細くなったり、コロコロした硬い便や下痢と便秘が交互に続いたりすることが挙げられます。
また、がんが結腸にある場合、慢性的な便通異常が起こりやすく、直腸に腫瘍ができると残便感が強まることがよくあります。

大腸がんと便の特徴を比較
| 症状の種類 | 主な特徴 | 起こりやすい部位 |
|---|---|---|
| 便が細くなる | 大腸内が狭くなり、通過する便が細長くなる | 結腸がん・直腸がん全般 |
| 下痢・便秘の反復 | 通常の排便リズムが乱れ、便の形状や状態が不安定 | S状結腸がん、直腸がん |
| コロコロ便 | 水分が十分に吸収され、固く小さい便になる | 下行結腸がん、S状結腸がん |
| 残便感 | 排便しても出し切れた感じがしない | 直腸がん |
血便や粘液便
大腸がんでは、腫瘍部分から出血が起こることがあり、便に血が混ざったり、鮮血が付着したりし、直腸がんの場合、便に赤い血液がつきやすく、痔と間違えられることも少なくありません。
結腸がんでは便の色が黒っぽく変化し、下痢とともに粘液が混ざるケースもあり、こうした変化に気づいたら医療機関で検査を受けることが大切です。

腹痛や腹部の張り
進行した大腸がんでは、腫瘍が腸管を塞ぎかけることで、腹部の痛みや張り感が強くなり、腸の通過障害が深刻化すると腸閉塞になる恐れがあり、ひどい腹痛や嘔吐を伴うことがあります。
S状結腸や下行結腸にできたがんは便の通過が滞りやすく、こうした症状が比較的顕著です。
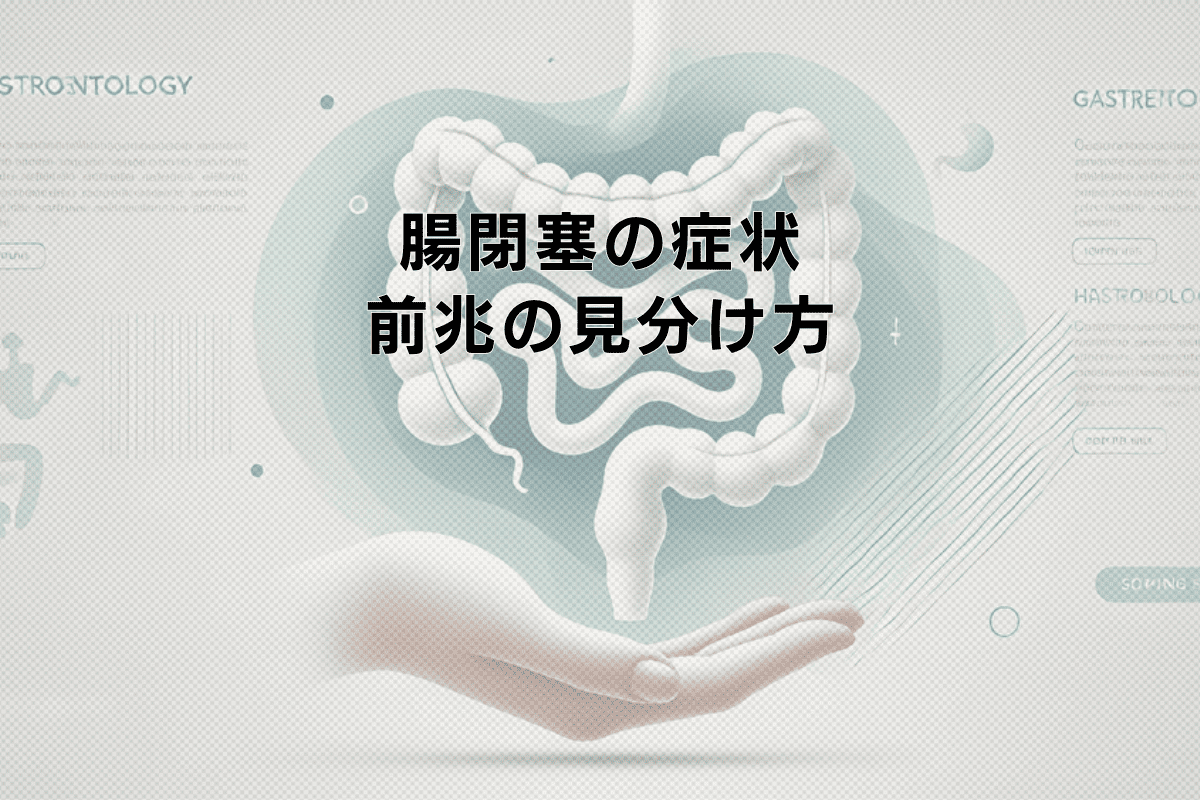
貧血や体重減少
大腸がんに伴う慢性的な出血により、血液中のヘモグロビンが減って貧血を起こし、長期にわたるわずかな出血でも、日々の積み重ねによって体の酸素供給量が低下し、全身の倦怠感や息切れを感じます。
また、がん細胞の増殖によって栄養を奪われたり、食欲不振や便通異常が続くことで体重が減少することもあります。
全身症状や転移による症状
大腸がんは肝臓や肺などの臓器へ転移しやすい特性があり、転移が起こると臓器の機能に影響が及び、黄疸や呼吸困難などの全身症状が発生し、腹膜播種という形で腹部全体にがんが広がる場合、強い腹痛や腹水貯留を起こすケースもあります。
大腸がんの原因とリスク要因
大腸がんを引き起こすと考えられる要因は、生活習慣や遺伝的背景、炎症性腸疾患など、さまざまです。
加工肉や高脂肪食への偏り
食生活が肉類中心になり、食物繊維や野菜が不足すると、大腸がんのリスクが上がり、赤身肉や加工肉を頻繁に摂取する場合、腸内環境が変化し、発がん性物質が増える可能性があるとされてきました。
一方、食物繊維を豊富に含む野菜や果物、大豆製品をバランスよく食べると、便通が整いやすくなり腸の粘膜を健康に保ちやすいと考えられています。
肥満や運動不足
肥満や体重過多、運動不足は大腸がんのリスクを高める要素の1つです。
内臓脂肪が蓄積すると炎症やホルモンバランスの乱れが起こり、がん細胞が増殖しやすくなりますが、適度な運動を習慣にすると腸の働きが活発になり、便の停滞時間が短縮するため、発がん性物質が腸内にとどまる時間も短くなります。
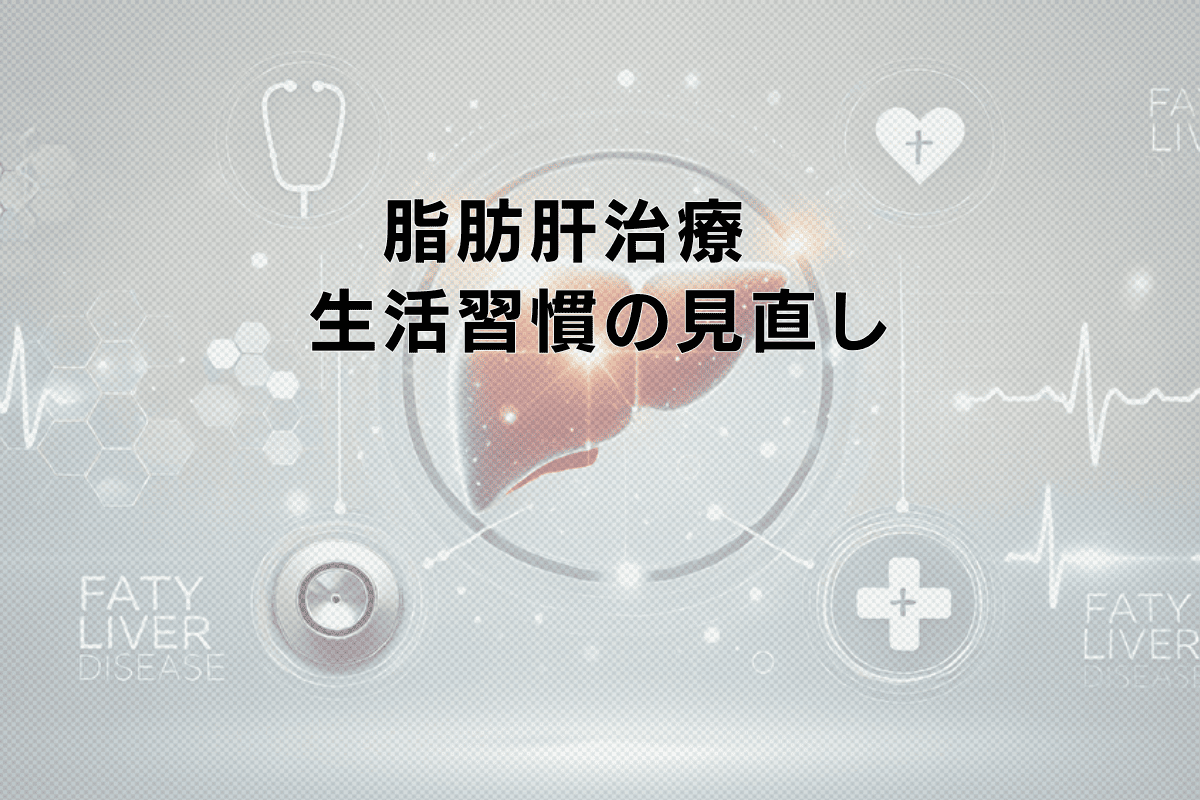
飲酒や喫煙
アルコール摂取量が多い人や、長年喫煙を続けている人は大腸がんを含む多くのがんのリスクが高まり、特に喫煙は肺がんだけでなく、大腸がんの危険因子です。
過度のアルコールとタバコの併用は、より大腸がんの発生リスクを押し上げる可能性があるため、できるだけ控えてください。
炎症性腸疾患など他の病気
潰瘍性大腸炎やクローン病など、腸管に慢性的な炎症が起こる疾患を持つ人は、大腸がんのリスクが高くなり、炎症が長期にわたる場合、腸粘膜の細胞が異常増殖を起こしやすくなり、がん化の可能性が高まります。
こうした基礎疾患を持つ人は、定期的な大腸内視鏡検査を受けて早期発見に努めることが大切です。

遺伝性の要因
家族性大腸腺腫症やリンチ症候群(遺伝性非ポリポーシス大腸がん)は、若年層でも大腸がんを発症しやすい遺伝的素因をもつ代表的な病態です。該当するかどうかは遺伝子検査や家族歴の詳細調査によって確認されることがあります。
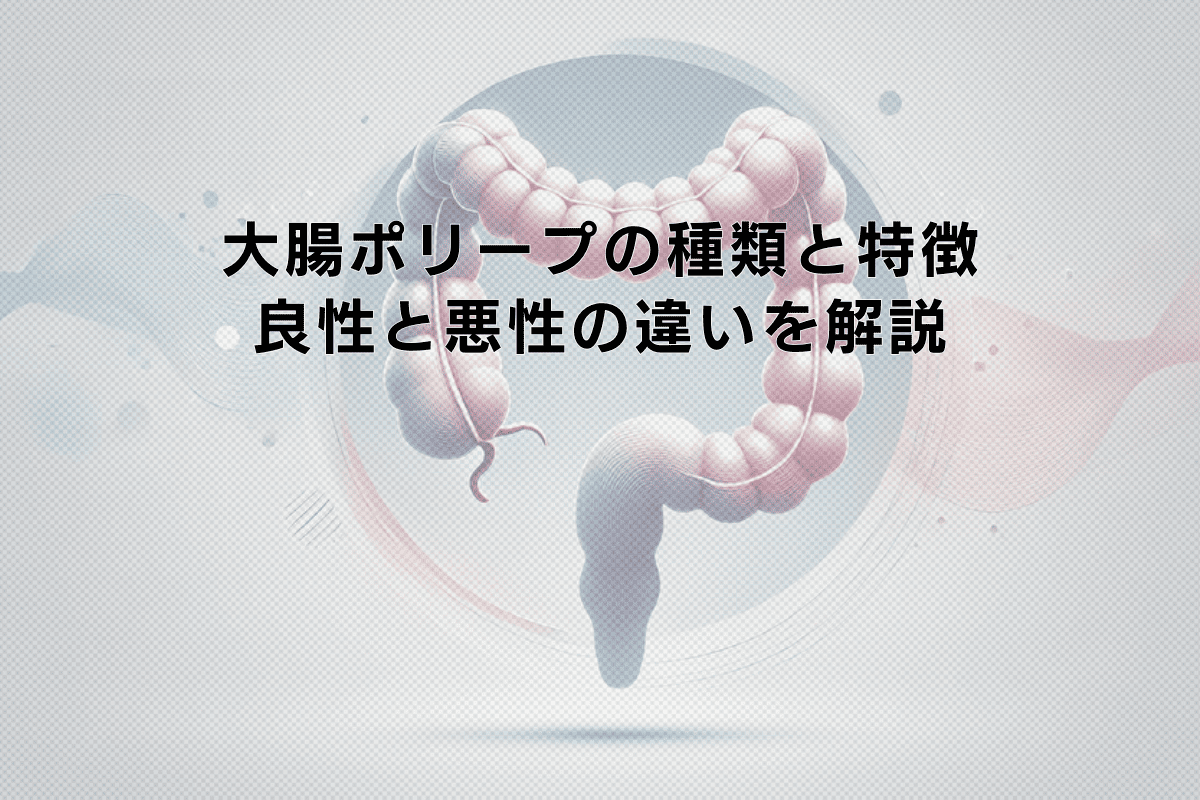
主なリスク要因と特徴
| リスク要因 | 特徴 | リスク軽減策 |
|---|---|---|
| 高脂肪食・赤身肉・加工肉 | 腸内で有害物質を生じやすく、粘膜に負担をかける | 食物繊維を含むバランスの良い食事 |
| 肥満・運動不足 | 内臓脂肪の蓄積によるホルモンバランスの乱れ | 適度な運動習慣・体重管理 |
| 飲酒・喫煙 | アルコール分解産物やタバコの有害成分が細胞を傷つける | 禁酒・禁煙、または大幅に減らす |
| 炎症性腸疾患 | 長期間にわたる腸粘膜の炎症で細胞異常が起こりやすい | 定期検診と内視鏡検査の実施 |
| 遺伝的要因 | 特定の遺伝子変異により、腺腫が若くして発生しやすい | 家族歴のある人は早期から継続的な検査 |
大腸がんの検査方法
ここでは、大腸がんを見つけるために行う主な検査と、その特徴について取り上げます。早期発見は治療の成功率を大きく高めるため、定期的な検診や疑わしい症状があるときの早期受診が重要です。
便潜血検査
便潜血検査は、便の中に微量に混ざっている血液を検出し、痛みを伴わず、比較的簡単に実施できるため、多くの自治体や企業の健康診断で取り入れられている方法です。
陽性であっても必ずしも大腸がんというわけではありませんが、ポリープや痔などによる出血の可能性があるため、精密検査として大腸内視鏡検査を受ける流れになります。
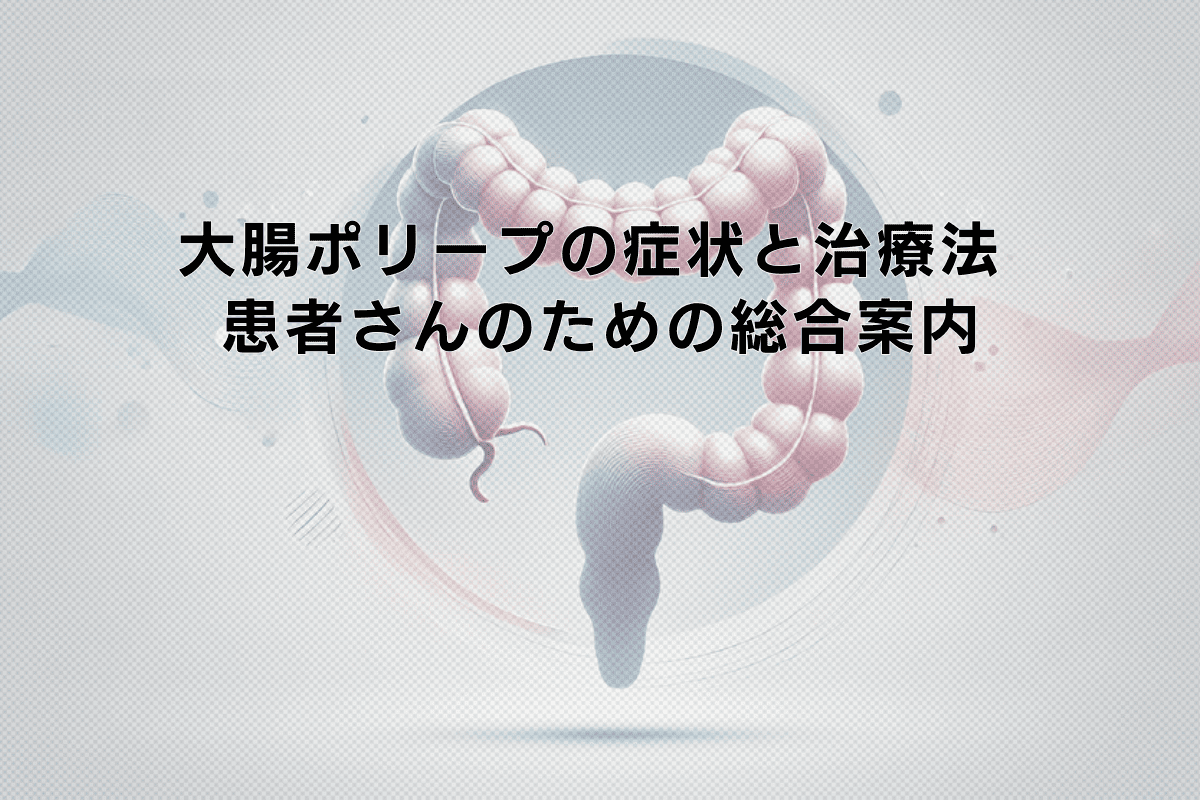
便潜血検査の特徴
| 検査の特徴 | 内容 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 検査方法 | 検体として便を採取し、血液の有無を調べる | 痛みがなく手軽にできる | 偽陽性や偽陰性が起こる可能性 |
| 検査結果の判定 | 陽性or陰性で結果を判断 | 大規模検診に適している | 詳細な原因まではわからない |
| 判定後の流れ | 陽性の場合、大腸内視鏡検査などを検討 | 早期発見につながりやすい | 痔などの出血でも陽性になる可能性 |
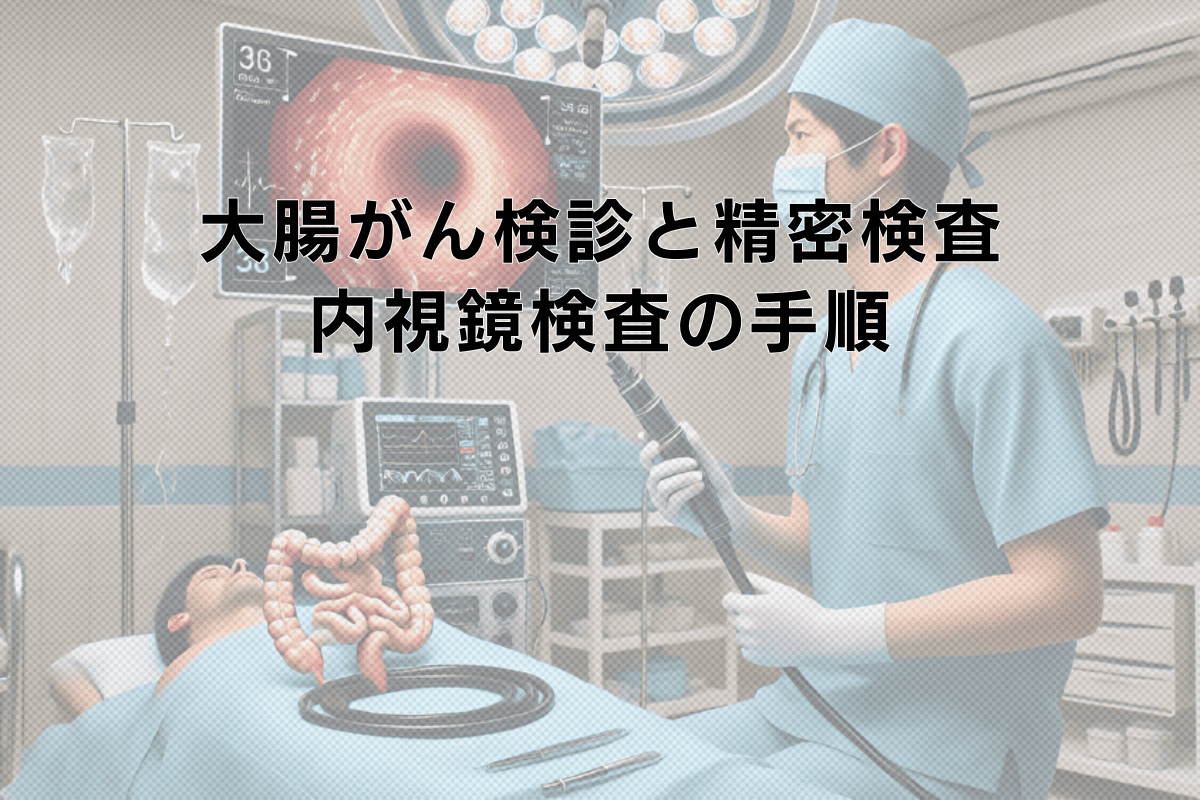
大腸内視鏡検査
内視鏡検査(大腸カメラ)は、肛門から内視鏡を挿入して大腸内を直接観察する検査で、腫瘍やポリープがあればその場で組織を採取して病理検査を行い、良性か悪性かを確認します。
早期の段階なら、小さなポリープや早期がんをその場で切除できることもあり、診断と治療が同時に可能な方法です。
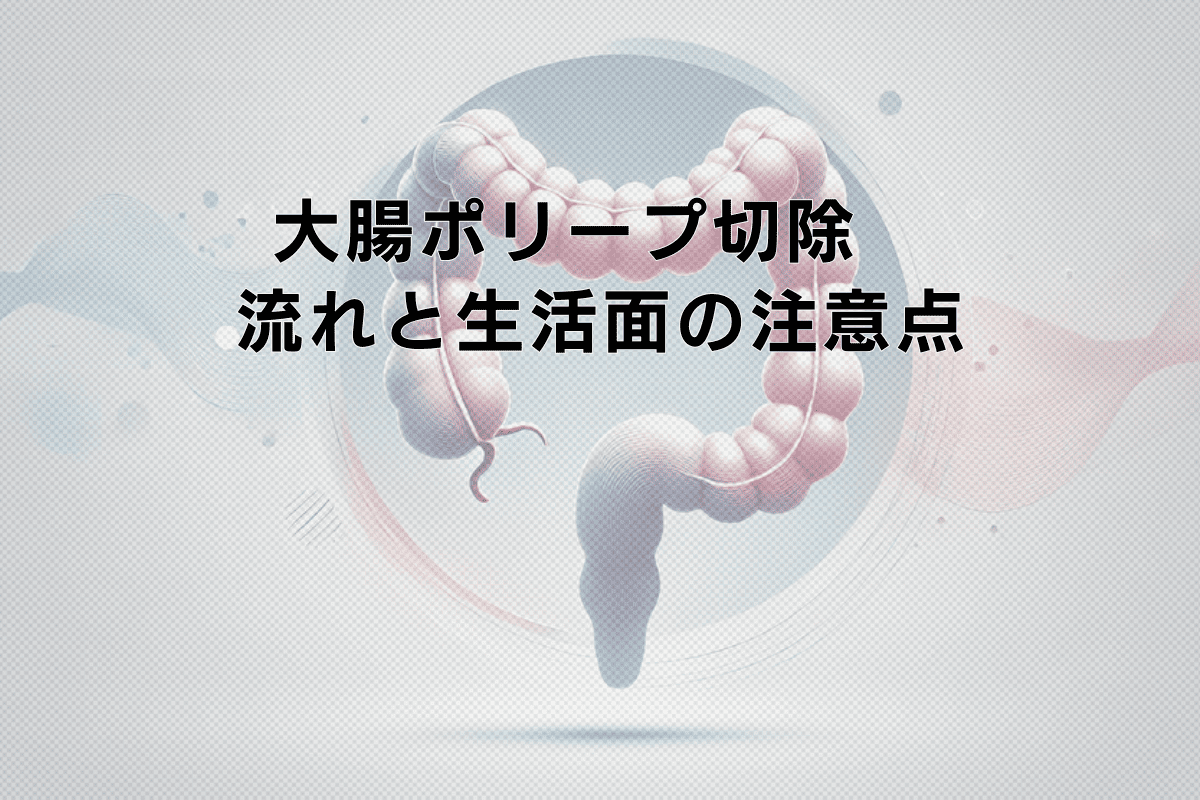
造影検査やCT検査
バリウムを用いた造影検査では、大腸内の形状をX線で映し出し、ポリープや腫瘍による欠損像を確認し、大腸CT検査(仮想内視鏡)では、CTスキャンの画像を解析することで3Dの大腸像を作り出し、ポリープなどの異常を発見します。
ただし、内視鏡検査よりも小さい病変を見逃す可能性があるため、最終的な確定診断には内視鏡検査が推奨されることが多いです。
血液検査
血液検査で腫瘍マーカー(CEA、CA19-9など)の値を測定することもあり、腫瘍マーカーが高い場合、大腸がんや他のがんが疑われる可能性がありますが、決定的な診断指標ではありません。
腫瘍マーカーは進行度や再発の監視に用いることが多く、陽性だからといって必ずしもがんであるとは限らない点に留意が必要です。
検査ごとのメリット・デメリット
| 検査名 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 便潜血検査 | 手軽で費用も比較的安価。大規模検診でよく使用 | 出血していない病変や偽陽性・偽陰性の可能性 |
| 大腸内視鏡検査 | 直接観察でき、必要に応じてポリープ切除も可能 | 前処置が大変、検査に多少の負担 |
| 造影検査 | 腸全体の形状をX線で確認できる | 小さい病変の見落としリスクあり |
| 大腸CT検査 | 3D表示で全体像を把握しやすい | 内視鏡ほど正確な診断は困難 |
| 腫瘍マーカー | 簡単な採血で数値の変動を把握 | がん以外でも値が変動することがある |
大腸がんの進行とステージ
大腸がんがどのように進行していくか、病期(ステージ)の概念とともに解説しますが、ステージは治療方針や予後に直結する重要な指標です。
ステージの概念
がんは、腫瘍の大きさやリンパ節転移の有無、遠隔転移の有無などに応じてステージに分類され、大腸がんのステージは0期からⅣ期まであり、数字が大きくなるほど進行度が高いです。
早期のステージ(0期やⅠ期)では内視鏡治療だけで完結する場合もありますが、Ⅲ期以上では手術や化学療法を組み合わせることが多くなります。
早期がんと進行がんの違い
早期の大腸がんは粘膜内や粘膜下層にとどまっており、腸壁を深く侵潤しておらず、内視鏡で切除可能な場合が多く、治療後の生存率も高いです。
進行した大腸がんは腸壁の筋層や漿膜を越えて浸潤し、リンパ節や他の臓器(肝臓や肺など)に転移するリスクが上がり、進行がんになると治療が複雑化し、手術や化学療法、放射線療法など複数の方法を検討する必要が出てきます。
転移の経路
大腸がんがリンパ節に転移しやすいことはよく知られていますが、血行性に肝臓や肺へ遠隔転移を起こすことも珍しくありません。
腫瘍が周囲の臓器へ直接浸潤するケースもあり、周囲組織との癒着が手術の難易度を上げることもあり、特に肝転移は大腸がんの代表的な転移先で、定期的な画像検査でフォローアップすることが大切です。
再発と経過観察
大腸がんの治療を終えても、一定の確率で再発する可能性があります。再発には局所再発(手術を行った部位付近)や遠隔再発(転移によるもの)があり、ステージが高いほど再発リスクは上昇します。
治療後も定期的に内視鏡検査や画像検査を受け、再発の早期発見と早期治療に努めることが重要です。

ステージ分類の大まかな目安
| ステージ | 腫瘍の深達度 | リンパ節転移 | 遠隔転移 |
|---|---|---|---|
| 0期 | 粘膜内 | なし | なし |
| Ⅰ期 | 粘膜下層、筋層まで | なし | なし |
| Ⅱ期 | 漿膜近くまたは超える | なし | なし |
| Ⅲ期 | 腸壁外へ浸潤 | あり | なし |
| Ⅳ期 | さらに広範囲へ浸潤 | ありorなし | あり(肝臓や肺など) |
大腸がんの主な治療法
大腸がんは他のがんと同様にステージや患者の体力、腫瘍の性質に応じてさまざまな治療が組み合わせられます。
内視鏡治療
早期の大腸がんや小さいポリープなどは、内視鏡的粘膜切除術(EMR)や内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)によって切除する場合があり、治療は体への負担が比較的小さく、入院期間が短い場合もあります。
ただし、がんが粘膜下層を越えて深く浸潤しているケースや、大きな腫瘍は内視鏡治療の適応外となることが多いです。

外科手術
結腸がんや直腸がんの手術では、腸管のがんを含む部分と、その周囲のリンパ節をまとめて切除し、直腸がんの場合は、腸管の位置や腫瘍の大きさに応じて人工肛門が必要になることもあります。
近年は腹腔鏡手術が普及し、開腹手術より傷が小さく回復が早い場合があると報告されていますが、腫瘍の進行度や部位によっては適応が限定されます。
化学療法
大腸がんの進行度が高い場合や、手術後の再発予防として化学療法(抗がん剤治療)が行われることがあり、複数の薬剤を組み合わせるレジメンが使用され、がん細胞の増殖を抑制し、再発リスクを下げる効果が期待されます。
抗がん剤は副作用があるため、治療中や治療後の副作用対策が大切です。
放射線療法
主に直腸がんの治療で、手術前に放射線療法を行って腫瘍を縮小させ、手術の成功率を高めるケースがあります。
化学療法と放射線療法を組み合わせる化学放射線療法も検討される場合があり、がんの部位や大きさ、患者の全身状態を考慮しながら最適な治療法を選択していきます。
免疫療法など
一部の大腸がんで、免疫チェックポイント阻害剤が効果を示す場合があるので、遺伝子変異の有無などを調べることで、免疫療法が適応になるかどうか判断されます。
しかし、誰にでも同様の効果が期待できるわけではないため、医師との十分な相談が重要です。
治療法ごとの特徴と留意点
| 治療法 | 主な適応ステージ | 特徴 | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 内視鏡治療 | 0期、Ⅰ期が中心 | 体への負担が比較的小さい | 腫瘍が大きい場合は適応外 |
| 外科手術 | 0期~Ⅲ期、Ⅳ期の一部 | 根治を目指せる可能性が高い | 術後の合併症リスク、人工肛門の可能性 |
| 化学療法 | Ⅱ期~Ⅳ期 | がん細胞の増殖を抑制、再発防止を図る | 副作用対策が必要 |
| 放射線療法 | 主に直腸がん | 手術前に腫瘍を縮小、化学療法との併用もあり | 周辺組織への照射の副作用 |
| 免疫療法 | 特定の遺伝子変異 | 免疫の働きを活性化 | 適応例が限られる |
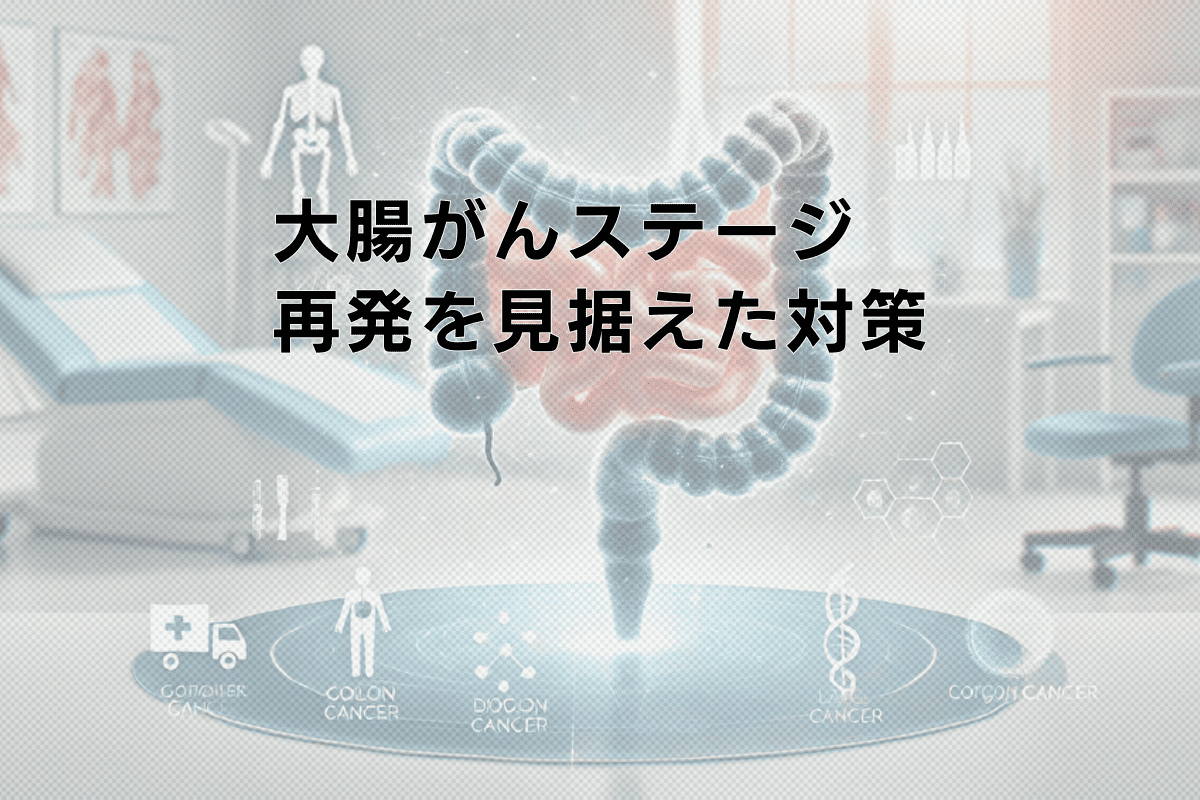
日常生活での注意点と予防
大腸がんの予防と治療後の再発予防のためには、日常生活の見直しが大切で、食生活や運動習慣など具体的な工夫を紹介します。
食習慣の見直し
高脂肪・高カロリーの食事、加工肉や赤身肉の過剰摂取は、大腸がんのリスクを高める傾向がある一方で、食物繊維やビタミン、ミネラルを豊富に含む野菜や果物は腸の健康を保つ助けになります。
魚や大豆製品など良質なたんぱく源を取り入れつつ、バランスの良い食事を心がけると腸内環境を整えやすいです。
大腸がん予防に役立つ食品
| 食品の種類 | 主な栄養素 | 期待できる働き |
|---|---|---|
| 野菜・果物 | 食物繊維、ビタミン類 | 便通を良好に保ち、酸化ダメージを抑える |
| 魚 | 良質なたんぱく質、DHA・EPA | 体に必要な栄養を補い、炎症を抑える可能性 |
| 大豆製品 | 植物性たんぱく質、イソフラボン | ホルモンバランスを整える助けになることがある |
| 発酵食品 | 乳酸菌など | 腸内環境を整えて、便通をスムーズにする |
適度な運動と体重管理
週に数回程度のウォーキングや水泳、軽いジョギングなど、有酸素運動を継続的に行うと、腸の蠕動運動が活性化して便通が良くなります。また、肥満は大腸がんのリスク要因の1つでもあり、体重を適正範囲に維持することが大切です。
禁煙と飲酒制限
喫煙は大腸がんのみならず、肺がんや胃がんなど多くのがんに関連するリスクを高めるので、タバコを吸っている人は、この機会に禁煙を検討してください。
飲酒は適量を大きく超えるとリスク増大につながるため、節度ある範囲での嗜み方を心がける必要があります。
生活習慣で気をつけるポイント
- 炭水化物や脂肪に偏らない食事を意識する
- 毎日20~30分程度の有酸素運動を取り入れる
- タバコは控える、あるいは完全にやめる
- アルコールは適量に抑える
- 便の形状や回数、色に日頃から目を向ける
定期的な検診と早期発見
大腸がんは無症状のまま進行することがあり、早期発見には定期的な検診が欠かせず、便潜血検査で陽性になった場合は、放置せずに内視鏡検査を受けることが重要です。
40歳を過ぎたら、少なくとも数年に1回のペースで便潜血検査や大腸内視鏡検査を受けることを検討してください。
病院・クリニックを受診するタイミング
早期診断につなげるためには、不調を感じた段階で相談することがポイントで、自覚症状や検診結果などを踏まえ、どのようなタイミングで受診すればよいかを説明します
便に血が混じっている場合
血便や下血が見られた場合、痔などの良性疾患が原因のこともありますが、大腸がんの可能性を否定できないため早めの受診が大切です。特に便の表面に鮮血が付着していたり、トイレで便器が赤く染まる場合には専門医の診断を受けましょう。
長引く便通異常や腹痛
便秘や下痢が断続的に続いたり、腹痛が慢性的に続いているような場合、大腸がんや大腸ポリープなどの器質的疾患も視野に入れる必要があります。
市販薬で症状をやり過ごす前に、専門医に相談して原因をはっきりさせると、適切な対処につながりやすいです。
大腸がんの疑いを持つタイミング
| タイミング | 対処法 |
|---|---|
| 血便・黒色便に気づいた | 消化器内科や外科を受診して、便潜血検査や内視鏡検査を検討 |
| 慢性的な便通異常(下痢・便秘の繰り返し、細い便など) | 医師に相談し、原因が機能性か器質性かを鑑別 |
| 家族に大腸がんの既往歴が多い | 若い年代から定期的に大腸カメラを検討 |
| 腹痛や腹部膨満感が長期間続く | 腸閉塞や腫瘍の可能性を考慮し、専門医に相談 |
検診での異常結果
便潜血検査で陽性だった場合や、血液検査や人間ドックの結果で何らかの異常が認められた場合も、放置せず速やかに医療機関を受診すると安心です。疑わしい兆候があれば検査を受け、必要に応じた治療や経過観察を進めましょう。
不安な時は専門医に相談
インターネットや書籍の情報は参考になりますが、自己判断はリスクがあります。腹痛や血便などの症状があるときは、消化器科や消化器内科、外科などの専門医を受診し、内視鏡検査や画像診断を実際に受けることが大切です。
まとめ
大腸がんは男女を問わず発症リスクがあり、早期の段階では自覚症状に乏しく、便の状態や血便、慢性的な腹痛、体重減少などに気づいたときには、がんの可能性も視野に入れ、医療機関を受診することが重要です。
便潜血検査や大腸内視鏡検査は、比較的確実に腫瘍やポリープを見つける手段で、早期に発見できれば内視鏡治療など負担の少ない方法で治せるチャンスが高まります。
治療には内視鏡治療、外科手術、化学療法、放射線療法などがあり、ステージや患者さんの状態に合わせて選択されます。
生活習慣の改善や定期的な検診の受診は、大腸がんの発症や再発リスクを下げるためにも大切です。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査とはどのような検査なのか】
大腸がんの症状について理解できたら、次は実際の検査方法について、この記事で一緒に勉強してまいりましょう。検査への不安を軽減し、適切なタイミングで受診を検討されている方に特におすすめです。
【大腸がん初期症状の見逃しを防ぐ 便の変化や腹痛の基本知識】
大腸がんの全体像についての理解が深まりましたら、さらに初期症状の具体的な見分け方についても知っておくと、より早期の気づきにつながります。この記事で一緒に学んでまいりましょう。
参考文献
Cappell MS. Pathophysiology, clinical presentation, and management of colon cancer. Gastroenterology Clinics of North America. 2008 Mar 1;37(1):1-24.
Holtedahl K, Borgquist L, Donker GA, Buntinx F, Weller D, Campbell C, Månsson J, Hammersley V, Braaten T, Parajuli R. Symptoms and signs of colorectal cancer, with differences between proximal and distal colon cancer: a prospective cohort study of diagnostic accuracy in primary care. BMC family practice. 2021 Dec;22:1-3.
Alexiusdottir KK, Möller PH, Snaebjornsson P, Jonasson L, Olafsdottir EJ, Björnsson ES, Tryggvadottir L, Jonasson JG. Association of symptoms of colon cancer patients with tumor location and TNM tumor stage. Scandinavian journal of gastroenterology. 2012 Jul 1;47(7):795-801.
McDermott FT, Hughes ES, Pihl E, Milne BJ, Price AB. Prognosis in relation to symptom duration in colon cancer. British journal of surgery. 1981 Dec;68(12):846-9.
Alsayed MA, Surrati AM, Altaifi JA, Alharbi AH, Alfouti RO, Alremaithi SM. Public Awareness of Colon Cancer Symptoms, Risk Factor, and Screening at Madinah-KSA. International Journal Of Pharmaceutical Research & Allied Sciences. 2019 Jan 1;8(1).
Sun V, Borneman T, Koczywas M, Cristea M, Piper BF, Uman G, Ferrell B. Quality of life and barriers to symptom management in colon cancer. European Journal of Oncology Nursing. 2012 Jul 1;16(3):276-80.
Duineveld LA, van Asselt KM, Bemelman WA, Smits AB, Tanis PJ, van Weert HC, Wind J. Symptomatic and asymptomatic colon cancer recurrence: a multicenter cohort study. The Annals of Family Medicine. 2016 May 1;14(3):215-20.
Greenwald P. Colon cancer overview. Cancer. 1992 Sep 1;70(S3):1206-15.
Ahmed M. Colon cancer: a clinician’s perspective in 2019. Gastroenterology research. 2020 Feb;13(1):1.
Jullumstrø E, Lydersen S, Møller B, Dahl O, Edna TH. Duration of symptoms, stage at diagnosis and relative survival in colon and rectal cancer. European Journal of Cancer. 2009 Sep 1;45(13):2383-90.