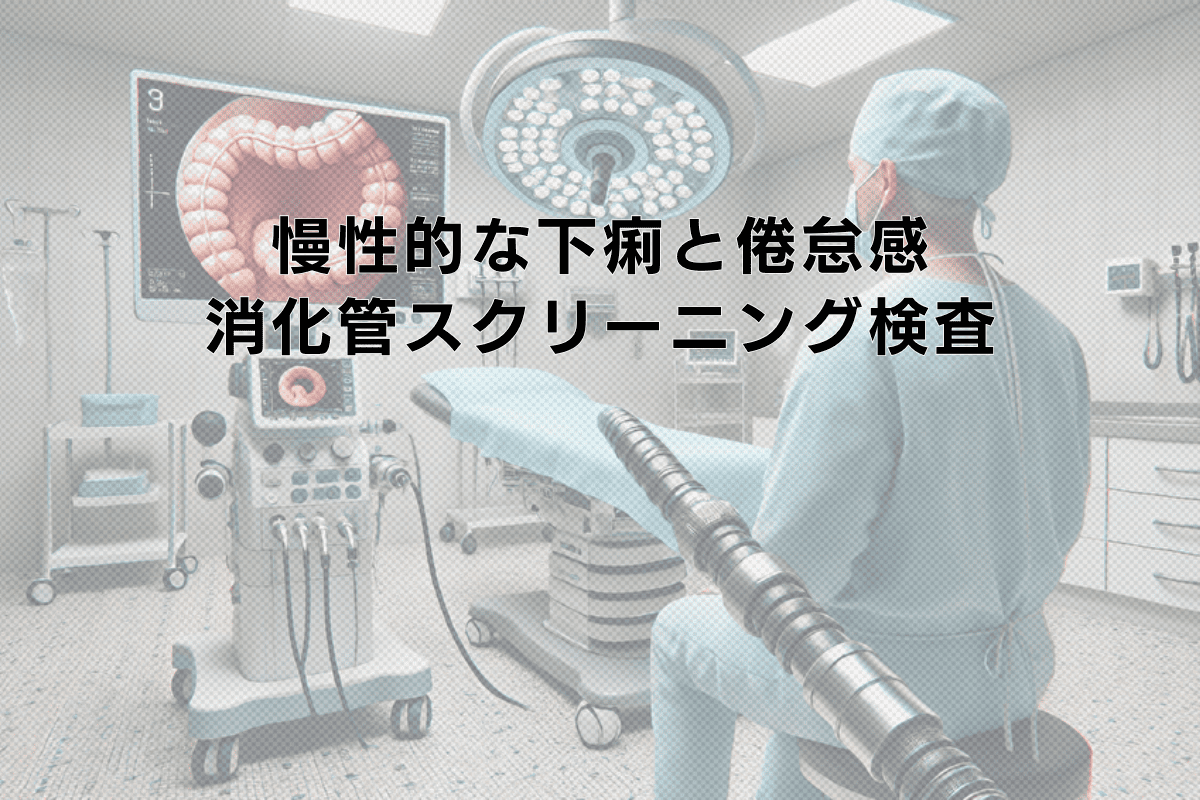数週間にわたって下痢が続き、同時に体のだるさやしんどい感覚が抜けないというような経験はありませんか。
一時的な体調不良だと思っていても、長く続く症状の裏には、消化管の何らかの異常が隠れている可能性があります。
この記事では、慢性的な下痢と倦怠感の原因となりうる病気や、診断のために行われる消化管のスクリーニング検査について詳しく解説します。
下痢と倦怠感が同時に起こる背景
下痢と倦怠感は多くの方が経験するありふれた症状ですが、二つが同時に慢性的に続く場合、体の中で何が起きているのでしょうか。
水分と電解質の損失
私たちの体は約60%が水分で構成されていて、体液には、ナトリウムやカリウム、クロールといった電解質が溶け込んでおり、神経の伝達や筋肉の収縮など、生命活動の維持に重要な役割を担っています。
下痢が続くと、便として排出される水分量が著しく増加し、同時に、重要な電解質も大量に失われます。体が脱水状態に陥り電解質のバランスが崩れると、筋肉の力が入りにくくなったり、意識がもうろうとしたりします。
これが、しんどいと感じる倦怠感の直接的な原因の一つです。
体液バランスに関わる主な電解質
| 電解質 | 主な役割 | 欠乏時の主な症状 |
|---|---|---|
| ナトリウム | 体液量の調節、神経伝達 | 倦怠感、頭痛、吐き気 |
| カリウム | 筋肉の収縮、心臓の機能維持 | 脱力感、不整脈、筋力低下 |
| クロール | 浸透圧の維持、胃酸の生成 | 筋痙攣、めまい |
栄養吸収の障害
食べ物からエネルギーや体の材料となる栄養素を吸収する小腸や大腸の働きは、私たちが元気に活動するために欠かせません。
しかし、消化管に炎症や何らかの機能異常があると、栄養吸収がうまくいかなくなり、炭水化物や脂質、タンパク質といった三大栄養素の吸収が妨げられると、体はエネルギー不足に陥ります。
また、活動に必要なビタミンや、血液を作るために大事な鉄分などのミネラルの吸収も低下し、貧血になったりエネルギーを生み出す効率が悪くなり、持続的な倦怠感や疲労感につながるのです。
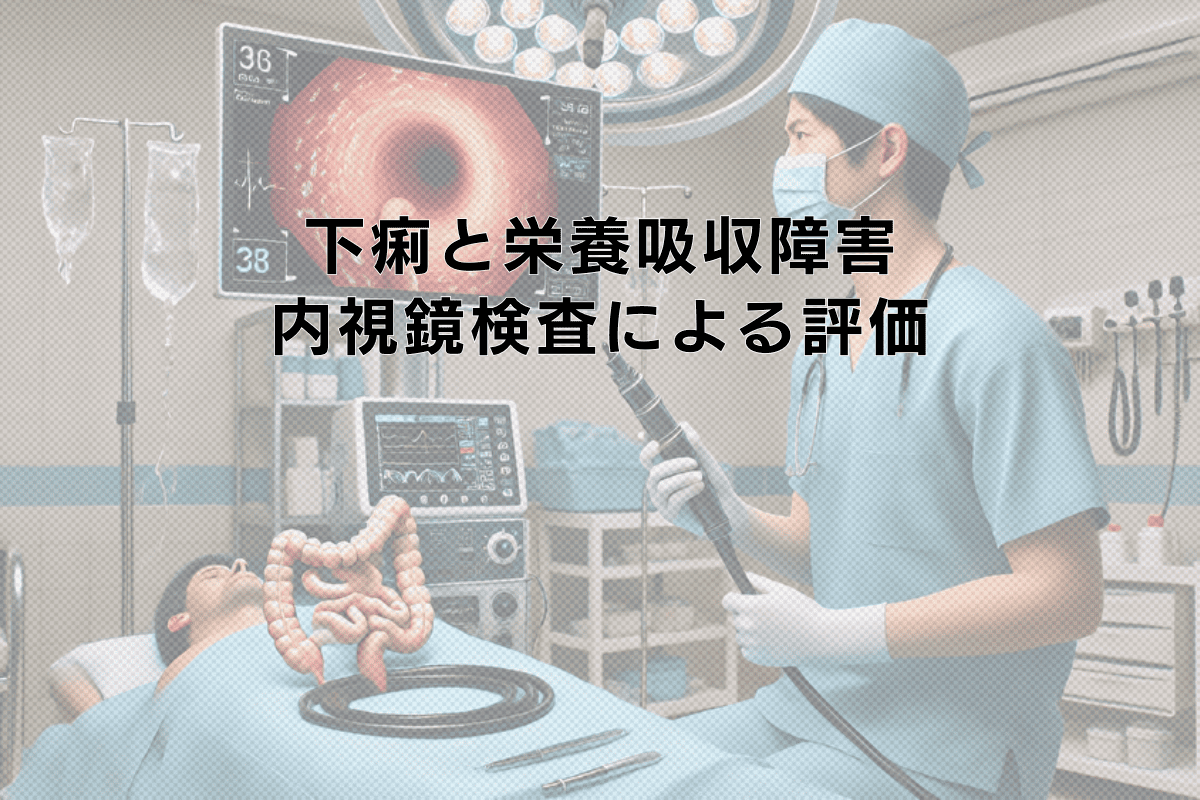
消化管の炎症反応
消化管の粘膜が病原体への感染や自己免疫の異常などによって炎症を起こすと、体は治そうと防御反応を示し、サイトカインという物質が体内で放出されます。
サイトカインは、免疫細胞を活性化させて炎症をコントロールする重要な役割を持ちますが、同時に脳にも作用して、発熱や食欲不振、そして強い倦怠感を起こすことが知られています。
インフルエンザにかかったときに感じる独特のだるさも、サイトカインの働きによるものです。
慢性的な下痢の原因が消化管の持続的な炎症にある場合、サイトカインが常に体内で作られ続けることになり、長引く倦怠感の原因となります。
慢性的な下痢と倦怠感を起こす消化器の病気
長引く下痢と倦怠感は、消化器系の病気が原因となっている場合があります。症状は似ていても、背景にある病気は様々です。ここでは、代表的な消化器疾患について解説します。
感染性腸炎
ウイルスや細菌などの病原体が腸に感染することで起こる病気です。
通常は急性の下痢を起こしますが、一部の病原体では症状が長引くことがあり、旅行者下痢症の原因となる特定の細菌や、ジアルジアなどの原虫感染では、数週間にわたり下痢や腹部不快感、倦怠感が続くことがあります。
汚染された水や食べ物の摂取が原因となることが多く、海外渡航歴や特定の食品の喫食歴が診断の手がかりになることもあります。
下痢を起こす主な病原体
| 分類 | 代表的な病原体 | 特徴 |
|---|---|---|
| ウイルス | ノロウイルス、ロタウイルス | 冬場に多く、感染力が強い |
| 細菌 | カンピロバクター、サルモネラ菌 | 食中毒の原因となることが多い |
| 原虫 | クリプトスポリジウム、ジアルジア | 症状が長期化することがある |
炎症性腸疾患(IBD)
炎症性腸疾患は、主にクローン病と潰瘍性大腸炎で、自身の免疫系が消化管を誤って攻撃してしまうことで、腸に慢性的 な炎症や潰瘍を起こす原因不明の病気です。
下痢や腹痛、血便といった消化器症状に加え、発熱や体重減少、強い倦怠感が特徴的な症状として現れます。
活動期と寛解期(症状が落ち着いている時期)を繰り返しながら、長く付き合っていく必要があり、若年層での発症が多いことも特徴です。
過敏性腸症候群(IBS)
明らかな炎症や潰瘍などの器質的な異常がないにもかかわらず、腹痛や腹部の不快感、下痢や便秘などの便通異常が慢性的に続く病気です。ストレスや生活習慣の乱れが、腸の運動機能や知覚過敏に影響を与えることが原因と考えられています。
下痢が主な症状となる下痢型のIBSでは、突然の便意に悩まされたり通勤や通学が困難になったりするなど、生活の質に大きく影響し、倦怠感や頭痛、不眠といった腸以外の症状を伴うことも少なくありません。
炎症性腸疾患と過敏性腸症候群の症状比較
| 症状 | 炎症性腸疾患(IBD) | 過敏性腸症候群(IBS) |
|---|---|---|
| 血便 | しばしば見られる | 基本的にはない |
| 発熱・体重減少 | 見られることがある | まれ |
| 内視鏡所見 | 潰瘍や炎症などの異常あり | 明らかな異常なし |
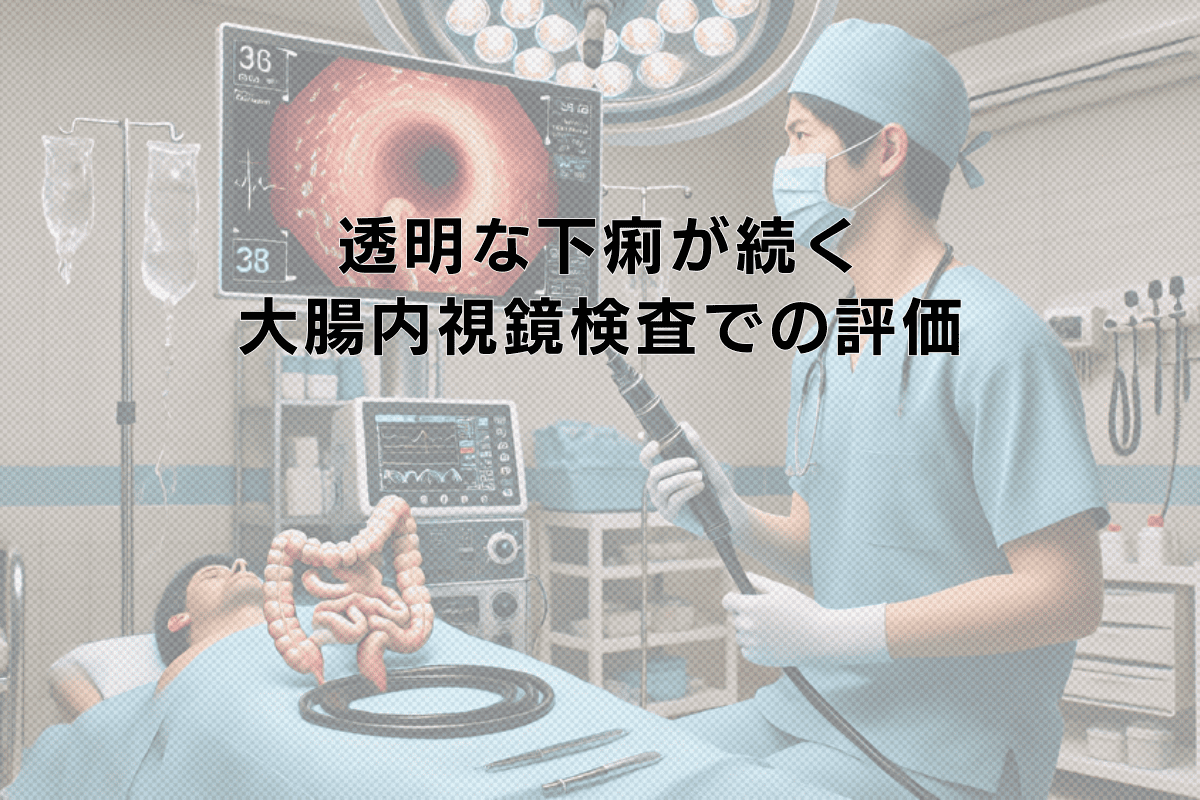
その他の消化器疾患
上記以外にも、慢性的な下痢と倦怠感の原因となる病気はあります。例えば、セリアック病は、小麦などに含まれるグルテンに対する免疫反応が小腸の粘膜を傷つけ、吸収不良を起こす病気です。
また、顕微鏡的大腸炎は内視鏡では正常に見えても、組織を顕微鏡で調べると炎症が見つかる病気で、水様性の下痢が特徴で、膵臓の機能低下による消化不良や、甲状腺機能亢進症のような内分泌系の病気が原因で下痢が続くこともあります。
自己判断のリスクと医療機関受診の重要性
症状が続くとインターネットで調べたり、市販薬を試したりする方も多いかもしれませんが、安易な自己判断には危険が伴います。なぜ専門家である医師の診断が必要なのか、解説します。
症状の悪化と慢性化
市販の下痢止めは、一時的に症状を抑える効果があるかもしれませんが、原因が取り除かれたわけではないため、薬の効果が切れると症状が再発します。
感染性腸炎の場合下痢止めで腸の動きを無理に止めると、病原体や毒素の排出が遅れ、かえって回復を妨げてしまうことがあります。
原因に応じて対応をしないまま時間を過ごすと、症状がだらだらと続き、生活の質を著しく低下させます。
重篤な病気の見逃し
慢性的な下痢と倦怠感は、時に大腸がんなどの重篤な病気のサインである可能性も否定できません。
注意すべき危険信号(レッドフラッグサイン)
- 意図しない体重減少
- 血便や黒色便
- 夜間に下痢で目が覚める
- 50歳以上で初めて出現した症状
- 大腸がんや炎症性腸疾患の家族歴

不適切な市販薬の使用
薬局では様々な種類の胃腸薬が販売されていますが、自分の症状の原因が何であるかわからないまま薬を選ぶのは、的の外れた治療を試みるようなものです。
過敏性腸症候群の症状を和らげる薬は炎症性腸疾患には効果がありませんし、治療を受ける機会を遅らせるだけです。また、抗生物質の乱用は、腸内細菌のバランスを崩し、新たな問題を起こす可能性もあります。
市販薬使用における注意点
| 薬剤の種類 | 主な作用 | 注意すべき点 |
|---|---|---|
| 止瀉薬(下痢止め) | 腸の動きを抑える | 感染性腸炎では使用に注意が必要 |
| 整腸剤 | 腸内環境を整える | 根本的な原因解決には至らない場合がある |
| 鎮痙薬 | 腹痛を和らげる | 器質的疾患の症状を隠してしまう可能性がある |
消化管スクリーニング検査の概要
医療機関では症状の原因を特定するために様々な検査を組み合わせて行い、これをスクリーニング検査と呼びます。問診から始まり、血液検査、便検査、そして内視鏡検査など、段階的に原因を絞り込んでいきます。
スクリーニング検査の目的
スクリーニング検査の最大の目的は、症状の背後にある原因を正確に突き止めることです。炎症の有無や程度、感染症の存在、栄養状態、さらにはがんなどの悪性疾患の可能性を評価します。
原因がわかれば最も効果的な治療方針を立てることができ、また、過敏性腸症候群のように重篤な病気がないことを確認すること自体が、患者さんの安心につながり、治療の第一歩となる場合もあります。
どのような場合に検査を検討するか
すべての下痢や倦怠感で、大がかりな検査が必要ではないものの、特定の条件に当てはまる場合は、詳しい検査を検討することが推奨されます。
症状が数週間以上続いている、市販薬で改善しない、体重が減ってきた、血便があるといった場合は、一度専門医に相談するのがよいでしょう。
検査を検討するべき症状や状況
| 項目 | 具体例 | 解説 |
|---|---|---|
| 症状の持続期間 | 4週間以上続く下痢 | 一過性ではない可能性が高い |
| 危険信号 | 体重減少、血便、発熱 | 重篤な疾患の可能性を考慮する |
| 年齢 | 50歳以上 | 大腸がんなどのリスクが高まる |
検査までの一般的な流れ
まずは、医師による詳しい問診から始まり、いつからどのような症状があるのか、食事の内容、海外渡航歴、家族の病気などについて詳しく話を聞きます。その後、身体診察でお腹の音を聞いたり、触って痛みがないかなどを確認します。
このような情報をもとに、医師は必要な検査を計画します。血液検査や便検査は比較的簡単に行えますが、内視鏡検査など、準備が必要な検査については、日程を調整して後日行うことになります。
具体的な消化管スクリーニング検査の種類
ここでは、実際に行われる主なスクリーニング検査について、一つひとつ見ていきます。
問診や身体診察といった基本的な診察から、血液検査、便検査、そして消化管の内部を直接観察する内視鏡検査まで、それぞれの検査がどのようなもので、何を調べるために行われるのかを理解しましょう。
問診と身体診察
診断の第一歩であり、最も重要な情報源です。医師は患者さんの話に耳を傾け、症状の詳しい内容(下痢の頻度、便の性状、腹痛の場所など)、生活習慣、既往歴などを聞き取り、考えられる病気をおおよそ絞り込みます。
身体診察では聴診、打診、触診などを行い、お腹の状態を客観的に評価し、基本的な診察から得られる情報が、その後の検査計画の土台です。
血液検査
採血によって、全身の状態を把握するための多くの情報を得られます。
体内の炎症の程度を示すCRP(C反応性タンパク)や赤沈(血沈)、貧血の有無を調べる血球数(ヘモグロビン値など)、栄養状態を反映するアルブミン値、肝臓や腎臓、甲状腺の機能などを評価します。
結果から、炎症性腸疾患の活動性や、栄養吸収障害による貧血、その他の内臓疾患の可能性などを探ります。
血液検査で評価する主な項目
| 検査項目 | 何がわかるか | 基準値から外れる場合の主な原因 |
|---|---|---|
| CRP / 赤沈 | 体内の炎症の強さ | 感染症、炎症性腸疾患 |
| ヘモグロビン | 貧血の有無 | 消化管出血、鉄分吸収障害 |
| アルブミン | 栄養状態 | 栄養吸収障害、タンパク漏出 |
便検査
便そのものを調べることで、消化管の状態に関する直接的な情報を得られます。
目には見えない微量の出血がないかを調べる便潜血検査、細菌やウイルスがいないかを確認する便培養検査、腸の炎症の程度を数値で評価する便中カルプロテクチン検査などがあります。
特に便中カルプロテクチン検査は、炎症性腸疾患と過敏性腸症候群を区別するのに役立つ、比較的新しい検査です。
目的別の主な便検査
| 検査名 | 主な目的 | 陽性の場合に疑われること |
|---|---|---|
| 便潜血検査 | 消化管出血の有無 | 大腸ポリープ、大腸がん、炎症 |
| 便培養検査 | 病原性細菌の有無 | 感染性腸炎 |
| 便中カルプロテクチン | 腸管の炎症の程度 | 炎症性腸疾患 |
内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)
先端にカメラがついた細い管(スコープ)を口や肛門から挿入し、食道、胃、十二指腸や、大腸全体の粘膜を直接観察する検査で、炎症や潰瘍、ポリープ、がんなどの病変をリアルタイムで確認できます。
また、疑わしい部分があれば、その場で組織の一部を採取(生検)し、顕微鏡で詳しく調べる病理組織検査を行うことも可能です。
各検査でわかることと準備
それぞれの検査が診断においてどのような役割を果たすのか、そして検査を受けるにあたってどのような準備が必要になるのかを詳しく解説します。
血液検査から得られる情報
血液検査は、消化管の病気を間接的に評価するのに役立ちます。
CRPが高値であれば腸に強い炎症が起きている可能性を示唆し、炎症性腸疾患が疑われ、ヘモグロビン値が低ければ、自覚症状のない消化管からの出血や、鉄分の吸収不良が考えられます。
また、特定の抗体を調べることで、セリアック病のスクリーニングも可能です。
便検査の重要性と採取方法
便検査は、患者さん自身で便を採取する必要があるため、正しい方法で行うことが重要です。検査容器や採取方法は検査の種類によって異なりますので、医療機関の指示に正確に従ってください。
便潜血検査
大腸がん検診で広く行われる検査で、便の表面を専用のスティックでこすって採取します。食事制限は通常必要ありません。
便培養検査
感染が疑われる場合に行います。下痢便の中からできるだけ粘液や血液が混じっている部分を採取すると、原因菌が見つかりやすくなります。
便中カルプロテクチン検査
少量の便を専用の容器に採取します。この検査は腸の炎症度を客観的に評価できるため、症状の原因が炎症によるものか、機能的なものかを判断する上で非常に有用です。
内視鏡検査の実際と前処置
内視鏡検査は、消化管の内部を直接見ることができる最も確実な診断法の一つです。
胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)は、前日の夜から絶食するだけで比較的簡単な準備で済む一方、大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査)は、腸の中を空にしてきれいにするために、しっかりとした前処置が必要になります。
大腸カメラのための食事(検査前日)の例
| 食べてよいもの | 避けるべきもの | 理由 |
|---|---|---|
| 素うどん、おかゆ、白米 | 玄米、雑穀パン、そば | 繊維が多く腸に残りやすい |
| 豆腐、卵、白身魚 | キノコ類、海藻類、ゴマ | 消化が悪く腸壁に付着する |
| 具のないスープ、透明な飲料 | 牛乳、色の濃いジュース | 腸内視認性の低下や誤診の原因になる |
検査後の対応と生活上の注意点
検査を受けて終わりではなく、検査結果に基づいて正確な診断を受け、治療を開始することがゴールです。また、診断された病気と上手く付き合っていくためには、日々の生活習慣や食事を見直すことも重要になります。
検査結果の解釈
すべての検査結果が出揃ったら、医師がそ総合的に解釈し診断を伝えます。なぜその診断に至ったのか、それぞれの検査結果が何を示しているのかについて、説明を受けましょう。疑問や不安な点があれば、質問することが大切です。
診断に基づく治療方針
診断が確定したら、病気に合わせた治療を開始します。炎症性腸疾患であれば炎症を抑えるための薬物療法が中心で、過敏性腸症候群であれば、生活習慣の改善指導や症状をコントロールする薬が処方されます。
また、感染性腸炎であれば、原因となる病原体に応じた抗菌薬や、症状を和らげる対症療法を行います。
食事や生活習慣で心がけること
病気の種類や状態によって推奨される食事は異なりますが、一般的に、消化管に負担をかけない食生活が基本です。暴飲暴食を避け、消化の良いものを中心にバランスの取れた食事を心がけましょう。
また、十分な睡眠、適度な運動、ストレス管理も、腸の健康を保つ上で大事な要素です。
定期的な経過観察の大切さ
慢性的な消化器疾患の多くは一度の治療で完治するものではなく、長期的な管理が必要で、症状が落ち着いている寛解期であっても、定期的に医療機関を受診し、経過を観察することが重要です。
よくある質問
消化管の検査に関して、多くの方が抱く疑問や不安についてお答えします。事前に知っておくことで、安心して検査に臨めます。
- 検査は痛いですか
-
感じ方には個人差がありますが、医療機関では苦痛を最小限に抑えるための工夫をしていて、胃カメラでは、喉の麻酔をしっかり行います。
また、希望に応じて鎮静剤を使用することで、うとうとと眠っているような状態で検査を受けることも可能です。
大腸カメラでも同様に鎮静剤が使え、特に、お腹の手術歴がある方や、痩せ型で腸が曲がりくねっている方は、鎮静剤の使用を検討すると良いでしょう。
- 検査にかかる時間はどのくらいですか
-
検査そのものにかかる時間は、胃カメラで5分から10分程度、大腸カメラで15分から30分程度が目安です。ただし、これは観察のみの場合で、ポリープの切除など処置を行う場合はもう少し時間がかかります。
また、検査前の準備や、鎮静剤を使用した後の休憩時間を含めると、来院から帰宅まで全体で2時間から3時間程度を見ておくと安心です。
- 検査後すぐに普段の生活に戻れますか
-
鎮静剤を使用しなかった場合は、検査終了後すぐに日常生活に戻れます。食事も、特に指示がなければ普段通りで構いません。鎮静剤を使用した場合は、検査当日は意識がはっきりするまで院内で1時間ほど休む必要があります。
また、安全のため、当日は車やバイク、自転車の運転はできず、重要な判断を伴う仕事や、危険な作業も避けてください。
次に読むことをお勧めする記事
【下痢と腹部症状だけが出るときの消化管内視鏡検査の重要性】
慢性的な下痢と倦怠感の基本を押さえたら、次は実際の内視鏡検査がどのような場合に必要になるかを知っておくと安心です。症状の見極めと適切な受診タイミングを判断する際に特に参考になる内容です。
【下痢と栄養吸収障害の関係|内視鏡検査による腸管機能の評価】
倦怠感=栄養吸収不良という視点を加えると小腸病変や膵機能まで見渡せます。鉄欠乏・脂肪便などのサインを整理し、検査の意義を再確認。
参考文献
Matsumoto Y, Nadatani Y, Otani K, Higashimori A, Ominami M, Fukunaga S, Hosomi S, Kamata N, Kimura T, Fukumoto S, Tanaka F. Prevalence and risk factor for chronic diarrhea in participants of a Japanese medical checkup. JGH Open. 2022 Jan;6(1):69-75.
Tanaka M, Takai M, Wakai S, Sakagami K, Ito H. Understanding fatigue among Japanese patients with inflammatory bowel disease: insights from international comparisons and meta-analysis. Intestinal Research. 2025 Jan 22.
Ihara E, Manabe N, Ohkubo H, Ogasawara N, Ogino H, Kakimoto K, Kanazawa M, Kawahara H, Kusano C, Kuribayashi S, Sawada A. Evidence-based clinical guidelines for chronic diarrhea 2023. Digestion. 2024 Dec 9;105(6):480-97.
Tokuda Y, Takahashi O, Ohde S, Shakudo M, Yanai H, Shimbo T, Fukuhara S, Hinohara S, Fukui T. Gastrointestinal symptoms in a Japanese population: a health diary study. World Journal of Gastroenterology: WJG. 2007 Jan 28;13(4):572.
Raman M. Testing for chronic diarrhea. InAdvances in Clinical Chemistry 2017 Jan 1 (Vol. 79, pp. 199-244). Elsevier.
Juckett G, Trivedi R. Evaluation of chronic diarrhea. American family physician. 2011 Nov 15;84(10):1119-26.
Schiller LR, Pardi DS, Sellin JH. Chronic diarrhea: diagnosis and management. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2017 Feb 1;15(2):182-93.
Sujatha-Bhaskar S, Grigorian A, de Virgilio C. Fatigue and Bloody Diarrhea. InSurgery: A Case Based Clinical Review 2019 Oct 17 (pp. 303-309). Cham: Springer International Publishing.
Burgers K, Lindberg B, Bevis ZJ. Chronic diarrhea in adults: evaluation and differential diagnosis. American family physician. 2020 Apr 15;101(8):472-80.
Hanevik K, Kristoffersen EK, Sørnes S, Mørch K, Næss H, Rivenes AC, Bødtker JE, Hausken T, Langeland N. Immunophenotyping in post-giardiasis functional gastrointestinal disease and chronic fatigue syndrome. BMC infectious diseases. 2012 Dec;12:1-9.