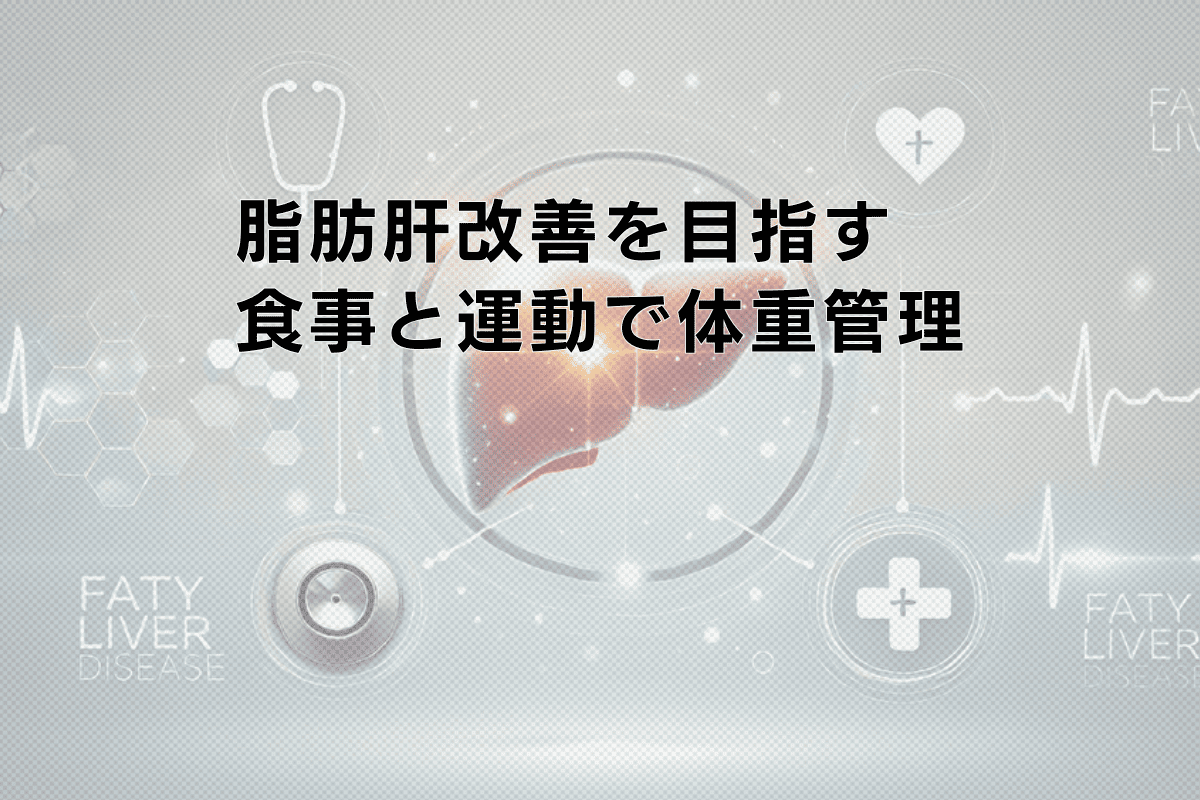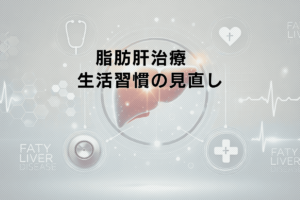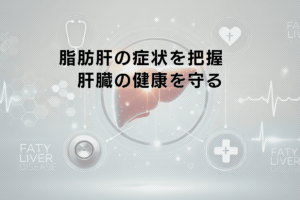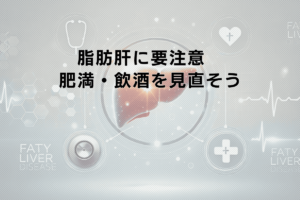脂肪肝は肝臓に脂肪が過剰にたまっている状態を指し、肥満や糖質の摂取量が多い方だけでなく、アルコールをよく飲む方や運動不足の方にも起こる疾患です。
脂肪が肝臓にたまっていると聞くと軽く考えがちですが、放置すると肝硬変や肝がんなどの深刻な病気に進行する可能性があります。
ここでは、脂肪肝の原因や症状、生活習慣の見直し方法、治療と受診の目安などを解説しながら、食事や運動で肝臓をいたわる具体的な取り組みを紹介します。
脂肪肝とはどんな状態か
脂肪肝は、肝臓に脂肪が過剰に蓄積し、肝細胞の機能が損なわれやすくなる状態で、肝臓は体内のエネルギーや脂質、毒素の代謝を担う重要な器官なので、その働きが滞ると全身の健康に影響を及ぼします。
肝臓が担う働き
肝臓はタンパク質や脂質、糖質の代謝だけでなく、アルコールや薬物などの分解機能を担い、中性脂肪の合成や消化液である胆汁の生成など多彩な役割を果たしています。
こうした代謝活動によって体内のバランスが保たれ、エネルギーの産生や老廃物の処理が効率よく進むのが正常な状態です。
脂肪が増える仕組み
過剰なカロリー摂取や飲酒、糖質のとり過ぎなどによって消費しきれないエネルギーが脂肪として肝臓に蓄えられ、脂肪肝になります。肥満だけでなく、無理なダイエットや食事内容の偏りでも肝機能が乱れ、中性脂肪が蓄積することがあります。
アルコール性と非アルコール性
脂肪肝はアルコール性脂肪肝と非アルコール性脂肪肝(MASLD)に大きく分かれます。
アルコール性の場合は、習慣的な飲酒量の多さが原因となりやすく、非アルコール性の場合は肥満や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病の影響が大きいです。
いずれも放置すると肝硬変や肝炎へと進行する可能性があるため、早い段階で改善を意識することが重要です。
自覚症状の少なさ
脂肪肝は自覚症状が乏しく、「健康診断の血液検査で初めて中性脂肪の数値が高いと言われた」「人間ドックで肝臓の異常を指摘された」などのきっかけで発覚する例が多いです。
そのため、特に肝臓に疲れや痛みを感じていなくても、日頃から健康診断を受けて体の状態をチェックすることが大切になります。
脂肪肝のポイント
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 肝臓の機能 | 代謝・解毒・胆汁生成など多様 |
| 脂肪肝の主な原因 | 過剰なカロリー、糖質、アルコール、肥満、無理なダイエットなど |
| 自覚症状 | ない場合がほとんど |
| 放置時のリスク | 肝硬変、肝炎、肝臓がんなど |
| 改善の重要性 | 生活習慣を見直すことで進行を防ぎ、全身の健康状態を保ちやすくなる |
脂肪肝が起こる原因と注意すべき生活習慣
脂肪肝が進行する原因として、肥満や飲酒に限らずさまざまな生活習慣が挙げられます。
原因を正しく理解することで、改善へのアプローチもしやすくなります。
肥満と脂肪蓄積の関係
肥満は脂肪肝の大きな原因のひとつで、内臓脂肪が多い人は中性脂肪やインスリン抵抗性が上昇しやすく、肝臓にも脂肪がたまりやすくなります。
肥満を伴う糖尿病や高血圧などの生活習慣病がある場合は、肝臓に対するリスクがさらに高まるのが注意点です。
アルコールの過剰摂取
アルコールをたくさん飲む人は、肝臓がアルコール分解に集中してしまい、中性脂肪の代謝が追いつかず脂肪が増えやすくなります。
また、アルコールの摂取量が多いほど肝炎や肝硬変へ進行しやすくなるため、1日あたりの飲酒量を意識したり休肝日を設けたりして、肝臓への負担を小さくすることが大切です。
過剰な糖質や偏った食事
炭水化物や果糖が豊富な食品を過剰に摂取している人、偏食や甘いものの食べ過ぎなどで栄養バランスが乱れている人は、体内で余った糖質が脂肪合成に回り、中性脂肪が増加します。
また、無理なダイエットで必要な栄養をとらない場合も、かえって肝臓の機能が低下して脂肪肝を悪化させる可能性があります。
運動不足とエネルギー消費の低下
運動不足は肥満だけでなく、全身の基礎代謝を低下させ、脂肪燃焼の効率を下げる原因です。
有酸素運動の機会が少ない人や、デスクワーク中心で身体を動かす時間が限られる人は、エネルギーの消費量が少ないために脂肪肝につながりやすくなります。
注意したい生活習慣
- 食べる量や栄養バランスが偏っている
- 夜遅くに食事することが多い
- お酒の量が多く、休肝日を設けていない
- 外食やファストフードなど高カロリー食が多い
- デスクワークや車移動が中心で運動量が極端に少ない
脂肪肝の症状と進行リスク
脂肪肝は初期のうちに大きな症状が出にくいため、気づかないうちに進行し、肝臓の機能障害や生活習慣病を悪化させるケースが多いです。自分の体にどのようなサインがあるか知っておくと早期に対処できます。
症状が目立ちにくい理由
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど痛みを感じにくい特徴があり、脂肪がたまってもすぐに分かる形で影響が表れないことが多いです。肩こりや疲労感、全身のだるさなどの軽微な変化にとどまる場合もあります。
進行による合併症
脂肪肝が進むと、肝臓の炎症状態が強まり、アルコール性や非アルコール性の肝炎を起こすことがあり、さらに悪化すると肝硬変や肝がんのリスクも高まり、長期にわたって肝機能の低下を招く点が深刻です。
糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病と合併している場合、全身的な状態悪化につながる可能性があります。
女性にも増える脂肪肝
脂肪肝は男性に多いイメージがありましたが、近年は食生活の多様化やストレス、ダイエットの失敗などを背景に女性でも増える傾向があります。
特に若い世代の無理なダイエットはホルモンバランスを乱し、体重は減っても肝臓に脂肪が蓄積しやすくなってしまう場合がある点に要注意です。
放置の危険性
自覚症状が出にくいからこそ、脂肪肝を放置する人が少なくありません。
定期的な健康診断や人間ドックで肝機能に異常を指摘された際には、「痛みがないから大丈夫」と考えず、内科や消化器内科の診察を受けるなど、早期の受診が必要です。
脂肪肝が進行したときに考えられる状態
| 病名 | 特徴 |
|---|---|
| 肝炎 | 肝細胞の炎症が強くなり、だるさや黄疸などが現れることがある |
| 肝硬変 | 肝臓が硬く、修復できないほど傷つく。腹水など肝臓が機能しないような重篤な状況になる可能性がある |
| 肝がん | 肝炎や肝硬変を経て発症リスクが高まる。適切な治療や管理が重要 |
食事の見直しと栄養バランスの取り方
脂肪肝の改善には、まず食事内容を振り返り、過剰な脂質や糖質、アルコールの摂取を控えながら、必要な栄養素をバランスよくとることが大切です。
カロリーと糖質を意識する
肥満を改善するうえで、1日の摂取カロリーを把握して適切な量をとることが基本で、炭水化物や果物など糖質を多く含む食品は中性脂肪を増やしやすいので、食べる量やタイミングに注意する必要があります。
極端に制限すると体がエネルギー不足を感じて筋肉量が落ち、基礎代謝が下がるので、適度なコントロールが重要です。
タンパク質とビタミンの摂り方
肝臓はタンパク質の合成や分解で大きな役割を果たしているため、肉や魚、大豆製品、卵などから良質なたんぱく質を摂取すると、肝細胞の再生をサポートしやすくなります。
また、ビタミンB群やビタミンC、ビタミンE、ミネラルなどの栄養は肝臓の機能維持に役立つため、野菜や果物、ナッツ類、海藻などをバランスよく取り入れましょう。
肝臓に役立つ栄養素
| 栄養素 | 働き | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| 良質なたんぱく質 | 肝細胞の再生・修復を助け、筋肉量を維持する | 肉・魚・大豆製品・卵 |
| ビタミンB群 | エネルギー代謝を促し、肝機能を補助 | 豚肉・レバー・納豆・卵 |
| ビタミンC | 抗酸化作用により肝細胞へのダメージを軽減 | 柑橘類・イチゴ・ブロッコリー・ピーマン |
| ビタミンE | 活性酸素を抑え、脂肪肝の進行を防ぐ可能性がある | アーモンド・かぼちゃ・植物油 |
| 食物繊維 | 血糖値の急上昇を緩和し、脂質の過剰吸収を抑える | 野菜・果物・海藻・きのこ類 |
お酒のコントロール
アルコール性脂肪肝の場合、禁酒または飲酒量の大幅な制限が欠かせません。お酒を飲むときは水を併用して肝臓への負担を軽減し、1日あたりの飲酒量がどの程度なのかを意識することが大切です。
休肝日を週に2日以上設けると、肝臓が回復する時間をとりやすくなります。
飲酒量の目安とアルコールの量
| 種類 | 量 | アルコール度数(%) | 含まれるアルコール量 |
|---|---|---|---|
| ビール | 500ml | 5 | 約20g |
| 日本酒 | 180ml | 15 | 約22g |
| 焼酎(25%) | 100ml | 25 | 約20g |
| ワイン(12%) | 200ml | 12 | 約19g |
| ウイスキー(40%) | 60ml | 40 | 約19g |
食事のタイミングと方法
夜遅い時間の食事や就寝前の間食は脂肪蓄積を促進しやすいので、できるだけ就寝3時間前には食べ終わるように心がけてください。また、野菜や汁物から先に食べることで血糖値の急上昇を抑え、中性脂肪の合成を抑制しやすくなります。
運動習慣でエネルギー消費を高める
食事の見直しとあわせて運動を取り入れると、エネルギーの消費量が増えて肝臓に脂肪がたまりにくくなる効果が期待できます。特に運動不足やデスクワーク中心の人は意識して体を動かすことが大切です。
有酸素運動の取り入れ方
ウォーキングやジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動は、体脂肪をエネルギーとして燃焼しやすく、肝臓に蓄積した脂肪を減らすのに有効です。
週3~4回、1回30分以上を目安に行うと、肥満や生活習慣病のリスクを下げる可能性が高まります。
有酸素運動の例
- ウォーキング(速歩きで20~30分程度)
- 軽いジョギング(疲れすぎないペースで10~20分程度)
- サイクリング(通勤や買い物時に取り入れる)
- プールでの水中ウォーキング
筋力トレーニングの役割
筋肉量が増えれば基礎代謝が上がり、エネルギー消費量も増えます。スクワットや腕立て伏せ、腹筋などの簡単な筋トレを日常に組み込むと、より効率的に脂肪を燃焼しやすい体作りができ、内臓脂肪の減少にも寄与します。
日常の動きを増やす工夫
運動といっても特別な時間を作るのが難しい人は、日常動作を少し見直すだけでもエネルギー消費を増やすことが可能です。
エレベーターやエスカレーターを使わずに階段を使う、車ではなく自転車で移動する、デスクワークの合間に軽いストレッチを挟むなど、こまめに体を動かす工夫を意識してみましょう。
運動量を増やすアイデア
- 駅や職場で階段を使う
- 自転車や徒歩で通勤・通学する
- 1日1万歩を目安に歩数を意識する
- 座りっぱなしを避け、定期的に立ち上がって体を動かす
運動不足の注意点
急に激しい運動を始めると、体に負荷がかかりすぎて続かないことがあるので、継続できる範囲から始め、少しずつ運動時間や強度を上げてください。
特に高齢者や持病がある方は医師に相談し、安全に行える運動プログラムを計画することが大切です。
脂肪肝の検査と医療機関の受診タイミング
脂肪肝は症状が軽微なうちに発見しやすい病気ですが、異常が判明しても放置する人が少なくないため、早めの受診が重要です。ここでは検査方法や医療機関を受診する目安について確認します。
健康診断や人間ドックの血液検査
健康診断や人間ドックの結果でALT、AST、γ-GTPなどの肝機能数値が高い場合、脂肪肝の可能性があると考えられます。中性脂肪、総コレステロール、血糖値、HbA1cなどもあわせて確認し、総合的に脂肪肝や生活習慣病のリスクを把握しましょう。
主な血液検査項目と意味
| 検査項目 | 意味 |
|---|---|
| ALT(GPT) | 肝細胞の障害で上昇しやすい |
| AST(GOT) | 肝臓や心臓、骨格筋などの幅広い臓器で上昇 |
| γ-GTP | 飲酒量や胆道系の状態で影響を受けやすい |
| 中性脂肪 | 過剰だと脂肪肝や生活習慣病のリスクを高める |
| 血糖値・HbA1c | 糖尿病やインスリン抵抗性の有無を確認 |
画像検査による診断
肝臓の状態を調べるために、超音波(エコー)やCT、MRIなどの画像検査を行い、肝臓にどの程度脂肪が蓄積しているかを調べる方法がありエコー、検査は負担が少なく、スクリーニングとしてよく使われます。
内科・消化器内科への受診
血液検査や画像検査で脂肪肝が疑われた場合は、内科や消化器内科で詳しい検査と診察を受けます。クリニックや病院で定期的に受診し、医師の指示のもと生活習慣の見直しや必要に応じた薬物療法を行うことが大切です。
受診のタイミング
以下のような状態に当てはまる人は、できるだけ早めに医療機関を受診し、放置を避けるよう意識してください。
医療機関を受診したほうが良い目安
- 健康診断で肝機能数値の異常を指摘された
- お腹まわりが急に増え、肥満が目立ち始めた
- お酒を毎日飲み、量や回数が増えている
- 疲労感やだるさが続き、全身が重い感じがある
- 糖尿病や脂質異常症、高血圧といった生活習慣病を複数抱えている
脂肪肝を改善・予防するためのポイント
脂肪肝から肝硬変や肝炎などへの進行を防ぎ、肝臓の機能を守るには、生活習慣全体を見直すことが鍵です。
ストレスとの上手な付き合い方
ストレスが強いと暴飲暴食やアルコールの過剰摂取につながりやすくなります。ウォーキングや趣味の時間を増やす、睡眠を十分にとるなど、自分なりのリラックス方法を見つけることが大切です。
定期的な健康診断
脂肪肝は血液検査の数値から早期に発見しやすい病気ですが、自覚症状がほとんどないため、健康診断や人間ドックの結果を見逃さないことが重要です。
異常を指摘されたら積極的に内科や消化器内科で相談し、必要に応じて追加の検査や治療を受けてください。
生活習慣を見直すときに役立つポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 食事管理 | カロリーや糖質、アルコールを意識し、バランスを整える |
| 運動習慣 | 有酸素運動と筋トレを継続し、エネルギー消費を増やす |
| ストレスケア | 趣味や休息を取り入れ、暴飲暴食を避ける |
| 定期的な健診 | 早期発見・早期対策につなげ、肝臓の状態を把握する |
| 医療機関への相談 | 不安があれば早めに受診し、生活習慣病との併発を防ぐ |
小さな習慣の積み重ね
ダイエットに失敗してリバウンドを繰り返すよりも、日々の食事量や飲酒量を少しずつ調整し、習慣的に運動を取り入れるといった小さな変化を継続するほうが、長期的には健康的な体重や肝機能の改善につながりやすいです。
薬物療法やサプリメントの活用
医師の判断で、脂肪肝や生活習慣病を改善するための薬が処方される場合があり、たとえば糖尿病治療薬の一部はインスリン抵抗性を改善する効果が期待され、肝臓への脂肪蓄積を抑えることも考えられます。
ただし、薬だけに頼るのではなく、食事や運動などの生活習慣を同時に見直すことが大切です。サプリメントの使用を検討する場合も、必ず医師と相談してから行ってください。
まとめ
脂肪肝は食事や飲酒、運動不足などの生活習慣と深く関わる病気であり、自覚症状がないまま進行してしまうことが多いです。
しかし、適切なタイミングで生活を見直し、肥満や飲酒量、糖質の摂取、運動不足を改善することで、肝臓の機能を守り、肝硬変や肝炎といった深刻な状態への移行を抑えることが可能です。
定期的な健康診断や人間ドックの結果に注意を払い、必要に応じて内科や消化器内科で診察を受けるようにし、日常生活の中で継続的に取り組むことが大切になります。
体重管理や栄養バランス、適度な運動を意識しながら、気になることがあれば医師や専門家に相談し、長く健康を維持してください。
参考文献
Kamada Y, Takahashi H, Shimizu M, Kawaguchi T, Sumida Y, Fujii H, Seko Y, Fukunishi S, Tokushige K, Nakajima A, Okanoue T. Clinical practice advice on lifestyle modification in the management of nonalcoholic fatty liver disease in Japan: an expert review. Journal of Gastroenterology. 2021 Dec 1:1-7.
Okanoue T, Umemura A, Yasui K, Itoh Y. Nonalcoholic fatty liver disease and nonalcoholic steatohepatitis in Japan. Journal of gastroenterology and hepatology. 2011 Jan;26:153-62.
Hamaguchi E, Takamura T, Sakurai M, Mizukoshi E, Zen Y, Takeshita Y, Kurita S, Arai K, Yamashita T, Sasaki M, Nakanuma Y. Histological course of nonalcoholic fatty liver disease in Japanese patients: tight glycemic control, rather than weight reduction, ameliorates liver fibrosis. Diabetes care. 2010 Feb 1;33(2):284-6.
Watanabe S, Hashimoto E, Ikejima K, Uto H, Ono M, Sumida Y, Seike M, Takei Y, Takehara T, Tokushige K, Nakajima A. Evidence-based clinical practice guidelines for nonalcoholic fatty liver disease/nonalcoholic steatohepatitis. Journal of gastroenterology. 2015 Apr;50(4):364-77.
Kojima SI, Watanabe N, Numata M, Ogawa T, Matsuzaki S. Increase in the prevalence of fatty liver in Japan over the past 12 years: analysis of clinical background. Journal of gastroenterology. 2003 Oct;38:954-61.
Yamazaki H, Tsuboya T, Tsuji K, Dohke M, Maguchi H. Independent association between improvement of nonalcoholic fatty liver disease and reduced incidence of type 2 diabetes. Diabetes care. 2015 Sep 1;38(9):1673-9.
Kawamura Y, Arase Y, Ikeda K, Seko Y, Imai N, Hosaka T, Kobayashi M, Saitoh S, Sezaki H, Akuta N, Suzuki F. Large-scale long-term follow-up study of Japanese patients with non-alcoholic Fatty liver disease for the onset of hepatocellular carcinoma. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2012 Feb 1;107(2):253-61.
Endo Y, Ohta M, Tada K, Nakanuma H, Saga K, Masuda T, Hirashita T, Iwashita Y, Ozeki Y, Masaki T, Inomata M. Improvement of non‐alcoholic fatty liver disease after laparoscopic sleeve gastrectomy in Japanese obese patients. Annals of gastroenterological surgery. 2019 May;3(3):285-90.
Eguchi Y, Kitajima Y, Hyogo H, Takahashi H, Kojima M, Ono M, Araki N, Tanaka K, Yamaguchi M, Matsuda Y, Ide Y. Pilot study of liraglutide effects in non‐alcoholic steatohepatitis and non‐alcoholic fatty liver disease with glucose intolerance in J apanese patients (LEAN‐J). Hepatology Research. 2015 Mar;45(3):269-78.
Uehara D, Seki Y, Kakizaki S, Horiguchi N, Tojima H, Yamazaki Y, Sato K, Yamada M, Uraoka T, Kasama K. Long-term results of bariatric surgery for non-alcoholic fatty liver disease/non-alcoholic steatohepatitis treatment in morbidly obese Japanese patients. Obesity surgery. 2019 Apr 15;29:1195-201.