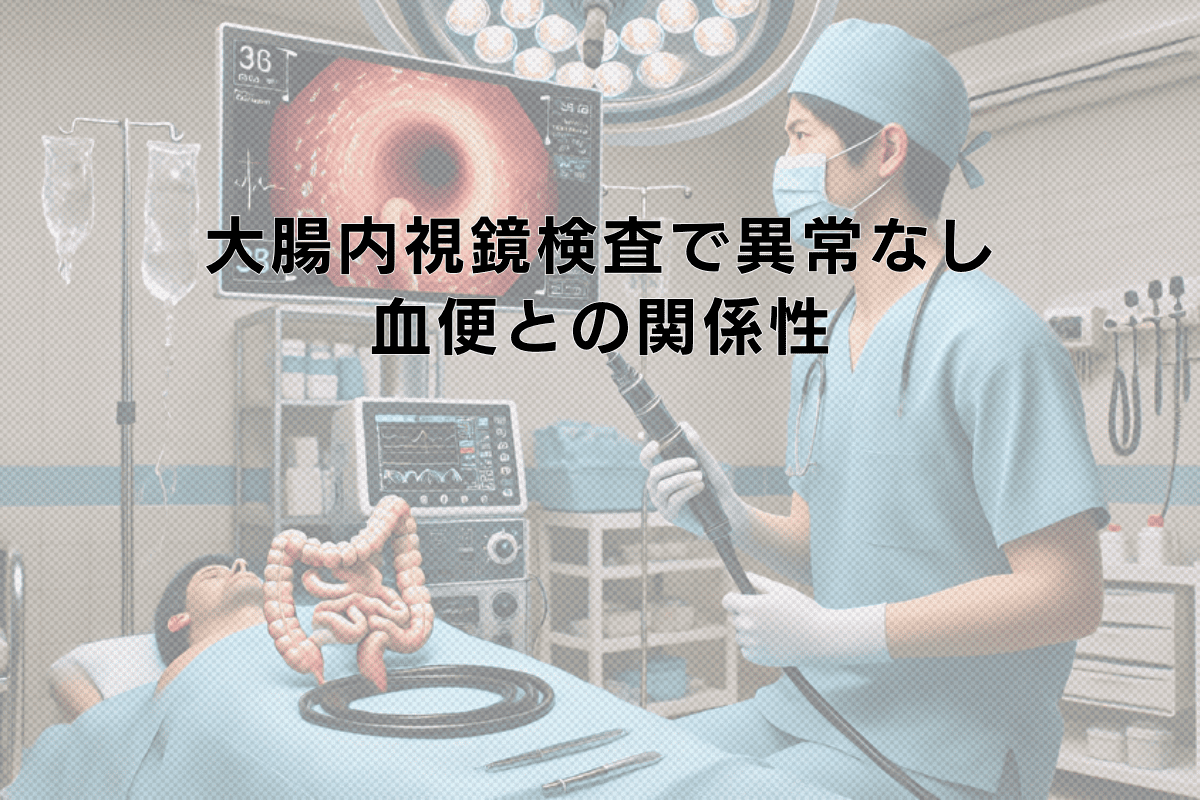血便や腹痛などの症状で勇気を出して大腸内視鏡検査(大腸カメラ)を受けた結果、特に異常はなく安心したのもつかの間、検査後も血便が続いたり、しばらくして再び血便が出ることがあります。
この記事では、なぜ大腸内視鏡検査で異常なしと診断されたにもかかわらず、血便が出ることがあるのか、その理由と関係性について詳しく解説します。
大腸内視鏡検査の異常なしが意味すること
まず、大腸内視鏡検査で医師が伝える異常なしという言葉が、具体的にどのような状態を指すのかを正しく理解することが重要です。背景には、検査の目的と観察範囲が深く関わっています。
検査で確認している範囲と目的
大腸内視鏡検査は、肛門から内視鏡(スコープ)を挿入し、直腸から盲腸(小腸とのつなぎ目)までの大腸全体の粘膜を直接観察する検査です。
主な目的は、大腸がんや前段階である大腸ポリープ、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患など、大腸の粘膜に形態的な変化を起こす病変を発見することにあります。
異常なしという診断は、基本的に重大な疾患が見つからなかったことを意味します。
異常なしは出血の原因が全くない、ではない
重要なのは異常なしという結果が、必ずしも出血する可能性のある原因が全くないことを保証するものではないという点で、大腸内視鏡検査は、あくまで検査時点での大腸粘膜の状態を評価するものです。
出血が一時的であったり大腸粘膜以外の場所が原因であったり、あるいは内視鏡では捉えきれない性質の出血である場合には、検査所見としては異常なしと判断されることがあります。
異常なしの診断で否定される主な疾患
| 疾患分類 | 具体的な疾患名 | 検査で分かること |
|---|---|---|
| 腫瘍性疾患 | 大腸がん、大腸ポリープ | 粘膜の隆起や凹凸、色調の変化の有無が分かる。 |
| 炎症性腸疾患 | 潰瘍性大腸炎、クローン病 | 粘膜のびらん、潰瘍、発赤、腫れなどの有無が分かる。 |
| その他の炎症 | 重度の感染性腸炎、虚血性大腸炎 | 活動期の炎症所見(発赤、むくみ、出血など)が分かる。 |

大腸由来の出血
大腸内視鏡検査の時点では粘膜に明らかな異常が見られなくても、出血の原因が大腸にあるケースは少なくありません。これは出血が一過性であったり、特定の条件下でだけ出血するためです。
大腸憩室出血
大腸の壁の一部が、風船のように外側に飛び出した袋状のくぼみを大腸憩室と呼びます。憩室があること自体は病気ではありませんが、憩室の内部を通る血管が何らかのきっかけで傷つき、突然出血する(大腸憩室出血)ことがあります。
特徴は、腹痛を伴わずに突然大量の鮮血便や赤黒い血便が出ることで、出血は自然に止まることも多いですが、大量出血の場合は入院や内視鏡による止血治療が必要です。
大腸内視鏡検査では憩室の存在は確認できますが、出血がすでに止まっている場合、どの憩室から出血したかを特定することは困難です。
そのため、検査結果としては憩室はあるものの、活動性の出血はなく異常なしと説明されることがあります。
虚血性大腸炎
大腸の血管が一時的に詰まったり血流が悪くなることで、大腸の粘膜に炎症や潰瘍が生じる病気です。突然の強い腹痛から始まり、その後、下痢と血便が現れます。
多くは一過性の血流障害であり、安静にすることで数日から1週間程度で粘膜は自然に修復されるため、症状が落ち着いてから大腸内視鏡検査を受けるとすでに粘膜が治癒しており、異常なしと診断されます。
しかし、特徴的な病歴から、過去に虚血性大腸炎が起きた可能性を推測することは可能です。
感染性腸炎
カンピロバクターやサルモネラ菌、病原性大腸菌などの細菌感染によって、腸の粘膜に炎症が起こり、下痢や腹痛、血便を引き起こすことがあります。これも一過性の疾患であり、多くは自身の免疫力で治癒に向かいます。
症状が軽快した後に検査を受けると、炎症が治まり粘膜が正常に戻っているため、異常なしとなり、便の培養検査などを行わないと原因菌を特定できない場合もあります。
大腸由来の出血原因の特徴
| 原因疾患 | 主な症状 | 内視鏡検査時の所見 |
|---|---|---|
| 大腸憩室出血 | 腹痛を伴わない突然の血便 | 憩室は確認できるが、出血部位は特定困難なことが多い。 |
| 虚血性大腸炎 | 突然の腹痛、その後の下痢・血便 | 治癒後であれば、所見は正常なことが多い。 |
| 感染性腸炎 | 下痢、腹痛、発熱、血便 | 治癒後であれば、所見は正常なことが多い。 |
大腸以外の出血
血便の原因が、そもそも大腸内視鏡検査の観察範囲の外にある場合も考えられます。特に肛門からの出血は非常に多く、大腸カメラでは診断が難しいです。
痔核(いぼ痔)からの出血
血便の最も一般的な原因は、痔核(いぼ痔)です。排便時に硬い便が通過する際に内痔核の表面が傷ついたり、強くいきむことでうっ血した痔核から出血したりします。
症状は、便器が真っ赤になるような鮮やかな色の出血や排便後にポタポタと血液が滴下する、トイレットペーパーに血液が付着するなどです。
大腸内視鏡検査は主に大腸の奥を観察するための検査であり、肛門周辺の詳細な観察には適していません。
スコープの挿入・抜去時に痔核を認識することはできますが、その場で確定診断や重症度の評価をすることは難しく、大腸内に異常がなければ異常なしと報告され、肛門科の受診を勧められることがあります。
裂肛(切れ痔)からの出血
硬い便の通過などによって肛門の皮膚が切れてしまう状態が裂肛(切れ痔)で、排便時に強い痛みを伴い、トイレットペーパーに少量の鮮血が付着します。出血量は比較的少ないことが多いですが、痛みが強いため自覚しやすいです。
肛門の病気であるため、大腸内視鏡検査では直接の診断対象とはなりません。
肛門疾患による出血の特徴
| 疾患名 | 出血の色・量 | 痛みの有無 |
|---|---|---|
| 内痔核(いぼ痔) | 鮮血。ポタポタ垂れる、シャーっと出ることも。 | 通常、痛みはないことが多い。 |
| 裂肛(切れ痔) | 鮮血。ペーパーに付着する程度。 | 排便時に強い痛みを伴う。 |
小腸からの出血の可能性
まれですが、出血の原因が小腸にある可能性も考えられます。小腸は、胃と大腸の間にある約6〜7メートルもある長い臓器で、通常の胃カメラや大腸カメラでは観察できません。
小腸からの出血は、腫瘍や潰瘍、血管の異常(血管異形成)などが原因で、黒っぽい便が出ることが多いですが、出血量が多い場合は赤黒い血便となることもあります。
胃と大腸の両方に異常がないにもかかわらず原因不明の貧血や血便が続く場合に、小腸出血を疑い、カプセル内視鏡などの専門的な検査を検討します。
検査の限界と見逃しの可能性について
異常なしと言われた方が最も心配するのが、がんなどの重大な病気が見逃されたのではないかということでしょう。残念ながら100%完璧な検査というものはなく、ごくまれに見逃しが起こる可能性はゼロではありません。
しかしリスクを理解し、いかに低減させるかが重要です。
前処置(腸管洗浄)の重要性
大腸内視鏡検査の精度を左右する最も大きな要因の一つが、前処置の状態です。検査前に飲む下剤によって、大腸の中がどれだけきれいになっているかどうかが、観察の質に直結します。
便の洗い残しが多いと、その下に隠れたポリープや早期がんを見逃す原因となります。指示通りに下剤を服用し、最終的に便が透明な液体になるまでしっかりと腸管を洗浄することが、見逃しを防ぐための患者さん自身の最も重要な役割です。

ヒダの裏など、観察しにくい部位の存在
大腸には、ヒダ(ハウストラ)が多数あります。ヒダの裏側や、カーブのきつい部分(S状結腸や脾彎曲部など)は、内視鏡の死角になりやすく、病変が見逃されるリスクがわずかながらあります。
経験豊富な専門医はスコープを巧みに操作し、体位を変えたり吸引してヒダを広げながら、死角をできるだけなくすよう努めて観察します。
平坦型・陥凹型病変という見つけにくいがん
大腸がんやポリープと聞くと、キノコのように隆起した形を想像する方が多いかもしれませんが、中には粘膜の表面を這うように広がる平坦なタイプや、わずかにへこんだ陥凹型の病変もあります。
正常な粘膜との区別がつきにくく発見には高度な観察技術と経験が要求され、NBI(狭帯域光観察)などの画像強調機能を持つ高性能な内視鏡を用いることで、発見率は向上します。
見逃しリスクを低減するための要素
- 十分な腸管洗浄(質の高い前処置)
- 経験豊富な専門医による検査
- 画像強調機能などを備えた高性能な内視鏡システムの使用
- 十分な観察時間をかけた丁寧な検査
異常なしと言われた後の対処法と経過観察
一度異常なしという結果が出た後、どのように過ごしどのような点に注意すれば良いのかを知っておくことは、将来の安心に繋がります。
血便が続く場合の記録の重要性
もし検査後も血便が続くあるいは再発した場合は、状態をできるだけ詳しく記録しておくことが、次の診断の大きな手がかりになります。
血便が出た際に記録すべき項目
| 項目 | 記録する内容の例 |
|---|---|
| 時期・頻度 | いつからか、毎日か、週に1回か、排便のたびにか |
| 色・量 | 鮮血、赤黒い、黒い。ポタポタ、ペーパーに付く程度、便器が染まる |
| 随伴症状 | 腹痛、発熱、下痢、便秘、残便感などの有無 |
再受診を検討すべき症状
以下のような症状が現れた場合は、放置せずに検査を受けた医療機関に再度相談するか、あるいは肛門科などの専門科を受診してください。
- 血便の回数や量が増えてきた
- 腹痛や発熱など、新たな症状が出現した
- 貧血の症状(めまい、立ちくらみ、息切れなど)がある
- 便が細くなってきた、便秘がひどくなった
定期的な内視鏡検査の意義
今回異常なしと診断されたとしても、それが将来にわたって大腸がんにならないことを保証するものではありません。大腸がんは、生活習慣の欧米化などを背景に年々増加しています。
がんのリスクが高まる40歳を過ぎたら症状がなくても定期的に大腸内視鏡検査を受けることが、がんの早期発見・予防のために最も有効な手段です。
質の高い大腸内視鏡検査を受けるために
異常なしという結果に真の安心感を得るためには、受けた検査そのものの質が高いことが大前提となります。質の高い検査とは、見逃しのリスクを限りなくゼロに近づけるための努力を多方面から行っている検査のことです。
消化器内視鏡専門医による検査の重要性
大腸内視鏡検査は医師の技術と経験によって、精度や患者さんの苦痛度が大きく変わります。日本消化器内視鏡学会が認定する専門医は厳しい基準をクリアした、内視鏡に関する高度な知識と技術を持つ医師です。
微細な病変を発見する観察眼や、苦痛を少なくスコープを挿入する技術に長けており、質の高い検査を受けるための最も重要な要素と言えます。
高性能な内視鏡システムの役割
近年の内視鏡技術の進歩は目覚ましく、ハイビジョン画質や拡大機能、特殊な光を用いて病変を浮かび上がらせる画像強調機能(NBIなど)を搭載した内視鏡が普及しています。
高性能な機器を用いることで、従来では発見が難しかった平坦な病変や微小な早期がんの発見率が格段に向上します。クリニックがどのような機器を使用しているかも、検査の質を判断する一つの材料です。
よくある質問
最後に、大腸内視鏡検査で異常なしと言われた方からよく寄せられる質問についてお答えします。
- ストレスで血便が出ることはありますか
-
ストレスが直接的な原因となって、消化管から物理的に出血することは通常ありません。
しかし、強いストレスは自律神経のバランスを乱し、胃酸の分泌を増やして胃潰瘍を起こしたり、腸の蠕動運動に影響を与えて便秘や下痢を悪化させることがあります。
便秘によって便が硬くなり痔が悪化して出血する、という間接的な関係は考えられますが、血便が見られた場合は、まず器質的な疾患がないかを確認することが最優先です。
- 赤い食べ物を食べると便が赤くなりますか
-
トマトやパプリカ、スイカ、ビーツ、赤い色素を使った清涼飲料水やかき氷などを大量に摂取すると、色素が便に混じり、血便のように見えることがあります。
便全体が均一に赤っぽかったり食べ物の残渣が見られる場合は、食事の影響である可能性が高いですが、自己判断は禁物です。
ティッシュで拭いた際に血液のようににじむかどうかなどを確認し、判断に迷う場合は医療機関に相談してください。
- 一度異常なしと言われたら、もう検査は不要ですか
-
今回の検査で異常がなかったということは、現時点での安心材料ですが、将来にわたってポリープやがんが発生しないことを保証するものではありません。大腸がんのリスクは年齢とともに上昇します。
今回の検査の結果やご自身の年齢、家族歴などを考慮して、医師から推奨された適切な間隔(通常は3〜5年後など)で、定期的に内視鏡検査を受け続けることが、将来の大腸がん予防のために最も重要です。
次に読むことをお勧めする記事
【下部消化管内視鏡検査の観察範囲と手順】
本記事で“異常なしと血便”の関係を整理できたら、実際の観察範囲と手順も確認しておくと安心です。初めて受ける方や再検査予定の方に特に有用です。
【小腸内視鏡検査の種類と特徴|カプセル内視鏡との使い分け】
大腸で出血源が見つからない場合の“次の選択肢”も知っておくと包括的に判断できます。カプセルとバルーンの役割分担を俯瞰できます。
参考文献
Osada T, Ohkusa T, Okayasu I, Yoshida T, Hirai S, Beppu K, Shibuya T, Sakamoto N, Kobayashi O, Nagahara A, Terai T. Correlations among total colonoscopic findings, clinical symptoms, and laboratory markers in ulcerative colitis. Journal of gastroenterology and hepatology. 2008 Dec;23:S262-7.
Morikawa T, Kato J, Yamaji Y, Wada R, Mitsushima T, Shiratori Y. A comparison of the immunochemical fecal occult blood test and total colonoscopy in the asymptomatic population. Gastroenterology. 2005 Aug 1;129(2):422-8.
Nagata N, Ishii N, Manabe N, Tomizawa K, Urita Y, Funabiki T, Fujimori S, Kaise M. Guidelines for colonic diverticular bleeding and colonic diverticulitis: Japan Gastroenterological Association. Digestion. 2019 Jan 14;99(Suppl. 1):1-26.
Nakama H, Kamijo N, Fujimori K, Horiuchi A, Fattah AA, Zhang B. Clinical diagnostic accuracy of faecal occult blood test for anal diseases. International Journal for Quality in Health Care. 1997 Jan 1;9(2):139-41.
Endo H, Kato T, Sakai E, Taniguchi L, Arimoto J, Kawamura H, Higurashi T, Ohkubo H, Nonaka T, Taguri M, Inamori M. Is a fecal occult blood test a useful tool for judging whether to perform capsule endoscopy in low-dose aspirin users with negative colonoscopy and esophagogastroduodenoscopy?. Journal of gastroenterology. 2017 Feb;52:194-202.
Macrae FA, John DJ. Relationship between patterns of bleeding and Hemoccult sensitivity in patients with colorectal cancers or adenomas. Gastroenterology. 1982 May 1;82(5):891-8.
Rockey DC, Koch J, Cello JP, Sanders LL, McQuaid K. Relative frequency of upper gastrointestinal and colonic lesions in patients with positive fecal occult-blood tests. New England Journal of Medicine. 1998 Jul 16;339(3):153-9.
Chen KC, Chung CS, Hsu WF, Huang TY, Lin CK, Lee TH, Weng MT, Chiu CM, Chang LC, Chiu HM. Identification of risk factors for neoplastic colonic polyps in young adults with bloody stool in comparison with those without symptom. Journal of gastroenterology and hepatology. 2018 Jul;33(7):1335-40.
Fine KD, Nelson AC, Ellington TR, Mossburg A. Comparison of the color of fecal blood with the anatomical location of gastrointestinal bleeding lesions: potential misdiagnosis using only flexible sigmoidoscopy for bright red blood per rectum. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 1999 Nov 1;94(11):3202-10.
Carpenter HA, Talley NJ. The importance of clinicopathological correlation in the diagnosis of inflammatory conditions of the colon: histological patterns with clinical implications. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2000 Apr 1;95(4):878-96.