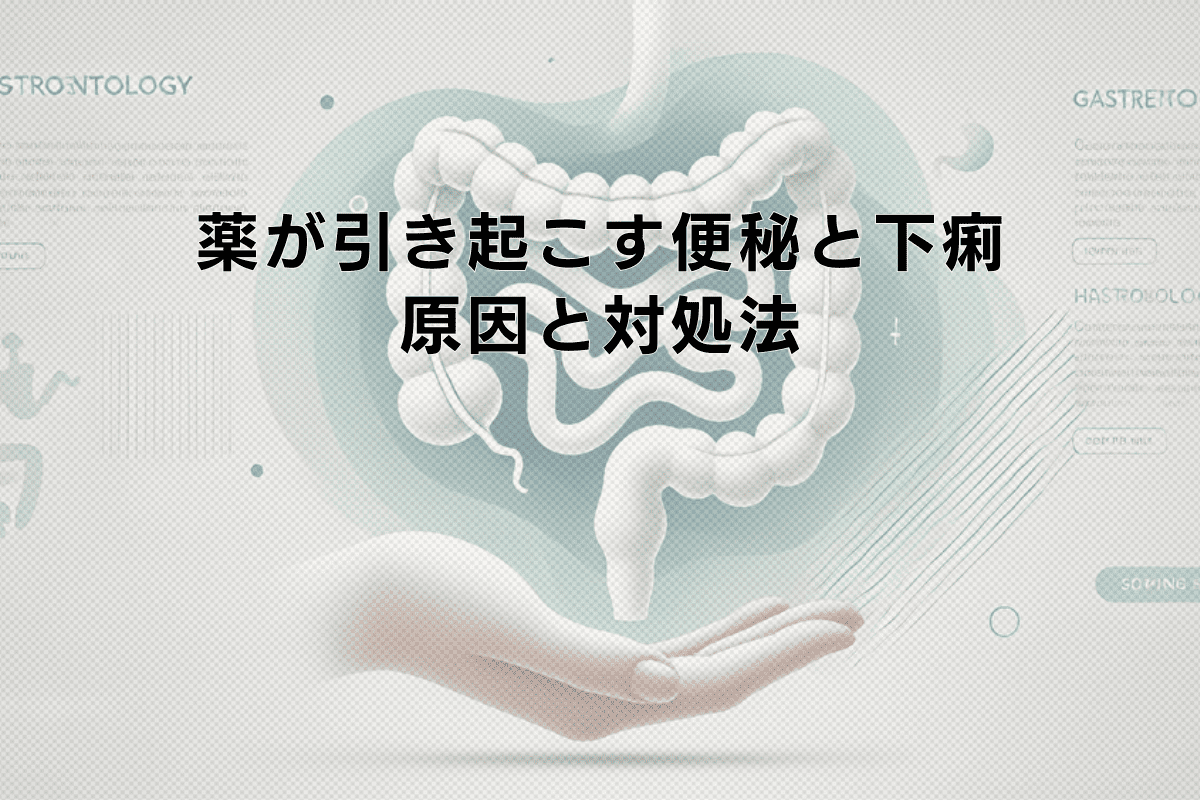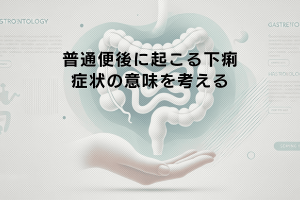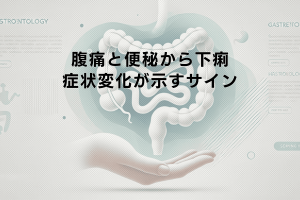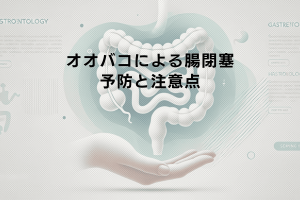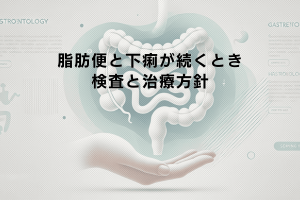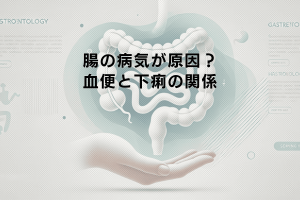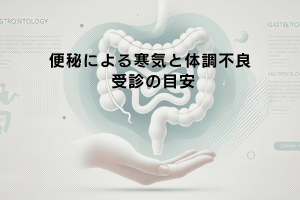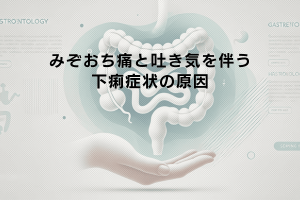病気の治療のために薬を飲み始めたら、急に下痢になったり、逆にお通じが悪くなったりして、戸惑った経験はありませんか。それは、薬の副作用かもしれません。
薬は病気を治すために重要な役割を果たしますが、時にお腹の調子に影響を与えることがあります。
この記事では、どのような薬が便秘や下痢を引き起こしやすいのか、原因から、ご自身でできる対処法、そして専門家へ相談するタイミングまで、詳しく解説します。
薬の副作用として現れる便通異常
薬を服用した後に起こる便秘や下痢は、決して珍しいことではありません。多くの薬には、主となる作用のほかに、意図しない作用、つまり副作用が現れる可能性があります。
消化器系は特に薬の影響を受けやすい器官の一つであり、便通の異常はその代表的な症状です。
なぜ薬で便秘や下痢が起こるのか
薬が便秘や下痢を引き起こす理由は、薬の種類によって様々です。腸の動き(蠕動運動)を活発にしすぎる薬は下痢を、逆に動きを鈍くする薬は便秘を起こし、また、腸内の水分量に影響を与える薬もあります。
腸内の水分が多くなれば便は軟らかくなり下痢に、水分が吸収されすぎると便は硬くなり便秘になります。
さらに、腸内にいる細菌のバランス(腸内フローラ)を変化させる薬、特に抗生物質は、善玉菌を減らしてしまい、腸内環境が乱れることで下痢を起こすことが知られています。
副作用は誰にでも起こりうる
薬の副作用の現れ方には個人差があり、同じ薬を同じ量だけ服用しても、副作用が全く出ない人もいれば、強く出てしまう人もいます。
これは、年齢、性別、体質、肝臓や腎臓の機能、そしてその時に服用している他の薬など、多くの要因が関係しているためです。特に高齢者や、複数の薬を服用している方は、副作用が出やすい傾向にあるため注意が必要です。
副作用は特別な人にだけ起こるものではなく、薬を服用するすべての人に起こりうる可能性があると認識することが大切です。
自己判断で服用を中止する危険性
便秘や下痢といった副作用がつらいからといって、ご自身の判断で薬の服用を中止することは非常に危険です。
処方された薬は病気の治療に必要不可欠なもので、勝手にやめてしまうと、病気が悪化したり、治療が長引いたりする可能性があります。特に、血圧の薬や感染症の治療薬などを急に中断すると、体に深刻な影響を及ぼすこともあります。
副作用がつらい場合は一人で悩まず、まずは処方した医師や薬剤師に相談することが何よりも重要です。
医師や薬剤師への相談の重要性
薬による便通異常を感じたら、ためらわずに専門家へ相談しましょう。現在の症状を詳しく伝えることで、それが薬の副作用なのか、あるいは他の原因によるものなのかを判断する手助けをしてくれます。
副作用であると判断された場合でも、すぐに薬を中止するのではなく、症状を和らげる薬を追加したり、副作用の少ない別の薬に変更したりと、様々な対応策を検討してくれます。安心して治療を続けるためにも、専門家との連携はとても大事です。
下痢を引き起こしやすい主な薬の種類
下痢は、薬の副作用の中でも比較的多く見られる症状の一つです。ここでは、特に下痢を引き起こす可能性のある代表的な薬の種類について解説します。ご自身が服用している薬が該当するかどうかを確認し、症状が出た際の参考にしてください。
抗生物質
細菌による感染症の治療に使われる抗生物質は、下痢の副作用がよく知られています。抗生物質は、病気の原因となる悪い細菌だけでなく、私たちの腸内にいる良い働きをする細菌(善玉菌)まで攻撃してしまうことがあります。
そうなると、腸内フローラのバランスが崩れ、腸の動きが異常になったり、特定の悪玉菌が増殖したりして下痢を引き起こします。特に広範囲の細菌に効くタイプの抗生物質ほど、下痢を起こしやすいです。
下痢を起こしやすい薬の例
| 薬の種類 | 主な用途 | 下痢が起こる主な理由 |
|---|---|---|
| 抗生物質 | 細菌感染症の治療 | 腸内フローラのバランスが乱れるため |
| 非ステロイド性抗炎症薬 | 解熱、鎮痛、抗炎症 | 腸の粘膜を傷つけ、炎症を起こすことがあるため |
| 一部の糖尿病治療薬 | 血糖値を下げる | 糖の吸収を抑制し、腸内の浸透圧が変化するため |
痛み止め(非ステロイド性抗炎症薬)
熱を下げたり、痛みを和らげたりする目的で広く使われる非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)も、消化器系の副作用を起こすことがあります。
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は、炎症や痛みの原因物質であるプロスタグランジンの生成を抑えますが、プロスタグランジンには胃や腸の粘膜を保護する働きもあります。
薬によってプロスタグランジンが減少すると、腸の粘膜が荒れてしまい、炎症や潰瘍ができて下痢や腹痛を引き起こすことがあるのです。
糖尿病治療薬
血糖値を下げるために使われる糖尿病治療薬の中にも、下痢を副作用として持つものがあります。
食事に含まれる糖質の吸収を遅らせるタイプの薬は、吸収されなかった糖が腸内に残ることで腸内の浸透圧が高まり、腸管内に水分が引き込まれて便が緩くなり、下痢や腹部の張りといった症状が出やすくなります。
多くの場合、服用を続けていくうちに体がお薬に慣れて症状は軽快しますが、続く場合は相談が必要です。
化学療法薬(抗がん剤)
がんの治療に用いる化学療法薬(抗がん剤)は、副作用として下痢が高頻度で起こることが知られています。抗がん剤は、分裂が活発ながん細胞を攻撃しますが、正常な細胞の中でも分裂が速い腸の粘膜細胞もダメージを受けてしまいます。
粘膜細胞が傷つくと、水分の吸収がうまくいかなくなったり、腸が炎症を起こしたりして、激しい下痢につながることがあります。抗がん剤による下痢は、脱水や栄養障害を起こしやすいため、特に注意深い管理が必要です。
便秘を引き起こしやすい主な薬の種類
下痢とは逆に、腸の動きを鈍くさせたり、便を硬くしたりすることで便秘を起こす薬もあります。便秘は下痢ほど急激な症状ではないため、薬の副作用だと気づかれにくいこともあります。
医療用麻薬(オピオイド鎮痛薬)
がんの痛みや、他の鎮痛薬では抑えられない強い痛みの治療に使われるオピオイド鎮痛薬は、非常に高い頻度で便秘の副作用を起こします。オピオイドは、腸の神経に作用して蠕動運動を強力に抑制し、便の腸内通過時間を著しく遅らせます。
また、腸管からの水分吸収を促進するため、便が硬く、排出しにくくなります。このタイプの薬を服用する際は、便秘を防ぐための下剤が一緒に処方されることが多いです。
便秘を起こしやすい薬の例
| 薬の種類 | 主な用途 | 便秘が起こる主な理由 |
|---|---|---|
| オピオイド鎮痛薬 | 強い痛みの緩和 | 腸の蠕動運動を強力に抑制するため |
| 一部の抗うつ薬 | うつ病、不安障害の治療 | 抗コリン作用により腸の動きが鈍くなるため |
| カルシウム拮抗薬 | 高血圧、狭心症の治療 | 腸の筋肉の収縮を緩めてしまうため |
抗うつ薬・抗精神病薬
うつ病や統合失調症などの治療に用いられる薬の一部にも、便秘の副作用が見られます。これは抗コリン作用という働きが原因です。抗コリン作用は、アセチルコリンという神経伝達物質の働きをブロックします。
アセチルコリンには消化管の運動を活発にする働きがあるため、妨げられると腸の動きが鈍くなり、便秘になりやすいです。口の渇きや尿が出にくいといった他の症状を伴うこともあります。
カルシウム拮抗薬(降圧薬)
高血圧や狭心症の治療に広く使われているカルシウム拮抗薬も、便秘の原因となることがあります。
カルシウム拮抗薬は、血管の筋肉(平滑筋)を緩めて血管を広げ、血圧を下げる働きがあります。
しかし、腸の壁も同じ平滑筋でできているため、薬の作用が腸にも及ぶと腸の収縮運動が弱まってしまい、便を送り出す力が低下して便秘を起こします。特に高齢の方で起こりやすい副作用の一つです。
咳止め(鎮咳薬)
つらい咳を抑えるために使われる一部の鎮咳薬、特にコデインリン酸塩など麻薬性の成分を含むものは、便秘を起こしやすいことが知られています。
この成分は脳の咳中枢に作用して咳を鎮めますが、同時にオピオイド鎮痛薬と同様に腸の蠕動運動を抑制する作用も持っています。そのため、長期間服用すると便秘になることがあります。
風邪などで一時的に使用する場合は問題になることは少ないですが、注意は必要です。
薬による下痢の症状と特徴
薬が原因で起こる下痢には、いくつかの特徴があります。これらの特徴を知っておくことは、ご自身の症状が薬の副作用によるものかどうかを考える上での手がかりです。
突然始まる水様性の下痢
薬による下痢は、特定の薬を飲み始めてから数時間後、あるいは数日後に、比較的突然始まることが多いです。水のようにサラサラとした便(水様便)が頻繁に出ることがあります。
ウイルス性の胃腸炎と症状が似ていることもありますが、発熱や吐き気などを伴わない場合も多く、原因となる薬の服用との時間的な関連性が疑うポイントになります。原因薬の服用を中止すると症状が改善することが多いのも特徴の一つです。
腹痛や腹部の不快感を伴う場合
下痢だけでなく、お腹の痛みやゴロゴロ鳴る感じ、お腹が張る感じといった腹部の不快感を伴うことも少なくありません。これは、薬の影響で腸の動きが過剰になったり、腸内でガスが発生しやすくなったりするためです。
痛み止め(NSAIDs)が原因の場合は、腸の粘膜に炎症や潰瘍ができている可能性もあり、キリキリとした強い痛みが現れることもあります。痛みが強い場合や、特定の場所が持続して痛む場合は注意が必要です。
- 激しい腹痛や持続する腹痛
- 高熱(38.5℃以上)
- 血便(便に血が混じる)
- 強い脱水症状
症状が続く期間と注意点
下痢が続く期間は、原因となる薬の種類や個人の体質によって異なります。抗生物質による下痢などは、薬の服用期間中や服用後数日まで続くことが一般的です。
多くは原因薬を中止すれば数日で改善しますが、中には「偽膜性腸炎」という特殊な腸炎を発症し、薬をやめた後も下痢や血便、発熱が続くことがあります。
これはクロストリジウム・ディフィシルという菌が腸内で異常増殖することで起こるもので、専門的な治療が必要です。下痢が長引く場合は軽視できません。
脱水症状への警戒
下痢が続くと、便と一緒に体内の水分と電解質(ナトリウムやカリウムなど)が大量に失われ、脱水症状を起こす危険があります。特に高齢者や小さなお子さんは脱水になりやすいため、注意が大事です。
口の中が乾く、尿の量が減る、体がだるいといったサインは脱水の初期症状で、進行すると、めまいや立ちくらみ、意識がもうろうとすることもあります。下痢の際は、水分補給を常に意識することが最も重要です。
脱水症状のサイン
| 症状の段階 | 主なサイン | 対処法 |
|---|---|---|
| 軽度 | 喉の渇き、尿量の減少、皮膚の乾燥 | 経口補水液やスポーツドリンクでこまめに水分補給 |
| 中等度 | めまい、頭痛、倦怠感、頻脈 | 速やかな水分補給、改善しない場合は医療機関へ |
| 重度 | 意識障害、血圧低下、けいれん | 直ちに救急要請、点滴による水分補給が必要 |
薬による便秘の症状と特徴
下痢に比べて症状の進行が緩やかな便秘は、薬の副作用として見過ごされがちですが、放置すると生活の質を大きく低下させる原因にもなります。薬が原因で起こる便秘の典型的な症状と、体の変化について解説します。
排便回数の減少と硬い便
最も分かりやすい症状は、排便回数が減ることです。毎日あったお通じが2〜3日に1回になったり、週に2回以下になったりします。
また、薬の影響で腸の動きが鈍くなり、便が腸内にとどまる時間が長くなるため、水分が過剰に吸収されてしまいます。
その結果、便はウサギの糞のようにコロコロと硬くなったり、水分が少なくカチカチになったりして、排便が非常に困難になります。強くいきまないと便が出ない状態も特徴です。
残便感や腹部の張り
便が硬くてスムーズに排出できないため、排便後もまだ便が残っているようなすっきりしない感覚(残便感)を伴うことが多いです。
また、腸内に便やガスが溜まることで、お腹がパンパンに張って苦しく感じたり、お腹がゴロゴロ鳴ったりすることもあります。洋服のウエストがきつく感じるなど、外見上の変化として現れることもあります。
便秘の時に注意したいこと
| 項目 | 具体的な注意点 | 理由 |
|---|---|---|
| 排便時のいきみ | 強くいきみすぎない | 血圧の上昇や痔の原因になるため |
| 市販の下剤の使用 | 自己判断で連用しない | 依存性や腸へのダメージの可能性があるため |
| 症状の放置 | 長引く場合は医師に相談する | 腸閉塞など重篤な状態につながる恐れがあるため |
食欲不振や吐き気につながることも
便秘が続くと、腹部の不快感だけでなく、全身の症状に発展することがあります。腸に便が溜まっている状態が続くと、胃の動きも悪くなり、食欲がなくなったり、吐き気やむかつきを感じたりします。
また、肌荒れや吹き出物、頭痛、イライラ感など、一見すると便秘とは関係なさそうな症状の原因となっている場合もあります。
慢性化するリスク
薬による便秘を放置していると、症状が慢性化してしまうリスクがあります。腸の動きが悪い状態が当たり前になってしまい、薬の服用が終わった後も便秘が続いてしまうことがあります。
また、市販の刺激性下剤を自己判断で長期間使い続けると、腸がその刺激に慣れてしまい、薬なしでは排便できなくなる「下剤依存」の状態に陥ることもあり、便秘は早めに対処を行うことが、慢性化を防ぐ上で重要です。
自宅でできる対処法と生活習慣の工夫
薬の副作用による便秘や下痢が起きた場合、医師に相談することが基本ですが、症状が軽い場合はご自身の生活習慣を見直すことで、症状を和らげることができる場合もあります。
ここでは、食事や運動など、日常生活の中で取り入れられる工夫についてご紹介します。
下痢の時の食事と水分補給
下痢の時は、腸に負担をかけない、消化の良い食事を心がけることが基本で、おかゆやうどん、すりおろしたりんご、バナナ、豆腐などがおすすめです。
脂肪分の多い食事や、香辛料などの刺激物、冷たい飲み物は腸を刺激して症状を悪化させる可能性があるため避けましょう。最も重要なのは水分補給です。
水やお茶だけでなく、失われた電解質を補うために、経口補水液やスポーツドリンクをこまめに、少しずつ飲みます。
下痢の時に適した食事
| 食品分類 | おすすめの食品 | 避けるべき食品 |
|---|---|---|
| 主食 | おかゆ、よく煮込んだうどん、食パン | 玄米、ラーメン、パスタ |
| 主菜 | 鶏ささみ、白身魚、豆腐、卵 | 脂身の多い肉、揚げ物、加工肉 |
| その他 | バナナ、りんご、じゃがいも、かぼちゃ | 柑橘類、きのこ類、海藻類、乳製品 |
便秘の時の食事と水分補給
便秘の解消には、食物繊維を十分に摂ることが効果的です。食物繊維には、水に溶けやすい水溶性食物繊維(海藻、こんにゃく、果物など)と、水に溶けにくい不溶性食物繊維(きのこ、豆類、ごぼうなど)があります。
両方をバランス良く摂ることが理想です。また、食物繊維は水分を吸収して便を軟らかくするため、1日に1.5〜2リットルを目安に、こまめな水分補給を忘れないようにしましょう。
朝起きてすぐにコップ一杯の水を飲むことも、腸を刺激し、排便を促すのに役立ちます。
便秘解消に役立つ食品
| 栄養素 | 働き | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| 水溶性食物繊維 | 便を軟らかくする | わかめ、昆布、りんご、オートミール |
| 不溶性食物繊維 | 便のかさを増やし、腸を刺激する | ごぼう、きのこ類、豆類、玄米 |
| 発酵食品 | 善玉菌を増やし、腸内環境を整える | ヨーグルト、納豆、味噌、キムチ |
腸内環境を整える意識
下痢も便秘も、腸内環境の乱れが関係していることが多くあります。日頃から腸内環境を整えることを意識した生活を送ることが、症状の予防や改善につながります。
ヨーグルトや納豆、味噌などの発酵食品に含まれる善玉菌(プロバイオティクス)と、その善玉菌のエサとなる食物繊維やオリゴ糖(プレバイオティクス)を一緒に摂る「シンバイオティクス」という考え方も有効です。
- 発酵食品を摂る
- 食物繊維を摂る
- 十分な睡眠
- 適度な運動
適度な運動とストレス管理
体を動かすことは、腸の働きを活発にする上で効果的です。特に、ウォーキングや軽いジョギングなどのリズミカルな運動は、全身の血行を良くし、自律神経のバランスを整えることで、腸の蠕動運動を促します。
また、腹筋を鍛えることも、排便時にいきむ力をサポートし、さらに、ストレスは自律神経を介して腸の機能に直接影響を与えます。
趣味の時間を持ったり、ゆっくりと入浴したりするなど、自分なりのリラックス方法を見つけ、上手にストレスを管理することも、健やかなお通じには重要です。
医療機関に相談するタイミング
セルフケアを試みても症状が改善しない場合や、症状が重い場合は、ためらわずに医療機関を受診することが大切です。
症状が重い・長引く場合
薬による副作用だとしても、症状が日常生活に支障をきたすほど重い場合や、1週間以上続く場合は、医師の診察を受けるべきです。
特に、下痢に伴って高熱が出たり、便に血が混じったり、激しい腹痛がある場合は、他の病気の可能性も考えられるため、早急な対応が必要です。
便秘の場合も、強い腹痛や吐き気を伴う時や、市販薬を使っても全く排便がない時は、腸閉塞など重篤な状態に陥っている可能性もあるため、すぐに医療機関に相談してください。
市販薬を使用する前の注意点
薬の副作用による下痢や便秘に対して、自己判断で市販の薬を使用することには注意が必要です。下痢止め薬は、無理に下痢を止めると、体にとって有害なものを体外に排出するのを妨げてしまい、かえって回復を遅らせることがあります。
特に、感染性の腸炎が疑われる場合には使用してはいけません。便秘薬も、種類によっては長期連用で依存性を生むものがあります。まずは原因となっている薬を処方した医師や薬剤師に相談し、指示を仰ぐのが最も安全な方法です。
医師に伝えるべき情報
医療機関を受診する際は、ご自身の症状についてできるだけ詳しく、正確に伝えることが、適切な診断と治療につながります。
いつから症状が始まったか、どのような症状がどのくらいの頻度で起こるか、便の状態(色、形、量など)、他に気になる症状はないか、などを具体的に説明できるように準備しておきましょう。
また、現在服用しているすべての薬(処方薬、市販薬、サプリメントを含む)がわかるように、お薬手帳などを持参することが大切です。
医師に伝えるべき情報リスト
| 項目 | 具体的な内容 | なぜ重要か |
|---|---|---|
| 症状について | いつから、どんな便が、何回くらい、腹痛の有無など | 症状の重症度や原因を推測する手がかりになる |
| 服用中の薬 | 処方薬、市販薬、サプリメントのすべて | 原因薬の特定や、薬の飲み合わせを確認するため |
| 既往歴・アレルギー | これまでにかかった病気や、薬のアレルギー歴 | 診断や治療薬の選択に影響するため |
薬の変更や調整の可能性
医師に相談した結果、症状が薬の副作用によるものだと判断された場合、いくつかの対応が考えられます。
症状が軽ければ、そのまま様子を見ることもあり、症状が生活に影響している場合は、副作用を緩和する薬(整腸剤や下剤など)を追加で処方することがあります。
また、可能であれば、同じような効果を持ち、副作用の少ない別の種類の薬に変更したり、薬の量を調整したりすることも選択肢です。
よくある質問
最後に、薬の副作用による便秘や下痢に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。
- 副作用の出やすさに個人差はありますか
-
副作用の現れ方は、年齢、性別、体質、遺伝的な背景、肝臓や腎臓の機能、栄養状態、そして他に服用している薬など、非常に多くの要因に影響されます。
そのため、同じ薬を服用しても、副作用が強く出る人もいれば、全く出ない人もいます。
- 薬を飲み始めてからどれくらいで症状が出ますか
-
下痢の場合、早いものでは服用後数時間で症状が出ることもあれば、数日経ってから現れることもあります。抗生物質による腸内フローラの変化が原因の場合は、服用中盤から後半にかけて症状が出やすい傾向があります。
便秘は、下痢に比べると症状の出現が緩やかで、数日から1週間以上かけて徐々にお通じが悪くなることが多いです。
- 整腸剤を一緒に飲んでも良いですか
-
自己判断で市販の整腸剤を服用する前に、まずは処方医や薬剤師に相談するのが原則です。特に抗生物質を服用している場合、抗生物質の種類によっては、整腸剤に含まれる菌が殺されてしまい効果が期待できないことがあります。
医師は、薬の特性を理解した上で、適切な種類の整腸剤を処方したり、服用するタイミングを指示したりしてくれます。副作用対策として整腸剤が処方されている場合は、指示通りに服用してください。
- 副作用が出たら、その薬はもう使えませんか
-
副作用が出たからといって、その薬が二度と使えなくなるわけではありません。症状の程度にもよりますが、量を減らしたり、副作用を抑える薬と一緒に使ったりすることで、問題なく服用を続けられる場合も多くあります。
また、体が薬に慣れることで、最初のうちだけ出ていた副作用が自然に治まることもあります。
次に読むことをお勧めする記事
【繰り返し起こる下痢の症状と大腸内視鏡による精密検査】
薬の影響を理解したところで、持続・反復する下痢時の検査の考え方も把握しておくと安心です。検査で何が分かるかを丁寧に解説しています。
【腸にいい食べ物を知る 腸内環境を整える方法】
薬の副作用による便通異常の基本を押さえたら、次は実際の腸内環境改善について知っておくと安心です。薬を服用中の方に特に参考になる食事の工夫をご紹介しています。
参考文献
Philip NA, Ahmed N, Pitchumoni CS. Spectrum of drug-induced chronic diarrhea. Journal of clinical gastroenterology. 2017 Feb 1;51(2):111-7.
Toney RC, Wallace D, Sekhon S, Agrawal RM. Medication induced constipation and diarrhea. Practical Gastroenterology. 2008 May;32(5):12.
Abraham B, Sellin JH. Drug-induced diarrhea. Current gastroenterology reports. 2007 Oct;9(5):365-72.
Chassany O, Michaux A, Bergmann JF. Drug-induced diarrhoea. Drug safety. 2000 Jan;22:53-72.
Ratnaike RN, Milton AG, Nigro O. Drug‐Associated Diarrhoea and Constipation in Older People 1. Diarrhoea. The Australian Journal of Hospital Pharmacy. 2000 Aug;30(4):165-9.
Fosnes GS, Lydersen S, Farup PG. Constipation and diarrhoea-common adverse drug reactions? A cross sectional study in the general population. BMC clinical pharmacology. 2011 Dec;11:1-9.
Ratnaike RN, Jones TE. Mechanisms of drug-induced diarrhoea in the elderly. Drugs & aging. 1998 Sep;13:245-53.
Gattuso JM, Kamm MA. Adverse effects of drugs used in the management of constipation and diarrhoea. Drug safety. 1994 Jan;10(1):47-65.
Barberio B, Savarino EV, Black CJ, Ford AC. Adverse events in trials of licensed drugs for irritable bowel syndrome with constipation or diarrhea: systematic review and meta‐analysis. Neurogastroenterology & Motility. 2022 Jun;34(6):e14279.
Li W, Liu C, Zhang Z, Cai Z, Lv T, Zhang R, Zuo Y, Chen S. Exploring the top 30 drugs associated with drug-induced constipation based on the FDA adverse event reporting system. Frontiers in Pharmacology. 2024 Sep 2;15:1443555.