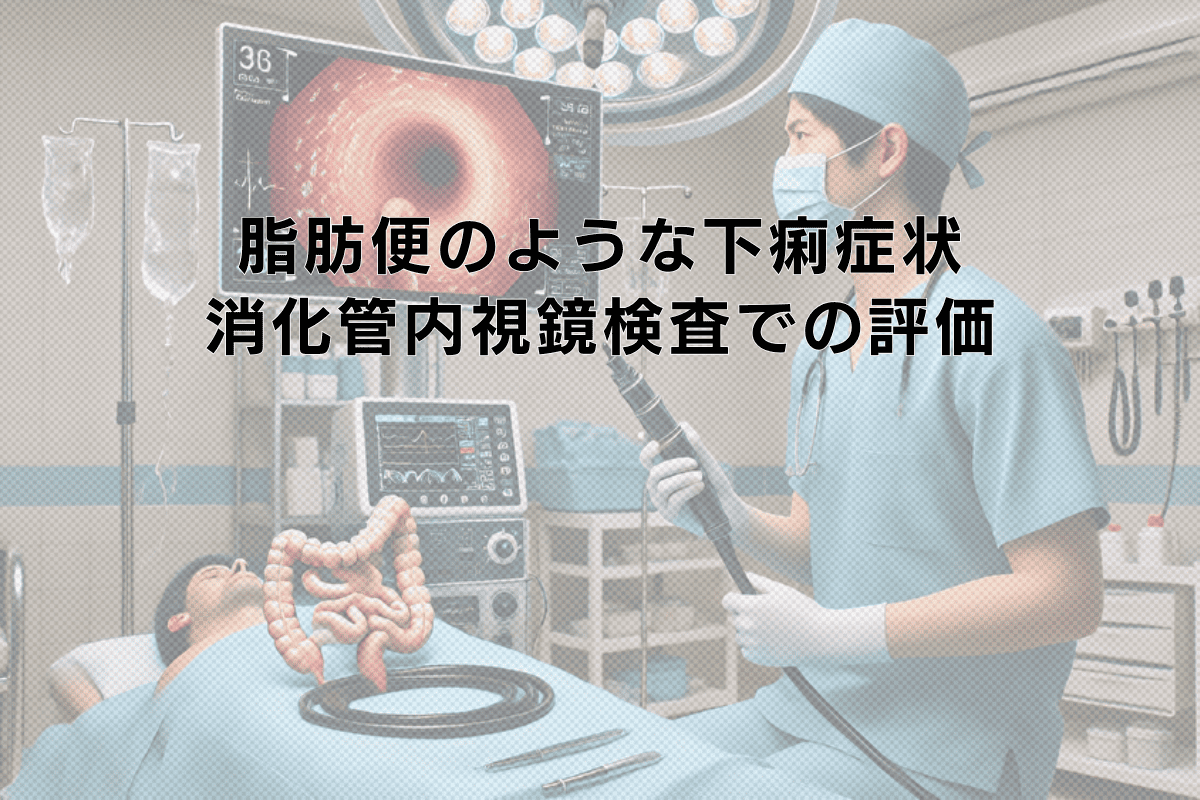便が白っぽく、水に浮いたり、油が浮いていたりする。そんな脂肪便のような下痢の症状に、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
単なる食べ過ぎによる一時的なものなのか、それとも何かの病気のサインなのか、判断に迷うこともあるでしょう。
この記事では、脂肪便を伴う下痢がなぜ起こるのか、その原因から、背景に隠れている可能性のある病気、そして正確な診断に欠かせない消化管内視鏡検査の重要性まで、詳しく解説します。
脂肪便とは何か?特徴と見分け方
脂肪便とは、消化・吸収されなかった脂肪分が、通常よりも多く含まれた便のことです。
健康な人でも食事の内容によっては便中の脂肪分が増えることはありますが、継続的に見られる場合は、消化器系のどこかに問題が生じているサインかもしれません。
脂肪便の見た目と臭いの特徴
脂肪便には、いくつかの特徴的な見た目があります。
まず、色が白っぽく、クリーム色や淡黄色に見えることがあり、これは、正常な便の色素であるビリルビンが、速い腸の通過時間や胆汁の分泌異常によって十分に混ざらないために起こります。
また、便器の水に油がキラキラと浮いていたり、水に流しても便器にべったりと便が付着して取れにくかったりするのも特徴です。臭いに関しては、酸っぱいような、鼻につく独特の不快な臭いがすることがあります。
脂肪便の主な特徴
| 観察ポイント | 特徴的な所見 | 考えられる理由 |
|---|---|---|
| 色 | 白っぽい、淡黄色、クリーム色 | 胆汁の不足、腸管通過時間の短縮 |
| 状態 | 水に浮く、油滴が浮く、便器に付着しやすい | 脂肪分が多く、比重が軽いため |
| 臭い | 酸っぱいような、腐敗したような不快臭 | 脂肪の異常発酵による |
なぜ脂肪が便に混じるのか
私たちが食事から摂取した脂肪(中性脂肪)は、そのままでは体内に吸収できません。まず、肝臓で作られる胆汁によって乳化され、次に膵臓から分泌されるリパーゼという消化酵素によって、脂肪酸とグリセリンに分解されます。
そして、細かくなった状態ではじめて小腸の粘膜から吸収されます。消化・吸収のいずれかの段階に問題が生じると、脂肪は吸収されずにそのまま大腸へと送られ、便と一緒に排泄されてしまい、これが、脂肪便の正体です。
通常の下痢との違い
通常の下痢は、主に腸管での水分吸収がうまくいかないことや、腸の蠕動運動が過剰になることで起こります。便のほとんどは水分であり、水様性や泥状になるのが一般的です。
脂肪便を伴う下痢は、水分の問題に加えて、脂肪の消化吸収不良という要素が加わります。そのため、単に便が緩いだけでなく、前述したような白っぽい色や油が浮くといった特徴的な見た目を伴うことが多いのです。
この見た目の違いが、原因を探る上での重要な手がかりとなります。
家庭でできる簡単なチェック方法
医療機関での正確な診断が基本ですが、家庭でも便の状態を観察することで、ある程度の判断材料を得ることができます。排便後はすぐに流さず、便の色、形、量、そして水に浮くかどうかなどを確認する習慣をつけましょう。
特に、脂っこい食事をした後に症状が出やすいか、特定の薬を飲んだ後から始まったかなど、症状と生活習慣との関連性を記録しておくことも大切です。
脂肪便や脂っぽい下痢を引き起こす主な原因
脂肪便を伴う下痢は、消化・吸収という複雑な工程のどこかに異常があることを示唆しています。原因は、単純な食生活の問題から、特定の臓器の機能低下まで多岐にわたります。
ここでは、脂肪の消化・吸収に関わる三つの主要な要素、分解、乳化、吸収の観点から、原因を詳しく見ていきましょう。
食生活の問題(脂質の過剰摂取)
最も単純で、多くの人が経験する原因が、脂質の過剰摂取です。天ぷらや揚げ物、脂肪分の多い肉類、生クリームをたっぷり使った洋菓子などを一度に大量に食べると、胆汁や膵液の分泌が追いつかず、消化能力の限界を超えてしまいます。
その結果、消化しきれなかった脂肪がそのまま便として排泄され、一時的な脂肪便や下痢を起こします。この場合は、病的なものではなく、食生活を見直すことで改善します。
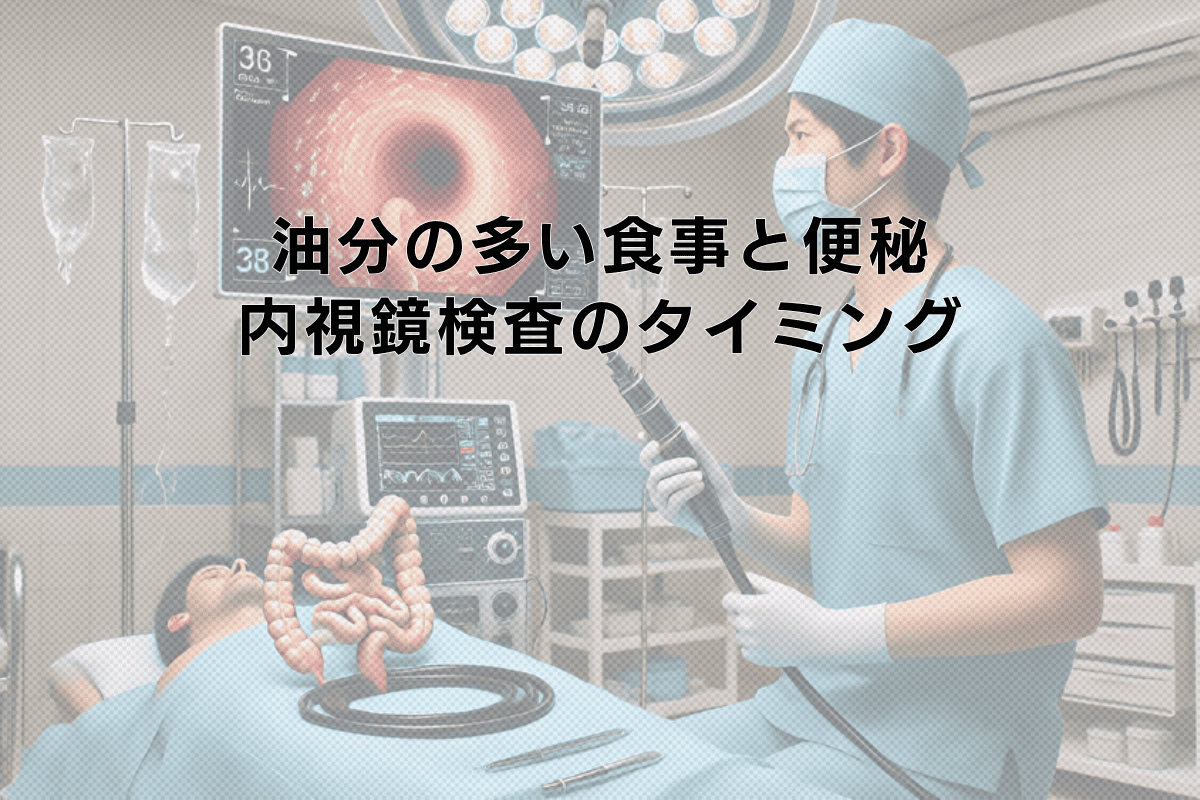
消化酵素の不足(膵臓の機能低下)
脂肪を分解する上で中心的な役割を果たすのが、膵臓から分泌される消化酵素リパーゼです。何らかの原因で膵臓の機能が低下し、リパーゼの分泌が不足すると、脂肪を十分に分解できなくなり、慢性的な脂肪便の原因となります。
代表的な病気として慢性膵炎があり、長期間にわたるアルコールの過剰摂取などが主な原因です。膵臓がんによって膵管が詰まり、膵液の流れが悪くなることでも同様の症状が起こり得ます。
脂肪の消化・吸収の異常と関連臓器
| 異常の段階 | 主な原因 | 関連する臓器・疾患 |
|---|---|---|
| 分解の異常 | 消化酵素(リパーゼ)の分泌不足 | 膵臓(慢性膵炎、膵臓がんなど) |
| 乳化の異常 | 胆汁の分泌・排出障害 | 肝臓、胆のう、胆管(肝硬変、胆石、胆管がんなど) |
| 吸収の異常 | 小腸粘膜の障害 | 小腸(クローン病、セリアック病、感染症など) |
胆汁の分泌異常(肝臓・胆のうの問題)
脂肪を水に溶けやすくし、消化酵素が働きやすいようにする乳化剤の役割を担うのが胆汁です。胆汁は肝臓で作られ、胆のうで濃縮された後、十二指腸に分泌されます。
そのため、肝硬変などで肝臓の機能が低下して胆汁の生産量が減ったり、胆石やがんによって胆管が詰まって胆汁の流れが滞ったりすると、脂肪の乳化が不十分になります。
その結果、リパーゼが効率よく働けず、脂肪が吸収されないまま排泄されてしまいます。
小腸での吸収不良
脂肪が消化酵素によって分解されたとしても、最終的に吸収する小腸の粘膜に問題があれば、脂肪便の原因となります。
クローン病やセリアック病のように、小腸の粘膜に広範囲な炎症や萎縮があると、栄養素を吸収するための表面積が減少し、吸収不良を起こします。
また、胃や小腸の手術で小腸の一部を切除した場合や、特定の感染症によっても、同様に吸収機能が低下することがあります。
- 脂質の過剰摂取
- 膵臓の機能低下
- 肝臓・胆のうの問題
- 小腸の吸収不良

脂肪便を伴う代表的な消化器疾患
継続する脂肪便や脂っぽい下痢は、消化器系の病気のサインである可能性があります。症状が似ていても、原因となる病気は様々で、治療法も異なります。
ここでは、脂肪便を特徴的な症状とする代表的な消化器疾患について、概要と脂肪便以外の症状にも触れながら解説します。
慢性膵炎
慢性膵炎は長期間にわたる膵臓の炎症により、膵臓の細胞が破壊され、徐々に線維化していく病気です。主な原因は長年のアルコール多飲ですが、原因不明の特発性も多く見られます。
膵臓の組織が硬くなることで、消化酵素を分泌する外分泌機能と、インスリンなどを分泌する内分泌機能の両方が低下します。リパーゼの分泌が著しく低下すると、脂肪の消化不良が起こり、特徴的な脂肪便が見られるようになります。
上腹部の鈍い痛みや背中の痛み、体重減少、糖尿病の発症なども伴います。
膵臓がん・胆道がん
膵臓がんや胆管がん、胆のうがんといった悪性腫瘍も、脂肪便の原因となり得ます。がんが膵管を圧迫したり塞いだりすると、膵液の流れが妨げられ、消化酵素が十二指腸に届かなくなります。
また、胆管ががんで閉塞すると、胆汁が流れなくなり、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)と共に、白っぽい脂肪便(灰白色便)が現れます。
このような病気は初期症状が出にくいため、脂肪便や黄疸といった症状に気づいた時には、病気が進行していることも少なくありません。早期発見が非常に重要です。

疾患別の特徴的な症状
| 疾患名 | 脂肪便以外の主な症状 | 注意すべきポイント |
|---|---|---|
| 慢性膵炎 | 上腹部や背中の痛み、体重減少、糖尿病 | 長期の飲酒歴がある場合は特に注意 |
| 膵臓がん・胆道がん | 黄疸、腹痛、背部痛、急激な体重減少 | 黄疸が出た場合は速やかに医療機関へ |
| クローン病 | 腹痛、下痢、血便、発熱、体重減少、肛門病変 | 若年層に発症することが多い |
吸収不良症候群(クローン病など)
吸収不良症候群とは、小腸での栄養素の吸収が慢性的に障害される状態の総称で、原因となる代表的な病気がクローン病です。
クローン病は、口から肛門までの消化管のあらゆる場所に、非連続的な深い炎症や潰瘍を起こす原因不明の病気です。
小腸に広範囲な病変があると、脂肪だけでなく、タンパク質やビタミン、ミネラルなど、様々な栄養素の吸収が障害され、慢性的な下痢、腹痛、体重減少、貧血、栄養失調などを引き起こします。
薬剤性の影響
一部の医薬品の副作用として、脂肪便や下痢が起こることもあります。
肥満治療薬の一種であるオルリスタットは、消化管での脂肪の吸収を直接阻害する作用を持つため、副作用として油っぽい便や下痢が起こりやすいことが知られています。
また、一部の抗生物質や化学療法薬なども、腸内環境を変化させたり、腸粘膜に影響を与えたりすることで、二次的に脂肪の吸収不良を起こす可能性があります。
特定の薬を飲み始めてから症状が出た場合は、薬剤性の可能性を考えることが必要です。
なぜ消化管内視鏡検査が必要なのか
脂肪便のような下痢が続く場合、その原因を正確に突き止めるために、消化管内視鏡検査、胃カメラや大腸カメラは不可欠な検査です。
症状だけでは原因の特定が困難
腹痛、下痢、脂肪便といった症状は、これまで見てきたように、非常に多くの病気で共通して見られます。慢性膵炎なのか、クローン病なのか、あるいは悪性腫瘍なのか、症状の聞き取りだけでは病気を正確に区別することはできません。
原因を推測することはできても、確定診断には至らないのです。不正確な診断に基づいて治療を始めても効果は期待できず、本来治療すべき病気の発見を遅らせてしまう危険性があります。
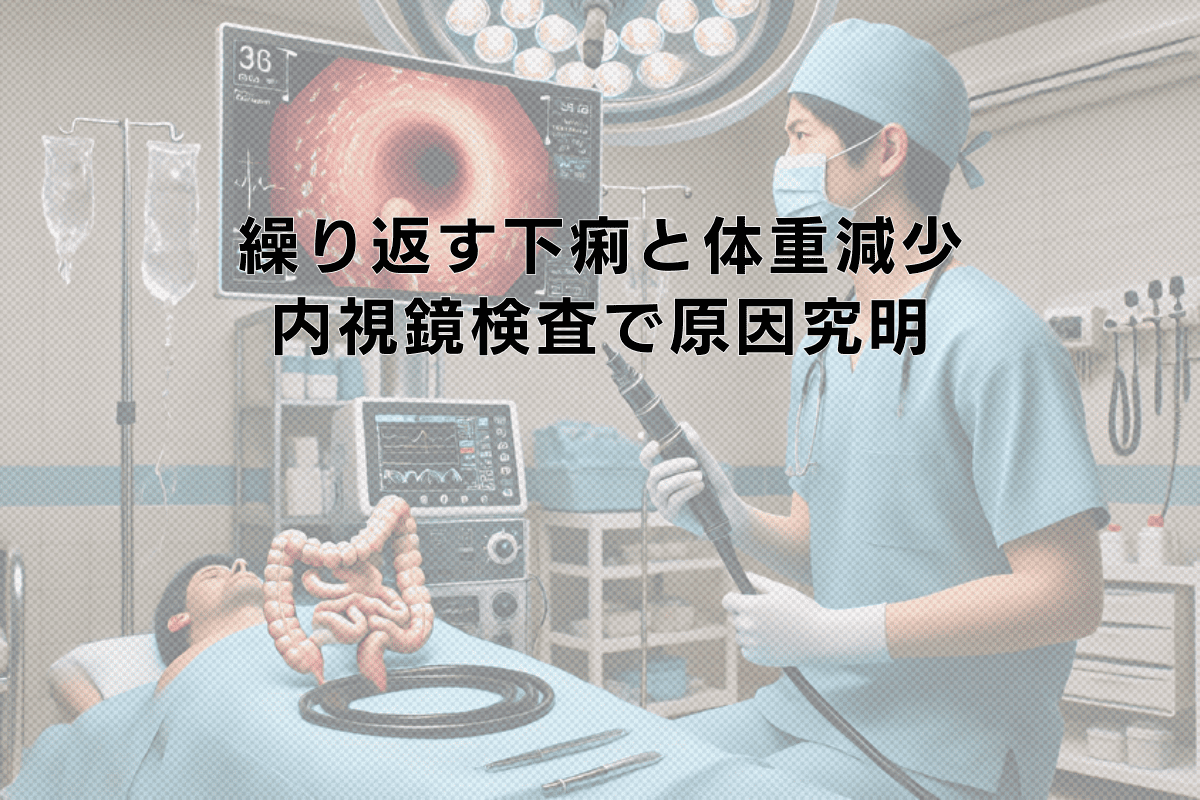
消化管粘膜を直接観察する重要性
内視鏡検査の最大の利点は、食道、胃、十二指腸、そして大腸といった消化管の粘膜の状態を、医師が直接目で見て確認できることです。
粘膜の色や血管の走り方、炎症の有無やその程度、潰瘍やポリープ、がんなどの病変の存在を、リアルタイムで詳細に観察できます。
クローン病に特徴的な縦走潰瘍や敷石像、あるいは大腸がんの腫瘤などを直接確認することで、診断は大きく前進します。CTやエコーでは分からない、粘膜表面の微細な変化を捉えることができるのが、内視鏡検査の強みです。
内視鏡検査の主な目的
| 目的 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 直接観察 | 粘膜の炎症、潰瘍、ポリープ、がんなどを目で見て確認する |
| 生検 | 疑わしい部分の組織を採取し、顕微鏡で詳しく調べる(病理診断) |
| 治療 | ポリープの切除や、出血部位の止血などを行う |
生検による確定診断
内視鏡検査では、観察するだけでなく、疑わしい部分の組織を少量採取することができ、生検または組織診断と呼びます。採取した組織を顕微鏡で詳しく調べる(病理組織検査)ことで、がん細胞の有無や、炎症の種類などを確定的に診断できます。
見た目だけでは良性か悪性か判断が難しいポリープも、生検によって確定診断が可能です。確定診断は、その後の治療方針を決定する上で最も重要な情報となります。
隠れた重篤な病気を見逃さないために
脂肪便の原因として、頻度は高くないものの、膵臓がんや大腸がんといった命に関わる病気が隠れている可能性も考慮しなくてはなりません。
初期には自覚症状が乏しいことが多く、症状が出た時には進行しているケースも少なくありません。内視鏡検査は、こうした重篤な病気を早期の段階で発見するためにも、極めて重要な役割を果たします。
特に、40歳を過ぎたら、症状がなくても定期的に内視鏡検査を受けることが、がんの早期発見につながります。
消化管内視鏡検査での評価基準と観察ポイント
医師は内視鏡検査を行う際、どのような点に注目して消化管の内部を観察しているのでしょうか。脂肪便という症状から、原因となりうる病気を念頭に置き、それぞれの疾患に特徴的な所見がないかを注意深く探しています。
上部消化管内視鏡(胃カメラ)での評価
胃カメラでは、食道、胃、そして小腸の入り口である十二指腸までを観察し、脂肪の消化・吸収に重要な役割を果たす十二指腸は、特に重要です。
膵臓からの膵液と、肝臓・胆のうからの胆汁は、十二指腸のファーター乳頭という場所から分泌されます。乳頭部に腫瘍などによる閉塞がないか、炎症やむくみはないかを確認します。
また、セリアック病や一部の吸収不良症候群では、十二指腸の粘膜のヒダ(輪状ヒダ)が低くなったり、消失したりする所見が特徴的です。
胃カメラでの主な観察ポイント
| 観察部位 | 主なチェック項目 | 関連する疾患 |
|---|---|---|
| 胃 | 炎症、潰瘍、萎縮、腫瘍の有無 | 胃炎、胃潰瘍、胃がん |
| 十二指腸 | ファーター乳頭部の異常、粘膜の炎症・萎縮、潰瘍 | 膵臓・胆道疾患、セリアック病、クローン病 |
下部消化管内視鏡(大腸カメラ)での評価
大腸カメラでは、大腸全体と、小腸の最後の部分である回腸末端を観察します。脂肪便の原因が小腸での吸収不良にある場合、特に回腸末端は重要な観察部位となります。
クローン病は、この回腸末端に好発することが知られており、特徴的なアフタ性潰瘍や縦走潰瘍、敷石像といった所見がないかを注意深く探します。
また、大腸全体を観察することで、炎症性腸疾患のもう一つの代表である潰瘍性大腸炎との鑑別や、大腸がんやポリープの有無も同時に確認することが可能です。
小腸内視鏡やカプセル内視鏡の役割
胃カメラや大腸カメラでは観察できない、十二指腸より奥の小腸部分に病気の原因が疑われる場合、さらに専門的な検査が必要になることがあります。それが、小腸内視鏡やカプセル内視鏡です。
小腸内視鏡は、口や肛門から長いスコープを挿入して小腸を観察するもので、生検も可能です。カプセル内視鏡は、ビタミン剤のような大きさのカメラ付きカプセルを飲み込み、消化管を通過しながら撮影された画像を解析します。
脂肪便のような下痢への対処と生活改善
脂肪便のような下痢の症状がある場合、原因を特定し治療を受けることが最も重要ですが、それと同時に、日々の生活習慣を見直すことも症状の緩和や再発予防につながります。
食生活の見直しと脂質の管理
脂肪便の直接的な原因は、消化しきれないほどの脂肪です。まずは、ご自身の食生活を振り返り、脂質の摂取量を見直すことが基本となります。揚げ物や炒め物、脂肪分の多い肉類、バターや生クリームを多く使った料理は控えめにしましょう。
調理法を揚げる・炒めるから、蒸す・茹でる・焼くなどに変えるだけでも、摂取する脂質の量を大きく減らすことができます。一度にたくさん食べるのではなく、消化器への負担が少ない食事を、回数を分けて摂ることも有効です。
- 揚げ物、炒め物を避ける
- 脂肪の多い肉類(バラ肉など)を控える
- 調理法を工夫する(蒸す、茹でる)
- バランスの取れた食事を心がける

アルコールの摂取を控える重要性
アルコールは、脂肪便の原因となりうる膵臓や肝臓に、直接的なダメージを与える最大の要因の一つで、特に、慢性膵炎の最大の原因は長年のアルコール多飲です。
すでに膵臓や肝臓の機能が低下している場合にアルコールを摂取すると、病状をさらに悪化させることになります。脂肪便や脂っぽい下痢の症状がある場合は、原因がはっきりするまでは、アルコールの摂取を控えるべきです。
自己判断での下痢止め薬のリスク
つらい下痢の症状を、市販の下痢止め薬で止めたいと考えるかもしれませんが、自己判断での使用には注意が必要です。下痢は、体にとって不要なものや有害なものを排出しようとする防御反応の一面も持っています。
無理に下痢を止めると、原因物質が腸内に留まり、かえって状態を悪化させる可能性があり、特に、細菌感染などが原因の場合、下痢止め薬の使用は禁忌となることもあります。
まずは医療機関を受診し、原因に応じた適切な薬を処方してもらうことが大切です。
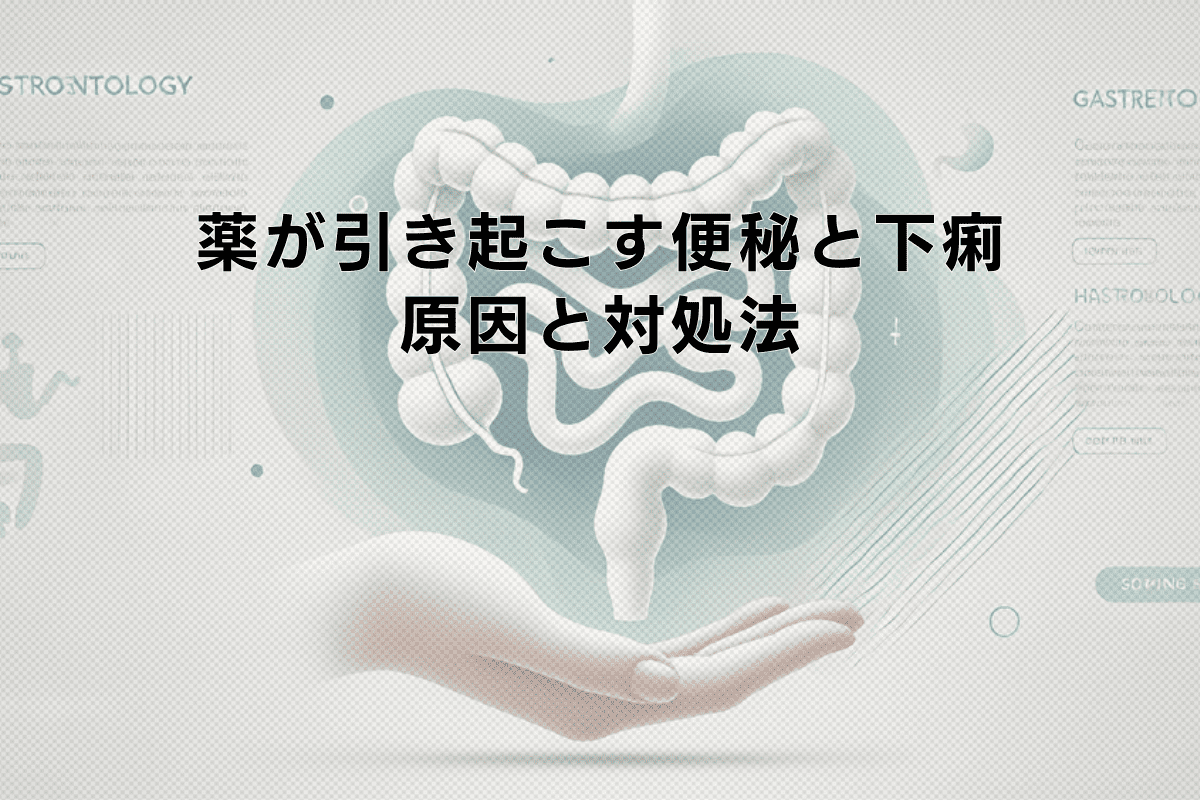
生活改善のポイント
| 項目 | 具体的な行動 | その理由 |
|---|---|---|
| 食事 | 低脂肪食を心がけ、バランス良く食べる | 消化器への負担を減らし、脂肪の過剰摂取を防ぐ |
| 飲酒 | 禁酒または節酒を徹底する | 膵臓や肝臓へのダメージを防ぎ、病状の悪化を避ける |
| 市販薬 | 自己判断での下痢止め薬の使用は避ける | 原因に応じた適切な治療の機会を逃すリスクがある |
よくある質問
最後に、脂肪便や消化管内視鏡検査に関して、多くの方が抱く疑問や不安についてお答えします。
- 脂肪便は自然に治りますか
-
暴飲暴食や脂質の多い食事の摂りすぎによる一時的なものであれば、食生活を改善することで自然に治まることがほとんどです。
しかし、その背景に慢性膵炎や吸収不良症候群、あるいは腫瘍などの病気が隠れている場合は、原因疾患の治療を行わない限り、自然に治ることはありません。放置することで病気が進行してしまう可能性があります。
症状が続く場合は、自己判断で様子を見ず、専門医の診断を仰ぐことが重要です。
- 内視鏡検査は苦しいですか
-
かつては内視鏡検査に対して、苦しい、つらいというイメージがありましたが、近年では技術や機器が大きく進歩し、患者さんの負担は大幅に軽減されています。
多くの医療機関では、鎮静剤(静脈麻酔)を使用して、うとうとと眠っているようなリラックスした状態で検査を受けることができます。
- 検査の前に食事制限はありますか
-
正確で安全な検査を行うために、食事制限が必要です。胃カメラの場合は、検査前日の夕食は消化の良いものを早めに済ませ、その後は絶食となります。
検査当日は、水やお茶など、糖分を含まない透明な飲み物であれば、検査の数時間前まで摂取可能なことが多いです。
大腸カメラの場合は、より厳密な準備が必要で、検査前日は消化の良い食事(検査食)をとり、夜に下剤を服用します。そして検査当日は、朝から数時間かけて、腸内をきれいにするための洗腸液を約1〜2リットル飲みます。
- 検査費用はどのくらいかかりますか
-
内視鏡検査は、医師が必要と判断して行う場合、健康保険が適用されます。3割負担の場合、胃カメラの費用目安は5,000円から15,000円程度、大腸カメラの費用目安は7,000円から25,000円程度です。
ポリープを切除するなどの治療を同時に行った場合は、その分の費用が加算されます。詳細な費用については、検査を受ける前に医療機関に確認してください。
次に読むことをお勧めする記事
【下痢と栄養吸収障害の関係|内視鏡検査による腸管機能の評価】
脂肪便の背景には“吸収”の問題が関わります。消化吸収の全体像と、生検を含む内視鏡で何を確認するのかを押さえると、次の検査選択がより明確になります。
【繰り返す下痢と体重減少の症状|内視鏡検査による原因究明】
脂肪便について理解を深めたら、次は類似する下痢症状について知っておくと安心です。体重減少を伴う下痢でお悩みの方に特に参考になる内容です。
参考文献
Bo-Linn GW, Fordtran JS. Fecal fat concentration in patients with steatorrhea. Gastroenterology. 1984 Aug 1;87(2):319-22.
Ulshen MH. Diarrhea and steatorrhea. Primary pediatric care (4th ed., pp. 1020-1033). St. Louis, MO: Mosby. 2001.
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Corinaldesi R, Stanghellini V, Barbara G, Tomassetti P, De Giorgio R. Clinical approach to diarrhea. Internal and emergency medicine. 2012 Oct;7:255-62.
Headstrom PD, Surawicz CM. Chronic diarrhea. Clinical Gastroenterology and hepatology. 2005 Aug 1;3(8):734-7.
Nakamura T, Takebe K, Kudoh K, Ishii M, Imamura KI, Kikuchi H, Kasai F, Tandoh Y, Yamada N, Arai Y, Terada A. Steatorrhea in Japanese patients with chronic pancreatitis. Journal of gastroenterology. 1995 Jan;30:79-83.
Schiller LR, Pardi DS, Sellin JH. Chronic diarrhea: diagnosis and management. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2017 Feb 1;15(2):182-93.
Luk GD, Hendrix TR. Microscopic examination of stool as a screening test for steatorrhea. Gastroenterology. 1978 May 1;74(5):1134.
Camilleri M. Chronic diarrhea: a review on pathophysiology and management for the clinical gastroenterologist. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2004 Mar 1;2(3):198-206.
Sakaria SS, Rutherford RE. Chronic diarrhea. Sitaraman and Friedman’s Essentials of Gastroenterology. 2018 Jan 16:89.