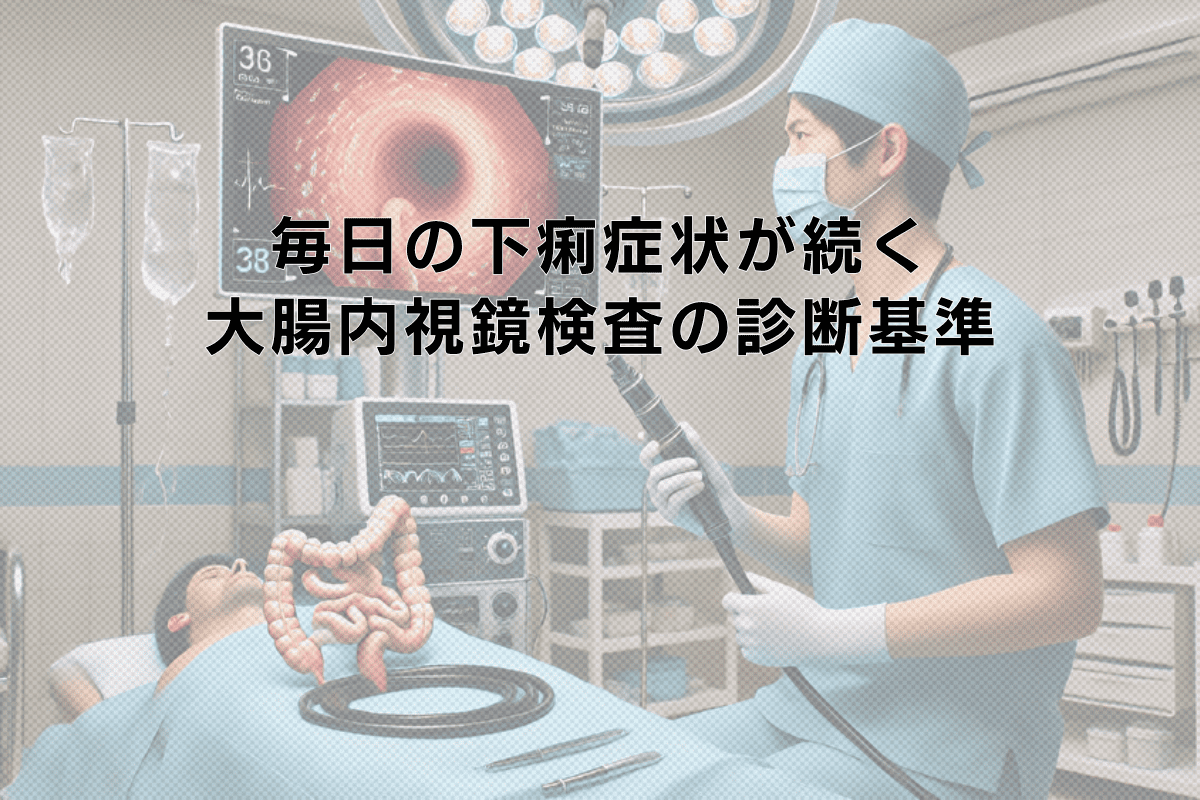毎日続く下痢の症状は、多くの方にとって深刻な悩みです。単なる体調不良と片付けてしまうこともありますが、背景には注意すべき病気が隠れている可能性も否定できません。
この記事では、なぜ毎日下痢が続くのか、原因としてどのようなことが考えられるのかを解説します。
そして、医療機関で受ける大腸内視鏡検査が、正確な診断のためにいかに重要であるか、具体的な診断基準についても詳しく説明します。
毎日続く下痢、背景にあるもの
下痢が毎日続く状態は、身体からの重要なサインです。一時的なものであれば様子を見ることもできますが、慢性的に続く場合はその原因を正しく理解することが大切です。
下痢の原因は、食生活やストレスといった日常的な要因から、特定の病気まで多岐にわたります。
急性下痢と慢性下痢の違い
下痢は、症状が続く期間によって大きく二つに分類し、一つは「急性下痢」、もう一つは「慢性下痢」です。毎日続く下痢は多くの場合、慢性下痢に該当します。
二つの違いを理解することは、ご自身の状態を把握する上で最初の重要な一歩となります。
下痢の期間による分類
| 分類 | 症状が続く期間 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 急性下痢 | 2週間以内 | ウイルス・細菌感染、食中毒、薬の副作用など |
| 遷延性下痢 | 2週間から4週間 | 急性から慢性への移行期、一部の感染症など |
| 慢性下痢 | 4週間以上 | 過敏性腸症候群、炎症性腸疾患、大腸がんなど |
急性下痢は、原因がはっきりしていることが多く、原因が取り除かれれば自然に回復に向かいます。
一方で、4週間以上にわたって下痢が続く慢性下痢の場合は、背景に何らかの病気が隠れている可能性を考え、専門的な検査が必要になることがあります。
考えられる生活習慣の原因
病気だけが下痢の原因ではなく、日々の生活習慣が腸に負担をかけ、下痢を引き起こしているケースも少なくありません。特に食生活は腸内環境に直接影響を与えます。
例えば、脂っこい食事や香辛料の多い刺激的な食べ物は、腸を刺激し、便の水分量を増やしてしまいます。また、アルコールの過剰摂取も腸の粘膜を傷つけ、下痢の原因となります。
乳製品に含まれる乳糖を分解する酵素が少ない「乳糖不耐症」の方も、牛乳やヨーグルトを摂取すると下痢をしやすいです。
ストレスと下痢の関係性
心と体は密接につながっており、特に腸は「第二の脳」とも呼ばれるほど、ストレスの影響を受けやすい臓器です。強いプレッシャーや不安、緊張を感じると、自律神経のバランスが乱れます。
自律神経は腸の動きをコントロールしているため、バランスが崩れると、腸が過剰に動いてしまい、食べ物が十分に水分を吸収される前に排出されて下痢となります。これは、過敏性腸症候群(IBS)の典型的な症状の一つでもあります。
下痢が続く場合に考えられる主な病気
毎日の下痢が生活習慣の改善やストレスの軽減で良くならない場合、何らかの病気が原因である可能性を考慮する必要があります。消化器系の病気には、症状が似ていても異なる対応が必要なものが多くあります。
過敏性腸症候群(IBS)
過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome, IBS)は、大腸内視鏡検査などで調べても、炎症や潰瘍といった目に見える異常が見つからないにもかかわらず、腹痛や腹部の不快感を伴う下痢や便秘が続く病気です。
ストレスや生活リズムの乱れが主な原因と考えられており、日本人の10人に1人がこの病気を持っているとも言われています。特に、通勤や通学の途中、大事な場面で急にお腹が痛くなり、トイレに駆け込みたくなるのが特徴です。
IBSは、症状の現れ方によっていくつかのタイプに分類されます。
過敏性腸症候群の主なタイプ
| タイプ | 主な症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| 下痢型(IBS-D) | 突然の激しい腹痛と水様性の下痢 | 男性に比較的多く見られます。 |
| 便秘型(IBS-C) | 硬くてコロコロした便、排便困難 | 女性に比較的多く見られます。 |
| 混合型(IBS-M) | 下痢と便秘を交互に繰り返す | 症状が変動しやすいです。 |
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)
炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease, IBD)は、腸に原因不明の炎症が起こり、びらん(ただれ)や潰瘍ができる病気の総称です。主に「潰瘍性大腸炎」と「クローン病」の二つがあります。
どちらも国の難病に指定されており、長期的な治療が必要で、下痢に加えて、血便、腹痛、発熱、体重減少などの症状を伴うことが多く、過敏性腸症候群との鑑別が重要です。
潰瘍性大腸炎とクローン病の比較
| 項目 | 潰瘍性大腸炎 | クローン病 |
|---|---|---|
| 主な炎症場所 | 大腸の粘膜(連続的に広がる) | 口から肛門までの全消化管(非連続的に発生) |
| 特徴的な症状 | 粘血便(粘液と血液が混じった便) | 腹痛、体重減少、痔ろう |
| 炎症の深さ | 粘膜層(浅い) | 全層性(深い) |
これらの病気は放置すると症状が悪化し、生活の質を著しく低下させる可能性があるため、早期の診断と適切な治療の開始が大切です。
大腸がんやポリープ
毎日の下痢は、大腸がんやその前段階であるポリープのサインである可能性もゼロではありません。
がんや大きなポリープが腸内にできると、腸管が狭くなることで便が通りにくくなり、便秘と下痢を繰り返したり、便が細くなったりすることがあります。また、腫瘍の表面から出血することで、便に血が混じる(血便)こともあります。
大腸がんは早期に発見すれば治癒率が高い病気です。特に40歳を過ぎたら、症状がなくても定期的な検査を考えることが推奨されます。
医療機関を受診するべき下痢の基準
「このくらいの下痢で病院に行くのは大げさかもしれない」と考える方もいるかもしれません。しかし、中には専門的な診断や治療を必要とする下痢もあります。
ここでは、どのような状態であれば医療機関を受診するべきか、具体的な基準を示します。ご自身の症状と照らし合わせてみてください。
下痢が続く期間の目安
前述の通り、下痢が4週間以上続いている場合は「慢性下痢」と定義され、一度専門医に相談することをお勧めします。一時的な体調不良であれば、通常は数日から2週間程度で改善に向かいます。
しかし、それ以上続く場合は、生活習慣だけではない、何らかの医学的な原因が潜んでいる可能性が高まります。
特に、市販の下痢止めを飲んでも症状が全く改善しない、あるいは薬をやめるとすぐに再発するという場合は、受診の重要なサインです。
注意すべき付随症状
下痢だけでなく、他の症状が伴う場合は特に注意が必要です。症状は、より深刻な病気の可能性を示唆していることがあります。以下のような症状が一つでも当てはまる場合は、早めに医療機関を受診してください。
- 明らかな血便(便に血が混じる、便器が赤くなる)
- 38度以上の発熱
- 我慢できないほどの激しい腹痛
- 意図しない体重減少(半年で5%以上)
- 吐き気や嘔吐
危険な兆候を示す症状
| 症状 | 考えられる主な病気 | 緊急性 |
|---|---|---|
| 血便 | 炎症性腸疾患、大腸がん、感染性腸炎など | 高い |
| 高熱 | 感染性腸炎、炎症性腸疾患の活動期など | 高い |
| 体重減少 | 大腸がん、クローン病、吸収不良症候群など | 中〜高い |
年齢とリスク要因
年齢も受診を判断する上での一つの基準です。一般的に、年齢が上がるにつれて大腸がんなどの悪性疾患のリスクは高まります。
特に40歳以上で初めて慢性的な下痢を経験した場合や、血縁者に大腸がんや炎症性腸疾患にかかった方がいる場合は、リスクが高いと考えます。
リスク要因に当てはまる方は、症状が軽くても一度専門医に相談し、大腸内視鏡検査の必要性について話し合いましょう。
大腸内視鏡検査で何がわかるのか
慢性的な下痢の原因を正確に突き止めるために、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)は極めて有効な手段です。この検査は、肛門から内視鏡を挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体の内部を直接観察するものです。
医師が自分の目で腸の中を見ることができるため、レントゲンやCTではわからない微細な変化も捉えることができます。
大腸粘膜の直接的な観察
大腸内視鏡検査の最大の利点は、大腸の粘膜をリアルタイムで、かつ詳細に観察できる点です。モニターを通して、粘膜の色、血管の走行、表面の凹凸などを隅々まで確認します。
正常な粘膜はピンク色で滑らかですが、炎症が起きていると赤く腫れたり、ただれたり(びらん)、えぐれたり(潰瘍)し、炎症性腸疾患や感染性腸炎の診断に直結します。
また、過敏性腸症候群のように、粘膜に異常が見られないことを確認することも、診断上非常に重要です。
ポリープやがんの早期発見
大腸内視鏡検査は、大腸がんや前段階であるポリープを発見するための最も確実な方法で、数ミリ程度の小さなポリープでも発見することが可能です。
ポリープの中には、放置すると将来的にがん化する可能性があるもの(腺腫性ポリープ)も含まれ、検査中にこのようなポリープを発見した場合、その場で切除することもできます。
ポリープの段階で切除することで、将来の大腸がんを予防することにつながります。
組織の一部を採取する生検
内視鏡で観察して異常が疑われる部分が見つかった場合、その組織の一部を鉗子という小さな器具でつまみ取ることができます。これが「生検」または「組織生検」です。採取した組織は、顕微鏡で詳しく調べる病理検査に提出します。
病理検査によって、炎症の具体的な種類や程度、細胞が良性か悪性か(がん細胞か否か)を確定診断でき、見た目だけでは判断が難しい病気の診断において、生検は決定的な情報をもたらします。
生検で確定診断が期待できる病気
| 病気のカテゴリー | 具体的な病名 | 診断のポイント |
|---|---|---|
| 腫瘍性疾患 | 大腸がん、大腸ポリープ | 細胞の異型度(悪性度)の判定 |
| 炎症性腸疾患 | 潰瘍性大腸炎、クローン病 | 特徴的な炎症細胞の有無や分布 |
| その他 | アメーバ赤痢、サイトメガロウイルス腸炎 | 病原体の確認 |
大腸内視鏡検査による診断の流れ
大腸内視鏡検査を受けることが決まったら、どのような準備が必要で、当日はどのように進むのか、不安に思う方もいるでしょう。ここでは、検査前から検査後までの一般的な流れを解説します。
検査前の食事制限と下剤の服用
正確な検査を行うためには、大腸の中を空っぽにして、きれいな状態にする必要があり、検査前日から準備が始まります。通常、検査前日は消化の良い食事を摂るように指示があります。
きのこや海藻、種のある果物など、繊維質が多く腸に残りやすいものは避けてください。
検査前日の食事例
| 種類 | 食べて良いもの | 避けるべきもの |
|---|---|---|
| 主食 | おかゆ、うどん、食パン(耳なし) | 玄米、雑穀米、ライ麦パン |
| おかず | 豆腐、鶏ささみ、白身魚、卵 | きのこ類、海藻類、こんにゃく、豆類 |
| 飲み物 | 水、お茶、透明なジュース | 牛乳、乳製品、色の濃いジュース |
検査当日の朝または前日の夜から、腸管洗浄剤(下剤)を約1〜2リットル服用し、数時間のうちに何度も排便があり、最終的には便が透明な液体だけになります。前処置が検査の精度を左右するため、指示通りに正しく行うことが重要です。

検査当日の流れ
医療機関に到着したら、まず体調の確認や着替えを行います。検査室に入り、検査台の上で体の左側を下にして横になり、その後、鎮静剤や鎮痛剤を希望した場合は、点滴で薬剤を投与します。
薬が効いてきて、リラックスした状態で検査が始まります。医師が肛門から内視鏡をゆっくりと挿入し、大腸の一番奥(盲腸)まで進めていき、内視鏡を抜きながら、大腸の内部を隅々まで観察します。
検査時間自体は、個人差はありますが、通常15分から30分程度です。
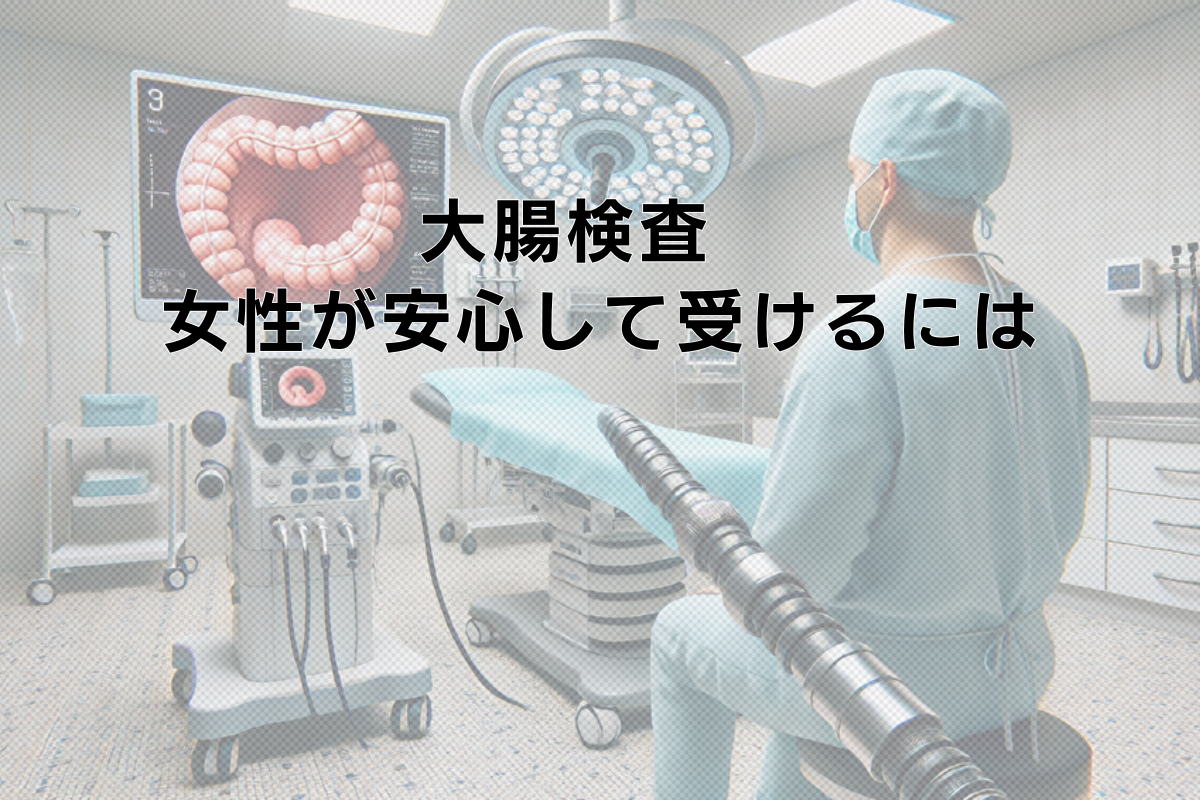
検査後の注意点
検査が終了したら、鎮静剤の効果が覚めるまで、リカバリールームで1時間ほど休み、鎮静剤を使用した場合、当日は車やバイク、自転車の運転はできません。公共交通機関を利用するか、家族に送迎を頼む必要があります。
食事は、検査で腸に空気をたくさん入れているため、お腹の張りが落ち着いてから、消化の良いものから摂るようにしてください。もしポリープを切除した場合は、数日間は飲酒や激しい運動、旅行などを控えるよう指示があります。
何か異常を感じた場合は、すぐに検査を受けた医療機関に連絡することが大切です。
- 当日の車の運転は控える
- 食事は消化の良いものから
- 激しい腹痛や多量の出血があれば連絡する
大腸内視鏡検査の診断基準とは
大腸内視鏡検査において、医師はどのような点に着目し、診断を下しているのでしょうか。単に「異常がある・ない」だけではなく、観察される所見の一つひとつが、病気を特定するための重要な手がかりとなります。
粘膜の色や血管の様子の評価
健康な大腸の粘膜は、光沢のあるピンク色をしており、粘膜の下にある血管が規則正しく透けて見えます。しかし、炎症が起こると粘膜は赤みを帯び(発赤)、腫れぼったくなります(浮腫)。
炎症が強くなると血管の模様が不明瞭になったり、消えてしまったりします。この血管透見の消失は、潰瘍性大腸炎などの活動性を評価する重要な基準です。
また、粘膜がもろくなり、内視鏡が軽く接触しただけで出血しやすくなる(易出血性)のも、活動性の炎症を示す所見です。
びらんや潰瘍の有無と特徴
びらんや潰瘍は、炎症によって粘膜が傷ついた状態で、びらんは浅い傷、潰瘍はさらに深い傷を指します。これらの有無はもちろん、その形、大きさ、分布の仕方が診断の鍵となります。
潰瘍性大腸炎では、炎症が直腸から連続的に広がり、多数のびらんや浅い潰瘍が見られるのが特徴です。
一方、クローン病では、深い縦長の潰瘍(縦走潰瘍)や、敷石のような見た目(敷石像)が特徴的で、病変が飛び飛びに存在する(区域性病変)ことが多いです。
炎症性腸疾患における内視鏡所見の例
| 所見 | 潰瘍性大腸炎で典型的 | クローン病で典型的 |
|---|---|---|
| 血管透見の消失 | はい | はい |
| びまん性発赤 | はい | いいえ |
| 縦走潰瘍・敷石像 | いいえ | はい |
ポリープや腫瘍の形態的特徴
ポリープや腫瘍が見つかった場合、その大きさや形、色、表面の模様などを詳細に観察し、病変が良性か悪性(がん)か、あるいはがん化する可能性があるものかを見分けるための重要な情報です。
表面が赤みを帯びている、形がいびつである、表面が崩れているなどの所見は、がんを疑うサインです。
内視鏡の先端から特殊な光を当てたり(NBI観察)、色素を散布したりすることで、病変の表面構造をより詳しく観察し、診断の精度を高める技術もあります。観察所見に基づき、生検を行うか、その場で切除するかを判断します。
下痢の症状を和らげるための生活習慣
毎日の下痢に悩む方にとって、医療機関での診断と治療はもちろん重要ですが、日々の生活習慣を見直すことも症状の改善につながります。ここでは、ご自身で取り組むことができるセルフケアについて解説します。
食事内容の見直し
腸に負担をかけない食事を心がけることが基本です。特に下痢がひどい時は、消化が良く、温かいものを中心に摂りましょう。暴飲暴食を避け、1回の食事量を減らして回数を増やすことも有効です。
下痢の際に心がけたい食事
| 分類 | 推奨される食品 | 控えた方が良い食品 |
|---|---|---|
| 炭水化物 | おかゆ、よく煮込んだうどん、パン | ラーメン、パスタ、食物繊維の多いパン |
| タンパク質 | 鶏ささみ、白身魚、豆腐、卵 | 脂身の多い肉、揚げ物、加工肉 |
| その他 | りんご、バナナ、野菜スープ | 香辛料、カフェイン、アルコール、冷たい飲み物 |

十分な水分補給の重要性
下痢が続くと、体内の水分と電解質(ナトリウムやカリウムなど)が大量に失われ、脱水症状を引き起こす危険があります。脱水を防ぐためには、こまめな水分補給が何よりも大切です。
ただの水やお茶だけでなく、失われた電解質も補給できる経口補水液やスポーツドリンクを利用し、一度にたくさん飲むのではなく、少量ずつ頻繁に飲むことを心がけてください。
ストレス管理とリラックス法
ストレスが下痢の大きな原因となっている場合、心身をリラックスさせることが症状の緩和につながります。自分に合ったストレス解消法を見つけることが重要です。
- ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる
- 好きな音楽を聴いたり、読書をしたりする時間を作る
- 軽いウォーキングやストレッチを行う
- 信頼できる友人や家族に話を聞いてもらう
完璧を目指さず、少しでもリラックスできる時間を持つことを意識するだけでも、腸の状態は変わってくる可能性があります。
よくある質問
最後に、大腸内視鏡検査に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。
- 大腸内視鏡検査は痛いですか?
-
腸が曲がりくねっている部分を内視鏡が通過する際に、お腹が張るような感覚や痛みを感じることがあります。
しかし、多くの医療機関では、鎮静剤や鎮痛剤を使用して、うとうとと眠っているような、リラックスした状態で検査を受けることができ、苦痛をほとんど感じずに検査を終えることが可能です。
検査を受ける前に、痛みが不安であることを医師や看護師に伝えて、鎮静剤の使用について相談してください。
- 検査時間はどのくらいかかりますか?
-
検査そのものにかかる時間は、大腸の長さや形、状態によって異なりますが、一般的には15分から30分程度です。ポリープを切除するなどの処置を行う場合は、もう少し時間がかかることもあります。
ただし、これはあくまで検査室に入ってから出るまでの時間です。来院してから着替え、前処置の確認、検査、そして検査後の休憩(鎮静剤を使用した場合)まで含めると、全体では2〜3時間程度の時間を見ておくと良いでしょう。
- 検査後すぐに普段の生活に戻れますか?
-
鎮静剤を使用しなかった場合は、検査後すぐに日常生活に戻ることができます。鎮静剤を使用した場合は、効果が完全に切れるまで注意が必要です。当日の乗り物の運転は絶対に避けてください。
デスクワークなどの軽作業は可能ですが、重要な判断を伴う仕事は翌日以降にすることをお勧めします。
食事や運動に関する制限は、ポリープ切除の有無によって異なりますので、検査後の医師からの説明をよく聞いて、指示に従ってください。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
毎日続く下痢と大腸内視鏡検査の基本を押さえたら、次は実際の検査準備について知っておくと安心です。3日前からの準備方法を知ることで、検査を受ける方に特に参考になる内容です。
【腹痛や下痢が頻繁に起こる原因 検査と治療について】
毎日の下痢について理解が深まると、関連する腹痛や消化器症状についても知りたくなる方が多いようです。症状の全体像と治療の意外な繋がりが見えてくる内容です。
参考文献
Shah RJ, Fenoglio-Preiser C, Bleau BL, Giannella RA. Usefulness of colonoscopy with biopsy in the evaluation of patients with chronic diarrhea. The American journal of gastroenterology. 2001 Apr 1;96(4):1091-5.
Kagueyama FM, Nicoli FM, Bonatto MW, Orso IR. Importance of biopsies and histological evaluation in patients with chronic diarrhea and normal colonoscopies. ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo). 2014 Jul;27:184-7.
Juckett G, Trivedi R. Evaluation of chronic diarrhea. American family physician. 2011 Nov 15;84(10):1119-26.
Filliettaz SS, Juillerat P, Burnand B, Arditi C, Windsor A, Beglinger C, Dubois RW, Peytremann-Bridevaux I, Pittet V, Gonvers JJ, Froehlich F. Appropriateness of colonoscopy in Europe (EPAGE II)–chronic diarrhea and known inflammatory bowel disease. Endoscopy. 2009 Mar;41(03):218-26.
Yamauchi Y, Arai M, Akizue N, Ohta Y, Okimoto K, Matsumura T, Fan MM, Imai C, Tawada A, Kato J, Kato N. Colonoscopic evaluation of diarrhea/colitis occurring as an immune-related adverse event. Japanese Journal of Clinical Oncology. 2021 Mar;51(3):363-70.
Arai M, Taida T, Fan MM, Imai C, Tawada A, Takiguchi Y. Evaluation of diarrhea as immune-related adverse event by colonoscopy. Annals of Oncology. 2018 Oct 1;29:vii56.
Ihara E, Manabe N, Ohkubo H, Ogasawara N, Ogino H, Kakimoto K, Kanazawa M, Kawahara H, Kusano C, Kuribayashi S, Sawada A. Evidence-based clinical guidelines for chronic diarrhea 2023. Digestion. 2024 Dec 9;105(6):480-97.
Shen B, Khan K, Ikenberry SO, Anderson MA, Banerjee S, Baron T, Ben-Menachem T, Cash BD, Fanelli RD, Fisher L, Fukami N. The role of endoscopy in the management of patients with diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2010 May 1;71(6):887-92.
Marshall JB, Singh R, Diaz-Arias AA. Chronic, unexplained diarrhea: are biopsies necessary if colonoscopy is normal?. American Journal of Gastroenterology (Springer Nature). 1995 Mar 1;90(3).
Burgers K, Lindberg B, Bevis ZJ. Chronic diarrhea in adults: evaluation and differential diagnosis. American family physician. 2020 Apr 15;101(8):472-80.