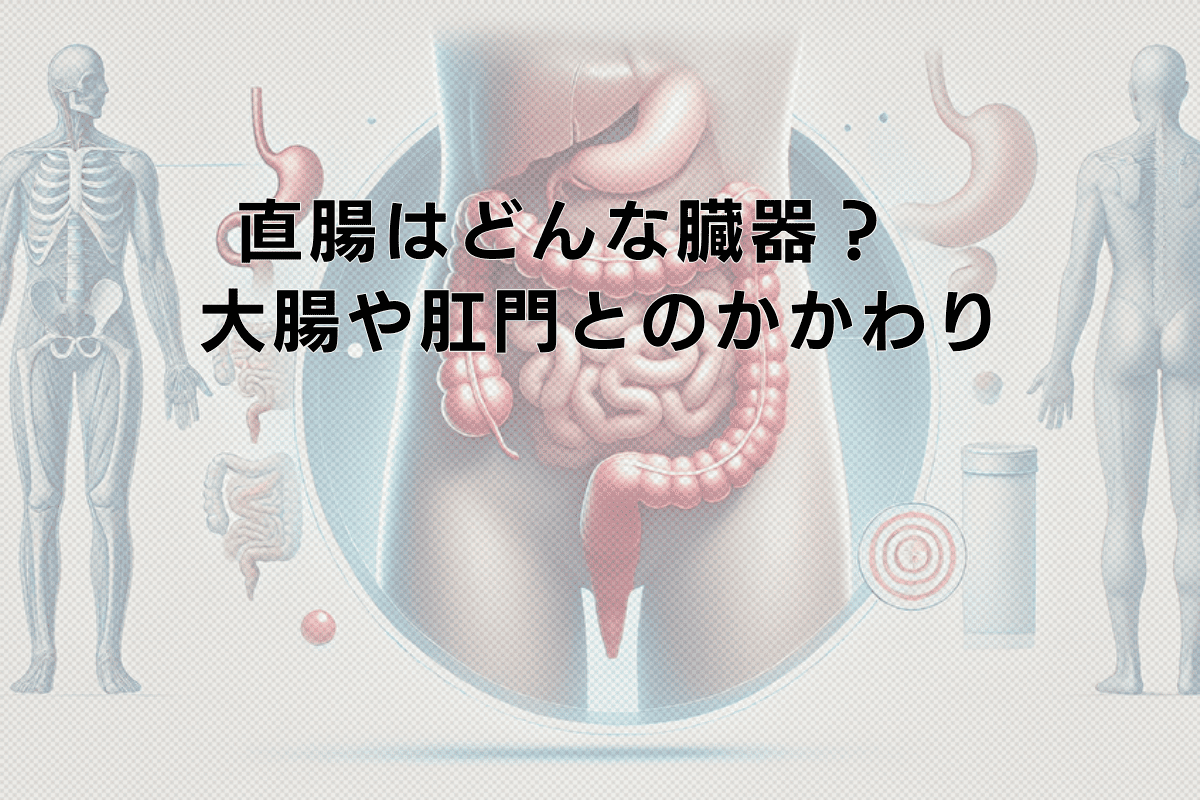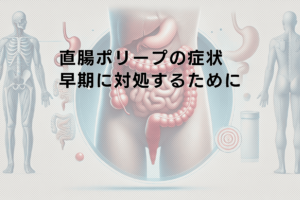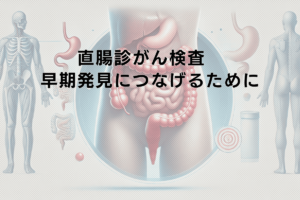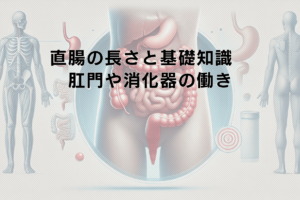直腸は大腸の終末部位として知られ、肛門へとつながる重要な管状の臓器です。
消化の流れを考えるうえで見落とされがちですが、直腸に生じる病気として代表的な直腸がんや排便障害などは、放置すると重篤化する可能性があります。
また、直腸にかかわるがんが大腸がんの中でも発生頻度が高く、手術や治療方針によっては肛門を温存できるかどうかが変わるため、日常生活の質に大きく影響を及ぼすことも珍しくありません。
直腸と大腸の構造を知る
直腸や肛門がどのように機能し、日々の排便を支えているのかを理解することは、病気の予防や早期発見に役立ちます。
直腸は大腸がんの部位の中でも比較的発症例が多く、便意や排便トラブルを自覚した際に、早めの受診を考えるきっかけになるでしょう。
大腸の全体像
大腸は結腸と直腸から成り、結腸はさらに上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸に分かれ、結腸を通過してきた食物残渣は、水分が再吸収されて硬い便へと変化し、最終的に直腸に蓄積されます。
便が一定量に達すると便意が起こり、適切なタイミングで排便が行われる仕組みです。
大腸の主な区分
| 区分 | 主な役割 | 位置(体の部位) |
|---|---|---|
| 盲腸 | 小腸と大腸の接続部分 | 腹部の右下に位置 |
| 上行結腸 | 水分吸収の促進 | 右腹部を上下に走行 |
| 横行結腸 | 水分・電解質の吸収に加え、便の輸送 | 右腹部から左腹部へ横断 |
| 下行結腸 | 便のさらなる形成 | 左腹部を上下に走行 |
| S状結腸 | 便を溜め、直腸へ送り出す前の曲線状部分 | 骨盤付近(左下腹部) |
| 直腸 | 便を蓄える最終区間 | 骨盤の奥から肛門へ続く |
直腸と肛門の構造
直腸は肛門につながる最終段階の管であり、肛門括約筋という筋肉が尿や便をコントロールする働きを担います。
肛門括約筋は内括約筋と外括約筋に分かれ、内括約筋が自律神経の支配で無意識に弛緩・収縮を行い、外括約筋が意識的に排便をコントロールできる部分です。
排便時には直腸の神経が便意を感じ取り、必要に応じて外括約筋が弛緩して便を排出します。
消化器系の流れ
口から摂取した食物は、胃や小腸で栄養を吸収され、大腸で水分や電解質が吸収されます。
最後に直腸に便が移動し、適切なタイミングで肛門から排出されるというシンプルな流れですが、ここに腫瘍や炎症が発生すると、便意の異常や痛み、出血などが起こりやすくなります。
特に直腸付近では血便や排便回数の増加などが起こりやすいので、早期発見につながりやすい反面、放置してしまうと進行が早まるリスクもあるため注意が必要です。
直腸に多い病気と症状
直腸はがんをはじめ、肛門近くで発生する痔やポリープなど、多くの病気が発生しやすい部位でもあります。
大腸がんの一部である直腸がんは、肛門との距離が近いため、排便機能や肛門温存の可否に直結し、治療や手術を受けるうえで大きな判断を必要とするケースが少なくありません。
直腸がん
直腸がんは、大腸がんのなかでもS状結腸に近い上部直腸から肛門側に近い下部直腸まで、さまざまな部位に発生し、排便時に血便や便の形状異常(細くなる、断続的になる)に気づいたら早めの検査が大切です。
初期には自覚症状が少ない場合もあるため、定期的な大腸がん検診を受けることが有効な手段となります。
直腸がんの主な症状
- 血便(鮮血や暗赤色の出血)
- 便が細くなる、便量が減少する
- 便が出きらない感じ(残便感)
- 排便回数が増える、あるいは下痢や便秘が続く
- 肛門付近の不快感、痛み
痔(じ)
痔は大腸ではなく肛門に近い部分で起こる病気ですが、直腸側からの血行不良や圧力が影響します。痔核や裂肛、痔ろうなどの総称であり、いずれも排便時に痛みや出血が起こりやすいのが特徴です。
軽度の痔なら生活習慣の改善で治癒する場合もありますが、重度になると手術が必要なケースもあるため、痛みや出血が続く場合は早めに医療機関を受診してください。
ポリープ
大腸や直腸の壁から隆起した形で発生する腫瘍性または非腫瘍性のものをポリープと呼びます。良性のポリープであっても、放置すると将来的に悪性化(がん化)する可能性があり、小さいうちに内視鏡で切除しておくことが大切です。
とくに家族性ポリポーシスや過去に大腸がんを患った方は、定期的な内視鏡検査が推奨されます。
直腸瘤
直腸壁が肛門方向に突出し、排便障害を引き起こす状態です。特に女性に多く、出産などで骨盤底筋が緩むことによって発症しやすいです。
便が直腸瘤にたまって出にくくなるため、残便感や頻繁なトイレ通いが起こり、QOLが低下するケースもあります。
直腸に多い病気の概要
| 病気名 | 主な症状・特徴 | 治療法 |
|---|---|---|
| 直腸がん | 血便、便の細さ、頻尿など | 内視鏡手術、外科手術、放射線治療、化学療法 |
| 痔 | 排便時の出血や痛み、肛門付近の腫れ | 薬物療法、生活習慣改善、重症例は手術 |
| ポリープ | 無症状が多いが、放置でがん化リスクあり | 内視鏡での切除 |
| 直腸瘤 | 排便障害、残便感 | 生活習慣指導、骨盤底筋トレーニング、手術 |
直腸がんの検査と治療方法
大腸がん全体の中で直腸がんの占める割合は少なくなく、その治療の要としては手術が挙げられます。便意や排便に直結する部位であるため、肛門をどの程度温存できるか、術後の排便機能をどう保つかが重要なテーマです。
検査の流れ
直腸がんの検査は、まず便潜血検査や直腸指診、肛門鏡検査などで異常を把握し、内視鏡検査(大腸カメラ)で病変の有無を確認します。
内視鏡でポリープや腫瘍が見つかった場合は、一部を採取して病理検査を行い、がんかどうかを判定し、さらなる精密検査としてCT、MRI、PETなどを使い、腫瘍の進行度や転移の有無を調べることがあります。
直腸がん検査の主な項目
| 検査名 | 内容・目的 |
|---|---|
| 便潜血検査 | 便に血が混じっていないかのスクリーニング |
| 直腸指診 | 医師が指を挿入し、しこりや腫瘍を触診する |
| 内視鏡検査 | カメラで大腸内を観察し、病変の位置や大きさを確認 |
| CT/MRI | 転移や局所浸潤の有無を視覚的に評価 |
| PET検査 | がん細胞の代謝活性を捉え、全身転移を確認 |
手術の種類
直腸がんの手術では、患部の位置や大きさ、肛門との距離によって切除範囲が異なり、肛門から近いほど肛門括約筋を温存するのが難しくなり、人工肛門(ストーマ)が必要です。
一方で、直腸がんの早期発見や技術の進歩によって、肛門を残したまま切除できる肛門温存手術が増えています。
代表的な直腸がん手術
- 低位前方切除術:肛門との距離が十分にある場合、肛門括約筋を温存
- 超低位前方切除術:肛門に近いが一定の距離があれば、ギリギリまで腫瘍を切除し肛門を残す
- Miles手術(腹会陰式直腸切断術):腫瘍が肛門付近にまで進行し、括約筋温存が困難な場合、直腸と肛門を切除してストーマを造設
放射線治療・化学療法
直腸がんでは、手術前後に放射線治療や化学療法を併用することがあり、肛門に近い下部直腸がんは、腫瘍を小さくしてから手術することで肛門温存を可能にするために、放射線と抗がん剤を組み合わせる治療が行われる場合があります。
再発や転移への対処
直腸がんが進行している場合、肝臓や肺などに転移が認められることがあり、転移が少数であれば手術で取り除く、あるいは化学療法で抑えることが検討されます。
再発リスクがあるため、手術後も定期的な通院と検査を続ける必要があり、症状や腫瘍マーカーの変化を見逃さないことが大切です。
肛門温存と排便機能への配慮
直腸がんの治療で課題となるのが、肛門をどれだけ残せるかという点です。
排便機能は日常生活の質(QOL)に直結するため、肛門温存が可能な場合は大きなメリットであるものの、腫瘍が肛門付近にある場合は、がんの切除範囲が広くなり、肛門を残せない事態も考えられます。
肛門温存手術の意義
肛門を残すと聞くと、一見治療が不十分になるのではと不安を感じるかもしれませんが、根治性と機能温存のバランスをとることは医療者が常に考慮しています。
放射線や化学療法と組み合わせることで腫瘍を小さくし、手術範囲を最小限に抑える方針がとられることもあり、切除範囲を小さくして肛門括約筋を温存することが目標です。
肛門温存を検討する主な要素
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 腫瘍の位置 | 肛門から何cm上部にあるか |
| 腫瘍の大きさ | 括約筋や周辺組織への浸潤度 |
| 放射線・抗がん剤の効果 | 前処置で腫瘍をどこまで縮小できるか |
| 患者の希望 | 生活の質と治療効果のバランスをどう考えるか |
ストーマ(人工肛門)の必要性
肛門付近に広範に病変が及んでいる場合や、切除範囲が大きい場合には、やむを得ず肛門を切除し、ストーマを造設する手術が選択されます。
ストーマを持つこと自体は生活への制限を感じるかもしれませんが、適切なストーマケアや慣れによって通常の社会生活を営むことは可能です。
排便機能の維持とリハビリ
肛門温存手術を受けた後には、排便コントロールが難しくなり、直腸の貯留機能が弱まったり、括約筋の強度が低下したりするため、一時的に頻繁な便意や便漏れが起こるケースがあります。
これに対しては、排便習慣の改善や骨盤底筋トレーニングなどが行われ、時間とともに改善することが期待できます。
術後のQOL向上
直腸がん手術後の排便コントロールが安定してくれば、再び日常生活を充実させられ、腸内環境の改善を意識した栄養管理や、適度な運動で骨盤底筋群を強化するアプローチが重要です。
病院選びとサポート体制
直腸がんを含む大腸がんの治療や手術では、専門的な施設や医師の経験が大きく影響し、肛門温存を目指す高度な手術を得意とする病院がある一方、手術後のリハビリやサポートに注力している施設もあります。
病院を選ぶ視点
- 手術実績と専門医の数
- 放射線治療や化学療法の設備・実績
- 消化器外科の認定医が在籍しているか
- 術後リハビリやストーマケアの支援体制が整っているか
- 患者さんが納得のいくインフォームド・コンセントが行われているか
セカンドオピニオンの活用
重い病気ほど、治療方法や手術方針が複数存在する場合があるので、専門医からの説明だけで決定せず、別の医療機関でセカンドオピニオンを求めることも有効です。
特に肛門温存可否のボーダーラインにある患者さんにとっては、リスクとメリットを多角的に検討する大きな助けになるでしょう。
家族や職場への対応
大腸がんや直腸がんで手術を受けると、入院期間や術後の通院が必要になり、家族や職場からのサポートが欠かせません。
特にストーマ造設後はケアの方法を家族と共有したり、職場での就労環境を調整したりといった協力が必要となります。退院前に医療スタッフから指導や相談が受けられることが多いので、遠慮なく質問すると安心です。
直腸がんの予防と検診の意義
直腸がんを含む大腸がんの発生リスクを下げるには、定期的な検診と生活習慣の見直しが重要です。早期に発見できれば、体への負担が少ない治療で済む可能性が高まります。
生活習慣の改善
大腸がんのリスクを高める要因として、脂質や動物性タンパク質に偏った食事、食物繊維不足、過度の飲酒、喫煙、運動不足などが挙げられます。
これらを意識的にコントロールすることは、腸だけでなく全身の健康増進につながります。
大腸がんリスク低減のための食習慣
- 野菜や果物、海藻類を積極的に摂取
- 赤肉や加工肉の過剰摂取を控える
- 適度な水分補給で便通をスムーズに
- 腸内環境を整える発酵食品(納豆、ヨーグルト等)を取り入れる
大腸がん検診
便潜血検査や内視鏡検査が大腸がんの検診方法として一般的で、便に目立った血が混じっていなくても、潜在的に出血している可能性があるため、年に1回程度の便潜血検査は負担が少なく導入しやすいです。
異常が見つかれば内視鏡検査を受け、必要ならばポリープ切除などを行う流れとなります。
早期発見のメリット
大腸がんは早期であれば内視鏡手術や部分的な切除で済む場合が多く、生存率も高くなり、直腸がんでは肛門温存の可能性が格段に高まり、術後の生活の質を維持しやすくなります。
逆に進行してからの発見では、手術が大掛かりになりやすく、合併症のリスクや再発の可能性も高まるため、検診の意義は大きいです。
まとめ
直腸は大腸の終末部位でありながら、肛門と密接に関係し、排便機能や生活の質に大きな影響を与える重要な臓器です。
直腸がんは大腸がんの一部として多くの方に起こり得る病気であり、特に肛門温存の可否が日常生活に直結するため、治療を検討するうえで慎重な判断が必要になります。
検査や手術方法は多岐にわたり、放射線治療や化学療法と組み合わせることで肛門温存の可能性を高める戦略もあります。
また、予防の観点から見ると、定期的な検診や生活習慣の改善が大腸がんリスクを下げるだけでなく、全身的な健康増進にも寄与します。
参考文献
Hashiguchi Y, Muro K, Saito Y, Ito Y, Ajioka Y, Hamaguchi T, Hasegawa K, Hotta K, Ishida H, Ishiguro M, Ishihara S. Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum (JSCCR) guidelines 2019 for the treatment of colorectal cancer. International journal of clinical oncology. 2020 Jan;25:1-42.
Saito N, Moriya Y, Shirouzu K, Maeda K, Mochizuki H, Koda K, Hirai T, Sugito M, Ito M, Kobayashi A. Intersphincteric resection in patients with very low rectal cancer: a review of the Japanese experience. Diseases of the colon & rectum. 2006 Oct 1;49(1):S13-22.
Yano H, Moran BJ. The incidence of lateral pelvic side-wall nodal involvement in low rectal cancer may be similar in Japan and the West. Journal of British Surgery. 2008 Jan;95(1):33-49.
Heald RJ, Moran BJ. Embryology and anatomy of the rectum. InSeminars in surgical oncology 1998 Sep (Vol. 15, No. 2, pp. 66-71). New York: John Wiley & Sons, Inc..
Zaheer S, Pemberton JH, Farouk R, Dozois RR, Wolff BG, Ilstrup D. Surgical treatment of adenocarcinoma of the rectum. Annals of surgery. 1998 Jun 1;227(6):800-11.
Dyson T, Draganov PV. Squamous cell cancer of the rectum. World journal of gastroenterology: WJG. 2009 Sep 9;15(35):4380.
Volante M, Grillo F, Massa F, Maletta F, Mastracci L, Campora M, Ferro J, Vanoli A, Papotti M. Neuroendocrine neoplasms of the appendix, colon and rectum. Pathologica. 2021 Feb;113(1):19.
Tomita N, Ishida H, Tanakaya K, Yamaguchi T, Kumamoto K, Tanaka T, Hinoi T, Miyakura Y, Hasegawa H, Takayama T, Ishikawa H. Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum (JSCCR) guidelines 2020 for the clinical practice of hereditary colorectal cancer. International Journal of Clinical Oncology. 2021 Aug;26(8):1353-419.
Nougaret S, Gormly K, Lambregts DM, Reinhold C, Goh V, Korngold E, Denost Q, Brown G. MRI of the Rectum: A Decade into DISTANCE, Moving to DISTANCED. Radiology. 2025 Jan 7;314(1):e232838.
Salimoglu S, Kilinc G, Calik B. Anatomy of the Colon, Rectum, and Anus. Colon Polyps and Colorectal Cancer. 2021:1-22.