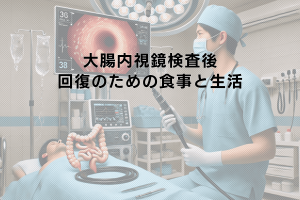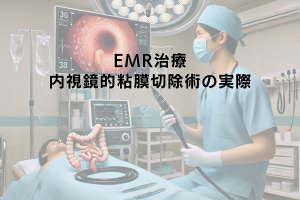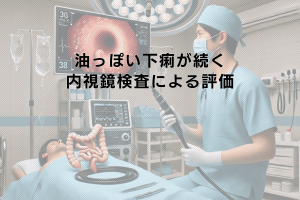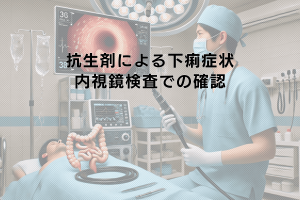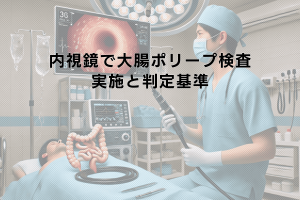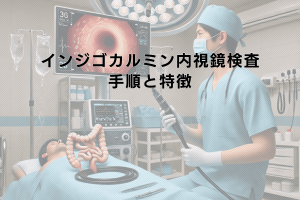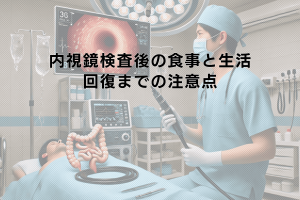突然の嘔吐と下痢の症状は、非常につらく、日常生活にも大きな支障をきたします。多くの場合、原因はウイルスや細菌による急性胃腸炎ですが、中には注意が必要な病気が隠れていることもあります。
特に、自己判断での薬の使用は、かえって症状を長引かせたり、悪化させたりする危険も伴うので注意が必要です。
この記事では、嘔吐と下痢が同時に起こる原因から、ご家庭でできる初期対応、市販薬との付き合い方、そして医療機関を受診すべきタイミングについて詳しく解説します。
嘔吐と下痢が同時に起こる主な原因
嘔吐と下痢は、体が有害なものを排出しようとする防御反応です。症状が同時に現れる場合、消化管、特に胃や腸に何らかの急性の炎症が起きていることを示唆します。原因は多岐にわたりますが、多くは感染によるものです。
ウイルス性胃腸炎
冬場に流行することが多いウイルス性の胃腸炎は、嘔吐や下痢を引き起こす最も一般的な原因の一つです。ノロウイルスやロタウイルス、アデノウイルスなどが代表的で、非常に感染力が強いのが特徴です。
汚染された食物や水、あるいは感染者の吐物や便を介して人から人へと感染が広がり、症状は突然の吐き気や嘔吐から始まり、続いて水のような下痢、腹痛、発熱などを伴うことが多くあります。
ウイルス性胃腸炎と細菌性胃腸炎の比較
| 項目 | ウイルス性胃腸炎 | 細菌性胃腸炎 |
|---|---|---|
| 主な原因 | ノロウイルス、ロタウイルス | カンピロバクター、サルモネラ |
| 流行時期 | 冬期に多い | 夏期に多い |
| 主な症状 | 嘔吐、水様性下痢、発熱 | 腹痛、血便、高熱 |
細菌性胃腸炎
細菌による胃腸炎は夏場に多く見られ、カンピロバクターやサルモネラ菌、病原性大腸菌(O-157など)が主な原因菌です。加熱が不十分な肉類(特に鶏肉)や卵、あるいは汚染された水や食品を摂取することで感染します。
ウイルス性と比較して、腹痛がより強く、粘液や血液が混じった便(粘血便)が出ることが特徴で、高熱を伴うことも少なくありません。
食中毒
食中毒は、ウイルスや細菌だけでなく、それらが産生する毒素によっても起きます。例えば、黄色ブドウ球菌は食品中で増殖する際に毒素を作り出し、この毒素を摂取すると数時間以内に激しい嘔吐を引き起こします。
原因となる食品を食べてから症状が出るまでの時間が短く、原因によって症状は様々ですが、嘔吐と下痢が主な症状となるケースが多いです。
食中毒の主な原因
- 細菌(サルモネラ、カンピロバクターなど)
- ウイルス(ノロウイルスなど)
- 細菌が産生する毒素(黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌など)
- 自然毒(キノコ、フグなど)
その他の原因
感染症以外にも、暴飲暴食、ストレス、薬の副作用、あるいは特定の病気が原因で嘔吐や下痢が起こることもあります。
過敏性腸症候群(IBS)では、ストレスをきっかけに下痢や便秘を繰り返し、炎症性腸疾患(クローン病や潰瘍性大腸炎)では、長期にわたる下痢や血便が見られ、急性胃腸炎とは異なるアプローチでの対応が必要です。
まず考えるべき家庭での対処法
突然の嘔吐や下痢に見舞われた際、医療機関を受診する前に家庭でできることはいくつかあり、症状が比較的軽い初期段階では、適切なセルフケアが回復を助けます。
ただし、症状が重い場合や悪化する場合には、ためらわずに医療機関を受診することが大切です。
水分補給の重要性と正しい方法
嘔吐と下痢によって、体は水分と電解質(ナトリウムやカリウムなど)を大量に失い、脱水症状が起きると、倦怠感や頭痛、めまいなどが現れ、重症化すると意識障害に至ることもあります。
最も重要な対処は、失われた水分と電解質を補給することです。ただし、一度に大量の水を飲むと、胃が刺激されて再び嘔吐を誘発する可能性があるので、少量ずつ、頻繁に水分を摂りましょう。
経口補水液は、水分と電解質を効率よく吸収できるように調整されており、このような状況での水分補給に適しています。
自宅でできる経口補水液の作り方(緊急時)
| 材料 | 分量 | 役割 |
|---|---|---|
| 湯冷まし | 1リットル | 水分の補給 |
| 砂糖 | 40g(大さじ4.5杯) | 水分とナトリウムの吸収促進 |
| 食塩 | 3g(小さじ0.5杯) | 電解質の補給 |
※レモン汁などを加えると飲みやすくなります。これはあくまで緊急用であり、市販の経口補水液の利用を推奨します。
食事の工夫と避けるべき食べ物
症状があるときは、胃腸に負担をかけない食事が基本です。嘔吐が続いている間は無理に食べる必要はなく、水分補給を優先しましょう。吐き気が少し落ち着いてきたら、消化の良いものから少量ずつ試していきます。
おかゆやうどん、すりおろしたリンゴ、バナナなどが適しています。回復に合わせて徐々に普段の食事に戻していきますが、完全に症状がなくなるまでは、胃腸に負担のかかる食事は避けてください。
脂っこいもの、香辛料などの刺激物、食物繊維の多い野菜、冷たい飲み物は、下痢を悪化させる可能性があるため注意が必要です。
症状があるときに適した食事と避けるべき食事
| 分類 | 適したもの | 避けるべきもの |
|---|---|---|
| 主食 | おかゆ、よく煮込んだうどん | 玄米、パン、ラーメン |
| タンパク質 | 豆腐、白身魚、鶏のささみ | 脂身の多い肉、揚げ物 |
| その他 | バナナ、リンゴ、野菜スープ | 柑橘類、キノコ類、海藻類、乳製品 |
安静の必要性
嘔吐や下痢の症状があるときは体力を消耗していて、無理に動くと回復が遅れるだけでなく、脱水症状を助長することにもなりかねません。学業や仕事のことは一旦忘れ、体を横にしてゆっくりと休むことが重要です。
腹部を温めると、腹痛が和らぐことがあります。休息を十分にとり、体の回復力に任せることも大切な治療の一つです。
市販薬を使用する際の注意点
ドラッグストアでは、下痢や吐き気に対する様々な薬が販売されており、手軽に入手できますが、嘔吐や下痢の症状に対して自己判断で薬を使用することには、いくつかのリスクが伴います。
症状の原因によっては、薬の使用が逆効果になることもあるため、正しい知識を持つことが大切です。
自己判断で薬を選ぶリスク
嘔吐や下痢は、体が病原体や毒素を体外に排出しようとする重要な防御反応です。安易に薬でこの働きを止めてしまうと、原因物質が体内に留まり、かえって回復を遅らせてしまう可能性があります。
細菌性胃腸炎が疑われる場合に強力な下痢止め薬を使用すると、菌が腸管内に滞留し、症状が悪化したり、重篤な合併症を引き起こしたりする危険があります。
どの薬を選ぶべきか、そもそも薬を使うべき状況なのかを自己判断するのは非常に難しいことです。
下痢止め薬が症状を悪化させる場合
市販の下痢止め薬には、腸の動きを抑制するタイプ(ロペラミド塩酸塩など)と、腸内の水分を吸収して便を固めるタイプ、腸粘膜を保護するタイプなどがあります。
特に腸の動きを止める薬は、細菌性胃腸炎やO-157などの出血性大腸炎の際には使用してはいけません。病原菌の排出を妨げ、菌が産生する毒素が体内に吸収されやすくなるためです。
血便や高熱を伴う下痢の場合は、自己判断での下痢止め薬の使用は絶対に避け、速やかに医療機関を受診してください。
市販の下痢止め薬の種類と注意点
| 薬の種類 | 主な作用 | 注意が必要なケース |
|---|---|---|
| 腸運動抑制薬 | 腸のぜん動運動を抑える | 細菌性・ウイルス性胃腸炎(血便、発熱時) |
| 収れん薬・吸着薬 | 腸粘膜保護、有害物質の吸着 | 他の薬との併用時に効果を弱める可能性 |
| 生菌製剤(整腸剤) | 腸内環境を整える | 即効性は期待できない |
吐き気止め薬の選び方と限界
市販の吐き気止め薬は、乗り物酔いや二日酔いを対象としたものが多く、感染性胃腸炎による激しい嘔吐に対しては効果が限定的で、嘔吐が激しいと、経口で薬を服用すること自体が困難です。
また、薬を飲んでもすぐに吐いてしまうため、十分な効果が期待できません。嘔吐が頻回に続く場合は、脱水のリスクが非常に高いため、市販薬で様子を見るのではなく、医療機関で点滴や注射による治療を受けることを検討しましょう。
特に、お子様や高齢者では脱水が急速に進行するため、早期の受診が重要です。
医療機関を受診すべき危険なサイン
ほとんどの急性胃腸炎は数日で自然に回復しますが、中には迅速な医療介入が必要な危険な状態もあります。どのような場合に医療機関へ行くべきか、目安を知っておくことは非常に重要です。
脱水症状の具体的な兆候
水分補給が追いつかずに脱水が進むと、体に様々なサインが現れ、体が危険な状態に陥っていることを示す警告です。特に、お子様や高齢者は脱水になりやすいため、周囲の人が注意深く観察することが大事です。
以下の表にあるような症状が複数見られる場合は、緊急性が高いと考え、夜間や休日であっても医療機関に相談してください。
脱水症状のセルフチェックリスト
| チェック項目 | 具体的な状態 |
|---|---|
| 尿の回数・量 | 半日以上尿が出ていない、色が濃い |
| 口・舌の状態 | 口の中や舌が乾いている、唾液が少ない |
| 皮膚の状態 | 皮膚の弾力がない(手の甲の皮膚をつまんで離しても、すぐ戻らない) |
| 全身の状態 | ぐったりしている、めまいや立ちくらみがする |
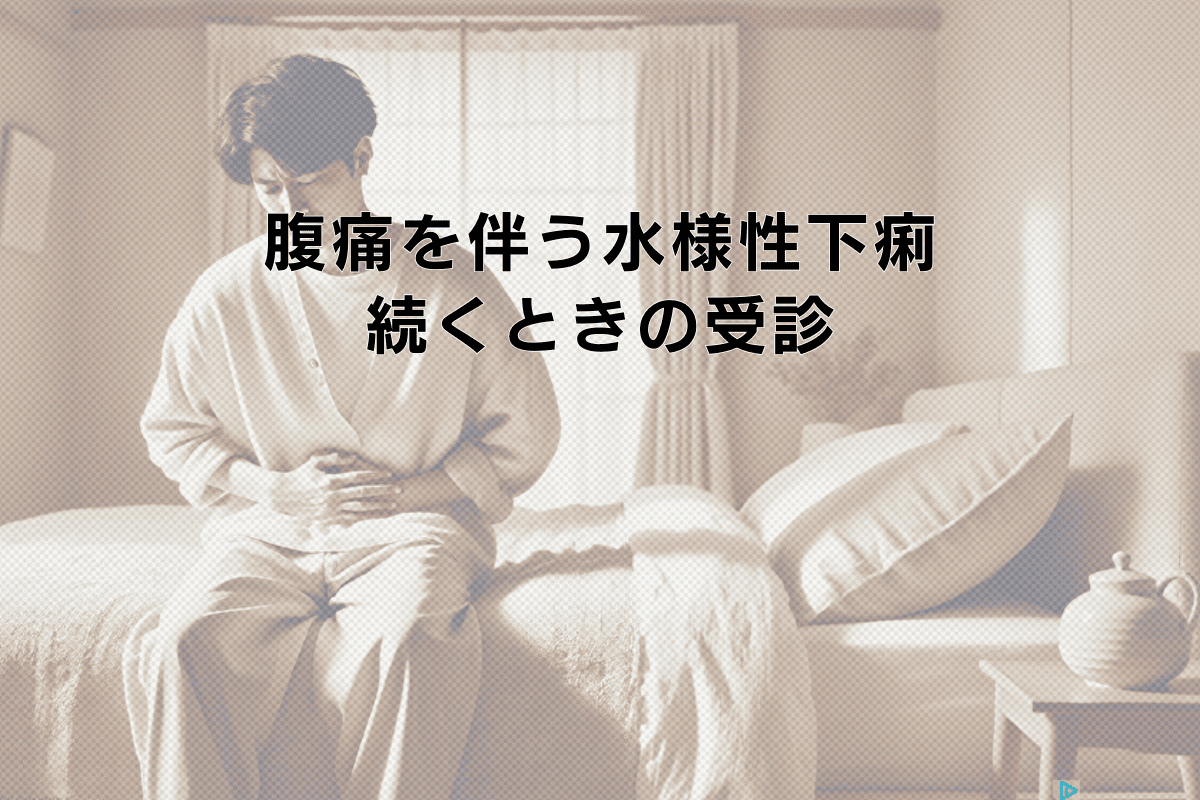
激しい腹痛や血便が見られる場合
我慢できないほどの激しい腹痛が続く場合や、便に血が混じる(鮮血、赤黒い便、黒いタール状の便など)場合は、単なる胃腸炎ではない可能性があります。
腸重積、虚血性腸炎、大腸憩室炎、炎症性腸疾患、あるいは大腸がんなどの重篤な病気のサインかもしれません。腹痛が特定の場所に限定され、持続する場合は注意が必要です。
このような症状は、緊急の処置や検査を必要とすることがあるため、自己判断で様子を見るのは危険です。
高熱が続く、または意識がもうろうとする時
38.5度以上の高熱が続く、あるいは呼びかけに対する反応が鈍い、意識がはっきりしない症状は、体が重度の感染症や脱水に陥っているサインです。細菌が血流に入る菌血症や敗血症といった危険な状態に進行している可能性も考えられます。
命に関わることもあるため、一刻も早く医療機関を受診し、適切な治療を開始することが必要です。救急車の要請もためらわないでください。
医療機関を受診すべき危険なサインのまとめ
- 水分が全く摂れず、嘔吐を繰り返す
- 半日以上、尿が出ていない
- 便に血液が混じっている
- 我慢できないほどの強い腹痛がある
- 高い熱が続いている
- ぐったりして意識がはっきりしない
症状が改善しない、または悪化する場合
家庭での対処法を試しても2〜3日経っても症状が全く改善しない、あるいは日に日に悪化していく場合も、医療機関で受診することが大切です。
長引く症状の背後には、治療が必要な特定の病原菌(例えば、抗生物質が必要な細菌)や、感染症以外の原因が隠れている可能性があります。
医師が行う診察と初期治療
医療機関を受診すると、医師はまず患者さんの状態を正確に把握するための診察を行います。症状の原因を探り、重症度を判断した上で、一人ひとりに合った治療方針を決定します。
問診で確認する内容
診察は詳しい問診から始まり、医師は、診断の手がかりを得るために、様々な質問をします。
いつから症状が始まったか、嘔吐や下痢の回数や性状、腹痛の場所や強さ、発熱の有無、食事内容、周囲での同様の症状の人の有無など、できるだけ具体的に伝えることが重要です。
服用中の薬やアレルギー、過去の病気についても忘れずに伝えましょう。
問診でよく尋ねられること
- 症状はいつから始まったか
- 嘔吐や下痢の回数、便の状態(水様便、泥状便、血便など)
- 最後に食事や水分を摂ったのはいつか
- 海外渡航歴や特殊な食品の摂取歴
- 家族や職場など、周囲に同様の症状の人はいるか
身体診察と基本的な検査
問診に続いて身体診察を行い、医師は聴診器で腸の音を聞いたり、お腹を触って痛みの場所や程度を確認したりします。脱水の兆候がないか、皮膚や粘膜の状態も注意深く観察し、必要に応じて、血液検査や便検査を行うこともあります。
血液検査では、炎症の程度や脱水の状態、電解質のバランスなどを評価し、便検査は、原因となるウイルスや細菌を特定するための大切な検査です。
症状を和らげるための薬物療法
診察の結果に基づき、症状を緩和するための薬が処方されますが、原因によっては薬を使わない方が良い場合もあり、医師は必要性を慎重に判断します。
処方される薬には、吐き気を抑える制吐剤、腸内環境を整える整腸剤、腹痛を和らげる鎮痙剤などがあり、また、細菌性胃腸炎が強く疑われ症状が重い場合には、抗生物質が処方されることもあります。
医療機関で処方される主な薬
| 薬の種類 | 目的 | 備考 |
|---|---|---|
| 制吐剤 | 吐き気や嘔吐を抑える | 内服薬のほか、坐薬や注射もある |
| 整腸剤 | 乱れた腸内細菌のバランスを整える | 下痢の回復を助ける |
| 抗生物質 | 原因となる細菌を殺菌する | 細菌性胃腸炎が疑われる場合に限る |
点滴による水分・栄養補給
嘔吐が激しくて水分を口から摂れない場合や、脱水症状が進行している場合には、点滴(静脈内輸液)による治療が行われます。点滴は、水分と電解質、ビタミンなどを直接血管内に投与するため、速やかに脱水状態を改善することができます。
口から水分を摂るのが難しい患者さんにとって、点滴は非常に有効な治療手段です。体力が著しく低下している場合には、栄養補給を目的とした点滴を行うこともあります。
内視鏡検査が必要になるケースと時期
嘔吐や下痢といった急性の症状が治まった後も、何らかの異常が疑われる場合や、症状が長引く場合には、原因を詳しく調べるために内視鏡検査(胃カメラや大腸カメラ)が検討されることがあります。
ここでは、どのような場合に内視鏡検査が必要となり、どのタイミングで実施するのが適切なのかを解説します。
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)を検討する状況
上部消化管内視鏡検査、いわゆる胃カメラは、食道、胃、十二指腸を直接観察する検査です。
急性の嘔吐や腹痛が治まった後も、みぞおちの痛みが続く、黒い便(タール便)が出た、貧血が指摘された、といった場合には、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃がんなどの病気が隠れている可能性があります。
また、強い吐き気が続く場合にも、胃の運動機能の異常などを評価するために検査を行うことがあります。
下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)を検討する状況
下部消化管内視鏡検査、いわゆる大腸カメラは、大腸全体と小腸の一部を観察する検査です。急性胃腸炎の症状、特に血便がみられた場合には、原因を特定するために重要です。
感染性腸炎の治癒後の状態を確認するほか、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)、大腸憩室出血、虚血性腸炎、そして大腸がんやポリープといった病気の発見に繋がります。
下痢が長期間続く、便に血が混じる状態が改善しない、腹痛が続くなどの症状があれば、大腸カメラを検討すべきサインです。
内視鏡検査で発見される可能性のある疾患例
| 検査 | 考えられる主な疾患 |
|---|---|
| 胃カメラ | 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、胃がん |
| 大腸カメラ | 大腸がん、大腸ポリープ、潰瘍性大腸炎、クローン病 |
急性期を過ぎてから検査を行う理由
嘔吐や下痢が激しい急性期には、内視鏡検査は通常行いません。患者さんの体力が消耗しており、検査による負担が大きいためです。
また、腸管の炎症が強い時期に検査を行うと、かえって状態を悪化させたり、穿孔(腸に穴が開くこと)のリスクを高めたりする可能性があります。
まずは点滴や薬物療法で症状を落ち着かせ、全身状態が改善してから、改めて検査の計画を立てるのが一般的です。症状が落ち着いてから原因を精査することが、安全かつ正確な診断につながります。
検査で判明する可能性のある疾患
内視鏡検査は粘膜を直接観察できるため、非常に多くの情報を得られ、胃カメラでは、ピロリ菌感染の有無や萎縮性胃炎の程度なども評価でき、将来の胃がんリスクを知る手がかりになります。
大腸カメラでは、がん化する可能性のあるポリープを発見し、その場で切除することも可能です。急性の症状をきっかけに内視鏡検査を受けることで、自覚症状のなかった別の病気が早期に発見されるケースも少なくありません。

よくある質問
嘔吐や下痢の症状に関して、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 症状が落ち着いたら、すぐに普段の食事に戻して良いですか
-
すぐに普段通りの食事に戻すのは避けるべきです。症状が治まっても、胃腸の粘膜はまだダメージを受けており、消化機能も低下しています。
ここで急に脂っこいものや刺激の強いものを食べると、再び症状がぶり返すことがあります。まずは、おかゆやうどん、白身魚、豆腐など、消化の良いものから少量ずつ再開してください。
数日かけて、ゆっくりと食事の量と種類を増やしていくことが、胃腸をいたわり、スムーズな回復につながるポイントです。
- 家族にうつさないために気をつけることは何ですか
-
感染性胃腸炎、特にウイルス性のものは非常に感染力が強く、家族内での感染を防ぐためには、厳重な対策が必要です。最も重要なのは、手洗いの徹底です。
調理の前、食事の前、トイレの後、患者さんのケアをした後は、石鹸と流水で丁寧に手を洗いましょう。
患者さんの吐物や便を処理する際は、使い捨ての手袋とマスクを着用し、次亜塩素酸ナトリウム(家庭用塩素系漂白剤を薄めたもの)で汚染された場所を消毒します。患者さんとのタオルの共用も避けるべきです。
- 薬を飲んでも嘔吐してしまう場合はどうすれば良いですか
-
内服薬を飲んでもすぐに吐いてしまう場合、薬の成分が吸収されず、効果が期待できません。このような状況で無理に薬を飲み続けるのは困難です。
水分すら受け付けないほどの激しい嘔吐が続く場合は、脱水のリスクが非常に高まっています。市販薬での対応には限界があるため、速やかに医療機関を受診してください。
- 内視鏡検査はつらい検査なのでしょうか
-
過去の経験から、内視鏡検査に対して「つらい」「苦しい」というイメージをお持ちの方も少なくないかもしれません。
しかし、近年の内視鏡検査は、機器の進歩や技術の向上により、以前よりもずっと楽に受けられるようになっています。
多くの医療機関では、患者さんの苦痛を和らげるために、鎮静剤(眠くなる薬)を使用して、うとうとと眠っているような状態で検査を行います。
検査に対する不安や恐怖心が強い場合は、事前に医師に相談し、鎮静剤の使用について確認してみることをお勧めします。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸の状態で変化する下痢の症状と内視鏡検査のタイミング】
嘔吐と下痢の基本を押さえたら、内視鏡が必要になるケースと自宅で様子を見られる目安も確認しておくと安心です。受診判断に迷いやすい方に特に参考になります。
【内視鏡スコープの消毒・洗浄方法と衛生管理の重要性】
検査が必要となった場合に備え、衛生管理と安全性も知っておくと不安が減ります。洗浄・消毒の流れを具体的に理解できます。
参考文献
Kawamura T, Wada H, Sakiyama N, Ueda Y, Shirakawa A, Okada Y, Sanada K, Nakase K, Mandai K, Suzuki A, Kamaguchi M. Examination time as a quality indicator of screening upper gastrointestinal endoscopy for asymptomatic examinees. Digestive Endoscopy. 2017 Jul;29(5):569-75.
Niikura R, Nagata N, Yamada A, Honda T, Hasatani K, Ishii N, Shiratori Y, Doyama H, Nishida T, Sumiyoshi T, Fujita T. Efficacy and safety of early vs elective colonoscopy for acute lower gastrointestinal bleeding. Gastroenterology. 2020 Jan 1;158(1):168-75.
Manabe N, Haruma K, Kamada T, Kusunoki H, Inoue K, Murao T, Imamura H, Matsumoto H, Tarumi KI, Shiotani A, Hata J. Changes of upper gastrointestinal symptoms and endoscopic findings in Japan over 25 years. Internal Medicine. 2011;50(13):1357-63.
Nomura K, Iizuka T, Kaji D, Yamamoto H, Kuribayashi Y, Tanaka M, Furuhata T, Yamashita S, Kikuchi D, Matsui A, Mitani T. Utility of endoscopic examination in the diagnosis of acute graft‐versus‐host disease in the lower gastrointestinal tract. Gastroenterology Research and Practice. 2017;2017(1):2145986.
Fukumoto A, Tanaka S, Shishido T, Takemura Y, Oka S, Chayama K. Comparison of detectability of small-bowel lesions between capsule endoscopy and double-balloon endoscopy for patients with suspected small-bowel disease. Gastrointestinal Endoscopy. 2009 Apr 1;69(4):857-65.
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Kahn KL, Kosecoff J, Chassin MR, Solomon DH, Brook RH. The use and misuse of upper gastrointestinal endoscopy. Annals of internal medicine. 1988 Oct 15;109(8):664-70.
Fry LC, Carey EJ, Shiff AD, Heigh RI, Sharma VK, Post JK, Hentz JG, Fleischer DE, Leighton JA. The yield of capsule endoscopy in patients with abdominal pain or diarrhea. Endoscopy. 2006 May;38(05):498-502.
Early DS, Ben-Menachem T, Decker GA, Evans JA, Fanelli RD, Fisher DA, Fukami N, Hwang JH, Jain R, Jue TL, Khan KM. Appropriate use of GI endoscopy. Gastrointestinal endoscopy. 2012 Jun 1;75(6):1127-31.
Dimenäs E, Glise H, Hallerbäck B, Hernqvist H, Svedlund J, Wiklund I. Well-being and gastrointestinal symptoms among patients referred to endoscopy owing to suspected duodenal ulcer. Scandinavian journal of gastroenterology. 1995 Jan 1;30(11):1046-52.