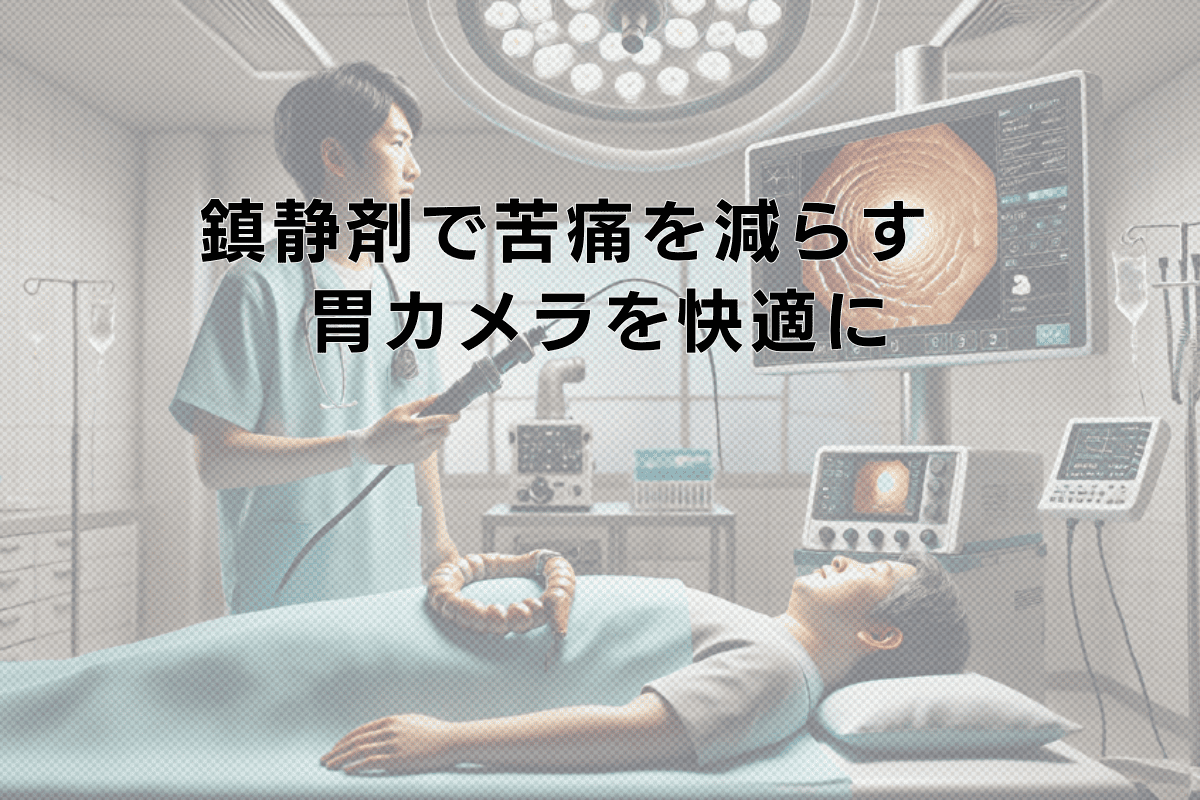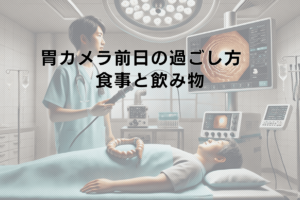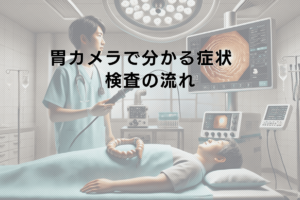胃カメラによる内視鏡検査は、胃がんや食道がん、逆流性食道炎などの病気を早期発見するうえで重要ですが、嘔吐反射や苦痛を不安に感じる人は少なくありません。
こうした不安を軽減する方法として鎮静剤の使用があります。薬の力を借りて検査を楽に受けやすくなります。
本記事では、鎮静剤を使った胃カメラ検査の具体的な流れやメリット・デメリット、費用面、使用時の注意点などを幅広く解説します。患者さんが安心して検査を受けられるための参考になれば幸いです。
胃カメラ鎮静剤を使う内視鏡検査とは何か
はじめに、胃カメラと鎮静剤について全体像を確認します。胃カメラは内視鏡検査の一つで、食道から胃、十二指腸などの消化器を観察して病変を見つけたり、生検を行ったりできる検査です。
鎮静剤は静脈から投与することが多く、ウトウトとした意識の中で内視鏡検査を受けられるようにします。
胃カメラ検査の目的
胃カメラ検査は、以下のような病気や状態を発見するために行います。
- 胃がんや食道がん、十二指腸がんなどの悪性腫瘍
- 胃潰瘍や十二指腸潰瘍
- 逆流性食道炎や食道裂孔ヘルニア
- ポリープや、萎縮性胃炎などのピロリ菌感染による胃の慢性炎症など
患者さんの症状やリスクを確認し、消化器内視鏡専門医が検査の適切なタイミング・方法を判断します。
鎮静剤と麻酔の違い
よく混同されがちですが、鎮静剤と麻酔には違いがあります。
- 鎮静剤(静脈麻酔)は眠っているような感覚に近く、不安や痛みを感じにくくします。
- 一般的な全身麻酔は呼吸も管理しなければならず、大掛かりな処置になります。
胃カメラ検査では、全身麻酔ほどの深い眠りではなく、意識はある程度残る場合が多いです。
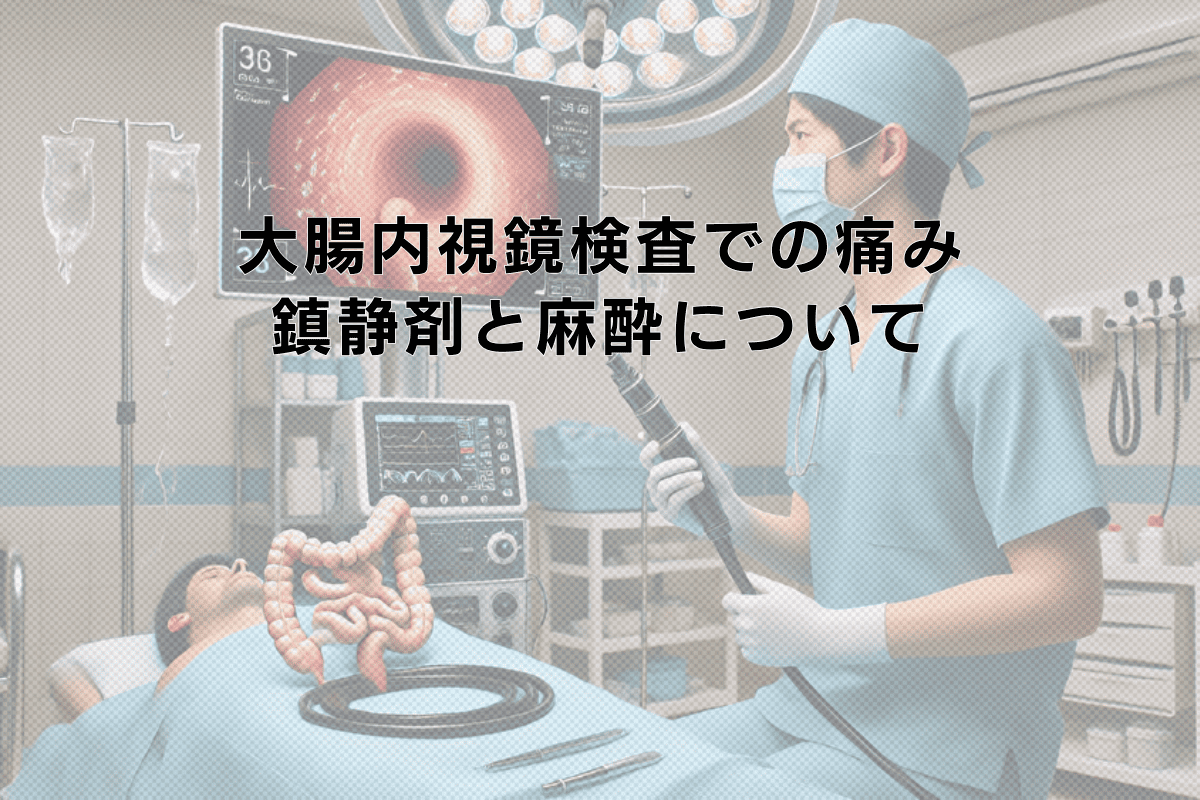
経口内視鏡と経鼻内視鏡
胃カメラは、口から挿入する経口内視鏡と、鼻から挿入する経鼻内視鏡があり、太さや検査時の感覚に違いがあります。
経鼻内視鏡はスコープが細い分、嘔吐反射や痛みが出にくい一方で、鼻腔が狭い人には向かないこともあります。
胃カメラ鎮静剤を使うことへの不安
鎮静剤を使用することで、完全に意識がなくなるわけではないものの、検査当日は眠気を引きずる人もいます。医師との相談で、体調や予定を踏まえたうえで使用の可否を検討してください。
また、検査後には、車・バイクの運転は控えてください。
鎮静剤使用時に注意したい場面
| 場面 | 注意点 |
|---|---|
| 車・バイク等の運転 | 鎮静剤が抜けきらないと事故リスクが高まる |
| 仕事・会議 | 集中力や判断力に影響が及ぶ可能性 |
| 家族の介護・育児 | 不安定な意識状態で見守るのは難しい場合がある |
| 飲酒 | 鎮静剤の作用とアルコールが相乗効果を起こしやすい |
―――――――――――――――――――――――――
鎮静剤を使った胃カメラのメリットとデメリット
鎮静剤を使用するか否かは、患者さんの希望や症状、検査の状況などを考慮して決めます。どのようなメリット・デメリットがあるかを知っておくと、検査を受ける際の不安も軽減できるでしょう。
メリット:苦痛や不安感の軽減
- 嘔吐反射が起きにくく、オエッとなる苦痛が少なくなる
- 検査中の不安が少なく、リラックスした状態を保ちやすい
- 胃や十二指腸の奥まで丁寧に観察しやすい
鎮静剤を使わない場合に比べ、やはり検査時のストレスが少なくなるという点が大きな利点です。苦痛が減る分、体への負担を抑え、患者さん自身も検査に集中できないストレスから解放される傾向があります。
デメリット:費用負担や当日の行動制限
- 鎮静剤による追加費用が必要になる可能性
- 検査後に意識がはっきりするまで休む必要がある
- 車やバイクなどの運転、あるいは自転車での帰宅が難しいことが多い
鎮静剤は保険適用の範囲内でも追加の自己負担が発生する場合があります。また意識レベルが低下している時間帯は行動に制限が出るため、検査の日程を決める際には配慮が必要です。
副作用や合併症のリスク
鎮静剤の副作用として、呼吸や血圧の変動などが挙げられます。ただし、消化器内視鏡専門医や医療機関の体制が整っていれば、モニタリングを行い、リスクを最小限に抑えて検査を行えます。
鎮静剤を使う人と使わない人の違い
いくつかの条件や体質により、鎮静剤の使用が望ましい人や、避けたほうがよい人がいます。
- 鎮静剤を使ったほうがよい傾向がある人
- 嘔吐に対して恐怖心がある人
- 苦痛や痛みに極度に弱い人
- 過去に内視鏡検査で強い不安やトラウマを感じた人
- 鎮静剤の使用を避けたほうがよい場合
- 極端に呼吸機能や心機能が低下している人
- 重篤なアレルギー体質である人
- 高齢で介護が必要であり、検査後の状況把握が困難な人
胃カメラ鎮静剤使用時の費用や保険適用
費用面は検査を検討するうえで重要なポイントです。保険診療の場合と自費診療の場合では内容が異なり、同じ鎮静剤を使うにしても、施設によって費用負担が異なることがあります。
保険診療の場合
一般的に胃カメラ検査は保険適用が可能で、症状がある人や医師が必要と判断した場合は3割負担(一部1割や2割負担などの人もいる)で受けられます。ただし、鎮静剤に関しては医療機関によって扱いが異なるため、事前に確認すると安心です。
保険診療での自己負担割合の一例
| 年齢・状況 | 自己負担割合 | 例 |
|---|---|---|
| 一般的な国保・社保加入 | 3割 | 30歳の会社員など |
| 70歳以上 | 2割 or 1割 | 所得区分で変わる場合 |
| 生活保護 | 0割 | 自己負担なし |
自費診療の場合
人間ドックや検診目的で胃カメラ検査を受けるときは、自費診療になるケースもあります。自費診療では保険が効かない分、費用が高めになる可能性があるものの、検査内容やオプション(ピロリ菌検査など)を自由に選びやすいのが利点です。
鎮静剤にかかる追加費用
医療機関によって、鎮静剤が無料の場合もあれば、数千円程度の追加費用がかかることがあります。投与する薬剤の種類や医師の管理体制、検査後のリカバリールームの使用などで費用が変動しますので、予約の際に確認するとよいでしょう。
費用を抑えるための工夫
- 医師の判断で大腸内視鏡検査と同時に行う場合、トータルの費用を抑えられる場合があります
- 自費検査の場合、医療機関によっては健康診断と併用して受けると割引がある場合があります
- 必要な検査だけを選ぶ
検査を受ける際には、費用とリスク、メリットのバランスを考えて選択することが大切です。

鎮静剤を使った胃カメラ検査の流れ
実際に鎮静剤を使用して行う胃カメラ検査の当日は、どのように進むのかをあらかじめ知っておくと安心感が高まります。検査前日から当日までの流れを順を追って説明します。
検査前日から当日までの準備
- 検査前日の夕食は消化が良いものを食べる。就寝前から飲水も控える場合が多い
- 指定がある場合は、前日や当日朝に飲む下剤や消泡剤を用いる
- 血液をサラサラにする薬を服用している場合は、医師の指示に従い一時的に服用を調整する
検査前に準備しておきたいもの
- 保険証、診察券など
- 過去の検査結果、他院からの紹介状
- 内服薬やアレルギーの情報をまとめたメモ
- 楽な服装、眼鏡よりはコンタクトレンズのほうが望ましい場合あり

受付と問診
当日はクリニックや内科を受診し、受付で手続きを行います。問診票には症状やアレルギー、既往症などを記入し、医師による診察や血圧・心拍数などの確認を行います。鎮静剤を使用する場合は同意書が必要になることがあります。
問診時によく聞かれる内容例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 既往症 | 心疾患や高血圧、喘息、糖尿病など |
| 内服薬 | 血圧の薬や抗血栓薬、糖尿病薬、精神科の薬など |
| アレルギー | 薬剤や麻酔、鎮静剤、食物、医療用テープなど |
| 検査への不安 | 過去の胃カメラ経験、嘔吐反射の強さなど |
検査中の流れ
- 点滴や静脈注射で鎮静剤を投与し、意識レベルを調整する
- 喉や鼻に局所麻酔を行ってスコープを挿入する
- 医師がスコープを進めながら、食道・胃・十二指腸を観察する
- 必要に応じて組織を採取して検査に回す
- モニターを見ながら医師が病変や出血、潰瘍などを確認する
鎮静剤でリラックスしているため、多くの患者さんは嘔吐反射をあまり感じず、気づいたら検査が終わっていたと感じる場合もあります。
検査後の休憩と説明
検査が終わったらリカバリールームなどで少し休み、意識とバイタルが安定したら医師から結果の説明を受けますが、組織検査の結果は後日になる場合があります。
検査後すぐに飲食が可能なケースもあれば、しばらく様子をみることを促される場合もあるため、スタッフの指示に従ってください。
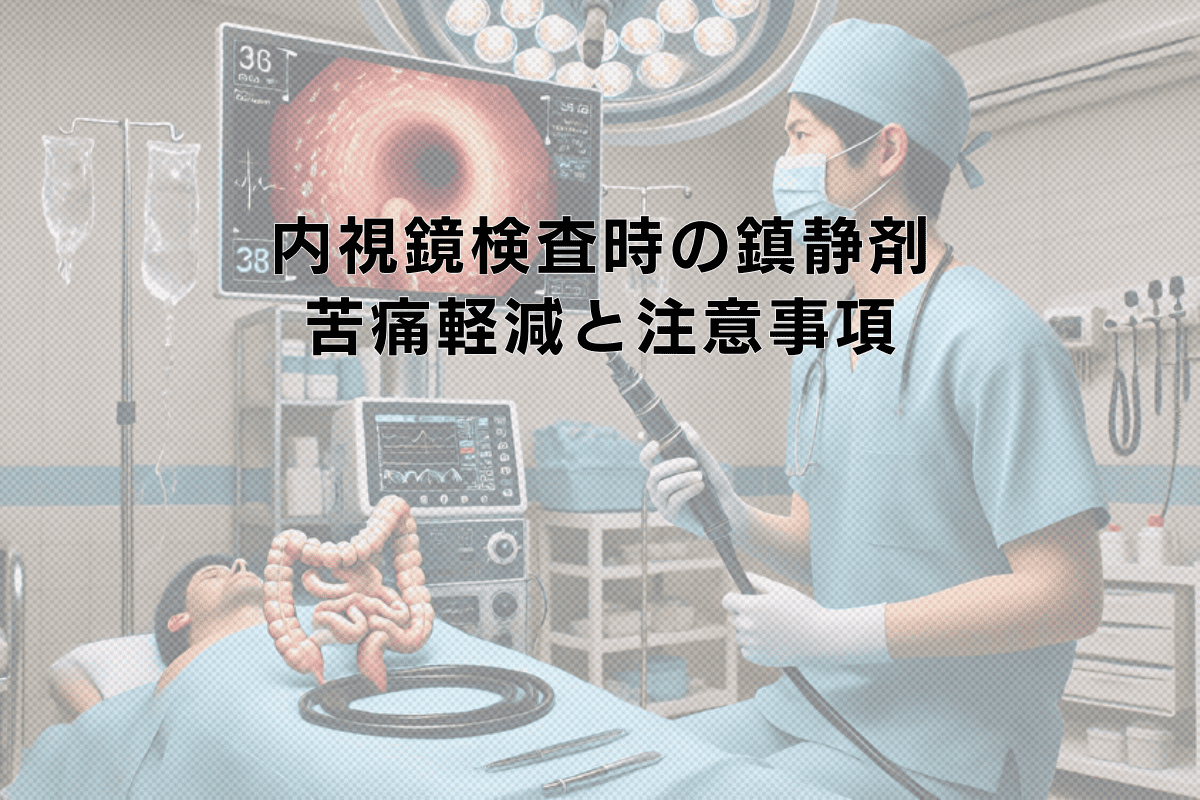
よくある質問と注意点
鎮静剤を使った胃カメラ検査については、患者さんからさまざまな質問や不安が寄せられます。ここでは、よくある問いとその回答を整理します。
Q:お酒に強い人だと鎮静剤が効きにくいって本当?
お酒に強い人は肝臓の代謝能力が高い傾向にありますが、鎮静剤の効き方は個人差が大きく一概には言えません。医師が患者さんの体重や体質に合わせて鎮静剤を調整するので、必要以上に心配する必要はありません。
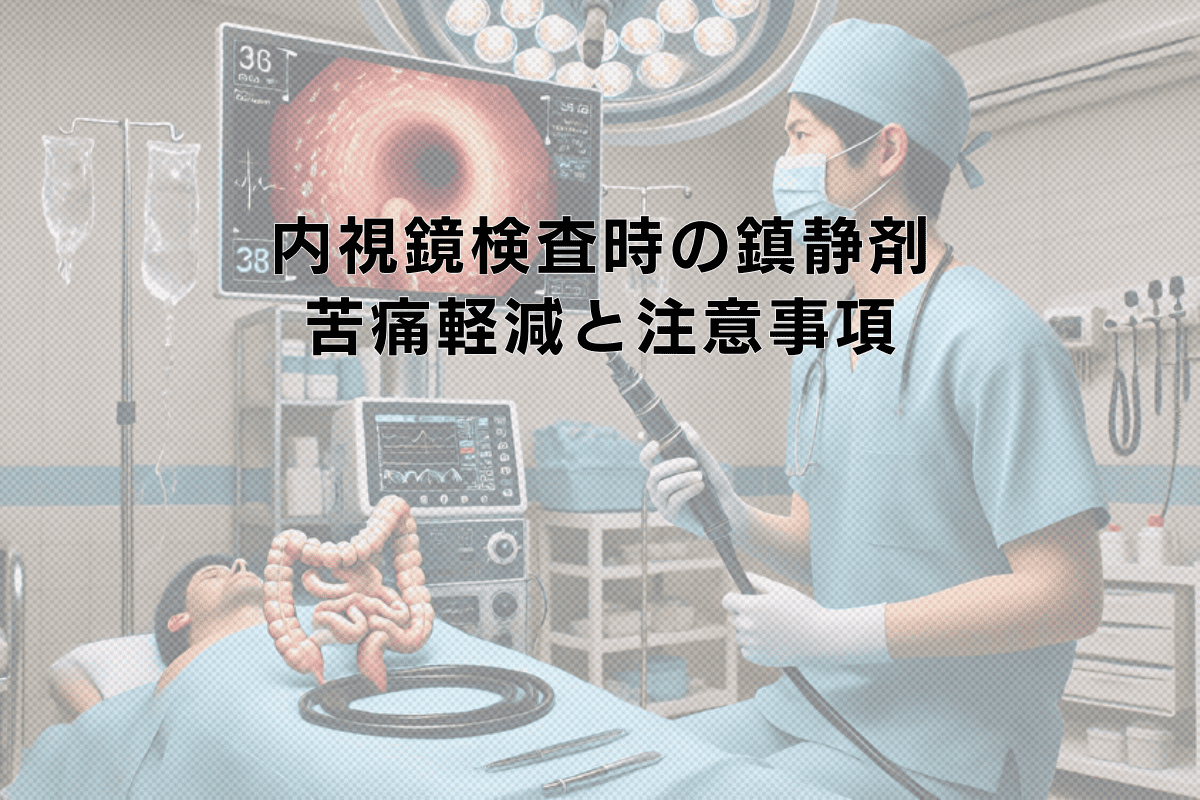
Q:検査後、すぐに仕事や運転をしてもいい?
鎮静剤の作用が残っている場合、注意力や判断力が低下することがあります。当日の車やバイクの運転は避け、公共交通機関や家族の送迎などを利用してください。仕事に復帰するにしても、体がだるいと感じるようなら無理は禁物です。
検査後の過ごし方のポイント
- 検査当日はできる限り安静を心がける
- 特に車やバイク、自転車の運転は避ける
- アルコール摂取を控える
- 体調に不安がある場合は早めに医師に相談する
Q:胃カメラ検査中に苦痛は本当にない?
鎮静剤の使用により、強い嘔吐反射や痛みは軽減される可能性が高いですが、完全に何も感じないわけではありません。
逆流性食道炎が強い人や個人的に痛みに敏感な人、挿入時にスコープが通りにくい形状の人などは、少し違和感が残る場合があります。
Q:胃カメラ検査でわかる病気はどれくらいある?
食道、胃、十二指腸の粘膜病変や潰瘍、ポリープ、がん、ピロリ菌感染の有無などがわかります。定期的に受診することで、胃がんや食道がんなどの重篤な病気の早期発見につながります。
胃カメラで発見できる主な病気と特徴
| 病気名 | 特徴 |
|---|---|
| 胃がん | 初期症状がほぼなく進行すると体重減少や食欲不振など |
| 逆流性食道炎 | 胸やけや呑酸が起こりやすい |
| 胃・十二指腸潰瘍 | 激しい腹痛や出血を伴う場合がある |
| ピロリ菌感染症 | 胃潰瘍や胃がんを引き起こすリスクが高まる |
| 食道がん | 嚥下障害や体重減少がみられる場合が多い |
―――――――――――――――――――――――――
胃カメラ検査を快適に受けるための工夫
胃カメラ検査はときに苦痛を伴うものというイメージがありますが、医療機関側も患者さんが安心して受けられるよう、さまざまな工夫を行っています。患者さん自身も、事前の準備や意識づくりで検査を乗り切りやすくなります。
医療機関の選び方
- 消化器内視鏡専門医が在籍しているか
- 鎮静剤に対応しているか
- 経鼻内視鏡や細径スコープを導入しているか
これらの条件を確認することで、より適切なクリニックや内視鏡検査が受けやすくなります。
医療機関選びのチェックリスト
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 専門医の在籍 | 消化器内視鏡専門医の資格を持つ医師が担当するか |
| 鎮静剤対応 | 鎮静剤・局所麻酔のどちらにも対応しているか |
| 内視鏡の種類 | 経口と経鼻の両方に対応しているか |
| アクセスと診療時間 | 通いやすい立地か、土日や祝日に検査ができるか |
| 口コミや評判 | 実際に受けた人の体験談や評価を参考にできるか |
不安な場合の事前相談
検査前に問診の時間を十分に設けている医療機関もあります。不安が強い人や初めて胃カメラ検査を受ける人は、遠慮せず医師やスタッフに相談し、疑問を解消してください。
痛みの感じ方や薬の副作用は人それぞれ異なるため、少しでも安心できる方法を一緒に検討しましょう。
事前相談で確認したいこと
- 嘔吐反射が強いときの対策
- 鎮静剤以外のリラックス方法(音楽や深呼吸など)
- 当日や検査後の予定への影響
- 大腸内視鏡検査との同時検査が可能か
胃カメラ以外の検査との組み合わせ
大腸内視鏡検査、人間ドックと合わせて受けることで、スケジュールや費用を効率的に組み立てることができます。
特に大腸内視鏡と同時に行うことは、トータルの負担を抑えたい人には検討しやすい方法です。
検査後のフォローアップ
組織検査などで気になる病変が見つかったら、早めに再診を受けて治療方針を決定することが大切です。逆流性食道炎や潰瘍などは、薬の内服治療や生活習慣の見直しを行うだけで症状を改善する場合もあります。

定期的な受診と早期発見の大切さ
胃カメラ検査は、胃がんや食道がんといった重大な病気の早期発見につながります。鎮静剤を使えば以前ほど苦痛が強い検査ではなくなり、負担を減らせます。
たとえ症状がなくても、40代~50代以降は定期的な検診・検査を受けると安心です。
発見が遅れるとどうなるか
症状がはっきり出る段階では、病気がかなり進んでいることがあります。食欲不振や体重減少、胸やけなどが持続的に起きる場合は、できるだけ早めにクリニックや内科を受診してください。
中には、ピロリ菌の長年の感染で慢性的に胃炎が進行していて、気づかないうちに胃がんリスクが高まっているケースもあります。
ピロリ菌の検査と除菌
胃カメラ検査時に組織を採取してピロリ菌検査を行うことも多く、陽性なら除菌治療を行うことで将来的な胃がんリスクを抑える可能性があります。
ピロリ菌除菌のステップ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 検査 | 抗体検査、尿素呼気試験、内視鏡生検、PCR検査などの方法 |
| 2. 除菌治療 | 抗生物質と胃酸抑制薬を組み合わせた内服を継続 |
| 3. 判定 | 再度の呼気試験などで菌が残っていないか確認 |
| 4. 定期検査 | 除菌後も胃がん発生の可能性はゼロではないため継続検査 |
受けっぱなしにしないことの大切さ
検査を受けた後、医師の説明をよく聞いてフォローアップの受診時期を守るようにしてください。
胃カメラで観察できる領域は食道から十二指腸までですが、もしほかの消化器症状がある場合は、大腸カメラなど他の内視鏡検査も検討すると安心です。
家族や周囲への声かけ
自分が検査を受けることによって病気のリスクを把握できるだけでなく、家族や友人にも胃カメラ検査の大切さを共有するきっかけになります。特に胃がんや大腸がんは早期発見・早期治療が重要です。
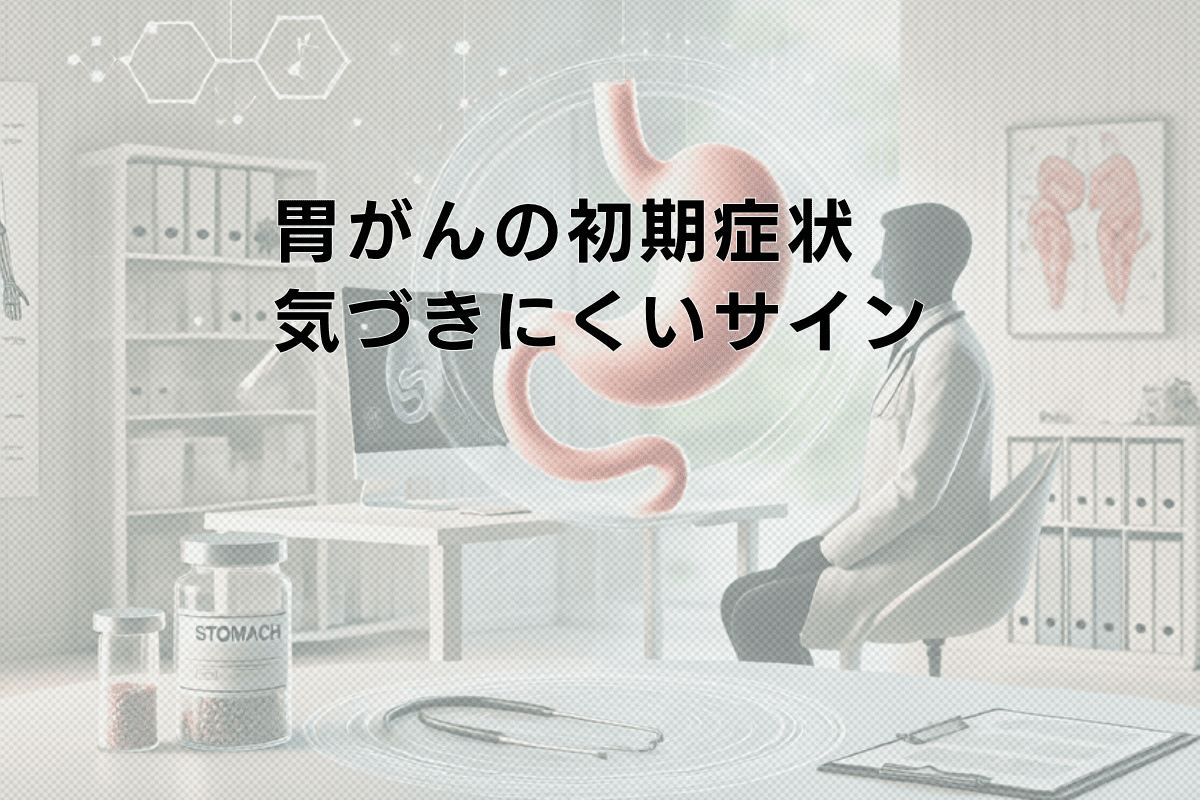
まとめ
胃カメラ検査は、食道や胃、十二指腸の病気を早期に発見して治療するために大切な方法で、鎮静剤を使うことで、嘔吐反射や苦痛を和らげ、より楽に検査を受けることができます。
一方で、検査後の行動制限や追加費用、呼吸や血圧への影響なども把握し、医師と十分に相談することが欠かせません。
鎮静剤を使用した胃カメラ検査を検討している人は、事前に医師やスタッフに不安を伝え、費用や当日の流れ、検査後の過ごし方などについて具体的に確認するとよいでしょう。
症状がなくても、定期的に内視鏡検査を受けることが、胃がんや食道がんの早期発見につながります。
次に読むことをお勧めする記事
【胃カメラ前日どう過ごす? 準備で気をつけたい食事と飲み物】
鎮静剤を使った胃カメラ検査について理解できたら、次は実際の検査準備の方法について、こちらの記事で一緒に勉強してまいりましょう。検査予定が決まった方や具体的な準備が知りたい方に特におすすめです。
【内視鏡検査費用の目安と流れ 胃と大腸のチェック方法】
鎮静剤を使った胃カメラについての理解が深まりましたら、さらに内視鏡検査全般の費用体系についても知っておくと、より包括的な理解につながります。こちらの記事で一緒に学びましょう。
参考文献
Froehlich F, Schwizer W, Thorens J, Köhler M, Gonvers JJ, Fried M. Conscious sedation for gastroscopy: patient tolerance and cardiorespiratory parameters. Gastroenterology. 1995 Mar 1;108(3):697-704.
Chen L, Liang X, Tan X, Wen H, Jiang J, Li Y. Safety and efficacy of combined use of propofol and etomidate for sedation during gastroscopy: systematic review and meta-analysis. Medicine. 2019 May 1;98(20):e15712.
Kang S, Lu J, Zhou HM. Anesthetic strategy for obese patients during gastroscopy: deep sedation or conscious sedation? A prospective randomized controlled trial. Journal of anesthesia. 2021 Aug;35:555-62.
Ristikankare M, Julkunen R, Heikkinen M, Mattila M, Laitinen T, Wang SX, Hartikainen J. Sedation, topical pharyngeal anesthesia and cardiorespiratory safety during gastroscopy. Journal of clinical gastroenterology. 2006 Nov 1;40(10):899-905.
Leslie K, Allen ML, Hessian E, Lee AY. Survey of anaesthetists’ practice of sedation for gastrointestinal endoscopy. Anaesthesia and Intensive Care. 2016 Jul;44(4):491-7.
Chen B, Lu L, Zhai J, Hua Z. Effect of moderate versus deep sedation on recovery following outpatient gastroscopy in older patients: a randomized controlled trial. Surgical Endoscopy. 2024 Mar;38(3):1273-82.
Tang S, Zheng Y, Li X, Zhang Y, Zhang Z. Optimizing sedation in gastroscopy: a study on the etomidate/propofol mixture ratio. Frontiers in Medicine. 2024 Jun 12;11:1392141.
Shi W, Cheng Y, He H, Fang Q, Hu Y, Xu X, Shuai Y, Zhang J, Fang X, Wang Z, Zhang Y. Efficacy and safety of the remimazolam-alfentanil combination for sedation during gastroscopy: a randomized, double-blind, single-center controlled trial. Clinical therapeutics. 2022 Nov 1;44(11):1506-18.
Early DS, Lightdale JR, Vargo JJ, Acosta RD, Chandrasekhara V, Chathadi KV, Evans JA, Fisher DA, Fonkalsrud L, Hwang JH, Khashab MA. Guidelines for sedation and anesthesia in GI endoscopy. Gastrointestinal endoscopy. 2018 Feb 1;87(2):327-37.
Xiao X, Xiao N, Zeng F, Chen H, Zhang L, He X. Gastroscopy sedation: clinical trial comparing propofol and sufentanil with or without remimazolam. Minerva Anestesiologica. 2022 Jan 24;88(4):223-9.