大腸内視鏡検査、いわゆる大腸カメラについて、一度検査を受けたら次はいつ受ければ良いのか、疑問に思う方は少なくないでしょう。
検査の間隔は、個人の年齢や健康状態、前回の検査結果、家族の病歴など、さまざまな要因によって変わります。
この記事では、大腸内視鏡検査の適切な間隔について、詳しく解説します。
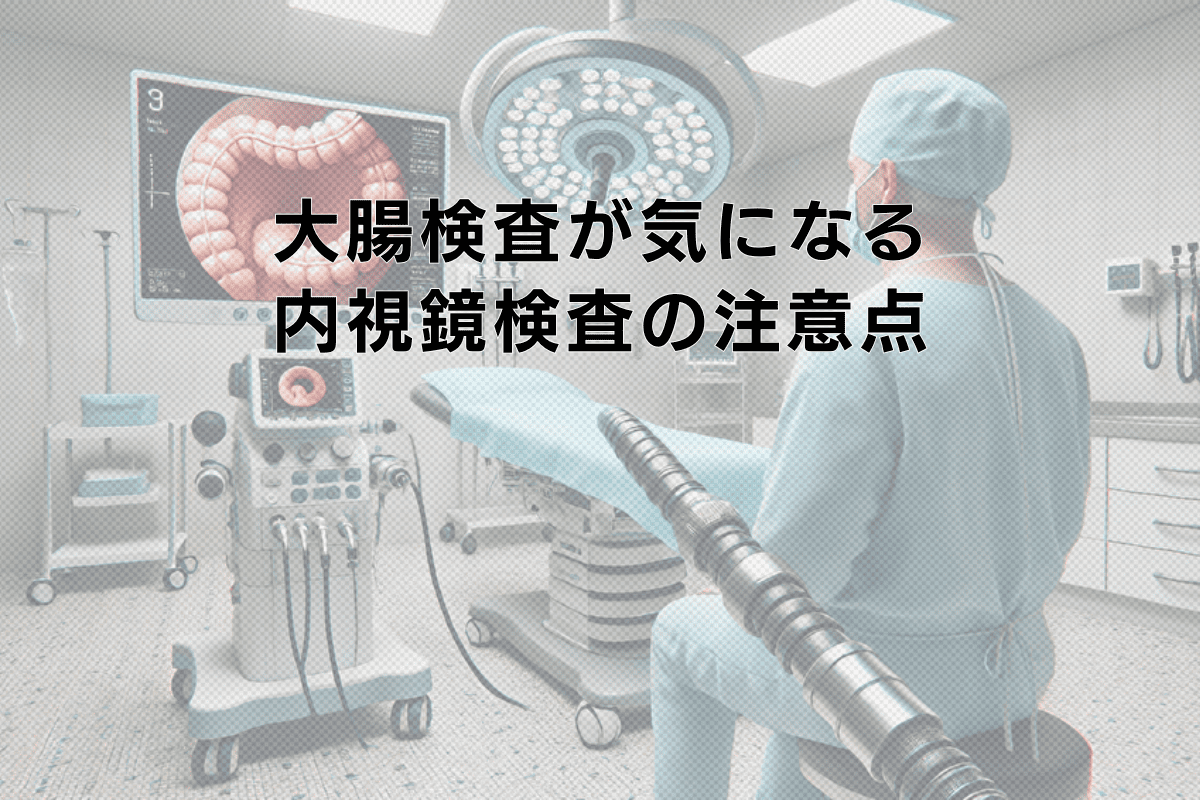
大腸内視鏡検査の受診間隔の重要性
大腸内視鏡検査は、大腸がんやその前段階であるポリープを発見するために非常に有効な検査で、適切な間隔で検査を継続することが、将来の大腸がんリスクを低減させる上で極めて重要です。
なぜ検査間隔を知ることが大切なのか
大腸がんは、早期に発見すれば高い確率で治癒が期待できるがんです。
多くの場合、がんは良性のポリープから発生し、数年かけてゆっくりと大きくなり、がん化するので、ポリープの段階で発見し切除することが、大腸がんの最も効果的な予防法となります。
検査間隔が長すぎると、前回の検査では見つからなかった、あるいは非常に小さかったポリープが、次の検査までの間にがん化してしまう可能性があります。
ただし、不必要に短い間隔で検査を繰り返すことは、身体的、経済的な負担を増やすことにもつながります。
大腸がんの早期発見と予防における役割
大腸内視鏡検査の大きな役割は二つあります。一つは、既に発生してしまったがんを早期の段階で発見することで、もう一つは、将来がんになる可能性のあるポリープを発見し、その場で切除することによるがんの予防です。
ポリープががん化するまでには一般的に5年から10年程度の時間が必要と考えられていて、時間的な猶予があるからこそ、定期的な内視鏡検査が有効です。
適切な間隔で大腸の内部を観察し、ポリープがあれば切除を続けることで、大腸がんの発生リスクを大幅に下げることができます。
大腸がんの進行度と5年生存率の関係
| ステージ | がんの状態 | 5年相対生存率の目安 |
|---|---|---|
| 0 | がんが粘膜内にとどまる | 95%以上 |
| I | がんが固有筋層内にとどまる | 約90% |
| II | がんが固有筋層を越えている | 約80% |
| III | リンパ節に転移がある | 約70% |
| IV | 他の臓器に遠隔転移がある | 約15% |
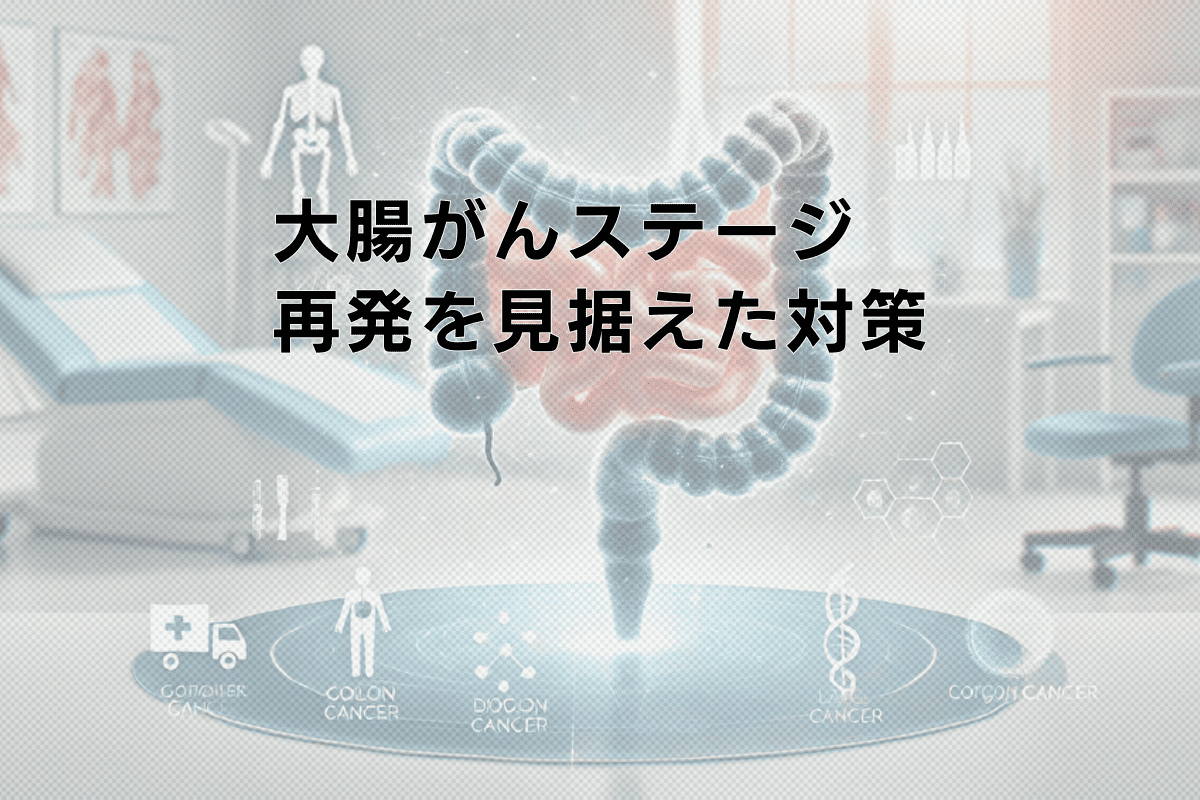
大腸内視鏡検査の基本的な目的と役割
大腸内視鏡検査がなぜ重要なのかを理解するためには、目的と役割を正確に知ることが大切です。内視鏡検査は、単に大腸の中を覗くだけのものではありません。診断から治療、そして予防まで、多岐にわたる重要な役割を担っています。
観察と診断-大腸の内部を直接見る
大腸内視鏡検査の最も基本的な役割は、先端に高性能カメラが付いた細い管(スコープ)を肛門から挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体の粘膜を直接、詳細に観察することです。
医師はモニターに映し出される鮮明な映像を見ながら、炎症、潰瘍、ポリープ、がんなどの異常がないかを隅々まで確認します。
ミリ単位の微細な病変も見つけることが可能で、その色や形、表面の構造から、病変の性質をおおよそ推測することもできます。
他の画像検査、例えばCT検査などでは発見が難しい平坦な病変や、ごく早期のがんを発見できる点が、内視鏡検査の大きな利点です。
大腸内視鏡検査でわかる主な疾患
| 疾患名 | 主な特徴 | 内視鏡検査の役割 |
|---|---|---|
| 大腸ポリープ | 粘膜がイボ状に隆起したもの | 発見と切除(予防) |
| 大腸がん | 悪性の腫瘍 | 早期発見、組織採取 |
| 炎症性腸疾患 | 潰瘍性大腸炎、クローン病など | 診断、活動性の評価 |
| 大腸憩室症 | 腸壁が外側に袋状に突出 | 診断、出血源の特定 |
| 虚血性腸炎 | 血流障害による腸の炎症 | 特徴的な粘膜所見の確認 |
ポリープの切除-がん化する前の予防的治療
大腸内視鏡検査のもう一つの非常に重要な役割は、がんになる可能性のあるポリープ(特に腺腫性ポリープ)を発見した場合に、その場で切除できることです。
これはポリープ切除術(ポリペクトミー)と呼ばれ、スコープの先端からスネアという輪っか状の細いワイヤーを出し、ポリープの根元に引っ掛けて高周波電流で焼き切ります。
痛みを感じることはほとんどなく、予防的治療により、将来発生するはずだった大腸がんの芽を摘むことができます。検査と治療を一度に行えることは、患者さんの負担を軽減する上でも大きなメリットです。
切除したポリープは回収し、病理検査で詳しく調べます。
組織の採取-良性か悪性かを確定する
内視鏡で観察した際に、ポリープやがんが疑われる病変、あるいは炎症などが見つかった場合、一部を採取して顕微鏡で詳しく調べることがあり、これが生検(せいけん)です。
スコープの先端から鉗子(かんし)を出し、病変の一部を少量つまみ取り、組織片を病理検査にかけることで、病変が良性なのか悪性なのか、どのような種類の細胞でできているのかを確定診断します。
確定診断に基づいて、その後の治療方針が決定され、がんであることが確定すれば、進行度を調べるための追加検査や、手術などの本格的な治療計画が立てられます。正確な診断を下す上で、組織の採取は欠かせない手技です。
推奨される大腸内視鏡検査の一般的な間隔
大腸内視鏡検査をいつから始め、どのくらいの間隔で受ければ良いのかは、多くの人が関心を持つ点です。ここでは、特に大きなリスク要因がない健康な方を対象とした、一般的な推奨間隔について解説します。
初めて検査を受ける年齢の目安
大腸がんの発生率は、40歳を過ぎた頃から増加し始め、50歳以降でさらに高くなります。多くの国のガイドラインでは、特に症状やリスク要因がない場合でも、40歳または50歳を節目として一度目の大腸内視鏡検査を受けることを推奨しています。
日本では、自治体や職場の健康診断で行われる便潜血検査が一次検診として普及しており、陽性となった場合に精密検査として大腸内視鏡検査を受ける流れが一般的です。
しかし、便潜血検査は進行がんでは陽性率が高いものの、早期がんやポリープでは見逃されることもあります。がん予防の観点からは、40歳を過ぎたら一度、専門医に相談の上で内視鏡検査を検討することをお勧めします。
リスクがない場合の基本的な検査頻度
初めて受けた大腸内視鏡検査で、特に異常(ポリープ、がん、炎症など)が全く認められなかった場合、次回の検査までの間隔は比較的長く設定できます。
これは、新しいポリープが発生し、それががん化するまでにはある程度の年月を要するためです。
一般的には、検査の質が担保されている(大腸の奥までしっかりと観察できている)という前提で、5年から10年に一度の検査が推奨されることが多いですが、これはあくまで現時点でリスクが低いと判断された場合です。
年齢が上がるにつれてリスクは高まるため、医師によってはもう少し短い間隔を勧めることもあります。

リスクがない場合の年齢別推奨間隔の目安
| 年齢 | 推奨される検査間隔 | 備考 |
|---|---|---|
| 40代 | 5~10年 | 初回の検査で異常がなかった場合 |
| 50代~60代 | 5年前後 | がんの好発年齢のためやや短縮を検討 |
| 70代以上 | 医師と相談の上決定 | 全身状態や期待余命を考慮 |
年齢による推奨間隔の変化
大腸がんのリスクは加齢とともに上昇するため、推奨される検査間隔も年齢に応じて変化することがあります。
40代で受けた検査で異常がなかった場合、次は5~10年後で良いかもしれませんが、60代で受けた検査で異常がなかったとしても、次は3~5年後を勧められるかもしれません。これは、年齢が上がるほどポリープが発生しやすくなるためです。
また、75歳や80歳を超えてからの検査については、画一的な基準はありません。
個人の健康状態、過去の検査歴、検査に伴う偶発症のリスク、本人の意思などを総合的に考慮し、検査を続けるかどうか、続ける場合の適切な間隔を医師と慎重に相談して決める必要があります。
ポリープの有無と種類で変わる検査間隔
前回の検査で大腸ポリープが見つかったかどうか、そしてポリープがどのような性質のものだったかは、次回の検査間隔を決める上で最も重要な要因の一つです。
ポリープを切除した場合は、再発や新たなポリープの発生を監視するために、通常よりも短い間隔でのフォローアップが必要となります。
ポリープがなかった場合の次回検査
内視鏡検査でポリープやがん、その他の異常が全く見つからなかった場合は、大腸がんのリスクは低いと判断でき、次回の検査は5年から10年後が一般的な目安です。
ただし、検査の際に下剤の服用が不十分で腸内がきれいになっておらず、観察が不十分だったと判断された場合は、より短い期間での再検査を勧められることがあります。
ポリープを切除した場合の考え方
検査でポリープが見つかり、切除した場合、その人は「ポリープができやすい体質」である可能性が考えられます。
一度ポリープができた場所とは別の場所に、新たなポリープが発生するリスクが、ポリープがなかった人に比べて高いことがわかっています。
ポリープを切除した後は定期的な監視が必要で次回、の検査間隔は、切除したポリープの種類、大きさ、数、病理検査の結果によって細かく決められます。
ポリープの種類と特徴
| ポリープの種類 | がん化のリスク | 特徴 |
|---|---|---|
| 腺腫性ポリープ | あり(大腸がんの前がん病変) | 最も一般的なタイプ。切除対象となる。 |
| 過形成性ポリープ | 基本的には低い | 直腸やS状結腸に多い。小さいものは経過観察。 |
| 炎症性ポリープ | なし | 腸の炎症によってできる。がん化しない。 |
ポリープの種類や大きさ、数による違い
切除したポリープが病理検査で腺腫と診断された場合、その後の検査間隔はさらに細かく設定されます。特に重要視されるのは、腺腫の大きさ、数、そして組織学的な異型度(細胞の顔つきの悪さ)です。
大きさが1cm未満の腺腫が1~2個だった場合は、次回の検査は3~5年後が目安となります。
大きさが1cm以上の腺腫、数が3個以上の腺腫、あるいは異型度の高い腺腫があった場合は、より高いリスクがあると判断し、1年後や3年後といった短い間隔での再検査を推奨します。
これは、大きなポリープや多数のポリープが見つかった人は、見逃されている小さなポリープが存在する可能性や、新しいポリープが短期間で発生する可能性が高いと考えられるためです。
ポリープの数・大きさ別の推奨間隔の目安
| 前回の検査所見 | 推奨される次回の検査間隔 |
|---|---|
| 1cm未満の腺腫が1~2個 | 3~5年後 |
| 1cm以上の腺腫 | 3年以内 |
| 腺腫が3個以上 | 3年以内 |
| 絨毛成分を多く含む腺腫 | 3年以内 |
| 高度異型を伴う腺腫 | 1年後など短期での再検査を検討 |
複数のポリープが見つかった場合
腺腫性ポリープが3個以上見つかった場合、多発性ポリープと呼ばれ、大腸がんのハイリスク群と見なされます。
たとえ一つ一つのポリープが小さくても、大腸粘膜全体がポリープを発生させやすい状態にあるため、次回の検査は3年以内に行うことが強く推奨されます。
また、10個以上のポリープが見つかった場合は、さらにリスクが高いと判断し、1年後の検査を検討することもあります。多数のポリープを一度の検査で完全に取りきれなかった場合も、短期間での再検査が必要です。
検査間隔に影響を与えるその他のリスク要因
ポリープの有無だけでなく、個人の体質や生活習慣、過去の病歴なども、大腸内視鏡検査の間隔を決める上で考慮すべき重要な要素です。リスク要因を持つ方は、一般的な推奨間隔よりも短い間隔で検査を受けることが勧められます。
大腸がんの家族歴がある場合
血縁者(特に親、兄弟姉妹、子)に大腸がんになった人がいる場合、ご自身の大腸がんリスクは高まり、遺伝的な要因や、共通の生活習慣が影響していると考えられます。
特に、50歳未満の若さで大腸がんを発症した血縁者がいる場合は、リスクがさらに高いです。
家族歴がある方は、血縁者が大腸がんと診断された年齢よりも5年から10年早い年齢、あるいは40歳になった時点のいずれか早い方で初回の内視鏡検査を開始し、その後は3~5年ごとの定期的な検査を受けることが推奨されます。
家族歴は非常に重要な情報ですので、検査を受ける際には必ず医師に伝えてください。
大腸がんの主なリスク要因
| 分類 | 具体的なリスク要因 |
|---|---|
| 変えられない要因 | 年齢(50歳以上)、大腸がんの家族歴、遺伝性疾患 |
| 生活習慣 | 赤肉・加工肉の過剰摂取、野菜・果物不足 |
| 肥満、運動不足、過度の飲酒、喫煙 | |
| 既往歴 | 大腸ポリープの既往、炎症性腸疾患 |
炎症性腸疾患(IBD)の既往歴
潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患(IBD)を長期間患っている方は、大腸がんの発生リスク(いわゆるcolitic cancer)が健康な人よりも高いことが知られています。
炎症が長期間続くことで、大腸粘膜の細胞に遺伝子異常が蓄積しやすくなるためで、炎症の範囲が広い(全大腸炎型など)場合や、発症からの期間が長い(8年以上)場合は、リスクが高まります。
IBDの患者さんは、症状が落ち着いている時期でも、1~2年ごとの定期的な内視鏡検査(サーベイランス)を受け、がんや前がん病変である異形成(dysplasia)がないかを注意深く監視することが必要です。
炎症性腸疾患の種類と特徴
| 疾患名 | 主な炎症部位 | 特徴的な症状 |
|---|---|---|
| 潰瘍性大腸炎 | 大腸の粘膜 | 血便、下痢、腹痛 |
| クローン病 | 消化管全体(口から肛門まで) | 腹痛、下痢、体重減少、発熱 |
生活習慣と大腸がんリスク
日々の生活習慣も大腸がんのリスクと深く関わっています。以下のような生活習慣がある方は、リスクが高まる可能性があります。
- 赤肉(牛、豚、羊など)や加工肉(ハム、ソーセージなど)の摂取が多い
- 野菜や果物の摂取が少ない
- 肥満
- 運動不足
- 過度の飲酒
- 喫煙
生活習慣は、直接的に検査間隔を決定するものではありませんが、医師が個々のリスクを評価する上での参考情報となり、リスクが高いと判断された場合、より積極的な検査スケジュールが提案される可能性があります。
内視鏡検査と並行して、生活習慣を改善していくことも、大腸がん予防にはとても大切です。
腹部の症状がある場合の考え方
これまでに述べた検査間隔は、基本的に症状がない方を対象としたものです。
もし、便に血が混じる、便通の異常(便秘や下痢の繰り返し)、腹痛、体重減少、貧血といった何らかの症状がある場合は、次回の予定を待たずに、速やかに医療機関を受診する必要があります。
このような症状は、大腸がんやその他の消化器疾患のサインである可能性があり、症状がある場合は、検査間隔のルールにとらわれず、その都度、医師の診察と判断を仰ぐことが重要です。
検査間隔を自己判断する危険性と専門医への相談
インターネットや書籍で大腸内視鏡検査に関する情報を簡単に得られるようになりました。しかし、そのような情報だけを頼りにして、ご自身の検査間隔を自己判断することには大きな危険が伴います。
インターネット情報だけを頼る問題点
インターネット上には、有益な情報もあれば、不正確な情報や古い情報、あるいは個人の体験談に基づいた偏った意見も混在しています。
一般的なガイドラインを知ることはできても、その情報がご自身の特定の状況、例えば前回のポリープの詳しい病理結果や、ご自身の家族歴の重要度などに当てはまるかどうかは分かりません。
情報に一喜一憂し、本来必要な検査を先延ばしにしたり、逆に不必要な検査を繰り返したりする可能性があります。情報はあくまで参考とし、最終的な判断は医学的な専門知識を持つ医師に委ねることが賢明です。
個々の状況に合わせた判断の必要性
大腸内視鏡検査の適切な間隔は、多くの要因が複雑に絡み合って決まります。年齢、性別、過去の検査結果、ポリープの数・大きさ・病理組織、家族歴、既往歴、生活習慣、現在の症状など、考慮すべき点は多岐にわたります。
専門医は情報をすべて総合し、医学的な知識と経験に基づいて、最も合理的で安全な検査計画を立案します。画一的な基準を自分に当てはめるのではなく、オーダーメイドの医療計画を立てることが、効果的ながん予防の鍵です。
医師に相談するタイミング
以下のようなタイミングで、専門医に相談することをお勧めします。
- 40歳を過ぎて、まだ一度も大腸内視鏡検査を受けたことがない
- 便潜血検査で陽性と判定された
- 血便や腹痛など、気になる症状がある
- 前回の検査から推奨された期間が経過した
- 家族が新たに大腸がんと診断された
相談の際には、これまでの病歴や家族歴、服用中の薬、気になる症状などを正確に伝えることが大切です。医師との対話を通じて、ご自身の状況を正しく理解し、納得のいく検査計画を一緒に立てていきましょう。
大腸内視鏡検査の間隔に関するよくある質問
最後に、大腸内視鏡検査の間隔に関して、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 毎年検査を受ける必要はありますか
-
ほとんどの場合、毎年大腸内視鏡検査を受ける必要はありません。
大腸ポリープががんに進行するには通常数年の時間がかかるため、前年の検査で異常がなかったにもかかわらず、翌年に進行がんが見つかるというケースは極めて稀です。
ただし、遺伝性の疾患(家族性大腸腺腫症など)がある方や、多数のポリープを分割して切除した後のフォローアップなど、ごく一部の特殊な状況では、1年後の検査が指示されることがあります。
医師から指示された間隔を守ることが重要です。
- 便潜血検査で陰性なら内視鏡検査は不要ですか
-
便潜血検査は、便に混じった微量の血液を検出する簡便で有効な検査ですが、万能ではありません。
早期のがんやポリープは、常に出血しているわけではないため、検査のタイミングによっては出血を捉えられず、陰性と判定されることがあります(偽陰性)。
便潜血検査が陰性であったにもかかわらず、内視鏡検査で進行がんが見つかるケースもあります。便潜血検査はあくまでスクリーニング(ふるい分け)検査です。
40歳を過ぎたら、一度は内視鏡検査で大腸全体を精密に調べることをお勧めします。便潜血検査が陰性であっても、腹部の症状がある場合や、大腸がんの家族歴があるなどのリスク要因を持つ方は、内視鏡検査を検討してください。
- 検査の間隔が空きすぎるとどうなりますか
-
医師から推奨された検査間隔よりも大幅に期間が空いてしまうと、その間に新たなポリープが発生し、発見されないまま大きくなったり、がん化してしまったりするリスクが高まります。
特に、以前の検査でリスクの高いポリープを切除した方は注意が必要です。
大腸がんは早期発見が何よりも大切で、推奨された検査スケジュールを守ることが、ご自身の健康を守る上で非常に重要です。
もし、予定通りに受診できなかった場合は、気づいた時点ですぐに医療機関に連絡し、相談してください。
- 検査費用は間隔によって変わりますか
-
検査の間隔自体が直接的に費用を変えることはありません。費用は、行われた手技の内容によって決まり、観察のみで終わる場合と、生検(組織採取)やポリープ切除術を行う場合とでは、費用が異なります。
ポリープを切除した場合は、観察のみの場合よりも費用は高くなります。検査間隔が短いから安い、長いから高い、ということはなく、その都度の検査内容によって費用は変動します。
以上
次に読むことをお勧めする記事
【良性の大腸ポリープにおける経過観察のポイント】
検査間隔の基本を読んで、“切除した自分は次はいつ?”と感じた方へ。病理結果別の再検査目安や注意点を整理し、不安の解像度を上げます。
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
検査間隔の次は“当日の準備”。何を食べ、何を避けるか、下剤の流れまで実践的に把握しておくと当日の負担が軽減します。
参考文献
Saito Y, Oka S, Kawamura T, Shimoda R, Sekiguchi M, Tamai N, Hotta K, Matsuda T, Misawa M, Tanaka S, Iriguchi Y. Colonoscopy screening and surveillance guidelines. Digestive Endoscopy. 2021 May;33(4):486-519.
Matsuda T, Fujii T, Sano Y, Kudo SE, Oda Y, Hotta K, Shimoda T, Saito Y, Kobayashi N, Sekiguchi M, Konishi K. Randomised comparison of postpolypectomy surveillance intervals following a two-round baseline colonoscopy: the Japan Polyp Study Workgroup. Gut. 2021 Aug 1;70(8):1469-78.
Saito H, Kudo SE, Takahashi N, Yamamoto S, Kodama K, Nagata K, Mizota Y, Ishida F, Ohashi Y. Efficacy of screening using annual fecal immunochemical test alone versus combined with one-time colonoscopy in reducing colorectal cancer mortality: the Akita Japan population-based colonoscopy screening trial (Akita pop-colon trial). International Journal of Colorectal Disease. 2020 May;35(5):933-9.
Minamitani M, Tatemichi M, Mukai T, Katano A, Ohira S, Nakagawa K. Adherence to national guidelines for colorectal, breast, and cervical cancer screenings in Japanese workplaces: a survey-based classification of enterprises’ practices into “overscreening,”“underscreening,” and “guideline-adherence screening”. BMC Public Health. 2024 Aug 15;24(1):2223.
Tanaka S, Kashida H, Saito Y, Yahagi N, Yamano H, Saito S, Hisabe T, Yao T, Watanabe M, Yoshida M, Saitoh Y. Japan Gastroenterological Endoscopy Society guidelines for colorectal endoscopic submucosal dissection/endoscopic mucosal resection. Digestive Endoscopy. 2020 Jan;32(2):219-39.
Kobayashi D, Takahashi O, Arioka H, Fukui T. The optimal screening interval for gastric cancer using esophago-gastro-duodenoscopy in Japan. BMC gastroenterology. 2012 Oct 17;12(1):144.
Kashiwagi K, Inoue N, Yoshida T, Bessyo R, Yoneno K, Imaeda H, Ogata H, Kanai T, Sugino Y, Iwao Y. Polyp detection rate in transverse and sigmoid colon significantly increases with longer withdrawal time during screening colonoscopy. PloS one. 2017 Mar 22;12(3):e0174155.
Tanaka S, Saitoh Y, Matsuda T, Igarashi M, Matsumoto T, Iwao Y, Suzuki Y, Nozaki R, Sugai T, Oka S, Itabashi M. Evidence-based clinical practice guidelines for management of colorectal polyps. Journal of Gastroenterology. 2021 Apr;56(4):323-35.
Lee KJ, Inoue M, Otani T, Iwasaki M, Sasazuki S, Tsugane S. Colorectal cancer screening using fecal occult blood test and subsequent risk of colorectal cancer: a prospective cohort study in Japan. Cancer detection and prevention. 2007 Jan 1;31(1):3-11.
Kawamura T, Oda Y, Toyoizumi H, Kato M, Sekiguchi M, Takamaru H, Mizuguchi Y, Horiguchi G, Kobayashi K, Sada M, Yokoyama A. Risk of colorectal cancer among fecal immunochemical test‐positive individuals by timing of previous colonoscopy: A multicenter analysis. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2025 Jan;40(1):153-8.










