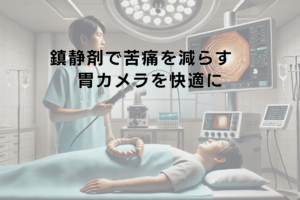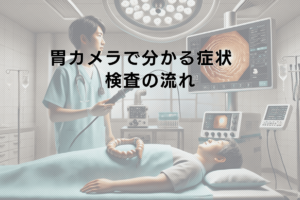胃カメラ検査は、胃の状態を詳しく観察できる内視鏡検査の1つで、食道から十二指腸までの上部消化管の異常の有無を調べる目的で行いますが、検査精度を高めて安全に受けるためには、前日の食事内容や生活習慣の管理がとても重要です。
前日にどのような食べ物や飲み物を選ぶか、何時ごろまでに食事を終えるか、どんな点に気をつけて就寝すればよいかなど、具体的に把握しておくと安心です。
ここでは、胃カメラ前日に気をつけたいポイントを中心に、当日の流れから検査後の生活上の留意点までまとめて解説します。
受診を予定している人や今後検査を受ける可能性のある人にとって、疑問を解消しながら当日まで落ち着いて準備できるよう、詳しくご紹介します。
胃カメラ検査とは何か
胃カメラ検査は、先端にカメラが付いた内視鏡を口または鼻から挿入し、胃や食道、十二指腸の内側を観察する方法です。
大腸の内視鏡検査(大腸カメラ)と並び、消化器を詳しく調べる代表的な検査として知られています。
バリウム検査でも胃の状態を調べられますが、胃カメラ検査は粘膜の微細な変化や出血の原因、逆流性食道炎、潰瘍などを直接確認できるのが特徴です。

経口と経鼻の違い
経口法は口から内視鏡を入れる一般的な方法で、経鼻法は鼻から内視鏡を入れる方法です。どちらも医師の判断や患者さんの希望、検査機関の設備などに応じて選ばれます。
経鼻法のメリットは「口から挿入するときよりも吐き気が起きにくい」点ですが、鼻腔が狭い場合などは難しい場合があります。
鎮静剤を使って眠ったような状態で行うことも可能なので、過去に検査で苦痛が強かった人や検査に不安を抱える人は、クリニックで相談するとよいでしょう。
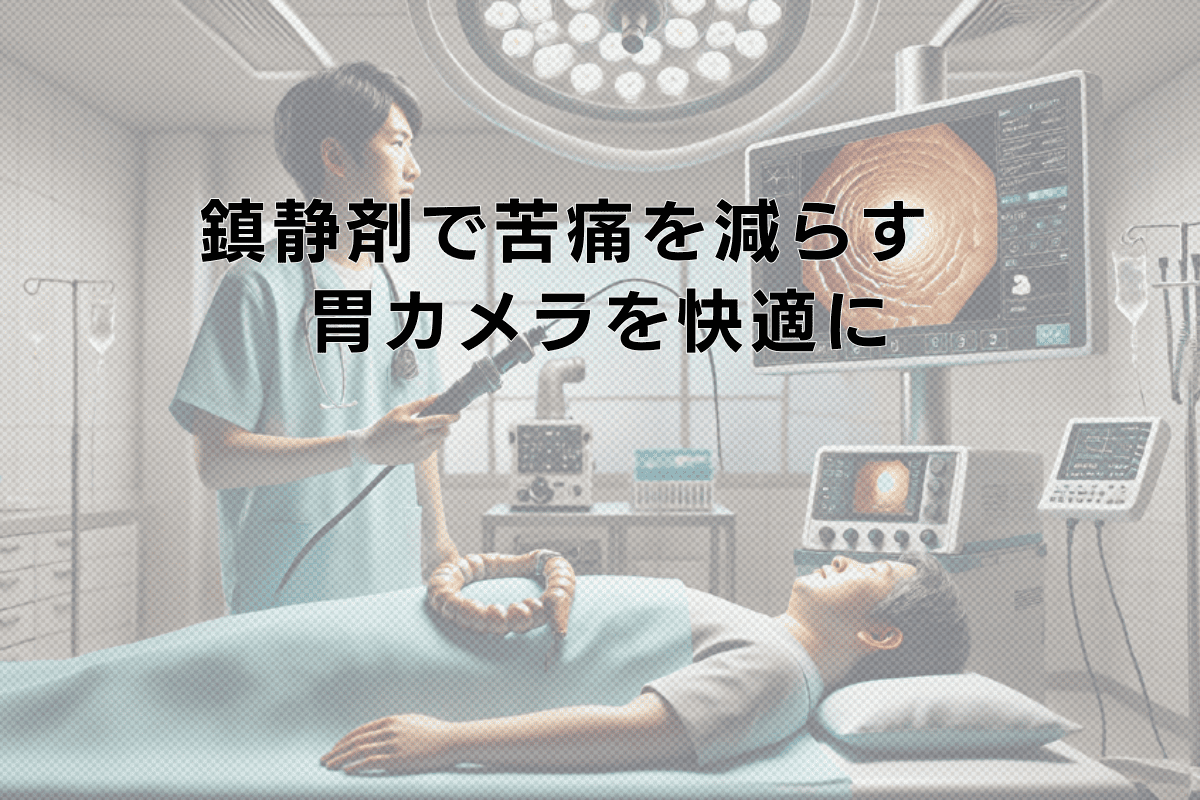
胃がんや胃潰瘍などの早期発見に役立つ
胃カメラ検査は、胃がんや胃潰瘍・十二指腸潰瘍、ピロリ菌による慢性胃炎、逆流性食道炎など幅広い疾患の早期発見に役立ちます。がんや潰瘍は初期段階では症状が軽く、自覚しにくいことが多いです。
検診や健康診断の際に合わせて受ける人も増えており、一度異常が見つかった場合やピロリ菌に感染している場合には、定期的に受けることが推奨されています。
検査所要時間と費用の目安
胃カメラ検査の所要時間は、おおむね5分~15分程度ですが、鎮静剤を使う場合は、検査後の安静時間が必要になるため、30分~1時間程度クリニックや病院で過ごすことが多いです。
費用は保険の適用範囲や行う処置内容、各医療機関の診療形態によっても異なり、保険診療で3割負担の場合、症状がある人の検査であれば、おおむね数千円~1万円前後になります。

胃カメラ前日の基礎知識
胃カメラ検査では、胃の中に食べ物や水分が残りにくい状態を作ることが理想です。前日に食べたものがきちんと消化されずに胃の中に残っていると、観察が不十分になり、検査時間が長引いたり中断したりする原因になることがあります。
脂質の多い食事や食物繊維が多い食品は消化に時間がかかり、胃の中に残りやすい傾向があります。
胃カメラ検査前日は早めの夕食がおすすめ
前日の夕食は、寝る直前ではなく消化の時間をしっかりと確保するために、20時ごろまでに済ませる人が多いです。
医療機関によっては「検査前日は21時までに食事を終わらせてください」と指示することもあり、指示内容や自身の就寝時間に合わせて調整します。食べる時間を早めることで胃が空になりやすく、検査に支障が出にくいです。
アルコールや刺激物は前日から控える
アルコールや香辛料の強い食べ物などは、胃の粘膜を刺激してしまい、消化に負担がかかります。検査の精度に影響が出るリスクを避けるため、胃カメラ検査が決まったら、前日からはなるべく控えるほうが無難です。
また、タバコも胃酸の分泌を促すため、消化器への負担が増す可能性があります。
前日に確認しておきたい服用中の薬
慢性疾患の治療で薬を飲んでいる場合は、必ず主治医からの指示を受けてください。特に糖尿病の薬や血液をサラサラにする抗血小板薬・抗凝固薬などは、検査当日に飲んでよいか、またどのタイミングで飲むかが重要となります。
必要があれば診療予約の段階でクリニックに相談し、疑問点を解消しておきましょう。
胃カメラ前日の食事の基本
ここでは、前日の食事でどのような食べ物が向いているのか、また避けたほうがよい食品は何かを整理します。消化の良い食品や、調理方法の工夫がポイントになります。
避けるとよい食べ物・調理
消化に時間がかかる食品や、胃を刺激しやすい食品は前日に控え、揚げ物や脂肪分の多い肉、硬い繊維の多い野菜、キノコ類、海藻類、唐辛子などは避ける人が多いです。
海藻はヘルシーなイメージがありますが、食物繊維が多く、意外にも胃に残りやすいです。
また、以下のような食品は胃カメラ前日の夕食にはあまり好ましくありません。
前日に避けたい主な食材や料理
- フライ、唐揚げなどの揚げ物
- 脂身の多い肉やベーコンなど
- キノコ類(しいたけ、えのき、しめじなど)
- 海藻類(わかめ、昆布、ひじきなど)
- タコやイカなど、噛み切りにくい食材
- 食物繊維豊富な根菜類(ごぼう、れんこんなど)
- 辛味や刺激物が強い料理
消化に良い食事の具体例
一方、白米やうどん、おかゆ、豆腐、白身魚や鶏ささみのように脂質の少ない食品は消化が良く、前日の食事におすすめで、野菜を摂る場合はやわらかく煮るなどして、繊維が大きく残らないように調理するといいでしょう。
油を控えめにし、味付けは薄味を意識して調整します。
消化しやすい夕食の一例
| 食事内容 | ポイント |
|---|---|
| 主食:やわらかめのご飯またはおかゆ | 繊維が少なく、消化によい |
| 主菜:白身魚の煮付け | 脂質が少なく、胃の負担が比較的軽い |
| 副菜:にんじんや大根を柔らかく煮た煮物 | 食物繊維をやわらかくして消化を促しやすい |
| 汁物:澄まし汁やみそ汁(具少なめ) | 食べやすく水分補給もしやすい |
胃の中に残りやすい食品と注意点
前日に避けるべきかどうか、迷いやすい代表的な食品について挙げます。全く食べられないわけではありませんが、大量に摂取すると検査精度や検査時間に影響する可能性が高まります。
胃に残りやすい代表的な食品
| 食品 | 胃に残りやすい理由 | 控えたいポイント |
|---|---|---|
| 乳製品(牛乳、ヨーグルト) | 胃酸の働きで凝固しやすく、胃に長く留まりやすい | 大量摂取や濃いタイプは避ける |
| 麺類(ラーメン、パスタ) | 油分や塩分が多い場合、消化に時間がかかる | スープやソースも脂質を控える |
| コーヒー | 胃酸分泌を促し、刺激が強くなりがち | 検査前日は控えめにしておく |
| きのこ類 | 繊維が豊富でかみ切りにくく、塊状で残りやすい | よく噛んでも残ることがある |
夕食の時間帯と量のコントロール
寝る直前に食事をすると、胃の消化時間が不十分になるので、前日は20時まで、遅くとも21時までに夕食を済ませるよう調整し、量は普段よりやや少なめを意識してください。眠る直前に高カロリーな食事をすると、消化に余計な負担がかかります。
胃カメラ前日の飲み物と水分摂取
胃カメラ検査の際は、胃を観察しやすい状態に整えるため、水分摂取にも気を配る必要があります。色の濃い飲料やアルコールの扱いなど、迷いがちなポイントを確認しましょう。
水・お茶・スポーツドリンクはおすすめ
前日は適度に水分を摂って問題ありません。普段通り水やお茶を飲むことは大丈夫です。
お茶の場合は緑茶やほうじ茶など、カフェインが含まれるものでも少量なら問題になりにくいですが、心配な場合はノンカフェインのお茶にするとさらに安心です。
またスポーツドリンクは水分補給に便利ですが、糖分が含まれているため、がぶ飲みは避けます。
アルコールは避ける
アルコールは胃や腸を刺激し、出血リスクや嘔吐リスクを高める可能性があり、検査の精度や安全性が損なわれる懸念があるため、前日は控えるよう指示されるのが一般的です。
酔いが覚めずに検査に臨むと、鎮静剤との相互作用も考えられ、危険を伴う場合があります。
濃い色の飲み物やジュースに注意
コーヒー、紅茶、コーラ、果汁ジュースなど、色の濃い飲み物を多量に飲むと、胃の中に沈殿物が残りやすくなることがあります。
全く飲んではいけないというわけではありませんが、心配な人は前日は薄めのお茶や水を中心にし、また牛乳やヨーグルトドリンクなど乳製品ベースの飲み物は胃の中に残りやすくなるため、夜遅い時間には控えてください。
水分摂取量の目安
のどが渇いていないか常に注意して、こまめな水分補給を心がけましょう。脱水状態になると便秘気味になりやすく、体調も崩しがちです。検査前でも適度な水分摂取は推奨されます。
大量に飲む必要はありませんが、合計1リットル~1.5リットル程度の範囲で、日中から夕方にかけて分散して飲んでください。
前日の水分補給に適した飲み物
| 飲み物 | 特徴 |
|---|---|
| 水 | 胃への負担が少なく、24時間いつでも摂取しやすい |
| お茶(緑茶、麦茶、ほうじ茶など) | カフェインが気になる場合はノンカフェインを選択 |
| スポーツドリンク | 電解質補給にもなり便利だが、糖分の摂り過ぎに注意 |
| ハーブティー | 刺激が少ないものを選ぶと負担が軽い |
夕食後から就寝前までの注意点
夕食を無事に終えてから就寝までの時間も大切です。食後の過ごし方や休息の取り方で、検査当日のコンディションが変わる場合があります。
なるべく早めに体を休める
前日は無理な運動や仕事を控え、早めに休むことで当日の体調が整えやすくなります。
胃カメラ検査では緊張や不安から寝付きが悪くなる人もいますが、疲れを蓄積するとかえって検査がつらくなる可能性があるので、早めの就寝を心がけましょう。
仕事がある場合の過ごし方
仕事の都合などでどうしても夕食が遅くなる場合は、消化に悪い食品を避け、一度に大量に食べないよう注意してください。
また、激しい運動や長時間の残業も、体のリズムを乱して睡眠不足につながる恐れがあり、仕事の段取りを工夫し、なるべく体力を温存することが大切です。
タバコを吸う人への注意点
タバコは胃酸の分泌を促し、胃の粘膜を荒らす原因にもなるため、前日のうちは本数を減らすことや、できれば控えることが推奨されます。
どうしても吸いたい場合は検査に支障が出ない範囲で節度を保ち、直前(少なくとも検査当日の朝)は吸うのを避けます。
当日朝に服用する薬の確認
就寝前に飲む薬がある人、起床後すぐに飲む薬がある人は、あらかじめ医師や看護師に確認したうえで従来どおり飲んでよいかチェックしてください。
胃カメラ検査では検査直前の服用を避けるよう指示されるケースもあるため、服用スケジュールを見直す必要があります。
よくある質問
ここでは、胃カメラ検査を初めて受ける人や久しぶりに受ける人から寄せられることの多い質問をピックアップし、簡単にまとめます。事前に疑問を解消しておくと、余裕を持って準備できます。
検査前日に油ものを食べてしまったら?
少量であれば大きな問題にはならない場合が多いですが、量が多かったり時間が遅かったりすると、胃の中に食物が残って観察に支障が出るリスクがあります。
もし前日に重い食事をしてしまったときは、当日の朝に病院やクリニックへ連絡して指示を仰いでください。
水やお茶なら直前まで飲んでも大丈夫?
検査を受ける医療機関の指示によりますが、多くは「検査2~3時間前までは水分を摂ってもよい」とされています。ただし乳製品や果物ジュースなど、成分が多い飲み物は胃に滞留しやすく、検査中に嘔吐リスクが高まる可能性があります。
当日の朝食は何時までに食べられる?
多くのクリニックや病院では胃カメラ検査当日の朝食を控えるよう指示しています。どうしても朝に何か口に入れたい場合でも、前日夜から絶食を指示されるケースがほとんどです。
検査当日朝に水やお茶をどの程度飲んでよいかなど、細かい部分は予約時または前回診察時に確認しておきましょう。
鎮静剤を使うかどうか迷ったとき
検査の苦痛を和らげるために鎮静剤を使う方法がありますが、その後の安静が必要になり、当日の車の運転は控えなければなりません。仕事や家事の都合などとあわせて検討し、医師に相談してください。
当日の検査の流れと留意点
胃カメラ検査当日は来院時や検査直前の準備も大切で、どのような手順で検査を行うのか、大まかな流れを把握しておくことが安心につながります。
受付から検査前の準備
検査を予約したクリニックや内科に来院したら、受付で問診票や保険証などの提出を行い、その後、検査室へ案内されるまでに血圧測定や問診、着替えが行われます。
また、鎮静剤を使用する場合は、同意書にサインすることが求められる場合があります。
口からか鼻からかの選択
医師と相談のうえ、口からの胃カメラ、あるいは鼻からの胃カメラを選択します。
鼻からの内視鏡の場合は局所麻酔用の薬を鼻腔に注入する作業が入り、鼻にチューブを通して十分に通りやすくするステップが追加されます。
一方、口からの胃カメラは咽頭部分の麻酔に加え、鎮静剤を使う場合もあります。
検査中の過ごし方
検査では、長いチューブ状の内視鏡を胃の中まで挿入し、隅々まで観察します。口からの場合は、嘔吐感を感じる人もいますが、できるだけ落ち着いてゆっくり呼吸するように心がけてください。
鎮静剤を使用している場合は半分眠ったような状態で検査を受けるので、苦痛は少なく感じることが多いです。医師がカメラを回転させたり送気したりしながら粘膜をチェックし、必要に応じて組織検査(生検)を行うこともあります。
検査後の説明と注意点
検査終了後、医師から胃の状態や検査結果の概要について説明があります。組織検査を行った場合は、正式な結果は後日別の診療日に受け取ることがほとんどです。
鎮静剤を使用した場合は、回復室などで30分~1時間ほど安静にしてから帰宅し、意識がはっきりしていても、しばらくは車の運転を避けるよう指示されます。
検査後の過ごし方
胃カメラ検査後は、喉や胃に少し刺激を受けている状態ですので、帰宅後や検査当日の食事など、気をつけたいポイントを押さえましょう。
帰宅後の安静と水分摂取
検査直後は喉の麻酔が残っていたり、鎮静剤の影響が続いたりするため、唾液の飲み込みがうまくいかないことがあります。自分の感覚が戻ってきたのを確認してから、少量ずつ水やお茶などを摂り始めてください。
帰宅後はできれば半日程度はゆっくり過ごし、激しい運動や長時間の外出は避けると安心です。
検査当日の食事
医師から特別な指示がなければ、検査後数時間程度経過すれば普通に食事を摂ることができますが、喉に違和感や痛みがある場合は、刺激の少ない食べ物から始めます。
アルコールや香辛料のきいた料理などは、検査当日は控えたほうが無難です。
検査後におすすめの軽めの食事例
| 食事 | 具体例 |
|---|---|
| やわらかい主食 | おかゆ、うどんなど |
| 胃に優しいおかず | 白身魚のやわらかい調理、温野菜 |
| スープ系 | 具が少ないスープや味噌汁 |
| デザート | ゼリーやヨーグルトなど |
生検を行った場合
組織検査(生検)をした場合は、傷口からの出血を防ぐため、当日の飲酒や激しい運動、入浴を控えるように指示を受けることがあります。
場合によっては、数日間程度は消化に良い食事を続けたほうがよいこともあるため、術後・検査後の過ごし方について医師や看護師とよく相談してください。
喉の痛みや違和感があるとき
胃カメラの通過により、喉に少し擦過傷ができたり、むくんだりして痛みを感じることがあります。ほとんどの場合は1日~2日で軽減しますが、痛みが強かったり、発熱や嘔吐などの症状がある場合は、医師に連絡してください。
胃カメラと大腸カメラの同日検査について
場合によっては胃カメラと大腸カメラを同日に受ける人もいて、さまざまなメリットがありますが、大腸カメラの前処置が必要になるため、前日の食事制限が厳格になります。
専用食を利用する選択肢もありますので、医療機関が指示する内容に合わせて食事管理をすることが大切です。
同日検査のメリット
- 一度の鎮静剤で両方の検査を受けられる
- 複数日の通院や検査時間を省略できる
- 症状の原因が胃腸にまたがっている場合、一度に観察できる
同日検査の注意点
- 大腸カメラ前の下剤服用により、十分な排便が必要になる
- 前日の食事がより制限される(繊維質を減らす必要が強い)
- 検査後の安静時間や体調管理もまとめて必要になる
胃カメラ検査と大腸カメラ検査を同日に行う前日の食事例
| 時間帯 | 食事の例 | ポイント |
|---|---|---|
| 朝食 | 消化の良いパン1枚+豆腐やたまご+薄めのスープ | 繊維の多い食材や脂質を抑え、あっさりした朝食を心がける |
| 昼食 | うどん、素うどん+とろろ昆布のトッピングなど | 海藻類は少量、具材もシンプルに |
| 夕食 | 大腸カメラ専用食または軽いおかゆ+やわらかいおかず | 医療機関で推奨される食事をできるだけ守る |
ポリープ切除が必要になった場合
大腸カメラでポリープを見つけた場合、その場で切除を行うケースがあります。
医師が総合的に判断し、術後の食事や生活の指導を行います。また、切除後の大腸出血リスクがあるため、アルコールや激しい運動はしばらく控えることが大切です。
検査に向けた準備のまとめと受診の目安
胃カメラ検査で正確な結果を得るためには、前日の食事や飲み物に気を配りながら、無理のない生活リズムを心がけることが重要です。ここで、前日・当日までの流れを簡単に振り返ります。
胃カメラ前日と当日のチェックリスト
- 前日の夕食
- 消化の良い食材(うどん、おかゆ、白身魚、豆腐など)を選ぶ
- 夜遅くなりすぎないよう、20~21時までに食事を終える
- アルコール、脂質の多い料理、刺激物、食物繊維が多い食品は控える
- 前日の水分補給
- 水やお茶を中心に、必要に応じてスポーツドリンクも取り入れる
- 牛乳やジュース、コーヒーなどは控えめに
- 当日朝
- 基本的に絶食だが、水やお茶なら検査2~3時間前程度までは少量摂取してよい場合が多い
- 糖尿病などの薬を服用している人は、医師の指示に従う
- 鎮静剤を使う場合は車の運転を控えるように予定を調整する
- 検査中
- リラックスを心がけ、口から挿入の場合は軽く唾を吐き出すイメージで呼吸に集中する
- 鼻から挿入の場合は局所麻酔の薬液を十分に浸透させ、違和感があってもなるべく落ち着く
- 検査後
- 結果の簡単な説明を受け、組織検査の有無に応じて帰宅までの時間を過ごす
- 鎮静剤使用時は意識がはっきりしていても、当日の車の運転や危険作業は避ける
- 喉や胃に違和感がある場合は無理せず消化の良い食事を少量ずつ摂る
胃がんや逆流性食道炎などの疑いがある場合
胸焼けや胃痛、吐き気、黒い便、慢性的な胃もたれなどの症状がある場合、早期発見のためにも医療機関で相談し、症状に応じて胃カメラ検査を受けるのがおすすめです。
早期に受診することで、胃がんなどの重大な疾患を見つけられる可能性が高まり、その後の治療計画も立てやすくなります。
まとめ
胃カメラ検査は、胃や食道、十二指腸の状態を詳しく調べ、逆流性食道炎や胃潰瘍、胃がんなど、さまざまな疾患を早期に発見できる重要な方法です。
検査前日は消化に良い食事を選ぶ、アルコールや刺激物を控える、水やお茶などの水分をしっかり摂る、就寝時間を早めて体を休めるなどの準備が求められます。
当日は医師や看護師の説明を十分に聞き、鎮静剤の使用や検査後の過ごし方について相談しながら、なるべくリラックスして検査を受けてください。
次に読むことをお勧めする記事
【胃カメラで分かる症状 検査の流れ】
胃カメラ前日の準備について理解が深まったら、次は実際の検査当日の流れについて知っておくと安心です。初めて検査を受ける方に特に参考になる内容です。
【鎮静剤で苦痛を減らす 胃カメラを快適に受けるために】
胃カメラの準備について学んだ皆さんには、鎮静剤の知識も合わせて持っていただくと、より安心して検査を受けることができます。
参考文献
Callaghan JL, Neale JR, Boger PC, Sampson AP, Patel P. Variation in preparation for gastroscopy: lessons towards safer and better outcomes. Frontline Gastroenterology. 2016 Jul 1;7(3):187-90.
Coleman WH. Gastroscopy: a primary diagnostic procedure. Primary Care: Clinics in Office Practice. 1988 Mar 1;15(1):1-1.
Shi Y, Zhang X, Wang Y, Shi W, Xing X. Effect of different gastric mucosa preparation programs on the quality of painless gastroscopy. Chinese Journal of Practical Nursing. 2024 Jun 1;40(1):8-12.
Callaghan J, Neale J, Boger P, Patel P. PTU-211 Patient preparation prior to gastroscopy: a UK wide survey. Gut. 2012 Jul 1;61(Suppl 2):A271-2.
Adamiec C, Dyrla P, Gil J, Nowak T, Wołyńska-Szkudlarek A, Bobula M. Preparation for gastroscopy by premedication as a criterion of high quality endoscopy. Paediatrics and Family Medicine. 2017;13(2):170.
Ortega-Moya SP, Martínez-Cabrera I, Guzmán MT, Miyashiro EI, Moreno JR. Visualization of mucosa by gastroscopy evaluation using pre-preparation procedure with simethicone. Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research. 2022;10(2):318-27.
Fourie L, Nell V. Psychological preparation for gastroscopy: A brief intervention reduces patient stress more than a detailed intervention. South African Journal of Psychology. 1990 Mar;20(1):25-31.
Parahoo K, Ridley T, Thompson K, Melby V, Humphreys G. A qualitative evaluation of information leaflets for gastroscopy procedure. Journal of evaluation in clinical practice. 2003 Nov;9(4):423-31.
Li J, Liu Y, Lin H, Huang J, Zhang C. Feasibility study of shortening the no drinking time before gastroscopy to two hours. Digestive Medicine Research. 2021 Mar 30;4.
Greenfield SM, Webster GJ, Brar AS, Mun KA, Beck ER, Vicary FR. Assessment of residual gastric volume and thirst in patients who drink before gastroscopy. Gut. 1996 Sep 1;39(3):360-2.