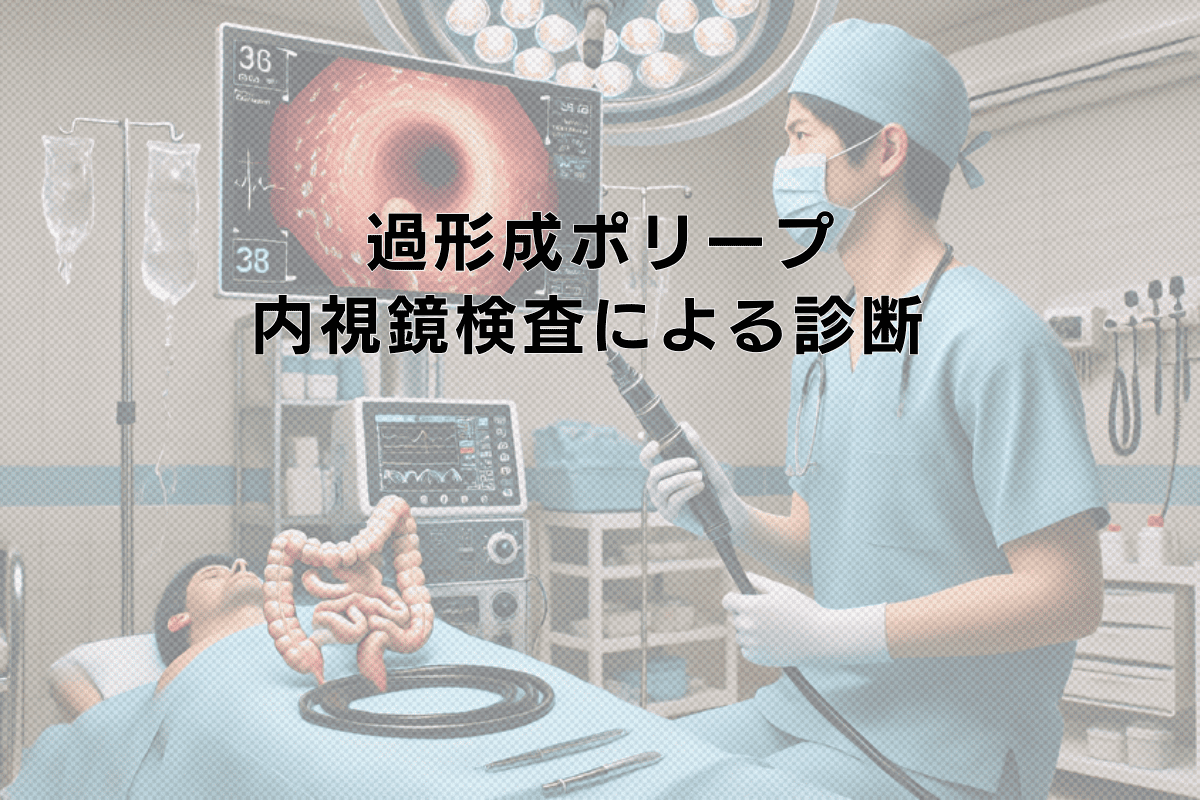大腸カメラ検査を受けると、しばしばポリープが見つかり、その中でも最も頻繁に発見されるものの一つが過形成ポリープです。
このポリープは、基本的には良性であり、がん化する可能性は極めて低いと考えられていますが、まれにがん化のリスクを持つ特殊なタイプもあるため、正確な診断が重要です。
この記事では、過形成ポリープとは何か、特徴や原因、なぜ内視鏡による専門的な診断が必要なのかを詳しく解説します。
過形成ポリープとは何か
過形成ポリープは、大腸の粘膜にできるイボのような隆起物の一種です。大腸ポリープの中でも最も一般的なタイプであり、多くの場合、健康診断や人間ドックの大腸内視鏡検査(大腸カメラ)で偶然発見されます。
ポリープの基本的な定義
ポリープとは、消化管などの粘膜から内側に向かってきのこ状やイボ状に盛り上がった組織全般を指す言葉で、特定の病名ではなく、あくまでも組織の形状を表現する医学用語です。
ポリープには、将来的にがんになる可能性を持つ腫瘍性のものと、その可能性が極めて低い非腫瘍性のものがあります。過形成ポリープは、後者の非腫瘍性ポリープの代表格です。
大腸の粘膜細胞が過剰に増殖した結果として形成されますが、増殖は細胞の寿命が延びたことによるもので、がん細胞のように無秩序に増え続けて周囲の組織を破壊するような悪性の性質は持っていません。
過形成ポリープの発生原因
過形成ポリープは、複数の要因が複雑に関与していると考えられていますが、最も大きな要因として挙げられるのが加齢です。
年齢を重ねると、大腸粘膜の細胞が新しく生まれ変わるサイクル(ターンオーバー)に軽微な乱れが生じやすくなります。
このサイクルが正常に機能しなくなると、古い細胞が適切に排出されずに残り、積み重なることでポリープを形成するのです。
また、食生活の欧米化、特に高脂肪・低繊維の食事は腸内環境を変化させ、ポリープ発生の一因となる可能性があります。
さらに、喫煙、過度のアルコール摂取、肥満といった生活習慣も、大腸粘膜への慢性的な刺激や炎症を起こし、発生リスクを高めることが多くの研究で指摘されています。
大腸ポリープの分類
| 分類 | 代表的なポリープ | 特徴 |
|---|---|---|
| 非腫瘍性ポリープ | 過形成ポリープ | 細胞の過剰な増殖によるもので、基本的にはがん化しない。 |
| 非腫瘍性ポリープ | 炎症性ポリープ | 潰瘍性大腸炎など、腸の炎症が治る過程で形成される。 |
| 腫瘍性ポリープ | 腺腫性ポリープ | がん化する可能性があり、前がん病変と位置づけられる。 |
他のポリープとの違い
大腸ポリープには過形成ポリープ以外にも、さまざまな種類があり、臨床現場で特に重要視されるのが、がん化する可能性のある腺腫性ポリープ(腺腫)との鑑別です。
内視鏡検査でポリープが発見された際、がん化リスクの低い過形成ポリープなのか、それとも将来的ながんを防ぐために切除を検討すべき腺腫なのかを正確に見分けることが、専門医の重要な役割となります。
一般的な過形成ポリープは、通常、白っぽく平坦な形状をしていますが、腺腫は赤みを帯びていたり、表面が脳回状にゴツゴツしていたりすることが多いです。
しかし特徴は絶対的なものではなく、小さな腺腫が過形成ポリープのように見えることもあります。
見た目だけで100%の判断を下すのは難しく、特殊な光を用いた画像強調観察や拡大観察、必要に応じて組織の一部を採取する生検による病理組織診断が大事です。
過形成ポリープの主な特徴と症状
過形成ポリープは、見た目や大きさ、症状の有無においていくつかの特徴を持っていますが、それはあくまで一般的な傾向であり、最終的な診断は内視鏡専門医による総合的な評価が不可欠です。
見た目の特徴
内視鏡で大腸内を観察した際、過形成ポリープは一般的に周囲の正常な粘膜と同じような色調、あるいはやや白っぽく褪色して見え、形状は平坦なもの(表面型)や、なだらかに盛り上がっているもの(隆起型)がほとんどです。
表面は滑沢でつるりとしており、拡大して観察すると点状の血管が規則正しく透けて見えることもあります。これは、がん化するポリープに見られるような不規則で太い血管とは異なる所見です。
腺腫性ポリープがしばしば示すような強い赤みや、表面の凹凸は少ない傾向にあり、肛門に近い直腸やS状結腸といった大腸の左側に多く見られます。
サイズによる分類
過形成ポリープの大多数は、直径5mm以下の小さなものです。
このサイズのポリープは、がん化のリスクが限りなくゼロに近いと考えられているため、通常は切除の対象とはならず、定期的な経過観察が選択されますが、まれに10mm以上にまで大きくなることもあります。
一般的に、10mmを超える大きな過形成ポリープ、特に大腸の右側(盲腸や上行結腸など、肛門から遠い部位)に発生したものは、がん化する潜在能力を持つ鋸歯状病変という特殊なタイプである可能性を考慮しなくてはなりません。
ポリープの大きさと対応の目安
| サイズ | 一般的な対応 | 備考 |
|---|---|---|
| 5mm以下 | 経過観察 | がん化のリスクは極めて低い。 |
| 6mm~9mm | 経過観察または切除を検討 | 場所や形状によって判断が分かれる。 |
| 10mm以上 | 切除を推奨 | がん化の可能性がある鋸歯状病変との鑑別が重要。 |
自覚症状はほとんどない
過形成ポリープが原因で、腹痛や下痢、便秘といった何らかの自覚症状が現れることはなく、ポリープが小さいうちはもちろん、ある程度の大きさになっても同様です。
ポリープが非常に大きくなった場合には、まれに便が通過する際に擦れて出血し、便に血が混じったり(血便)、便潜血検査で陽性となったりすることがありますが、これは極めて例外的なケースになります。
ほとんどの場合、症状が全くないまま進行するため、自分自身でポリープの存在に気づくことは不可能です。
過形成ポリープとがん化のリスク
過形成ポリープと診断された際に、多くの方が最も心配されるのが、がん化の可能性ですが、一般的な過形成ポリープが直接がんになることはありません。
しかし、近年では見た目が酷似しており、がん化する可能性のある特殊なタイプのポリープの存在が広く知られるようになり、両者を正確に鑑別することが非常に重要視されています。
基本的にはがん化しない良性のポリープ
従来から知られている、ごく一般的な過形成ポリープは非腫瘍性のポリープであり、定義上、良性です。細胞の核に異型(がん細胞に見られるような形の異常)がなく、正常な細胞の範囲内での増殖にとどまります。
内視鏡検査で色調や表面構造から典型的な過形成ポリープと判断された小さなポリープは、無理に切除する必要はなく、定期的な経過観察で十分です。
がん化の可能性がある特殊なタイプ(鋸歯状病変)
近年重要性が注目されているのが、鋸歯状病変(きょしじょうびょうへん)と呼ばれる一連のポリープ群で、顕微鏡で組織を観察すると、腺管の構造がノコギリの歯のようにギザギザしていることから、このように名付けられました。
鋸歯状病変は、従来の大腸がんの発生経路として知られていた腺腫とは異なる、特殊な遺伝子異常を介してがんを発生させることが分かってきました。
過形成ポリープと鋸歯状病変の比較
| 項目 | 一般的な過形成ポリープ | 鋸歯状病変 (SSLなど) |
|---|---|---|
| がん化リスク | ほとんどない | あり |
| 主な発生部位 | 直腸・S状結腸(左側) | 盲腸・上行結腸(右側) |
| 内視鏡での見え方 | 平坦で色が薄い | 粘液が付着し、境界が不鮮明なことがある |
鋸歯状病変のさらなる理解
鋸歯状病変はさらにいくつかのタイプに分類され、代表的なものに、sessile serrated lesion(SSL)や、Traditional serrated adenoma(TSA)があります。
特にSSLは、平坦で境界が不明瞭、表面に粘液が付着していることが多く、通常の観察で見逃されやすく、また、主に大腸の右側に発生し、急速にがんに進行することがあるため、注意が必要です。
内視鏡医は、粘膜の色調のわずかな変化や血管の走行パターン、粘液の付着具合など、微細な所見を捉えてこのような病変を診断します。
疑わしい場合は、インジゴカルミンなどの色素を散布して病変の輪郭を明瞭にしたり、拡大観察を行ったりして、より詳細な評価を行います。
リスクを高める要因
過形成ポリープは、遺伝的な素因も一部関係すると考えられていますが、やはり生活習慣が大きく影響します。
喫煙は、発がん物質が血流を介して大腸粘膜に到達し、細胞の遺伝子にダメージを与えることでポリープの発生を促進し、過度のアルコール摂取は、代謝の過程で生じるアセトアルデヒドが同様に粘膜を傷つけます。
また、肥満、特に内臓脂肪の蓄積は、インスリン抵抗性を起こし、細胞増殖を促す物質の分泌を高めることが知られていて、動物性脂肪や赤肉中心の食生活は、腸内の悪玉菌を増やし、発がんを促進する腸内環境を作り出すと考えられています。
- 喫煙
- 過度のアルコール摂取
- 肥満(特に内臓脂肪)
- 動物性脂肪や赤肉中心の食生活
内視鏡検査による診断の重要性
過形成ポリープの存在を確実に知り、それが心配のない良性のものであるか、あるいは切除を考慮すべき特殊なタイプなのかを判断する唯一の方法が、大腸内視鏡検査です。
早期発見の唯一の手段
過形成ポリープや類似病変には自覚症状がないため、知らないうちに発生し、気づかないまま大きくなっている可能性があります。
症状が出てからでは進行がんとして発見されることもある大腸がんとは異なり、ポリープは症状のない無症状の段階で発見し、性質を正確に評価した上で対処することが予防の基本になります。
大腸内視鏡検査は、ミリ単位の非常に小さなポリープも見つけ出すことが可能な、極めて感度の高い検査法です。
確定診断の流れ
内視鏡検査では、まず高解像度のカメラを通してモニターに映し出される大腸の内部を、空気や二酸化炭素で広げながら隅々まで観察し、ポリープが見つかった場合、形、色、大きさ、表面の模様、硬さなどを多角的に評価します。
経験豊富な専門医であれば、見た目から、ポリープが過形成ポリープなのか、腺腫なのか、あるいは早期がんなのかを、ある程度の精度で推測することが可能です。
しかし、最終的な確定診断を下すためには、ポリープの一部または全体を採取し、それを顕微鏡で詳しく調べる病理組織診断が必要です。
内視鏡診断で用いられる観察技術
| 観察方法 | 原理 | 目的 |
|---|---|---|
| 通常光観察 | 白色の光で粘膜を照らす。 | ポリープの存在や大きさ、形状を把握する。 |
| 画像強調観察(NBIなど) | 特殊な光で血管や表面構造を強調する。 | ポリープの種類の鑑別や、がん化の可能性を評価する。 |
| 拡大観察 | 最大で約100倍まで拡大して観察する。 | 粘膜表面の微細な模様(ピットパターン)を評価し、より正確な診断を行う。 |
内視鏡検査の準備と当日の流れ
大腸内視鏡検査を安全かつ正確に実施するためには、事前の準備が非常に重要で、目的は、大腸の中を空っぽにして、粘膜をきれいに洗い流し、観察しやすい状態にすることです。ここでは、検査の準備から当日の流れ、検査後までを説明します。
検査前の食事制限
通常、検査の前日は、消化の良い食事を心がける必要があります。食物繊維を豊富に含む野菜(ごぼう、きのこ類など)や海藻類、種のある果物(キウイ、いちごなど)は、消化されにくく腸内に残りやすいため、避けましょう。
うどん、おかゆ、豆腐、白身魚、鶏のささみなどが推奨されます。多くの医療機関では、検査を受ける方向けに専用の検査食(レトルト食のセット)が用意されていて、活用すると、献立に悩む必要がなく、安心して食事制限を行えます。
水分摂取は非常に重要で、脱水を防ぎ、腸をきれいにするためにも、水やお茶、スポーツドリンクなど、色のついていない透明な飲み物を積極的に摂取してください。
検査前日に避けるべき食品の例
| 分類 | 具体的な食品名 | 避ける理由 |
|---|---|---|
| 繊維の多い野菜 | ごぼう、きのこ類、海藻類 | 消化されにくく、腸内に残りやすい。 |
| 種のある果物 | いちご、キウイ、スイカ | 種が腸壁に残り、スコープの視野を妨げる。 |
| 脂肪の多い食品 | 揚げ物、バター、ラーメン | 消化に時間がかかり、腸の動きを悪くする。 |

下剤の服用について
検査当日の朝、または前日の夜と当日の朝の2回に分けて、腸管洗浄液(下剤)を服用します。
約1.5リットルから2リットルの液体を、数時間かけてゆっくりと飲み進めます。近年では、味のついた飲みやすいタイプや、錠剤と少量の液体を組み合わせるタイプなど、様々な種類の下剤が登場し、以前よりも負担は軽減されています。
服用を開始してしばらくすると便意が始まり、何度かトイレに通うことになり、最終的に、便が固形物を全く含まない、黄色く澄んだ透明な液体になれば、腸内がきれいになったサインであり、検査の準備は完了です。
検査当日の手順
予約時間に合わせて医療機関に到着したら、まず問診や体調の確認を行い、検査着に着替え、その後、検査室に移動し、ベッドに左側を下にして横になります。検査に伴うお腹の張りや不快感を和らげるために、鎮静剤を使用することが一般的です。
腕の静脈から薬を投与しうとうとと眠っているようなリラックスした状態になると、医師が肛門から内視鏡をゆっくりと挿入し、モニターで内部を確認しながら、大腸の一番奥にある盲腸まで進めます。
その後、スコープを抜きながら、ひだの裏側なども含めて粘膜を詳細に観察していき、検査時間自体は、およそ15分から30分程度です。ポリープが見つかった場合、その場で切除することもあります。
過形成ポリープが見つかった後の対応
内視鏡検査で過形成ポリープが見つかった場合、画一的な方針があるわけではなく、ポリープの大きさ、形状、組織の種類、個数、患者さん自身の年齢や既往歴などを総合的に考慮して、個別に方針が決定されます。
経過観察という選択肢
発見されたポリープが直径5mm以下の小さなもので、色調や表面構造から典型的な過形成ポリープと診断された場合は、特別な処置は行わず、そのまま経過観察となるのが最も一般的です。
次回の内視鏡検査の推奨時期は、他に腺腫などのポリープがなかったか、大腸がんの家族歴といった他のリスク要因を考慮して総合的に判断されますが、通常は2年から5年後が目安となります。
フォローアップ検査の間隔の目安
| 検査所見 | 推奨される次回の検査時期 | 根拠 |
|---|---|---|
| 異常なし | 5年後 | リスクが低いと考えられるため。 |
| 小さな過形成ポリープのみ | 5年後 | 異常無しと同じ扱い。 |
| 腺腫を切除した | 1~3年後 | 再発や見逃しのないことを確認するため。 |

ポリープ切除が必要な場合
一方で、ポリープ切除(ポリペクトミー)が推奨されるケースもあります。
ポリープが10mm以上の大きさである場合、がん化のリスクがある鋸歯状病変の可能性が否定できない場合、あるいは見た目だけでは良性の過形成ポリープと腺腫との鑑別が難しい場合などです。
切除は、治療であると同時に、ポリープ全体を回収して病理組織検査にかけることで、最も正確な診断(確定診断)を下すという目的も兼ねています。
切除は内視鏡を用いて行われるため、お腹を切る必要はなく、体への負担が少ないのが少なく、通常、痛みを感じることはありません。
切除で用いられる主な手技
従来から行われているのは、内視鏡の先端からスネアと呼ばれる輪っか状のワイヤーを出し、ポリープの根元に引っ掛けて高周波電流を流して焼き切る「ホットスネアポリペクトミー」で、止血効果が高いのが利点です。
ただし近年では、通電せずにスネアを絞めるだけで機械的に切除する「コールドスネアポリペクトミー」が主流になりつつあります。
この方法は、切除後の出血や穿孔といった合併症のリスクが低いとされ、小さなポリープに対して安全に行うことができます。どちらの方法を選択するかは、ポリープの大きさや形状によって医師が判断します。
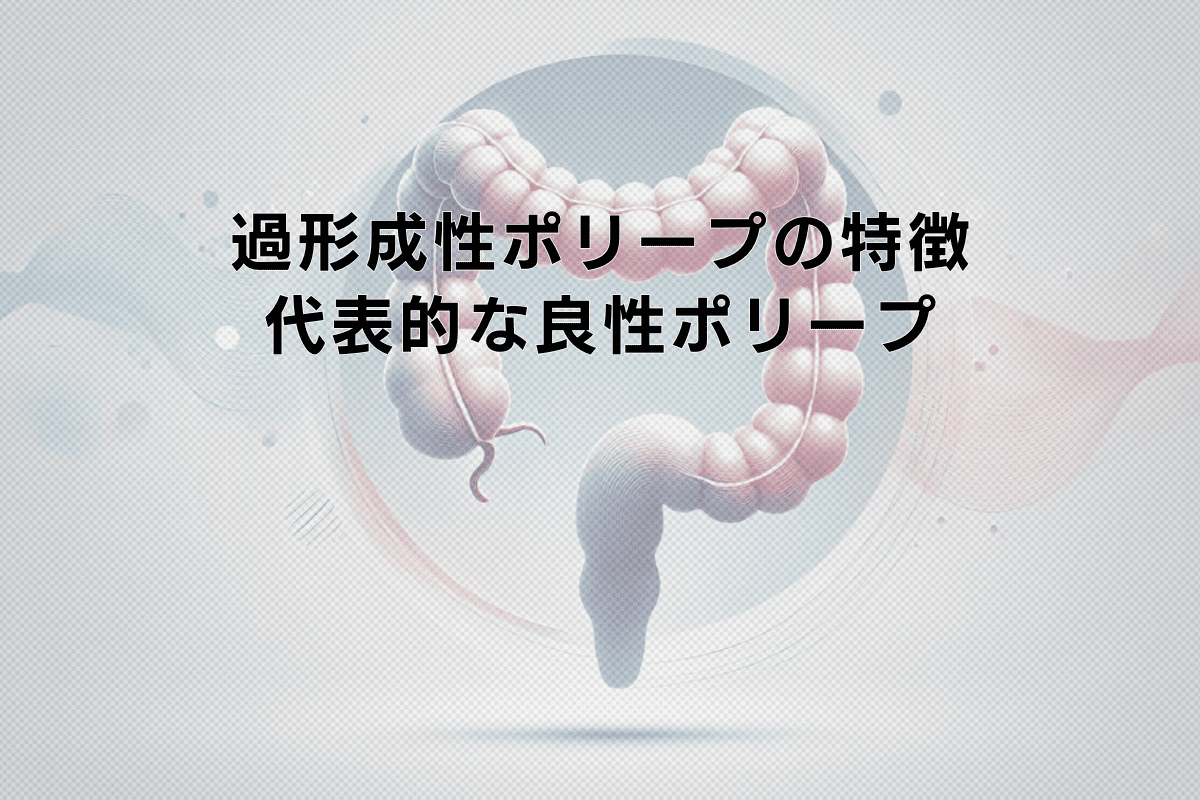
切除後の注意点
ポリープを切除した後は、偶発症と呼ばれる合併症(出血や穿孔など)を防ぐために、いくつかの注意点があり、最も重要なのは、食事と生活の制限です。
切除当日は消化の良い食事にとどめ、アルコール飲料や香辛料の強い刺激物は、腸管の安静を保つため、1週間程度は避ける必要があります。
また、血圧が上昇するような激しい運動や、長時間の入浴、腹圧のかかる仕事、遠方への旅行なども、後から出血するリスクを高めるため、一定期間控えるように指示されます。
切除後の生活制限の目安
| 項目 | 制限期間の目安 | 理由 |
|---|---|---|
| アルコール摂取 | 約1週間 | 血管を拡張させ、出血のリスクを高めるため。 |
| 激しい運動 | 約1週間 | 血圧や腹圧の上昇により、後出血を誘発する恐れがあるため。 |
| 長距離移動・旅行 | 約1週間 | 万が一の出血時に、迅速な医療対応が困難になるため。 |
過形成ポリープの予防と生活習慣
過形成ポリープの発生を100%防ぐ確実な方法はありませんが、リスクを低減させるために日々の生活習慣を見直すことは非常に有効です。毎日の小さな積み重ねが、将来の大きな病気を防ぐ力になります。
食生活の見直し
健康な大腸を維持するための食事の基本は、バランスの取れた食生活です。食物繊維を豊富に含む野菜、果物、海藻、きのこ類、全粒穀物を積極的に摂取することが推奨されます。
食物繊維は便のカサを増やして便通を整え、腸内の発がん性物質や有害物質が腸の粘膜に接触する時間を短くする働きがあります。
動物性脂肪や赤肉(牛肉、豚肉、羊肉など)および加工肉(ハム、ソーセージなど)の過剰な摂取は、腸内環境を悪化させ、悪玉菌を増やす原因となるため、控えめにしましょう。
また、発酵食品であるヨーグルト、納豆、味噌などを日々の食事に取り入れることも、腸内の善玉菌を増やし、腸内フローラのバランスを整える上で役立ちます。
腸の健康をサポートする栄養素
| 栄養素 | 多く含む食品 | 期待される働き |
|---|---|---|
| 食物繊維 | 野菜、豆類、きのこ類 | 便通を改善し、腸内環境を整える。 |
| オリゴ糖 | 玉ねぎ、ごぼう、バナナ | 善玉菌のエサとなり、その働きを活発にする。 |
| 乳酸菌・ビフィズス菌 | ヨーグルト、チーズ、味噌 | 腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌を抑制する。 |
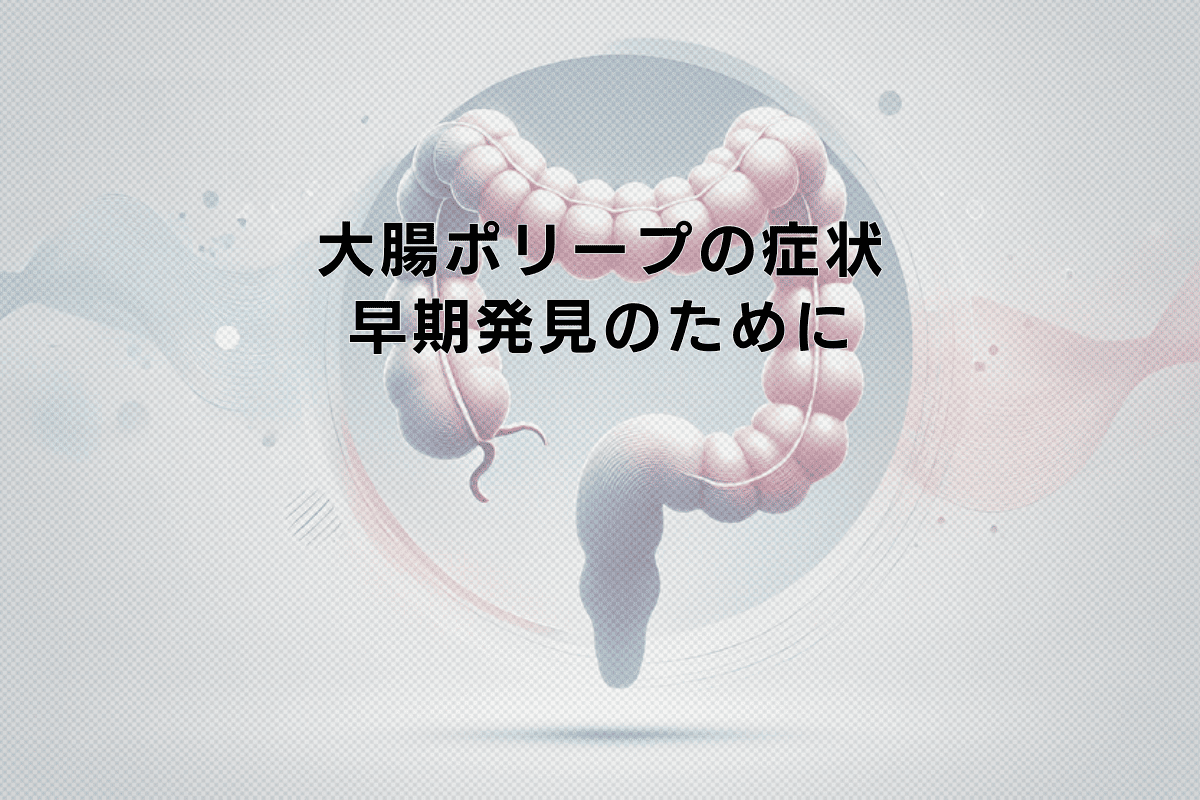
適度な運動の習慣
定期的な身体活動は、全身の健康に良いだけでなく、大腸の健康維持にも直接的に貢献し、腸の蠕動(ぜんどう)運動、すなわち便を前に押し出す動きを活発にし、便秘の解消に役立ちます。
便が腸内に長くとどまることは、有害物質と粘膜の接触時間を長くするため避けるべきで、また、運動は肥満の予防・解消にもつながり、ポリープ発生のリスクを間接的に低下させます。
ウォーキングや軽いジョギング、水泳といった有酸素運動を、週に合計150分程度行うのが理想的です。
定期的な検診の大切さ
最も重要な予防策は、定期的な大腸内視鏡検査を受けることです。生活習慣の改善はポリープ発生のリスクを確実に減らすことはできますが、残念ながらゼロにすることはできません。
遺伝的な要因など、自分でコントロールできない要素も存在するためです。大腸がんのリスクが上がり始める40歳を過ぎたら、症状が全くなくても一度は大腸内視鏡検査を受けることが強く推奨されます。
検査でポリープが見つからなければ、当面は安心して過ごせますし、もしポリープが見つかったとしても、小さいうちであれば、簡単な処置で将来のがん化の芽を摘むことができます。
有効な予防策
- 禁煙
- 節度ある飲酒
- 適正体重の維持
過形成ポリープに関するよくある質問
- 過形成ポリープは何歳くらいから注意が必要ですか?
-
過形成ポリープ自体はどの年代でも発生する可能性がありますが、一般的に年齢とともに発生頻度は高くなります。大腸がんのリスクが高まり始める40歳を一つの目安として、大腸の健康に関心を持つことが推奨されます。
症状がなくても、40歳を過ぎたら一度、大腸内視鏡検査を検討するのが良いでしょう。ただし、家族歴などによっては、より早期からの検査が勧められることもあります。
- 過形成ポリープは遺伝しますか?
-
過形成ポリープそのものが直接的に遺伝するわけではありませんが、ポリープができやすい体質、つまり遺伝的素因が関係する可能性は考えられます。
血縁関係の近いご家族に大腸がんや多数の大腸ポリープになった方がいる場合は、一般の方に比べてポリープやがんの発生リスクが高まることが知られています。
- 便潜血検査で陰性なら、内視鏡検査は不要ですか?
-
便潜血検査は、大腸がん検診として広く行われている有効な検査ですが、万能ではありません。
この検査は、ポリープやがんからの微量な出血を検出するものなので、出血していない早期のがんや、ほとんど出血しない過形成ポリープや腺腫を見つけることはできません。
便潜血検査が陰性であっても、内視鏡検査で進行がんが見つかるケースもあります。便潜血検査が陰性であることは、あくまで「現時点で出血する病変はない可能性が高い」ことを示すに過ぎません。
大腸の健康状態を確実にチェックするためには、内視鏡検査が最も信頼性の高い方法です。
- ポリープを切除すれば、もう安心ですか?
-
ポリープを切除することは、ポリープが将来がん化するのを防ぐ上で非常に有効な手段ですが、一度ポリープができたということは、その方の大腸が「ポリープができやすい環境」にあることを示唆しています。
今回切除した場所以外に、将来また新しいポリープが発生する可能性があるので、切除後もそれで終わりではなく、定期的に内視鏡検査を受け、大腸全体の健康状態を継続的に見守っていくことが非常に重要です。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
過形成ポリープの基本を押さえたら、次は実際の大腸内視鏡検査の準備について知っておくと安心です。初めて検査を受ける方や、検査前の不安を解消したい方に特に参考になる内容です。
【大腸がん検査方法の選び方 – 血液検査から内視鏡検査まで】
内視鏡以外の選択肢や、それぞれの長所・短所も知っておくと納得感が高まります。ご自身のリスクに応じた検査計画づくりの参考に。
以上
参考文献
Hongo M, Fujimoto K, Gastric Polyps Study Group. Incidence and risk factor of fundic gland polyp and hyperplastic polyp in long-term proton pump inhibitor therapy: a prospective study in Japan. Journal of gastroenterology. 2010 Jun;45(6):618-24.
Miwata T, Hiyama T, Oka S, Tanaka S, Shimamoto F, Arihiro K, Chayama K. Clinicopathologic features of hyperplastic/serrated polyposis syndrome in Japan. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2013 Nov;28(11):1693-8.
Shida Y, Ichikawa K, Fujimori T, Fujimori Y, Tomita S, Fujii T, Sano Y, Oda Y, Goto H, Ohta A, Tanaka S. Differentiation between sessile serrated adenoma/polyp and non-sessile serrated adenoma/polyp in large hyper plastic polyp: A Japanese collaborative study. Molecular and Clinical Oncology. 2013 Jan 1;1(1):53-8.
Toyoshima O, Nishizawa T, Watanabe H, Matsuno T, Yoshida S, Takahashi Y, Mizutani H, Ebinuma H, Fujishiro M, Saito Y. Endoscopic characteristics to differentiate SSLs and microvesicular hyperplastic polyps from goblet cell-rich hyperplastic polyps. Endoscopy International Open. 2024 Nov;12(11):E1251-9.
Chiba H, Tachikawa J, Arimoto J, Ashikari K, Kuwabara H, Nakaoka M, Goto T, Higurashi T, Muramoto T, Ohata K, Nakajima A. Endoscopic submucosal dissection of large pedunculated polyps with wide stalks: a retrospective multicenter study. Endoscopy. 2021 Jan;53(01):77-80.
Hasegawa R, Yao K, Ihara S, Miyaoka M, Kanemitsu T, Chuman K, Ikezono G, Hirano A, Ueki T, Tanabe H, Ota A. Magnified endoscopic findings of multiple white flat lesions: a new subtype of gastric hyperplastic polyps in the stomach. Clinical Endoscopy. 2018 Nov 21;51(6):558-62.
Hizawa K, Fuchigami T, Iida M, Aoyagi K, Iwashita A, Daimaru Y, Fujishima M. Possible neoplastic transformation within gastric hyperplastic polyp: application of endoscopic polypectomy. Surgical endoscopy. 1995 Jun;9(6):714-8.
Sano W, Sano Y, Iwatate M, Hasuike N, Hattori S, Kosaka H, Ikumoto T, Kotaka M, Fujimori T. Prospective evaluation of the proportion of sessile serrated adenoma/polyps in endoscopically diagnosed colorectal polyps with hyperplastic features. Endoscopy international open. 2015 Aug;3(04):E354-8.
Kuribayashi K, Ishii T, Ishidate T, Ban N, Hirata Y, Hashida H, Saito K, Iwashiro N, Ohara M, Ishizaka M, Azuma M. Two cases of inverted hyperplastic polyps of the colon and association with adenoma. European journal of gastroenterology & hepatology. 2004 Jan 1;16(1):107-12.
Nishizawa T, Watanabe H, Yoshida S, Matsuno T, Nakagawa H, Tamada K, Ebinuma H, Fujishiro M, Saito Y, Toyoshima O. Hyperplastic polyp-like adenoma: a subtype of colonic adenoma with a proliferative zone confined to the lower two-thirds of the crypt. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 2024 Mar 3;59(3):378-83.