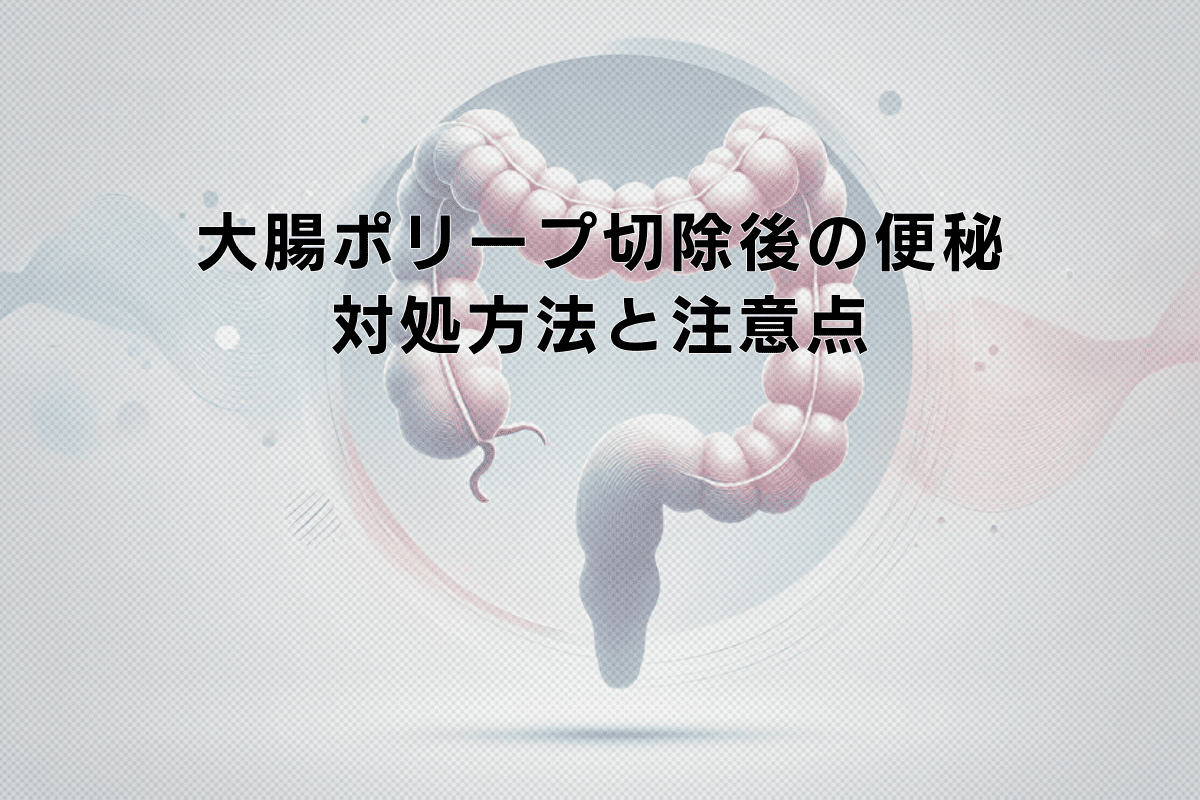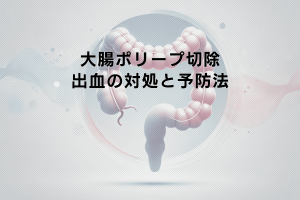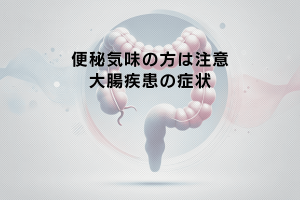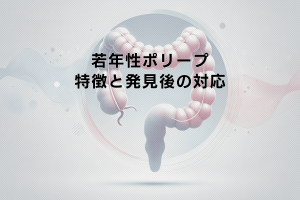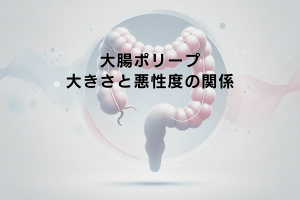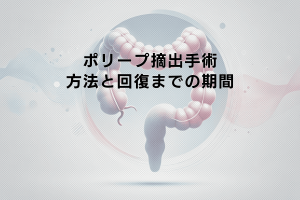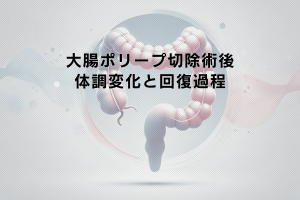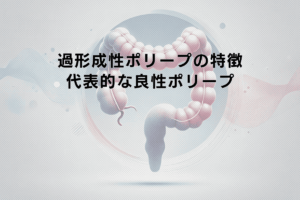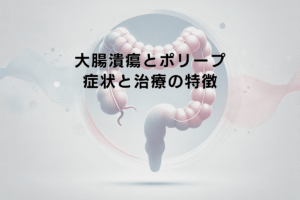大腸内視鏡検査でポリープを切除した後、ほっとしたのも束の間、今度は便が出ない、お腹が張って苦しいといった便秘の症状に悩まされることがあります。
切除後は出血や穿孔などの合併症に注意が向きがちですが、便秘もまた多くの人が経験する不快な症状の一つです。普段は便秘とは無縁な方でも、切除後特有の理由で一時的に排便のリズムが乱れることは珍しくありません。
この記事では、なぜ大腸ポリープ切除後に便秘が起こりやすいのか、原因から、ご自宅でできる食事や生活習慣の工夫、市販薬を使う際の注意点、どのような場合に医療機関へ相談すべきかまで詳しく解説していきます。
なぜ大腸ポリープ切除後に便秘になりやすいのか
大腸ポリープ切除後に多くの人が便秘を経験するのには、いくつかの明確な理由がありますが、検査や処置に伴う一時的な体の変化が原因であり、多くの場合、時間の経過とともに改善していきます。
検査前の下剤の影響
大腸内視鏡検査を安全かつ正確に行うためには、腸の中を完全に空っぽにする必要があるため、検査前日や当日に約1リットルから2リットルの液体下剤を服用します。
下剤は腸管洗浄剤とも呼ばれ、小腸から大腸の隅々まで、腸管内にある内容物をすべて洗い流す強力な作用があり、切除後すぐに便の材料となるものが腸内に全く存在しない状態になります。
私たちが食べたものが胃や小腸で消化され、残りカスが大腸に送られて十分な量の便が形成されるまでには、通常2日から3日程度の時間が必要です。
切除後数日間排便がないのは、腸が空になっていることによる当然の帰結であり、多くの場合、生理的な現象なので、便秘と勘違いして不安に思う方もいますが、まずは便の材料が腸内にたまるのを待つことが大事です。
食事制限による便量の減少
ポリープ切除後は、切除した部分の傷を安静に保ち、出血などの合併症を防ぐために、一時的な食事制限が指示され、消化の良いおかゆやうどん、すりおろしたりんご、豆腐などを中心とした、食物繊維の少ない低残渣食が推奨されます。
食物繊維は、人間の消化酵素では分解されずに大腸まで届き、便の骨格を形成し、水分を吸収して便のかさを増やす重要な役割を担っています。
食事制限では食物繊維の摂取が厳しく制限されるため、作られる便の量そのものが物理的に少なくなるのです。
便の量が少ないと、大腸の壁を十分に刺激して便意を催すほどの大きさにならないため、腸内に便がとどまる時間が長くなり、便秘傾向になります。
切除後の食事内容の変化
| 時期 | 食事内容の例 | 便への影響 |
|---|---|---|
| 切除直後〜数日 | おかゆ、素うどん、豆腐、白身魚の煮付け、プリン | 食物繊維が少なく、便量が減少しやすい |
| 通常の食事 | 玄米、野菜、きのこ、海藻類、豆類 | 食物繊維が豊富で、十分な便量が保たれる |
腸内環境の一時的な変化
検査前に服用する強力な下剤は、便だけでなく、腸内に生息している約100兆個ともいわれる多種多様な腸内細菌も一緒に洗い流してしまうのです。
腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌などが絶妙なバランスを保って共存し、腸内フローラ(腸内細菌叢)を形成していて、腸内細菌は、腸のぜん動運動をコントロールしたり、便の形成に関わったり、さらには免疫機能にも深く関与しています。
腸内フローラが下剤によって一時的にリセットされると、腸の機能が低下し、排便のリズムが乱れやすいです。
洗い流された腸内細菌が、日々の食事などを通じて再び元のバランスを取り戻すまでには少し時間がかかり、その間、便秘や逆にお腹が緩くなるといった症状が出ることがあります。
手術後の活動量低下とストレス
ポリープ切除は日帰りで行うことが多いですが、体にとっては一種の手術であり軽微な侵襲を伴い、切除後は、出血のリスクを避けるために、1週間程度は激しい運動や長時間の移動、腹圧のかかる力仕事などを控えるよう指示されます。
体の活動量が低下すると、腸のぜん動運動も不活発になりがちです。また、無意識のうちに切除した部分をかばったり、排便時にいきむことで傷口が開いてしまうのではないかという不安を感じたりすることも、精神的なストレスとなります。
脳と腸は自律神経を介して密接に連携しており(脳腸相関)、ストレスは腸の働きをコントロールしている副交感神経の活動を抑制するため、便秘の大きな悪化要因となり得ます。
切除後の便秘が体に与える影響
切除後の便秘は、単に便が出ないという不快感だけでなく、体の様々な部分に好ましくない影響を及ぼす可能性があります。特に、腸に傷がある状態での便秘には、通常時よりも慎重な対応が必要です。
腹部の不快感と痛み
便が腸内に長時間滞留すると、便に含まれる水分が腸壁から過剰に吸収され、便はますます硬く、排出しにくくなります。
硬くなった便や、滞留した便が腸内細菌によって異常発酵して発生したガスによって腸が内側から圧迫されると、お腹の張り(腹部膨満感)や、シクシクとした痛み、けいれん性の腹痛を起こすことがあります。
不快感が続くと、食欲不振や吐き気につながることもあり、生活の質を大きく低下させる原因となります。
切除創部への負担増加
ポリープを切除した後の大腸の粘膜には、出血予防のために金属製のクリップで縫縮されているか、あるいは電気メスで焼灼したことによるかさぶたのようなものができている状態です。
傷が完全に治癒するまでには、1週間から2週間程度かかります。
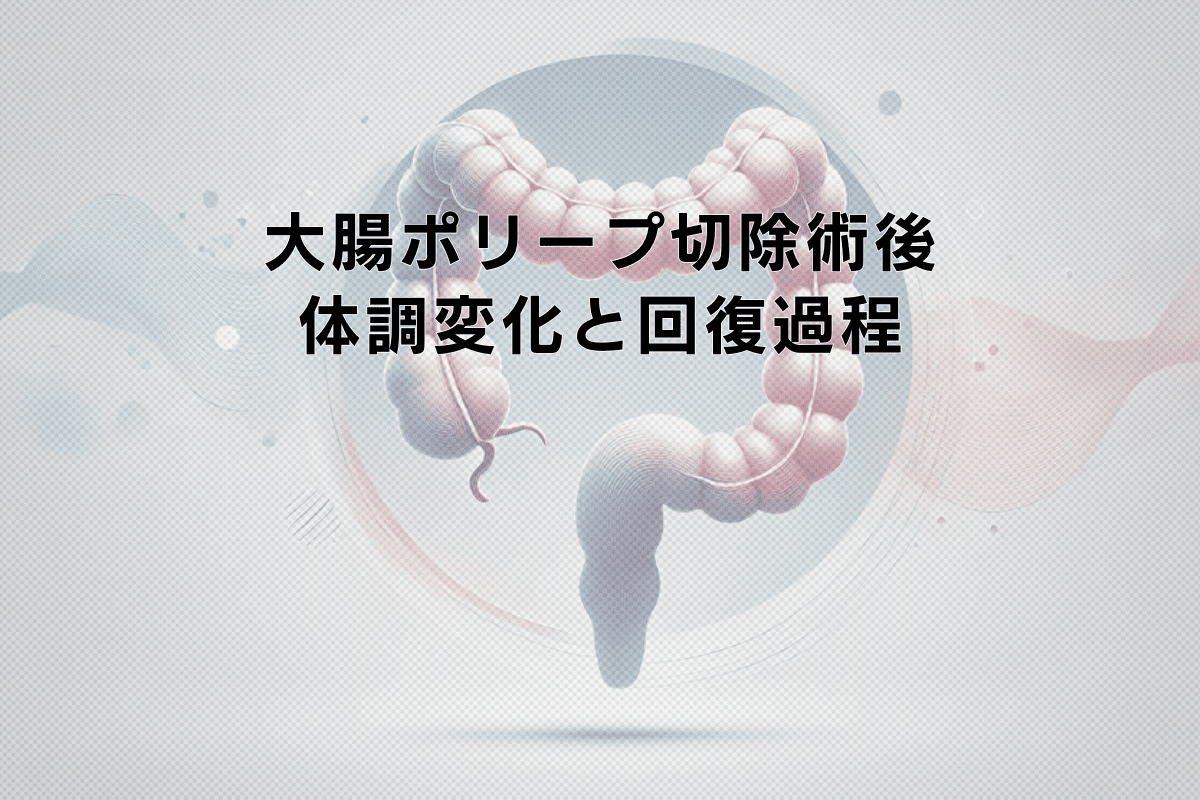
便秘になって硬くなった便がこの創部を通過する際、物理的にこすれて刺激となり、治癒を遅らせたり、クリップが早期に脱落したり、最悪の場合は出血(後出血)を起こしたりするリスクがあります。
また、排便時に強く長い時間いきむことも、腹圧を急激に上昇させ創部の血管に負担をかけるため、避けましょう。便秘を解消し、自然でスムーズな排便を促すことは、創部の安静を保つ上でも非常に重要です。
便秘が創部に与えるリスク
| 便の状態 | リスク | 理由 |
|---|---|---|
| 硬い便 | 創部の機械的刺激、出血、治癒遅延 | 硬い便が通過する際に創部をこするため |
| 強いいきみ | 腹圧上昇による出血、クリップの脱落 | 急激な腹圧上昇が血管や創部に負担をかけるため |
血圧の上昇といきむことのリスク
排便時に強く歯を食いしばっていきむと、胸腔内圧が上昇し、心臓に戻る血液が一時的に減少し、その後、息を解放したときに血圧が急上昇します。
これはバルサルバ法と同様の生理的な反応ですが、高血圧や心臓に持病がある方にとっては、心筋梗塞や不整脈、脳卒中の引き金となる可能性も否定できないので、切除後の安静期間中は、体に余計な負担をかけるべきではありません。
便秘によって毎回の排便が苦痛になり、強いいきみを繰り返すことは、循環器系への負担という観点からも避け、便を柔らかく保ち、いきまずに排便できる状態を目指すことが大切です。
全身の倦怠感や食欲不振
便秘が続くと、腸内で悪玉菌が優勢になり、アンモニアや硫化水素、インドールといった有害物質が産生されやすくなります。
有害物質が腸から吸収されて血流にのって全身を巡ると、肌荒れや頭痛、肩こり、原因のはっきりしない倦怠感などを起こすことがあります。また、お腹が張って苦しい状態が続くと、食事を摂ること自体が億劫になり、食欲不振に陥ります。
食事が十分に摂れないと、体力回復が遅れるだけでなく、便の材料も不足するため、さらに便秘が悪化するという悪循環に陥りやすくなるのです。
自宅でできる便秘の対処法(食事編)
切除後の便秘を改善するためには、まず食事内容の見直しが基本です。腸に負担をかけず、スムーズな排便を促すための食事のポイントを解説します。
水分を十分に摂取する重要性
硬い便を柔らかくするためには、十分な水分摂取が何よりも重要です。便の約70%から80%は水分で構成されており、体内の水分が不足すると、大腸で便から水分が余計に吸収されてしまい、便はカチカチに硬くなります。
切除後は、意識してこまめに水分を摂るように心がけてください。1日に1.5リットルから2リットルを目安に、水や白湯、麦茶など、カフェインや糖分を含まない飲み物を少しずつ、回数を分けて飲むのが効果的です。
朝起きてすぐにコップ一杯の水を飲むと、胃結腸反射が促され、休んでいた腸が動き出して便意を感じやすくなるため、おすすめの習慣です。
水分補給に適した飲み物
| 推奨される飲み物 | 避けた方が良い飲み物 |
|---|---|
| 水、白湯、麦茶、ハーブティー | コーヒー、紅茶、緑茶(カフェインの利尿作用) |
| 具なしのスープ、味噌汁 | アルコール飲料(脱水と後出血のリスク) |
食物繊維の適切な摂り方
便秘解消に食物繊維が有効なのはよく知られていますが、切除後はその種類と摂り方に工夫が必要です。
食物繊維には、水に溶けて便をゲル状に柔らかくする水溶性食物繊維と、水に溶けずに便のかさを増して腸を刺激する不溶性食物繊維があります。切除直後は、腸への刺激が少ない水溶性食物繊維を多く含む食品から摂り始めるのが良いでしょう。
熟したバナナや煮りんご、海藻類(わかめスープなど)、大麦などが挙げられ、創部の状態が落ち着いてきたら、徐々に不溶性食物繊維(きのこ類、根菜類など、加熱して柔らかくしたもの)も取り入れていくのが理想的です。
食物繊維の種類と食品例
| 種類 | 特徴 | 多く含む食品(切除後に取り入れやすいもの) |
|---|---|---|
| 水溶性食物繊維 | 便を柔らかくする、善玉菌のエサになる | 海藻類、熟した果物(バナナ、りんご)、オートミール、大麦 |
| 不溶性食物繊維 | 便のかさを増やす、腸を刺激する | きのこ類、根菜類(よく煮たもの)、豆類、葉物野菜 |

腸に優しい発酵食品の活用
下剤によって乱れた腸内環境を整えるためには、善玉菌(プロバイオティクス)を多く含む発酵食品を食事に取り入れるのが効果的です。
ヨーグルトや乳酸菌飲料、納豆、味噌、麹といった食品には、ビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌が豊富に含まれていて、善玉菌は、腸内で短鎖脂肪酸などの有益な物質を作り出し、腸のぜん動運動を活発にしてくれます。
また、善玉菌のエサとなるオリゴ糖(玉ねぎ、ごぼう、バナナなどに含まれる)や水溶性食物繊維(プレバイオティクス)を一緒に摂ると、より効果的に腸内環境を改善することが可能です。
避けるべき食事と飲み物
切除後1週間から2週間程度は、腸に負担をかける食事は避けるべきです。唐辛子やカレー粉などの香辛料を多く使った刺激の強い料理、脂肪分の多い揚げ物やこってりした肉料理は、消化に時間がかかり、腸の動きを悪くすることがあります。
また、アルコールは血行を促進するため、後出血のリスクを高める可能性があるので、医師の許可が出るまでは禁酒を守ってください。
コーヒーや紅茶、緑茶に含まれるカフェインには利尿作用があるため、水分補給のつもりで飲みすぎると、かえって体内の水分を排出し、便秘を助長することがあるため注意が必要です。
自宅でできる便秘の対処法(生活習慣編)
食事の見直しと合わせて、日々の生活習慣を少し工夫することも、便秘の解消につながります。体に大きな負担をかけない範囲で、できることから取り入れてみましょう。
無理のない範囲での適度な運動
切除後の安静期間が終わったら、医師の許可のもとで軽い運動を始めるのがおすすめです。特にウォーキングは、全身の血行を良くし、腸に心地よい物理的な刺激を与えてぜん動運動を促す効果が期待できます。
まずは1日15分から20分程度の散歩から始めて、体調を見ながら徐々に時間や距離を延ばしていくと良いでしょう。腹筋を鍛えるような激しい運動や、重いものを持つような動作は、創部に負担がかかるため、医師の許可を得てからにしてください。
また、家の中でできる軽いストレッチやヨガも、リラックス効果と血行促進の両面から有効です。
規則正しい排便習慣の確立
毎日決まった時間にトイレに行く習慣をつけることも、排便リズムを取り戻す上で大切で、朝食後は胃に食物が入ることで大腸の動きが活発になる胃結腸反射が起こりやすく、便意を感じやすいゴールデンタイムです。
便意がなくても、朝食後にトイレに座る時間を5分程度設けてみてください。繰り返すことで、体が排便の時間を覚え、自然な便意が起こりやすくなります。
トイレでは焦らず、前傾姿勢をとると直腸がまっすぐになり、便を排出しやすくなり、足元に低い台を置くのも効果的です。
排便を促すための工夫
| 項目 | 具体的な方法 |
|---|---|
| トイレタイムの固定 | 毎日同じ時間(特に朝食後)にトイレに座る |
| 排便時の姿勢 | ロダンの考える人のような前傾姿勢をとる、足台を置く |
お腹を温めることの効果
腹部を外から温めると、胃腸の血行が良くなり、リラックス効果によって副交感神経が優位になり、腸のぜん動運動が活発になることが期待できます。
ぬるめのお湯にゆっくり浸かる入浴や、腹巻きの使用、お腹に蒸しタオルや湯たんぽを当てるなどが手軽な方法です。また、おへその周りを時計回りに「の」の字を描くように優しくマッサージするのも、腸への直接的な刺激となり効果的です。
就寝前に行うと、体がリラックスして寝つきも良くなり、翌朝の自然なお通じにつながりやすくなります。
ストレス管理とリラックス法
便が出ないことへの焦りや不安は、それ自体がストレスとなり、自律神経のバランスを乱して便秘を悪化させます。まずは、切除後しばらく便が出ないのは自然なことだと理解し、あまり思い詰めないことが大事です。
意識的にリラックスする時間を作り、心身の緊張をほぐしましょう。ゆっくりと腹式呼吸を行う、瞑想する、好きな音楽を聴く、アロマテラピーを取り入れる、趣味に没頭するなど、ご自身に合った方法を見つけてください。
十分な睡眠時間を確保することも、ストレス軽減と腸の機能回復の両方にとって重要です。
便秘薬の使用に関する注意点
食事や生活習慣の改善で効果が見られない場合、便秘薬の使用を考えることもありますが、切除後のデリケートな腸に自己判断で市販薬を使用することにはリスクも伴います。
市販薬を自己判断で使うリスク
市販の便秘薬には様々な種類がありますが、中にはセンナやビサコジルといった成分を含む、大腸を直接刺激して無理やりぜん動運動を起こさせるタイプ(刺激性下剤)があります。
切除後の腸にこのような強い刺激を与えると、けいれん性の激しい腹痛が起こったり、創部に負担をかけてしまったりする可能性があります。
また、連用すると腸がその刺激に慣れてしまい、薬なしでは排便できなくなることもあるため、安易な使用は避けるべきです。切除後の便秘に対しては、まずかかりつけの医師や薬剤師に相談することが大原則です。
便秘薬の種類と特徴
| 種類 | 作用 | 注意点 |
|---|---|---|
| 刺激性下剤 | 腸を直接刺激し、ぜん動運動を強制的に起こす | 腹痛が強く出ることがある。切除後は自己判断での使用は避けるべき。 |
| 機械的下剤 | 便の水分量を増やして柔らかくし、排出しやすくする | 効果は穏やか。切除後には比較的使いやすいが、医師の指示が必要。 |
医師から処方された薬の正しい使い方
ポリープ切除後に便秘になることを見越して、あらかじめ便を柔らかくする薬(酸化マグネシウムなどの機械的下剤)が処方されることがあります。
このタイプの薬は、腸を直接刺激するのではなく、腸管内に水分を引き込んで便の水分量を増やし、カチカチの便を柔らかくして自然な排便を促すものです。効果は穏やかで、依存性も少なく、切除後の使用にも適しています。
医師から薬が処方された場合は、指示された用法・用量を必ず守って服用してください。
効果を高めるためには、コップ一杯以上の多めの水で服用することが重要で、効果が出ないからといって、自己判断で量を増やしたり、他の薬を追加したりすることは絶対にやめましょう。
医療機関に相談すべき便秘のサイン
ほとんどの切除後の便秘は一時的なものですが、中には注意が必要なケースもあります。以下のような症状が見られる場合は、自己判断で様子を見ずに、ポリープを切除した医療機関に速やかに連絡し、指示を仰いでください。
激しい腹痛や吐き気を伴う場合
単なるお腹の張りとは異なる、我慢できないほどの激しい腹痛や、冷や汗、吐き気・嘔吐などを伴う場合は、腸閉塞(イレウス)や、まれではありますが穿孔(腸に穴が開くこと)による腹膜炎など、重篤な状態の可能性があります。
便やガスが全く出ず、お腹がパンパンに張ってカエルのように硬くなるような場合も同様です。これは緊急を要するサインですので、夜間や休日であってもためらわずに医療機関に連絡してください。
数日間全く排便がない状態
切除後2日から3日程度排便がないのは一般的ですが、食事を普通に摂っているにもかかわらず、4日以上全く排便も排ガス(おなら)もない状態が続く場合は、一度相談した方が良いでしょう。
腹痛やお腹の張りがどんどん強くなる場合は、腸の動きが著しく悪くなっている可能性があり、何らかの介入が必要になることがあります。
受診を検討するべき期間の目安
| 状況 | 目安 |
|---|---|
| 食事を再開してからの期間 | 4日以上、便もガスも全く出ない |
| 腹部症状 | 時間と共に腹痛や張りが悪化する |
便に血が混じる、黒い便が出る
排便時に少量の鮮血がトイレットペーパーに付着する場合は、便が硬くて肛門が切れた(切れ痔)可能性もありますが、切除後の後出血の可能性も否定できません。
便器が真っ赤になるほどの出血、便全体に血液が混じっている、レバーのような血の塊が出る、あるいは黒くてドロドロした便(タール便)が出る場合は、腸管内でまとまった量の出血が起きているサインです。
出血量が多い場合は貧血やショック状態に至ることもあるため、すぐに医療機関に連絡してください。
対処法を試しても改善しない
食事や生活習慣の工夫を1週間程度続けても便秘が全く改善しない、あるいは処方された薬を飲んでも効果が見られない場合も、一度医師に相談しましょう。便秘の原因が他にある可能性や、薬の種類や量の調整が必要な場合があります。
我慢しすぎず、専門家のアドバイスを求めることが、早期解決への近道です。
危険な症状のまとめ
- 我慢できないほどの激しい腹痛、嘔吐
- 便器が赤くなるほどの血便や黒い便
- 4日以上の完全な排便・排ガスの停止
- 悪化し続ける腹部膨満感、発熱
大腸ポリープ切除後の便秘に関するよくある質問
- 切除後、いつから普通の食事に戻せますか。
-
切除したポリープの大きさや数、切除方法によって異なりますが、一般的には1週間程度の食事制限が推奨されることが多いです。
最初の2〜3日はおかゆやうどんなどの流動食に近いものから始め、その後、徐々に通常の食事形態に戻していきます。
食物繊維の多い野菜や刺激物、脂っこいもの、アルコールなどは、少なくとも1週間、場合によっては2週間程度は避けた方が安全です。
- 便意があるのに出ないのはなぜですか。
-
一つは、便が直腸まで下りてきているものの、水分が吸収されすぎて硬くなっているためにスムーズに排出できない状態で、水分不足や食物繊維不足が背景にあることが多いです。
もう一つは、切除後の違和感や痛みへの不安から、無意識に肛門括約筋が緊張してしまい、便の出口を狭めてしまっている可能性(機能性便排出障害)です。
リラックスしてトイレに座り、前傾姿勢をとるなどの工夫を試してください。それでも改善しない場合は、便を柔らかくする薬の使用などを検討するため、医師に相談するのが良いでしょう。
- ウォシュレットを強く使うのは問題ないですか。
-
切除後、特に最初の1〜2週間は、ウォシュレットの使用を控えるか、使うとしても水圧を最も弱くして短時間で済ませましょう。
また、肛門周囲の必要な皮脂まで洗い流してしまい、皮膚のバリア機能を低下させ、かゆみや炎症を起こすこともあります。
- 次の検診まで便秘が続いても大丈夫ですか。
-
軽い便秘で、お腹の張りもそれほど強くなく、食事も摂れているのであれば、食事や生活習慣の工夫を続けながら次の検診まで様子を見ることも可能です。
しかし、危険なサイン(我慢できないほどの激しい腹痛、血便、4日以上全く便が出ない)が見られたり、便秘のせいで食事が摂れない、日常生活に支障が出ているといった場合は、切除を受けた医療機関に連絡して相談してください。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸ポリープ切除後の出血|正常な経過と注意が必要な症状】
便秘対処を学んだ今、“どの出血は様子見で、どの出血は受診?”と感じる方も多いはず。時期別のサインと対応を整理し、不安時の判断を助けます。
【大腸ポリープ切除術後の体調変化と回復過程】
切除後の数日〜2週間の過ごし方を全体像で把握すると、便秘対策も位置づけが明確に。安静・運動・食事再開など回復の道筋をつかめます。
以上
参考文献
Shibata C, Funayama Y, Fukushima K, Takahashi KI, Ogawa H, Haneda S, Watanabe K, Kudoh K, Kohyama A, Hayashi KI, Sasaki I. Effect of calcium polycarbophil on bowel function after restorative proctocolectomy for ulcerative colitis: a randomized controlled trial. Digestive diseases and sciences. 2007 Jun;52(6):1423-6.
Komori S, Akiyama J, Tatsuno N, Yamada E, Izumi A, Hamada M, Seto K, Nishiie Y, Suzuki K, Hisada Y, Otake Y. Prevalence and risk factors of constipation symptoms among patients undergoing colonoscopy: a single-center cross-sectional study. Digestion. 2024 Aug 9;105(4):299-309.
Teramoto A, Aoyama N, Ebisutani C, Matsumoto T, Machida H, Yoshida S, Uchima N, Utsumi T, Tochio T, Hirata D, Iwatate M. Clinical importance of cold polypectomy during the insertion phase in the left side of the colon and rectum: a multicenter randomized controlled trial (PRESECT study). Gastrointestinal Endoscopy. 2020 Apr 1;91(4):917-24.
Ichise Y, Horiuchi A, Nakayama Y, Tanaka N. Prospective randomized comparison of cold snare polypectomy and conventional polypectomy for small colorectal polyps. Digestion. 2011 Jul 1;84(1):78-81.
Higurashi T, Hosono K, Takahashi H, Komiya Y, Umezawa S, Sakai E, Uchiyama T, Taniguchi L, Hata Y, Uchiyama S, Hattori A. Metformin for chemoprevention of metachronous colorectal adenoma or polyps in post-polypectomy patients without diabetes: a multicentre double-blind, placebo-controlled, randomised phase 3 trial. The Lancet Oncology. 2016 Apr 1;17(4):475-83.
Du F, Xu F, Yang Z, Zhang Y, Gao Z. Post-Polypectomy Care: Balancing Comfort and Nutritional Needs. Current Topics in Nutraceutical Research. 2024 May 1;22(2).
Hassan C, Quintero E, Dumonceau JM, Regula J, Brandão C, Chaussade S, Dekker E, Dinis-Ribeiro M, Ferlitsch M, Gimeno-García A, Hazewinkel Y. Post-polypectomy colonoscopy surveillance: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline. Endoscopy. 2013 Oct;45(10):842-64.
Ligato I, Ruffa A, Sbarigia C, Petrucciani N, Esposito G. Surprising complication of intussusception after colonoscopy. a case report and a review of the literature. JOURNAL OF SURGERY. 2024;9(1).
Park SK, Lee MG, Jeong SH, Yang HJ, Jung YS, Choi KY, Kim H, Kim HO, Jeong KU, Chun HK, Park DI. Prospective analysis of minor adverse events after colon polypectomy. Digestive Diseases and Sciences. 2017 Aug;62(8):2113-9.
Ichise Y, Horiuchi A, Nakayama Y, Tanaka N. Prospective randomized comparison of cold snare polypectomy and conventional polypectomy for small colorectal polyps. Digestion. 2011 Jul 1;84(1):78-81.