胃カメラや大腸カメラなどの内視鏡検査と聞くと、「痛い」「苦しい」という印象をお持ちの方は少なくありません。
実際に不快感を覚える方もいますが、医療技術の進歩や鎮静剤の使用によって痛みや不安をやわらげられる場合もあります。
本記事では、内視鏡検査の概要や痛みが生じる原因、苦痛を軽減する方法、検査前後の注意点などを詳しくお伝えしていきます。
消化器内科などで行われる内視鏡検査に対する疑問や不安を、少しでも解消するきっかけになれば幸いです。
内視鏡検査で痛みを感じる理由とは
胃内視鏡検査(胃カメラ)と大腸内視鏡検査(大腸カメラ)は、どちらも消化器の内部を観察するための検査ですが、痛みの感じ方に違いがあります。
胃カメラでは、喉からスコープを挿入するときの嘔吐反射や異物感が主な苦痛の要因になります。

一方、大腸カメラでは、腸内に空気や二酸化炭素を送りながら挿入していくことで生じる腹部の張りや、腸の曲がり角を通過するときの違和感が大きな理由です。

挿入時のカメラの通過による刺激
内視鏡を挿入するとき、胃や大腸の粘膜を傷つけないように注意しながら行いますが、内視鏡は柔軟性を持った器具であっても一定の太さがあり、体の湾曲に沿って曲げながら進める必要があります。
このとき、壁が引き延ばされたり粘膜が押されることで痛みを感じることがあり、特に腸の折り返しが多い方や、腸同士が癒着している方は、挿入をスムーズに行いにくいため痛みを訴えるケースが多いです。
空気や二酸化炭素での膨張感
大腸内視鏡検査の際、視野を広げて粘膜を観察しやすくするために空気や二酸化炭素を腸に注入するので、腸が膨張し、圧迫感を覚える場合があります。二酸化炭素の方が体内への吸収が早く、検査後のお腹の張りや痛みが軽いと言われています。
医師が空気の量や注入のタイミングを調整しながら検査を行いますが、検査中に違和感を覚えたら遠慮せず声に出して伝えることが大切です。
過度な緊張と不安
検査に対する強い不安や緊張は、痛みの感じ方を増幅しやすいです。筋肉がこわばることで、内視鏡の通過時に余計な抵抗が生まれやすくなり、痛みを強く感じてしまう可能性があります。
検査前にリラックスしやすい環境を作ることや、事前に医師やスタッフとコミュニケーションを取っておくことが、不安を減らすためには重要です。
過去の手術歴や持病による影響
過去に腹部の手術を受けた方は、癒着や腸の形状変化などが起こり、その結果、内視鏡を挿入する経路が通常とは異なり、痛みを感じやすいことがあります。
大腸の憩室や炎症などの疾患がある人も、腸が敏感な状態であるため、痛みを自覚しやすく、検査前にしっかりと既往歴を医師に伝えることが大切です。
胃内視鏡検査と大腸内視鏡検査の違い
胃カメラは、食道から胃や十二指腸にかけての粘膜を直接観察したり、組織を採取して病気の有無を調べたりします。大腸カメラは主に大腸(結腸や直腸)の内側を観察し、大腸ポリープや大腸がんなどを早期発見することが目的です。
検査前に使用する下剤や準備
胃カメラの場合は、検査の6~8時間前(または前日の夜)から食事を控え、胃の中を空っぽにしておく必要があります。大腸カメラの場合は、腸内をきれいにするために下剤(洗浄剤)を飲んで、便を出し切ることが大切です。
下剤の味や飲む量に負担を感じる方もいますが、しっかりと腸の中を空にしておかないと正確な診断が難しくなります。医療機関によっては、下剤の種類が選べる場合もあるため、苦痛を感じる方は相談してみるとよいでしょう。
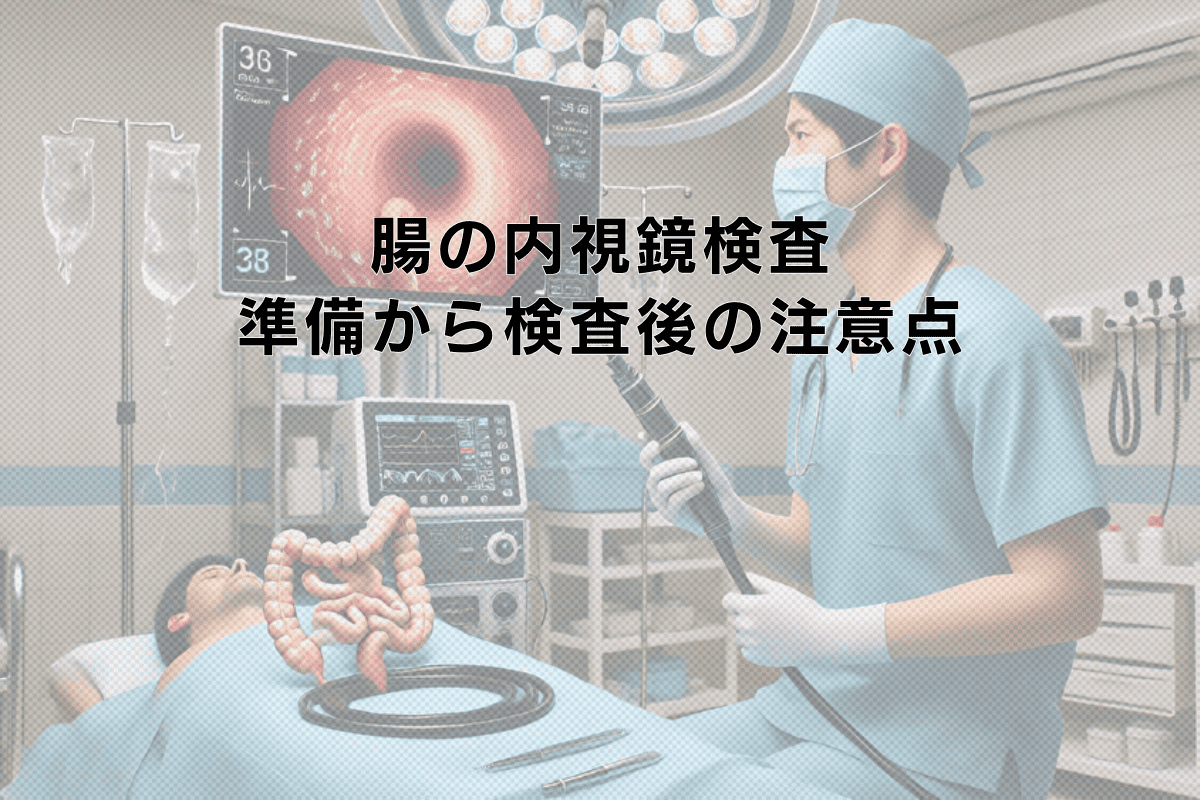
検査にかかる時間と負担
胃カメラはスムーズに進めば5~10分程度で終了することが多いですが、大腸カメラは観察範囲が広く、場合によってはポリープ切除などの治療行為を行うことがあるため、15~30分程度かかる場合もあります。
検査時間が長いと、その分だけ違和感や痛みを感じるリスクも高まるため、可能であれば鎮静剤を使って受けた方が楽に感じることが多いです。
合併症やリスクの頻度
内視鏡検査は安全性が高い医療行為であるものの、ごくまれに穿孔(器具が腸壁を突き破ってしまうこと)や出血などのリスクがあり、大腸内視鏡検査でポリープを切除するときには、切除部位からの出血や穿孔の可能性がわずかに高まります。
ただし、医師が慎重に検査と治療を行うため、重大な事故の頻度は低く、ほとんどの方が大きなトラブルなく終えています。
検査後の経過観察や日常生活の制限
胃カメラ後は、のどの麻酔や違和感がしばらく残ることがありますが、大半の方は検査直後から飲食も可能です。
一方、大腸カメラでポリープを切除した場合は、切除した部分の出血リスクを抑えるために、数日は激しい運動を避けるように指示されることがあります。
検査後の過ごし方や来院のタイミングについても、医師や看護師から説明があるので、不明点は遠慮せずに確認してください。
痛みを軽減するさまざまな方法
内視鏡に際する痛みを減らすために、麻酔や経鼻内視鏡、炭酸ガスなどの使用など、いくつかの方法があります。
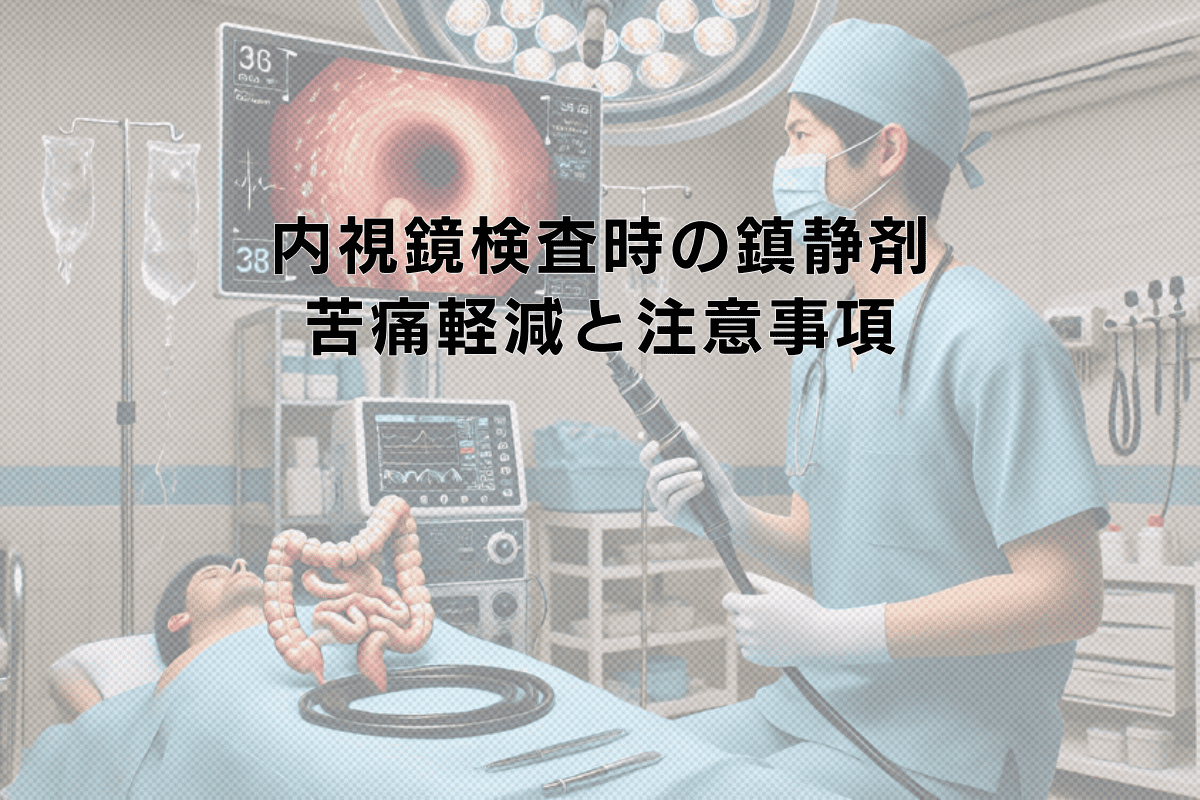
麻酔による負担軽減
内視鏡検査では、静脈麻酔や鎮静剤を使用して検査を受ける選択肢があり、鎮静剤を使うことで意識がぼんやりした状態になり、検査中の痛みや違和感を感じにくくできます。
胃カメラでは、のどの表面に局所麻酔を施すことで嘔吐反射を抑えやすくする方法もあります。
経鼻内視鏡による負担軽減
胃内視鏡検査には、口から挿入する方法だけでなく、鼻から細い内視鏡を挿入する「経鼻内視鏡」があります。従来の口からの検査に比べると嘔吐反射が起きにくいとされ、検査中に会話もできるため、楽に受けられるケースが多いです。
ただし、鼻腔が狭い方などには適さない場合もありますので、事前に医師と話し合って選択することをおすすめします。
検査時の姿勢や技術
医師が内視鏡の操作に慣れていること、そして患者さんの姿勢を適切に調整して検査を進めることも、痛み軽減に大きく関わります。軸保持短縮法や水浸法のように、腸にかかる負担を軽くする技術を使うことで、挿入時の痛みを抑えられます。
検査中に痛みや違和感を感じた際は、遠慮せずに「痛いです」「張って苦しいです」などと医師や看護師に伝えてください。
炭酸ガス送気装置の利用
大腸内視鏡検査では、検査中に腸を広げるためにガスを送気します。従来は空気を入れていましたが、最近では炭酸ガスを用いることで検査後の腹部膨満感を抑えられ、また、体内への吸収が早く、検査後にお腹の張りが残りにくいです。
ポリープ切除時の対応
大腸内視鏡検査では、検査中に大腸ポリープを発見した場合、その場で切除するケースがあり、この時、切除自体の痛みはほとんどありませんが、電気メスを使って切る際にわずかな刺激や熱感を感じることがあります。
また、切除後に出血や腹痛が起きる場合もあるため、ポリープ切除の可能性がある場合は、検査後しばらく安静を保つことが重要です。
内視鏡検査前の準備と注意点
内視鏡検査の前には、食べ物や下剤などの準備や、さまざまな注意点があり、また、持病がある方や、妊娠・授乳中の方は特別な配慮が必要です。
食事制限や下剤のタイミング
胃内視鏡検査を受ける方は、検査当日の朝まで禁食にして、検査数時間前まで水分は摂ってよいケースが一般的です。
大腸内視鏡検査の方は、前日から消化の良い食事に切り替え、検査当日の朝から下剤を飲み始めます。医療機関の指示をしっかり守り、腸内をきれいにすることが大切です。
持病がある場合の主治医への相談
高血圧や糖尿病など、何らかの持病がある場合は、検査前に主治医へ内視鏡検査を受けてもよいか確認してください。服用中の薬があれば、いつまで飲んでよいか、当日はどうするかなどの説明を受け、検査当日に医師に伝えておきます。
特に血液をサラサラにする薬を飲んでいる方や、抗血小板剤を使用している方は注意が必要です。
妊娠中や授乳中の方への配慮
妊娠中や授乳中の方が内視鏡検査を受ける場合は、検査の必要性とリスクを十分に検討することが大切です。鎮静剤やX線を伴う検査(透視下での大腸内視鏡など)は、胎児や乳児への影響を考慮しなくてはいけません。
必ず事前に妊娠や授乳の可能性を伝え、医師と相談したうえで検査を受けるかどうかを決めてください。
アレルギーへの注意
薬剤アレルギーやラテックスアレルギーなどがある方は、内視鏡検査で使用する鎮静剤や器具に関連して症状が出ることがあります。
過去に何かしらのアレルギー反応を起こした経験があれば、検査前に医師や看護師に申し出ておくことが大切で、場合によっては、使用する薬剤や器具の種類を切り替える配慮が可能です。
医師との事前の対話
不安や疑問を感じる場合は、遠慮なく医師や看護師に質問してください。検査の必要性や流れ、痛みを軽減する方法などを事前に把握しておくと安心感が高まります。
質問例
- 「鎮静剤を使いたいのですが、可能でしょうか?」
- 「検査後はどのくらい休んだほうがいいですか?」
- 「ポリープ切除をした場合、食事はいつから摂れますか?」
- 「受ける検査はどのくらいの時間がかかる見込みでしょうか?」
こうした情報を事前に得ておくだけでも、検査当日の不安は大きく減ります。
検査中にリラックスするコツと注意点
検査中に不安になることは自然なことです。ここでは、不安を解消する方法をいくつか説明します。
呼吸法や声かけ
内視鏡検査中に緊張すると腹筋や全身の筋肉が硬くなり、痛みを感じやすくなるので、意識して深くゆっくり呼吸することで体がリラックスし、カメラが通過しやすくなります。
また、痛みや違和感を感じたら、すぐに「痛い」「苦しい」と伝えることが大切です。医師は手元の感触や患者さんの声を頼りに検査を進めているため、遠慮しないで訴えることがスムーズな操作につながります。
自分に合った検査方法を選ぶ
口からの胃カメラが苦手な方は、経鼻内視鏡や鎮静剤を使った検査を提案してもらうなど、自分が受けやすい方法を医師とともに選択することが大切です。
大腸カメラの場合も、痛みが強い方は鎮静剤を使う、炭酸ガス装置を利用する、水浸法を行うなどさまざまな対策が考えられます。医療機関によって設備や方針が異なるため、初診時に相談してみるとよいでしょう。
強い痛みのときは検査を一時停止
大腸内視鏡検査では、腸の屈曲部を通過する際に痛みが生じやすいですが、あまりに強い痛みを感じる場合は、検査を一時的に止めたり、体位を変えたりして内視鏡の通過をスムーズにする工夫を行います。
呼吸を整えたり、腹部に軽く圧迫を加えたりすることで、痛みをやわらげられることがあります。痛みをこらえすぎると、医師側にも伝わらず検査操作が難航し、結果的に検査時間が長引いて負担が増えることもあるため、無理をしないでください。
検査後の過ごし方とフォローアップ
検査後は麻酔の使用有無、ポリープを切除したか、で過ごし方に注意が必要です。帰宅後も、食事に関しての注意点もあります。
検査直後の身体の状態
胃カメラの後は、のどの麻酔が切れるまではむせる可能性があるので、医師や看護師が飲食開始のタイミングを指示し、大腸カメラの場合、検査後は腸内に残った空気や二酸化炭素で腹部の張りを感じることがあります。
鎮静剤を使用した場合は、一時的にふらつきや眠気が残ることもありますので、可能なら車の運転は控え、家族やタクシーなどで帰宅するほうが安全です。
ポリープ切除後の注意点
大腸ポリープを切除した方は、少量の出血や腹痛が起こる可能性があるため、検査当日は激しい運動を避け、できるだけ安静に過ごしてください。
翌日以降も出血や腹痛が続く場合は、放置せずに医療機関へ連絡して指示を仰ぐことが大切です。切除部分の傷が完全に治るまでは、医師の判断に従って入浴や飲酒の制限を守りましょう。
食事や水分補給
胃や大腸に問題がない場合は、検査後数時間経てば普段どおりの食事を摂れますが、検査によって刺激を受けているので、最初の食事は消化の良いものや柔らかいものを選ぶと安心です。
水分補給も適度に行い、アルコール飲料や刺激物は避けてください。ポリープ切除を行った場合は、医師から食事制限の指示が出ることが多いので、指示に従いながら段階的に日常の食事に戻していきましょう。
結果の説明とフォローアップ
内視鏡検査の結果は、検査直後におおまかに説明を受けられることが多いですが、病理検査などの精密検査を行う場合は、後日あらためて報告を受けることになります。
異常が見つかった場合、追加の検査や治療、生活習慣の改善指導などを受ける可能性があります。医師やスタッフとのコミュニケーションを大切にして、今後の治療方針や受診のタイミングを相談してください。
結果説明で医師に確認したいポイント
- 見つかった病変の具体的な状態
- 追加検査の必要性
- 今後の受診間隔
- 生活習慣のアドバイス
医療機関の選び方とよくある質問
医療機関や医師の経験
内視鏡検査は、医師の技術と経験に左右される面があります。年間に行う内視鏡検査の件数や、ポリープ切除などの治療の実績が多い医師ほど、スムーズに検査を進めやすい傾向があります。
「検査が痛かった」「苦しかった」という口コミが少ない医療機関を選ぶのも、一つの方法です。
診療時間やアクセス
病院やクリニックによっては、平日だけでなく週末や祝日に内視鏡検査を受け付けている場合があります。仕事の都合などで平日受診が難しい方は、診療時間やアクセスしやすさも検討してみてください。
定期的な通院やフォローアップが必要なケースもあるため、長期的に通いやすい場所かどうかを確認しておくと安心です。
設備や対応の違い
炭酸ガス送気装置を導入しているか、経鼻内視鏡があるか、鎮静剤を使用できる体制が整っているかなど、医療機関ごとに設備や対応が異なります。
自分がどの部分に不安を感じるかを整理し、それをカバーしてくれる設備や体制を持つクリニックを選ぶと、より安心して検査を受けられる可能性が高いです。
よくある質問
以下に、患者さんから寄せられやすい質問と簡単な回答例を示します。詳しくは担当医に確認してください。
受診前によくある質問
- Q:大腸内視鏡検査のための下剤が飲みにくいのですが、どうしたらいいですか?
- A:検査前日に味付きの下剤を出している医療機関もあります。つらい場合は医師や看護師に相談しましょう。
- A:検査前日に味付きの下剤を出している医療機関もあります。つらい場合は医師や看護師に相談しましょう。
- Q:胃カメラと同時に大腸カメラも受けられますか?
- A:一度の鎮静剤で両方の検査を組み合わせるケースがありますが、病院の方針や患者さんの体力を考慮して判断します。
- A:一度の鎮静剤で両方の検査を組み合わせるケースがありますが、病院の方針や患者さんの体力を考慮して判断します。
- Q:検査当日に生理になってしまったのですが、受けても大丈夫ですか?
- A:大腸内視鏡検査の場合、特に問題がないことが多いですが、気になる場合は事前に連絡を取り、気軽に相談してください。
- A:大腸内視鏡検査の場合、特に問題がないことが多いですが、気になる場合は事前に連絡を取り、気軽に相談してください。
- Q:過去に大腸ポリープの切除を受けたのですが、何年おきに検査を受けるべきでしょうか?
- A:病変の状態や大きさにより異なりますが、半年から1年ごとのフォローアップを提案することが多いです。
内視鏡検査のまとめ
内視鏡検査における「痛い」というイメージは、実際に痛みを体験する方がいる一方で、鎮静剤や医師の技術、検査法の工夫によって大幅に軽減できます。
緊張や不安を和らげるために、医師やスタッフとこまめにコミュニケーションを取り、自分に合った方法を選んで受けることが大切です。胃や大腸の疾患は早期発見が大切であり、特に大腸がんは無症状のまま進行することも珍しくありません。
内視鏡検査を受けるメリット
- 直接的な観察で正確な診断ができる
- ポリープなどが見つかった際、その場で切除や治療が可能
- 早期発見・早期治療により重症化を防ぎやすい
- 検査後に生活習慣改善のアドバイスを受けられる
病気の早期発見と生活習慣の見直し
胃潰瘍やピロリ菌感染、大腸ポリープや大腸がんなど、内視鏡検査で見つけられる疾患は多岐にわたります。
検査結果を踏まえて医師から「こういう食事を心がけてください」「この薬を続けましょう」などのアドバイスを受けられるため、健康管理に役立ちます。
症状がなくても定期的に検査を受けることで、大きな病気のリスクを下げられる可能性があります。
今後の受診タイミング
一度内視鏡検査を受けたあと、特に問題がなければ数年おきに受けるなど、医師から提案されたタイミングに合わせて定期検査を行うのが理想です。
過去にポリープを切除した経験がある方や、家族に大腸がんの既往者がいる方は、より短い間隔での検査を勧められることがありますので、指示を守って早め早めの受診を意識します。
次に読むことをお勧めする記事
【鎮静剤で苦痛を減らす 胃カメラを快適に受けるために】
内視鏡検査の痛みについて基本を押さえたら、次は実際の鎮静剤を使った胃カメラ検査について知っておくと安心です。痛みが不安な方に特に参考になる内容です。
【内視鏡検査費用の目安と流れ 胃と大腸のチェック方法】
検査の痛みについて理解が深まったところで、費用や全体的な流れについても知っておくと、より包括的な理解ができます。
参考文献
Skovlund E, Bretthauer M, Grotmol T, Larsen IK, Hoff G. Sensitivity of pain rating scales in an endoscopy trial. The Clinical journal of pain. 2005 Jul 1;21(4):292-6.
Lauriola M, Tomai M, Palma R, La Spina G, Foglia A, Panetta C, Raniolo M, Pontone S. Intolerance of uncertainty and anxiety-related dispositions predict pain during upper endoscopy. Frontiers in Psychology. 2019 May 15;10:1112.
Shah SG, Brooker JC, Thapar C, Williams CB, Saunders BP. Patient pain during colonoscopy: an analysis using real-time magnetic endoscope imaging. Endoscopy. 2002 Jun;34(06):435-40.
Bashiri M, Akçalı D, Coşkun D, Cindoruk M, Dikmen A, Çifdalöz BU. Evaluation of pain and patient satisfaction by music therapy in patients with endoscopy/colonoscopy. The Turkish journal of gastroenterology. 2018 Sep;29(5):574.
Yao Y, Qiu S, Xue Y, Wang B, Zhang Y, Wang X. Effects of Virtual Reality on Relieving Pain During Endoscopy in Adults: A Systematic Review and Meta‐Analysis of Randomised Clinical Trials. Journal of Clinical Nursing. 2024.
Sedlack RE, Kolars JC, Alexander JA. Computer simulation training enhances patient comfort during endoscopy. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2004 Apr 1;2(4):348-52.
Trevisani L, Zelante A, Sartori S. Colonoscopy, pain and fears: Is it an indissoluble trinomial?. World journal of gastrointestinal endoscopy. 2014 Jun 6;6(6):227.
Kwon JS, Kim ES, Cho KB, Park KS, Park WY, Lee JE, Kim TY, Jang BK, Chung WJ, Hwang JS. Incidence of propofol injection pain and effect of lidocaine pretreatment during upper gastrointestinal endoscopy. Digestive diseases and sciences. 2012 May;57:1291-7.
Triantafillidis JK, Merikas E, Nikolakis D, Papalois AE. Sedation in gastrointestinal endoscopy: current issues. World journal of gastroenterology: WJG. 2013 Jan 1;19(4):463.
Levy I, Gralnek IM. Complications of diagnostic colonoscopy, upper endoscopy, and enteroscopy. Best practice & research Clinical gastroenterology. 2016 Oct 1;30(5):705-18.










