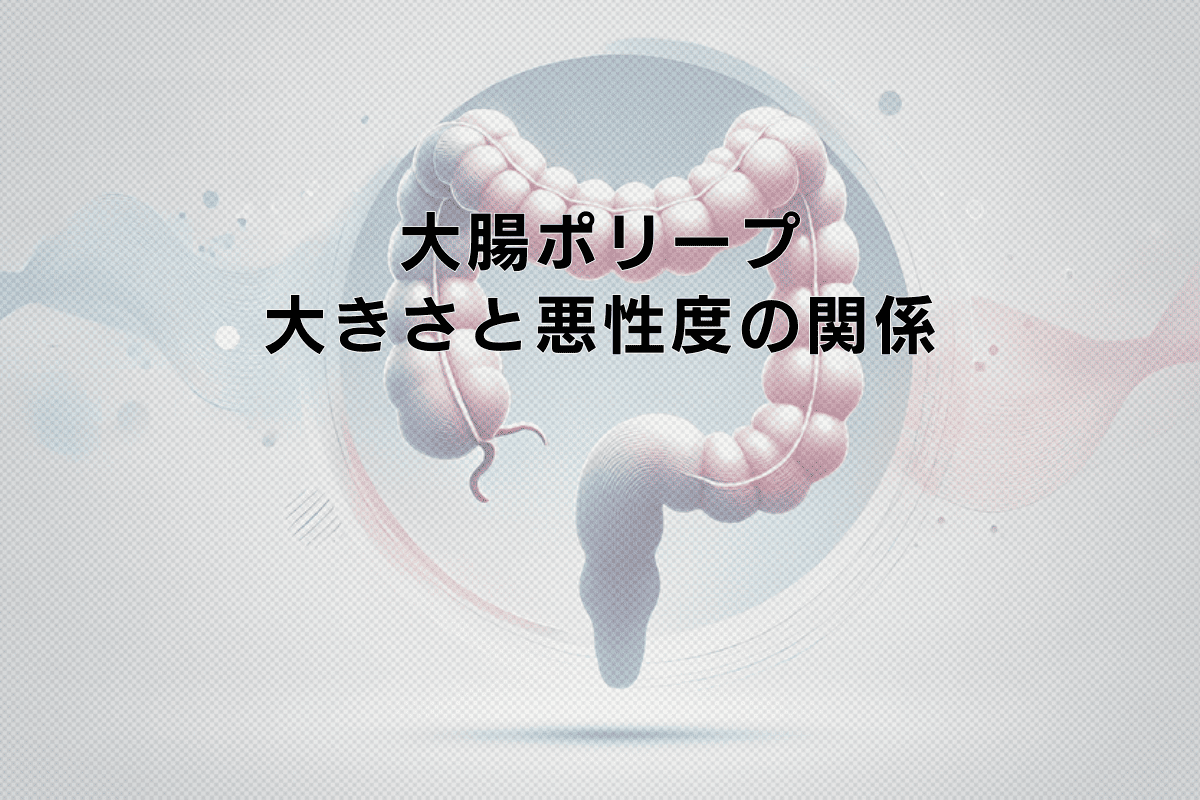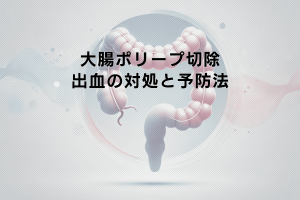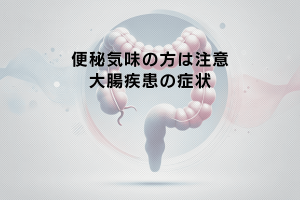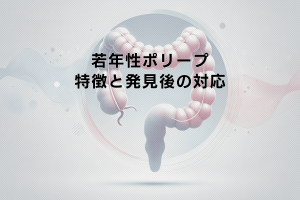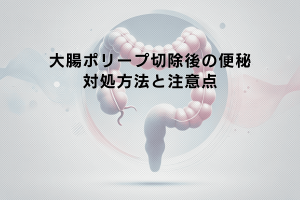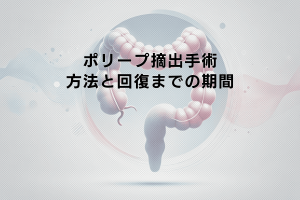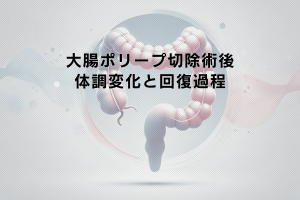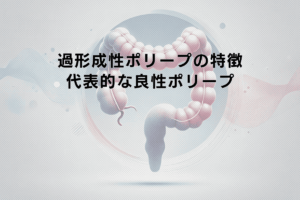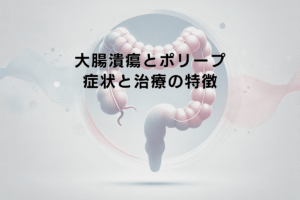大腸内視鏡検査(大腸カメラ)でポリープが見つかったと告げられたとき、多くの方がまず気になるのは、がんである可能性、すなわち悪性度ではないでしょうか。
5mm、10mm、20mmといった具体的な数値を聞くと、その大きさがどの程度の危険性を示すのか、すぐにでも知りたくなるものです。
この記事では、大腸ポリープの大きさと悪性度がどのように関連しているのか、詳しく解説します。
また、大きさだけでなく、悪性度を判断するために医師がどのような点に注目しているのか、大きさによって治療方針がどう変わるのかについても、説明します。
そもそも大腸ポリープとは何か
大腸ポリープの大きさと悪性度の関係を理解するためには、まず大腸ポリープそのものがどのようなものであるかを知っておくことが大切です。
大腸粘膜にできる隆起性の病変
大腸ポリープとは、大腸の内側を覆っている粘膜の表面にできる、イボのように隆起した病変の総称です。
形はキノコのように茎を持つもの(有茎性)や、平べったく盛り上がったもの(無茎性)など様々で、大きさも数ミリの小さなものから、数センチに及ぶ大きなものまで多岐にわたります。
健康診断の便潜血検査で陽性反応が出たことをきっかけに、大腸内視鏡検査を受けて発見されることが多いですが、自覚症状がないまま偶然見つかることも少なくありません。
大腸の壁は内側から粘膜、粘膜下層、固有筋層、漿膜(しょうまく)という層構造になっており、ポリープは最も内側の粘膜から発生します。
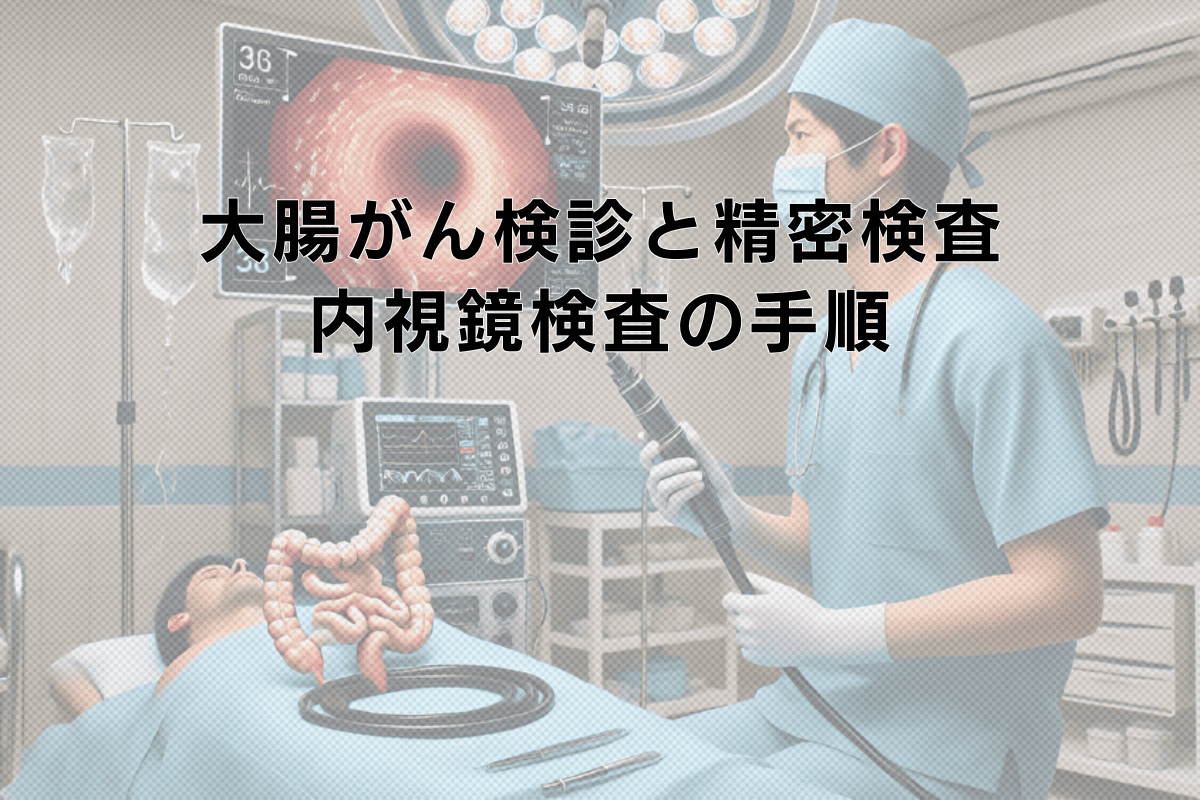
ポリープの種類(腫瘍性と非腫瘍性)
大腸ポリープは、細胞の性質によって大きく二つのタイプに分類し、一つは将来的にがん化する可能性のある腫瘍性ポリープ、もう一つは基本的にはがん化しない非腫瘍性ポリープです。
大腸内視鏡検査でポリープを切除する主な目的は、腫瘍性ポリープをがんになる前に取り除くことです。
腫瘍性ポリープの代表が腺腫(せんしゅ)で、大腸がんの多くは、腺腫が長い年月をかけて少しずつ大きくなり、その過程でがん細胞が発生して進行していくと考えられています。
また、近年では鋸歯状(きょしじょう)病変と呼ばれるタイプのポリープも、別の経路でがん化する前がん病変として重要視されます。
一方、非腫瘍性ポリープには過形成性ポリープや炎症性ポリープなどがあり、通常、がん化のリスクは低いとされています。
しかし、内視鏡で見ただけでは両者を100%正確に区別することは難しいため、ある程度の大きさ以上のポリープは切除して病理組織検査で詳しく調べることが一般的です。
ポリープの主な種類と特徴
| 分類 | 主な種類 | がん化のリスク |
|---|---|---|
| 腫瘍性ポリープ | 腺腫 | あり(大腸がんの主要な前がん病変) |
| 鋸歯状病変 (SSA/Pなど) | あり(近年重要視されている) | |
| 非腫瘍性ポリープ | 過形成性ポリープ | 基本的には低い(一部例外あり) |
| 炎症性ポリープ | ほとんどない |
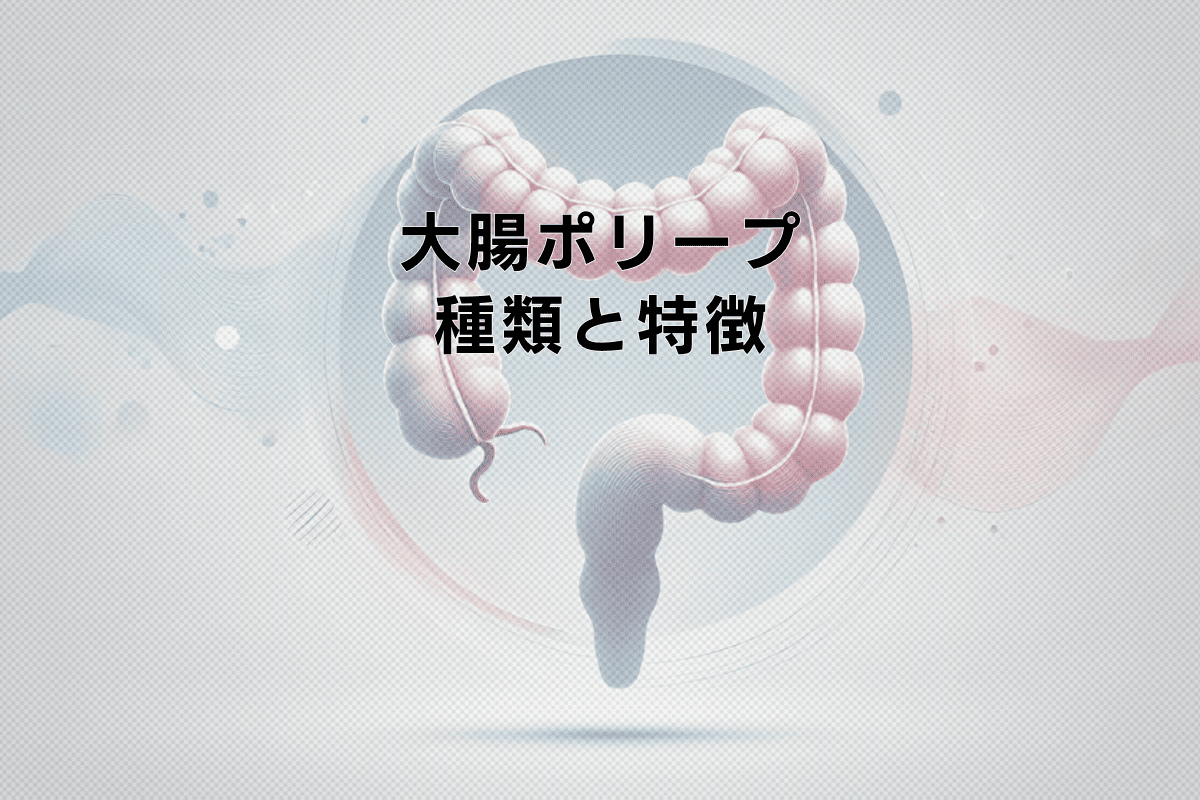
なぜポリープができるのか
大腸ポリープ、特にがん化する可能性のある腺腫が発生する明確な原因は完全には解明されていませんが、複数の要因が複雑に関与していると考えられています。
遺伝的な要因もその一つで、家族に大腸がんや大腸ポリープの既往がある方は、発生リスクが高まり、また、生活習慣との関連も深く指摘されています。
赤肉(牛、豚、羊など)や加工肉(ハム、ソーセージなど)の過剰な摂取は、腸内での発がん物質の産生を促す可能性があり、リスクを高める要素です。
逆に、食物繊維の豊富な野菜や果物は、便通を整え、発がん物質が腸管に接触する時間を短くすることで、リスクを低減させる効果が期待されています。
ポリープの発生に関与すると考えられる要因
- 加齢(50歳以上でリスクが増加)
- 食生活(赤肉や加工肉の過剰摂取、野菜・果物の摂取不足)
- 肥満、運動不足
- 喫煙、過度のアルコール摂取
ほとんどが無症状という特徴
大腸ポリープの最も厄介な特徴は、小さいうちはほとんど自覚症状がないことです。
ポリープがかなり大きくなったり、がん化して進行したりして初めて、便に血が混じる(血便)、便が細くなる、便秘と下痢を繰り返す、腹痛などの症状が現れますが、症状が出たときには、病状がかなり進んでいるケースも少なくありません。
症状がない段階で、定期的な大腸内視鏡検査によってポリープを発見し切除することが、大腸がんを予防する上で最も効果的で重要な手段です。
便潜血検査は、こうした無症状のポリープや早期がんからの微量な出血を捉えるための有効なスクリーニング検査です。
大腸ポリープの大きさとがん化率の密接な関係
大腸ポリープ、特に腺腫が見つかった場合、その悪性度を判断する上で最も重要な指標となるのが大きさです。
一般的に、ポリープは大きくなればなるほど、内部にがん細胞を含む確率(がん化率)が高くなることが多くの研究で明らかになっています。
大きさと悪性度の相関関係
腺腫は、正常な粘膜の細胞の遺伝子に異常が生じることから発生し、発生したばかりの小さな腺腫は、まだ良性の状態です。
しかし、時間の経過とともに細胞分裂を繰り返す中で、さらなる遺伝子異常が積み重なり、細胞の顔つきが悪く(異型度が強く)なっていき、ある一定の段階を超えると、制御不能な増殖を始めるがん細胞へと変化します。
この遺伝子変異の蓄積という考え方が、ポリープの成長とがん化の根底にあります。
ポリープが大きくなるということは、それだけ細胞分裂の回数が多く、遺伝子異常が蓄積する機会も多かったことを意味するため、ポリープのサイズとがん化率には明確な正の相関関係が存在するのです。
5mm未満のポリープのがん化リスク
直径が5mm以下の小さなポリープは、微小ポリープとも呼ばれ、このサイズのポリープにがん細胞が含まれている確率は非常に低く、研究報告にもよりますが、おおむね0.5%未満です。
ほとんどが良性の腺腫か、がん化のリスクが低い過形成性ポリープのため、施設によっては積極的に切除せず、経過観察の方針をとることもあります。
ただし、多数個ある場合や、小さいながらも表面の形状が悪性を示唆する陥凹(へこみ)などが見られる場合には、サイズが小さくても切除を検討します。
6mmから9mmのポリープのがん化リスク
直径が6mmから9mmのポリープになると、がん化率は少しずつ確実に上昇していき、がん化率は、約2%から10%程度と報告されています。
5mm以下と比較するとリスクは明らかに高くなるため、原則として内視鏡的に切除することが国内外のガイドラインで推奨されています。
この段階で切除することで、将来のがんへの進行を高い確率で未然に防ぐことができます。
10mm以上のポリープのがん化リスク
直径が10mm(1cm)を超えると、がん化率はさらに大きく上昇し、10mmから19mmのポリープではがん化率は約10%から25%、20mm(2cm)以上になると、確率は40%から50%以上に達するとも言われています。
20mmを超える大きなポリープの場合は、すでに粘膜下層まで浸潤した進行がんである可能性も考慮し、より慎重な診断と治療方針の決定が必要です。大きさは、治療の緊急性や切除方法を選択する上での決定的な要因の一つとなります。
ポリープの大きさとがん化率の目安
| ポリープの大きさ | がんが含まれる確率(目安) | 一般的な対応 |
|---|---|---|
| 5mm以下 | 0.5%未満 | 経過観察または切除 |
| 6mm 〜 9mm | 2% 〜 10% | 原則として切除 |
| 10mm以上 | 10%以上(サイズとともに急増) | 切除(より慎重な診断と治療が必要) |
大きさ以外の悪性度を判断する要因
ポリープの大きさは悪性度を予測する上で非常に重要な指標ですが、それだけが全てではありません。内視鏡専門医は、大きさ以外にも様々な所見を総合的に評価して、ポリープの性質をより正確に判断しようと努めています。
ポリープの組織型(腺腫とそれ以外)
ポリープにはがん化する可能性のある腺腫と、リスクが低い非腫瘍性ポリープがあり、腺腫はさらに、顕微鏡で見たときの組織の構造によって管状腺腫、絨毛管状腺腫、絨毛腺腫の3つに分類します。
絨毛成分(細かく枝分かれしたビロードのような構造)が多くなるほど、異型度が高く、がん化しやすい傾向があることが知られています。
内視鏡でもある程度の推測は可能ですが、最終的な確定診断は切除した組織を顕微鏡で調べる病理組織検査によって行います。
腺腫の組織型と特徴
| 腺腫の組織型 | 特徴 | がん化のリスク |
|---|---|---|
| 管状腺腫 | 腺管が管状構造を形成。最も一般的。 | 比較的低い |
| 絨毛管状腺腫 | 管状構造と絨毛構造が混在。 | 中程度 |
| 絨毛腺腫 | 絨毛構造が主体。 | 比較的高い |

腺腫内の異型度(グレード)
異型度とは細胞の顔つきの悪さ、つまり正常な細胞からどれだけかけ離れているかを示す指標です。腺腫の細胞は、正常な大腸粘膜の細胞と比べて、核が大きくなったり形が不揃いになったりするなどの異型を示します。
異型が軽度なものを低異型度腺腫、高度なものを高異型度腺腫と呼び、高異型度腺腫は、がんになる一歩手前の状態、あるいはごく初期のがん(粘膜内がん)とほぼ同義であり、切除が強く推奨されます。
異型度も、最終的には病理組織検査で確定します。
表面の形状や色調(内視鏡所見)
内視鏡でポリープを観察する際、専門医は大きさだけでなく、見た目からも多くの情報を得ています。
表面がゴツゴツと不整である、一部がへこんでいる(陥凹)、色が周囲の粘膜よりも赤みが強い、あるいは逆に白っぽくなっている、表面にびらんや出血が見られる、といった所見は、悪性度が高いことを示唆するサインです。
このような所見がある場合は、たとえポリープが小さくても、がん細胞が含まれている可能性を考えて慎重に対応します。
ポリープの形状(有茎性・亜有茎性・無茎性)
ポリープの全体的な形も重要な情報で、キノコのようにくびれのある茎を持つ有茎性ポリープは、比較的切除が容易です。
茎がなく平坦に広がる無茎性(表面型)のポリープは、がん細胞が発生した場合、横方向だけでなく、粘膜の下の層へ深く浸潤しやすい傾向があります。
特に、表面が平坦で中央がへこんでいるような陥凹型の病変は、小さくても早期から深い層へ浸潤する悪性度の高いがんである可能性があり、最も注意を要するタイプです。これをデノボがんと呼ぶこともあります。
悪性度を疑う内視鏡所見
- 表面の凹凸不整
- 陥凹(へこみ)の存在
- 強い発赤や色調の変化
- 出血しやすい、もろい
内視鏡検査におけるポリープの評価方法
近年の内視鏡技術の進歩は目覚ましく、単にポリープを見つけるだけでなく、その場で悪性度をかなり高い精度で診断することが可能になってきています。
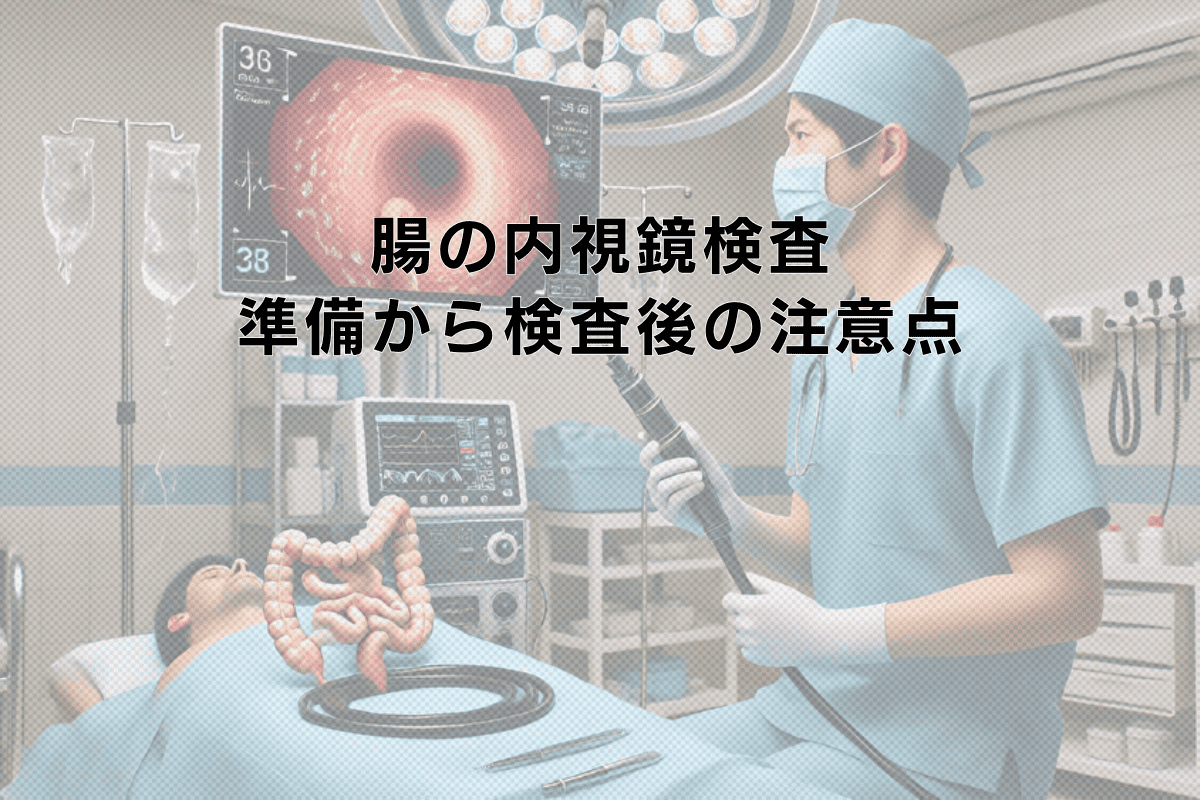
通常光観察と拡大観察
まず、内視鏡の基本的な機能である通常光(白色光)で大腸全体を観察し、ポリープの有無、場所、大きさ、形状などを確認します。ポリープが見つかると、次に内視鏡のズーム機能を使って表面を最大で約100倍にまで拡大して詳しく観察します。
拡大観察を行うことで、肉眼ではわからないような粘膜表面の微細な模様や血管の走行を詳細に評価でき、ポリープの性質をより深く知ることができます。
画像強調観察(NBIやBLIなど)
画像強調観察は、特殊な波長の光を粘膜に当てることで、表面の微細な血管や模様をより鮮明に映し出す技術です。代表的なものにNBI(Narrow Band Imaging)やBLI(Blue LASER Imaging)があります。
がん組織に特徴的な、太さや形が不規則な新生血管網が茶色く強調して表示されるため、ポリープが良性か悪性かを判断する上で極めて有用な情報を得ることができます。
画像強調観察でわかること
| 観察技術 | 原理 | 主な利点 |
|---|---|---|
| NBI / BLI | 血液中のヘモグロビンに吸収されやすい特殊な短波長の光を利用する | 粘膜表層の毛細血管のパターンを強調し、腫瘍血管を明瞭に描出する |
ピットパターン分類による診断
拡大観察や画像強調観察と併せて行われるのが、ピットパターン診断で、ピットとは、大腸粘膜の表面にある無数の小さなくぼみ(腺管の開口部)のことです。
ピットの形や配列パターンは、ポリープの組織型を反映しており、良性か悪性か、さらにはがんの場合の深達度(がんの深さ)までもある程度推測することが可能です。
正常な粘膜は綺麗な円形のピットが規則正しく並んでいますが、腺腫では円形や星芒状のピットが密集し、がん化が進むとピットの構造が乱れたり、消失したりします。
ピットパターン分類の概要
| パターン分類 | 主な所見 | 対応する病変 |
|---|---|---|
| I, II 型 | 正常な円形や星芒状のピット | 正常粘膜、過形成性ポリープ |
| III, IV 型 | 円形や管状、脳回状のやや不規則なピット | 腺腫 |
| V 型 | ピット構造が不明瞭、あるいは消失 | がん |
超音波内視鏡による深達度診断
ポリープが大きく、内視鏡所見からがんが疑われる場合には、超音波内視鏡(EUS)を用いてがんの深達度(大腸の壁のどの深さまでがんが達しているか)を調べることがあります。
内視鏡の先端から超音波を出すことで、大腸の壁を層構造として描き出し、がんが粘膜下層にとどまっているか、それより深い固有筋層にまで及んでいるかを評価します。
この情報は、内視鏡で切除できるか、あるいは外科手術が必要かを判断する上で極めて重要です。
ポリープの大きさに基づいた治療方針
大腸ポリープの治療方針は、主に大きさと、内視鏡所見から推測される悪性度に基づいて決定します。すべてのポリープを必ず切除するわけではなく、個々の状況に応じて最適な対応を選択します。
5mm以下の微小ポリープの扱い
5mm以下の微小ポリープはがん化率が極めて低いため、扱いは施設の方針や患者さんの状況によって異なり、直腸に多発する過形成性ポリープなどは、切除せずに経過観察とすることも少なくありません。
一方で、将来のがん化のリスクを完全に取り除くという観点や、診断の正確性を期すために、発見したポリープはサイズにかかわらず全て切除する(Cold Polypectomyという通電しない安全な方法を用いることが多い)方針の施設も増えています。
6mmから19mmのポリープの切除
6mm以上のポリープは、大きくなるにつれてがん化率が上昇するため、原則として内視鏡的切除の適応となります。このサイズのポリープは、ほとんどの場合、日帰りまたは短期入院での内視鏡治療が可能です。
切除することで、がんへの進行を予防できるだけでなく、切除した組織を病理検査に出して確定診断を得られるという大きな利点があります。
20mm以上の大きなポリープの切除
20mm(2cm)を超える大きなポリープは、がんを含んでいる可能性がかなり高くなり、また、サイズが大きいために通常の内視鏡切除では一括で取り除くことが難しく、より高度な技術を要する場合があります。
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)といった専門的な手技が必要になることも多く、入院が必要となることがほとんどです。
がんが粘膜下層深くまで浸潤している可能性が疑われる場合は、リンパ節転移のリスクを考慮し、内視鏡治療ではなく外科的な腸管切除術を選択することもあります。
ポリープの大きさ別治療方針の目安
| ポリープの大きさ | 一般的な治療方針 | 主な切除方法 |
|---|---|---|
| 5mm以下 | 経過観察または切除 | コールドポリペクトミー |
| 6mm 〜 19mm | 内視鏡的切除 | ポリペクトミー、EMR |
| 20mm以上 | 内視鏡的切除または外科手術 | EMR、ESD、外科手術 |
切除せずに経過観察を選択する場合
ポリープを切除せずに経過観察とするのは、主にがん化のリスクが極めて低いと判断される小さな非腫瘍性ポリープの場合です。
また、ご高齢の方や重篤な心臓病、呼吸器疾患などをお持ちの方で、ポリープ切除に伴う偶発症(出血や穿孔)のリスクが、ポリープを放置するリスクを上回ると判断される場合にも、経過観察が選択されることがあります。
その場合、1年後など、一定期間をあけて再度内視鏡検査を行い、ポリープの大きさや形に変化がないかを確認していくことになります。
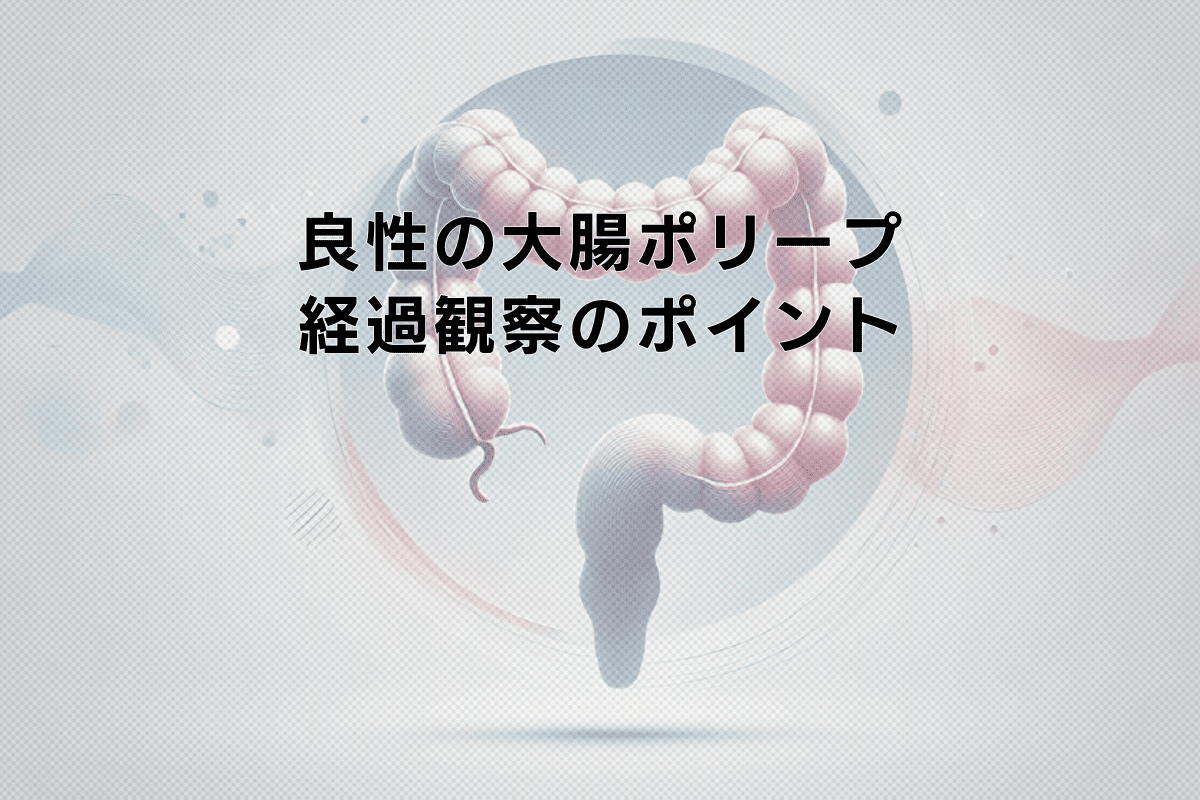
大腸ポリープの主な切除方法
内視鏡による大腸ポリープの切除方法は、ポリープの大きさや形状に応じていくつかの手技を使い分けます。いずれも、開腹手術に比べて体への負担が格段に少ない治療法です。
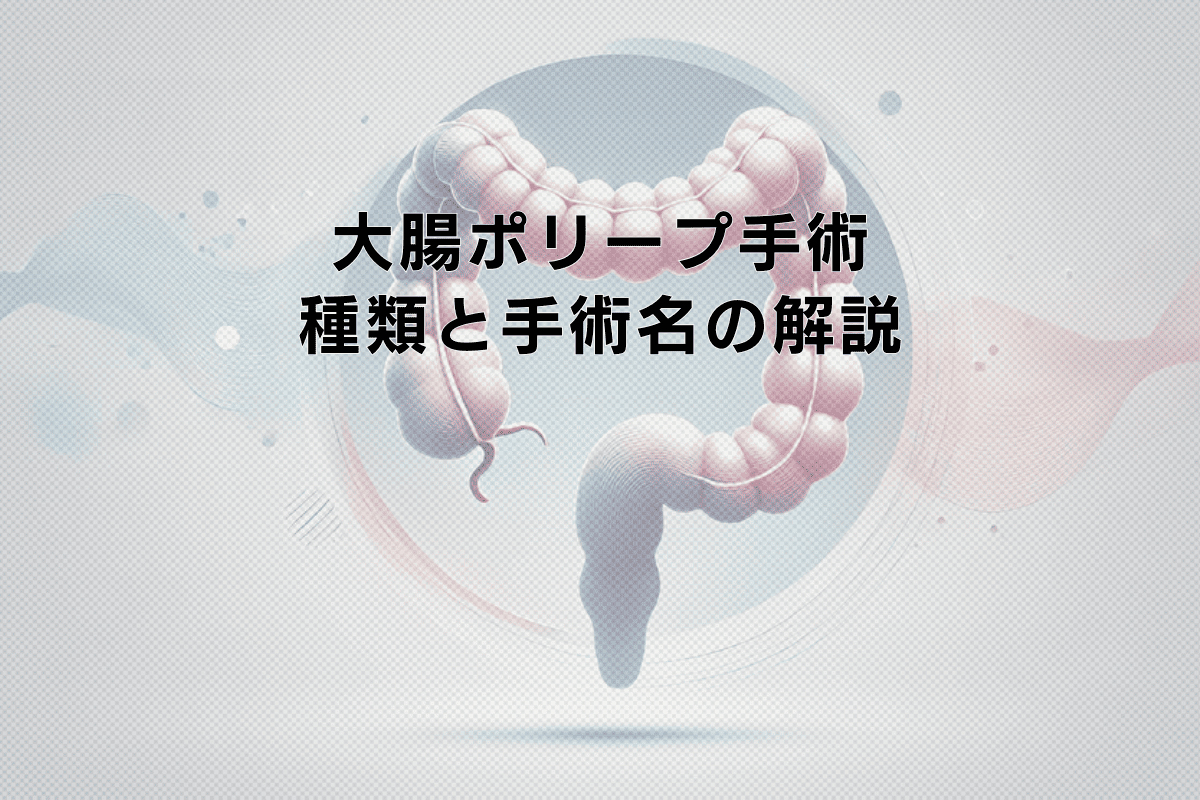
内視鏡的ポリープ切除術(ポリペクトミー)
主に茎のある有茎性ポリープに対して行われる、最も基本的な切除方法です。スネアと呼ばれる金属製の輪状のワイヤーを内視鏡の先端から出し、ポリープの茎に引っ掛けて締め付け、高周波電流を流して焼き切ります。
比較的小さなポリープであれば、この方法で安全かつ迅速に切除でき、近年では、通電しないコールドポリペクトミーも小さなポリープに対して広く行われています。
内視鏡的粘膜切除術(EMR)
茎のない無茎性や平坦なポリープに対して広く用いられる方法です。
ポリープの下の粘膜下層に生理食塩水などを注入して、ポリープ全体を人工的に盛り上げると、ポリープが下の固有筋層から浮き上がり、安全に切除しやすくなります。
その後、ポリペクトミーと同様にスネアをかけて高周波電流で焼き切り、一般的に20mm程度までのポリープが良い適応とされます。
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)
EMRでは一括で切除することが難しい20mm以上の大きなポリープや、早期がんに対して行われる、より高度な技術を要する治療法です。
専用の電気メスを用いて、ポリープ周囲の粘膜を切開し、さらに粘膜下層を少しずつ剥がし取っていくことで、大きな病変でも確実に一括で切除することを目指します。
手技の難易度が高く、治療時間も長くなるため、経験豊富な専門医がいる限られた施設で行われます。

主な内視鏡的切除方法の比較
| 切除方法 | 主な対象 | 手技の概要 |
|---|---|---|
| ポリペクトミー | 有茎性の小さなポリープ | スネアで茎を絞めて焼き切る |
| EMR | 無茎性、平坦なポリープ(〜20mm) | 粘膜下層に液体を注入し、盛り上げてから焼き切る |
| ESD | 大きなポリープ(20mm〜)、早期がん | 電気メスで病変周囲を切開し、剥離する |
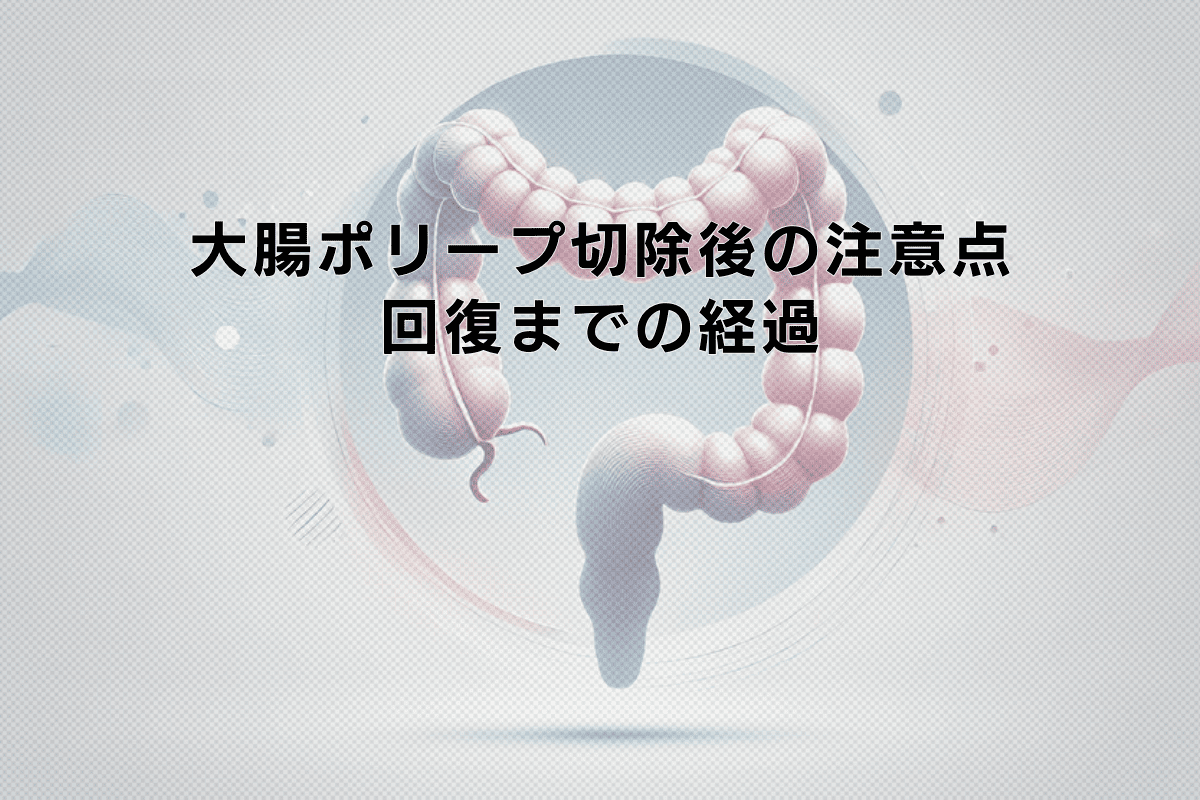
外科的手術が必要になるケース
内視鏡検査の結果、がんが粘膜下層よりも深い層まで浸潤していることが強く疑われる場合や、リンパ節への転移の可能性がある場合には、内視鏡治療の適応とはならず、外科的な腸管切除術が必要となります。
これは、がん細胞が周囲のリンパ管や血管に入り込んで全身に広がっている可能性があり、がんのある部分の腸管と所属リンパ節を一緒に切除する必要があるためです。
また、ポリープが非常に大きかったり、内視鏡が届かない場所に存在したりする場合も、外科手術が選択されることがあります。現在では、腹腔鏡手術のような低侵襲な外科手術が主流です。
大腸ポリープの大きさと悪性度に関するよくある質問
- 小さなポリープは放置しても大丈夫ですか。
-
5mm以下の微小ポリープはがんである可能性が極めて低いため、内視鏡所見から明らかに良性(過形成性ポリープなど)と判断できる場合は、切除せずに経過観察とすることがあります。
しかし、腺腫は時間とともに大きくなり、がん化する可能性があります。
現在では、通電しないコールドポリペクトミーという安全な切除手技が普及したため、将来のリスクを考慮して小さな腺腫も発見時に切除する方針の医療機関が増えています。
最終的な方針は、ポリープの所見や個々の患者さんの年齢、健康状態などを総合的に判断して決定しますので、担当医とよく相談することが大切です。
以下の記事も参考にしてください
【いつ大腸がん検査を受けるべきか|症状チェックから精密検査まで】
大腸がん検査を受けるべきタイミングは、年齢やリスク要因によって異なります。症状チェックから便潜血検査、内視鏡検査までの流れを理解することで、適切な時期に検査を受けることができます。 - ポリープを切除すればもう大腸がんの心配はありませんか。
-
ポリープを切除することは、ポリープが将来がん化するのを防ぐ上で非常に有効ですが、ポリープができやすい体質そのものが変わるわけではないため、別の場所に新たなポリープ(異時性病変)が発生する可能性があります。
一度ポリープを切除した方は、そうでない方と比べて、定期的な大腸内視鏡検査を継続して受けることが極めて重要です。
検査の間隔は、切除したポリープの数、大きさ、組織型などによって決められますが、通常は1年から3年ごとの検査が推奨されます。
- ポリープの大きさは食事で変えられますか。
-
食事の工夫によって、できてしまったポリープを小さくしたり、消滅させたりすることは、残念ながらできません。
ポリープの成長は、細胞の遺伝子レベルでの変化によるものであり、食事内容で直接コントロールすることは困難です。
しかし、長期的な視点で見れば、食物繊維を豊富に摂り、赤肉や加工肉を控えるといったバランスの取れた食事は、新たなポリープの発生リスクを低減させる上で重要であると考えられています。
- 一度にたくさんのポリープが見つかった場合、リスクは高いですか。
-
ポリープが多数(例えば10個以上)見つかる場合や、血縁者に若くして大腸がんになった方がいる場合は、家族性大腸腺腫症(FAP)やリンチ症候群といった遺伝性の病気の可能性も考慮する必要があります。
これらの病気は通常よりも若年で、かつ多発性にポリープやがんが発生するリスクが非常に高いことが特徴です。
多数のポリープが見つかった場合は、個々のポリープの大きさと同時に、遺伝的な背景がないかどうかも含めて慎重に評価し、より厳重なサーベイランス(監視)計画を立てることが重要です。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸ポリープの内視鏡治療 – 早期発見と切除術の重要性】
大きさと悪性度の基本を押さえたら、実際のポリープ切除の流れや適応を知っておくと安心です。検査〜治療の具体像をイメージしたい方に参考になります。
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
大腸ポリープの大きさと悪性度の関係について理解したら、次は実際の検査準備について知っておくと安心です。3日前からの食事制限や下剤の服用方法など、検査を初めて受ける方に特に参考になる内容です。
以上
参考文献
Hiraoka S, Kato J, Fujiki S, Kaji E, Morikawa T, Murakami T, Nawa T, Kuriyama M, Uraoka T, Ohara N, Yamamoto K. The presence of large serrated polyps increases risk for colorectal cancer. Gastroenterology. 2010 Nov 1;139(5):1503-10.
Tanaka S, Saitoh Y, Matsuda T, Igarashi M, Matsumoto T, Iwao Y, Suzuki Y, Nozaki R, Sugai T, Oka S, Itabashi M. Evidence-based clinical practice guidelines for management of colorectal polyps. Journal of Gastroenterology. 2021 Apr;56(4):323-35.
Watabe H, Yamaji Y, Okamoto M, Kondo S, Ohta M, Ikenoue T, Kato J, Togo G, Matsumura M, Yoshida H, Kawabe T. Risk assessment for delayed hemorrhagic complication of colonic polypectomy: polyp-related factors and patient-related factors. Gastrointestinal endoscopy. 2006 Jul 1;64(1):73-8.
Ochiai Y, Inoshita N, Iizuka T, Nishioka H, Yamada S, Kitagawa M, Hoteya S. Clinicopathological features of colorectal polyps and risk of colorectal cancer in acromegaly. European Journal of Endocrinology. 2020 Mar;182(3):313-8.
Sano Y, Hotta K, Matsuda T, Murakami Y, Fujii T, Kudo SE, Oda Y, Ishikawa H, Saito Y, Kobayashi N, Sekiguchi M. Endoscopic removal of premalignant lesions reduces long-term colorectal cancer risk: results from the Japan polyp study. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2024 Mar 1;22(3):542-51.
Yamaji Y, Mitsushima T, Yoshida H, Watabe H, Okamoto M, Wada R, Ikuma H, Kawabe T, Omata M. The malignant potential of freshly developed colorectal polyps according to age. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention. 2006 Dec 1;15(12):2418-21.
Kawamura T, Takeuchi Y, Yokota I, Takagaki N. Indications for cold polypectomy stratified by the colorectal polyp size: a systematic review and meta-analysis. Journal of the Anus, Rectum and Colon. 2020 Apr 28;4(2):67-78.
Summers RM. Polyp size measurement at CT colonography: what do we know and what do we need to know?. Radiology. 2010 Jun;255(3):707-20.
Unal H, Selcuk H, Gokcan H, Tore E, Sar A, Korkmaz M, Bilezikci B, Demirhan B, Gur G, Yilmaz U. Malignancy risk of small polyps and related factors. Digestive diseases and sciences. 2007 Oct;52(10):2796-9.
Øines M, Helsingen LM, Bretthauer M, Emilsson L. Epidemiology and risk factors of colorectal polyps. Best practice & research Clinical gastroenterology. 2017 Aug 1;31(4):419-24.