大腸内視鏡検査は、大腸がんやポリープなどの病気を早期に発見するためにとても重要な検査で、検査を正確に行うためには、事前に大腸の中をきれいにする必要があります。
その際、下剤(腸管洗浄剤)を服用し、何度も排便を繰り返すことで大腸内を洗浄し、この過程で、ご自身の便の色がどのように変化していくかを確認することが、検査の精度を左右する大事な指標です。
この記事では、大腸内視鏡検査の準備段階における便の色の変化、検査が可能と判断する基準、色がうまく変化しない場合の対処法などについて、詳しく解説します。

大腸内視鏡検査の準備と便の観察の重要性
大腸内視鏡検査は、ただ単に医療機関へ行けば受けられるものではありません。検査の精度を高め、安全に実施するために、受検者自身による事前の準備がとても大切で、大腸の中を空にするための準備は、検査の成否を分ける鍵です。
準備が適切に行われたかを判断する上で、ご自身の目で便の状態を確認する作業が重要になります。
なぜ大腸内視鏡検査が必要か
大腸内視鏡検査の最大の目的は、大腸がんの早期発見と予防です。大腸がんは、早期の段階では自覚症状がほとんどなく、症状が現れたときには、すでに進行しているケースも少なくありません。
しかし、内視鏡検査によってがんになる前のポリープの段階で発見し切除することで、がんへの進行を防ぐことが可能です。
また、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患の診断や、治療効果の判定、経過観察にも、この検査は大きな役割を果たします。
定期的に検査を受けることで、自覚症状のない病変を発見し、早期治療につなげることが、ご自身の健康を守る上で非常に有効です。
検査前の準備の流れ
検査の準備は、通常、検査日の数日前から始まり、まずは食事制限を行い、消化しにくい食べ物を避けます。これは、食物の残りかすが腸内に残らないようにするためです。
検査前日には、消化に良い検査食などを中心に摂取し、夜に錠剤などの下剤を服用する場合もあります。
検査当日は、朝から腸管洗浄剤という液体の下剤を数時間かけて飲み始め、大腸内に残っている便をすべて排出し、腸内を空の状態にします。この一連の準備が、大腸の粘膜を隅々まで観察するための土台を作り、検査の質を保証します。
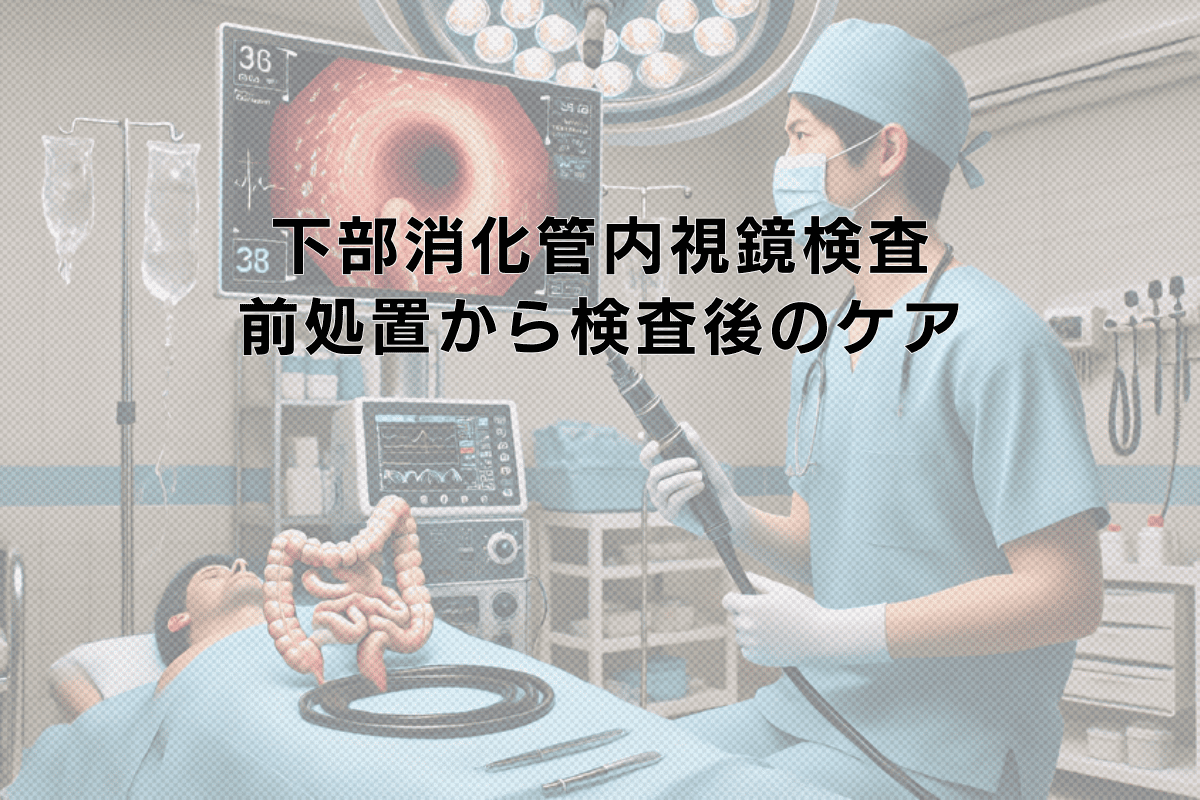
便の色の観察が大事な理由
腸管洗浄剤を飲むと、頻繁に便意をもよおし、徐々に便の状態が変化していきます。最初は固形物が混じった便が出ますが、回数を重ねるごとに水分だけになり、最終的には透明に近い液体になるのです。
医師や看護師は、便の色や透明度を見て、大腸の中が十分にきれいになったかを判断します。もし、便にかすが残っていたり、色が濁っていたりすると、泥水の中で物を探すように、小さなポリープや病変が見逃される原因になります。
ご自身で便の色を観察し、状態を医療機関に正確に伝えることが、質の高い検査につながります。
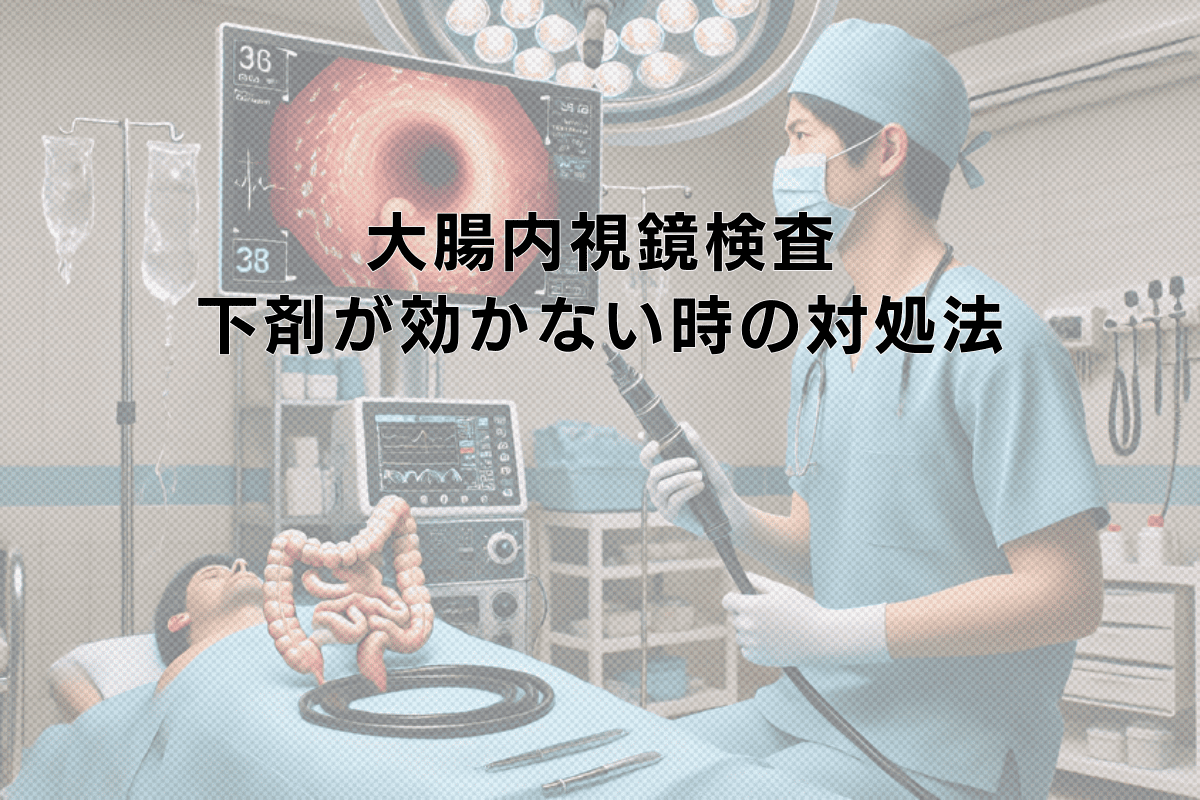
検査前の食事制限と便への影響
大腸内視鏡検査の成功は、大腸の壁がどれだけきれいに観察できるかにかかっているため、検査数日前からの食事管理が非常に重要です。
食べた物は消化・吸収され、残りかすが便となり、消化しにくい食べ物は、大腸内に長く留まり、検査の妨げになる可能性があります。
検査3日前から意識する食事
検査の3日前からは、食物繊維の多い食品や、種のある果物などを避けるように心がけましょう。食物繊維は消化されにくいので、腸内に残りやすく、特に、玄米や雑穀米、きのこ類、海藻類、こんにゃくなどは注意が必要です。
また、トマトやキウイ、イチゴなどに含まれる小さな種は、消化されずに腸内に残り、内視鏡の管に詰まってしまうこともあるため、避けてください。
食物繊維の多い食品や、種のある果物を避けることで、検査当日の腸管洗浄がスムーズに進みやすくなります。普段から便秘気味の方は、少し早めに食事制限を始めることも有効です。

食事内容の基本方針
食事の基本は、消化が良く、腸に残りにくいものを選ぶことです。白米やうどん、食パン(胚芽やふすまを含まないもの)、豆腐、卵、脂肪の少ない鶏肉や白身魚などが適していて、調理法も、揚げるよりは煮る、蒸すといった方法が良いでしょう。
| 分類 | 摂取を勧める食品 | 避けるべき食品 |
|---|---|---|
| 主食 | 白米、おかゆ、うどん、食パン | 玄米、雑穀米、そば、パスタ、コーンフレーク |
| 主菜 | 鶏ささみ、白身魚、卵、豆腐、はんぺん | 脂肪の多い肉(バラ肉)、加工肉、青魚 |
| 野菜・果物 | 具のないスープ、じゃがいも、バナナ | きのこ類、海藻類、種のある果物(キウイ、イチゴ) |
検査前日に摂取を勧める食事
検査前日は、食事制限がさらに重要で、多くの医療機関では、専用の検査食を用意しているので、活用することをお勧めします。
検査食は、消化が良く、腸内にかすが残りにくいように計算されて作られているため、何を食べれば良いか迷う必要がなく安心です。
ご自身で食事を用意する場合は、おかゆや具のないスープ、素うどん、豆腐、プリン、ゼリー(色の濃いものを除く)などが良いでしょう。固形物は昼食までとし、夕食は固形物を避けて、具のないスープや透明な飲料のみにすることが一般的です。
- おかゆ(梅干しや佃煮は除く)
- 具のないコンソメスープや味噌汁の上澄み
- 豆腐(薬味なし)
- 透明なゼリーや飴
検査前日に避けるべき食事
検査前日には、消化の悪いものはもちろん、色の濃い飲み物も避ける必要があります。
牛乳やヨーグルトなどの乳製品は腸の壁に白い膜を張ってしまい、観察の妨げになることがあるため控えましょう。
また、赤や紫、緑などの色の濃いジュースや飲み物は、腸の粘膜に色が残り、炎症や出血と見間違える可能性があるため、水やお茶、透明なスポーツドリンクなどを飲んでください。アルコールも腸を刺激するため、控えることが必要です。
前日に特に注意する食品群
以下の食品は、少量でも腸内に残りやすいため、前日は絶対に摂取しないように注意が必要です。
| 食品の種類 | 具体的な例 | 避ける理由 |
|---|---|---|
| 乳製品 | 牛乳、ヨーグルト、チーズ | 腸壁に白い膜が残り、観察の妨げになるため |
| 色の濃い飲料 | ぶどうジュース、野菜ジュース、青汁 | 腸粘膜に着色し、病変との区別が難しくなるため |
| 繊維質の多い食品 | ごぼう、きのこ、ほうれん草、豆類 | 消化されずに残りやすく、洗浄を妨げるため |

食事内容が便の色に与える影響
普段の便の色は、食べたものや胆汁の色素によって決まり検査、前の食事制限は、便の色にも影響を与えます。
繊維質の少ない食事を続けると、便の量は少なくなり、色も薄くなる傾向があり、これは、便を構成する固形成分が少なくなるためです。
検査前日の夜や当日の朝に飲む下剤の効果を最大限に引き出すためにも、食事制限は便の性状を変化させ、排出しやすい状態を作る上で大事な役割を担っています。
下剤(腸管洗浄剤)の役割と便の色変化
検査当日に行う準備の核心が、腸管洗浄剤の服用です。大腸内を物理的に洗い流し、観察に適した状態にするための液体状の下剤で、多くの受検者が、この過程を最も大変だと感じますが、正確な検査のためには避けて通れません。
ここでは、腸管洗浄剤の種類や飲み方、服用後の便がどのように変化していくかを段階的に説明します。
下剤の種類と特徴
腸管洗浄剤にはいくつかの種類があり、それぞれ味や飲む量、特徴が異なり、代表的なものに、ポリエチレングリコール(PEG)製剤や、硫酸ナトリウム・硫酸カリウム・硫酸マグネシウムなどを配合した製剤があります。
医療機関は、受検者の年齢や既往歴(特に腎臓や心臓の病気)、普段の便通の状態などを総合的に考慮して、最も適した洗浄剤を選択します。ご自身に合わないと感じる場合は、医師に相談することも可能です。
| 洗浄剤の種類 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| PEG製剤 | 約2リットルを服用。スポーツドリンクに近い味。 | 飲む量が多いが、体内への吸収が少なく安全性が高い。 |
| 硫酸塩配合剤 | 約1リットル+水。塩味が強く、味が濃いめ。 | 腎機能が低下している場合は注意が必要。飲む量は少ない。 |
| ピコスルファートナトリウム | 前日に錠剤や液体を服用し、当日は水分のみ。 | 当日の水分摂取量が自己管理となり、脱水に注意が必要。 |

下剤の正しい飲み方
腸管洗浄剤は、医療機関の指示に従って、決められた量を決められた時間をかけてゆっくりと飲むことが大切です。一般的には、コップ1杯(約180ml)を10〜15分かけて飲むペースが推奨されます。
一度に大量に飲むと、吐き気や腹部膨満感の原因となることがあり、味に飲みにくさを感じる場合は、冷やして飲むと少し飲みやすくなることがあります。
また、洗浄剤の服用と並行して、水やお茶などの水分を十分に摂ることも、脱水を防ぎ、洗浄効果を高める上で重要です。
服用開始後の便の変化
腸管洗浄剤を飲み始めると、30分から1時間ほどで最初の便意を感じることが多く、個人差はありますが、その後は何度もトイレに行くことになります。
最初はまだ形のある便や、泥状の便が出ますが、これは、大腸内に残っていた便が排出され始めたサインです。この段階ではまだ腸内はきれいになっておらず、洗浄は始まったばかりなので、慌てずに、指示通りに洗浄剤を飲み続けましょう。
何度か排便するうちに、固形物はなくなり、水のような便へと変わっていきます。
便の色変化の段階的推移
服用を続け排便を繰り返すうちに、便の状態は劇的に変化し、固形物がなくなり、水のような便に変わります。色も、茶色から徐々に黄色へと薄くなっていきます。
最終的には、尿のような透明感のある黄色い液体になれば、腸内がきれいになったと判断でき、この色の変化をご自身でしっかりと確認することが、準備完了の目安です。
便の状態変化の目安
| 段階 | 便の状態 | 色の目安 |
|---|---|---|
| 初期(1〜3回目) | 固形物のある便、泥状の便 | 濃い茶色 |
| 中期(4〜7回目) | 固形物がなくなり、水様便になる。かすが混じる。 | 茶色〜黄色で濁っている |
| 最終段階(8回目以降) | 完全に水様になり、透明感が出る。かすがほぼない。 | 黄色透明〜無色透明 |
検査可能となる便の色の判断基準
腸管洗浄剤を飲み終えた後、最終的にご自身の便の色を確認し、検査を実施できる状態かどうかを判断します。
ここでは、検査が可能となる便の色の具体的な基準について、状態を詳細に説明することで、画像を見るようにイメージできるよう解説します。
検査ができる便の状態とは
大腸内視鏡検査を行うための理想的な状態とは、大腸の粘膜を隅々まで詳細に観察できる状態、つまり、便の残りかすが一切ない状態です。
便の色が透明に近くなり、便器の底の模様や色がはっきりと見えるようになれば、準備が整ったと考えて良いでしょう。かすが浮いていたり、色が濁っていたりする場合は、まだ洗浄が不十分な可能性があります。
黄色透明な便(理想的な状態)
最も理想的な状態は、薄い麦茶や、色の薄いリンゴジュースのような、完全に透明な黄色の液体で、便器の中を見ても、固形物や目に見えるかすが全く浮いていない状態を目指します。
この状態であれば、数ミリ単位の微細なポリープや、粘膜のわずかな色の変化なども見逃すことなく、精度の高い観察が可能です。
黄色は、便の色素であるビリルビンではなく、腸管洗浄剤そのものの色や、わずかな腸液の色が反映されたものです。
薄い黄色の便(許容範囲)
完全に無色透明にならなくても、薄い黄色で、便器の底が見える程度の透明度があれば、多くの場合、検査は問題なく実施できます。ごくわずかな、コショウの粉のような小さなかすが浮いている程度であれば許容範囲と判断されます。
ただし、全体的に濁っていて底が見えにくい場合は、まだ不十分です。
検査可能な便の判断基準
| 判断 | 色 | 透明度・状態 |
|---|---|---|
| 理想的 | 黄色透明〜無色透明 | 固形物やかすが全くない。便器の底がはっきり見える。 |
| 許容範囲 | 薄い黄色 | 固形物はないが、ごくわずかなかすが浮いていることがある。 |
| 洗浄不十分 | 茶色〜濃い黄色 | 全体的に濁っており、便器の底が見えにくい。かすが多く浮いている。 |
便の残渣(固形物)が混じる場合
腸管洗浄剤をすべて飲み終えても、まだ便に固形物のかす(残渣)が混じっている場合は、洗浄が不十分である可能性が高く、前日や数日前に食べた消化の悪いものの影響が考えられます。
このような状態では、小さな病変がかすに隠れて見えないため、検査の精度が著しく低下し、場合によっては、検査を延期する必要も出てきます。医療機関に到着後、看護師に正直に便の状態を伝え、指示を仰いでください。
便の色が変化しない場合の主な原因と対処法
指示通りに腸管洗浄剤を飲んでいるにもかかわらず、便の色がなかなか透明にならないと、不安になるものです。これにはいくつかの原因が考えられます。
食事制限が不十分だった可能性
最も多い原因は、検査前の食事制限がうまくできていなかったケースです。食物繊維の多い野菜やきのこ類、種のある果物などを知らずに食べてしまうと、腸内に残り、洗浄剤を飲んでもなかなか排出されません。
食事制限の指示は、一見細かいように思えますが、一つ一つに理由があり、次回の検査の際は、渡された指示書を再度よく確認し、忠実に守ることが重要です。不明な食品があれば、食べる前に医療機関に確認してください。
下剤の服用方法に問題があった場合
腸管洗浄剤を飲むペースが速すぎたり、逆に遅すぎたり、あるいは指示された量をすべて飲みきれなかったりした場合も、洗浄が不十分になる原因です。
また、洗浄剤と一緒に飲むべき水分量が不足していると、便が十分に洗い流されません。吐き気などを感じた場合は、無理をせず一時中断し、少し休んでから再開しましょう。
服用時のセルフチェック
- 指示された量を全量飲みきれているか
- 決められたペースで飲めているか
- 洗浄剤以外の水分(水やお茶)も十分に摂っているか
水分摂取が不足しているケース
腸管洗浄は、洗浄剤の力だけでなく、十分な水分によって便を洗い流すことで成り立っています。
洗浄剤を飲むことだけに集中してしまい、水やお茶などの水分摂取がおろそかになると、体は脱水傾向になり、腸内の水分も不足し、便の排出が滞り、腸内がきれいになりにくくなります。
洗浄剤自体が体内の水分を腸に集める働きをするため、意識してこまめに水分を補給することが、脱水を防ぎ、洗浄効果を高める上でとても大切です。
| タイミング | 摂取する水分 | 目安量 |
|---|---|---|
| 洗浄剤服用中 | 水、お茶、透明なスポーツドリンク | 洗浄剤の量に加えて500ml〜1L程度 |
| 洗浄剤服用後 | 水、お茶 | 喉の渇きに応じて、検査まで適宜補給 |
便秘症や体質による影響
普段から頑固な便秘症の方は、腸の動きが比較的ゆっくりであるため、通常の方と同じ量の洗浄剤では腸内がきれいになりにくいことがあります。
また、以前に腹部の手術を受けたことがある方は、腸が癒着して便が通過しにくい場所がある可能性も考えられます。
このような場合は、事前に医師に相談し、下剤の種類を変更したり、前日から下剤を服用したりするなど、特別な対策を講じることが必要です。
事前にご自身の状況を伝えておくことで、医療機関側も個人に合わせた準備計画を立てることができます。自己判断で市販の便秘薬などを追加で使用することは絶対に避けてください。
検査後の便の状態と注意点
無事に検査が終了した後も、体調が完全に元に戻るまでには少し時間がかかり、特に、食事を再開した後の便の状態は、気になる点の一つでしょう。
ここでは、検査後の便の特徴や、食事による変化、そしてどのような症状に注意すべきかを解説します。
検査直後の便の特徴
検査が終わった直後は、まだ腸管洗浄剤や検査時に注入した空気の影響が残っているため、お腹が張った感じがしたり、水のような便が少量出たりすることがあります。これは自然な反応であり、心配は要りません。
腸内に残った空気がおならとして排出されるにつれて、お腹の張りは徐々に改善していきます。無理に我慢せず、ガスは排出するようにしましょう。
食事再開後の便の変化
検査後の最初の食事は、お腹にやさしい消化の良いものから始め、おかゆやうどん、スープ、豆腐などが適しています。食事を再開すると、腸の動きも活発になり、徐々に通常の便が作られるようになります。
検査後、1〜2日は便が出ないこともありますが、これは腸内が完全に空になっているためで、異常ではありません。
その後、最初に形成される便は、少し軟らかいことが多いですが、食事内容が通常に戻るにつれて、普段の硬さと色に戻っていきます。
検査後の食事の進め方
| 時期 | 食事内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 検査当日 | おかゆ、うどん、スープ、豆腐など | 消化の良いものを選び、暴飲暴食は避ける。 |
| 検査翌日 | 通常の食事に近いもの | 刺激物やアルコール、脂っこいものは引き続き控える。 |
| 検査翌々日以降 | 通常の食事 | 体調を見ながら、普段の食生活に徐々に元に戻す。 |
血便など注意を要する症状
通常、検査後の経過は良好ですが、まれに合併症が起こる可能性もあり、注意が必要なのは、検査後の出血です。
もし、検査後に以下のような症状が現れた場合は、合併症の可能性があるため、ためらわずにすぐに検査を受けた医療機関に連絡してください。
- 何度も続く血便(便器が赤くなるような出血)
- 我慢できないほどの強い腹痛、どんどん痛みが強くなる
- 腹部が板のように硬くなる、発熱する
検査中にポリープを切除した場合は、数日経ってから出血するリスクがゼロではありません。多くの場合、自然に止まりますが、念のため注意が必要です。医療機関から渡された緊急連絡先を必ず確認しておきましょう。
日常生活に戻るまでの目安
ほとんどの場合、検査の翌日には通常の日常生活に戻ることができますが、検査当日は鎮静剤の影響が残っている可能性があるため、車や自転車の運転、危険を伴う作業、重要な判断を伴う仕事は絶対に避けてください。
食事も、翌日からは徐々に普段の内容に戻していけますが、腸を休ませるため、数日間は香辛料などの刺激物やアルコールの摂取は控えましょう。
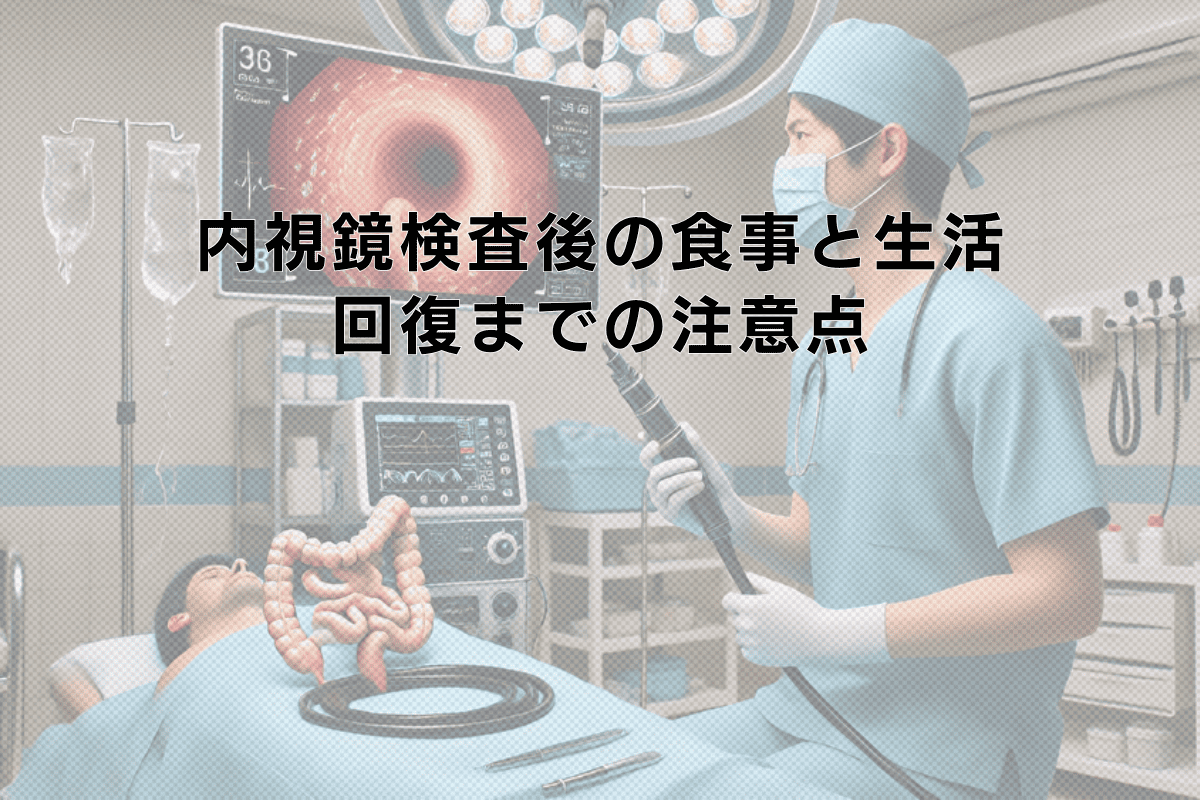
大腸内視鏡検査における便の色に関するよくある質問
最後に、大腸内視鏡検査の準備、特に便の色に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で回答します。
- 下剤を飲んでも便意がありません。どうすれば良いですか。
-
腸管洗浄剤を飲み始めてから最初の便意が来るまでの時間には個人差があります。1時間以上経っても全く便意がない場合は、体が冷えている、あるいは水分が不足している可能性があります。
お腹を優しくマッサージしたり、室内を少し歩いたりして腸の動きを促してみてください。それでも便意が来ない場合は、自己判断で服用を続けず、医療機関の指示を仰いでください。
- 便の色がなかなか透明になりません。検査は中止になりますか。
-
指示通りに洗浄剤を全量飲み終えても便の色が濁っている場合、まずはその状態を医療機関に正直に伝えましょう。追加で下剤を服用したり、浣腸を行ったりすることで、検査が可能になる場合もあります。
それでも腸内がきれいにならないと判断された場合は、安全で正確な検査のために、後日改めて検査を計画することもあります。
見えない部分を残したまま検査を強行するより、万全の状態で再検査する方が、ご自身のためになります。
- 検査当日の朝、固形物を食べてしまいました。
-
検査当日の朝は絶食が原則で、もし誤って固形物を食べてしまった場合は、正直に医療機関に申し出てください。食べたものや量によっては、検査の時間を午後にずらしたり、延期したりする必要があります。
隠したまま検査を受けると、食物が内視鏡の妨げになり、正確な診断ができないだけでなく、安全上の問題も生じる可能性があります。
- 検査後、いつから通常の便の色に戻りますか。
-
検査後、通常の食事を再開してから1〜3日程度で、普段の茶色い便に戻ることが一般的で、食事を始めても、すぐには便が出ないこともよくあります。腸内に食べ物が溜まり、便が形成されるまでの時間が必要です。
もし、検査後数日経っても黒い便(タール便)や赤い便が続く場合は、出血の可能性も考えられるため、検査を受けた医療機関に相談してください。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
便の色変化の基本を押さえたら、次は実際の検査準備の全体像について知っておくと安心です。3日前からの食事制限や下剤の服用タイミングなど、具体的な準備方法を詳しく解説しています。
【大腸内視鏡検査で下剤が効かない場合の対処方法】
便がなかなか透明にならないとき“どうすれば?”と思う方へ。飲み方の工夫や当日の対処、便秘傾向の方の準備ポイントを具体的に示しています。
以上
参考文献
Ikematsu H, Takara Y, Nishihara K, Kano Y, Owaki Y, Okamoto R, Fujiwara T, Takamatsu T, Yamada M, Tomioka Y, Takeshita N. Possibility of determining high quantitative fecal occult blood on stool surface using hyperspectral imaging. Journal of Gastroenterology. 2025 Jan;60(1):77-85.
Sakamoto T, Ikematsu H, Tamai N, Mizuguchi Y, Takamaru H, Murano T, Shinmura K, Sasabe M, Furuhashi H, Sumiyama K, Saito Y. Detection of colorectal adenomas with texture and color enhancement imaging: Multicenter observational study. Digestive Endoscopy. 2023 May;35(4):529-37.
Saito Y, Oka S, Kawamura T, Shimoda R, Sekiguchi M, Tamai N, Hotta K, Matsuda T, Misawa M, Tanaka S, Iriguchi Y. Colonoscopy screening and surveillance guidelines. Digestive Endoscopy. 2021 May;33(4):486-519.
Saito Y, Kodashima S, Matsuda T, Matsuda K, Fujishiro M, Tanaka K, Kobayashi K, Katada C, Horimatsu T, Muto M, Ohtsuka K. Current status of diagnostic and therapeutic colonoscopy in Japan: The Japan Endoscopic Database Project. Digestive Endoscopy. 2022 Jan;34(1):144-52.
Niikura R, Nagata N, Yamada A, Honda T, Hasatani K, Ishii N, Shiratori Y, Doyama H, Nishida T, Sumiyoshi T, Fujita T. Efficacy and safety of early vs elective colonoscopy for acute lower gastrointestinal bleeding. Gastroenterology. 2020 Jan 1;158(1):168-75.
Tadano T, Abe K, Sasaki S, Terasawa T, Hosono S, Katayama T, Hoshi K, Nakayama T, Hamashima C. Serious adverse events associated with bowel preparation for colonoscopy in Japan: Systematic review. Digestive Endoscopy. 2025 Jun 9.
Niikura R, Hirata Y, Suzuki N, Yamada A, Hayakawa Y, Suzuki H, Yamamoto S, Nakata R, Komatsu J, Okamoto M, Kodaira M. Colonoscopy reduces colorectal cancer mortality: A multicenter, long-term, colonoscopy-based cohort study. PloS one. 2017 Sep 28;12(9):e0185294.
Matsuda T, Ono A, Kakugawa Y, Matsumoto M, Saito Y. Impact of screening colonoscopy on outcomes in colorectal cancer. Japanese journal of clinical oncology. 2015 Oct 1;45(10):900-5.
Hashimoto Y, Kuribayashi S, Itoi Y, Satou K, Nakata K, Kasuga K, Tanaka H, Hosaka H, Masuo T, Maruhashi K, Furuya K. Safety of full bowel preparation and colonoscopy in elderly patients with ulcerative colitis: A real‐world multicenter retrospective cohort study. Den Open. 2024 Apr;4(1):e275.
Nagata N, Niikura R, Sakurai T, Shimbo T, Aoki T, Moriyasu S, Sekine K, Okubo H, Imbe K, Watanabe K, Yokoi C. Safety and effectiveness of early colonoscopy in management of acute lower gastrointestinal bleeding on the basis of propensity score matching analysis. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2016 Apr 1;14(4):558-64.










