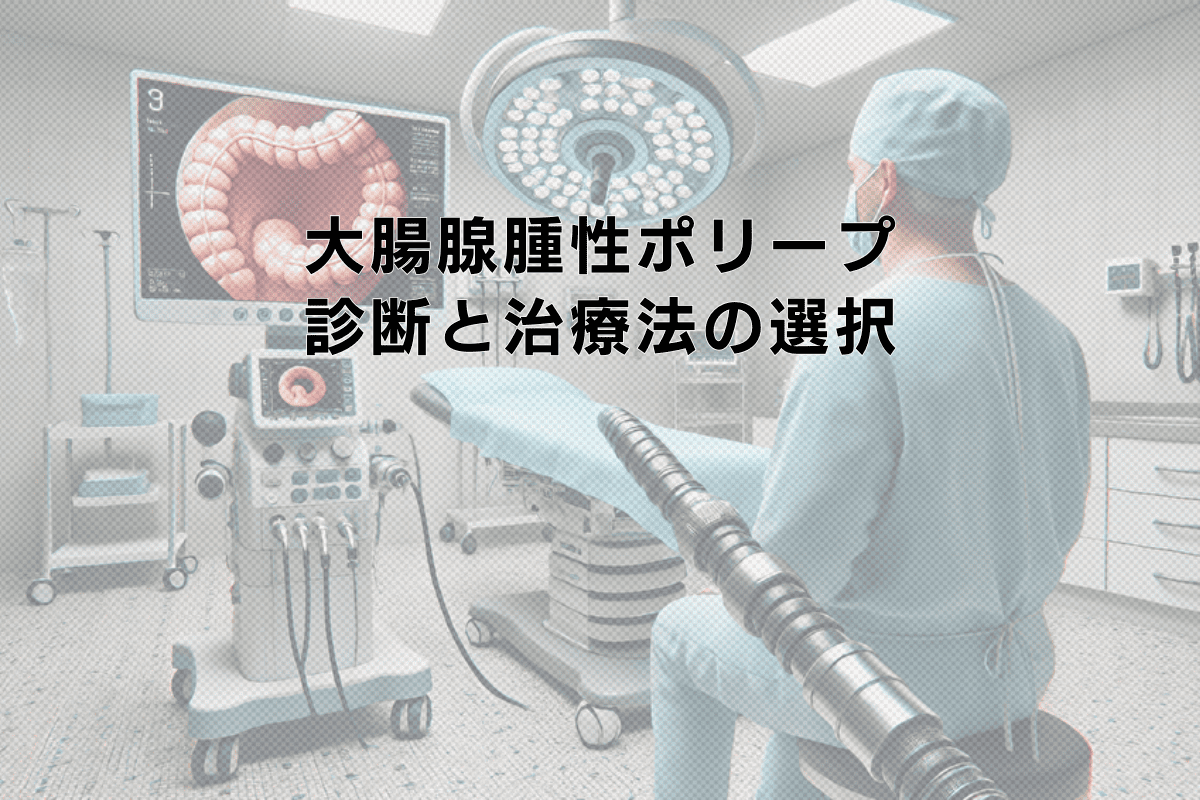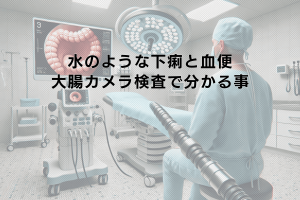大腸カメラ検査でポリープが見つかったと告げられたとき、多くの方が不安に感じるかもしれません。しかし、腺腫性ポリープは、適切な時期に発見し、正しく治療することで、大腸がんの予防に繋がります。
この記事では、大腸腺腫性ポリープとは何か、なぜ治療が必要なのか、そしてどのような診断方法や治療法の選択肢があるのかを、詳しく解説します。
大腸腺腫性ポリープとは何か
大腸腺腫性ポリープは、大腸の最も内側にある粘膜から発生する、きのこ状やいぼ状の隆起した病変です。
すべてのポリープが危険なわけではありませんが、腺腫性ポリープは、放置すると時間をかけてがんに進行する可能性があるため、前がん病変として重要視されています。
ポリープと腺腫の基本的な違い
大腸ポリープは、大腸粘膜にできる隆起性病変の総称で、組織のタイプによって、腫瘍性ポリープと非腫瘍性ポリープに大別されます。
非腫瘍性ポリープには、過形成性ポリープや炎症性ポリープなどがあり、基本的にがん化する心配はありませんが、腫瘍性ポリープの代表が腺腫性ポリープです。
腺腫は、良性腫瘍に分類され、細胞には異形成(正常とは異なる形質に変化すること)が見られ、がんへと進展する潜在的な能力を持っています。
大腸ポリープの分類
| 大分類 | 主な種類 | がん化のリスク |
|---|---|---|
| 腫瘍性ポリープ | 腺腫性ポリープ | あり(前がん病変) |
| 非腫瘍性ポリープ | 過形成性ポリープ | ほとんどない |
| 炎症性ポリープ | ない |
なぜ腺腫性ポリープが問題になるのか
腺腫性ポリープが問題視される最大の理由は、大腸がんの発生母地となるからです。
大部分の大腸がんは、正常な粘膜から直接発生するのではなく、腺腫性ポリープが徐々に大きくなり、内部でがん細胞が発生・増殖するというAdenoma-carcinoma sequence(腺腫-がん連関)と呼ばれる経路をたどると考えられています。
腺腫の段階で切除することは、将来発生する可能性のある大腸がんの芽を摘むことに直結し、予防的な観点から、腺腫性ポリープの発見と治療は、大腸がん対策において極めて重要です。
腺腫性ポリープの主な種類と特徴
腺腫性ポリープは、顕微鏡で見たときの組織の構造(組織型)によって、主に3つのタイプに分類され、それぞれのタイプで、がん化するリスクが異なります。
最も多いのが管状腺腫で、比較的がん化のリスクは低いとされ、絨毛腺腫は、絨毛状の構造を多く含み、がん化のリスクが管状腺腫より高いです。
そして、両者の中間的な性質を持つのが管状絨毛腺腫で、一般的に、絨毛成分の割合が高いほど、またポリープのサイズが大きいほど、がん化のリスクは高まる傾向にあります。
腺腫の組織型とがん化リスク
| 組織型 | 特徴 | がん化リスクの目安 |
|---|---|---|
| 管状腺腫 | 管状の構造が主体の腺腫。最も一般的。 | 低い |
| 管状絨毛腺腫 | 管状構造と絨毛構造が混在する。 | 中程度 |
| 絨毛腺腫 | 絨毛状の構造が主体の腺腫。 | 高い |
発生の主な原因と危険因子
大腸腺腫性ポリープの発生には、遺伝的な要因と環境的な要因が複雑に関与していると考えられています。
遺伝的要因としては、家族性大腸腺腫症(FAP)のように特定の遺伝子変異によって多数のポリープが発生する疾患もありますが、多くは多因子が関わる散発性です。
環境的な要因、すなわち生活習慣が大きく影響することが知られており、高脂肪・低繊維の食生活、赤肉や加工肉の過剰摂取、肥満、運動不足、過度の飲酒、喫煙などが危険因子として挙げられています。
このような因子は、腸内環境の変化や慢性的な炎症を起こし、大腸粘膜の細胞が異常をきたすきっかけになると考えられています。
腺腫性ポリープの症状と発見のきっかけ
大腸腺腫性ポリープは、初期の段階では自覚症状がほとんどないことが多く、知らないうちに発生し、ゆっくりと成長しているケースが少なくありません。そのため、症状が出てからではなく、症状がない段階でいかに発見するかが重要です。
ほとんどが無症状であるという事実
小さな腺腫性ポリープがあるだけでは、体に何らかの症状が現れたり痛みや違和感を感じることもなく、排便の習慣に変化が起きることもまれです。
ポリープがかなり大きくなったり、がん化して進行したりして初めて、症状として認識されるようになり、無症状の期間が長いことが、大腸ポリープの発見を遅らせる一因になります。
注意すべき自覚症状
ポリープが大きくなるといくつかの症状が現れることがあり、最も分かりやすいのは、便に血が混じる血便や、便の表面に血液が付着する状態です。ポリープの表面はもろく、硬い便が通過する際に擦れて出血することがあります。
また、ポリープから分泌される粘液によって、便に粘液が混じることもあります。
さらにポリープが大きくなると、腸管を狭窄させ、便秘や下痢、腹痛、お腹の張りといった便通異常を起こすことがあり、まれに、ポリープが原因で腸重積を起こし、激しい腹痛をきたすこともあります。
ポリープの大きさと関連症状
| 症状 | 主な原因 | 注意点 |
|---|---|---|
| 血便・便への血液付着 | ポリープ表面からの出血 | 痔の出血と自己判断しないことが重要です。 |
| 便通異常(便秘・下痢) | 大きなポリープによる腸管の狭窄 | 市販薬で改善しない場合は注意が必要です。 |
| 腹痛・腹部膨満感 | 腸管の通過障害 | 他の消化器疾患との鑑別が必要です。 |
便潜血検査の重要性
症状がない段階でポリープを発見するための有効な入り口となるのが、便潜血検査で、便の中に目には見えない微量の血液が混じっていないかを調べる、簡便で体への負担がない検査です。
便潜血検査で陽性となった場合、出血源を特定するために精密検査として大腸内視鏡検査を行います。陽性者のうち、実際に大腸がんと診断されるのは数パーセントですが、約30〜40パーセントの方に腺腫性ポリープが見つかるといわれています。
発見されるその他の経緯
便潜血検査以外にも、腺腫性ポリープが発見されるきっかけはあり、原因不明の貧血を精査する中で、消化管からの慢性的な出血が疑われ、大腸内視鏡検査を行った結果、ポリープが見つかることがあります。
また、腹痛や便通異常といった何らかの腹部症状のために大腸内視鏡検査を受け、原因とは別に偶然ポリープが発見されるケースも少なくありません。
さらに、血縁者に大腸がんやポリープの既往がある方が、リスクを考慮して自主的に検査を受け、ポリープが発見されることもあります。
大腸内視鏡検査による精密な診断
大腸腺腫性ポリープの診断において大腸内視鏡検査は大変重要で、肛門から細いスコープを挿入し、直腸から盲腸までの大腸全域を直接観察するものです。
粘膜の状態をリアルタイムで詳細に評価できるため、ポリープの有無はもちろん、性状までを高い精度で診断することができます。

内視鏡検査の役割と目的
大腸内視鏡検査の第一の目的は、ポリープをはじめとする病変を発見することですが、役割は発見だけにとどまりません。
発見したポリープが、治療が必要な腺腫性ポリープなのか、放置可能な非腫瘍性ポリープなのかを、その場で鑑別診断することが重要な目的です。
さらに、腺腫性ポリープであった場合には、大きさ、形状、表面の模様などを詳細に観察し、がん化している可能性がないかを評価します。
そして、必要に応じて組織の一部を採取したり、小さなポリープであればその場で切除したりすることも可能で、診断と治療を同時に行える点が、検査の大きな利点です。
通常光観察と画像強調観察
従来の内視鏡検査では、通常の白色光(通常光)で粘膜を観察していました。
しかし、技術の進歩により、特定の波長の光を当てたり、画像処理を加えたりすることで、粘膜表面の微細な血管の走行パターンや、腺管の模様(ピットパターン)を強調して表示する画像強調観察が可能です。
代表的なものにNBI(Narrow Band Imaging)やBLI(Blue Laser Imaging)などがあり、特殊な光を用いることで、病変の境界がより明瞭になり、ポリープの良性・悪性の鑑別診断の精度が飛躍的に向上しています。
画像強調観察で得られる情報
| 観察モダリティ | 原理 | 主な利点 |
|---|---|---|
| NBI | 血液中のヘモグロビンに吸収されやすい狭帯域光を使用 | 粘膜表層の毛細血管を鮮明に描出 |
| BLI | 短波長のレーザー光を使用 | 血管パターンと表面構造の両方を高精細に描出 |
| LCI | 白色光に短波長狭帯域光を組み合わせる | わずかな粘膜の色の違いを強調 |
大きさ、形状、表面構造の評価
内視鏡医は、ポリープを発見すると、特徴を多角的に評価します。まず、大きさを計測し、一般的に、ポリープは大きいほどがん化のリスクが高まります。
次に、形状を観察し、茎を持つ有茎性ポリープか、平坦で茎のない無茎性(表在性)ポリープかなどを分類します。表面が陥凹しているタイプのポリープは、小さくてもがん化している可能性があり注意が必要です。
さらに、拡大内視鏡を用いて表面構造を詳細に観察し、腺管の開口部であるピットのパターンを分類することで、ポリープが腫瘍性か非腫瘍性か、さらにはがん化しているかどうかを高い精度で推定することができます。

組織生検による確定診断
内視鏡観察によってある程度の診断は可能ですが、最終的な確定診断に用いられるのは、ポリープの一部または全体を採取し、顕微鏡で調べる病理組織検査です。
内視鏡的切除を行った場合は、切除したポリープ全体が検査の対象となり、病理組織検査では、ポリープが腺腫であるかどうかの確定、腺腫の組織型(管状、絨毛など)の分類、細胞の異型度(正常からのずれの程度)の評価を行います。
また、がん細胞が含まれていないか、含まれている場合は深達度(がんがどれくらい深く潜っているか)などを詳細に評価します。
診断後の治療方針の決定
大腸内視鏡検査で腺腫性ポリープと診断された後、次の段階として治療をどうするかを決定します。
すべての腺腫性ポリープを画一的に治療するのではなく、個々のポリープのがん化リスクや、患者さん自身の体の状態などを総合的に評価し、治療方針を考えます。
治療の必要性を判断する基準
腺腫性ポリープの治療(内視鏡的切除)を行うかどうかは、主にそのポリープを放置した場合のがん化リスクに基づいて判断します。
リスクが非常に低いと考えられる小さなポリープの一部では経過観察を選択することもありますが、腺腫と診断されたポリープは、将来のがん予防の観点から切除することが推奨されます。
特にがん化のリスクが高いと判断される特徴を持つポリープは、積極的な治療の対象となります。治療方針は、医師が一方的に決めるのではなく、検査結果を基に患者さんへ十分な説明を行い、同意を得た上で進めることが大切です。
- 大きさ
- 肉眼的な形状
- 表面構造のパターン
- 組織型と異型度
ポリープの大きさとがん化のリスク
ポリープの大きさは、がん化のリスクを判断する上で最もシンプルで分かりやすい指標で、ポリープの直径が大きいほど、内部にがん細胞が含まれている確率が高いです。
5mm以下の微小なポリープではがんの含有率は極めて低いですが、6mmから9mmのポリープでは数パーセント、10mmを超えるとがんの含有率は約10%、20mmを超えると30%以上になると報告されています。
多くの医療機関では、5mmを超える腺腫性ポリープは原則として切除の対象です。
ポリープの大きさとがん含有率の目安
| ポリープの直径 | がん含有率(おおよその目安) | 一般的な対応 |
|---|---|---|
| 5mm以下 | 1%未満 | 経過観察または切除 |
| 6mm – 9mm | 約2-5% | 切除を推奨 |
| 10mm以上 | 約10%以上 | 切除の強い適応 |
異型度(グレード)の評価
異型度とは、生検や切除したポリープの組織を顕微鏡で観察した際に、細胞の核の大きさや形、配列などが正常な細胞からどれだけ異なっているか(ずれているか)の度合いを示すものです。
異型度は、低異型度(low grade)と高異型度(high grade)に分類され、低異型度は、正常に近い良性の状態ですが、高異型度は、がん細胞に一歩近い状態、いわば顔つきの悪い細胞が増えていることを意味します。
高異型度腺腫は、がん化への移行リスクが高いと考えられ、carcinoma in situ(上皮内がん)として扱われることもあります。異型度の評価は、治療の緊急性や切除後の経過観察の方針を決定する上で重要な情報です。
患者の全身状態と希望の考慮
治療方針を決定する際には、ポリープ自体の評価だけでなく、患者さん自身の体の状態(全身状態)や、治療に対する意向も十分に考慮します。
非常に高齢であったり、心臓や肺、血液疾患など重篤な持病を持っていたりする方の場合、内視鏡治療に伴う偶発症(出血や穿孔など)のリスクが、ポリープを放置するリスクを上回ると判断されることもあります。
また、血液をサラサラにする薬(抗血栓薬)を服用している場合は、休薬のリスクと治療の必要性を慎重に天秤にかける必要があります。
治療のメリットとデメリットについて医師から十分な説明を受け、患者さん自身が納得した上で治療法を選択することが何よりも重要です。
内視鏡的ポリープ切除術の種類
大腸腺腫性ポリープの標準的な治療法は大腸内視鏡を用いた切除術で、開腹手術とは異なり体への負担が少なく、入院期間も短い、あるいは日帰りで施行可能で、ポリープの大きさや形状、場所などに応じて、いくつかの手技が使い分けられます。

コールドポリペクトミー
コールドポリペクトミー(非通電性ポリペクトミー)は、主に10mm以下の比較的小さなポリープに対して行われる切除法です。スネアと呼ばれる金属製の輪状のワイヤーをポリープの根元にかけ、電気を流さずに機械的に締め付けて切除します。
従来の方法(ホットポリペクトミー)では、高周波電流を流して焼き切っていましたが、通電による熱損傷が周囲の組織に及ぶため、後から出血や穿孔(腸に穴が開くこと)が起こるリスクがありました。
コールドポリペクトミーは、熱損傷がないため、治療後の偶発症のリスクが非常に低いです。手技が簡便で安全性が高いことから、近年、小さなポリープに対する標準的な切除法として広く普及しています。
内視鏡的粘膜切除術(EMR)
内視鏡的粘膜切除術(EMR: Endoscopic Mucosal Resection)は、主に20mm程度までの、茎のない平坦な(無茎性)ポリープに対して行われます。
まずポリープの下の粘膜下層に生理食塩水などの液体を注入し、ポリープを人工的に盛り上げることにより、ポリープが筋層(腸の壁の深い層)から浮き上がり、安全に切除できるようになります。
また、粘膜下層に注入した液体が、通電時の熱が筋層へ伝わるのを防ぐクッションの役割も果たし、盛り上がったポリープにスネアをかけて、高周波電流を流しながら焼き切ります。
比較的大きな病変も、安全かつ確実に一括で切除することを目指す手技です。
EMRの主な手順
- 病変の確認とマーキング
- 粘膜下層へ局所注射
- スネアによる絞扼
- 高周波電流による切除
- 切除後の創部の確認と止血処置
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD: Endoscopic Submucosal Dissection)は、EMRでは一括切除が困難な20mm以上の大きなポリープや、早期大腸がんが疑われる病変に対して行われる、より高度な技術を要する治療法です。
スネアで一括して焼き切るのではなく、ITナイフやデュアルナイフといった特殊な電気メスを用いて、病変周囲の粘膜を切開し、さらにその下の粘膜下層を少しずつ剥がしながら病変を剥離・切除します。
大きな病変であっても分割せずに一括で切除できるため、取り残しが少なく、正確な病理診断が可能になるという大きな利点があります。
ただし、手技が複雑で時間もかかり、出血や穿孔のリスクもEMRより高いため、高度な技術と経験を持つ専門医によって慎重に行われる治療法です。
各切除術の比較
| 切除術 | 主な対象 | 特徴 |
|---|---|---|
| コールドポリペクトミー | 10mm以下の小さなポリープ | 非通電で安全性が高い。手技が簡便。 |
| EMR | 20mm程度までの無茎性ポリープ | 粘膜下層に液体を注入し、安全に切除。 |
| ESD | 20mm以上の大きな病変、早期がん | 電気メスで剥離。大きな病変も一括切除可能。 |
ポリープ切除後の注意点と経過観察
内視鏡的ポリープ切除術は比較的安全な治療ですが、治療である以上、一定の確率で偶発症(予期せぬ有害事象)が起こる可能性があります。また、一度ポリープを切除しても、それで終わりではありません。
切除後の偶発症とその対策
ポリープ切除後に起こりうる主な偶発症は、出血と穿孔です。出血には、切除直後に起こるものと、数日から1週間程度経ってから起こるもの(後出血)があり、後出血の多くは、切除した部分のかさぶたが剥がれることによって起こります。
ほとんどは自然に止まりますが、便器が真っ赤になるほどの出血が続く場合は、緊急で内視鏡による止血術が必要です。
穿孔は、腸の壁に穴が開いてしまう状態で、頻度は非常にまれですが、起こった場合は腹膜炎を引き起こす可能性があるため、緊急手術になることもあります。
偶発症のリスクを減らすため、切除後は安静にし、食事や生活上の注意が必要です。
食事や生活上の注意
切除後の腸管は傷ができている状態なので、傷の治りを妨げないよう、術後しばらくは食事や生活にいくつかの制限が必要です。食事は、当日から可能ですが、おかゆやうどんなど、消化が良く、腸に負担をかけないものから始めます。
香辛料などの刺激物や、脂肪分の多い食事、アルコールは、腸管を刺激し血流を良くするため、出血のリスクを高める可能性があり、少なくとも1週間程度は避けましょう。
また、腹圧がかかるような激しい運動や、重いものを持つ作業、長時間の移動や旅行なども、同様の理由で1週間程度は控えてください。
切除後1週間の生活の目安
| 項目 | 推奨されること | 避けるべきこと |
|---|---|---|
| 食事 | 消化の良いもの(おかゆ、うどん、豆腐など) | 刺激物、脂肪の多いもの、アルコール |
| 運動 | 散歩などの軽い運動 | 激しい運動、筋力トレーニング |
| 入浴 | シャワー浴 | 長時間の入浴、サウナ |
定期的なサーベイランス(経過観察)の重要性
ポリープを切除した後も、定期的な大腸内視鏡検査によるサーベイランス(経過観察)を続けることが非常に重要です。
腺腫性ポリープができたということは、大腸がポリープのできやすい環境にあることを示唆しているので、切除した場所以外に新たなポリープが発生したり、非常に小さくて見逃されたポリープが大きくなったりする可能性があります。
サーベイランスの間隔は、切除したポリープの数、大きさ、組織型、異型度などによって個別に決定し、一般的には1年から3年ごとの検査が推奨されることが多いですが、リスクに応じて間隔は調整されます。
よくある質問
大腸腺腫性ポリープの診断や治療に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。
- 腺腫性ポリープは必ずがんになりますか
-
腺腫性ポリープは前がん病変ですが、すべての腺腫ががんに進行するわけではなく、多くは良性のままですが、どのポリープが将来がん化し、どれがしないかを確実に見分けることは現時点では困難です。
また、がん化する可能性のあるポリープを放置すれば、時間とともにリスクは高まるため、将来のがんを予防するという観点から、発見された腺腫性ポリープは原則として切除することが推奨されています。
- 切除したポリープは再発しますか
-
同じ場所からの再発と、別の場所に新しくできる場合があります。内視鏡で完全に切除できていれば、同じ場所からポリープが再発する(遺残再発)ことはまれです。
しかし、大きなポリープを分割して切除した場合などは、わずかに残った組織から再発する可能性があります。より重要なのは、別の場所に新しいポリープが発生すること(異時性発生)です。
ポリープができやすい体質そのものが変わるわけではないため、一度切除した方も、定期的な内視鏡検査で新しいポリープができていないかを確認し続けることが大切です。
- ポリープ切除は痛みを伴いますか
-
大腸の粘膜には痛覚(痛みを感じる神経)がなく、内視鏡検査中にポリープを切除したり、組織を採取(生検)したりする際に、直接的な痛みを感じることはありません。
ただし、検査中に腸が空気で伸びることによるお腹の張りや、内視鏡が腸の曲がり角を通過するときの違和感や圧迫感を痛みとして感じることがあります。
多くの医療機関では、苦痛を和らげるために鎮静剤を使用するなどの工夫をしていますので、不安な方は事前に相談してください。
- ポリープを予防する方法はありますか
-
完全に予防することは難しいですが、リスクを減らす生活習慣はあり、大腸腺腫性ポリープの危険因子とされる生活習慣を避けることが、予防に繋がると考えられています。
食物繊維を豊富に含む野菜や果物を多く摂り、赤肉や加工肉の摂取を控える、バランスの取れた食生活が重要です。また、適度な運動を習慣づけ、肥満を解消すること、禁煙、節度ある飲酒もリスク低下に有効とされています。
健康的な生活習慣を心がけると共に、定期的な検診を受けることが、ポリープの早期発見と大腸がん予防の最も確実な方法です。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
大腸腺腫性ポリープの診断には大腸内視鏡検査が不可欠です。この検査を受ける前の3日間からの準備や食事制限について知っておくと、より正確な検査結果を得ることができ、安心して検査に臨めます。
【大腸ポリープ毎年発見される方の検査と予防対策】
腺腫性ポリープについて理解が深まったところで、ポリープが再発しやすい方の検査間隔や予防対策についても知っておくと、長期的な健康管理に役立ちます。定期的な検査の重要性が見えてきます。
以上
参考文献
Tanaka S, Saitoh Y, Matsuda T, Igarashi M, Matsumoto T, Iwao Y, Suzuki Y, Nishida H, Watanabe T, Sugai T, Sugihara KI. Evidence-based clinical practice guidelines for management of colorectal polyps. Journal of gastroenterology. 2015 Mar;50(3):252-60.
Tanaka S, Saitoh Y, Matsuda T, Igarashi M, Matsumoto T, Iwao Y, Suzuki Y, Nozaki R, Sugai T, Oka S, Itabashi M. Evidence-based clinical practice guidelines for management of colorectal polyps. Journal of Gastroenterology. 2021 Apr;56(4):323-35.
Iwama T, Tamura K, Morita T, Hirai T, Hasegawa H, Koizumi K, Shirouzu K, Sugihara K, Yamamura T, Muto T, Utsunomiya J. A clinical overview of familial adenomatous polyposis derived from the database of the Polyposis Registry of Japan. International journal of clinical oncology. 2004 Aug;9(4):308-16.
Matsubara T, Beppu N, Ikeda M, Ishida H, Takeuchi Y, Nagasaki T, Takao A, Sasaki K, Akagi K, Sudo T, Ueno H. Current clinical practice for familial adenomatous polyposis in Japan: A nationwide multicenter study. Annals of Gastroenterological Surgery. 2022 Nov;6(6):778-87.
Yamaguchi T, Ishida H, Ueno H, Kobayashi H, Hinoi T, Inoue Y, Ishida F, Kanemitsu Y, Konishi T, Tomita N, Matsubara N. Upper gastrointestinal tumours in Japanese familial adenomatous polyposis patients. Japanese journal of clinical oncology. 2016 Apr 1;46(4):310-5.
Yamaji Y, Mitsushima T, Ikuma H, Watabe H, Okamoto M, Kawabe T, Wada R, Doi H, Omata M. Incidence and recurrence rates of colorectal adenomas estimated by annually repeated colonoscopies on asymptomatic Japanese. Gut. 2004 Apr 1;53(4):568-72.
Ikeda Y, Mori M, Yoshizumi T, Sugimachi K. Cancer and adenomatous polyp distribution in the colorectum. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 1999 Jan 1;94(1):191-3.
Ishikawa H, Wakabayashi K, Suzuki S, Mutoh M, Hirata K, Nakamura T, Takeyama I, Kawano A, Gondo N, Abe T, Tokudome S. Preventive effects of low‐dose aspirin on colorectal adenoma growth in patients with familial adenomatous polyposis: Double‐blind, randomized clinical trial. Cancer medicine. 2013 Feb;2(1):50-6.
Yachida T, Nakajima T, Nonaka S, Nakamura K, Suzuki H, Yoshinaga S, Oda I, Moriya Y, Masaki T, Saito Y. Characteristics and clinical outcomes of duodenal neoplasia in Japanese patients with familial adenomatous polyposis. Journal of Clinical Gastroenterology. 2017 May 1;51(5):407-11.
Yamadera M, Ueno H, Kobayashi H, Konishi T, Ishida F, Yamaguchi T, Hinoi T, Inoue Y, Kanemitsu Y, Tomita N, Ishida H. Current status of prophylactic surgical treatment for familial adenomatous polyposis in Japan. Surgery today. 2017 Jun;47(6):690-6.