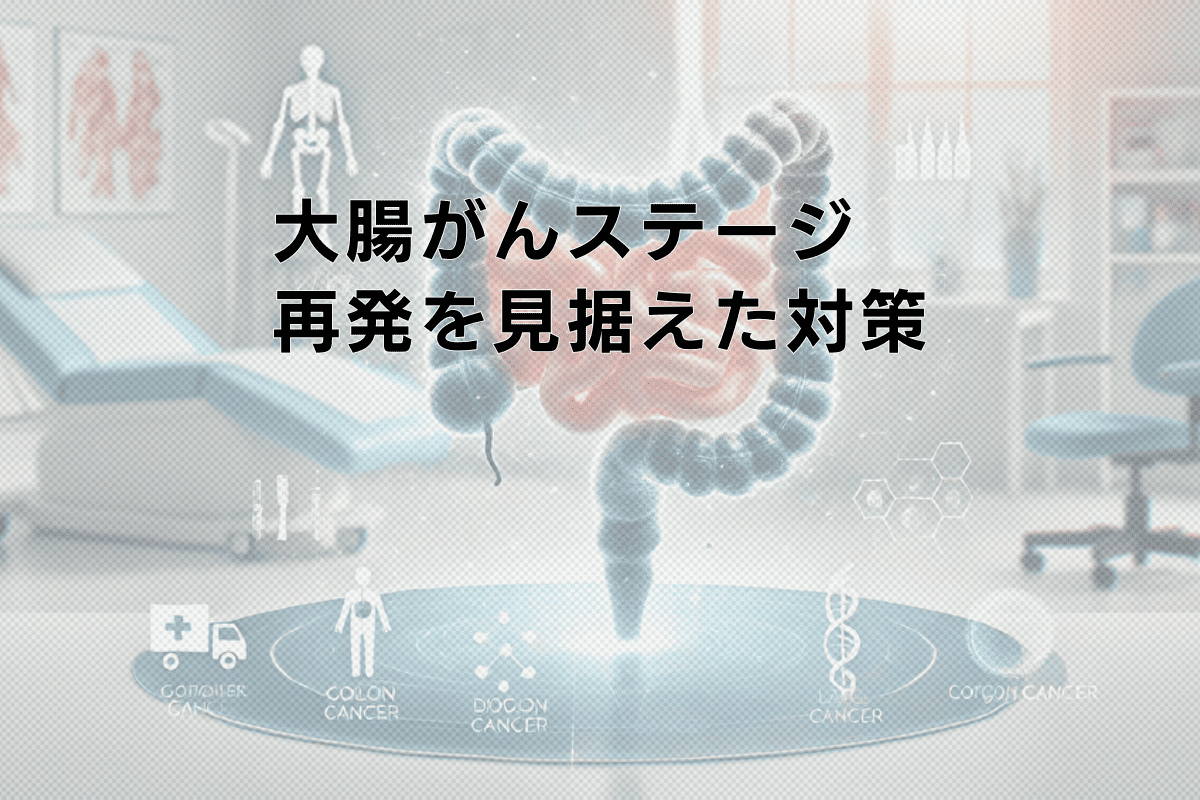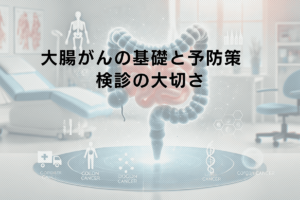大腸がんは日本を含む多くの国々で発症頻度が高いがんの1つであり、治療へ進むためには、ステージ(病期)の正しい理解が重要です。
大腸がんは粘膜から生じ、リンパ節を介して身体の各臓器へ転移を引き起こす可能性があります。検査法や治療法は近年大きく進歩し、ステージに応じた多様な選択肢が確立されています。
治療後の再発を予防し、生存率を高めるためには、手術だけでなく内視鏡治療、薬物療法、生活習慣の見直しなどを総合的に考えることが大切です。
ここでは大腸がんのステージ分類の概要から、それぞれの段階における治療の考え方、再発や転移への対応、日常生活で気をつける点に至るまで、幅広い情報を整理します。
大腸がんステージとは何か
大腸がんの発生から進行に至る過程には個人差がありますが、病気の状態を客観的に分類するためにステージ(病期)という指標が用いられます。
これは大腸の壁への浸潤の深さ、リンパ節への転移の有無、他の臓器への転移の状況といった要素を総合的に評価して決定されます。
大腸がんの特徴
大腸がんは大腸の粘膜から生じる悪性腫瘍(がん)であり、結腸や直腸に発生します。粘膜から始まり、粘膜下層や固有筋層、さらに漿膜へと深く広がっていくにつれて、リンパ節や肝臓、肺などへの転移が起こりやすくなります。
大腸がんの大きな特徴は、段階が早ければ内視鏡切除といった比較的侵襲の少ない方法で対応できる点で、進行が進むほど治療の複合化が必要です。
期分類の基本(T、N、M因子)
大腸がんのステージを決める基本的な分類には、以下の3つの因子が重要です。
- T因子:がんが大腸の壁のどこまで浸潤しているか
- N因子:周囲のリンパ節にがんが転移しているか
- M因子:肝臓や肺など他の臓器へ転移しているか
壁への深達度が浅くリンパ節転移や他臓器転移がない場合は早期がんに分類され、壁の深い層へ浸潤し、複数のリンパ節が侵されている場合や、遠隔臓器に転移がある場合はステージが進行していると考えます。
大腸がんのステージと進行度
| ステージ | T因子(壁への浸潤) | N因子(リンパ節転移) | M因子(他臓器転移) |
|---|---|---|---|
| 0 | 粘膜内 | なし | なし |
| I | 粘膜下層~固有筋層 | なし | なし |
| II | 固有筋層を越え、漿膜まで、または周囲組織まで | なし | なし |
| III | 幅広い浸潤 | あり | なし |
| IV | 幅広い浸潤 | ありorなし | あり |
進行度と症状との関係
大腸がんがまだ小さい段階では症状が出にくいことが多く、がんが進行するにつれ、以下のような症状を自覚しやすくなります。
- 血便や下痢、便秘などの便通異常
- 腹痛やお腹の張り
- 体重減少、倦怠感
- 貧血
- 大腸がんがさらに拡大した場合、腸閉塞など
腸管のどの部分に発生したかによっても症状が変わり、結腸よりも直腸がんのほうが便に血が混じっていることを自覚しやすいとされていますが、いずれにしても、定期検査を受けることで早期発見をめざすことが重要です。
ステージ分類が大切な理由
がんの深達度やリンパ節・遠隔転移の有無によって、治療法の選択が大きく変わります。
ステージが早ければ内視鏡での切除で十分対応できる可能性がありますし、進行度が高いほど手術と薬物療法を組み合わせて長期の治療プランを組むことが必要です。
治療後の再発予防や経過観察の計画を立てる上でも、ステージは非常に重要な役割を果たします。
大腸がんのステージ分類と特徴
ステージ0からIVまで、おおまかに5つに分かれるのが大腸がんの代表的な病期分類です。各段階には特徴があり、治療法や治療後の観察方法にも違いがあります。
ステージ0の特徴
ステージ0は、がん細胞が大腸の粘膜内にとどまっている状態で、いわゆる「上皮内がん」と呼ばれる段階であり、内視鏡による切除が検討されます。
一般的には症状がほとんど出ず、検診や内視鏡検査を受けて偶然見つかることも珍しくありません。切除後の再発リスクも極めて低く、経過観察が中心となる場合が多いです。
ステージIの特徴
ステージIは、がんが粘膜下層から固有筋層くらいまで達している段階ですが、リンパ節転移や他臓器への転移は確認されていません。
内視鏡切除が可能な場合もありますが、腫瘍の大きさや深達度によっては外科的手術を選択することもあります。まだ早期の部類に入り、手術後の生存率は比較的高いです。
ステージIIの特徴
ステージIIは、がんが固有筋層を越えて漿膜や周辺組織にまで広がっているものの、リンパ節転移が確認されていない状態です。すでに腫瘍が大腸壁を深く越えているため、外科手術による切除と周囲リンパ節の切除が中心となります。
再発リスクがステージIよりも高まる傾向がありますが、治療と経過観察によって長期的なコントロールが期待できます。
ステージIIIの特徴
ステージIIIは、がんがより深く浸潤しているかどうかにかかわらず、リンパ節への転移がある段階です。
リンパ節の転移個数などによって細かく分類されますが、基本的には手術に加え、術前もしくは術後に薬物療法(抗がん剤治療など)を組み合わせます。
再発を抑えるためにも追加治療の重要性が高くなり、長期にわたる経過観察や定期的な検査が必要です。
ステージIVの特徴
ステージIVは、すでにがんが他の臓器へ転移している状態です。代表的な転移先は肝臓、肺、腹膜などであり、転移先や大腸がんの状態に応じて複合的な治療が検討されます。
場合によっては手術では切除できず、薬物療法(化学療法、分子標的薬など)や放射線治療を組み合わせて長期生存や生活の質をめざします。
治療は段階が進むほど複雑になりますが、長期的にがんと付き合う「慢性病」的な考え方も取り入れながら対策を続けることが多いです。
ステージ別の再発リスク要素
| ステージ | 壁への浸潤 | リンパ節転移 | 他臓器転移 | 再発リスク |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 粘膜内 | なし | なし | 極めて低い |
| I | 粘膜下層~固有筋層 | なし | なし | 低い |
| II | 漿膜まで浸潤 | なし | なし | やや高まる |
| III | 幅広く浸潤 | あり | なし | 高い |
| IV | 幅広く浸潤 | ありorなし | あり | 非常に高い |
ステージに応じた治療法の考え方
大腸がんの治療法は、内視鏡治療や外科的手術、薬物療法、放射線治療など多岐にわたり、ステージが進むほど治療の組み合わせが必要になるケースが多いです。
内視鏡治療の適応
ステージ0からIの比較的早期の大腸がんでは、内視鏡による切除が大きな選択肢です。内視鏡治療にはポリペクトミー、内視鏡的粘膜切除術(EMR)、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)などさまざまな方法があります。
手術よりも身体への負担が少ないため、がんが粘膜や粘膜下層にとどまっている場合は積極的に検討する価値がある治療法です。
ただし、がんが固有筋層に近い深さにまで達している場合や、リンパ節転移の可能性が高い場合は、手術による切除が勧められます。

外科的手術とリンパ節切除
大腸がんがより深く浸潤している場合やリンパ節転移が疑われる場合は、外科的手術が中心です。
結腸がんの場合は結腸の一部を切除し、直腸がんの場合は直腸を含む周辺組織の切除が実施され、リンパ節切除も重要で、転移の有無を調べるための病理検査にも役立ちます。
近年は腹腔鏡下手術やロボット支援下手術など、開腹手術に比べて創部が小さくなる方法も普及しています。
代表的な外科的手術の手法と対象
| 手術法 | 特徴 | 対象となるステージ |
|---|---|---|
| 腹腔鏡下結腸切除 | お腹に数か所の小さな切開を加え、カメラと器具を挿入して行う | ステージI~III |
| 開腹手術 | お腹を大きく開き、直接視認しながら行う | 幅広いステージ |
| 直腸切除(低位前方切除など) | 直腸がんの部位に合わせて切除範囲を調整する | ステージI~III(直腸) |
| 右/左半結腸切除 | 結腸の右側または左側を選択的に切除 | 結腸特定部位の腫瘍 |
薬物療法の選択肢
薬物療法には、主に化学療法と分子標的薬、免疫療法などがあり、ステージIIIやIVでは多くの場合に検討されます。
手術前に腫瘍を小さくする目的で使ったり(術前化学療法)、手術後に再発のリスクを下げるために行ったり(術後補助化学療法)と、さまざまなタイミングで実施されます。
がんの性質や遺伝子変異の有無によって使用する薬剤は異なり、患者さんの状態を考慮しながら決定することが大切です。
主な薬物療法の種類
- 化学療法(抗がん剤治療)
- 5-FU系、オキサリプラチン、イリノテカンなど
- 分子標的薬
- 抗EGFR抗体薬、抗VEGF抗体薬など
- 免疫チェックポイント阻害薬
- 一部の特殊な遺伝子変異がある大腸がんで使用されることが多い
放射線治療の役割
大腸がんでは、直腸がんの治療に放射線治療を組み合わせることがしばしば行われ、進行度が高い直腸がんの場合、術前に放射線治療と化学療法を併用して腫瘍を縮小させ、手術をしやすくするアプローチがとられます。
放射線治療は副作用として便や排尿のトラブルを引き起こす可能性がありますが、手術との組み合わせで治療効果を高める戦略です。
再発・転移に対する治療
大腸がんは治療後に再発を起こすリスクがあり、肝臓や肺、腹膜への転移が多いと報告されています。治療後の定期検査を受け、早期に再発を見つけ出し、適切な追加治療を行うことが重要です。
転移の好発部位と特徴
- 肝臓転移:大腸から肝臓へは門脈を介して転移が起こりやすいです。肝臓内に複数の病変が見られることもあります。
- 肺転移:大腸がんが血行性により肺へ拡散する場合があります。
- 腹膜播種:がん細胞が腹膜表面に広範囲に広がる状態で、治療が難しくなる傾向があります。
再発が起こりやすいタイミング
| 時期 | 考えられる再発・転移のパターン |
|---|---|
| 術後1~2年 | まだ微小転移がコントロールされず、肝臓などの病変が表面化することも |
| 術後3~5年 | 遅れて生じたリンパ節転移や肺転移 |
| 術後5年以降 | 比較的少ないが、まれに遅発性再発がみられる |
再発リスクを下げるための取り組み
再発によるリスクを防ぐには、術後補助化学療法を適切な期間行うこととともに、定期的なCTやMRI検査などを受けて再発を早期に発見することが大切です。
また、食生活の改善や禁煙・禁酒など生活習慣を整えることで体力維持を図り、がんの再発・転移の可能性を下げることが期待されています。
再発時の治療方針
再発が発見された場合は、再び外科的切除が可能か、もしくは薬物療法や放射線治療を優先するかを判断します。肝転移が限局的であれば、肝切除術やラジオ波焼灼療法(RFA)を検討できます。
肺への転移でも病変が小さければ外科的切除が視野に入ります。一方、腹膜播種のように広範囲にわたる再発では、薬物療法が中心になり、病状をコントロールしながら生活の質を保つ工夫が必要です。
進行例における生活の質
ステージIVの患者さんや再発例では、完治をめざす治療が難しいケースも出てきますが、治療によってがんの進行を抑え、生活の質を保ちながら長期的に通院を続けられます。
症状コントロールを重視し、主治医や看護師、臨床心理士、栄養士などの多職種チームと連携することで、生活の工夫を見いだしやすくなります。
- 痛みや下痢、便秘などの症状対策
- 心のケア(不安を解消するためのカウンセリングなど)
- 食事内容の管理
- 家族や職場とのコミュニケーション
大腸がんステージと検査の重要性
大腸がんを見つける際には便潜血検査や内視鏡検査、CTやMRIなど、いくつかの方法が用いられ、病期を正確に把握するために欠かせません。治療後の経過観察でも、がんが再発していないか、転移が進んでいないかなどを確認します。
診断に用いる検査方法
- 便潜血検査:大腸がんの検診に広く導入され、血液が混じっていないかを調べる簡易検査です。
- 大腸内視鏡検査:内視鏡で直接大腸の粘膜を観察します。ポリープや早期がんの段階から発見し、そのまま切除できる場合もあります。
- 画像検査:CTやMRI、PET-CTなど。腫瘍の広がりやリンパ節転移、遠隔転移を把握する上で重要です。
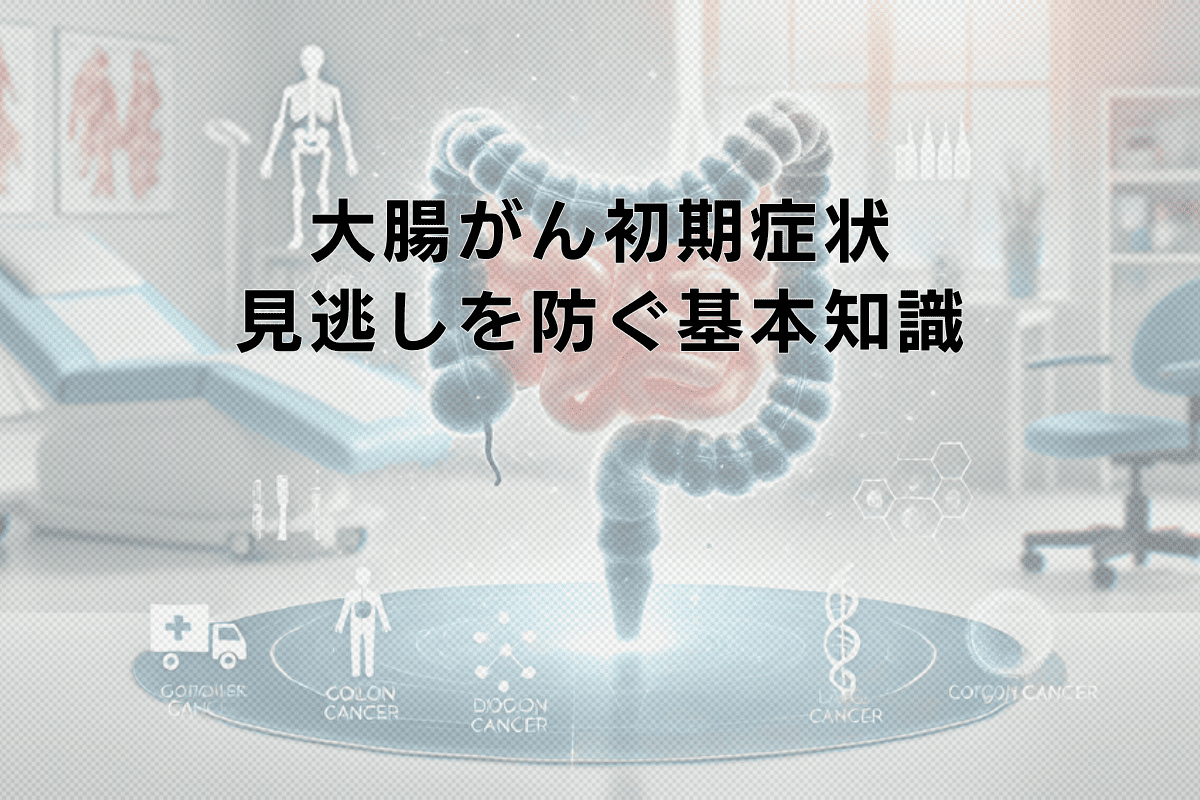
ステージごとの検査でわかること
早期の段階では内視鏡所見から得られる粘膜の状態が治療法の決定に関わり、ステージが進むとCTやMRIで臓器への転移状況を確認し、手術の可否や薬物療法の必要性を判断します。
再発リスクが高いステージでは治療後の定期検査がより細かくなり、病状の変化を見逃さないようにします。
ステージ別による代表的な検査スケジュール
| ステージ | 診断時の主な検査 | 術後フォローの目安 |
|---|---|---|
| 0 | 大腸内視鏡 | 定期的な内視鏡(年1回程度) |
| I | 大腸内視鏡、CT | 半年~1年ごとのCTや内視鏡 |
| II | 大腸内視鏡、CT、MRI | 3~6か月ごとの画像検査、腫瘍マーカー |
| III | 大腸内視鏡、CT、MRI、PET-CTなど | 3か月ごとに画像検査、腫瘍マーカー |
| IV | 上記+必要に応じて詳細検査 | 2~3か月ごとに画像検査、症状の確認 |
早期発見をめざす検診
大腸がんは早期に発見すれば治りやすく、生存率も高いがんの1つで、40歳以降は定期的に検診を受けることが推奨され、便潜血検査で陽性となった場合は大腸内視鏡検査を受けることが有効です。
大腸ポリープの段階で切除できれば、大腸がんの発生を防ぐことにもつながります。
- 大腸がん検診の受診率がまだ十分に高くない
- 便秘や下痢など、自覚症状が続く場合は早めに医師へ相談する
- 家族歴がある場合はより注意深く受診を検討する
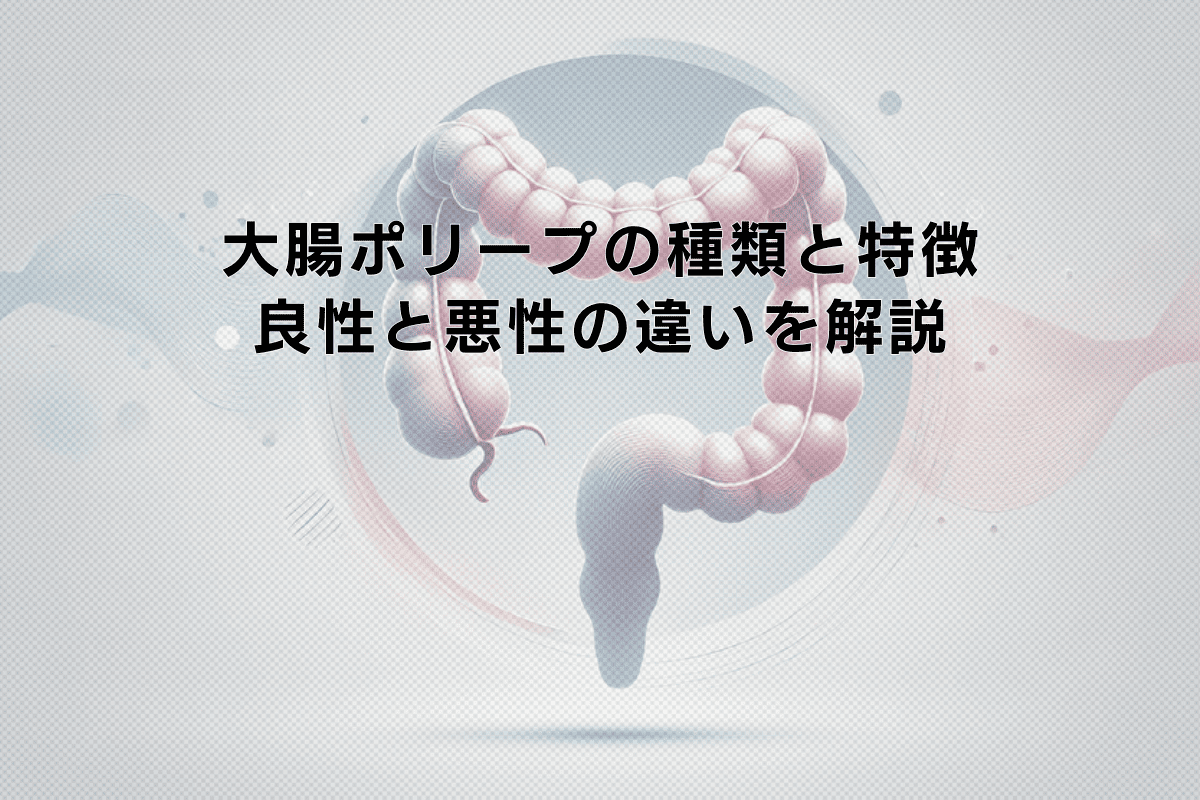
病理検査から得られる情報
手術や内視鏡で切除した組織は、顕微鏡による病理検査が行われ、がんの種類(組織型)や浸潤の深さ、リンパ節への転移数などが詳細にわかります。病理検査は再発リスクの見積もりや追加治療の必要性を判断するための大切な情報です。
病理検査の結果をもとにガイドラインに沿った治療計画を立てることで、長期的な経過観察の質を高められます。
大腸がんと日常生活・サポート
治療を受けながら普段の生活を維持するためには、食事や運動、仕事の調整などに配慮が必要です。また家族や周囲のサポート体制を充実させることで、精神的なストレスを軽減し、再発予防にもつなげやすくなります。
治療後の食事と栄養
大腸がんの術後や薬物療法中は食欲不振や下痢、便秘が起こりやすいため、バランスのよい食事を心がける工夫が役立ちます。
炭水化物、タンパク質、脂質のバランスを整え、ビタミンやミネラル、食物繊維も適度に摂取できるよう意識するとよいでしょう。
- 脂っこいものや刺激物を控える
- 野菜や果物でビタミン・ミネラルを補う
- 水分をこまめに摂取して便秘を防ぐ
- 食事量は少なめに始めて体調をみながら増やす
大腸がん治療後に意識したい栄養バランス
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 体力維持、組織修復 | 肉、魚、大豆製品、乳製品 |
| 炭水化物 | エネルギー源 | ご飯、パン、麺類、いも類 |
| 脂質 | エネルギー源、ホルモン合成の材料 | 油、バター、ナッツ類、青魚の脂 |
| ビタミン・ミネラル | 代謝機能の調整、免疫力維持 | 野菜、果物、海藻類、きのこ類 |
| 食物繊維 | 腸内環境の改善 | 野菜、果物、穀類、豆類 |
痛みや副作用への対策
放射線治療や薬物療法の最中は下痢や便秘、脱毛、倦怠感、食欲不振などが現れる場合があります。医師や薬剤師と相談しながら緩和策を取り、痛みに対しては鎮痛薬や適切な休養を組み合わせることで生活を整えることが重要です。
また、外科的手術後の創部痛や排泄の変化なども起こりやすいため、遠慮なく医療スタッフに相談してください。
- 痛みの程度を日々記録して医師に伝える
- 体調に合わせて仕事や家事を調整する
- 無理せず休息をとり、疲労をためない
- 薬の副作用を把握して、不安な点は早めに質問する
仕事や家事との両立
ステージIIIやIVの患者でも、治療計画によっては外来通院しながら仕事や家事を続けられる人もいます。職場に事情を伝えて勤務形態を柔軟にしてもらったり、家事を家族に協力してもらうなど、負担を分散する工夫が必要です。
休養を十分にとりながら、体調に合わせて働き方を考えていくことが再発予防にもつながります。
生活と治療の両立を考えるときのポイント
- 通院スケジュールを把握し、負担が少ない日程を職場と相談する
- 症状の悪化を予防するため、適宜休暇を取得できるよう手続きしておく
- 家族や近しい人にも治療状況を伝え、困りごとがあれば協力を得る
- 地域や行政の支援制度を活用して経済的・精神的に無理をしない
家族や周囲のサポート体制
大腸がんは治療期間が長くなる場合が多いため、家族や友人、職場の理解を得ることが大切です。
再発や転移の不安がある場合、一人で悩まずに医療ソーシャルワーカーやカウンセリングなどの支援を受けることで、精神的ストレスを減らし、前向きな治療と生活を継続するエネルギーを得やすくなります。
- カウンセリングや患者会に参加し、同じ立場の人と情報交換する
- 診断や治療方針を理解しやすいように家族も診察に同席する
- 相談できる窓口(病院の相談室、地域の支援団体など)を知っておく
患者さん・家族が活用しやすいサポート
| サポート内容 | 主な利用先や担当 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 医療ソーシャルワーカー | 病院の医療相談室 | 経済的・心理的支援の相談 |
| がん相談支援センター | 各がん診療連携拠点病院 | 情報収集、専門スタッフとの面談 |
| 患者会・家族会 | 地域コミュニティやオンライン | 同じ悩みを持つ人との交流 |
| 心理カウンセラー | 病院、クリニックなど | ストレス緩和、気持ちの整理 |
大腸がんはステージ(病期)の把握が重要であり、その進行度に応じた治療法を選択していくこと、治療後も再発や転移に気を配りながら日常生活を整えることが大切です。
ステージが進むほど治療は複雑化しますが、医師や看護師をはじめとする医療チームや家族のサポートをうまく活用しながら、可能な限り症状コントロールと生活の質の両立をめざします。
大腸がんは検査を受けることで早期発見できるチャンスが高まりますので、定期的な検診や健康診断も改めて意識してください。
次に読むことをおすすめする記事
【大腸がん症状を知る 兆候から治療まで】
大腸がんのステージについて理解が深まったら、次は実際の症状や治療の流れについて知っておくと安心です。症状の見極め方から検査、治療まで、実際に大腸がんに関わる方に特に参考になる内容です。
【大腸ポリープの症状と早期発見のために知っておきたいこと】
大腸がんのステージについて理解が深まると、関連する大腸ポリープについても知りたくなる方が多いようです。がん化前の段階での予防や早期発見という意外な繋がりが見えてくる内容です。
参考文献
Ulanja MB, Rishi M, Beutler BD, Sharma M, Patterson DR, Gullapalli N, Ambika S. Colon cancer sidedness, presentation, and survival at different stages. Journal of oncology. 2019;2019(1):4315032.
Dotan E, Cohen SJ. Challenges in the management of stage II colon cancer. InSeminars in oncology 2011 Aug 1 (Vol. 38, No. 4, pp. 511-520). WB Saunders.
Ahmed M. Colon cancer: a clinician’s perspective in 2019. Gastroenterology research. 2020 Feb;13(1):1.
Gupta P, Chiang SF, Sahoo PK, Mohapatra SK, You JF, Onthoni DD, Hung HY, Chiang JM, Huang Y, Tsai WS. Prediction of colon cancer stages and survival period with machine learning approach. Cancers. 2019 Dec 12;11(12):2007.
Benson AB, Arnoletti JP, Bekaii-Saab T, Chan E, Chen YJ, Choti MA, Cooper HS, Dilawari RA, Engstrom PF, Enzinger PC, Fleshman JW. Colon cancer. Journal of the National Comprehensive Cancer Network. 2011 Nov 1;9(11):1238-90.
Chakrabarti S, Peterson CY, Sriram D, Mahipal A. Early stage colon cancer: Current treatment standards, evolving paradigms, and future directions. World journal of gastrointestinal oncology. 2020 Aug 8;12(8):808.
O’Connell JB, Maggard MA, Ko CY. Colon cancer survival rates with the new American Joint Committee on Cancer sixth edition staging. Journal of the National Cancer Institute. 2004 Oct 6;96(19):1420-5.
Leufkens AM, van den Bosch MA, van Leeuwen MS, Siersema PD. Diagnostic accuracy of computed tomography for colon cancer staging: a systematic review. Scandinavian journal of gastroenterology. 2011 Jul 1;46(7-8):887-94.
Böckelman C, Engelmann BE, Kaprio T, Hansen TF, Glimelius B. Risk of recurrence in patients with colon cancer stage II and III: a systematic review and meta-analysis of recent literature. Acta oncologica. 2015 Jan 2;54(1):5-16.
Kehoe J, Khatri VP. Staging and prognosis of colon cancer. Surgical Oncology Clinics. 2006 Jan 1;15(1):129-46.