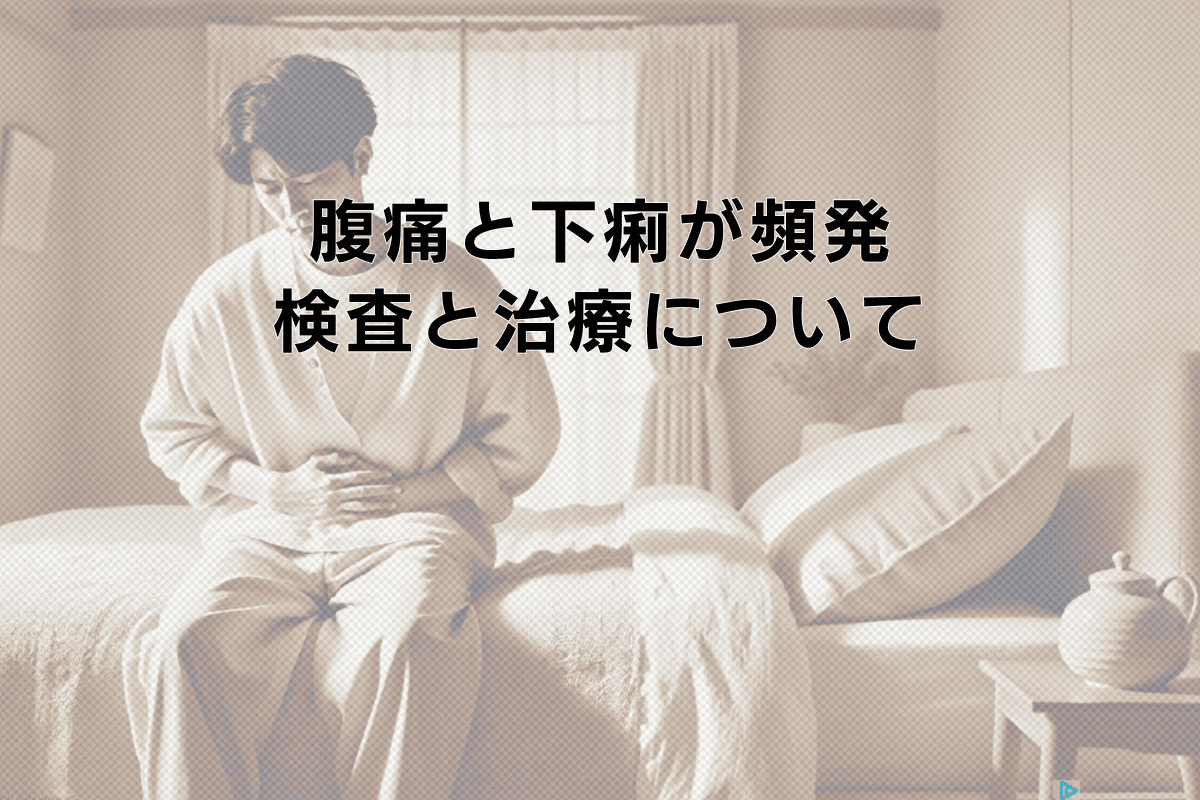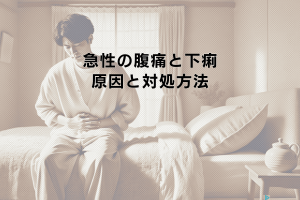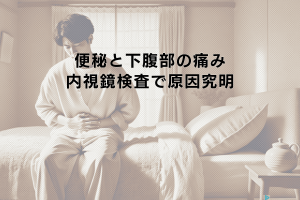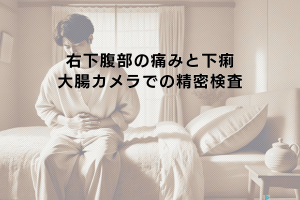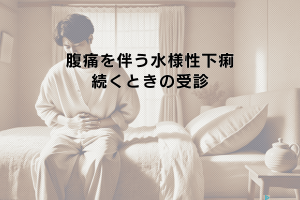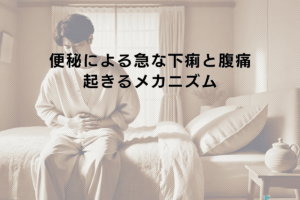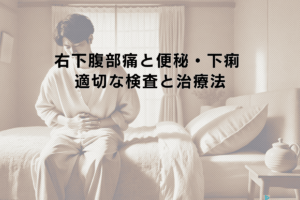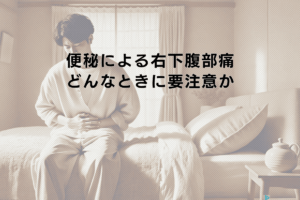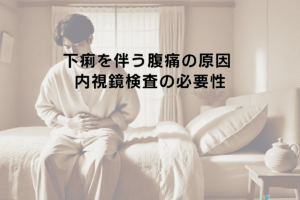腹痛と下痢に悩む方は少なくありませんが、一時的な食べすぎやストレスなどの軽度な原因だけでなく、過敏性腸症候群や感染性腸炎、大腸がんなど重要な病気が潜んでいる場合もあります。
腹痛と下痢は日常生活に大きな負担をもたらすだけでなく、きちんと対処しないと症状が長引き、さらに重症化してしまう可能性があります。
必要に応じて内科や消化器内科での受診を検討しながら、自分の状態や症状の特徴を正しく理解してケアを進めることが大切です。
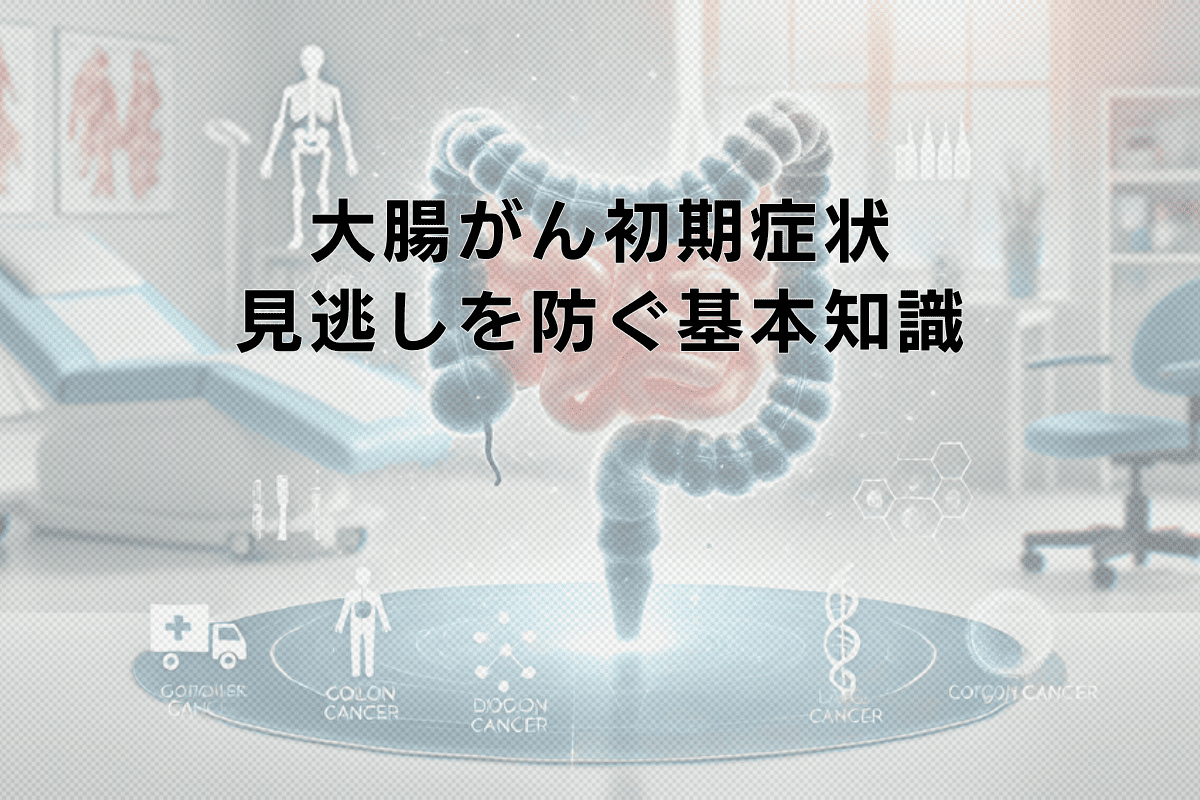
胃腸の働きと腹痛・下痢の関係
消化器官は食事から得た栄養や水分を効率よく吸収し、不必要な成分を便として排出する重要な役割を担います。腹痛と下痢は、この消化器官の機能が乱れた結果として起こりやすい症状ですが、原因はさまざまで、対処法も異なります。
消化器官の基本的な流れ
| 器官 | 主な役割 | 特徴 |
|---|---|---|
| 口 | 食物を噛み、唾液で湿らせる | 消化の最初のステップ |
| 食道 | 口から胃まで食物を運ぶ | 蠕動運動により食物を胃へとスムーズに輸送 |
| 胃 | 胃酸や消化酵素で食物を部分的に分解 | 胃潰瘍や胃がんなどの病気が起こることもある |
| 十二指腸 | 胆汁酸や膵液を加えてさらに食物を消化 | 炎症が生じると腹痛を伴うことがある |
| 小腸 | 栄養と水分を吸収する | 過敏性腸症候群などで機能異常を起こすことも |
| 大腸 | 水分を吸収し便を形成、排出に備える | 便秘や下痢、大腸がんなどのトラブルが起こりやすい |
上記のようなプロセスのうち一部に異常が生じると、腹部に痛みを伴う下痢が起こりやすくなります。
腹痛と下痢が同時に起きる背景
- 消化管の炎症や感染
- 過敏性腸症候群などの機能的な異常
- 暴飲暴食や過度なストレス
- 胃酸や酵素のバランス崩れによる消化不良
- 腸の蠕動運動の乱れ
これらが複合的に作用することもあり、原因を特定しにくいケースが多いです。
腸が敏感になる理由
腸は消化だけでなく、免疫やホルモン分泌など様々な役割を担うため、ストレスや生活習慣の乱れに敏感に反応します。
特に精神的緊張が長く続くと、神経伝達物質が過剰に分泌されて腸の蠕動運動が乱れ、急な下痢や腹痛を引き起こすことがしばしばあります。
腹痛下痢に注目すべきサイン
- 便に血が混じる(血便)の有無
- 体重が急に減少しているか
- 発熱などの全身症状があるか
- 痛みの部位が変わったり激しくなったりしていないか
これらのサインがある場合は、腸や消化器に深刻な異常が潜んでいる可能性があるため、できるだけ早めに受診することが大切です。
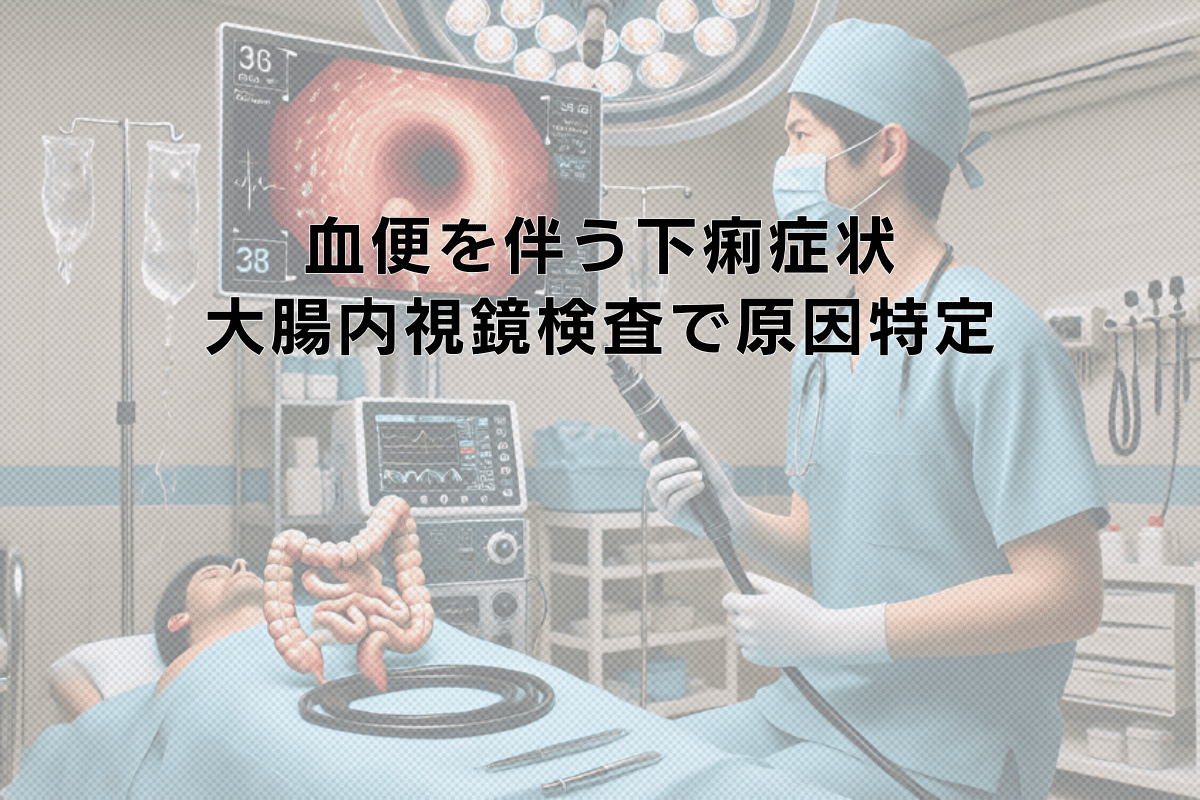
腹痛下痢を引き起こす主な原因
腹痛と下痢の原因は1つではなく、多くの要因が絡み合っていて、軽度で一過性のものから慢性的に続く疾患までさまざまです。ここでは代表的な原因を解説します。
急性の感染性腸炎
ウイルスや細菌の感染により腸が炎症を起こすと、突発的に強い腹痛や水分を多く含んだ便が出やすくなり、食中毒やノロウイルスなどが典型例で、多くの場合は嘔吐や発熱を伴うケースも見受けられます。
| 主な原因微生物 | 主な感染源 | 特徴 |
|---|---|---|
| ノロウイルス | 汚染された食品 | 激しい嘔吐・下痢、冬場に流行が多い |
| ロタウイルス | 汚染された水 | 乳幼児の下痢の原因としてよく知られる |
| サルモネラ菌 | 鶏卵、生肉 | 腹痛・下痢・発熱が起こることが多い |
| カンピロバクター | 鶏肉 | 潜伏期間が2~5日程度で嘔吐や下痢が出やすい |
感染性腸炎の場合、多くは数日から1週間程度で症状がおさまりますが、水分や電解質の補給は重要です。症状が激しい時は、脱水や電解質バランスの乱れに注意してください。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群は、検査をしても炎症や潰瘍などの明確な異常が見つからないのに下痢や便秘が繰り返し起こり、腹痛を伴うことが特徴的です。
ストレスや緊張状態がきっかけとなり、腸の運動や分泌が乱れ、便がゆるくなったり頻回に排便したりする症状が出ます。
| 型 | 主な症状 |
|---|---|
| 下痢型 | 朝や通勤途中など決まったタイミングで下痢が起こる |
| 便秘型 | 便秘が続き、たまに下痢を挟む場合もある |
| 交互型 | 下痢と便秘が交互に繰り返される |
生活習慣の改善やストレスマネジメントが有用であり、内科・消化器内科で相談すると必要に応じて整腸薬や症状を抑える薬を処方してもらえます。
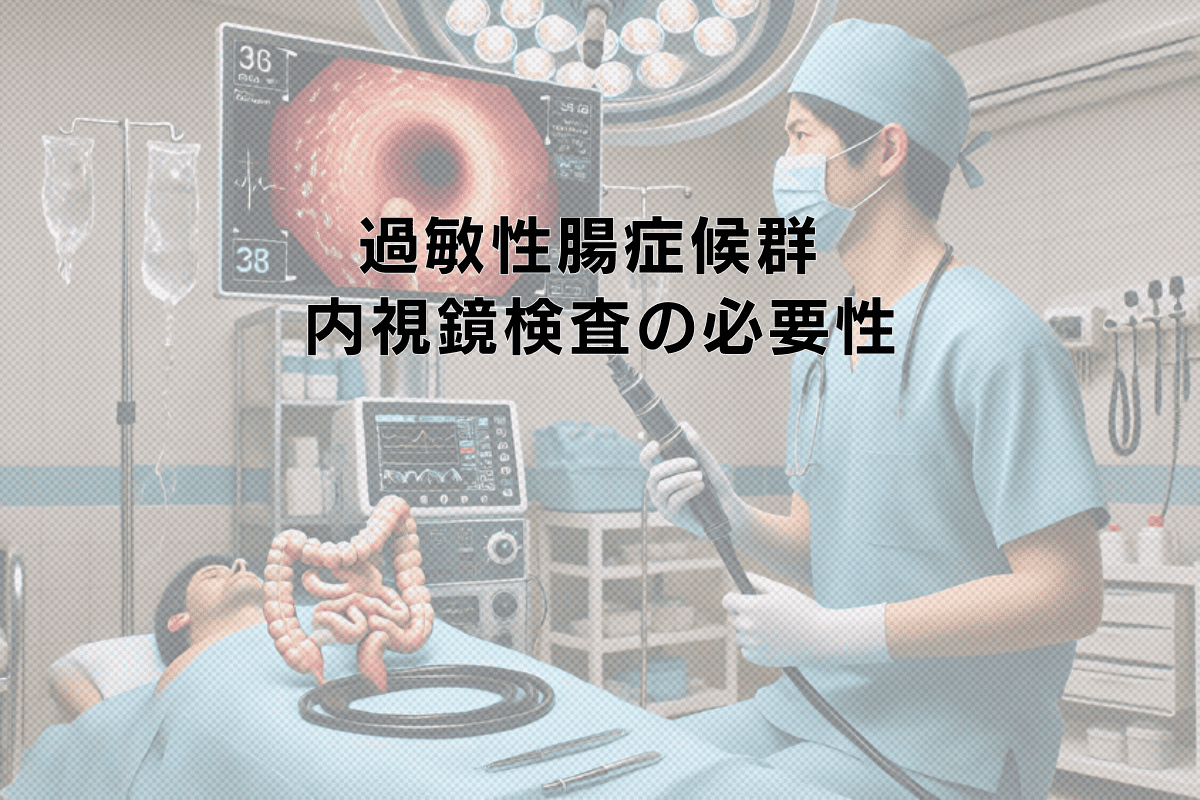
潰瘍性大腸炎・クローン病
これらは炎症性腸疾患に分類され、免疫異常などが原因と考えられ、大腸や小腸に慢性の炎症や潰瘍が生じ、下痢や血便、腹部の痛みが繰り返し起こるのが特徴です。進行に伴い、体重減少や貧血、発熱などの全身症状が出ることもあります。
| 疾患名 | 病変部位 | 主な症状 |
|---|---|---|
| 潰瘍性大腸炎 | 大腸がほとんど。まれに小腸も。 | 血便、粘液便、持続する下痢や腹痛 |
| クローン病 | 口から肛門までの消化管 | 血便、腹痛、瘻孔形成、栄養吸収障害 |
自己判断だけでは発見が遅れる可能性があるため、血便が出たり長期にわたる下痢が続く時は内視鏡検査などを含む検査が必要です。

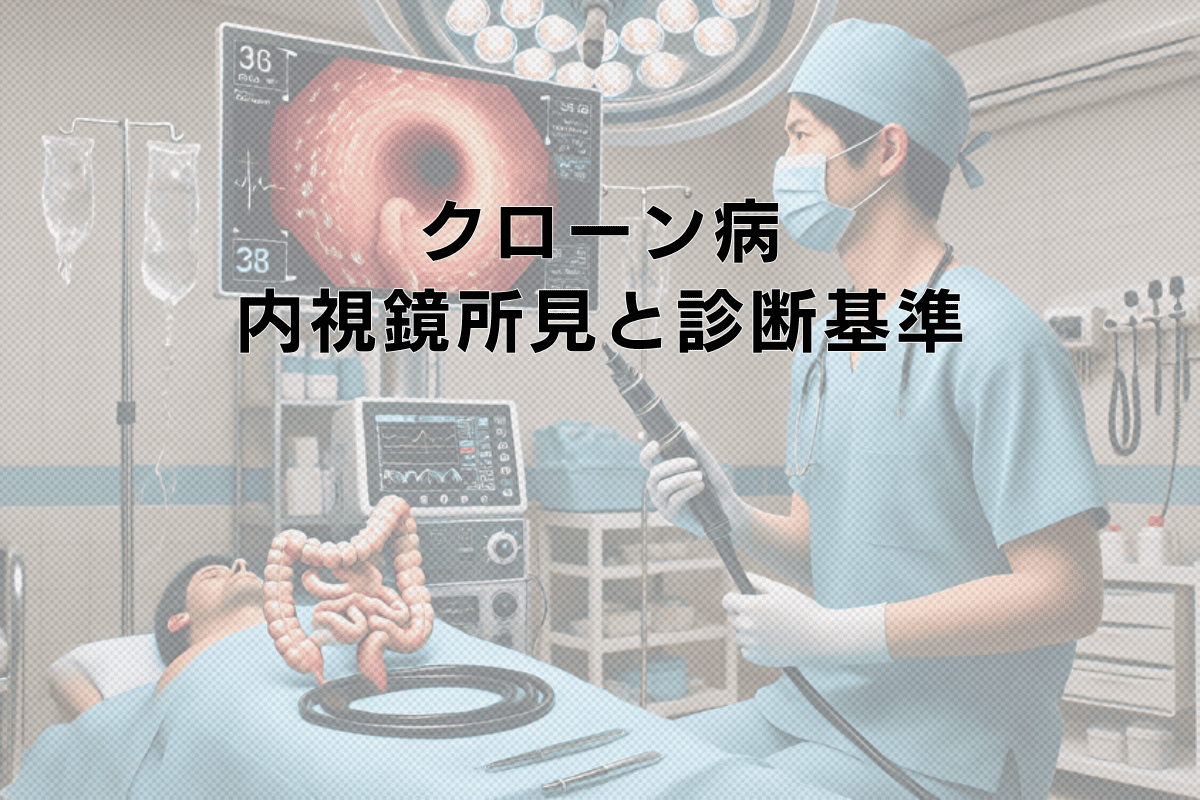
暴飲暴食やストレスによる下痢
過度に油分や糖分の多い食事や、アルコールを大量に摂取すると、腸の働きが過剰になり、下痢や腹痛が起こりやすくなります。また、緊張や不安で神経が高ぶった状態では腸の蠕動運動が乱れ、急な腹部の痛みと下痢を伴うことも多いです。
- 暴飲暴食による消化不良
- ストレスで交感神経が優位になり腸が過剰に動く
- 過度のカフェインや香辛料の摂取
これらに該当する方は、食習慣を見直したり、適度にリラックスを心がけたりすることが大切です。
危険なサインと専門的な検査が必要なケース
腹痛と下痢は一過性に終わることが多い症状ですが、なかには重大な病気が隠れていることがあります。以下のようなサインがある場合は、ただの腹痛下痢ではない可能性が高いため、早めの受診が重要です。
高熱や血便を伴う
下痢だけでなく高い熱がある、あるいは便に血液が混じる(血便)状態が続くときは、細菌やウイルスの強い感染、潰瘍性大腸炎や大腸がんなどの重篤な病気を疑うことが必要です。
特に血便は粘液状で赤いものや黒いタール便など、色合いによっても病変の部位が異なる場合があります。
| 血便の色合い | 主な病変部位 | 代表的な病気 |
|---|---|---|
| 鮮紅色 | 肛門~下部結腸 | 痔、直腸がん、潰瘍性大腸炎など |
| 暗赤色 | 大腸全般 | 潰瘍性大腸炎、大腸がん |
| 黒色(タール便) | 上部消化管 | 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん |
鮮紅色の血が便に混ざる場合は肛門付近や下部結腸の炎症が考えられ、黒色便であれば上部消化管からの出血が疑われ、どのタイプにせよ放置すると症状が悪化するケースがあります。
体重減少や長期間続く下痢
体重が急に落ちている、もしくは腹痛と下痢が数週間以上続く場合、クローン病や潰瘍性大腸炎などの慢性炎症性腸疾患を始めとする深刻な病気が潜んでいる可能性が高いです。
そうした病気では腸からの栄養吸収が障害され、体力が落ちることもあります。
夜間や就寝中に痛みで目が覚める
単なるストレスが原因の過敏性腸症候群では、夜間に激しい痛みを伴うことはあまり多くありません。夜中や明け方に急に痛みで目が覚める場合、胃や大腸に潰瘍ができている、あるいは胆石や腸閉塞といった他の腹部疾患も考えられます。
夜間の激しい痛みや止まらない下痢を感じるときは、救急診療の利用も視野に入れる必要があります。
専門的な検査が必要な理由
腹痛と下痢の原因が複雑で、時には腸だけでなく胃や十二指腸、さらには肝臓や胆のうといった他の臓器のトラブルが関係することもあります。医師はまず問診で症状の特徴や生活習慣を確認し、必要に応じて以下の検査を行います。
| 検査名 | 目的 | メリット・特徴 |
|---|---|---|
| 血液検査 | 炎症反応、貧血状態、栄養状態、感染の有無を確認 | 全身状態の把握が可能 |
| 便検査 | 細菌やウイルス、潜血などを検出 | 感染症や出血の有無を簡便にチェックできる |
| 腹部超音波検査 | 腸以外の臓器(肝臓、胆のう、すい臓など)の形態をみる | 放射線被曝がなく安全性が高い |
| CT/MRI検査 | 詳細な腹部の断面画像を得る | 炎症や腫瘍の存在、腸管の状態を立体的に把握できる |
| 内視鏡検査 | 大腸や胃の内部を直接観察する | ポリープなどを発見した場合、その場で切除も行いやすい |
これらの検査を組み合わせることで、潜在的な大腸がんや潰瘍性大腸炎といった重篤な疾患を早期に発見できる機会が増えます。

腹痛・下痢の治療や予防に役立つ方法
腹痛や下痢への対処法は、原因に応じて大きく異なりますが、基本的な治療方針と日常的な予防策について知っておくことは大切です。
軽症であれば食事療法や生活習慣の見直しで改善が期待できますが、重度の場合は薬物療法や内視鏡下での治療が必要になることもあります。
薬物療法の選択
- 整腸薬(乳酸菌製剤など):腸内細菌のバランスを整える
- 止瀉薬(ロペラミドなど):腸の蠕動運動を抑制し下痢を緩和する
- 抗菌薬・抗ウイルス薬:感染性腸炎の場合
- 抗炎症薬・ステロイド:潰瘍性大腸炎やクローン病の炎症を抑制
薬物療法を始める際には、医師や薬剤師の説明をよく聞き、副作用にも注意しながら使用する必要があります。
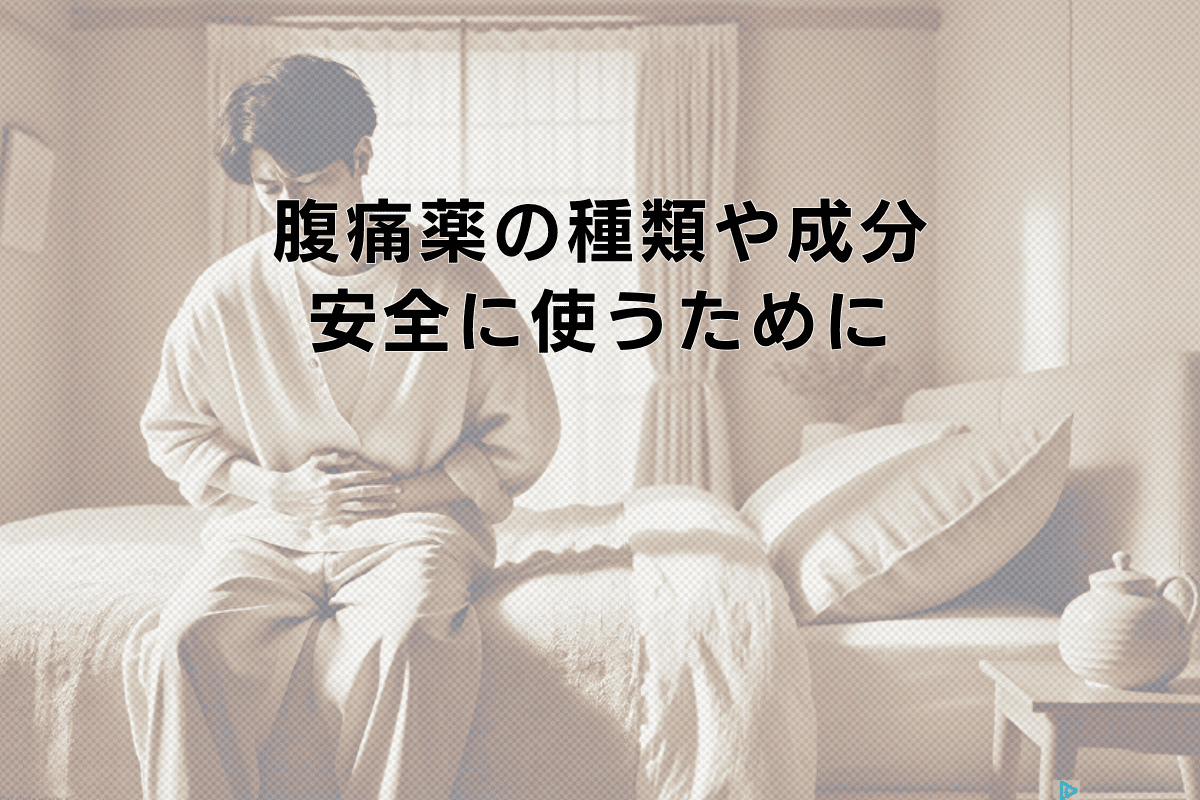
食事と水分補給
下痢がある場合は脱水や電解質の喪失に気をつけながら、胃腸に過度な負担をかけない食生活を心がけることが基本です。以下の点に着目してください。
- 水分補給はこまめに行い、スポーツドリンクなどで電解質を補う
- 脂肪分や香辛料の多い食事は避ける
- 温かく消化の良いものを中心に取り入れる
- アルコールやカフェイン飲料の摂取を控える
消化不良を起こすと腸管に食物が長くとどまり、発酵やガスの発生が増えて腹痛が悪化することがあるため、暴飲暴食は控えましょう。

生活習慣の見直し
ストレスや睡眠不足、運動不足といった生活習慣の乱れは、腸の働きを不安定にする大きな要因です。適度な運動は腸の蠕動を促すと同時にストレス発散にもつながり、夜間の良質な睡眠は自律神経のバランスを整える効果が期待できます。
腹痛下痢を予防する生活習慣の例
- 毎晩6~7時間の睡眠を確保する
- ストレッチやウォーキングなど適度な運動を継続する
- 1日3食を規則正しく摂り、暴飲暴食を避ける
- ストレスを溜め込みすぎない工夫(趣味やリラクゼーションなど)
習慣を整えるだけで下痢や腹痛が緩和されるケースも多く見られます。
早期受診の大切さ
腹痛と下痢が軽度な場合はしばらく様子を見ることも選択肢となりますが、症状が続く場合や血便・発熱などの緊急性を感じる症状があるときは放置せず、専門の医療機関で相談することが重要です。
医師は問診だけでなく、必要に応じて各種検査を行い、最適な治療方針を提案してくれ、早めの受診は重篤な病気の見逃しを防ぎ、治療期間の短縮や再発予防にもつながります。
日常生活で実践できる改善策
腹痛と下痢を抱える方にとって、日常の小さな心がけが大きな差を生む場合があります。急性の感染症や慢性炎症性疾患でも、生活全般を見直すことで症状が緩和しやすくなるケースがあるので、できる範囲で取り組むことがおすすめです。
ストレス管理の工夫
メンタル面が腸に与える影響は意外に大きく、特に過敏性腸症候群ではストレスが症状の悪化要因となりやすいです。心身ともにリラックスできる環境や時間を作り、趣味や入浴などで気分転換を図ると、自律神経のバランスが整いやすくなります。
ストレスを軽減する方法
- ゆっくり湯船に浸かる
- 深呼吸や軽い瞑想を取り入れる
- 自分が楽しめる趣味を定期的に実践する
- 適宜カウンセリングや友人との会話などで気持ちを吐き出す
過度なストレスは腸の蠕動運動を乱し、下痢や腹痛に直結するため、意識的にコントロールすることが重要です。
適度な運動
激しい運動ではなく、30分程度のウォーキングやストレッチなどを毎日行うだけでも腸の動きが改善しやすくなります。運動不足の方が急に激しい運動を始めると体に負担がかかるため、できる範囲から徐々に習慣化を目指してください。
排便習慣の確立
時間帯を決めてトイレに行くなど、一定のリズムをつくることで腸が規則正しい動きをしやすくなります。
便意がなくても朝食後や夕食後など決まったタイミングでトイレに座る習慣をつけると、下痢と便秘を繰り返している方にも役立つ場合があります。
毎日の習慣として取り入れやすい例
- 朝起きたらコップ1杯の水を飲む
- 朝食後にトイレに座る時間を作る
- 夜間に軽いストレッチを行いリラックスしてから就寝する
こうした工夫で腸の動きを整えると、腹痛や下痢が起こりにくい環境をつくりやすくなります。
早めに医療機関へ相談
自己判断で市販の下痢止めを使い続けて症状を抑えるだけでは、根本的な原因が改善しないまま病気が進行するリスクがあり、とりわけ血便を伴う場合や、極端に痩せるほど下痢が続く場合は内科や消化器内科を早めに受診しましょう。
医療機関を選ぶときのポイント
- 内科や消化器内科など、腹痛や下痢の診察経験が豊富な医院を探す
- 長引く症状や重症の兆候がある場合は大きな病院で詳細な検査も視野に入れる
- 問診時には下痢や痛みの頻度、便の状態などを具体的に説明する
現在の自分の症状を正確に伝えることがスムーズな診断・治療へとつながります。
まとめ
腹痛と下痢は多くの方が経験するトラブルですが、原因は一時的な暴飲暴食やストレスから感染性腸炎、炎症性腸疾患、大腸がんなど幅広くあります。
症状が軽い場合は日常的な食事や生活習慣の見直し、ストレス管理、適度な運動などを組み合わせて改善することが期待できますが、血便や体重減少、高熱などの深刻なサインがあるときは早急な受診が重要です。
内科や消化器内科では検査や問診をもとに治療法を提案し、必要に応じて薬物療法や内視鏡検査を実施します。自己判断だけに頼らず、安心して日常生活を続けるためにも、症状が気になる方は医師への相談を検討してください。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査とはどのような検査なのか】
腹痛と下痢の原因について理解が深まったら、次は実際の検査方法について知っておくと安心です。大腸内視鏡検査を検討中の方に特に参考になる内容です。
【消化器官の機能と働き|内視鏡検査で分かること】
腹痛と下痢について学んだ皆さんには、消化器官全体の働きの知識も合わせて持っていただくと、より包括的な理解ができます。
参考文献
Reisinger EC, Fritzsche C, Krause R, Krejs GJ. Diarrhea caused by primarily non-gastrointestinal infections. Nature Clinical Practice Gastroenterology & Hepatology. 2005 May 1;2(5):216-22.
Schiller LR, Pardi DS, Sellin JH. Chronic diarrhea: diagnosis and management. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2017 Feb 1;15(2):182-93.
Mrouf A, Albatish I, Mosa MJ, Abu-Naser SS. Knowledge Based System for Long-term Abdominal Pain (Stomach Pain) Diagnosis and Treatment.
Alhmoud T, Arif H, Auyang E, Samedi V, Parasher G. Chronic abdominal pain, ascites, and diarrhea: seeing red. Digestive diseases and sciences. 2014 Apr;59:740-3.
Stark TD, Mtui DJ, Balemba OB. Ethnopharmacological survey of plants used in the traditional treatment of gastrointestinal pain, inflammation and diarrhea in Africa: future perspectives for integration into modern medicine. Animals. 2013 Mar 4;3(1):158-227.
Törnblom H, Holmvall P, Svenungsson B, Lindberg G. Gastrointestinal symptoms after infectious diarrhea: a five-year follow-up in a Swedish cohort of adults. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2007 Apr 1;5(4):461-4.
Fry LC, Carey EJ, Shiff AD, Heigh RI, Sharma VK, Post JK, Hentz JG, Fleischer DE, Leighton JA. The yield of capsule endoscopy in patients with abdominal pain or diarrhea. Endoscopy. 2006 May;38(05):498-502.
Bercovitz ZT. The differential diagnosis of diarrhea and bloody stools. Medical Clinics of North America. 1954 May 1;38(3):817-33.
Sharma S, Bhatia R, Vasudevan A. Abdominal pain and diarrhea in peptic ulcer disease. Gastroenterology. 2021 Aug 1;161(2):e48-9.
De Boissieu D, Chaussain M, Badoual J, Raymond J, Dupont C. Small-bowel bacterial overgrowth in children with chronic diarrhea, abdominal pain, or both. The Journal of pediatrics. 1996 Feb 1;128(2):203-7.