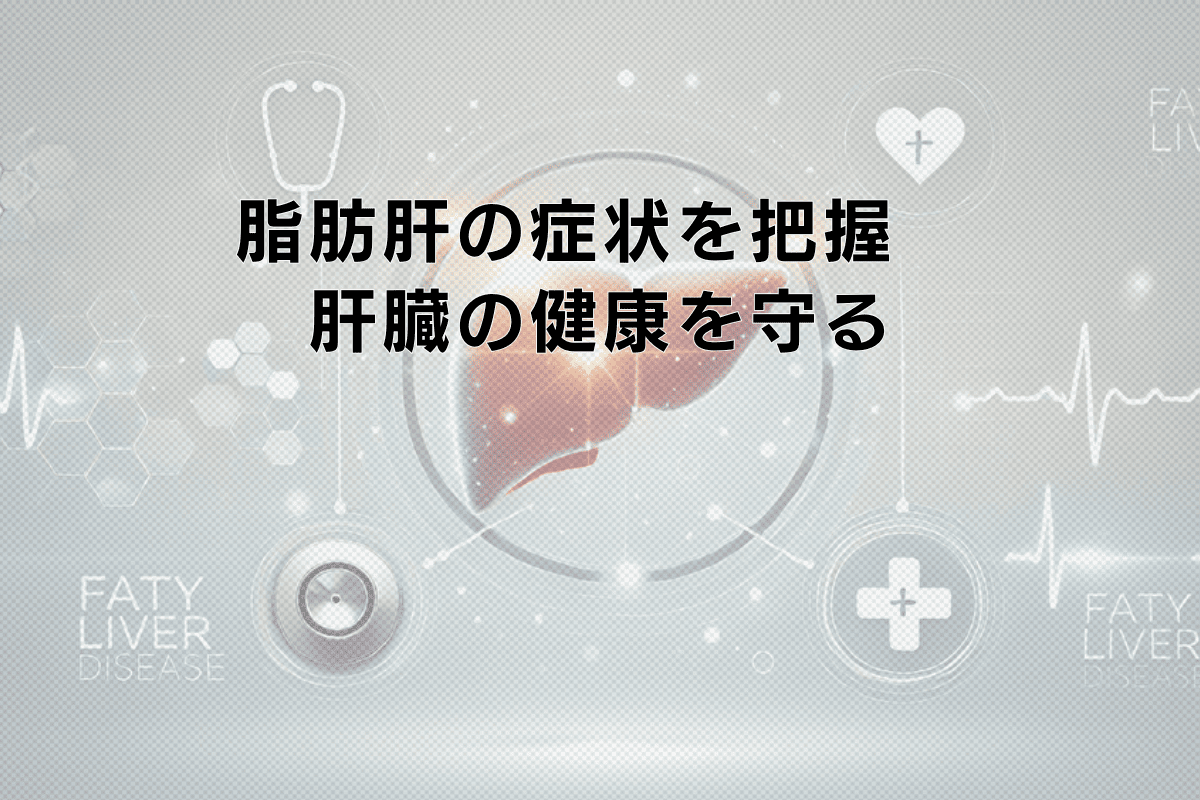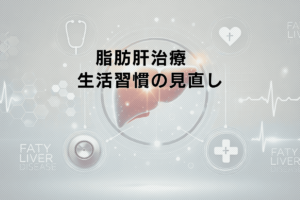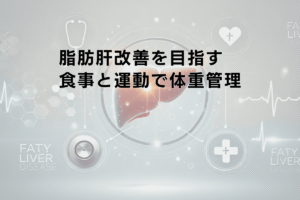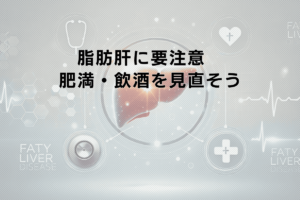脂肪肝は肝細胞に脂肪が多く蓄積した状態を指し、健康診断などで偶然見つかることがよくあります。
自覚症状がほとんどないため放置しがちですが、進行すると肝臓の炎症や肝硬変、さらには肝臓がんへのリスクを高める可能性があります。
食事や運動など生活習慣を見直すことで改善や予防に取り組めるケースも多いため、脂肪肝の原因や症状を正しく理解しながら適切にケアしていくことが大切です。
この機会に肝臓の働きや脂肪肝の検査方法、治療法などを把握し、自分の体を守る一歩を踏み出してください。
脂肪肝とは何か
日常生活でよく耳にする「脂肪肝」は、肝臓の細胞に中性脂肪などの脂肪が過剰に蓄積した状態です。
肝臓は体内で重要な働きを数多くこなしており、余分な糖や脂質を一時的に蓄えてエネルギー供給を調節する場でもありますが、過剰なカロリー摂取や飲酒などが続くと肝臓内の脂肪が増えすぎ、肝機能の低下につながる可能性が高まります。
なぜ肝臓に脂肪がたまるのか
肝臓は糖質や脂質などを代謝・貯蔵する機能を担いますが、エネルギー過剰の状態が続けば中性脂肪が次々に蓄えられ、さらに、脂肪を代謝する働きが衰えると、脂肪が分解・排出されずに残りやすくなります。
アルコール性脂肪肝や代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)という形で区分されるのが特徴です。
肝臓の働きと影響
肝臓は解毒、栄養素の貯蔵、胆汁の生成、ホルモン分解など多岐にわたる役割を持つ臓器で、脂肪肝が進行すると、肝機能のバランスが崩れやすくなり、全身的な不調に発展する場合もあります。
アルコール性脂肪肝と非アルコール性脂肪肝
脂肪肝は大きくアルコール性と非アルコール性(MASLD)の2つに分かれ、MASLDの一部はMASH(代謝機能障害関連脂肪肝炎)へ移行する危険性が知られています。
前者は多量飲酒により肝臓が脂質代謝をうまく処理できず、脂肪肝に陥るもので、後者は肥満や糖尿病、運動不足などに起因する生活習慣病の1つです。
軽度のうちに対策を始める必要
脂肪肝そのものは自覚症状が少なく、軽度の段階では健康診断などで偶然に見つかることが多いですが、症状がないからといって安心できるわけではなく、放置すると肝硬変や肝がんへと進むリスクが高まります。
また
生活習慣の見直しなど早期からの取り組みが重要です。
脂肪肝の症状と特徴
脂肪肝は初期段階では顕著な自覚症状がほとんどなく、「沈黙の臓器」と呼ばれる肝臓の特徴が現れています。実際、疲れやすさやだるさなど日常生活でありがちな症状に埋もれてしまうため、知らずに進行しているケースも少なくありません。
自覚症状が乏しい理由
肝臓は再生能力が高く、ある程度のダメージならば機能を維持でき、さらに、痛みを感じる神経がほとんどないため、炎症や損傷が軽度のうちは強いサインを発しにくいです。
その結果、脂肪肝になっていても、検査数値が上昇するまで本人が気づかない場合が多くなります。
疲労感や倦怠感が出ることも
一部の人では、慢性的な疲労感、肩こり、右上腹部の違和感などの軽い症状を感じることがありますが、こうした症状は他の病気やストレスとも紛らわしいため、「自分が脂肪肝だ」と自覚しづらいのが現実です。
もし生活習慣や肥満など思い当たる節があるなら、こうした軽微な不調を見逃さないようにすることが大切です。
症状チェックリスト
気になる状態
- 眠っても疲れが抜けにくい
- 肩や背中が張るような感じが続く
- 右上腹部に重苦しい感じがある
- やや肥満気味なのに筋力が落ちてきた
- お酒を頻繁に飲むか食事が偏っている
いくつか当てはまる場合は、医療機関で検査を受けてください。これらのサインは特定の病気に限らないものの、脂肪肝との関連性を確認するきっかけになります。
脂肪肝が進行した場合のリスク
放置するとアルコール性脂肪性肝炎や代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)に進み、肝硬変や肝がんへの発展リスクが高まります。
進行すると、黄疸や腹水、食道静脈瘤といった重い症状が出現し、生命にかかわる重大な疾患へつながる可能性も否定できず、早期の段階で対策を講じることが肝要です。
脂肪肝の原因とリスク要因
脂肪肝はアルコールや食事習慣などさまざまな原因によって肝臓に脂肪が蓄積してしまいます。ここでは、脂肪肝が生じやすい主なリスク要因を整理しながら、自分がどの程度当てはまるかチェックしてみましょう。
アルコール性脂肪肝
1日に大量のアルコールを摂取する習慣があると、肝臓はアルコール分解を最優先し、脂質代謝が後回しになり、肝細胞内に中性脂肪がたまりやすくなります。
男性では1日ビール大瓶2本以上、女性では1本以上を常習的に飲む場合、アルコール性脂肪肝を疑う指標となることが多いです。
アルコール性脂肪肝になりやすい条件
| 条件 | 理由 |
|---|---|
| 多量飲酒(毎日ビール2本以上など) | アルコール分解を優先するため脂肪が蓄積しやすくなる |
| 栄養バランスが偏り肝臓に負荷が大きい | タンパク質やビタミン不足で修復や解毒能力が落ちる |
| 他の生活習慣病や肥満 | 複合的に肝への負担が増える |
アルコール依存は自身で気づきにくいケースもあるため、飲酒量が多い自覚がある場合は、少しずつでも減酒を検討してください。
代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)
アルコールをあまり飲まない人でも、過剰なカロリー摂取や糖質中心の食事、肥満、運動不足などの要因で肝臓に脂肪が蓄積します。このようなアルコールを飲まない方に起こる脂肪肝で糖尿病、高脂血症、高血圧などの生活習慣病が合併しているものを、代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)と呼びます。
MASLDは以前、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)と呼ばれていましたが、2023年より現在の名称となりました。
これまでのNAFLDは、アルコールやウイルスなどを原因としない脂肪肝であり、MASLDとは厳密には分類方法が異なりますが、MASLDとNAFLDは95%以上の方が一致すると報告されています。
主な代謝機能障害関連脂肪性肝疾患の要因
- 食事のカロリー過多、脂質や糖質の摂りすぎ
- 運動不足や長時間のデスクワーク
- 遺伝的要因やホルモンバランスの乱れ
- 急激なダイエットで筋肉が減少
生活習慣の乱れは日本でも増えており、脂肪肝発症の裾野が広がってきています。
飲酒と肥満が重なるケース
アルコール性と非アルコール性が明確に区分できない場合もあり、飲酒しながら高カロリー食や甘い物が好きという人は、両方のリスクを抱えています。
こうした場合、肝臓へのダメージが重なりやすく、脂肪肝の進行が速まる恐れがあるため要注意です。
複合的なリスク
- 毎日ビール大瓶1本以上を継続している
- 運動の習慣がなく肥満度が高い
- スナック菓子や甘い物、揚げ物が好き
- 血液検査で中性脂肪や血糖値が高め
炎症性腸疾患や自己免疫疾患との関連
稀なケースですが、一部の炎症性腸疾患や自己免疫疾患、甲状腺機能低下症などでも脂肪肝が誘発されることがあるので、こうした背景疾患を持つ方は、定期的な肝機能検査や医師との相談を続けることが大切です。
脂肪肝の検査と診断方法
脂肪肝は自覚症状が乏しいため、客観的な検査によって見つかるのが一般的で、どのような検査が行われるのかを把握しておくと、健康診断やクリニック受診の際にスムーズに対応できます。
血液検査(肝機能評価)
健康診断などで行われるAST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPなどの値が高値を示すと、肝機能異常を疑うきっかけになりますが、脂肪肝ではこれらの値が必ずしも大きく上昇するわけではありません。
LDLコレステロールや中性脂肪が高い、血糖値が高めといった他の項目との総合判断が重要です。
主な肝機能に関する数値表
| 項目 | 正常範囲(おおよそ) | 脂肪肝での傾向 |
|---|---|---|
| AST(GOT) | 10〜40 U/L | 軽度上昇または正常範囲内の場合が多い |
| ALT(GPT) | 5〜45 U/L | 軽度〜中等度上昇することが多い |
| γ-GTP | 10〜50 U/L | アルコール摂取で上昇しやすい |
| LDLコレステロール | < 140 mg/dL | 脂肪肝のある人は高値を示す傾向 |
| 中性脂肪(TG) | 50〜150 mg/dL | 肥満や飲酒量が多いと高値になりやすい |
上記のような数値の変動はあくまで目安ですが、総合的な評価で脂肪肝が疑われることが多いです。
画像診断(腹部超音波検査など)
エコー(超音波)検査やCT、MRIなどの画像診断は、肝臓に脂肪がどの程度蓄積しているかを視覚的に判断する有力な方法です。腹部超音波検査は低侵襲で費用負担も少なく、健康診断でも比較的一般的に行われます。
画像診断の特徴
- エコー(腹部超音波):肝臓のエコー輝度の上昇などで脂肪肝を推測
- CTスキャン:肝臓と脾臓のCT値の比較で脂肪沈着を評価
- MRI:より詳細な脂肪量の推定が可能
これらの検査結果を血液検査などと併せて総合的に診断します。
FibroScan®
FibroScan®は端子から出される振動の伝わる速さを測定し、肝臓の硬さを確認する検査です。また、超音波が肝臓を通過する時の減衰量を測定することで肝臓にたまった脂肪量を確認することが出来ます。
健康診断の活用
会社や自治体の健康診断を定期的に受けることで、血液検査や腹部超音波検査の結果をもとに早期に脂肪肝を発見しやすくなります。
中高年以降、肥満やメタボリックシンドロームの疑いがある人は毎年の検査結果をしっかりと比較し、数値の変化を見逃さないことが大切です。
健康診断で注意すべき項目
- AST, ALT, γ-GTP
- 中性脂肪, LDLコレステロール
- 空腹時血糖, HbA1c
- 腹部超音波結果
- FibroScan®
こうした項目で異常値が示された場合は、早めの対策を検討しましょう。
脂肪肝の治療と改善方法
脂肪肝は生活習慣の見直しによって大きく改善する可能性がある一方、すでに炎症を起こしている場合やMASHに進展している場合は、専門的な治療が求められます。
食事療法
脂肪肝の第一選択として、カロリーコントロールや栄養バランスの改善が挙げられます。特に糖質や脂質を摂りすぎている場合は、削減することが重要です。
極端なダイエットではなく、適切な範囲で総摂取カロリーを減らし、野菜やたんぱく質を意識的に取り入れていきます。
食事内容の見直しのテーブル
| 改善項目 | 具体的な工夫 |
|---|---|
| 糖質の制限 | 白米やパン、麺類を適量に減らし、全粒粉や雑穀米などを活用 |
| 脂質の見直し | 揚げ物やバター、ラードなど飽和脂肪酸を控え、魚やオリーブオイルなどに置き換える |
| たんぱく質 | 肉・魚・大豆製品をバランスよく摂取し、過度な動物性脂肪は控える |
| 野菜や果物 | 毎食野菜を先に食べ、食物繊維で血糖値の急上昇を抑制 |
適度に炭水化物を摂りながらも、血糖値を安定させる食べ方が必要です。
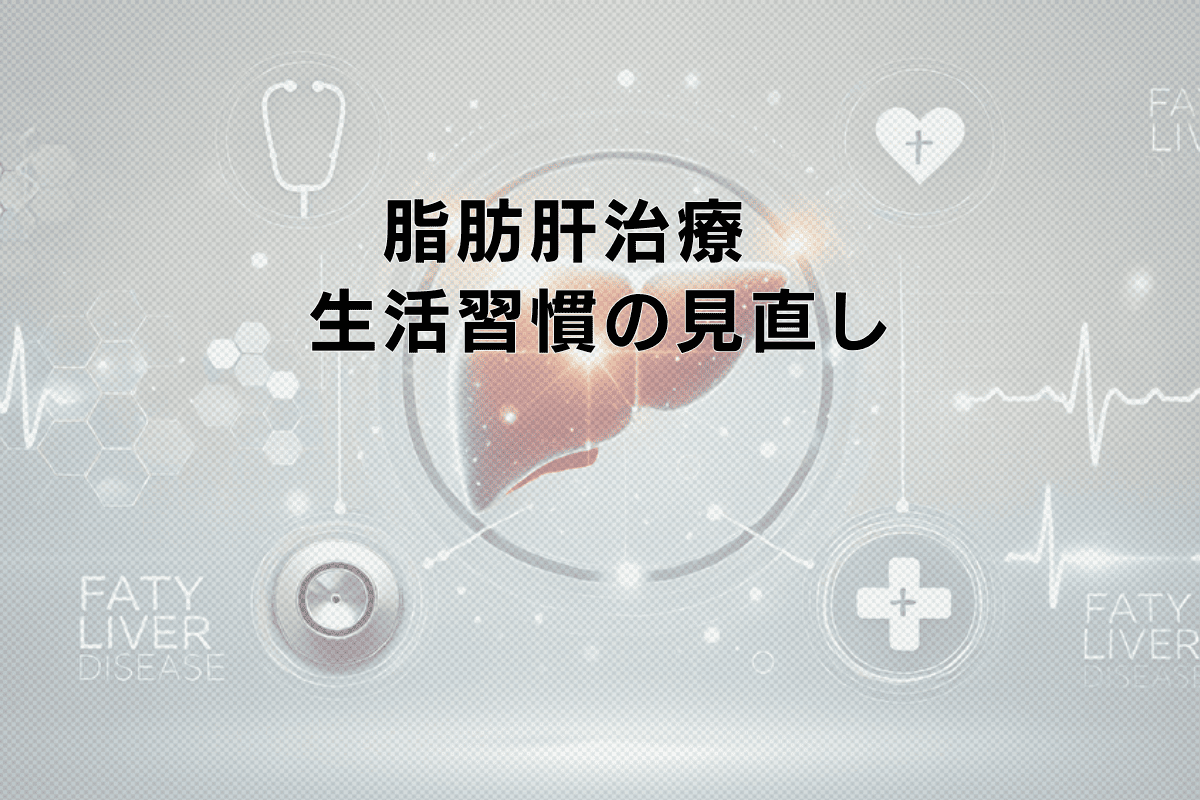
運動療法
体脂肪を燃焼し、筋肉を増やして基礎代謝を高めることは、肝臓内の脂肪減少にも有効で、ウォーキングやジョギングなど有酸素運動を週3~5回、1回30分以上行い、可能なら筋力トレーニングで筋肉量を維持するとより効果的です。
運動習慣のポイント
- ウォーキングや軽いジョギングを週合計150分程度
- 筋トレを週2~3回取り入れ、下半身や体幹を重点的に鍛える
- エスカレーターではなく階段を使うなど日常生活で活動量を増やす
- 無理のない範囲で徐々に負荷を上げる
定期的な運動はインスリン抵抗性の改善や体重減少につながり、脂肪肝のリスクを低減します。
薬物療法とサプリメント
現時点では脂肪肝を直接治療する特効薬はありませんが、合併している高脂血症や糖尿病、高血圧などをコントロールする薬が処方されることがあります。
また、ビタミンEやウルソデオキシコール酸など、肝機能改善に寄与するとされる薬も使われるケースがありますが、効果には個人差があります。サプリメントは薬ではないため、医師に相談してから使う方が安心です。
一部の薬剤と役割
| 薬剤名 | 目的 |
|---|---|
| フェノフィブラート、フィブラート系など | 中性脂肪を下げる |
| ビタミンE製剤 | 抗酸化作用で肝細胞の炎症を緩和 |
| SGLT2阻害薬(糖尿病治療薬) | 体重と血糖を管理し、肝臓への脂肪蓄積を抑える |
これらはあくまで補助的な側面が強く、生活習慣の改善との併用が中心です。
禁酒のすすめ
アルコールが原因となっている脂肪肝の場合、まずは飲酒量の減少が最優先で、アルコール性脂肪肝でも禁酒や減酒により肝機能が回復する可能性がありますが、続けられなければ改善は望めません。
飲酒が習慣化している人は、少量からでも減らしていく努力が大切です。
飲酒量を減らすコツ
| 工夫 | 具体例 |
|---|---|
| 飲む日を決める | 週2日は休肝日を設けるなど |
| 種類を変える | アルコール度数の低いものやハーフサイズ缶を選ぶ |
| ペースを落とす | ノンアルコール飲料や水と交互に飲む |
| 家飲みの管理 | 家にビールのケース買いをせず、都度少量だけ購入しておく |
アルコール依存の疑いがある場合は専門医療機関での相談が欠かせません。
脂肪肝の予防と日常ケア
脂肪肝は予防可能な生活習慣病の1つとして位置付けられており、継続的なケアが重要です。ここでは、日々の習慣や定期検査を通じて肝臓の状態を見守る方法をご紹介します。
日常生活でのポイント
栄養バランスに配慮した食事や適度な運動はもちろん、ストレスコントロールや睡眠管理など、トータルで健康を意識したライフスタイルが大切です。
毎日の習慣として意識したいこと
- 毎食野菜やたんぱく質をしっかりとる
- 炭水化物の摂取量を見直し、加工食品やスナック菓子を控える
- ウォーキングや軽いジョギングを週複数回行う
- 睡眠をしっかりとり、ストレスをため込まない
- できる範囲でアルコール量を減らす
こうした習慣を積み重ねることで肝臓に負担がかかりにくい環境を作れます。
生活習慣を数値化する
自分の行動や体重変化などを記録し、数値でチェックすると、変化や達成感を得やすくなります。特に肥満を合併している場合、体重の5-10%程度の減量が、肝組織(脂肪化、炎症、線維化)の改善に有効とされています。
歩数計やスマートウォッチ、食品記録アプリなどを活用し、食事カロリーや歩数を見える化することが励みになるでしょう。
生活チェックに役立つこと
| 項目 | 具体例 | メリット |
|---|---|---|
| 歩数 | 1日8000歩を目標に設定 | 運動量を把握し、歩数を増やすモチベーションになる |
| 食事カロリー | アプリで1日の摂取量を記録 | カロリー過多や糖質過剰に気づきやすい |
| 体重・体脂肪率 | 週1回は測定してノートやアプリに記録 体重の5-10%程度の減量を目標に | ダイエットや維持の成果が把握できモチベ維持 |
| 飲酒量 | ビール缶の本数やアルコール度数をメモ | 飲みすぎの自覚を持ちやすく減酒のきっかけになる |
| 睡眠時間 | 就寝・起床時間をアプリでトラッキング | 生活リズムの乱れに気づきやすく改善が期待できる |
継続して取り組める仕組みを作ることが成功のカギです。
定期検診の受診
脂肪肝の早期発見や経過観察には定期的な健康診断が役立ち、特に35歳以降は1年に1回の健康診断や人間ドックを受け、血液検査と腹部エコーなどで肝臓の状態をチェックしましょう。
検診時に注目したい項目
- AST, ALT, γ-GTPなどの肝機能
- 中性脂肪, LDLコレステロールなどの脂質
- 空腹時血糖やHbA1cなど糖代謝系
- 腹部超音波検査結果
次に読むことをお勧めする記事
【脂肪肝治療 重要性と生活習慣の見直し】
脂肪肝の症状について理解が深まったら、次は実際の治療方法について知っておくと安心です。食事療法や運動療法の具体的な取り組み方法をご紹介しています。
【消化器官の機能と働き|内視鏡検査で分かること】
脂肪肝を学んだ皆さんには、消化器官全体の知識も合わせて持っていただくと、より包括的な健康管理ができます。内視鏡検査で発見できる病気についても詳しく解説しています。
参考文献
Newton JL. Systemic symptoms in non-alcoholic fatty liver disease. Digestive diseases. 2010 May 7;28(1):214-9.
Kistler KD, Molleston J, Unalp A, Abrams SH, Behling C, Schwimmer JB, Nonalcoholic Steatohepatitis Clinical Research Network (NASH CRN). Symptoms and quality of life in obese children and adolescents with non‐alcoholic fatty liver disease. Alimentary pharmacology & therapeutics. 2010 Feb;31(3):396-406.
Khoonsari M, Azar MM, Ghavam R, Hatami K, Asobar M, Gholami A, Rajabi A, Tameshkel FS, Amirkalali B, Sohrabi M. Clinical manifestations and diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease. Iranian journal of pathology. 2017;12(2):99.
Singh H, Pollock R, Uhanova J, Kryger M, Hawkins K, Minuk GY. Symptoms of obstructive sleep apnea in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Digestive diseases and sciences. 2005 Dec;50:2338-43.
Choudhury J, Sanyal AJ. Clinical aspects of fatty liver disease. InSeminars in liver disease 2004 Nov (Vol. 24, No. 04, pp. 349-362). Copyright© 2004 by Thieme Medical Publishers, Inc., 333 Seventh Avenue, New York, NY 10001, USA..
Rafiei R, Bemanian M, Rafiei F, Bahrami M, Fooladi L, Ebrahimi G, Hemmat A, Torabi Z. Liver disease symptoms in non-alcoholic fatty liver disease and small intestinal bacterial overgrowth. Romanian Journal of Internal Medicine. 2018 Jun 1;56(2):85-9.
Hoque M, Rahman MM, Hasan MA, Uddin MN, Mondol A. Understanding Non Alcoholic Fatty Liver Disease: Causes, Symptoms and Treatment. International Journal of Research Publication and Reviews. 2023 Sep;4(9):2084-9.
Catanzaro R, Calabrese F, Occhipinti S, Anzalone MG, Italia A, Milazzo M, Marotta F. Nonalcoholic fatty liver disease increases risk for gastroesophageal reflux symptoms. Digestive diseases and sciences. 2014 Aug;59:1939-45.
Houghton-Rahrig LD, Schutte DL, von Eye A, Fenton JI, Given BA, Hord NG. Exploration of a symptoms experience in people with obesity-related nonalcoholic fatty liver disease. Nursing outlook. 2013 Jul 1;61(4):242-51.
Newton JL, Pairman J, Wilton K, Jones DE, Day C. Fatigue and autonomic dysfunction in non-alcoholic fatty liver disease. Clinical Autonomic Research. 2009 Dec;19:319-26.