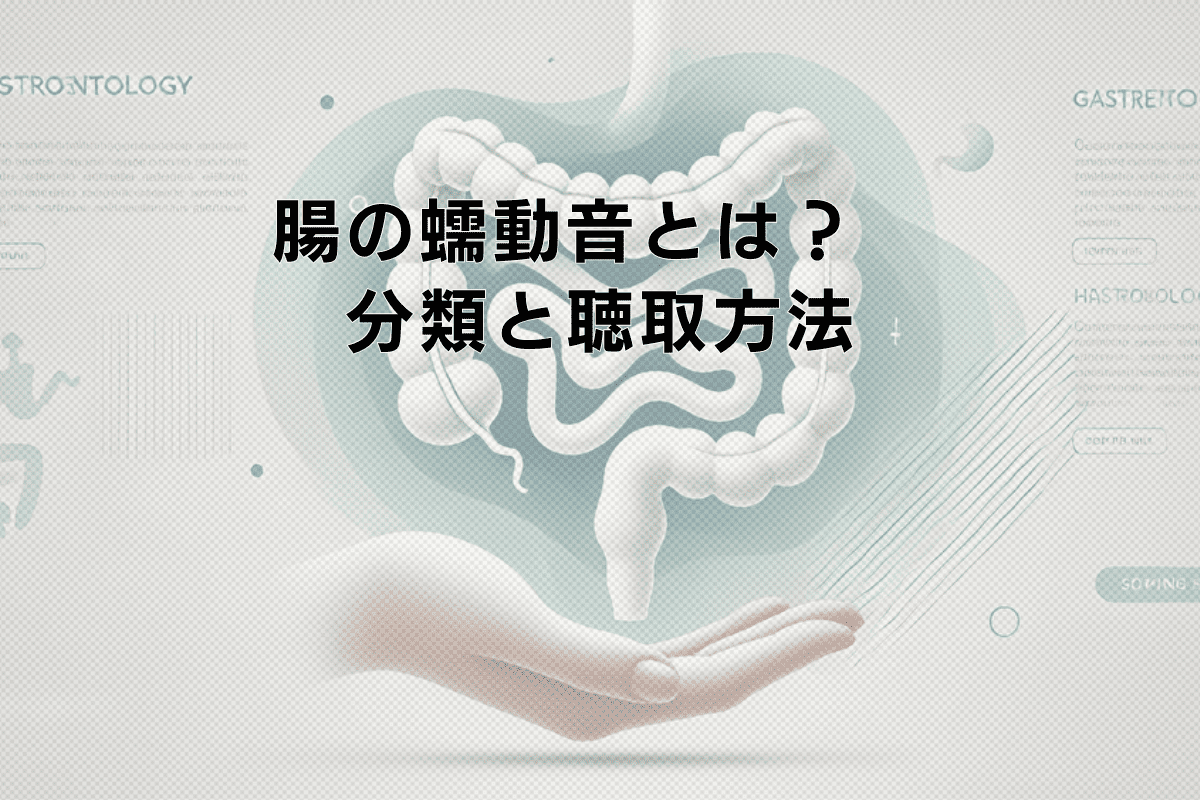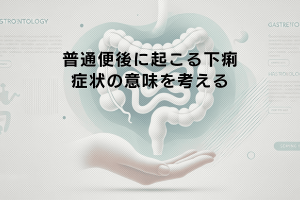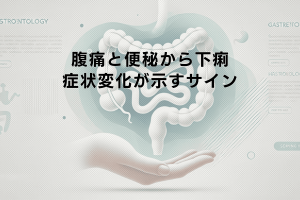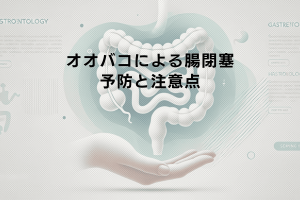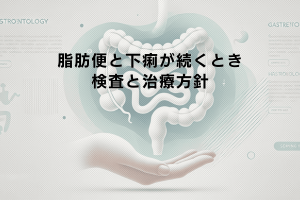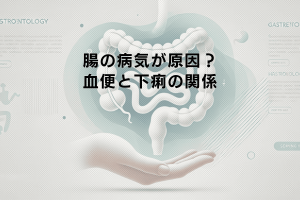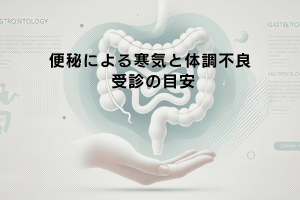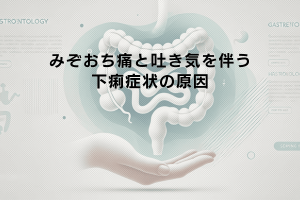腸蠕動音は、お腹の中で発生する音のことで、胃腸が食べ物を移動させたり、消化や吸収を進めたりする過程で生じます。
食後のゴロゴロとした音や空腹時の鳴りなど、日常で耳にしたことがある人は多いかもしれませんが、腸蠕動音の聴取と評価は医療現場において重要です。
異常な音の有無や音の強弱によって、腸の状態を把握できる場合があり、便秘や腸閉塞などのトラブルを早期に発見する手がかりになります。ここでは腸蠕動音の概要から分類、聴診方法や異常例まで詳しく解説します。
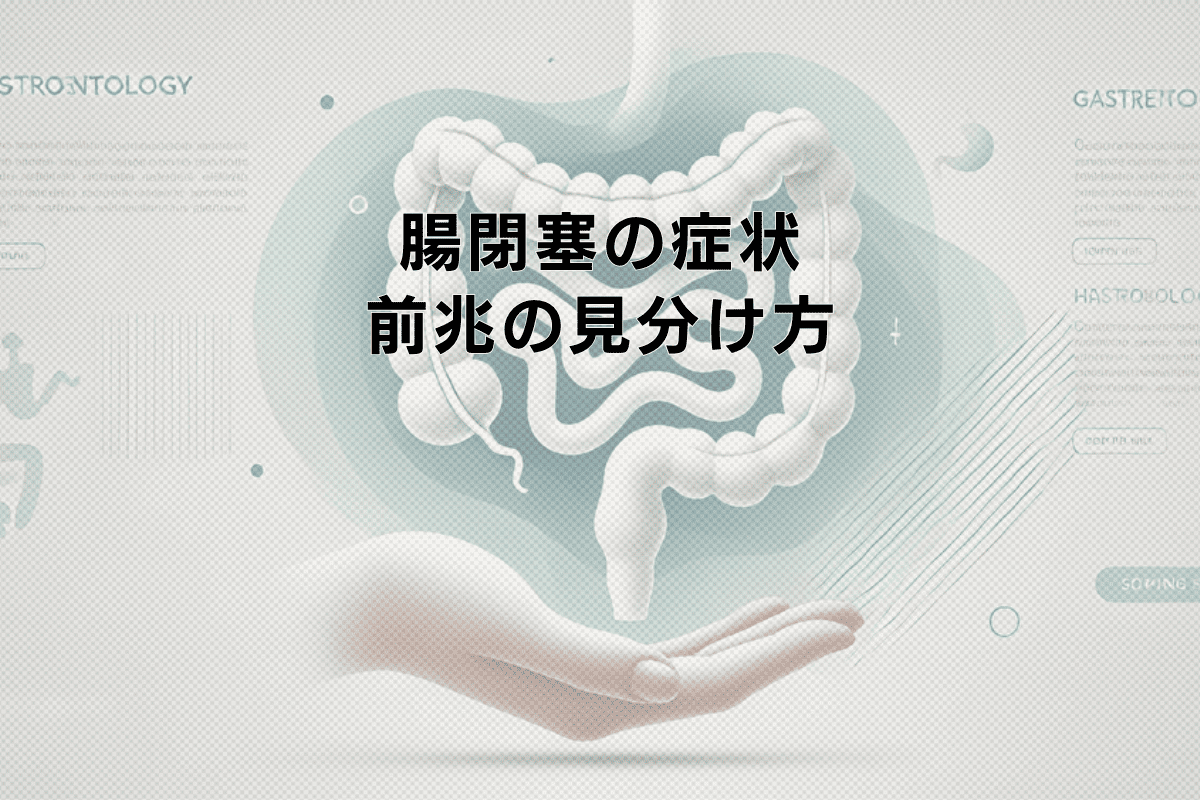
腸蠕動音の概要
腸蠕動音は、腸の動きに合わせて発生する音の総称です。腸が収縮と弛緩を繰り返し、食物やガスなどが腸管内を移動する過程で起こる振動を音としてとらえられ、私たちが「お腹が鳴る」と感じる現象の多くは、この腸蠕動音です。
腸蠕動音は健康状態や食後のタイミング、空腹時などによって変動し、腸内環境を知る手がかりとしても評価されています。
腸蠕動音はどのように生まれるのか
腸では、食物や消化液が混ざり合いながら大腸へ送られ、必要な栄養素や水分が吸収された後に便として排出され、この移動や混合を促す運動が蠕動(ぜんどう)運動で、周囲の組織やガスが振動することで生じる音です。
腸壁は筋繊維でできており、自律神経の働きによって規則的に動くため、意識しなくても一定リズムで音が出る場合があります。

腸の動きと関連する要因
| 要因 | 腸蠕動音への影響 | 具体例 |
|---|---|---|
| 食事のタイミング | 食後は腸の活動が高まり、音が大きくなる傾向 | 食後30分~1時間後にゴロゴロとした音を感じることが多い |
| 空腹時 | 胃腸が収縮しやすく、やや高い音が鳴ることも | お腹が空くと頻繁にグーッという音が出るケース |
| 自律神経のバランス | 交感神経優位では動きが抑制され音は減少 | ストレスが強いときにお腹の音が少なく感じる |
| 運動や姿勢 | 適度な運動で腸の活動が促され音が増える | ウォーキング中に腸が刺激され、音が大きくなる |
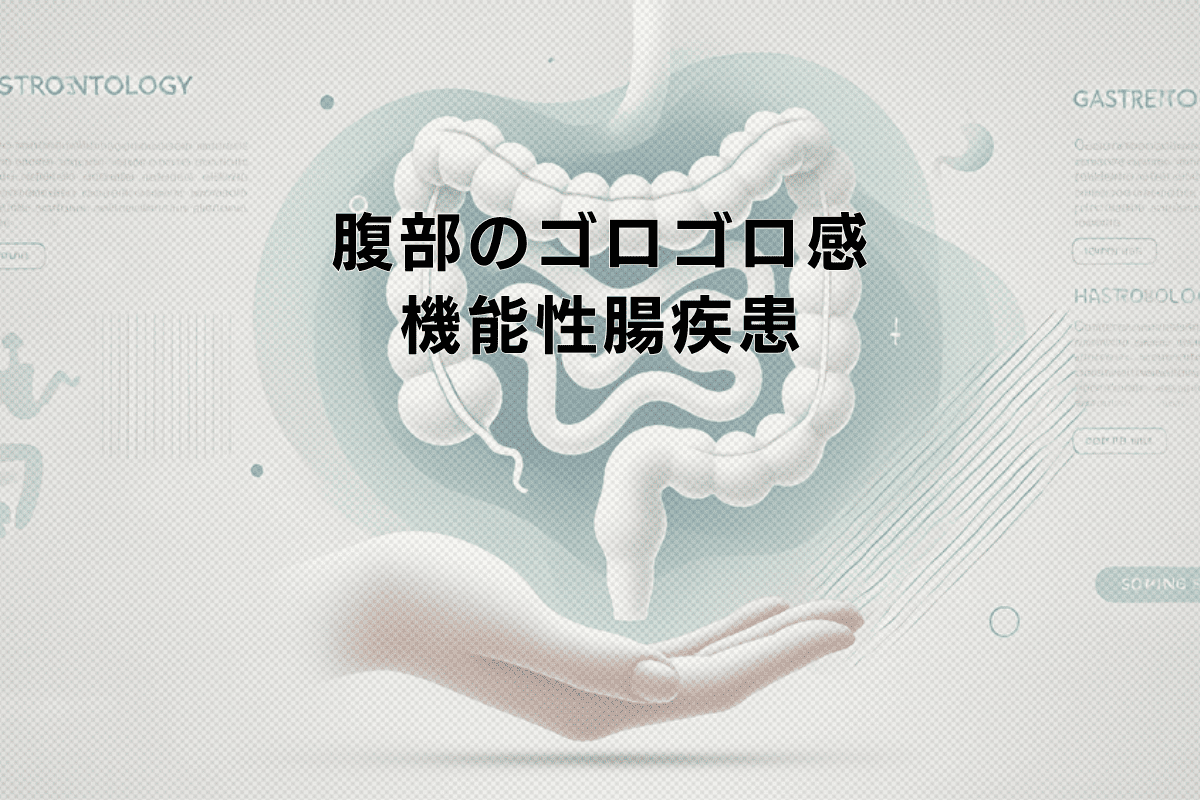
腸蠕動音を聞く意味
腸蠕動音を聴取することは医療機関や看護の現場で行われており、お腹の状態を判断する材料になります。腸の動きが正常かどうかを確認したり、便秘や腸閉塞などの病態が疑われる場合に診察やアセスメントの一環として聴かれたりします。
音が亢進しているのか、減弱しているのかによって異なる可能性を推測できるため、患者さんの健康管理に大きく貢献します。
- 便秘が続く場合に腸蠕動音を確認する
- 開腹手術後に腸の動きが再開しているかを評価する
- 腸閉塞が疑われる際に聴診して音の有無を判断する
- 下痢が続くときの腸の活動性を推測する
腸蠕動音と消化器科受診の必要性
食事や生活習慣に気をつけてもお腹の音に異常を感じる場合や、長期にわたる便秘や下痢、強い腹痛を伴うときには消化器科を受診することをおすすめします。
音の有無だけでなく、痛みや吐き気などの症状を総合的に判断することで、腸の疾患を早期に発見できる可能性が高まります。
腸蠕動音が生じる仕組み
腸蠕動音はなぜ鳴るのか、その仕組みを理解すると腸内活動や消化プロセスへの理解も深まります。腸管の構造や食物の移動経路とあわせて確認すると、毎日の食事や生活習慣が腸にどれほど影響を与えているのかが見えてきます。
腸管の基本構造
ヒトの消化管は口から始まり、食道、胃、小腸、大腸を経て肛門につながっています。腸蠕動音の発生源である小腸と大腸には筋層があり、食物を送り出す役割を持っています。
筋層が規則正しく収縮と弛緩を繰り返すことで、食物残渣やガスが移動し、そのときに生じる振動が腸蠕動音として聞こえます。
主な消化管の区分
| 部位 | 役割 | 音との関連性 |
|---|---|---|
| 胃 | 胃酸と消化酵素で食物を分解 | 胃の内容物が小腸へ移動する際にも音が出ることがある |
| 小腸 | 栄養吸収や分解を進める | 腸蠕動音の中心的な発生部位 |
| 大腸 | 水分吸収や便の形成を行う | 便が移動するときに独特のゴロゴロとした音が出やすい |
| 肛門 | 便を排出する通路 | 排便時にはガスが動く音が聞こえることがある |
蠕動運動と分節運動
腸の運動には、腸内容物を奥へ押し進める蠕動運動と、小刻みに分割して混合を行う分節運動があり、蠕動運動は長い距離を移動させるイメージで、大腸では緩やかな波となって進むのに対し、小腸では比較的速い波が走る場合があります。
分節運動は腸管内の内容物を満遍なく混合しながら吸収を促進するための動きです。これらが組み合わさって腸蠕動音が発生します。
- 蠕動運動:長い距離の移動
- 分節運動:内容物の混合と吸収促進
- 自律神経の働き:交感神経と副交感神経がバランスを保つ
自律神経とのかかわり
腸の運動は自律神経によって制御されており、副交感神経が優位のときには腸の動きが活発になり、交感神経が優位のときには腸の動きが抑制される傾向があります。
緊張状態が続くと腸蠕動音が少なくなり、リラックスしているときに鳴りやすいのは、自律神経が大きく影響している証拠です。
自律神経と腸蠕動音
- 副交感神経優位:音が増加しやすい
- 交感神経優位:音が減少することが多い
- ストレス:腸の働きを抑え、便秘を招きやすい
- 休息:腸が動きやすくなる
ガスと腸液が関与する理由
腸内には消化液やさまざまな細菌があり、食物残渣を分解するときにガスが発生し、ガスが腸管内を移動するときにも音が鳴りやすいです。特に発酵が盛んな小腸や大腸の区域では、大きな音が聞こえる場合があります。
ガスが過剰にたまるとお腹の張りや腹部膨満感につながり、腸蠕動音も通常より強くなるか、逆に詰まるような音が聞こえることがあるため、注意が必要です。
腸内ガスが増える原因
| 原因 | 具体例 | 音への影響 |
|---|---|---|
| 食物繊維の過剰摂取 | 大量の野菜や豆類を一度にとり過ぎると腸内発酵が強まる | ガスが多くなり音が亢進することがある |
| 腸内細菌のバランスの乱れ | 悪玉菌が増加し発酵が進みすぎる | お腹の張りや下痢・便秘が生じる |
| 飲み込みすぎた空気 | 早食いや炭酸飲料の摂取が続く | ガスが腹部に滞留して腸蠕動音が響きやすくなる |
| ストレスや過度の緊張 | 呼吸が浅くなり空気を飲み込む量が増加することがある | 交感神経優位で腸の動きは抑制も、ガスは溜まる |
腸蠕動音の分類
腸蠕動音には、大きく分けて正常・亢進・減弱・消失などの分類があり、どの分類に当てはまるかによって、腸内環境の状態や潜在的なリスクを推察できます。
診察時には看護師や医師が聴診器を使って音の強さや頻度をチェックし、総合的に判断します。
正常な腸蠕動音とは
正常な腸蠕動音は、規則的で間欠的に「グルグル」「ゴロゴロ」といった音が聞こえ、5~30回/分程度のリズムを保つことが多いです。
個人差はありますが、空腹時にやや高く響く音、食後に活発になる音が聞こえる場合は、おおむね正常と捉えられます。音の有無だけでなく、音の大きさやリズムも含めて総合的に判断することが大切です。
正常な腸蠕動音の特徴
- 5~30回/分程度で規則的に聞こえる
- 空腹時にはやや高めの音になる傾向
- 食後は活発なゴロゴロ音
- 両腹部や周囲でバランスよく聴こえる
亢進した腸蠕動音
亢進とは、腸の動きが通常より活発になっている状態で、小腸や大腸が激しく蠕動していると、ゴロゴロ、キュルキュル、あるいは長く続く響きが聴こえ、頻度も30回/分以上になることがあります。
下痢や腸炎などによって腸が刺激されている場合や、ストレスで自律神経が乱れているときにも起こりやすいです。
腸蠕動音が亢進しやすい要因
| 要因 | 具体例 | 見られる症状 |
|---|---|---|
| 下痢 | 細菌性腸炎やウイルス性腸炎など | 頻繁な排便、腹痛、脱水のリスク |
| 刺激物の多い食事 | 辛い物やカフェイン、アルコールの摂取過多 | 胃腸の動きが過敏になり音が大きくなる |
| 神経性の腸過敏 | 過敏性腸症候群(IBS)など | 便秘と下痢の繰り返しや腹痛 |
| 極度の緊張やストレス | 自律神経のバランスが乱れる | 一時的に音が増えたり変化が激しくなる |
減弱した腸蠕動音
腸の動きが低下しているときには、腸蠕動音が減弱し、1分間に5回未満のゆったりとしたリズムになったり、ほとんど聴こえなくなったりすることがあり、便秘が続いていたり、術後で腸管機能が回復していなかったりする際にみられます。
特に手術後の腸閉塞を防ぐためには、聴取方法による評価が大切です。
消失した腸蠕動音
消失は、腸蠕動音がまったく聴こえない状態で、少なくとも5分間は聴取を続けても全く音を確認できない場合に「消失」と判断することが多いです。
この場合、術後の腸麻痺や重篤な腸閉塞などを疑います。緊急性の高い病態が潜んでいる可能性があるため、医療現場では即座の対処や検査が行われます。
腸蠕動音の主な分類と特徴
| 分類 | 主な特徴 |
|---|---|
| 正常 | 5~30回/分程度で連続的に聴こえ、食後や空腹時に強弱が見られる |
| 亢進 | 30回/分以上で大きなゴロゴロ音やキュルキュル音が目立つ |
| 減弱 | 5回/分未満で音が小さく、まばらにしか聞こえない |
| 消失 | 5分以上聴取しても音が全く聴こえない |
| 補足として | 人によっては1分あたりの回数よりも音の質感や出現間隔が評価の対象になることがある |
腸蠕動音の聴取方法
腸蠕動音を正しく把握するためには、聴診器を使った聴取方法やチェックのコツを知ることが大切です。
医師や看護師が病院で行うような手法を、患者さん自身がすべて行う必要はありませんが、基礎的な流れを理解することで検診や診療の際の不安軽減にもつながります。
聴診の基本ステップ
聴診は通常、ベッドに仰臥位に横になった状態で行います。衣服による雑音を避けるため、腹部を出して落ち着いた環境で始めるのが一般的です。
聴診器を腹部4区(右上腹部、左上腹部、右下腹部、左下腹部)にあて、それぞれ数十秒から1分以上かけて音を聞き取ります。腸蠕動音は一定のリズムを刻むことが多いので、合計5分程度かけて確認します。
腸蠕動音聴取の流れ
- 患者さんにリラックスした姿勢をとってもらう
- 衣服やシーツがこすれる音を減らすよう配慮する
- 聴診器を4区画に順番にあて、数十秒~1分耳を澄ます
- 音の有無、強弱、頻度をメモに取りながら記録する
- 音が確認できない場合は時間を延ばして再チェックする
ベル型と膜型の使い分け
聴診器にはベル型と膜型があり、それぞれ拾いやすい音の種類が違い、腸蠕動音は比較的低周波音に分類され、ベル型のほうが聞き取りやすいといわれています。
ただし、聴診器の構造や個人の聴取しやすさによって膜型で聞き取る場合もあるため、医療者が使いやすい方法で行うことが多いです。
聴診器のベル型と膜型
| 種類 | 得意とする音の範囲 | 腸蠕動音への適性 |
|---|---|---|
| ベル型 | 低周波音(心臓の一部音や血管雑音など) | 低音成分を含む腸蠕動音も拾いやすい傾向 |
| 膜型 | 高周波音(肺音や一部の心音、クリック音など) | 腸蠕動音も聴けるが低音を拾いにくいことがある |
術後や特定の状態での聴取の注意点
開腹手術や腹部手術後は、腸の動きが一時的に低下しやすくなります。腸蠕動音の減弱や消失が観察され、術後数日経過してもまったく音が戻らない場合は腸管麻痺や腸閉塞などの合併症が疑われるため、医師や看護師が慎重に経過を追います。
病棟では音の回復状況を1日数回チェックして、排ガスや排便があるかどうかとも併せて判断します。
- 術後数日間は減弱傾向が続くことがある
- ストーマ造設後も腸蠕動音を聴取して状態を把握する
- 消失が続くときはイレウス(腸閉塞)等を検討
聴診で得られる情報をどう活用するか
聴取結果は、医師の診断や看護師のケア方針を考える際の指標になり、便秘や下痢など消化機能の不調がある場合は食事の内容を調整したり、水分摂取量を増やしたりするなどのサポートが検討されます。
腸蠕動音の評価は、患者さんの身体を総合的に理解するうえで重要です。
聴取結果の活用例
- 便秘患者の下剤投与や排便ケアのタイミングを判断する
- 腸閉塞リスクがある患者への早期検査や画像診断を提案
- 食事形態を変更する際の目安(軟食から普通食への移行など)
- 医療チーム内で評価を共有して、状態悪化を防ぐ
腸蠕動音の異常と考えられる症状
腸蠕動音の異常は、便秘や腸閉塞、過敏性腸症候群などの消化器トラブルと関連することが多いです。
異常音としては、極端に大きい音が絶え間なく続く場合や、音がほとんど聴こえなくなる消失などが挙げられ、いずれも医療的なケアや相談を要する可能性があります。
便秘による腸蠕動音の変化
便秘が長引くと、腸管内に溜まった便が蠕動運動を阻害し、音が減弱することがあります。食物繊維や水分摂取不足、ストレスなどが便秘の原因になることが多いため、ライフスタイルの見直しも重要です。
また、慢性化すると腸内環境が悪化し、悪玉菌が増えることでガスが発生し、独特の鳴り方をするケースもあります。
便秘の主な原因
| 原因 | 概要 | 腸蠕動音への影響 |
|---|---|---|
| 食物繊維不足 | 野菜や果物をあまりとらない食生活 | 腸内容物が少なく音が減弱する |
| 水分不足 | 便が硬くなり排出されにくくなる | 腸の動きが鈍り音が減る |
| 運動不足 | 腹筋や腸への刺激が少なくなる | 音を生む運動が衰え便が滞留する |
| ストレスや環境の変化 | 自律神経の乱れで腸の活動が抑制される | 音が極端に小さくなる |
腸閉塞(イレウス)の疑い
腸管が物理的あるいは機能的に塞がれ、食物やガスが通過できなくなる状態が腸閉塞です。初期段階では強いゴロゴロ音が聴こえることもありますが、悪化するとまったく音が聞こえなくなるケースがあります。
吐き気や腹痛、腹部膨満感などの症状が併発することが多いため、早めの受診と検査が必要です。
過敏性腸症候群との関連
過敏性腸症候群(IBS)では、ストレスや食事内容などで下痢や便秘を繰り返す場合が多く、腸蠕動音も亢進と減弱が交互に現れることがあり、一定のリズムを保たず不規則になる傾向がみられます。
下痢症状のときは音が大きく、便秘症状のときは音が少なくなるなど、日によって変動が大きいことが特徴です。
IBSの主なタイプ
- 便秘型:排便回数が少なく、硬い便が主体
- 下痢型:水様便や軟便、腹痛が生じやすい
- 混合型:便秘と下痢が交互に起きる
- 分類に関わらずストレスとの関係が深い
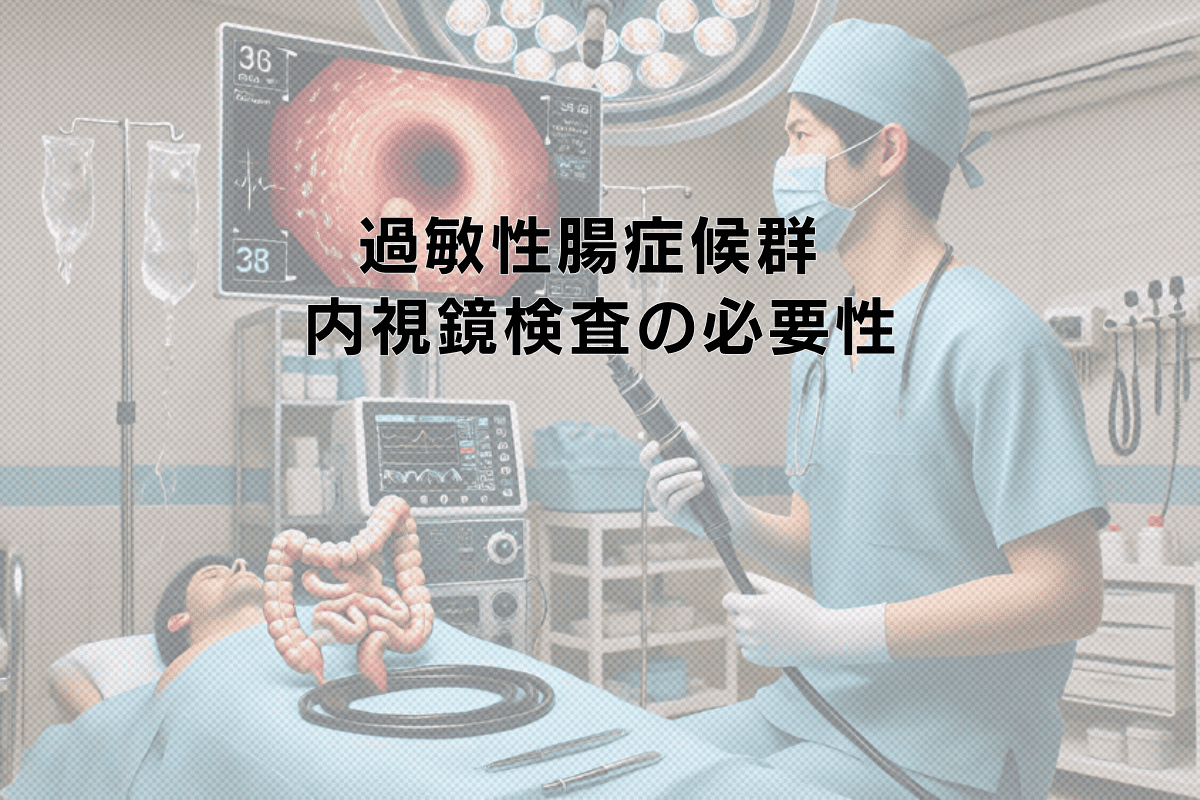
腸炎や感染症による腸蠕動音の変化
細菌やウイルスによる腸炎にかかると、炎症が腸壁を刺激して蠕動音が亢進することがあり、激しい下痢や腹痛、嘔吐なども併発することが多く、脱水に陥る危険性があるため、早期の対応が必要です。
感染症の場合は保菌者との接触、食事由来の感染を防ぐため、手洗いや食材管理を徹底します。
主な腸炎の原因
| 原因 | 具体例 | 音への影響 |
|---|---|---|
| 細菌感染 | サルモネラ、腸炎ビブリオ、カンピロバクターなど | 腸を刺激し音が亢進して下痢や激痛を伴う |
| ウイルス感染 | ノロウイルス、ロタウイルスなど | 集団発生しやすく、嘔吐や下痢がひどい時は音が過度に活発 |
| 毒素型食中毒 | 黄色ブドウ球菌などの毒素 | 急な発症とともに腸蠕動音が激しくなることが多い |
腸蠕動音に注目する意義と受診のすすめ
腸蠕動音は、消化器の状態を知るための身近な手がかりで、お腹の不調が続くときや、音の強さや頻度に極端な変化があると感じたときは、早めに専門家の意見を聞くと安心です。
医療機関では、問診や触診、聴診、画像検査など総合的に調べて原因を特定し、適切なケアや治療を提供します。

クリニック受診を検討すべきタイミング
軽度の便秘や下痢は一時的な生活習慣の乱れで起こることもありますが、症状が長期間続く場合や腹痛や嘔吐を伴う場合は放置せず受診が望まれます。
腸蠕動音の異常が長引いていると、重大な消化器疾患が隠れている可能性も否定できません。腸閉塞や大腸がん、炎症性腸疾患などは早期発見が治療効果に影響するため、医師への相談を優先してください。

受診を考える主な症状
- 便秘や下痢が2週間以上続く
- 音の変化に加えて強い腹痛や血便がある
- 嘔吐や発熱などの全身症状を伴う
- 排便時や排ガスが長く止まっている
看護師や医療者への相談の仕方
看護師や医師に腸蠕動音の異常を感じていることを伝える際は、いつから音に変化を感じ始めたか、どのようなときに症状が悪化するかなど具体的に説明するとスムーズです。
医療者はこうした情報をもとに消化器の状態をアセスメントし、追加の検査を行うかどうか判断します。
腸の健康を保つための工夫
毎日の生活習慣を見直して腸をケアすることは、蠕動運動を安定させ、腸蠕動音の異常を予防するうえで大切です。食物繊維や発酵食品をバランスよく摂取し、水分補給や適度な運動を心がけると、腸内環境を良好に保ちやすくなります。

腸の健康に配慮した生活習慣
| 項目 | 実践の例 |
|---|---|
| 食事 | 野菜、果物、海藻、発酵食品をバランスよく摂り、刺激物は控えめにする |
| 水分補給 | 1日1.5~2.0リットルの水分を目安に、こまめに摂る |
| 運動 | ウォーキングや軽いストレッチで腸への刺激を促す |
| ストレス対策 | 趣味や休息の時間を設け、自律神経のバランスを整える |
次に読むことをお勧めする記事
【腸閉塞の原因と治療法|早期発見と対処の重要性】
腸蠕動音の基本を押さえたら、次は実際の腸閉塞の原因と治療について知っておくと安心です。腸蠕動音の消失と関連する重要な病態について、より具体的に理解できる内容です。
【胃カメラで分かる症状 検査の流れ】
腸蠕動音について理解が深まると、関連する上部消化管の検査についても知りたくなる方が多いようです。消化器全体の健康管理という観点から、新たな発見があるかもしれません。
参考文献
Baid H. A critical review of auscultating bowel sounds. British journal of nursing. 2009 Oct 8;18(18):1125-9.
Gu Y, Lim HJ, Moser MA. How useful are bowel sounds in assessing the abdomen?. Digestive surgery. 2010 Nov 1;27(5):422-6.
Felder S, Margel D, Murrell Z, Fleshner P. Usefulness of bowel sound auscultation: a prospective evaluation. Journal of surgical education. 2014 Sep 1;71(5):768-73.
Zaborski D, Halczak M, Grzesiak W, Modrzejewski A. Recording and analysis of bowel sounds. Euroasian journal of hepato-gastroenterology. 2016 Jul 9;5(2):67.
Breum BM, Rud B, Kirkegaard T, Nordentoft T. Accuracy of abdominal auscultation for bowel obstruction. World Journal of Gastroenterology: WJG. 2015 Sep 9;21(34):10018.
Read TE, Brozovich M, Andujar JE, Ricciardi R, Caushaj PF. Bowel sounds are not associated with flatus, bowel movement, or tolerance of oral intake in patients after major abdominal surgery. Diseases of the Colon & Rectum. 2017 Jun 1;60(6):608-13.
Milton GW. Normal bowel sounds. Medical Journal of Australia. 1958 Oct;2(15):490-3.
Inderjeeth AJ, Webberley KM, Muir J, Marshall BJ. The potential of computerised analysis of bowel sounds for diagnosis of gastrointestinal conditions: A systematic review. Systematic reviews. 2018 Dec;7:1-8.
Ching SS, Tan YK. Spectral analysis of bowel sounds in intestinal obstruction using an electronic stethoscope. World Journal of Gastroenterology: WJG. 2012 Sep 9;18(33):4585.
Drake A, Franklin N, Schrock JW, Jones RA. Auscultation of bowel sounds and ultrasound of peristalsis are neither compartmentalized nor correlated. Cureus. 2021 May;13(5).