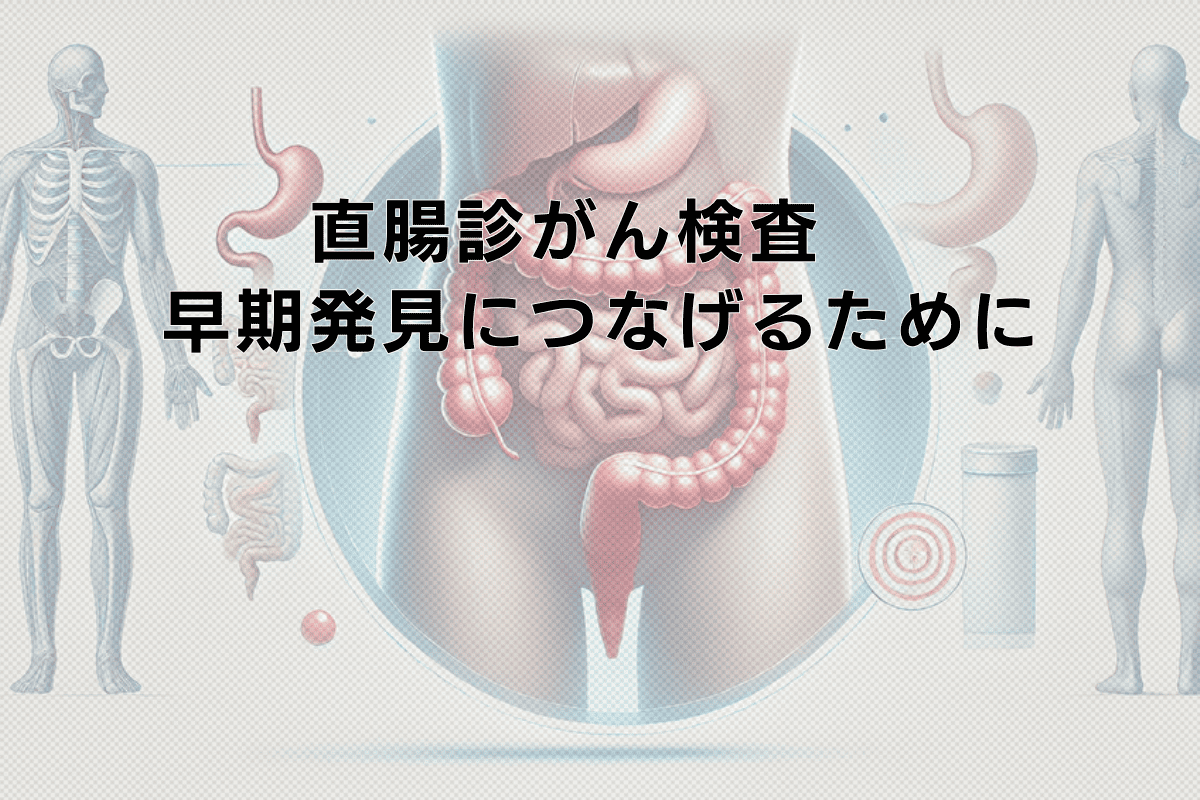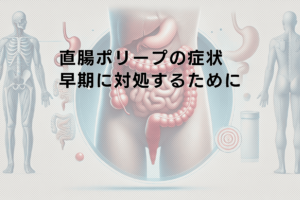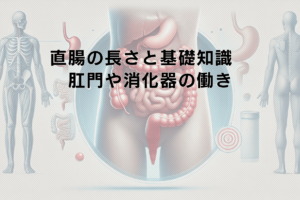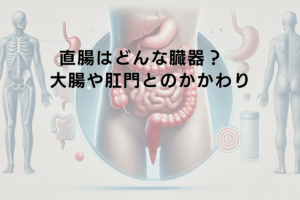直腸診は、医師が肛門から指を挿入して直腸や周囲の状態を確認する検査方法で、消化器の病気、大腸がんや直腸がんなどが疑われる場合に限らず、肛門周辺の異常を調べるうえでも行われることがあります。
肛門から指を入れる検査と聞くと抵抗感がある方もいるかもしれませんが、早期のがん発見につながる可能性があり、診断や治療の方針を定めるための大切なステップです。
この記事では、直腸診とあわせて行われる検査、医師の視点からみた意義、そして診断や治療の流れについて、できるだけ詳しく解説します。
直腸診とは何か
病気やがんを早期に発見したり、消化器系の異常を見つけたりするために行う検査のうち、医師が直接肛門から指を入れて直腸内部の様子を確認するものが直腸診です。
消化器内科をはじめ、前立腺の検診時にも行われることがあり、肛門や直腸に関わる病気を把握できます。
目的と特徴
医師が指を挿入して直腸壁や周辺組織に触れ、がんや痔核などの腫瘤、炎症、硬さの異常などを触診で確かめることで、視覚的な観察だけではわからない質感を把握できる点が特徴です。大腸がんや直腸がんの早期発見にも結びつく可能性があります。
どんな病気がわかるのか
直腸診は、がんに限らず以下のような異常にもアプローチします。
- 直腸がんや大腸がんなどの悪性腫瘍
- 肛門の内側にできた痔核(内痔核)
- 直腸壁の裂傷や潰瘍
- 前立腺がん(男性の場合、前立腺の硬さを評価)
- その他の炎症性疾患や腸管の変形
痛みや抵抗感はあるか
個人差があるものの、医師がゆっくりと指を挿入するため、大きな痛みはないことが多いですが、肛門周辺が敏感な方や炎症のある場合は痛みや不快感を強く感じることがあります。
リラックスを心がけ、医師に違和感があれば遠慮なく伝えることが大切です。
他の検査との組み合わせ
直腸診だけでは大腸がん全体を発見しきれない可能性があるため、状況に応じて大腸内視鏡検査や便潜血検査、CTやMRIなどの画像検査と組み合わせて総合的に診断します。
直腸診の役割
| 視点 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 肛門~直腸周辺の病変を触診で確かめる |
| 対象となる病気 | 大腸がん、直腸がん、痔核、炎症、前立腺がんなど |
| メリット | 視覚検査ではわからないしこりや硬さを触知できる |
| デメリット | 肛門からの挿入に抵抗感がある、全大腸を網羅できない |
| 必要性 | 症状や疑いのある病変を初期段階で把握する手段の一つ |
直腸診と大腸がん検査の関係
直腸診は大腸がんや直腸がんの診断として完全ではありませんが、一部の異常を見つけるきっかけになることがあります。検診やがん診断を受ける際には、直腸診だけに頼らず、内視鏡検査なども検討する必要があります。

大腸がん・直腸がんの発生部位
大腸がんは結腸と直腸に分けられ、直腸部分のがんを直腸がんと呼びます。肛門に近い部分のがんであれば指で触れてしこりを感じる可能性がありますが、もう少し上部にあると直腸診だけでは見落とされることがあります。
直腸診の検診での位置づけ
かつては大腸がん検診の一環として直腸診が行われる場合がありましたが、直腸診のみで早期発見できるがんは限られるため、多くの医療機関では、便潜血検査や大腸内視鏡検査が推奨されるようになってきました。
直腸診の主な役割は、肛門や直腸付近の病変を補足的に確認する程度と考えられています。
直腸診でわかる病気とわからない病気
肛門近くや直腸下部にあるがんであれば、指先で硬さや隆起を感じて発見につながる場合があるものの、結腸や直腸上部などから発生する大腸がんは発見しづらいです。したがって、直腸診で異常がなくてもがんの可能性がゼロとは言えません。
大腸内視鏡検査との組み合わせ
大腸がんを総合的に調べるなら、大腸内視鏡検査が重要で、カメラを腸内に挿入して、腸の内面を直接観察します。
直腸診と比べてカバー範囲が広く、ポリープや小さながんを発見しやいので、便潜血検査や内視鏡検査を正しいタイミングで受けると、大腸がんの早期発見・治療につながりやすいです。
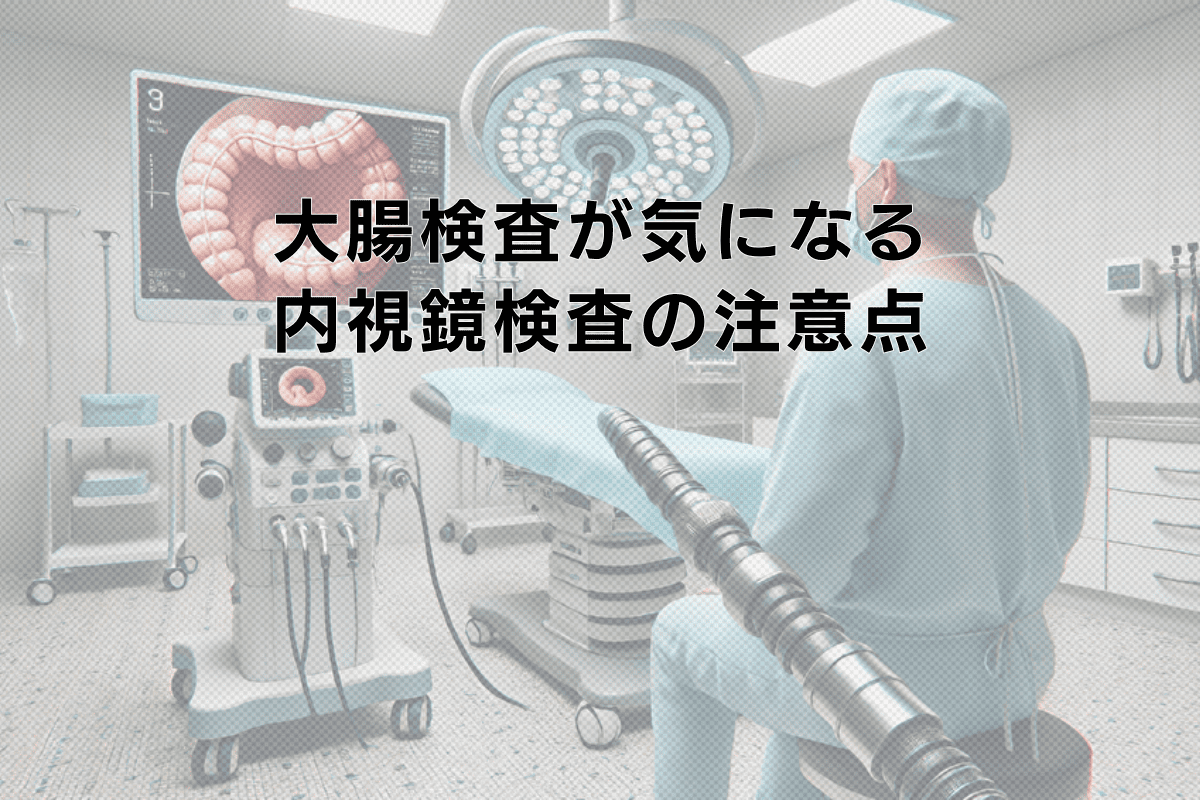
大腸がんの検査方法比較
| 検査方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 直腸診 | 指で触診する | 肛門・直腸近くのしこりや硬さを把握可能 | 検出範囲が限定的 |
| 便潜血検査 | 便中の血液反応を検査 | 手軽で費用が比較的安く、集団検診にも向く | 小さな出血がなければ陰性になる可能性 |
| 大腸内視鏡検査 | カメラで大腸内を直接観察 | 病変があればその場で組織採取や切除が可能 | 下剤や検査時間などの負担が大きい |
| 注腸X線検査 | 造影剤とX線を使って大腸の形を撮影 | 比較的負担が少なく広範囲を映し出せる | 微細な病変や平坦型ポリープは見落としやすい |
| CT/MRI検査 | 画像で腸の形態や周辺組織を把握 | 他の臓器の状態も同時に確認しやすい | 小さい病変の発見精度は内視鏡に劣ることも |
直腸診の具体的な方法
直腸診は、内視鏡検査やCTなどとは手順が異なり、指を使って行うシンプルな検査方法で、医師が行う手順や注意点を理解しておくと、不安を軽減できます。
検査の流れ
- 患者は横向きに寝たり、膝を抱える姿勢になったりして肛門を医師が診やすい体位を取る
- 医師が手袋を装着し、潤滑剤を指に塗り、ゆっくりと肛門から直腸内へ挿入
- 直腸壁の硬さや腫瘤の有無、痛みの有無などを確認
- 必要に応じて肛門周辺も視診、触診する
直腸診のステップ
| 項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 体位の取り方 | 左側臥位や膝胸位(膝を抱える)など、肛門が観察しやすい姿勢 |
| 手袋と潤滑剤 | 感染防止と痛み軽減のため必須 |
| 指の挿入 | 抵抗がある場合はゆっくり進める |
| 触診 | 前立腺、直腸粘膜、肛門付近の状態を調べる |
よくある不安と対処
- 痛みへの恐れ
医師が潤滑剤を用い、慎重に挿入するため過度の痛みは少ない。もし痛みが強い場合は遠慮なく伝える - プライバシー
カーテンや個室で実施し、露出を最小限に抑える - 恥ずかしさ
医療上必要な行為であり、慣れた医師は迅速に行うので短時間で終わる
検査前の準備
通常、直腸診だけでは下剤を飲むなどの大掛かりな準備は要しません。ただし、内視鏡検査などを同時に行う場合は、腸管を空にするために下剤を使用したり、検査前日から消化にやさしい食事にしたりすることがあります。
検査時間の目安
個人差はありますが、直腸診自体は数分程度で終わることが多く、検査後に痛みや出血がないか簡単に確認して終了します。
直腸診が有効な病気・がんとは
直腸診で見つけられる病変は、肛門や直腸の下部に限られますが、限定的な範囲でも特定のがんや病気を早めに発見・治療につなげる場合があります。
大腸がんの一部
肛門から近い位置に発生した直腸がんは、進行度により指先で感じる可能性があります。ただし、より高位の直腸がんや結腸癌には対応しづらく、あくまでも補助的な意義が中心です。
肛門付近の病変
肛門ポリープや痔核のほか、肛門周辺の腫瘍や炎症を把握でき、直接の視診よりさらに奥の粘膜を触れることで、表面の変化を察知する助けになります。
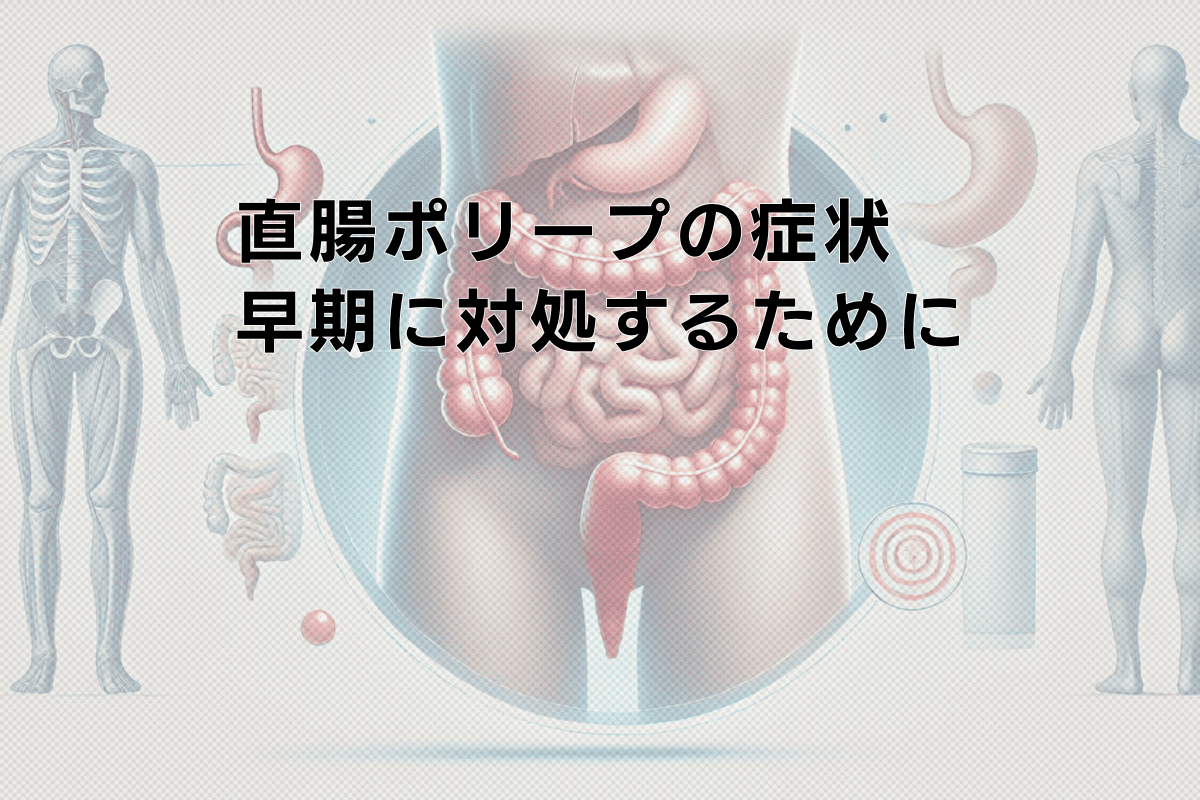
肛門周辺で確認される代表的病変
| 病変名 | 特徴 | 直腸診での検知度 |
|---|---|---|
| 内痔核 | 直腸側にできる痔核で、出血しやすい | 指で腫れや柔らかさを触れる |
| 肛門ポリープ | 肛門付近の粘膜が盛り上がった良性腫瘍 | 小さいものは見落としやすい |
| 肛門周囲膿瘍 | 感染による膿のたまりで、痛みが強い | 炎症や腫れを指で感じる |
| 腫瘍 | 良性~悪性まで幅広い | 位置や大きさにより発見可 |
前立腺がんとの関わり
男性においては、前立腺の裏側を直腸越しに触れるため、前立腺がんを疑うきっかけになることがあります。前立腺がんのスクリーニングではPSA検査(血液検査)と組み合わせることが多いですが、直腸診も腫大や硬化を察知する手段です。
その他の腸疾患
クローン病や潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患で直腸付近に潰瘍があると、触診で異常を感じる場合があります。詳しい診断には内視鏡検査が欠かせませんが、初期評価として有用です。

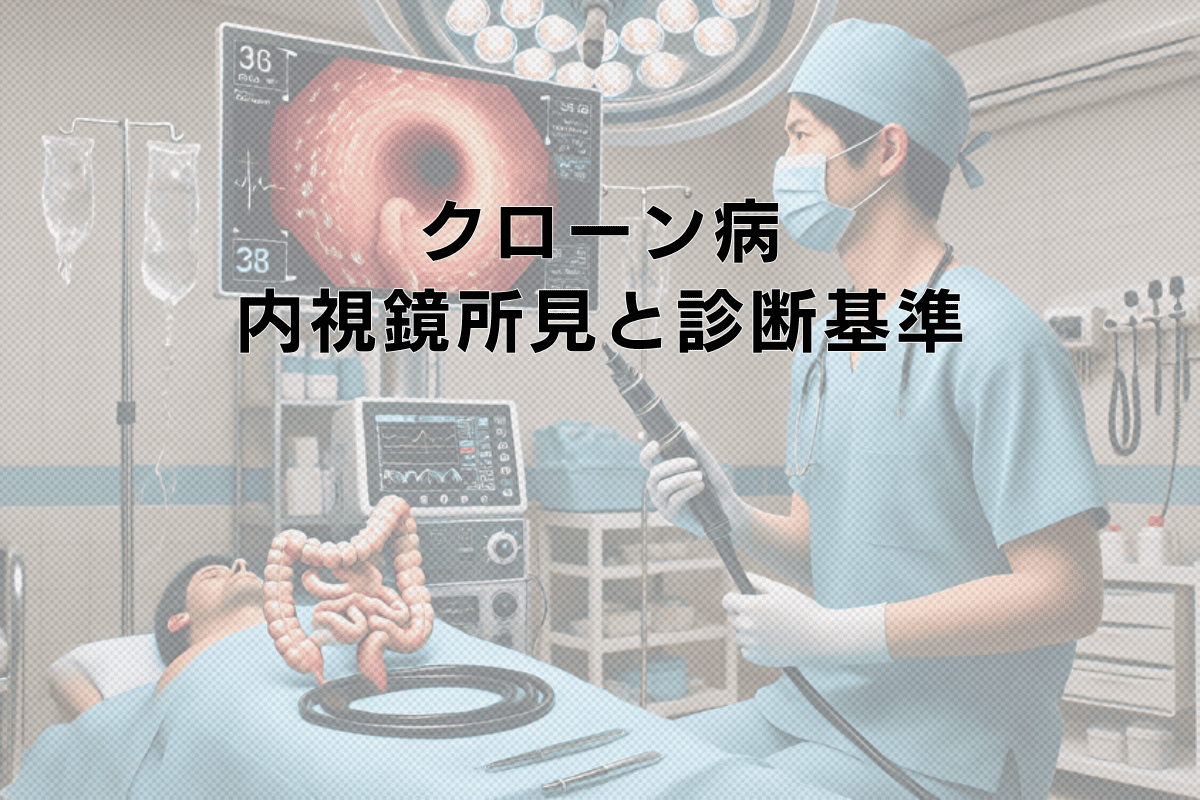
直腸診の実施後に行う診断や治療
直腸診で異常の可能性が指摘された場合、その後のステップとしてさらに詳しい検査や治療が必要です。
異常が疑われた場合のフロー
- 画像検査や内視鏡検査の追加
直腸診でしこりや硬さを感じた場合、大腸内視鏡やCT/MRIなどの精密検査へ移行する - 生検による組織診断
腫瘍らしき部位がみつかれば、生検で組織を採取して良性か悪性かを診断 - 治療方法の検討
悪性が確定した場合は手術や内視鏡治療、放射線や抗がん剤など患者の状態に応じて選ぶ
直腸診後の対応
| 結果・所見 | 追加検査 | 主な治療プラン |
|---|---|---|
| 肛門周囲の腫れ | 血液検査、超音波検査 | 痔核治療、抗生物質、外科的処置など |
| 直腸下部のしこり | 大腸内視鏡、CT/MRI、生検 | 外科手術、内視鏡治療、放射線や化学療法 |
| 前立腺が肥大 | PSA検査、前立腺生検 | 内服薬、放射線治療、前立腺摘除手術など |
| 特に異常なし | 定期検診や注意深い経過観察 | 定期的な大腸検診や生活習慣の改善 |
大腸内視鏡検査との連携
直腸診後に「さらなる検査が必要」と判断された場合、大腸内視鏡検査を行い、大腸全体を観察することが一般的です。ポリープの切除や組織の生検も同時に行えるため、早期診断と早期治療の両方にメリットがあります。
血液検査や便潜血検査との併用
がんや炎症の可能性を高める指標が血液検査で見つかることもあり、また、直腸診だけでなく便潜血検査で陽性が出た場合には、ほぼ確実に大腸内視鏡などの精密検査が推奨されます。
手術や治療の流れ
もし直腸がんなどが疑われる場合、医師は腫瘍の位置や大きさ、進行度を総合評価し、結果に応じて手術の範囲や方法(腹腔鏡手術、開腹手術など)、放射線や化学療法を組み合わせるかどうかが決まります。
早期発見なら内視鏡的切除だけで済む可能性があります。
直腸診を受ける前に準備しておくこと
直腸診そのものは比較的簡単な検査ですが、患者側が知っておくと安心できるポイントがあります。実際に受診する前にチェックしておきましょう。
自分の症状や履歴を整理する
医師に伝えるために、以下の項目をあらかじめまとめておくと、スムーズな診療ができます。
- 下痢や便秘などの便通の変化
- 便に血が混じる、黒っぽい便などの症状
- 腹痛や残便感、肛門痛
- 家族や親戚に大腸がん・直腸がんの既往歴
- 前立腺がんや他のがんにかかったことがあるか
どのような服装で行くか
直腸診は下半身を部分的に露出する必要があるため、着脱のしやすい服装で行くのがおすすめです。検査着を用意している医療機関もありますが、必ずしも全院で用意しているわけではありません。
チェックリスト(受診前に確認したい項目)
- 下着やズボンがゆったりしているか
- 痛み止めなどの薬を服用している場合は、医師に報告したか
- 月経中の場合は、できれば日程をずらすか相談したか
- 持病やアレルギーのある薬を把握しているか
同時に行う検査の有無
便潜血検査や血液検査、大腸内視鏡検査を同じタイミングで行う場合があるので、事前に医療機関からの案内を確認してください。特に大腸内視鏡検査を同日実施する場合は、前日の食事制限や当日の下剤服用など追加の準備が求められます。

心理的な準備
直腸診に対する心理的なハードルは少なくありませんが、次のような考え方で臨むと安心感を得やすいです。
- 早期発見につながる大切な検査
- 医師にとってはよく行う一般的な診察であり、恥ずかしがる必要はない
- 検査時間は短い
- 痛みがあれば遠慮なく伝える
直腸診後のフォローアップと日常生活
直腸診が終わった後、異常がなくても定期的な検診や健康管理は続けましょう。異常が見つかった場合は、早めに治療を始めることが重要です。
異常なしの場合
目立った異常がなければ、大腸がんや直腸がんの定期検診を数年おきに受けるなどして経過をみて、年齢やリスクに応じて、便潜血検査や内視鏡検査の受診タイミングを医師と相談して決めると安心です。
痔や軽度炎症が見つかった場合
痔核や肛門周囲の炎症がある場合は、坐薬や軟膏、生活習慣の改善で対応することが多く、肛門に負担をかけすぎないよう、便秘予防や食物繊維摂取を意識した食事を続けることが大切です。
食事や生活習慣の見直し
- 水分をこまめに摂取して便を柔らかくする
- 野菜や果物など食物繊維を多めにとる
- 排便時に長時間いきまない
- 座り仕事の方は適度に立ち上がり、血行を促進する
- 運動不足を避けるためウォーキングなどを継続する
がん疑いの場合
もし直腸診でがんが疑われる病変に触れた場合は、内視鏡検査や生検を行い確定診断を目指し、そのうえで、進行度や部位に応じた外科治療や放射線治療、化学療法などが選択されます。
早期に発見できれば内視鏡的切除などの負担が小さい治療で済むことが少なくありません。
前立腺の異常で転院が必要
男性で前立腺の異常を疑われた場合、泌尿器科など専門の診療科へ紹介されるケースもあり、PSA検査や前立腺生検などを組み合わせて、がんの有無や進行度を診断します。
長期的な視点で見る直腸診の意義
直腸診は、がんやさまざまな肛門疾患を見つける重要な入り口となりえるので、全体の範囲を網羅する検査ではありませんが、肛門や直腸周辺に何らかの異変がある場合、医師が早期に把握できる可能性を高めます。
継続的な検査の重要性
1回の直腸診で異常がなかったとしても、年齢を重ねるにつれ新たな病気が生じることがあります。大腸がんや直腸がんは徐々に進行する病気であるため、定期的な検診や内視鏡検査を受ける習慣が欠かせません。
医師とのコミュニケーション
直腸診における不安や疑問点、痛みの程度などは、遠慮なく医師に伝えましょう。医師も患者さんが安心して受けられるよう配慮し、必要に応じて検査方法を調整します。
医師に相談したいこと
- 直腸診の具体的手順や体勢
- 痛みや出血があった場合の対処法
- 大腸内視鏡検査や便潜血検査を行う時期
- 家族歴がある場合のリスクや対策
- 日常の便通や腹痛などの症状へのアドバイス
早期発見と生活習慣
消化器疾患や大腸がんの予防には、検診や検査だけでなく、食事や運動など日々のライフスタイルも影響します。直腸診で異常が見つかれば早期治療に移行できますが、見つかる前にリスクを下げる工夫も大切です。
大腸がん予防のためにできること
- アルコールや喫煙を控える
- 肉類や動物性脂肪の摂取をほどほどに
- 野菜や果物を積極的に食べる
- 定期的に運動を行い、肥満を防ぐ
- ストレスを溜めず、睡眠をしっかり確保
まとめ
直腸診は、肛門や直腸の下部に生じた異常を見つけるうえで欠かせない検査のひとつで、大腸がんや直腸がんのうち、肛門に近い部位の病変であれば、直腸診によって触知できる場合があります。
ただし、全ての大腸病変をカバーできるわけではなく、内視鏡検査や便潜血検査、画像検査などを組み合わせることが早期発見には重要です。
前立腺がんや肛門周囲の炎症、痔核などの診断にも有用であり、定期的な受診や検査を行うことで健康を維持できます。
直腸診は、肛門や直腸周辺の異常を触知する検査で、大腸がんや痔、前立腺がんなどの発見に役立ちます。大腸内視鏡や便潜血など他の検査と組み合わせると早期診断が期待でき、治療の方向性を決める際にも大切です。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸検査が気になる方へ 内視鏡検査の注意点】
直腸診で『次は内視鏡も検討を』と言われた方へ。検査前後の流れや鎮静の有無、実際に受けた方の声を交え、当日のイメージがつかめる内容です。
【大腸がん初期症状の見逃しを防ぐ 便の変化や腹痛の基本知識】
直腸診について理解すると、関連する大腸がんの初期症状についても知りたくなる方が多いようです。意外な繋がりが見えてくる内容です。
参考文献
Talley NJ. How to do and interpret a rectal examination in gastroenterology. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2008 Apr 1;103(4):820-2.
Hennigan TW, Franks PJ, Hocken DB, Allen-Mersh TG. Rectal examination in general practice. British Medical Journal. 1990 Sep 8;301(6750):478-80.
Tantiphlachiva K, Rao P, Attaluri A, Rao SS. Digital rectal examination is a useful tool for identifying patients with dyssynergia. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2010 Nov 1;8(11):955-60.
McFarlane MJ. The rectal examination. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd edition. 1990.
Orkin BA, Sinykin SB, Lloyd PC. The digital rectal examination scoring system (DRESS). Diseases of the colon & rectum. 2010 Dec 1;53(12):1656-60.
Wong RK, Drossman DA, Bharucha AE, Rao SS, Wald A, Morris CB, Oxentenko AS, Ravi K, Van Handel DM, Edwards H, Hu Y. The digital rectal examination: a multicenter survey of physicians’ and students’ perceptions and practice patterns. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2012 Aug 1;107(8):1157-63.
Kessler C, Bauer SJ. Utility of the digital rectal examination in the emergency department: a review. The Journal of emergency medicine. 2012 Dec 1;43(6):1196-204.
Muris JW, Starmans R, Wolfs GG, Pop P, Knottnerus JA. The diagnostic value of rectal examination. Family Practice. 1993 Mar 1;10(1):34-7.
Dixon JM, Elton RA, Rainey JB, Macleod DA. Rectal examination in patients with pain in the right lower quadrant of the abdomen. British Medical Journal. 1991 Feb 16;302(6773):386-8.
Dobben AC, Terra MP, Deutekom M, Gerhards MF, Bijnen AB, Felt-Bersma RJ, Janssen LW, Bossuyt PM, Stoker J. Anal inspection and digital rectal examination compared to anorectal physiology tests and endoanal ultrasonography in evaluating fecal incontinence. International journal of colorectal disease. 2007 Jul;22:783-90.