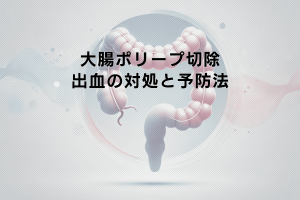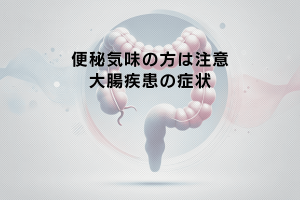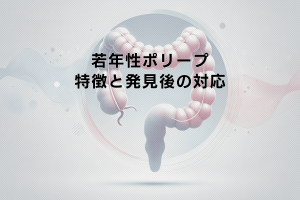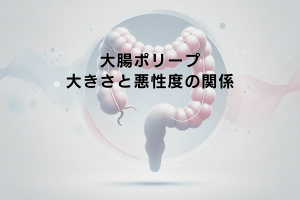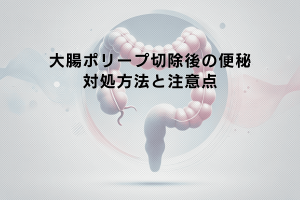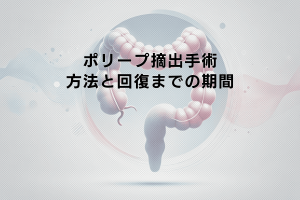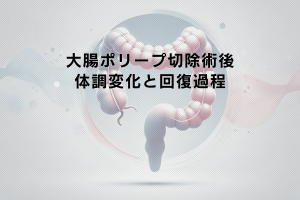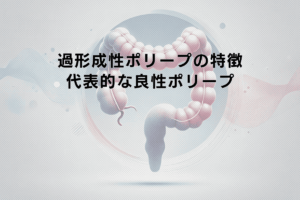潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜に慢性的な炎症や潰瘍が生じる炎症性腸疾患です。、血便や下痢、腹痛などの症状を起こし、増悪と寛解を繰り返す特徴があります。
早期に的確な診断を受けることが重要で、その際に内視鏡検査が有用となります。原因として遺伝や免疫異常との関わりが示唆されていますが、生活習慣やストレスの影響も考えられています。
進行すると重大な合併症を起こす可能性があるため、気になる症状がある場合は医療機関で相談すると安心です。
この記事では潰瘍性大腸炎の特徴と症状、内視鏡検査による診断のポイントを中心に解説します。
潰瘍性大腸炎とは
炎症性腸疾患の中で代表的なものが潰瘍性大腸炎と呼ばれています。粘膜に炎症が及ぶことで出血や潰瘍を起こす慢性疾患で、近年は患者数が増えており、早期の診断とケアが重要です。
潰瘍性大腸炎の定義
大腸全体、あるいは一部の粘膜が慢性的に炎症を起こし、びらんや潰瘍が生じ、症状は寛解と悪化を繰り返す経過をたどり、寛解期には症状が落ち着きますが、悪化期には血便や下痢が強まる傾向があります。
症状の度合いや大腸内での炎症の広がり方には個人差があります。
潰瘍性大腸炎と大腸の関係
大腸は主に水分の吸収と便の形成を担当する重要な消化器官です。潰瘍性大腸炎によって粘膜に炎症が広がると、血管や組織が傷ついて出血しやすくなります。
下痢や血便が生じると同時に、長期的には栄養状態が悪くなり、炎症の程度によっては肛門に近い直腸から大腸全体にまで及びます。

ほかの炎症性腸疾患との比較
炎症性腸疾患には潰瘍性大腸炎のほかにクローン病があります。クローン病は口から肛門までの消化管全体に炎症が及ぶ可能性があるのに対し、潰瘍性大腸炎は大腸のみが対象です。また、炎症の広がり方や病変の深さにも違いがあります。
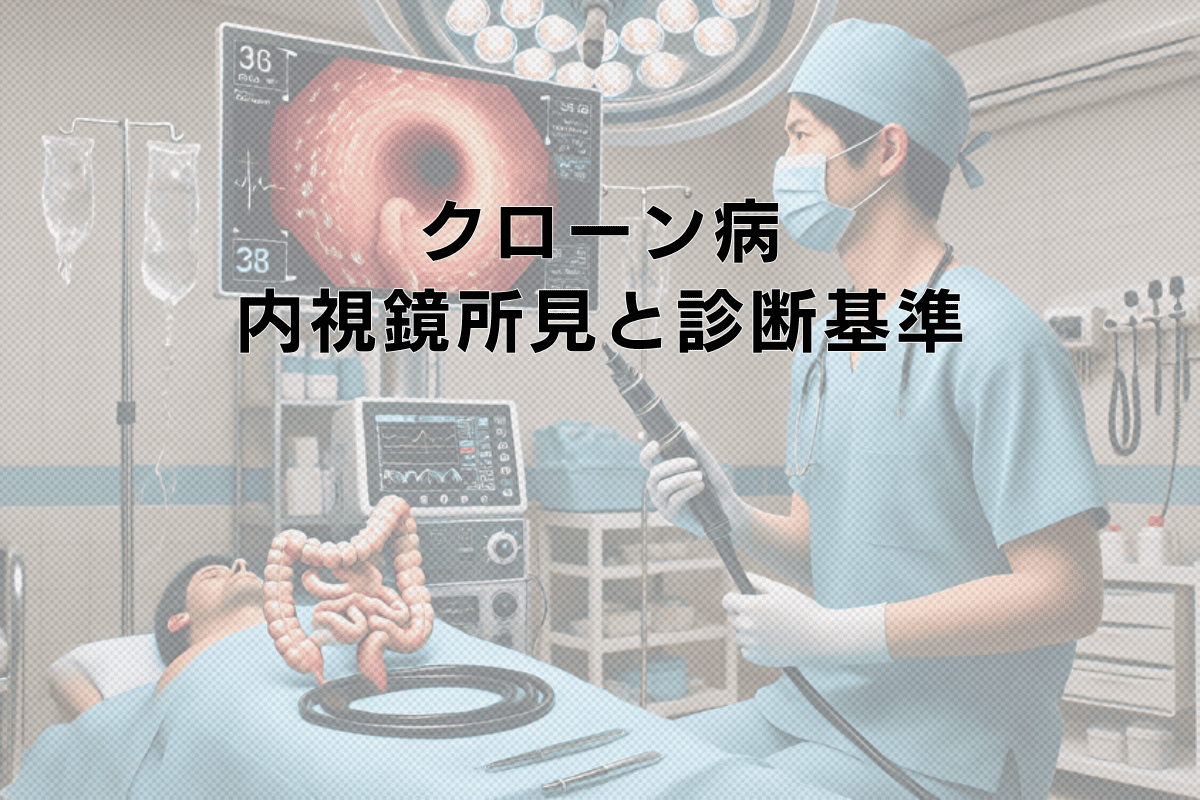
潰瘍性大腸炎とクローン病の大まかな違い
| 比較項目 | 潰瘍性大腸炎 | クローン病 |
|---|---|---|
| 病変の範囲 | 大腸(特に直腸から口側に連続的に広がる) | 口から肛門までの全消化管(飛び石状) |
| 病変の深さ | 粘膜層まで | 消化管の全層 |
| 主な症状 | 血便・下痢、腹痛 | 下痢、腹痛、瘻孔形成など |
| 合併症の傾向 | 大腸がんのリスクが上昇 | 狭窄や痔瘻などが起こりやすい |
| 発症年齢のピーク | 若年〜中年に多い | 若年層に多い |
これらの違いを把握することで、自身の病気がどちらに当てはまるかをイメージしやすくなるでしょう。
短期間で判断するのは難しい場合がありますが、検査を受けると診断が明確になりやすいです。原因の解明が進む一方で、生活習慣や遺伝的要因が関わる可能性もあります。
日常で感じやすい兆候
- トイレに行く回数が増える
- 便に血液が混ざっている
- なんとなく疲れやすい
- 体重が減ってきたように思う
大腸の痛みや血便を自覚したら、早めに医療機関で相談して正しい診断を受けることが大切です。
潰瘍性大腸炎の主な症状
潰瘍性大腸炎は炎症が大腸の粘膜に及ぶため、便に血液が混ざったり、下痢や腹痛が出たりといった症状を起こし、症状の強さや頻度は、炎症の広がりや個人差によって変わります。
血便・下痢
血便は潰瘍性大腸炎を疑う代表的な症状の1つで、炎症を起こした粘膜が出血し、便とともに排出されます。
同時に水分の吸収が不十分になるため下痢を伴うことが多く、血便と下痢が続く状態があると、体力が消耗しやすくなり、悪循環を招きます。
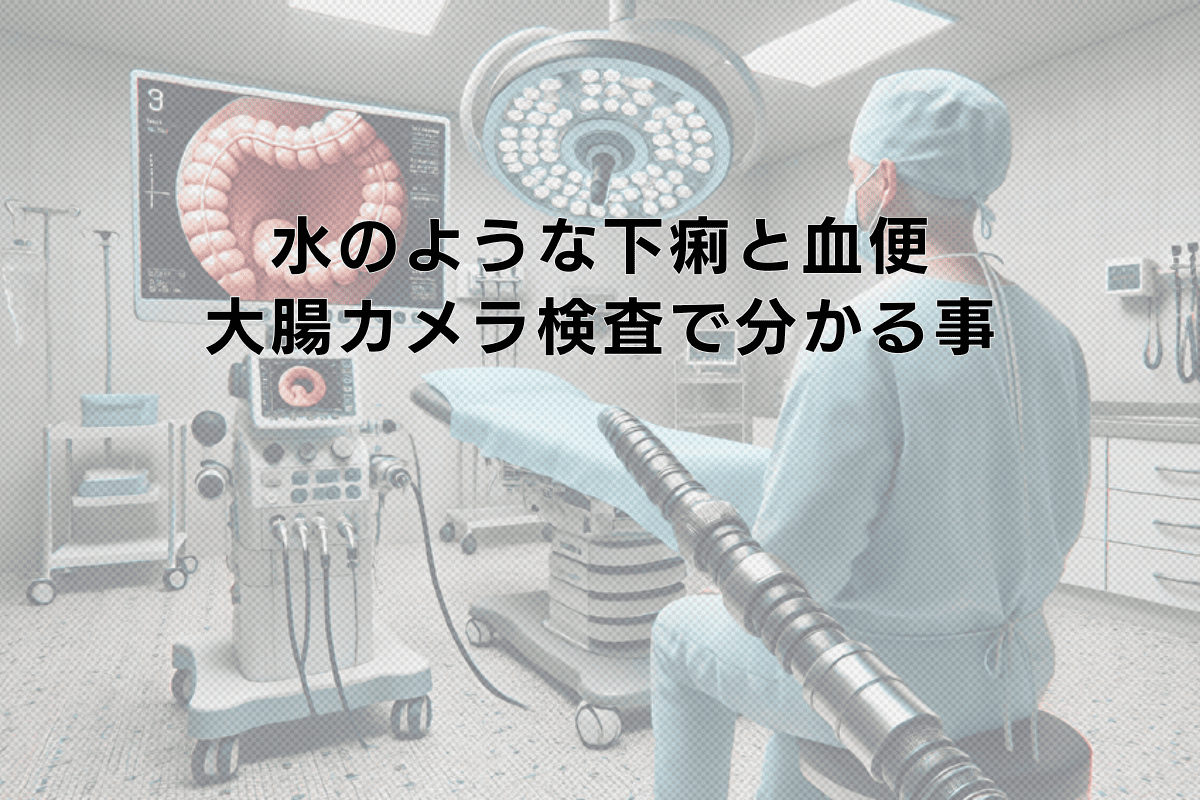
腹痛と腹部不快感
潰瘍性大腸炎の炎症により腸壁が刺激を受け、腹痛や腹部の不快感を覚えます。痛みは軽度の鈍痛から激しい差し込みまで様々です。便意が近づくほど痛みが増し、慢性的に痛みが続くと日常生活に支障を来たすことがあります。
倦怠感や体重減少
便の回数が増え、水分や栄養の吸収が不十分になることで倦怠感や体重減少を起こしやすくなり、慢性化すると貧血や栄養失調につながり、疲労が抜けない状態になります。
自己判断で食事制限を極端に行うと、さらに症状を悪化させることがあります。
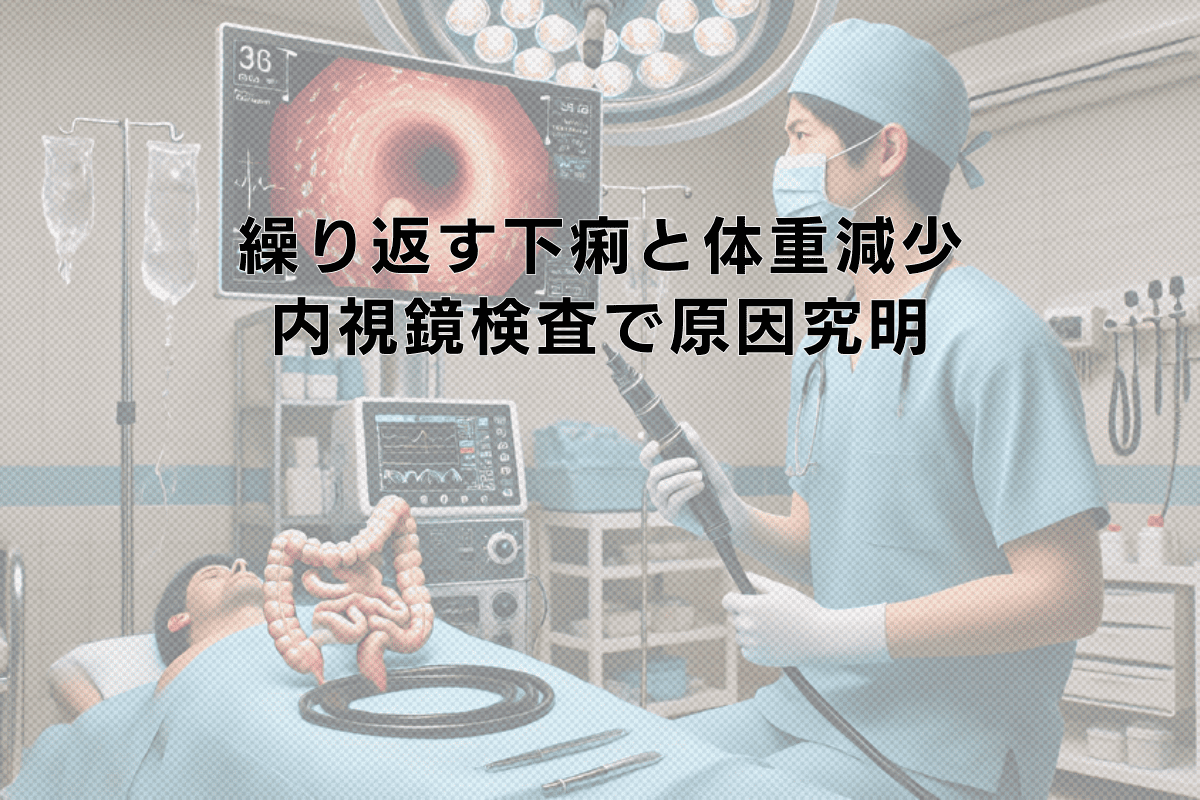
病変の範囲と症状の相関
直腸に限局する場合と、大腸全域に炎症が及ぶ場合では症状の出方が異なり、大腸全体に病変が広がると、出血量が増えて症状が強まる傾向があります。治療方針を検討するうえで病変の範囲は重要な情報です。
潰瘍性大腸炎の炎症範囲と主な症状
| 炎症範囲 | 主な特徴 | 症状の傾向 |
|---|---|---|
| 直腸のみ | 下痢や血便は軽度〜中等度 | 肛門付近の不快感や血便の頻度が増える |
| 左側大腸 | 下行結腸〜直腸に炎症が及ぶ | 血便・腹痛・下痢が比較的多い |
| 全大腸 | 大腸全域にわたって粘膜に炎症が及ぶ | 症状が強く出やすく、全身状態が悪化 |
炎症の範囲が広いほど、便通異常や出血のリスクが高まるので適切な検査で状態を把握することが大切です。
潰瘍性大腸炎の原因と発症リスク
潰瘍性大腸炎の発症メカニズムは完全には解明されていませんが、遺伝的要因や免疫バランスの乱れなど複数の要因が関与していると推測されています。
遺伝的要因
家族や血縁者に潰瘍性大腸炎の患者がいる場合、発症リスクが高まると報告されていますが、遺伝的要因だけで発症するわけではなく、環境因子や生活習慣などの複合的な要素が影響する可能性があります。
免疫異常との関連
体内の免疫システムが何らかの理由で過剰に反応し、大腸粘膜を攻撃してしまうことで炎症を引き起こすとの説があります。また免疫バランスが崩れる要因として、ウイルスや細菌感染などが考えられます。
食生活や生活習慣の影響
高脂肪や高カロリーの食事、過度の飲酒や喫煙などは腸内環境を悪化させる一因です。また、忙しい生活による不規則な食事や睡眠不足なども発症リスクに影響するといわれています。
心理的ストレスとの関わり
ストレスは自律神経系やホルモン分泌に影響を与え、免疫機能を変動させる可能性があります。多忙な環境や人間関係などで強いストレスを感じると、腸への負担が増すことがあります。
潰瘍性大腸炎の発症や症状の悪化のきっかけとしてストレスが関与している可能性もあります。
潰瘍性大腸炎に関わる要因
| 要因 | 具体例 | 対応策・注意点 |
|---|---|---|
| 遺伝的要素 | 血縁者に潰瘍性大腸炎を患う人がいる | 病歴を医師に共有する |
| 免疫異常 | 免疫システムが自己組織を攻撃 | ウイルス感染の既往や他の自己免疫疾患の確認 |
| 食生活の乱れ | 不規則な食事、高脂肪・高カロリー食 | 食物繊維やバランスの良い食事を意識する |
| ストレス | 過度のプレッシャー、睡眠不足 | リラックスできる時間を確保して精神面を整える |
複数の要因が重なることで発症に至ると考えられます。予防のためにも、生活習慣の見直しとこまめな健康チェックが重要です。
少しでも疑わしい症状を感じたときは、早期診断に役立つ受診を検討すると安心です。周囲や専門家に相談すると心の負担も軽減しやすくなります。
- 食事を見直して腸に負担をかけにくい料理を選ぶ
- 睡眠時間と休息をしっかり確保する
- 血便や腹痛などの症状を日記に記録して早めに医師に伝える
これらは誰にでも取り組みやすいことなので、症状がなくても実践すると健康維持に役立ちます。
潰瘍性大腸炎の診断の流れ
潰瘍性大腸炎を疑ったときは問診や身体診察から検査へと進み、症状の程度や部位を把握します。血液検査や便検査で炎症や感染症の有無を調べ、画像検査や内視鏡検査で腸内の状態を確認します。
問診や身体診察
医師は症状の内容や頻度、下痢や血便の回数などを詳細に尋ねます。身体診察では腹部の触診や直腸診などを行い、炎症や痛みの部位を確認します。過去の病歴や家族歴も診断の手がかりです。
血液検査・便検査
血液検査では貧血や炎症マーカー(CRPなど)、肝機能や腎機能を調べ、潰瘍性大腸炎では炎症が続くためCRPや白血球数が高まることがあります。便検査では潜血や菌の有無などを確認し、感染症との鑑別を行います。
画像検査
場合によってはX線やCT、MRIなどの画像検査を行い、腸の形態的変化や合併症の有無を調べます。透視検査ではバリウムを用いて大腸の輪郭を観察します。しかしこれらの検査は補助的であり、大腸カメラが主流です。
鑑別が必要なその他の疾患
潰瘍性大腸炎と症状が似ている病気として、感染性大腸炎や虚血性大腸炎、大腸がんなどがあります。これらを除外するためにも、総合的な検査が必要です。
潰瘍性大腸炎と間違えやすい主な疾患
| 疾患名 | 主な特徴 | 潰瘍性大腸炎との違い |
|---|---|---|
| 感染性大腸炎 | 細菌やウイルスによる急性の下痢や発熱 | 原因微生物がはっきりしていて抗菌薬が有効な場合が多い |
| 虚血性大腸炎 | 血流不全による大腸の炎症 | 高齢者や動脈硬化のある人に多い |
| 大腸がん | 腫瘍が大腸内に発生し、出血や狭窄を引き起こす | 病変の形態が異なり、画像検査や内視鏡検査で区別可能 |
これらの疾患を鑑別したうえで、潰瘍性大腸炎が疑われる場合は内視鏡検査を行います。大腸内視鏡検査では粘膜の状態や潰瘍の有無を直接観察できるため、早期の段階で診断が行いやすいです。
内視鏡検査による潰瘍性大腸炎の診断ポイント
潰瘍性大腸炎の診断を明確にするには、大腸カメラによる内視鏡検査が重要です。カメラを挿入して大腸の粘膜を直接観察し、潰瘍の有無や炎症の範囲、出血状況などを調べます。
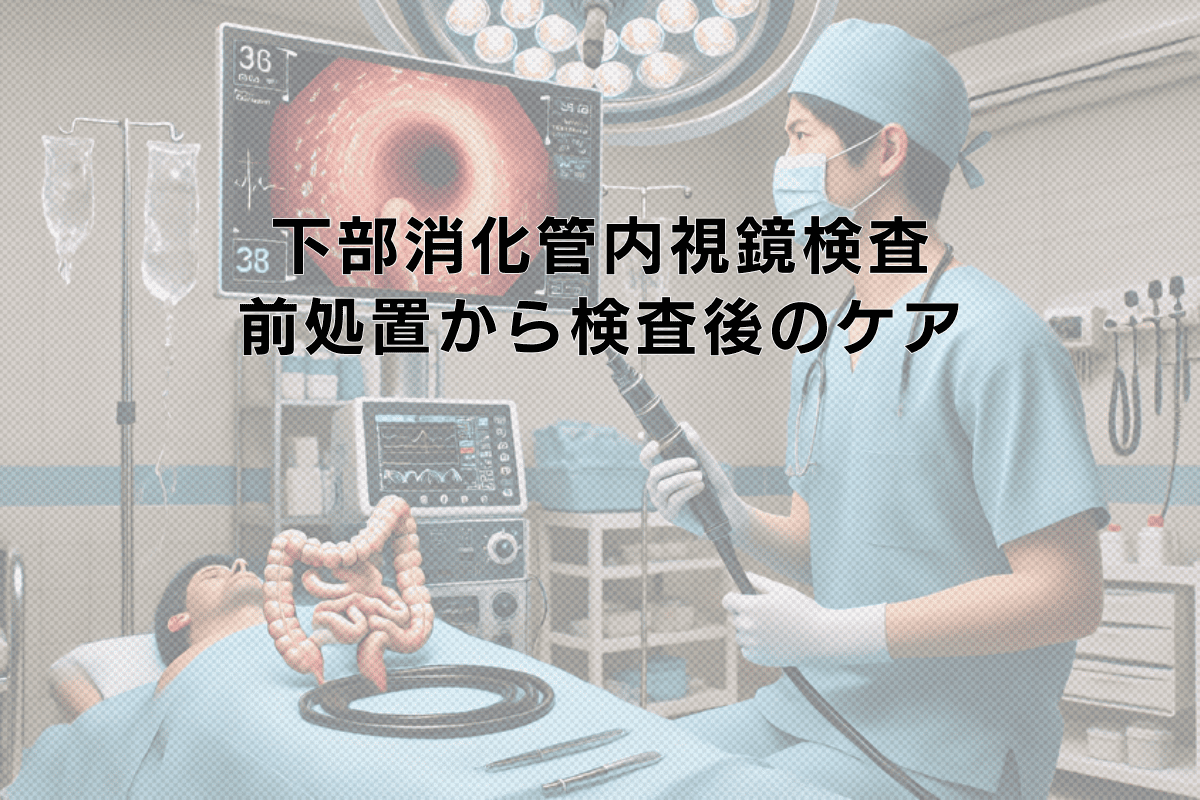
内視鏡検査のメリット
内視鏡検査では大腸内部をリアルタイムで観察し、生検(組織の一部を採取)によって病理組織を確認でき、画像検査ではわかりにくい粘膜表面の微細な変化も把握できるため、潰瘍性大腸炎の診断や重症度の判定に有用です。
治療の効果判定や再発の有無を確かめる際にも役立ちます。
検査時に観察する潰瘍性大腸炎の所見
潰瘍性大腸炎の粘膜所見には出血やびらん、偽ポリポーシスなどが挙げられます。粘膜が鮮紅色で血液や粘液が付着している場合、炎症が活動的である可能性があります。びらんや潰瘍の分布が連続的に広がることも典型的です。
潰瘍性大腸炎内視鏡所見の確認事項
医師は内視鏡画像を見ながら、粘膜の赤みや腫れ、びらん、潰瘍の大きさや数などを総合的に判断し、粘膜面の脆さや出血量の多寡によっても活動性を推測します。
潰瘍性大腸炎で特徴的なのは、病変が途切れなく連続している点や直腸から口側へ広がっていく点です。
組織検査の重要性
内視鏡検査で疑わしい病変を見つけた際には、組織の一部を採取して顕微鏡で観察します。粘膜組織の炎症細胞の種類や浸潤の深さなどを調べると、潰瘍性大腸炎か他の病気かを区別しやすくなります。
組織検査によって早期発見や合併症の把握につなげることが重要です。
内視鏡検査の主なチェックポイント
| チェック項目 | 確認内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 粘膜の色調 | 赤みが強い、まだら状、粘液や血液付着の有無 | 活動期かどうかの目安になる |
| びらん・潰瘍の範囲 | どの部位にどの程度の広がりがあるか | 病変が連続しているかを確認 |
| 粘膜の脆さ | 軽い刺激でも出血するか | 潰瘍性大腸炎の活動度を推測できる |
| 偽ポリポーシスの有無 | 既存の粘膜が飛び出したような病変の有無 | 慢性的炎症の影響が現れる箇所 |
内視鏡検査で潰瘍性大腸炎を診断した後は、その重症度や範囲に応じて治療方針を検討します。
短時間で検査を終わらせるために鎮静剤を使う場合が多いですが、不安な点は担当医に相談すると安心です。
- 検査前には食事制限や腸内を洗浄する薬の服用を行う
- 痛みや不快感を軽減するために鎮静剤を使用するケースがある
- 内視鏡の進行状況を説明しながら検査を進める場合もある
- 受診者の状態を考慮して安全に配慮した検査を実施する
内視鏡検査は詳細な診断を得るうえで大切で、早期発見により重症化を防ぎやすくなるため、症状が気になる場合は早めの受診をおすすめします。
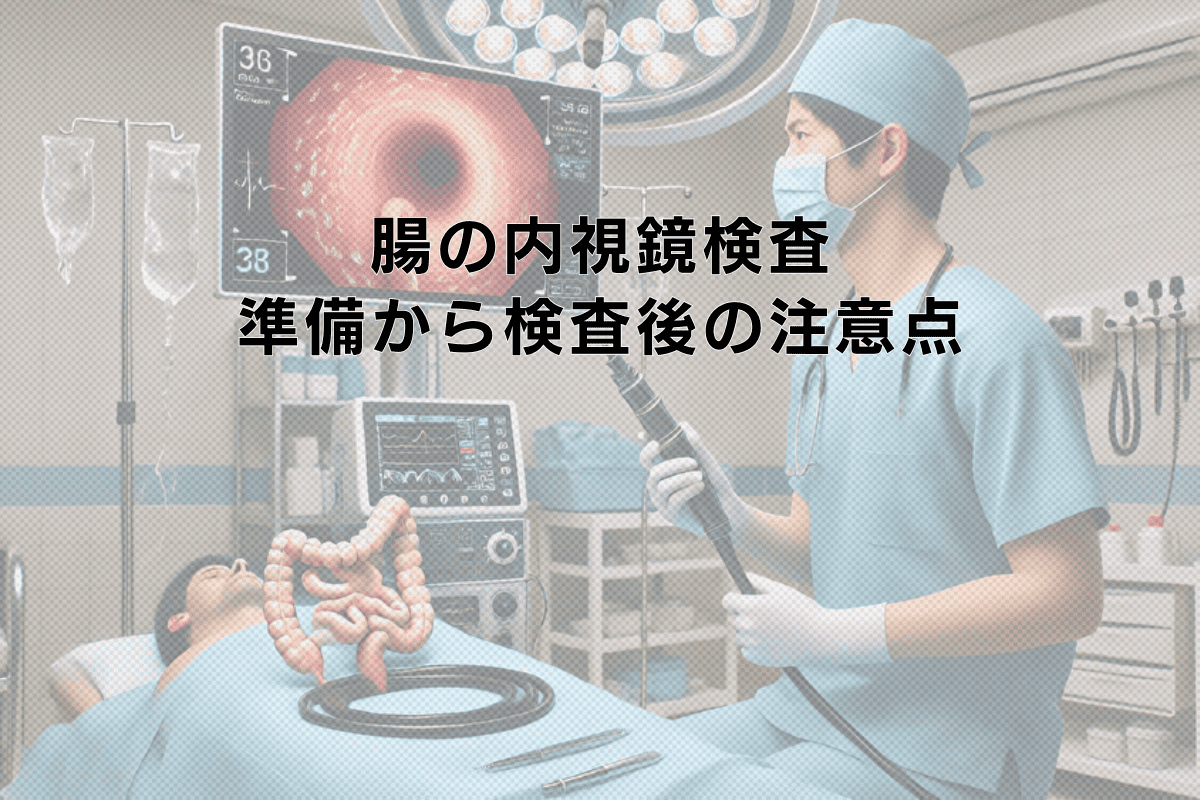
病状や合併症に応じた治療の方向性
潰瘍性大腸炎の治療は症状や病変の広がり、合併症の有無によって異なります。薬物療法を中心に、必要に応じて手術を選択することもあります。合併症を早期に把握して対処すると症状のコントロールがしやすくなります。
軽症から中等症の場合
軽症から中等症では、5-ASA(5-アミノサリチル酸)製剤やステロイドなどを使用して症状の改善を目指します。
5-ASA製剤は腸内の炎症を抑える働きがあり、寛解維持にも有効な場合があります。ステロイドは短期間で症状を和らげる力がありますが、長期使用による副作用にも注意が必要です。
重症の場合
重症になるとステロイドの点滴や免疫調整薬を用いて症状をコントロールし、状況によっては生物学的製剤を使用するケースもあります。
激しい出血や中毒性巨大結腸症などの合併症が疑われる場合、手術が治療オプションに含まれ、状態が急変する恐れがあるため、入院管理で慎重に経過を観察します。
合併症対策
潰瘍性大腸炎は大腸がんのリスクが高まることが指摘されており、長期間にわたって炎症が続くと腸粘膜に異常細胞が生じやすくなります。
また、貧血や骨粗しょう症、肝臓や胆管などに関連した病変が出現する場合もあるので、合併症に対する定期的な検査が大切です。

再発予防のためのフォローアップ
潰瘍性大腸炎は再発を繰り返すことがあるので、治療によって寛解した後も、適宜フォローアップ検査を行って炎症の再燃を早期に察知することが必要です。
食事管理や生活習慣の改善、ストレスコントロールなどのセルフケアも欠かせません。
潰瘍性大腸炎治療に使用される薬
| 薬の種類 | 主な作用 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 5-ASA製剤 | 大腸粘膜の炎症を抑制 | 長期的に使用する場合も多い |
| ステロイド | 炎症を短期的に強力に抑える | 副作用(骨粗しょう症、高血圧など)に注意 |
| 免疫調整薬 | 免疫系の過剰反応をコントロール | 感染症リスクの上昇に気を配る |
| 生物学的製剤 | 炎症性サイトカインをブロック | 高価であり、定期的な効果判定が必要 |
治療薬の組み合わせや使用期間は個々の状態に合わせて検討します。医師の指示に従って管理することで、症状の緩和や再発リスクの低減が期待できます。
日常生活で気をつけたいポイント
潰瘍性大腸炎と診断された場合、治療だけでなく日常の過ごし方にも配慮すると症状の改善や再発予防につながります。食事やストレス対策、定期的な通院などを意識すると安定した生活を送りやすくなります。
食事の工夫
大腸に刺激の強い食品は避け、消化が良く栄養バランスのとれた食事を意識すると腸内環境が落ち着きやすくなります。
揚げ物や脂身の多い肉類、香辛料の強い料理などは症状を悪化させる可能性があるので、魚や野菜などを中心に適量を守りながら取り入れると良いです。

ストレスマネジメント
過度なストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、腸の働きを不安定にすることがあります。
運動や趣味の時間を取り入れて気分転換を図る、十分な睡眠を取るなど、心身をリラックスできる方法を見つけて実践すると症状のコントロールに役立ちます。

定期的な通院と検査
一時的に症状が落ち着いても、炎症が再燃することがあるため定期的な通院で状態を確認することが大切です。医師の診察や血液検査、内視鏡検査などを受けながら、薬の処方や用量の調整を行うと再発のリスクを抑えやすくなります。
体調の変化と早期対応
腹痛や血便、下痢の悪化を感じた場合は自己判断せずに医療機関へ相談すると重症化を防ぎやすくなります。通院のタイミングを逃すと、症状が急速に悪化する可能性があるため注意が必要です。
日常生活で気を配るポイント
| 項目 | おすすめの行動 | 注意点 |
|---|---|---|
| 食事 | 脂っこいものを控えめに、野菜や魚を意識 | 極端な制限や過度なサプリに頼らない |
| ストレス対策 | 適度な運動や趣味の時間を確保 | ストレスを抱え込まずに周囲と共有する |
| 休養と睡眠 | 就寝時間を一定にし、十分な睡眠を取る | 不規則な生活が続くと症状が出やすい |
| 通院と検査 | 定期的な受診で薬の効果や炎症状態を確認 | 症状が落ち着いていても自己判断で中断しない |
日常生活を整えることが、潰瘍性大腸炎の安定した管理にとって非常に重要で、辛い症状があるときは無理をせず、こまめに主治医と相談しながら対策を検討すると安心です。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査とはどのような検査なのか】
潰瘍性大腸炎の診断について理解が深まったら、次は実際の内視鏡検査の流れについて知っておくと安心です。検査を検討している方に特に参考になる内容です。
【腹痛や下痢が頻繁に起こる原因 検査と治療について】
潰瘍性大腸炎について学んだ皆さんには、腹痛と下痢の原因全般の知識も合わせて持っていただくと、より包括的な理解ができます。
参考文献
Feuerstein JD, Cheifetz AS. Ulcerative colitis: epidemiology, diagnosis, and management. InMayo Clinic Proceedings 2014 Nov 1 (Vol. 89, No. 11, pp. 1553-1563). Elsevier.
Conrad K, Roggenbuck D, Laass MW. Diagnosis and classification of ulcerative colitis. Autoimmunity reviews. 2014 Apr 1;13(4-5):463-6.
Langan RC, Gotsch PB, Krafczyk MA, Skillinge DD. Ulcerative colitis: diagnosis and treatment. American family physician. 2007 Nov 1;76(9):1323-30.
Kucharzik T, Koletzko S, Kannengiesser K, Dignass A. Ulcerative colitis—diagnostic and therapeutic algorithms. Deutsches Ärzteblatt International. 2020 Aug;117(33-34):564.
Collins P, Rhodes J. Ulcerative colitis: diagnosis and management. Bmj. 2006 Aug 10;333(7563):340-3.
Kaenkumchorn T, Wahbeh G. Ulcerative colitis: making the diagnosis. Gastroenterology Clinics. 2020 Dec 1;49(4):655-69.
Stange EF, Travis SP, Vermeire S, Reinisch W, Geboes K, Barakauskiene A, Feakins R, Fléjou JF, Herfarth H, Hommes DW, Kupcinskas L. European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis: definitions and diagnosis. Journal of Crohn’s and Colitis. 2008 Mar 1;2(1):1-23.
Hanauer SB. Update on the etiology, pathogenesis and diagnosis of ulcerative colitis. Nature clinical practice Gastroenterology & hepatology. 2004 Nov 1;1(1):26-31.
Baumgart DC. The diagnosis and treatment of Crohn’s disease and ulcerative colitis. Deutsches Ärzteblatt International. 2009 Feb;106(8):123.
Dignass A, Eliakim R, Magro F, Maaser C, Chowers Y, Geboes K, Mantzaris G, Reinisch W, Colombel JF, Vermeire S, Travis S. Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis part 1: definitions and diagnosis. Journal of Crohn’s and Colitis. 2012 Dec 1;6(10):965-90.