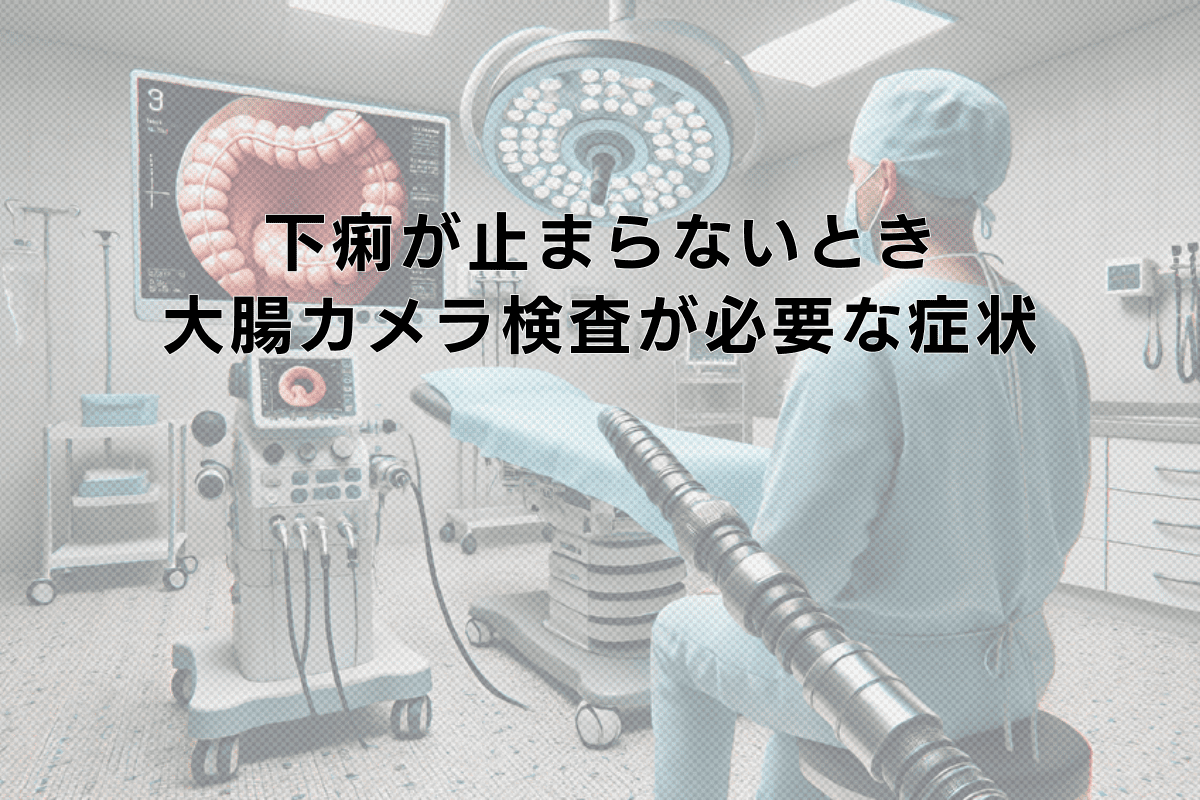下痢が長期間続いてつらいと感じている方は少なくありません。急性の腹痛や軽度のものなら自然に治まることもありますが、明らかに長引いているときは腸に何らかの異常が潜んでいる可能性があります。
原因不明で下痢が止まらない状態が続くときは、大腸カメラ検査を視野に入れて早めに医療機関を受診することが重要です。
この記事では、どういった症状のときに内視鏡検査を検討するか、下痢が止まらない原因として考えられる疾患や大腸カメラ検査に関する知識を解説します。
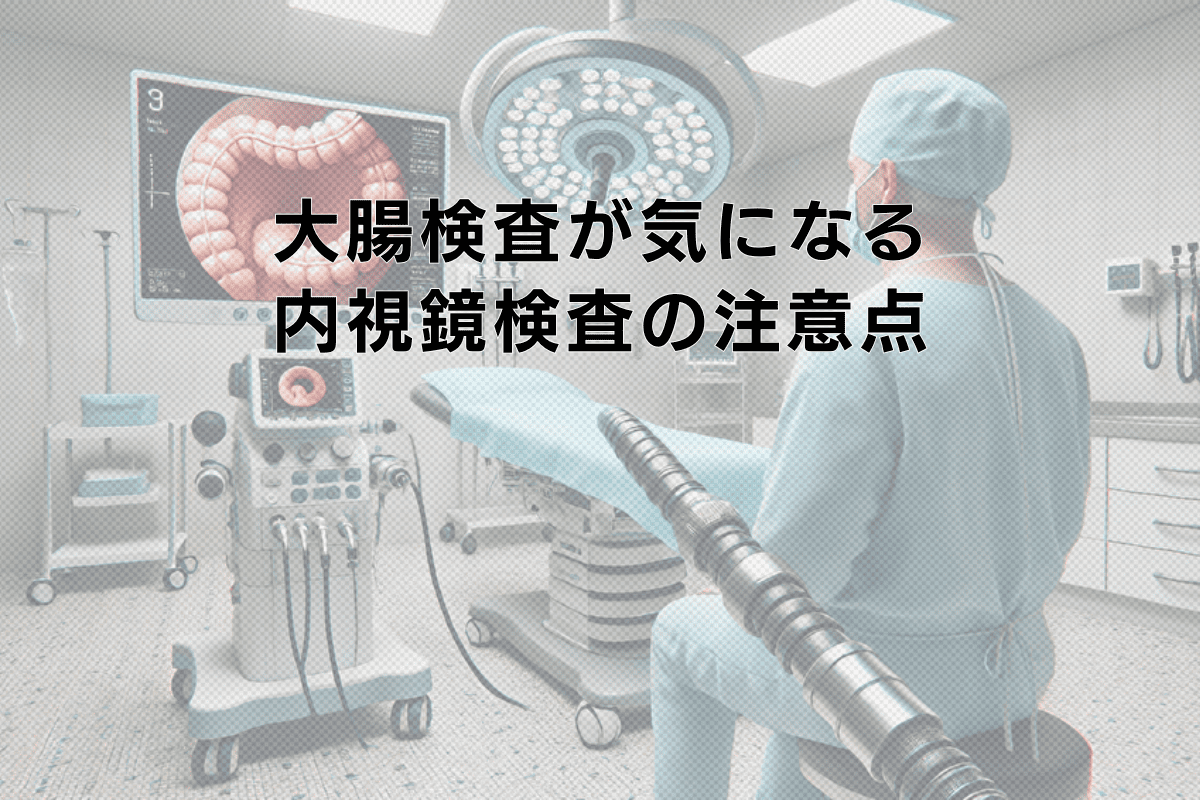
下痢が続く状態とは何か
下痢は便が異常に軟らかかったり水様性になる状態で、日常生活に支障をきたすほど症状が強いときは要注意です。数日経っても下痢が止まらない場合は、消化器系の問題が疑われます。
長引く下痢を理解するうえで、まずは下痢が続く状態や一般的な原因、体への影響を考えてみましょう。
急性と慢性の違い
下痢には大きく分けて急性下痢と慢性下痢があります。急性下痢は数日から長くても2週間程度で治まることが多く、食中毒やウイルス感染などで起こりやすいです。
一方で慢性下痢は2週間以上続くものを指し、過敏性腸症候群や炎症性腸疾患などが関係しているケースがあります。生活習慣の見直しをしても改善しない慢性の状態は専門的な検査が必要です。
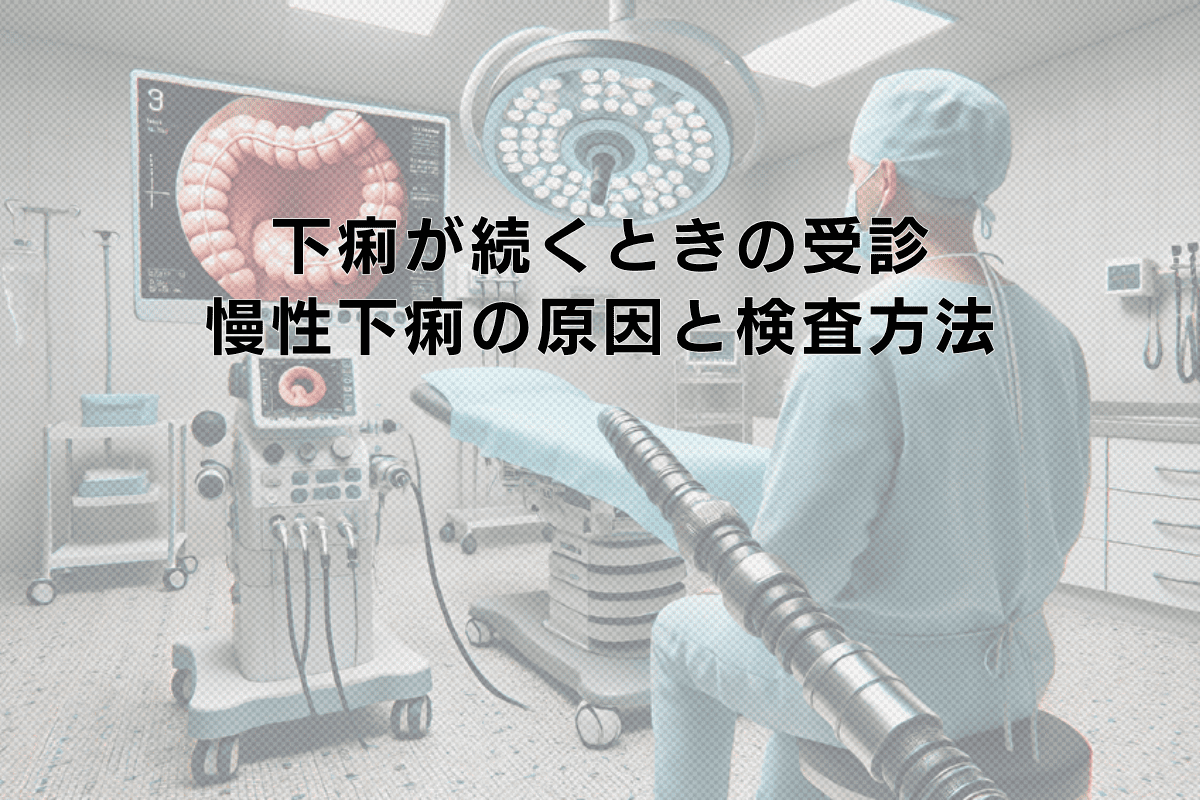
食事や生活習慣が原因の場合
下痢が続く背景には、食事の内容や生活リズムなどの習慣が隠れている場合があり、香辛料の多い食事やアルコール、ストレス、睡眠不足などが下痢を誘発しやすくします。
こうした要因を取り除いても下痢が止まらないときは、器質的な腸の異常があるかもしれません。
症状の放置による影響
下痢が止まらない状態が長引くと、脱水や電解質バランスの乱れが進行し、体力の低下や栄養吸収の障害につながる可能性があり、体重の減少や倦怠感、脱水症状などを感じたら早めに受診しましょう。
大腸カメラ検査を検討すべき理由
長期的な下痢に対しては、大腸カメラ検査による大腸内の状態確認が重要で、大腸カメラ検査では、ポリープや炎症、腫瘍性病変の有無など多様な異常を直接目視できます。
下痢が止まらない状態が続く場合に、原因を的確に見極めるうえで有用です。
下痢が長期化する原因の主な分類
| 主な分類 | 特徴 | 代表的な疾患・要因 |
|---|---|---|
| 感染性 | ウイルスや細菌などが関与 | ウイルス性胃腸炎、細菌性腸炎など |
| 炎症性 | 腸壁に炎症や潰瘍を形成 | 潰瘍性大腸炎、クローン病 |
| 機能性 | 精神的ストレスや体質が関与 | 過敏性腸症候群 |
| その他 | 吸収不良や内分泌異常など | 甲状腺機能亢進症、膵臓病など |
大腸カメラ検査が必要となるサイン
下痢が止まらない場合、単なるウイルス感染などであれば時間とともに症状が軽快していきますが、明らかに長期化している、あるいは激しい腹痛や血便などを伴うなら放置は危険です。
異常サインに注目し、早期に大腸カメラ検査を検討してください。
血便や粘液便を伴うとき
下痢が長期間続き、便に血が混じる場合は潰瘍やポリープ、腸管出血などの病変が疑われ、また便に粘液が多量に混じる場合も腸の炎症や感染症が隠れていることがあります。
こうした症状を確認したときは、大腸カメラ検査によって腸内の詳細をチェックすることが大切です。
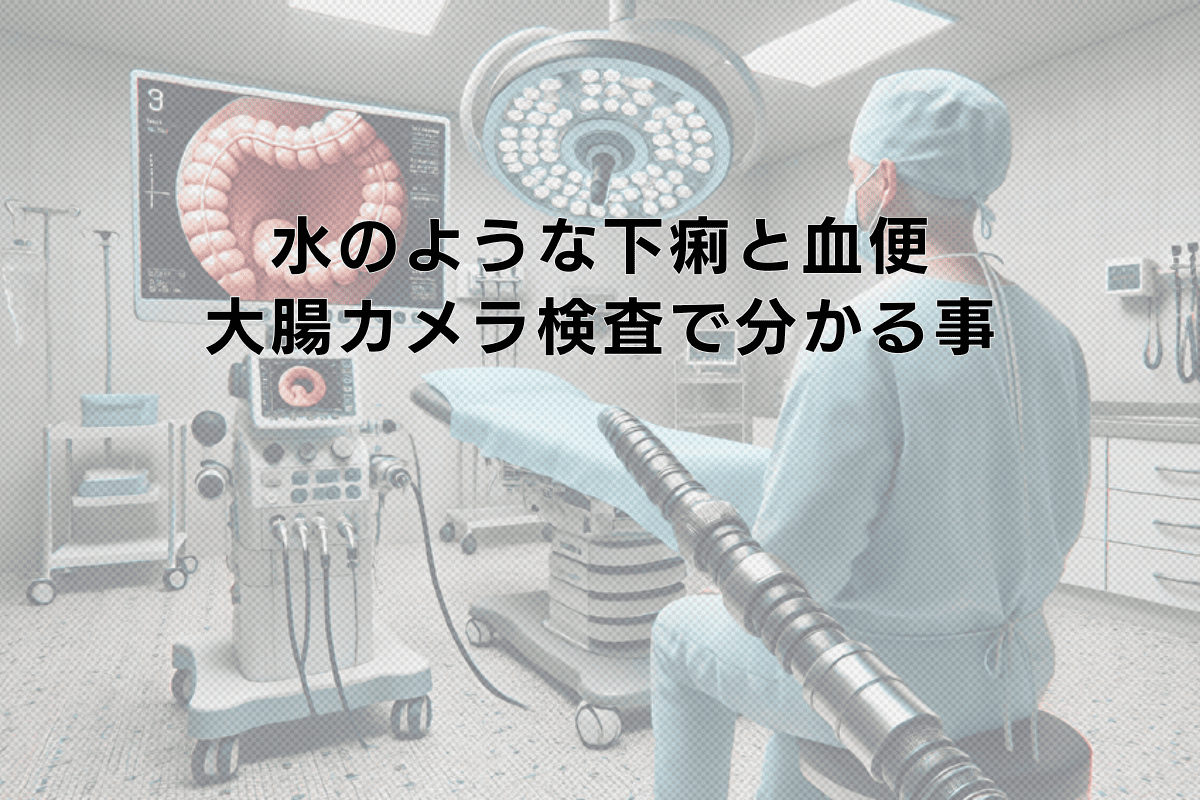
激しい腹痛や体重減少を伴うとき
下痢だけでなく激しい腹痛や持続的な痛みがあるときは、過敏性腸症候群ではなく重度の炎症が起こっている可能性があります。さらに体重減少が顕著であれば、栄養不良や炎症性腸疾患など深刻な疾患を疑う必要があります。
夜間に何度もトイレに行くとき
昼間だけでなく、睡眠中に便意が起こってしまうときは炎症性疾患など器質的な異常が原因のケースが少なくありません。夜間に下痢や腹痛で起きてしまうときも大腸カメラ検査を早期に検討したほうが安心です。
便意や便の性状が急激に変化したとき
比較的健康だった方でも、急に便の形状や排便回数が変化することがあります。
例えばそれまで正常な便だったのに、水様便が頻回に出始めたり、極端な腹痛を伴いながら軟便が続く状態に変化した場合は、重篤な病変の発症を疑われます。早期診断に大腸カメラ検査が有益です。
大腸カメラ検査が必要となる可能性がある症状の目安
| 症状 | 主な背景疾患の例 | 検査を考えるタイミング |
|---|---|---|
| 血便を伴う下痢 | 潰瘍性大腸炎、大腸ポリープなど | 数日以内に要受診 |
| 激しい腹痛と発熱 | 細菌性腸炎、クローン病など | 症状の強さ次第で即受診 |
| 夜間頻回排便 | 炎症性腸疾患、直腸病変など | 1~2週間続いたら要検討 |
| 体重減少と水様性下痢 | 慢性腸疾患、吸収不良症候群など | 明らかに下痢が長引く場合 |
下痢が止まらない原因として考えられる疾患
下痢が止まらない 原因には多種多様な疾患が挙げられます。ここでは代表的なものを紹介し、その特徴を確認してみましょう。いずれも長引く下痢に関与することがあるので、検査の必要性を検討するときの参考にしてください。
炎症性腸疾患(IBD)
潰瘍性大腸炎やクローン病などに代表される炎症性腸疾患は、腸管に慢性的な炎症や潰瘍を生じ、腹痛や血便、下痢などを引き起こします。症状の悪化と緩和を繰り返すことが多く、大腸カメラ検査による病変部位の確認が診断に欠かせません。

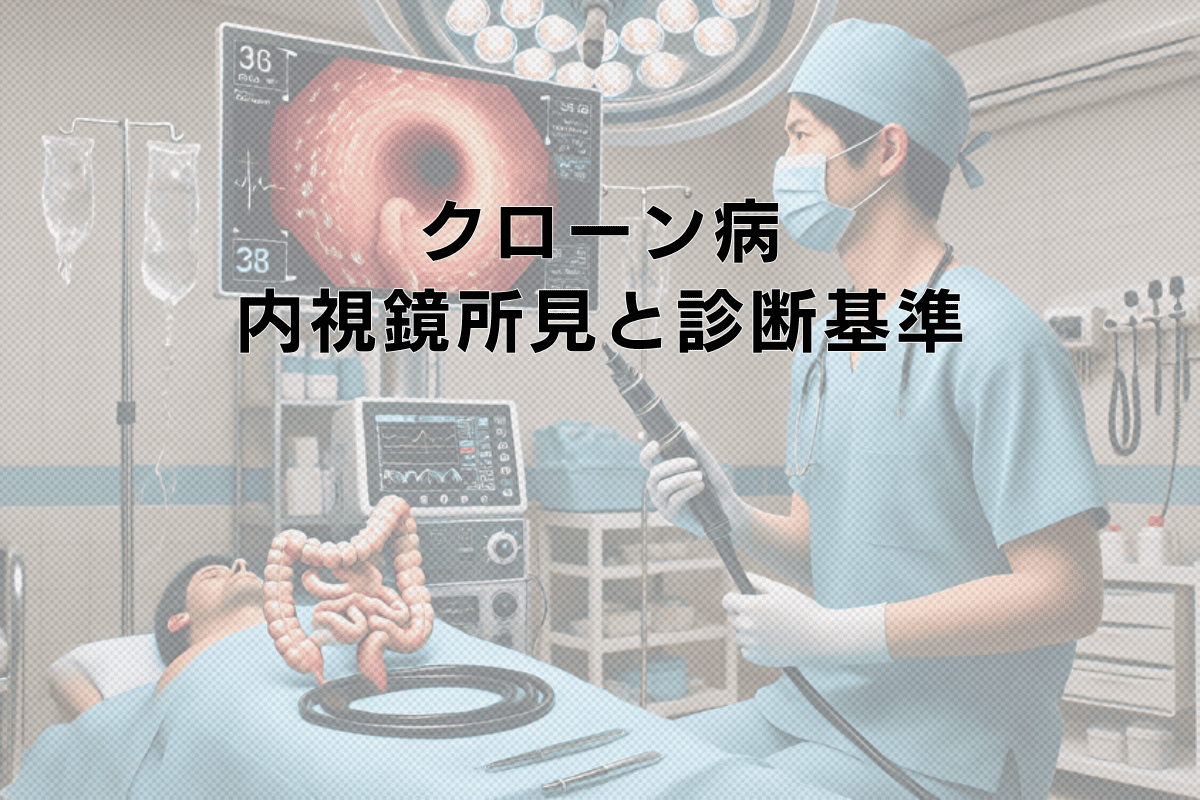
過敏性腸症候群(IBS)
慢性的な腹痛や便通異常を伴う機能性疾患で、生活習慣の乱れやストレスなどが主に関連すると考えられています。過敏性腸症候群の場合は、大腸カメラ検査で器質的異常が見つからないことが特徴です。
ただし下痢が止まらない症状が長期化しすぎる場合は、他の病気との鑑別のため検査を受けることが必要です。
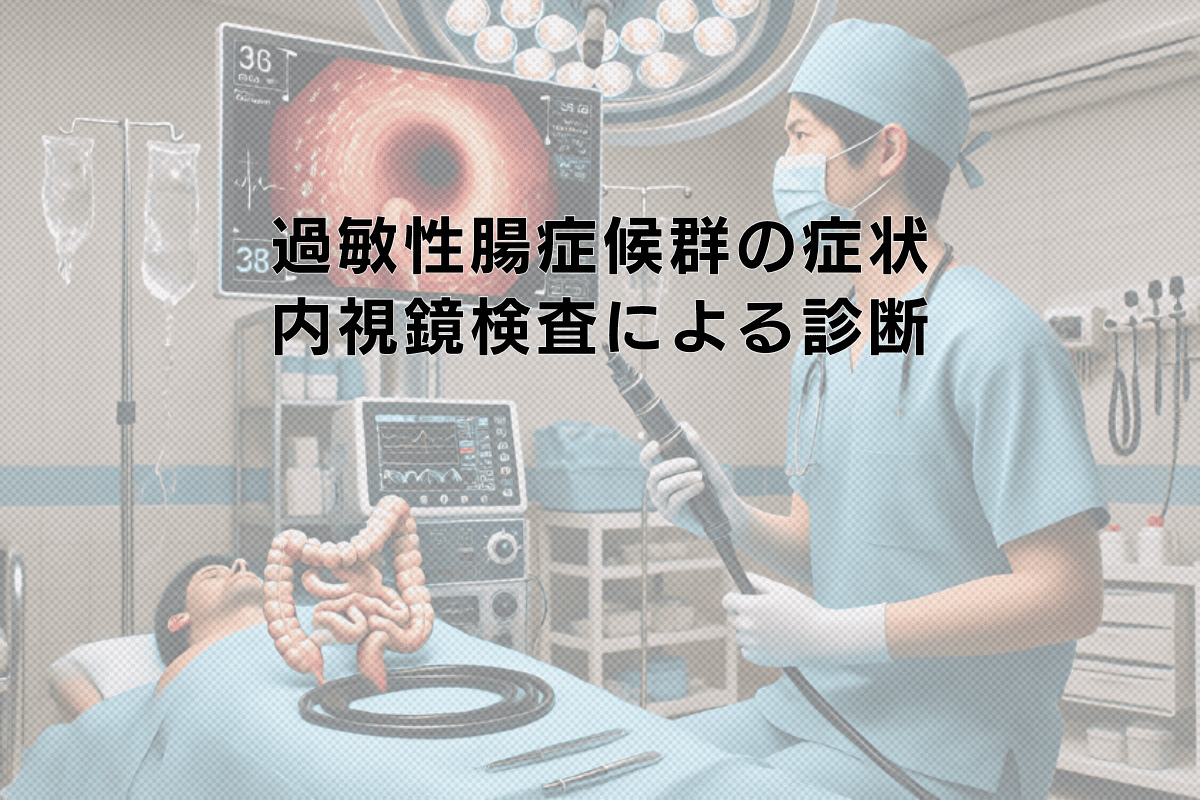
細菌性・ウイルス性の腸炎
食事や飲み水を通じて侵入した病原菌が原因で、急激な下痢や嘔吐、発熱などを起こします。通常は数日から1週間程度で症状が軽快しますが、免疫力低下や高齢者などのケースでは長引くこともあり、下痢が止まらない状態になる場合があります。
その他の吸収不良や内分泌疾患
甲状腺機能の異常や膵臓の酵素分泌障害など、腸以外の臓器の問題が下痢の要因となることもあり、下痢が続く理由が見当たらないときは、血液検査や画像検査などとあわせて大腸カメラ検査の実施が検討されます。
長期下痢に関連する主な疾患と特徴
| 疾患名 | 主な症状 | 特徴 | 大腸カメラでの所見 |
|---|---|---|---|
| 潰瘍性大腸炎 | 血便・粘液便、腹痛 | 大腸全体に及ぶことがある | 粘膜のびらんや潰瘍 |
| クローン病 | 腹痛、体重減少 | 口から肛門まで病変が生じる | 潰瘍や瘻孔など複雑な炎症 |
| 過敏性腸症候群 | 腹痛、便通異常 | 精神的ストレスと関連 | 器質的異常はほぼなし |
| 細菌性腸炎 | 急性下痢、発熱 | サルモネラ菌などが原因 | 急性期の粘膜炎症 |
大腸カメラ検査の特徴とメリット
下痢が止まらない状態が続くとき、大腸カメラ検査を行うことで得られる情報は多岐にわたり、症状に応じた内視鏡検査は、治療方針を正しく決めるために重要な手がかりです。
具体的な検査の流れや痛みの程度、メリットを理解しておくと安心して検査を受けることができます。
検査の手順と所要時間
通常、大腸カメラ検査は腸内を空にするための下剤の服用から始まります。検査当日に腸内をきれいにし、内視鏡を肛門から挿入して大腸全域を観察します。
所要時間は個人差がありますが、観察のみの場合でおよそ15分~30分程度で、組織を採取する場合は多少時間が延びることもあります。

苦痛をやわらげる方法
以前は大腸カメラ検査に対して苦痛が大きいという印象がありましたが、鎮静剤や鎮痛剤を使用した検査によって、痛みや不快感を大きく軽減できます。検査前に医師と相談し、より苦痛を抑えられる方法を選びましょう。
病変の早期発見ができる
下痢が止まらない原因として、腸の炎症だけでなくポリープや腫瘍などが隠れている場合があり、大腸カメラ検査では、目視による詳細な観察と同時にポリープ切除などの処置が可能です。
症状が軽度の段階で重篤な病変を発見し、治療につなげやすくなります。
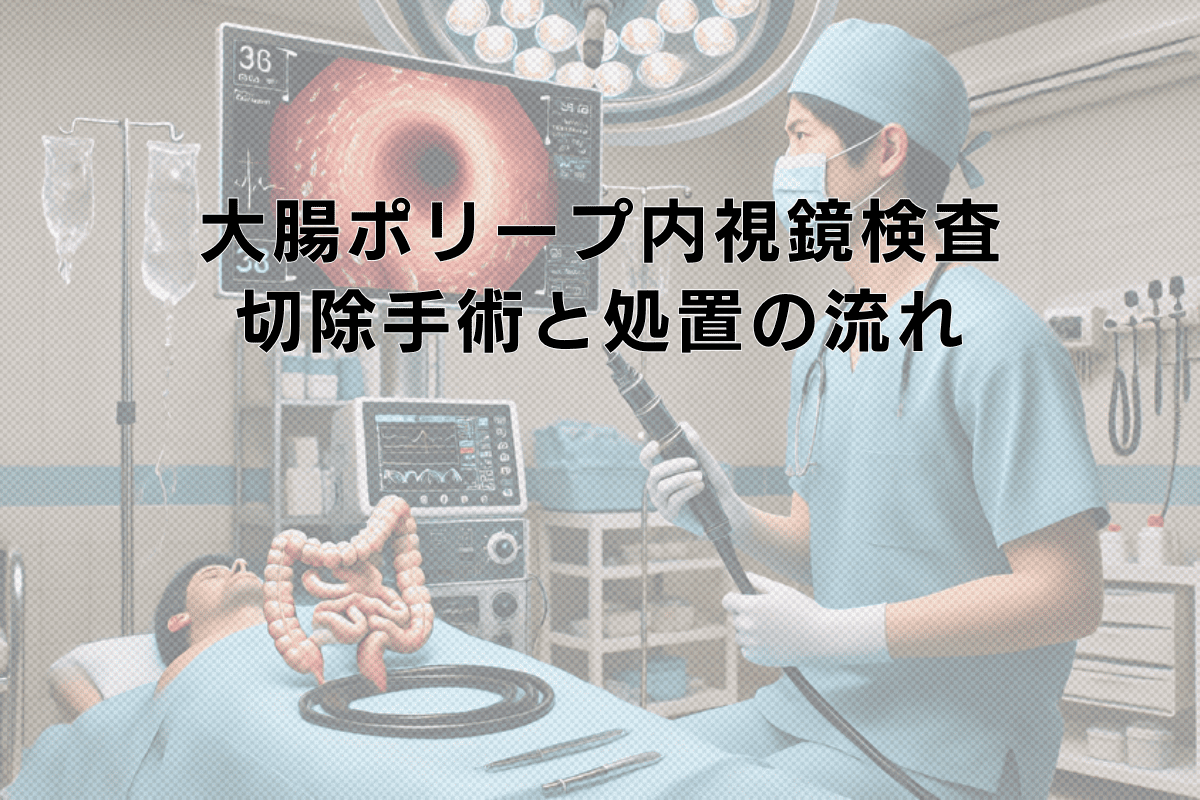
大腸カメラ検査を受けるタイミング
下痢がある程度続いており、血便や体重減少、夜間の腹痛など明らかに異常を感じる症状があるときは早めに受けるほうが安全です。
年齢や家族歴によっては定期的な検査が推奨されることもあるため、自分のリスクを客観的に把握しておくといいでしょう。
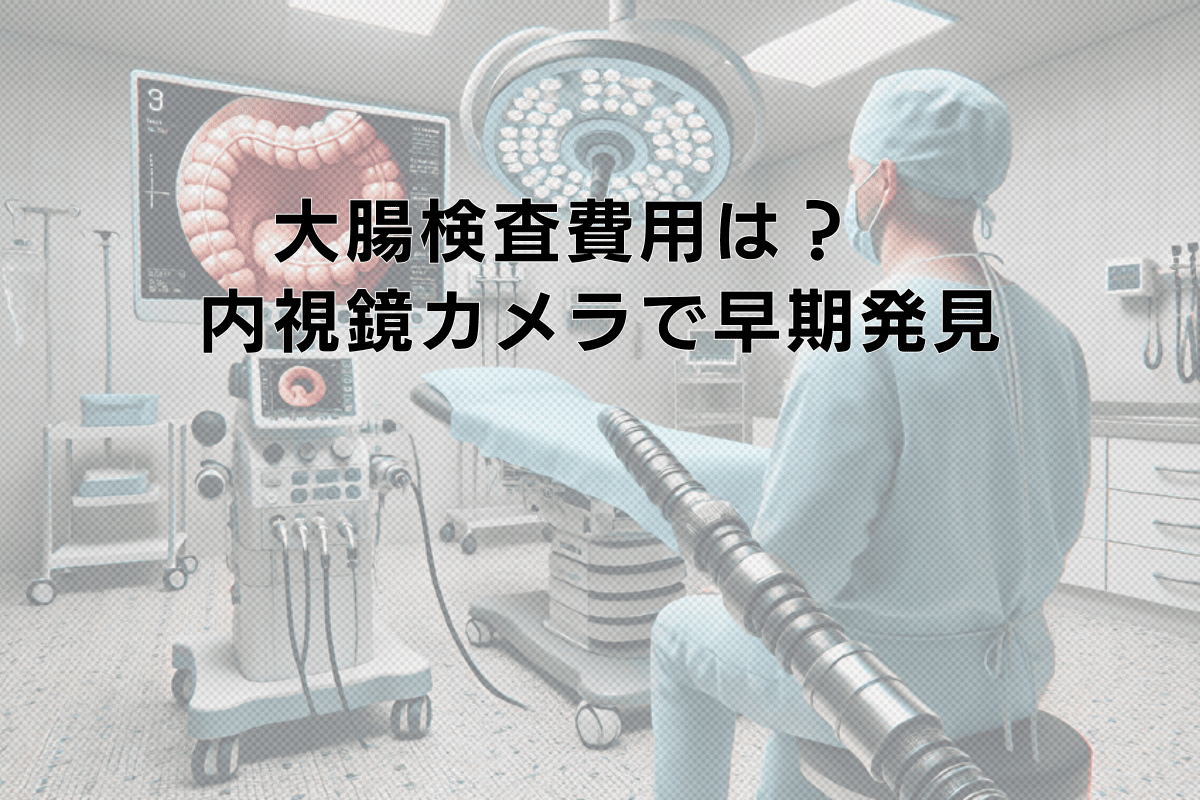
大腸カメラ検査の利点と注意点
| 利点 | 注意点 |
|---|---|
| 腸内を直接観察できるため確定診断に役立つ | 下剤の服用が必要で準備に時間がかかる |
| ポリープ切除など治療が同時に行いやすい | 検査中の不快感を避けるために鎮静剤が必要な場合がある |
| 組織検査が可能で原因診断に有利 | 検査後にまれに出血や腹痛が起こることがある |
受診前にチェックしたいポイント
下痢が止まらない状態がどの程度深刻なのかを見極めるためには、日々の生活状況や症状の推移を把握しておくと診察時に役立ち、医師に伝える情報が増えるほど、検査や治療の指針が立てやすくなります。
症状の日数や便の回数
下痢が始まってからの日数と、1日に何回程度トイレに行くのかを大まかに記録しましょう。とくに2週間以上続くようなケースは慢性化している可能性が高く、大腸カメラ検査が必要となるケースが増えます。
便の色や形状、出血の有無
普段の便との違いを把握しておくと、診断のヒントになるので、黄色い水様便や黒色便、粘液便、血液の混入など、便の形状や色の変化を正確に把握しておき、鮮血が混じる場合はできるだけ早く受診してください。
併発している症状
下痢だけでなく発熱や吐き気、食欲不振、だるさなどの全身症状があるかどうかも重要です。強い脱水感や体重減少があるときは深刻な疾患のサインを見逃さないようにしましょう。
日常生活の改善状況
食事内容を変えたり、アルコールを控えたり、ストレスを減らす努力をしても下痢が止まらないときは、器質的な異常の可能性が高まります。自分で取り組んだ改善策を記録し、効果があったかどうかを医師に伝えてください。
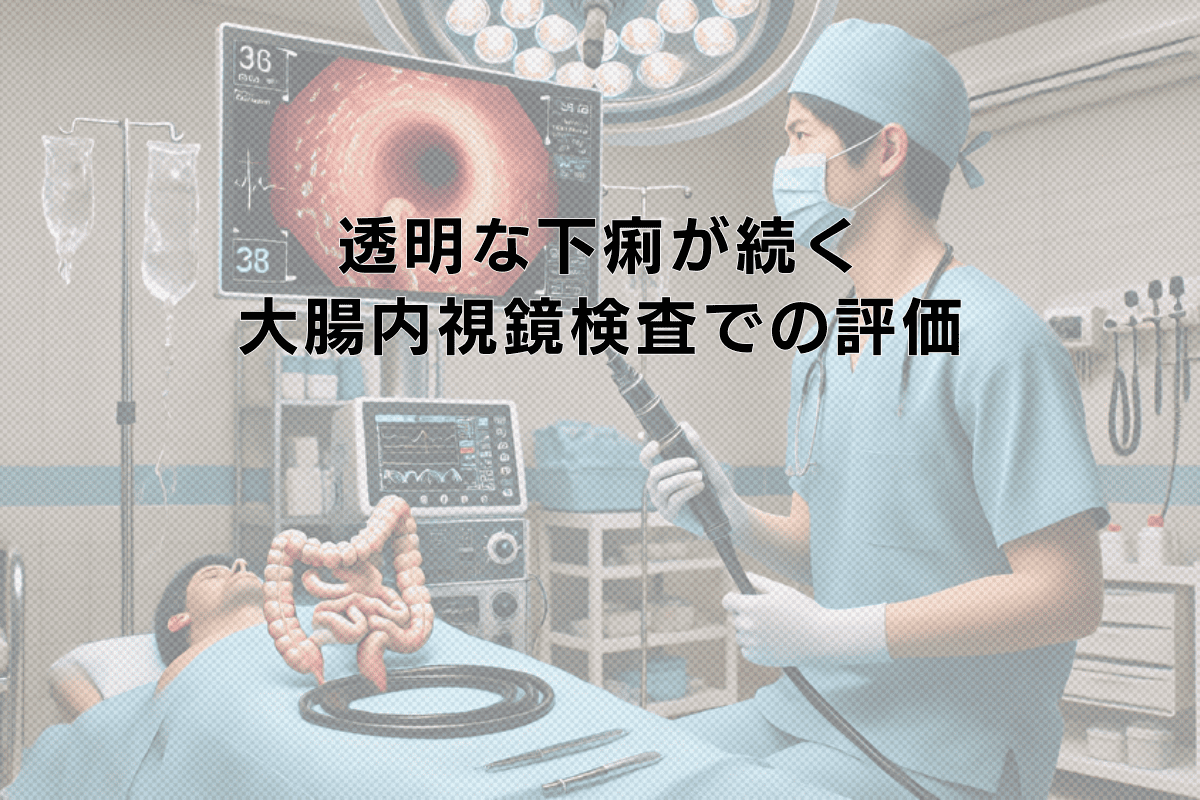
受診時に医師へ伝えるとよい項目
| チェック項目 | 具体例 | 医師への情報提供のメリット |
|---|---|---|
| 下痢の継続期間 | 2週間、1か月など | 慢性下痢かどうかの判定材料 |
| 排便回数 | 1日5回など | 症状の重症度の推測 |
| 便の性状 | 水様便、粘液便、血便 | 疾患の種類を絞りやすくなる |
| 付随症状 | 発熱、腹痛、嘔吐 | 原因の方向性を探りやすい |
下痢が止まらないときのセルフケア
下痢が止まらない時は病院での検査や治療が必要な場合も多いです。軽度の場合には生活習慣の見直しだけで改善するケースもありますが、セルフケアで症状が改善しないときは、早期に医療機関を受診してください。
水分補給と電解質バランス
長引く下痢によって水分や電解質が失われると、体力の低下やめまい、だるさの原因になるので、経口補水液などでミネラル補給を心がけるとともに、脱水症状を避けるために一定量の水分摂取を行います。
消化にやさしい食事
暴飲暴食を避け、消化にやさしい食べ物を選ぶと腸への負担が軽減します。おかゆ、うどん、野菜スープなど腹部に優しいメニューを心がけ、また香辛料の多い食品や脂肪分の多い食品は控えめにしましょう。
胃腸にやさしい食材の例
- おかゆや軟飯
- 白身魚やささみ
- 大根やにんじんなど加熱した野菜
- ヨーグルトなど発酵食品
ストレスマネジメント
精神的な緊張が下痢を誘発または悪化させる場合があり、適度な運動やリラックスできる時間を設けることを意識します。ストレスがたまると過敏性腸症候群のような機能性の不調も悪化しやすくなります。
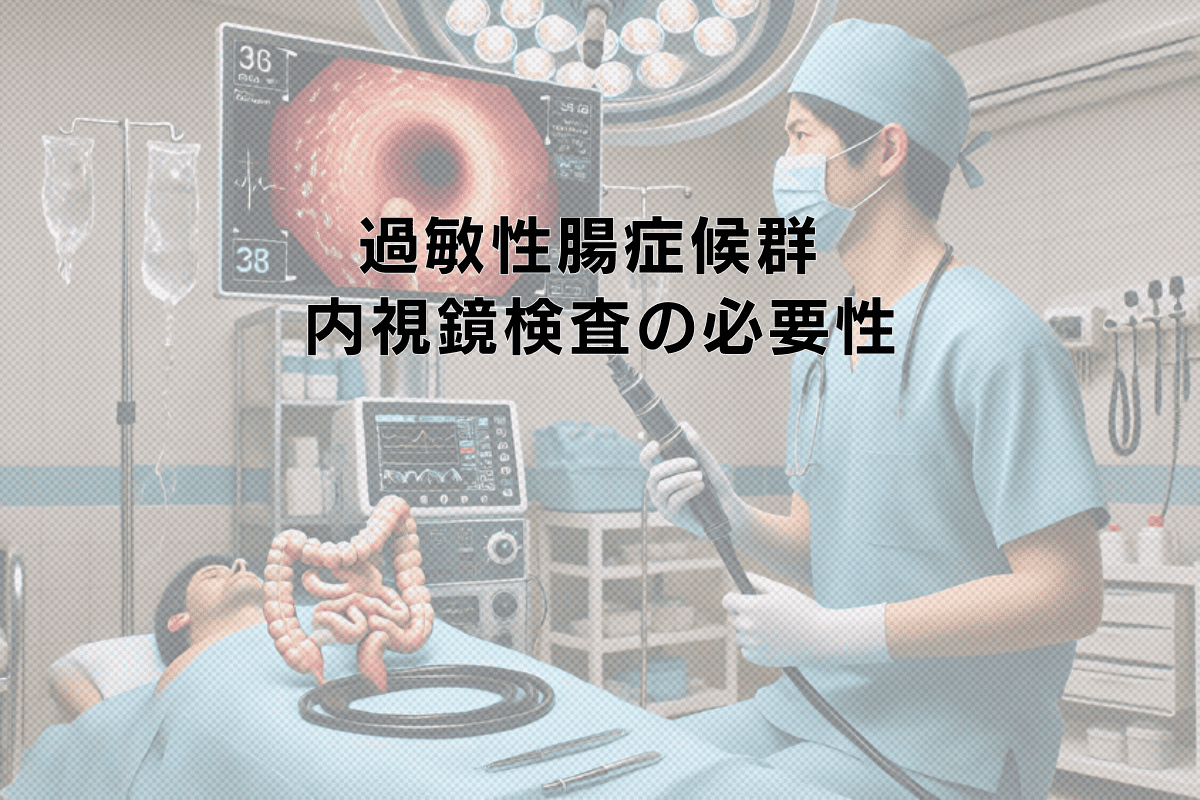
薬の使用について
市販の下痢止め薬は一時的に症状を和らげる手段にはなりえますが、原因自体を解決できないことがあります。感染性の腸炎では下痢止めによって有害物質を排出しにくくなる場合もあるため、注意が必要です。
自己判断で長期使用せず、医師に相談するほうが安心です。
下痢のときにおすすめの食材と避けたい食材
| おすすめの食材 | 理由 | 避けたい食材 | 理由 |
|---|---|---|---|
| おかゆ・うどん | 胃腸への負担が少ない | 辛いカレー・キムチ | 刺激が強く粘膜を傷つけやすい |
| 白身魚・ささみ | タンパク質が豊富で消化が良い | 脂っこい揚げ物 | 脂肪分が多く消化に負担 |
| 野菜スープ | ビタミン・ミネラル補給 | アルコール類 | 腸を刺激して炎症を悪化させる |
| 発酵食品(ヨーグルトなど) | 腸内環境を整えやすい | 炭酸飲料 | 腸を膨張させて不快感が増す |
大腸カメラ検査後の過ごし方と再検査の目安
大腸カメラ検査を受けたあとも油断せず、自身の状態をしっかりと観察することが大切です。必要に応じて再検査や別の治療を組み合わせることで、下痢が止まらない状態を解消するきっかけが見えてきます。
検査直後の注意点
鎮静剤を使用した場合は、検査後しばらくはぼんやりする可能性があるので、車の運転など危険を伴う行動は控え、できれば家族や知人に付き添ってもらったほうが安全です。検査後の腹部膨満感は時間とともに落ち着いていきます。
軽度の出血や腹痛がある場合
ポリープ切除や組織採取を行った場合、わずかな出血があることがあります。腹痛や出血量が増えてきたり、血便が続くようなら医師に相談してください。検査後数日は激しい運動を避け、安静を保つと安心です。
検査後に気をつけたい症状
- 下腹部の強い痛みが持続する
- 血便が続く、または増える
- 発熱や嘔吐などの全身症状が出る
- 極端な体力低下や立ちくらみがある
検査結果と次のステップ
検査結果に異常がなければ、原因が機能性の可能性があり、それでも下痢が止まらないときは、ストレス対策や食生活の再調整などさらに掘り下げた対処を行う必要があります。
一方で炎症やポリープなど何らかの異常が確認された場合は、医師の指示に従って治療を開始します。
定期的な検査が推奨されるケース
炎症性腸疾患のように再燃を繰り返す病気の場合や、大腸ポリープが見つかったケースでは、定期的なフォローアップ検査が推奨されます。再発防止や進行を防ぐため、医療機関を活用してください。
大腸カメラ検査後の経過観察の目安
| 状況 | 例 | 再検査の頻度 |
|---|---|---|
| ポリープを切除した | 5mm以上のポリープ | 1年以内に経過観察 |
| 炎症性腸疾患が疑われる | 潰瘍性大腸炎、クローン病 | 症状次第で適宜受診 |
| 異常なしだが下痢が継続 | 過敏性腸症候群を含む機能性腸疾患 | 症状が変化しなければ追加検査も検討 |
まとめ
長期間にわたって下痢が止まらないとき、大腸カメラ検査によって腸管内部を直接観察し、原因を絞り込むことができます。
特に血便や体重減少、夜間の排便などを伴う場合は早急な受診が望ましく、慢性的な腹痛や便通異常に悩む方も、内視鏡検査で器質的異常を確認し、治療方法を検討することが大切です。
生活習慣の改善やストレスの管理で軽減する場合もありますが、一向に良くならないと感じたら専門的な検査を受けることで安心につながります。
- 下痢 止まらない背景には、炎症性腸疾患や感染症、機能性腸疾患、内分泌異常などさまざまな要因がある
- 長引く下痢に対しては大腸カメラ検査で腸内を直接確認することが有効
- 血便や夜間排便、体重減少など重症度の高い症状がある場合は早期の受診を検討
- 検査後も症状の記録や生活習慣の見直しが重要で、必要に応じて再検査を受ける
- 放置すると脱水や栄養障害のリスクが高まるため、症状が長引けば医師に相談を
下痢が長引く人が意識したいポイント
| 意識したいポイント | 理由 | 具体的な工夫 |
|---|---|---|
| 食事内容を見直す | 腸への負担を減らし症状を和らげる | 香辛料、脂肪分は控えめに |
| 水分・電解質補給 | 脱水症を防止し体調を整える | 経口補水液の適切な摂取 |
| ストレス対策 | 過敏性腸症候群など機能性疾患を悪化させにくい | リラックス法や適度な運動 |
| 早めの検査受診 | 重篤な疾患を見逃さない | 大腸カメラ検査による原因究明 |
次に読むことをお勧めする記事
【常に下痢の症状が出る方へ – 大腸カメラ検査による原因特定】
下痢が止まらない原因の基本を押さえたら、次は実際の大腸カメラ検査による診断の流れについて知っておくと安心です。常に症状にお悩みの方に特に参考になる内容です。
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
検査を決めたら『何を食べていいの?』が次の疑問に。3日前からの具体的なメニュー例や下剤のコツを紹介しています。
参考文献
DuPont HL. Persistent diarrhea: a clinical review. Jama. 2016 Jun 28;315(24):2712-23.
Shen B, Khan K, Ikenberry SO, Anderson MA, Banerjee S, Baron T, Ben-Menachem T, Cash BD, Fanelli RD, Fisher L, Fukami N. The role of endoscopy in the management of patients with diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2010 May 1;71(6):887-92.
Marshall JB, Singh R, Diaz-Arias AA. Chronic, unexplained diarrhea: are biopsies necessary if colonoscopy is normal?. American Journal of Gastroenterology (Springer Nature). 1995 Mar 1;90(3).
Juckett G, Trivedi R. Evaluation of chronic diarrhea. American family physician. 2011 Nov 15;84(10):1119-26.
Brenner DM, Domínguez-Muñoz JE. Differential diagnosis of chronic diarrhea: an algorithm to distinguish irritable bowel syndrome with diarrhea from other organic gastrointestinal diseases, with special focus on exocrine pancreatic insufficiency. Journal of clinical gastroenterology. 2023 Aug 1;57(7):663-70.
Fan K, Eslick GD, Nair PM, Burns GL, Walker MM, Hoedt EC, Keely S, Talley NJ. Human intestinal spirochetosis, irritable bowel syndrome, and colonic polyps: A systematic review and meta‐analysis. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2022 Jul;37(7):1222-34.
Kamp EJ, Kane JS, Ford AC. Irritable bowel syndrome and microscopic colitis: a systematic review and meta-analysis. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2016 May 1;14(5):659-68.
Nagata N, Ishii N, Manabe N, Tomizawa K, Urita Y, Funabiki T, Fujimori S, Kaise M. Guidelines for colonic diverticular bleeding and colonic diverticulitis: Japan Gastroenterological Association. Digestion. 2019 Jan 14;99(Suppl. 1):1-26.
Sokic-Milutinovic A, Pavlovic-Markovic A, Tomasevic RS, Lukic S. Diarrhea as a clinical challenge: general practitioner approach. Digestive Diseases. 2022 May 10;40(3):282-9.
Burgers K, Lindberg B, Bevis ZJ. Chronic diarrhea in adults: evaluation and differential diagnosis. American family physician. 2020 Apr 15;101(8):472-80.