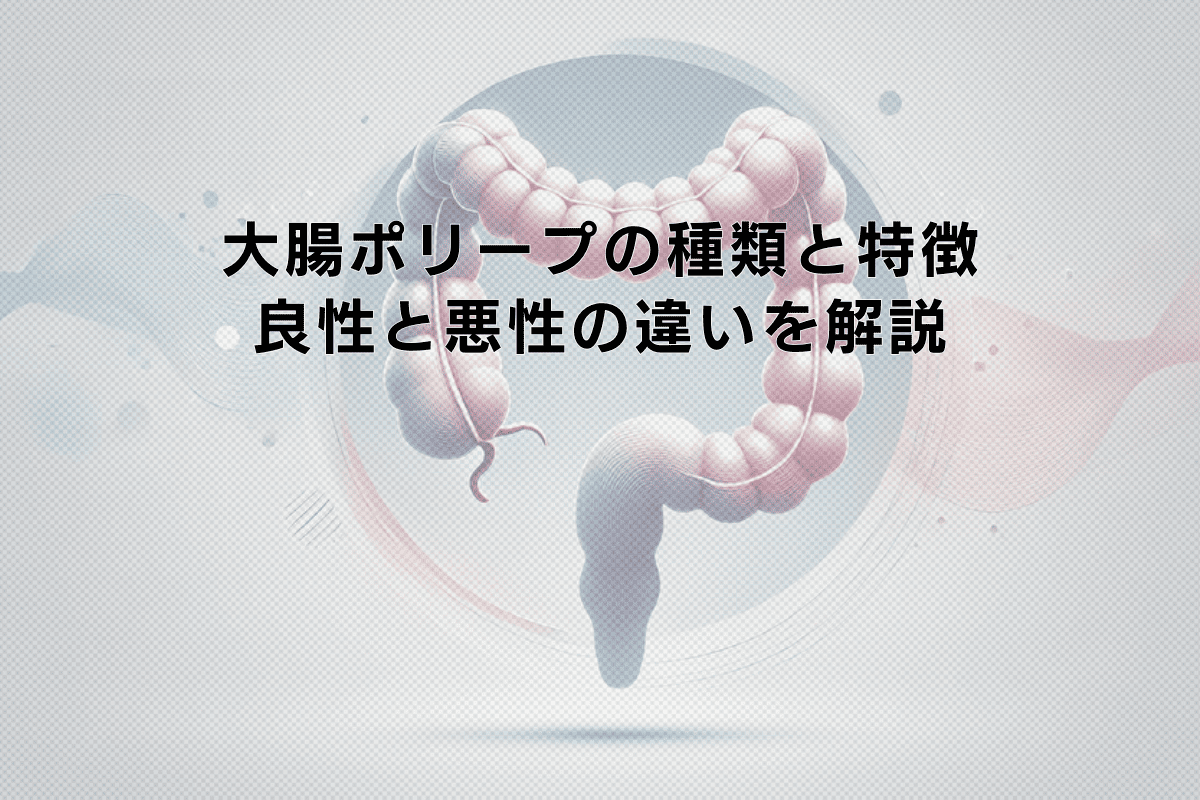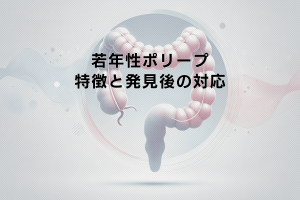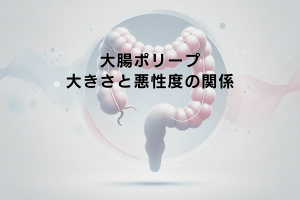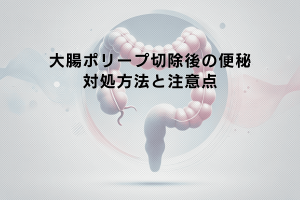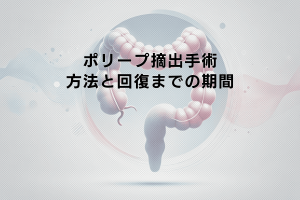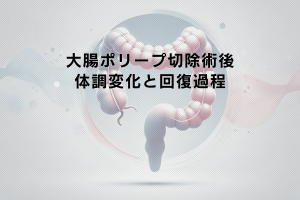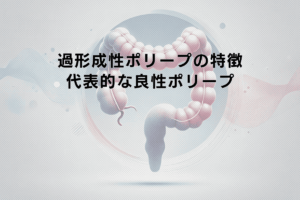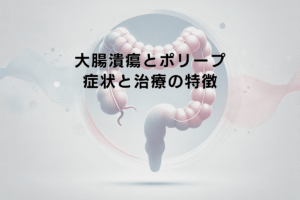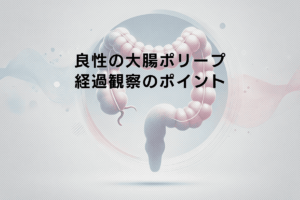大腸内視鏡などの検査で「ポリープがあります」と言われると、不安になる方が多いでしょう。
そもポリープとはどのようなものなのか、良性と悪性ではどう異なるのかを知っておくと、検査や治療のイメージがつかみやすくなります。
大腸内で見つかるポリープのなかには、そのまま放置するとがん化する可能性をもつものもあり、早期発見と対応が大切です。
この記事では大腸ポリープの特徴を種類別に解説し、見つかったときにどのような判断が必要かを説明します。
大腸ポリープとは何か
大腸の壁に隆起した組織が形成される状態で、粘膜が一部だけ盛り上がった形状や、茎のあるキノコ状の形を取る場合など、外見上のバリエーションが豊富です。
多くの場合は良性ですが、がん化のリスクがある種類のポリープもあるため、定期的な検査で早い段階で見つけ、切除や経過観察を行うことが重要です。
ポリープができる背景
大腸は食物のカスから水分を吸収し、便として形成する重要な器官で、粘膜細胞が絶えず新陳代謝を繰り返す一方、何らかの原因で細胞増殖が異常に進むと、隆起としてポリープが生じます。
原因としては加齢や食生活の乱れ、喫煙、飲酒、遺伝要因などが考えられています。
粘膜と腺の関係
大腸の内壁は粘膜で覆われその粘膜には腺組織があり、腺腫性ポリープの場合、腺組織が増殖してできることが多いです。一方、過形成性ポリープや炎症性ポリープなど、種類によって形成のメカニズムは若干異なります。
良性と悪性の境界
ポリープが小さいうちは良性のまま経過するものが多いですが、大きくなる過程で一部の細胞が異常増殖し、がん化に至る場合があります。全てのポリープが危険なわけではなく、組織検査で悪性所見があるかどうかを調べることが大切です。
大腸ポリープの発症率
中高年になるほど大腸ポリープをもつ人は増えると報告されていて、健康診断や人間ドックで、大腸内視鏡検査を受けて初めて見つかる方も少なくありません。
自覚症状がない状態でも存在することがあるため、定期的な検査を意識すると早期発見につながります。
大腸ポリープの年齢別発見割合
| 年代 | 発見される割合の傾向 | 主な理由 |
|---|---|---|
| 30代 | やや低い | 発生率自体が低めだが若年性ポリープも存在するケースあり |
| 40代 | 増加傾向 | 食生活や生活習慣病の影響が出始め、発見率が上がる |
| 50代 | さらに増加 | 検診で内視鏡検査を受ける機会が増え、見つかる例が多い |
| 60代 | 高い割合 | 加齢による細胞増殖の異常や長年の習慣からポリープができやすい |
大腸ポリープを軽視しないためのポイント
- 小さいポリープは自覚症状が乏しいことが多い
- 種類によってはがん化リスクが高い場合がある
- 家族歴や食生活の習慣を踏まえた早期検査が役立つ
良性と悪性の違い
大腸ポリープとがんは同じ腫瘍でも、細胞レベルで大きな違いがあります。
良性ポリープは基本的に周囲の組織に浸潤や転移を起こしませんが、悪性(がん化)するとまわりの組織を侵し、血流やリンパを介して別の臓器に転移する恐れが出てきます。
良性ポリープの特徴
良性ポリープは粘膜表面に限局して細胞増殖し比較的ゆっくり成長します。腫瘍が小さいうちは症状がほとんどなく、健康診断や大腸内視鏡検査で偶然見つかるケースが多いです。
腺腫性ポリープであっても大きさが小さく、組織検査で悪性所見がなければ定期的な観察だけで済む場合もあります。
悪性ポリープの特徴
悪性ポリープはがん細胞が含まれている、もしくはがん化の段階にあるポリープで、粘膜層を超えて腸管の壁に浸潤し始めるリスクがあるため、内視鏡で切除できる場合は早めに対応が必要です。
サイズが大きくなるほどがん化リスクも高まる傾向があるので、早期発見が重要になります。
ポリープとがんの違い
良性の状態から悪性の状態への連続性を想定すると、ポリープの段階で発見できれば治療の選択肢が広がります。
悪性は転移や再発のリスクを伴い、より大がかりな治療が必要になることがあるため、「ポリープとがんの違い」を理解して早期対応を心がけることが大切です。
良性・悪性の比較
| 分類 | 成長速度 | 浸潤・転移 | 治療 |
|---|---|---|---|
| 良性 | 比較的ゆっくり | なし | 観察または内視鏡切除 |
| 悪性(がん) | 進行が早まる場合がある | 浸潤・転移の可能性がある | 内視鏡治療または手術、必要に応じて他の治療 |
注意したいポイント
- サイズが大きくなるほどがん化率が上昇する
- 見た目だけでは良性・悪性を判断しにくい
- 組織検査が最終的な診断に役立つ
代表的な大腸ポリープの種類
大腸に発生するポリープには複数のタイプがあります。見た目や組織の性質によって分類され、それぞれがん化のリスクや治療方針が異なります。主な種類を把握しておくと検査結果の意味が理解しやすくなるでしょう。
腺腫性ポリープ
大腸ポリープの中でも頻度が高く、腺組織の異常増殖によって発生します。腺腫性のものは放置すると将来的にがん化するリスクがあるので、内視鏡で見つかった場合は積極的に切除することが推奨されるケースが多いです。
過形成性ポリープ
粘膜の過形成によって生じるポリープで、比較的がん化リスクが低いですが、サイズが大きかったり、大腸の特定部位(右側結腸など)にある場合、まれに進行性の病変と関連することもあります。形状や大きさ、位置によっては切除が検討されます。
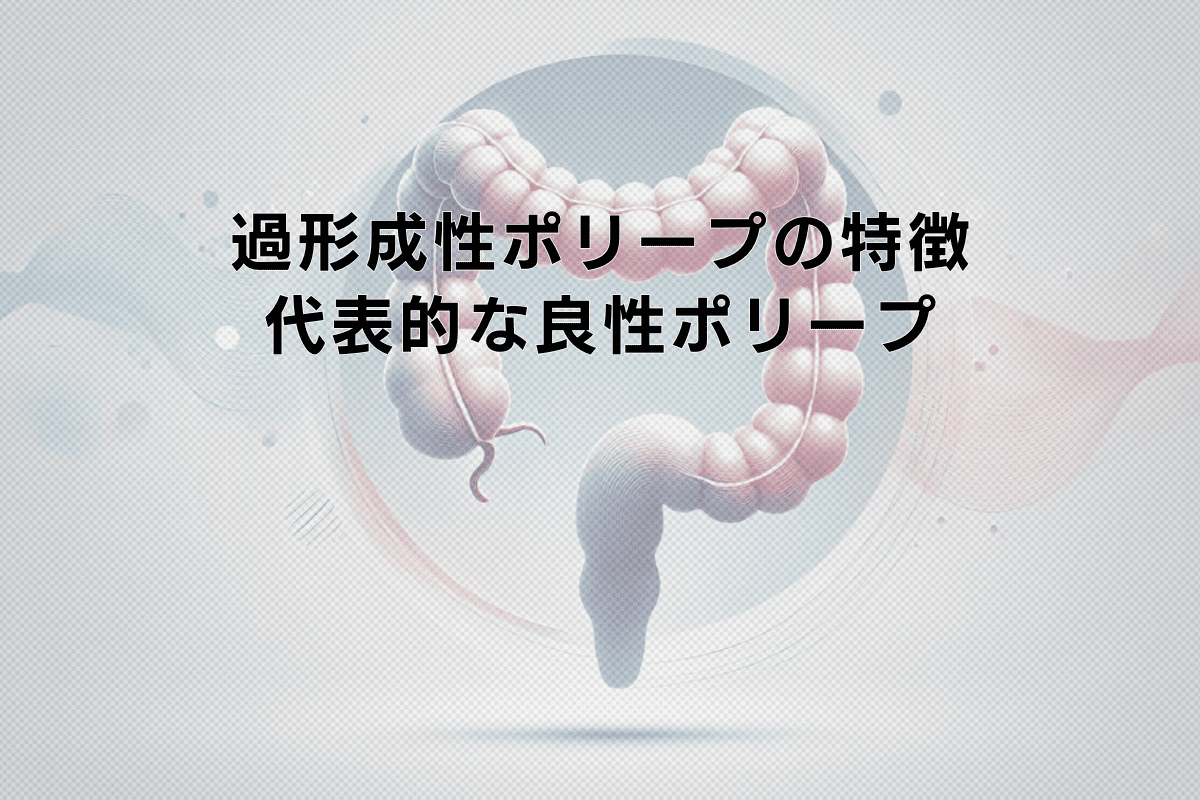
炎症性ポリープ
潰瘍性大腸炎やクローン病など、大腸の慢性的な炎症に伴って形成されるタイプです。炎症が強いときに一時的にポリープ状に見える場合もあり、基礎疾患の治療と並行して経過を観察します。
腺腫性と異なり、単独でのがん化リスクは高くありません。
稀少タイプ
家族性大腸腺腫症のように多発性のポリープを形成する遺伝的疾患や、過誤腫性ポリープなど、比較的まれなタイプもあります。遺伝性疾患が疑われる場合は専門的な検査・治療が必要になるケースがあります。
大腸ポリープの分類
| 種類 | 主な特徴 | がん化リスク |
|---|---|---|
| 腺腫性 | がんの前段階とされ、大きさが増すほど危険度が上がる | 高め |
| 過形成性 | 比較的リスクは低めだが、場所や大きさ次第で注意が必要 | 低め~中程度 |
| 炎症性 | 基礎疾患の炎症に伴って発生。単独でがん化に進む可能性は低い | 低い |
| 遺伝性疾患由来 | 家族性大腸腺腫症などがあり、多数のポリープが大腸内に発生する | 高リスクの場合も |
大腸ポリープの性質を見極めるために役立つ考え方
- 病理検査で腺腫性か過形成性かを判別する
- 大きさが大きい場合は積極的に切除することが多い
- 炎症性は基礎疾患のコントロールも重要
大腸ポリープとがんの関係
大腸内のポリープの一部は、長い年月を経てがん化するリスクがあり、特に腺腫性ポリープが大きくなるにつれ、可能性が高まります。ポリープとがんの関係を理解することで、定期的な検査の大切さを再確認できます。
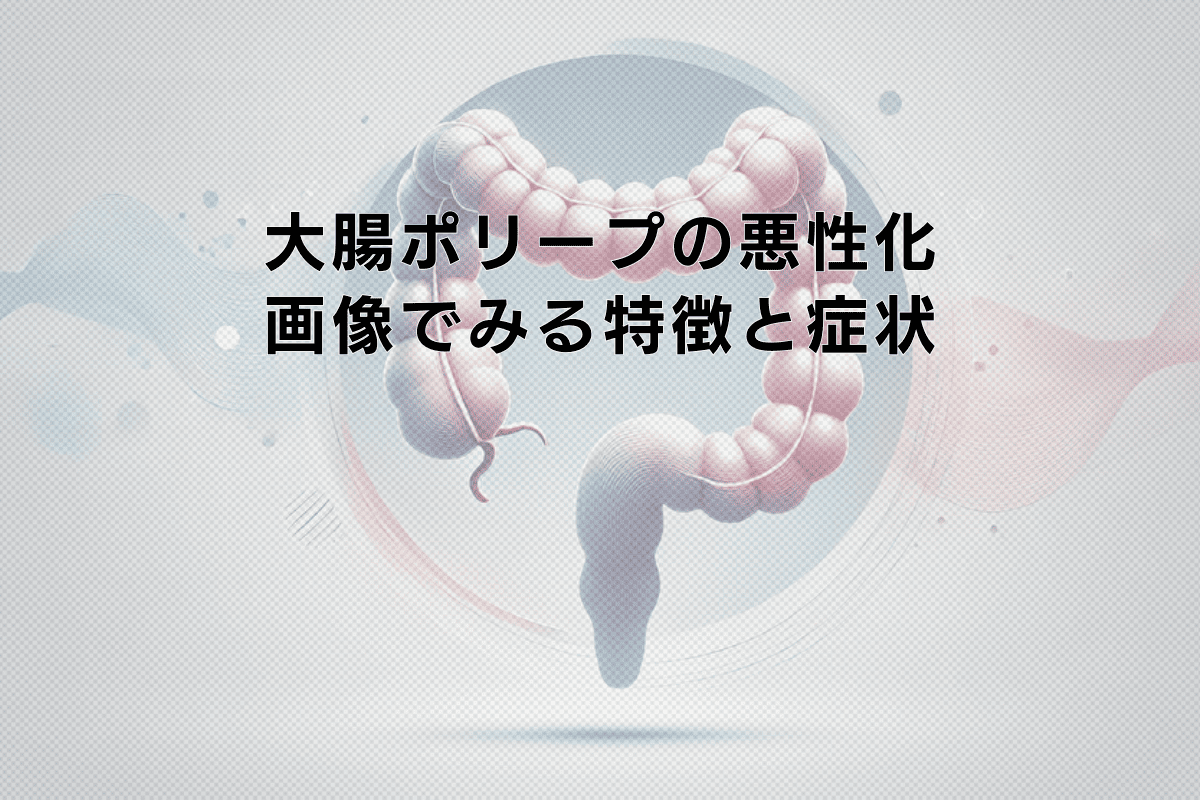
腺腫から腫瘍への進行
腺腫性ポリープが発見された場合、小さな段階で切除するとがんになる前に取り除けます。逆に放置すると細胞の異常増殖が進み、粘膜内がんや浸潤がんへと進行する危険があります。
全てが必ずがん化するわけではないものの、予防的観点から早めの処置が検討されるケースが多いです。
内視鏡検査での早期発見
大腸の状態を直接観察できる大腸内視鏡検査は、ポリープとがんを見分けるために非常に重要です。表面の形状や色調、触れた感触などから良悪性をある程度推測できますが、最終的には切除した組織の病理検査が決め手になります。
医師が悪性の可能性があると判断した場合は、その場で切除または生検を行うことが一般的です。
進行に関わる因子
- ポリープの大きさ
- ポリープの形状(茎付きか平坦かなど)
- 組織型(腺腫性か過形成性か)
- 患者の年齢・生活習慣
ポリープ発見後に注意したいこと
- 内視鏡検査で切除可能かどうか医師と相談する
- 組織検査で悪性かどうかを確認する
- 切除後のフォローアップ検査を怠らない
大腸がんとの関連性を理解するメリット
大腸ポリープが見つかった際に、がん化リスクを正しく理解できれば、検査や切除の必要性を実感しやすくなります。
腺腫性ポリープの中でも、形状が分葉状や隆起が大きい場合は要注意とされるため、医師の説明を聞いて早めに切除を決断するかどうかを検討すると安心です。

大腸ポリープとがんの関連
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 腺腫性ポリープ | がんの前段階として知られる。サイズが大きいほど危険度が上がる |
| 切除タイミング | 大きさや形状、患者のリスク要因により早期切除を提案されることが多い |
| フォローアップ | 再発リスクを考慮して定期的な内視鏡検査を受ける |
症状とリスク要因
大腸ポリープは小さいうちは無症状のことが多く、気づかないまま数年が経過するケースもありますが、ポリープが大きくなったり、炎症や潰瘍を起こすと便に血が混じるなどの症状が現れます。
さらに、飲酒や喫煙、食事内容などがリスク要因になることがあります。
症状の有無
初期の段階で顕著な症状が出ることは少なく、腫瘍が大きくなると便秘や下痢を繰り返す、血便が出るなどの異常がみられる場合があり、腹痛や便の形状変化に加え、貧血や体重減少が続く場合は早めの検査が大切です。
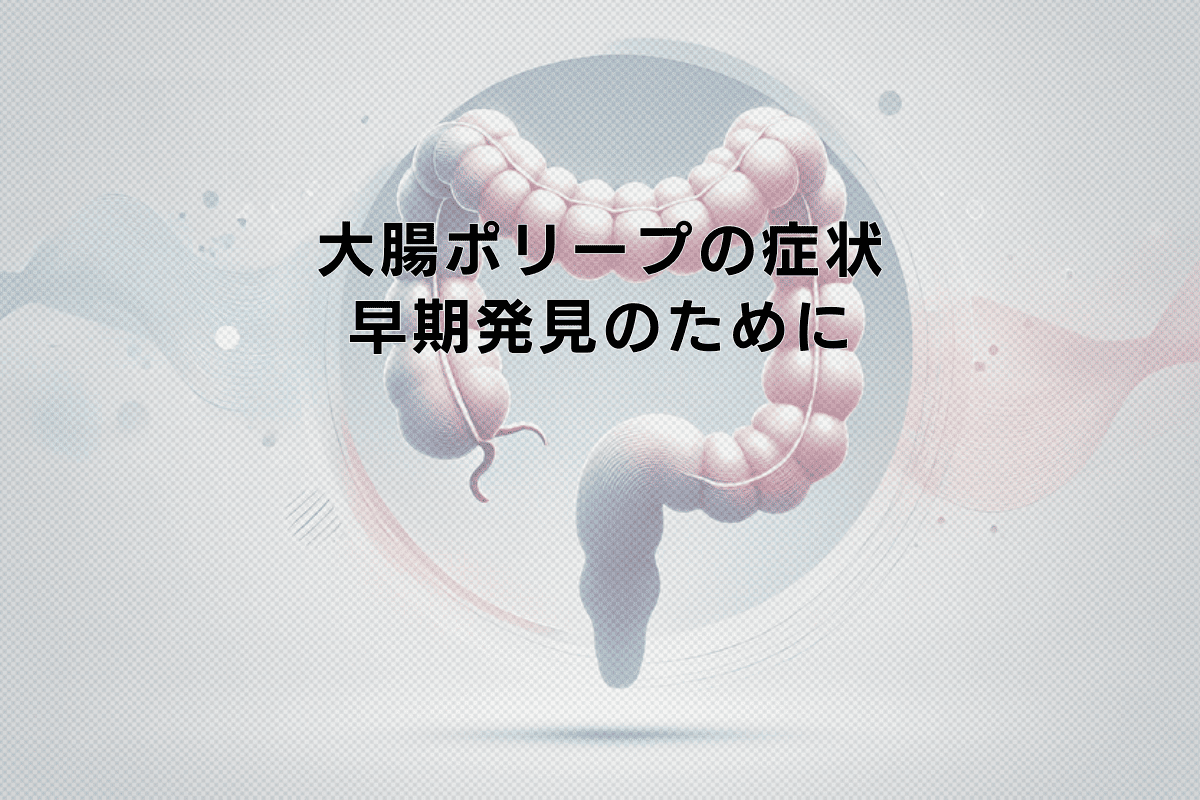
リスク要因となる生活習慣
大腸ポリープの発生と食生活には関連があると考えられており、肉や脂質中心の食生活で野菜や食物繊維が不足している場合、腸内環境が悪化しやすくなる可能性があります。
また、過度な飲酒や喫煙も有害物質が腸に影響を及ぼし、細胞増殖の異常を招くリスクが指摘されています。
大腸ポリープ形成を助長しやすい習慣
- 高脂肪・低食物繊維の食事
- 長年の喫煙
- 多量の飲酒
- 運動不足
遺伝的素因
家族性大腸腺腫症のように、多発性ポリープを形成しやすい遺伝性疾患があり、家族に大腸がんや多発性ポリープの方がいる場合は、早めに内視鏡検査を受けることでリスクを把握しやすくなります。
若くしてポリープが見つかることも珍しくないため、遺伝的要因がある方は定期検診を視野に入れたほうが安心です。
潰瘍性大腸炎などの既往
大腸の慢性炎症が続く潰瘍性大腸炎やクローン病などの病歴がある場合、炎症性ポリープができることがあります。
炎症性ポリープ自体のがん化リスクはそれほど高くありませんが、基礎疾患に伴う合併症や腸粘膜のダメージを考慮しながら定期検査を行うことが望ましいです。

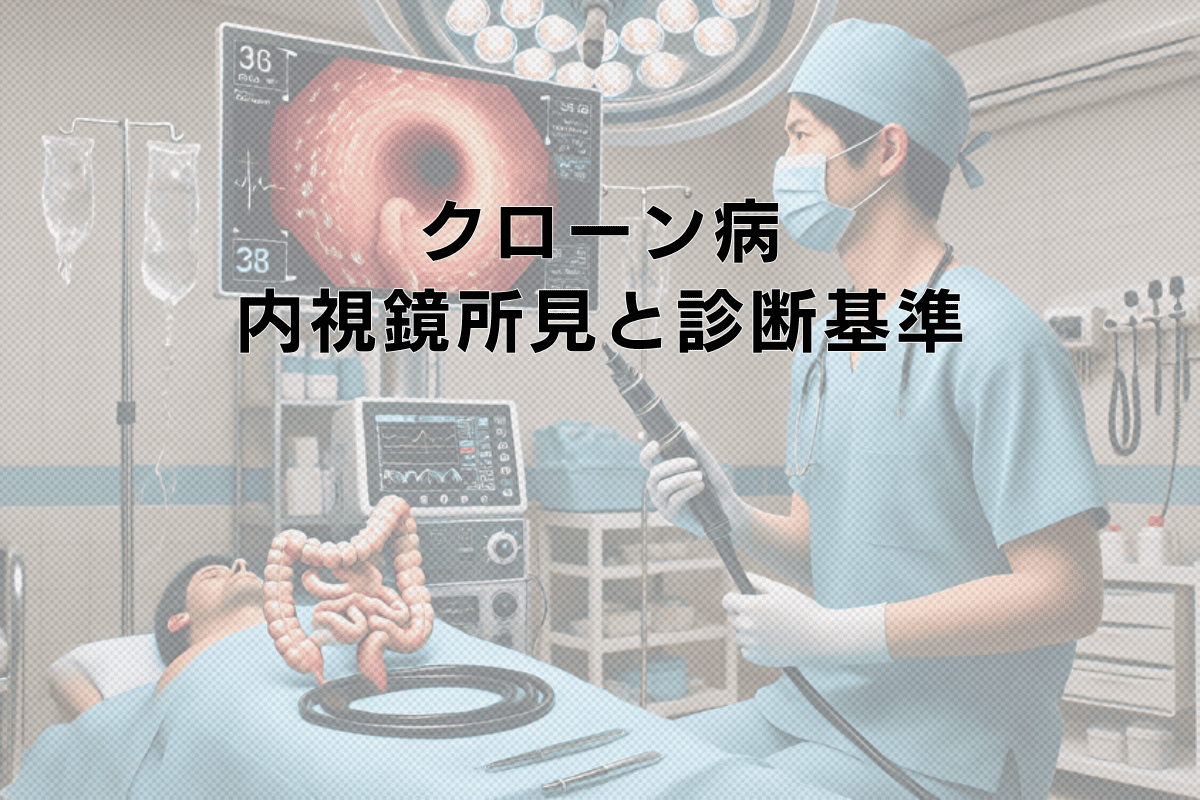
大腸ポリープを疑う症状
| 症状 | 備考 |
|---|---|
| 血便 | 腸管内の粘膜が傷つくと便に血が混じる |
| 下痢・便秘の繰り返し | 大きなポリープが通過障害を引き起こす可能性 |
| 腹痛・お腹の張り | 腸内に腫瘍があると痛みや張りが続く場合あり |
| 体重減少 | 消化吸収の異常や慢性炎症で栄養状態が悪化 |
生活習慣を見直すポイント
- 肉類と野菜のバランスを考慮する
- 適度な運動を取り入れる
- 喫煙はできる限り控える
- アルコール摂取量を調整する
大腸ポリープの検査方法
大腸ポリープの有無や種類を確認するための代表的な検査は、大腸内視鏡(大腸カメラ)と便潜血検査、CTコロノグラフィなどです。
精密に観察するなら大腸内視鏡がもっとも有用で、疑わしい病変をその場で切除・生検できるという大きなメリットがあります。
便潜血検査
健康診断で実施されることが多い簡易的な検査で。肉眼では見えない血液を便の中から検出します。陽性の場合は、大腸ポリープや大腸がんの可能性が否定できないため、追加の内視鏡検査を案内されるケースが多いです。
ただし、陰性でも病変がないと断言はできないため、大腸ポリープ、潰瘍性大腸炎などの既往がある方は大腸カメラ検査の検討が必要です。

大腸内視鏡検査
大腸の内部を直接観察できる検査方法で、ポリープが疑われる部位を詳細に確認でき、検査前には下剤で腸内をきれいにし、肛門からカメラを挿入して粘膜を観察します。
ポリープが見つかれば、サイズや形状によっては内視鏡下で切除することが可能で、病理検査で良性か悪性かを確かめられる点も大きな特徴です。

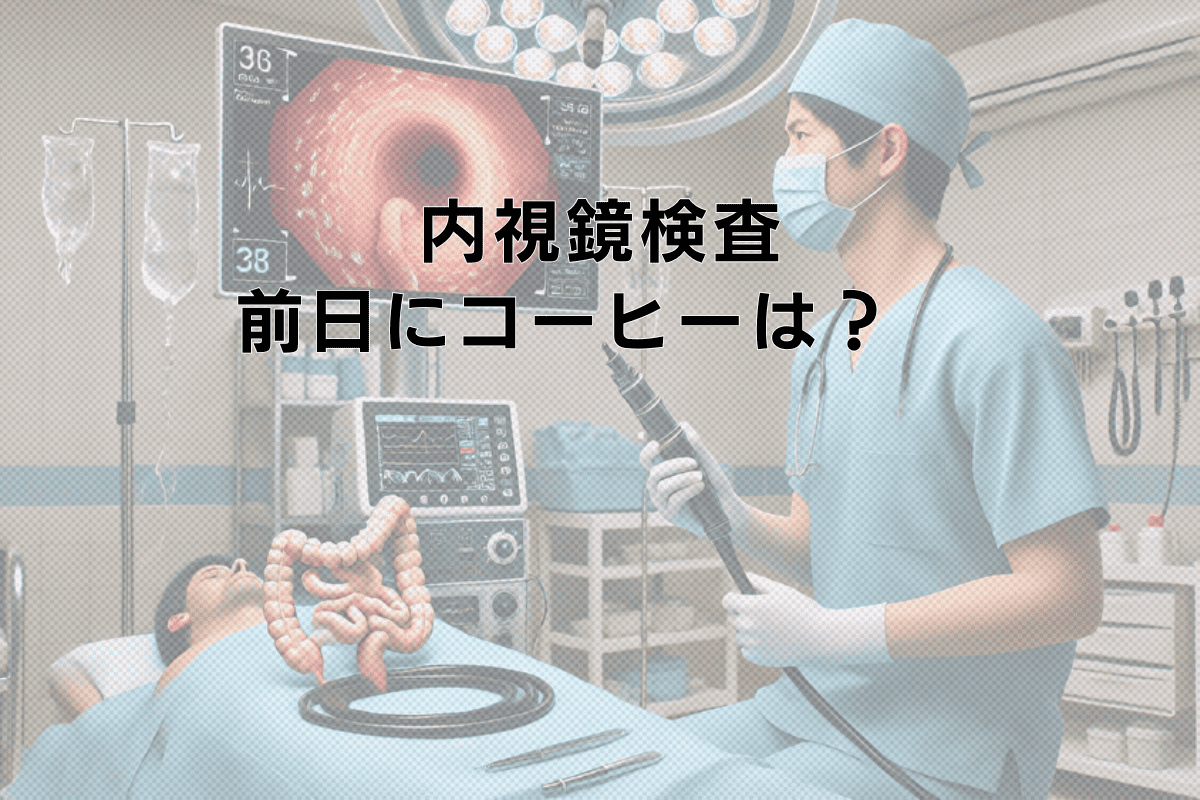
検査手順とポイント
| 手順 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| 前処置 | 下剤を飲んで腸内をきれいにする | 視野確保がしやすくなり、小さな病変も発見しやすい |
| 挿入 | 肛門からスコープを入れて大腸全体を観察 | 直接観察により病変の正確な把握ができる |
| ポリープ切除 | スネアなどの器具を用いてポリープを切除 | がん化予防や病理検査のための組織採取が可能 |
| 組織検査 | 切除したポリープの細胞を顕微鏡で調べる | 良性・悪性の確定診断と治療方針の決定に役立つ |
大腸内視鏡検査中の不安を軽減するための工夫
- 鎮静剤を使ってリラックスした状態で検査を受ける
- 痛みの少ない挿入技術を持つクリニックを選ぶ
- 恥ずかしさを軽減するための専用着が用意されている施設もある
CTコロノグラフィ
CTスキャンを使って大腸を3D画像化し、腫瘍の有無を間接的に観察する方法です。実際に内視鏡を挿入しないため、身体的負担が軽いと感じる方もいます。
しかし病変が見つかった場合、最終的には内視鏡検査で切除や生検を行わなければ正確な診断ができないので、スクリーニングとして使われることがありますが、内視鏡検査に比べると確定的な診断力は限定的です。
他の検査方法
超音波内視鏡やMRI検査など、状況に応じて使い分ける手段はありますが、大腸ポリープの診断精度や治療方針の判断という意味では、大腸内視鏡が主軸となることが多いです。
治療と予防
大腸ポリープの治療は主に内視鏡による切除が中心で、大きさや位置、数、病理学的所見などによって切除方法が選ばれ、がん化のリスクを減らすことを目指します。また、生活習慣の改善や定期的な検査が予防や再発防止に役立ちます。
内視鏡的切除の方法
スネアと呼ばれるワイヤー状の器具でポリープを根元から切除する手技が一般的です。
ポリープが小さい場合はポリペクトミー、大きめのポリープや平坦型の場合はEMR(内視鏡的粘膜切除術)やESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)などが選択されることもあります。
いずれの場合も、出血リスクや穿孔リスクを最小限に抑えながら行われます。
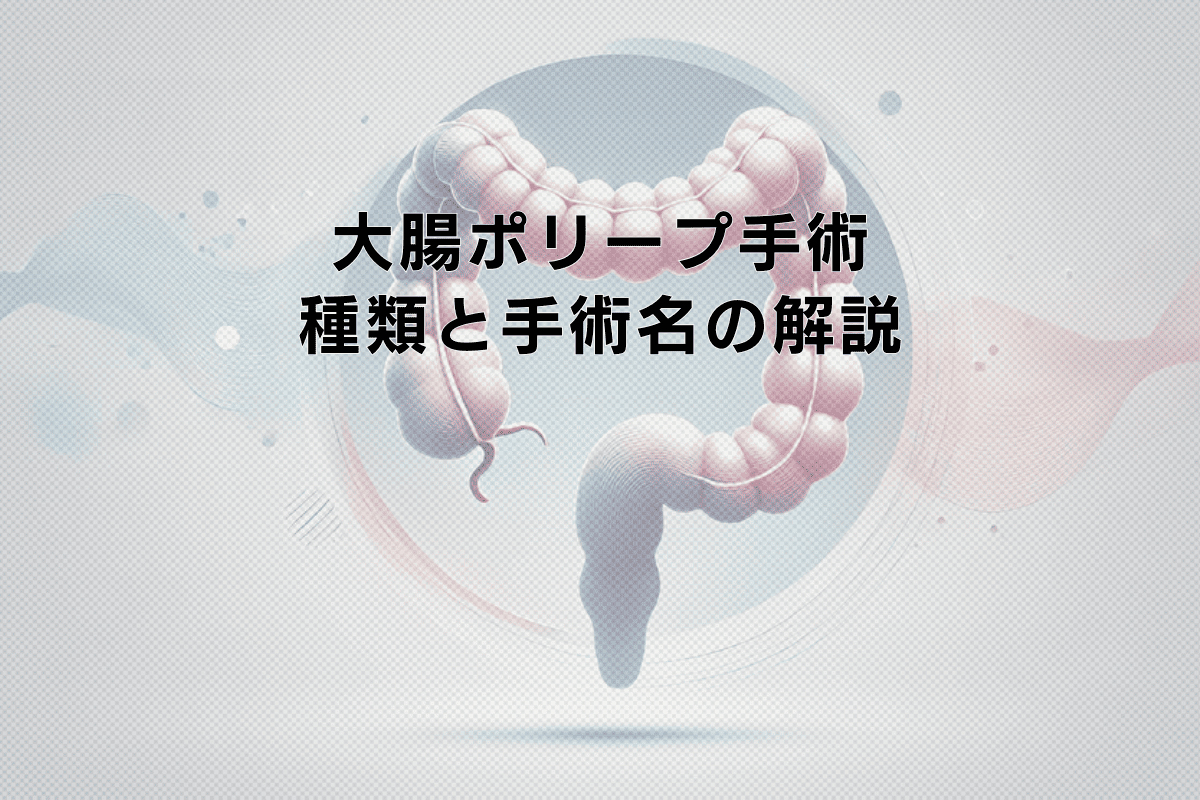
大腸ポリープの主な切除技術
| 手技 | 対象となるポリープ形状 | 特徴 |
|---|---|---|
| ポリペクトミー | 茎付きの小さなポリープ | 電気スネアを使用し、茎の部分を焼き切って摘出する |
| EMR(粘膜切除術) | 比較的大きい表在型ポリープ | 粘膜下に液体を注入し浮かせた上でスネアで切除する |
| ESD(粘膜下層剥離術) | より広範囲の病変や平坦型ポリープ | 専用ナイフで粘膜下層を剥離しながらポリープを一括切除する |
外科手術が必要なケース
ポリープが大きく、内視鏡では完全切除が難しい場合や、すでに深く浸潤した悪性病変と確認された場合は、外科的手術が検討されます。腫瘍の進行度や場所によっては、大腸の一部を切除し、リンパ節の摘出も行うケースがあります。
術前・術後での内視鏡検査や化学療法など、複数の治療法を組み合わせることもあります。
再発防止のためのアプローチ
ポリープを切除した後でも、新たなポリープができる可能性は残るので、再発を防ぎ、健康な腸を保つためには、定期的な内視鏡検査と生活習慣の見直しが大切になります。
内視鏡検査の頻度は個人のリスク要因や医師の判断によりますが、1~3年おきに検査を行う方が多いです。
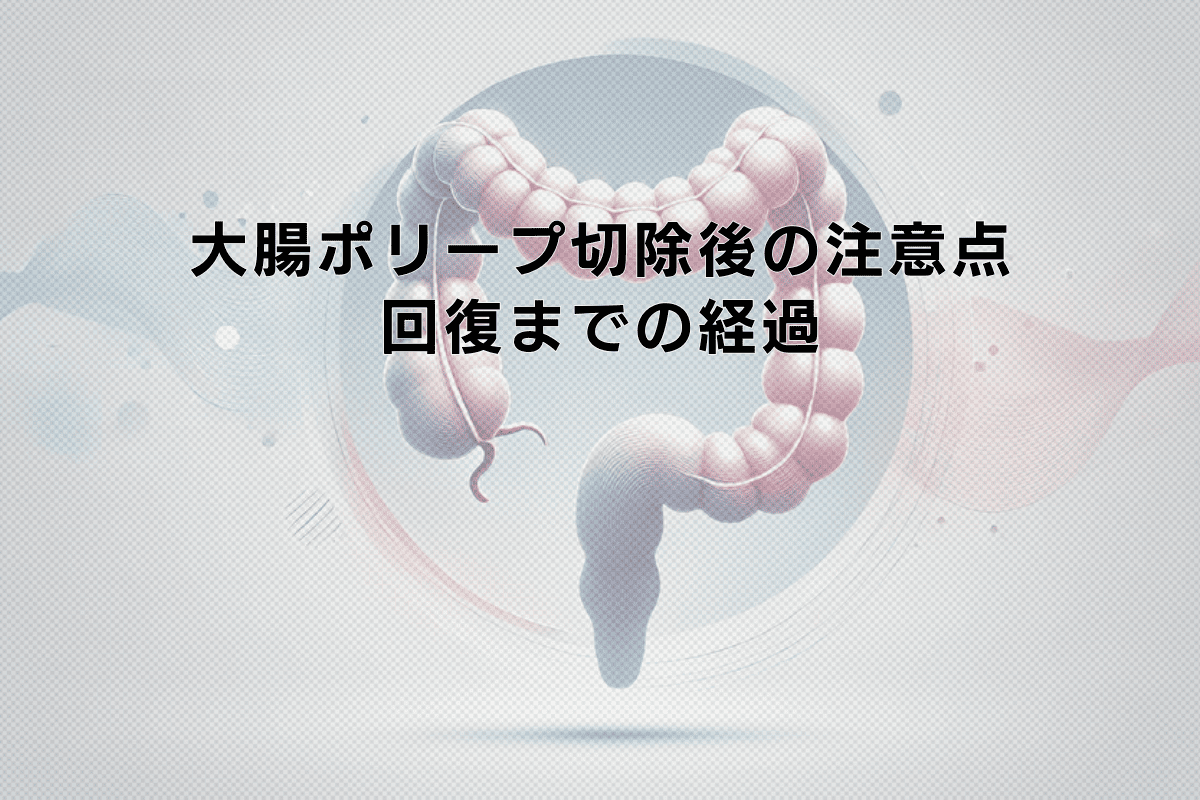
生活習慣改善リスト
- 野菜や果物を増やしたバランスの良い食事を心がける
- 適度な運動を継続する
- 飲酒や喫煙の量をできるだけ減らす
- 規則的な排便習慣を維持する
予防医学の観点
大腸内視鏡検査を早めに受けることは、ポリープを「がん化する前」に見つけて対処するうえで有効です。高脂肪食や不規則な生活が続いていると自覚がある場合は、定期健診にプラスして内視鏡検査の導入を検討します。
大腸ポリープの予防と再発防止に役立つ取り組み
| 取り組み | 効果 |
|---|---|
| 定期検査の受診 | 新規ポリープや再発ポリープを早期発見できる |
| 腸内環境の改善 | 食物繊維や発酵食品で善玉菌を増やし腸を健康に保つ |
| 適度な運動 | 腸の蠕動を促進し、便秘を予防できる |
| ストレスマネジメント | ホルモンバランスを整え、免疫力を高める |
よくある質問
大腸ポリープについては、検査や治療、再発の可能性などで不安が生じやすいものです。代表的な疑問を解説しますので、受診や治療を検討する際の参考にしてください。
- ポリープが見つかったら必ず切除が必要ですか?
-
大きさや形状、組織型などによります。小さな過形成性ポリープなどはがん化リスクが低く、定期的に観察を行う場合もあります。
一方、腺腫性でサイズが大きめのポリープや悪性所見が疑われるものは、内視鏡による切除が推奨される傾向が強いです。
- 切除後に痛みや出血はありますか?
-
ポリープ切除後、少量の出血が見られることはありますが、多くの場合は自然に止まり、痛みについても大きなポリープを切除した場合を除けば、それほど強くはありません。
医師の指示通りに安静を保ち、食事や運動を控えると安全です。
- 大腸ポリープとがんの違いは何が決め手になるのでしょうか?
-
ポリープとがんの違いをはっきりさせるには、内視鏡で切除または生検し、病理検査で細胞の状態を確認することが不可欠です。見た目だけでは良性か悪性かを判断しづらい場合もあるため、組織検査が大切なステップになります。
- 再発予防のために食生活で気をつけるポイントを教えてください
-
野菜や果物、海藻、豆類を意識的に摂り、腸内細菌を整えることが推奨されます。脂質や糖分の高い食品ばかりに偏らないようにし、適切な摂取カロリーを守ることも大切です。
アルコールや喫煙を控え、規則正しい睡眠とストレス管理を行うとより効果的です。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸ポリープの症状と早期発見のために知っておきたいこと】
大腸ポリープの種類について理解が深まると、具体的な症状や早期発見のポイントについても知りたくなる方が多いようです。予防と健康管理との意外な繋がりが見えてくる内容です。
【大腸がん症状を知る 兆候から治療まで】
ポリープと大腸がんは深い関係があります。がんの初期症状や検査法も知っておくことで、将来の不安を減らせます。
参考文献
Bujanda L, Cosme A, Gil I, Arenas-Mirave JI. Malignant colorectal polyps. World journal of gastroenterology: WJG. 2010 Jul 7;16(25):3103.
Aarons CB, Shanmugan S, Bleier JI. Management of malignant colon polyps: current status and controversies. World Journal of Gastroenterology: WJG. 2014 Nov 21;20(43):16178.
Hassan C, Zullo A, Risio M, Rossini FP, Morini S. Histologic risk factors and clinical outcome in colorectal malignant polyp: a pooled-data analysis. Diseases of the colon & rectum. 2005 Aug 1;48(8):1588-96.
Sullivan BA, Noujaim M, Roper J. Cause, epidemiology, and histology of polyps and pathways to colorectal cancer. Gastrointestinal Endoscopy Clinics. 2022 Apr 1;32(2):177-94.
Brown IS, Bettington ML, Bettington A, Miller G, Rosty C. Adverse histological features in malignant colorectal polyps: a contemporary series of 239 cases. Journal of clinical pathology. 2016 Apr 1;69(4):292-9.
LOTFI AM, SPENCER RJ, ILSTRUP DM, MELTON III LJ. Colorectal polyps and the risk of subsequent carcinoma. InMayo Clinic Proceedings 1986 May 1 (Vol. 61, No. 5, pp. 337-343). Elsevier.
Ginsberg GG, Al-Kawas FH, Fleischer DE, Reilly HF, Benjamin SB. Gastric polyps: relationship of size and histology to cancer risk. American Journal of Gastroenterology (Springer Nature). 1996 Apr 1;91(4).
Netzer P, Forster C, Biral R, Ruchti C, Neuweiler J, Stauffer E, Schönegg R, Maurer C, Hüsler J, Halter F, Schmassmann A. Risk factor assessment of endoscopically removed malignant colorectal polyps. Gut. 1998 Nov 1;43(5):669-74.
Øines M, Helsingen LM, Bretthauer M, Emilsson L. Epidemiology and risk factors of colorectal polyps. Best practice & research Clinical gastroenterology. 2017 Aug 1;31(4):419-24.
Winawer SJ, O’brien MJ, Waye JD, Kronborg O, Bond J, Frühmorgen P, Sobin LH, Burt R, Zauber A, Morson B. Risk and surveillance of individuals with colorectal polyps. Who Collaborating Centre for the Prevention of Colorectal Cancer. Bulletin of the World Health Organization. 1990;68(6):789.