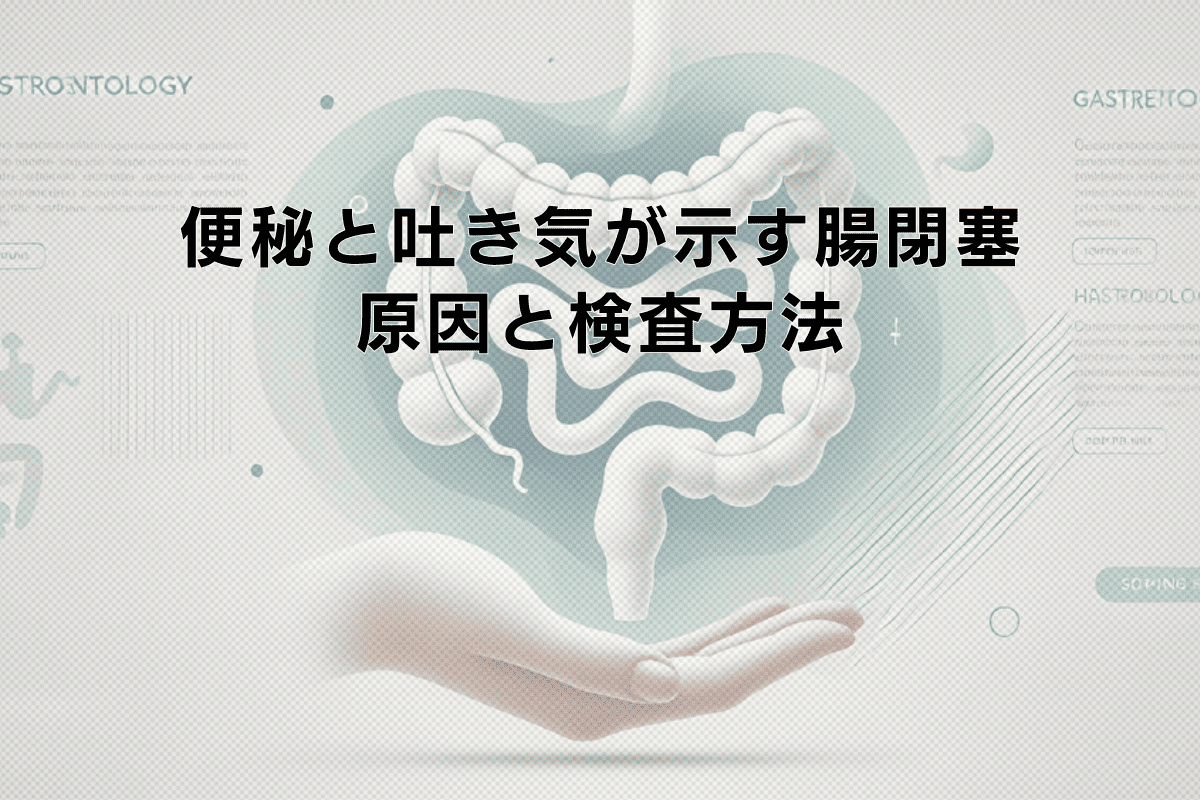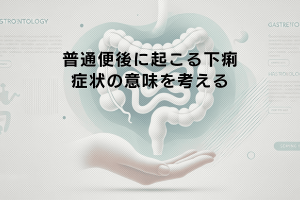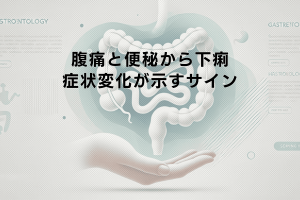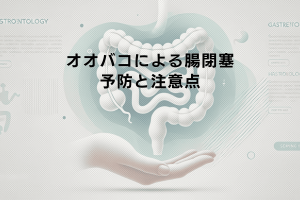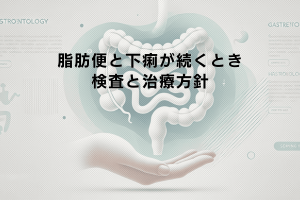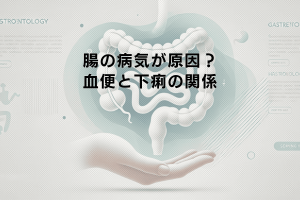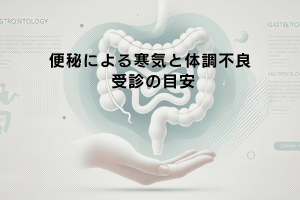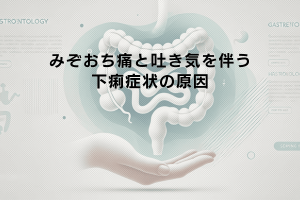便秘が続いて吐き気を伴うとき、胃腸の働きに大きな負荷がかかっている可能性があります。
さらに状態が進行すると腸閉塞を疑う必要があります。腸が塞がると内容物が行き場を失い、強い腹痛や嘔吐などを起こすので注意が必要です。
本記事では便秘と吐き気が同時に生じる背景、腸閉塞に至るメカニズム、早めに行いたい検査方法や内視鏡を利用する理由などを詳しく解説し、日常で気をつけたい点も紹介します。
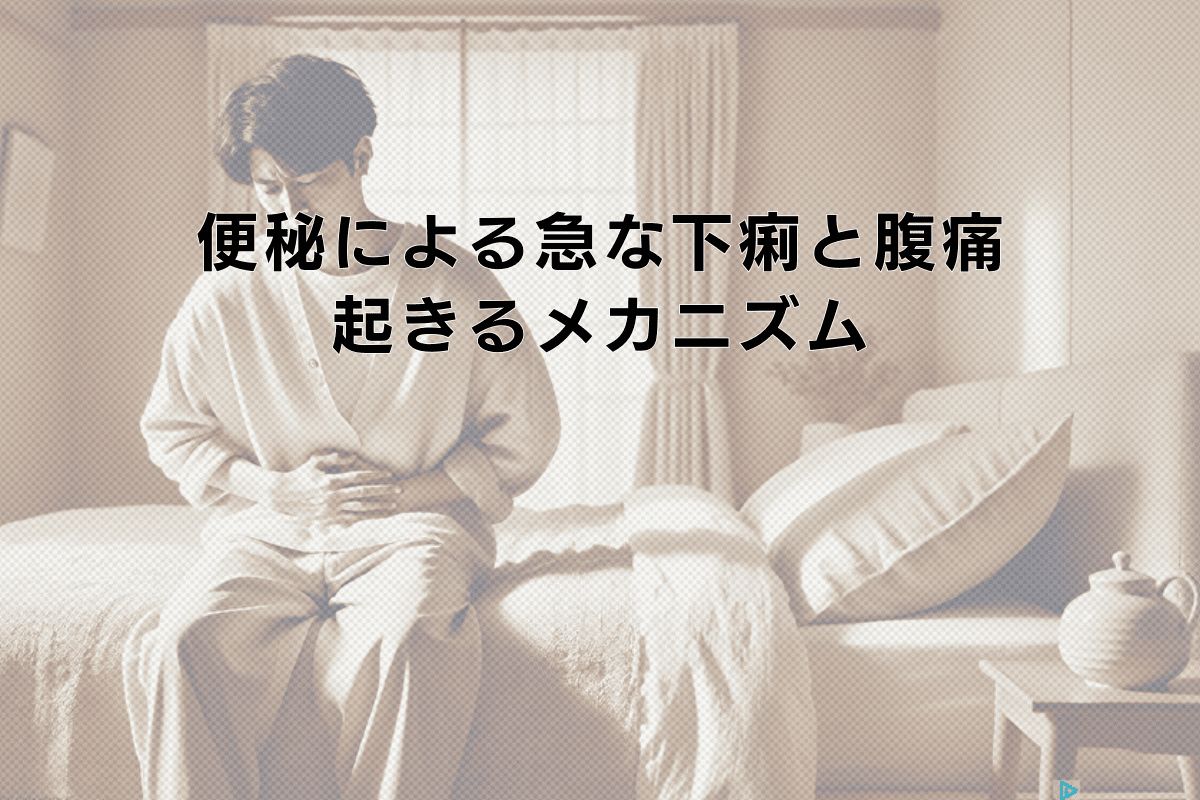
便秘と吐き気が同時に起こる理由
消化管のトラブルは生活に大きな影響を与えます。便秘に吐き気が重なる場合は、単なる食事の乱れだけではなく、腸管の動きそのものに異常があるかもしれず、原因を知ることが状態の悪化を防ぐうえでとても大切です。
胃腸の動きに関する基本的な仕組み
胃や腸は、食べた物を消化・吸収しながら大腸へ送る役割を担い、胃酸や消化酵素、腸の蠕動運動などが連携し、スムーズに内容物を運びます。ここで何らかの異常が生じると、排便のリズムが崩れ、便秘や吐き気を起こします。
腸の蠕動運動が弱まると、消化管に滞留する時間が延び便が固くなりやすくなり、その状態で食べ物を摂取し続けると胃腸に負担がかかり、吐き気を感じることがあるのです。
体の仕組みとして、胃から腸へと順に移動する流れが妨げられると、上部消化管にも影響が及びやすくなります。
消化管の通過障害と症状の関係
腸管内の内容物が順調に進まないと、腸内にガスや便がたまりやすくなり、消化管の通過障害が強まると腹部膨満が顕著になり、吐き気や腹痛が発生する可能性が高いです。
便秘が長期化して腸閉塞が疑われる状況では、食べ物や水分が先に進めないため、腹部の激しい張りや嘔吐を伴うことがあります。
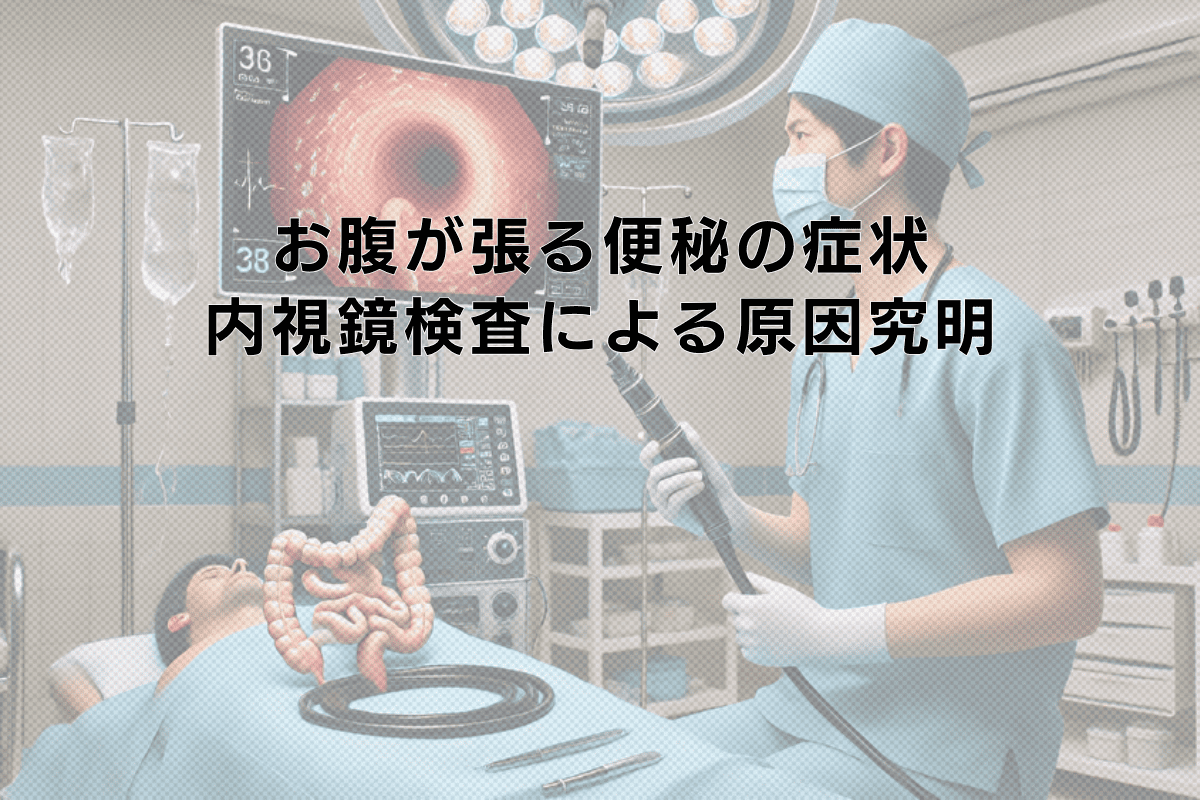
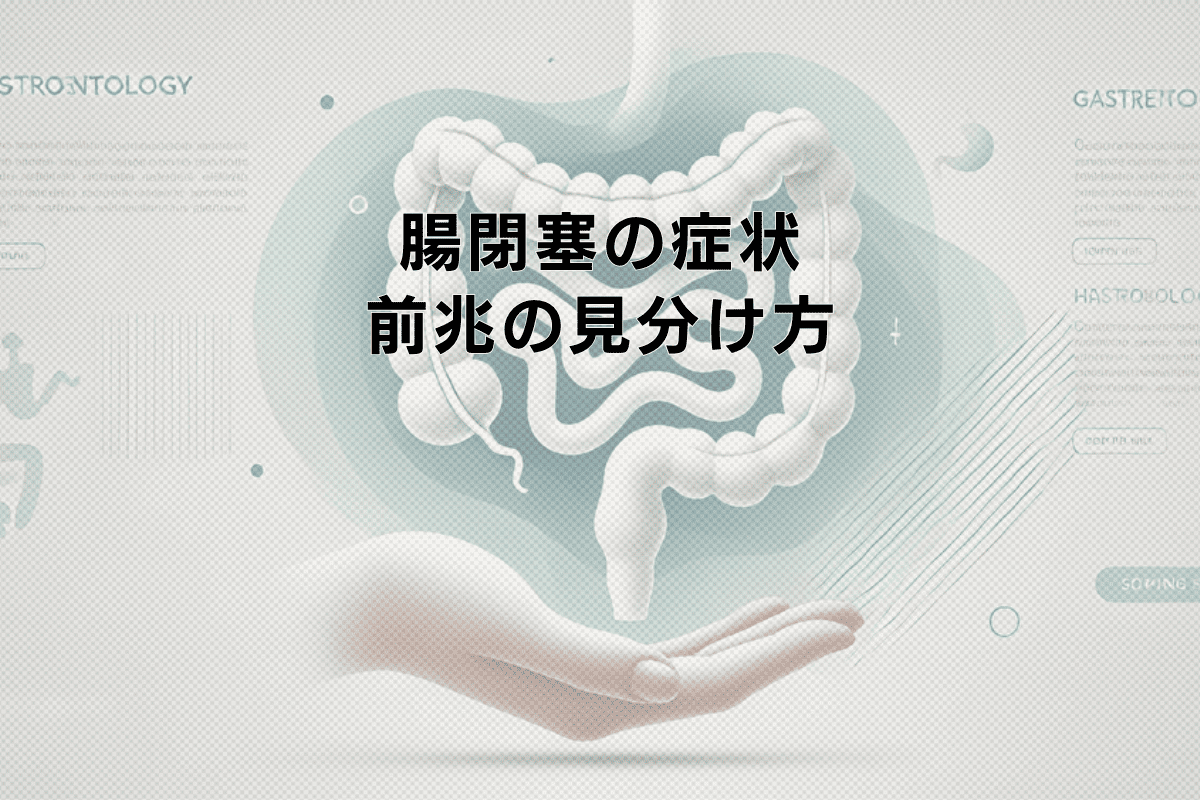
便秘と吐き気に影響する要因
| 要因 | 特徴 |
|---|---|
| 腸の蠕動運動の低下 | 加齢や食生活の乱れで腸の動きが鈍くなり、便秘や腹部不快感を起こす |
| 腹部内圧の上昇 | 腹筋や骨盤底筋の弱まりで圧力コントロールが不十分になり、便が出にくくなる |
| 消化酵素の分泌異常 | 胃酸や消化液の量が減ると食物の分解が遅れ、吐き気や胸やけを伴うことがある |
| 腸内ガスの過剰発生 | 腸内細菌のバランスが崩れるとガスの生成量が増え、膨満感や不快感を強く感じる |
自律神経の影響
胃腸は自律神経のコントロール下にあります。ストレスが続くと交感神経が優位になり、腸の動きが低下しやすくなります。便秘と吐き気が並行して起きる場合、仕事や生活環境などのストレスが影響していることも多いです。
自律神経の乱れを整える方法としては、適度な休息や軽い運動、十分な睡眠などを心がけることが挙げられます。
腸内環境が悪化する要因には、食習慣やストレスだけでなく、生活リズムの乱れも含まれ、寝不足や夜型の生活などで自律神経のバランスが崩れると、便秘や吐き気の頻度が増えることが少なくありません。
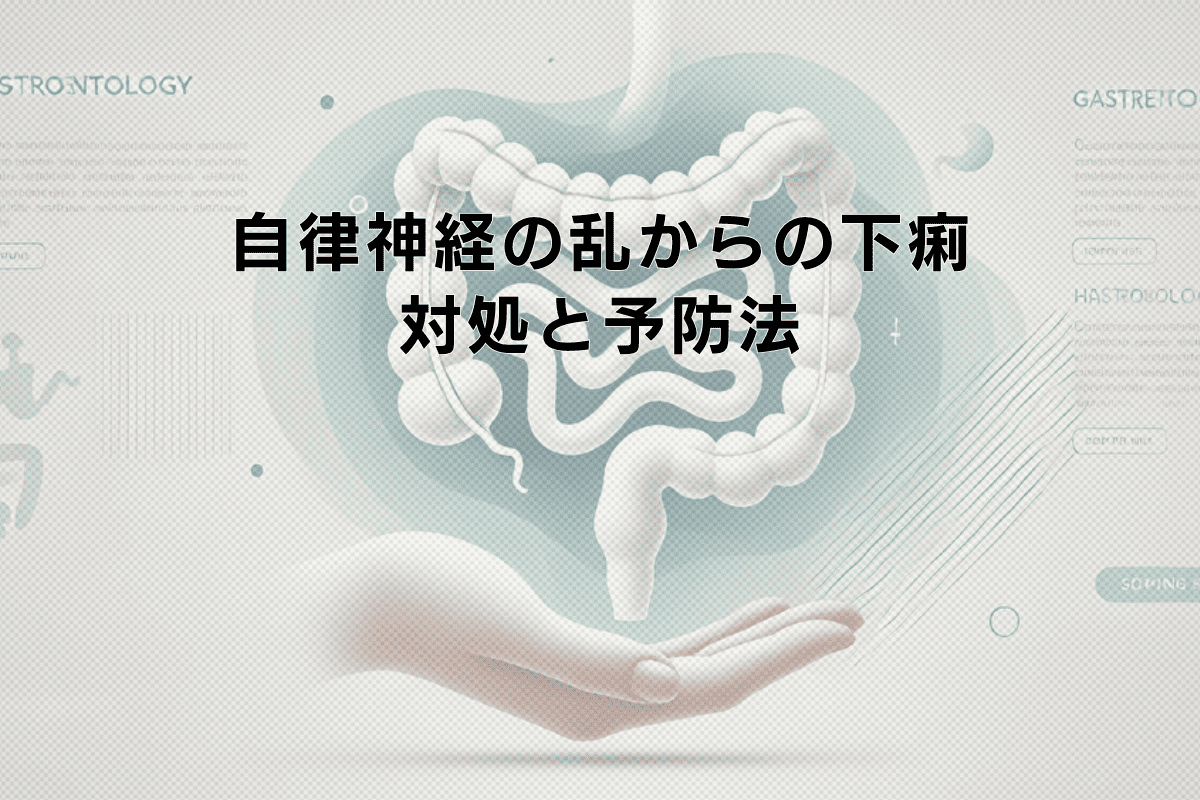
身近な要因との関連
食事の偏りは便秘や吐き気を誘発しやすい要因です。野菜や果物からの食物繊維、水分、良質な油分などをバランスよく摂らないと、便が硬くなり排出しにくくなります。
また、日常的に忙しく食事を抜いたり、早食いをしたりすると、消化機能に負担をかけ、さらに仕事などで強い緊張状態が長引けば、ストレスホルモンの増加とともに胃腸への血流量が減りやすくなり、便秘と吐き気が同時に起こる場合があります。
日常で意識したいこと
- 食物繊維が豊富な野菜を意識的に取り入れる
- 朝食を抜かずに規則正しく食事を摂る
- 普段よりも水分を十分に補給する
- 強いストレスを感じたら軽い運動や趣味で気分を変える
腸閉塞の主な原因
腸閉塞は、腸管内の通過が物理的または機能的に遮断されて起こる病態です。便秘が続いて腸閉塞へ進行するケースもあり、原因を知って早めに対策することが重要です。
既往手術による癒着
腹部の手術歴がある場合、術後の癒着が腸閉塞の大きな原因です。術後の傷が回復する過程で、組織同士が癒着してしまうことがあり、癒着が腸の動きを阻害し、通過障害を起こす場合があります。
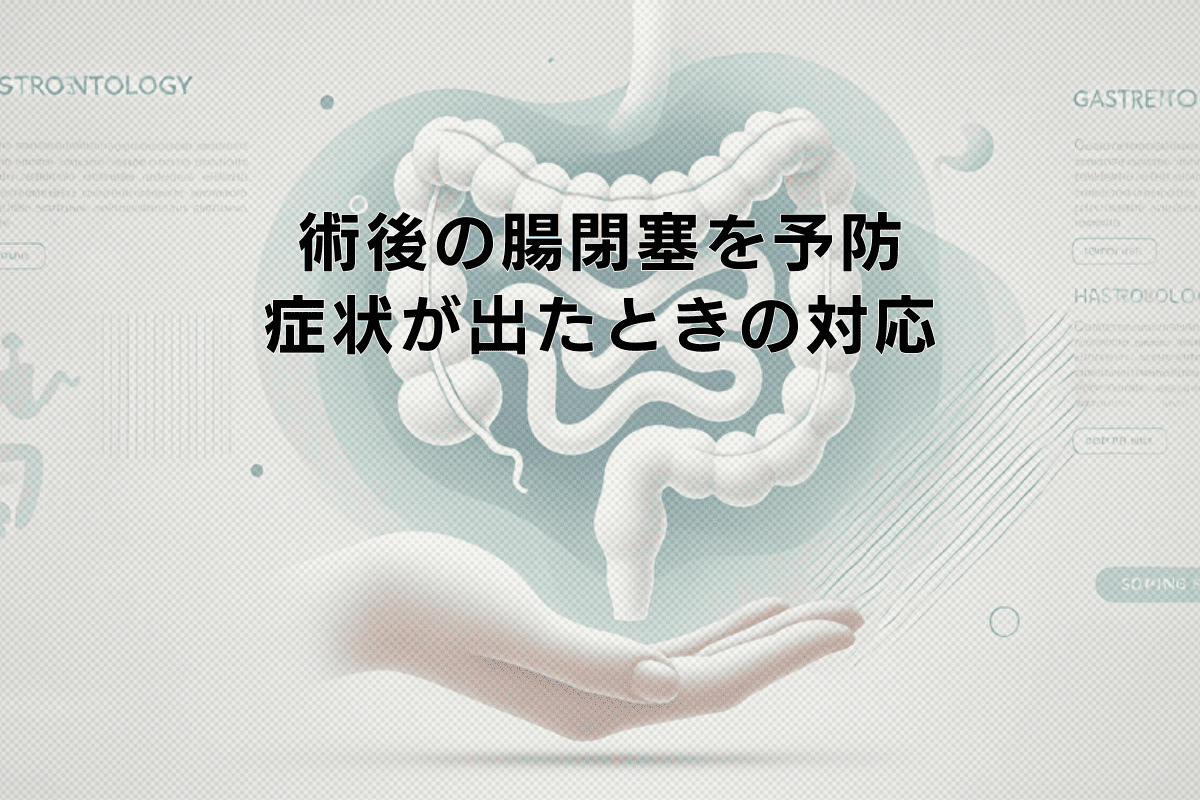
腸閉塞と手術歴
| 原因 | 具体的な例 | 発生リスク |
|---|---|---|
| 術後癒着 | 開腹手術の跡が腸管を引っ張り、腸の通過を妨げる | 腹部手術歴が多いほど高まる |
| 他の臓器との癒着 | 腹膜、肝臓、子宮など周辺臓器と腸がくっつく | 複数回の手術経験で増加 |
| フィブリン形成異常 | 術後の炎症反応が強く、組織間にフィブリンが過剰に発生 | 体質や手術部位で異なる |
手術後の早期から軽い運動や術後管理を正しく行うことが、腸の動きを保つうえで大切ですが、焦って活動を行うと傷の回復に影響が出る場合があるため、主治医と相談しながら少しずつ体を動かすことが望ましいです。
腸の捻じれや重積
腸自体が捻じれてしまうことを軸捻転といいます。捻じれの強い部分で内容物の通過が止まり、血行障害も併発すると急激な痛みや嘔吐がみられます。重積は腸の一部が隣の腸管に入り込む状態で、小児に多いものの成人でも発生します。
これらの状態が長引くと腸管の壊死リスクが高まり、緊急手術が必要です。
腫瘍やポリープによる閉塞
大腸がんや腸管内にできるポリープなどの病変が腸腔を狭くし、通過障害を起こすケースがあり、特に腫瘍がある場合は出血や慢性的な痛み、便秘以外の症状も出ることがあります。
腸の中に腫瘍が広がると、便やガスの通り道が狭くなり、便秘から腸閉塞へと進展する例も少なくないので、便に血が混じるなどの異変があれば早めに医療機関を受診することが大切です。
体質的要因や生活習慣
腸閉塞は先天性の腸管疾患や、慢性的に腸の蠕動運動が低下している人にも見られます。また生活習慣の乱れによる便秘が続くと腸壁が刺激に対して過敏になり、腸閉塞のリスクが高まります。
遺伝的要因も含め、腸管の形態や機能に個人差があるため、家族にも腸トラブルが多い場合は意識して体調管理を行いましょう。
腸閉塞が疑われる症状の特徴
腸閉塞は急性の症状として発症することが多く、激しい腹痛や嘔吐、便やガスが出なくなるなどの変化が起こります。一方、慢性的に腸閉塞が進んでいるケースでは便秘や吐き気がしばしば続き、やがて急に悪化することもあるため注意が必要です。
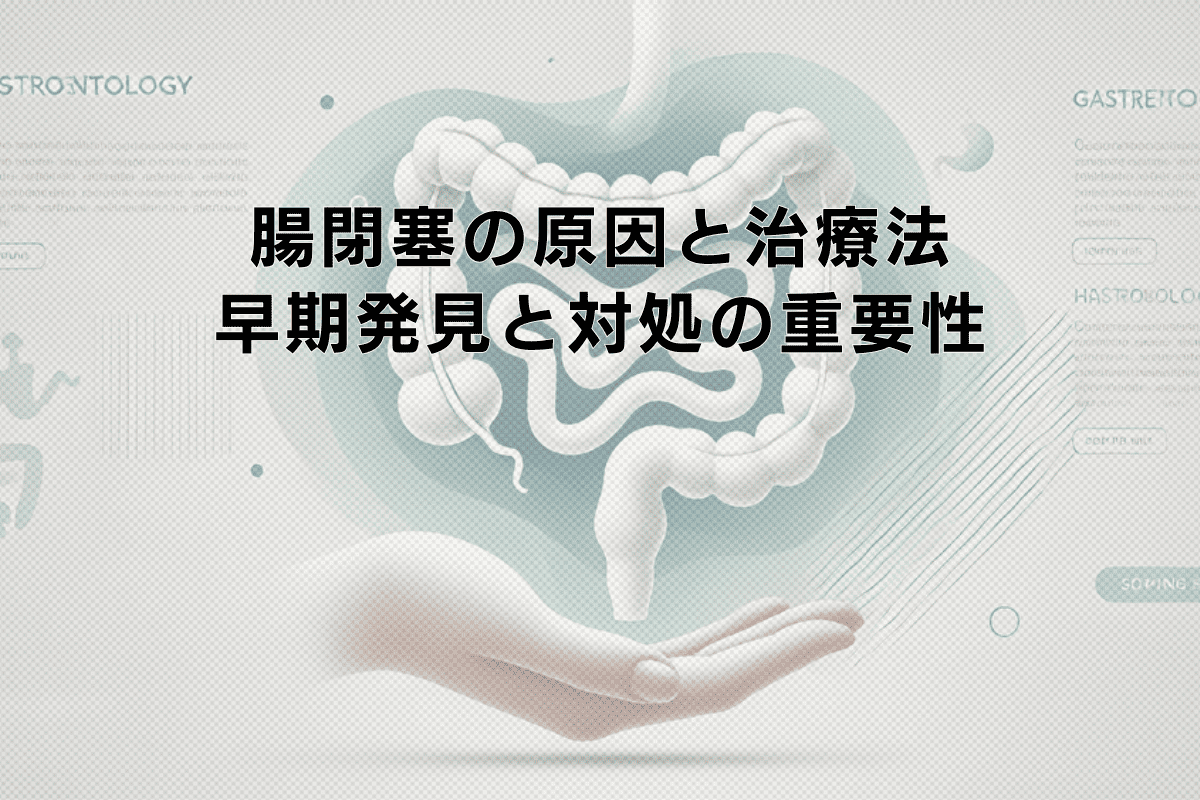
腹痛の現れ方
腸閉塞では、おへそ周辺や下腹部に差し込むような痛みが間欠的に起き、痛みは波を打つように襲ってくる場合が多く、ガスや便が溜まって腸管が伸展することで強い苦痛を生じます。
痛みが持続的ではなく、ある程度の時間差で繰り返し起こるのが特徴で、痛みは急な姿勢の変化などで増強することもあります。
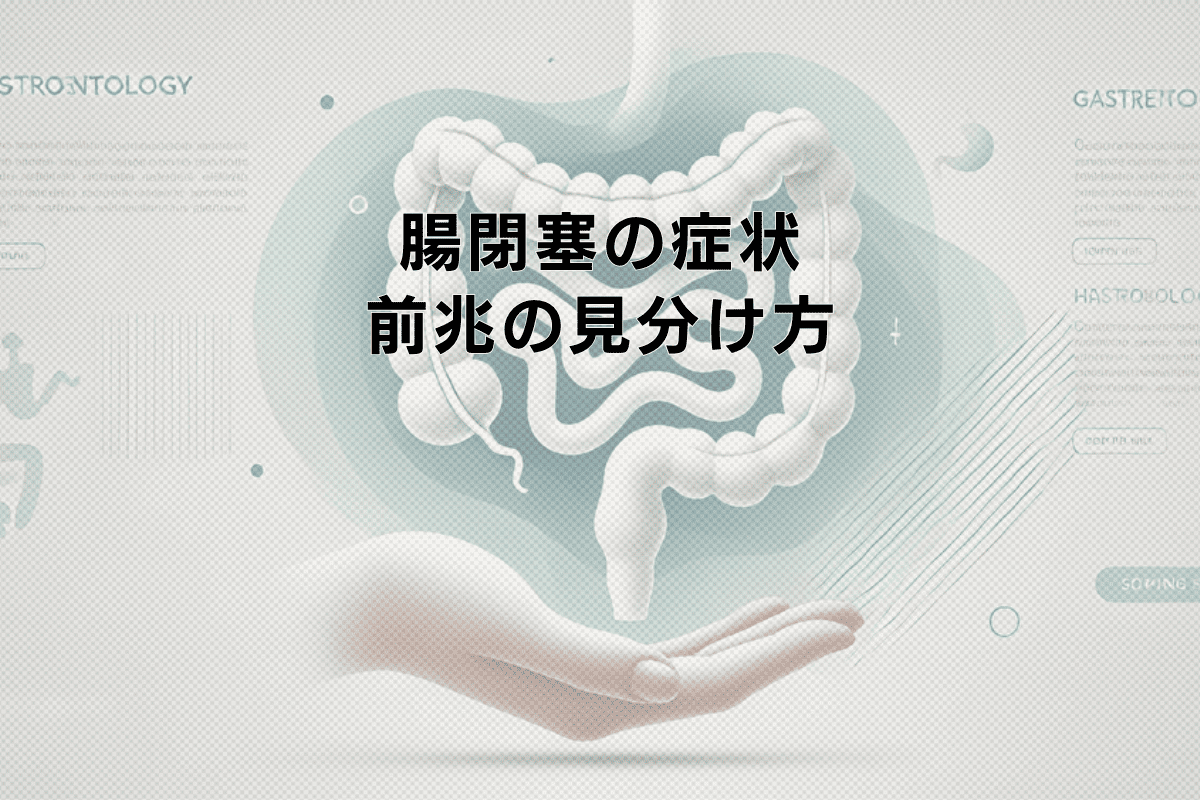
ガスの排出障害
腸が塞がるとガスが体外に出にくくなり、腹部膨満が顕著です。
普段から排便や排ガスが少ない方で、急にお腹の張りがひどくなった場合、腸閉塞の初期段階である可能性があります。ガスが溜まると見た目にも腹部の張りが分かりやすくなり、息苦しさや動きにくさを感じることもあります。
腸閉塞に多い初期症状と感じ方
| 症状 | 主な感覚 | ポイント |
|---|---|---|
| 腹痛 | 波のように襲う強い痛み | 下腹部~おへそ周辺が多い |
| 吐き気~嘔吐 | 消化物や胆汁を吐く | 嘔吐後も不快感が続くことが多い |
| 腹部膨満 | 腹がパンパンに張る | 仰向けに寝るとさらに圧迫感を覚える |
| 便やガスの停止 | 排便・放屁が全くできなくなる | 大腸より手前で塞がると出にくい状態が続く |
腹部膨満の程度
腸閉塞の種類や部位によって膨満の程度に違いがあり、小腸の上部で閉塞が起こると吐き気や嘔吐が早期に強く出ますが、下部の大腸付近で閉塞すると腹部の膨満感が顕著になります。
大腸性の腸閉塞は、大量のガスが行き場を失うため、腹囲が急速に増加しやすく、鏡で見ても腹部が明らかに突き出ている場合は要注意です。
嘔吐の仕組み
通過障害がある状態で無理に食事や水分を取ると、胃腸から先へ送れない分が逆流して嘔吐を起こします。
胃から十二指腸、小腸を通過できない内容物が溜まってしまい、体は嘔吐という手段を使って圧力を逃がそうとし、嘔吐が始まると体力が消耗しやすく、脱水リスクが高まるため、判断を誤ると危険です。
重度の腸閉塞で生じやすい嘔吐症状
- 食後数十分で吐き気が止まらない
- 胆汁混じりの黄緑色の液体を吐く
- 嘔吐後に一時的に楽になるが、すぐ再び激しい痛みが襲う
- 全身倦怠感が増し、水分補給もままならない
便秘から腸閉塞に至るリスク
便秘を軽視すると腸内に便が溜まるだけでなく、腸管全体の機能が低下しやすくなります。長期の便秘は腸閉塞の発症リスクを高め、急性の症状が出たときに対処が遅れるケースも少なくありません。
慢性的な腸管への負担
便秘が習慣化すると、大腸内に硬くなった便が慢性的に滞留し、その分腸内圧が高まるため、腸壁への刺激が強いです。
粘膜や腸の筋肉が過度の緊張状態に陥りやすく蠕動運動が乱れ、腸閉塞に近い状態を引き起こす可能性があり、胃から腸への移動にも影響が及ぶと、吐き気や嘔吐も同時にみられることがあります。
高齢者の消化機能低下
高齢者は筋力が弱り自律神経の調節機能も低下しやすいので排便力が下がり、便秘を起こしやすくなります。また高齢者は腹部の手術歴を有するケースも多く、術後癒着などで腸閉塞を起こすリスクがさらに高まります。
加齢による腸管の弾力の低下も相まって、少しの通過障害が重大な閉塞につながりやすいです。
水分不足の影響
水分を十分に摂らないと便が硬くなり、腸内での移動が遅くなり、便秘状態が続くほど腸内の内容物は水分を吸収されてさらに硬くなり、便塊が巨大化してしまうことがあります。
こうした状況が続けば、腸管を閉塞に近い状態に追い込みやすくなります。運動量の多い人や発汗しやすい環境にいる人は、体内の水分不足に気づきにくく、リスクが高いです。
疾患の合併の可能性
腸閉塞は単独で起こる場合だけでなく、炎症性腸疾患や大腸がん、狭窄性の病変など多岐にわたる疾患と関連することがあります。便秘を放置していると、何らかの大腸疾患を見落としてしまうケースもあります。
体質的に腸が弱い人や腹部に慢性的な不調がある方は、定期的な検査や早期受診を検討したほうが安心です。
早めに検討したい検査方法
便秘に吐き気まで生じているときや、腸閉塞が疑われる状況では、迅速な検査が判断の手がかりになります。早期発見と治療に繋げるためにも、医療機関での検査を前向きに考えましょう。
レントゲン検査
腹部レントゲンは腸閉塞を疑う際の代表的な初期検査で、ガスのたまり具合や位置を確認し、腸がどの程度拡張しているかを視覚的に把握できます。
小腸や大腸のどの部分に通過障害があるかをおおまかに推定し、治療方針を立てるうえで重要な参考になります。レントゲン検査は比較的短時間で行えるので、急性の腹痛を訴える患者さんにも実施しやすいです。
CT検査
CT検査では、腸や周辺臓器の状態を断面画像で詳細に確認でき、腸の捻じれや癒着、腫瘍の有無なども把握しやすく、レントゲンではわかりづらい微細な病変を検出できることが利点です。
腹痛や便秘、吐き気の原因が腸閉塞かどうかを調べる際に積極的に使われています。CT検査を受けるときは、造影剤を使用する場合もあるため、アレルギー歴や腎機能などの確認が必要です。
主な画像検査の特徴
| 検査名 | 特徴 | 適したシーン |
|---|---|---|
| レントゲン | 腸管内のガスパターンを把握 | 急性症状の際の初期診断 |
| CT | 断面画像で腸や周辺臓器を詳細に見る | 癒着や腫瘍などの部位特定に有用 |
| MRI | 軟部組織をより鮮明に描出 | 腸以外の臓器への波及評価に利用 |
大腸カメラと胃カメラ
腸閉塞の疑いがある状態で大腸カメラを行う場合は、通過可能な範囲内で腸管内部を直接観察し、ポリープや腫瘍が原因であれば、その場で組織を採取して病理検査に回すこともできます。
胃カメラについては、嘔吐や上腹部痛が強いときに上部消化管の問題を調べるために用いられ、胃や十二指腸の狭窄部位や潰瘍の有無、腫瘍の兆候などを把握するうえで有用です。
血液検査などの補助検査
腸閉塞の状態を総合的に評価するために血液検査も行われ、白血球数の増加やCRP値の上昇がみられる場合、炎症が強まっていると判断できます。
また電解質異常や脱水の有無を把握することで、点滴などの補液計画を立てられ、尿検査や心電図なども患者さんの全身状態を知るために重要です。
検査前に確認したいこと
- 過去の手術歴や基礎疾患の有無
- 造影剤や麻酔に対するアレルギーの有無
- 通常の食事・水分摂取ができない場合の点滴や処置の必要性
- 検査後に入院や経過観察が必要になる可能性
内視鏡検査でわかること
腸閉塞の原因に腫瘍やポリープ、炎症性疾患などが含まれるとき、内視鏡検査で直接視認できる情報は治療方針の決定に役立ちます。
大腸カメラや胃カメラを活用すると、単なる便秘だと思っていた症状が実際は重篤な疾患によるものだったと判明するケースもあります。
大腸カメラによる確認ポイント
大腸カメラは肛門から挿入し、大腸全体から盲腸付近までを観察します。
便秘が続き、腸閉塞が疑われる際には、大腸内の腫瘍や炎症、出血の跡などを確認し、病変が見つかれば、その部位の組織を一部採取して病理検査を行います。ポリープが小さい場合は、切除可能なケースもあります。
腸壁の状態を直接見ることで、CTやレントゲンだけではわからない表面の異常を把握できる点が大きなメリットです。

胃カメラが役立つ場面
胃や十二指腸に狭窄や腫瘍があると、吐き気や嘔吐が頻発するため腸閉塞に似た症状を呈することがあり、こうした場合、胃カメラを使って上部消化管の内腔を観察することで原因を突き止められます。
胃カメラによる観察では、出血や潰瘍、炎症の程度を把握しやすく、必要に応じて組織検査も実施します。腸だけではなく、胃や十二指腸のトラブルが原因で便秘に吐き気が加わっている可能性も否定できません。

内視鏡検査のメリットとデメリット
| 項目 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 直接観察 | 腸管や胃壁の表面を目で確認できる | 検査前の下剤服用や絶食などの準備が必要 |
| 病変の早期発見 | ポリープや小さな炎症でも見つけやすい | 腸閉塞が重症の場合は挿入困難なケースもある |
| 病理検査が可能 | 組織を採取して悪性か良性かを判定できる | 生検による出血や穿孔のリスクがわずかにある |
| ポリープ切除 | 軽度の病変なら検査時に切除できる | 切除後は当日の運動制限や食事制限が生じる |
生検の必要性
内視鏡検査中に見つかった病変については、悪性か良性かを調べるために生検を行うことがよくあり、特にサイズの大きいポリープや表面がただれている部位は、確実に調べておくことが大切です。
検体を病理検査で詳しく調べることで、がん細胞の有無や進行度がわかり、その後の治療計画に大きく影響します。
合併症の防止に向けた対策
内視鏡検査後には、ごくまれに出血や穿孔といった合併症が起こることがあり、大腸カメラでポリープ切除を行った場合は切除面の出血や腸壁の薄い部分が破れるリスクもあります。
医療機関では検査後の状態観察や安静を確保し、万が一のトラブルに備えていて、また患者さん自身も自宅に戻った後、腹痛や血便などがあれば速やかに連絡できる体制を整えておくことが重要です。
内視鏡検査後に注意しておきたい点
- 尿や便に血が混じるような異常は早めに報告する
- しばらくは運動を控え、検査当日は長風呂や飲酒を避ける
- 担当医から指定された再診日や経過観察の予定を守る
- 水分補給や消化に優しい食事を心がける
日常生活で気をつけたいポイント
腸閉塞を防ぐためには、生活習慣の改善が欠かせません。腸内環境を整えることで便秘や吐き気に悩まされる機会が減り、健康を維持しやすくなります。小さな心がけの積み重ねが大腸カメラや胃カメラの必要性を軽減させる一因にもなるでしょう。
食生活の見直し
野菜や果物、全粒穀物、発酵食品など、食物繊維や善玉菌を増やす食材を意識して取り入れることが便秘解消に役立ちます。
水溶性食物繊維を多く含む海藻やきのこ類、オートミールなどは便を柔らかくし、排便をスムーズにする作用が期待できます。
極端なダイエットや朝食抜きなどの習慣があると、胃腸への負担が大きいので、バランスの良い食事を心がけてください。
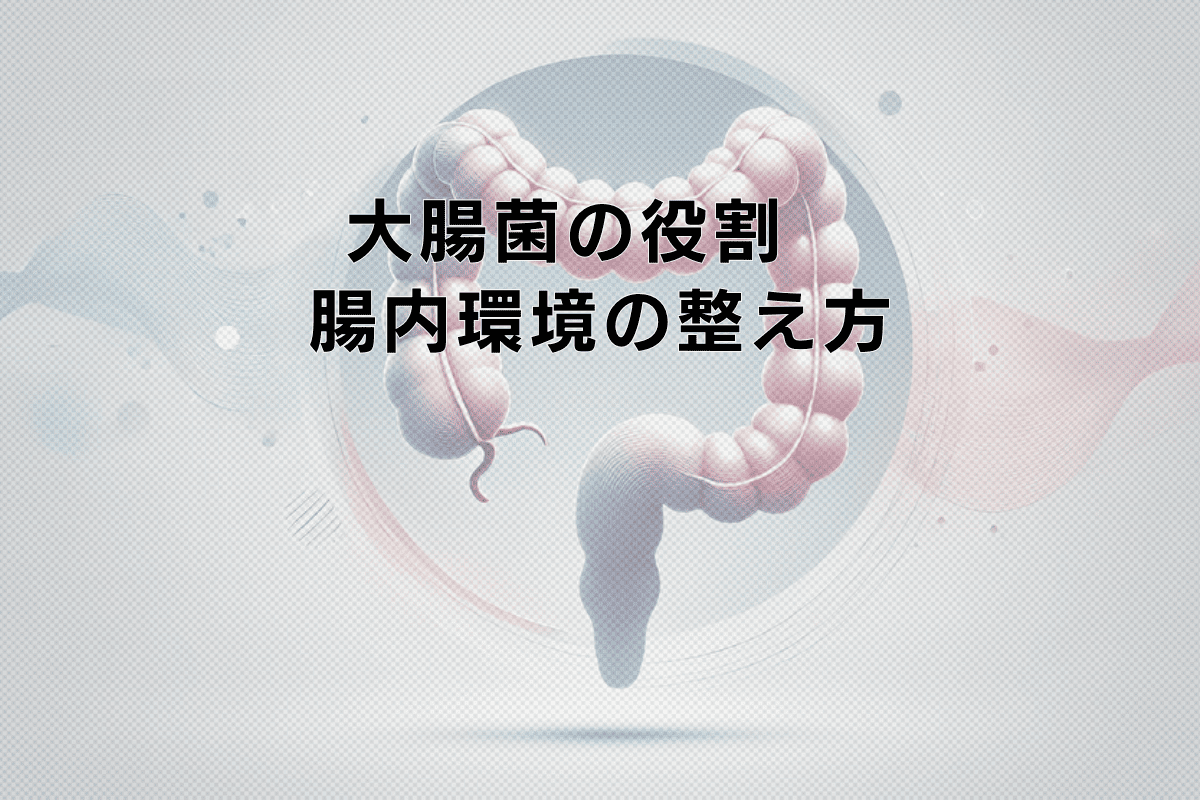
適度な運動の重要性
ウォーキングや軽い筋力トレーニングは腸の蠕動運動を活発にし、便秘を防ぐサポートになります。運動のタイミングは朝や昼間が理想的で、食後少し時間を置いてから行うと胃腸に急激な負荷を与えずに済みます。
運動不足や長時間のデスクワークは腸の動きを停滞させる要因となるので、無理のない範囲で体を動かすことが大切です。
身体を動かすメリット
| 運動種類 | 期待できる効果 |
|---|---|
| ウォーキング | 全身の血行が良くなり腸の蠕動運動も活発化する |
| 軽い筋力トレーニング | 腹筋や背筋を強くし、腹圧が適切にかかりやすくなる |
| ヨガやストレッチ | 自律神経を整える効果があり、リラックスも得られる |
こまめな水分摂取
体内の水分量が十分だと便が柔らかく保たれ、排出しやすくなり、1日に飲む水分量は、食事や気温、運動量などによって変わりますが、目安として1.5~2リットル程度の水分補給を検討するとよいでしょう。
ただし短時間に大量の水分を摂ると胃腸に負担がかかるため、少量ずつこまめに補給します。カフェインの多いコーヒーや緑茶は利尿作用があるので、水分として計算しにくい点に注意してください。
便意を我慢しない習慣
便意を感じても仕事や外出先で我慢する機会が多い人は、便秘を起こしやすくなります。
直腸に便がたまると脳に排便指令が送られますが、それを何度も無視していると感覚が鈍り、排便困難を助長するので、便意を感じたらできるだけ早めにトイレに行く習慣をつけると、腸内環境を安定させやすいです。
よくある質問
- 便秘と吐き気が長く続いていますが、市販薬で対処しても大丈夫でしょうか。
-
市販薬は一時的に便通を促す場合に活用できますが、長期間使い続けると腸の働きが弱まる恐れがあります。特に吐き気を伴うときは腸閉塞などのリスクを見極める必要があるため、医療機関で検査を受けると安心です。
慢性的に便秘が続く場合は、腸管の通過障害やその他の疾患が隠れていないかを早めに確認することをおすすめします。
- 腸閉塞を疑う症状があるものの、急激な痛みや嘔吐はありません。検査は受けるべきでしょうか。
-
激しい症状が出ていなくても、慢性的な腸閉塞の可能性は否定できないので、腹部の強い張りや便が極端に出づらい状態が続く場合は医療機関を受診しましょう。
レントゲンやCT検査によって原因がはっきりすることがあり、大事に至る前に対応すれば、入院や手術を回避できる場合もあります。
- 大腸カメラ検査が怖いのですが、腸閉塞が疑われる場合、やはり必要ですか。
-
腸閉塞の急性期にはリスクはありますが、腸閉塞の原因を突き止めるために大腸カメラは役立ちます。ポリープや腫瘍が隠れている場合、内視鏡で直接観察しないと発見が難しい場合があります。また、腸閉塞を改善させるためのイレウスチューブやステントを留置するなど、腸閉塞の治療のために行われることも多いです。
検査に不安がある方は、鎮静剤を使った方法を相談できる医療機関もあるため、受診時に希望を伝えてください。検査で得られる情報は治療計画に直結するため、大切な選択肢のひとつです。
- 高齢の親が便秘と吐き気を繰り返しています。日常で気をつけると良いことはありますか。
-
高齢者の場合、筋力低下や自律神経の乱れによって腸の動きが低下しやすくなります。食物繊維や水分を十分に摂取するよう工夫し、ウォーキングなど無理のない運動を取り入れると良いでしょう。
排便のタイミングを逃さないことも重要で、症状が強いときは早めの受診を検討し、医師の指示に従いながらケアを続けてください。
次に読むことをお勧めする記事
【腸閉塞の原因と治療法|早期発見と対処の重要性】
便秘と吐き気から腸閉塞について理解を深めたら、次は実際の治療法や予防策について知っておくと安心です。早期発見の重要性を学びたい方に特に参考になる内容です。
【腸の健康が体を支える – 腸内環境を整える】
腸閉塞を予防するためには、日々の腸内環境づくりも大切です。食事や生活習慣のポイントを総合的に学べる内容です。
参考文献
Hibbard KR, Propst A, Frank DE, Wyse J. Fatalities associated with clozapine-related constipation and bowel obstruction: a literature review and two case reports. Psychosomatics. 2009 Jul 1;50(4):416-9.
Griffiths S, Glancy DG. Intestinal obstruction. Surgery (Oxford). 2023 Jan 1;41(1):47-54.
Rami Reddy SR, Cappell MS. A systematic review of the clinical presentation, diagnosis, and treatment of small bowel obstruction. Current gastroenterology reports. 2017 Jun;19:1-4.
Sykes N, Ripamonti C, Bruera E, Gordon D. Constipation, diarrhoea and intestinal obstruction. ABC of palliative care. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing. 2006 Oct 6:29-35.
Baines MJ. ABC of palliative care. Nausea, vomiting, and intestinal obstruction. BMJ: British Medical Journal. 1997 Nov 1;315(7116):1148.
Ripamonti C. Bowel obstruction. Handbook of Advanced Cancer Care. 2003 Mar 27:460.
Demarest K, Lavu H, Collins E, Batra V. Comprehensive diagnosis and management of malignant bowel obstruction: a review. Journal of Pain & Palliative Care Pharmacotherapy. 2023 Jan 2;37(1):91-105.
Gore RM, Silvers RI, Thakrar KH, Wenzke DR, Mehta UK, Newmark GM, Berlin JW. Bowel obstruction. Radiologic Clinics. 2015 Nov 1;53(6):1225-40.
Hollerweger A, Wüstner M, Dirks K. Bowel obstruction: sonographic evaluation. Ultraschall in der Medizin-European Journal of Ultrasound. 2015 Jun;36(03):216-38.
Markogiannakis H, Messaris E, Dardamanis D, Pararas N, Tzertzemelis D, Giannopoulos P, Larentzakis A, Lagoudianakis E, Manouras A, Bramis I. Acute mechanical bowel obstruction: clinical presentation, etiology, management and outcome. World journal of gastroenterology: WJG. 2007 Jan 21;13(3):432.