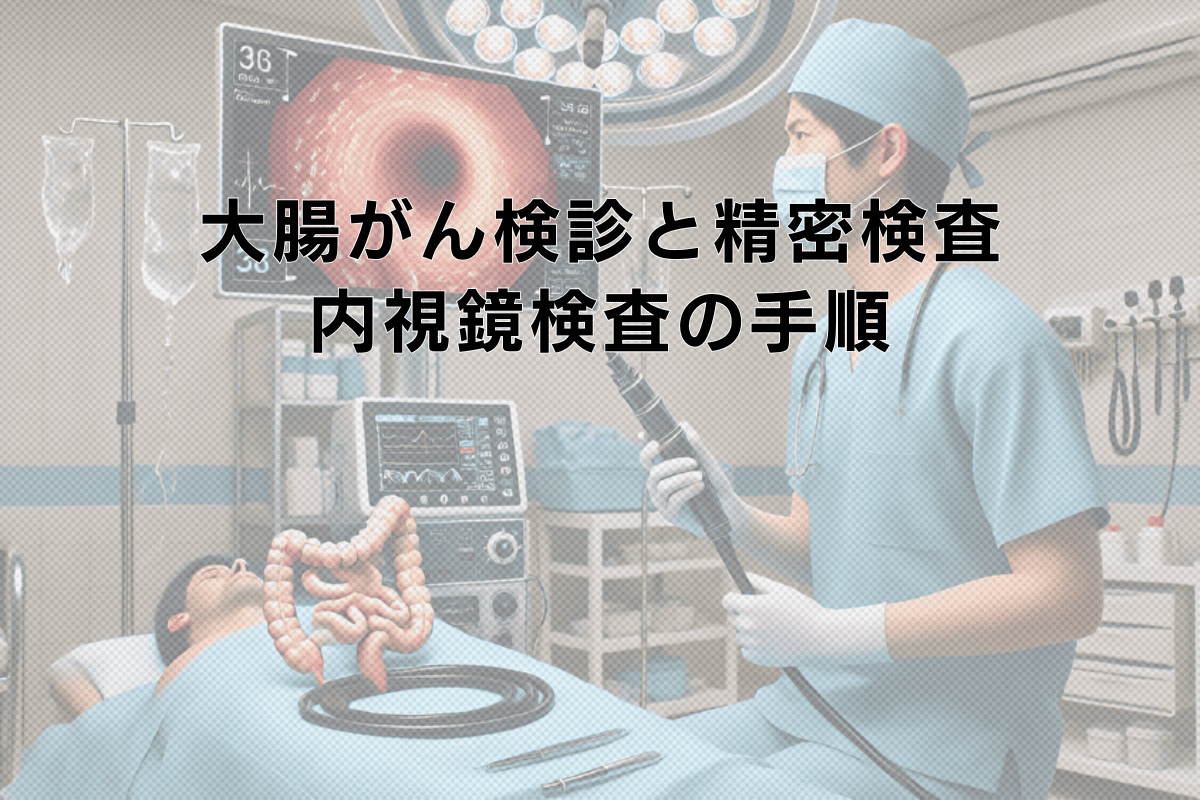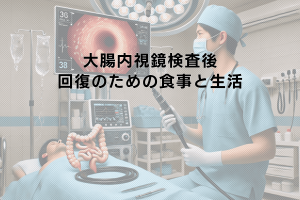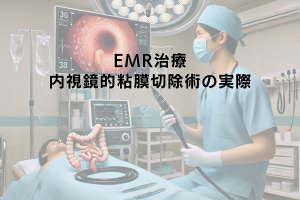大腸がんは日本で増加傾向にある疾患で、早期発見と治療が大切です。大腸がんの検診を受けて要精密検査と判定された場合、内視鏡検査へ進むことが多いです。
身体への負担や不安を軽減するためにも、検査の手順や注意点を正しく理解することが重要になります。
本記事では、大腸がんの検診から大腸がんの精密検査に至る全体像を解説し、内視鏡検査の流れをわかりやすく紹介します。
大腸がんの検診が必要とされる理由
大腸がんは消化管の末端部である大腸に発生しやすい悪性腫瘍の一種で、生活習慣や食事の傾向など複数の要因が重なることでリスクが高まります。
早い段階で症状がほとんど現れないことも多く、気づかないうちに進行してしまうケースもあるので、大腸がんの検診を受けることが、健康を維持するうえで大切です。

大腸がんとは
大腸がんは結腸や直腸といった大腸に腫瘍ができる状態で、初期のうちは自覚症状がほとんどなく、検診を受けないと見つからないことが少なくありません。
進行すると血便や腹痛、体重減少などの症状が出る場合がありますが、症状のみでは他の消化器疾患と見分けにくいです。
大腸がんは加齢とともに発生率が高くなる傾向があり、50代や60代で受診する方が多く見られますが、最近では若い年代でも発症する例が報告されており、40代より前の世代でも油断できない病気といえます。
早期発見の重要性
治療を成功させるためには早期の段階で発見することが重要です。早期に見つかった大腸がんは内視鏡を使った切除が可能なケースが多く、大がかりな外科手術を行わずに治療できる場合があります。
検診を受け、便潜血検査などで早期に異常を見つけられれば、生存率が上がるとされます。
また、大腸ポリープのうち将来的にがん化する可能性があるものも早めに対処できるため、検診をこまめに受けることが安心につながり、特に家族や親族に大腸がん経験者がいる場合は、より注意が必要です。
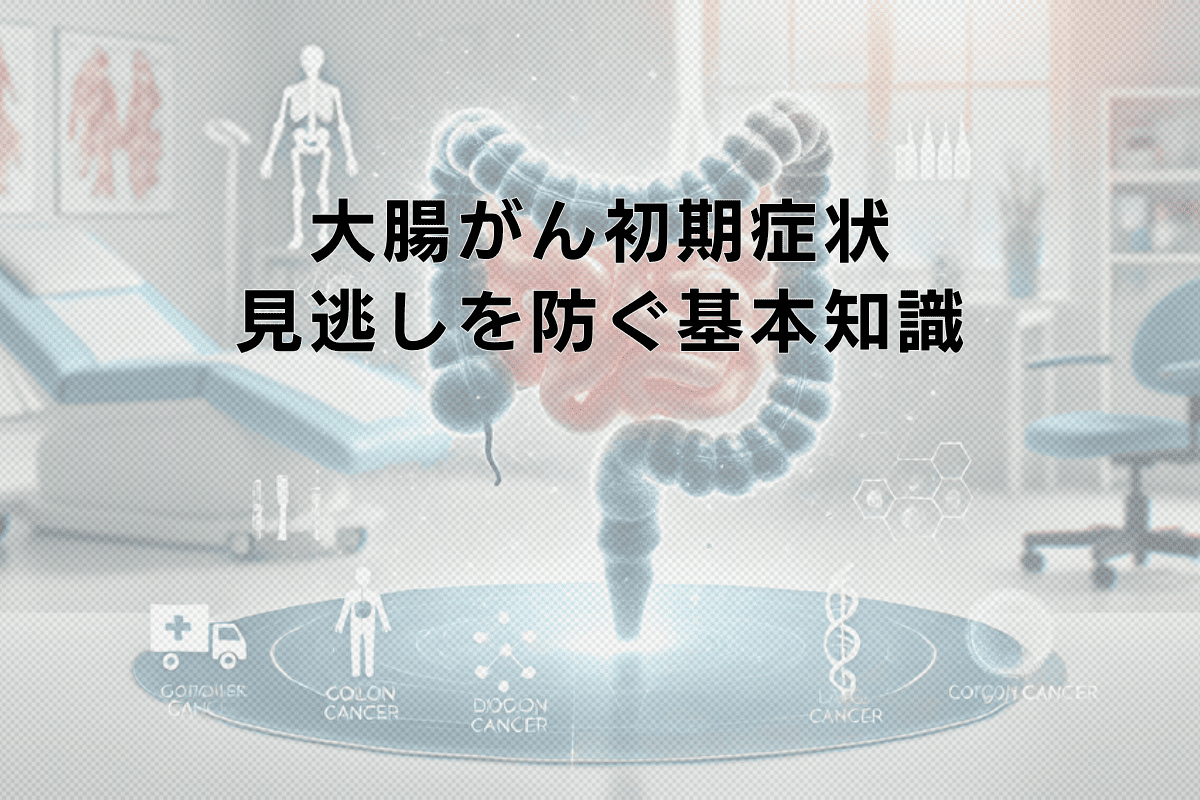
検診で見つかる病変の種類
大腸がんの検診で主に発見される病変には、以下のようなものがあります。
- ポリープ(腺腫性ポリープなど)
- 早期がん(大腸粘膜にとどまっている段階)
- 進行がん(粘膜下層や筋層を超えて浸潤している段階)
ポリープの中には放置するとがん化する可能性があるものがあります。軽度のポリープなら内視鏡で切除でき、早期の段階で腫瘍を取り除くほど、体への負担や治療の難易度が下がる傾向があります。

大腸がんリスク因子
| 因子 | 内容 |
|---|---|
| 家族歴 | 親・兄弟姉妹などに大腸がんがあるとリスクが高まることがある |
| 年齢 | 50代以降で発症率が上がる傾向がある |
| 食生活 | 高脂肪・高たんぱくの食事や食物繊維不足の影響が指摘されている |
| 運動不足 | 身体活動量が少ないと腸の動きが鈍り、便が大腸に長くとどまりやすくなる可能性がある |
| 肥満 | 肥満傾向が強いと大腸がんの発症リスクが上がるとの報告がある |
| 過度な飲酒・喫煙 | アルコールの摂取量が多い方や喫煙者にも発症リスクの上昇がみられる |
大腸がんの検診では、リスク因子がある方は特に早めの受診が大切です。
大腸がんリスクを高める可能性がある生活習慣
- 肉中心の食事が多い
- 野菜や果物をあまり食べない
- 慢性的な便秘が続いている
- 運動不足が続いている
- 長期間にわたる喫煙習慣がある
検診を受けるタイミングは、一般的には40代以降が推奨されますが、遺伝的要因などがある場合はより早い段階での受診が勧められます。すでに何らかの消化器症状を感じる方は、年齢にかかわらず一度医療機関に相談すると安心です。
大腸がんの検診で何がわかるか
大腸がんの検診では、主に便潜血検査や画像検査などを通じて大腸内部の病変を推定します。簡便に受けられる便潜血検査を入り口とする方が多いですが、画像検査や血液検査を併用する場合もあります。
複数の検査結果を総合的に判断して、精密検査が必要かどうかを決めることが一般的です。
潜血検査の仕組み
便潜血検査は、採取した便の中に血液が含まれているかを調べる検査です。大腸ポリープや大腸がんがある場合、粘膜からわずかに出血して便に血液が混ざることがあり、この血液を化学的に検出することで陽性か陰性かを判定します。
陽性となった場合でも、痔や生理など別の要因で血が混じることもあるため、必ずしも大腸がんだと断定できるわけではありません。
便潜血検査は手軽に行える反面、陽性でも実際には大腸がん以外が原因の可能性がある他、陰性でも病変が見つかる可能性があるなど、一定の限界があります。
そのため、疑わしい場合は内視鏡検査などの精密検査によって確認することが欠かせません。
画像検査との比較
便潜血検査だけでなく、CTコロノグラフィなどの画像検査を活用することもあります。大腸カメラを挿入する前段階のスクリーニングとして、より詳細な大腸の形態を把握したい場合に行うことがあります。
画像検査の特徴
- 身体への負担が比較的少ない
- 大腸全体の形態を把握しやすい
- ポリープなど病変部位の予測ができる
一方で、CT検査ではポリープを発見しても直接切除できないため、疑わしい部分があれば結局内視鏡を使った精密検査に移行します。
検査方法の特徴
| 検査方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 便潜血検査 | 便中の血液の有無を調べる | 費用・負担が比較的小さい | 陽性でも精密検査が必要、陰性でも見逃しがある |
| CTコロノグラフィ | CT画像で大腸の形状を立体的に把握 | 大腸全体を一度に撮影できる | ポリープが疑われても切除はできない |
| 大腸カメラ | 内視鏡を肛門から挿入し、大腸内部を直接観察・処置する | 病変をその場で確認・切除できる | 検査前の下剤服用など準備が必要 |
検診結果の見方
便潜血検査の結果が陰性の場合は、おおむね問題ないと判断されることが多いですが、陰性でも症状がある方やこれまでに大腸がん・大腸ポリープを治療された方、家族歴がある方は、安心せずに医療機関で相談してください。
陽性になった場合は、大腸がんの精密検査として内視鏡検査へ進む可能性が高いです。
画像検査を受けた場合、異常所見があると判断されたら早めに内視鏡検査の予約を取り、病変の性状を詳しく確認します。何も異常がなかったときは、定期的に検診を続けることで早期発見の機会を逃さないようにしましょう。
大腸がんの精密検査が行われるまで
便潜血検査や画像検査の結果から、疑わしい所見がある場合は大腸がんの精密検査として内視鏡検査が推奨されます。検診の段階では見つからなかった小さな病変が、精密検査によって明らかになることもあります。
特に症状がない段階で発見できれば、治療の選択肢は広がります。
要精密検査と判断されるケース
検診結果の報告書に「要精密検査」と記載されることがあります。
代表的なケース
- 便潜血検査が陽性だった
- 画像検査でポリープなどの影が指摘された
- 血液検査で腫瘍マーカーが高値を示した
- 大腸がんが疑われる症状が持続している
これらに該当する場合、医師から内視鏡検査を提案されることが多いです。
要精密検査と判断される主な項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 便潜血検査陽性 | 2日法で2日とも陽性の場合や1日でも高い数値が出た場合 |
| 画像検査異常所見 | CTなどでポリープらしき影や腸壁の隆起が指摘された場合 |
| 症状の持続 | 下血・便通異常・腹痛などが2週間以上継続している場合 |
| 腫瘍マーカー高値 | CEAやCA19-9などが基準値を超えた場合 |

精密検査までの流れ
要精密検査とされた場合は、消化器内科や内視鏡検査が行える医療機関を紹介されます。紹介先を自分で選択できるケースでは、通いやすさや検査機器の充実度などを考慮して決定してください。
検査の予約が確定したら、指定された日程にあわせて検査前の準備を進めます。医療機関からは、内視鏡検査前の食事制限や下剤の飲み方などの説明が行われるため、指示をしっかり守ることが大切です。
準備が不十分だと、腸内に残った便が邪魔をして十分な観察ができない場合があります。
適切な医療機関の選び方
大腸カメラや胃カメラ検査を専門的に行う施設は増えており、各地域で多様な選択肢があります。
選ぶ際のポイント
- 医師の専門分野(消化器内科の経験が豊富か)
- 設備の充実度(内視鏡機器の質や麻酔などの対応)
- アクセスの良さや通院のしやすさ
- インターネットや口コミ情報での評価
大腸がんの検診で陽性と出たあとど、の程度の期間で精密検査を受けるかは人によって異なりますが、異常所見があった場合は早めの受診が安心です。
内視鏡検査の基本
内視鏡検査には大腸カメラと胃カメラの2種類があり、大腸カメラは肛門から、胃カメラは口もしくは鼻から管状のカメラを挿入して、内部の様子を直接観察します。
医師は異常を発見した際、必要に応じて組織を採取したりポリープを切除したりできます。
大腸カメラと胃カメラの違い
大腸カメラは主に大腸の病変を確認し、胃カメラは食道・胃・十二指腸付近の病変を確認するために用いられます。検査に対する不安や抵抗感は個人差がありますが、大腸カメラの場合は下剤の服用と肛門からのカメラ挿入が必要です。
大腸カメラと胃カメラの比較
| 検査名 | 観察範囲 | 挿入経路 | 主な目的 |
|---|---|---|---|
| 大腸カメラ | 盲腸から直腸までの大腸全域 | 肛門から内視鏡を挿入 | 大腸ポリープや大腸がんの有無を調べ、必要に応じて切除する |
| 胃カメラ | 食道・胃・十二指腸 | 口または鼻から内視鏡を挿入 | 胃潰瘍や胃がんなどの病変がないかを直接確認する |
大腸がんの検診で要精密検査となった場合は、大腸カメラが優先されることが多いですが、場合によっては胃カメラも合わせて行うことがあります。特に上部消化管にも症状がある場合や、総合的な精査を希望する場合に検討されます。


内視鏡検査の対象となる症状
大腸がんや胃がんの疑いだけでなく、慢性的な腹痛、黒色便(上部消化管出血の疑い)、血便、貧血の原因調査など、さまざまな状況で内視鏡検査が提案されます。なぜ検査が必要と判断されたのかを医師に確認すると、より安心して受けられます。
大腸カメラの検討対象
- 便に血液が混じる
- 慢性的な便秘や下痢
- 血液検査で炎症反応が高い
- 腹部膨満感や原因不明の貧血
内視鏡検査の安全性
内視鏡検査は技術と機器が進歩しており安全性が高く、検査時には鎮静剤を使用するケースもあり、苦痛を軽減しながら行えます。強い痛みを感じた場合は検査を中断・調整するなどの対応も可能です。
ただし、ごくまれに腸壁の傷や穿孔などが起こるリスクはあるので、高齢者や慢性疾患を抱えている方は、検査前に医師との相談が必要です。
医療機関によっては、検査当日にポリープ切除を行う場合もあり、その際は出血リスクなどを考慮して検査前後の注意点をしっかり理解することが求められます。
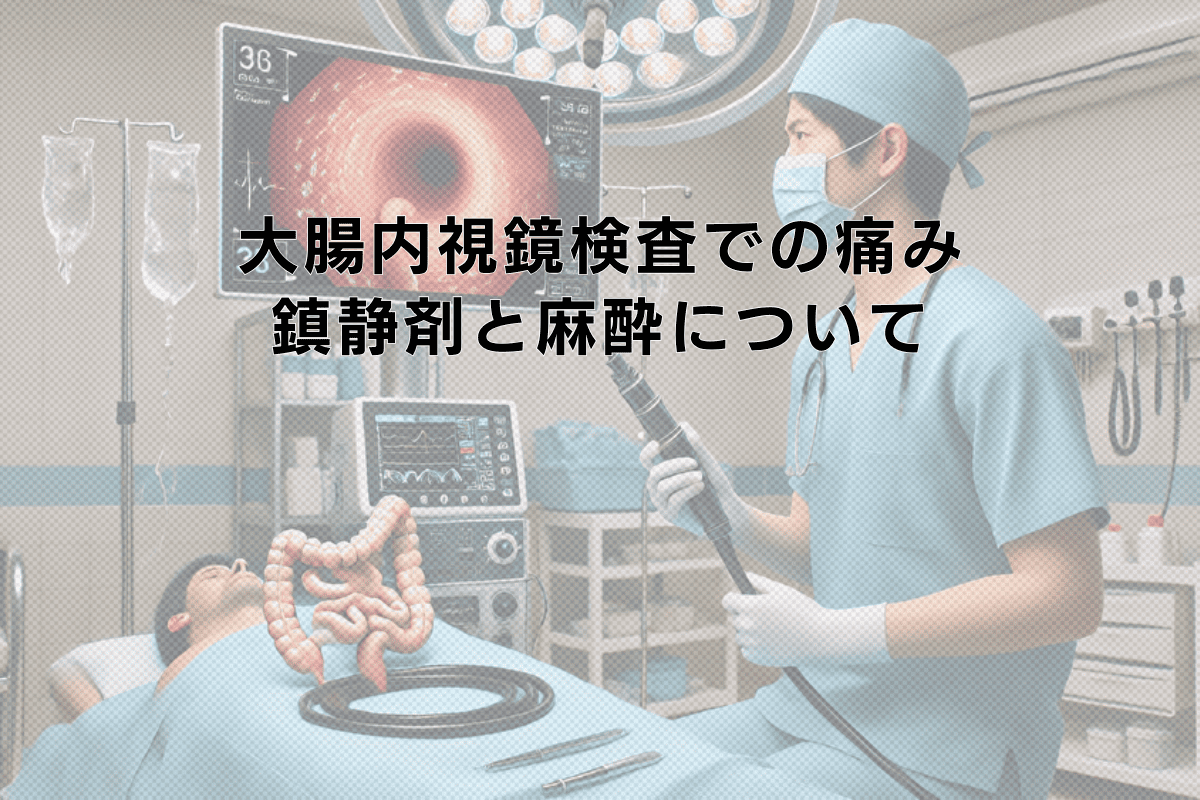
内視鏡検査の前に準備しておくこと
大腸カメラでは腸内をきれいにしてから検査を行い、事前の下剤服用や食事制限が欠かせません。準備を正しく行うことで、検査時間を短縮し、見落としを減らすことにつながります。
検査前の食事制限
通常、検査前日は消化に良い食事を心がけ、量を控えめにするように指示を受けます。脂っこいものや食物繊維が多い食品を多量に摂取すると、消化不良が起こりやすくなり、腸内に便が残りやすくなるため注意が必要です。
検査前に控えたい食品
| 食品分類 | 具体例 |
|---|---|
| 繊維が多い | キノコ類、海藻類、生野菜、玄米など |
| 脂質が多い | 揚げ物、脂身の多い肉料理 |
| 種子・殻がある | ゴマ、トウモロコシ、ナッツ類 |
| その他 | アルコール、香辛料が強い料理 |
腸内をきれいにするための食事制限は医師や看護師から詳しく説明されます。前日にあまり量を食べすぎず、バランスの良い軽めの食事を心がけましょう。

下剤の飲み方
大腸カメラ検査当日の朝から、大量の下剤を数時間かけて飲む指示を受けることが一般的で、腸内を空っぽにして初めて、内視鏡による観察やポリープの発見がしやすくなります。
下剤の種類や量は個人の体格や体調によって異なりますが、2~3時間かけて2Lほどの下剤を飲む例が多いです。
腸の状態を確認するため、排便が何回起きたかや、便の色がどのくらい透明に近づいたかをセルフチェックしながら進め、飲みづらい場合は、こまめに休憩を取りながら飲みます。
注意したい服薬状況
普段から血液をサラサラにする薬(抗凝固薬)や糖尿病治療薬などを飲んでいる場合、内視鏡検査時に出血や血糖値コントロールが問題になることがあります。検査前の問診や予約時の案内で、現在の服薬状況を医師に正確に伝えることが大切です。
以下のような薬を飲んでいる方は事前に医師へ申し出ましょう。
- 抗凝固薬(ワルファリン、DOACなど)
- 抗血小板薬(アスピリンなど)
- 糖尿病治療薬(インスリン注射、経口血糖降下薬)
- 降圧薬
連絡を怠ると、検査が延期になったり出血リスクが高まったりする可能性があります。個別に対応が異なるため、必ず医師の指示に従ってください。
検査前に気を付けたいポイント
- 診療予約時に服薬内容を申告する
- 検査前日は指定された軽めの食事にとどめる
- 水分は適度に摂取し、脱水を予防する
- 指示どおりに下剤を飲み、便が透明に近づくまで続ける
- 体調不良を感じたときは早めに医療機関に相談する
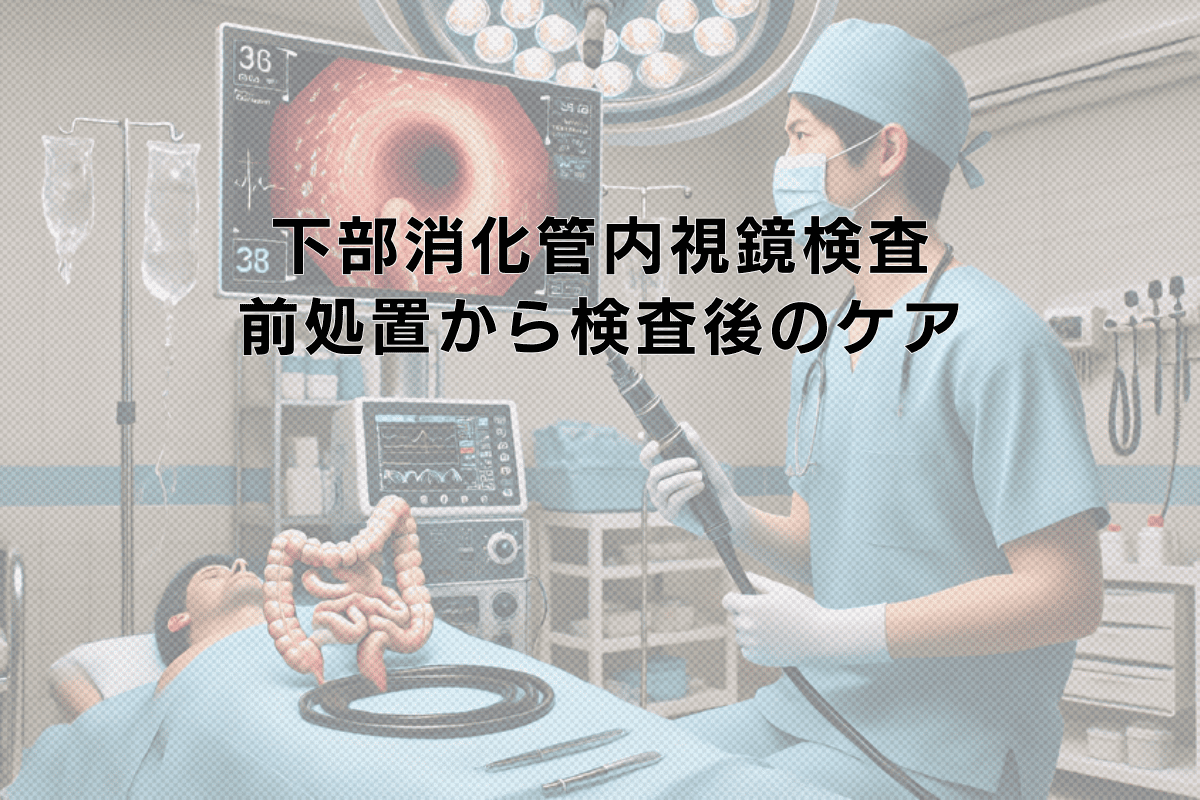
内視鏡検査当日の流れ
内視鏡検査当日は、医療機関へ来院してから下剤を飲む場合と、自宅で飲んできて腸内がきれいになったことを確認してから来院する場合があります。予約時に指示された方法に従って準備を進めてください。
来院から検査開始まで
受付を済ませたあと、更衣室などで検査着に着替えるよう指示されることが一般的です。検査の前に看護師や医師から改めて説明を受け、同意書に署名する場合もあります。
初めて内視鏡検査を受ける方は、検査室の雰囲気や機器の説明を受けることで、不安をやわらげることができるでしょう。
検査当日のタイムライン
| 時間帯 | 主な内容 |
|---|---|
| 8:30 | 来院・受付・問診 |
| 9:00 | 更衣、血圧・脈拍測定、検査前説明 |
| 9:30 | 鎮静剤を希望する場合は投与準備 |
| 10:00~ | 内視鏡検査開始 |
| 10:30~ | 検査終了後、回復室で休憩 |
| 11:00~ | 医師から検査結果の簡単な説明 |
検査は通常10~30分ほどで終わることが多いですが、ポリープの切除や病変が多い場合には、もう少し時間がかかる可能性があります。
検査当日に持参したいもの
- 健康保険証・医療証
- 紹介状(他院からのものがある場合)
- 現在服用中の薬またはお薬手帳
- 検査後に必要な着替えやナプキンなど
- 車で来院しない場合に備える交通手段の確認
麻酔や鎮静剤を使用する場合、車の運転は避ける必要があります。必要に応じて家族や友人の付き添いを依頼すると安心です。
検査中のポイント
内視鏡検査では肛門からスコープをゆっくり挿入して、大腸全体を観察していき、痛みや強い違和感を感じたときは遠慮なく医師に伝えてください。
ポリープが見つかった場合、サイズや形状、部位によっては検査当日に切除が行われることがあり、その際、出血リスクに備えてクリップ止血を行うなどの処置が実施される場合もあります。
検査中には空気や水を入れて大腸を膨らませるため、腹部膨満感を感じることが珍しくありません。検査後は体内に入った空気を排出すれば徐々に解消されます。
検査後の経過観察
検査が終わったあとは、ベッドやソファで横になりながら麻酔が切れるのを待ち、意識がはっきりしてきたら、医師から検査で撮影した画像を見ながら所見の説明を受ける流れです。
組織検査を行った場合は、病理検査の結果が出るまで数日から2週間ほどかかります。
ポリープ切除を実施した場合は、出血や穿孔のリスクがあるため、数時間程度の安静が求められ、大量出血などの異常が起きた場合は、すぐに医療スタッフへ伝えて対応を受けてください。
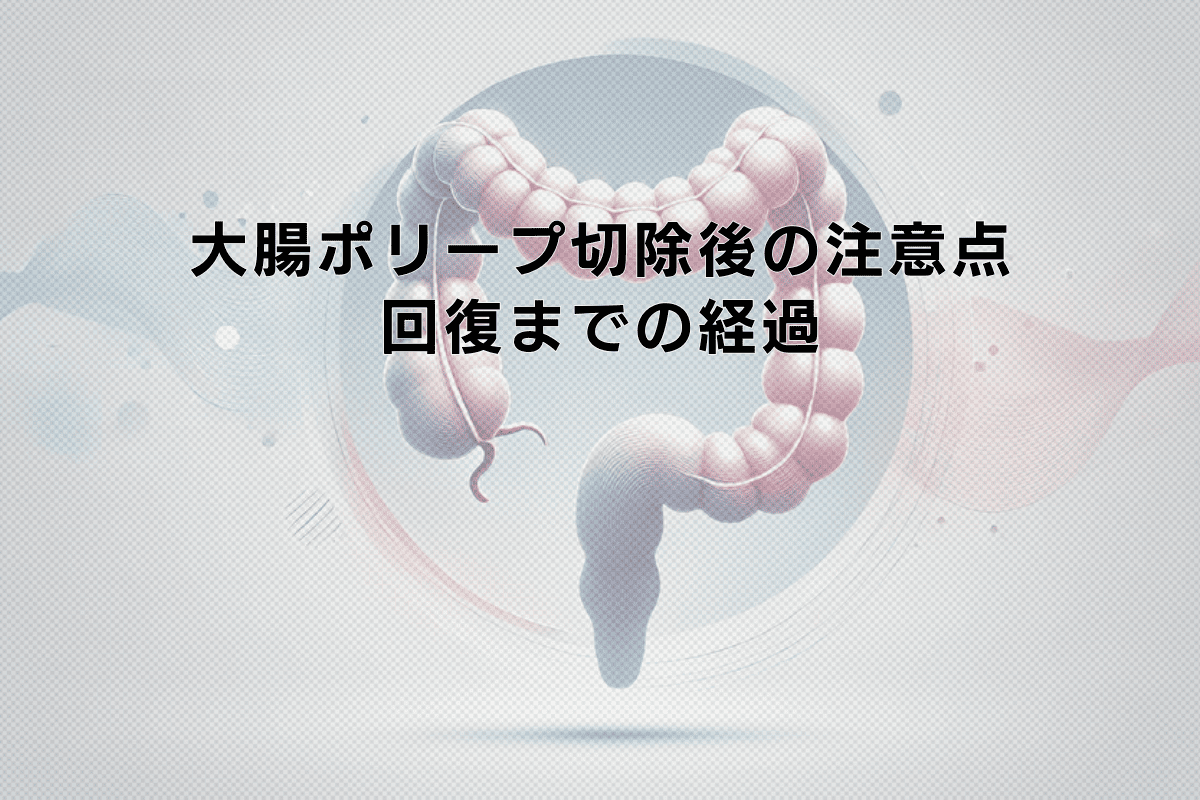
内視鏡検査後に気を付ける点
内視鏡検査が終わった後も、しばらくは体調管理や食事内容に注意してください。検査当日から翌日にかけて軽度の腹部膨満感を感じることがありますが、多くの場合は自然に回復します。
検査後の食事指導
検査後は、腸管が刺激を受けているため消化に優しい食事を心がけてください。ポリープ切除を行った場合は、出血を防ぐために刺激の強い食べ物やアルコールを控えたほうがよいでしょう。
スープやおかゆ、やわらかく煮た野菜など、消化によい食品を選ぶと身体への負担が少なくなり、食事の量は少しずつ戻します。
ポリープ切除後の注意点
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 食事 | 消化しやすいものを選び、過度な刺激物やアルコールは数日間控える |
| 運動 | 激しい運動は傷口からの出血リスクを高めるため、医師の指示に合わせて控えめにする |
| 入浴 | 施行当日はシャワー程度にとどめるのが望ましい |
| 便秘・下痢への対処 | 何日も排便がない場合や下痢が長引く場合は医師へ相談する |
体調が悪化した場合の対応
検査後に以下のような症状が出たときは、念のため早めに医療機関へ連絡してください。
- 腹痛が強い・出血が止まらない
- 38℃以上の発熱
- 吐き気や嘔吐が続く
- 強いめまいや意識障害を感じる
これらの症状はまれですが、万が一のトラブルを速やかに対処するために、医療スタッフや担当医に連絡を取ってください。
検査後に疑わしい症状が出た場合
- 腹痛や下腹部の強い張り
- 便に鮮血が混ざる
- 寝汗を頻繁にかく
- 心拍数の上昇や息切れ
自分では軽い不調だと思っていても、重大な合併症の初期症状である可能性が否定できません。早期対応が安心につながります。
ポリープ切除後の安静期間
内視鏡検査でポリープを切除した場合、切除部位からの出血リスクがあるため、数日間は重いものを持ったり過度に身体を動かさないようにします。
傷口は目に見えませんが、大腸粘膜にできた小さな傷口は、刺激を受けると出血することがあるので、医師の判断にもよりますが、おおむね2~3日間は負担の少ない生活を心がけると良いでしょう。
よくある質問
内視鏡検査を初めて受ける方や、検査に対して不安を抱いている方から寄せられる質問はさまざまです。代表的なものを挙げて解説します。
- 検査に伴う痛みについて
-
大腸カメラや胃カメラでは、挿入時や空気を入れる時に不快感を覚えることがありますが、鎮静剤の使用やスコープ技術の向上によって、痛みや苦痛を最小限に抑える工夫が一般的になっています。
強い痛みを感じる際は、検査の途中でも医師や看護師に伝えると適宜対応が可能です。
不安をやわらげるための対策
対策 内容 鎮静剤の使用 検査中の意識レベルを下げ、痛みや恐怖心を緩和する こまめな声かけ 医師や看護師からの説明や配慮によって心理的ストレスを減らす リラックスできる姿勢をとる 無理に力を入れず、深呼吸を意識することで苦痛を軽減する 希望に合った機関や医師を選ぶ 痛みに配慮した検査を実施している施設を探し、事前に相談する - 検査費用の目安
-
費用は保険適用かどうかや、検査中にポリープ切除を行うかによって大きく異なります。
初診料や検査内容に応じて総額で5,000~10,000円程度になることもあれば、ポリープ切除が加わると15,000~30,000円程度になる場合があります。
医療機関によって検査設備や処置内容が異なるため、詳しくは事前の問い合わせや医師の説明を確認してください。
以下の記事も参考にしてください。
⇒内視鏡検査費用の目安と流れ 胃と大腸のチェック方法
内視鏡検査の費用相場や保険適用の条件、ポリープ切除時の追加費用について具体的に説明しています。
検査前の準備として費用面の不安を解消できます。 - 再検査が必要な場合
-
内視鏡検査の結果に応じて、追加の検査が提案されることがあります。組織検査の結果が疑わしかったり、ポリープを切除した跡の観察が必要だったりする場合に再度の内視鏡検査が行われることもあります。
再検査を先延ばしにすると病変が進行するリスクがあるため、医師から再度の検査を勧められた際には、早めに日程を調整して受診すると安心です。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
内視鏡検査の基本を押さえたら、次は実際の前処置を詳しく知っておくと安心です。検査日が近い方に特に役立つ具体的な準備手順をまとめています。
【大腸ポリープの基本症状から治療法まで – 患者さんのための総合案内】
大腸がん検診について理解が深まると、関連する大腸ポリープについても知りたくなる方が多いです。がん予防の観点からも重要な情報です。
参考文献
Saito Y, Oka S, Kawamura T, Shimoda R, Sekiguchi M, Tamai N, Hotta K, Matsuda T, Misawa M, Tanaka S, Iriguchi Y. Colonoscopy screening and surveillance guidelines. Digestive Endoscopy. 2021 May;33(4):486-519.
Matsuda T, Ono A, Kakugawa Y, Matsumoto M, Saito Y. Impact of screening colonoscopy on outcomes in colorectal cancer. Japanese journal of clinical oncology. 2015 Oct 1;45(10):900-5.
Sano Y, Byeon JS, Li XB, Wong MC, Chiu HM, Rerknimitr R, Utsumi T, Hattori S, Sano W, Iwatate M, Chiu P. Colorectal cancer screening of the general population in East Asia. Digestive Endoscopy. 2016 Apr;28(3):243-9.
Tanaka S, Kashida H, Saito Y, Yahagi N, Yamano H, Saito S, Hisabe T, Yao T, Watanabe M, Yoshida M, Saitoh Y. Japan Gastroenterological Endoscopy Society guidelines for colorectal endoscopic submucosal dissection/endoscopic mucosal resection. Digestive Endoscopy. 2020 Jan;32(2):219-39.
Saito Y, Kodashima S, Matsuda T, Matsuda K, Fujishiro M, Tanaka K, Kobayashi K, Katada C, Horimatsu T, Muto M, Ohtsuka K. Current status of diagnostic and therapeutic colonoscopy in Japan: The Japan Endoscopic Database Project. Digestive Endoscopy. 2022 Jan;34(1):144-52.
Hamashima C, Goto R. Potential capacity of endoscopic screening for gastric cancer in Japan. Cancer science. 2017 Jan;108(1):101-7.
Vuik FE, Nieuwenburg SA, Moen S, Spada C, Senore C, Hassan C, Pennazio M, Rondonotti E, Pecere S, Kuipers EJ, Spaander MC. Colon capsule endoscopy in colorectal cancer screening: a systematic review. Endoscopy. 2021 Aug;53(08):815-24.
Loeve F, Brown ML, Boer R, van Ballegooijen M, van Oortmarssen GJ, Habbema JD. Endoscopic colorectal cancer screening: a cost-saving analysis. JNCI: Journal of the National Cancer Institute. 2000 Apr 5;92(7):557-63.
Brenner H, Heisser T, Cardoso R, Hoffmeister M. Reduction in colorectal cancer incidence by screening endoscopy. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology. 2024 Feb;21(2):125-33.
Seeff LC, Richards TB, Shapiro JA, Nadel MR, Manninen DL, Given LS, Dong FB, Winges LD, McKenna MT. How many endoscopies are performed for colorectal cancer screening? Results from CDC’s survey of endoscopic capacity. Gastroenterology. 2004 Dec 1;127(6):1670-7.