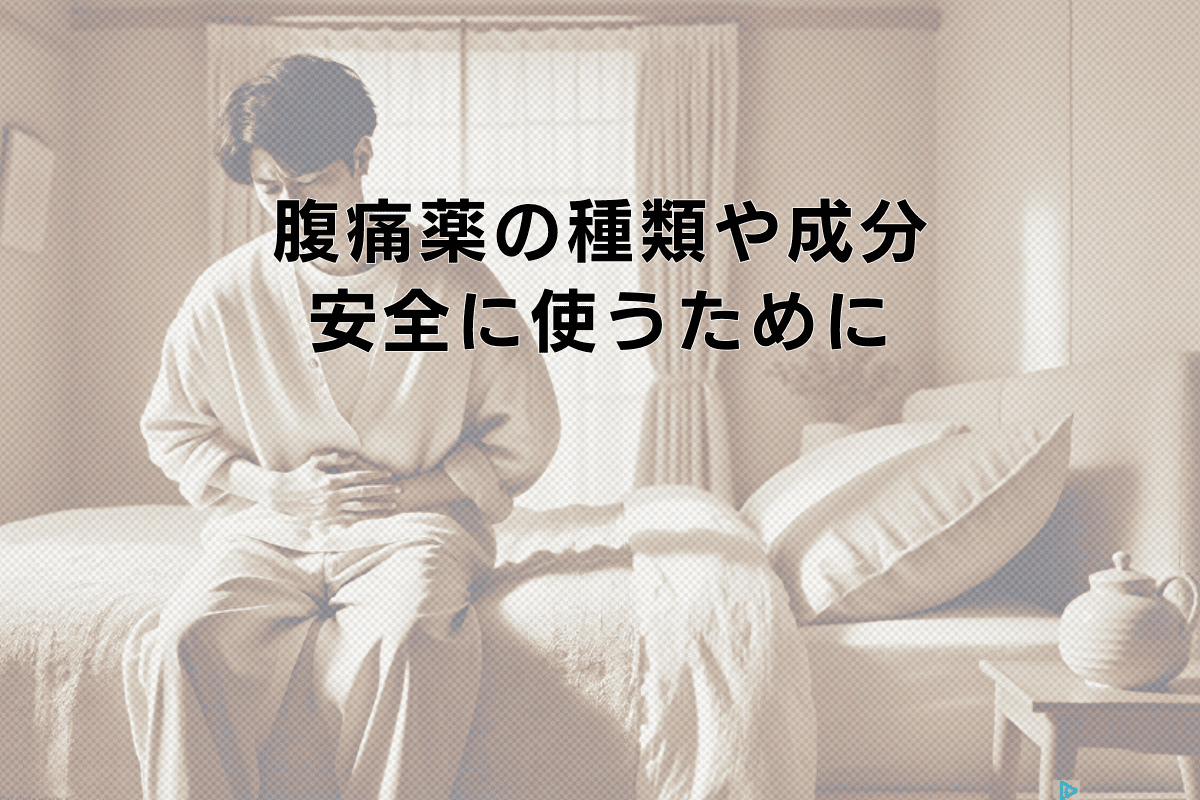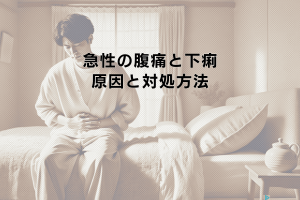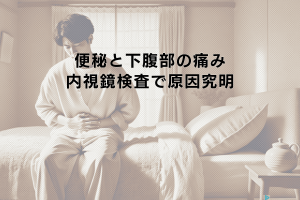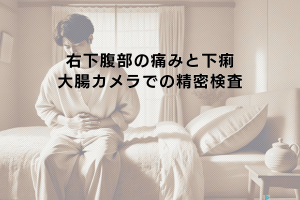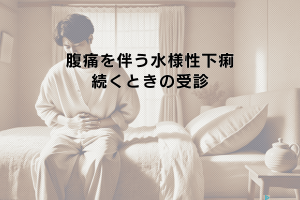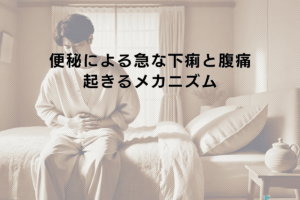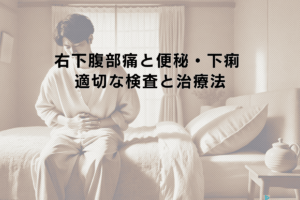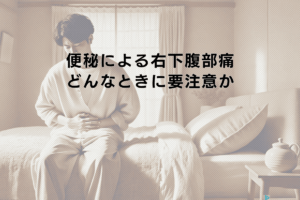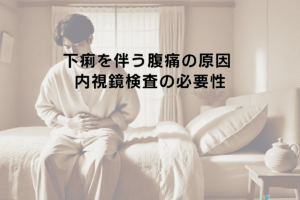腹痛を感じる場面は、食べ過ぎや下痢、便秘、胃腸の炎症など多岐にわたります。
市販薬を活用すると一時的に痛みがやわらぐ場合がありますが、原因に合わない薬を選ぶと症状が長引いたり悪化したりする可能性も否定できません。
腹痛薬を使用するうえでは、痛みの特徴や併発している症状、服用するタイミングをしっかり考えることが大切で、服用する際の注意点や薬の成分を知りながら、必要に応じて医薬品に頼る方法や病院での診察を検討しましょう。
腹痛薬を使う前に理解しておきたいこと
腹痛は胃や腸をはじめとする消化器の様々な要因から起こる症状ですが、実際には急にお腹が痛み始めると「とりあえず薬を飲んで抑えよう」という流れになりがちです。
しかし、漫然と薬を使うよりも、まずは痛みの部位や性質、便通の状況を把握してから成分や種類を選ぶ方ことが大切です。
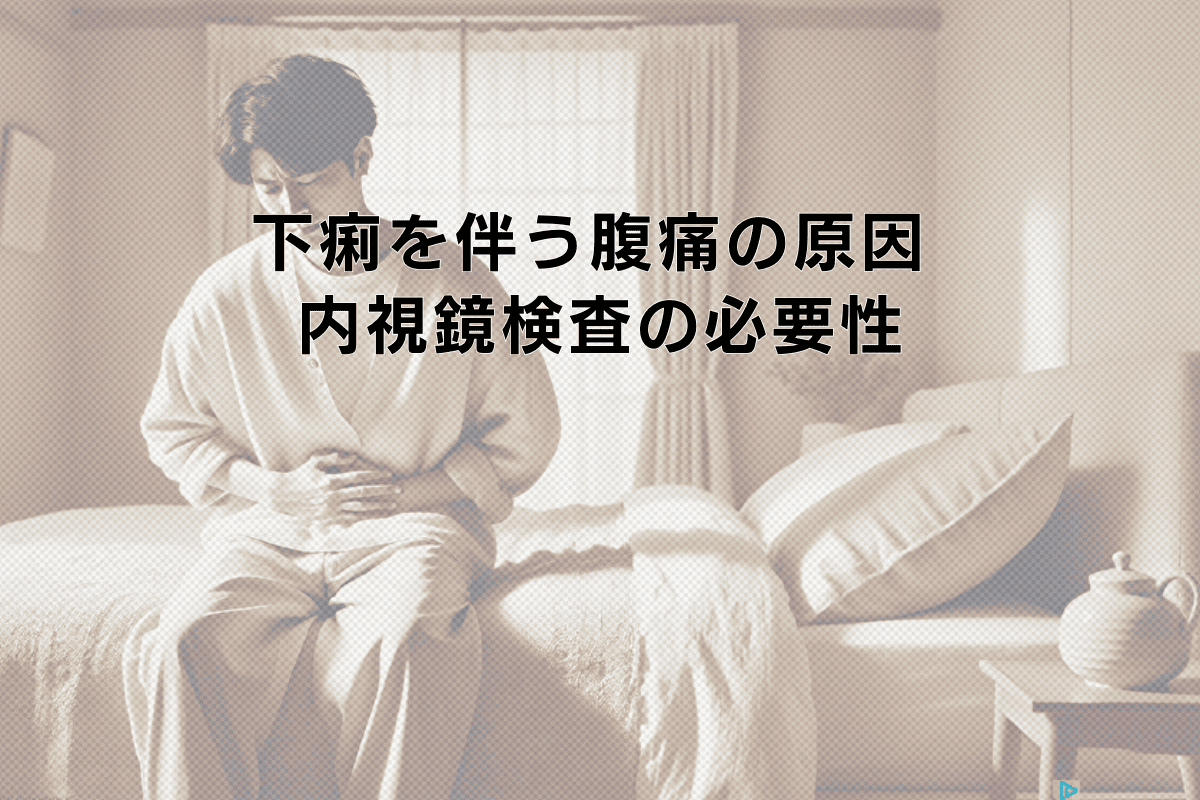
どのような腹痛に薬が役立つのか
腹痛とひと口に言っても、下痢や便秘、ガス溜まり、急性の胃痛など症状はさまざまで、市販薬の場合、鎮痛作用で痛みを和らげるものや胃酸を抑えるもの、腸の動きを整えるものなど、成分の役割が異なります。
痛みの原因を大まかに把握したうえで、必要に応じて薬を選びましょう。
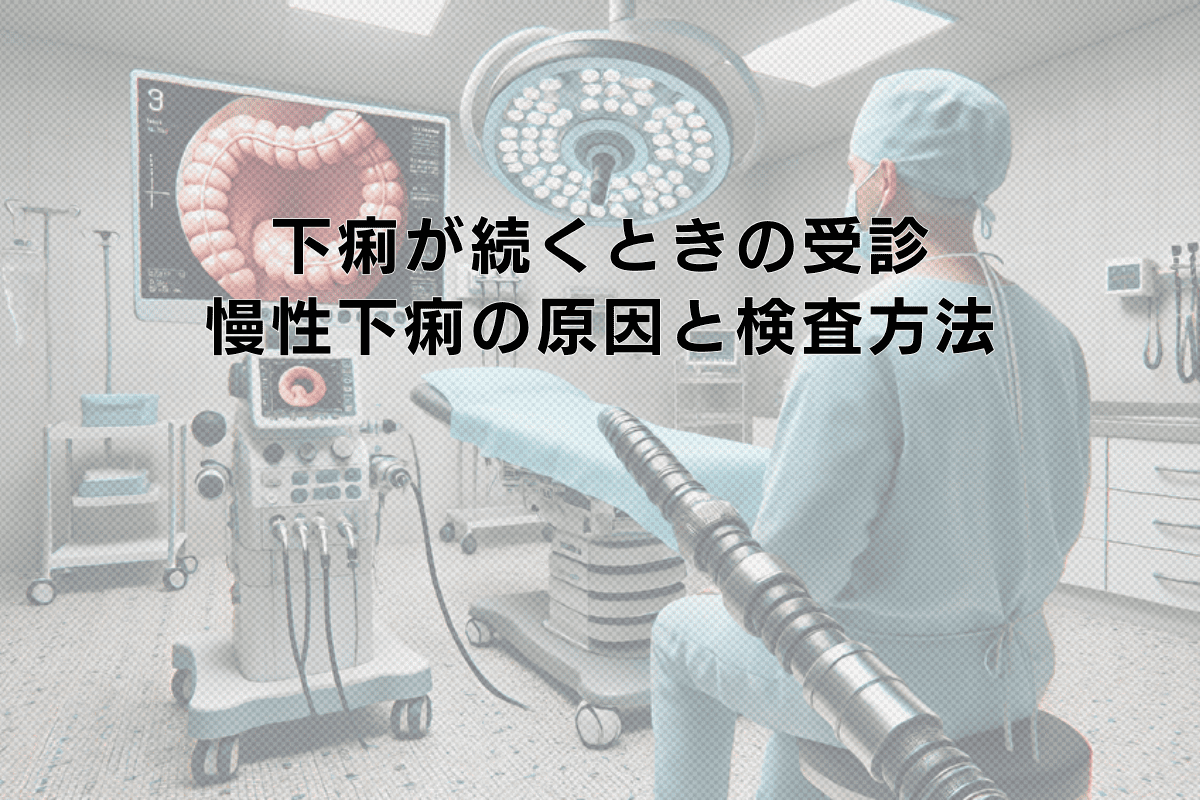
市販薬と処方薬の違い
医薬品には大きく分けて市販薬(OTC薬)と処方薬(病院などで医師が処方する薬)の2種類があり、市販薬は比較的軽い症状に対応することを目的とし、副作用が少ないように調整されていますが、効果もマイルドなものが多いです。
一方、処方薬は症状に合わせて医師が判断し、成分や用量が調節されています。原因不明や重度の腹痛であれば、医療機関での受診を視野に入れた方が安心です。
鎮痛薬だけでは解決しないケースもある
ロキソニンやイブプロフェンなどの鎮痛薬は、痛みを抑える効果がありますが、腹痛の原因を除去できるわけではありません。例えば、腸の炎症がある場合やウイルスが原因の場合は、根本的な治療が必要になるケースが多くなります。
痛み止めで症状を一時的に緩和しても、原因が解決されないまま時間が経つと、症状が長引いたり合併症を起こしたりする可能性があるため注意が必要です。
痛みの性質を確認する意義
腹痛薬を上手に活用するには、自分の痛みがどのような性質か簡単にでも把握することが大切で、次のような観点で症状をチェックすると、適した薬選びに役立ちます。
- 痛む部位は上腹部か下腹部か、おへその周囲か
- 痛み方はキリキリ、シクシク、刺すよう、鈍痛など
- 時間帯や食事との関連(食後に痛む、空腹時に悪化など)
- 便秘が続いているか、下痢が起きているか
- ガスが溜まったように感じるか
情報を整理すると、薬剤師や医師に相談する際にも説明がしやすく、アドバイスをもらいやすくなります。
腹痛の主な原因と症状の特徴
腹痛を引き起こす原因は実に多彩であり、消化器そのもののトラブルから精神的なストレス、ウイルス感染や腸内環境の乱れなど、多岐にわたります。
ここでは、代表的な原因と症状の特徴を解説しながら、薬で改善しやすいケースと、専門的な治療が必要なケースを見極めるポイントを考えていきます。
消化器の炎症や感染
ウイルスや細菌などに感染し腸や胃が炎症を起こすと、腹痛とともに下痢、発熱、嘔吐などが起こりやすく、いわゆる食あたりやノロウイルスなどが原因で、強い痛みを伴うことがあります。
軽度の場合は市販の下痢止め薬で対処することもありますが、高熱を伴ったり長期化するときは医療機関での受診が必要です。
主な感染性腹痛
| 感染タイプ | 代表的な病原体 | 症状 |
|---|---|---|
| 細菌性腸炎 | サルモネラ菌、カンピロバクターなど | 腹痛、下痢、発熱、嘔吐 |
| ウイルス性腸炎 | ノロウイルス、ロタウイルスなど | 水様性下痢、嘔吐、腹痛 |
| 寄生虫感染 | クリプトスポリジウムなど | 継続的な下痢、栄養吸収障害 |
炎症が強い場合は感染を抑える薬が必要ですが、市販の薬には限界があります。

過敏性腸症候群
便秘や下痢を繰り返す過敏性腸症候群では、腹痛が慢性的に起こりやすく、腸の働きが過敏になり、ストレスをきっかけに症状が出るケースが多いとされています。
市販の整腸薬や便秘薬を使用することで一時的に症状が緩和することがありますが、根本的にはストレスマネジメントや生活習慣の改善が重要です。
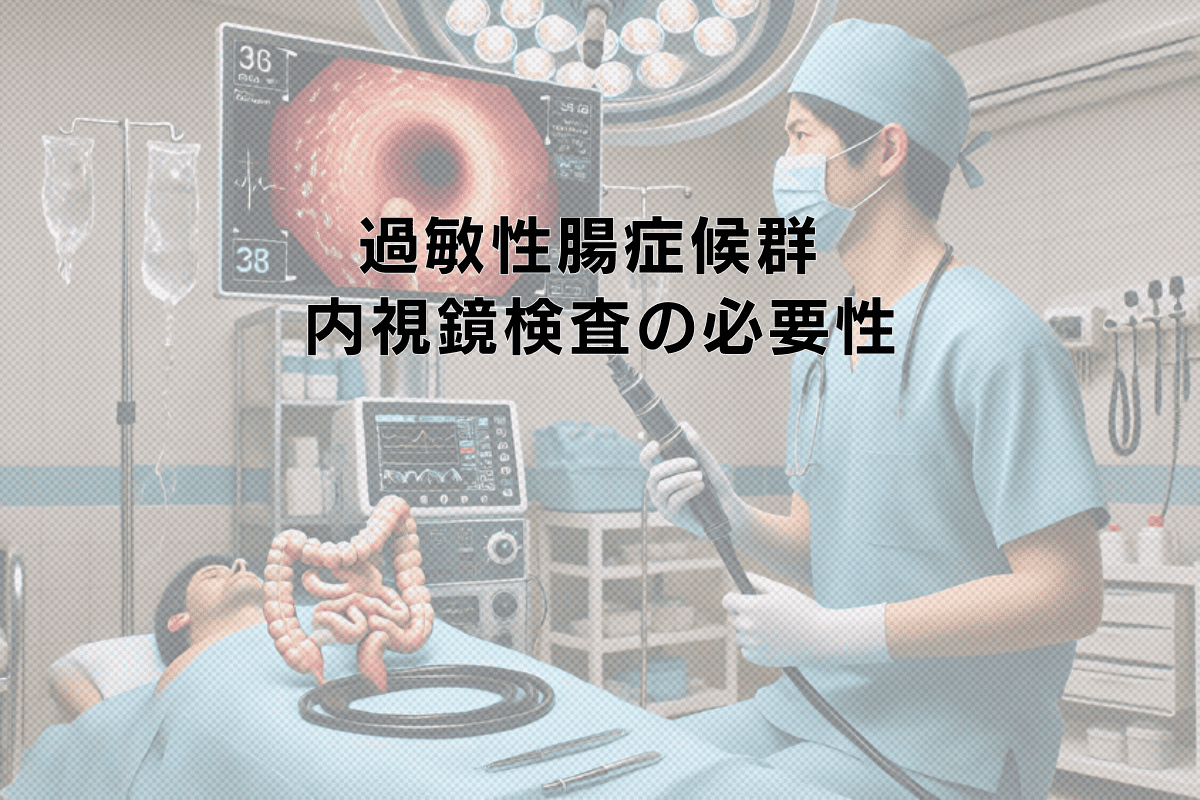
胃酸の過剰分泌や胃潰瘍
胃酸が必要以上に分泌されて胃の粘膜を刺激すると、胃痛や胸やけ、酸っぱいものがこみ上げるような症状を引き起こし、進行すると胃潰瘍になり、出血や吐血を伴うケースもあります。
H2ブロッカーや胃酸を中和する薬(制酸薬)などは市販薬としても入手できますが、強い痛みや吐血、黒色便などがある場合は受診が必要です。
胃酸過多が疑われるサイン
- 空腹時にキリキリとした痛みが走る
- 胸焼けや胃もたれが続く
- 酸っぱい液体を吐き上げることがある
- ストレスが溜まると痛みが増す
胃を保護する成分や胃酸を抑制する成分が入った胃腸薬で症状が和らぐ場合がありますが、激しい痛みが続くときは注意が必要です。

腸の動きと便秘の影響
便秘が続くと腸内にガスや老廃物が溜まり、下腹部に鈍い痛みや張りを感じる場合があり、便秘薬や食物繊維などで排便を促すと痛みが緩和することが多いです。
ただし、慢性便秘の場合、ただの便秘に見えて実際には腸にポリープがある、あるいは大腸がんの初期症状ということもあるため、注視する必要があります。
よくある便秘の特徴
| 種類 | 症状 | 対策 |
|---|---|---|
| 弛緩性便秘 | 腸の蠕動運動が弱く便が進まない | 食物繊維や水分摂取、運動習慣 |
| けいれん性便秘 | 過度な緊張で腸が収縮して便が通りにくい | ストレスケアや精神面のリラックス |
| 直腸性便秘 | 便意があっても排便を我慢してしまう | 排便習慣の確立 |
弛緩性の便秘には酸化マグネシウム系がよく用いられ、けいれん性便秘には腸の過度な収縮を抑える薬が使われます。
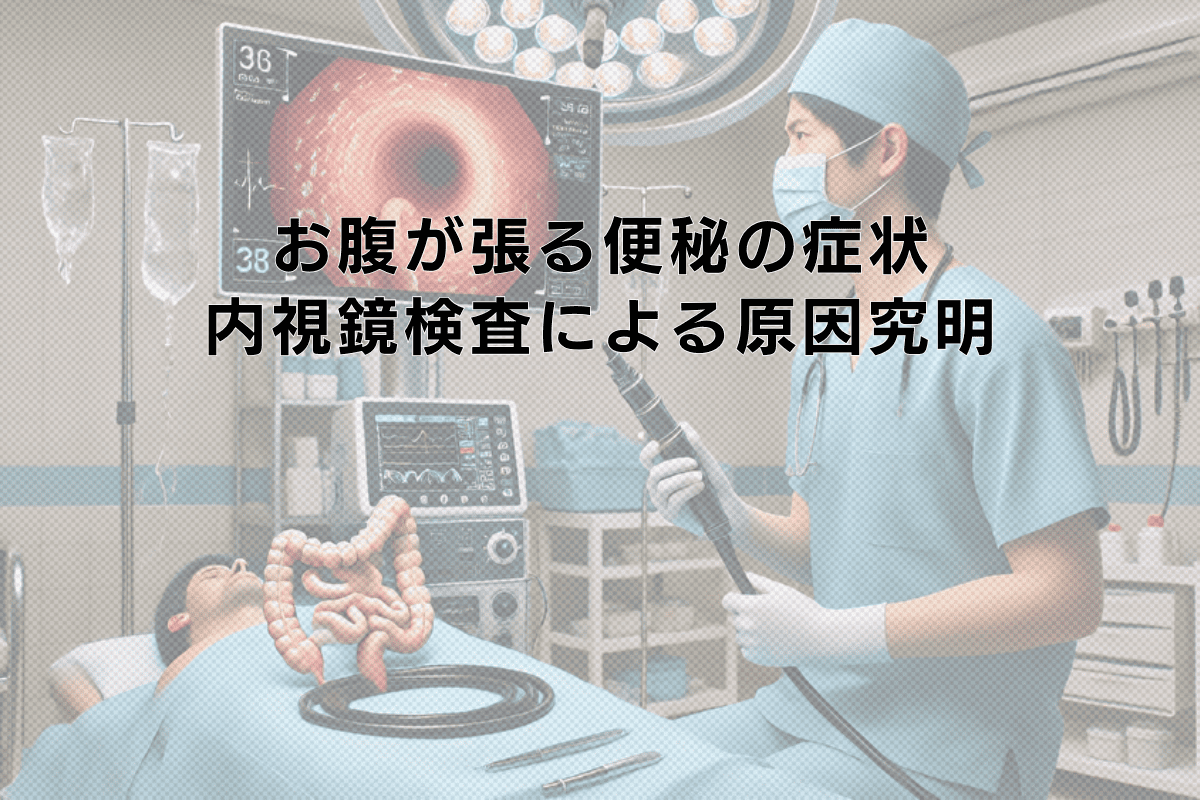
腹痛薬の種類と主な成分
市販薬の選択肢は多彩であり、どのような成分がどのように作用するのかを理解すると、症状に合わせて選びやすくなります。
主な薬の分類
医薬品としての腹痛薬は複数の目的を持った成分が配合されている場合が多いです。
- 鎮痛成分:ロキソニン(ロキソプロフェン)、イブプロフェンなど
- 胃酸抑制成分:ファモチジン、ラニチジン、制酸薬(炭酸水素ナトリウム、酸化マグネシウムなど)
- 整腸成分:乳酸菌やビフィズス菌、酪酸菌など
- 止瀉成分:ロペラミド塩酸塩、タンニン酸アルブミンなど
- 抗コリン成分:ブチルスコポラミン臭化物など
鎮痛薬は痛みを感じる神経の働きを抑制し、胃酸抑制成分は過剰な胃酸分泌を抑えることで胃痛や胸やけを緩和します。整腸成分は腸内環境を整え、止瀉成分は腸の動きを抑えて下痢を止めるなど、それぞれ役割が異なります。
鎮痛成分と併用する際の注意点
鎮痛成分だけでは腹痛の原因を取り除けるわけではないため、必要に応じて他の成分と組み合わせると効果的です。
胃酸過多が原因の腹痛の場合は、鎮痛薬だけでなく制酸薬やH2ブロッカーなどが含まれた胃腸薬を選ぶ方が根本的な対処となります。ただし、鎮痛薬の服用が多い人は胃の粘膜を傷めやすくなるため、胃腸への負担に注意が必要です。
鎮痛成分を使うときの注意点
- 既に他の痛み止めを使っていないか確認する
- 長期間服用しない
- 胃潰瘍や十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎などの既往がある場合は注意
- 服用の際は水をしっかり取り、可能なら食後に飲む
鎮痛成分には解熱・消炎作用を持つ第1類医薬品や第2類医薬品も多いため、購入時は薬剤師の説明を聞くことが大切です。
整腸成分や乳酸菌製剤
腸内環境が乱れていると感じる場合や、軽度の下痢や便秘が続く場合は、乳酸菌製剤やビフィズス菌などが配合された整腸薬を使う方法があります。
これらの成分は腸内のバランスを整えてガス溜まりや腹部膨満感を抑え、緩やかに便通を改善する効果が期待されます。急性の激しい腹痛には即効性はやや低いですが、慢性的な腹部の不快感や便通異常には使いやすいです。
整腸成分の種類と目的
| 成分 | 主な働き | 代表的な医薬品例 |
|---|---|---|
| 乳酸菌(アシドフィルス菌など) | 善玉菌を増やし有害菌の増殖を抑える | 新ビオフェルミンSなど |
| 酪酸菌 | 酪酸を作りだし、腸管のバリア機能を維持したり、炎症を抑えたりする | ミヤBMなど |
| ビフィズス菌 | 大腸での発酵を促し便の水分量を調整 | ビオフェルミン下痢止めなど |
腸内細菌は抗生物質や食事の偏りなどで大きく変化するため、整腸薬の使用で一時的に補うのは良い方法です。
胃酸抑制や胃粘膜保護成分
胃痛や胃酸過多が疑われる場合は、胃酸分泌を抑えるH2ブロッカー成分(ファモチジンなど)や、胃粘膜を保護する成分(メチルメチオニンスルホニウムなど)を含む胃腸薬が用いられます。
症状によっては制酸薬(炭酸水素ナトリウムや酸化マグネシウム)を含む総合胃腸薬を選びます。
胃酸関連の成分
| 成分名 | 働き | 注意点 |
|---|---|---|
| ファモチジン | H2受容体を抑制し胃酸分泌を抑える | 空腹時に服用すると効果的な場合あり |
| 制酸薬(炭酸水素Naなど) | 胃酸を中和して胃粘膜を保護する | 効果は比較的短時間 |
| メチルメチオニンスルホニウム | 胃粘膜の修復を促す | 胃の粘膜保護に役立つ |
胃もたれや胸やけ、胃痛を伴う場合にこれらの成分が含まれる薬を利用すると症状が改善しやすいですが、持続的な痛みがある際は受診を検討した方がよいです。
腹痛薬を使うときの注意点と服用のタイミング
腹痛薬は正しいタイミングと方法で服用することが大切ですが、症状や薬の種類によって注意点が異なり、胃腸薬や鎮痛薬を服用するときに気をつけたいポイントを詳しく解説します。
食前・食後・食間の違い
市販薬の説明書には「食後すぐ」「食間(食後2~3時間)」「就寝前」など、具体的な服用タイミングが明記されています。
胃腸薬の多くは食後に飲むよう指示されますが、腸の動きを抑えたい下痢止め薬などではタイミングが異なる場合があり、用法を守らないと想定外の副作用が出る可能性もあるため、薬剤師の説明や添付文書をよく確認しましょう。
服用タイミングのリスト
- 食後:胃酸を抑えたり食物と一緒に作用させたい成分が多い
- 食間:食物と混じらず胃腸への刺激を抑えるため
- 就寝前:夜間の症状が強まる場合の対策
さらに、酸化マグネシウム系の便秘薬は水を大量に飲む必要があるなど、成分によって異なる指示があります。
用量を守る重要性
市販薬は誰でも簡単に手に取れますが、その分、誤った用量で長期間使い続けるリスクも高まり、鎮痛薬を過剰に服用すると胃腸への負担が増し、逆に腹痛や胃炎を引き起こすことがあります。
決められた錠数や頻度を超えて使わないよう、必ずパッケージや添付文書の指示を確認することが重要です。
飲み合わせの問題
複数の薬を同時に服用すると、成分が重複したり作用が増強・減弱することがあり、NSAIDs系の鎮痛薬(ロキソニンなど)を複数併用すると胃への負担が大きくなる可能性があります。
また、処方薬を飲んでいる方は市販薬との相互作用に注意が必要です。
飲み合わせ
| 組み合わせ | 影響 | 例 |
|---|---|---|
| 複数の鎮痛薬(NSAIDs) | 胃粘膜の刺激増強 | ロキソニン+イブプロフェンの併用など |
| 抗凝固薬+解熱鎮痛薬 | 出血リスクの増加 | ワルファリン+アスピリンなど |
| 抗コリン薬+抗ヒスタミン薬 | 口渇や便秘、排尿困難などの副作用増強 | ブスコパン+眠くなる系の抗ヒスタミン薬 |
このように、飲み合わせの観点は非常に幅広いため、疑問があれば薬剤師に相談することをお勧めします。
症状が改善しない場合の対処
市販薬を数日服用しても痛みが治まらない、あるいは悪化していると感じる場合は自己判断を続けるのではなく、クリニックで診察を受けることが必要です。
特に、強い腹痛や下痢を伴うケース、血便や高熱が続くケースなどは早めに医師に相談してください。
専門家への相談とクリニック受診の目安
腹痛薬を使うことで一時的に症状が治まる場合もあれば、原因が解消されずに再発を繰り返す場合もあり、クリニックでの診察や専門医への相談がどのようなときに求められるかについて説明します。
受診を検討すべきサイン
- 3日以上市販薬を飲んでも症状が改善しない
- 発熱や嘔吐など全身症状を伴う
- 血便や黒色便などの異常な便が見られる
- 疲労感や体重減少が著しい
上記のような症状が見られたり、激しい痛みが続く場合は診察を優先します。
内科や消化器内科でできる検査
医師は問診で痛みの場所や特徴を把握し、必要に応じて血液検査や便検査、腹部エコー、内視鏡検査などを行うことで、重篤な病気や炎症性腸疾患、大腸ポリープなどを早期に見つけられます。
市販薬を飲んでいると、症状が一時的に軽くなり病気の発見が遅れる恐れもあるため、長引く腹痛には慎重な対応が大切です。
クリニックで行われる代表的な検査
| 検査名 | 目的・特徴 | メリット |
|---|---|---|
| 血液検査 | 感染症や貧血、炎症の有無を調べる | 小さな異常も数値で把握しやすい |
| 便検査 | 細菌やウイルス、潜血などを確認 | 下痢や血便の原因特定に役立つ |
| 腹部エコー | 肝臓、胆のう、すい臓などの状態を画像で観察 | 放射線被ばくがなく安全性が高い |
| CT/MRI | 詳細な腹部断面画像で臓器の形状異常を検出 | 腫瘍や大きな炎症、閉塞の有無がわかる |
| 内視鏡検査 | 胃や大腸の内部を直接観察。ポリープ切除なども可能 | 早期発見・早期治療につながる |

処方薬での治療
長引く腹痛には内服薬による治療が選択されることも多く、消化性潰瘍であればプロトンポンプ阻害薬(PPI)、過敏性腸症候群なら腸の運動を整える薬や抗不安薬が使われる場合があります。
処方薬は医師の診察と処方を受ける必要があり、自己判断で市販薬を使い続けるよりも効果的に治療を進められるケースも多いです。
処方薬
| 処方薬の種類 | 主な役割 | 代表的な薬剤 |
|---|---|---|
| PPI(プロトンポンプ阻害薬) | 胃酸分泌を強力に抑える | オメプラゾール、ランソプラゾールなど |
| H2ブロッカー | 胃酸の分泌を抑制 | ファモチジンなど |
| 抗菌薬 | 細菌性腸炎などを抑える | ニューキノロン系、ペニシリン系など |
| 整腸薬 | 腸内環境を整え、便通を正常化する | ビオフェルミン、ラックビーなど |
| 抗不安薬 | ストレスによる腸の異常運動を軽減 | ソラナックス、リーゼなど |
生活習慣の見直しと腹痛予防
腹痛薬を使って一時的に改善しても、原因となる生活習慣が変わらないと再発を繰り返す可能性があります。
日常生活で気をつけたいポイントや腹痛予防のコツを紹介し、習慣として取り入れることで胃や腸をケアしやすくする方法を解説します。
食事バランスと水分摂取
暴飲暴食や高脂質、高糖分の食事は胃腸に負担をかけ、腹痛の頻度が上がることがあるので、食事はバランスを意識し、タンパク質や野菜、炭水化物、ビタミン・ミネラルなどをまんべんなく摂ることが重要です。
また、水分摂取をこまめに行うと便通も整いやすくなり、便秘や下痢を防ぐサポートになります。
胃腸に配慮した食習慣のリスト
- ゆっくり噛んで食べる
- 夜遅い時間に大量の食事をしない
- 冷たすぎる飲み物や熱すぎる飲食物は避ける
- 空腹が長く続くことをできるだけ避ける
- アルコールやカフェインを控えめにする
これらの習慣は胃腸にかかる負担を減らし、腹痛を起こしにくい環境を作ります。
運動とストレスケア
適度な運動は血行を促進し、腸の蠕動運動を保つのに役立ちます。激しい運動でなくとも、ウォーキングやストレッチなど軽めの運動を毎日続けるだけでも便通や胃腸の調子が整いやすくなります。
さらに、ストレスは自律神経のバランスを乱し、過敏性腸症候群や急性の腹痛を引き起こしやすくするため、意識してリラックスできる時間を設けることも欠かせません。
睡眠と生活リズム
睡眠不足や不規則な生活リズムはホルモンバランスを崩し、胃酸の分泌や腸の運動にも悪影響を与え、夜更かしや徹夜が続くと、朝から腹痛が起こるケースも見受けられます。
できる限り就寝・起床の時間をそろえ、1日6~7時間の睡眠を確保することを意識しましょう。
生活習慣を整える方法
| 項目 | 意識すべきポイント | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 睡眠 | 就寝・起床時間を一定にし深い眠りを確保 | 自律神経が安定し胃腸トラブルを減らす |
| 運動 | 毎日のウォーキングや軽い筋トレを続ける | 血行促進と蠕動運動の改善 |
| ストレス管理 | 趣味やリラクゼーション、カウンセリングの活用 | 過敏性腸症候群などのストレス由来の腹痛を和らげる |
| 食事 | バランス良くよく噛んで食べる | 消化負担の軽減と便通の正常化 |
自分の体質を知る大切さ
胃腸が弱い、便秘体質、脂っこい食事をすると下痢しやすい、といった個人差は大きく、自分の体質を理解し、合わない食品や環境を可能な範囲で避けることも腹痛予防には有効な手段です。
痛みが出る前に対策を講じることで、薬を使う頻度を減らし、胃腸を安定させやすくなります。
次に読むことをお勧めする記事
【腹痛原因を知って早めの対応 消化器の病気を見逃さない】
腹痛薬の基本を押さえたら、次は実際の腹痛の原因について詳しく知っておくと安心です。薬で対処すべき症状と、専門的な治療が必要な症状を見分けるポイントをご紹介しています。
【消化器官の機能と働き|内視鏡検査で分かること】
腹痛薬について学んだ皆さんには、消化器全体の働きの知識も合わせて持っていただくと、より包括的な理解ができます。消化器官の基本的な働きから内視鏡検査で発見できる疾患まで、総合的な消化器の健康管理について説明しています。
参考文献
Falch C, Vicente D, Häberle H, Kirschniak A, Müller S, Nissan A, Brücher BL. Treatment of acute abdominal pain in the emergency room: a systematic review of the literature. European Journal of Pain. 2014 Aug;18(7):902-13.
Weydert JA, Ball TM, Davis MF. Systematic review of treatments for recurrent abdominal pain. Pediatrics. 2003 Jan 1;111(1):e1-1.
Flasar MH, Cross R, Goldberg E. Acute abdominal pain. Primary Care: Clinics in Office Practice. 2006 Sep 1;33(3):659-84.
Korterink JJ, Rutten JM, Venmans L, Benninga MA, Tabbers MM. Pharmacologic treatment in pediatric functional abdominal pain disorders: a systematic review. The Journal of pediatrics. 2015 Feb 1;166(2):424-31.
Törnblom H, Drossman DA. Centrally targeted pharmacotherapy for chronic abdominal pain: understanding and management. Gastrointestinal Pharmacology. 2017:417-40.
Törnblom H, Drossman DA. Centrally targeted pharmacotherapy for chronic abdominal pain. Neurogastroenterology & Motility. 2015 Apr;27(4):455-67.
Wallander MA, Johansson S, Ruigómez A, Garcia Rodriguez LA. Unspecified abdominal pain in primary care: the role of gastrointestinal morbidity. International journal of clinical practice. 2007 Oct;61(10):1663-70.
Mueller‐Lissner S, Quigley EM, Helfrich I, Schaefer E. Drug treatment of chronic‐intermittent abdominal cramping and pain: a multi‐national survey on usage and attitudes. Alimentary pharmacology & therapeutics. 2010 Aug;32(3):472-7.
Martinez JP, Mattu A. Abdominal pain in the elderly. Emergency Medicine Clinics. 2006 May 1;24(2):371-88.
Drossman DA. Severe and refractory chronic abdominal pain: treatment strategies. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2008 Sep 1;6(9):978-82.