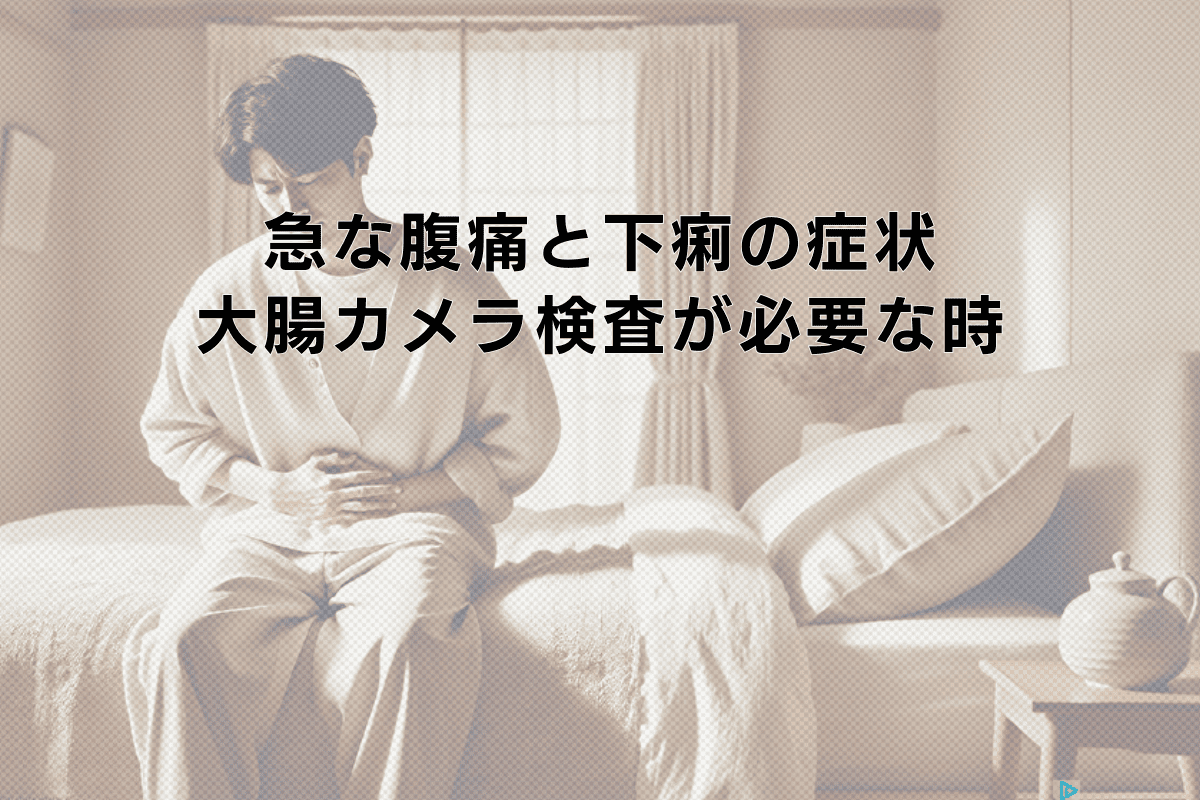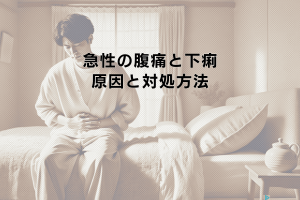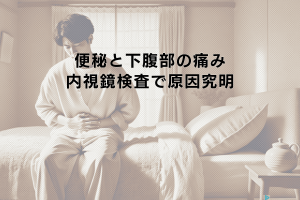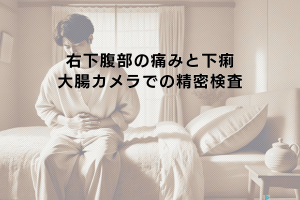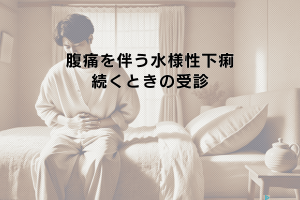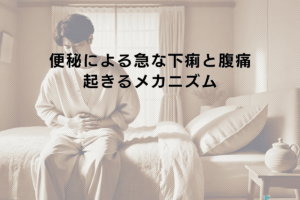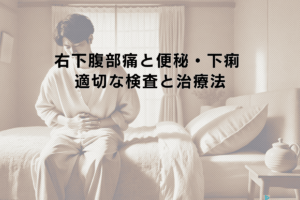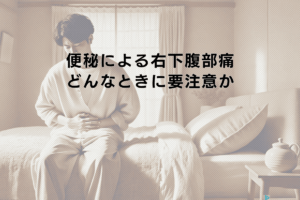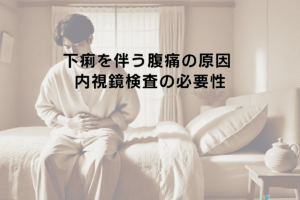急にお腹が痛くなり、そのまま下痢を繰り返してしまう経験は、多くの方にとって身近な悩みかもしれません。
食あたりや一過性の体調不良であれば自然に回復することもありますが、なかなか症状が治まらない場合は、胃や腸に何らかのトラブルが起きている可能性があります。
感染症や過敏性腸症候群、さらに大腸ポリープや大腸がんなどの疾患が隠れているケースも考えられるため、専門的な検査が大切です。
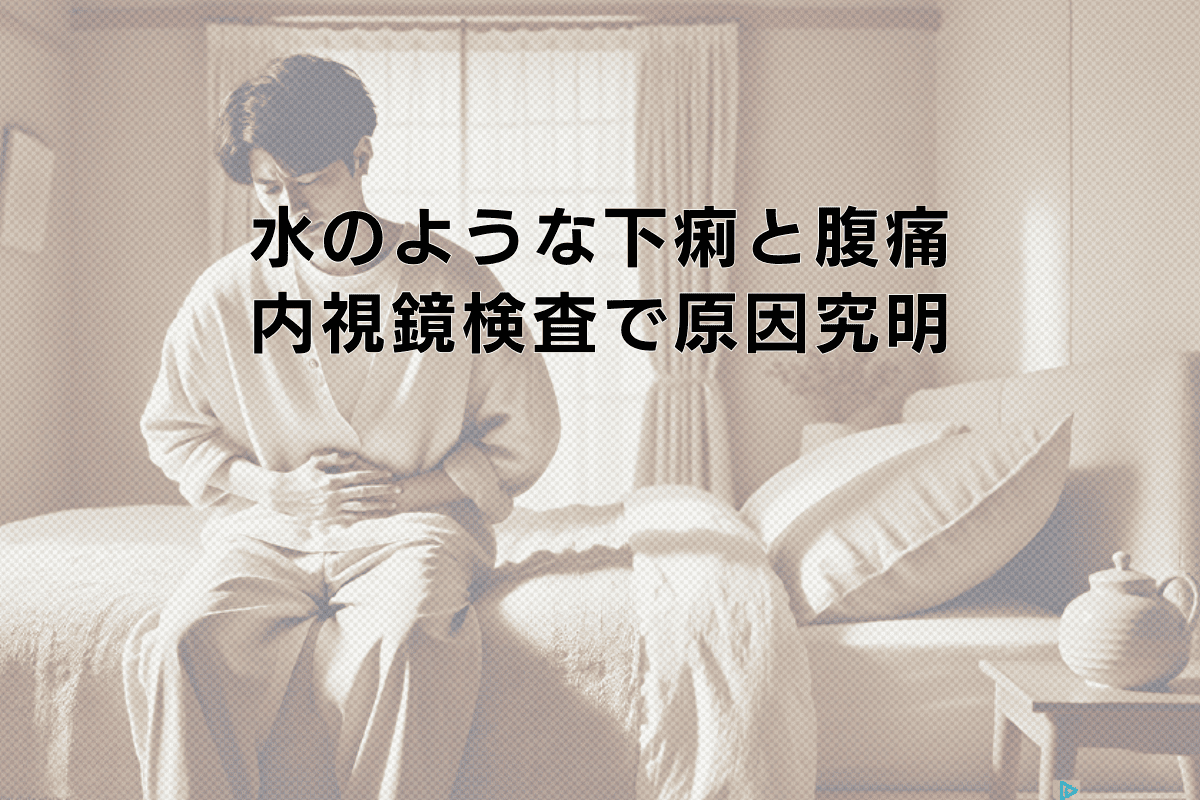
急な腹痛と下痢の特徴
突然の腹痛や下痢は、日常生活に大きな支障をきたし、短時間で何度もトイレに駆け込み、仕事や学業に集中できなくなるなど、困る場面が多々あるでしょう。
原因が単純なものから深刻な病気まで多岐にわたるため、腹痛と下痢が同時に起きるときに注目すべきポイントを知っておくことは大切です。
急に起こる腹痛と下痢の共通点
急な腹痛と下痢は、主に腸が強く刺激されている状態を示し、ウイルスや細菌などの感染症や食あたりによって腸内環境が乱れるケースのほか、ストレスや自律神経の乱れによって腸の動きが異常に活発になる場合も考えられます。
便の状態や痛みの種類には個人差がありますが、下記のような共通点が見受けられます。
- 突然の激しい腹痛をともなう、または腹痛後に急に下痢が始まる
- 水分量の多い便が数回~数十回出る
- お腹全体や下腹部に張りやゴロゴロした不快感を覚える
症状のタイミング
| タイミング | 可能性のある原因 |
|---|---|
| 食後30分~1時間以内 | 食あたり、感染性腸炎など |
| 強いストレスを感じた直後 | 過敏性腸症候群など |
| 朝起きてすぐ | 自律神経の乱れ、冷えなど |
| 深夜~早朝に突然起こる | 病原性微生物による感染、その他急性腸炎など |
短期的な下痢と慢性的な下痢の違い
下痢が1~2日で落ち着く場合は一時的な腸のトラブルの可能性が高いですが、1週間以上続く、あるいは何度も再発するようなら慢性化しているおそれがあります。
慢性的な下痢の特徴
- 便に粘液や血液が混ざる
- 体重減少や栄養不良が顕著になる
- 一定の時間帯や特定の状況で症状が悪化する
腹痛の種類や部位でわかること
腹痛には差し込むような痛み、鈍い痛み、キリキリした痛みなどさまざまな表現があり、痛む部位によっても、疑われる疾患が異なる場合があります。例えば右下腹部が鋭く痛むなら急性虫垂炎、左下腹部なら大腸の炎症が考えられます。
痛みが移動したり、一定しない場合は腸全体が刺激されている可能性が高いです。
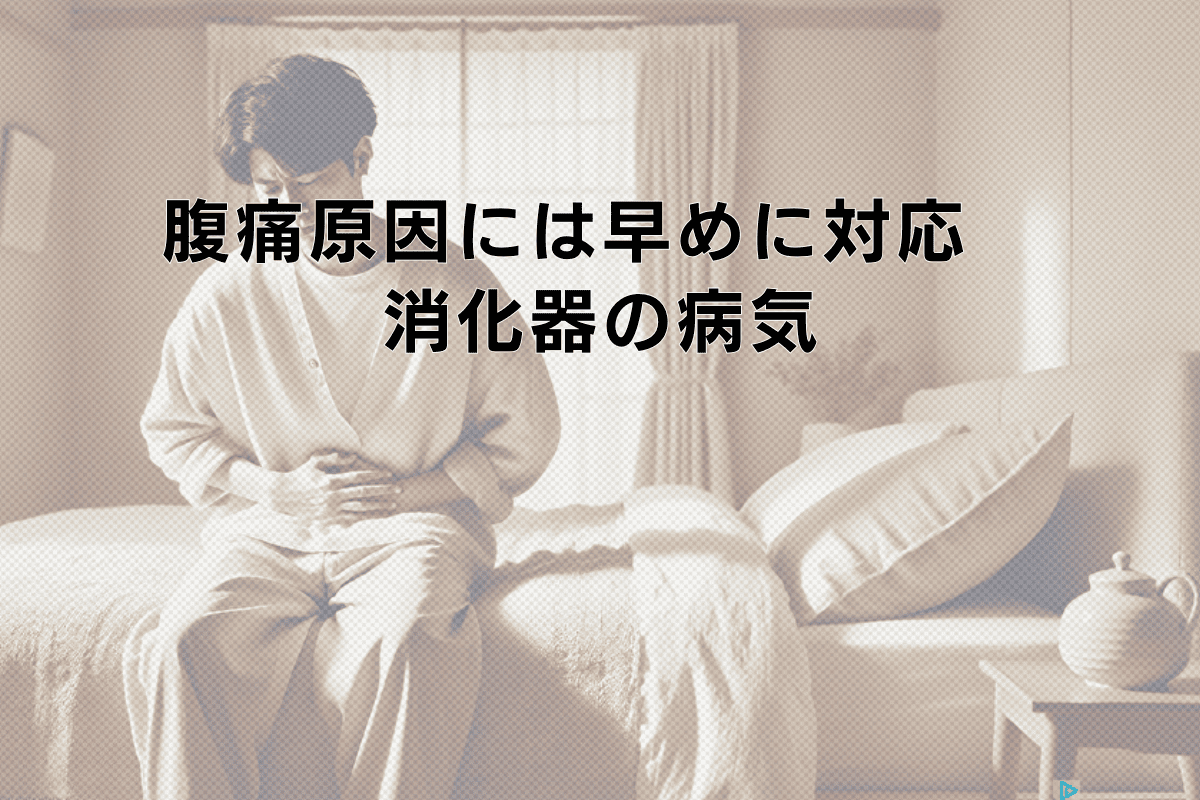
症状が落ち着いたと思っても油断は禁物
急な腹痛や下痢が一時的に収まっても、原因が解決されているとは限らず、腸に何らかの炎症やポリープがあると、しばらくして再度症状が出現することもあります。症状が繰り返すときは、自己判断で放置せず医師に相談することが必要です。
注意すべきサイン
- 強い腹痛とともに高熱がある
- 下痢に血液が混ざる
- 体重の急激な減少を伴う
- 下痢が2週間以上続く
- 便意を感じるたびに激痛を覚える
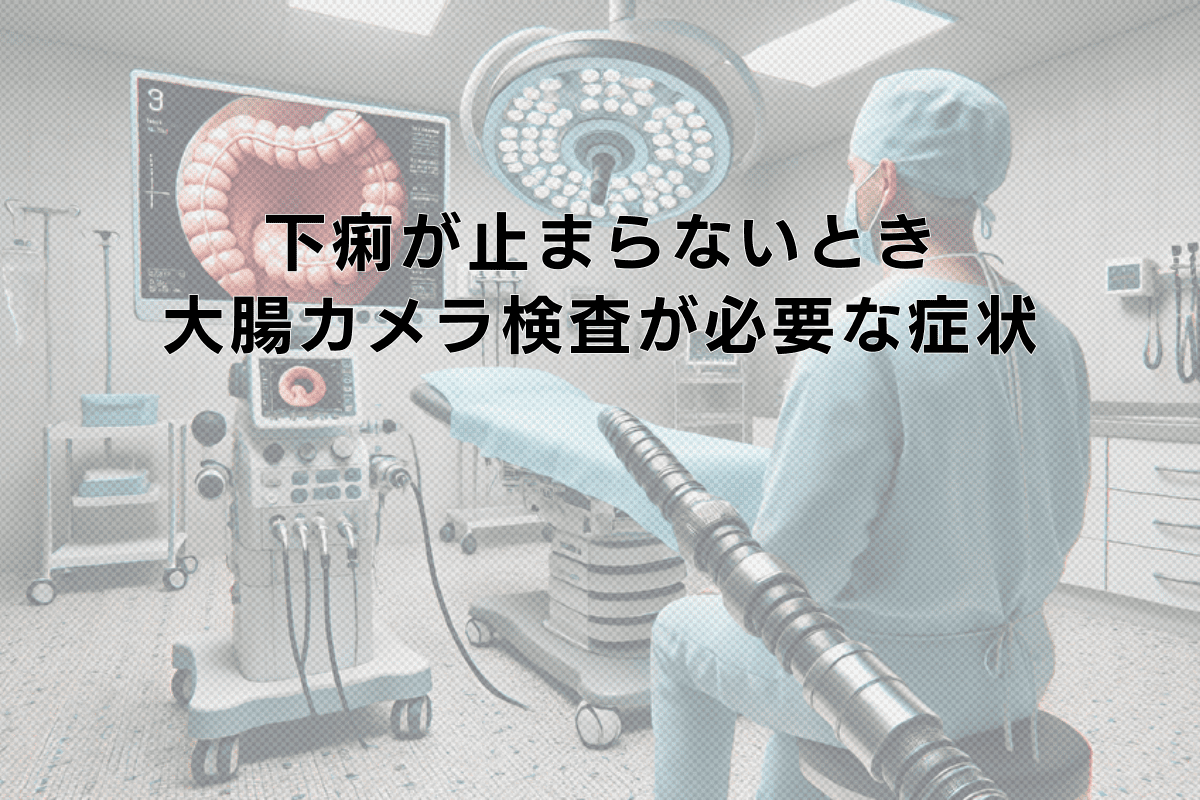
よくみられる原因
急な腹痛や下痢を引き起こす原因は多岐にわたり、食生活の乱れや精神的ストレスから、細菌感染や炎症性腸疾患までさまざまなメカニズムが考えられるため、原因を特定するには専門的な診断が役立ちます。
感染性腸炎
ウイルスや細菌によって腸が炎症を起こす状態で、原因となる病原体はノロウイルス、ロタウイルス、病原性大腸菌などが知られ、飲食物を介して体内に侵入することが多いです。
下痢だけでなく、嘔吐や発熱をともなうケースもあり、水分補給や安静が大切ですが、重症化した場合は入院治療が必要になることもあります。
過敏性腸症候群
ストレスや自律神経の乱れによって腸の運動が過剰になり、下痢や便秘、腹痛を繰り返す病気です。器質的な異常(腸に明らかな病変がある状態)が見当たらないにもかかわらず、腹痛と下痢が慢性的に続きます。
生活習慣の改善や薬物療法で症状が安定する場合もあります。
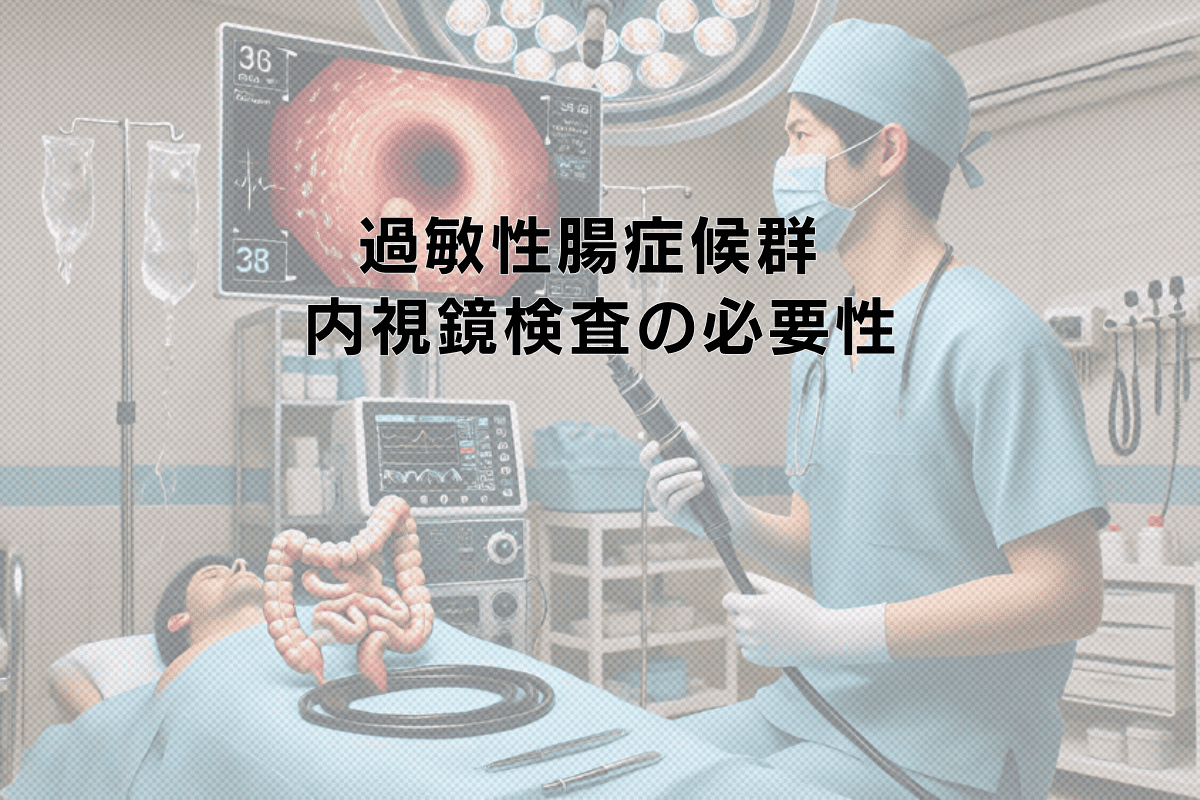
主な原因別の特徴
| 原因 | 主な特徴 | 付随症状 |
|---|---|---|
| ウイルス感染 | 急な発熱、嘔吐、激しい下痢 | 脱水症状 |
| 細菌感染 | 腹痛、血便、発熱 | 腸内出血、脱水 |
| 過敏性腸症候群 | ストレスにより悪化、ガス溜まりによる張り | 便秘と下痢が交互に起こる場合あり |
| 炎症性腸疾患 | 粘血便、持続する下痢 | 慢性的な疲労、体重減少、発熱 |
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)
自己免疫の異常で腸に慢性的な炎症が生じる病気で、潰瘍性大腸炎では大腸の内側にびらんや潰瘍が広範囲に及び、粘血便や腹痛がみられます。
クローン病は消化管のあらゆる部位が炎症を起こす可能性があり、下痢や腹痛が長期化するので、治療には専門医の診断と継続的なケアが欠かせません。

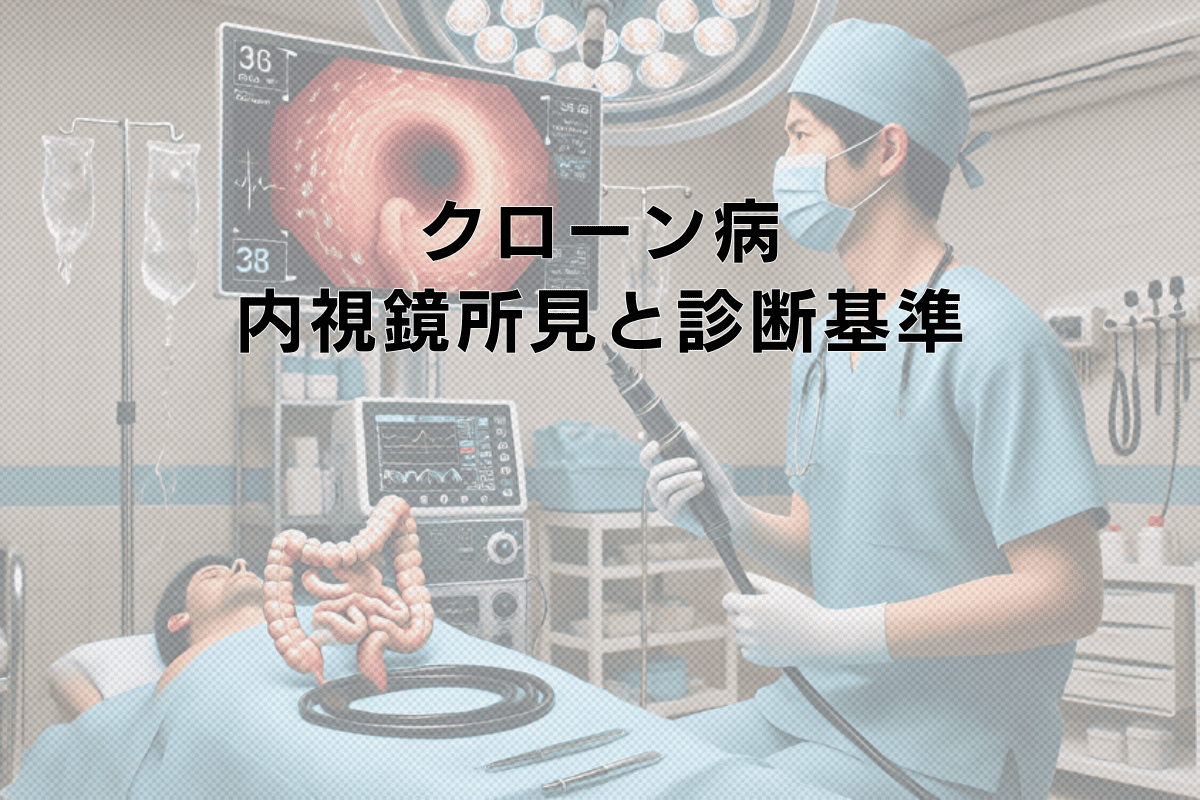
食事内容やライフスタイル
辛い物や脂っこい料理を過度に摂取したり、不規則な食事時間が続いたりすると腸に負担がかかり、急に下痢や腹痛を起こすことがあり、また、アルコールやカフェインの取り過ぎでも腸内の水分バランスが乱れ、下痢を誘発しやすくなります。
睡眠不足や過度なストレスも腸の働きを乱す要因の1つです。
下痢を助長しやすい食材・飲み物
- カフェインを多く含むコーヒーやエナジードリンク
- 香辛料の強いカレーや唐辛子入り食品
- 脂質の多いフライや脂っこい肉料理
- アルコール飲料の大量摂取
大腸カメラ検査が必要になるタイミング
急な腹痛や下痢は自然に治まる場合も少なくありませんが、特定のケースでは大腸カメラなどの内視鏡検査が必要です。深刻な病気を見逃さないために、どんなタイミングで受診を考えるべきか把握しておきましょう。
2週間以上症状が続く場合
単なる食あたりや軽い感染症であれば、多くは数日~1週間程度で改善がみられますが、2週間以上腹痛や下痢が続く場合は、腸に何らかの慢性炎症や器質的な異常があるかもしれません。
大腸カメラ検査は大腸内を直接観察できるため、潰瘍やポリープを見つけるのに有効です。
大腸カメラ検査を検討すべき症状
| 症状 | 受診の目安 |
|---|---|
| 下痢が2週間以上続く | 早期に消化器科を受診 |
| 血便がある、または便に粘液が混じる | 出血量にかかわらず早めに受診 |
| 便が細くなったり形状が変わったりしている | 数日~1週間で改善しなければ受診 |
| 強い下腹部痛や発熱を伴う | すぐに医療機関を受診 |
血便や粘液便がみられるとき
血便や粘液便は、大腸粘膜に病変があるサインの場合が多く、炎症性腸疾患や大腸ポリープ、大腸がんなど、重大な病気の初期症状として見られる可能性があるため、放置は禁物です。
トイレで便を確認した際に血液が付着している、あるいは便全体が黒っぽいなどの異常を感じたら早めに医師の診察を受けてください。
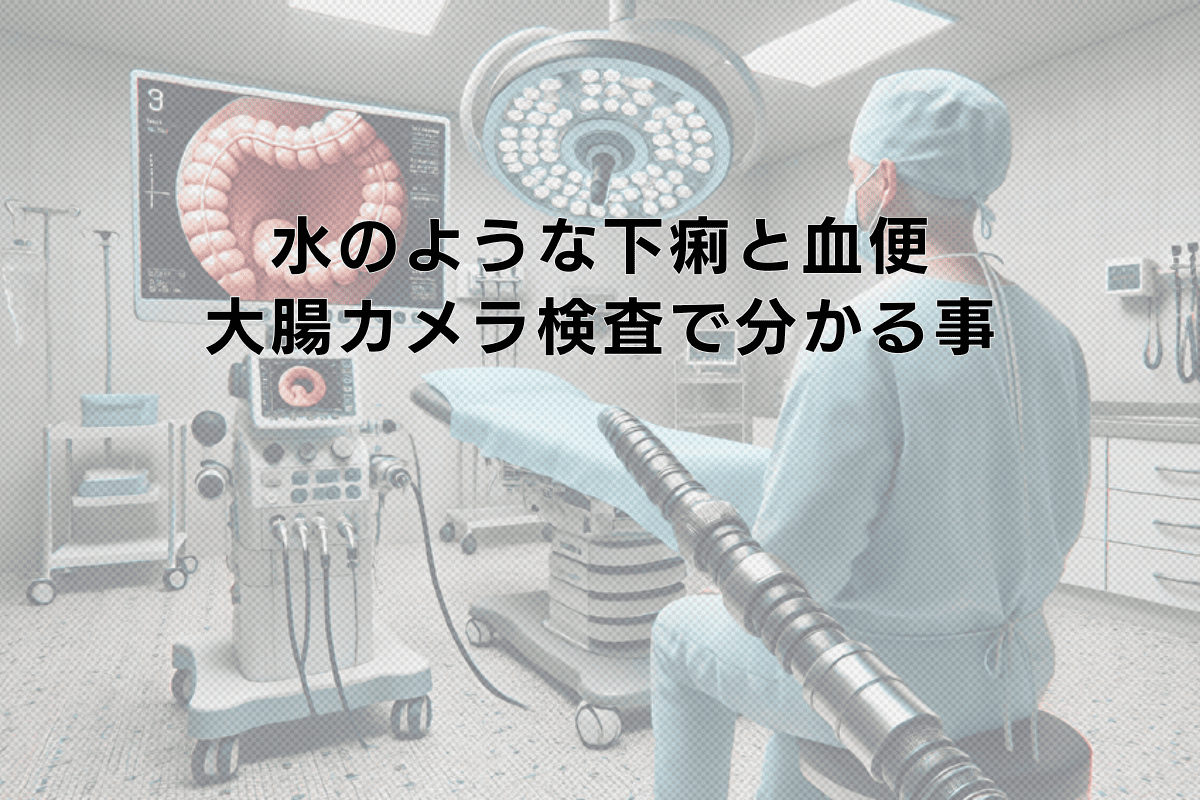
体重減少や倦怠感があるとき
慢性的な下痢や腹痛が続くと栄養吸収がうまくいかず、体重減少や強い倦怠感が現れやすくなり、体内の水分・電解質のバランスが崩れ、脱水症状を引き起こすリスクも高まります。
こうした症状が重なる場合、大腸や小腸に何らかの器質的な障害があるかもしれないため、大腸カメラ検査の受診を検討することが重要です。
症状が急速に悪化したり繰り返したりする場合
短期間で何度も繰り返し下痢に襲われる、腹痛の度合いが日に日に強まるといった変化は見逃せません。
急速に腸の状態が悪化しているか、別の合併症が潜んでいる可能性もゼロではないため、専門医に相談し早期に検査を受けることが必要です。
大腸カメラ検査を受ける目安
- 下痢や腹痛が2週間以上続く
- 血便や粘液便が出現する
- 便が極端に細くなる、形が歪になる
- 体重減少や強い倦怠感、発熱をともなう
- 症状が急激に悪化する、あるいは再発を繰り返す
内視鏡検査でわかる主な病気
大腸カメラ(大腸内視鏡検査)は、大腸内の状態を直接確認できる非常に有用な手段で、下痢や腹痛が長引く場合、内視鏡検査で原因となる病変を発見できる可能性があります。
早期発見・早期治療がカギとなる病気も多いため、検査を受けることが大切です。

大腸ポリープ
大腸の粘膜に発生するいぼ状の隆起物で、良性から悪性まで幅広い種類があり、ポリープは初期には症状がほとんどなく、放置すると一部が大腸がんに進行する可能性があります。
大腸カメラ検査ではポリープを直接観察し、必要に応じて切除・病理検査で悪性の有無を調べられます。
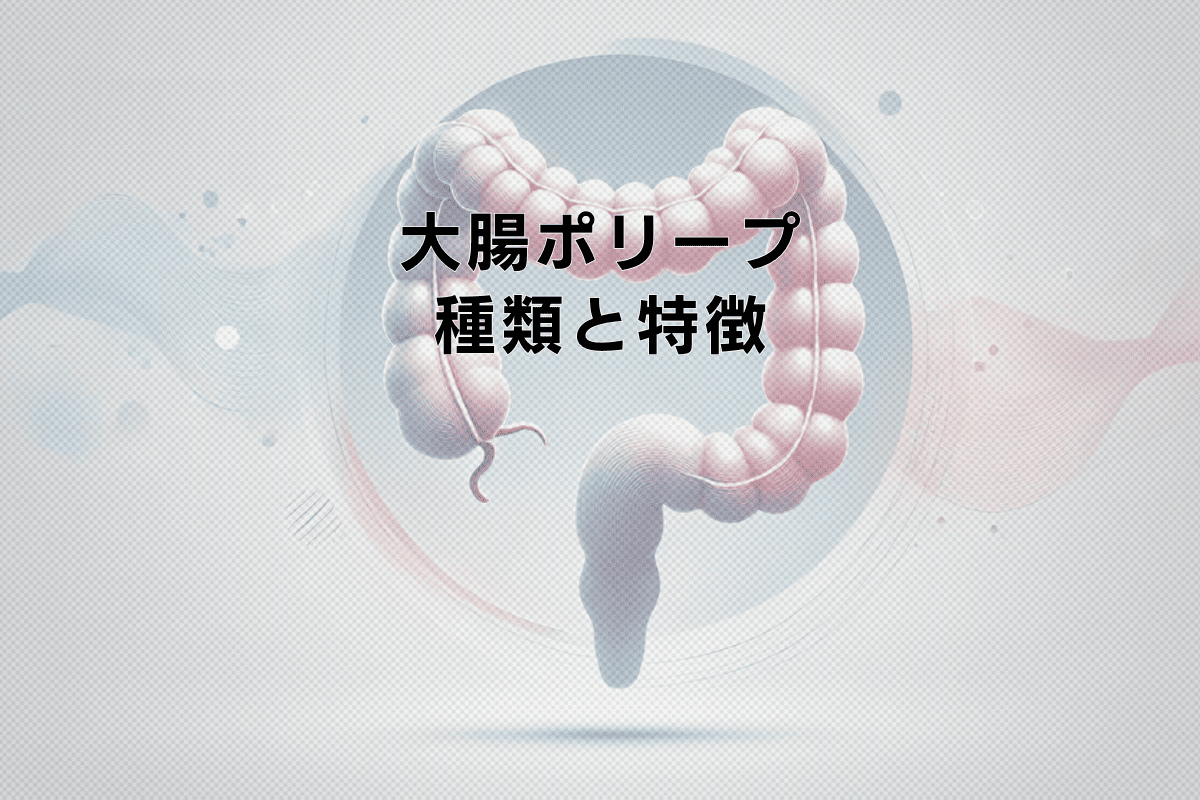
大腸がん
大腸がんは日本人のがん罹患数・死亡数の上位に位置し、早期発見が非常に重要です。血便や便通異常、体重減少などが初期症状として現れる場合がありますが、自覚症状がないまま進行するケースも少なくありません。
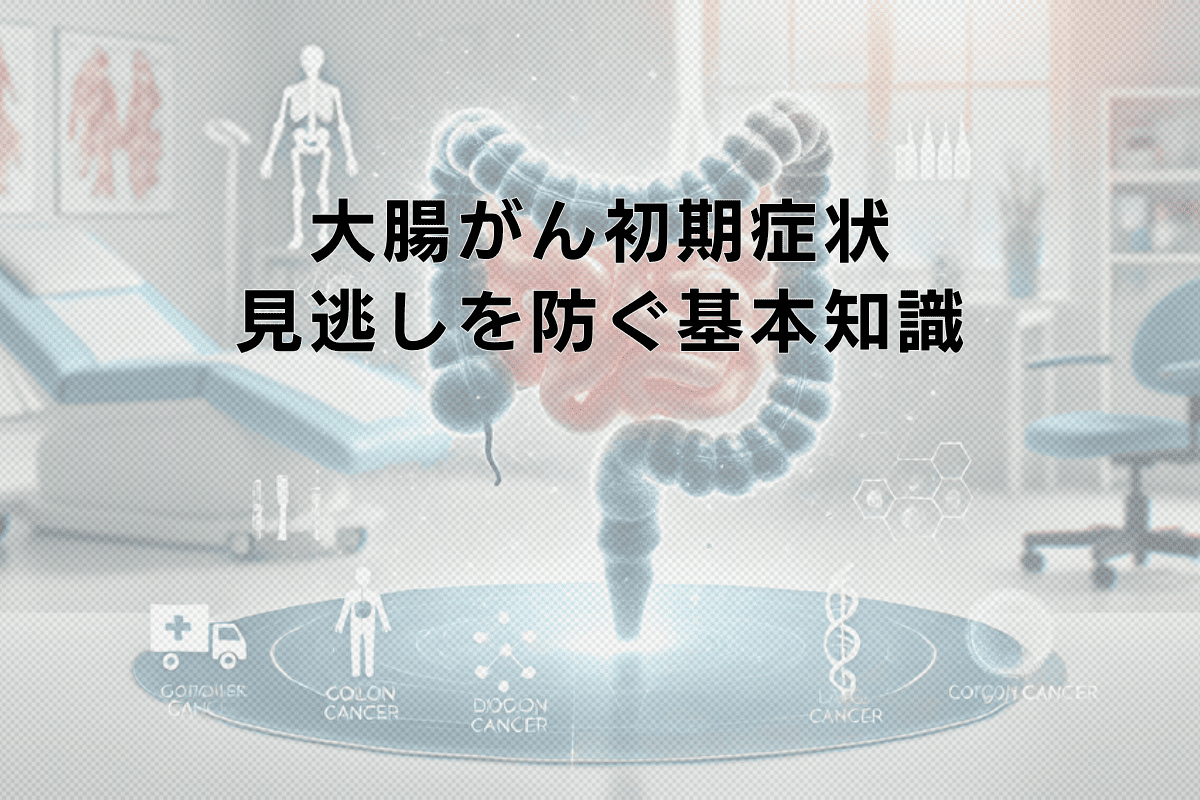
大腸ポリープ・大腸がんの特徴
| 項目 | 大腸ポリープ | 大腸がん |
|---|---|---|
| 形状 | いぼ状の隆起、平坦型 | 潰瘍形成や隆起、浸潤など多彩 |
| 症状 | 初期症状はほぼなし | 血便、便通異常、体重減少など |
| 悪性化の可能性 | 腺腫性ポリープは高い | 既に悪性腫瘍 |
| 検査法 | 内視鏡検査、病理組織検査 | 内視鏡検査、CT、病理組織検査など |
| 治療 | 内視鏡的切除、外科手術 | 外科手術、化学療法、放射線療法 |
潰瘍性大腸炎やクローン病
炎症性腸疾患は、粘膜に潰瘍やびらんができている状態で、血便や下痢、腹痛が長期にわたって続きやすく、重症化すると大腸全体に病変が広がることもあります。内視鏡検査により炎症の範囲と程度が分かり、治療方針の決定に役立ちます。
憩室炎や虚血性大腸炎
憩室炎も急な腹痛と下痢の原因となることがあります。典型的には局所的な腹部の激痛ですが、全体に痛みが広がるケースもあります。
また、血管のトラブルによって大腸がうまく血液供給を受けられない虚血性大腸炎では、下痢に血液が混ざることがあり、激しい痛みをともなう場合があります。いずれも内視鏡検査で状況確認を行うことが可能です。
炎症性腸疾患や虚血性大腸炎の主な特徴
- 潰瘍性大腸炎:粘血便、下痢が続く、発熱や全身倦怠感
- クローン病:小腸から大腸まで幅広い範囲で潰瘍が生じる
- 虚血性大腸炎:突発的な腹痛と血便、高齢者に多い傾向
- 憩室炎:腹部の鋭い痛み、嘔吐や食欲不振をともなう
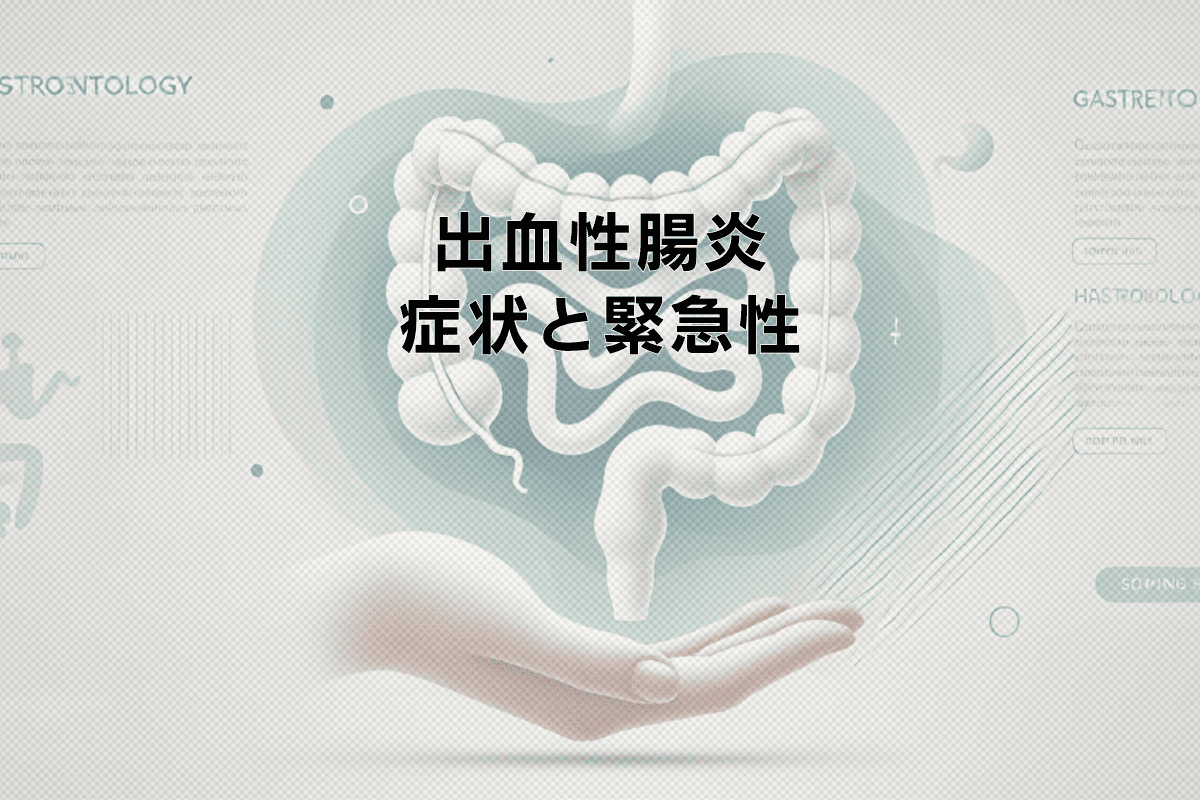
日常生活で気をつけたいポイント
急な腹痛や下痢を予防するには、腸の健康を保つライフスタイルが欠かせません。普段の食事や睡眠、ストレス対策などちょっとした心がけが腸内環境の改善につながります。
食生活の見直し
腸に優しい食事を心がけることで、急激な下痢や腹痛を起こしにくくなる可能性があり、食物繊維が豊富な野菜、果物、海藻類や発酵食品などをバランスよく取り入れるとよいでしょう。
脂質や香辛料の多い食事、アルコールやカフェインの過剰摂取は腸を刺激しやすいため、摂りすぎには注意が必要です。
食事を工夫するポイント
| 食事のポイント | 具体的な実践例 |
|---|---|
| 食物繊維を多く摂る | 野菜スープ、根菜類、きのこ、海藻など |
| 発酵食品を取り入れる | ヨーグルト、納豆、味噌、漬物など |
| 脂肪分の多い料理を控える | 揚げ物やこってりしたラーメンを減らす |
| 刺激物の摂取を控える | 辛いスパイス、カフェイン、アルコールを適度に |
| こまめな水分補給 | 水分不足にならないよう、定期的に水を飲む |

ストレスケアと睡眠の質
ストレスや睡眠不足は自律神経の乱れを引き起こし、腸の働きを不安定にします。
自分に合ったリラックス法を見つけたり、就寝前にはスマートフォンやパソコンなどの光刺激を避けたりするなど、質の高い休息を確保すると腸の調子も整いやすくなります。
適度な運動習慣
ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動を週数回取り入れると、腸の蠕動運動が活性化し便通がスムーズになりやすいです。過度の運動は疲労やストレスにつながる場合があるため、自分の体力に合った運動量を選びましょう。
腸の健康を意識した生活習慣
- 朝食を抜かず規則正しい食事リズムを作る
- スマートフォン使用や飲酒は就寝の2時間前までに済ませる
- 仕事や学業の合間に軽いストレッチや呼吸法を取り入れる
- 散歩やウォーキングなどの軽い運動を継続する
- こまめに水分を補給し、脱水を防ぐ
大腸カメラ検査の流れ
大腸カメラ検査に対して「痛そう」「準備が大変そう」といったイメージを抱く方も多いかもしれませんが、検査の手順や注意点をしっかり押さえておくと安心です。
検査前の準備
検査前日は、消化しやすい食事をとり、検査当日は下剤を飲んで腸内を空っぽにし、医師から注意事項を説明されるので、指示を守って行動するとスムーズに進められます。
大腸カメラ検査前日の注意点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 食事制限 | 繊維の多い野菜や海藻、脂っこい食品は避ける |
| 水分補給 | 水や薄めたスポーツドリンクなどを積極的に飲む |
| 下剤の服用 | 指定の時間に開始し、排出が透明になるまで継続 |
| 睡眠 | 十分な休息をとり、体力を確保 |
検査当日~検査中
検査当日は腸をカメラで観察しやすくするため、胃腸の動きを抑える薬や鎮静剤を使うことがあり、鎮静剤を使用すると、ウトウトしたり軽い眠気を感じながら検査を受けるため、不快感がやわらぎやすいです。
カメラを肛門から挿入して大腸を隅々までチェックし、必要に応じて組織の一部を採取したりポリープを切除したりします。

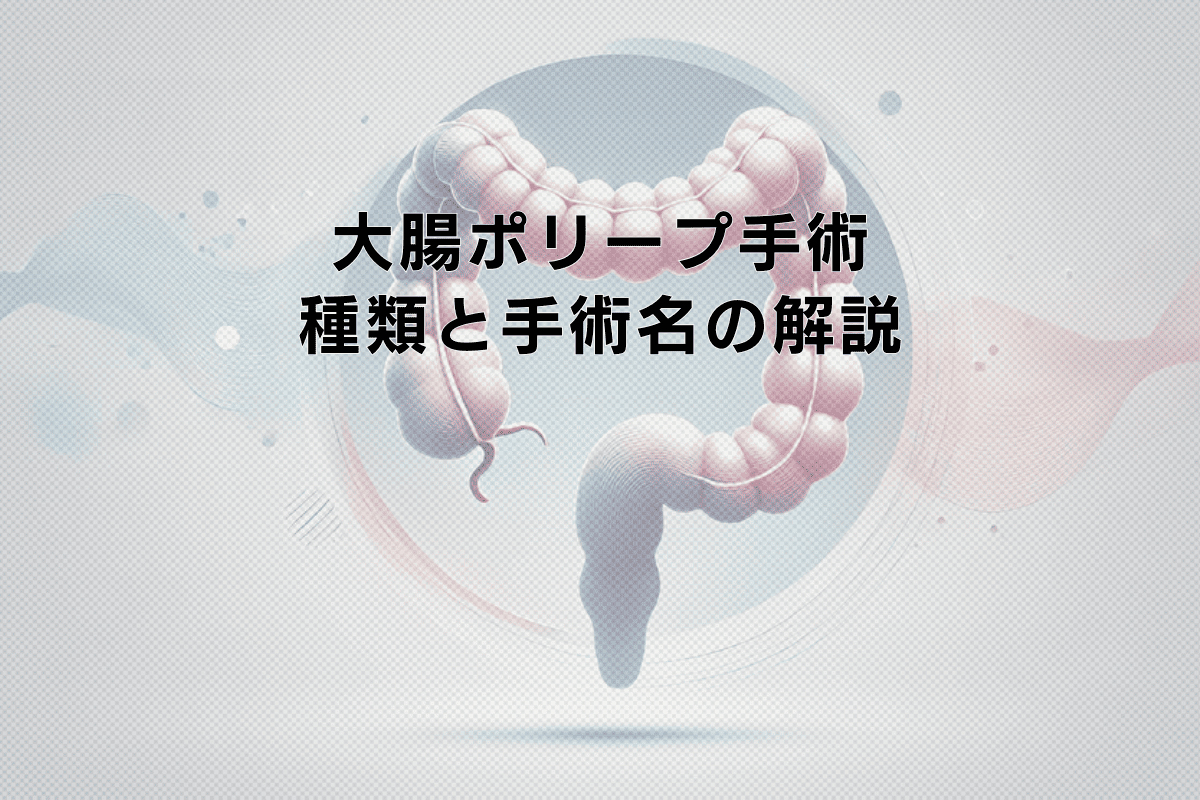
検査後の経過観察
検査後は腸にガスが溜まっているためお腹の張りを感じることがありますが、多くの場合は数時間で楽になります。ポリープ切除などを行った場合は出血リスクを防ぐために安静が必要となり、しばらくは激しい運動を避けてください。
大腸カメラ検査全体の手順
- 検査前日~当日:下剤や食事制限などで腸内を整理
- 検査直前:着替え、鎮静剤や鎮痙剤の投与
- 検査中:カメラを挿入し、大腸内部を隅々まで観察
- 必要に応じた処置:ポリープ切除や組織採取
- 検査後:休憩と安静、医師の説明と注意事項を確認
検査への不安を軽減するコツ
初めての大腸カメラ検査や、過去に痛みが強かった経験のある方は、不安を抱えることが多いかもしれません。しかし医療技術の進歩や検査のノウハウが蓄積された現代では、できるだけ苦痛を和らげる工夫が行われています。
医師やスタッフとのコミュニケーション
検査前に不安な点や疑問点を医師や看護師に遠慮なく伝えましょう。鎮静剤の使用方法や、痛みが生じた場合にどう対応してくれるのかを確認すると、精神的な負担が軽くなります。
また、自分の体質や過去の検査歴を伝えることで、より快適なケアを受けられる可能性があります。
不安を軽減するための質問例
| 質問内容 | 目的 |
|---|---|
| 検査にどのくらい時間がかかるか | スケジュールの見通しを立てて安心する |
| 鎮静剤は使用できるか | 痛みや不快感を減らす方法を把握する |
| どのような合併症に注意するか | 検査後に起こりうるリスクを事前に知る |
| 食事や行動の制限はあるか | 検査後の生活リズムをイメージしやすくする |
鎮静剤の活用
痛みや不快感への恐怖が強い場合は、鎮静剤を使う選択肢があり、鎮静剤には個人差がありますが、ほとんど眠っているような状態で検査が行われ、検査後の記憶も曖昧になることが多いです。
使用後はふらつきや眠気が残る場合があるため、検査当日は車の運転を控えるなどの注意が必要になります。
適切な準備を行うことで検査は受けやすくなる
大腸カメラ検査は身体の負担を最小限に抑えつつ、正確な診断情報を得られる手段です。準備段階でしっかりと腸を空にし、検査時には鎮静や医師とのコミュニケーションを図れば、多くの方が大きな苦痛なく検査を終えられます。
検査前後の過ごし方
| 時期 | 具体的な対策 |
|---|---|
| 検査前 | 下剤と食事制限をしっかり守り、身体を清潔にする |
| 検査中 | 落ち着いて大きく呼吸し、痛みがあれば即報告 |
| 検査後 | 安静にして体調を確認。特に食事は医師の指示に従う |
Q&A
急な腹痛や下痢で悩む方や、これから大腸カメラ検査を検討している方が気になりやすい疑問点をまとめました。自分の症状や不安に照らし合わせて参考にしてください。
- 病院に行くタイミングがわかりません。どの程度の症状で受診すればいいですか?
-
1~2日で治まる軽い下痢や腹痛であれば、様子を見てもよい場合があります。
しかし2週間以上続く、血液や粘液が混ざった便が続く、体重が減るほどの下痢があるなど、明らかに普段と違う異常が見られる場合は早めに受診することが望ましいです。
- 大腸カメラ検査は痛いと聞いたのですが、我慢できないほどでしょうか?
-
検査時の痛みの感じ方には個人差がありますが、鎮静剤を活用すればウトウトした状態で検査を受けられます。その場合、痛みや違和感が大幅に軽減される傾向があるため、恐怖心が強い方でも受けやすくなります。
- 下剤を飲むのがつらそうです。何か負担を減らす工夫はありますか?
-
下剤の味に慣れない方は、適度に冷やした状態で飲むと味が緩和されることがあります。また、飲む間に無理のない範囲で休憩を挟んだり、ストローを使って口に触れる量を少なくしたりするのも効果的です。
飲み終わる時間をしっかり確保して、焦らず取り組むと飲みやすくなるでしょう。
- 大腸カメラ検査の結果、異常が見つからなかった場合でも安心できますか?
-
大腸カメラ検査で異常が見つからなければ大きな病気の可能性は低いと考えられますが、下痢や腹痛はさまざまな要因で起こります。
過敏性腸症候群や機能性ディスペプシアなど、内視鏡では確認しにくい要因があるかもしれません。医師と相談しながら、生活習慣の見直しやストレス対策を続けることも重要です。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査の前日に必要な準備と食事の注意点】
急な腹痛と下痢について理解が深まったら、次は実際の大腸カメラ検査の準備について知っておくと安心です。検査を検討されている方に特に参考になる内容です。
【腸の健康が体を支える 腸内環境を整える】
腹痛と下痢を防ぐには腸内環境の改善が欠かせません。食事・運動・睡眠を総合的に見直すコツを学びましょう。
参考文献
Mayumi T, Yoshida M, Tazuma S, Furukawa A, Nishii O, Shigematsu K, Azuhata T, Itakura A, Kamei S, Kondo H, Maeda S. The practice guidelines for primary care of acute abdomen 2015. Journal of General and Family Medicine. 2016 Mar 18;17(1):5-2.
Harano Y, Kotajima L, Arioka H. Case of cytomegalovirus colitis in an immunocompetent patient: a rare cause of abdominal pain and diarrhea in the elderly. International Journal of General Medicine. 2015 Mar 3:97-100.
Sobue I, Ando K, Iida M, Takayanagi T, Yamamura Y, Matsuoka Y. Myeloneuropathy with abdominal disorders in Japan: A clinical study of 752 cases. Neurology. 1971 Feb;21(2):168-.
Sasaki Y, Komatsu F, Kashima N, Sato T, Takemoto I, Kijima S, Maeda T, Ishii T, Miyazaki T, Honda Y, Shimada N. Clinical differentiation of acute appendicitis and right colonic diverticulitis: a case-control study. World Journal of Clinical Cases. 2019 Jun 26;7(12):1393.
Kanazawa M, Miwa H, Nakagawa A, Kosako M, Akiho H, Fukudo S. Abdominal bloating is the most bothersome symptom in irritable bowel syndrome with constipation (IBS-C): a large population-based Internet survey in Japan. BioPsychoSocial Medicine. 2016 Dec;10:1-8.
Nagata N, Ishii N, Manabe N, Tomizawa K, Urita Y, Funabiki T, Fujimori S, Kaise M. Guidelines for colonic diverticular bleeding and colonic diverticulitis: Japan Gastroenterological Association. Digestion. 2019 Jan 14;99(Suppl. 1):1-26.
Ito D, Hata S, Seiichiro S, Kobayashi K, Teruya M, Kaminishi M. Amebiasis presenting as acute appendicitis: Report of a case and review of Japanese literature. International Journal of Surgery Case Reports. 2014 Jan 1;5(12):1054-7.
Barr W, Smith A. Acute diarrhea in adults. American family physician. 2014 Feb 1;89(3):180-9.
Aranda-Michel J, Giannella RA. Acute diarrhea: a practical review. The American journal of medicine. 1999 Jun 1;106(6):670-6.
Flasar MH, Cross R, Goldberg E. Acute abdominal pain. Primary Care: Clinics in Office Practice. 2006 Sep 1;33(3):659-84.
Swischuk LE. Abdominal pain, vomiting, and diarrhea. Pediatric emergency care. 1999 Feb 1;15(1):70-3.