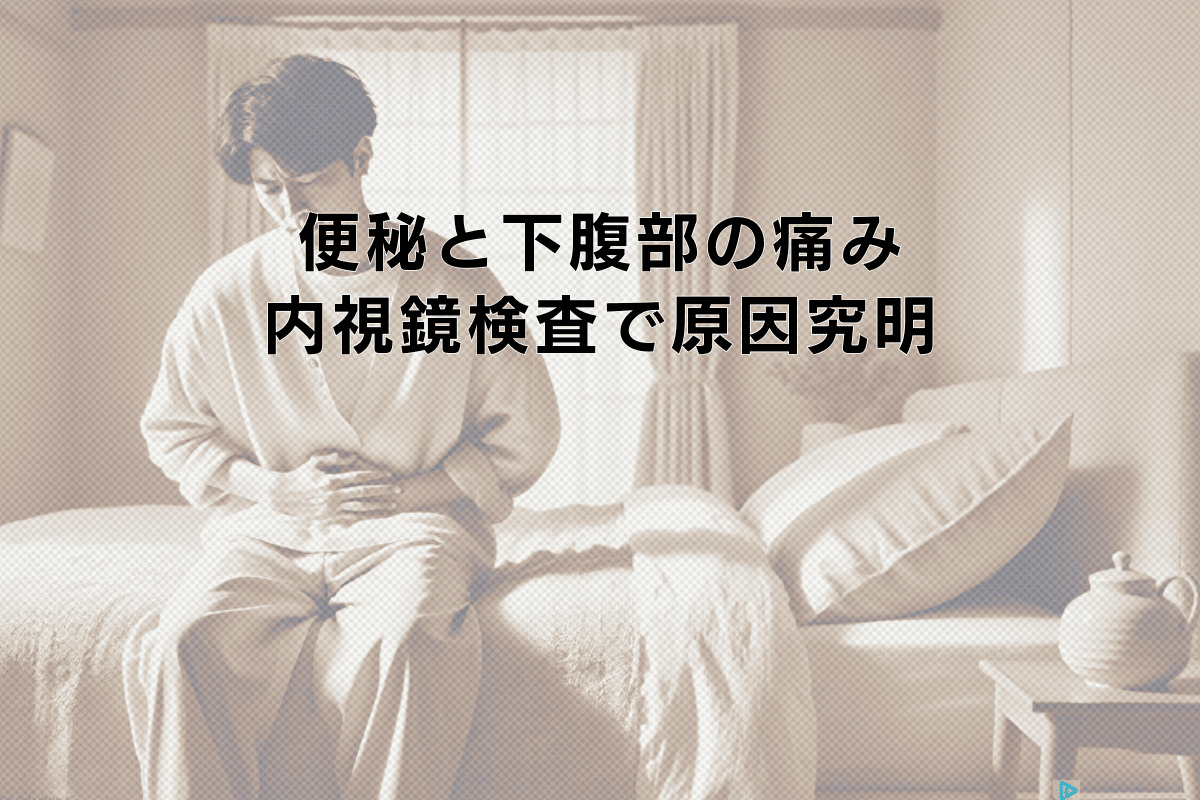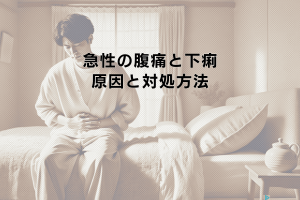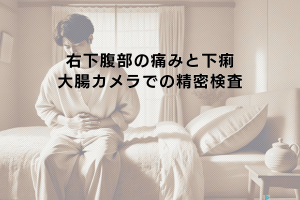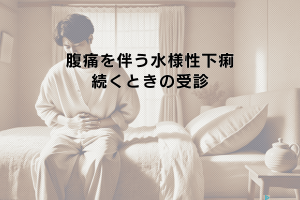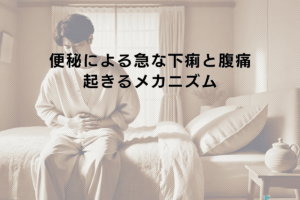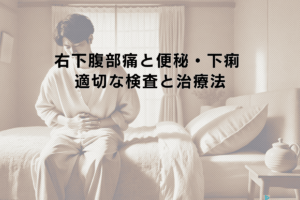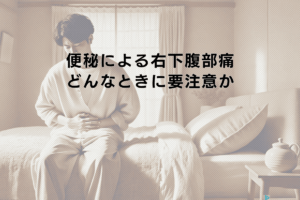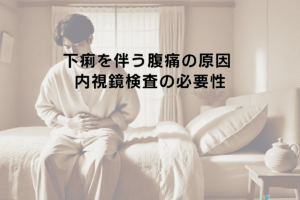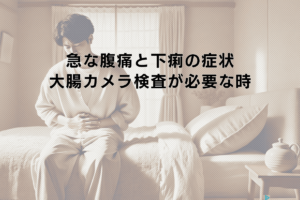多くの人が経験する便秘ですが、それに伴う下腹部の痛みや張りは、日常生活に大きな影響を与えます。
下腹部が張って苦しい、押すと痛いといった症状は、単に便が溜まっているだけでなく、何らかの病気が隠れているサインかもしれません。
この記事では、便秘と下腹部の痛みの関係、考えられる原因、正確な診断に繋がる大腸内視鏡検査の重要性について詳しく解説します。
下腹部の痛みと便秘の基本的な関係
便秘と下腹部痛は、消化器症状の中でも特に関連性が高いものです。多くの場合、排便によって腹痛は軽快しますが、痛みが持続したり、生活に支障をきたすほどの強さであったりする場合は、原因を慎重に探る必要があります。
なぜ便秘になるとお腹が痛くなるのか
便秘による腹痛の発生には、複数の要因が関わっていて、最も直接的な原因は、大腸内に滞留した便そのものです。
便が長く腸内にとどまると、水分が過剰に吸収されて硬くなり、硬い便の塊が繊細な腸の粘膜を物理的に圧迫し、刺激することで鈍い痛みが生じます。さらに、体は便を排出しようとして、腸を波打たせる蠕動運動を通常より強く起こします。
この過剰な腸の動きが、お腹がキューっと差し込むような、けいれん性の痛みを引き起こすのです。
下腹部に痛みが集中する理由
人間の大腸は、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸へと続き、便は、この経路を通りながら最終的にS状結腸や直腸に溜められます。
これらの部分は骨盤内に位置し、解剖学的に下腹部にあたるため、便の滞留による物理的な圧迫や、溜まったガスによる内圧の上昇といった刺激は、下腹部で強く感じられる傾向があります。
S状結腸は文字通りS字に大きく湾曲しているので、特に便が溜まりやすく、痛みの原因となりやすい部位です。
痛みの感覚と関連部位
| 痛みの感覚 | 主な原因 | 考えられる部位 |
|---|---|---|
| ズキズキする鈍い痛み | 硬い便による腸壁の持続的な圧迫 | S状結腸・直腸 |
| キューっと差し込む痛み | 便を排出しようとする腸の過剰な蠕動運動 | 大腸全体(特に下行結腸) |
| 張って重苦しい感じ | 腸内ガスによる内圧の上昇 | 大腸全体(特に下腹部) |
痛みの種類と便秘の重症度
痛みの性質は、便秘の状態や重症度を判断する上での重要な手がかりになり、お腹が全体的に張るような鈍痛は、主にガスの滞留が原因です。
特定の場所をピンポイントで押すと強く痛む、体を動かすと響くような鋭い痛み、冷や汗を伴うほどの激痛などは、単なる便秘ではなく、腸に強い炎症や閉塞が起きている可能性を示唆します。
痛みの強さや種類、持続時間などを注意深く観察することが大事です。
便秘が引き起こす下腹部の張りと不快感
便秘に伴う下腹部の張りは、多くの人が経験する不快な症状で、お腹がパンパンに膨らみ、衣服のウエストがきつく感じられたり、常に圧迫感があったりと、QOL(生活の質)を著しく低下させます。
下腹部の張りの正体はガス
腸内に便が長時間滞留すると、腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスが崩れ、ウェルシュ菌などのいわゆる悪玉菌が優勢になります。
悪玉菌は、タンパク質やアミノ酸を分解する過程で、硫化水素やインドール、スカトールといった腐敗ガスを発生させ、ガスは強いにおいを伴うのが特徴です。
通常、ガスは便と共に排出されますが、便秘で出口が塞がれていると、腸内に充満してしまいます。溜まったガスが風船のように腸を内側から膨らませ、下腹部の強い張りと不快感を起こすのです。
便秘時に発生しやすいガスの種類
| ガスの主成分 | 発生源 | 特徴 |
|---|---|---|
| 窒素、酸素 | 食事や会話時に飲み込んだ空気 | 無臭、ガスの約7割を占める |
| メタン、二酸化炭素 | 善玉菌による食物繊維の分解 | 無臭、腸のエネルギー源になることも |
| 硫化水素、アンモニア | 悪玉菌によるタンパク質の腐敗 | 腐卵臭、おならの強いにおいの原因 |
押すと痛いと感じる原因
下腹部を押したときに痛みを感じる場合、それは体が発している重要なサインで、専門的には圧痛と呼びます。溜まったガスや硬い便でパンパンに張った腸が、外からの圧迫によってさらに刺激されることで痛みを感じるのが一つ目の理由です。
二つ目の理由として、便秘が長引くことで腸管に炎症が起きている可能性が考えられます。特に、大腸の壁にできた憩室というポケットに便がはまり込んで炎症を起こす憩室炎では、炎症部位に一致して強い圧痛が見られます。
押した手を急に離したときに痛みが響く場合(反跳痛)は、腹膜炎の可能性もあり、より注意が必要です。
張りを和らげるための応急処置
下腹部の張りがつらいときは、まず体をリラックスさせ、腸の緊張を和らげることが重要です。腹部を蒸しタオルやカイロで温めると、血行が良くなり腸の動きが改善することがあります。
また、仰向けに寝て膝を立て、おへその周りを時計回りに優しくマッサージするのも、ガスの移動を助け、排出を促す効果が期待できます。
ただし、痛みが非常に強い場合や、押すと激痛が走る場合に自己判断で強くマッサージを行うのは危険です。症状が改善しない場合は、医療機関に相談してください。
注意すべき下腹部の痛みを伴う便秘のサイン
ほとんどの便秘は機能性のもので、生活習慣の改善で対応できますが、中には緊急の治療を要する、あるいは重大な病気が背景にあるケースもあります。
いつもの便秘だと軽視せず、これから挙げるような危険なサインを見逃さないことが、健康を守る上で非常に重要です。
単なる便秘ではない危険な症状
下腹部痛を伴う便秘に加えて、以下のような症状が一つでも見られる場合は、様子を見ずに速やかに医療機関を受診してください。
このような症状は、腸閉塞(イレウス)や大腸憩室炎、虚血性大腸炎、虫垂炎、さらには進行した大腸がんといった、緊急性の高い病気の可能性を示唆しています。
- 冷や汗が出るほどの我慢できない激痛
- 吐き気や嘔吐を繰り返す
- 38度以上の発熱がある
- 便に血が混じる(黒い便、赤黒い便)
痛みが長引く、または悪化する場合
一時的な痛みではなく、数日間にわたって痛みが続く、あるいは時間とともに痛みの程度がどんどん強くなっていく場合も、慎重な対応が求められます。
特に、体を動かすと響く、咳をするだけで痛む、といった症状は、腹膜にまで炎症が及んでいるサインかもしれないので、痛みの変化には常に気を配り、我慢せずに専門医の診察を受ける判断が大事です。
受診を検討すべき痛みの目安
| 症状 | 緊急度 | 考えられる状態 |
|---|---|---|
| 突然発症した、これまでにない激痛 | 高 | 腸閉塞、腸管穿孔、虚血性大腸炎など |
| 痛みが徐々に強くなり、発熱を伴う | 中 | 憩室炎、虫垂炎、感染性腸炎など |
| 鈍い痛みがずっと続き、体重が減ってきた | 低〜中 | 慢性的な炎症、大腸がんなどの腫瘍性病変 |
市販薬を飲んでも改善しないとき
市販の便秘薬や整腸剤を説明書の通りに服用しても症状が全く改善しない、あるいはかえって腹痛が悪化するような場合も、専門的な診察が必要です。
市販薬は多種多様ですが、自分の便秘のタイプに合っていない薬を使用すると、症状を悪化させることさえあります。
腸の動きが低下している弛緩性便秘の人が、腸を刺激するタイプの薬を飲むと効果が期待できますが、けいれん性便秘の人が使うと、腹痛がさらにひどくなる可能性があり、薬が効かない背景には、病気が原因である可能性も考えられます。
全身の不調を伴うケース
便秘や下腹部痛といったお腹の症状だけでなく、原因不明の体重減少、顔色が悪いと指摘される(貧血)、食欲がわかない、といった全身の症状が現れた場合、消化管のどこかで持続的な出血や栄養吸収の障害が起きている可能性があります。
大腸がんなどでは、がんからの慢性的な出血によって貧血が進行し、これが最初のサインとなることも少なくありません。症状は、体が発する重要な警告と捉えるべきです。
下腹部の痛みと便秘の裏に隠れる病気
下腹部の痛みや張りを伴う便秘は、様々な消化器疾患の一症状として現れることがあります。ここでは、代表的な病気について、特徴を詳しく解説します。自己判断はせず、気になる症状があれば専門医に相談することが重要です。
過敏性腸症候群(IBS)
過敏性腸症候群は、内視鏡検査などで調べても、腸に明らかな炎症や潰瘍といった器質的な異常が見つからないにもかかわらず、腹痛や腹部不快感、便通異常が慢性的に続く病気です。
ストレスや不安、生活リズムの乱れなどが、脳と腸の相互作用(脳腸相関)に影響を与え、腸が知覚過敏になったり、運動機能に異常をきたしたりすることが原因と考えられています。
便秘が優位なタイプ(便秘型IBS)では、ウサギの糞のようなコロコロした硬い便が特徴で、強い腹痛を伴うことが多いです。排便によって腹痛が一時的に和らぐ傾向があります。
大腸憩室症・憩室炎
大腸の壁の一部が、圧力に負けて外側に袋状にぽこっと飛び出したものを憩室と呼び、憩室が多数ある状態が大腸憩室症です。
憩室があるだけでは通常は無症状ですが、憩室の中に便などが詰まって細菌が感染し、炎症を起こすと憩室炎となります。憩室炎を発症すると、多くは左下腹部に持続的な強い痛みが生じ、発熱や吐き気を伴うこともあります。
炎症が強いと、憩室の壁が破れて穴が開く(穿孔)こともあり、その場合は緊急手術が必要です。
憩室炎の主な症状
| 症状 | 特徴 |
|---|---|
| 腹痛 | 持続的で局所的な痛み(S状結腸に多いため特に左下腹部) |
| 発熱 | 炎症の程度に応じて38度以上の高熱が出ることもある |
| 吐き気・嘔吐 | 炎症による腸の麻痺や機能低下が原因 |
炎症性腸疾患(IBD)
腸に原因不明の慢性的な炎症が起こる病気の総称で、主に大腸の粘膜に炎症が広がる潰瘍性大腸炎と、口から肛門までの消化管のあらゆる場所に炎症が起こりうるクローン病があります。
どちらの病気も、腹痛、下痢、血便などが主な症状ですが、炎症によって腸管がむくんで内腔が狭くなる(狭窄)と、便が通りにくくなり、便秘や腹部膨満感を起こすことがあります。
特にクローン病では狭窄をきたしやすく、腸閉塞の原因になることもあります。
大腸がん
大腸がんが進行し、腫瘍が大きくなることで腸管を物理的に塞いでしまうと、便の通過が妨げられ、便秘や下腹部痛、お腹の張りといった症状が現れます。
これは機械的な閉塞であり、症状が出た時点では、がんがかなり進行している可能性があります。便が細くなる、残便感がある、血便が出る、といった症状も大腸がんの重要なサインです。
症状は他の良性の病気でも見られますが、大腸がんの可能性を常に念頭に置き、早期に精密検査を受けることが極めて重要です。
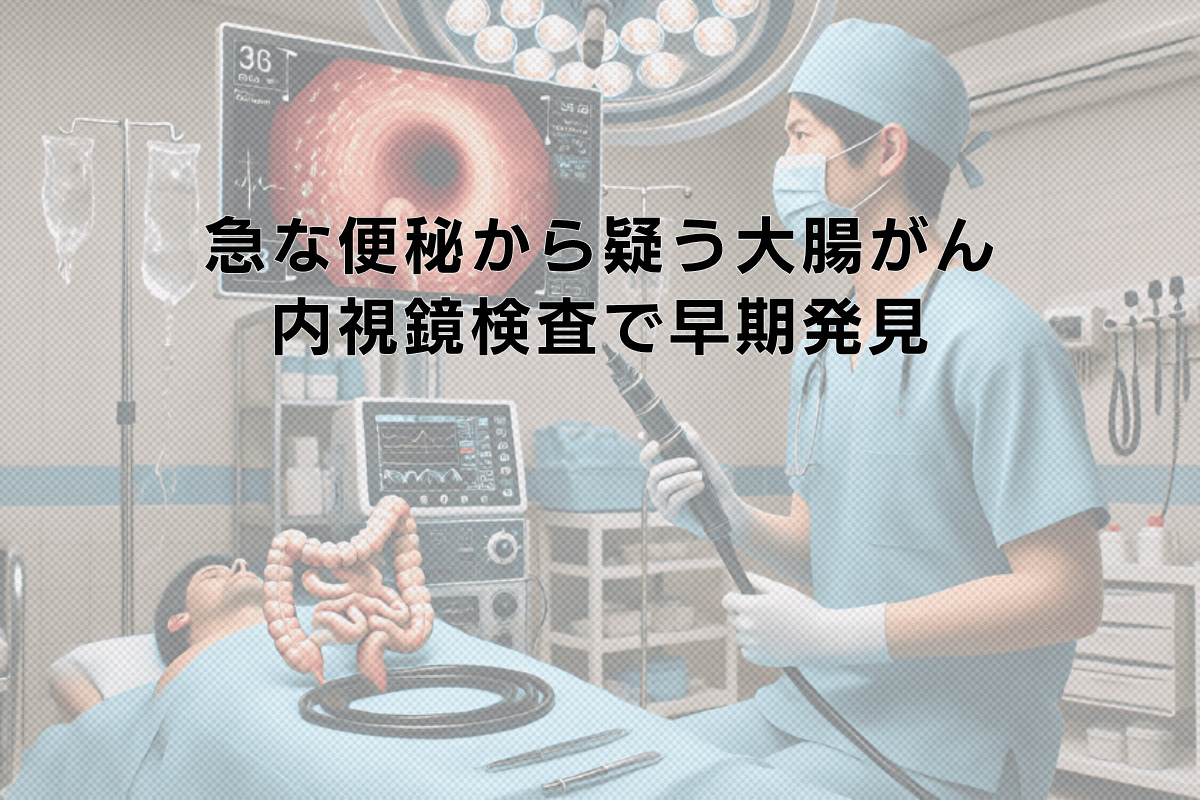
専門医による診察と診断の重要性
便秘と下腹部痛の原因を正確に突き止めるためには、消化器を専門とする医師による診察が欠かせません。
まずは問診で症状を詳しく伝える
診察の第一歩は、患者さんから症状について詳しく話を聞くことです。医師は、診断の手がかりとなる情報を得るために、様々な角度から質問をします。正確な情報を伝えることが、的確な診断への近道となります。
事前にメモを準備しておくと、伝え忘れを防ぐことができます。
問診で伝えると良い情報
| 項目 | 伝える内容の例 |
|---|---|
| 症状の始まりと経過 | 「1ヶ月前から便秘がちになり、1週間前から左下腹部が痛み出した」 |
| 痛みの特徴 | 「シクシクとした持続的な痛みで、食事の後や体を動かすと強くなる」 |
| 便の状態 | 「ウサギの糞のようにコロコロして硬い」「便の周りに血が付着していた」 |
腹部の触診でわかること
医師は身体診察(腹部診察)を行い、お腹の張りの程度、ガスの溜まり具合、痛みの正確な場所、異常な しこり(腫瘤)の有無、肝臓や脾臓の腫れの有無、腸が動く音(腸蠕動音)の亢進や減弱などを確認します。
触診は、緊急性の高い腹膜炎などを見分ける上でも、非常にシンプルかつ重要な診察手技です。
血液検査や画像検査の目的
問診や触診で得られた情報をもとに、診断を確定したり、他の病気との鑑別をしたりするために、追加の検査を行います。
血液検査では、体内の炎症の程度を示すCRP値や白血球数、貧血の有無を示すヘモグロビン値、栄養状態を示すアルブミン値などを調べます。
また、腹部超音波(エコー)検査やCT検査といった画像検査は、腸の壁の厚さや、憩室炎の有無、膿のたまり(膿瘍)の形成、腫瘍の存在などを視覚的に評価するために行われ、治療方針の決定に役立ちます。
大腸内視鏡検査で原因を究明する
下腹部痛を伴う便秘の原因を調べる上で、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)は最も直接的で、かつ多くの情報をもたらしてくれる検査です。
医師が直接、大腸の内部をくまなく観察することで、他の検査ではわからない粘膜レベルでの微細な変化を捉え、多くの病気の確定診断が可能になります。
大腸内視鏡検査とはどのような検査か
先端に高性能なCCDカメラが搭載された、直径1cm程度の細くしなやかなスコープを肛門から挿入し、直腸からS状結腸、下行結腸、横行結腸、上行結腸を経て、最も奥にある盲腸までの大腸全域の粘膜をリアルタイムで詳細に観察する検査です。
モニターに映し出される鮮明な画像を見ながら、炎症の程度や範囲、潰瘍、ポリープ、がんなどの病変がないかを隅々まで確認します。
特殊な光(NBI)を用いて、微細な血管の模様を強調表示し、病変の良悪性をより正確に判断することも可能です。
大腸内視鏡検査の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 検査時間 | 観察のみであれば通常15分〜30分程度(個人差や腸の長さによる) |
| 麻酔の使用 | 鎮静剤(静脈麻酔)を使用し、ウトウトと眠っている間に検査が可能 |
| 観察範囲 | 直腸から盲腸までの大腸全域と、小腸の一部(終末回腸) |
検査でわかることと安全性
この検査により、大腸がんやその前がん病変であるポリープ、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患、大腸憩室症、虚血性大腸炎など、便秘や腹痛の原因となりうる多くの病気を高い精度で診断できます。
また、疑わしい部分が見つかった場合は、その場で組織の一部をピンセットで採取(生検)し、顕微鏡で詳しく調べる病理検査に提出することが可能です。
これが確定診断に繋がり、小さなポリープであれば、検査中にその場で切除することもできます。
検査に伴う偶発症(出血や穿孔)のリスクはゼロではありませんが、頻度は非常に稀であり、経験豊富な専門医のもとで安全に施行される検査です。
検査前の準備と当日の流れ
正確で安全な検査のためには、大腸の中を便のない空っぽの状態で、きれいにしておく必要があり、検査前日は消化の良い、繊維質の少ない食事(検査食など)をとり、夜に下剤を服用します。
検査当日は、朝から約1〜2リットルの液体状の腸管洗浄剤を数時間かけて飲み、腸内を完全に洗浄し、便が透明な液体になったら準備完了です。医療機関に到着後は、検査着に着替え、鎮静剤を使用する場合は点滴の準備をします。
検査室で横になり、鎮静剤を投与された後、リラックスした状態で検査を開始します。
検査後の注意点
検査後は、鎮静剤の効果が完全に覚めるまで、1時間ほどリカバリールームで休みます。鎮静剤を使用した当日は、終日、車やバイク、自転車の運転はできません。食事は、医師の指示に従い、消化の良いものから少しずつ開始します。
組織を採取したりポリープを切除したりした場合は、アルコールや香辛料などの刺激物を1週間程度控える、激しい運動や長時間の移動を避けるなど、いくつかの制限事項があります。検査結果の説明をよく聞き、指示に従ってください。
便秘と下腹部痛を改善するための生活習慣
検査の結果、特に大きな病気が見つからなかった場合、便秘やそれに伴う下腹部痛は、日々の生活習慣を見直すことで大きく改善することが期待できます。
食生活の見直しと水分摂取
便秘解消には、食物繊維を豊富に含む食品を積極的にとることが基本です。
食物繊維には水に溶けて便をゲル状に柔らかくする水溶性食物繊維(海藻、果物、オクラなど)と、水に溶けずに便のかさを増や腸を刺激する不溶性食物繊維(きのこ類、豆類、根菜類など)があり、両方をバランス良く摂取することが理想です。
また、善玉菌を含む発酵食品(ヨーグルト、納豆など)や、善玉菌のエサとなるオリゴ糖を食事に取り入れることも、腸内環境の改善に役立ちます。
便を柔らかくするためには、十分な水分補給が何よりも重要で、1日に1.5リットルから2リットルを目安に、こまめに水分をとりましょう。
食物繊維を多く含む食品例
| 食物繊維の種類 | 特徴 | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| 水溶性 | 便を柔らかくし、善玉菌のエサになる | わかめ、昆布、りんご、大麦、オクラ |
| 不溶性 | 便のかさを増やし、腸の蠕動運動を促す | ごぼう、きのこ類、大豆、さつまいも、玄米 |

適度な運動と排便習慣
ウォーキングや軽いジョギング、ヨガなどの有酸素運動は、全身の血行を良くし、腸の蠕動運動を活発にする効果があり、また、腹筋を鍛えることも、排便時にスムーズにいきむための力をサポートします。
運動と合わせて、毎日決まった時間にトイレに行く習慣をつけることも大事です。
朝食後は胃に食べ物が入ることで大腸の動きが活発になる(胃・結腸反射)ため、排便のゴールデンタイムで、便意がなくても5分程度トイレに座る習慣をつけることで、体が排便のリズムを覚えやすくなります。
ストレス管理とリラックス法
脳と腸は自律神経などを介して密接に連携しており、これを脳腸相関と呼びます。強いストレスや緊張状態が続くと、自律神経のうち交感神経が優位になり、腸の動きが抑制されて便秘を起こすことがあります。
趣味に没頭する時間を持つ、ぬるめのお湯にゆっくり浸かる、アロマテラピーを取り入れる、十分な睡眠時間を確保するなど、自分なりのリラックス法を見つけて、心身の緊張を意識的にほぐすよう心がけましょう。
よくある質問
便秘と下腹部の痛みに関して、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 子供や高齢者の便秘と腹痛で気をつけることは何ですか
-
子供の場合、学校のトイレに行きたがらない、遊びに夢中になって便意を我慢するなど、生活習慣が原因で便秘になりやすいです。
腹痛を繰り返し訴える際は、便秘以外の病気の可能性も考え、まずはかかりつけの小児科医に相談しましょう。
高齢者は、食事量の減少や活動量の低下、腸の動きを鈍くする作用のある薬(降圧薬や抗うつ薬など)の服用、腹筋力の低下など、様々な要因で便秘になりがちです。
脱水にもなりやすいため、こまめな水分補給を促し、痛みが強い場合は自己判断せず、かかりつけ医に相談してください。硬い便が直腸で栓のようになってしまう糞便塞栓を起こすこともあり、注意が必要です。
- 女性は便秘になりやすいと聞きましたが、下腹部痛も関係しますか
-
女性は、月経周期に関わる女性ホルモンの一つである黄体ホルモンの影響で、大腸の動きが抑制されやすいため、特に排卵後から月経前にかけて便秘になりやすい傾向があります。
また、男性に比べて腹筋が弱いことや、ダイエットによる食事制限も便秘の一因です。
便秘による下腹部痛はもちろんですが、月経困難症や子宮内膜症、卵巣の病気といった婦人科系の疾患が下腹部痛の原因となることも少なくありません。
便秘の症状と月経周期が明らかに関連している場合や、便秘以外の不正出血などの症状がある場合は、婦人科への相談も検討すると良いでしょう。
- 大腸内視鏡検査はどのくらいの頻度で受けるべきですか
-
大腸がんの罹患率が高まり始める40歳を過ぎたら、特に症状がない場合でも、一度は大腸内視鏡検査を受けることが推奨されます。
検査でポリープなどの異常が何も見つからなかった場合、次回の検査までの期間は個人のリスクに応じて異なりますが、一般的には3年から5年後が目安です。
ただし、血縁者に大腸がんの人がいる、過去にポリープを切除したことがある、炎症性腸疾患と診断されているなど、リスクが高い場合は、より早い年齢から、より頻繁な検査が必要になることがあります。
- 市販の下剤を長期間使用しても大丈夫ですか
-
市販の下剤には様々な種類があり、漫然と長期間使用し続けることには注意が必要です。
センナやアロエ、大黄などが含まれる刺激性下剤は、大腸の粘膜を直接刺激して蠕動運動を強制的に起こすため、連用すると腸がその刺激に慣れてしまい、薬の量が増えたり、薬なしでは排便できなくなったりすることがあります。
また、腸の粘膜が黒くなる大腸メラノーシスという状態を起こすことも知られています。便秘の治療は、まず生活習慣の改善が基本です。
薬を使用する場合は、酸化マグネシウムなどの習慣性の少ないタイプから試し、自己判断で長期間使用するのではなく、医療機関で便秘のタイプを正しく診断してもらい、適切な薬を処方してもらうことが大切です。
以上
次に読むことをお勧めする記事
【大腸がん初期症状の見逃しを防ぐ 便の変化や腹痛の基本知識】
便秘や下腹部痛を学んだ皆さんには、大腸がんの初期サインも合わせて知っておくと、より包括的な理解ができます。受診の優先度判断にも役立ちます。
【大腸内視鏡検査での痛みを和らげる方法|鎮静剤と麻酔について】
便秘と下腹部痛の原因を調べる大腸内視鏡検査について理解が深まったら、次は実際の検査時の痛みや不安への対策について知っておくと安心です。初めて検査を受ける方に特に参考になる内容です。
参考文献
Komori S, Akiyama J, Tatsuno N, Yamada E, Izumi A, Hamada M, Seto K, Nishiie Y, Suzuki K, Hisada Y, Otake Y. Prevalence and risk factors of constipation symptoms among patients undergoing colonoscopy: a single-center cross-sectional study. Digestion. 2024 Aug 9;105(4):299-309.
Otani K, Watanabe T, Takahashi K, Nadatani Y, Ominami M, Fukunaga S, Hosomi S, Kamata N, Tanaka F, Nagami Y, Taira K. Upper gastrointestinal endoscopic findings in functional constipation and irritable bowel syndrome diagnosed using the Rome IV criteria: a cross-sectional survey during a medical check-up in Japan. BMC gastroenterology. 2023 May 3;23(1):140.
Arai YC, Shiro Y, Funak Y, Kasugaii K, Omichi Y, Sakurai H, Matsubara T, Inoue M, Shimo K, Saisu H, Ikemoto T. The association between constipation or stool consistency and pain severity in patients with chronic pain. Anesthesiology and pain medicine. 2018 Aug 11;8(4):e69275.
Yamada E, Kuriyama H, Uchida E, Murata Y, Hata Y, Tagri M, Isozaki Y, Oyamada H, Ozawa Y, Ito T, Mizuki A. Association between endoscopic findings related to colonic diverticula and bowel habits: A multicenter study in Japan. Journal of gastroenterology and hepatology. 2017 Dec;32(12):1938-42.
Cai J, Yuan Z, Zhang S. Abdominal pain, diarrhea, constipation-which symptom is more indispensable to have a colonoscopy?. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2015 Jan 1;8(1):938.
De Bosset V, Gonvers JJ, Vader JP, Dubois RW, Burnand B, Froehlich F. 9. Appropriateness of colonoscopy: lower abdominal pain or constipation. Endoscopy. 1999 Oct;31(08):637-40.
Filliettaz SS, Gonvers JJ, Peytremann-Bridevaux I, Arditi C, Delvaux M, Numans ME, Lorenzo-Zuniga V, Dubois RW, Juillerat P, Burnand B, Pittet V. Appropriateness of colonoscopy in Europe (EPAGE II)–functional bowel disorders: pain, constipation and bloating. Endoscopy. 2009 Mar;41(03):234-9.
Ratnasingham K, Lo T, Jamal K, Varatharajan L, Tabbakh Y, Kaderbhai H, West NJ. The role of colonoscopy and CT colonography in patients presenting with symptoms of constipation. The British Journal of Radiology. 2017 May 1;90(1073):20160147.
Popovic DD, Filipovic B. Constipation and colonoscopy. World Journal of Gastrointestinal Endoscopy. 2024 May 16;16(5):244.
Neugut AI, Garbowski GC, Waye JD, Forde KA, Treat MR, Tsai JL. Diagnostic yield of colorectal neoplasia with colonoscopy for abdominal pain, change in bowel habits, and rectal bleeding. American Journal of Gastroenterology (Springer Nature). 1993 Aug 1;88(8).